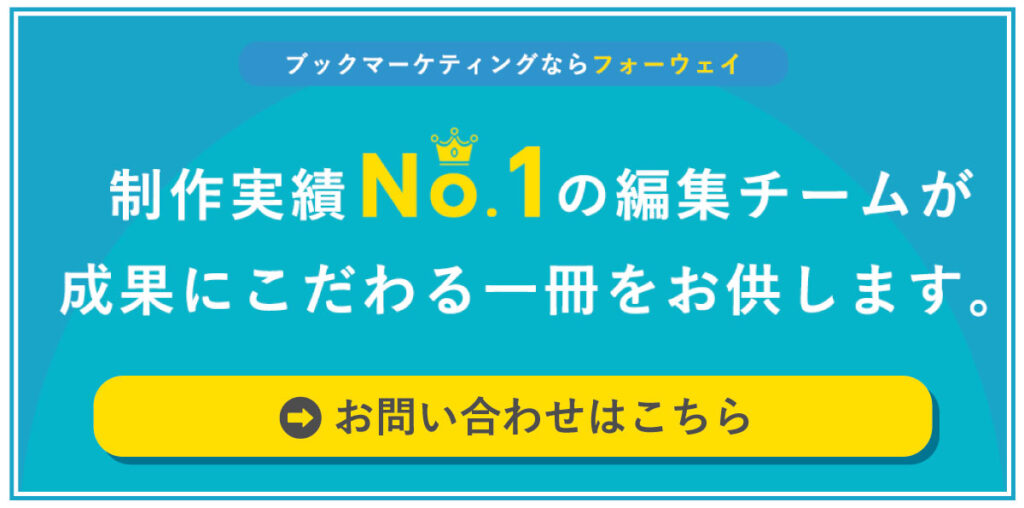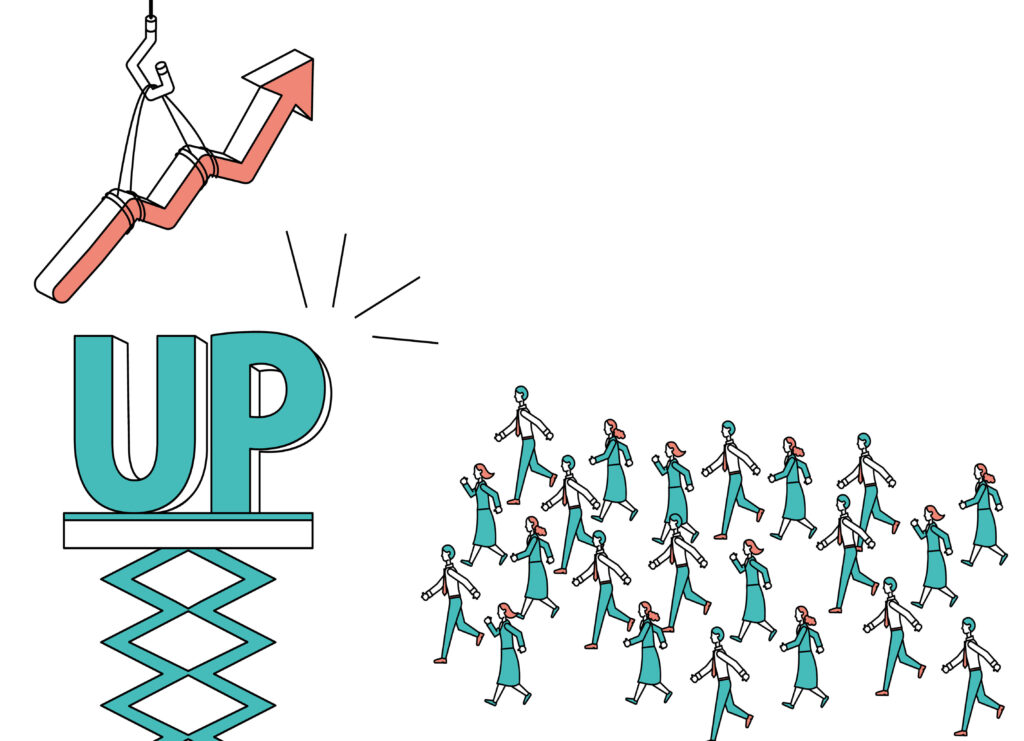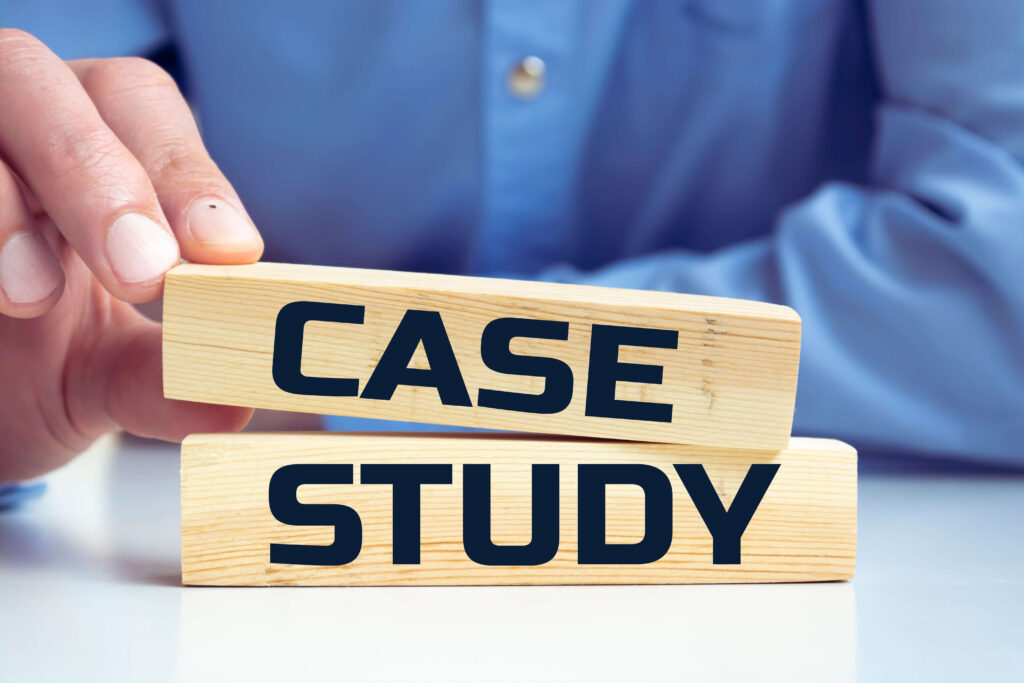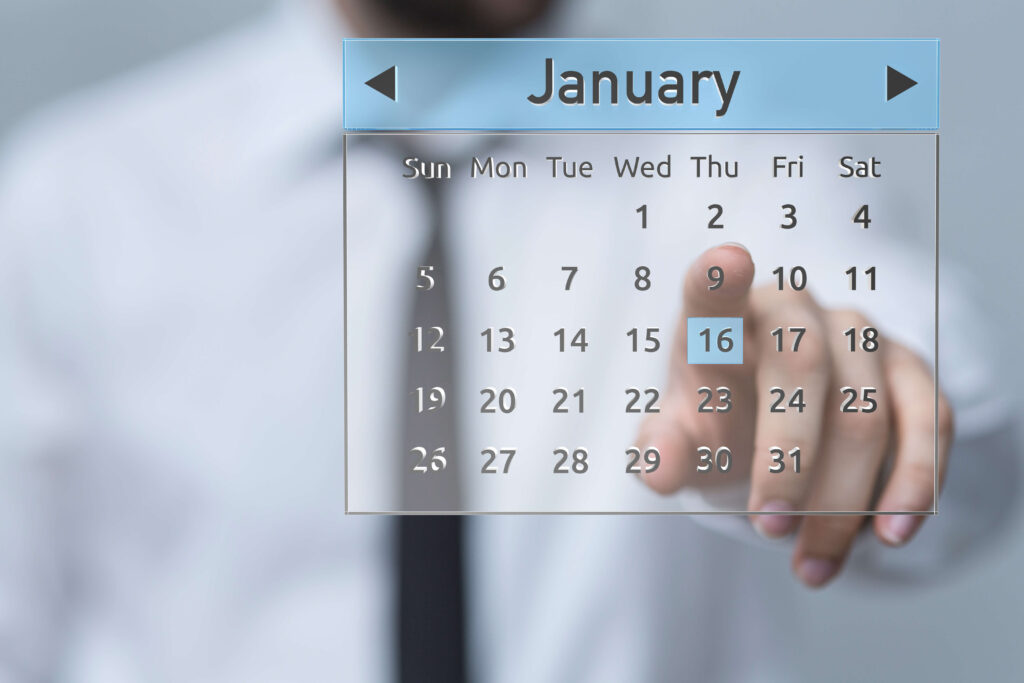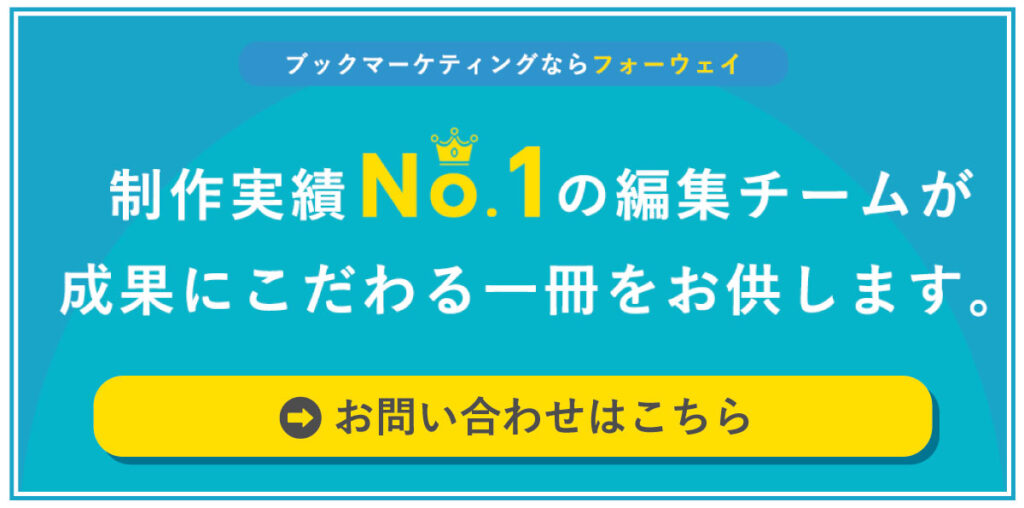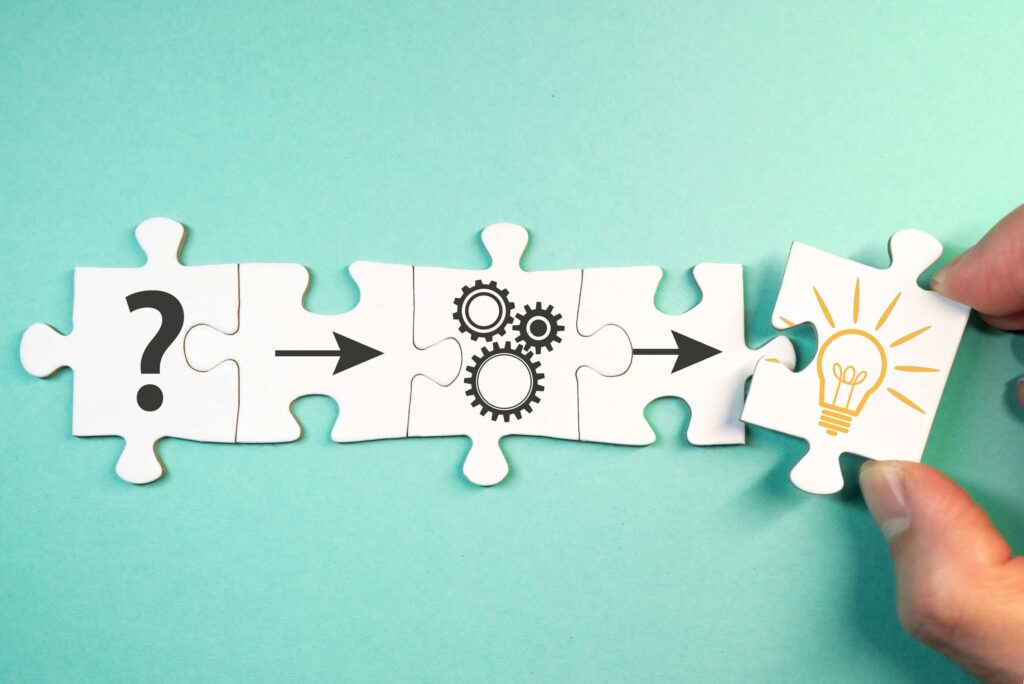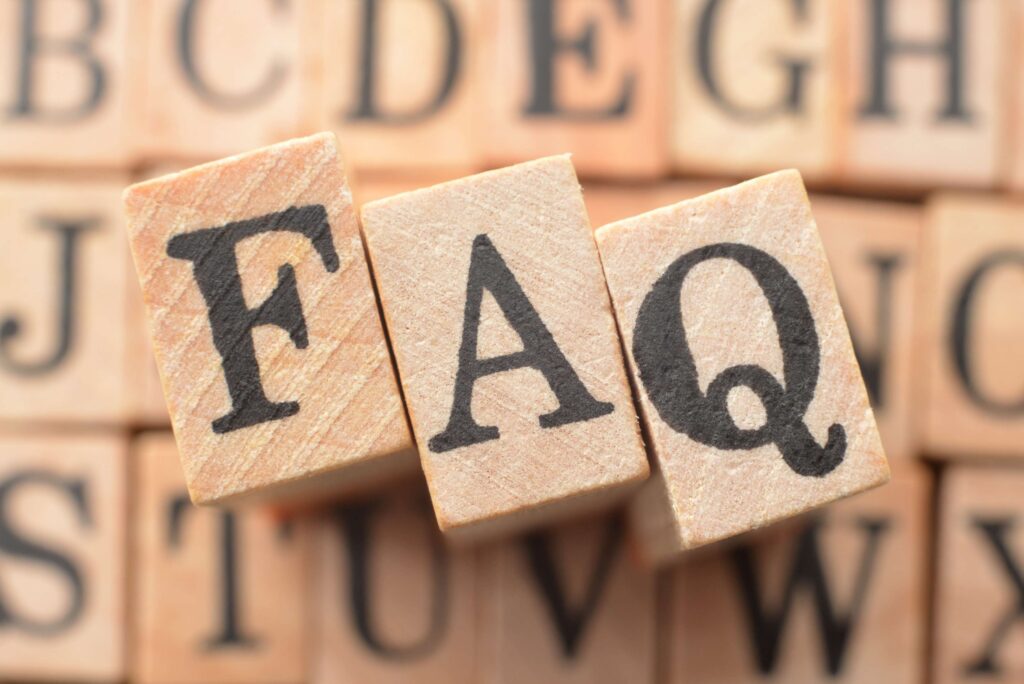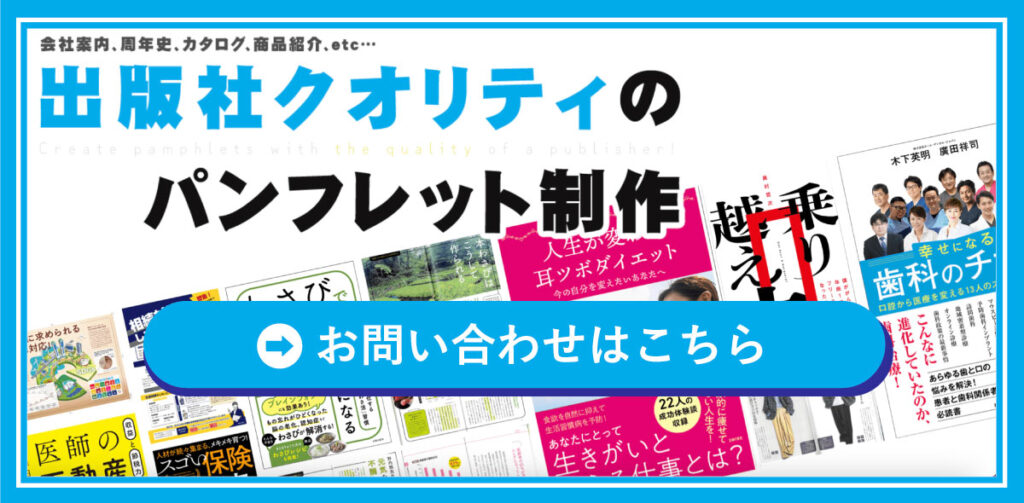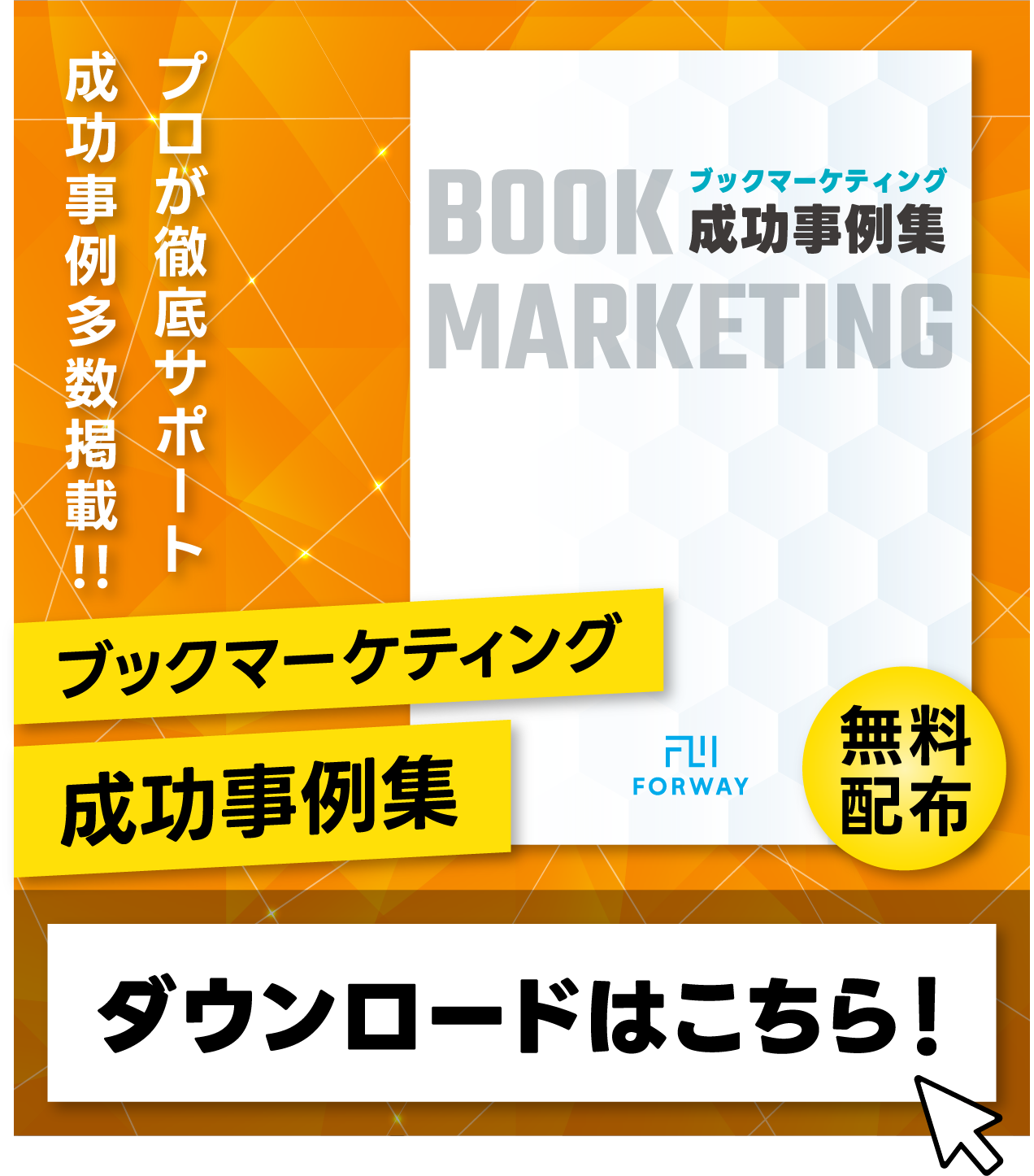売上を高めるうえで欠かせないのが「客単価」の分析と改善です。
客単価とは、1人の顧客が1回の取引で支払う平均金額のことを指します。
一見単純な指標に思えるかもしれませんが、「顧客が何をどのように買っているか」「自社の商品・サービスの価値がどれだけ適切に伝わっているか」といった重要な情報が詰まっています。
たとえば、同じ売上金額でも、少数の顧客が高額商品を購入しているのか、それとも多くの人が少額ずつ買っているのかで、事業の方向性や戦略は大きく変わるでしょう。
客単価に注目することで、売上の内訳がはっきり見えてくるため、「どのターゲット層にどうアプローチするか」「どの商品を主力にするか」といった判断もつきやすくなります。
本記事では、客単価の定義や計算方法をわかりやすく解説し、分析によって得られるメリットや具体的な単価アップの施策について紹介します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉客単価とは?定義と計算式をわかりやすく解説

まず最初に、客単価とは何かについて説明しておきましょう。
客単価の定義と計算式は、次の通りです。
◉-1、客単価の定義
客単価とは、「1人の顧客が1回の購入で支払う平均金額」のことです。
ECサイトや飲食店、小売店などのさまざまな業種で活用されている代表的な経営指標の一つです。
顧客1人あたりの購買金額を把握することで、経営状況や販売施策の効果を客観的に評価できるようになります。
◉-2、客単価の計算式
客単価の計算式は、次の通りです。
たとえば、1日の売上が50万円で、来店客数が250人だった場合、「500,000円÷250人=2,000円」と計算できます。
なお、曜日や時間帯によって売上や販売量に大きな差がある場合は、分析対象の期間を「曜日別」や「時間帯別」に区切ることで、より精度の高い分析が可能になります。
ここで注意すべきなのは、「客単価」は実際に購入した顧客のみを対象として算出される点です。
つまり、いくら多くの人を集客しても、購入に至らなければ売上には結びつかず、客単価にも反映されません。
一見当たり前に思えることですが、プロモーションやマーケティング戦略を立てるうえで重要な視点です。
◉客単価を分析するメリット

では、客単価を分析するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
一般的に、次の3つのメリットがあります。
・売上向上の具体的な戦略立案に役立つ
・ターゲット顧客ごとにマーケティング最適化を図れる
・他社との差別化ポイントを把握しやすくなる |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、売上向上の具体的な戦略立案に役立つ
「売上が思うように伸びない」「最近落ち込み傾向にある」といった場合に、客単価を分析すると原因を探る手がかりになります。
単に売上金額だけを見ていても、その内訳がわからなければ、有効な対策を講じることはできません。
たとえば、売上が前月より20%減少したとき、この数字だけでは、何が問題だったのかはわかりません。
しかし、客単価のデータを確認すれば、「来店客数は変わらないのに、1人あたりの購入金額が減っている」といった具体的な傾向が浮き彫りになります。
逆に、「客単価は変わらないのに客数が減っている」という傾向が把握できたときは、集客施策の見直しが必要になります。
◉-2、ターゲット顧客ごとにマーケティングの最適化を図れる
顧客単価の分析は、単に顧客一人あたりの購入金額がわかるだけでなく、マーケティング活動を最適化するためにも役立ちます。
特に、ターゲット顧客ごとの客単価を比較することで、より効果的なマーケティング施策を立てるための方向性がつかめます。
たとえば、商品カテゴリー別に客単価を分析すれば、売上に貢献しているジャンルを特定することが可能です。
また、性別・年齢・地域・購入頻度・購買チャネルなど、さまざまな属性で顧客を分類し、それぞれの客単価を算出することで、「誰に何をどのように訴求すればよいか」がより明確になります。
このように、客単価は「誰に何を売るか」という視点を磨くための重要な指標といえます。
◉-3、他社との差別化ポイントを把握しやすくなる
客単価の分析は、自社の販売戦略や商品・サービスの市場評価を把握するうえで有効な手段です。
特に、同業他社と比較することで、自社の強みや弱み、そして競合との差別化ポイントを客観的に見極めることができます。
たとえば、同じ業種・同規模の企業と比べて自社の客単価が低い場合、価格設定や販売手法、提案内容に改善の余地があると考えられます。
一方で、高い客単価を維持できているのであれば、それは顧客が自社の商品やサービスに対して高い価値を認識している証拠です。
このような分析を通じて、「なぜ選ばれているのか」「どこで差別化できているのか」を明らかにすることができ、今後の戦略立案にも役立ちます。
▶︎差別化戦略の詳細については、関連記事【差別化戦略の成功の秘訣ーメリットやデメリット、成功事例とは!?】もあわせて参考にしてください。
◉客単価を上げるための具体的な施策
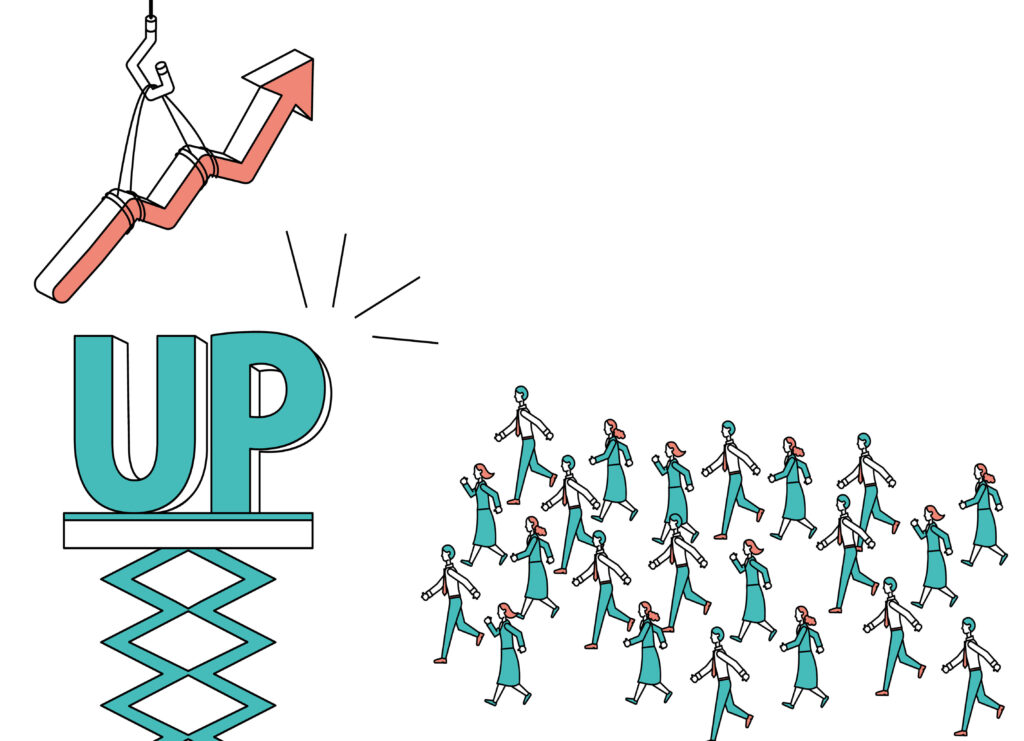
客単価を上げる具体的な施策として、次の4つが挙げられます。
・商品・サービスの設計で客単価を引き上げる施策
・販売方法で客単価を引き上げる施策
・購入しやすさを高めて客単価を引き上げる施策
・価値の訴求によって商品の魅力を高め、客単価を引き上げる施策 |
どのような施策なのか、詳しく見ていきましょう。
◉-1、商品・サービスの設計で客単価を引き上げる施策
商品やサービスそのものの価値を見直すことで、無理なく客単価を引き上げることができます。
顧客に「この金額を払っても良い」と納得して支払ってもらえるような仕組みを作ることで、値引きに頼らず安定的に売上を伸ばすことが可能になります。
◉-1-1、商品単価を上げる
客単価を引き上げる方法として、まず検討できるのが「商品単価の引き上げ」です。
一番シンプルな方法ですが、ただ価格を上げるだけでは「値上げ」と受け取られ、購入をためらわれる可能性があります。
そのため、「価格の引き上げ」と「提供価値の向上」をセットで行うことが重要です。
たとえば、素材の品質を高めたり、パッケージデザインを刷新したり、購入後のサポート体制を強化したりすることで、価格に見合う価値を感じてもらうことができます。
価格以上の満足感を提供することで、自然なかたちで商品単価を上げることが可能になります。
◉-1-2、高価格帯商品や限定品を追加する
顧客の選択肢の中に、あえて選びたくなるような高価格帯の商品や限定商品を加える方法も有効です。
すべての顧客が購入してくれなくても、一部の顧客が選んでくれるだけで全体の客単価を引き上げる効果があります。
たとえば、オーダーメイド対応品や季節限定品、数量限定品などがあります。
◉-1-3、購入特典を用意する
購入特典を用意することで、顧客の購買意欲を高め、自然と客単価の向上を促すことができます。
たとえば、「5,000円以上のご購入でオリジナルグッズをプレゼント」や「購入者限定で次回使えるクーポンを進呈」といった施策は、顧客にとって「もう少し買えば得をする」という動機づけになり、結果的に購入金額の底上げにつながります。
◉-2、販売方法で客単価を引き上げる施策
商品の販売手法を工夫することで、顧客がより自然に多くの商品や高価格帯の商品を選ぶように促すことができます。
ポイントは「お得感」や「選びやすさ」を意識した販売設計です。
◉-2-1、セット販売を導入してまとめ買いを促す
セット販売(バンドル販売)を導入することで、まとめ買いを促し、客単価の向上を図ることができます。
これは、複数の商品を組み合わせて一つのパッケージとして提供する販売手法です。
たとえば、飲食店では「メイン+ドリンク+デザート」のセット、小売店では「靴下3足組」といった組み合わせが考えられます。
また、「2点以上の購入で10%割引」「5,000円以上の購入で送料無料」というやり方もあります。
顧客にとっては単品購入よりもお得感があり、「せっかくならもう1点」といった追加購入につながりやすい点がメリットです。
◉-2-2、3段階の価格設定を行い、中価格帯の選択を促す
「松・竹・梅」のように、3つの価格帯を用意する方法です。
人は、最も安い選択肢には品質面で不安を感じやすく、最も高価な選択肢には手が届きにくいと感じる傾向があります。
その結果、無意識のうちに中間の価格帯を「妥当な選択」として選ぶ心理が働きます。
この心理を活用し、最も販売したい商品を中価格帯(竹)に設定し、その上下に高価格(松)と低価格(梅)の商品を配置することで、中価格帯の商品が選ばれやすくなります。
◉-2-3、上位商品を提案してアップセルを狙う
アップセルとは、顧客が検討している商品よりも上位のグレードや価格帯の商品を提案し、購入単価を引き上げる手法です。
「少しの追加予算で、より高品質な商品が手に入る」といった納得感を与えることで、顧客の選択を自然に上位商品へと誘導できます。
たとえば、美容院では「通常カット」に加えて「トリートメント付きプラン」を提案する、家電販売では「標準モデル」ではなく「高機能モデル」を紹介するといった施策が該当します。
ただし、過度な提案は押し売りと受け取られるリスクがあるため、顧客のニーズや状況を正確に把握し、それに基づいた適切な提案を行うことが重要です。
◉-2-4、関連商品を提案してクロスセルを狙う
クロスセルは、顧客が購入を検討している商品と一緒に使うと便利な商品を併せて提案する販売手法です。
たとえば、スマートフォンを買う顧客に、ケースや保護フィルム、充電器などを同時に提案するといったイメージです。
また、ECサイトなどでよく見られる「この商品を購入した人は、こちらの商品にも興味を持っています」といったレコメンド表示も、クロスセルの一種です。
◉-3、購入しやすさを高めて客単価を引き上げる施策
魅力的な商品やサービスを提供していても、顧客が「買いにくい」と感じるようであれば、客単価は伸び悩んでしまいます。
購買体験の中でストレスや不便さを感じさせないことは、結果として購入点数や売上の増加につながります。
◉-3-1、決済の選択肢を増やす
現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など、幅広い決済方法に対応することで、顧客が感じる購入時のハードルを大きく下げることができます。
特に近年はキャッシュレス決済を好む顧客が増加しており、対応していない場合は「買いたくても買えない」状況を招き、貴重な購買機会を失う可能性があります。
◉-4、価値の訴求によって商品の魅力を高め、客単価を引き上げる施策
顧客が高価格商品を購入するかどうかは、その商品に対する「納得感」や「共感」が得られるかどうかに左右されます。
価格が高い商品ほど、「なぜこの値段なのか」「価格に見合う価値があるのか」をきちんと伝える必要があります。
そのためには、商品そのもののスペックや特徴だけでなく、背景にあるストーリーやブランドの想いを、ターゲット顧客に合ったメディアでわかりやすく伝えることが重要です。
◉-4-1、SNSやホームページで商品の魅力をわかりやすく伝える
SNSや公式サイトでは、商品の魅力やこだわりをビジュアルでわかりやすく伝えることができます。
特にInstagramやX(旧Twitter)などのプラットフォームでは、写真や動画を活用して、使用シーンやビフォー・アフターの変化などを視覚的に訴求することが可能です。
「これならこの価格でも納得」と思ってもらうことができれば、購入につながる可能性が高くなります。
▶︎SNS運用のやり方については、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】もあわせて参考にしてください。
◉-4-2、書籍の制作・配布で商品の魅力や想いを届ける
SNSや公式サイトでは伝えきれない深い世界観やブランドの想いを伝える手段として効果的なのが、書籍による価値の訴求です。
書籍は、社会的信頼性の高いメディアであることに加えて、丁寧に作られた印象を与えるため、顧客との信頼関係の構築に役立ちます。
また、書籍は来店特典や購入特典としても活用できるため、商品やサービスのブランドイメージの構築と販売促進の両方に効果的です。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。
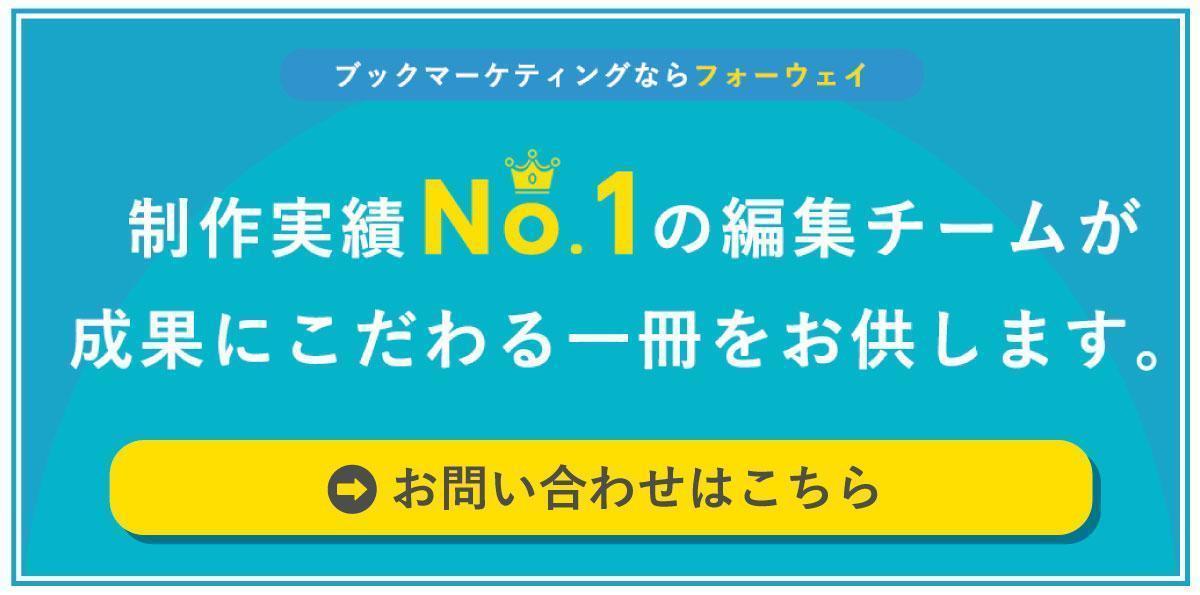
◉書籍出版によって客単価向上を実現した事例

実際に書籍を出版して客単価の向上を実現した事例を2つ紹介します。
・事例1:書籍出版で信頼を獲得し、法人保険の大型契約を実現した保険代理店の成功事例
・事例2:書籍出版を通じて専門性を可視化し、高単価案件の獲得に成功した公認会計士の事例 |
以下で、それぞれについて見ていきましょう。
◉-1、事例1:書籍出版で信頼を獲得し、法人保険の大型契約を実現した保険代理店の成功事例
法人保険を専門に取り扱う保険代理店の経営者は、業界の現状や課題を明らかにしながら、自社で実践している「一律報酬型」の給与制度が人材育成と業績向上に有効であるという持論をまとめた書籍を出版しました。
この書籍は業界内で大きな注目を集め、多くの反響を獲得。
出版をきっかけに顧客からの問い合わせが増加し、保険に関する相談だけでなく、経営理念や組織づくりに関する助言を求められるまでになりました。
企業との信頼関係が深まり、自社の価値観やスタンスが明確に伝わったことで、顧客視点に立った本質的な保険提案が可能となり、結果として法人保険の大型契約の受注を実現しました。
1社あたりの契約単価が上昇し、全体の売上拡大にもつながる成果を上げています。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、事例2:書籍出版を通じて専門性を可視化し、高単価案件の獲得に成功した公認会計士の事例
ある会計事務所の代表を務める公認会計士は、自身の豊富な海外勤務経験をもとに「海外ビジネス展開におけるリスク管理とマネジメント戦略」に関する専門書を出版しました。
この出版によって、「海外進出を支援できる高い専門性を持つ会計士」という専門家としての立場が確立され、顧客にもその実力が具体的に伝わるようになりました。
その結果、主力業務である海外進出企業向けの監査支援やアドバイザリー業務で、これまで見られたような過度な価格交渉に応じる必要がなくなったといいます。
提案段階からプランニングを一任されるケースが増え、業務そのものの価値が適切に評価されるように。
自然と客単価も向上し、事務所全体の売上アップにもつながっています。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉【まとめ】価値訴求による客単価向上を実現するために「書籍出版」を活用しよう!
この記事では、客単価の定義や計算方法をはじめ、分析によって得られるメリットや単価を引き上げるための具体的な施策、さらには成功事例までを幅広く紹介しました。
売上の向上を目指す経営者やマーケティング担当者にとって、「客単価」は単なる数値ではなく、顧客理解・商品戦略・価値訴求のすべてにおいて起点となる重要な指標です。
きちんと分析を行うことで、感覚に頼らない論理的で持続的な売上成長を実現することができるでしょう。
そして近年、客単価向上の手段として注目されているのが、「書籍出版」によるマーケティングです。
書籍は、商品の魅力や特長を伝えるだけでなく、企業の歴史や開発の裏側、ブランドに込めた想いなど、より深い価値を物語として伝えることができます。
さらに、流通を通じた新規顧客との接点づくりや、既存顧客との信頼関係の強化にもつながる有効な施策です。
株式会社フォーウェイでは、「ブックマーケティングサービス」を提供しており、書籍出版を通じて企業の価値や想いを発信するサポートをしています。
客単価を高める施策の一つとして、ぜひ「書籍出版」をご検討ください。
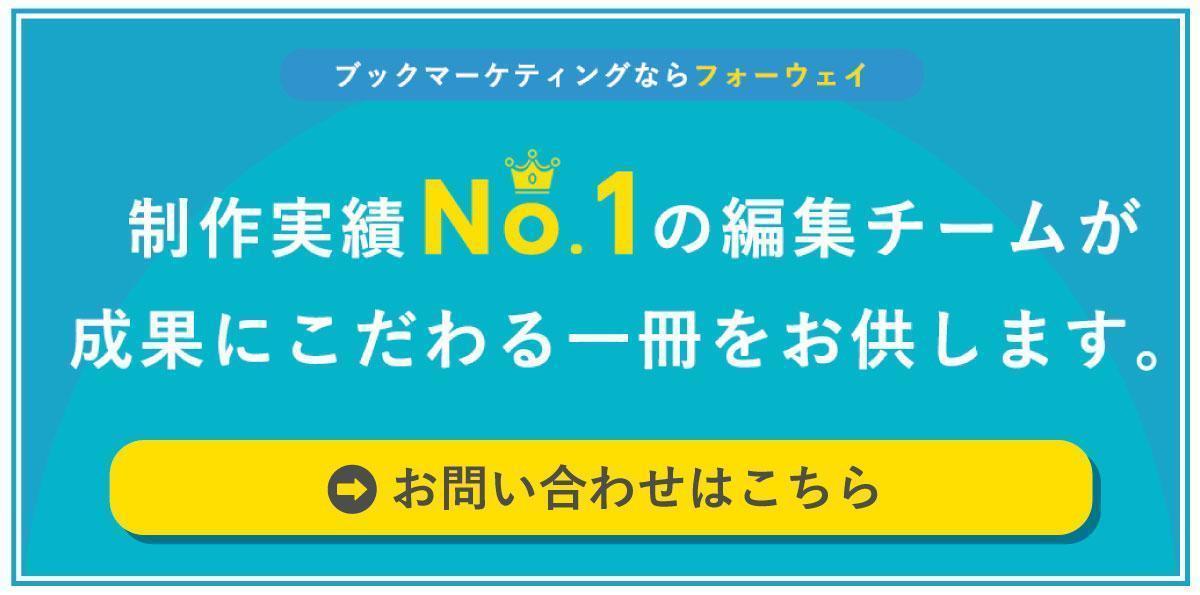

価格競争から抜け出せず、「価格を下げなければ売れない」と悩んでいる企業は少なくありません。
特に、商品やサービスの違いが明確に出しにくい業界では、価格競争に巻き込まれてしまうリスクが常につきまとっているといっても過言ではありません。
しかし、価格の安さだけで選ばれる状態が続くと、企業の利益もブランドも徐々にすり減り、衰退していってしまいます。
そうならないためにも、競合他社との価格競争から脱却していく必要があります。
この記事では、価格競争から脱却し、価格ではなく価値で選ばれる企業に変わるための実践的な方法について分かりやすく解説いたします。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉価格競争が企業にもたらすリスク

価格を下げることで一時的な売上を確保できる場合もありますが、それはあくまで短期的な対処方法にすぎません。
結果として、次の4つのリスクが生じて企業の競争力を大きく損なうことにつながります。
・利益率の低下
・商品・サービス品質の低下
・顧客ロイヤリティの低下
・ブランドイメージの低下 |
以下では、それぞれのリスクについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、利益率の低下
価格を下げると、売上は一時的に増えますが、利益率は確実に低下します。
十分な利益を確保できなければ、商品開発や人材育成といった将来への投資が難しくなり、企業の成長は次第に鈍化していくでしょう。
最終的には、利益減少に歯止めがかからず、打つ手が尽きて撤退や倒産に追い込まれるケースも少なくありません。
◉-2、商品・サービス品質の低下
価格を下げたうえで利益を確保しようとすると、仕入れコストや人件費の削減に踏み切らざるを得なくなります。
しかし、その影響で製品やサービスの品質は徐々に損なわれ、顧客満足度も次第に低下していきます。
品質の低下は、クレームや返品の増加、リピート率の減少といった悪循環を招き、最終的には企業への信頼そのものを揺るがすリスクとなりかねません。
◉-3、顧客ロイヤリティの低下
「価格が安いから選んだ」という顧客は、より低価格の競合商品が登場すれば、迷わずそちらに流れてしまう傾向があります。
価格以外の価値で選ばれていない場合、顧客との継続的な関係を築くのは困難です。
このような状態では、リピート購入や紹介をしてくれるロイヤリティの高い顧客が育ちにくくなり、長期的な利益につながる顧客との関係構築がしにくくなります。
◉-4、ブランドイメージの低下
頻繁な値下げを繰り返すと、「安さだけが魅力のブランド」「品質に不安があるのでは」といったイメージが定着しやすくなります。
その結果、どれだけ優れた商品やサービスを提供していても、本来の強みや価値が伝わらなくなり、企業のブランド価値が下がってしまうでしょう。
ブランドイメージが損なわれることで、価格以外の面で差別化することが難しくなり、さらなる値下げに頼らざるを得ないという悪循環に陥るリスクが高まります。
◉価格競争に巻き込まれてしまう原因

近年の価格競争の激化には、「比較サイト」や「レビュー文化」の浸透、市場のコモディティ化など、外部環境の変化が影響しています。
しかし、それ以上に重要なのが、企業側の姿勢や構造に起因する要因です。
企業が価格競争に巻き込まれてしまう主な原因として、次の5つが挙げられます。
・商品・サービスの価値が顧客に正しく伝わっていない
・コモディティ商品を取り扱っている
・安さをウリにしている
・競合他社と差別化ができていない
・営業部門に「値下げしてでも数字を取る」という文化がある |
以下では、それぞれの要因について詳しく解説していきます。
◉-1、商品・サービスの価値が顧客に正しく伝わっていない
たとえ他社より優れた商品やサービスを提供していても、その価値が顧客に伝わらなければ、最終的な購入判断は価格になってしまいます。
商品やサービスの価値が正しく伝わっていなければ、他社と価格で戦わざるを得なくなり、自然と価格競争に引き込まれていきます。
自社の強みや商品・サービスの価値を顧客に正しく伝える努力が不足していることが、価格競争に巻き込まれる原因の一つといえるでしょう。
◉-2、コモディティ商品を取り扱っている
どこで買っても大きな違いがない商品やサービスは、顧客にとって価格が判断基準になりやすいという傾向があります。
たとえば、以下のようなものがこれに該当します。
・事務用品
・日用品
・BtoB向けの部品や資材
・OEM製品 |
このような商品は、顧客から見ると違いが分かりづらいため、最も分かりやすい比較要素である「価格」が重視され、結果として価格競争に巻き込まれやすくなります。
そのため、価格以外の価値をどう打ち出すかが重要であり、明確な差別化要素がなければ価格競争から抜け出すのは困難でしょう。
◉-3、安さをウリにしている
「業界最安値」や「他社より〇%安い」といったアピールは、一時的な集客効果をもたらす反面、自ら価格競争に踏み込む行為でもあります。
こうしたアピールを続けていると、値下げが当たり前の状態となり、利益率が圧迫されていくという悪循環に陥ります。
安さをウリにするのではなく、「その価格で得られる価値は何か」を伝える視点が欠かせません。
◉-4、競合他社と差別化ができていない
商品やサービスの特徴、営業資料やWebサイトの内容などが競合他社と似通っていると、顧客は価格以外で比較することができなくなり、必然的に価格競争に陥ってしまいます。
差別化できていなければ、顧客にとって「選ぶ理由」は価格だけになってしまうからです。
価格以外の魅力を打ち出せなければ、顧客は最終的に「より安い方」を選ぶ傾向が強くなり、持続的な競争優位を築くことが難しくなります。
◉-5、営業部門に「値下げしてでも数字を取る」という文化がある
営業現場で「とにかく今月の数字を達成する」というノルマを重視しすぎると、「値引きしてでも購入してもらう」という安易な受注体質が生まれやすくなります。
このような姿勢が常態化すると、営業部門にとどまらず、組織全体に「価格で勝負するのが当たり前」といった意識が広がりやすくなります。
その結果、商品の価値を伝える工夫や、課題解決型の提案営業といった本来重視すべきアプローチが育ちにくくなるのです。
中長期的に見れば、価格競争からの脱却をますます困難にする大きな要因となります。
◉価格競争から脱却し、価値で選ばれる企業になるための方法

価格競争から抜け出し、価格ではなく価値で選ばれる企業になるためには、戦略的な見直しと社内体制の再構築が欠かせません。
そのための実践的な方法として、次の5つを紹介します。
・ターゲットの見直し
・自社や商品・サービスのUSPを再定義する
・商品・サービスに独自性(機能・体験・世界観)を持たせる
・ストーリーテリングによりファンを増やす
・営業・マーケティング部署を中心とした社内の意識・体質を変える |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、ターゲットの見直し
まず重要なのは、「誰に売るか」を見直すことです。
価格を重視する層ばかりにアプローチしていては価格競争から抜け出せないので、価格よりも価値を重視する顧客層にターゲットを絞ることが効果的です。
見込み顧客のニーズを再定義し、価格以外の魅力を求めている層に焦点を当てて、訴求内容や接点を見直していきましょう。
◉-2、自社や商品・サービスのUSPを再定義する
次に、自社や商品のUSP(Unique Selling Proposition)、すなわち顧客にとっての「選ぶ理由」を再設計します。
価格以外のどこに魅力があるのかを明確に言語化して発信していくことが、価値を重視する顧客層に響くアプローチになります。
たとえば、次のような視点について、自社の強みを洗い出してみましょう。
・高品質・高性能・専門性
・サポートの手厚さ
・納期の早さ・対応スピード
・社会的信頼
・長年の実績・顧客との関係性
・導入しやすさ
・パッケージング |
自社では当たり前と思っていたことでも、顧客から見ると大きな価値である可能性があります。
実際の顧客の声をヒアリングしながら、選ばれている理由を客観的に再発見することがUSPの見直しに有効です。
◉-2-1、高品質・高性能・専門性
競合には真似できない品質や技術、専門性は強力な差別化要素になります。
たとえば、「精度が1.5倍高い検査機器」「特定業界向けに開発された高耐久フィルター」「自社開発エンジンによる2倍以上の処理性能」「40年以上の実績を が裏付ける品質」などは、大手企業の資本力だけでは再現が難しい領域です。
こうした独自性の高い強みを明確に打ち出すことが、競争優位性を確立するポイントです。
◉-2-2、サポートの手厚さ
きめ細やかで手厚いサポート体制も顧客に選ばれる理由になります。
たとえば、「導入から初期設定まで専任スタッフがオンラインで対応」「電話・チャット・メールすべて即日返信」「マニュアルと操作研修がセットで初心者でも安心」といった対応は、かゆいところに手が届くサポートとして高く評価されます。
大手企業が規模の都合上提供しづらいサービスこそが、小回りの利く企業の差別化ポイントになり得ます。
◉-2-3、納期の早さ・対応スピード
納期の早さや対応スピードも強みになります。
たとえば、「午前11時までの注文は当日出荷」「初回見積もりは24時間以内に回答」「突発案件にも即日対応できる在庫体制あり」などの迅速な対応は顧客の信頼につながります。
ただし、過度なスピード対応は社内に負担をかけるため、持続できる体制を整えることが重要です。
◉-2-4、社会的信頼
地域活動への参加なども地域に特化した差別化に有効です。
「地域で50年以上の歴史」「行政や教育機関との協業実績」など、全国的な認知度が低くても、地域での強い支持を得ている企業は数多くあります。
地元に根ざした活動の積み重ねは、他社にはない信頼を築きます。
◉-2-5、長年の実績・顧客との関係性
積み重ねてきた実績は、何よりの信頼の証です。
たとえば、「創業50年」「累計導入企業2,000社以上」「15年以上継続取引の企業多数」「大手メーカー●●社に10年以上納品」といった具体的な数字があると、顧客に安心感を与えます。
特にBtoB取引においては、このような数字の裏付けがあると大きな説得力を持ちます。
◉-2-6、導入しやすさ
使いやすく、導入しやすい商品やサービスは、初めての顧客にとって大きな安心材料です。
たとえば、「初期費用ゼロで月額定額制から始められる」「マニュアルや初期設定キットが付属しており、現場ですぐに活用できる」「ITに不慣れでも安心の電話サポート付き」といった特徴は、現場の実用性を重視する顧客に高く評価されます。
また、導入のハードルが低いことで、購買意欲を後押しする効果も期待できます。
◉-2-7、パッケージング
商品やサービス自体での差別化が難しい場合は、パッケージや提供形式を工夫することで独自性を打ち出すことが可能です。
たとえば、キッコーマンは「しぼりたて生しょうゆ」を卓上ボトルで展開することで、他社と一線を画す価値を生み出しました。
このように、包装・提供方法・サブスクリプション化などで新たな価値を生むことができます。
特にコモディティ化しやすい商品やサービスを取り扱う企業は、パッケージングで競合他社との差別化を図るのがおすすめです。
◉-3、商品・サービスに独自性(機能・体験・世界観)を持たせる
価格だけで選ばれる状態から脱却するためには、商品やサービスに「体験価値」や「ブランドの世界観」などの情緒的な価値を加えることが有効です。
たとえば、「購入からアフターサポートまで一貫した顧客体験」や「ブランドの想いを物語として体現する演出」などを通じて、顧客の共感や愛着を引き出し「その企業で買いたい」と思わせることができます。
◉-4、ストーリーテリングによりファンを増やす
創業の理念や創業の背景、困難を乗り越えたエピソードなど、単なる商品説明では伝えきれない人間的な価値を伝える手法がストーリーテリングです。
企業の想いや価値観に共感した顧客は、価格ではなくそのブランドの姿勢に惹かれ、長期的な関係を築くロイヤルユーザーへと変わっていきます。
◉-4-1企業のストーリーを伝えるなら書籍出版がおすすめ
企業の想いや成り立ち、価値観を深く伝えたいなら、書籍が有効です。
書籍はマーケティングツールの中でも、社会的信頼性や専門性が高く、WebサイトやSNSと比べて「権威性のある情報発信」が可能になります。
また、読者は書籍という形式であれば長文をじっくり読んでくれるため、深い共感やファン化につながりやすいのも特徴です。
さらに、営業資料や広報活動におけるPRツールとしても活用でき、新規リード獲得のきっかけとしても効果が期待できます。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。

◉-5、営業・マーケティング部署を中心とした社内の意識・体質を変える
どれだけ価値を訴えても、現場が「売るためには値下げが必要」という意識のままでは、価格競争からの脱却は困難です。
そのため、営業やマーケティング部門を中心に、「価格ではなく価値で選ばれる」という文化を社内に浸透させることが重要です。
具体的には、教育や評価制度の見直し、KPI設計の再構築などを通じて、価格以外の魅力を語れる組織体制を整えていく必要があります。
◉書籍出版により価格競争から脱却した成功事例
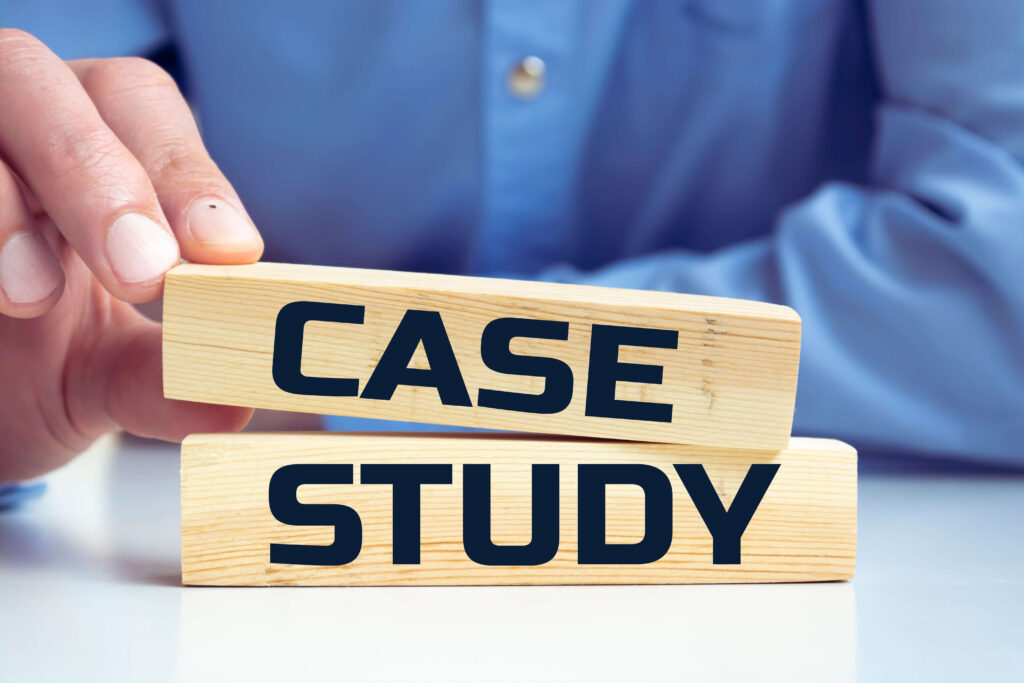
価格ではなく価値で選ばれるための手段として、近年注目を集めているのが書籍出版を活用したブランディングです。
ここでは、実際に書籍出版を通じて、価格競争から脱却し、自社ならではの強みを市場に浸透させた2つの事例を紹介します。
・事例1:常識を覆す持論を展開して注目を集めた保険代理店
・事例2:書籍出版により独自の強みをPRした会計事務所 |
以下で、それぞれ詳しく紹介します。
◉-1、事例1:常識を覆す持論を展開して注目を集めた保険代理店
保険商品は、どの保険代理店が販売しても商品内容も価格も基本的には同じという性質があります。
そのため、提案力や信頼性といった「見えにくい価値」が重視される業界だといえます。
そんな中で、この保険代理店の経営者は「成果報酬型ではなく、一律報酬型の給与制度こそが業績拡大につながる」という、業界の常識とは真逆の持論を打ち出し、その考えを一冊の書籍として出版しました。
この書籍は大きな話題を呼び、問い合わせが急増。
保険契約の件数が増えただけでなく、保険会社からの講演依頼も相次ぐなど、出版をきっかけに存在感が一気に高まりました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、事例2:書籍出版により独自の強みをPRした会計事務所
税理士・会計士業界も、価格競争に陥りやすい分野の一つです。
特に中小企業向けの税務顧問業務では、「記帳や申告だけしてくれればいいから安くしてほしい」といった要望が多く、価格以外で選ばれる理由をいかに示すかが課題となっています。
このような状況の中で、東京と名古屋で会計事務所を開設している代表者は、自らの海外における勤務経験を活かして「海外へのビジネス展開におけるリスクやマネジメントのポイント」をまとめた書籍を出版しました。
その結果、「外資系企業やグローバル案件にも対応できる会計事務所」であることを伝えることができ、結果として他事務所との差別化に成功しました。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉【まとめ】価格競争から脱却し、本質的な価値で選ばれる企業を目指そう!
この記事では、価格競争のリスクや価格競争に巻き込まれてしまう原因、価格競争から脱却して価値で選ばれる企業になるための方法などについて事例を交えて解説しました。
価格競争から抜け出すためには、「安さ」以外の魅力を明確に伝え、選ばれる理由を構築することが不可欠です。
その手段の一つとして、注目されているのが書籍出版です。
フォーウェイが提供する「ブックマーケティングサービス」は、企業が持つ強みや創業の背景、商品・サービスに込めた想いなどをプロの編集者が丁寧に掘り下げ、書籍という形で見える化します。
書籍出版は、単なる宣伝だけでなく、「信頼性」「専門性」「共感力」を備えた強力なブランディング手段です。
書籍という形で自社の独自性や強みを明確化することで、価格ではなく価値で選ばれる企業を目指すことが可能になります。
書籍出版に少しでもご興味のある方は、ぜひ一度フォーウェイまでお気軽にご相談ください。


企業が10周年・50周年といった節目を迎える際、多くの担当者が悩むのが「周年記念をどのように進めればいいのか」という点です。
周年記念は単なるお祝い事ではなく、企業の価値や歴史、理念を再確認し、社内外に発信する貴重な機会でもあります。
しかし、「何から手をつければよいのか」「どのような施策が効果的なのか」「どの部署を巻き込むべきか」など、企画段階で考えなければならないことは少なくありません。
また、周年記念は「数年に一度」や「数十年に一度」と頻度が低く、社内にナレッジが蓄積されにくいため、ゼロから着手するケースも多いでしょう。
本記事では、そもそも「周年とは何か」という基本から、周年記念事業を行う目的や進め方、そして成果につなげるための施策例まで、わかりやすく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
◉企業の周年とは?

周年とは、企業が創業や設立のタイミングを記念して、10周年や50周年といった節目でお祝いやイベントを実施することです。
企業の創業50周年記念といった事業立ち上げからの節目を祝うこともあれば、ブランドの立ち上げ10周年などを祝うケースもあります。
会社のほか、店舗や病院施設、福祉施設、学校など、業種・業態に関わらず、節目を祝うイベントとして催されます。
このような節目のタイミングで、周年を祝う社内外の関係者を招くイベントや記念品の制作などを行うのが通例です。
◉企業が周年記念を行う目的

企業が周年記念を行う主な目的として、次の6つを挙げることができます。
| 企業のブランド力の向上社内外のステークホルダーとの関係強化企業の理念や歴史、ビジョンの再整理・再発信企業のブランド再構築のきっかけ社員のモチベーション向上と組織力の強化採用・広報活動の強化 |
以下では、それぞれの目的について詳しく見ていきましょう。
▶︎周年記念を行う目的については、関連記事【周年事業の目的と意義ーー社史・周年史制作のもたらすもの】もあわせて参考にしてください。
◉-1、企業のブランド力の向上
周年記念は、企業が長年にわたり顧客や社会から信頼を積み重ねてきた「確かな実績」を象徴するものです。
特に10年、20年、50年といった節目は、企業の継続性や安定性を社会に示す絶好のタイミングであり、ブランド価値を再定義・強化する重要な機会となります。
このような節目に合わせて、企業理念を込めたメッセージの発信や記念キャンペーンの実施、メディアへの露出を積極的に行うことで、取引先や顧客、さらには求職者に対して「信頼できる企業である」というイメージをより強く訴求することが可能です。
◉-2、社内外のステークホルダーとの関係強化
周年記念は、日ごろから支えてくれている顧客や取引先、株主、地域社会、そして社員に対し、感謝の気持ちを改めて伝える機会です。
たとえば、周年イベントの開催や記念品の贈呈、特別キャンペーンの実施などは、感謝の意を伝えると同時に、相互のつながりを強化する有効な手段となります。
◉-3、企業の理念や歴史、ビジョンの再整理・再発信
周年記念は、これまでの歩みを振り返るだけでなく、企業の原点や存在意義を改めて見つめ直す機会でもあります。
この節目を活かして、「なぜ自社が存在するのか」「どこへ向かっていくのか」という企業理念やビジョンを再整理して、社内外に向けて力強く発信することが可能です。
◉-4、企業のブランド再構築のきっかけ
周年記念は、企業がブランドを再構築する絶好のタイミングといえます。
たとえば、ブランドロゴの刷新やコーポレートメッセージの見直し、Webサイトのリニューアルなど、通常であれば社内外の調整に時間を要する大きな施策も、「○○周年を機に」という明確な理由があれば、受け入れられやすくなります。
節目となる周年をきっかけにすれば、大胆な変革も違和感なく自然に進めることができ、新たなブランドイメージを浸透させたり、企業の次なるステージを切り開くきっかけになったりするでしょう。
◉-5、社員のモチベーション向上と組織力の強化
周年記念は、社員一人ひとりの貢献を称える場としても活用できます。
これまでの歩みや成果を共有することで、「自分たちがこの企業の成長に携わってきた」という誇りや実感が生まれます。
記念式典での表彰や記念動画の上映などを行えば、感謝の気持ちを具体的に伝えられるでしょう。
また、部門を超えて協力する記念プロジェクトの推進は、社員同士の一体感を高めるとともに、組織力の底上げにもなります。
◉-6、採用・広報活動の強化
周年記念は、企業の魅力を内外に伝える広報・採用活動の強化にもつながります。
周年を機に企業理念や社風、ビジョンなどを再定義し、社史や小冊子、特設サイト、映像コンテンツ、SNSなどで発信することで、求職者に対して企業の価値観や文化をより明確に伝えることが可能になります。
また、周年をテーマとした特集や取材など、メディア露出の機会も増えやすく、企業認知の向上やブランドイメージの強化にも効果的です。
特に中小企業や成長中の企業にとっては、外部への認知度を高めるチャンスとなるでしょう。
◉企業の周年記念の方法

企業の周年記念の具体的な方法として、次の7つがあります。
・周年記念のイベント開催
・社外向けキャンペーン・プロモーション
・ノベルティ配布・プレゼント企画
・周年限定商品の販売
・コラボレーション施策
・感謝を込めたメッセージの発信
・オリジナルコンテンツの企画と制作 |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、周年記念のイベント開催
周年記念の方法として代表的なものはイベントの開催です。
従業員やその家族、取引先など、感謝の意を表明した自社に関係する多くの人たちを招くパーティーが節目で開催されます。
このような周年記念の式典やパーティーは、普段過ごしている会社とは異なる空間で実施することが多いです。
たとえば、ホテルなどの豪華な空間を貸し切って開催するなどが考えられます。
自社の周年記念式典およびパーティーの模様を動画に撮影して、後日DVDとして配布したり、広報の一環でプレスリリースを配信したりする方法も良いでしょう。
◉-2、社外向けキャンペーン・プロモーション
周年記念を機に、顧客への感謝を込めた社外向けキャンペーンやプロモーションを実施するのも効果的です。
たとえば「創業○周年記念感謝キャンペーン」として、SNSを活用したフォロー&リポスト企画や、記念品が当たるプレゼント企画を展開するといった方法が挙げられます。
また、特別割引や限定クーポンなどの特典を用意すれば、顧客の購買意欲を喚起し、売上促進にもつなげられます。
周年という明確なテーマがあることで、キャンペーンにストーリー性を持たせやすく、企業のブランドイメージの向上にもつながるでしょう。
◉-2-1、販促イベントの開催
周年記念を盛り上げる施策として、リアルイベントを活用した販促プロモーションも効果的です。
具体的には、以下のような企画が考えられます。
・スタンプラリー・抽選会・スクラッチカードといった参加型の企画
・キッチンカーや地域密着型の出店イベント
・お笑い芸人やパフォーマーを招いたステージ演出 |
来場者が楽しめる体験を企画することで、企業への親近感や好印象を高めることができます。
◉-2-2、周年キャンペーン
周年をきっかけにした、ユーザーに向けたキャンペーンや特典の提供も一つの手段です。
周年記念限定の割引クーポンを発行して、ユーザーにはSNSなどで拡散してもらえる効果が期待できます。
「周年」というキーワードを皮切りに話題性を醸成することで、多くのユーザーと新規でつながるきっかけとなり得ます。
◉-3、ノベルティ配布・プレゼント企画
周年記念を盛り上げる施策として、来店者や参加者への特典としてノベルティを配布するのも有効な方法です。
配布するノベルティは、Tシャツやマグカップ、ボールペンなど、日常的に使える実用性の高いアイテムがおすすめです。
企業ロゴや周年ロゴを入れたオリジナルデザインにすることで、記念品としての価値も高まり、ブランド認知の拡大にもつながります。
◉-4、周年限定商品の販売
周年記念で限定商品を制作して販売するのもよくある方法の一つです。
商品販売を主たる事業とする会社であれば、限定商品をWEBサイトや広告などで打ち出し、消費者にインパクトを与えることができるでしょう。
また、購入者特典としてノベルティをセットにするなど、付加価値を加える施策もおすすめです。
さらに、レストランといった飲食事業であれば、周年記念の限定メニューを提供するのも一案です。
普段は提供されない特別メニューだからこそ、特にリピーターに来店を促すきっかけとなるでしょう
◉-5、コラボレーション施策
周年記念を機に、地元企業や人気ブランドと連携し、コラボレーション商品を企画・販売する方法もあります。
また、インフルエンサーやクリエイターとタイアップした周年記念企画もおすすめです。
限定性や話題性のあるコラボレーション施策は、ファン層の拡大や新たな顧客層へのリーチにつながり、ブランド価値も高められるでしょう。
◉-6、感謝を込めたメッセージの発信
周年記念は、さまざまな人たちに感謝の気持ちを表明する貴重な機会です。
そこで、日ごろの感謝をメッセージカードなどに込めて、社員や取引先の人たちに贈ってみましょう。
周年ならではの貴重なギフトや記念品を用意するのもおすすめです。
◉-7、オリジナルコンテンツの企画と制作
周年記念の施策として、企業独自のストーリーや価値観を伝える「オリジナルコンテンツ」の制作も効果的です。
企業の歴史や理念、社員の声などを活かした多様な表現手段を通じて、社内外へのメッセージ発信とブランディングを強化することができます。
◉-7-1、記念動画
周年の節目に、自社の歩みやビジョンをストーリーとして表現した記念動画を制作する企業もあります。
たとえば、ドキュメンタリーやブランドムービーといった形式で、経営者・社員へのインタビューや現場の風景を織り交ぜることで、リアリティと共感性の高いコンテンツになります。
◉-7-2、周年誌・記念誌・社史
周年の節目をまとめた冊子やデジタルブックも、企業の歩みや価値を可視化する有力な手段です。
たとえば、「年表+エピソード+社員の声」といった構成でストーリー性を持たせることで、読み物としての魅力が高まり、社員の参画意欲も引き出せます。
冊子形式とデジタルブックの併用が一般的で、書店流通は行わないのが基本です。
特にBtoB企業においては、取引先や学生を対象とした採用活動における訴求力が高いことが特徴です。
▶︎周年誌の詳細については、関連記事【周年史とは?出版目的や具体的な制作の流れや活用方法について解説】もあわせて参考にしてください。
▶︎記念誌の詳細については、関連記事【記念誌とは?読んでもらうためのコツや活用アイデアを解説】もあわせて参考にしてください。
▶︎社史の詳細については、関連記事【読まれ、活用される社史を作るコツ!作成後の有効活用方法も解説】もあわせて参考にしてください。
◉-7-3、周年ロゴ・スローガン
ロゴやスローガン、キャッチコピーで周年の世界観を表現する方法もあります。
作成したロゴやスローガンは、名刺・封筒・Webサイト・SNSアイコンなどに展開することで、企業メッセージに一貫性が生まれ、社内外への浸透力が高まります。
◉-7-4、周年記念特設Webサイト・Webページ
周年の世界観を表現する専用のWebサイトや特設ページを制作することで、情報発信を強化できます。
コンテンツとしては、以下のような情報を掲載するのが一般的です。
・企業の歴史タイムライン
・周年のコンセプト
・紹介社員インタビュー
・記念ムービー
・イベント情報 |
イベント終了後もブランドページとして残すことで、持続的なプロモーション資産として機能します。
◉-7-5、書籍出版(企業出版)
周年記念の機会に「書籍出版」を行うことは、企業にとって価値の高い施策といえます。
ブランド資産や企業理念を整理し、社会的信頼性を伴ったメッセージとして可視化できる点が魅力です。
周年記念誌とは異なり、一般書籍として流通させることで、社内外への発信力や信頼性の向上が期待できます。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。

◉企業の周年記念の効果を高めるうえで重要なポイント

周年記念でよくある失敗が、次の4つです。
・準備不足でグダグダのイベントになってしまう
・見た目だけのイベントで終わってしまう
・費用対効果が合わない
・社内の共感が得られなくて終わる |
しかし、このような失敗をすることなく、周年記念を一つのきっかけとして、その後の会社の業績に良い影響を与えることは十分可能です。
具体的には、次のポイントを意識して計画する必要があります。
・1年〜2年前から資料収集をすすめる
・目的を明確にする
・多くの社員を巻き込む
・一貫性のあるコンセプトとメッセージ
・社外への積極的な発信
・周年記念を資産として残す工夫
・振り返りと効果測定 |
企業の周年記念の効果を高めるうえで重要な7つのポイントを見ていきましょう。
◉-1、1年〜2年前から資料収集をすすめる
周年記念に向けて記念誌や社史を制作する場合、大量の資料や記録の収集が必要となります。
過去の社内報や写真、社外の掲載記事、沿革データなど、情報は多岐にわたるため、プロジェクトが本格始動する前段階から、計画的に資料収集や整理を進めておくことが重要です。
早い段階で準備を始めておけば、制作スケジュールに余裕が生まれ、直前になって情報が不足するというトラブルを未然に防ぐことができます。
◉-2、目的を明確にする
周年記念の効果を高めるには、まず「なぜやるのか」「何を達成したいのか」という目的を明確に定めることが不可欠です。
ただ記念日を祝うという目的だけでは、単発のイベントで終わってしまい、その後に続く効果は得られません。
たとえば、「社員のモチベーション向上」「社外へのブランド価値発信」など、具体的な目的を設定することが重要です。
◉-3、多くの社員を巻き込む
周年記念を経営層主導の「自己満足イベント」で終わらせないためには、社員一人ひとりを当事者として巻き込むことが大切です。
具体的な取り組み例としては、以下のような施策が挙げられます。
・周年ロゴの社内コンテスト
・記念ムービーや記念誌への社員の声・写真の掲載
・若手社員を中心とした実行委員会の結成 |
実際にある大手企業では、周年記念の一環として小説仕立ての書籍を制作し、その企画・執筆を若手社員中心のプロジェクトチームが担当しました。
営業やSE、総務などの部署から有志メンバーが参加し、完成した書籍が実際に書店に並んだことで、参加社員のモチベーションや帰属意識が大きく高まったといいます。
このように、自らが関わった成果が形として残る経験は、社内での評価向上やプロジェクトの継続的展開にもつながりやすく、企業全体に良い影響をもたらします。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【本を出版するには?現役書籍編集者が本の出し方を分かりやすく解説】もあわせて参考にしてください。
◉-4、一貫性のあるコンセプトとメッセージ
周年記念の取り組みでは、企業の「らしさ」を体現した統一感のあるコンセプト設計が不可欠です。
ロゴやスローガン、Webサイト、パンフレット、イベント演出など、すべての要素に一貫したメッセージを通すことで、社内外に強い印象を残すことができます。
また、デザインやコピー、表現のトンマナ(トーン&マナー)を統一することで、ブランドの世界観を効果的に伝えることが可能です。
◉-5、社外への積極的な発信
周年記念は、社外に自社の魅力や存在感をアピールするチャンスです。
次のような複合的なPR手段を使って、計画的な情報発信を行っていきましょう。
・プレスリリース配信+記者向けイベント
・SNS(X、Instagram、YouTube)での周年企画・動画展開
・採用サイトや企業紹介資料への周年要素組み込み
・周辺記念書籍の出版
・周年記念Webサイトの作成 |
こうした施策を複合的に展開し、メディア掲載の機会を増やすことが重要です。
▶︎PRのやり方については、関連記事【企業が広報に使える媒体とは?種類や費用対効果の高い選び方を解説!】もあわせて参考にしてください。
◉-6、周年記念を資産として残す工夫
周年記念で制作したムービーや社史、写真、社員の声などは、継続的なコンテンツとして再活用できます。
たとえば、以下のような活用方法があります。
・採用資料や営業資料への再利用
・SNS投稿やオウンドメディアへの二次展開
・Webサイト内のストーリーページとしての常設掲載 |
周年記念のコンテンツを「1日限り」で終わらせず、長期的に活用することで、ブランド強化にもつながります。
◉-7、振り返りと効果測定
周年記念を終えた後こそ、次への改善に向けた振り返りが欠かせません。
効果測定の方法として、以下があります。
・アンケート・ヒアリングによる社内評価
・SNSでの反応、WebサイトのPV数、取引先からの反響などの外部評価
・成果をまとめたレポート化・社内共有 |
実施して終わりにするのではなく、成果の可視化と評価を通じて、次の周年企画や他のマーケティング施策へと活かしていきましょう。
◉企業の周年記念の計画・実施の手順
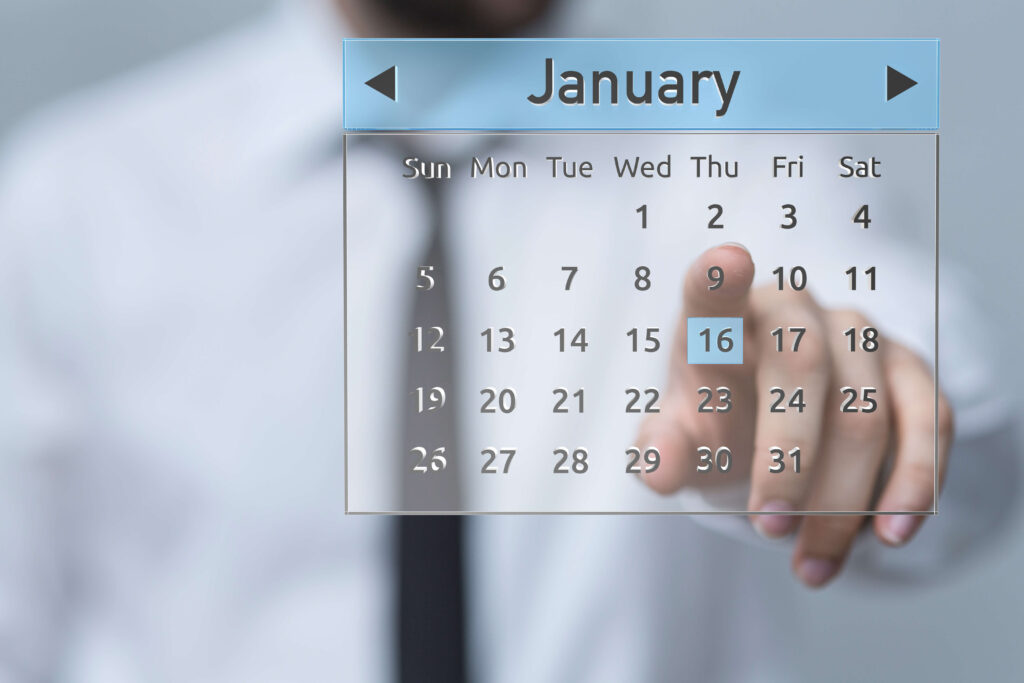
ここでは、企業の周年記念事業を計画・実施する手順について解説します。
一般的には、次の7つのステップで行います。
・ステップ1:【1年前】周年のゴール設定と目標の明確化
・ステップ2:【10ヶ月〜8ヶ月前】周年記念プロジェクト体制の構築
・ステップ3:【10ヶ月〜8ヶ月前】広報・宣伝戦略と大枠のスケジュールの決定
・ステップ4:【8ヶ月〜5ヶ月前】具体施策の企画・外注選定
・ステップ5:【5ヶ月〜2ヶ月前】制作と準備
・ステップ6:【1ヶ月〜当日】周年記念の実施
・ステップ7:【終了後】広報・宣伝戦略と大枠のスケジュールの決定 |
順を追って詳しく見ていきましょう。
◉-1、ステップ1:【1年前】周年のゴール設定と目標の明確化
周年記念のイベントをするにせよ、出版をするにせよ、ゴールの設定は最重要といえます。
周年事業を実施することで、「何を目指すのか」「どう見せたいのか」「どんなことを伝えたいのか」「何を作り出したいのか」といった目的をまず設定しましょう。
さらに、ターゲットの設定も重要です。
社員やその家族がメインのターゲットなのか、もしくは社外の取引先や潜在顧客、採用応募者がターゲットとなりうるのかなど、会社の予算を使って施策を実施する以上は、一つの経営戦略として施策実施後にどのようになっているのかの理想を思い描くと良いでしょう。
◉-2、ステップ2:【10ヶ月〜8ヶ月前】周年記念プロジェクト体制の構築
周年記念事業を成功させるために重要なポイントになるのが「どのようなプロジェクト体制を築くか」です。
準備段階を整えることが、プロジェクト全体の成功を左右するといっても過言ではありません。
まずは、各部門からメンバーを選出し、社内横断型の実行委員会を編成します。
役割ごとにチームを分けるのが一般的で、たとえば以下のような体制が想定されます。
・イベント企画チーム
・制作・クリエイティブチーム
・広報・PRチーム
・予算・進行管理チーム |
それぞれが明確な役割を持つことで、作業の抜け漏れを防ぎ、スムーズな進行を可能にします。
特に周年記念事業は、会社全体を巻き込んで進める「共創型」のプロジェクトとして設計することが重要です。
◉-3、ステップ3:【10ヶ月〜8ヶ月前】広報・宣伝戦略と大枠のスケジュールの決定
周年イベントを実施するには、広報や宣伝活動の戦略立案をしなければなりません。
周年事業をやる以上は知ってもらって、メディアにも取り上げられる、またとない機会だからです。
周年記念式典といったイベント実施の時期を確定させ、その期日に向けてプレスリリースや広告宣伝の準備を行いましょう。
イベントの規模にもよりますが、具体的な企画やアイデアを具現化するまでに半年程度は要すると考えられます。
そのため、広報や宣伝のスケジュールは全体で共有しながら丁寧に進めることをおすすめします。
◉-4、ステップ4:【8ヶ月〜5ヶ月前】具体施策の企画・外注選定
この段階では、周年記念の目的やゴールに基づき、「どのような施策を行うか」の具体的な中身を設計します。
たとえば、以下のような施策の組み合わせが考えられます。
・社内向け:記念式典、社員表彰、記念動画、記念誌
・社外向け:特設Webサイト、書籍出版、顧客向けキャンペーン、展示イベント
・ブランド強化:ロゴリニューアル、タグライン刷新、記念グッズ制作 |
必要に応じて外部パートナー(制作会社・PR会社・デザイナー・ライターなど)を選定してアサインします。
◉-5、ステップ5:【5ヶ月〜2ヶ月前】制作と準備
企画内容と外注先が決まったら、いよいよ実施に向けた制作フェーズに入ります。
記念映像やパンフレット、Webサイト、記念品など、制作物の進行管理に加えて、イベント運営に必要な備品や会場手配、登壇者との調整も行います。
制作はスケジュール通りに進まないこともあるため、修正対応や納期の遅れに備えて、余裕をもった工程管理が不可欠です。
トラブルが発生した際にも慌てず対応できるよう、事前の段取りを丁寧に進めておきましょう。
なお、周年記念に合わせて書籍出版を検討している場合は、他の制作物と比べて取材・執筆・編集などに時間がかかるのが一般的です。
そのため、1年前後の制作期間を見込んでおくとよいでしょう。
特に書籍は早い段階で企画を立ち上げ、全体スケジュールの初期段階から計画に組み込んでおくことが大切です。
◉-6、ステップ6:【1ヶ月〜当日】周年記念の実施
本番当日に向けて各施策の最終チェックを行い、運営チームで緊密に連携しながらリハーサルと確認作業を行います。
特にイベント当日は、「誰が・いつ・どこで・何をするのか」を明確にした詳細な運営マニュアルを準備しておくと安心です。
また、式典や展示の様子、参加者の表情などを写真や動画で記録しておくと、後日のレポート作成やSNS・メディアでの情報発信に活用できます。
◉-7、ステップ7:【終了後】振り返りと今後の情報発信計画の策定
周年記念の実施が無事終了した後も、それで終わりではありません。
施策の成果や社内外の反響を振り返り、今後の企業活動へとつなげる姿勢が大切です。
具体的には、以下のような対応を行います。
・社内向け:実施報告書の共有、アンケートによるフィードバック収集
・社外向け:公式レポートやSNSでの発信、メディア掲載記事の拡散 |
また、周年を機に自社の理念やビジョンを再整理した場合は、それをどのように情報発信していくのかという広報・宣伝戦略やスケジュールを決定します。
これらによって、周年記念事業が一過性ではなく、企業文化として根付くようになります。
◉近年は周年記念の書籍を出版する企業も多い!

近年では、その後のPRに長く活用できるという点や、通常の書籍と同様に書店流通することによる認知度向上の効果が期待できることから、企業出版を活用して書籍を出版する会社が増えてきています。
周年記念を機に書籍出版を行うことによる効果としては主に次の5つが考えられます。
・顧客ロイヤルティ向上に良い影響がある
・競合他社との差別化につながる
・出版を通じた認知度の向上につながる
・求職者にとって良いイメージがつく
・周年記念イベント後も営業・マーケティング・広報に活用しやすい |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、顧客ロイヤルティ向上に良い影響がある
周年記念の施策で重要な要素として考えられるのは、これまでの愛顧の気持ちをイベントやキャンペーンで表すことでしょう。
日ごろの感謝を示すイベントやキャンペーンを実施することで、顧客のロイヤリティ向上が期待できます。
たとえば、宝酒造の人気いも焼酎ブランド「一刻者」の20周年キャンペーンとして実施されたのが、「マストバイキャンペーン」です。
「頑固にこだわって20年」というキャッチフレーズを打ち出し、商品の購入者のうち抽選で500名に「一刻者」オリジナル陶器をプレゼントしました。
信頼の強固なロングセラー商品のファンに対して、オリジナル陶器をプレゼントすることでブランドのより一層のファン化が進んだ事例といえます。
◉-2、競合他社との差別化につながる
周年事業は、その貴重な機会をきっかけに競合他社との差別化を図る手段としても効果的です。
周年を記念した特別な企業ロゴを作れば、他社とは異なる印象をユーザーに印象付けることができます。
前述したキャンペーンやイベントなども差別化にはもってこいの方法ですが、ほか自社ならではの趣向を凝らしたノベルティを作成して配布するなどもおすすめの方法です。
このように競合他社では真似できない特別な手段を用いることで、現代ではSNSでユーザーが拡散してくれるPR効果も期待できるのです。
▶︎競合他社との差別化の詳細については、関連記事【差別化戦略の成功の秘訣ーメリットやデメリット、成功事例とは!?】もあわせて参考にしてください。
◉-3、出版を通じた認知度の向上につながる
周年史は、社内向けに配布するインナーツールと、社内外どちらにも訴求が可能になる流通書籍のタイプがあります。
この流通書籍として周年史を制作すると、一般の書店へ流通・配本されるため、一般読者への認知促進の効果が期待できます。
詳細は後ほどの事例紹介で解説しますが、会社の歴史を紐解く周年史を作ろうとして、結果的に自社製品にスポットを当てた出版をしたことで、全国各地の企業から「商品を仕入れたい」という声が殺到しました。
それだけでなく、出版をきっかけにテレビのディレクターの目にとまり、全国放送のバラエティ番組に著者の出演が決定。全国の視聴者に向けて自社製品のPRをすることができました。
▶︎認知度を上げる方法の詳細については、関連記事【経営者必読!認知度向上の方法と効果的なマーケティングの選択肢】もあわせて参考にしてください。
◉-4、求職者やその親にとって良いイメージがつく
一般市場に流通した書籍を出版している企業という箔がつくことで、求職者にとっては親御さんへの説得材料になります。
たとえば、競合他社に大手がひしめく業界で、書籍を手に取ったことをきっかけに親御さんから子どもに対して、「この企業を受けなさい」と中堅の企業を推薦した事例もあるほどです。
▶︎採用ブランディングのやり方については、関連記事【採用ブランディングとは?選ばれる企業になるための進め方とは】もあわせて参考にしてください。
◉-5、周年記念イベント後も営業・マーケティング・広報に活用しやすい
書籍は、周年記念イベントが終了した後も多方面で活用できます。
配布しやすく、自社の魅力や実績を効果的に伝えられるため、営業やマーケティング、広報活動をする際に役立つでしょう。
具体的には、営業提案時の資料として同封したり、リード獲得施策として配布したりすることで、信頼感を高めることができます。
また、書籍の内容をSNSと連動させて情報発信したり、一部を広報素材としてメディアに提供したりすることも可能です。
◉周年記念出版の成功事例

周年記念で書籍を出版して成功した事例は多々ありますが、ここでは次の3つの事例を紹介します。
・事例1:100周年記念出版をきっかけに商品が爆売れした老舗家具メーカー
・事例2:70周年記念出版が販路拡大に大きく貢献した食品製造会社
・事例3:30周年記念出版が中途採用に大きな効果を発揮した生命保険会社 |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、事例1:100周年記念出版をきっかけに商品が爆売れした老舗家具メーカー
ある老舗家具メーカーでは、創業100周年を機に記念書籍を出版しました。
著者は当時の経営トップで、廃業寸前の赤字企業をV字回復させた改革の手法を解説する内容となっています。
この書籍が人気テレビ番組の制作スタッフの目にとまり、後に番組出演のオファーへとつながりました。
番組放送後は企業サイトへのアクセスが集中し、サーバーが一時ダウンするほどの反響を呼びました。
結果として、出演からわずか1ヶ月間で前年の売上を超えるという大きな成果が得られたといいます。
なお、この書籍は100周年の前年に出版されたもので、周年事業全体も大きな盛り上がりを見せました。
◉-2、事例2:70周年記念出版が販路拡大に大きく貢献した食品製造会社
愛知県の食品製造会社は、創業70周年をきっかけに書籍を出版しました。
当初は社史の制作を検討していましたが、自社製品の有用性を訴求する書籍を出版することに方針転換しました。
一般的に使用されているサラダ油の過剰摂取に警鐘を鳴らし、その解決策としてこめ油の有用性を説いたのです。
この書籍が反響を呼び、全国から新規取引の問い合わせを獲得することができました。
また、TV番組への出演も決定し、メディアへのPRにも効果がありました。
◉-3、事例3:30周年記念出版が中途採用に大きな効果を発揮した生命保険会社
ある大手生命保険会社では、創業30周年の節目に、自社の理念や事業の意義を広く社会に伝える目的で記念書籍を出版しました。
同社は外資系保険会社との合弁によって日本市場に参入し、ライフプランニングという考え方をより多くの人々に理解してもらう必要性を感じていました。
その一環として、当時教育分野で高い実績を持ち、東京や大阪などの公教育改革にも関わっていた著名人に執筆を依頼。
教育と人生設計の視点を交えた内容により、幅広い層に共感を呼ぶ書籍が完成しました。
書店プロモーションは東京都、大阪府、愛知県などの大都市圏を中心に展開され、結果として7万部を超えるヒットを記録しました。
また、この書籍は社内にも好影響をもたらし、若手社員やマネージャー層への理念浸透に貢献。
さらに、中途採用の新入社員の多くが書籍を通じて企業への理解を深めており、ライフプランナーという職業に対する共感や憧れを育むきっかけにもなりました。
◉【まとめ】周年記念を「将来へ向けての再スタート」にしよう!
この記事では、企業が周年記念を迎えるにあたっての目的や意義、実施までの流れ、そして出版を活用した成功事例について紹介してきました。
周年記念は、企業のこれまでの歩みを振り返ると同時に、これからのビジョンを発信する機会です。
その想いや価値観を社内外に届ける手段として、注目されているのが「書籍出版(企業出版)」です。
フォーウェイが提供する「ブックマーケティングサービス」では、企業の歴史や価値観、創業者の想い、未来への展望などをプロの編集者が丁寧にヒアリングし、一冊の書籍として形にします。
書籍は、周年記念の場を一過性のイベントで終わらせず、その後の営業・採用・ブランディング活動にまで活かせる「資産」として活用できます。
周年記念にあたって書籍の出版にご興味をお持ちの方は、ぜひ一度フォーウェイまでご相談ください。
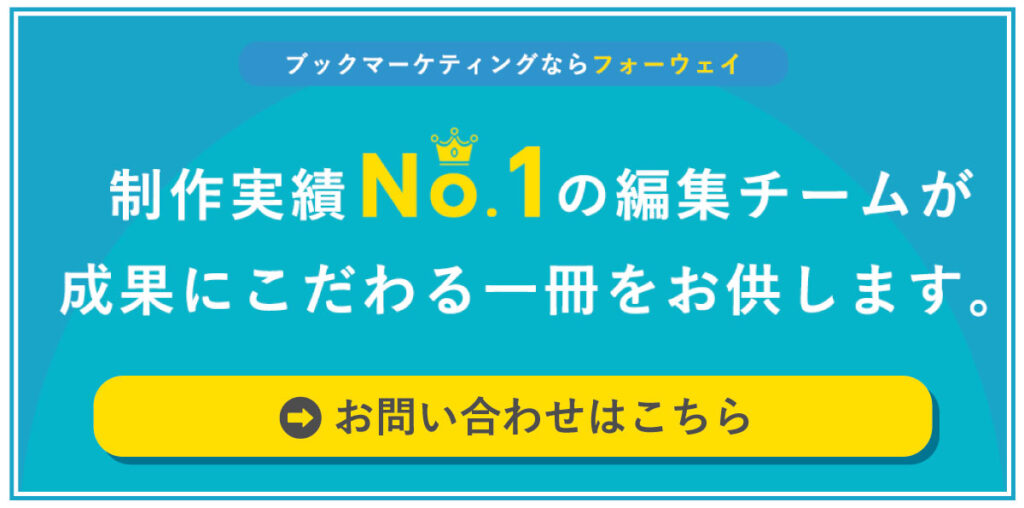

企業イメージは、無意識のうちに人々の判断や行動に大きな影響を与えています。
実際に、店頭に商品の価格や機能が同等のものが複数あっても、結局は「信頼できそう」「誠実そう」と感じられる企業イメージの良い方が選ばれやすくなります。
たとえば、広く知られている大手メーカーと無名のノーブランド品が同じ価格で並んでいたとしたら、多くの方が大手メーカーの商品を手に取るでしょう。
このように企業イメージは、顧客の購買行動や取引先、投資先、株主の判断、求職者の判断に大きな影響を無意識のうちに与えている重要な要素です。
しかし、企業イメージを良くしようと思っても、具体的にどのような方法が選択肢としてあるのか、分からない方も多いと思います。
本記事では、企業イメージを向上させるための方法について詳しく解説いたします。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉企業イメージとは?

企業イメージとは、顧客や取引先、株主などのステークホルダーが企業に対して抱く印象のことです。
また、外部からの印象だけではなく、企業内部の社員が持つイメージも含まれます。
「おしゃれ」や「高級感がある」、「リーズナブル」など、企業イメージはその企業の個性でもあり、資産でもあります。
商品やサービスの品質、広告の印象のほか、「社会貢献に積極的」といった企業の姿勢や取り組みなども企業イメージに関わる要素です。
ただし、企業イメージは良いものばかりとは限りません。
万が一、企業や社員の不祥事がニュースで流れたりSNSで拡散されたりすれば、一気に企業イメージが失墜する可能性もあります。
逆に、企業イメージを向上させれば、さまざまなメリットが生まれます。
◉企業イメージの向上で得られるメリット

企業イメージの向上で得られるメリットは、次の5つです。
・売上・利益の向上につながる
・優秀な人材の採用につながる
・顧客満足度の向上につながる
・従業員エンゲージメントの向上につながる
・投資家・株主・取引先からの信頼向上につながる |
以下の段落で、それぞれ詳しく解説します。
◉-1、売上・利益アップにつながる
企業イメージを高めることによって、売上や利益のアップにつながりやすいのがメリットの一つです。
イメージの良い企業が提供している商品やサービスならば、「使ってみよう」「試してみよう」といった前向きな購買行動が生まれやすくなります。
競合他社との差別化が生まれると、より顧客の興味を引く可能性も上がるでしょう。
また、イメージの良い企業には信頼も生まれ、取引先との間でも事業を有利に進めやすくなるのもメリットです。
良い企業イメージによって知名度が上がれば、結果としてさらなる売上や利益の拡大につながる可能性が高まります。
◉-2、優秀な人材の採用につながる
イメージの良い企業には、人材が集まりやすいメリットもあります。
現代の少子高齢化や労働人口の減少による人材不足の状況下では、優秀な人材の確保は重要な課題です。
イメージの良い企業は求職者の選択肢として検討される可能性が高く、実際に応募者も集まりやすい傾向があります。
また、企業のイメージが社会的に浸透していれば、家族や周囲からの理解や支持も得やすく、求職者にとっての安心材料にもなります。
企業の認知度が上がり、理念や企業文化が定着すれば、採用時のミスマッチが少なくなり、内定辞退率も低く抑えられるでしょう。
優秀な人材を採用しやすくするためにも、企業イメージを高めることが重要です。
◉-3、従業員エンゲージメントの向上につながる
企業イメージが良いと、社員は自分の職場に対して誇りや愛着を持ちやすくなり、仕事への意欲や満足度が自然と高まります。
モチベーションが高まれば、業務の質も向上し、結果としてより良い商品やサービスの提供につながります。
また、快適な職場環境は社内の人間関係や雰囲気にも良い影響を与え、離職率の低下も期待できるでしょう。
◉-4、顧客満足度の向上につながる
従業員のエンゲージメントの向上によって、顧客満足度にも良い影響を与えるメリットがあります。
エンゲージメントの高い社員は、業務に対して主体的に取り組むため、自ら発言したり、改善提案や新たなアイデアを出したりする機会が増えます。
その結果、商品やサービスの質が向上し、顧客への提供価値も高まるでしょう。
こうした好循環の背景には、企業イメージの良さが関係しているといえます。
ポジティブな企業イメージが従業員の誇りや帰属意識を高め、エンゲージメントの向上を後押しするのです。
◉-5、投資家・株主・取引先からの信頼向上につながる
企業イメージには、数値では測りにくい「信頼感」や「安心感」といった非財務情報も含まれます。
具体的には、以下のような要素です。
- コンプライアンス遵守
- 環境・社会・ガバナンス(ESG)への配慮
- 誠実な経営姿勢
- 情報開示の透明性
投資家や株主、取引先が関心を寄せるのは、財務情報だけにとどまりません。
コンプライアンスを遵守する姿勢や経営姿勢の誠実さなど、企業の信頼性を示す非財務情報にも注目が集まるようになっています。
また、社会問題やSDGsに対する関心が高まり、環境・社会・ガバナンスへの配慮がなされていることも企業を判断する重要なポイントです。
これらの姿勢が可視化されることで「この企業は信用できる」「長期的に安心して付き合える」という評価につながり、投資家・株主・取引先から信用を得やすくなります。
◉企業イメージを向上させる4つの手法
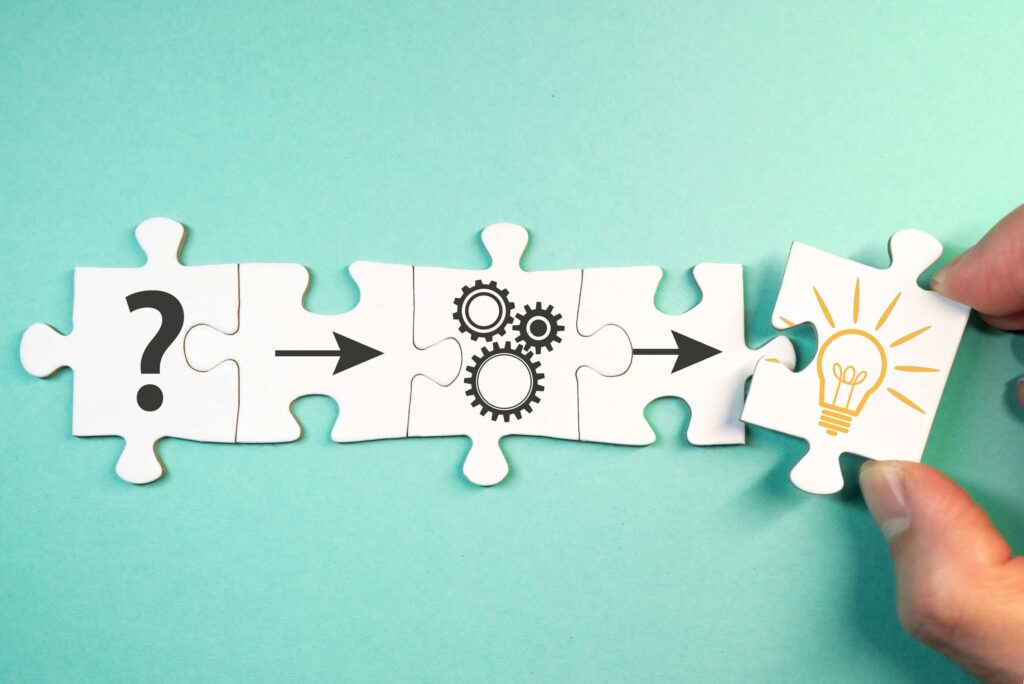
企業イメージを向上させる手法として、主に以下4つがあります。
・アウターブランディング
・インナーブランディング
・採用ブランディング
・ストーリーブランディング |
それぞれの手法を以下の段落で詳しく解説します。
◉-1、アウターブランディング
アウターブランディングは顧客や取引先など、社外に向けたブランディング活動のことです。
具体的な施策は、以下の3つがあります。
・ロゴやブランドカラーを決める
・インパクトのあるキャッチコピーを作る
・広告やCMでアピールする |
以下の段落では、それぞれの施策をさらに掘り下げます。
▶︎アウターブランディングのやり方については、関連記事【企業ブランディングとは?効果や具体的な8つの手法を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
◉-1-1、ロゴやブランドカラーを決める
企業のイメージを広く浸透させるために有効な方法の一つが、ロゴやブランドカラーを決めることです。
一目で企業を想起できるようなロゴや、ブランドを象徴するカラーを用いることで、視覚的に印象づけるブランディングが可能になります。
また、コンセプトが伝わるパッケージデザインを決めて、発信するのも効果があります。
◉-1-2、インパクトのあるキャッチコピーを作る
耳に残るキャッチコピーやつい口ずさみたくなるキャッチコピーを作成するのも効果的です。
必ずしも企業名が入っている必要はありません。
聴覚に訴えることで、その言葉から企業を連想してもらうことができれば、十分な効果が期待できます。
聞いた瞬間にその企業が思い浮かぶようなキャッチコピーが定着すれば、ブランドの認知が高まり、効果的なブランディングが実現できたと評価できます。
◉-1-3、広告やCMでアピールする
商品やサービスの強みなどを、広告やCMで発信するのもアウターブランディングの手法です。
また、企業文化や経営のビジョンのアピールも、他社との差別化になります。
従来のような紙媒体の広告やテレビCMに加え、WebサイトやSNSも活用すると効果的です。
◉-2、インナーブランディング
インナーブランディングは、社内に向けたブランディング活動です。
インナーブランディングを実施し、社員の企業に対する理解が深まったり、業務に対する考え方が浸透したりすれば、従業員エンゲージメントの向上に役立ちます。
具体的な施策は、次の3つがあります。
・働き方改革に取り組む
・経営陣と社員で企業理念を共有する
・健康経営に取り組む |
以下の段落で各施策を掘り下げます。
▶︎インナーブランディングのやり方については、関連記事【インナーブランディングとは?組織としての連携を強化し企業価値を高めるための手法を解説】もあわせて参考にしてください。
◉-2-1、働き方改革に取り組む
働き方改革への取り組みは、インナーブランディングを行ううえで大切な要素です。
職場が働きやすい環境になれば、従業員エンゲージメントの向上が期待できます。
具体的には、以下のような取り組みです。
・柔軟な働き方(テレワーク・フレックスタイムなど)を推進する
・長時間労働を是正する
・業務を効率化する |
働きやすい環境作りに力を入れることで、従業員のエンゲージメントや帰属意識の向上を目指しましょう。
◉-2-2、経営陣と社員で企業理念を共有する
企業イメージを良くするためには、社員が経営陣と企業理念を共有していることも重要です。
業務に対する考え方や行動が社員に浸透すれば、モチベーションのアップにもつながります。
一方で、社員が自社の企業理念を共有できていないと、外部に向けた効果的なアピールもできません。
特に企業規模が大きくなると、理念を全社員に浸透させることが容易ではなくなります。
そのため、経営陣と社員が直接関われる場を設けたり、研修を実施したりなど、企業理念を深く理解できるように働きかけることが大切です。
◉-2-3、健康経営に取り組む
健康経営とは、企業が社員の体や心の健康に配慮する経営のことです。
具体的な施策としては、以下が挙げられます。
・定期検診の受診率を上げる
・生活習慣病予防対策やメンタルヘルス対策に力を入れる
・ワークライフバランスを推進する |
心身の健康は、業務のパフォーマンスにも大きな影響を与える要素です。
また、健康経営に取り組むことで、「社員を大切にする会社」というポジティブなイメージを社外にも与えることができます。
◉-3、採用ブランディング
採用ブランディングは、求職者に向けて行う採用にフォーカスしたブランディング活動を指します。
人材の採用において、企業イメージは重要です。
採用ブランディングでは企業の魅力を発信し、優秀な人材の確保を目指します。
主な施策は、以下の3つです。
・福利厚生を充実させる
・教育体制を充実させる
・社会貢献への姿勢をアピールする |
以下の段落で、それぞれ詳しく解説します。
▶︎採用ブランディングのやり方については、関連記事【採用ブランディングとは?選ばれる企業になるための進め方とは】もあわせて参考にしてください。
◉-3-1、福利厚生を充実させる
採用ブランディングでは、「この会社で働きたい」と思ってもらえるように魅力をアピールすることが重要です。
なかでも、福利厚生は求職者の多くが就職先の企業を選ぶ基準の一つです。
もし、仕事内容や給与などの条件が同じであれば、福利厚生が充実している企業が選ばれる可能性が高いでしょう。
たとえば、休暇制度や各種手当はもちろんのこと、社内イベントやクラブ活動への支援など、自社独自の制度も魅力的なアピールポイントになります。
こうした福利厚生の内容を採用ブランディングにうまく取り入れることで、企業としての働きやすさや社風を具体的に伝えることができ、求職者からの共感や関心を得やすくなるでしょう。
◉-3-2、教育体制を充実させる
教育体制を充実させることも、採用ブランディングでは効果的です。
具体的には、研修制度を設けたり、自己啓発や資格取得の支援を充実させたりするといった施策があります。
また、キャリアパスを具体的に示すことで、求職者は入社後をイメージしやすくなります。
教育体制をアピールする際は、特に他社にはない特徴や独自の取り組みを盛り込むと、その企業ならではの要素をアピールできるでしょう。
◉-3-3、社会貢献への姿勢をアピールする
近年、さまざまな社会課題への関心が高まるなかで、企業の社会貢献活動に注目する求職者が増えています。
そのため、採用ブランディングにおいても、社会貢献に対する姿勢を積極的に発信することが有効です。
環境問題や社会的な課題、SDGsなどに対する取り組みを明確に伝えることで、自社の価値観にマッチする人材を集めやすくなります。
◉-4、ストーリーブランディング
ストーリーブランディングは、企業や創業者の思い、商品・サービスについてのストーリーを発信する手法です。
発信方法には、大きく分けて2つあります。
・WebサイトやSNSで発信する
・経営者の思いを「物語」として伝える書籍を出版する |
2つの手法について、以下の段落でそれぞれ解説します。
▶︎ストーリーブランディングのやり方については、関連記事【ストーリーブランディングとは?企業の物語を伝えてファンを作る方法】もあわせて参考にしてください。
◉-4-1、WebサイトやSNSで発信する
ストーリーブランディングでは、企業が持つストーリーや自社の商品・サービスについて、紙媒体のパンフレットのほか、WebサイトやSNSを活用して発信します。
他社と似た商品やサービスを提供していても、創業者の思いや現在に至るストーリーは同じではありません。
そのため、アプローチしたいターゲット層に合わせて媒体を選び、ストーリーを効果的に発信する必要があります。
▶︎情報発信の方法については、関連記事【企業の情報発信に有効なツールはどれ?効果的に活用するコツも解説】もあわせて参考にしてください。
◉-4-2、経営者の思いを「物語」として伝える書籍を出版する
ストーリーブランディングのなかでも、特に経営者の思いなどを書籍にまとめて出版する方法が「ブックマーケティング(企業出版)」です。
書籍はインターネット上の情報よりも「信用できる」と感じる人が多く、書籍を出版している企業自体の信頼度も自然と高まりやすいというメリットがあります。
また、書籍という媒体を活用することで、ここまでに解説した以下のような複数のブランディング効果を一度に得ることができます。
・アウターブランディング
・インナーブランディング
・採用ブランディング
・ストーリーブランディング |
書籍の出版は、企業のブランド価値を多角的に高める有効な手段です。
経営者の想いを「物語」という形で発信することで、社内外の信頼を深め、自社の価値をより強く社会に届けることができます。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。

◉書籍出版により世の中の企業イメージを向上させた成功事例
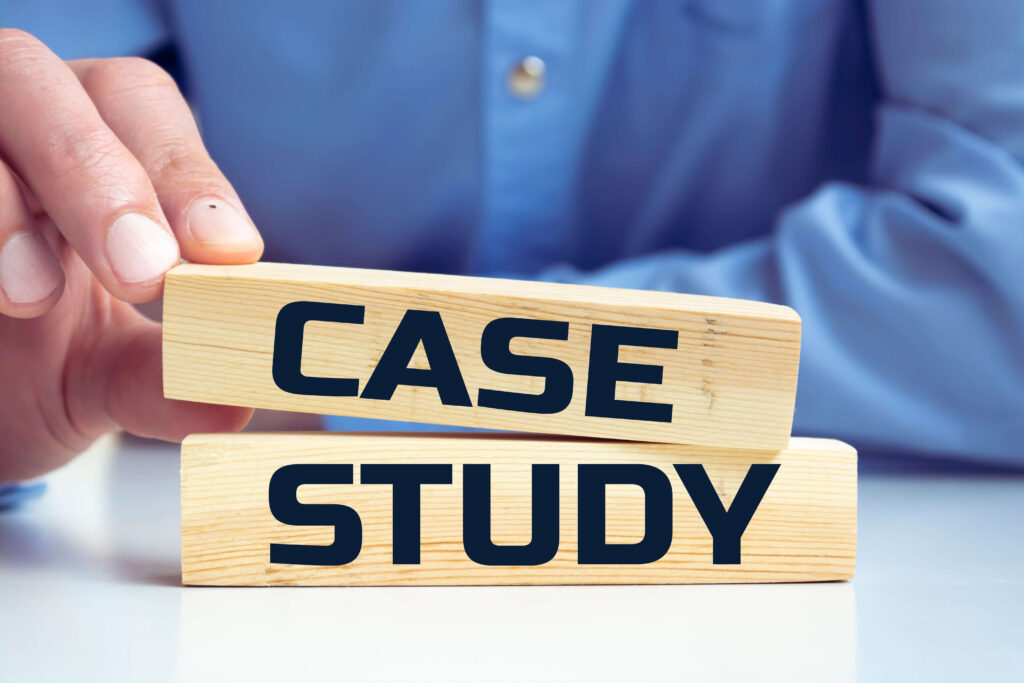
実際に書籍出版で企業イメージを向上させた事例を2つ紹介します。
・差別化が難しい業界で独自の企業イメージを確立した保険代理店
・自社のコンセプトを世の中に広めることに成功した公認会計士事務所 |
それぞれの実例を以下で詳しく見ていきましょう。
◉-1、差別化が難しい業界で独自の企業イメージを確立した保険代理店
扱う商品での差別化が難しい保険業界で、書籍出版により独自のイメージを確立した保険代理店の事例です。
この代理店では、同業他社からのコンサルティング依頼を目的として書籍を出版し、発売直後から複数の依頼がありました。
出版をきっかけに業界内での評価が高まり、大口案件の獲得や大手企業からの講演依頼など、長期的なブランディングにも効果が出ています。
出版にあたって社長自身も自分の成長を実感し、社員の意識にも良い影響を与えているようです。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、自社のコンセプトを世の中に広めることに成功した公認会計士事務所
コンセプトを書籍で発信し、自社の強みをアピールすることに成功した公認会計士事務所の事例です。
書籍を通じて、代表者が米国・英国で培ったキャリアや、日本企業の海外子会社での監査経験に基づく「海外進出で失敗する日本企業の実態」をストーリー仕立てで発信しました。
その結果、自社の専門性を明確に打ち出すことができ、出版後は同業者の協力も得て拡散されています。
また、セミナー登壇の依頼がすぐに入り、商談にも直結するなど、出版の効果が短期間で現れました。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉企業イメージに関するよくある質問
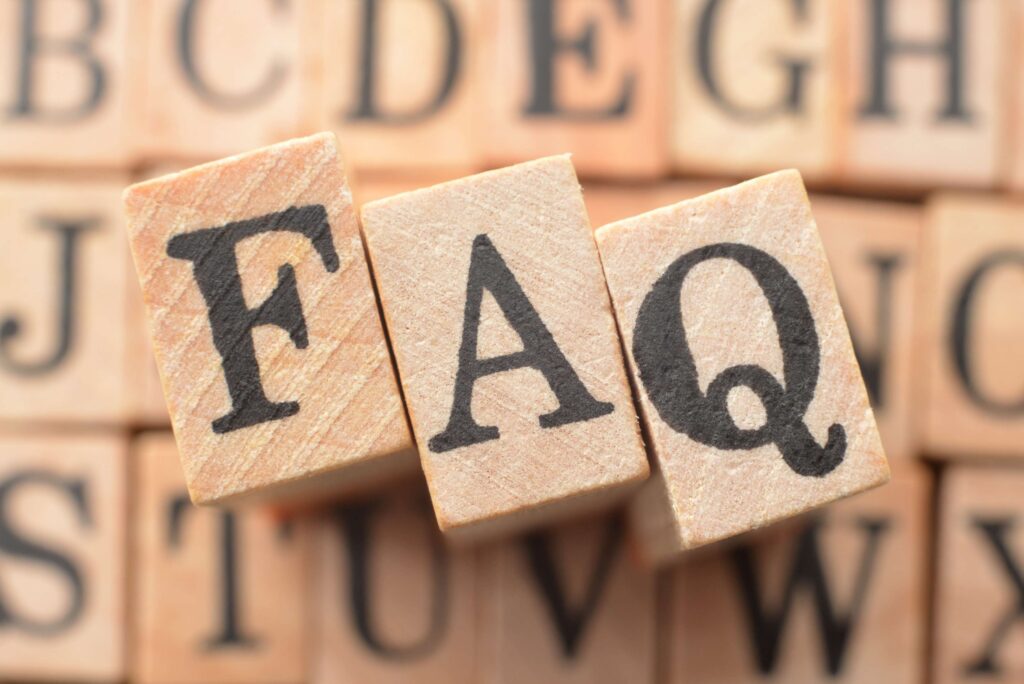
企業イメージに関してよく疑問に思われるのが、「一度毀損してしまった企業イメージは回復できるのか」という点です。
以下で毀損してしまった企業イメージを回復できる可能性も含めて、詳しく解説します。
◉-1、一度毀損してしまった企業イメージは回復できる?
企業イメージは感情や印象に基づくものであるため、ネガティブな印象が強いと定着しやすいのが特徴です。
しかし、条件がそろえば、回復できる可能性は高くなります。
実際に不祥事を起こしても、その後に復活した企業は少なくありません。
大企業でいえば、ユニクロの外国人技能実習生への待遇に関する批判や、不二家の製造管理に関する不祥事などがありました。
一度毀損してしまった企業イメージの回復に必要な条件は、以下の4つです。
・迅速で誠実な初動対応(謝罪など)
・透明性のある情報開示
・原因究明と再発防止策の提示
・長期的な信頼回復のための継続的施策 |
企業イメージを毀損してしまった場合、まずは迅速な対応が求められます。
そして、イメージを毀損してしまった内容について、透明性のある情報開示を行うことが重要です。
原因究明や再発防止策の提示、信頼を回復するための継続的な施策にも真摯に取り組む必要があります。
◉【まとめ】企業イメージを高めて自社の魅力をアピールしよう!
企業イメージが良ければ、売上・利益の向上や優秀な人材の確保、従業員エンゲージメントや顧客満足度の向上につながります。
また、企業イメージは、投資家・株主・取引先から信頼を得るためにも重要です。
企業イメージを向上させる手法は、アウターブランディングやインナーブランディング、採用ブランディング、ストーリーブランディングの4つがあります。
なかでも企業の歴史や価値観、経営者の思いを「物語」として丁寧に伝え、社内外の共感を生む手段としてブックマーケティングが効果的です。
フォーウェイでは出版を中心にクライアントの成長を支援しており、ブックマーケティングのサービスを展開しています。
企業イメージを高める施策を求めているのなら、フォーウェイのブックマーケティングを検討してみてください。


企業のターニングポイントである周年。
周年は一つの節目で、社員や取引先へ感謝や今後のビジョンを示す良い機会となります。10周年や50周年、100周年と、周年事業を検討する企業のタイミングはさまざまです。
頻繁に実施する施策ではないため、企業側にノウハウがないということも珍しくありません。
そこで、今回は周年事業を実施する目的と意義を整理し、周年事業の方法や社史・周年史制作について解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
◉周年事業の目的とは

周年事業とは、企業の一種のアニバーサリーという見方もあります。とはいえ、イベントを実施するにも予算がかかります。
企業として記念事業を実施するという場合、やはり目的を整理しておくのがよいでしょう。
まず、周年事業を実施するにあたり、「社内向け」か「社外向け」かで目的は大きく変わります。それぞれ確認していきましょう。
◉-1、社内向け周年事業の目的は社員のモチベーションを上げビジョンを共有すること
企業が創業・設立から10周年、20周年、30周年と会社を存続させることができるのは、働く社員全員が現場で貢献してくれているからです。
2021年度の企業の倒産件数は6,015件と、2000年以降で最少という低水準でした。
しかし、過去10年を振り返ると、計85,939件と決して少ない数字ではありません(帝国データバンク倒産集計を参照)。
中小企業白書によると、企業の存続率(生存率)は1年後が約97%、5年後が約82%、10年後が約70%と減少していき、22年後は50%を下回ると言われています。
そんな中、周年を迎えられる企業は、非常に価値あることであり、そこに社員の活躍がある点は無視できません。
そのため、周年事業は企業を支える全てのステークホルダーに対して、感謝の意を示すとても良い機会なのです。
通常、社員は業務に従事しているため、社員全員が集結する機会はあまりありません。
経営者の考え方や会社の理念、今後のビジョンを示し、社員に日頃の感謝の意を表明することで、モチベーション向上を狙うことが可能になります。
未来に向けてのビジョンを共有することで、社員も何のために業務にあたっているか、何のためにその会社で働いているかを今一度再認識することができ、全社的に一体感を生み出すことが期待できます。
社内向けの目的は次のような内容が考えられます。
・社員に感謝を伝える機会
・会社の歴史や理念の理解促進を図る
・社員間のコミュニケーション活性化
・社員のモチベーション向上
・今後のビジョンや経営計画の共有
◉-2、社外向けの周年事業の目的は取引先との関係性強化
周年事業は対外的に発信することも意義があります。
働く社員はもちろん必要不可欠ですが、会社存続のためには取引先も大きな存在です。
仕事を円滑に進めるためやサービスの価値を向上させるためのパートナー企業の存在や会社の売上に欠かせないクライアント企業などです。
会社としての今後のビジョンを意思表明することも大切ですし、周年という機会を使ってこれまでの実績や今後の取り組みについてPRすることも同時に重要です。
社外向けの目的は次のような内容が考えられます。
・取引先に感謝を示し、関係性強化を図る
・企業イメージの刷新や再認識
・新商品や新サービスの発表や販売促進のためのプロモーション
・周年の記念商品やサービスを販売して売上向上を図る
社内向けと社外向けそれぞれで目的が異なるため、目的に合わせた施策を実施することを検討しましょう。
◉周年事業の方法とは

企業の大事な節目となる周年事業に何を実施したらよいのでしょうか。
まずは社内向けと社外向けそれぞれで考えられる代表的な方法を紹介します。
◉-1、社内向け:社員旅行で結束力を高める
社内向けに周年事業としての取り組みを実施する目的は、社員同士のコミュニケーション活性化やモチベーション向上が挙げられます。
そこで、「社員旅行」は社員同士が長時間一緒に過ごし、さらに普段自分たちでは行くことが難しい旅行先に会社の予算で行けるという非日常体験は、モチベーションを上げるのに効果的な手段の一つです。
ただし、社員が多ければ、人数分の旅費がかかり、旅行先の滞在費も高額な予算を用意する必要があります。
さらに長時間会社の行事で拘束されることを好まない社員もいるでしょう。
そのように社員の意に反した周年事業になると、逆にモチベーションや帰属意識が下がるなどの危険性すらあります。
◉-2、社外向け:周年記念キャンペーンで特別感あるサービスを提供
周年という節目は、対外的な発信に成功すれば、メディアにも取り上げてもらえる可能性が高まります。
そこで「周年記念キャンペーン」と銘打った特別な商品やサービス、記念品を提供することで、取引先との関係性強化を図ることが可能です。
会社としては売上や利益向上が狙えるため、会社の存在感や業績を上げるよい機会となるでしょう。
ただし、キャンペーン内容の企画自体が魅力的なものでないと、結果的にさほど売上にも繋がらない可能性も考えられます。
どのように告知をするかというPR手段も検討する必要があり、肩透かしな施策とならないように注意しましょう。
◉-3、社内・社外向け:記念式典を開催
社内と社外どちらにも周年をきっかけに企業としてのあり方をアピールするとしたら、「周年記念式典」を開催するのが通例です。
社員や取引先など関係者を1ヶ所に集めることで、社員同士だけでなく、社員と取引先の関係性構築にも繋がるよい機会となります。
呼びかけをする人数によって規模感や予算の検討が必要ですが、会社としての今後のビジョンを発信する場としてもこの上ないチャンスです。
ただし、新型コロナウイルスの流行もあり、1ヶ所に大人数が集まることにためらいのある人も多いでしょう。
全国各地から人を呼ぶことを鑑みると、そのための交通費・旅費もかかってくるため、予算が潤沢にある企業でないと実施は難しいかもしれません。
◉企業のメッセージを社内外に発信するには周年史の制作がおすすめ

周年事業の重要性はここまでに紹介したとおりですが、社内外同時にメッセージが発信できる手段として周年史制作があります。
社員の帰属意識を高めるために「社内報」という手段もありますが、簡易的なパンフレットやチラシのような社内報を作っても、いずれ捨てられるのがオチです。
そこで企業や創業者・代表者の考え方を色濃く反映させた周年史の制作は、周年事業の一環として効果的な方法です。
◉-1、周年史の作り方と目的の整理
周年事業としての「周年史」の作り方は、マーケティングやブランドの設計と同様に、まずは目的を明確化させることが最重要です。
社員向けであれば、「周年史で何を知ってほしいか」「周年史を読むことをきっかけにどう行動してほしいか」など、作った後の目的をしっかり定めた方が軸のある意義あるものができます。
社外向けも同様で、「周年史でイメージを刷新したい」「普段のコミュニケーションだけでは伝えきれない会社としての理念やメッセージを理解してほしい」など、なぜ社外の取引先に読んでもらいたいかを明確化させることです。
そのうえで、企業向けの出版や周年史制作を請け負っている出版社や制作会社、印刷会社などに依頼をして制作しましょう。
ただ、社員にも取引先にも読んでもらえる読み応えのある企画にするためには、企業出版や周年出版を手掛けた実績のある出版社や出版コンサルタントに相談することをおすすめします。
◉-2、出版すれば社員のモチベーション向上や社外へのPRが同時に実現可能
周年事業として大々的に周年史・社史を制作するのならば、書店に流通させる出版という選択肢も検討したいところです。
前述した周年史制作の目的にもよりますが、社内向けだけでなく、社外にもメッセージを発信したいとき、書店に流通させることで、一石二鳥で社内外どちらへのアピールにも繋がります。
たとえば、出版社の流通戦略によって、商圏や社員の居住地域を中心に配本を実施することで、社員は活動範囲内の書店に自分が働く会社の本が置かれていることに誇りを感じ、モチベーションが上がるのです。
一般市場に流通されるため、既存の取引先だけでなく、新規の取引先にも自社の存在を知ってもらう機会となります。
くわえて、会社の存在を知ってもらうという意味では、採用面でも効果が期待できます。会社の出版物を読んで入社いただくことで、帰属意識が高まり、採用後の定着率向上にも寄与します。
自社では自分たちが把握できる範囲で、社員や取引先に書籍を配布して読んでもらうことも可能です。
出版物は著作権も企業に帰属するため、書籍内のコンテンツは会社のホームページ等で二次利用することもできるので、活用の幅はとても広いのです。
▶企業の出版については、関連記事【企業の自費出版を考えるーー効果的な戦略の組み立て方と出版社の選び方】もあわせて参考にしてください。
◉【まとめ】50年、100年と未来に存続していくために周年事業は超重要
以上のように、周年事業は企業のこれまでとこれからの立ち位置を再認識して、関係各所との関係性を強化するためにとても大切です。
これまでの会社の歴史を振り返り、今後のビジョンを社内外に発信することで会社はさらに成長することができます。
周年事業は企業の一大イベントです。周年のタイミングの1年前〜2年前に準備を開始する企業も多く、その期間を利用して入念に準備をしていきましょう。


世の中は情報に溢れ、企業が情報発信しても全く見られなかったり、読まれなかったり、反応がほとんどなかったりが当たり前の時代。
・HPを作って情報発信を行ってみたけれど、閲覧者がほとんどいない…
・SNSで情報発信をしているが反応がいまいち…
・色々な媒体で情報発信を行っているのに、成果につながらない… |
そんな情報発信に関する悩みを抱え、どの情報発信ツールをどのように使えば良いのかが分からなくなっている経営者や広報・マーケティング担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、情報過多の時代にしっかりとターゲットに自社の情報を届けるために知っておくべき企業の情報発信に有効なツールや、それぞれの効果的な活用方法などを詳しく解説いたします。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉企業の情報発信に有効なツール一覧

企業が情報発信するために有効なツールとしては、以下のようなものがあります。
◉-1、HP(ホームページ)
HPは企業が情報発信を行うための軸となる情報発信ツールの1つです。
HPでは、主にミッションやビジョン、行動指針といった経営方針や、会社の沿革、行っている事業や商品・サービスの紹介、所在地や代表者名のような会社概要など、企業の基本情報を発信します。
HPに掲載する内容を定期的に更新したり、ブログ機能をつけてお知らせをしたり、「スタッフブログ」や「コラム」で記事という形で情報発信をしたり、比較的自由に情報発信を行うことができるというのが特徴です。
また、HPは銀行口座の開設や融資の審査などの際にHPの情報が求められたり、企業の信頼性を図る一つの指標ともなっており、企業の情報発信の基幹となる必須ツールとも言えるでしょう。
しかし、HP上で発信した情報をターゲットに見てもらえるまでにはタイムラグが発生するため、時間の経過とともに変わるトレンド性や即効性の高い情報の発信には不向きです。
恒久性のある情報をきちんと保存していく情報発信媒体として活用するのが効果的と言えます。
なお、HPをただ単に作っただけでは見てもらえません。
URLをSNSなどでシェアしたり、SEO対策をして検索結果で上位表示させたり、ブログ投稿で入り口を増やしたりするなど、HP上で情報発信を行っていることを周知していく施策を合わせて行う必要があります。
◉-2、SNS
SNSは気軽に情報を発信してフォロワーとの間でコミュニケーションを取ることができるツールです。
リアルタイムで膨大な情報が流れており、拡散性が高い反面、情報の寿命が短いという特徴があります。
また、SNSといっても多くの種類があります。
それぞれ、情報発信の方法やユーザー層、特性が異なるので、企業が発信したい情報や、ターゲットに合わせてSNSを使い分けていくことが大切です。
| SNS名 | 国内月間アクティブユーザー数 | 主なユーザー層 | 情報発信の方法 | 特性 |
| LINE | 9,600万人(2023年9月時点) | 全世代(中でも50代が多め) | ・LINEメッセージ | 自社サービスと連携してメルマガや1to1施策で活用できるSNS |
| YouTube | 7,120万人(2023年5月時点) | 全世代 | ・ショート動画・動画 | 世界最大の動画SNS。インフルエンサーマーケティングに活用される |
| X(旧Twitter) | 6,658万人(2024年1月時点) | 20代〜30代が過半数 | ・140文字以内の投稿・長文の投稿・画像 / 動画 | リアルタイム性のある情報が投稿され、情報拡散しやすい、一方で炎上しやすいSNS |
| Instagram | 6,600万人(2023年12月時点) | 20代〜30代で半数を占める | ・画像・リール動画・ストーリー | 雑誌感覚で食や美容、メイク、ファッションなどビジュアルの情報発信と相性が良いSNS |
| Facebook | 2,600万人(2019年3月時点。それ依頼発表なし) | 30代〜50代が多い | ・文章 / 画像 / 動画による投稿 | 実名登録がマストなため、安心感があり、ビジネスシーンでの活用が多いSNS |
| TikTok | 2,800万人(2024年2月時点) | 10代〜20代で半数を占める | ・ショート動画 | エンタメ系の投稿と相性が良く、企業の採用などによく使われるSNS |
▶︎SNS運用については、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】もあわせて参考にしてください。
◉-2-1、X(旧Twitter)
X(旧Twitter)は140文字の短文でコミュニケーションをするSNSです。
国内の月間アクティブユーザーは約6,658万人(2023年5月時点)で、若年層のユーザーが多い傾向にあります。
X上では、リアルタイム性の高い情報が日々飛び交っており、情報拡散がしやすいのが特徴。
興味を引く投稿はリポストなどによって拡散されて爆発的な集客を得ることもできます。
フォロワーからの反応も早いため、たとえば、次のようなトレンド性や即効性の高い情報の発信に向いています。
・新商品やサービスのティーザー(「あと数日で販売開始」など)
・期間限定のキャンペーン告知
・システム障害などの緊急情報
・時事性の高い情報 |
こういった特徴から東北大震災など災害の際の現地情報収集元として活用されたり、選挙活動など政治などにも活用されています。
一方で、投稿した情報がすぐに古くなってしまうため、あまり変化のない情報発信には向いていません。
むしろ、HPやWebメディアで発信した恒久的な情報を広く拡散するためにXを活用したりします。
◉-2-2、Instagram
Instagramは画像や動画の投稿がメインのSNSです。
国内の月間アクティブユーザーは約6,600万人(2023年12月時点)で、メインユーザーは20代~40代です。
総務省の「令和5年 情報通信に関する現状報告の概要」によれば、特に20代の利用者が最も多く、約78.6%の人が利用。
次いで10代(約72.3%)、30代(約57.1%)と利用者が多くなっています。
また、性別で言えば女性ユーザーの利用が約59%と多くなっています。
2017年に「インスタ映え」という言葉が流行語大賞を受賞したように、食や美容、メイク、衣類、アクセサリー・雑貨などの見た目のビジュアルが重要な情報発信と相性が良いのが特徴です。
近年、ビジネスアカウントの登場や、ストーリーズ、リール動画などさまざまな機能が追加された上、投稿から商品ページに直接遷移するショップ機能がついたため、自社で販売する商品やサービスの情報発信やブランディングなどに活用する企業も増えてきています。
一方で、ビジュアルで訴求が難しい情報との相性が悪いため、文章での情報発信や訴求には向いていません。
◉-2-3、Facebook
FacebookはMeta社が運営する全世界の利用者数が30億人を超える世界最大のSNSで、他のSNSとは違い、実名利用が必須なので炎上しにくく、ビジネスユーザーの利用が多いのが特徴。
国内の月間アクティブユーザーは約2,600万人(2019年3月時点、それ以降発表なし)で、30代~50代のユーザーが多い傾向があります。
実名登録が必須という制度上、企業の代表や営業マンなどが情報を投稿したり、DMで営業メールを送ったり、人主体での発信がメインになってしまうため、企業主体の発信には利用されない傾向があります。
企業による情報発信の場合、プラットフォーム内に年齢や性別、居住地、趣味・嗜好、行動傾向など膨大なデータが蓄積されており、精度の高いターゲティングができるということから、広告などが主に活用されます。
◉-2-4、TikTok
TikTokは中国発のショート動画SNSです。
15〜60 秒の短尺動画の投稿がメインです。
国内の月間アクティブユーザーは約2,800万人(2024年2月時点)で、総務省の「令和5年 情報通信に関する現状報告の概要」によれば、10代の利用率が約62.4%、20代の利用率が46.5%と多いことから、若年層向けの情報発信におすすめのSNSです。
X(旧Twitter)と同様にトレンド性の高い情報との相性がよく、拡散性も高いのが特徴。
1つの動画が一気に数千、数万、数十万回再生されるなど、話題になると一気に情報が拡散していきます。
若年層のユーザーが多いことや、エンタメ性のある投稿が多いことから、企業の採用活動などに活用されることが多くなっています。
◉-2-5、YouTube
YouTubeは世界最大の動画共有サイトで、国内のアクティブユーザーは約7,120万人(2023年5月時点)です。
ショート動画と長尺の動画が投稿でき、自社の商品やサービスに関連する有益な情報を分かりやすく紹介したり、YouTuberなどとコラボしたインフルエンサーマーケティングなどに活用されます。
Google社が運営しているため、Googleの動画検索などに表示ができ、SEO効果が期待できるのも特徴です。
YouTube内でも検索需要があり、動画の概要欄などを最適化してYouTubeの検索結果で上位表示を目指すことでより閲覧されるように工夫することも可能です。
▶︎Youtube動画については、関連記事【YouTube動画の作り方をカンタン解説!初心者でも再生回数を稼ぐテクニック】もあわせて参考にしてください。
◉-2-6、note
noteは文章や写真・イラスト・音楽・映像などの作品を配信できるブログ形式のサイトで、月間アクティブユーザー(ブラウザ数)は約5,145万人(2023年11月現在)です。
クリエイターやビジネスパーソンなどにブログとして、自社のノウハウや商品・サービスの開発背景などの情報発信に利用されています。
最大の特徴は、記事コンテンツの有料販売ができる点です。
情報発信自体を収益化することができます。
◉-2-7、LINE
LINEはLINEヤフー株式会社が運営するメッセージ型のSNSです。
国内の月間アクティブユーザー数は約9,700万人で、SNSというよりはメッセージアプリという印象が強いかもしれません。
企業アカウントを作成することで、友だち登録してくれたユーザーに向けてメッセージやクーポン・キャンペーン情報を送ることができたり、メルマガのような感覚で情報発信ができるのが特徴。
LINEから直接HPやECサイト、予約ページに遷移させたり、さまざまな機能が備わっていたり、個別にメッセージを送れたり、メルマガシステムなどに比べて気軽にユーザーと密にやりとりできる情報発信ツールとして多くの企業に活用されています。
◉-3、メルマガ
メルマガは登録した顧客やステークホルダーに、自社の製品やサービス、イベント、キャンペーンなどの情報を定期的に発信するツールです。
近年ではMA(マーケティング・オートメーション)ツールと連携して顧客の行動やステータスなどによってメールを出し分けたり、OnetoOne施策に欠かせないものとなっています。
また、見込み客獲得や顧客教育や、引き上げ(アップセル)になくてはならないツールと言えるでしょう。
送られたメールは新しく届くメールにどんどん流されていくため、新商品・サービスの販売、セミナー開催などの告知情報など、即効性やトレンド性の高い情報発信に適しています。
◉-4、オウンドメディア
オウンドメディアは企業が所有する情報発信メディアの総称です。
たとえば、自社のHPで更新しているコラムや、HPのサブドメインや別ドメインで運営するジャンルの情報発信に特化したWebメディアなどがオウンドメディアに該当します。
アメブロやはてなブログなどのブログサービス、noteなどのSNSなどと比べて、自社の意思によって自由に情報発信やコンテンツの保存ができ、第三者に削除されないという特徴があります。
一方で、記事を更新したからと言ってすぐに見られることはありません。
あるキーワードでの検索順位が上がったり、更新した記事をメルマガやSNSなどで告知することで見てもらえるようになってきます。
そのため、即効性やトレンド性の高い情報発信には向いていません。
知っておくと便利なお役立ち情報や知識、悩みの解決方法など長期間変わらないような情報発信に適しています。
▶︎SEO対策については、関連記事【SEO対策とは? 効果的な戦略の組み立て方と対策方法】もあわせて参考にしてください。
▶︎参照:オウンドメディアのメリット・デメリットとは?成果を出すポイントを解説! | COUNTER株式会社 | 埼玉県越谷市のデジタルマーケティングカンパニー
◉-5、ブログ
ブログはもともと個人の意見や情報を公開するプラットフォームでしたが、現在では企業の情報発信や集客ツールとしての利用が多くなっています。
「アメブロ」「はてなブログ」などのブログサービスを利用したり、自社HP内にブログ機能を設置して情報発信を行うのが一般的なやり方です。
自社HPに設置したブログを更新した場合は、オウンドメディアと同様にすぐに見られることはありませんが、ブログサービスを利用した場合には、「新規更新欄」などに掲載されるためSNSのnoteと同様に比較的早く見てもらうことができます。
そのため自社スタッフの日記など、リアルタイムの情報発信であればブログサービスの方が適しています。
検索経由でしっかりと発信したい情報などであれば自社HPに設置したブログを利用する方が良いと言えるでしょう。
◉-6、プレスリリース(PR)
プレスリリースは企業からメディアに向けた公式な情報発信手段です。
新商品や新サービスの発表や業績報告・業務提携・キャンペーンの案内などをメディアに対して行い、Webメディアや雑誌、新聞、TVなどで取り上げてもらうことが目的です。
ターゲット層が多く閲覧している各メディアに取り上げられることで認知獲得につながる可能性があります。
メディア側は常に新しい情報の種を探しているので、時代性やトレンド、今までになかったような切り口での情報発信を心がけることで、取り上げられやすくなります。
◉-7、Googleビジネスプロフィール
GoogleビジネスプロフィールはGoogleマップ上でビジネス情報を発信できる無料のサービスです。
たとえばGoogleマップ上で「駅名 居酒屋」と検索すると、多くの居酒屋の情報が出てきます。
表示できる情報は所在地・営業時間・電話番号・最新情報などがあり、最新情報を活用すると新商品・キャンペーン情報をタイムリーに発信することが可能です。
Googleマップ上に表示される情報であるため、店舗のあるビジネスとの相性が良いのが特徴。
店舗系ビジネスではぜひ活用しておくべき情報発信ツールと言えるでしょう。
◉-8、DM
DMは企業がターゲット層に郵送や電子メールを送付するという情報発信方法です。
具体的にはターゲット層の企業のリスト1つひとつにDMを郵送したり、企業のメールアドレスに直接広告メールを送付したりします。
郵送DMはコストはかかるものの、実体のあるものが届きますので比較的レスポンス率が高く、顧客の認知や関心を高めることが可能です。
利用できるクーポンなど次のアクションにつなげやすいオファーをつけておくのがポイントです。
メールについては基本的に無視されますが、郵送DMほど手間をかけずに多くのリスト向けに送付できるというメリットがあります。
郵送DMは確度の高いターゲット層向けや、高単価商品・サービスの場合、メールについてはBtoB向けの商品・サービスの場合、などうまく使い分けをしていくことが重要です。
◉-9、チラシ
チラシは1枚の紙の両面または片面に情報を印刷したものです。
商品やイベントなどの案内・告知を目的として大量に配布するために利用されます。
代表的な配布方法は、新聞折込チラシ・ポスティング・街頭ビラ配りなどです。
実態のあるものがターゲットに届くため、WebやSNSなどに比べて見てもらいやすいのがメリットと言えます。
地域密着型のビジネス(水道修理、士業、マッサージ店、美容院、不動産など)におすすめの情報発信方法です。
しかし制作に手間とコストがかかるので、ターゲット層の多いエリアをしっかりとセグメントをした上で配布していくのがポイントです。
◉-10、パンフレット
パンフレットは複数枚の紙を折り曲げて重ねて冊子にした印刷物です。
会社案内や製品・サービスの詳細な紹介など、情報量の多い用途に利用されます。
WebやSNS、また1枚もののチラシやDMとは違い、何度も作り直したりすることは難しいため、中長期で変わらないような情報の発信に向いています。
一方で、「パンフレットをきちんと作れるようなしっかりとしたところなんだ」という紙媒体ならではの信頼性のアピールにもつながるのが特徴です。
また、パンフレットはWebやSNSとは違い、机に並べて比較検討しやすいということもあり、大学や学習塾、老人ホーム・介護施設、建設会社など、商品やサービス、取引先選びの際に比較検討をするような業界の情報発信ツールとしてもおすすめです。
▶︎パンフレットのマーケティング活用については、関連記事【商品やサービスが売れるパンフレットを作るポイントと有効活用方法】もあわせて参考にしてください。
◉-10-1、パンフレットによる企業の情報発信成功事例
ある投資スクールでは、投資に興味があるものの何から取りかかれば良いのか分からないという人に向けて「入校を後押しする」パンフレットを制作。
パンフレットの中で、投資スクールのサービス内容や講師陣、受講料などの説明のほかに、実際に投資スクールを受講して利益を得た人のインタビューを掲載したり、メディア実績を掲載したりして、信頼性が得られるような工夫を行いました。
その結果、パンフレットを読んで「自分でもできるかもしれない」という気持ちになった多くの方から問い合わせが増え新規入校者の増加につながっています。
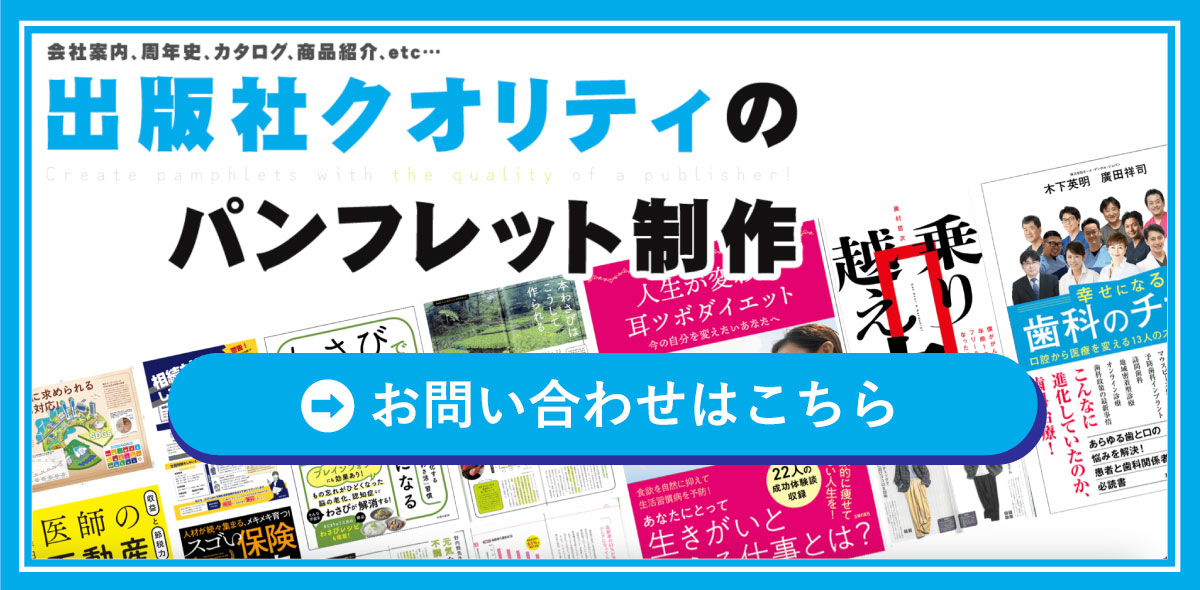
◉-11、名刺
名刺は名前や会社名・所属・住所などのプロフィールを記載した情報発信ツールです。
ビジネス上の初対面の相手に自分のプロフィール情報を伝えるのに適していますが、話のきっかけづくりや、後で見返した時に相手が興味を持つような工夫をするのがおすすめです。
掲載できる情報は少ないですが、うまく興味を惹くことができれば新規顧客の獲得にもつながる可能性があります。
◉-12、書籍
書籍は自社や自社の商品・サービスのことをより詳しく知ってもらいたい場合に有効な情報発信ツールです。
書籍の最大の特徴は社会的信頼性が高いことで、出版をきっかけに各種メディアに取り上げられたり、著者がセミナー講師に招かれたりすることもあります。
また、WebやSNSとは違い「読まれる媒体である」ということが大きな特徴です。
一般的な書籍の場合、7万字~10万字もの情報を盛り込むことができます。
そのため、商品やサービスの情報だけでなく企業の歴史・創業者の想い・理念・開発秘話などをストーリー性を持ってまとめて伝えることが可能です。
ただし、出版しただけで読まれる訳ではないですし、注目される訳でもないので、その点には注意しましょう。
出版後の書店配本はもちろんのこと、SNSやクラウドファンディング、SEOなどあらゆるデジタルマーケティングを駆使して、ターゲットの手元に届けることができてはじめて効果を発揮します。
信頼性の高さから、不動産投資や保険、コンサル、住宅など、契約までのリードタイムが長い業界、富裕層向けビジネス、広告規制が厳しい健康食品やサプリなどの情報発信に向きます。
また、競合が多すぎて差別化が難しいような業界や、あらゆるWebマーケティングなどをやり尽くした後のさらなる会社の発展、認知度拡大のための情報発信ツールとしても有効です。
▶︎ブックマーケティングについては、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】もあわせて参考にしてください。
◉-12-1、書籍による企業の情報発信成功事例
ある保険代理店の経営者は、保険業界の実態と保険業界に定着している「成果報酬型」の給与体系を「一律報酬型」に変えることによって業績向上が目指せるという持論を世に問うために書籍を出版。
その結果顧客や同業者からの見られ方が大きく変わって、大型契約などの成約に成功したり、講演会の講師に招かれたりするようになりました。
書籍の出版によって自社の信頼性が高まって、商談の際に顧客企業の経営にまで踏み込んだ相談を受けるケースも出てきています。
本来の出版目的であった、同業の保険代理店からのコンサル依頼がまず数件。そして驚いたのは、保険会社から講演の依頼が来たり同業支援の話が回ってきたりと、「保険会社にとって頼れる代理店」というありがたいイメージを持ってもらえるようになったことです。保険代理店はコンビニより数が多いうえ、扱う商品で差別化ができません。保険会社側から一目置いてもらえる代理店になることの価値はとても大きいんです。
引用元:【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店 |
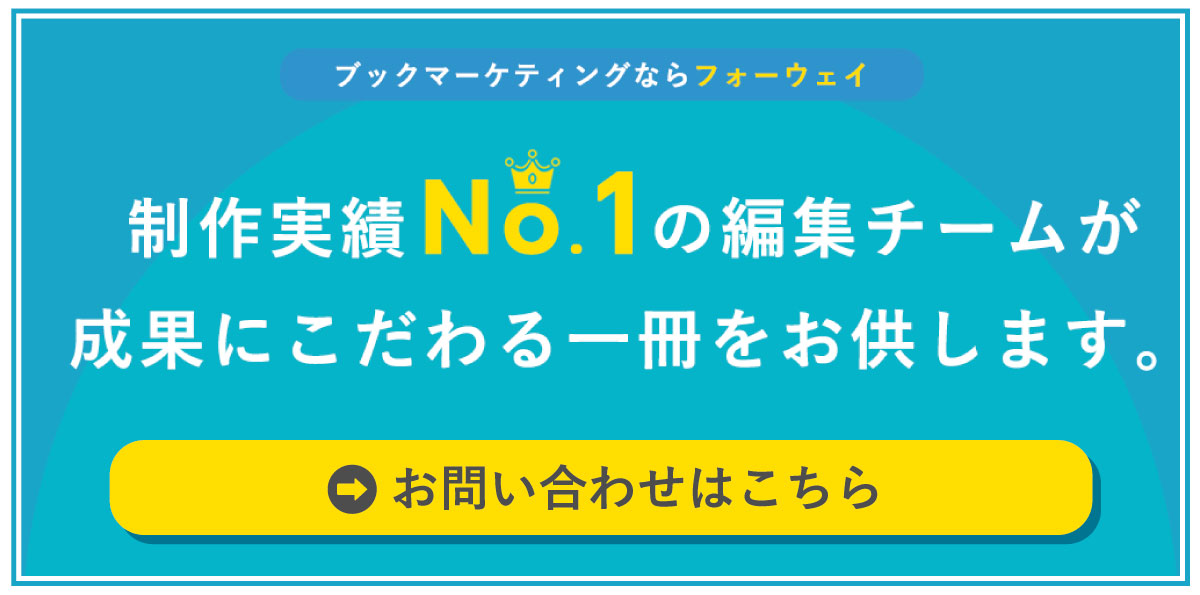
◉-13、ニュースレター
ニュースレターは、主に企業のファンづくりのためのコミュニケーションツールとして定期的にメールや郵送で配信されるものです。
ターゲットは顧客だけではなく、株主や従業員・メディア関係者などのさまざまなステークホルダーです。
DMが広告宣伝を主目的としているのに対して、ニュースレターは企業に対して親しみを持ってもらうことに重きを置いていることが特徴です。
そのため、商品やサービスの情報というよりはむしろ関連するお役立ち情報や、企業の社長、社員、スタッフなどのインタビュー、などの情報発信に向いています。
Web上のブログなどと比べて読まれやすく、印象に残りやすいのがメリットと言えるでしょう。
◉-14、Web広告
Web広告はインターネット上のメディアに掲載される広告の総称で、検索時に表示される広告やSNSで表示される広告などです。
Web広告と言っても広告の出し方や出す媒体によって、次のように多くの種類があります。
・リスティング広告
・ディスプレイ広告
・アフィリエイト広告
・記事広告
・動画広告
・メール広告
・SNS広告 |
そのため、年齢や性別などの属性によってターゲティングをして、特定のターゲットに向けて効率的に広告を配信することができるという特徴があります。
また、Web広告の閲覧数やクリック数などを集計してほぼリアルタイムに広告効果を分析でき、分析結果を見ながら訴求内容やターゲットの変更が行えるのも特徴の1つです。
コラムのような読み物系ではなく、商品やサービスの宣伝に向く情報発信ツールです。
◉-15、TVCM
テレビ番組の途中や番組の間に放送されるCMを活用する方法です。
企業が自社の商品やサービスの宣伝をするために、テレビ局のCM枠を購入して広告を配信します。
TVCMは年代や性別を問わず幅広い視聴者へ効率的に情報発信を行えるマス広告の一つで、即効性があり商品やサービスの認知や購買意欲を促進するというメリットがあります。
大きく認知を広げていきたい時におすすめの情報発信方法と言えるでしょう。
地方ローカル局や、TverなどのネットTVなど比較的安価で活用できるTVCMも増えてきていますが、キー局などは数千万円〜数億円など多額の費用がかかるので、なかなか情報発信方法としてはハードルが高い方法と言えます。
また、番組を見ている視聴者層や、曜日、時間帯などのターゲットは可能ですが、Web広告のように細かなターゲティングができず、広告効果の測定が難しいというデメリットもあります。
◉-16、デジタルサイネージ
デジタルサイネージは駅や店舗・施設・オフィスなどに、ディスプレイやプロジェクターを設置して情報を発信するシステムです。
従来ポスターや看板で情報発信していたものが、デジタルサイネージに置き換わってきています。
最初にデジタルサイネージが使われたのは駅構内でしたが、最近では各種店舗や病院・宿泊施設・銀行・学校などあらゆるところに設置されています。
◉情報過多の中、企業が情報発信ツールを効果的に活用するポイント

これまでに紹介してきたように多くの情報発信ツールがありますが、これらを何の意図もなく使っているだけでは効果的な情報発信はできません。
次の3つのポイントを押さえた上で、明確な意図と戦略をもって情報発信ツールを使い分けることが企業の情報発信のコツです。
◉-1、情報発信の目的を明確にする
情報発信をする際は「誰に何を伝えて」「どうしたいのか」という目的を明確にする必要があります。
なぜなら目的に応じた最適な情報発信ツールを選定しなければならないからです。
たとえば数日限定キャンペーンの応募者を増やす目的で、即効性やトレンド性の薄いHPを選択しても期待する効果は得られないでしょう。
情報発信の目的が「集客や問い合わせ数や売上数の向上」なのか、「認知度を拡大していきたい」のか、「世の中に周知したい」のかなどを明確にすることが大切です。
◉-2、情報発信ツールの得意・不得意を把握する
情報発信ツールには得意・不得意があるので、これをきちんと把握しておく必要があります。
たとえばX(旧Twitter)は拡散性が大きいため話題性やトレンド性のある情報発信は得意ですが、しっかりと文章を読みこんでもらいたい長文の情報発信は不得意です。
Instagramは画像や動画で視覚的に訴求するような情報発信は得意ですが、文章での情報発信は不得意です。
このように、「自社の発信したい情報をうまく訴求できる媒体は何か?」をしっかりと考えた上で情報発信ツールを選定していく必要があります。
◉-3、デジタルとアナログをうまく組み合わせる
企業の情報発信では、デジタルとアナログをうまく組み合わせることが効果的です。
たとえば、リコーが行なった「DM実証実験結果」によれば、顧客をWebサイトに誘導する手段としてeメール(メルマガ)を使っていましたが、開封率は13.8%、Webサイト遷移率は1.5%と低い成果しか出ていなかったそうです。
そこでeメール送付後に紙のDMを送る検証実験を行ったところ、Eeメールの開封率が5.5倍の75.8%に、Webサイト遷移率が3.4倍の4.4%に大幅に向上。
つまりデジタルだけでは弱かった訴求が、アナログの強みをうまく組み合わせることによって大きな相乗効果が得られることが確認できたのです。
このように、デジタルの時代だからデジタルだけを活用するのではなく、アナログの特性も活かしていくことでより効果的な情報発信が可能になります。
▶︎デジタルマーケティングとアナログマーケティングの効果的な活用については、関連記事【デジタル全盛期だからこそ重要なアナログマーケティング戦略】もあわせて参考にしてください。
◉-3-1、デジタルとアナログをうまく組み合わせた成功事例
ある不動産投資会社の経営者は、医師をターゲットとして「高収入な医師に最も効果的な節税対策は不動産投資である」という書籍を出版。
企画段階からSNSやクラウドファンディングなどのデジタルのプロモーションを検討し、出版タイミングに合わせて実施しました。
その結果、狙い通りに多くの医師に書籍を購入してもらうことができ、書籍を購入した医師から成約を獲得して売上を倍増させることに成功。
また、既存顧客からの口コミなどによって評判が広がり、新規顧客の獲得にもつながっています。
書籍というアナログな情報発信ツールとSNSやクラウドファンディングなど、デジタルな情報発信ツールを組み合わせ成果につながった好例と言えます。
◉【まとめ】情報発信ツールを効果的に活用しよう!
本記事では企業の情報発信に有効なツールの特徴や企業が効果的に活用するためのポイントについて解説しました。
情報発信ツールには多くの種類がありますので、目的を明確にしたうえで適切なツールを選ぶことが大切です。
また、デジタル全盛の現代だからこそ、デジタルとアナログをうまく組み合わせることが効果的です。
デジタルマーケティングと書籍やパンフレット、チラシなどアナログマーケティングとの組み合わせをお考えなら、まずはフォーウェイにご相談ください。
お悩みや課題に合わせて最適なご提案をさせていただきます。
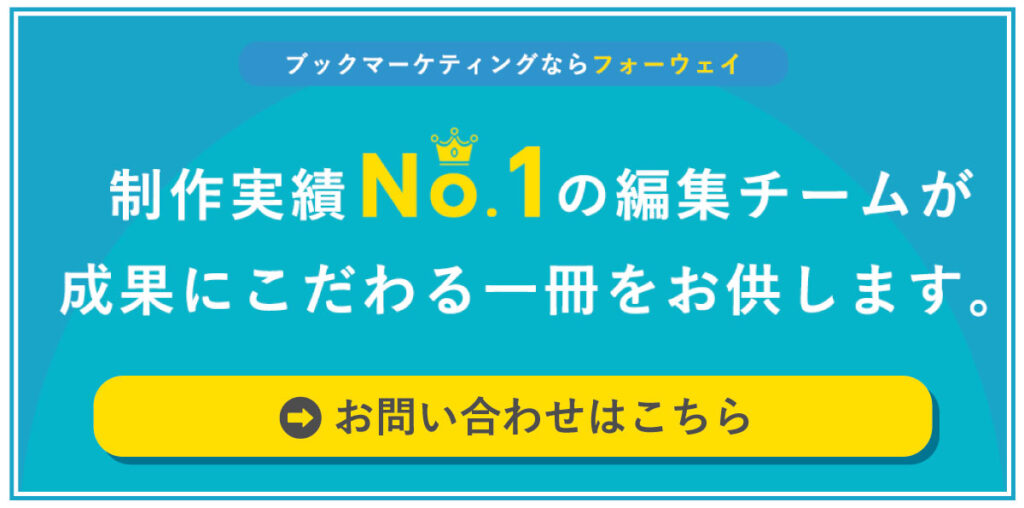
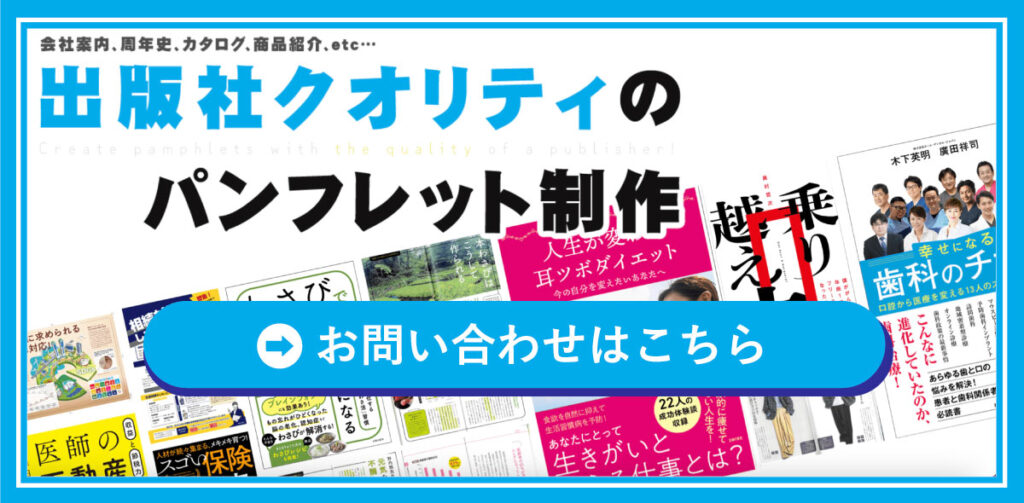

インナーブランディングは、企業価値を高め業績の向上につなげるために欠かせないものです。
社内に目を向けず対外的なブランディングばかりに力を入れていたら、「思ったほど効果が上がらなかった」という経験をした方は多いのではないでしょうか。
企業ブランディングや事業ブランディングなどの対外的なブランディングはもちろん重要ですが、より高い効果を得るためにはインナーブランディングの実施が必要不可欠です。
この記事では、インナーブランディングとはどのようなものか、企業が実施する場合のメリット、効果的な手法を詳しく解説いたします。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉インナーブランディングとは?

インナーブランディングとは、企業が理念、ビジョン、価値観などを従業員に浸透させ、社内からブランド力を強化するための取り組みで、インターナルブランディングとも言います。
従業員が企業の一員としての自覚を持ち、従業員自身がブランドを体現できる存在になることを目的としています。
たとえば、企業が新しいスローガンを掲げた時に、「スローガンの意味をより詳しく説明したポスターや動画を社内で共有する」「全社ミーティングなどで、経営者がスローガンに込めた思いを語る場を設ける」などはインナーブランディングの一例です。
このように、まずは働いている企業が大切にしていることを深く理解してもらい、ブランドのファンになってもらうことでモチベーションや社員エンゲージメントを高めることが期待できます。
従業員が自社のブランドを理解して誇りを持って働いていれば、顧客対応においても自然にその価値観が表れるようになるという良い循環が生まれるのです。
◉-1、アウターブランディングやエクスターナルブランディングとの違い
アウターブランディング(エクスターナルブランディング)とは、主に顧客や取引先、株主、社会全体などの社外ステークホルダーに対して、企業のブランド価値やイメージを向上させるための取り組みを指します。
一方で、インナーブランディングは社内の従業員に向けて行われるブランディング活動です。
たとえば、新しいブランドロゴを発表した時に、アウターブランディングでは、記者発表やプレスリリースなどの手法を用いて、社会全体に認知してもらうのが目的です。
一方で、インナーブランディングでは、新しいロゴに込めた想いを社員に向けて説明したり、ロゴをプリントしたユニフォームを配布するなどして、ブランドに対する親しみや誇りを持ってもらうために行動します。
アウターブランディングで発信する情報とインナーブランディングで浸透させた理念が一致すれば、ブランドのイメージが社内外で一貫性を持ち、より効果的な企業・事業ブランディング活動につながります。
◉企業がインナーブランディングを実施するメリット

ここでは、インナーブランディングによって得られる代表的な6つのメリットについて解説します。
メリット1:企業価値が向上する
メリット2:従業員が自社への理解を深められる
メリット3:組織のチームワークや生産性が向上する
メリット4:企業独自の文化や価値観が強化される
メリット5:採用時のミスマッチを防げる
メリット6:従業員の定着率が向上する |
それぞれについて見ていきましょう。
◉-1、メリット1:企業価値が向上する
インナーブランディングを通して、ブランドの理念が社内にしっかりと浸透すれば、顧客対応や業務に一貫性が生まれ、外部からの企業評価が高まります。
たとえば、「お客様第一主義」を掲げる企業であれば、従業員の行動にもその姿勢が現れます。
結果として、リピーターの獲得や口コミによる新規顧客の増加にもつながり、企業価値が継続的に高まっていくのです。
たとえば、世界的なホテルブランドとして知られるザ・リッツ・カールトンは、お客様に最高のサービスを提供するために、上司に許可を得ずにゲスト1人につき最大2,000ドルを顧客サービスに使える制度を導入しています。
このような裁量権の付与により、従業員のパフォーマンスが向上し、結果的にブランドの価値を高めることに成功しました。
◉-2、メリット2:従業員が自社への理解を深められる
インナーブランディングによって、企業が掲げるビジョンやミッションを可視化して共有化することで、従業員の理解が深まります。
理念や価値観を正しく理解した従業員は、自身の仕事の意義を実感しやすくなり、業務への取り組み姿勢や意識が変わってきます。
給料の金額や、仕事内容など分かりやすい雇用条件だけが従業員の働きがいを作る訳ではないのです。
たとえば、「明るい未来をつくる」という理念を持つ企業があったとします。
インナーブランディングによってその理念を浸透できていれば、従業員はただ目の前の業務に追われるのではなく、「自分は人々の未来のために行動している」「この仕事は社会のためになっている」という自覚を持つことが可能です。
結果として、モチベーションやパフォーマンスの向上などの良い効果が現れます。
◉-3、メリット3:組織のチームワークや生産性が向上する
共通の価値観を持つことで、チームとしての一体感が生まれやすくなります。
インナーブランディングによって、部門を超えたコミュニケーションが活性化し、組織全体の連携が強化されるのです。
たとえば、社内イベントやワークショップなどを通じて従業員同士の交流が増えれば、部署間の垣根が低くなり、情報共有や協力体制がスムーズになります。
その結果、業務の重複や時間ロスも減り、組織全体の生産性の向上が期待できます。
◉-4、メリット4:企業独自の文化や価値観が強化される
インナーブランディングは、企業独自の文化を育み、維持するうえでも大きな役割を果たします。
企業文化は、従業員の行動規範や判断基準に直結するため、組織の一体感を生む重要な要素です。
たとえば、ベンチャー企業で「チャレンジ精神」を大切にしている場合、その姿勢が全社に浸透していれば、変化に強い組織づくりが可能になります。
このように、インナーブランディングを通じて文化や価値観を共有することが、企業の持続的成長に貢献し、結果として外部からの評価も高めることにつながります。
◉-5、メリット5:採用時のミスマッチを防げる
インナーブランディングをした上で採用活動を行えば、採用を担当する従業員一人ひとりがブランドの核を理解しているため、ブレないメッセージを伝えることができます。
その結果、「この会社はこういう考え方をしている」と理解したうえで応募する人が増えるため、入社後のミスマッチが起きにくくなるのです。
入社後のギャップによる早期離職を防ぐとともに、採用活動の質を高める効果が期待できます。
◉-6、メリット6:従業員の定着率が向上する
従業員が企業の理念やビジョンに共感し、自身の仕事がその一部を担っていると実感できれば、会社への帰属意識が高まるため、従業員の定着率アップにつながります。
特に今時の若手社員にとっては、「働きがい」を感じられるかどうかが、長く働くモチベーションに直結する時代。
実際に株式会社日本能率協会総合研究所が300人以上の企業に勤務する正社員1万人を対象にアンケートを実施したところ、25歳〜34歳でかつ「直近3年以内に転職を考えたことはない」理由として、「今の仕事にやりがいを感じているから(以下、仕事のやりがい)」(26.9%)が一番多くなっています。
インナーブランディングによって企業の方向性が明確に伝えられ、従業員がその一部として認識されれば、組織への信頼感や安心感も高まり、定着率が自然と上がっていくのです。
◉インナーブランディングに効果的な7つの手法

インナーブランディングには、自社の状況や企業文化に合った適切な手法を採用することが重要です。
特に効果的な手法は以下の7つです。
<1>社内SNSやコミュニケーションツールを導入する
<2>社内報やイントラネットを活用する
<3>ワークショップや研修を実施する
<4>社内イベントを開催する
<5>日報を制度化する
<6>ブランドムービーを作成する
<7>書籍を出版する(ブックマーケティング) |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、<1>社内SNSやコミュニケーションツールを導入する
社内SNSやコミュニケーションツールは、日常の業務連絡だけでなく、気軽な情報共有や雑談の場としても有用です。
従業員同士が気軽にコミュニケーションを取れる環境を作ることで、垣根を越えた交流やアイデアの共有が活発になり、組織としての一体感を高める効果が期待できます。
また、経営層や管理職からのメッセージをリアルタイムで発信する場としても活用でき、トップの想いが従業員にダイレクトに伝わりやすいなど、風通しの良い環境になりやすいのもポイントです。
◉-2、<2>社内報やイントラネットを活用する
社内報やイントラネット(企業や組織内部のみで利用できる、クローズドなネットワーク環境のこと)は、会社の方向性や価値観、成功事例などを共有する手段として活用できます。
ポイントはある程度定期的に発信することと、従業員の目を惹くような企画を考えることです。
「社内だから見てくれるだろう」と、ただ発信するだけではダメです。
「ただでさえ仕事で忙しいのにこんなの見てられるか!」と、捨てられたり、無視されてしまうのが当たり前だと思っておきましょう。
たとえば、社長インタビューに少し突っ込んだ質問を入れたり、社員のインタビューを掲載したり、社内を巻き込んで自分ごとにさせるような企画が有効です。
こういったエンタメ性のある発信をしていくことで、徐々に企業理念が身近に感じられるようになったり、自身の役割に誇りを持つきっかけにもなります。
◉-3、<3>ワークショップや研修を実施する
インナーブランディングは、知識を伝えて共有するだけでなく、体験を通じて伝えていくことも重要です。
ブランドの理念や価値観に基づいたワークショップや研修を開催し、従業員の理解を深めるとともに、自分ごととして捉える意識を育てることができます。
さらに、ディスカッションやグループワークを取り入れた形式であれば、他のメンバーと意見を交わす中で自社ブランドへの認識が深まり、チーム全体の一体感も自然と高まります。
頭で理解するだけではなく、しっかりと腑に落とすことができるので、社員一人ひとりの理解度を上げるには効果的な方法と言えるでしょう。
◉-4、<4>社内イベントを開催する
社内イベントは、社員同士のつながりを強化し、企業文化を楽しく体感できる場です。
たとえば創業記念パーティーや表彰式、レクリエーションなどを通じて、企業のビジョンやミッションを再認識して共有することができます。
イベントは非日常的な空間でありながらも、企業らしさを表現する絶好の機会です。
「うちの会社らしいな」と従業員が感じられるような演出やコンテンツを設けることで、企業への共感や帰属意識が高まり、インナーブランディングが自然と進んでいきます。
◉-5、<5>日報を制度化する
日報は、業務報告だけでなく、価値観や理念の再確認の機会としても活用できます。
たとえば、日報の中に「ブランドに基づいた行動の振り返り」などの項目を設けると、日々の業務の振り返りを通じて自然とブランドへの理解が深まります。
管理職によるフィードバックがあるとなお効果的です。
従業員は「見てもらえている」「方向性が共有されている」と実感でき、モチベーションの向上にもつながります。
◉-6、<6>ブランドムービーを作成する
企業の理念や想いを映像で伝える「ブランドムービー」も効果的なツールです。
文章やプレゼン資料では伝わりにくい情熱や空気感も、映像であれば直感的に伝えることができます。
たとえば、創業時の想いや商品開発に込めたストーリーなどを、ドキュメンタリー風にまとめると、従業員の共感を得やすくなります。
新入社員研修や全社ミーティングなどで活用すれば、組織全体での価値観の共有が一層スムーズになり、ブランドへの理解と愛着が自然に深まっていくことでしょう。
◉-7、<7>書籍を出版する(ブックマーケティング)
近年、インナーブランディングの手法として注目を集めている手法が「企業出版」です。
出版というと、会社以外の方に認知を広げるための手法だと思っている方が多いと思いますが、インナーブランディングにも効果的なのです。
創業のきっかけや経営理念、商品開発の裏話、経営者のビジョンなどをまとめた書籍などは、従業員にとって「会社の物語」を深く知ることのできる貴重なツールです。
書籍という形であれば、後から入社した社員にも手渡しやすく、組織全体での一貫したインナーブランディングの効果が期待できます。
また、社外へのブランディングにも効果を発揮します。
このように、インナーブランディングとアウターブランディングをつなぐ役割を果たすという点でも「企業出版」という手法は注目されています。
▶︎企業出版(ブックマーケティング)については、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方」】もあわせて参考にしてください。

◉インナーブランディングを成功させるポイント

インナーブランディングは、一般的な手法をただ実施すれば自動的に成果が出るというものではありません。
ここでは、インナーブランディングを実践するうえで意識しておきたい4つのポイントを紹介します。
・ポイント1:従業員を巻き込む
・ポイント2:長期的な視点で取り組む
・ポイント3:自社に合う手法やツールを活用する
・ポイント4:経営層と現場のコミュニケーションを強化する |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、ポイント1:従業員を巻き込む
インナーブランディングは、経営層がトップダウンで理念を伝えるだけでは十分な効果は得られません。
重要なのは、従業員一人ひとりがブランドを「自分ごと」として捉えられるかどうかですので、一方的な情報伝達ではなく、コミュニケーションを通じた巻き込みが必要です。
たとえば、ブランドや理念をテーマにしたワークショップなどを開催し、従業員の意見や価値観を引き出す機会を設けるのがおすすめです。
こういった巻き込みを促すイベントなどを通じて、社員一人ひとりの自発的な参加意識を高めていきましょう。
◉-2、ポイント2:長期的な視点で取り組む
インナーブランディングは、一度実施したらすぐに成果が現れるものではありません。
理念や価値観を社内に浸透させ、行動として根づかせるには、ある程度の時間と継続的な取り組みが必要です。
短期的なイベントやキャンペーンに頼るのではなく、中長期的な視点で計画を立て、段階的に進めていくことが重要です。
◉-3、ポイント3:自社に合う手法やツールを活用する
インナーブランディングにはさまざまな手法やツールがありますが、どれも万能というわけではありません。
重要なのは、自社の業種や企業規模、従業員の働き方に合った方法を選び、柔軟に活用していくことです。
たとえば、オフィス勤務が中心の企業では、ポスター掲示などが有効ですが、テレワークが主流の企業ではイントラネットやオンライン動画、社内チャットツールを活用した施策の方が効果的でしょう。
また、ある程度の社員数を抱える企業であれば、社内報や小冊子、企業出版(ブックマーケティング)などの紙ものの配布物などが有効です。
◉-4、ポイント4:経営層と現場のコミュニケーションを強化する
インナーブランディングを成功させるには、経営層と現場の従業員との間のコミュニケーションが不可欠です。
いくら素晴らしい理念を掲げても、それが現場の実情と食い違っていては、従業員の共感は得られません。
経営陣が一方的に理念を発信するのではなく、現場の声に耳を傾け、やりとりを続けていくことが大切です。
◉インナーブランディングの成功事例

インナーブランディングの成果は、企業文化、従業員のエンゲージメント、パフォーマンスなどのいろいろな側面で表れます。
ここでは、実際に書籍出版を活用して従業員のモチベーションが向上した事例を紹介します。
◉-1、書籍を出版して従業員が育つ組織に変化した事例
保険代理店を営む経営者は、保険業界の現状と問題点を解説し、これからの保険代理店経営に必要な考え方やシステムについての持論をまとめた書籍を出版。
保険業界では成果に応じて給与が決まる「成果報酬型」が当たり前ですが、その結果として少数のスーパー営業マンに頼る経営になってしまうのが実情です。
この場合、スーパー営業マンが辞めてしまうと、会社にとっては大打撃になります。
著者である保険代理店の経営者はこれに疑問を持ち「一律報酬型」に変えることによって、アベレージヒッターを育てて業績拡大ができることを紹介しました。
出版の結果、書籍のタイトル通りに「社員の採用・定着・育成」に非常に大きな効果があったのはもちろん、成約率の向上、新規コンサル契約の獲得などに大きな効果が出たそうです。
また、出版後に自分自身のマネジメントが大きく変わったことや、従業員が従業員それぞれが自分で考えるようになるなど、経営者自身、また社内にも良い影響が出ているとのこと。
◉【まとめ】インナーブランディングに書籍(企業出版)という選択肢を
この記事では、インナーブランディングの定義や導入のメリット、具体的な手法、成功のポイント、成功事例などについて幅広く解説してきました。
インナーブランディングは、一言でいえば従業員の意識や行動を内側から変えていくアプローチです。
理念やビジョンの共有を通じて、企業文化を醸成し、組織の一体感を育むことは、これからの時代の企業経営に欠かせません。
インナーブランディングには多くの手法がありますが、その中でも特に注目したいのが、企業出版(ブックマーケティング)という選択肢です。
経営者の思い、創業の物語、ブランドにかける情熱を言語化して社員に届けることができる点で、書籍は強力なインナーブランディングツールといえます。
また、社内だけではなく社外への発信としても活用できるため、社内外の両面からブランディングを強化する一石二鳥の手法と言えるでしょう。
もしインナーブランディングの一環として書籍を活用するのであれば株式会社フォーウェイの企業出版(ブックマーケティング)をおすすめします。
業界最多の企業出版の実績をもつ編集チームが全面的にサポートします。


近年の求人市場では、少子高齢化や専門的なスキルを持つ人材の需要増加などの影響もあり、多くの業界で優秀な人材の確保が難しくなっています。
実際に、厚生労働省が発表したデータによれば、令和6年の平均有効求人倍率は約1.25倍と高い水準を維持していることから、「売り手市場」と言われることも少なくありません。(※1)
人手不足が深刻化している業界も多く、ただ求人情報を発信するだけでは必要な人材を確保できないケースが増えています。
こうした状況で優秀な人材を確保するためには、採用ブランディングで企業の魅力や価値観を効果的に伝えることが必要不可欠です。
この記事では、採用ブランディングとはどのようなものなのか、というところから、手順や効果的な手法を解説いたします。
参考※1:厚生労働省『一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について』
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉採用ブランディングとは

採用ブランディングとは、企業が求職者に向けて、理念や魅力、社内の雰囲気などを発信していく取り組みを指します。
「企業がどのような人材を求めているのか」、「どのような人材が自社にマッチするのか」という点を明確にし、自社に共感してくれる人材や長く貢献してくれる人材を確保することが目的です。
たとえば、総合不動産メーカーのオープンハウスは、今の時代には珍しい体育会系のカルチャーを全面に押し出すことで、成長意欲の強い一部の層から憧れの企業になっています。
また、グループウェアサービスを展開するサイボウズはオウンドメディア「サイボウズ式」などを活用して「働きやすさ」や「チームワーク」をアピールしました。
その結果、中途採用の応募者数が3倍にまで増加したそうです。
これらの企業は、独自の企業文化や自社の魅力、働き方などを積極的に発信しているため、「この会社で働きたい」と思ってもらえるようになるのです。
◉-1、採用マーケティングとの違い
採用ブランディングに似た用語に、採用マーケティングがあります。
採用マーケティングは、求職者をターゲットとしたマーケティング全般を指す言葉です。
そのため、求人広告の出稿や採用イベントの開催など、具体的な施策まで含んでいます。
一方で、採用ブランディングでは、企業の価値観や文化、働く環境などを発信し、求職者からの信頼や共感を築くことを重視しています。
簡単に言えば、採用マーケティングは行動を促すための手段で、採用ブランディングは信頼や共感を築くための基盤ということです。
◉-2、広報との違い
広報も、採用ブランディングとは似た意味合いのある用語です。
ただし、広報は企業全体の認知度向上やイメージアップを目的として行われ、顧客や投資家はもちろん、メディアに至るまで幅広いステークホルダーを対象としています。
一方で、採用ブランディングが対象としているのは、主に求職者であるという点が大きく異なるポイントです。
広報と採用ブランディングは組み合わせて行うことで相乗効果が期待できます。
◉企業が採用ブランディングを実施するメリット

では、企業が採用ブランディングを実施すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
考えられるメリットとして、以下の7つが挙げられます。
・自社の認知度が向上する
・応募者の質と数が向上する
・入社後のミスマッチを防ぎ定着率を向上させられる
・採用後もモチベーションが高い状態を保ってもらえる
・社員のエンゲージメントが向上する
・企業全体のブランド力向上につながる |
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
◉-1、自社の認知度が向上する
採用ブランディングに力を入れることで、自社の認知度を上げられるのは大きなポイントです。
自社が掲げる企業理念や事業内容はもちろん、どのような社会貢献をしているのかなど、企業文化や魅力を伝えることで、自社に興味を持ってくれる人を増やせます。
たとえば、フリマアプリを運営するメルカリは、採用を目的としたオウンドメディア「mercan(メルカン)」を開設し、社員の働き方や企業文化を発信。
これにより、測定期間中にメルカリに内定した人の「mercan」認知率は100%に達し、採用活動に大きく貢献しています。
SNSなども含め、さまざまなチャネルを活用して採用ブランディングを行うことで、応募者だけではなく社会全体に知ってもらえるチャンスが増え、認知度を高められます。
◉-2、応募者の質と数が向上する
採用ブランディングで認知度が向上すると、それまで自社を知らなかった層からの応募も増え、応募者の質と数が向上します。
自社の企業文化や働き方、魅力がきちんと伝わっていれば、自社に共感してくれる人材からの応募も期待できます。
採用ブランディングによって求める人材像を明確にしておけば、応募前から共感や理解を深められるため、自社にマッチした人材が集まりやすくなるのがメリットです。
たとえば、ブログサービス「Ameba」などを展開するサイバーエージェントは、「CyberAgent Way(サイバーエージェント・ウェイ)」というオウンドメディアを運営し、社員のインタビューや企業文化、働き方に関するコンテンツを発信しています。
このような情報発信によって、「この会社は働きやすそうだ」「自分に合っている」と思ってもらうことができ、効率的な採用活動ができるようになります。
◉-3、入社後のミスマッチを防ぎ定着率を向上させられる
採用ブランディングによってすでに自社への理解を深めている人材を得られると、入社後のミスマッチを防げるのも大きなメリットです。
事前に企業の文化や価値観を理解している人材であれば入社後にギャップを感じることも少なく、定着率が向上します。
企業にとって、せっかく採用した人材が早期に退職してしまうのは大きな損失です。
退職者が出れば、再び採用活動をしなくてはならないケースもあります。
人材の採用には広告費や人材会社に支払う費用などが必要なのはもちろん、手間や時間もかかります。
採用ブランディングによって離職率の低減や人材育成の効率化が図れれば、中長期的に見ても採用コストの削減につながるのがメリットです。
◉-4、採用競合と差別化できる
採用ブランディングによって自社の強みや独自性、カルチャーなどをしっかり発信していけば採用競合と差別化でき、応募者の目にとまりやすくなります。
ただし、自社に応募してくれる人材が、競合他社にも同時に興味を持っていたり、応募していたりすることも少なくありません。
業務内容に差がなければ待遇や社風、将来性など、別の観点が決め手になるため、採用ブランディングによって競合他社と差別化できるポイントをアピールすることが重要です。
たとえば、ユニクロは、「服を通じて世界を良くする」という理念のもと、発展途上国への支援活動や環境保護活動を積極的に行っています。
このような社会貢献活動を採用ブランディングの一環として発信することで、企業の理念に共感する求職者を引き寄せ、他社との差別化を図っています。
採用ブランディングを通して自社の強みや独自性をはっきりと伝えることで、採用競合と差別化し、優秀な人材を確保することが可能です。
◉-5、採用後もモチベーションが高い状態を保ってもらえる
採用ブランディングがうまくいっていれば、採用した人材とはすでに企業理念やビジョンを共有できています。
また、社内の雰囲気も採用ブランディングでアピールした通りであれば、入社後もギャップを感じることなく、モチベーションが高い状態で仕事に取り組むことが可能です。
結果として組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。
◉-6、社員のエンゲージメントが向上する
採用ブランディングを実施している企業では、既存社員のエンゲージメント向上にも良い影響を及ぼします。
社員のエンゲージメントとは、自社の理念や価値観に対して理解・共感することで、達成に向けて貢献しようとする意識を指します。
採用ブランディングを行っていると既存社員のエンゲージメント向上に良い影響を及ぼすのは、企業の文化や価値観を社外に向けてに発信する機会が増えることが理由です。
たとえば、採用ブランディングの一環としてイベントや説明会を行っている企業であれば、担当者は「企業側の人間」として企業の理念や魅力を伝えていく必要があります。
その結果、既存社員も自社の理念をはじめとする方向性を再確認することができ、エンゲージメントの向上につながるのです。
◉-7、企業全体のブランド力向上につながる
企業のビジョンや価値観を明確にしたうえで採用ブランディングを行えば、企業全体のブランドイメージの向上にもつながります。
ほとんどの企業では、自社の商品やサービスなどをアピールするために広告戦略を練り、ブランド力を高めるために努力しています。
採用ブランディングでは商品やサービスだけにとどまらず、働く場所としても魅力があることを伝えられるため、企業全体のブランド力も高められるのがポイントです。
その結果、顧客はもちろん取引先などからの信頼も高まり、ビジネス全体の成長も期待できます。
◉採用ブランディングを実施する手順

採用ブランディングを実施する手順は以下の通りです。
ステップ1:自社の理念やビジョン、価値観を整理する
ステップ2:求める人材を具体的に洗い出す
ステップ3:求める人材から共感を得られる採用コンセプト・戦略を策定する
ステップ4:接点となるコミュニケーションツールをデザインする
ステップ5:施策を実行し、測定・改善を繰り返す(PDCAを回す) |
ここからは、5つのステップを順に解説していきます。
◉-1、ステップ1:自社の理念やビジョン、価値観を整理する
採用ブランディングを実施するためには、自社の理念やビジョン、価値観などを明確にできていなければ進められません。
採用活動で求職者に伝えたいメッセージもブレてしまうため、まずは自社についての分析を行います。
理念やビジョン、価値観や社風のほか、業務内容や福利厚生など、自社の魅力として発信できる要素を洗い出し、併せて強みや弱みについても客観的に把握しておくことで、求職者に伝えるべき自社の魅力も明確になります。
◉-2、ステップ2:求める人材を具体的に洗い出す
採用ブランディングでは求める人材の典型的な人物像、いわゆる「ペルソナ」を設定することも大切です。
技術スキルや経験などの表面的な要素だけではなく、価値観や仕事に対する姿勢など、細かく定義しましょう。
たとえば、「協調性がある」「論理的思考力が高い」など具体的に定義します。
求める人材は「チームワークを重視できる人」「チャレンジ精神旺盛な人」など、企業によって様々です。
自社が採用したい人物像を細かく定めておくことで、伝えるべきメッセージにもズレがなくなります。
◉-3、ステップ3:求める人材から共感を得られる採用コンセプト・戦略を策定する
採用ブランディングを実施する際は、採用活動をするにあたって核となる採用コンセプトをしっかり求職者に伝えられることも重要です。
そのためには自社の魅力や軸となる部分を言語化し、「どのような人と一緒に働きたいのか」「企業としてどうありたいのか」など、求職者に伝えたい内容を採用コンセプトに落とし込む必要があります。
たとえば、「チームワークを大切にする文化」を持つ企業の場合、「協力し合いながら働ける人を歓迎します」といったメッセージを採用コンセプトに組み込むことで、狙った人材を多く取り込むことが可能です。
採用コンセプトや戦略を作成する際は、どのような場や媒体を使って発信するのかも併せて考えておきましょう。
◉-4、ステップ4:接点となるコミュニケーションツールをデザインする
求職者との接点(タッチポイント)となるコミュニケーションツールをデザインする際は、統一感のあるものにすることが大切です。
採用コンセプトや戦略に沿って情報発信をしていくために、自社のイメージに合ったロゴや色、写真や動画のテイストなどを整えましょう。
ホームページの採用サイトやパンフレット、SNSなど、さまざまなツールが考えられますが、一貫して企業をイメージでき、魅力が伝わるデザインにすることがポイントです。
◉-5、ステップ5:施策を実行し、測定・改善を繰り返す(PDCAを回す)
採用ブランディングは求職者に向けて企業の魅力を発信し、選ばれる確率を高めるのが目的であるため、実行後に採用コンセプトや戦略が機能しているかどうかを分析しなければなりません。
応募者数や応募者の質、内定後の辞退率や入社後の定着率などを分析し、うまくいっていないポイントや改善すべき部分を把握し、PDCAを回していくことが求められます。
求職者に対するアンケートや採用サイトの解析なども参考にしながら、定期的な検証・改善を繰り返し、ブランド力向上を目指すことが大切です。
◉採用ブランディングに効果的な手法

採用ブランディングは、さまざまな手法を組み合わせると、自社の魅力を効率よく進めることが可能です。
採用ブランディングに効果的なものとして、具体的には以下の8つの手法があります。
・採用専門のWebサイトの構築
・SNSを活用した情報発信
・社員インタビューやブログの発信
・採用イベントや説明会の開催
・インターンシップや職場体験の実施
・動画コンテンツの制作
・採用パンフレットの制作
・書籍の出版(ブックマーケティング) |
それぞれの手法を具体的に見ていきましょう。
◉-1、採用専用のWebサイトの構築
自社の基本情報を発信するコーポレートサイトだけではなく、採用専門のWebサイトを用意すると採用ブランディングでは効果的です。
採用専門のWebサイトは求める人材像などの求職者が求める情報に特化した発信をしているのが特徴で、理念や企業文化、社員の働き方などをより分かりやすく伝えられます。
先輩社員のリアルな声や、社内イベントの様子なども掲載すると良いでしょう。
◉-2、SNSを活用した情報発信
SNSを活用すると、リアルタイムで自社の情報を発信できます。
採用専用のアカウントを作成し、SNSでオフィスの雰囲気や社員の活動、プロジェクトの進行状況などをこまめに投稿すれば、求職者にリアルな企業の姿を届けることが可能です。
たとえば、三井物産株式会社の公式Instagramでは、仕事に対して抱えている思いをインタビュー形式で発信するコンテンツ「1min Question」を投稿しています。
また、ストーリーハイライトを活用し、採用サイトのインタビュー記事への導線を作成。
SNSを活用して採用サイトへの自然な流入を促している事例です。
SNSは企業と求職者が、気軽にコミュニケーションを取りやすい特徴もあります。
拡散力のあるSNSは、きっかけがあれば一気にフォロワー数を増やせる可能性があるため、採用ブランディングにSNSを活用するのもおすすめです。
◉-3、社員インタビューやブログの配信
ブログの記事や動画などで社員のインタビューを公開するのも、採用ブランディングの効果的な手法の一つです。
SNSは拡散力の高さが特徴ですが、まとまった情報を見せるのには向いていません。
一方で、ブログは伝えられる情報量が多いツールです。
実際にその企業で働く先輩社員の具体的な話をブログで発信すれば、求職者が社風や業務内容、キャリアパスなどもイメージしやすくなります。
自社のドメインを構築してブログ記事を公開する企業もありますが、最近ではnoteやWantedlyに代表される外部メディアを利用する企業も増えています。
◉-4、採用イベントや説明会の開催
説明会や企業セミナーの開催、職場見学会や社員交流会の実施なども、企業と求職者が接触できるチャンスになります。
求職者が社内を見学したり社員と直接話ができたりする機会を設けることで、実際に社内の雰囲気を体感してもらうことが可能です。
自社のビジョンや魅力などもダイレクトに伝えられるため、求職者の心も掴みやすくなります。
◉-5、インターンシップや職場体験の実施
実際の業務に携わってもらうインターンシップを実施し、求職者に職場を体験してもらうのも効果的な採用ブランディングの手法です。
たとえ短期間であっても、求職者にとっては働き方や実務をよりリアルに感じられる場となります。
「この会社で働くとこんな感じなんだ」という体験ができる貴重な機会になり、応募にもつながります。
◉-6、動画コンテンツの制作
社員のインタビューや社内イベントの様子、社員が実際に勤務している風景などをまとめたダイジェストを、動画として配信するのも効果的です。
ブログでも同様の発信は可能ですが、動画コンテンツではよりリアルな情報を視覚的に発信できます。
また、拡散しやすい性質を持っているのもメリットです。
文字では伝わりにくい情報やリアルな雰囲気もストレートに伝えやすく、映像ならではの臨場感を活かして自社の魅力をアピールできます。
◉-7、採用パンフレットの制作
紙媒体の採用パンフレットは企業の魅力を伝えるツールとして以前から活用されていますが、現代の採用活動においても有効です。
説明会などで配布されることが多く、信用性が高いのが特徴です。
手元にあると、その企業のことを思い出すきっかけにもなり、見返してもらいやすく、他社と比較しやすくなるメリットがあります。
▶︎採用パンフレットの作り方については、関連記事【人材獲得につながる採用パンフレットを作るコツ!効果的な活用方法も解説】もあわせて参考にしてください。

◉-8、書籍の出版(ブックマーケティング)
ブックマーケティングとは、書籍の持つ高い信頼性をマーケティングに活用する手法です。
自社の理念やストーリー、社長の思いやビジネスの進め方などを書籍としてまとめ、それを読んでもらうことでビジョンや価値観を深く理解してもらうことができます。
インターネットでさまざまな情報を調べられる時代になりましたが、「書籍を出している企業」という事実はそれだけで信頼性にもつながります。
▶︎ブックマーケティングのやり方については、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】もあわせて参考にしてください。

◉ブックマーケティングを活用したブランディングの成功事例

採用ブランディングに使える8つの手法のなかでも、特にブックマーケティングを活用した成功事例を紹介します。
◉-1、書籍に出版によりスムーズな人材確保が実現した事例
とある保険代理店は、保険業界に関する持論を提唱した書籍を出版。
契約の獲得によるインセンティブのみが報酬となる給与形態に疑問を呈し、自社の営業パーソンを正社員かつ固定給で雇用しました。
この経営論を書籍化した結果、出版直後から目的としていた保険代理店からのコンサル依頼が入り始めました。
また、講演の依頼や同業支援の話などが増え、「保険会社にとって頼れる代理店」というイメージが定着し、見られ方が変わったことを実感されています。
さらに、本を読んでこの保険代理店に求人応募をした人が複数人現れるなど、人材採用の面でも効果を発揮しています。
ブックマーケティングがベンチャー企業としてもう一段上のステージに上がるきっかけとなり、人材の採用・育成にも困らない会社となりました。
◉【まとめ】より質の高い人材を求めるなら書籍(企業出版)を活用しよう!
採用ブランディングとは、企業が求職者に向けて自社の理念や魅力などを発信していく取り組みです。
採用ブランディングによって自社の認知度が向上すれば、求職者の増加やミスマッチの防止、既存社員のモチベーションやエンゲージメント向上のようなメリットが得られます。
採用ブランディングでは、採用専用のWebサイト構築やSNS・ブログによる発信など、いくつか効果的な手法はありますが、「信頼性」「権威性」「企業に対する深い理解」という点に注目するならブックマーケティングがおすすめです。
フォーウェイでは、ブックマーケティングのサービスを主軸として、デジタル施策やオフライン施策から各種ツールの作成まで、各種サービスを展開しています。
採用ブランディングの一環として書籍の活用を検討している方は、フォーウェイにご相談ください。


商品・サービスを提供している企業の多くは「自社の商品・サービスをもっと多くの人に知って欲しい」「競合他社との価格競争から脱却したい」という悩みを抱いています。
そんな悩みを解決するカギとなるのが「商品ブランディング」です。
競争が激しく、選択肢が多い現代では、ただ単に良い商品を作るだけでは他社が提供する商品・サービスに埋もれてしまいます。
他社との競争から脱却し「選ばれる商品」になるためには、商品・サービスの持つ価値や魅力を明確にし、顧客の心に訴えかけるブランドを構築する必要があるのです。
この記事では、「商品ブランディングとは」というところから、効果や手順、具体的な手法を解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉商品ブランディングとは?
商品ブランディングとは、ただ単に商品・サービスに名前やロゴを与えるだけでなく、商品・サービスに関する独自の価値観やイメージを顧客へ浸透させる活動のことを言います。
商品ブランディングでは、特にブランドのストーリーや価値観を伝え、ニーズや感情に訴えかけることが、競合商品との差別化に効果的です。
商品ブランディングが成功すると「この商品は◯◯な価値がある」「このブランドの商品だから安心して買える」などといった印象を持ってもらうことができます。
確立されたブランドができれば、安易な価格競争とは無縁の領域でビジネス展開ができるようになります。
長期的な信頼関係と顧客ロイヤリティを構築するためには、商品ブランディングが欠かせません。
◉-1、事業ブランディングとの違い
事業ブランディングと商品ブランディングは、ブランド戦略の対象範囲と目的が異なります。
事業ブランディングは、顧客をはじめ取引先や株主といった様々なステークホルダーに向けて行われますが、商品ブランディングは主に顧客がターゲットとなります。
目的という視点から見れば、事業ブランディングは企業が行っている事業の中の一つの価値を高めるための活動であるのに対し、商品ブランディングは事業が展開する商品を訴求するものです。
たとえば、世界的に人気のゲーム会社「任天堂」は、ゲーム専用機の製造事業のほかにも、グッズの制作・販売などいくつかの事業を展開しています。
いくつかある事業の中で、ゲーム専用機の製造事業にフォーカスして行うのが事業ブランディング、「Nintendo Switch」など個別の商品を訴求するのが商品ブランディングです。
事業ブランディングが成功すると、結果として事業全体や企業、商品・サービスのイメージ向上にも繋がります。
逆もまたしかりで、商品ブランディングが成功すれば、事業のイメージが向上するという相乗効果が生まれるのです。
◉企業が商品ブランディングで得られる7つの効果
商品ブランディングで得られる効果は、即時的に得られる効果よりも持続的に得られる効果の方が多いのが特徴です。
商品ブランディングの成功は、商品・サービスだけでなく企業にも大きな価値をもたらし、時間が経過するごとに効果がはっきりと現れます。
では、企業が商品ブランディングを積極的に行うことで得られる効果には、どのようなものがあるのでしょうか。
考えられる7つの効果は以下の通りです。
効果1:商品の知名度が向上する
効果2:価格競争に巻き込まれにくくなる
効果3:顧客ロイヤリティが向上する
効果4:マーケティング効果が向上する
効果5:ビジネスチャンスが増える
効果6:優秀な人材の確保につながる
効果7:社員のモチベーションが向上する |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、効果1:商品の知名度が向上する
商品ブランディングがうまくいくと、総合的な知名度向上に繋がります。
たとえば、スマートフォンの代表格であるiPhoneは「シンプルでスタイリッシュ」「直感的に操作できるユーザーインターフェース」などのデザイン・操作性により差別化を実現。
これらを一貫して訴求することにより消費者の関心を引き、ブランド価値や知名度を向上させることに成功しました。
「どんな商品か」「なぜ選ぶべきか」という理解を伴った知名度向上は、ファンの創出と継続的な購買に良い影響をもたらすでしょう。
◉-2、効果2:価格競争に巻き込まれにくくなる
商品ブランディングに成功すると、顧客はブランドのストーリーやイメージ、信頼性などに共感し、価格以上の価値を感じてくれるようになることから、安易な価格競争に陥りにくくなります。
確立されたブランドは顧客のロイヤリティを高めることから、多少価格が高くても選ばれる傾向が強いです。
たとえば、冷蔵庫を例にすると、「値段は安いがブランド名を聞いたことがない商品」よりも「値段は少し高いがブランド名を知っていて愛着を持っている商品」を選ぶ方が多いでしょう。
「ブランドで商品が売れる」というのは、安心感やステータス、自己表現などといった無形の価値が価格よりも重視されることを表しています。
商品ブランディングが成功すると、価格競争への依存から脱却できるため、より高い収益性と持続的な成長が期待できます。
◉-3、効果3:顧客ロイヤリティが向上する
商品ブランディングは商品の販売のみに止まらず、顧客との関係性を育むこともできます。
ブランド体験を通して、顧客が商品に愛着と信頼感を抱き、機能的な価値を超えた結びつきができるのは、商品ブランディングならではのものです。
魅力的なブランドストーリーや共感を呼ぶコミュニケーション、期待を超える顧客体験が積み重なれば顧客はブランドのファンとなり、継続的にブランドを選び続けてくれます。
強力な顧客ロイヤリティは長期的な売り上げの安定と成長に欠かせません。
◉-4、効果4:マーケティング効果が向上する
商品ブランディングによってマーケティング活動の一貫性が生まれ、方向性にもブレがなくなるため、高い効果が期待できるようになります。
また、顧客がすでにブランドの価値観や個性を理解していれば、マーケティング施策への反応がよくなり、共感に基づいた行動も期待できます。
たとえば、価値観や個性に共感し、愛着を持っている商品ブランドのキャンペーンや新商品の発売情報であれば、全く知らないブランドのものよりも受け入れやすいはずです。
さらに、一定の共感が得られれば、顧客はSNSや口コミサイトから自社商品やサービスの良さを発信してくれるようになります。
商品ブランディングができていれば、より少ない投資で大きな成果を得ることも夢ではありません。
◉-5、効果5:ビジネスチャンスが増える
確立されたブランドイメージは、顧客からの信頼と認知度を高める効果があり、新商品や関連サービスへの展開がスムーズになります。
具体的には、メディアへの露出や新規顧客の獲得、新市場の参入などです。
ブランドへの信頼感から参入障壁を下げる働きも期待できます。
たとえば、アウトドアウェアを販売する「パタゴニア」は、企業の社会的責任(CSR)に関する取り組みを評価され、企業や団体とのビジネスチャンスが増えました。
確立されたブランドは、他の企業とのコラボやライセンス供与によって、新たな収益源を生み出す可能性も秘めています。
さらには、投資家からの資金調達など、企業全体の成長に関して想定されるシナジー効果は想像以上のものです。
◉-6、効果6:優秀な人材の確保につながる
魅力的なブランドイメージは採用にも良い影響を与えます。
伝わりやすく共感を得やすいブランドストーリーやメッセージがあれば、より多くの人材を募ることも難しくはありません。
商品ブランディングによって良いイメージをつけることができれば、企業イメージも向上します。
その結果、「こんなに素敵な商品をつくる会社なら働いてみたい」「自分もこの会社で商品をつくってみたい」と感じてもらえるようになるのです。
若い世代は給与のみならず、企業の価値観や社会貢献度を重視する傾向があります。
強い商品ブランドは、若く優秀な人材を募る際に大いに役立つでしょう。
◉-7、効果7:社員のモチベーションが向上する
自分が関わる商品が確かなブランドイメージを持ち、多くの顧客に愛されている事実は、社員のモチベーションに良い効果をもたらします。
「良いものを作って多くの人々に喜んでもらっている」という実感は日々の業務への取り組みを支える大切な要素です。
商品ブランディングは企業の方向性と価値観を明確に示してくれるため、社員は自分の仕事の意義を理解しやすくなる効果もあります。
商品ブランディングは、共通の目標に向けてみんなで働く意義をもたらしてくれるでしょう。
◉商品ブランディングの実施手順
商品ブランディングを進めていく上で大切なポイントは、一貫性のある情報発信を継続的に行うことです。
とはいえ、ただ単に同じ情報を発信し続ければいいというというわけではありません。
自社の強みをもとに設定した価値感を「核」として設定し、発信していくことが重要になります。
戦略を実行に移す前後の手順も入念に行うことを意識した上で、順を追って進めていきましょう。
商品ブランディングの実施手順は以下の通りです。
ステップ1:現状分析
ステップ2:ブランディング戦略を練る
ステップ3:商品・サービスのビジュアルを開発する
ステップ4:戦略を実行に移す
ステップ5:実行・測定・改善を繰り返す(PDCAを回す) |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、ステップ1:現状分析
現状分析を行う際は、最初に自社商品の強みと弱み、ターゲットユーザー、市場における立場を客観的に分析します。
分析ができたら、競合商品のブランドイメージやシェア率、価格帯などを分析しつつ、差別化ポイントを洗い出していきましょう。
現状分析では、ブランドが置かれている立場を明確にしなければいけません。
正しい現状分析ができれば、その後に続く戦略立案もスムーズです。
◉-2、ステップ2:ブランディング戦略を練る
現状分析で得られた情報を元に、具体的なブランディング戦略の立案に進みます。
ブランディング戦略を練る段階では、理想的なブランドイメージや顧客へのメッセージ、競合との差別化ポイント、長期的なブランドの目標などを明確に定義します。
どのような価値を顧客に提供して関係性を作り上げたいのか、ブランドの個性をどのように表現するのか、などといったブランドの核となる重要な部分です。
たとえば、スキンケアブランドである「二ベア」は、「肌がふれあう。 ただそれだけで、人は人をあたためることができる。まもることができる。一生の素肌に。」という一貫したブランドメッセージを発信。
顧客の情緒面に訴えかけ、「保湿クリームと言えば二ベア」とイメージされるまでになりました。
ブランディング戦略が決まると、自然にマーケティング施策やコミュニケーション戦略の方向性が定まってきます。
一貫性のあるブランドイメージを築き上げるためには、ブランディング戦略は欠かせません。
◉-3、ステップ3:商品・サービスのビジュアルを開発する
商品のサービスとビジュアルの開発は、ブランドイメージを具現化し、顧客へ視覚的にアピールする大切な段階です。
ロゴ、パッケージデザイン、ウェブサイト、広告クリエイティブ、店舗デザインなどには、一貫したブランドのメッセージが込められている必要があります。
一貫性のあるビジュアルはブランドの認知度向上や競合との差別化において、大きな意味を持っています。
◉-4、ステップ4:戦略を実行に移す
次の段階では、ブランディング戦略を元に、具体的な手法を実行していきます。
戦略を実行に移す段階では、広告、SNS運用、コンテンツマーケティング、プレスリリースなど、様々な手法を通して一貫したブランドメッセージを発信することが欠かせません。
大切なポイントは、それぞれの手法がブランド戦略との整合性を維持しつつ、ターゲットへ効果的にリーチできているかという点です。
いきなりすべてがうまくいくことは少ないため、微調整を繰り返しながら理想に近づけていく必要があります。
◉-5、ステップ5:実行・測定・改善を繰り返す(PDCAを回す)
一通りマーケティングを終えた後は、効果をより最大化するためのPDCAが必要です。
PDCAを継続的に回すことで、市場の変化と顧客の反応に柔軟に対応することができます。
ブランド戦略の最適化を目指すためにアップデートを繰り返していきましょう。
◉商品ブランディングに効果的な手法
商品ブランディングでは、自社の強みや長所をもとに、価値感や個性を様々な手法を用いて訴求していくことが重要になります。
商品ブランディングに効果的な手法は以下の9つです。
・広告の運用
・SNSの活用
・インフルエンサーとの連携
・コンテンツマーケティングの実施
・メディアへの露出
・イベント・ポップアップストア・展示会の開催
・プレスリリースの配信
・メールマーケティングの実施
・書籍の出版(企業出版) |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、広告の運用
ブランドの認知度向上とイメージの浸透において、広告の運用は欠かせません。
それぞれの顧客に合わせたメッセージとビジュアルによって、ブランドの価値や個性を効果的に伝えることができます。
商品ブランディングに用いられる広告には、主に以下のようなものがあります。
・マス広告
・デジタル広告
・デジタルサイネージ広告
・デジタル音声広告
たとえば、マス広告の一つであるテレビCMは、幅広い層に対して情報を届けられることやテレビという媒体に対する信頼性が高いことがメリットです。
放映期間中は繰り返し目にしてもらえることも多いため、ブランドに対して愛着や信頼感を持ってもらうことができます。
特にお茶や水などの飲料、ティッシュ・トイレットペーパーなど消耗品など差別化しにくい商品は、「見たことがある商品」「信頼できる商品」を選ぶ傾向にあるため、テレビCMが適しています。
このように、自社の商品・サービスに適した媒体で継続的に広告運用することは、商品ブランディングに効果的です。
◉-2、SNSの活用
SNSの運用は、顧客との関係性を構築する上で欠かせません。
企業と顧客がお互いにコミュニケーションをとることで、ブランドへの共感と信頼感を育むことができます。
たとえば、「Instagramのライブ配信を実施し、視聴者からのコメントを読みながらやりとりする」という手法は近年様々な企業で取り入れられています。
ライブ配信の場で商品を詳しく紹介したり、商品の開発秘話などを伝えたりすることも商品ブランディングに有効です。
特に、視覚的なコンテンツは、ブランドイメージの効果的な訴求や口コミの拡散にも効果があります。
▶︎SNS運用のやり方については、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】もあわせて参考にしてください。
◉-3、インフルエンサーとの連携
インフルエンサーは、抱えているフォロワーから深い信頼や愛着を得ていることが多いため、連携すれば顧客との信頼関係をより強くすることができます。
旅行に関するサービスを提供する企業であれば、旅行に特化したインフルエンサーと連携することで、そのインフルエンサーが抱える旅行好きのフォロワーに訴求することができます。
何かのカテゴリに特化したインフルエンサーは、そのカテゴリに興味を持つフォロワーを抱えているため、ピンポイントに訴求することが可能になるのです。
ただし、ブランドイメージに合わないインフルエンサーを選んでしまうとイメージダウンにつながる恐れがあるため、選任する際は「ブランドイメージに合うかどうか」という点も考慮しましょう。
◉-4、コンテンツマーケティングの実施
コンテンツマーケティングは、オウンドメディアや、ブログなどで顧客にとって価値ある情報を提供することで、ブランドへの理解や愛着を深めてもらうための手法です。
SEO対策を施すことで検索流入も期待できるため、新規の顧客獲得にも効果的です。
たとえば、クラシコムが運営するECサイト「北欧、暮らしの道具店」では、商品の背景や使用シーンを紹介するコンテンツを公開することで、顧客が商品購入後のイメージや愛着を持ちやすくしています。
継続的なコンテンツマーケティングを行えば、顧客と強い関係性を築くことが可能です。
▶︎コンテンツマーケティングについては、関連記事【コンテンツマーケティングとは? 広告費を削減して売上を増やす方法】もあわせて参考にしてください。
◉-5、メディアへの露出
メディアへの露出ができるようになると、短期間で広い認知度と信用を獲得できます。
特に、テレビや雑誌などはその媒体自体が信頼性が高いものなので、顧客に良い印象を与え、ブランドに権威性をもたらします。
ただし、ポジティブなメディア露出は口コミ効果も伴って絶大な効果を発揮しますが、ネガティブな情報は逆に拭いきれない悪い印象を与えてしまうため、注意が必要です。
◉-6、イベント・ポップアップストア・展示会の開催
イベント・ポップアップストア・展示会の開催は、顧客との接点を作り出し、ブランドを体験してもらうための貴重な機会です。
リアルなコミュニケーションを通じて商品の魅力やブランドの世界観を伝えることができます。
たとえば、化粧品を訴求したい場合は、ポップアップストアを出店し実際に手に取って試してもらうのも一つの方法です。
顧客がイベントやポップアップストア、展示会で良い体験をすれば、ブランドに対する信頼性や愛着の向上につながります。
◉-7、プレスリリースの配信
プレスリリースの配信は、新商品や重要な情報を効率よくメディアへ届け、幅広い認知度と信頼性を獲得できる手段です。
プレスリリースによる客観的な情報は、ブランドの信頼感を高めつつ潜在的な顧客へのリーチも可能にします。
タイミングをよく吟味することによって大きな効果も期待できる施策です。
◉-8、メールマーケティングの実施
メールマーケティングは、ブランドロイヤリティを高めつつ既存顧客との関係性をより強くするために有効な手段です。
個別に送信される情報提供や限定オファーにて、顧客のエンゲージメントを促進し、リピート購入を促します。
ブランドの世界観を反映したメールデザインも大切です。
メールマーケティングの効果は折り紙付きですが、大きな効果を得るためにはテキストばかりの内容にならないよう、ひと工夫が求められます。
◉-9、書籍の出版(企業出版)
書籍の出版は、専門性と信頼性を高めつつ、ブランドの権威性を確立するための手段です。
自社が持つ知識や独自の視点を交えることによって、顧客からの信頼を集めつつ長期的な信頼関係を構築することができます。
商品の開発秘話、現場の声などを交えた内容にすることで商品・サービスへの信頼感や親しみやすさを伝えることも可能です。
このように、マーケティング戦略(ブランディング戦略)の一環として書籍を出版することをブックマーケティングと言います。
SNSの活用やコンテンツマーケティングなど他のブランディング手法と組み合わせることで効果を最大化させることが可能です。
▶︎ブックマーケティング(企業出版)については、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】もあわせて参考にしてください。

◉商品ブランディングにも応用できる!ブックマーケティングの成功事例
書籍を活用したブックマーケティングの成功事例を2件ご紹介します。
◉-1、本物のわさびの良さを伝えるために出版した老舗わさびメーカーの事例
わさび離れが進む昨今、本物のわさびの良さをPRするために、とある老舗わさびメーカーは出版プロジェクトに取り掛かりました。
書籍には老舗わさびメーカーの長い歴史の中で培われたわさびのおいしさの秘密や、健康効果に関する知識が詳しく伝えられています。
また、著名な料理研究家とのコラボによって、誌面を彩るわさびの色彩も十分に伝わる内容に仕上がりました。
出来上がった書籍は販売のみならず、営業用のプレゼン資料や小冊子にまとめた読み物として関係者に配布するなど、あらゆる場面で活躍しました。
わさびの本を使った広報活動が実を結び、本を読んだ関係者から無料でのラジオ出演や雑誌掲載に漕ぎ着けるまでに至ります。
結果として老舗わさびメーカーはブックマーケティングによって、広告出稿の費用対効果をはるかに上回る大成功を収めました。
◉-2、こめ油の有用性を伝えるために出版した食用油脂メーカーの事例
とある食用油脂メーカー企業は、企業設立75周年をきっかけに書籍出版を実施。
内容は、あえて「一般販売されているサラダ油の摂取が健康被害の原因になりうる」というテーマを選択し、よりこめ油の有用性を訴求する内容に仕上げました。
サラダ油の健康被害をテーマにした書籍出版は思わぬ反響を得ることとなり、全国放送の番組への出演依頼が相次ぎます。
出版をきっかけに問い合わせは大幅に増加し、著者のファンまでできる反響ぶりです。
結果としてBtoB取引の増加に繋がり、関東や名古屋の老舗有料企業や、遠く離れた鹿児島の企業との取引開始にも成功します。
小売店との取引獲得にも成功し、書籍出版が会社の業績を大きく変えることとなりました。
◉【まとめ】まずは自社商品の魅力をしっかりと把握することが重要!
商品ブランディングは、商品・サービスに根強いファンをつくるために欠かせないものです。
自社の商品・サービスの特性に合った手法を用いることで、ブランドの価値を高め、継続的な売り上げに繋げることができます。
商品ブランディングによって信頼度がアップすれば、新たな取引先の獲得や優秀な人材の獲得にも良い影響を及ぼします。
商品ブランディングを成功に導くために、まずは自社商品・サービスの魅力をしっかりと把握し、差別化できるポイントはどこにあるのか明確にしていきましょう。
商品ブランディングの一貫として書籍を活用したいのであれば、フォーウェイのブックマーケティングがおすすめです。
デジタル全盛の時代でありつつも、書籍の持つ意味は今だ衰えていません。
書籍を通じて届けられる質の高い情報は、確かな情報を得たい層から高い支持を獲得できるだけでなく、顧客から強い信頼を獲得できるはずです。


類似した商品やサービスが市場に溢れている昨今は、品質やデザインが優れているだけでは選ばれにくい時代です。
そのような状況では、企業の理念や価値観、社会的な姿勢といった企業そのものの魅力が、選ばれる決め手になりつつあります。
そこで注目されているのが「企業ブランディング」です。
本記事では、企業ブランディングの効果、実施手順、具体的な手法について解説いたします。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉企業ブランディングとは

企業ブランディングとは、企業の理念や価値観、ビジョンなどを明確にして社内外に発信し、企業のブランド価値を高める取り組みです。
商品やサービスの品質がどれほど優れていても、それを提供する企業に信頼がなければ、顧客から選んでもらうことはできません。
逆に、企業に一貫した姿勢や社会的な信頼があれば、商品やサービスそのものの評価も高まり、選ばれる理由になります。
たとえば、Apple社は世界中にアップル信者と呼ばれる熱烈なファンを獲得しています。
新型iPhoneの発売日には朝から長蛇の列ができるほどです。
同じ価格でiPhone以上の機能や性能が備わっているスマホは、世の中にたくさんありますが、企業ブランディングに成功したiPhoneは、機能や価格の競争対象とならずに顧客から選ばれ続けているのです。
◉-1、事業ブランディングとの違い
企業ブランディングと事業ブランディングは、ブランディングの対象が大きく異なります。
企業ブランディングが企業全体の信頼や価値を高める取り組みであるのに対し、事業ブランディングは事業の魅力や認知度を高める取り組みです。
企業ブランディングは企業全体の理念やビジョン、企業文化、社会的役割などを訴求する一方で、企業の中の各事業の強みや特徴を訴求します。
たとえば、楽器メーカーとして有名なヤマハを例にすると、ヤマハという企業全体を訴求するのが企業ブランディング、ヤマハが行っている「楽器事業」「音響機器事業」など個々の事業を訴求するのが事業ブランディングです。
企業ブランディングが成功すれば、企業の価値だけではなく、行っている事業の価値も向上させることができます。
◉企業ブランディングがもたらす8つの効果

企業ブランディングは、単なるイメージ戦略ではないため、企業の内外に多くのメリットをもたらします。
代表的な8つの効果は以下の通りです。
効果1:競合他社との差別化
効果2:顧客ロイヤリティの向上
効果3:信頼性の獲得
効果4:広告宣伝費の削減
効果5:価格競争からの脱却
効果6:優秀な人材の採用・定着
効果7:新規顧客の獲得
効果8:従業員のモチベーション向上 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、効果1:競合他社との差別化
企業ブランディングに成功してブランド価値が高まると、自社の製品やサービスにブランドという付加価値が付くことになります。
結果として競合他社との差別化を図ることができるのです。
たとえば、ダイソンには、「製品開発にただならぬこだわりを持ち、徹底的に作り込まれた高機能・高品質な製品を出す会社」というイメージを持つ人が多いと思います。
このイメージが自社の製品やサービスへの付加価値となり、たとえ他の製品より価格が高くても、他にコスパの良いものがあったとしても、「ダイソンの掃除機が欲しい」と選ばれる存在となります。
企業ブランディングに成功し、競合他社との差別化ができると、価格競争からの脱却や、新規参入企業の抑制、自社の特徴や強みの明確化などのメリットが得られますが、最大のメリットは「価格競争からの脱却」と言っても良いでしょう。
製品やサービスの基本機能は同じであっても、ブランドという付加価値が付くことによって差別化できるため、安定した企業経営を実現することができます。
◉-2、効果2:顧客ロイヤリティの向上
企業の理念やビジョンに共感が集まると、ブランドへの信頼が高まり顧客のロイヤリティも向上します。
顧客ロイヤリティとは、顧客が企業やブランドに対して抱く信頼や愛着を指すものです。
強い顧客ロイヤリティは、リピート購入の増加や口コミによる新規顧客の獲得など、企業にとって多くのメリットをもたらします。
たとえば、スターバックスは、「人々の心を豊かで活力のあるものにするために」というミッションのもと、顧客体験を重視した店舗運営を行っています。
店舗の雰囲気やスタッフの接客などが顧客の満足度を高め、強いロイヤリティを生み出している事例です。
このように、「この企業だから選ぶ」という心理が働けば、価格によらず選ばれ続けて安定した売上にもつながります。
◉-3、効果3:信頼性の獲得
効果的な企業ブランディングを行うことができれば、企業や自社の製品・サービスの信頼性を高めることができます。
たとえば、ダイソンは、創業者ジェームス・ダイソンが納得のいく掃除機を作るために、試作品を5,127台も作り開発を進めてきたプロセスを丁寧にユーザーに伝えています。
結果として、「高機能・高品質」だけではなく、「ジェームス・ダイソンが魂を込めて、試行錯誤をして作られた掃除機だから大丈夫だ」という信頼感の醸成に成功しました。
このように、企業ブランディングに成功すると、「この企業なら間違いない」「この企業なら期待に答えてくれる」という信頼感をユーザーに与えることができるようになります。
高い信頼性を有するブランドを作りあげることは容易なことではありませんが、信頼性の高いイメージを獲得しそれを維持することができれば、それは企業にとって大きな武器となるでしょう。
◉-4、効果4:広告宣伝費の削減
企業ブランディングに成功し、企業の知名度や認知度が向上すると、必要以上の広告宣伝をしなくても自社の製品やサービスが売れるようになります。
理由は2つあります。
1つはファンによるリピート購入が増えるため、2つ目は顧客のニーズが発生した時に選択肢に上がりやすくなるためです。
たとえば、「少し高級感のあるタオルをギフトとして送りたい」と思った時に、おそらくほとんどの人の頭の中に「今治タオル」が選択肢として思い浮かぶはずです。
このように「高級タオルと言えば今治タオル」というブランドが認知されれば、ニーズが発生した段階ですぐに選択肢にあがってくるようになります。
そのため、必要以上の広告宣伝をしなくても、自社の製品やサービスが安定的に売れるようになるのです。
テレビCMやWeb広告などは流している期間中は売上に貢献しますが、CMや広告をやめるとその効果がなくなるケースが多いものです。
しかし、企業ブランディングによって向上した企業の知名度や認知度は、継続的な経済効果を企業にもたらします。
このように、広告宣伝費が削減できることも企業ブランディングの大きなメリットの1つと言えるでしょう。
◉-5、効果5:価格競争からの脱却
企業ブランディングに成功すると自社の製品やサービスが高価格であったとしても購入してもらえるようになるため、価格競争から脱却できます。
たとえば、同じ素材・デザインの無地のパーカーでも、高級ブランドのタグやロゴがついているだけで、高額だったとしても「この高級ブランドの出しているパーカーならこれぐらいして当然だよな」と、市場が納得してくれるようになるのです。
また、自社の製品やサービスに固定客がつくようになり、リピート率の向上や、営業・販売コストの削減にもつながります。
◉-6、効果6:優秀な人材の採用・定着
企業が成長するためには優秀な人材を確保することが重要です。
企業ブランディングによって企業の魅力が広く周知されると、多くの人材が自社のことを知り好印象を抱いて応募してくることが期待できます。
たとえば、最強の町工場とも言われる浜野製作所は、どん底から這い上がった社長の創業ストーリーや、「脱下請け」の革新的なものづくりをいち早く打ち出し、「革新的な町工場」という企業ブランディングを確立しました。
企業ブランディングの一環として活用したのが「書籍の出版(ブックマーケティング)」です。
書籍の中で経営者のビジョンや考え方を共有したことで、深い共感を得ることができ、普通なら大企業やグローバル企業に行ってしまうような優秀な人材の確保ができるようになったそうです。
このように、求職メディアを利用しなくても、優秀な人材を獲得することができ、採用コストを大幅に削減できるのもメリットの1つと言えるでしょう。

◉-7、効果7:新規顧客の獲得
企業ブランドが認知されると、今まで接点のなかった層にも届き、新規顧客の獲得につながります。
特に、企業の価値観や社会的貢献に共感する消費者からの支持を得やすくなります。
たとえば、ヤンマーは、農業機械メーカーとしての伝統的なイメージを刷新するため、ブランドアイデンティティを「FLYING-Y」に統一し、デザイン面でも著名なデザイナーを起用しました。
これにより、若年層や新規顧客層からの注目を集め、ブランド価値の向上と新規顧客の獲得に成功しています。
◉-8、効果8:従業員のモチベーション向上
経営トップがビジョンや価値観を明確に発信すると、従業員のモチベーションやエンゲージメントが高まります。
たとえば、東京ディズニーリゾート(株式会社オリエンタルランド)では、従業員を「キャスト」と呼び、キャストをブランドの体現者としています。
最も重視すべきゴールや、5つの行動基準を共有し、キャスト自身が自分で考えて行動できるような教育方針を導入しているのが特徴です。
これにより、キャスト一人ひとりがブランドの価値や理念を理解している状態を作ることに成功しました。
理念が浸透すれば、自分の仕事が社会に貢献していることが実感でき、従業員の自発性や創造性が育まれ、モチベーションが向上します。

◉企業ブランディングの実施手順

企業ブランディングは、「どのような企業として世の中に認識されたいか」という根幹を定義する取り組みなので、最初の計画と準備が重要です。
企業ブランディングは、次のような5つのステップで進めます。
STEP1:現状分析を行う
STEP2:ターゲット顧客を明確にする
STEP3:ブランドの核(価値観・メッセージ)を策定する
STEP4:ブランド戦略を策定する
STEP5:実行・改善・測定を繰り返す |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、STEP1:現状分析を行う
まず最初に、自社や自社を取り巻く環境についての現状分析を行います。
ここでは、自社がどのように認知されているのか、競合環境はどうなっているのか、顧客が自社に抱いている印象やイメージは何かなどを調査することが大切です。
企業ブランディングの現状分析に用いられる代表的なフレームワークは、次の2つです。
| PEST分析 | 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4視点から、自社を取り巻くマクロ環境を分析する手法 |
| 3C分析 | 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3要素に着目して、自社の立ち位置を明確にする手法 |
PEST分析は、外部環境の大きな変化やトレンドを把握するのに適しており、3C分析は、具体的に市場でどのような競争が起こっているのかという点や、自社の立ち位置を明確にするのに適しています。
◉-2、STEP2:ターゲット顧客を明確にする
ブランディングでは、誰に伝えるかを明確にすることが重要です。
そのために、セグメント(顧客グループの分類)とペルソナ(具体的な理想顧客像)を設定します。
年齢や価値観などを細かく定めたペルソナを活用すると、より的確なメッセージ発信が可能です。
ターゲットを明確にすることで、ブランドのメッセージをピンポイントで届けることができます。
どの顧客層に対してどのような価値を提供するのかがはっきりするため、企業のブランドポジショニングも確立されていくのです。
また、マーケティング活動やプロモーション戦略をターゲットに合わせてカスタマイズすることも可能です。
◉-3、STEP3:ブランドの核(価値観・メッセージ)を策定する
ブランドの核となるのが、企業としてどんな価値を提供し、どんな存在でありたいのかという価値観やメッセージです。
ブランドの核には企業のミッション、ビジョン、バリューが含まれます。
ブランドの核は単なるスローガンではなく、企業としての哲学や世界観を明文化するもので、ここで決めたものがブランディングの軸となります。
ブランドの核がしっかりと定まることで、その後のマーケティング活動やコミュニケーションが一貫性を持ち、信頼感を高めることができるのです。
◉-4、STEP4:ブランド戦略を策定する
ブランドの核が明確になったら、次にそれを具体的にどのように伝えていくかを設計します。
具体的には、次のような要素があります。
・ロゴやカラー、フォントなどのビジュアル要素
・WebサイトやSNSでのメッセージの発信
・ブランディング広告やキャンペーン施策
ここで重要なことは、ブランドの方向性にブレがないように一貫したメッセージを発信していくことです。
ブランドがどのような立ち位置を取るのか、どのような市場に向けて発信するのかが定まるため、無駄の少ない効率的なマーケティング活動を行うことができます。
◉-5、STEP5:実行・改善・測定を繰り返す
ブランディングは一度やって終わりではありません。
実際に施策を実行したうえで、その効果を測定し必要に応じて改善し、PDCAサイクルを回します。
たとえば、次のような指標でブランド効果を評価していきます。
・SNSの投稿数やコメント数
・サイト滞在時間やコンバージョン率
経営環境や顧客ニーズの変化に合わせて継続的にアップデートすることが重要です。
◉企業ブランディングの手法

企業ブランディングを効果的に行うためには、一貫性が重要です。
それぞれの特徴を理解し、目的に応じて組み合わせることで、より強力なブランディングが可能になります。
企業ブランディングを効果的に行うための代表的な9つの手法は以下の通りです。
・ロゴとビジュアルアイデンティティの設計
・ブランディング広告の活用
・コンテンツマーケティングの実施
・SNSの活用
・インフルエンサーとのコラボレーション
・イメージキャラクターの作成
・イベント・セミナーの実施
・書籍の出版
・CSRの推進 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、ロゴとビジュアルアイデンティティの設計
ロゴや色、フォントといったビジュアル要素は、ブランドの世界観を視覚的に伝える重要なツールです。
たとえば、Appleのロゴやコカ・コーラの赤と曲線的なデザインなどは、強いブランドイメージを定着させています。
こうしたデザインには、まず企業の想いやストーリーを言葉として整理し、その内容をもとに一貫性あるビジュアルへ落とし込むプロセスが効果的です。
ロゴとビジュアルアイデンティティを作り上げるのと同時に使用方法についても厳しいガイドラインを設けることをおすすめします。
◉-2、ブランディング広告の活用
ブランディング広告は、企業の価値観や世界観を伝えるための広告手法です。
特に、企業ブランディングにおいては、マス広告、ディスプレイ広告、デジタル音声広告の3つが主に活用されます。
目的やターゲットに応じて使い分け、組み合わせることで、効果的にブランドイメージを浸透させることが可能です。
◉-2-1、マス広告
マス広告は、テレビCMや新聞・雑誌広告など、幅広い層にリーチできる伝統的な手法です。
信頼性やインパクトのある訴求に強く、企業の節目や社会的なメッセージ発信に適しています。
特に、ゴールデンタイムのテレビCMは、数百万人単位の視聴者にブランドをアピールできるため、一気に認知度を高め、ブランドを「知っている企業」に変えることが可能です。
マス広告の種類や特徴は次表の通りです。
| マス広告の種類 | 特徴 |
| テレビ | 全国規模での認知拡大に効果的 |
| ラジオ | 地域密着型の配信や「ながら聴き」に向く |
| 新聞 | 信頼性が高く、中高年層やビジネス層の読者が多い |
| 雑誌 | 専門性が高く読者ターゲットが明確で保存性も高い |
特に、新聞広告やNHKなどでの公共性の高いメディアでの広告出稿は、「この企業は信頼できる」と感じさせることができます。
特に保険・金融・医療など、信頼が重要な業種は信頼性を活用して広告を出稿すると良いでしょう。
◉-2-2、ディスプレイ広告
ディスプレイ広告は、画像や動画、フォント、色彩などを用いて、企業が伝えたいブランドイメージや世界観をそのまま表現できるのが強みです。
ターゲティング精度が高く、ペルソナに合わせた広告配信ができます。
また、リスティング広告とは異なり、検索行動をしていないユーザー(潜在顧客)にもリーチできるのが特徴です。
「知ってもらう」「印象づける」などの目的に適しており、ブランドの認知拡大に貢献します。
ディスプレイ広告の種類や特徴は次表の通りです。
| ディスプレイ広告の種類 | 特徴 |
| GDN(Google ディスプレイネットワーク) | Googleの提携先メディアに広告を配信できるネットワーク |
| YDA(Yahoo!ディスプレイ広告) | Yahoo! JAPANや提携メディアに配信される広告 |
| YouTube広告 | 動画による訴求力が高く、短時間で印象づけやすい |
広告のデザインがごちゃごちゃしていたり、メッセージが曖昧だったりすると、ユーザーには何の広告か分からずスルーされてしまいます。
ディスプレイ広告のビジュアルを作成する際は「誰に見せたいのか」「どんな印象を持ってもらいたいのか」を意識することが大切です。
◉-2-3、デジタル音声広告
音楽・音声メディアで配信される広告で、通勤中や作業中の「ながら聴き」で自然に情報が届き、声による共感や親近感を与えられます。
音声は、声のトーンやスピード、間などを通して、感情を伝えられるメディアです。
ナレーターやパーソナリティの声に親近感を持ちやすく、その親近感がそのまま企業の好感度に繋がります。
音声広告は、通勤中や家事の最中、運動中など、ながら時間に自然に耳に入ってくるため、視覚的広告よりもリスナーの注意を独占しやすいのが特徴です。
特に、Spotifyの音声広告は再生開始後はスキップできない仕様になっているため、広告が終了するまで視聴される割合は93%にのぼります。(※1)
デジタル音声広告の種類や特徴は次表の通りです。
| デジタル音声広告の種類 | 特徴 |
| Spotify | ・音楽ストリーミングサービス・無料ユーザー向けに楽曲の合間に音声広告が挿入される |
| YouTube | ・YouTube内で、音声中心の広告フォーマットを用いて配信・特にバックグラウンド再生時に効果的 |
| radiko | ・地上波ラジオをインターネット経由で聴けるサービス・地域密着型の広告展開が可能 |
| Voicy | ・パーソナリティによる音声コンテンツ配信プラットフォーム・情報感度の高いビジネス層へのアプローチに適している |
活用の具体例として、トヨタがSpotifyで出稿した音声広告が挙げられます。
若年層に向けたプロモーションの一環としてSpotifyを活用し、「ドライブに合うプレイリスト」とともに連動した音声広告を配信。
ブランドを「楽しいドライブ」と結び付けることで、ユーザーの印象に残りました。
視覚的なインパクトには欠けるため、短い言葉でどれだけ強く訴求するかが重要です。
参考※1:Spotify『デジタル音声広告って何?Spotifyの音声広告「きほんのき」』
◉-3、コンテンツマーケティングの実施
自社のWebサイトなどを利用して、顧客との信頼関係を構築する手法もあります。
これはコンテンツマーケティングと呼ばれ、顧客にとって役立つ知識やストーリーを発信し続けることによって、企業の信頼性を向上させるものです。
広告のように「売り込む」のではなく、価値ある情報を提供することで自然にブランドのファンを育てることができます。
多くの顧客は検索エンジンを利用して自分の興味や関心のある情報を検索するので、検索結果の上位に表示されるようなSEOライティングや、思わず読みたくなる、興味を湧かせるような企画力が重要となります。
主なコンテンツの種類と特徴は次表の通りです。
| コンテンツの種類 | 特徴 |
| オウンドメディア | ・企業が自社で運営する情報サイト・理念や専門性を継続的に発信できる |
| ブログ | ・社員の声や現場の情報を発信しやすい・柔軟な内容に対応可能 |
| 動画 | ・視覚と音でメッセージを伝えられる・SNSとも連携しやすい |
| ポッドキャスト | ・音声で継続的に情報を届けられる・通勤時間を狙った配信などに適している |
| ホワイトペーパー | ・専門性の高い資料でリード獲得や信頼構築に効果がある |
| メールマガジン | ・見込み顧客に直接情報を届け、関係性を維持できる |
| プレスリリース | ・企業のニュースや新商品を対外的に発信する |
| ランディングページ(LP) | ・特定の商品やサービスに特化したページ・成約率向上に効果がある |
たとえば、グループウェア開発のサイボウズは、自社の働き方改革やカルチャーを綴るコンテンツで、共感と話題性を両立し、ブランド好感度を向上させました。
このように、コンテンツマーケティングは、特に専門知識・ノウハウを持っている企業や、BtoB企業、化粧品などのリピート購入が重要な商品・サービスを展開する企業に向いています。
コンテンツは長期的に投稿していくことが前提となるため、短期的な数字ではなく企業の価値を伝え続ける姿勢が重要です。
▶︎コンテンツマーケティングについては、関連記事【コンテンツマーケティングとは? 広告費を削減して売上を増やす方法】をあわせて参考にしてください。
◉-4、SNSの活用
近年ではX(旧Twitter)やInstagram、TikTokなど、SNSを有効に活用して企業ブランディングを行う企業も増えています。
SNSは、ターゲット層や伝えたい内容の違いによってアカウントを使い分けられる上、Webサイトや文章、広告、CMなどでは伝わりきれない、社内の空気感や働いている社員の人間性、商品開発の細かいプロセスなどを、素早くユーザーに伝えることができます。
SNSの運用を成功させるポイントは、広告・宣伝ばかりを投稿するのではなく、ユーザーのニーズに寄り添った発信を心がけていくことです。
成果・結果を焦る余り、商品の広告や宣伝ばかり投稿していてはファンはつきません。
著名人とのコラボ企画を実施したり、フォロー&リポストキャンペーンを実施したり、代表者が想いを語ったり、開発者のこだわりをキャッチーに話したり、ユーザーといかに密なコミュニケーションを取れるかを考えていくことが何より重要です。
代表的なSNSの種類と特徴は次表の通りです。
| SNSの種類 | 特徴 |
| Facebook | 実名登録が基本で信頼性が高く、中高年層・ビジネス層に強い |
| Instagram | 写真・動画中心で、20~30代に人気 |
| X(旧Twitter) | 拡散力とリアルタイム性に優れ、幅広い世代が利用 |
| TikTok | 10~20代を中心に人気、トレンド性と拡散力が高い |
| YouTube | 中長尺動画の配信が可能で、専門性の高い発信に適している |
| LINE | 日本国内での利用率が高く、日常的な接点づくりに強み |
▶︎SNSマーケティングについては、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】をあわせて参考にしてください。
◉-5、インフルエンサーとのコラボレーション
インフルエンサーとの連携は、SNSを通じて多くの潜在顧客にリーチできる手法です。
特に若年層への訴求や、共感を得やすい第三者の推薦を得られる方法として有効です。
たとえば、海釣りに関する情報を発信しているインフルエンサーは、海釣りに興味があるフォロワーを多く抱えています。
そのため、海釣りに関する商品・サービスを展開している企業は、そのインフルエンサーとコラボレーションすれば、ターゲットにピンポイントで訴求することができるのです。
インフルエンサーに発信してもらうことができれば口コミのような効果が生まれ、ブランディングの効果を高めることができます。
インフルエンサーへの信頼も相まって企業自体の信頼も高めることが可能です。
ただし、インフルエンサーの価値観が自社ブランドと合っているかを慎重に見極めることが大切です。
◉-6、イメージキャラクターの作成
企業ブランディングにおいて、イメージキャラクターの作成も効果的な手法の1つです。
イメージキャラクターには、視覚的にストーリーやコンセプト・価値観などを伝える効果があるため、顧客の記憶に残りやすくブランドの認知度を高める効果が期待できます。
たとえば、不二家のペコちゃんや、ヤンマーのヤン坊・マー坊、NHKのチコちゃん、ソフトバンクのお父さん犬などが企業キャラクターとして有名です。
また、企業ではありませんが、ご当地キャラクターとして熊本のくまモンなども、キャラクターがきっかけで熊本に大きな経済効果をもたらしています。
このように接しやすいキャラクターがあることで、顧客との関係性が強くなり、購買意欲の向上による売上促進や競合他社との差別化にもつながります。
◉-7、イベント・セミナーの実施
企業が定期的に実施するイベントやセミナーも企業ブランディングに効果があります。
自社製品のプロモーションや自社の専門分野に関するセミナーや勉強会などを行うことによって知名度や顧客満足度の向上が期待できるのです。
また、企業の代表者や著名人を講師に招くことによって信頼感や安心感の向上が期待できます。
◉-8、書籍の出版
企業ブランディングの手法として企業出版という選択肢もあります。
企業出版と聞くと、企業が自費で名刺代わりに出版するようなイメージがあると思いますが、それとは目的が異なり、今注目されているブランディング手法の1つです。
企業出版は企業が自社の情報や専門知識を書籍の形式で出版し、著者のビジネスのブランディングや販促活動の一環として活用する手法です。
企業出版の代表的なメリットとして挙げられるのが、「業界内での知名度や信頼性の向上」「持続的な集客効果」「人材採用や人材教育への効果」です。
まず、出版物に自社の専門知識や実績をまとめることができるため、業界内での知名度や信頼性を高めることが可能です。
次に、出版物の流通期間は非常に長いため、広告やSNSなどと違って持続的な集客効果が期待できます。
また、出版物に企業理念やストーリー、自社商品の開発秘話などを盛り込むことができるため、人材採用や人材教育に効果を発揮することができます。
「文章を読まない」と言われる時代ですが、書籍を買う人は何らかの課題を持った上で文章を読みます。
そのため、一言では語れない創業ストーリーや、ビジネスモデル、こだわり、革新性、専門性を持っているような企業こそ、企業出版は「読まれる」という点で、おすすめの手法です。
企業出版を活用したマーケティング手法の一つに、ブックマーケティングがあります。
ブックマーケティングとは、企業出版などで出版した書籍やSNS、コンテンツマーケティングなど様々な手法を活用してブランディングやマーケティングを行い、信頼の獲得や認知の獲得といった企業の目的を達成するための手法です。
企業ブランディングを行うのであれば、企業出版という出版形態を活用しつつ、ブックマーケティングという視点からブランディングを行うのがおすすめです。
▶︎ブックマーケティング(企業出版)については、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】をあわせて参考にしてください。

◉-9、CSRの推進
CSR(企業の社会的責任)は企業の評価を高めるために重要なブランディング手法です。
CSRの推進が企業ブランディングに与える効果は、「社会と信頼関係の構築」「優秀な人材の獲得」など様々なものがありますが、最も効果が現れやすいのは「ブランドイメージの向上」でしょう。
たとえば、環境保全活動に取り組む企業は「エコに対する意識が高く、持続可能な社会に配慮する会社」として認知されやすくなります。
このように、CSRは企業のポジティブなイメージづくりに直結し、信頼性の高いブランドを形成する一助となるのです。
環境保護、地域社会への貢献、多様性の推進など、自社が社会に対してどのように責任を果たしているかを明確に発信することで、ポジティブなイメージを持ってもらうことができます。
◉企業ブランディングを成功に導く2つのポイント
企業ブランディングは一朝一夕で成果が出るものではありません。
特に重要な2つのポイントは以下の通りです。
・長期的な視点で取り組む
・適して指標を用いて効果検証する |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、長期的な視点で取り組む
企業ブランディングは短期間で効果が出るものではありません。
数年または10年ほどかかってやっとブランドイメージが定着することもありえます。
また、たとえ企業ブランディングが成功してブランド価値が向上したとしても、その後何もしなければ、時間と共にブランド価値は薄れていきます。
企業ブランディングは1度作り上げれば終わりではなく、それを維持して継続させることも重要なのです。
そのため、企業ブランディングには多くの時間とコストがかかりつづけることを認識しておきましょう。
◉-2、適した指標を用いて効果検証する
企業ブランディングを行っていく上では、定期的な指標のチェックが欠かせません。
しかし、企業ブランディングは、実際には目に見えない価値を伝えていくことになるため、効果検証がやりづらいという問題点があります。
たとえば、Web広告などであれば、クリック率や成約率など、数字で効果の検証をすることができますが、ブランディングの場合はどこでどのような数字に寄与しているのかを正確に測ることは難しいと言えます。
しかし、企業ブランディングは、企業として多大な時間とコストをかけて行うものだからこそ、方向性が間違っていないかどうか、などの判断は必要不可欠です。
そこで、企業ブランディングの評価によく用いられるのが「ブランドロイヤリティ」「ブランド認知度」「利益・売上貢献」と言った指標です。
効果検証がしづらい企業ブランディングですが、このように適した指標を使って、効果測定・評価をしていくことも重要です。
◉ブックマーケティング(企業出版)における企業ブランディングの成功事例

実際に、ブックマーケティング(企業出版)によって企業ブランディングに成功した事例を2件ご紹介します。
◉-1、出版による信頼性獲得で圧倒的な受注率を達成した不動産会社の事例
この不動産会社の経営者は、競合が多く、怪しい業者も多い中で、紹介から受注まで、顧客との関係性を構築していくまでに時間を必要としていました。
そのため、Web広告などでも正しくメリットを伝えきれず、悩んでいたそうです。
また、主要ターゲットが医師ということもあり、信頼性を獲得することに苦戦していました。
そこで、医師の悩みの1つである高額な税金について、最も効果的な節税対策として、不動産投資があることを紹介した書籍を出版。
書籍でしっかりと医師が不動産投資を行うメリットを詳しく説明したところ、多忙で節税対策などまで手が回らない多くの医師から信頼を得ることができ、発売2ヶ月で6億円の売上が生まれました。
結果として、医師向けの不動産投資の専門家としてのブランディングを確立。
その後も出版物を営業ツールとして配布したり、顧客間での紹介ツールに活用してもらったりすることによって、顧客との関係性構築までの時間の短縮につながり、成約率が飛躍的に上昇しています。
◉-2、セミナーや講演会依頼多数!新規事業の集客を実現した保険代理店の事例
この保険代理店の経営者は、保険業界に関する持論を提唱した書籍を出版。
保険業界の給与体系は成果に応じて給与が決まる「成果報酬型」が当たり前ですが、この保険代理店の経営者はこれに疑問を持ち「一律報酬型」に変えることを提唱していました。
つまり、少数のスーパー営業マンに頼る経営から、アベレージヒッターを育てていく再現性のある経営で業績拡大ができることを書籍で紹介したのです。
ひと言では伝え切ることができない持論について語った書籍を多くの業界関係者が読み、共感が生まれ、業界内でのブランディングを確立することができました。
結果として、多くのセミナーや講演会に招かれたり、新規のコンサル契約を獲得したり、紹介者が増えて本業の保険契約数が伸びるという効果が得られています。
◉【まとめ】企業によって最適なブランディング手法は異なる!まずは自社に合った手法を見つけよう
企業ブランディングは、企業が長期的に社会や顧客から信頼され、選ばれ続けるための戦略的な取り組みです。
重要なことは、自社の理念や価値観をしっかりと軸に据えたうえで、「誰に・どのように伝えるか」を明確にし、それに最適な手法を選ぶことです。
たとえば、前述した不動産会社や保険代理店の事例のように、ひと言で伝えることが難しいビジネスモデルや、こだわり、想いを持っているような方が、一瞬でユーザーメリットを伝えることが重要なWeb広告を活用してもあまり効果は期待できません。
一方で、ブックマーケティング(企業出版)という手法であれば、ターゲットに読んでもらえる、という点で有効なブランディング手段と言えます。
また、あらゆるブランディング手法などをすでにやっている企業がブランディングを強化していきたいという場合には、Web広告やSNSなど誰もができる手法よりも、ブックマーケティング(企業出版)やテレビCMなどのように、誰もがすぐにできない信頼性の高い手法を選んでいくことをおすすめします。
このように、会社によって最適なブランディング手法は異なります。
これから企業ブランディングを始める、または強化していきたいという方は、まずは自社に合ったブランディング方法は一体なんなのか、を考えるところから始めてみてはいかがでしょうか。