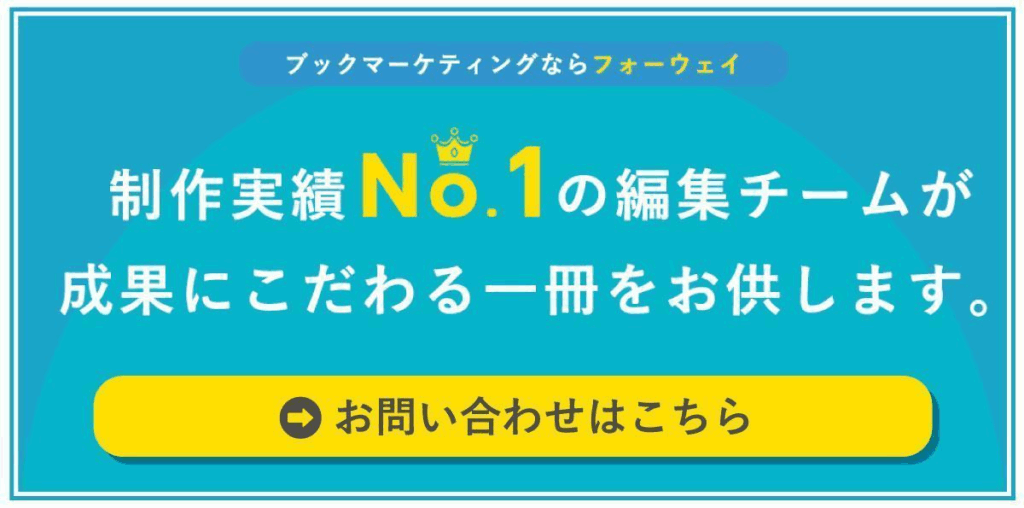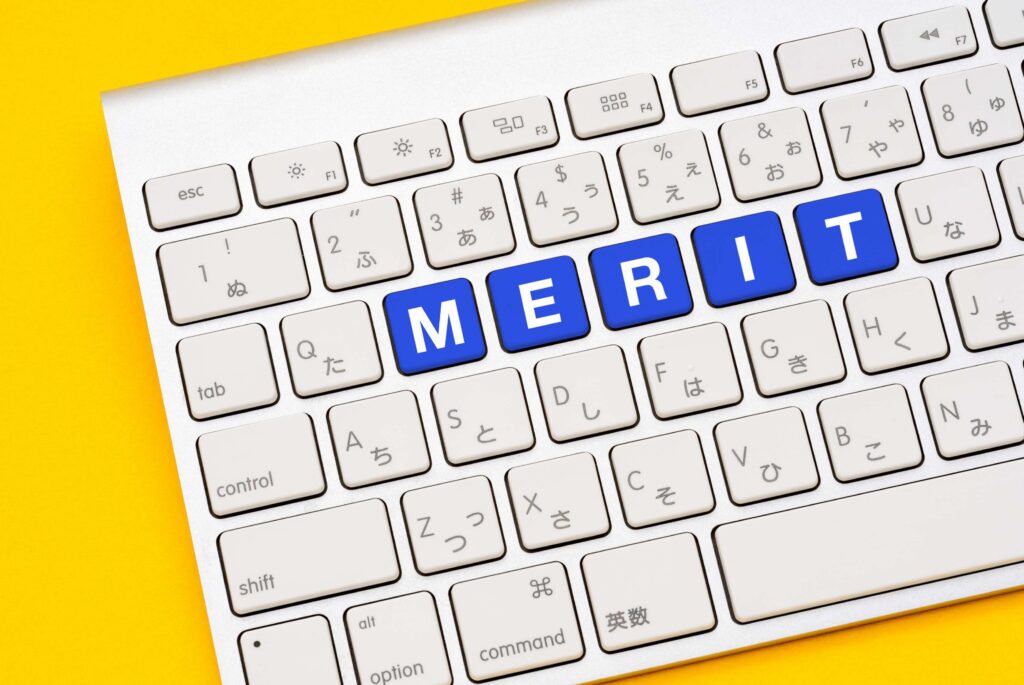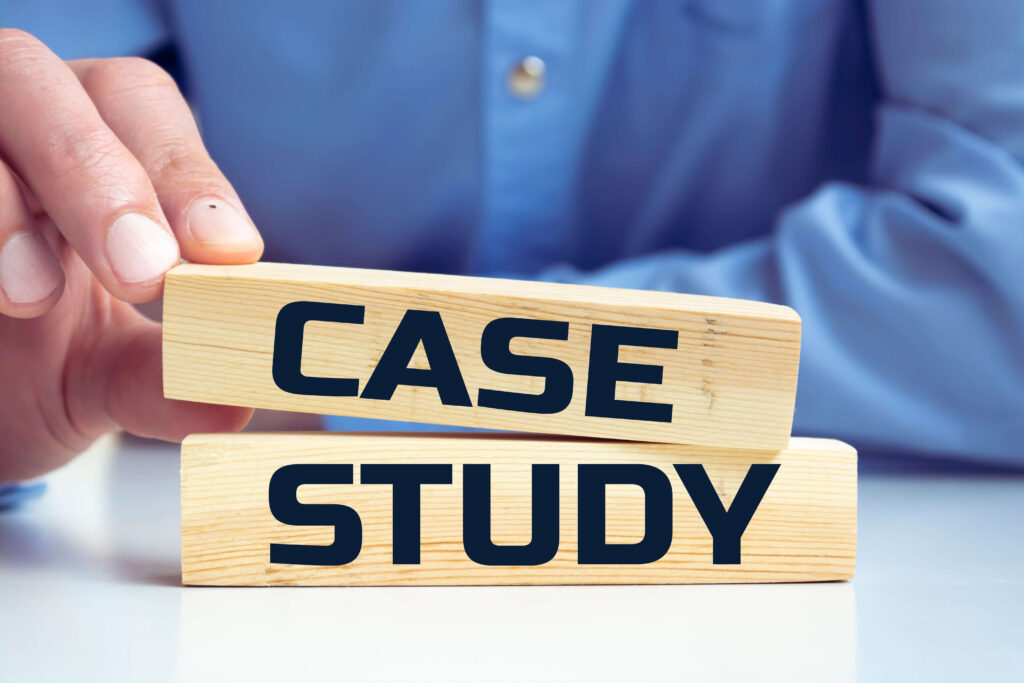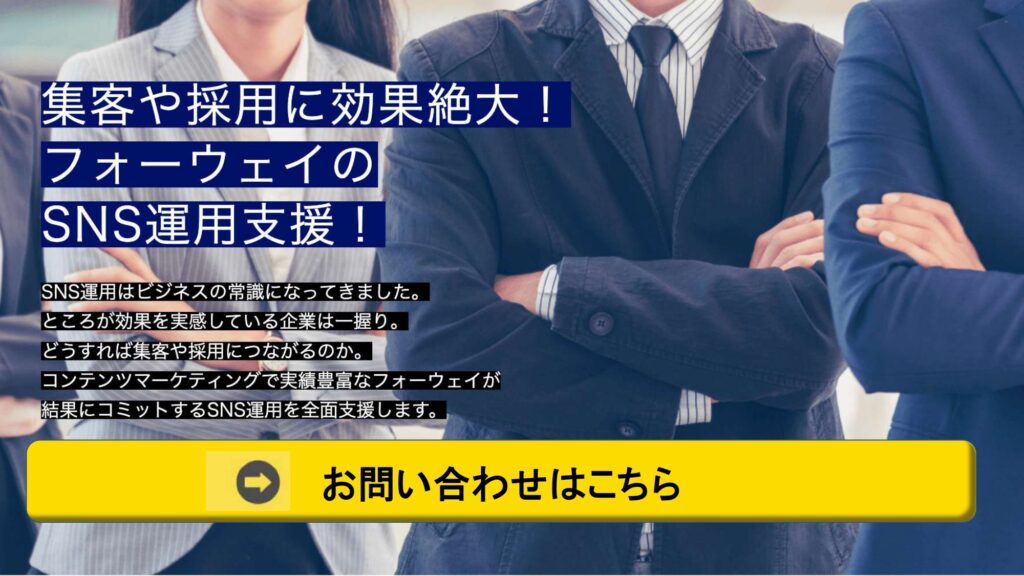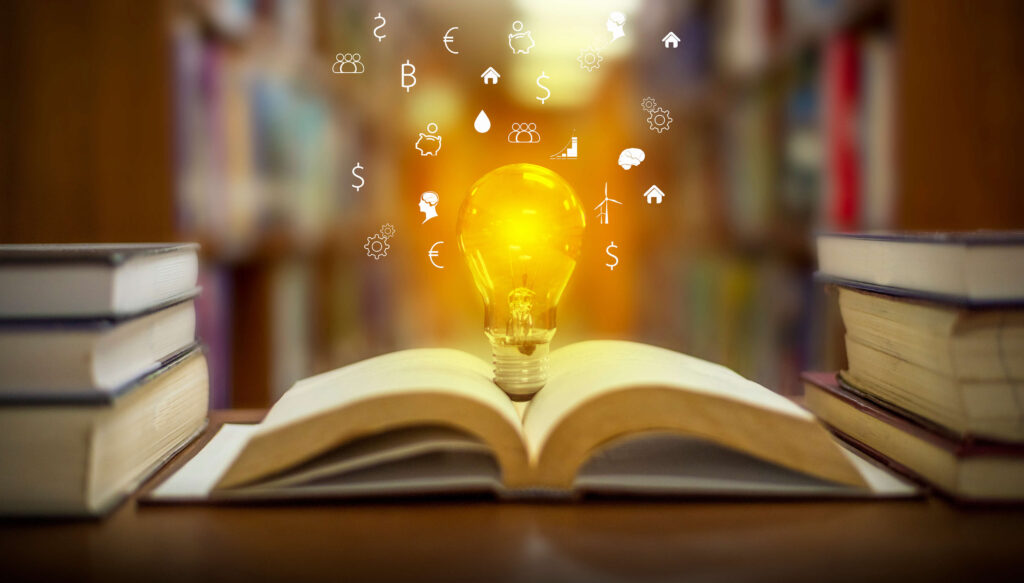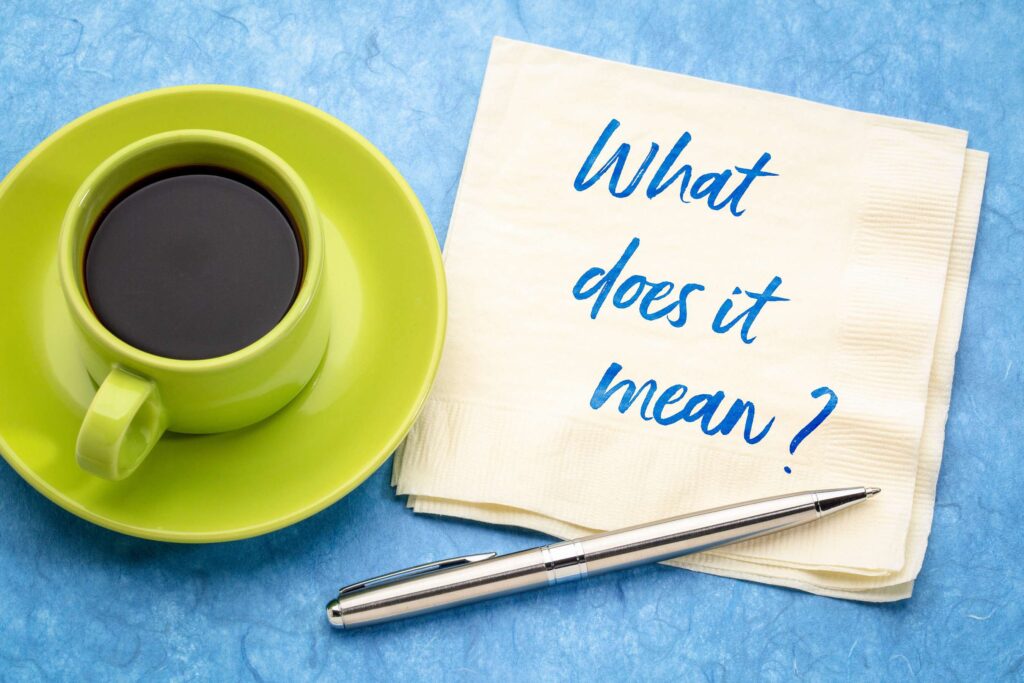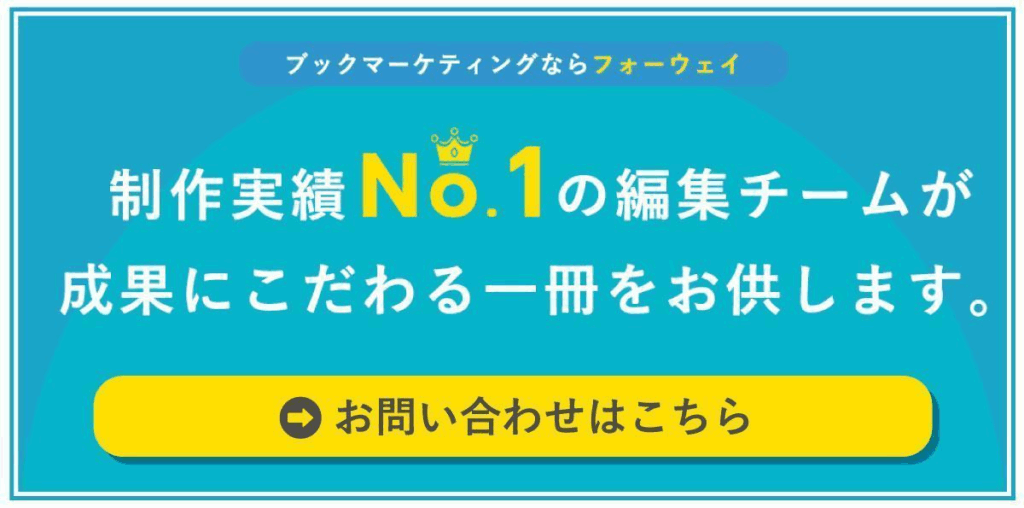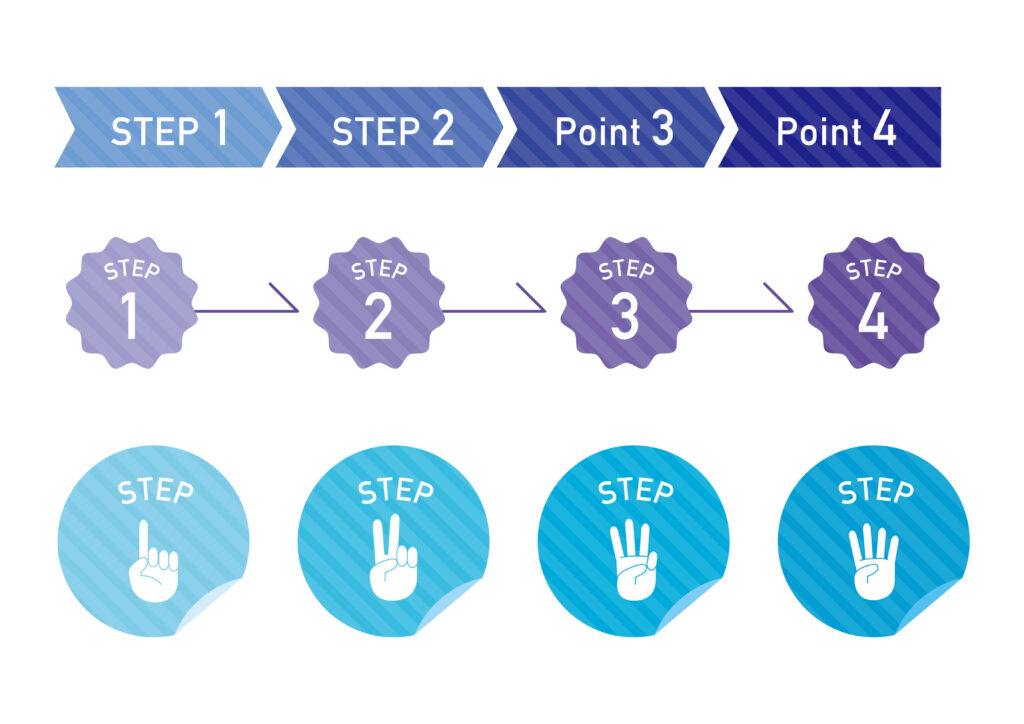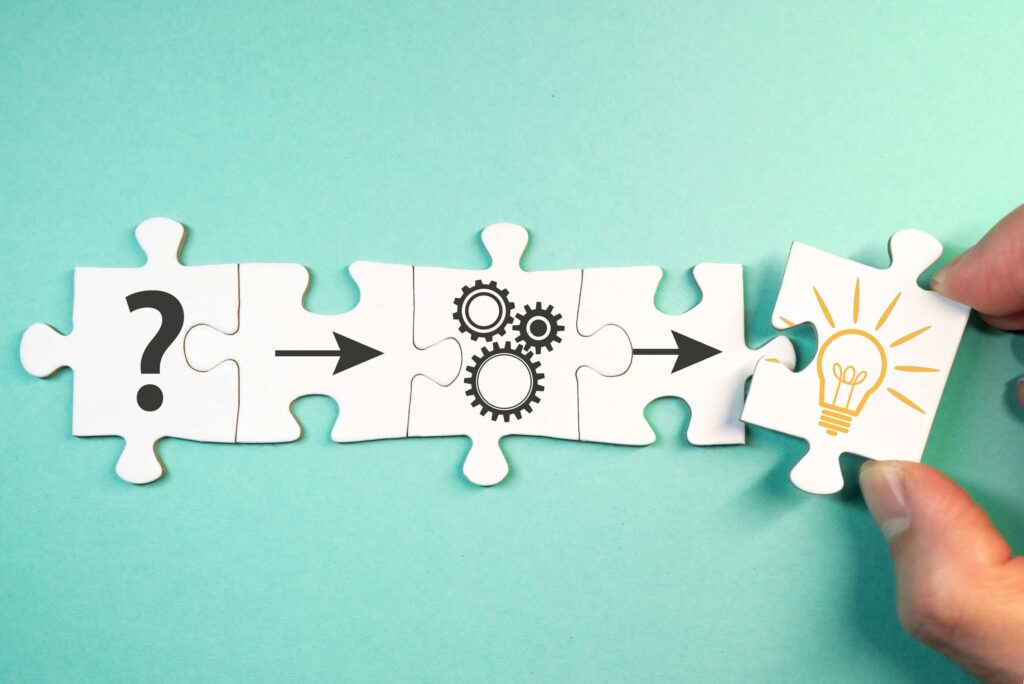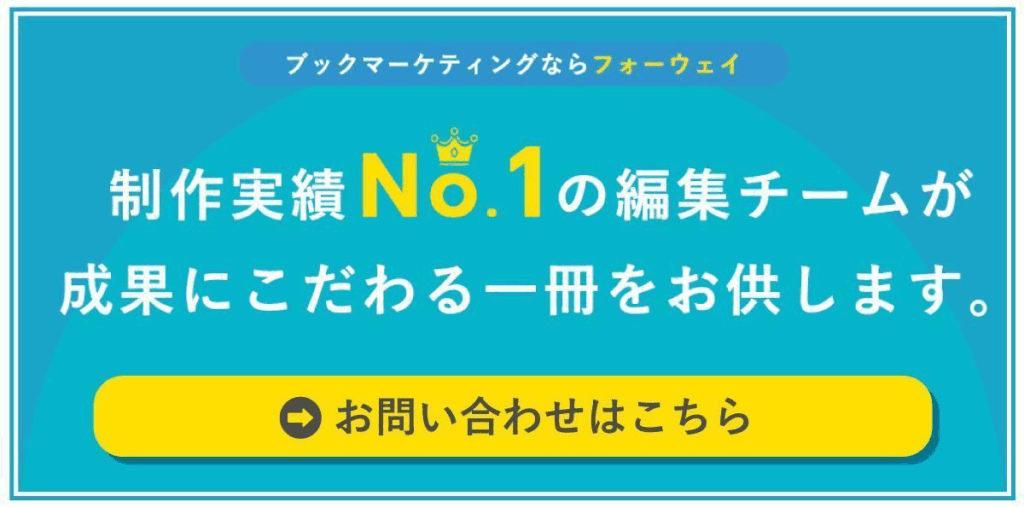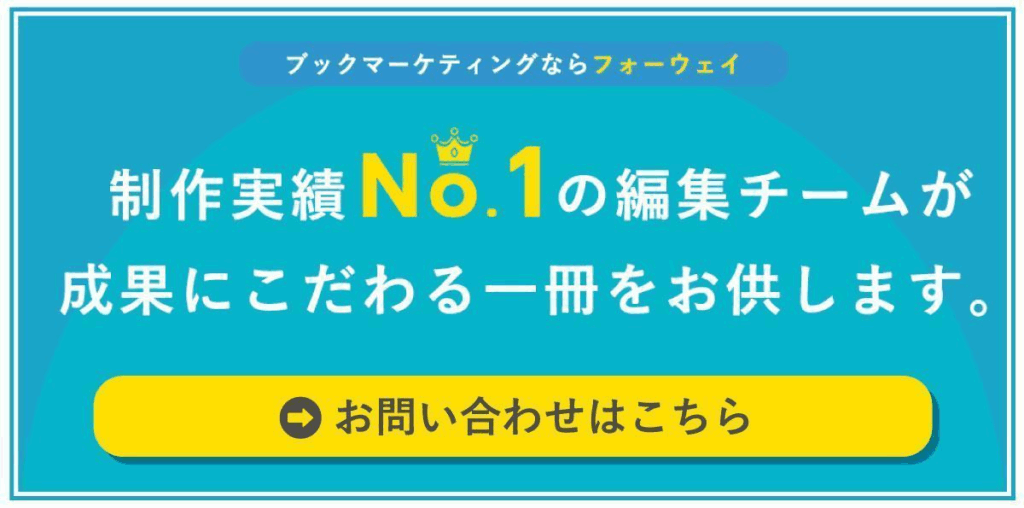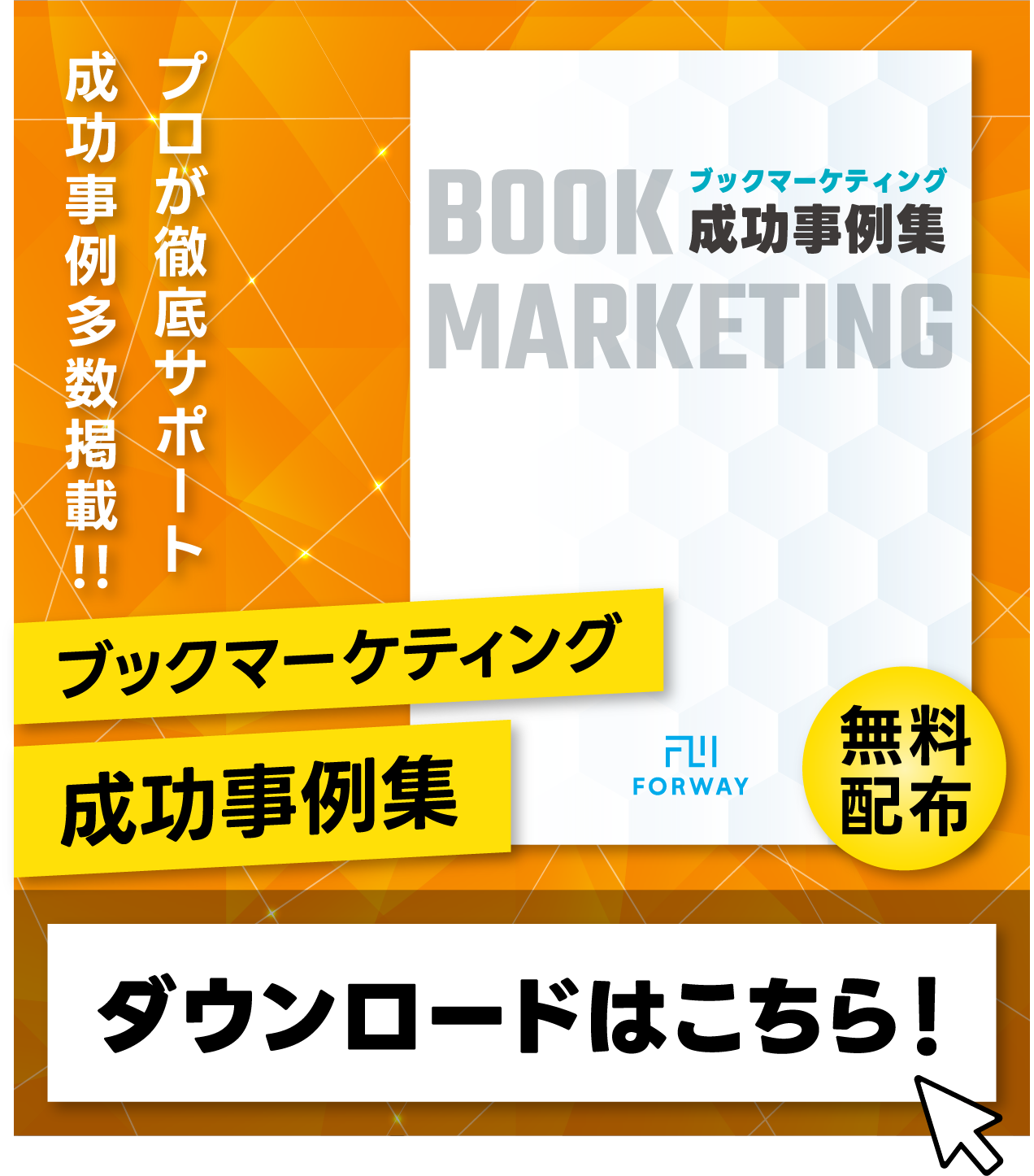トップセールスは、企業が事業を拡大していく過程で重要な役割を果たす取り組みとして注目されています。
社長が自ら動くことで、通常の営業活動では得られない信頼やスピードが生まれ、新たな取引や大型案件につながりやすくなるからです。
トップが前に出ることの意味や効果を正しく理解することで、自社の営業戦略のなかでどのように活用すべきかが見えてきます。
この記事では、社長が自ら営業する重要性について詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
トップセールスとは?

トップセールスとは、企業や組織において高い営業成果を継続的に上げている営業担当者や営業責任者を指します。
商品・サービスへの深い理解力や高い提案力、ヒアリング力を備え、顧客の成功を第一に考える姿勢を持っている点が特徴です。
その結果、個人の成果にとどまらず、組織全体の営業力向上にも好影響を与える存在となります。
一方で、トップセールスという言葉は、文脈によって「社長や創業者など企業のトップ自らが営業・広報・交渉の場に立つこと」を指す場合もあります。
この場合は、トップという立場だからこそ語れるビジョンや意思決定の背景、責任の所在を示しながら、相手の信頼や共感を得ていく営業活動を意味します。
権限や説得力、ブランドへの影響力が一般的な営業担当者とは異なるため、社長によるトップセールスには特有の効果があります。
◉社長によるトップセールスが重要な理由

社長が営業の第一線に立つトップセールスが重要とされる理由は、主に次の3点です。
- 社長が営業に出るだけで信頼されやすい
- 決裁者同士が直接話すことで商談が早く進む
- トップが動くと大型案件が生まれやすい
それぞれどのような理由なのかを詳しく見ていきましょう。
◉-1、社長が営業に出るだけで信頼されやすい
社長自らが商談の場に立つことで、相手企業は「この会社は本気で取り組んでいる」と受け止めやすくなり、信頼感が高まります。
トップが時間を割いて直接対応する姿勢そのものが、企業としての誠実さや覚悟を示すからです。
また、意思決定権を持つトップが説明を行うことで、話の内容に一層の説得力が生まれます。
その結果、相手が抱く不安や懸念もその場で解消しやすくなり、商談の前提となる信頼関係を短期間で築くことが可能になります。
◉-2、決裁者同士が直接話すことで商談が早く進む
社長と相手企業の決裁者が直接対話することで、意思決定のスピードが向上します。
通常の営業プロセスで発生する社内確認や持ち帰り検討が不要になり、その場で方向性が決まるケースが多いためです。
さらに、立場の近い決裁者同士だからこそ、条件面だけでなく経営判断の背景や本音を含めた議論が可能になります。
その結果、短期的な取引ではなく、継続的な関係構築を前提とした合意に至る可能性が高まります。
◉-3、トップが動くと大型案件が生まれやすい
企業のトップが前に出ることで、その商談は経営レベルの案件として扱われます。
相手側も重要案件として向き合うため、取引規模や契約期間を含めた検討が行われるようになります。
結果として、案件の検討範囲や契約期間についても踏み込んだ判断が行われ、より規模の大きい案件に発展しやすくなるのです。
◉トップセールスを成功させるための情報発信施策

トップセールスを成果につなげるためには、商談の場だけでなく、普段から社長自身の考えや姿勢を情報発信しておくことが欠かせません。
情報発信を通じて理解と信頼を積み重ねておくことで、商談を始める時点ですでに相手の信頼を得やすくなり、対話がスムーズに進むようになります。
社長が取り組みやすく、かつ効果の高い具体的な施策として、次の8つが挙げられます。
- 社長ブログやコラムで思想を発信する
- SNSで経営者としての視点や日常の気づきを共有する
- ニュースレターやメルマガで継続的な接点をつくる
- 動画コンテンツで社長の人柄と思想を伝える
- ウェビナーやセミナーで専門性とビジョンを示す
- 第三者メディアへの露出で信頼性を高める
- 社長名義のホワイトペーパーで価値観を体系化する
- 書籍出版で社長の思想を深く伝え、権威性を高める
以下では、それぞれの施策がどのようにトップセールスの成果に結び付くのかを詳しく見ていきましょう。
◉-1、社長ブログやコラムで思想を発信する
社長が自社の価値観や事業に対する考え方を文章として発信すると、商談前から企業としての姿勢や方向性を伝えられます。
トップの考えが事前に共有されている状態で商談に入るため、対話の質も高まります。
また、経営者自身の言葉には、他のコンテンツにはない重みがあるものです。
そのため、ブログやコラムを通じて考え方に触れた読者が企業そのものに関心を持ち、商談や問い合わせにつながるケースも少なくありません。
◉-2、SNSで経営者としての視点や日常の気づきを共有する
SNSでは、社長の日々の気づきや業界に対する見方を短い言葉で伝えられます。
継続的に発信することで、社長の考え方が少しずつ伝わり、読み手との距離が縮まります。
こうした発信に触れた相手は、初めて話す場面でも社長の人物像をある程度理解しているため、商談に入る際の心理的なハードルが下がり、対話がスムーズに進むのです。
▶︎SNSの詳細については、関連記事【【保存版】SNS運用とは?手順や失敗例、集客につなげる運用術を解説!】もあわせて参考にしてください。
◉-3、ニュースレターやメルマガで継続的な接点をつくる
社長名義のニュースレターやメルマガは、見込み顧客との接点を継続的に保つ手段として効果的です。
一度きりの接触ではなく、定期的に考え方や情報を届けると、関係性を段階的に深めていくことが可能です。
売り込みを前面に出さず、価値ある内容を積み重ねることで、いざ商談の機会が訪れた際に「信頼できる相手」として想起されやすくなります。
◉-4、動画コンテンツで社長の人柄と思想を伝える
動画は、文章だけでは伝わりにくい声のトーンや表情、話し方といった要素まで含めて伝えられる点が特徴です。
社長の人柄や誠実さが自然に伝わることで、企業に対する安心感や信頼感を持ってもらいやすくなります。
事前に動画を通じて考え方を理解したうえで商談に臨んでもらえると、相手も構えずに話を聞きやすくなり、冒頭から具体的な議論を進められるでしょう。
◉-5、ウェビナーやセミナーで専門性とビジョンを示す
社長がウェビナーやセミナーで直接テーマを解説することで、その分野に対する理解の深さや視座の高さが明確に伝わります。
単なる商品説明ではなく、業界全体や課題の背景をどうとらえているかを示せる点も特徴です。
参加者にとっては、情報を得る場であると同時に「この社長と話してみたい」と感じるきっかけにもなり、その後の商談につながる重要な接点となります。
◉-6、第三者メディアへの露出で信頼性を高める
外部メディアに取り上げられることは、社長の発信内容が第三者の視点で評価された結果です。
自社による情報発信だけでは得られない客観性が加わることで、社長の発言がより信頼できるものとして受け取られるようになります。
結果として、社長個人への信頼だけでなく、企業全体のイメージ向上にもつながり、商談に入る前段階での信頼をより確かなものにします。
◉-7、社長名義のホワイトペーパーで価値観を体系化する
市場や顧客の課題、自社が提供できる価値を社長の視点で整理し、資料としてまとめることで、トップの考え方を体系的に伝えることができます。
ホワイトペーパーでは、断片的な情報ではなく全体像を示せる点が強みです。
商談前にこうした資料に目を通してもらうことで、相手の理解度が高まり、具体的な議論に時間を使えるようになります。
▶︎ホワイトペーパーの詳細については、関連記事【マーケティングにおけるホワイトペーパーの役割とは?信頼を生む情報発信の仕組み】もあわせて参考にしてください。
◉-8、書籍出版で社長の思想を深く伝え、権威性を高める
社長の思想や経験を一冊の書籍としてまとめると、背景や判断の理由まで含めて体系的に伝えられます。
書籍は時間をかけて読まれる媒体であり、信頼形成において重要な役割を果たすのです。
また、書籍を出版できること自体が企業の信頼性を補完する要素となり、高単価サービスやBtoB領域では、商談の成功率を高める強力な施策になります。
▶︎書籍出版の詳細については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

書籍をトップセールス強化に活用するメリット
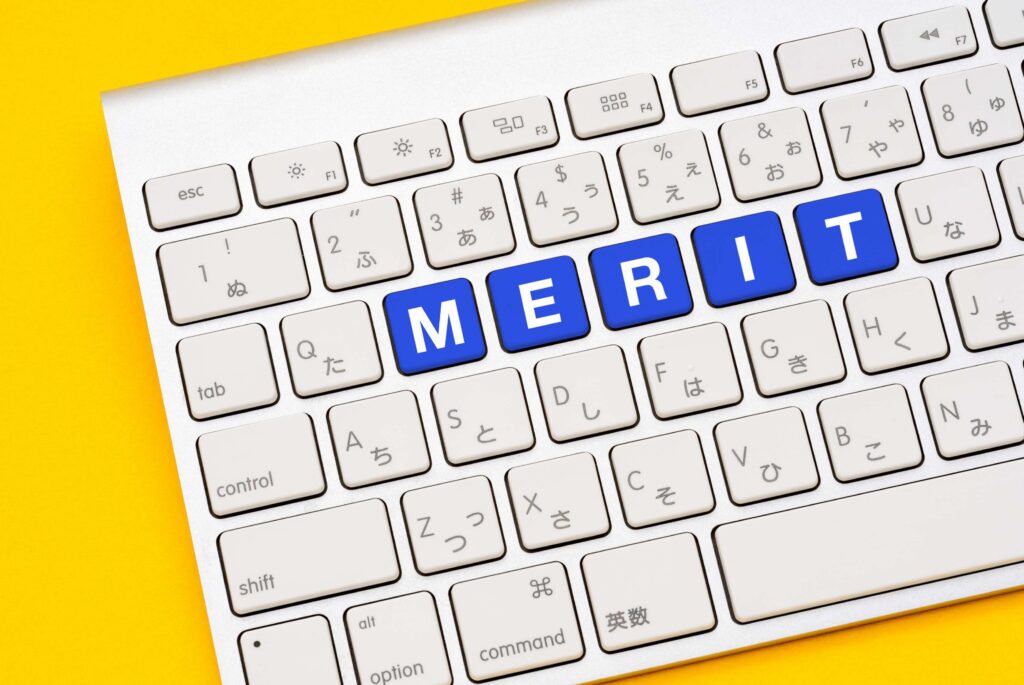
書籍を活用したトップセールスには、商談前の関係構築から営業活動の効率化まで、実務上の明確なメリットがあります。
代表的なポイントは、次の4つです。
- 商談前から顧客と信頼関係を築ける
- 長期間にわたって理念や価値観を伝えられる
- 営業活動の効率アップが図れる
- 読者からの紹介による新規顧客が獲得できる
以下で、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、商談前から顧客と信頼関係を築ける
書籍を読んだ状態で商談に進む顧客は、すでに社長の考え方や事業への姿勢を把握しています。
そのため、初回の商談の場でも前提が共有され、信頼関係を築くための土台が整った状態で話を進められます。
商談の際に一から背景を説明する必要が減り、より具体的で実務的な話に時間を使える点もメリットです。
◉-2、長期間にわたって理念や価値観を伝えられる
書籍は一度発行すれば、長期間にわたって読者の手元に残る媒体です。
社長の理念や価値観を、時間をかけて繰り返し伝えられる点は、他の情報発信手段にはない特徴といえます。
短期的な発信では伝えきれない背景や考え方まで含めて届けられるため、企業全体に対する理解が深まり、企業の方向性も明確に伝えることができます。
◉-3、営業活動の効率アップが図れる
書籍は営業資料としても活用できるため、顧客が事前に内容を理解したうえで商談に臨むことが可能です。
その結果、説明にかかる時間が削減され、より本質的な相談や判断に時間を使えるようになります。
また、書籍を通じて一定の信頼が形成されているため、商談の進行がスムーズになり、成約率の向上も期待できます。
◉-4、読者からの紹介による新規顧客が獲得できる
書籍は、顧客や関係者を通じて周囲に紹介されやすい媒体です。
読者が内容に共感した場合、知人や取引先に紹介してくれるケースも少なくありません。
その結果、書籍を通じて自社の理念や専門性を知った新たな層にリーチでき、営業活動の広がりを自然に生み出すことができるようになります。

書籍活用によるトップセールスの成功事例

ここでは、書籍活用によるトップセールスの成功事例を3つ紹介します。
- 書籍で持論を展開して大口案件や新規顧客を獲得した事例
- 社長の仕事観や経営哲学を書籍で訴えて採用強化を実現した事例
- 社長の経験や考え方を書籍で伝えてリピート率をアップした事例
以下で、それぞれの事例について詳しく見ていきましょう。
◉-1、書籍で持論を展開して大口案件や新規顧客を獲得した事例
法人向けの保険代理店の社長は、保険代理店向けのコンサルティング顧客の新規獲得と信頼性向上を目的に書籍を出版しました。
成果報酬が一般的な保険業界で、月額報酬制を採用して事業を伸長させた持論とノウハウを体系化して1冊の書籍にまとめています。
結果として、2週間で重版出来、出版記念セミナーには60名が参加し、うち5件が成約につながるなどの効果が得られました。
その後、さらなる事業拡大のために社名を変更し、そのタイミングでリブランディングのために2冊目の書籍を出版。
大手外資系生保の全国No.1セールスの実績を持つ社長が、「顧客に本当に必要とされる営業」の本質を体系化して公開し、さらなる事業拡大に成功しました。
【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店
◉-2、社長の仕事観や経営哲学を書籍で訴えて採用強化を実現した事例
湘南エリアを地盤に事業活動を行っている建設会社では、慢性的な人材不足が課題となっていました。
せっかくの受注機会を十分に活かせない状態が続いていたことから、人材の採用強化と自社のブランディングを目的として書籍を出版。
社長自身の仕事観や経営哲学、創業ストーリーなどを体系的にまとめて、地元の若手人材に「働きたい」会社だと思ってもらえるような内容にしました。
その結果、事前に書籍を読んで、その内容に共感した求職者の応募が増え採用率が向上しました。
また、年間500万円以上かかっていた採用エージェント費を削減することにも成功。
さらに、出版をきっかけに地元紙をはじめとした複数のメディアから取材依頼が寄せられ、地域内での認知度が一気に向上し、業界内で一目置かれるようになりました。
◉-3、社長の経験や考え方を書籍で伝えてリピート率をアップした事例
女性向けサプリメントを展開するサプリメントメーカーの経営者は、既存顧客との関係強化と新規顧客獲得の両立を目的として書籍を出版しました。
書籍には、社長自身の経験や健康に関する考え方をまとめ、読者にとって役立つ実用的な内容に仕上げました。
出版後の早い段階で、「書籍無料プレゼント」キャンペーンを実施したところ、想定を大きく上回る6倍もの応募を得ることができ、多くの新規顧客との接点を創出することにも成功。
加えて、書籍をきっかけに企業や商品の背景を理解してもらえるようになり、購入者のリピート率が向上しました。
自社メディアでの継続的なコミュニケーションとカスタマーサポートによって、ブランドへの信頼を高めることにも成功しました。
【事例コラム】”書籍無料プレゼント”に想定の6倍の応募、リピート率アップにインパクト!サプリメントメーカーの出版プロジェクト
◉【まとめ】トップセールスを成功させるために企業出版を有効活用しよう!
本記事では、トップセールスが企業にとって重要とされる理由や、成功につなげるための情報発信施策、書籍を活用するメリットや事例について解説しました。
トップセールスとは、企業のトップである社長が前面に立つことで、信頼性・スピード感・ブランド力を同時に高められる、非常に有効な営業手法です。
なかでも、書籍を活用した情報発信を組み合わせることで、商談前から見込み顧客に企業や経営者への理解を深めてもらいやすくなり、営業効率や成約率の向上が期待できます。
このように、企業出版は社長の思想を体系化し、長期的な信頼と事業機会を生み出す有効な手段なのです。
フォーウェイでは、企業出版による書籍を営業活動に活用する「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
これまで多くの企業の出版支援を行い、営業・採用・ブランディングといった分野での成果創出をサポートしてきました。
企業出版をマーケティングに活用したいとお考えの方は、ぜひフォーウェイまでお気軽にご相談ください。


近年、SNSやデジタル広告の普及によって、企業と顧客の接点は多様化しています。
一方で、「企業の想いをどう伝えるか」「ブランドをどう記憶に残すか」といった課題は、以前よりも難しくなっています。
こうした中で注目されているのが「キャラクターマーケティング」です。
キャラクターは、企業理念や価値を親しみやすい形で伝え、顧客とのコミュニケーションをスムーズにする役割を果たします。
この記事では、キャラクターマーケティングの効果や設計ポイント、成功事例などについて紹介します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
キャラクターマーケティングとは

キャラクターマーケティングとは、企業や商品・サービスの世界観を象徴するキャラクターを活用して、顧客との接点づくりとコミュニケーションを強化する手法です。
キャラクターには、ブランドの特徴をわかりやすく表現し、顧客の注意を引きやすいという特徴があります。
また、キャラクターを通じて企業が伝えたい情報を自然に届けることができるため、認知の獲得やロイヤルティの向上にもつながります。
このように、キャラクターは単なるデザイン要素ではなく、コミュニケーション全体を支えるために重要です。
企業がキャラクターマーケティングを行う目的

企業がキャラクターマーケティングを導入する目的は、キャラクターに「人格」をもたせて、ブランドメッセージを親しみやすい形で届けることです。
堅苦しくなりがちな企業理念や専門的な内容も、キャラクターが説明役として登場することで受け入れられやすくなります。
また、キャラクターの表情や言動は人の感情に訴えかけ、企業と顧客との心理的距離を縮める効果があります。
その結果、ブランドの理解促進や好感度の向上、継続的なファンづくりなど、複数の目的を同時に達成できることも特徴です。
キャラクターマーケティングが事業成長にもたらす効果

情報があふれている現代では「覚えてもらう工夫」が重要になっています。
キャラクターを使うと視覚的な印象を残しやすくなり、ブランドの世界観をわかりやすく伝えることができるようになります。
キャラクターを活用することによる主な効果は次の通りです。
- ブランドの認知度向上と差別化効果
- 顧客との心理的距離を縮める効果
- 継続的なファン育成につながる効果
- ブランドを資産化する効果
それぞれの効果を詳しく見ていきましょう。
◉-1、ブランドの認知度向上と差別化効果
市場に競合が多い場合でも、キャラクターを利用することでブランドの独自性を強く印象づけることができます。
特に視覚的に特徴のあるキャラクターは、一度見ただけで顧客に覚えてもらうことができ、広告やSNSに登場するたびに認知を積み重ねることができます。
さらに、同じ業界内に類似の商品やサービスが存在する場合でも、キャラクターの個性や世界観によって明確な差別化が可能です。
◉-2、顧客との心理的距離を縮める効果
人はキャラクターに対して感情移入しやすく、親しみを感じるとその背景にある企業や商品にも好意を抱くようになります。
キャラクターの言動やビジュアルは、企業メッセージに親しみをもたせ情報を受け取りやすい雰囲気をつくります。
結果として、企業への信頼醸成につながり、商品やサービスへの理解が進みやすくなるのです。
◉-3、継続的なファン育成につながる効果
キャラクターがSNSや動画の中で「語り手」として登場するだけで、情報を自然に読み進めてもらえるというメリットがあります。
キャラクターを通じてブランドの世界観が一貫して表現され、ストーリーが継続的に展開されるほど、顧客は先の展開に興味を持ちやすく、継続的なエンゲージメントにつながります。
企業と顧客のコミュニケーションを自然に維持できる点は、キャラクターマーケティングの強みです。
◉-4、ブランドを資産化する効果
魅力あるキャラクターは、ブランドの象徴として長期にわたり利用できる資産となります。
キャラクターを継続的に活用することで、企業が発信する情報のトーンが揃い、結果としてブランドの世界観が伝わりやすくなります。
また、キャラクターグッズの展開やライセンス販売などによって、新たな収益機会を生み出すことも可能です。
キャラクターマーケティングは主に2パターン

キャラクターマーケティングは主に次の2つの方法に分類できます。
以下で、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、既存キャラクター
既存キャラクターは、アニメや人気コンテンツなど、すでに認知されているキャラクターを企業のマーケティングに活用する手法です。
既存キャラクターの知名度を活用できるため、短期間で認知を拡大したい場合に効果的です。
また、キャラクター自体のファン層にリーチでき、話題化しやすいというメリットもあります。
一方で、ブランドとキャラクターの世界観の一致度に限界があり、他社と同じキャラクターを使う場合は独自性が出しにくいという側面もあります。
◉-2、オリジナルキャラクター
オリジナルキャラクターは、企業やブランド独自の世界観を体現するキャラクターをゼロから設計する手法です。
ブランドの世界観を一貫して伝えられるため、長期的なブランド資産として育てられます。
特にSNSや広告、出版物、イベントなど多様なチャネルで活用しやすく、顧客との関係性を深める効果が高いという特徴があります。
ただし、認知が広がるまで時間がかかるため、戦略的な育成と継続的な運用が不可欠です。
ブランド独自の世界観を構築したい企業や、長期視点で顧客と関係を築きたい場合に適しています。
キャラクターマーケティングを成功させるには?

キャラクターマーケティングを成功させるための施策として、主に次の4つの手法があります。
- 複数の顧客接点でキャラクターを活用する
- デジタル施策・イベント施策と連携する
- ファンのエンゲージメントを強化し、ファン層を育成する
- 出版物へのキャラクター活用によるブランド発信を行う
それぞれ、どのような手法なのかを詳しく見ていきましょう。
◉-1、複数の顧客接点でキャラクターを活用する
まずやるべきなのは、キャラクターの露出を増やして顧客に認知してもらうことです。
WebサイトやSNS、広告、イベントなど、顧客が利用する複数のチャネルでキャラクターを活用した露出を増やして認知の拡大を図ることが重要です。
たとえば、ある食品メーカーでは、自社オリジナルキャラクターをWebサイトの案内役として起用すると同時に、店頭POPやSNSにも継続的に登場させました。
その結果、購入前の認知度が向上し、SNSでの投稿数も増加するなど、ブランド全体の認知拡大につながっています。
◉-2、デジタル施策・イベント施策と連携する
デジタル施策としては、キャラクター自身のSNSアカウントを作成して企業メッセージを発信し、顧客に親近感を抱いてもらいエンゲージメントを高める手法があります。
また、イベントを開催して顧客との交流の場を設けてファン化を促進させることも可能です。
たとえば、あるアパレル企業は、キャラクター自身のSNSアカウントを運用し、イベント前にキャラクターが告知を行うことで参加申込数の増加につながった事例もあります。
複数のチャネルにキャラクターを登場させて、相乗効果を狙うことも考えられます。
◉-3、ファンのエンゲージメントを強化し、ファン層を育成する
キャラクターの認知が広がってきてファン層が獲得できたら、次のようなコミュニケーションを通じて関係性を深めていくことが重要です。
| 施策 | 具体的な内容 |
| 参加型キャンペーン | プレゼントキャンペーン、イベントの実施 |
| ユーザー生成コンテンツ(UGC)の促進 | SNSなどでファンによるコンテンツ発信 |
| ファンコミュニティの活用 | SNSなどでコミュニティを開設・運営 |
たとえば、ある雑貨メーカーで、キャラクターを使った写真投稿キャンペーンを実施したところ、ファンによるUGCが想定以上に拡散し、オンラインストアのアクセスが増えた事例があります。
また、地域密着型の飲食チェーンでは、キャラクターを用いたスタンプラリー企画を行い、限定ノベルティが話題となってファン化が進みました。
◉-4、出版物へのキャラクター活用によるブランド発信を行う
キャラクターは、情報を整理して分かりやすく伝えられる点で、出版物との親和性が高い存在です。
出版物内でキャラクターをナビゲーター役として配置することで、内容の理解度が高まり、企業理念や専門的な情報も無理なく読者に届けられます。
パンフレットやホワイトペーパーなどに継続的に登場させれば、表現のトーンや世界観に統一感が生まれ、長期的に活用できるブランド資産として育てていくことも可能です。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

出版物にキャラクターを取り入れる際の設計ポイント

企業パンフレットや採用案内、サービス紹介冊子などの出版物にキャラクターを取り入れる例は業種を問わず広がっています。
出版物でキャラクターを活用する際の主な設計ポイントとして、次の4つが挙げられます。
- ブランドトーンに合ったキャラクター設計を意識する
- 出版物全体にキャラクターを組み込む
- キャラクターの配置で読みやすさを高める
- キャラクターの表現ルールを設定する
以下で、それぞれについて詳しく解説します。
◉-1、ブランドトーンに合ったキャラクター設計を意識する
キャラクターを出版物で活用する際は、ブランドが伝えたい価値や方向性とキャラクターの性格・役割を一致させることが基本となります。
キャラクターの口調、行動、表情がブランドのトーンと合っていることで、出版物の内容が自然に受け取られやすくなります。
一貫性が保たれることで、読者の中にブランドの印象が定着し、長期的な信頼構築にもつながるのです。
◉-2、出版物全体にキャラクターを組み込む
キャラクターは単発で登場させるよりも、出版物全体に配置することで効果が高まります。
章やページごとにキャラクターがナビゲーターとして登場すると、読者は自然と読み進めやすくなり、出版物としての統一感が出ます。
キャラクターの役割を「案内役」「質問役」「まとめ役」などに設定することで、情報の流れが整理され、読者にストレスを与えない構成になるのです。
◉-3、キャラクターの配置で読みやすさを高める
難しい内容の噛み砕き役としてキャラクターを配置することで、読者の理解を助けることができます。
重要ポイントの説明や注意点の強調など、読んでほしい部分にキャラクターを添えるだけで、視線誘導が生まれ読みやすさが向上します。
特に専門性が高い内容を扱う場合は、キャラクターを要所に置くことで読者の負担が軽くなり、情報がスムーズに伝わる効果が期待できるのです。
◉-4、キャラクターの表現ルールを設定する
キャラクターを出版物で活用する際は、ビジュアルや口調に統一したルールを設けることが重要です。
表情・色・文字の扱い・セリフのトーンなどが場面ごとにばらつくと全体の印象が散漫になり、読者の理解を妨げてしまいます。
あらかじめ「どの場面でどの表情を使うか」「セリフはどの程度の口調にするか」などのガイドラインを定めておくことで、出版物全体に一貫性が生まれ、ブランドメッセージもより伝わりやすくなります。
キャラクターを活用した出版物の成功事例
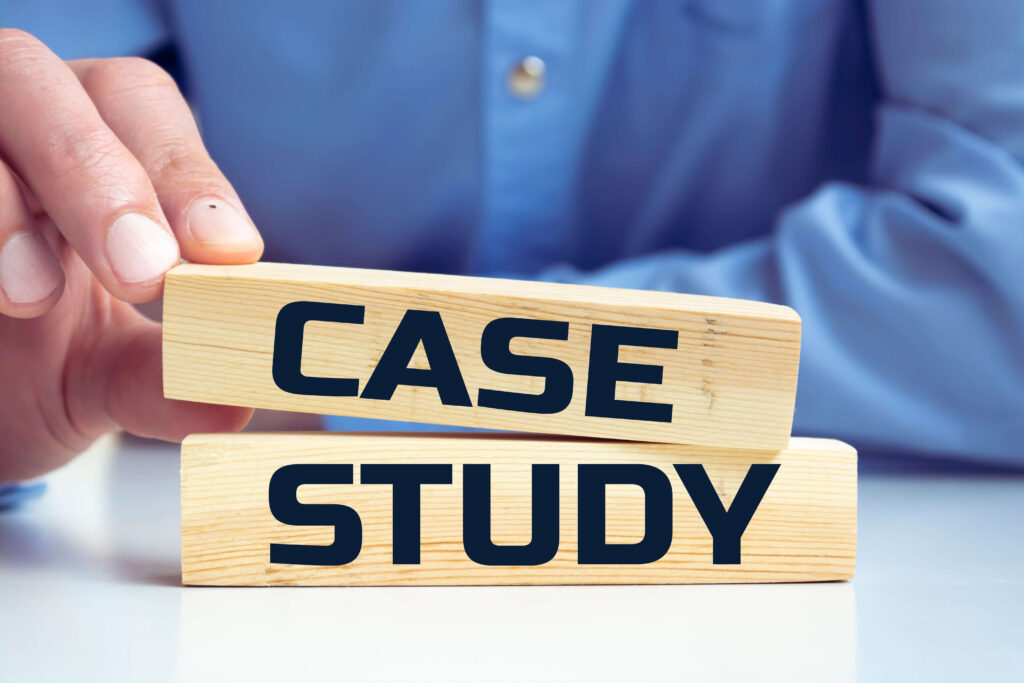
ここでは、紙媒体ならではの強みを生かした出版物の成功事例を5件紹介します。
- 観光パンフレットにおけるキャラクター活用
- 採用パンフレットでのキャラクター活用
- 会社案内冊子でのキャラクター活用
- 周年記念出版でのキャラクター活用
- ブランディング出版でのキャラクター活用
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、観光パンフレットにおけるキャラクター活用
群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」は、観光パンフレットやガイドブックで案内役として活躍しています。
観光地や名産品を紹介する際の導入役として登場し、冊子全体を親しみやすいトーンにまとめている点が特徴です。
ページごとに表情やポーズを変える工夫もあり、家族連れや若年層にとって読みやすいデザインを実現しています。
また、パンフレットから公式サイトやSNSへ誘導する導線にもぐんまちゃんが使われており、紙媒体とデジタル双方でブランド発信を支える存在となっています。
◉-2、採用パンフレットでのキャラクター活用
ある企業の新卒採用パンフレットでは、業界に対して抱かれがちな「まじめで堅い印象」をやわらげることを目的に、企業文化や職場の雰囲気を伝える案内役としてオリジナルキャラクターを導入しました。
冊子の各ページにキャラクターを配置し、制度や仕事内容のポイントを補足する構成としたことで、学生が内容を理解しやすくなり、最後まで読み進めてもらいやすくなったといいます。
◉-3、会社案内冊子でのキャラクター活用
あるBtoB企業では、セラミックなど専門性の高い事業内容をそのまま説明するのではなく、コーポレートキャラクターが噛み砕いて紹介する構成を採用しました。
キャラクターを通じて、「社会を支える存在として、目立たない部分で価値を提供している企業」という企業像を語ることで、抽象的になりがちな理念や事業の役割が直感的に伝わりやすくなった点が評価されています。
また、キャラクターが解説役として登場することで、難解になりがちな事業説明への心理的ハードルが下がり、読者がスムーズに内容へ入り込めるようになりました。
担当者からも、キャラクターの存在によって企業理解が早まり、「限られた時間の中でもブランドメッセージを効果的に伝えられた」との声が上がっています。
◉-4、周年記念出版でのキャラクター活用
リクルートが運営する不動産・住宅情報サイト「SUUMO」のブランドキャラクターとして知られているのが「スーモ」です。
スーモ誕生1周年を記念し、ブランドの世界観や価値観をより深く伝える施策として、絵本『スーモのさがしもの』が出版されました。
本施策では、キャラクターを物語の主人公に据えることで、Webサイトや広告だけでは伝えきれないスーモの個性や魅力を、体験的に感じてもらうことを狙っています。
出版物という形をとることで、ブランドの世界観を丁寧に表現できただけでなく、キャラクターへの親近感を高め、読者との心理的な距離を縮める効果も生まれました。
その結果、短期的な話題づくりにとどまらず、長期的なブランド浸透につながった好例といえるでしょう。
▶︎周年記念の詳細については、関連記事【企業が周年記念事業を成功させるポイント!おすすめの施策ややり方を解説】もあわせて参考にしてください。
◉-5、ブランディング出版でのキャラクター活用
自社をより身近に感じてもらう目的で、ブランディング出版として絵本を制作した企業もあります。
自社商品やサービスの価値をキャラクター化し、物語として表現することで、家族層を中心に自然な形でブランドに触れてもらう狙いがありました。
広告とは異なる接点として出版物を活用し、長期的な認知形成につなげた事例です。
【まとめ】出版物にキャラクターを取り入れてマーケティング効果を高めよう
この記事では、キャラクターマーケティングの目的や効果、設計ポイント、キャラクターを出版物に活用した成功事例などについて紹介しました。
出版物は情報を体系的に伝えられる媒体のため、キャラクターを活用して読者の理解が深まり、ブランドメッセージの浸透効果を高めることが期待できます。
出版物でキャラクターの存在感が確立できれば、WebやSNSへの展開もしやすくなり、企業全体のコミュニケーションを強化することが可能です。
フォーウェイは、企業の経営者や責任者が成果を生み出せるよう、企業出版(ブックマーケティング)を中心に、各種コンテンツを通じたブランド戦略支援を行っています。
キャラクターを取り入れた冊子制作や書籍出版を通じて、企業の想いや価値を分かりやすく伝えるブランディング支援にも対応しています。
キャラクターを活用した出版物についてのご相談やお問い合わせは、フォーウェイまでお気軽にお寄せください。


企業SNSを運用したいが、やり方がわからないーーこのように考えるマーケティングや広報の担当者は多いことでしょう。
以前は「個人の遊び」という印象が強かったSNSですが、時代はすっかり変わりました。SNSはビジネスにおけるコミュニケーションの重要な一部分である、という認識が多くの企業に浸透してきたのです。
しかし、企業SNSのアカウントが乱立するなかで、ビジネスにおけるメリットをきちんと獲得できているケースはごく一部と言わざるを得ません。
そこで本記事では、企業SNSの運用を考える方向けに、SNSによってビジネスメリットを実現する「運用のやり方」を解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
企業のSNS運用とは?

企業にとってSNS運用は、ビジネスの成長に欠かせないものとなっています。
企業のSNS運用は、一言でいえば「ビジネス目的」である点が最大のポイント。
個人のアカウントに比べてよりプロフェッショナルで戦略的な運用のやり方が求められます。
個人のSNS運用との違い
個人のSNS運用は、主に自己表現や交流が目的です。
もちろんSNSを通じたマネタイズに成功しているインフルエンサーなどの個人はいますが、そうした人たちはビジネス目的の運用という意味で、個人の趣味的なアカウントとは違う種類の運用だと言えるでしょう。
企業のSNS運用は、商品やサービスのプロモーションやブランドイメージの向上など、ビジネス上の目的があります。
そのため、やり方としても投稿内容や投稿頻度、ターゲット層など戦略的な視点が求められます。
また、ユーザーに悪印象を与えないようにする気配りも、個人アカウントに比べてより重要になるのです。
SNSマーケティングとの違い
SNSマーケティングは、SNSを活用してマーケティング活動を行うことです。
具体的には、下記のようなやり方があります。
・インフルエンサーマーケティング
・SNS広告運用
・ソーシャルリスニング
・SNSキャンペーンの実施 |
総じていえることとして、費用を投じたタイミングにだけ効果を発揮し、商品購入や問い合わせなど直接的なリターンを目指すのがSNS運用以外のSNSマーケティングです。
広告施策としての色が強い取り組みとも言い換えられます。
一方で、SNS運用はSNSマーケティングのくくりにはありますが、下記のような特徴があります。
・オーガニック投稿として自由度の高い発信が可能
・ユーザーとのコミュニケーションによりファン化を促進できる
・運用をやめたり頻度を鈍らせたりしてもアカウントや過去の投稿は残る
・一度フォローしてもらったユーザーをアカウントの資産として持ち続けられる
・長期にわたる施策の継続がやりやすい |
長期的なブランディングを目指したり、マーケティングの基盤を作ったりといった目的を達成するために適しているのがSNS運用です。
参考:SNSマーケティングとは?代表的な手法から戦略立案、成功事例まで徹底解説|株式会社ビーステップ
SNS運用が重要になっている理由

SNS運用がビジネスにおいて重要になっているトレンドは、データからもわかります。
「ソーシャルメディアマーケティング市場、2023年ついに1兆円を突破の予測【サイバー・バズ/デジタルインファクト調べ】」(https://webtan.impress.co.jp/n/2022/11/11/43642)によると、ソーシャルメディアマーケティングの市場規模は2020年の5,971億円から2022年には9,317億円へと大幅増加。
2027年には1兆8,868億円にまで市場が拡大すると推計されています。
SNS運用はやり方を工夫すれば大きなリターンを得られる一方で、フォロワーを増やすためにはどうしても一定の時間が必要です。
SNSの市場が伸びていくなかで、早く始めた企業ほど成功に近づくのは間違いありません。
SNS運用によって得られるメリット
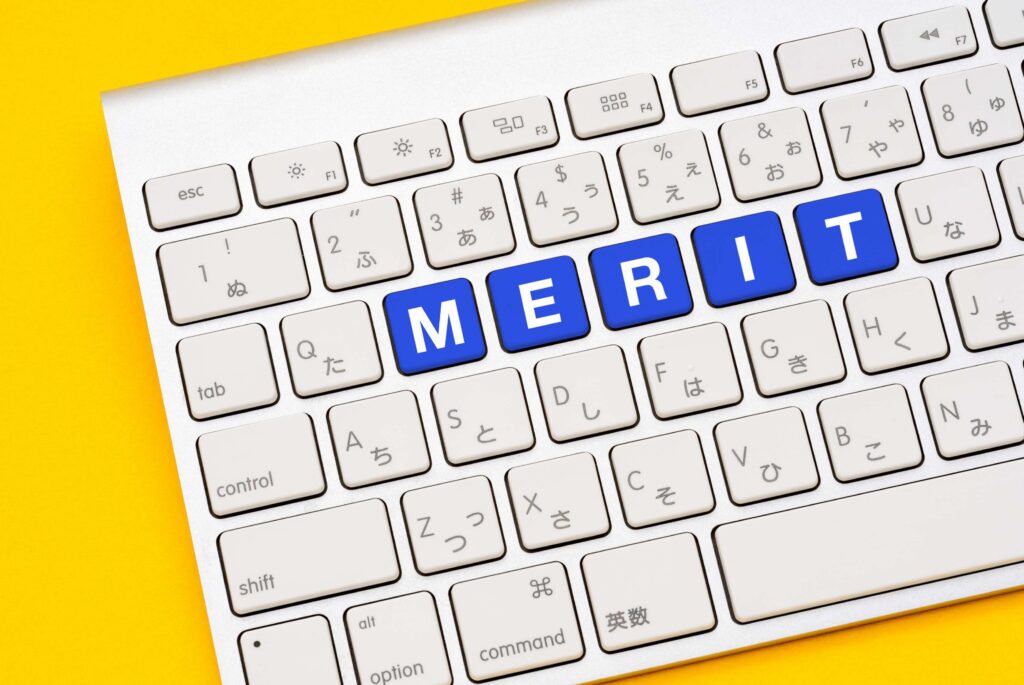
ここで、企業のSNS運用によって得られるメリットを改めて整理しましょう。
大きくいうと、以下の通りです。
・商品やサービスのプロモーションができる
・自社ターゲット層に直接訴求できる
・顧客とのコミュニケーションを深めることができる
・企業のブランドイメージを向上させることができる
・リアルタイムな情報の発信が可能になる |
いずれにも共通するのが、SNS運用によるメリットの発揮とは運用のやり方にかかっているということです。
SNSアカウントがあるだけで売上につながるような理想的状況を作るには、狙ったターゲット層のフォロワーをたくさん抱えた「強い」アカウントを作る労力を惜しまないことが、成功事例に共通した特徴です。
各SNSの特徴と運用のコツ

ビジネスでよく活用されるSNSは、主に以下の7つです。
・Instagram
・X(旧Twitter)
・Facebook
・LinkedIn
・LINE
・Tik Tok
・YouTube |
各SNSの特徴と運用のコツを詳しく解説します。
Instagram
Instagramは、写真や動画を投稿するSNSです。
ビジネスにおいては、商品の宣伝やイメージアップに活用されることが多く、特に若い世代に人気があります。
ただ、40代以上の層も利用率は低いものの、実数でいうと若年層に匹敵しており、実は全年齢に向けたアプローチにも使えます。
Instagramの運用のポイントは、以下の通りです。
・ハッシュタグや発見タブによって投稿を検索されやすくする
・投稿のビジュアルについて方向性を定め、ユーザーに価値を感じてもらえる投稿を一定頻度で続ける
・ストーリーズ機能を使い、日常的な情報を発信することでフォロワーとのコミュニケーションを深める
・インスタライブを使い、フォロワーとの関係性をより強化する |
勘違いされがちですが、「発信者のビジュアルが優れていて顔出しできる」「商品のきれいな宣伝写真がたくさんある」などの要素はInstagram運用で必須ではありません。
「商品のターゲット層が興味を持つノウハウを発信する」「日常風景の投稿でユーザーと距離感を縮める」など企画の方向性によって、あらゆるビジネスでInstagramの強みを発揮できます。
X(旧Twitter)
X(旧Twitter)は、140文字以内(X Premium加入者はそれ以上も可能)の短い文章を投稿することができるSNSです。
主にリアルタイム情報の収集や発信に使われ、特にニュースやトレンドに関する情報が多く取り扱われています。
Xの運用のポイントは、以下の通りです。
・アカウントのテーマに沿った自分なりの「情報提供」と「持論」を発信してフォロワーを増やす
・ほかのアカウントとコミュニケーションを増やし、タイムライン上の表示優先度を高める
・ほかのアカウントをフォローし、フォロー返しを獲得することでフォロワーを増やす |
Xは実名顔出しで運用するアカウントが多く、アカウント同士のコミュニケーションが重視されるカルチャーのSNSです。
企業アカウントとして活用する場合でも、事務的な発信だけでなく「中の人」の人柄が感じられるアカウントが好まれる場合があります。
リツイート機能でツイートが大きく拡散される仕様により、投稿が大きくバズる可能性のあるSNSでもあります。
Facebook
Facebookは、世界で最も利用者数の多いSNSの一つです。
友達や家族とのコミュニケーションが中心ですが、ビジネスにも活用されることが多く、商品の販売やブランドの発信などに使われます。
Facebookの運用のポイントは、以下の通りです。
・定期的にコンテンツを投稿することで、フォロワーの獲得やエンゲージメントの向上を目指す
・Facebookページを作成し、“いいね”を獲得することで拡散力を高める
・Facebookグループを作成し、ファンコミュニティを形成することで、ファンとの交流を深める |
Facebookは一定年齢以上の人のビジネス活用においては根強い人気のあるSNSです。
ただ、友達に追加する人数に5000人という制限があるため、つながりをたくさん増やして大きく拡散しようとする運用方針には向きません。
関係性のある相手から自社への認知を維持したり、仕事の相談をもらいやすくしたりする運用がFacebook活用のコツです。
LinkedIn
LinkedInは、ビジネス関係者が集まるSNSです。
求人情報やビジネスマッチングなどに使われることが多く、ビジネスユースに特化したSNSであるといえます。
LinkedInの運用のコツは、以下の通りです。
・原則実名登録なので、反感を招くような投稿は避ける
・ほかのアカウントと交流し、コミュニティなどにも積極的に参加する
・ターゲットに対して積極的にDMを送る |
いわゆる営業のためのDMや採用DMはほかのSNSだと嫌がられる場合がありますが、LinkedInはビジネスSNSである側面から、ほかアカウントへの直接アプローチは比較的、受け入れられているのが特徴です。
ただし、大量のスパム送信はLinkedIn側から制限をかけられる危険があります。
丁寧に絞り込んだターゲットアカウントに対し、一通一通、心を込めてDMを送ることが成果の秘訣です。
LINE
LINEは日本国内において、幅広い世代で利用されているSNSです。
2025年3月末時点のLINEアプリ月間アクティブユーザーはLINEの自社調べで約9,800万人、2023年1月1日時点の日本の人口約1億2,475万から推計すると、約70%以上が使っていることになります。
LINEにはビジネス用にLINE公式アカウントを開設できるサービスがあり、企業や店舗が友だち追加してくれた顧客に情報発信できます。
LINEの公式アカウントには以下のような特徴があります。
・リピーターが増える・売上につながる
・機能が充実・操作は簡単
・目的・用途に合わせて選べる料金プラン |
LINEが2021年7月に行った携帯電話のアンケートでは、LINE公式アカウントからメッセージを受け取って約80%がその日のうちに開封されていることが分かりました。
また、「よく行くお店のアカウントがあったら、友だち追加・フォローしたいサービス」として、57.8%がLINEと回答しています。
それだけ情報源としてLINEを活用したいと考えているユーザーは多く、リピーターの獲得や売上の向上につながりやすいSNSです。
LINEの公式アカウントはポイントカードの発行管理やクーポンの配信のほか、オリジナルのサブスクリプション型サービスを作成できます。
各種販促ツールも使えるなど、集客から販促まで活用できる機能が充実しているのもメリットでしょう。
3つの料金プランがあるため、想定するメッセージ数など、自社の状況に応じて選べます。
参考:LINEヤフーfor Business「LINE公式アカウント」
参考:総務省統計局「人口推計-2023年(令和5年)1月報-」
TikTok
Tik Tokは15~60秒程度の短い動画を投稿できるSNSで、X(旧Twitter)やFacebook、LINEなどに比べると比較的新しいサービスです。
Tik Tokの特徴は、以下の通りです。
・短尺動画がメイン
・若年層に人気
・トレンドに敏感
・拡散力が強い |
特に10~20代のユーザーが中心ですが、全世代でも利用率が伸びています。
総務省情報通信政策研究所が発表している「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」では、情報通信メディアの利用時間が報告されています。
主なソーシャルメディア系サービスやアプリの全世代利用率をみると、Tik Tokの利用率は2018年では10.3%でしたが、2020年には17.3%、2023年には32.5%にまで伸びました。
また、2023年の全世代利用率は32.5%であったのに比べ、10代は70.0%、20代では52.1%となっており、10~20代のユーザーが多いことが分かります。
短尺動画がメインということもあり、スキマ時間でも気軽に視聴しやすいのがTik Tokのメリットです。
限られた時間に伝えたい内容を盛り込む必要がありますが、「視覚的なインパクトを与えられる」「テンポの良いリズムで記憶に残りやすい」などのメリットがあります。
流行の音楽・ダンスや「○○チャレンジ」のようなトレンドに敏感な投稿が多く、ユーザーを巻き込み、拡散力が強いのも注目すべきポイントです。
Tik Tokには、ビジネス用の広告プラットフォーム「Tik Tok for Business」があります。
細かい設定の必要もなく、無料の動画広告制作ツールなどを利用して広告配信まですべてオンラインで完結します。
参考:総務省情報通信政策研究所「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」
YouTube
YouTubeの特徴は以下の通りです。
・短尺動画から長時間の動画まで投稿が可能
・ライブ配信もできる
・利用者の年齢層が幅広い |
YouTubeはTik Tokとは異なり、短尺動画だけではなく情報量の多い長時間の動画も投稿できます。
単に自社の商品やサービスを紹介するだけにとどまらず、商品の使い方を実演して見せるなど、How-To動画の提供も可能です。
リアルタイムで情報が更新されていくフロー型のSNSはバズって一気に拡散される可能性がある一方、短期間で忘れ去られることも考えられます。
しかし、YouTubeはストック型の動画として、コンテンツを蓄積しておけます。
たとえば、ギフト商品を扱う企業のコンテンツとして、「新社会人への贈り物におすすめのアイテム」や「お祝いのマナー」などの動画をアーカイブとして残しておいたとしましょう。
フロー型のSNSのように爆発的な拡散力はないかもしれませんが、ギフトを贈るシチュエーションでは、一定の再生回数を得られます。
YouTubeのコンテンツから自社のWebサイトへ誘導できるようにしておけば、売上にも結びつきやすくなります。
有益なコンテンツが蓄積されていくと中長期的に顧客の信頼を得られるメリットがあるため、ターゲット層が求める情報を把握し、コンテンツを充実させていくことが重要です。
新商品の発表会やセミナーなどには、ライブ配信も活用できます。
総務省情報通信政策研究所の「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によると、YouTubeの全世代の利用率は、2014年時点ですでに65.1%でした。
その後も徐々に利用率は上がり、2023年では全世代で87.8%です。
利用者の年齢層も幅広く、2023年時点では60代では66.3%にとどまっているものの、50代以下では80~90%台の高い利用率になっています。
幅広い層に自社の商品・サービスをアピールできるため、活用の幅は広いでしょう。
参考:総務省情報通信政策研究所「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」
SNS運用を始める前に決めること5つ

続いてはSNS運用の実践編です。
SNS運用は、やり方を決めずにとりあえず始めてみても成功率は低いです。
ビジネスにつなげるためには、事前準備がカギを握ります。
事前準備として考えるべき項目は、以下の通りです。
・決めること①運用の目的
・決めること②運用体制
・決めること③アカウントの方向性
・決めること④ターゲット層
・決めること⑤具体的なタスクとスケジュール |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
決めること①運用の目的
SNSを始める前に、まずは運用の目的を明確にすることが必要です。
たとえば、ブランド認知度の向上や製品やサービスの販売促進、情報発信や顧客対応など、目的はさまざまです。
目的に応じて運用するSNSの種類やコンテンツや投稿頻度、投稿内容、ターゲット層などが異なるため、運用の目的をはっきりと決めてから取り組むことが重要です。
気をつけたいのが、「運用目的は売上に決まっているでしょ」と単純に決めてしまうこと。
SNS運用は短期的な売上効果だけでなく、ブランディング効果やファンユーザーの獲得などさまざまな尺度での効果を視野に入れる必要があります。
長期的にアカウントを育てる施策だけに、短期の集客では広告施策より数値が劣る場合が多く、運用目的を売上だけと定めてしまうとスムーズな運用が進まない危険性が高いのです。
「短期で何を目的にするのか」「中期〜長期で何を目指すのか」など、細かく設計するのが成功するコツです。
▶︎SNS運用の目的設定については、過去コラム『SNS運用で大切な「目的設定」とは?運用効果を最大化する秘訣を徹底解説』で解説しているので、こちらもご参照ください。
決めること②運用体制
SNS運用では、運用担当者やチームの体制を整えることも大切です。
運用にあたっては、「誰が投稿するのか」「どのようなスケジュールで投稿するのか」「コメントやメッセージの返信は誰が担当するのか」といったことを明確にしておく必要があります。
また、社内で運用する場合は、社員の研修やマニュアル作成なども必要かもしれません。
会社としてSNS運用に取り組むときの体制で重要なのは、組織として担当者をフォローアップして運用を管理する仕組みをつくることです。
社内の担当者はほとんどの場合、SNSのプロではありません。
「いい感じにやっておいてくれ」と丸投げして放置していると、運用の目的が達成できないどころか投稿やアクション自体が止まってしまうケースも珍しくありません。
自社の貴重なリソースを使って、徒労に終わらないように気をつけましょう。
決めること③アカウントの方向性
SNSアカウントの方向性についても、事前に決めておくことが重要です。
たとえば、ファッションブランドのアカウントであれば、コーディネートの紹介や新作アイテムの情報を発信することが求められます。
一方で、医療機関のアカウントであれば、健康情報や病気の予防・治療についての情報提供がいいかもしれません。
アカウントの方向性を明確にしておくことで、フォロワーの期待に応えることができ、効果的な運用が可能になります。
たとえば、SNS運用の代行を請け負うプロであれば、クライアントへのヒアリングをもとにペルソナシートやアカウント構成シートといった資料を作成します。
ターゲット層や運用目的に合わせてデザインのトンマナから投稿文体まで細かく設定し、ブレない運用を実現するのです。
決めること④ターゲット層
SNSを利用するユーザーは、それぞれ年齢層や性別、興味関心、ライフスタイルなどが異なります。
運用するアカウントのターゲット層を明確にし、その層に合った投稿やコンテンツを提供することが必要です。
また、ターゲット層に応じて、運用するSNSや投稿する時間帯、投稿内容、コンテンツの種類なども変わってきます。
このターゲット設定は、「30代以上の女性」など大まかすぎるくくりではあまり意味がありません。
よくマーケティングで使われる「ペルソナ(代表的なターゲット像の架空のプロフィール)」を設定するのも効果的でしょう。
誰か一人に深く刺さるコンテンツはほかの人にも刺さるというのがSNS運用の原則です。
決めること⑤具体的なタスクとスケジュール
SNSの運用においては、具体的なタスクとスケジュールを決めておくことが大切です。
どのようなコンテンツを、どのようなタイミングで発信するのかを明確にすることで、運用がスムーズに行われます。
また、週次や月次での運用の報告や評価を行い、必要に応じて改善を行うことも大切です。
コツとしては、とにかくあいまいさを残さないこと。
「ネタがあるときに投稿する」「なるべくほかのアカウントに“いいね”する」といったルール設定ではなく明確に行動目標を決めましょう。
実際に運用をしてみると担当者に負担がかかりますが、強いアカウントを育てるにはそれなりの努力が必要です。
SNS運用の効果測定と運用改善

「SNSの運用成果は、どうやって評価・改善すればよいの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
SNS運用の効果を可視化するためには、以下のような指標を活用します。
・フォロワー数
・リーチ数
・エンゲージメント数(「いいね!」やコメント数など)
・コンバージョン数(集客数、商品の売上数など) |
計測すべき指標は、運用目的やどのSNSを用いるかによって変わってきます。
たとえば、対面アポイントの獲得を目標にする運用なら、DMのうちのアポイント率が指標になるでしょう。
改善項目としては普段の投稿の質よりも、アカウントの信頼性を高めるためのフォロワー増やDM文面の改善などの優先順位が高くなります。
おすすめとして、ある程度フォロワーが増えるまではフォロワー数だけをKPIにするのが良いでしょう。
SNS運用による効果の多くは、ある程度フォロワーがいないと発揮されにくいためです。
管理をシンプルにすることで運用もスムーズになります。
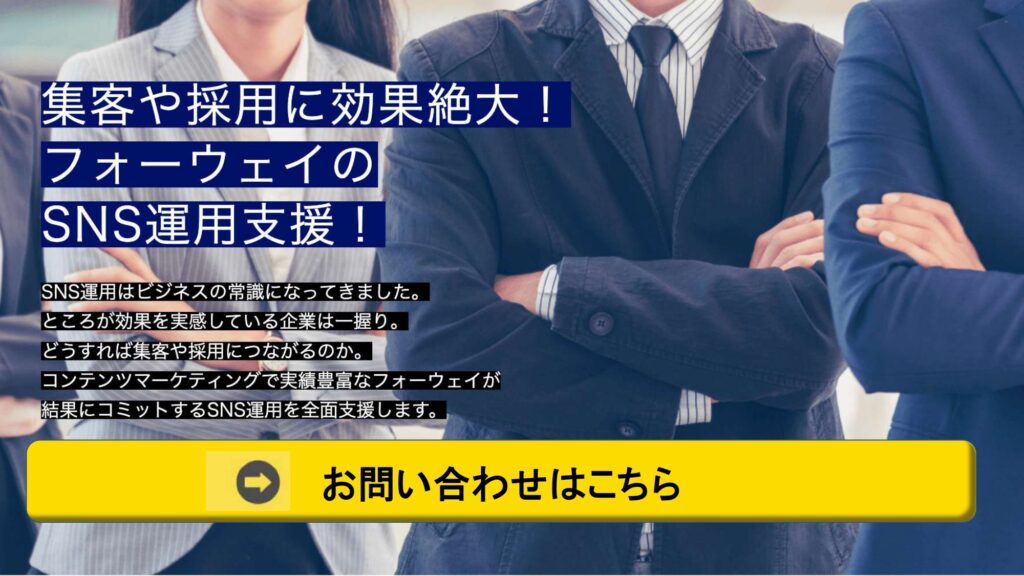
SNS運用のよくある失敗例4パターン
SNS運用をする際には、失敗の典型例に当てはまらないよう注意して運用しましょう。
よくある失敗例として、以下の4パターンがあります。
・失敗例①フォロワー数が増えない
・失敗例②運用が止まってしまう
・失敗例③運用の方向性が迷走する
・失敗例④炎上してしまう |
それぞれ詳しく解説します。
失敗例①フォロワー数が増えない
思うようにフォロワーが伸びないのは、SNS運用で最もよくある失敗ケースです。
理由として、たとえば下記が考えられます。
投稿頻度が低い
多くのSNSは、自アカウントの投稿がほかのユーザーのタイムラインに表示されることでフォローが発生します。
したがって、投稿が少なければどんなにアカウントを作り込んでいてもフォロワーが増えるチャンスはほとんどありません。
最低でもInstagramなら週3回、Xなら1日1回は投稿が必要です。
ほかアカウントとのコミュニケーション不足
「いいね」や「コメント」などほかのアカウントに対して自分からアクションするのも、フォロワーを増やすためには重要です。
ここを怠るとフォロワーはほとんど増えません。
ただし、アクションする先のアカウントの選定にもコツがあります。
リアクションを返してくれそうなアカウントや信頼度の高いアカウントの共通点を見出し、適切な相手に対してコミュニケーションを取る必要があります。
失敗例②運用が止まってしまう
SNS運用がストップしてしまう失敗事例はとても多いです。
その理由のほとんどは、はっきり方針を決めずに担当者に丸投げしたきり管理しない運用体制にあります。
投稿スケジュールの明確な設定と投稿物の確認、定例の確認ミーティングなどは組織内で必ず行いましょう。
また、「売上につながっていないからものすごくクオリティの高い投稿をしなきゃ」など、成果を焦って答えのない課題を設定してしまうのも投稿ストップの原因になります。
SNSは定期的にコンテンツを発信して自アカウントにあった運用のやり方を探っていくプロセスがとても重要です。
クオリティにこだわりすぎるよりも継続的な運用を重視しましょう。
失敗例③運用の方向性が迷走する
SNSの運用は、アカウントの方向性を守ることが重要です。
失敗例②に近いですが、成果を焦って方向性の切り替えを連発し、コンセプトのよくわからないアカウントになってしまうのもよくある失敗パターンです。
どんな方向性を試してみても、運用初期に一つの投稿でわかりやすい効果が発揮されることはなかなかありません。
まずは運用開始前のコンセプト設計を細かく行い、決めた方向性に則って腰を据えて取り組みましょう。
そうすれば長期的な成果に高い確率でつながります。
失敗例④炎上してしまう
SNSの運用で最も避けたい失敗が「炎上」です。
一度炎上してしまうと、ブランドイメージに大きなダメージを与えかねません。
具体的な炎上理由として、以下の3つが挙げられます。
・不適切な表現や誤解を招く
・投稿社内の機密情報や個人情報の漏えい
・社会的背景を無視した不用意な発言 |
悪気はなくても、意図せず自社の投稿がネガティブに解釈されることもあります。
炎上すると信頼回復にも長い時間とコストがかかるため、炎上リスクを理解したうえで活用することが重要です。
SNSの炎上を防ぐ対応策4選

SNS運用において、炎上を気にする方は多いかもしれません。
企業のSNS活用が普及するにあたって、炎上してしまった事例も多く聞かれるようになりました。
そこで以下に、SNSの炎上を防ぐための対応策を紹介します。
・炎上防止策①投稿ガイドラインの策定
・炎上防止策②対応ガイドラインの共有
・炎上防止策③投稿監視体制の整備
・炎上防止策④炎上事例の社内共有 |
4つの炎上防止策を見ていきましょう。
炎上防止策①投稿ガイドラインの策定
SNS運用を始める前に、社内でSNSマニュアルを策定しましょう。
このマニュアルには、発信内容のチェックや、危険な発言を行わないようにするためのガイドラインなどが含まれています。
ガイドラインを設定する際には、ぜひSNS慣れした若いスタッフの力を借りてください。
普段からSNSに慣れ親しんだ人間であれば、それぞれのSNSにおけるマナーを感覚で理解しています。
若いスタッフにたたき台をつくってもらったうえで、広報やリスク管理担当などプロの目で見てブラッシュアップする進め方がおすすめです。
炎上防止策②対応ガイドラインの共有
もしも炎上騒ぎが起こってしまった場合には、迅速かつ的確な対応が必要です。
SNS上でのトラブルの拡散を防ぐために、炎上した場合には速やかに謝罪し、原因究明を行いましょう。
ただし、SNS運用に慣れていない企業が担当者任せにする体制は危険です。
機転をきかせたつもりが火に油を注いでしまう可能性もあります。
投稿物だけでなく、炎上懸念がある場合の対応についても社内でガイドラインを設定し、フローを明確にするのがおすすめです。
弁護士やPR会社などの外部専門家にリアルタイムで相談できる体制を構築しておくのも効果的でしょう。
炎上防止策③投稿監視体制の整備
SNS上でのトラブルを未然に防ぐためには、定期的にSNSのコンテンツを監視し、問題のあるコメントや投稿に対して迅速に対応することが必要です。
また、不適切なコメントや投稿があった場合には、速やかに削除し、投稿者に対して注意喚起を行う必要があります。
投稿の監視には、「上司が毎日11時にチェック」「広報が朝礼でチェック」など、担当者ではなく第三者的な目線でチェックを入れる決まりごとを作っておきましょう。
社内リソース的に難しければアルバイト数人でチェックする体制でも、一般的な目線による第三者チェックは入れられます。
さらに、SNSコンテンツの監視を効率化するために、ソーシャルリスニングツールの活用もおすすめします。
Meltwaterのソーシャルリスニングツールは、SNSの投稿をリアルタイムで一元的に分析できるため、炎上の火種となりうる投稿の把握に役立ちます。
炎上防止策④炎上事例の社内共有
SNSの炎上を防ぐのに大事なのは、抽象的ながら社内のリテラシーです。
関係者の知識を増やし教育をしていくのが、時間はかかりますが炎上を防ぐために有効な施策です。
そこで、日々SNS上の炎上情報をウォッチし、社内で定期的に共有、ポイントを話し合う機会を設けましょう。
特に自社と業種や運用目的の近いアカウントが炎上してしまった事例は、貴重な学習材料になります。
SNS運用を成功させるためのコツ

SNS運用を成功させるためには、以下のようなコツがあります。
・目標を明確にする
・一貫性のある情報発信を意識する
・質の高いコンテンツを作成する
・データ分析に基づいた改善を行う
・ほかの集客施策と組み合わせる |
5つのコツについて詳しく解説します。
目標を明確にする
SNSを運用する際に重要なのは、「何のためにSNSを活用するのか」という目的とゴールを明確にすることです。
「自社の認知度を高めたいのか」「商品の購入につなげたいのか」「採用を強化やブランディングに力を入れたいのか」など、目的によって取るべき施策も違ってきます。
認知度を高めるのが目的なら、「SNS経由のWebサイト訪問者数を20%向上させる」のように、具体的な目標も設定できます。
目標を明確にすれば成果も見えやすく、投稿内容やKPI設定、分析の方針もブレません。
一貫性のある情報発信を意識する
SNSは「ブランドの人格」を映し出す場所です。
そのため、情報発信の仕方や内容に一貫性を持たせ、自社のイメージを損なわないようにする必要があります。
ビジュアルや投稿のトーンがバラバラでは、ユーザーに混乱を与えかねません。
たとえば、「シンプルながら温かみを感じる」イメージがそのブランドの「らしさ」ならば、色味やフォントもそのイメージに合わせて統一し、言葉選びも世界観や価値観に合わせるように心がけてください。
一貫性のある情報発信として、定期的なシリーズ投稿を設けるのも効果的です。
「このブランドらしさ」が定着すれば、ファンを育てることができます。
質の高いコンテンツを作成する
次々に投稿が更新されていくSNSは、情報量が膨大です。
ユーザーのスクロール速度も早いため、そのなかで目を留めてもらうためには、「質」の高いコンテンツが欠かせません。
そこで、以下の3点を意識することが重要です。
・見た瞬間に内容が伝わるビジュアル
・読者の悩みや興味に刺さるコピー
・保存したくなるようなノウハウ情報 |
読者の悩みや課題を解決する情報や興味を掻き立てるコピーで注意を引き、ビジュアルで内容がイメージできるようにしましょう。
一方的に商品やサービスをアピールするのではなく、保存したくなるような情報や再生したくなる動画などを盛り込むことが大切です。
データ分析に基づいた改善を行う
SNS運用は、「投稿して終わり」ではありません。
「どの投稿が反応を得られたのか」「どの時間帯の投稿が効果的なのか」など、以下の3点を踏まえた分析と改善が必要です。
・インサイト(解析ツール)を定期的にチェックする
・投稿のA/Bテストを行う
・KPI(リーチ数、保存数、クリック率など)を可視化する |
まずは、インサイト機能で定期的にリーチ数やフォロワー数、クリック率などをチェックし、記録してください。
特定の要素だけを変更した場合の成果を比較できるA/Bテストを実施すると、より高い成果を得られるパターンを見つけられます。
また、目標達成に向けた進捗を示すKPIは、可視化しておくと成果が見えやすいでしょう。
改善を繰り返すことで、SNS運用の精度は上がっていきます。
ほかの集客施策と組み合わせる
企業のSNS運用は、単体で完結させるものではありません。
SNS運用でより高い成果を生むポイントは、ほかの集客施策との組み合わせです。
SNSは、あくまでも入口であり、その先にある情報や体験にうまく接続できるかどうかがポイントになります。
ほかの集客施策との相乗効果でより高い成果を生み出し、ブランド理解や信頼構築はもちろん、行動喚起まで導くことが可能です。
SNSとの組み合わせで効果的なのは、以下の4つです。
・ブログ
・オフラインイベント
・広告運用
・ブックマーケティング |
各施策との組み合わせによる効果について、以下で詳しく解説します。
Webサイト・ブログとの連携
SNSとWebサイト・ブログとの連携でSNSから公式Webサイトやブログに誘導できると、商品の購入や問い合わせなどのコンバージョン(成果)に結びつきやすくなるのがメリットです。
ユーザーにとって、SNSは気軽にチェックできる点がメリットですが、一度の投稿で提供できる情報量はそう多くありません。
一方、情報が流れていくSNSとは違い、Webサイトやブログは必要な情報が整理されていて見つけやすい特徴があります。
SNSで興味を持ったユーザーを公式Webサイトやブログに誘導できれば、より自社の商品やサービスの詳細情報を紹介できます。
たとえば、新商品発売の告知はSNSで行い、機能の詳細や開発秘話などはブログ記事で公開するのも効果的な方法です。
「続きはプロフィールURLから!」のようにSNSの投稿からの導線を敷いておくと、興味を持ってくれたユーザーを確実にWebサイトに呼び込めます。
オフラインイベント・店舗との連携
以下のような施策により、SNSと実店舗やイベントを連動させることで来店促進やブランド体験の共有が可能です。
・SNSでイベント情報を事前告知する
・ストーリーズやライブ配信で現場の臨場感を伝える
・イベント参加者にハッシュタグ投稿を促す
・SNS経由での限定クーポンや特典を用意する |
SNSを使ってあらかじめイベントの情報提供やクーポンの配信などを行うと、興味を持ってくれたユーザーの来店を促しやすくなります。
イベントを開催する際、当日参加できない方に向け、InstagramのストーリーズやYouTubeのライブ配信などで発信すれば、現場の臨場感も伝えられるでしょう。
参加者にハッシュタグ付きの投稿を促すことで、イベントの情報拡散も期待できます。
BtoB企業なら会社説明会や展示会、セミナーや講演イベントなどをSNSと結び付けても、同様の相乗効果が期待できます。
ただし、BtoBの場合は成果を即時に得ることよりも、「信頼形成」や「専門性の訴求」が重要です。
オフラインイベントとSNSを掛け合わせてブランドの熱量を可視化することで、営業活動の後押しとなるケースもあります。
広告運用との組み合わせ
SNSはコストを抑えて広告宣伝できるのが大きなメリットですが、広告を使用せずにコンテンツを配信できる無料のオーガニック投稿だけでは、情報が届く範囲に限界があります。
もちろん、ユーザーにとって有益で魅力的なコンテンツは、拡散されてファンが増える可能性もあるでしょう。
ただ、せっかく情報を投稿しても、ターゲット層に届かなければ効果がありません。
広告運用と組み合わせ、より広範囲なターゲット層にアプローチすれば、集客力を高められます。
ブックマーケティングとの連携
ブックマーケティングは、書籍の出版をマーケティングに活用する手法です。
たとえば、ブックマーケティングで出版した書籍をSNSと連携させ、以下のように活用することも可能です。
・出版前からSNSで制作過程や想いを共有
・書籍の一部を図解や動画で発信して拡散
・SNSを活用した書籍プレゼントキャンペーンを実施 |
さらに注目すべきポイントは、書籍のコンテンツそのものはSNSのネタとして流用できる点です。
SNSでは「発信ネタが尽きてしまい、継続できなくなる」という課題を多くの企業が抱えています。
しかし、書籍の中には、すでにプロの編集者とともに構築された高品質な情報が豊富に詰まっています。
書籍の内容をSNS向けにアレンジして発信することで、コンテンツを少しずつ再利用でき、ネタ切れを防ぎながら、継続的な情報発信が可能になります。
▶︎ブックマーケティングについては、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】も合わせて参考にしてください。

SNS×ブックマーケティングの相乗効果とは?

SNSとブックマーケティングを掛け合わせることで、「信頼」と「共感」を育てられるメリットがあります。
編集者も交えてクオリティの高い書籍を出版すれば、読者に信頼性の高い情報を提供することが可能です。
書籍で打ち出した自社の専門性や理念、世界観を「日常の言葉」に落とし込んでSNSで伝えれば、ユーザーの理解や納得も深まりやすくなります。
また、SNSは拡散力があるのもメリットです。
書籍の発売をきっかけにアカウントの認知が広がったり、書籍を読んでくればフォロワーとの対話が生まれたりなど、良質なファン形成にもつながります。
出版を通じて得た「信頼」が、SNSを通じて強化される「接点」や「共感」が重なり、単なる集客以上のブランド価値を作り出せます。
▶︎ブックマーケティング(書籍の作り方)については、関連記事【本を出版するには?現役書籍編集者が本の出し方を分かりやすく解説】も合わせて参考にしてください。

SNS×ブックマーケティングで集客に成功した事例

実際にSNSとブックマーケティングを駆使し、集客に成功した事例を2つ紹介します。
・書籍出版とSNSの連動で問い合わせ・受注が劇的に増加した事例
・発売前からSNSを活用し、話題化に成功した事例 |
それぞれの事例を以下で詳しく解説します。
書籍出版とSNSの連動で問い合わせ・受注が劇的に増加した事例
資金調達支援のスペシャリストとしてのブランディングを目的に、書籍を出版した事例です。
出版する書籍には具体的な数字を入れて読者の興味を引き、ビジネス書の売れ行きが良好な大都市圏の書店を中心に配本する戦略をとりました。
また、この著者は、書籍発売から一定期間が経過した後も、Twitter(現X)で書籍プレゼントキャンペーンの告知を定期的に実施。
その継続的な投稿が注目を集め、キャンペーンの告知と連動する形でAmazonでの販売数が急増しました。
結果として書籍はロングセラーとなり、改訂版が出版されるまでに至りました。
書籍とSNS活用を組み合わせ、出版後は問い合わせが3~4倍アップしています。
発売前からSNSを活用し、話題化に成功した事例
商品の販促はもちろん、長期的なブランディングや顧客のファン化を目的として、「女性の悩み」に焦点を当てた書籍を出版した事例です。
「何一つ諦めることなく、女性に生涯にわたり輝いてほしい」という社長の思いを書籍として形にまとめました。
発売前から著者がSNSで積極的に情報発信を行ったことで注目を集め、予約が殺到し、発売前に重版が決定。
また、既存顧客を対象にした書籍プレゼント企画では、想定の8倍もの応募が集まる反響がありました。
出版が実績となり、新規顧客の獲得はもちろん、講演やメディア出演の機会も獲得しています。
SNS運用に関するよくある質問
最後にSNS運用について、よくある3つの質問に回答します。
SNSは毎日投稿しなければならない?
投稿は毎日する必要はありませんが、継続的に発信することが重要です。
定期的に投稿することで露出が増加し、自社がフォロワーにとってタイムライン上でよく見かける存在になりやすいでしょう。
しかし、内容が薄かったり質が悪かったりする投稿を重ねていても、ユーザーにとって価値のない情報になってしまうかもしれません。
コンテンツがパターン化して、飽きられる可能性もあります。
SNSでの発信は週2~3回など、無理なく続けられる頻度を設定してください。
「休まず続ける」ことが信頼やアルゴリズムの評価につながります。
どのようなコンテンツを投稿すればよい?
SNSで発信するコンテンツは、ユーザーが「見たい」「知りたい」と思う内容であることが重要です。
具体的には、以下のようなコンテンツがあります。
・商品の紹介
・サービスの活用事例
・Q&A
・舞台裏
・ユーザー参加型コンテンツ
・トレンド情報 |
実際に投稿する際は、競合他社にはない自社ならではの視点や世界観を反映させ、「らしさ」が伝わるようにしましょう。
また、単発で終わらせず、ストーリー性やシリーズ性を持たせて継続的に発信するのがおすすめです。
続きを待ち望むファンが増える可能性があり、つながりも深められます。
外注の運用パートナーは入れるべき?
SNS運用を外注化するかどうかは、企業の状況や目的によって異なります。
外注するメリットとしては、運用に必要な人材をスピーディに確保できることや、専門的なノウハウを持った運用パートナーを活用できることが挙げられます。
一つの考え方として、「人手が足りない」「アカウントを育てるのにそこまで長い期間をかけられない」という課題がある場合、外注を検討することがおすすめです。
ここまで述べたように、SNS運用をきちんとやると担当者にも組織にも意外に手間がかかります。
社員一人が常駐のような状態で対応している会社も多いです。
そうなると、人件費的にSNS運用会社に頼んだほうが安くつく場合も考えられます。
また、外注先は当然ノウハウを持っているため、プロの運用によって最短経路でアカウントを育ててくれるのは大きなポイントでしょう。
特に投稿コンテンツの企画は、一般企業のリソースではなかなか難しい場合も多いです。
ゼロの状態から探り探りでSNS運用をスタートすると、継続できても成果が出るのは数年後といったケースが少なくありません。
その時間を短縮して成果を確実にする選択肢として、外注を活用するのはおすすめです。
【まとめ】SNSとブックマーケティングを掛け合わせて、集客効果を高めよう!
ビジネスコミュニケーションや企業のブランディングでは、今やSNSの運用は欠かせません。
しかし、SNSにはさまざまな種類があり、特徴も異なります。
そのため、自社に合うSNSを選び、そのうえで運用体制を整えることが重要です。
また、SNSはほかの集客施策と組み合わせることで、より効果を発揮します。
特に信頼性や専門性を打ち出せるブックマーケティングと、拡散力のあるSNSは相乗効果が期待できます。
フォーウェイは、230社以上の実績を誇るブックマーケティングに加え、SNS運用をはじめとするマーケティング支援を行っています。
戦略立案から実行まで一貫してサポートが可能です。
SNS運用やブックマーケティングをご検討の際は、ぜひフォーウェイまでご相談ください。


経営者が本を出版しようと考える背景には、「自社の社会的信頼を高めたい」「企業理念を社会に伝えたい」といった目的があります。
そこで重要になるのは、「売れる本をつくる」ことではなく、本という媒体を通じて、いかにビジネス成果を得るかという視点です。
企業出版は、企業理念や自社の強みをわかりやすく社会に伝えて、売上や採用、ブランディングなどの企業活動につなげる手法として注目されています。
この記事では、企業の経営者や事業責任者に向けて、売れる本の共通点や企業出版で成果を出すための具体的なステップについて詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
経営者が狙うべき「売れる本」とは?
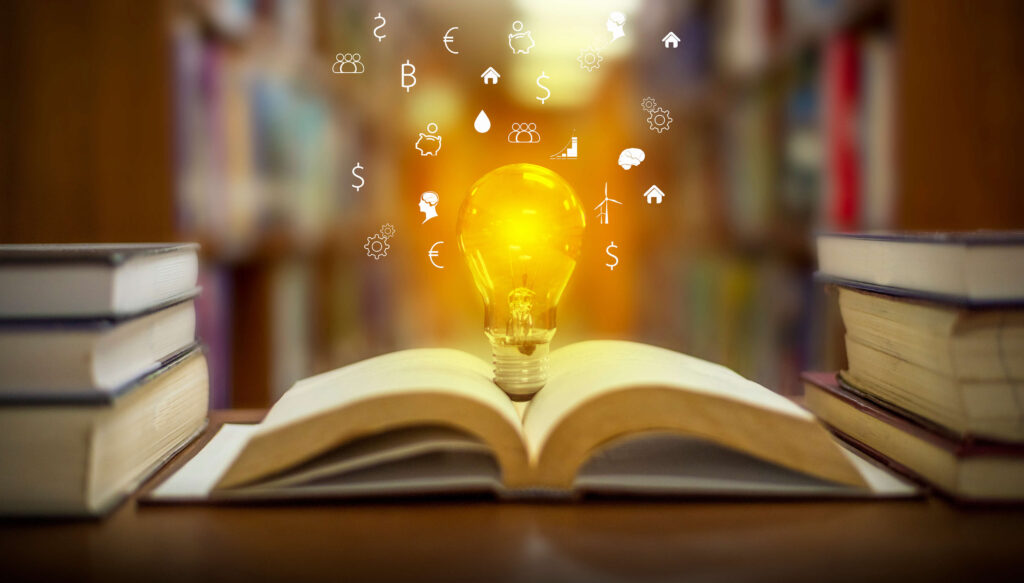
経営者が本を出版する際には、本の売上だけを基準にするのではなく、企業にどのような価値をもたらす本なのかを考えることが重要です。
ここでは、経営者が狙うべき「売れる本」の考え方について、次の2つの観点から整理します。
- 商業出版における「売れる本」と企業出版における「売れる本」の違い
- 重要なのは「ビジネスにおける成果」
それぞれの視点で押さえるべきポイントについて解説します。
◉-1、商業出版における「売れる本」と企業出版における「売れる本」の違い
商業出版は、本の市場性や話題性を重視し、どれだけ売れるかが目的になります。
出版社が読者ターゲットや内容を主導して設定するため、広く一般の読者に向けた企画となるのが特徴です。
一方、企業出版の目的は、自社の理念や強みを社会へ的確に伝えることにあります。
著者は経営者である場合が多く、読者として想定されるのは、顧客・取引先・業界関係者・就職希望者など、企業に関わる幅広いステークホルダーです。
そのため、経営者が目指すべき「売れる本」とは、販売部数よりも、企業の価値観を届け、信頼を築き、最終的にビジネス成果へつなげる一冊であるといえます。
◉-2、重要なのは「ビジネスにおける成果」
企業出版は、事業戦略を推進するための有効な手段です。
出版によって、以下のようにさまざまなメリットを得られます。
- 顧客からの信頼向上
- 新規リードの創出
- 既存顧客との関係強化
- 採用活動の質向上
また、書籍化することで理念やビジョンが明確に言語化され、社内外で共有しやすくなる点もメリットです。
企業としての方向性がよりはっきりし、顧客・社員・取引先との間に共通理解が生まれます。
こうした観点から、経営者にとって企業出版は単なる施策にとどまらず、ブランド価値を高めるための重要な投資だといえるでしょう。
書籍という媒体を通じて企業の姿勢や思想が伝わり、結果としてビジネス成果へとつながりやすくなります。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

企業出版で売れる本に共通する3つの要素

企業出版で売れる本には、読者に必要な情報がまとめられていて、企業の魅力や価値が明確に伝わるという共通点があります。
これは、読者ターゲットを適切に設定し、企業として伝えるべき内容が整理されていることによって生まれるものです。
ここでは、経営者が本を出版する際に押さえておきたい3つの重要なポイントを紹介します。
- 読者ターゲットを明確に設定している
- 独自の価値やストーリーが一貫している
- 出版後の活用設計(販促・PR・営業連携)がある
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、読者ターゲットを明確に設定している
成功する企業出版では、「誰に何を伝えるか」が明確に設定されています。
読者ターゲットを、たとえば顧客や業界の同業者、未来の社員などに設定して具体的に描き、その人が抱える課題や疑問に応える内容を設計することがポイントです。
漠然と「多くの人に読んでほしい」という発想では、結果として誰にも響かない本になってしまう可能性があります。
明確な読者像を描くことが、「売れる本」をつくる前提条件となります。
◉-2、独自の価値やストーリーが一貫している
企業や経営者がこれまでに経験してきた出来事、理念、成功や失敗のエピソードなど、他社にはないストーリーは読者の信頼と共感を生む重要な要素です。
読者は企業の背景や考え方に触れることで、「この会社に依頼したい」「この経営者と働きたい」と感じるようになります。
ストーリーが一貫しているほど、企業の姿勢や価値観が伝わりやすくなるのです。
理念から事業へのつながり、課題への向き合い方、解決に至るまでの道筋を丁寧に描くことで、読後に強い印象として残ります。
◉-3、出版後の活用設計(販促・PR・営業連携)がある
企業出版では、本をつくるだけで終わらせず、発行後にどのように活用するかを事前に設計しておくことが成果につながります。
たとえば、以下のように具体的な活用シーンを想定しておくことで、企業出版の効果が継続しやすくなります。
- 営業資料としての活用
- 展示会やセミナーでの配布
- 採用イベントでの紹介
本を出した後にどのように行動するかを決めておく企業ほど、売上や認知度の向上に結びつくのです。
本が売れることがビジネスにもたらすメリット

企業出版によって得られる成果は、単なる知名度向上にとどまらず、信頼性の向上、営業活動の効率化、採用力の強化など、多岐にわたります。
書籍という形で理念や強みを伝えることで、企業活動全体にプラスの効果を生み出せる点が特徴です。
ここでは、企業出版が企業にもたらす主なメリットを紹介します。
- 企業出版で信頼性と話題性を獲得できる
- 営業ツール・採用ツールとしても活用できる
- 競合との差別化ポイントになる
- 長期的なブランド資産になる
それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。
◉-1、企業出版で信頼性と話題性を獲得できる
書籍は、数ある情報発信手段の中でも特に社会的信頼性が高い媒体です。
企業の専門性や独自性を体系的に伝えられるため、ブランド価値を高める効果が期待できます。
また、第三者である出版社を通じて発行されることで、情報に客観性が付与される点も魅力です。
企業自らが発信する広告とは異なり、中立的な立場から認められた内容として受け止められやすくなります。
さらに、出版自体がニュース性を持つため、SNSや業界紙、地域メディアなどで取り上げられる可能性も広がります。
「書籍を出版した企業」という事実そのものが話題になり、自然と情報拡散が進むのも企業出版ならではのメリットです。
結果として、書籍を出している企業には「専門性が高く、信頼できる」という印象が生まれ、ブランドイメージ向上につながります。
◉-2、営業ツール・採用ツールとしても活用できる
営業活動の際に、事前に書籍を渡しておくことで企業の考え方や強みを理解してもらいやすくなり、信頼関係を築くきっかけになります。
また、採用活動では書籍が企業理念や文化を伝える役割を果たし、価値観に共感する人材の応募が増えることもメリットです。
書籍を読んだうえで応募する人は企業への理解が深く、採用のミスマッチを減らす効果も期待できます。
さらに、既存顧客からの紹介シーンで「この会社は書籍も出している専門家です」と自然に推薦してもらえることで、紹介の説得力が高まり、新たなビジネスチャンスにもつながります。
◉-3、競合との差別化ポイントになる
同業他社が書籍を出していない場合、書籍そのものが大きな差別化要素になります。
本を出版している企業は「その分野の第一人者」として認識されやすく、専門性や実績を示す有力な根拠として評価されます。
その結果、顧客からの信頼が高まり、価格だけで比較される状況から脱却しやすくなるのです。
さらに、書籍でノウハウなどを公開することで、競合には真似できない専門性のアピールが可能になります。
◉-4、長期的なブランド資産になる
書籍は一度発行すると長期にわたり残り続ける媒体で、広告やSNS投稿のように短期間で流れてしまうものとは異なります。
企業が大切にしてきた理念や経験を体系立てて発信することで、時間をかけて信頼や認知が蓄積されていきます。
こうした蓄積は企業ブランドを強固にする土台となり、中長期的な成長を支える力になるでしょう。
また、書籍が継続的に読まれることで、企業の価値観や姿勢が時代を超えて受け継がれていく点もメリットです。

企業出版で売れる本を作るための具体的なステップ

企業出版で成果を出すためには、書籍制作の流れを段階ごとに整理し、計画的に進めることが大切です。
ここでは、経営者が押さえておくべき具体的なステップを解説します。
- ステップ1:出版の目的とゴールを明確にする
- ステップ2:読者ターゲットと伝えるメッセージを設定する
- ステップ3:読者の共感を生む構成を設計する
- ステップ4:制作・編集の方向性を整理する
- ステップ5:出版後の活用戦略を設計する
- ステップ6:成果を検証し、次の施策につなげる
順を追って詳しく見ていきましょう。
◉-1、ステップ1:出版の目的とゴールを明確にする
最初に取り組むべきことは、「なぜ出版するのか」「何を達成したいのか」という目的を明確にすることです。
ブランディング、リード獲得、採用強化、信頼形成など、目的やゴールによって本の内容やトーン、構成は大きく変わります。
目的があいまいなままでは出版の効果が発揮されにくくなるため注意が必要です。
目的とゴールを数値や行動レベルで定義しておくと、制作途中の判断もぶれにくくなります。
◉-2、ステップ2:読者ターゲットと伝えるメッセージを設定する
次に取り組むのは、「誰に」「何を伝えるのか」を明確にすることです。
読者ターゲットには、企業経営者や顧客、取引先、就職希望者、業界関係者などを具体的に設定し、読者が抱える課題や期待に寄り添ったメッセージを設計します。
また、事業戦略上でどの層を集客したいのかを踏まえてターゲットを定めると、メッセージに一貫性と実効性が生まれるようになるので、この段階で事業全体との方向性が合っているかも確認しておくとよいでしょう。
読者を明確にすることで伝える内容に一貫性が生まれ、強調すべきポイントも判断しやすくなるため、メッセージがより的確に届くようになります。
◉-3、ステップ3:読者の共感を生む構成を設計する
章構成を考える際は、読者が理解しやすく、自然に読み進められる流れを意識します。
一般的には「事実」「考察」「価値」「未来」といった順序で構成すると、読者が納得しやすく、内容への共感も得られやすくなります。
読者の感情や思考の動きを踏まえて構成を組み立てることがポイントです。
構成を丁寧に設計することで、読者にきちんと企業の価値や意図が伝わるようになります。
◉-4、ステップ4:制作・編集の方向性を整理する
制作を進める前に、「誰が書くのか」「どのようなトーンで書くのか」を決めておくことが必要です。
ビジネス書の多くは専門のブックライターが執筆しており、著者自身がすべての文章を書くケースの方が実は少数派です。
ブックライターは経営者への丁寧なインタビューを通して、頭の中にあるノウハウや経験を言語化する専門職。
著者の想いや言葉を文章として再構成する役割であり、いわゆるゴーストライターとは異なります。
経営者本人が書く場合も、ライターに依頼する場合も、専門用語を多用しすぎず、企業の信念や想いが自然に伝わる文章になるよう意識しましょう。
伝えたい内容や表現の方向性をあらかじめ定めておくことで、書籍全体に一貫性が生まれます。
▶︎ゴーストライターについては、関連記事【ゴーストライターとはどういう意味?ビジネス書の執筆で活用すべき理由や高品質な原稿を書いてもらうためのポイントなども解説!】もあわせて参考にしてください。
◉-5、ステップ5:出版後の活用戦略を設計する
書籍をどの場面で活用するかを事前に具体的に決めておくことが重要です。
営業や採用、PR、講演、セミナーなど、社内外の接点に合わせて配布や紹介の方法を設計します。
また、出版前後には、プロモーションや広報、SNSでの発信などの動線を整えると、出版効果を高められます。
◉-6、ステップ6:成果を検証し、次の施策につなげる
出版後は、問い合わせ数、応募者の質、売上の変化など、具体的な指標を用いて成果を検証します。
結果を数値として把握することで、次の発信やブランディング施策、次回の出版企画に活かすことができます。
出版を単発のイベントとして終わらせず、経営のPDCAに組み込むことが効果を高めるポイントです。
検証と改善を繰り返すことで、ブランド戦略の一貫性と成果が高まります。
売れる本を生み出し、ビジネスで成果を上げた事例
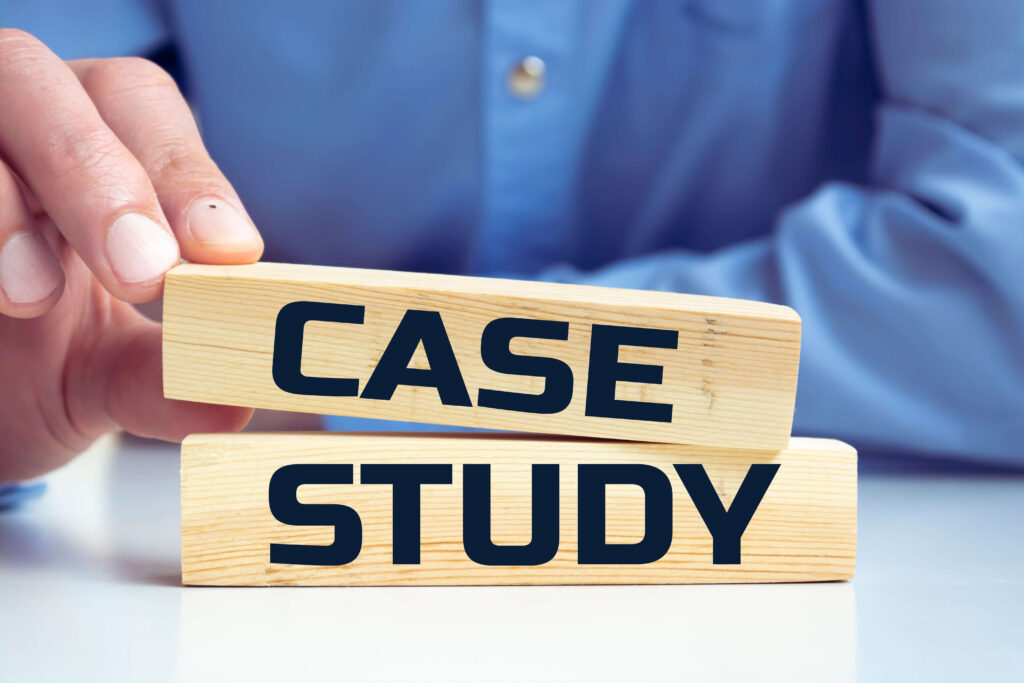
ここでは、売れる本によって実際にビジネスで成果を上げた事例を紹介します。
- 出版後2週間で重版出来!書籍をきっかけに問い合わせが増えた事例
- 権威性と信頼性を獲得し、10億円の売上に貢献した事例
- 出版後に新規顧客開拓とメディア露出が拡大した事例
3つの事例を詳しく見ていきましょう。
◉-1、出版後2週間で重版出来!書籍をきっかけに問い合わせが増えた事例
法人向け保険を専門とする保険代理店の経営者は、新規事業のコンサルティングの顧客獲得を目的に書籍を出版しました。
書籍では、保険業界で一般的な「成果報酬制」に対して、「月額報酬制」が業績向上に有効だという持論を展開して注目を集めました。
出版後2週間で重版出来、出版記念のセミナーの参加者60名のうち5件が成約につながるなどの成果につながりました。
【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店
◉-2、権威性と信頼性を獲得し、10億円の売上に貢献した事例
ある不動産会社の経営者は、高所得で納税額の高い医師に向けて、不動産投資が節税対策に有効であることを訴求する書籍を出版しました。
「医師」という明確なターゲットに向けて設計したことで、読者の多くが高い確度の見込み客となりました。
実際に、発売直後に寄せられた最初の10件の問い合わせは、全て成約につながりました。
自らお金を払って本を手に取る読者は、すでに課題を認識している「ホットリード」であることがわかります。
出版費用はすぐに回収でき、、6ヶ月で10億円もの売上向上に貢献しました。
◉-3、出版後に新規顧客開拓とメディア露出が拡大した事例
ある建設業専門の経営コンサルタントは、サービス内容の進化に合わせて自社のリブランディングのために書籍を出版しました。
新規顧客層へのアプローチを意識して「赤字続きの会社がみるみる蘇る」というタイトルを付けました。
発売から1ヶ月で重版出来、17媒体のWebニュースに掲載されてメディア露出が拡大。
その結果、コンサルティングや育成支援などで13件の新規顧客を獲得しました。
【まとめ】企業出版で売れる本をつくり、ビジネスで成果につなげよう
この記事では、売れる本の共通点や売れる本のビジネスメリット、企業出版の具体的なステップ、成功事例などについて詳しく解説しました。
企業出版は、単なるブランディング施策ではなく、企業の信頼性や売上の向上、採用への好影響などの成果を出すための経営課題の取り組みです。
フォーウェイでは、企業のブランディング力向上とマーケティング支援を目的としたブックマーケティング(企業出版)サービスを提供しています。
これまで数多くの企業様の書籍制作を手がけ、理念の可視化・専門性の発信・ブランド価値の向上につながる成果を生み出してきました。
もし「自社の想いを形にして世の中へ届けたい」「ブランド価値をさらに高めたい」とお考えでしたら、ぜひ一度フォーウェイへご相談ください。
企画構成から出版まで、経験豊富な担当者が丁寧にサポートいたします。


企業イメージは、顧客・取引先・株主・従業員・地域社会といったステークホルダーが企業に対して抱く総合的な印象を指します。
良い企業イメージを築くことは、信頼の獲得や採用・人材定着、売上向上につながります。
しかし、企業イメージは短期間で形成されるものではありません。
そのため、日々の情報発信や行動、理念の一貫性が重要となります。
この記事では、企業の経営者・事業責任者に向けて、企業イメージを向上させるための考え方や具体的な実践手法について解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
企業イメージとは

企業イメージは企業活動全体から形づくられるため、その仕組みを理解しておくことが、戦略的な取り組みを進めるうえで重要です。
ここでは、企業イメージの基本的な事項として、次の2つのポイントに分けて解説します。
以下で、それぞれ詳しく見ていきます。
◉-1、企業イメージの定義
企業イメージとは、顧客や従業員、取引先、社会などが企業に対して抱く印象や信頼、期待を総合したものを指します。
見た目や広告だけでなく、理念や日々の行動、社会的姿勢など、あらゆる接点によって形成されることが特徴です。
◉-2、企業イメージの構成要素
企業イメージは、次の5つの要素から成り立っています。
- ビジュアル
- コミュニケーション
- 商品やサービスの品質
- 従業員の対応
- 社会的責任
具体的には、ビジュアルとしてロゴやコーポレートカラー、Webサイトのデザインなどが挙げられます。
営業担当者の営業トーク、問い合わせ対応といった社外とのコミュニケーションも企業のイメージを左右する要素です。
企業の本質ともいえる商品やサービスの品質が、企業の評判に関わるのはいうまでもありません。
接客態度や電話応対などの従業員の対応も、企業イメージに影響します。
現代では、コンプライアンスの遵守や地域貢献、環境問題への取り組みのような、企業が社会的に責任を果たしているかどうかもイメージに影響をおよぼす要素です。
これらの5つの要素の一貫性が保たれることで、信頼性の高い企業イメージが確立されます。
企業イメージを向上させるメリット

企業イメージを向上させることは、信頼の獲得や収益性の向上、人材の採用や定着など、多方面に良い影響をもたらします。
主なメリットとして、次の4つが挙げられます。
- 顧客や取引先からの信頼が高まり、売上・利益が向上する
- 競合との価格競争に巻き込まれにくくなる
- 従業員満足度が向上し、優秀な人材の採用・定着につながる
- 社会的評価が高まり、持続的な企業成長を支える
以下で、具体的にどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
◉-1、顧客や取引先からの信頼が高まり、売上・利益が向上する
顧客や取引先は「信頼できる企業」から商品やサービスを選ぶ傾向が強く、企業イメージの良し悪しが売上や契約率に直結します。
たとえば、フォローに力を入れたことで、問い合わせだけで終わっていた見込み顧客が「御社に任せたい」と言ってくれるようになるなど、信頼を得ることが売上にもつながります。
信頼が高まるほど「選ばれる理由」が明確になり、競合他社との差別化が進むのです。
企業の信頼が高まることで、購入や継続的な取引につながり、結果として売上と利益の向上が期待できます。
◉-2、競合との価格競争に巻き込まれにくくなる
ブランド価値が確立された企業は、価格だけでなく、信頼や品質、社会的評価といった付加価値で選ばれるようになります。
こうした付加価値が確立されると、「価格以外の評価軸」で選ばれる機会が増え、価格競争への依存度が下がるのです。
そのため、競合他社との値下げ競争に陥りにくくなり、適正価格での取引や長期的な利益の確保が期待できます。
◉-3、従業員満足度が向上し、優秀な人材の採用・定着につながる
企業イメージが向上すると、社外だけでなく社内にも良い影響が生まれます。
社会から信頼される企業で働く誇りが従業員のモチベーションを高め、離職率の低下が期待できます。
また、理念に共感できる優秀な人材の応募が増えて、採用コストの削減や採用活動の効率化にもつながります。
◉-4、社会的評価が高まり、持続的な企業成長を支える
CSR活動や環境への取り組み、地域貢献などを通じて企業が社会に示す姿勢も、企業イメージの向上につながる要素です。
社会との信頼関係が深まることで、ステークホルダーからの期待や支持も安定し、企業の長期的な経営基盤が強化されます。
こうした取り組みの積み重ねによって、企業の社会的信頼の土台が形成され、持続可能な企業成長を支える基盤となります。
企業イメージを向上させる具体的な手法

企業イメージを高めるためには、外部への発信だけでなく、内部の意識改革や物語を通じた価値の伝達など、多角的な取り組みが必要です。
ここでは、代表的な4つの手法について解説します。
- アウターブランディング
- インナーブランディング
- ストーリーブランディング
- 採用ブランディング
以下で、それぞれについて詳しく解説します。
◉-1、アウターブランディング
アウターブランディングとは、社外に向けてブランド価値を発信し、理解や信頼を獲得するための取り組みです。
顧客や取引先、株主、従業員、地域社会などのステークホルダーに「どのような価値を提供できる企業なのか」を分かりやすく伝えることが重要になります。
アウターブランディングの主な手法は、以下の表の通りです。
| 主な手法 | 詳細 |
| コーポレートサイトの改善 | ・企業理念や強みが明確に伝わる構成
・デザインにすることで、企業理解が深まる
・第一印象を左右するため、信頼性を判断する重要な要素となる |
| SNS・オウンドメディアの活用 | ・企業の価値観や取り組みを継続的に発信でき、情報の透明性が高まる
・顧客との接点を増やし、関係構築を促進する |
| PR・広報活動の強化 | ・企業の取り組みや価値を社会に広く伝えることができる
・メディア掲載を通じて専門性の訴求や認知度の向上につながる |
| 顧客コミュニケーションの最適化 | ・丁寧な対応によって顧客満足度や信頼感の向上が期待できる
・充実したサポートは顧客の信頼を高め、長期的な関係構築に寄与する |
◉-2、インナーブランディング
インナーブランディングとは、従業員が企業理念やブランドの価値を理解し、自ら体現できる状態をつくる取り組みです。
従業員一人ひとりがブランドの担い手となることで、企業イメージは自然と外部にも良い形で広がっていきます。
インナーブランディングの主な手法は、以下の表の通りです。
| 主な手法 | 詳細 |
| 企業理念・ビジョンの浸透施策 | ・研修やワークショップを通じて、従業員が自社の価値や理念を理解できる
・理念が共有されることで、組織全体としての方向性が明確になり、行動の統一につながる |
| 社内コミュニケーションの活性化 | ・部署間の連携を円滑にし、組織全体の一体感を強化する
・意見交換が行われる環境を整えることで、ブランド価値の体現が進む |
| 表彰制度・評価制度の整備 | ・成果や行動を正しく評価する仕組みが、従業員の意欲向上に貢献する
・制度の透明性が組織文化の形成を支える |
| 研修・育成制度の拡充 | ・企業の価値観を理解した上で能力を伸ばす環境を整えられる
・理念に基づく行動が促進され、企業イメージの向上につながる |
▶︎インナーブランディングのやり方については、関連記事【インナーブランディングとは?施策や進め方、成功事例を紹介】もあわせて参考にしてください。
◉-3、ストーリーブランディング
ストーリーブランディングとは、企業や商品の背景にある物語を通じて価値を伝える手法です。
人はストーリーに共感しやすく、物語を通じて企業の価値や想いがより深く伝わる点が特徴です。
ストーリーブランディングの主な手法を、以下の表にまとめました。
| 主な手法 | 詳細 |
| 創業ストーリーの発信 | ・創業時の想いや背景を伝えることで、企業の存在意義や価値観が明確になる
・企業の原点を共有することで、顧客を含むステークホルダーとの共感が生まれ、信頼の構築につながる |
| 商品開発の裏側を紹介 | ・品質へのこだわりや開発部門の姿勢を具体的に示せる
・製品やサービスへの安心感や納得感を高め、ブランドに対する信頼と好感を高める |
| 従業員のストーリーを紹介 | ・従業員の働き方や成長の過程を紹介することで、企業文化や価値観が具体的に伝わる
・従業員のリアルな声が企業への信頼を高め、採用活動や社員の定着にも良い影響を与える |
| 顧客事例(ビフォーアフター)を活用 | ・商品やサービスが生み出す変化を具体的に示せる
・提供価値が明確になることで信頼性が高まり、新規顧客の獲得につながる |
| 書籍の出版 | ・企業の理念・専門性・実績を1冊の本に体系的にまとめて発信できる
・社会的信頼性の高いメディアとして受け取られ、潜在顧客の関心獲得にも効果がある
・書籍は長期的に残るため、企業イメージ向上に継続的に貢献する |
▶︎ストーリーブランディングのやり方については、関連記事【ストーリーブランディングとは?企業の物語を伝えてファンを作る方法】もあわせて参考にしてください。
◉-4、採用ブランディング
採用ブランディングとは、求職者から「働きたい」と思われる企業になるためのブランド構築を指します。
給与や福利厚生だけでなく、働く意義や企業文化を明確に伝えることで、優秀な人材の獲得につながります。
採用ブランディングの主な手法は、以下の表の通りです。
| 主な手法 | 詳細 |
| 採用サイト・採用SNSの強化 | ・専用サイトやSNSを通じて、企業文化や働く環境、従業員の姿を具体的に伝えられる
・求職者の企業理解が深まり、応募意欲の向上につながる |
| 企業カルチャーの可視化 | ・働く環境や価値観を明確に示すことで、ミスマッチ防止や採用精度の向上につながる
・求職者が企業との相性を判断しやすくなり、納得感の高い採用につながる |
| 求人票・募集要項のブラッシュアップ | ・仕事内容や求める人物像を明確化することで、適切な人材からの応募が増える
・業務内容や役割を正しく伝えられるため、入社後の定着率向上にもつながる |
| 採用広報・イベントの活用 | ・企業の魅力や働く価値を直接伝える機会をつくれる
・求職者との接点が広がり、応募意欲の向上に結びつく |
▶︎採用ブランディングのやり方については、関連記事【採用ブランディングの重要性とは? 目的やメリット、具体的な方法まで解説】もあわせて参考にしてください。
企業イメージを向上させるには信頼を継続的に築くことが重要!

企業イメージを向上させるために重要なのは、派手な広告や一時的な施策ではなく、顧客や社会からの信頼を継続的に積み上げていくことです。
優れた商品やサービスを提供していても、信頼が伴わなければ企業として正当に評価されず、長期的なファンを獲得することも難しくなります。
一方で、信頼を基盤としている企業は継続的な支持を得やすく、競合との差別化にもつながります。
企業出版(ブックマーケティング)なら持続的に企業イメージを高められる!

企業出版(ブックマーケティング)は、社外への発信、社内への浸透、社会との関係構築のすべてに効果的な手法です。
他の施策では得られない「信頼性」「統合性」「持続性」を兼ね備えており、企業イメージを長期的に高めることができます。
企業出版(ブックマーケティング)には、主に次の4つの特徴があります。
- 信頼性の高い情報をまとめて発信できる
- 企業理念を社内に浸透させることができる
- 社会的信頼や共感を醸成することができる
- 長期的なブランド資産化につながる
以下では、これらの特徴について詳しく解説します。
◉-1、信頼性の高い情報をまとめて発信できる
書籍という信頼性の高いメディアを通じて、企業の理念や実績、専門性を体系的に伝えることができます。
その内容は取引先や顧客、メディアからの評価向上につながり、企業の社会的信用を強化します。
書籍はWeb上の情報や断片的な内容だけを掲載している広告などに比べ、情報が豊富に盛り込まれているのが特徴です。
そのため、「この企業は何者か」を一冊で深く理解してもらえるツールとして機能します。
◉-2、企業理念を社内に浸透させることができる
書籍は、経営者の思想や企業の価値観を明確に示し、従業員が自社の方向性を理解しやすくします。
理念への共感や誇りが育まれ、組織としての行動の一貫性が高まります。
特に新入社員や中途入社した社員に対し、入社初期に企業文化をつかむための「共通テキスト」として活用できるのもメリットです。
◉-3、社会的信頼や共感を醸成することができる
書籍を通じて社会課題への向き合い方や企業としての責任を示すことで、社会からの信頼や共感を高めることが可能です。
また、CSRやSDGsの取り組みと組み合わせることで、倫理性や持続可能性を備えた企業イメージの構築にもつながります。
このような企業姿勢を書籍という形で言語化しておくことは、投資家や取引先などのステークホルダーが、自社のスタンスや長期的なビジョンを理解・評価するうえで重要な判断材料となります。
◉-4、長期的なブランド資産化につながる
書籍は時間が経っても残り続ける媒体であり、長期にわたり価値を発揮します。
営業・採用・広報など幅広い場面で活用でき、企業にとって継続的に使えるブランド資産となります。
また、書籍は増刷や改訂版の発行によって、内容をアップデートすることが可能です。
そのため、社会状況が変化したとしても、時代に合わせて価値を育て続けられます。
特に専門性の高いサービスを提供している企業や、創業のきっかけ・商品開発に独自のストーリーがある企業にとって、書籍は強力なブランド資産となります。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

出版によって企業イメージが向上した事例

ここでは、企業出版によって企業イメージを高めた事例を3つ紹介します。
- 出版を機に業界から一目置かれる存在へとイメージが向上した事例
- 出版をきっかけにブランド価値が向上し、顧客とのつながりを深めた事例
- 出版を通じて「海外進出支援の専門家」としてポジションを築いた事例
以下で、それぞれの事例について詳しく紹介します。
◉-1、出版を機に業界から一目置かれる存在へとイメージが向上した事例
法人保険を専門とする保険代理店は、自社の強みや経営ノウハウを体系的にまとめた書籍を出版しました。
書籍では、保険業界の「成果報酬型」を「一律報酬型」の給与体系に切り替えることで業績が向上した実例を紹介し、自社の独自性と専門性を明確に示しました。
出版後、業界内での認知度が一気に高まり、新規事業のコンサルティング契約を複数獲得することに成功。
さらに、大手保険会社からの講演依頼や共同マーケティングの打診が増えるなど、業界内で一目置かれる存在へと評価が高まりました。
【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店
◉-2、出版をきっかけにブランド価値が向上し、顧客とのつながりを深めた事例
女性向けサプリメントを販売するメーカーは、既存顧客との関係強化と新規顧客の獲得を目的に書籍を出版しました。
出版の狙いは、自社の信頼性を高めてファン化を促し、LTV(ライフタイムバリュー)の向上につなげること。
書籍では、代表者自身の経験や健康に対する考え方をまとめ、読者にとって役立つ実用的な内容に仕上げました。
その結果、読者が企業や商品の背景をより深く理解するようになり、購入者のリピート率が向上。
さらに、「書籍無料プレゼント」企画を実施したところ、想定の6倍の応募が寄せられ、多くの新規顧客との接点を創出することにも成功しました。
【事例コラム】”書籍無料プレゼント”に想定の6倍の応募、リピート率アップにインパクト!サプリメントメーカーの出版プロジェクト
◉-3、出版を通じて「海外進出支援の専門家」としてポジションを築いた事例
国際税務を専門とする公認会計士は、事務所開所後、海外勤務で得た実体験をもとに、海外進出企業が陥りやすい失敗をケーススタディ形式で解説した書籍を出版しました。
書籍では、失敗の背景や原因を具体的なストーリーとして描きながら、各ケースごとに企業が直面するリスクや課題、そして効果的な解決策を提示。
これから海外進出を目指す企業が避けるべき落とし穴を、実務目線で分かりやすくまとめています。
その結果、地元紙や全国紙、ラジオ番組からの注目が集まり、メディア露出が大きく増加しました。
書籍を通じて専門性が広く認知され、「海外進出支援の専門家」としてのポジションを確立。
ブランディングとビジネス拡大の両面で大きな成果を上げました。
【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士
【まとめ】企業イメージ戦略の中心に企業出版を位置づけよう!
この記事では、企業イメージを向上させるための基本的な考え方と具体的手法について解説しました。
企業イメージを向上させるためには、信頼を継続的に積み重ねる取り組みが欠かせません。
その中でも企業出版は、社外発信・社内浸透・社会的信頼を同時に高められる強力な手法です。
自社のブランド戦略の中心に企業出版を取り入れることで、持続的な企業イメージの向上が期待できます。
フォーウェイでは、企業出版(ブックマーケティング)サービスを提供しており、多くの企業がブランディング施策として活用しています。
ブックマーケティングサービスでは、企業理念や技術面での専門性、自社の成り立ちなどを含めた総合的な情報発信ができ、信頼性や権威性も高めることが可能です。
企業イメージの向上をお考えの方は、フォーウェイまでご相談ください。


ブランディングとは単なるデザインやロゴではなく、企業の存在意義や市場における立ち位置を象徴するものです。
しかし、変化の激しい現代においては、既存のブランド価値が時代や顧客の期待に合わなくなることがあります。
こうしたズレが大きくなると、企業が持っている魅力や強みが正しく伝わらず、市場での存在感が弱まってしまいます。
このような時にこそ、ブランドの意味そのものを見直すリブランディングを考える必要があるのです。
この記事では、リブランディングの意味や進め方、具体的な手法について詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
リブランディングとは?

リブランディングとは、ロゴやデザインを新しくする「見た目の変更」ではなく、ブランドの「本質的価値を再定義」する経営戦略です。
似ている言葉に「ブランディング」や「リニューアル」がありますが、それぞれ意味や目的は異なります。
ここでは、以下の違いについても説明します。
それぞれ見ていきましょう。
◉-1、ブランディングとの違い
ブランディングは新しいブランドを立ち上げ、ブランドの価値や世界観を市場に浸透させていく取り組みです。
一方、リブランディングは既存のブランドを現状に合わせて再定義する行為で、過去のブランド資産を活かしながら新しい方向性を打ち出すものです。
ブランディングは「ブランドを確立」する取り組み、リブランディングは「既存ブランドを再構築」する取り組みという違いがあります。
◉-2、リニューアルとの違い
リニューアルは、ロゴやデザイン、スローガンといった目に見える部分の刷新を中心とした取り組みです。
一方、リブランディングは、企業理念や価値観、提供価値そのものを見直す包括的な戦略プロセスです。
リニューアルが「見せ方の改善」であるのに対し、リブランディングは「存在意義や価値の再構築」という違いがあります。
リブランディングをやる意味はある?
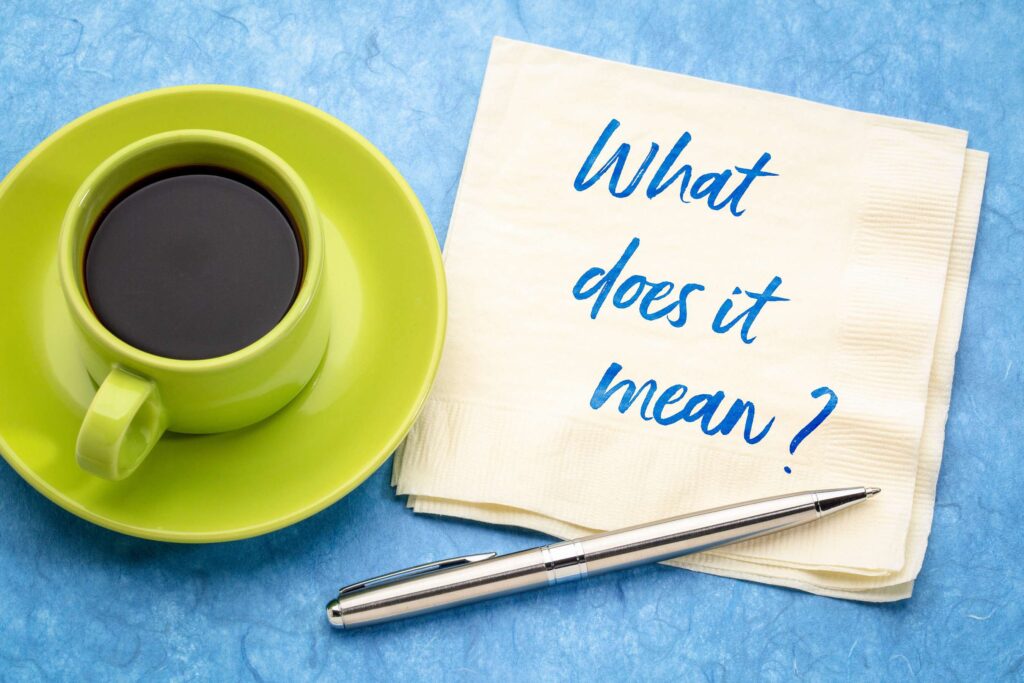
リブランディングは、すべての企業が必ず行うべきとは限りません。
市場環境や事業の方向性によって、「やる意味があるケース」と「やらない方がいいケース」が存在します。
リブランディングが必要か、見送るべきかを見極めることは、重要な経営判断です。
リブランディングをやる意味があるケース

ここでは、リブランディングを行う意味がある6つのケースについて紹介します。
- 時代や市場のニーズが変化したケース
- ブランドイメージと顧客の認識にズレが生じたケース
- 他社との差別化をより強くしたいケース
- 新サービス・新事業にブランドが合わないケース
- 時代に合わせて採用強化・組織文化の刷新をしたいケース
- 企業のネガティブイメージを払拭したいケース
以下からは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、時代や市場のニーズが変化したケース
市場環境や顧客の価値観が大きく変化し、これまでのブランドイメージが時代にそぐわなくなった場合には、リブランディングを検討すべきです。
近年では、デジタル化の進展やサステナビリティ志向の高まりなど、社会全体の価値観が急速に変わりつつあります。
こうした新たな潮流に対応するために、ブランドの意味や立ち位置を見直すケースが増えています。
リブランディングによって得られる効果は、以下の通りです。
- 時代の変化に合わせて企業の方向性を改めて示せる
- ブランドの意味を再整理して、新しいターゲット層に訴求しやすくなる
企業が自らの存在意義を再確認し、未来に向けてブランドを進化させる機会といえます。
◉-2、ブランドイメージと顧客の認識にズレが生じたケース
ブランドメッセージと、顧客の認識にズレが生じると、ブランドが伝えたい価値が十分に伝わらず、競争力を失うリスクがあります。
こうしたズレを修正し、ブランド本来の意味を再定義することもリブランディングの重要な役割です。
リブランディングの効果は、次の通りです。
- 企業価値と顧客の印象を再び一致させることができる
- 認識のズレが解消されて、企業への信頼感が高まる
顧客との認識のギャップを埋めることは、イメージの改善だけではなく、長期的なブランドの信頼を築くために重要です。
◉-3、他社との差別化をより強くしたいケース
市場が成熟化して、競合他社との差別化が難しくなってきたときもリブランディングを検討する必要があります。
自社の独自性を再定義し、競争優位性を再構築するための手段として有効です。
単なる価格や機能での差別化ではなく、ブランドの価値観や存在意義によって、他社にはない魅力を訴求することが重要です。
リブランディングによって得られる効果として、以下が挙げられます。
- 企業の独自性を明確に示すことができる
- 競合との差別化が進み、信頼性や存在感が高まる
競争が激化する今、自社の「らしさ」を明確に打ち出すことが、選ばれるブランドへと進化するために必要です。
◉-4、新サービス・新事業にブランドが合わないケース
新しいサービスや事業を立ち上げた際、既存ブランドの枠組みではその価値や方向性を十分に伝えきれないことがあります。
企業として新たな領域に踏み出すタイミングでは、ブランドの意味やメッセージが事業戦略と整合しているかを改めて確認し、ブランド全体を見直すリブランディングが必要です。
リブランディングで得られる効果は、次の通りです。
- メッセージに一貫性が生まれ、社内外の理解が得られやすくなる
- 企業の成長性や発展性を示すことで、将来的な評価につながる
事業の拡大や変革期こそ、ブランドの方向性を再定義するタイミングです。
◉-5、時代に合わせて採用強化・組織文化の刷新をしたいケース
リブランディングは社外向けだけではなく、社内の一体感を高める手段としても有効です。
ブランドの再定義を通じて社員が自社の存在意義を再確認することができます。
採用活動においても、企業文化に共感する人材を集めやすくなる効果があります。
リブランディングを行う意味は、次の通りです。
- 企業文化の刷新やモチベーションの向上につながる
- 社外にも企業の姿勢を伝えることができ採用強化につながる
社員一人ひとりがブランドの一部として誇りを持てるようになれば、組織全体の結束力が高まり、企業の持続的な成長にもつながります。
◉-6、企業のネガティブイメージを払拭したいケース
不祥事やトラブルを契機に、企業のネガティブイメージが広がってしまったようなときに、マイナスイメージを払拭するためリブランディングは有効です。
ブランドの方向性を見直して、企業としてどのような姿勢で再スタートするのかを明確に示すことが重要です。
リブランディングにより得られる効果は、次の通りです。
- 新しい価値観や改善の取り組みを伝えることで信頼が回復していく
- 社内でも次ステップに進むための一体感が生まれやすくなる
誠実な姿勢で変化を示すことができれば、過去の印象を乗り越え、より強い信頼と共感を築くチャンスになります。
リブランディングをする意味が薄いケース

一方で、企業が次のような課題を抱えている場合は、リブランディングを行っても根本的な解決には至らず、費用と時間が無駄になる可能性が高いといえます。
- 経営上の問題がブランドではなく商品・集客・営業力に起因しているケース
- 社長の気分転換や「デザインを変えたい」だけが理由のケース
- ブランドがまだ浸透していない創業初期のケース
こうしたケースでは、ブランドを見直す前に、まず事業内容や組織運営、商品力といった根本課題を整理・改善することが重要です。
ブランド基盤が未成熟な段階でリブランディングを行うと、コストや混乱が発生し、かえってブランド価値を損なうリスクもあります。
リブランディングの進め方

リブランディングを実践する際に、経営者が押さえておくべき基本的な6つのステップを解説します。
- ステップ1:現状分析を行う
- ステップ2:ブランドコアを見直し、言語化する
- ステップ3:ブランドアイデンティティの再構築を行う
- ステップ4:インナーブランディングを推進する
- ステップ5:アウターブランディングを推進する
- ステップ6:効果を検証し、継続的に運用する
順を追って詳しく見ていきましょう。
◉-1、ステップ1:現状分析を行う
まず、自社ブランドの現状を客観的に把握します。
顧客や市場からの評価、競合のポジショニング、社内のブランド理解度などを調査して、現状の課題と強みを明確にします。
現状分析が不十分だと、その後の方向性がブレやすくなるため入念な調査が必要です。
◉-2、ステップ2:ブランドコアを見直し、言語化する
次は、ブランドとして何を大切にし、どのような価値を社会に届けたいのかを明確にするステップです。
企業の存在意義(Purpose)、目指す未来像(Vision)、行動基準(Value)といったブランドコアを言語化することで、リブランディングの軸が明確になります。
社内外で共有できる基盤が定まることで、後のデザインやコミュニケーション設計にブレがなくなります。
◉-3、ステップ3:ブランドアイデンティティの再構築を行う
再定義したブランドコアをもとに、企業の世界観を視覚・言語・体験に落とし込んでいきます。
ロゴやカラー、スローガンなどの要素はその一部にすぎず、重要なのは「どんな印象を届けたいのか」というブランド体験の設計思想です。
ブランドアイデンティティの再構築の段階では、各要素の方向性(トーン&マナー・ビジュアルコンセプトなど)を定め、ブランドとしての一貫性を築く基盤を作ります。
◉-4、ステップ4:インナーブランディングを推進する
次に、インナーブランディングによってブランドの再定義を社内に浸透させます。
社員がブランドの意味を理解し、日々の業務に落とし込めるような状態をつくることが目的です。
説明会や研修、社内向け資料の整備などを通じて、リブランディングの本質的な価値を体現できるようにします。
▶︎インナーブランディングのやり方については、関連記事【インナーブランディングとは?施策や進め方、成功事例を紹介】もあわせて参考にしてください。
◉-5、ステップ5:アウターブランディングを推進する
インナーブランディングのあとは、ブランドの再定義を社外に発信するアウターブランディングを推進します。
新しいメッセージやビジュアル、ストーリーテリングを通じて顧客や市場に新たなブランド価値を伝えていきます。
広告や広報活動、SNS、イベントなどのタッチポイントを統一的に整えることがポイントです。
▶︎アウターブランディングのやり方については、関連記事【企業の情報発信に有効なツールはどれ?効果的に活用するコツも解説】もあわせて参考にしてください。
◉-6、ステップ6:効果を検証し、継続的に運用する
リブランディングは、一度実施して終わりというわけではありません。
そうした取り組みがどの程度成果につながっているかを定期的に評価します。
改善すべき点が見つかれば、その都度見直しを行っていくことで定着させます。
顧客認知度や社員理解度、売上・採用活動への影響などについて、必要に応じて取り組みを見直すことが重要です。
リブランディングの具体的な手法

ここでは、リブランディングを効果的に進めるための具体的な3つの手法を紹介します。
- ロゴやデザインの再設計
- 外部向けプロモーションの展開
- 発信コンテンツの見直し
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、ロゴやデザインの再設計
ブランドの印象を直感的に伝える要素がロゴやデザインです。
リブランディングの初期段階では、企業の新しい理念や価値観を反映する形で、ロゴやカラー、フォント、ビジュアルトーンなどを再設計します。
また、Webサイトや名刺、パンフレット、パッケージ、店舗デザインなど、顧客がブランドに触れるすべてのタッチポイントを統一することで、企業らしさを一貫して伝えられるようになります。
◉-2、外部向けプロモーションの展開
新しいブランドを市場に定着させるためには、効果的な外部への発信が欠かせません。
プレスリリースや広告キャンペーン、SNS発信、コラボイベントなどを通じて、新しいブランドのメッセージを顧客や社会に伝えます。
重要なのは、発信するチャネルごとに内容を変えるのではなく、トーンやビジュアル、メッセージを統一して一貫性を保つことです。
◉-3、発信コンテンツの見直し
ブランドの方向性が変わった場合、発信する情報内容とトーンも再構築する必要があります。
Webサイトやブログ、SNS、採用ページなどで使う言葉・表現・画像を見直して、新しいブランドメッセージに沿った形でアップデートします。
また、単に文章を変えるだけでなく、顧客とのコミュニケーションの在り方そのものを見直すことが重要です。
たとえば、これまで一方的な商品紹介中心だった発信を、顧客の課題解決や共感を軸としたストーリー型発信に切り替えるなど、より「顧客視点」を意識した情報発信に変えていきます。
◉-3-1、リブランディングするなら企業出版が効果的!
リブランディングする際の情報発信として「企業出版」は有効です。
書籍出版は、他の広告媒体では伝えきれない理念やストーリーを深く伝えることができ、経営者のメッセージを社会に発信する最適な手段です。
また、ブランド再定義の文脈を一冊の本として形にすることで、社内外の理解促進と信頼構築を同時に実現できます。
さらに、書籍は営業活動や採用活動、社内教育などで長期的に活用することが可能です。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

企業出版でリブランディングを成功させた事例
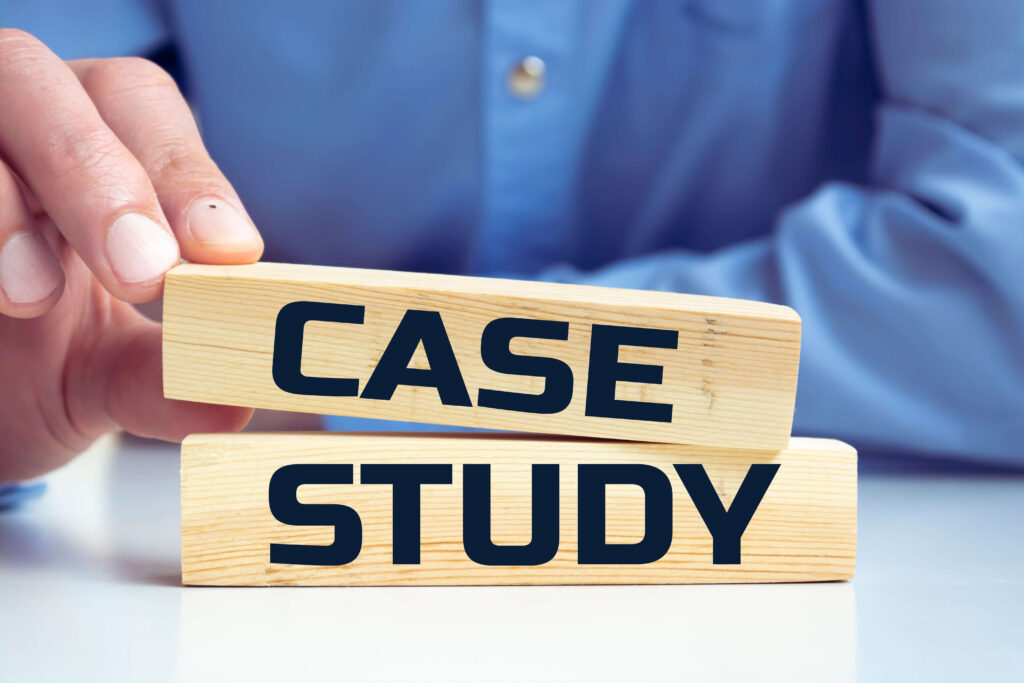
ここでは、企業出版をきっかけにリブランディングに成功した3つの事例を紹介します。
- 過去の書籍も重版出来!新規顧客開拓が実現した事例
- セミナー集客も成功!業界内でも書籍が好評を得た事例
- 公式ブック出版で食のブランドとしてポジションを確立した事例
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、過去の書籍も重版出来!新規顧客開拓が実現した事例
建設業専門の経営コンサルタントは、サービス内容の進化に合わせて自社ブランドを見直すため、新版として書籍を出版しました。
これまで十分に届いていなかった層へアプローチするため、「赤字続きの会社がみるみる蘇る」という明確な訴求を持つタイトルに刷新した点が特徴です。
発売1ヶ月で即重版、累計5,000部突破、前著も合わせて累計6万部超え、17媒体のWebニュースに掲載されるなど大きな反響を呼びました。
その結果、建設業向けコンサルティングや育成支援を中心に10件以上の新規顧客獲得へとつながりました。
◉-2、セミナー集客も成功!業界内でも書籍が好評を得た事例
法人向け保険代理店を経営する社長は、保険代理店向けコンサルティング事業の新規顧客獲得と信頼性向上を目的に、書籍を出版しました。
書籍は、成果報酬が主流の保険業界においてあえて月額報酬制を採用し、事業を成長させてきた独自ノウハウを体系的に整理した内容です。
発売からわずか2週間で重版が決定し、Amazonでは一時的に品切れになるほどの反響を獲得。
出版記念セミナーには60名が参加し、最終的に5件の成約につながりました。
さらに、書籍を読んだ保険会社からのセミナー依頼が増加し、採用活動にも良い影響が生まれるなど、出版をきっかけに多方面で大きな成果を上げることができました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2-1、社名変更に伴うリブランディング施策としても書籍を活用
保険代理店「株式会社イナバプランニングカンパニー」は、さらなる事業拡大のために「ハレノヒハレ株式会社」へ社名変更をし、そのタイミングでリブランディング施策として書籍を活用しました。
著者は外資系生保の全国No.1セールスの実績を持ち、書籍では「顧客に本当に必要とされる営業」の本質を体系化して公開。
社名変更という節目において企業出版を活用して成功を収めた事例です。
▶︎書籍の詳細については【【新刊発売】『大型契約が決まり続ける保険営業術』出版】もあわせて参考にしてください。
◉-3、公式ブック出版で食のブランドとしてポジションを確立した事例
トートバッグのヒットにより「アパレルブランド」というイメージが強まっていた企業が、公式ブックの出版を契機にリブランディングへ踏み出し、本来の「食のブランド」としての立ち位置を再び確立した事例です。
書籍では、生産者のこだわりや想いを丁寧に紹介するとともに、家庭で手軽に作れるレシピを掲載するなど、「豊かな食の魅力」が性別を問わず伝わるよう、企画・編集段階から工夫しました。
これらの取り組みにより、書籍は24,000部を超えるヒットとなり、男性比率30%という新たな顧客層を獲得。
従来のメイン層だった女性以外への認知も大きく広がりました。
さらに、「食のセレクトショップ」としてのブランドポジションを明確化し、企業が進むべき方向性を再確認できただけでなく、制作プロセスそのものが社員にとってブランドDNAを再認識する機会となり、社内浸透にもつながっています。
【まとめ】企業出版でリブランディングを成功させよう!
この記事では、リブランディングの意味や進め方、具体的な手法について詳しく解説しました。
時代や市場のニーズが変化したり、ブランドイメージと顧客の認識にズレが生じたりした場合は、リブランディングによって存在意義や価値を再定義する必要があります。
その際、企業出版は「理念・価値・ストーリー」を体系的に伝えることができるため、リブランディングの手段として有効です。
広告では届けきれないメッセージを、書籍という形で社内外に継続的に提示できるため、信頼性の向上や新規顧客の開拓にもつながります。
フォーウェイでは、企画立案から制作・流通までの一貫した企業出版(ブックマーケティング)サービスを提供しています。
書籍を通じて企業の理念や価値を再整理し、ターゲット層に響く形でストーリーとして発信することが可能です。
「自社の強みを可視化し、ブランド価値を高めたい」とお考えの方は、ぜひご相談ください。


高額商品や専門サービスを提供する企業にとって、富裕層の心をつかむことはビジネスの成長を左右する重要なテーマです。
しかし、富裕層の集客は一般消費者とは異なり、広告や低価格の訴求では成果を上げることはできません。
富裕層が重視するのは「信頼できる相手かどうか」です。
そのため、短期的な販促ではなく、専門性や世界観の一貫性を通じて信頼を積み上げていくアプローチが必要です。
この記事では、富裕層の集客を成功させるための手法やポイント、成功事例について詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
そもそも富裕層とは?

富裕層とは、単に高収入を得ている人を指すわけではありません。
金融資産を一定以上保有し、安定した資産運用や投資を行っている人々を含む広い概念です。
金融機関や調査機関によって定義は多少異なりますが、一般的には以下のように分類できます。
| 分類 | 純金融資産額 |
| 準富裕層 | 5,000万円~1億円未満 |
| 富裕層 | 1億円以上~5億円未満 |
| 超富裕層 | 5億円以上 |
野村総合研究所(NRI)の調査によれば、2023年時点で1億円以上の純金融資産を保有する富裕層と超富裕層の合計は約165.3万世帯に達しており、その内訳は富裕層が約153.5万世帯、超富裕層が約11.8万世帯という結果が示されています。
日本国内における富裕層は年々増加しており、投資・不動産・医療・教育など、さまざまな分野で影響力を拡大しています。
こうした層は、国内経済において重要な購買力と影響力を持ち、企業にとっても戦略的に無視できない顧客層といえるでしょう。
◉富裕層の集客に有効な手法

富裕層を対象とした集客では、一般的な広告やキャンペーンのように幅広い層への認知拡大を目指すよりも、信頼関係の構築と深いコミュニケーションが重要です。
ここでは、富裕層の心理や意思決定プロセスを踏まえて、5つの手法を紹介します。
- 知人やパートナー経由での紹介
- 限定感のある体験やイベントの活用
- 富裕層向けに特化した広告配信
- 富裕層ブランドとのコラボレーション施策
- 企業出版による専門性アピール
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、知人やパートナー経由での紹介
富裕層にとって、購買や投資の意思決定において影響力を持つのは「信頼できる人からの推薦」です。
知人やビジネスパートナーを通じた紹介は、広告にはない高い信頼性を持ち、成約につながりやすいという特徴があります。
そのため、企業は偶然の紹介に頼るのではなく、既存顧客やビジネスパートナーとの関係性を戦略的に構築し、自然な紹介が生まれる仕組みを整えることが重要です。
◉-2、限定感のある体験やイベントの活用
富裕層は、単なる商品ではなく、「体験」を重視する傾向があります。
そのため、少人数制や完全招待制などの特別な体験を提供するイベントが効果的です。
たとえば、高級住宅の内覧会や高級車の限定試乗会、専門家を招いたプライベートセミナーなどがあります。
このようなイベントで、他では得られないような価値を提供することが信頼関係を構築するきっかけになります。
◉-3、富裕層向けに特化した広告配信
富裕層を対象とした広告では、マス媒体での大量露出よりも、ターゲットの価値観やライフスタイルに寄り添った媒体選びがポイントとなります。
たとえば、高級志向の雑誌や経済・金融専門誌、ハイクラス層が閲覧するビジネスニュースサイトなど、信頼性と情報感度の高いメディアを活用することで、ブランドイメージを損なわずに訴求できます。
また、オンラインで広告を配信する場合は、属性でターゲティングするよりも、広告のコンテンツや文脈で興味を惹く方法が有効です。
◉-4、富裕層ブランドとのコラボレーション施策
富裕層は、信頼しているブランドやパートナーとの関係性を重視します。
そこで、コラボレーション施策として、すでに富裕層顧客を抱えている他ブランドや専門家との連携を行うことが効果的です。
たとえば、高級ホテルや不動産会社、金融機関、教育機関など、既存の信用ネットワークに属する企業と協働して共同イベントや限定キャンペーンを実施すると、自社の信頼性向上につながります。
こうしたコラボレーション施策は、販促効果だけでなく、「この企業は信頼できる」という印象を強化する役割も果たします。
◉-5、企業出版による専門性アピール
富裕層を惹きつけるには「信頼」と「専門性」が欠かせません。
企業出版(ブックマーケティング)は、この2つの要素を同時に高められる効果的なブランディング手法といえます。
書籍という形で企業の理念やノウハウ、実績を体系的に伝えることで、広告では得られない「知的な共感」を生み出すことができます。
また、書籍は出版社や編集者などの第三者を介するため、情報の信頼性が高まり、企業のブランド価値を一段上のレベルに引き上げる効果があるのです。
さらに、富裕層にとって「本を出している企業」は、社会的信用のある存在として認識されやすく、接点の質を高める効果も期待できます。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
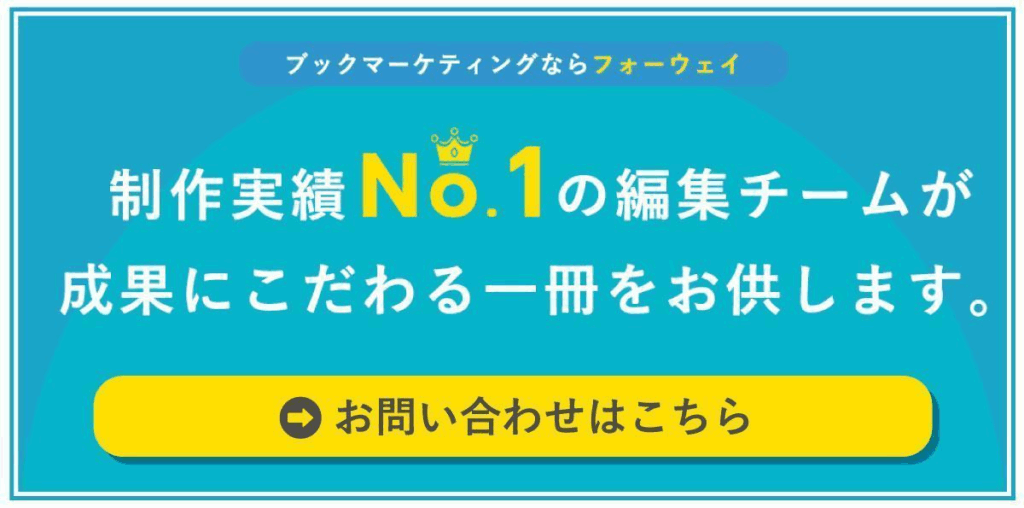
富裕層の集客を成功させるポイント

どんなに優れた商品やサービスであっても、「信頼」が得られなければ富裕層の集客にはつながりません。
ここでは、富裕層の集客を成功させるための4つのポイントを紹介します。
- 「信頼」を第一に導線を設計する
- 体験やブランドストーリーを提供する
- ブランドの世界観を一貫して伝える
- 時間をかけて関係を育てる意識を持つ
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、「信頼」を第一に導線を設計する
富裕層が重視するのは「信頼できる相手かどうか」です。
そのため、最初の接点から納品後のフォローに至るまで、あらゆるタッチポイントで信頼を積み上げる導線設計が重要です。
たとえば、専門性を示す実績や第三者による評価などを明確に提示し、透明性の高い説明を徹底する必要があります。
また、営業担当者の言葉遣いや姿勢、レスポンスの速さといった細部にまで配慮し、丁寧で誠実なコミュニケーションを徹底することが求められます。
過度なセールスよりも真摯な対応が、富裕層との長期的な信頼関係を築き、契約や紹介の拡大へとつながるでしょう。
◉-2、体験やブランドストーリーを提供する
富裕層はすでに生活に必要なモノをほとんど手にしているため、購買の動機は「機能」ではなく、「体験」や「共感」へと移っています。
そのため、「モノの性能や価格」よりも、「どのような体験が得られるのか」「そのブランドにどんな思想や物語が込められているのか」を訴求することが重要です。
たとえば、特別に設けられたプライベート空間でのテイスティング体験や、熟練の職人による製作工程を間近で見られるイベントなど、ブランドの美学や世界観を五感で体感できる機会は、富裕層の知的好奇心と感性を刺激します。
単なる販売促進ではなく、「このブランドの世界に共感したい」と思わせる体験が、富裕層の心を動かします。
◉-3、ブランドの世界観を一貫して伝える
富裕層は、ブランドの言葉や表現にブレがないかを見極めます。
Webサイトやパンフレット、SNS、イベント空間、営業担当者の言葉遣いに至るまで、すべての接点でトーンや価値観を統一することが信頼につながります。
つまり、一貫性が安心感を生み出し、その積み重ねがブランドへの信頼につながるのです。
また、装飾的な高級感よりも、余白の使い方や語彙の選び方、事実の提示方法など、細部の整合性が重要です。
短期的なキャンペーンで印象を操作するのではなく、長期的に一貫した世界観を築くことで、富裕層の記憶に残るブランドになります。
◉-4、時間をかけて関係を育てる意識を持つ
富裕層の集客では、短期的な「一度の購入」を狙うよりも「長く選ばれ続ける関係」を育てる姿勢が重要です。
高額な商品やサービスを扱う場合、購買までの検討期間が長く、紹介や口コミによる影響力も大きいため、短期的な成果を求めすぎると逆効果になることがあります。
定期的な情報提供やアフターフォローを通じて、継続的に接点を持ち続けることで、富裕層から「長く安心して付き合える企業」と認識されるようになります。
◉富裕層の集客には企業出版が効果的!

企業出版は、企業の理念や専門性を体系的に伝えることができることから、富裕層の集客に効果的です。
主な理由として、次の4つが挙げられます。
- 富裕層が求める信頼を出版で確立できる
- 企業の理念を明確に伝えられる
- 知的満足を与えて共感を生む
- 出版をきっかけに信頼関係が広がる
以下で、それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、富裕層が求める信頼を出版で確立できる
富裕層が重視するのは、「この企業は信頼できるか」という点です。
広告やSNSのように一過性の情報発信ではなく、企業出版は豊富な情報量を活かして、企業の専門性や理念、誠実な姿勢を体系的に伝えられます。
また、出版物は編集者や校正者といった第三者のチェックを経て完成するため、情報の正確性と客観性が担保されることもメリットです。
さらに、書籍というツール自体が信頼の象徴であるため、「本を出している企業」という事実が社会的な信用の裏づけとなります。
◉-2、企業の理念を明確に伝えられる
富裕層は商品やサービスの機能よりも、「企業の理念や価値観」に共感して購入の選択をします。
企業出版は、こうした企業の理念や背景、社会的使命を深く伝えることができる最適な手段です。
経営者の歩んできたストーリーや、企業が目指す未来像を一冊の本にまとめることで、企業の「軸」を読者に明確に伝えることができます。
◉-3、知的満足を与えて共感を生む
富裕層は知的好奇心が強く、新しい知識や視点に価値を感じる傾向があります。
企業出版では、業界の専門知識、独自のノウハウ、市場の分析などを体系的に伝えることができるため、「読む価値のある本」として知的満足を提供することが可能です。
また、内容が実践的かつ誠実であるほど、読者は「この企業はしっかり考えている」「社会的に意義のあることをしている」と感じ、企業に対する尊敬や共感を抱くようになります。
こうした知的共感は、富裕層との間に長期的な信頼関係を築くための重要な要素です。
◉-4、出版をきっかけに信頼関係が広がる
企業出版は、出版して終わりではなく始まりです。
書籍を通じて企業の理念や価値観に触れた読者が、セミナーやイベント、個別相談、共同プロジェクトなどへと関係を深めていくケースも少なくありません。
特に富裕層の場合は、「書籍を読んで感銘を受けた」「理念に共感した」といった動機で直接コンタクトを取ってくるケースがあり、そこから深い関係構築につながることもあります。
また、企業出版をきっかけとしてマスメディアやWebメディアからの取材機会が増え、結果として企業のブランド価値や社会的信用が大きく向上する事例も多く見られます。
▶︎企業出版(ブックマーケティング)については、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】も合わせて参考にしてください。

企業出版による富裕層集客の成功事例

ここでは、実際に企業出版を活用して富裕層の信頼を獲得し、事業成長につなげた3つの成功事例を紹介します。
- 医師を対象にした不動産投資ビジネスの出版事例
- アンティークコイン投資ビジネスの出版事例
- 生前の不動産対策に関する出版事例
3つの事例について詳しく見ていきましょう。
◉-1、医師を対象にした不動産投資ビジネスの出版事例
不動産会社の経営者は、高所得かつ納税額の高い医師に向けて、節税対策としての不動産投資を紹介する書籍を出版しました。
もともと紹介経由での新規顧客が中心で、関係構築に時間がかかる課題を抱えていましたが、書籍出版によって「医師専門の投資コンサルタント」という立ち位置を確立しました。
出版後は、Yahoo!ディスプレイ広告など従来の施策では得られなかった反響を次々と獲得。
発売1ヶ月で書籍読者からの問い合わせが複数寄せられ、医師との面談後に即決で10戸購入が成立し、出版費用をすぐに回収する成果を上げました。
また、大手病院勤務医からの問い合わせも増加し、発売から6ヶ月で読者反響から総額10億円の売上向上を達成。
会社の売上は前年比で2倍以上に成長しました。
書籍が「集客ツール」としてだけでなく、商談をスムーズに進めるクロージングツールとしての役割も果たしています。
◉-2、アンティークコイン投資ビジネスの出版事例
とある会社では、「アンティークコイン投資」をテーマに書籍を出版しました。
カバー装丁には、富裕層を意識してラグジュアリー感をもたせ、書籍の中では希少性や歴史的価値といった文化的観点からコイン投資の魅力を紹介しました。
その結果、出版直後から100名以上が無料資料をダウンロードし、数千万円規模の売上を記録。
また、出版記念セミナーでは3名の成約を獲得し、1件あたり数百万円の売上を達成しています。
さらに、書籍を読んだ医師からの問い合わせをきっかけに、面会からわずか3日で数億円規模の成約に至るなどの成果を上げました。
◉-3、生前の不動産対策に関する出版事例
ある不動産会社は、相続や事業承継を考えている富裕層に向けて、「生前の資産対策」の重要性を啓発する書籍を出版しました。
書籍の内容として、専門家の立場から法的・税務的アドバイスを分かりやすくまとめ、実際の事例を通じて読者の理解を深める構成にしました。
その結果、「単に物件を売る会社」ではなく「資産管理・承継を支援するパートナー」というブランドイメージを確立。
出版後は、書籍を読んで来社した顧客の理解度が高く、商談スピードが向上。
また、書籍連動セミナーでは400名を集客、60組以上が個別相談に参加し、その場で顧客化につながるケースが続出しました。
企業出版によって、自社の理念と専門性が伝わり、長期的な契約へ発展するケースも増えています。
◉【まとめ】富裕層の集客なら信頼を築ける企業出版がおすすめ!
この記事では、富裕層の集客に有効な手法や成功させるポイント、企業出版によって集客に成功した事例などについて紹介しました。
富裕層の集客では、一般的な広告やキャンペーンでは届かない「信頼」と「共感」をいかに築くかがポイントです。
この点で、企業出版は効果的な手法といえます。
書籍という媒体は、企業の思想や専門性を体系的に伝えるだけでなく、第三者の手を介することにより情報の信頼性が高まっているからです。
フォーウェイでは、書籍をマーケティングに活用する「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
富裕層の集客手段として活用されている事例も多く、書籍の出版からマーケティング全般までトータルでサポートさせていただきます。
富裕層の集客をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。


企業が持続的に成長していくためには、商品やサービスの魅力を外部に発信する「アウターブランディング」だけでなく、社員一人ひとりの意識をそろえ、企業理念や価値観を浸透させる「インナーブランディング」も重要です。
実際、社員が自社に誇りを持ち、ブランド価値を理解して行動できるようになると、組織の一体感が高まり、顧客へのサービス品質向上や採用力の強化といった効果も期待できます。
しかし、「具体的にどのように進めればよいのか」「どんな施策が効果的なのか」と悩む企業担当者も少なくありません。
そこでこの記事では、インナーブランディングの基本や実際の施策、導入のステップなどを解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
インナーブランディングとは?基本定義と目的

インナーブランディングとは、自社の理念やビジョン、ブランドの価値を社員に浸透させ、日々の業務や意思決定に反映させる取り組みです。
ここでは、次の2点について解説します。
・インナーブランディングの目的
・アウターブランディングとの違い |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、インナーブランディングの目的
インナーブランディングの主な目的は、社員が企業の方向性を理解し、自らの役割に誇りを持って働けるようにすることです。
また、経営理念やビジョン、価値観と現場の行動を一致させて、組織全体を同じ方向に進めることが狙いです。
社員が自社のブランドに誇りを持って働くことで、顧客対応においても自然にその価値観が表れて業績向上にもつながります。
◉-2、アウターブランディングとの違い
アウターブランディングが市場や顧客といった社外に向けた取り組みであるのに対し、インナーブランディングは社員に対してブランドを浸透させる活動を指します。
この2つは相反するものではなく、むしろ補完関係にあります。
社内での浸透が不十分なまま外部に発信しても、メッセージが形だけのものになりやすく、期待した効果は得られません。
一方で、社内に根付いた理念と社外への発信内容が一致することで、一貫したブランドイメージを築けます。
◉インナーブランディングが企業経営に与える4つの効果

インナーブランディングに取り組むことで、企業経営に以下のような効果があります。
・組織文化の強化につながる
・人材の定着と採用力が高くなる
・経営戦略を実行しやすくなる
・業績や成果の向上につながる |
4つの効果を見ていきましょう。
◉-1、組織文化の強化につながる
社員が共通の価値観や理念を理解し、行動に反映することで、企業独自の文化が強固になります。
組織文化が明確になると意思決定が速くなり、社内の一体感が高まるのです。
インナーブランディングを通じて組織文化や価値観を共有することが、企業の持続的成長につながります。
◉-2、人材の定着と採用力が高くなる
自社ブランドに誇りを持てる職場環境を整えることは、社員のモチベーションやエンゲージメントを高め、離職率の低下につながります。
「自分の仕事がその一部を担っている」と実感できれば、会社への帰属意識が高まるからです。
また、インナーブランディングが確立されている企業は、外部からも魅力的に映ります。
応募者は企業の理念に共感して入社を希望するため、採用活動においてもミスマッチが減り、優秀な人材を確保しやすくなります。
◉-3、経営戦略を実行しやすくなる
企業の経営方針や戦略を社員が理解し共感していると、現場の行動と経営の意図が一致しやすくなります。
その結果、経営戦略の実行スピードや精度が向上します。
◉-4、業績や成果の向上につながる
インナーブランディングを通じて、ブランドの理念が社内にしっかりと浸透すれば、顧客対応や業務に一貫性が生まれ、業績や成果の向上につながります。
こうした一貫性は顧客満足度を向上させ、リピーターの増加や新規顧客の獲得も期待できます。
結果として、売上や利益が向上し、企業価値が継続的に高まるという好循環を生み出せるでしょう。
◉【5ステップ】インナーブランディングの進め方
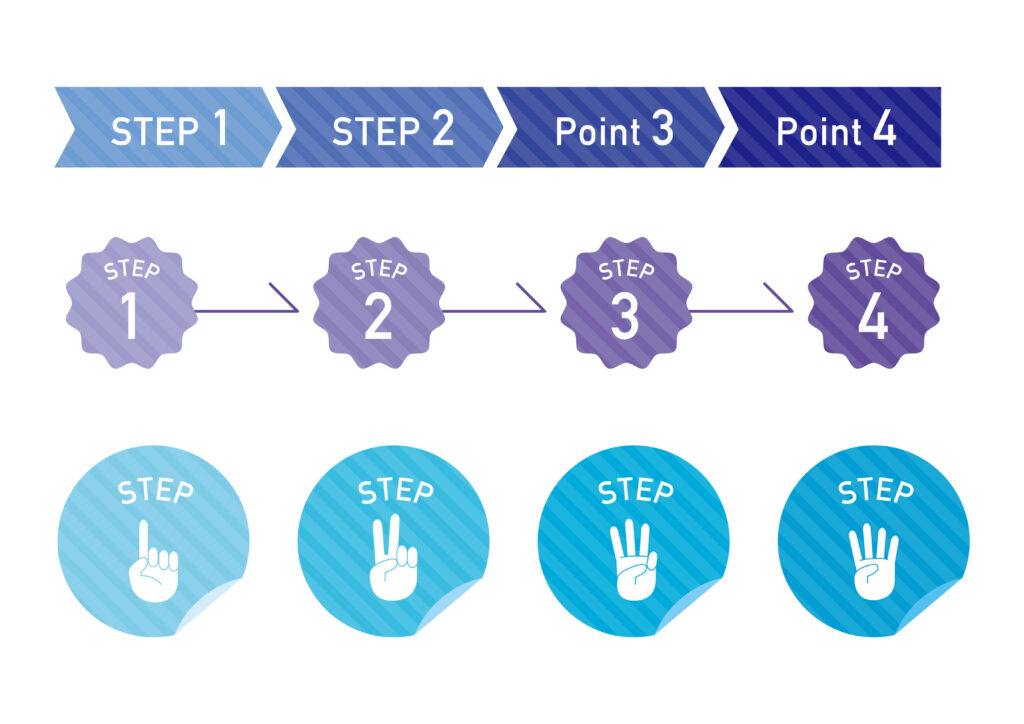
一般的に、インナーブランディングは次の5ステップで進めます。
・ステップ1.現状を把握して課題を整理する
・ステップ2.ビジョンとブランドの方向性を明確にする
・ステップ3.浸透させるための施策を設計する
・ステップ4.実行しながら社員の参加を促す
・ステップ5.成果を測定し改善につなげる |
順番に見ていきましょう。
◉-1、ステップ1.現状を把握して課題を整理する
まずは、自社の現状を客観的に見つめ直すことから始めます。
社員の満足度調査やインタビューを通じて、「会社の理念やビジョンを社員がどの程度理解し共感しているか」を把握します。
また、企業文化や組織風土における課題、部署間の連携状況、日々の業務における理念の浸透度合いなどの詳細な分析も必要です。
この段階で課題を明確にすることで、次に取るべき施策の方向性が定まってくるのです。
◉-2、ステップ2.ビジョンとブランドの方向性を明確にする
現状の課題が整理できたら、企業の目指すべき未来像、つまりビジョンとブランドの核となる価値観を改めて言語化します。
このとき、経営層だけでなく社員を巻き込んで議論する機会を設けることが重要で、より納得感のあるビジョンやブランドの価値観を創り上げることができます。
これらは抽象的なものではなく、「顧客にどのような価値を提供するのか」「社会に対してどのような存在でありたいのか」といった具体的な言葉で表現することが重要です。
◉-3、ステップ3.浸透させるための施策を設計する
次に、明確になったビジョンや価値観を社員に浸透させるための具体的な施策を設計します。
たとえば、経営理念を解説した書籍の制作、理念を体現する社員の表彰制度の導入、双方向のコミュニケーションを促す社内ツールの活用などがあります。
単発的なイベントではなく、日常の業務や評価制度に組み込むなど、継続的な効果が期待できる仕組みを考えることが成功のポイントです。
◉-4、ステップ4.実行しながら社員の参加を促す
ここでは、設計した施策を実際に実行に移します。
このとき、一方的な情報発信に終始するのではなく、社員が能動的に参加できる機会を増やすことが大切です。
たとえば、理念について語り合うワークショップの開催、社員が自社のブランドについてSNSで発信するキャンペーンなど、さまざまな社員を巻き込む企画を実行しましょう。
現場の小さな成功事例を共有することで、社員全員のモチベーションも高まり、自律的な行動が促されます。
◉-5、ステップ5.成果を測定し改善につなげる
施策の実行後は、その効果を定期的に測定して改善につなげます。
改めて社員満足度調査やエンゲージメント調査を行うと、理念の浸透度や社員の意識の変化を数値で把握することが可能です。
また、社員からのフィードバックを積極的に集め、「施策が期待通りの効果を生んでいるか」「改善すべき点はないか」を確認します。
このPDCAサイクルを回し続けることで、インナーブランディングの効果はより高まって行くのです。
◉インナーブランディングの具体的な施策
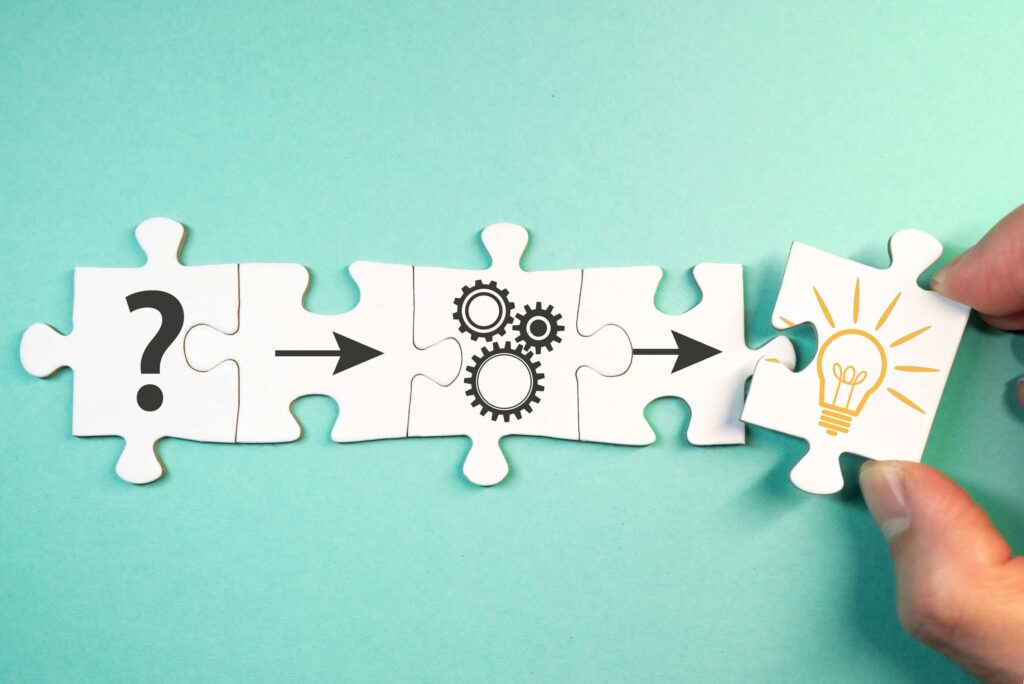
ここでは、インナーブランディングを成功させるための具体的な施策を5つ紹介します。
・研修やワークショップ
・書籍出版
・表彰制度
・1on1ミーティング
・社内ツールでの共有 |
それぞれ詳しく解説します。
◉-1、研修やワークショップ
研修やワークショップは、インナーブランディングの核となる施策です。
重要なのは、一方的に知識を伝える場にするのではなく、社員自身が企業理念を考え、意見を交わし合える「参加型の場」をつくることです。
たとえば、部門を越えてチームを編成し、「自社の理念を実現するためにできる改善案」を議論するワークショップを実施すれば、理念の理解が深まるだけでなく、部署間の連携強化や新たなアイデアの創出にもつながります。
このような体験型の学びは、社員同士の相互理解や信頼関係を深め、チーム全体の一体感を高める効果があります。
◉-2、書籍出版
書籍出版もインナーブランディングに有効な手段です。
企業の歴史や成功事例、商品開発の裏話、そして経営者の思いを本という形で残すことで、社員はいつでも立ち返って創業理念やビジョンを再認識できます。
書籍は、単なる情報共有を超えて社員が自社のブランドに誇りを持つきっかけとなるのです。
書籍を新入社員へ配布することで、会社の価値観をスムーズに伝えるツールにもなります。
また、社外への情報発信にも効果的で、インナーブランディングとアウターブランディングをつなぐ役割を果たします。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

◉-3、表彰制度
表彰制度や社内イベントは、企業理念を具体的な行動として示し、それを称賛することで組織の規範を明確にする役割があります。
企業理念に沿った行動をした社員を表彰する仕組みを導入することで、他の社員も「どのような行動が評価されるのか」を理解しやすくなり、行動指針が社内に浸透しやすくなります。
また、普段関わることの少ない他部署のメンバーと交流する社内イベントによって、組織全体の結束力が高まるでしょう。
◉-4、1on1ミーティング
上司と部下が定期的に向き合う1on1ミーティングも、インナーブランディングを推進するうえで重要な場です。
対話を通じて、個人の目標が企業のビジョンとどのように結びついているかを確認し、キャリアプランを話し合うことで、社員は自分の仕事が組織全体に与える影響を実感できます。
◉-5、社内ツールでの共有
社内ツール(掲示板、イントラネット、アプリなど)を活用した情報共有は、インナーブランディングを日常の中に根付かせる有効な方法です。
経営層からのメッセージ、企業理念を体現した社員のエピソード、各部署の取り組み事例などを発信することで、社員は常に企業ビジョンに触れ、自分の行動を理念と結びつけて考えやすくなります。
理念が一部の社員だけでなく、組織全体に浸透します。
◉書籍出版がインナーブランディングにおすすめな理由

インナーブランディングの施策として書籍出版がおすすめな理由として、次の4つが挙げられます。
・企業理念が浸透しやすくなる
・社員のモチベーションを上げられる
・採用活動に活用できる
・長期的に残る「資産」となる |
具体的な理由を見ていきましょう。
◉-1、企業理念が浸透しやすくなる
書籍として会社の理念や歴史、未来へのビジョンをまとめることで、抽象的になりがちなメッセージを具体的で分かりやすい形にできます。
社員はいつでも手にとって読み返すことができ、経営者の想いを深く理解する機会が得られるのです。
理念を物語として語ることで、単なるスローガンではなく、共感できる価値観として社員の心に根付きます。
◉-2、社員のモチベーションを上げられる
自社が社会に向けて書籍を出版することは、社員にとって誇りとなります。
自分たちの会社が特定の分野で専門性や権威性を認められることは、働く社員にとって大きな自信につながるからです。
また、書籍に社員の成功事例やインタビューを掲載すれば、社員は自分の仕事が会社のビジョンに直結していることを実感でき、モチベーションをさらに高められます。
さらに、会社の近隣の書店に自社の書籍が並ぶことで、「自分の働いている会社の本が書店に置かれている」という実感を得られ、社員の誇りややる気が一層高まることもあるでしょう。
加えて、新人社員にとっても、入社前に会社の文化や価値観を理解するための指針になり、早い段階で組織への共感や帰属意識を育むきっかけになります。
◉-3、採用活動に活用できる
書籍は、企業の魅力を伝える採用ツールとしても優れています。
ウェブサイトやパンフレットでは伝わりにくい企業の理念・価値観・文化を体系的に示すことができ、求職者により深い理解を与えられるからです。
書籍を通して企業の「ありのままの姿」を伝えることで、価値観に共感した質の高い人材の獲得につながります。
さらに、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
◉-4、長期的に残る「資産」となる
デジタルコンテンツが消費されていく現代において、書籍は物理的な形として残り、世代を超えて受け継がれる「資産」となります。
一時的なキャンペーンでは得られない、持続的なインナーブランディング効果を生み出します。
また、社史や理念をまとめた書籍は周年記念や外部PRの場でも活用でき、長期的に価値が高いです。
◉書籍出版×インナーブランディングの成功事例

ここでは、書籍出版によってインナーブランディングに成功した事例を3つ紹介します。
・出版で確度の高い顧客だけでなく、モチベーションの高い社員の採用にも成功した事例
・出版が社員のモチベーションを高めた事例
・出版がインナーブランディングと採用成功を後押しした事例 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、出版で確度の高い顧客だけでなく、モチベーションの高い社員の採用にも成功した事例
不動産投資会社の経営者は、自社の理念や事業への姿勢をまとめた書籍を出版しました。
経営者が書籍を通じて「顧客の長期的利益を第一に考える姿勢」を広く発信したことで、確度の高い顧客からの信頼を得ることに成功。
出版の効果はこれにとどまらず、理念に共感した読者が自ら入社を志望してくるという成果が生まれました。
結果として、顧客の信頼獲得と採用活動の成功につながっています。
◉-2、出版が社員のモチベーションを高めた事例
大手システムインテグレータは、最新の技術や社会の未来像をテーマにした書籍を出版しました。
自社の専門性や将来ビジョンが書籍として世に出ることで、社員一人ひとりが「自分たちは先端領域で社会に貢献している」という誇りを持つようになりました。
外部への情報発信が社内にも良い影響を与え、社員が主体的に学び成長しようとする姿勢が高まり、組織全体のモチベーション向上につながりました。
◉-3、出版がインナーブランディングと採用成功を後押しした事例
法人向けの保険代理店の経営者は、保険業界の現状と問題点を解説し、これからの保険代理店経営に必要な考え方をまとめた書籍を出版しました。
保険業界では「成果報酬型」の給与が当たりまえですが、その結果少数のスーパー営業マンに頼る構図になっていました。
そこで、書籍の中で「一律報酬型」によって社員全員が育つ仕組みを提案。
書籍で理念や方針を明確化したことで、社外からの信頼が高まると同時に、社員の意識も変化しました。
結果として、出版をきっかけに社員のモチベーションが向上し、人材の定着率が改善しています。
さらに、書籍を読んで応募した新しい人材の採用にもつながり、インナーブランディングと採用成功を同時に実現した好事例となりました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉【まとめ】書籍出版を活用してインナーブランディングを強化しよう
この記事では、企業の経営者や経営幹部に向けて、インナーブランディングの基本や実際の施策、導入のステップなどを解説しました。
インナーブランディングは、自社の理念やビジョン、ブランドの価値を社員に浸透させ、日々の業務や意思決定を効率化し、業績向上につなげる取り組みです。
さまざまな手法がありますが、なかでも書籍出版はインナーブランディングとアウターブランディングの両面に効果を発揮する施策として注目されています。
フォーウェイでは、書籍出版をマーケティングやブランディングに活用する「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
自社の理念やビジョンを一冊にまとめ、社内外に発信することで、ブランド価値を高めてみませんか。


経営者向けの広告は、一般的な営業手法や従来型の広告展開とは異なる特徴があります。
その理由として、経営者は多忙であり、限られた時間の中で効率的に情報収集を行い、会社の将来を左右する意思決定を下しているからです。
もし広告が経営者に響けば、短期間で導入や商談につながる可能性が高まるでしょう。
一方で、経営者向け広告は単なる露出だけでは効果を発揮しにくく、ターゲットに適した媒体や手法を選ぶことが欠かせません。
さらに、広告だけでは信頼関係を築いたり、潜在的なニーズを探り出したりするのは難しいため、広告以外の取り組みも合わせて行うことが重要です。
この記事では、広告戦略を検討している企業経営者や事業責任者の方に向けて、経営者向け広告の特徴や代表的な手法、広告以外の有効なアプローチ方法などについて詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
経営者向けに特化した広告出稿は効果的!

経営者は最終的な意思決定権を持ち、企業の方向性を左右する重要な立場にあります。
そのため、経営者に特化した広告には、次のような効果が期待できるのです。
・意思決定者に直接リーチできる
・非効率な営業活動をなくせる |
以下で、それぞれの効果について詳しく解説します。
◉-1、意思決定者に直接リーチできる
経営者は、商品やサービスの最終的な導入可否を決定します。
従来の広告手法では、まず担当者にアプローチし、そこから社内稟議を経て、ようやく経営者の決裁にたどり着くという長いプロセスを踏むのが一般的です。
その過程で、経営者に情報が届く前に却下されてしまうリスクも少なくありません。
もし経営者に直接リーチできれば、導入までのスピードを大きく短縮できることになります。
◉-2、非効率な営業活動をなくせる
多くの経営者は多忙なため、知らない電話や飛び込み営業に対応することはほとんどないでしょう。
そのため、従来の営業スタイルでは門前払いになりやすく、労力に見合う成果が得られにくいのです。
そこで有効なのが経営者向けに特化した広告の活用です。
経営者が自ら課題解決のための情報収集を行うタイミングで広告を提示できれば、関心を持ってもらえる確率が高まります。
結果として、無駄な営業活動を減らし、効率的に質の高いリードを獲得することが可能になります。
営業担当者は商談や提案に集中できるようになるので、より早く成果を出すことにつながるのです。
経営者向け広告は大きく分けて2種類

経営者に向けた広告は、次の2種類に分けることができます。
・オフライン広告|経営者が接触する媒体や場所に出稿する
・デジタル広告|特定の属性を持つ経営者に絞り込んでアプローチする |
以下では、それぞれの広告の具体的な方法について解説します。
◉-1、オフライン広告|経営者が接触する媒体や場所に出稿する
オフライン広告は、経営者が直接接触する機会の多い場所やシーンを狙って出稿することが重要です。
次のような場所や媒体に広告を出稿することで、効果的に認知を高めることができます。
・タクシー広告
・新幹線・飛行機内の広告
・空港ラウンジ・ゴルフ場での広告
・ビジネス誌・業界専門誌への広告掲載 |
4つの広告を見ていきましょう。
◉-1-1、タクシー広告
経営者は取引先への訪問や会合への移動などでタクシーを利用する頻度が高く、広告展開において有効な接点となります。
特に、車内モニターの動画広告や後部座席に貼られるステッカー広告は、移動中に自然と視界に入るため、訴求力が高いです。
◉-1-2、新幹線・飛行機内の広告
長距離移動の際に利用することが多い新幹線や飛行機も、経営者と接触できる場です。
座席前の情報誌や機内映像に広告を掲載すれば、移動中に自然と目に留まり、無理なくブランドを印象づけることが可能です。
◉-1-3、空港ラウンジ・ゴルフ場での広告
空港ラウンジやゴルフ場も、経営者が多く集まる場所です。
リラックスした状態で広告に触れることで、心理的な受け入れやすさも高まり、ポジティブなブランドイメージが形成されやすくなります。
◉-1-4、ビジネス誌・業界専門誌への広告掲載
情報収集に熱心な経営者は、ビジネス誌や業界専門誌を購読していることが多いため、これらの媒体への広告掲載は効果的です。
信頼性の高い媒体に掲載されることで、広告自体も価値ある情報として受け取られやすくなります。
◉-2、デジタル広告|特定の属性を持つ経営者に絞り込んでアプローチする
デジタル広告の場合も、経営者が持つ属性をターゲットとしてアプローチすることが有効です。
主なデジタル媒体としては、次のようなものがあります。
・SNS広告
・動画広告
・リスティング広告・ディスプレイ広告
・メール広告・DM |
それぞれ解説します。
◉-2-1、SNS広告
FacebookやInstagram、X(旧Twitter)やLinkedInなど、ビジネス層が積極的に利用するSNSは、経営者をターゲティングしやすい媒体です。
特にFacebookやInstagramは利用者数が多く、興味・関心や行動履歴に基づいたターゲティング精度が高いため、幅広い業界の経営者やビジネス層に効率的に広告を届けられます。
また、X(旧Twitter)は、情報の拡散性とリアルタイム性に優れており、経営者が業界動向や最新情報を収集する場として活用されるため、タイムリーな広告展開に適しています。
さらに、世界最大級のビジネスSNSのLinkedInは役職・業種・企業規模などで精緻なセグメント配信が可能で、意思決定者に直接リーチできることが特徴です。
経営者は情報収集や人脈形成の目的でSNSをチェックするため、自然な形で広告が目に留まりやすい環境が整っています。
◉-2-2、動画広告
短時間で強い印象を与えられる動画は、企業の経営理念やサービス価値を端的に伝える手段として効果的です。
テキスト広告や静止画広告に比べ、視覚と聴覚の両方に訴求できるため、記憶に残りやすいのが特徴です。
YouTubeのインストリーム広告や、ダイヤモンド・オンライン、日経ビジネス電子版などのビジネス系メディアでの動画枠を活用すれば、経営者がビジネス情報を収集しているタイミングで自然に接触できます。
◉-2-3、リスティング広告・ディスプレイ広告
経営者は課題解決のために、自ら検索エンジンで情報を調べるケースが少なくありません。
たとえば、「業務効率化」「資金調達」「M&A」「人材採用」など、経営者が検索しやすいキーワードに合わせて広告を出稿することで、ニーズが顕在化している層に的確にアプローチできます。
また、ディスプレイ広告を組み合わせれば、経営者が閲覧するビジネスメディアやニュースサイトで再度接触を図れるため、認知から検討、導入までをスムーズに促進することが可能です。
◉-2-4、メール広告・DM
ターゲットリストを活用したメールマーケティングやダイレクトメールは、経営者に直接広告を届けられる手段です。
特に経営層は日常的に多くのメールや郵送物に目を通すため、適切に設計されたメッセージであれば接触できる可能性が高いのです。
また、セグメントを絞り込み、関心度の高い層にピンポイントで届ければ、効率的に商談機会を創出できます。
経営者向け広告だけでは不十分!ほかのアプローチ方法も必要な理由

経営者に特化した広告は、認知や関心を高めるうえで大きな効果を持っています。
しかし、それだけに依存してしまうと成果が限定的になってしまいかねません。
主な理由として、次の3つが挙げられます。
・広告だけでは深い信頼関係を築けないから
・潜在的なニーズを掘り起こせないから
・他社との差別化が難しいから |
以下で、それぞれどのような理由なのかを見ていきましょう。
◉-1、広告だけでは深い信頼関係を築けないから
広告は「認知」や「関心」を広げるには効果的ですが、どうしても一方的な情報発信になりがちです。
経営者は商品やサービスの導入を判断する際に、企業の規模や実績だけでなく、経営理念やビジョン、担当者の人柄なども重視します。
広告だけではこれらを十分に伝えられず、「信頼」や「共感」といった深い関係性を築くのは難しいのが実情です。
また、広告で届けられる情報量が限定的であることも関係性の構築に不十分な要因です。
そのため、広告を通じて興味を持ってもらった後に、最終的な商談や契約につなげるためには、広告以外の方法で信頼を積み重ねることが欠かせません。
◉-2、潜在的なニーズを掘り起こせないから
広告は、すでに課題を明確に認識している経営者には効果的です。
たとえば、「業務効率化」というキーワードで検索している経営者には、解決策となるサービスを提示することができます。
しかし、多くの経営者は自社の課題を明確に言語化できていなかったり、潜在的な問題に気づいていなかったりします。
このような潜在ニーズを掘り起こすには、広告だけでは不十分です。
そこで、セミナーやウェビナー、専門的な質の高いコンテンツを通じて「気づき」を提供することが、初めて見込み客として認識してもらえるきっかけになります。
◉-3、他社との差別化が難しいから
特定の広告媒体は多くの企業が利用するため、競合他社の広告と並んで表示されることも少なくありません。
似たような広告が並ぶ中で、自社の強みや差別化ポイントを明確に伝えることはなかなか困難です。
そこで有効なのが、広告以外のアプローチ方法です。
たとえば、書籍出版やイベント登壇、専門性の高いオウンドメディアなどは、自社のユニークな価値や専門性を深く伝えることができ、競合との差別化につながります。
広告だけに頼らず、他のアプローチを組み合わせることで、経営者の記憶に残る存在になることができます。
経営者に届く!広告以外のアプローチ方法

広告は経営者に認知や関心を持ってもらう有効な手段ですが、信頼関係を築いたり、経営者自身がまだ自覚していない潜在的なニーズを掘り起こしたりするには限界があります。
そこで重要になるのが、広告以外の直接的かつ継続的なアプローチです。
ここでは、経営者に届く代表的な方法として、次の4つを紹介します。
・セミナー・ウェビナーの開催
・コンテンツマーケティングの活用
・業界のイベント・交流会への参加
・書籍出版(ブックマーケティング) |
それぞれどのような方法なのかを具体的に見ていきましょう。
◉-1、セミナー・ウェビナーの開催
経営者が関心を持ちやすいのは、自社の「経営課題の解決」や「業界の最新トレンド」に関する情報です。
セミナーやウェビナーを開催して、単なる商品説明ではなく専門的な知見や将来の展望を提示することで、信頼性と権威性を築くことにつながります。
また、リアルタイムで質疑応答できる点も経営者にとっては魅力的で、リード獲得や商談のきっかけになります。
◉-2、コンテンツマーケティングの活用
経営者は多忙な中でも「意思決定の参考になる情報」を求めています。
そのニーズに応える手段として、ホワイトペーパーや専門記事、動画などを活用したコンテンツマーケティングがあります。
特に、業界動向の解説や他社の成功事例、専門家によるインタビューなどは実務に直結する情報として価値が高く、経営者の興味を引きやすい内容です。
自社の商品やサービスを直接売り込むのではなく、価値ある情報を提供することで「信頼できる情報源」として認識されることがポイントとなります。
▶︎コンテンツマーケティングのやり方については、関連記事【コンテンツマーケティングとは?期待できる効果や具体的な手法、戦略の練り方まで解説!】もあわせて参考にしてください。
◉-3、業界のイベント・交流会への参加
経営者が集まる展示会や交流会、カンファレンスは、人脈形成や信頼関係を築く場です。
名刺交換や短時間の対話でも、リアルな接触は記憶に残りやすく、後日の商談につながるきっかけとなります。
広告にはない「対面の力」を活かすことで、より強固な関係が築けます。
◉-4、書籍出版(ブックマーケティング)
経営者に強い影響を与える手段として、書籍出版も効果的です。
書籍は深い専門性や実績を体系的に伝えられる媒体であり、広告よりも高い信頼性を持っています。
さらに、出版をきっかけにメディア露出や講演依頼が増えるケースも多く、経営者との接点を増やす効果があります。
特に専門性の高いテーマや経営課題に直結するテーマを扱えば、ターゲット層に深くアピールすることが可能です。
また、先に説明した「セミナー・ウェビナー」や「コンテンツマーケティング」「イベント・交流会」でも、書籍というアイテムを取り入れることによって、さらに効果を上げることができます。
たとえば、セミナーやウェビナーでは、書籍購入者に特典をつけたり、書籍のプレゼントによって集客を図ることができます。
コンテンツマーケティングでは、自社に著作権のある書籍の内容を引用するなどの横展開が可能です。
イベントや交流会では、書籍を持参して自己紹介のネタにしたり、書籍を出版していることで権威性を示したり、名刺代わりに書籍を配布して商談につなげたりと、幅広く活用できます。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

書籍出版で経営者にアプローチした事例

ここでは、実際に書籍出版を通じて経営者にアプローチした事例を3つ紹介します。
・出版で問い合わせの質が向上、受注単価2倍を実現した経営コンサルタント
・出版をきっかけに大型案件・人材・講演依頼が次々と舞い込んだ保険代理店
・出版1か月で即重版!ニュース掲載や新規顧客を獲得した建設業コンサルタント |
3つの事例を見ていきましょう。
◉-1、出版で問い合わせの質が向上、受注単価2倍を実現した経営コンサルタント
ある経営コンサルタントは、中小企業の経営者をターゲットに、自社の専門知識や実績を体系的にまとめた書籍を出版しました。
その結果、経営者層からの問い合わせが急増し、従来とは質の異なる顧客層を獲得できるようになりました。
特に、専門性と信頼性を評価して依頼してくれる経営者が増加し、結果として受注単価は出版前の2倍以上に向上。
相談件数も3〜4倍に拡大し、無料相談やコンサルティング指導も「1か月待ち」の状態となったと言います。
書籍出版によって「専門家としてのブランド」が定着し、同業他社との差別化、優秀な人材の獲得にもつながりました。
◉-2、出版をきっかけに大型案件・人材・講演依頼が次々と舞い込んだ保険代理店
ある法人保険代理店は、自社の経営ノウハウや人材育成の考え方をまとめた書籍を出版しました。
出版直後から経営者層や同業の保険代理店からの問い合わせが急増し、これまでアプローチできなかった層からの経営相談が数多く舞い込むようになりました。
特に、大型の法人契約が次々と決まるなど、直接的な売上アップに直結。
さらに、保険会社からの講演依頼や同業支援の依頼も増え、「保険会社にとって頼れる代理店」という強いブランドイメージが確立されました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-3、出版1か月で即重版!ニュース掲載や新規顧客を獲得した建設業コンサルタント
ある建設業専門のコンサルタントは、自身の最新ノウハウと豊富な実績をまとめた書籍を出版しました。
新聞広告の掲載をきっかけにAmazonや書店では売り切れが続出。
出版からわずか1か月で重版が決定し、累計発行部数は5,000部を突破しました。
さらに過去の著作との相乗効果も生まれ、シリーズ累計では6万部を超える大ヒットとなりました。
書籍は、livedoor NEWSやLINEニュースなど17媒体に取り上げられるなどメディア露出も拡大。
反響の大きさから、ターゲット層である大手建設会社からも「この本はどこで購入できますか?」と出版社に問い合わせが入るほどでした。
広告では得にくい信頼性と話題性を獲得し、ブランド価値を一気に高めることに成功しました。
【まとめ】広告よりも効果的!書籍出版で経営者にアプローチしよう
この記事では、経営者向け広告の特徴や代表的な手法、広告以外の有効なアプローチ方法、書籍出版の事例などについて解説しました。
経営者に向けた広告は、意思決定者に直接リーチできる点で大きなメリットがあります。
しかし、広告だけでは信頼関係を築いたり、潜在的ニーズを掘り起こすことには限界があります。
そこで有効なのが、広告以上に信頼性が高く、専門性や実績を体系的に伝えることができる書籍出版です。
フォーウェイでは、書籍をマーケティングに活用する「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
企業のブランディングにも直結する手法なので、経営者への新たなアプローチを検討している方は、ぜひフォーウェイまでお問い合わせください。


富裕層や高所得者向けに自社の商品やサービスをアピールしたい場合、適切な広告手法を選ぶことが重要です。
保有資産や年収、居住エリアなどの条件を絞れる広告手法なら、狙いたいターゲットにリーチできます。
しかし、「どんな広告手法が効果的なのだろう」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
富裕層は価格よりも価値や信頼性を重視し、日常的に多くの広告に触れているため、一般消費者向けの広告戦略がそのまま通用するとは限りません。
そこで本記事では、富裕層・高所得者向けの広告の種類や戦略のポイントなどについて解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
富裕層・高所得者向け広告とは

富裕層・高所得者向け広告とは、年収や資産規模が高い顧客層に特化して設計された広告手法です。
年収数千万円以上や、資産数億円といった高い経済力を持つ顧客層をターゲットとする業界で、富裕層・高所得者向けの広告が活用されます。
たとえば、高額商品やプレミアムサービス、高級不動産などを販売する際は、富裕層・高所得者向け広告が有効です。
また、投資商材やラグジュアリー体験などを訴求するケースでも活用できます。
◉-1、一般消費者向け広告との違い
一般消費者は、価格や機能、コストパフォーマンスといった実利的な価値を重視する傾向があります。
一方で、富裕層が重視する要素は、ブランドの信頼性や希少性、社会的評価などです。
そのため、一般消費者向け広告と富裕層向け広告では、効果的な表現や訴求軸、使用する媒体などが異なります。
富裕層・高所得層向け広告の種類

富裕層・高所得者層向け広告には、以下のような種類があります。
・運用型広告
・Webメディア広告
・情報誌広告
・タクシー広告
・サイネージ広告 |
それぞれ特徴が異なるため、商材の種類やターゲットに応じて最適な手法を選ぶことが重要です。
ここでは、各広告の特徴について解説します。
◉-1、運用型広告
運用型広告とは、広告主が配信先やターゲット、広告文などを自社で細かく設定して運用できる広告です。
検索エンジンの結果画面やSNS、Webサイト、ブログなどの広告枠に自社の広告を配信できます。
運用型広告は一般消費者向けにも活用されますが、富裕層向けでも利用することが可能です。
主な運用型広告のサービスとして、以下のようなものが挙げられます。
・Google広告
・Yahoo!広告
・Meta広告
・Microsoft広告
・LINE広告 |
これらを富裕層・高所得者向け広告として活用する際は、幅広く配信するのではなく、ターゲットの年収や職業、居住エリア、興味関心などを絞り込むことが重要です。
◉-2、Webメディア広告
Webメディア広告とは、オンラインで閲覧できるWebサイトやアプリに掲載される広告です。
富裕層が情報収集に利用する専門メディアや業界メディアに広告を出稿することで、信頼感を得られます。
経済・投資系、ラグジュアリーライフスタイル系のWebメディアは、読者層が明確なため、ブランドの格を損なわずに情報を届けることが可能です。
具体的なWebメディアとして、「Forbes Japan」や「ZUU ONLINE」などが挙げられます。
◉-3、情報誌広告
高級ホテルの客室や会員制クラブ、航空機内などに設置されるラグジュアリー系情報誌は、富裕層の手に直接届く媒体です。
誌面自体が高級感を演出しているため、情報誌広告を出すことで、ブランド価値を高める効果が期待できます。
情報誌広告を掲載できる主な媒体は、富裕層向けの情報誌「Nile’s NILE(ナイルスナイル)」や「PAVONE(パヴォーネ)」、ダイナースクラブの会員誌「シグネチャー」などです。
◉-4、タクシー広告
タクシー広告は、都市部のハイヤーやタクシーの後部座席モニターに配信できる広告です。
ハイヤーやタクシーの乗客には、経営者や役員クラスの人が含まれるため、タクシー広告を配信することでピンポイントにアプローチできます。
タクシー広告を出す際は、ターゲットの興味を引くために、商材の価値をわかりやすく訴求することが重要です。
また、移動中の限られた時間に情報を届けるため、簡潔かつ印象に残るクリエイティブを作る必要があります。
◉-5、サイネージ広告
サイネージ広告は、街中や施設内、建物の壁面などに設置されているディスプレイに配信できる広告です。
富裕層や高所得者がよく利用する場所にあるデジタルサイネージに広告を配信すると、自社の商品やサービスの認知を効果的に広げられます。
たとえば、空港ラウンジや高級マンション、ゴルフ場にサイネージ広告を出すと、富裕層・高所得者へのアプローチが可能です。
サイネージ広告の特徴として、視認性が高く、商品の世界観を短時間で伝えやすいことが挙げられます。
富裕層・高所得者向け広告で成果を出すポイント

富裕層・高所得者向け広告を出す際は、媒体選びだけでなく、以下のようなポイントも重要です。
・ターゲットを具体的に定義する
・価格ではなく、価値を訴求する
・洗練されたデザインと表現を追求する |
富裕層・高所得者向け広告で成果を出すポイントについて見ていきましょう。
◉-1、ターゲットを具体的に定義する
富裕層・高所得者層と一口に言っても、そのライフスタイルや価値観、興味関心は多岐にわたります。
そのため、自社のターゲットを具体的に定義することが、広告を出す際に重要です。
年齢層や性別、居住地域、家族構成、職業、役職、年収といったターゲット属性を明確にしましょう。
さらに、「どのような生活を送っているのか」「休日は何をしているのか」「どのような趣味を持っているのか」などを具体的に想定することも、広告の成果につながります。
◉-2、価格ではなく、価値を訴求する
富裕層は安さではなく、希少性やブランドストーリー、人生を豊かにする体験価値に惹かれる傾向があります。
そのため、富裕層向け広告を出す際は、価格ではなく価値を訴求することが重要です。
「なぜこの商品・サービスが特別なのか」「所有することでどんな価値が得られるのか」を明確に示すことで、興味を持ってもらいやすくなります。
◉-3、洗練されたデザインと表現を追求する
富裕層は日常的に質の高いデザインや演出に触れているため、広告クリエイティブも洗練されたデザインと表現を追求することがポイントです。
ターゲットとする富裕層にマッチする高品質なクリエイティブを作ることで、「本物を提供する企業である」という信頼感を持ってもらいやすくなります。
広告文の内容やフォント、配色、動画広告の場合は映像や音による演出など、細部まで妥協しない広告表現を追求する必要があります。
広告だけではない!富裕層・高所得層に効果的な集客施策

富裕層や高所得者に自社の商品・サービスを広める方法には、広告以外に以下のような手法があります。
・イベント出展
・富裕層向け商品・サービスとのコラボレーション
・セミナー・勉強会
・企業出版(ブックマーケティング) |
ここでは、各集客施策について解説します。
◉-1、イベント出展
富裕層が集まる展示会や限定イベントへの出展は、ターゲット層と直接関われる施策です。
たとえば、高級車やアート、ワイン、ジュエリー、海外不動産などをテーマにした展示会や、会員制・招待制の限定イベントに出展することが、認知拡大や商談の獲得につながります。
イベント出展時は、自社のブランドイメージを体験できるブース設計や、ストーリー性のあるプレゼンテーションを行い、ブランド価値を印象付けることが重要です。
◉-2、富裕層向け商品・サービスとのコラボレーション
自社と同じターゲット層を持つ高級ブランドと連携し、相互に送客をすることも、効果的な集客施策です。
たとえば、高級時計ブランドと高級ホテルの宿泊プラン、高級車メーカーとリゾート施設のタイアップといったコラボレーション企画が考えられます。
お互いの顧客に対して信頼ある企業として紹介されるため、初めての接触でも心理的なハードルが下がりやすいことが、コラボレーションのメリットです。
さらに、限定性や希少性を持たせた特別なプランを用意すると、より良い反応を得られる可能性があります。
◉-3、セミナー・勉強会
富裕層は自身の資産管理やライフスタイルの質向上に高い関心を持っています。
そのため、資産運用や税務、相続、健康などをテーマとしたセミナーや勉強会を開催することが、富裕層へのアプローチに有効です。
講師として各分野の専門家や著名人を起用すると、限定感や特別感を与えられるため、参加者の関心を高めて商談へつながりやすくなります。
また、参加者限定の相談会や交流会を設けて、より深い関係を構築することも効果的です。
◉-4、企業出版(ブックマーケティング)
企業出版は、自社の専門知識やブランドストーリー、理念などを一冊の書籍としてまとめることで、信頼性を高めるマーケティング施策です。
広告やWebサイトで発信する情報と異なり、書籍は多くの手間と時間をかけて出版されるため、権威性が高いという特徴があります。
中長期的にはブランド力を高め、競合との差別化が可能です。
ブックマーケティングの詳細については、以下の記事でも解説しています。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
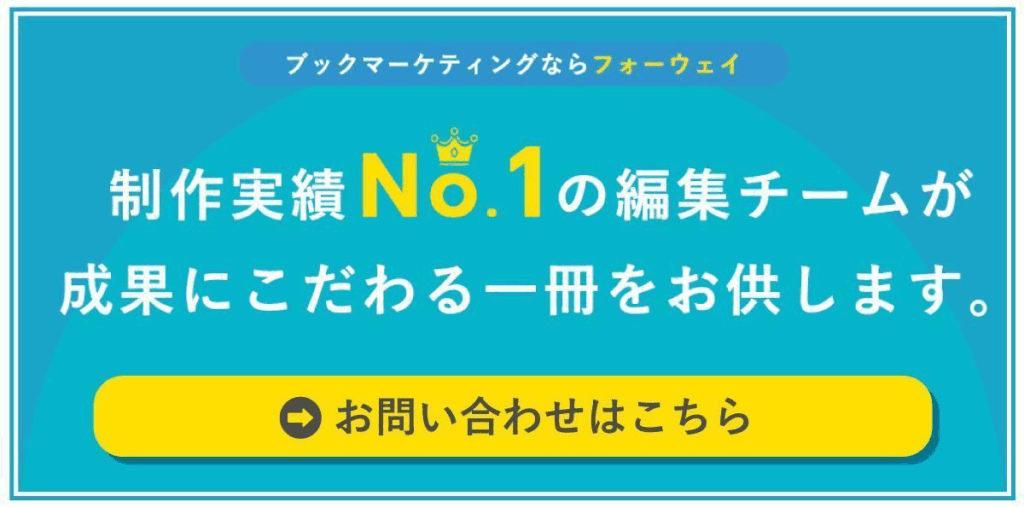
富裕層・高所得層にリーチするなら企業出版がおすすめ!
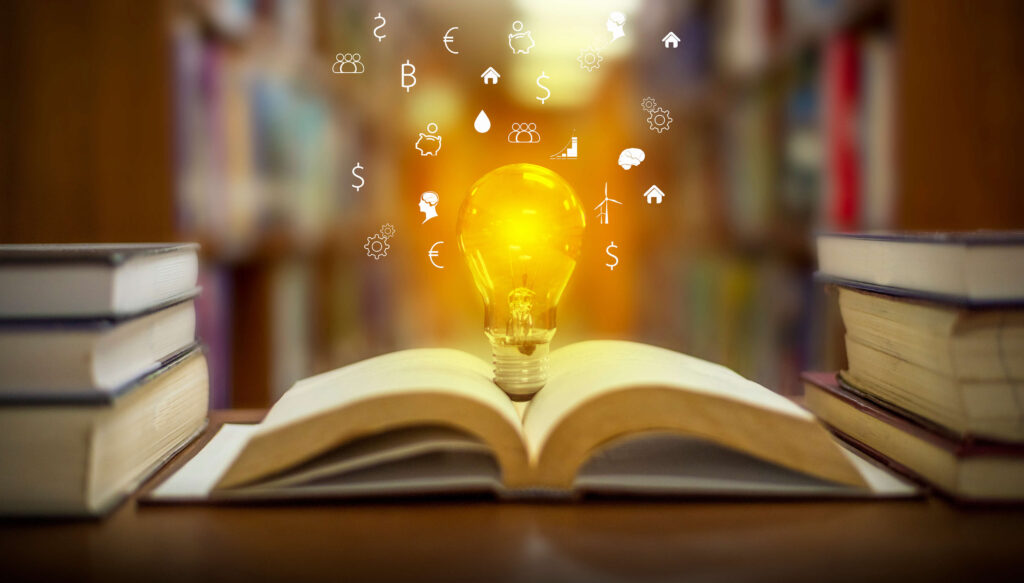
企業出版は、以下のような特徴があるため、富裕層・高所得者へのアプローチに有効です。
・信頼を獲得しやすい
・富裕層特有の購買行動に合っている
・継続的な見込み客(リード)の獲得につながる |
ここでは、企業出版ならではの特徴について解説します。
◉-1、信頼を獲得しやすい
富裕層は、信頼できる情報源から情報を得たいと考えていることが一般的です。
書籍を出版して、著者や企業の専門知識を体系的に伝えると、情報の信頼性を高められます。
一方的な宣伝ではなく、読者にとって有益な情報を届ける書籍は、信頼関係を築くための効果的な手段となります。
◉-2、富裕層特有の購買行動に合っている
富裕層は商品購入を検討する際、口コミや専門家の意見を参考にし、時間をかけて判断する傾向があります。
企業出版では、自社や商品・サービスに関する情報を詳しく伝え、富裕層に十分な検討材料を提供することが可能です。
書籍を通じて、企業の理念や商品・サービスの開発背景、創業者の想い、業界の課題といった深い情報を提供することで、富裕層から納得されやすくなります。
◉-3、継続的な見込み客(リード)の獲得につながる
一般的に、広告は出稿期間が終わると効果が途切れます。
一方で、書籍は出版後に長期的に残り続け、配布・販売を通じて新しい顧客へのリーチが可能です。
書店での流通をはじめ、セミナーやイベントでの配布、オンライン施策との組み合わせにより、長期的に安定したリード獲得ができます。
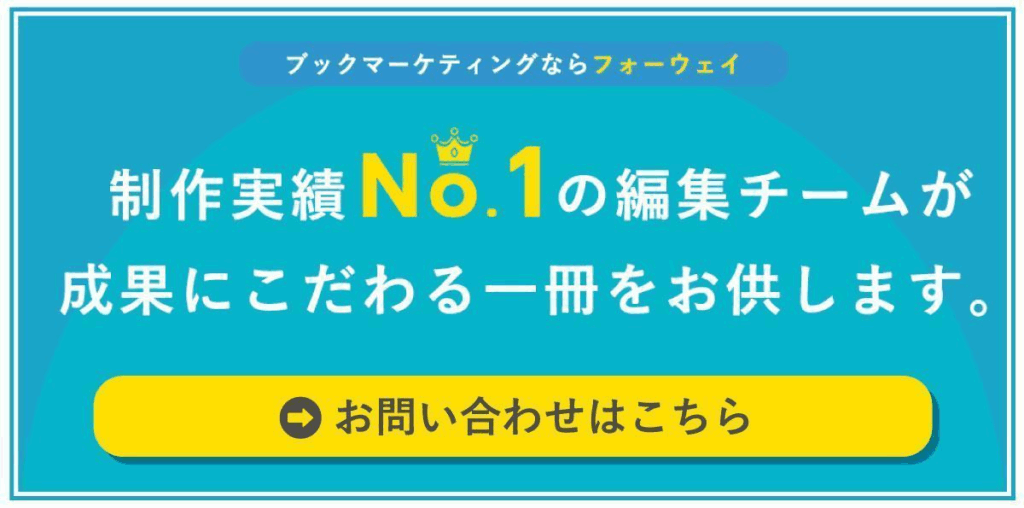
企業出版で富裕層・高所得者にリーチした成功事例
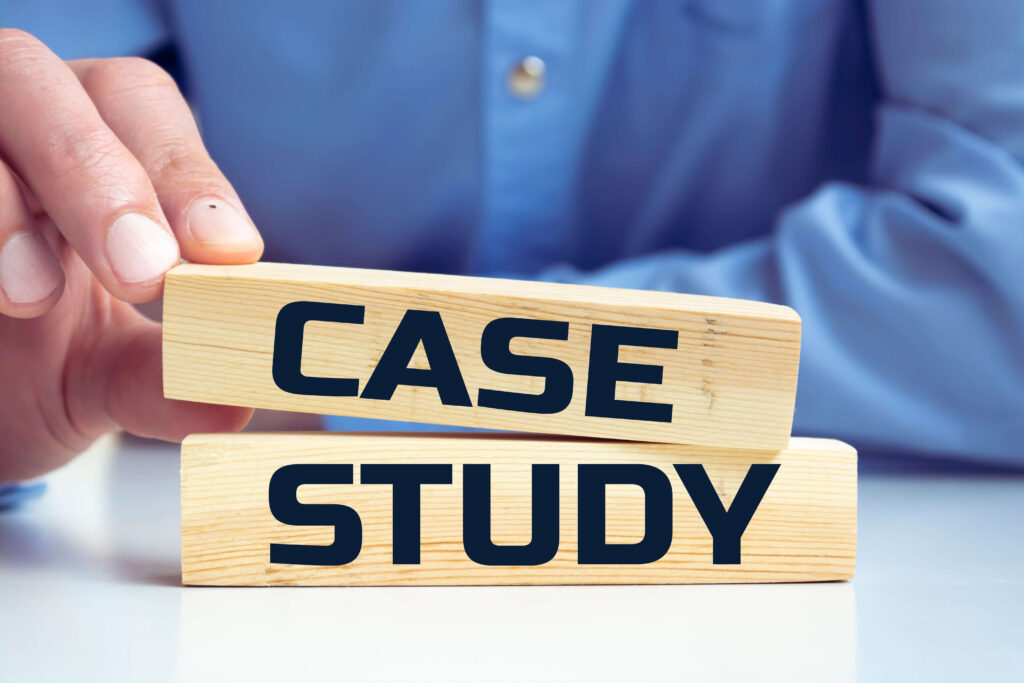
企業出版は、さまざまな業界における富裕層・高所得者向けとして有効です。
ここでは、企業出版で富裕層・高所得者にリーチした成功事例を3つ紹介します。
◉-1、アンティークコイン投資の分野で富裕層を獲得した事例
アンティークコインを扱う企業では、富裕層をターゲットにしたアンティークコイン投資に関する書籍を出版しました。
書籍の流通戦略として、投資関連書籍の販売好調店と、富裕層が住むエリアの書店に重点的に配本。
また、日経新聞の複数の広告枠に連続出稿し、認知度向上も図りました。
出版後間もなく100名以上の無料資料ダウンロードがあり、数千万円の売上につながっています。
また、出版記念セミナーでは、数百万円の売上を複数獲得。
書籍を購入した富裕層の顧客からも反響があり、面会の3日後に数億円の売上につながりました。
◉-2、セミナー講師に権威性がつき、富裕層から商談を獲得した事例
不動産投資業界のセミナー講師のブランディングを目的とした企業出版では、セミナー講師を著者、代表取締役を監修として書籍を制作しました。
同社が得意とする投資ノウハウをタイトルに据え、投資家の興味を引く書籍に仕上げたことも、企画編集のポイントです。
一都三県の中で高収入層の割合が多いエリアへの配本や、日本経済新聞への広告掲載、書籍のランキング獲得施策などを実施。
著者であるセミナー講師を指名する問い合わせが殺到し、出版後1か月で10件強の商談を獲得できました。
また、出版後に富裕層向けセミナーも開催し、不動産投資家やオーナー社長の集客にも成功しています。
◉-3、医師をターゲットに書籍を出版し、6か月で10億円以上の売上につながった事例
新規顧客の獲得経路がほとんど紹介のみに限られていた不動産投資企業では、医師をターゲットとした不動産投資の書籍を出版しました。
自社独自の不動産投資ノウハウや資産運用スキームをまとめ、権威性と信頼性を獲得することが、企業出版の狙いです。
書籍発売1か月で複数の反響があり、読者の医師との面談後に投資用区分10戸購入が決まりました。
また、大手病院の勤務医からの反響が成約につながるなど、出版から6か月で10億円以上の売上を獲得。
ほかにも書籍読者からの問い合わせがあり、不動産投資を検討している高所得者との商談が実現しています。
【まとめ】富裕層・高所得者向け企業出版で商品やサービスをアピールしよう!
富裕層・高所得者向けの広告は、高額商品やプレミアムサービスを販売するために有効な施策です。
価格の安さではなく、希少性やブランドストーリーなどの価値を訴求することで、富裕層からの信頼を得やすくなります。
また、富裕層・高所得者向けの集客施策の一つとして、企業出版も効果的です。
フォーウェイでは、富裕層・高所得者にリーチしたい企業に向けて、ブックマーケティングのサービスを提供しています。
企業出版で自社の商品やサービスを効果的にアピールしたい方は、ぜひフォーウェイにご相談ください。