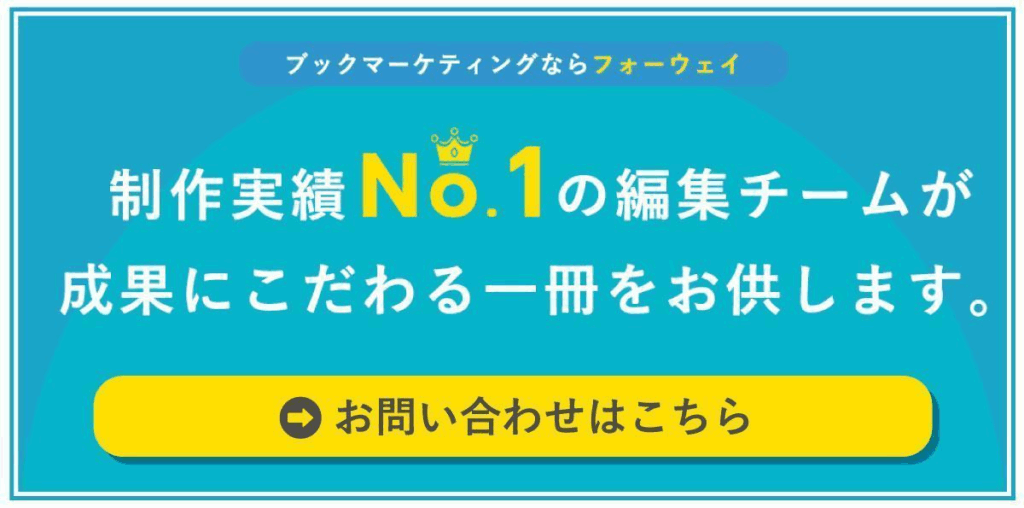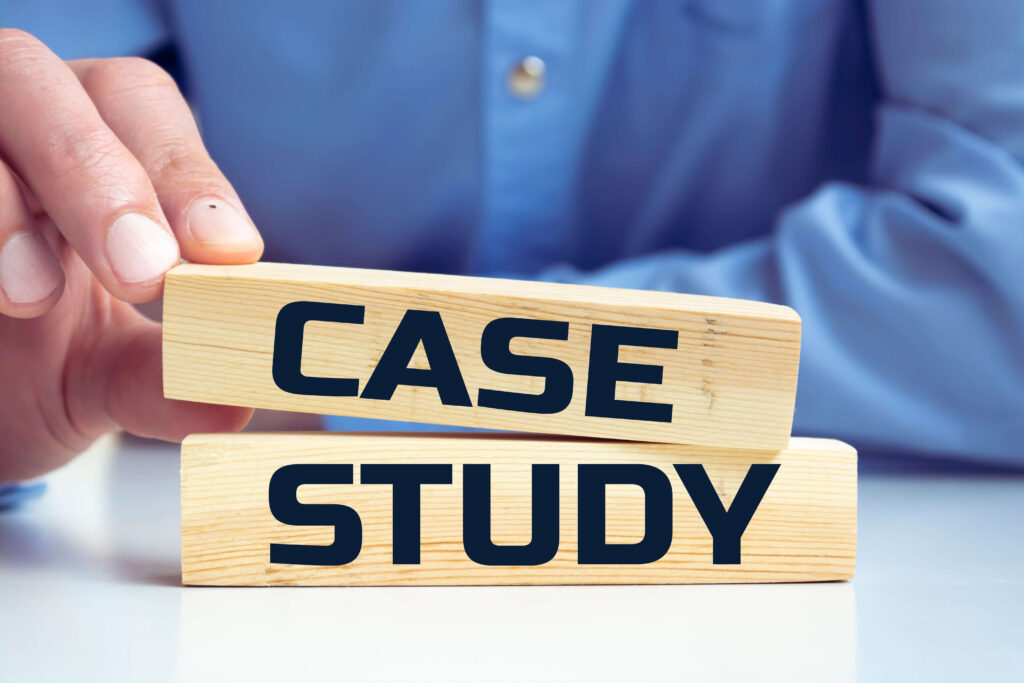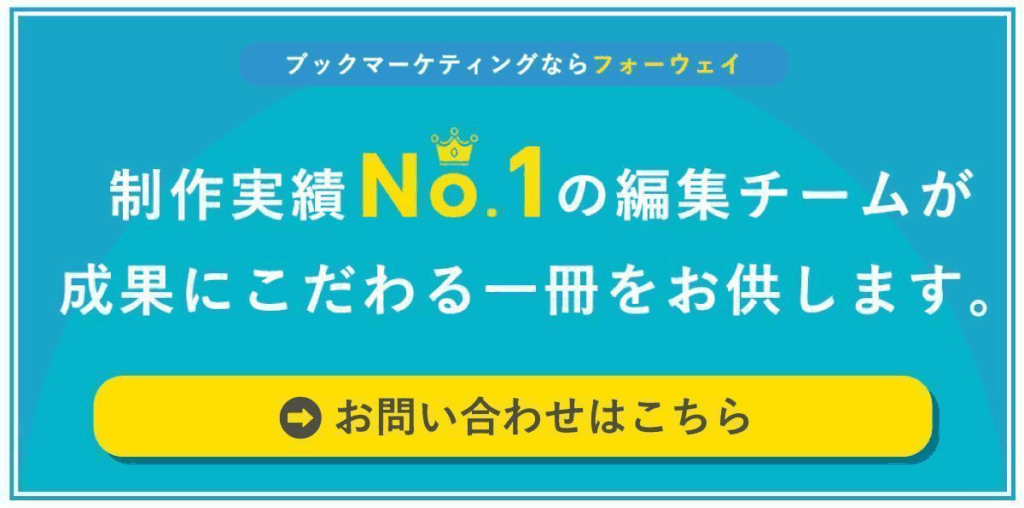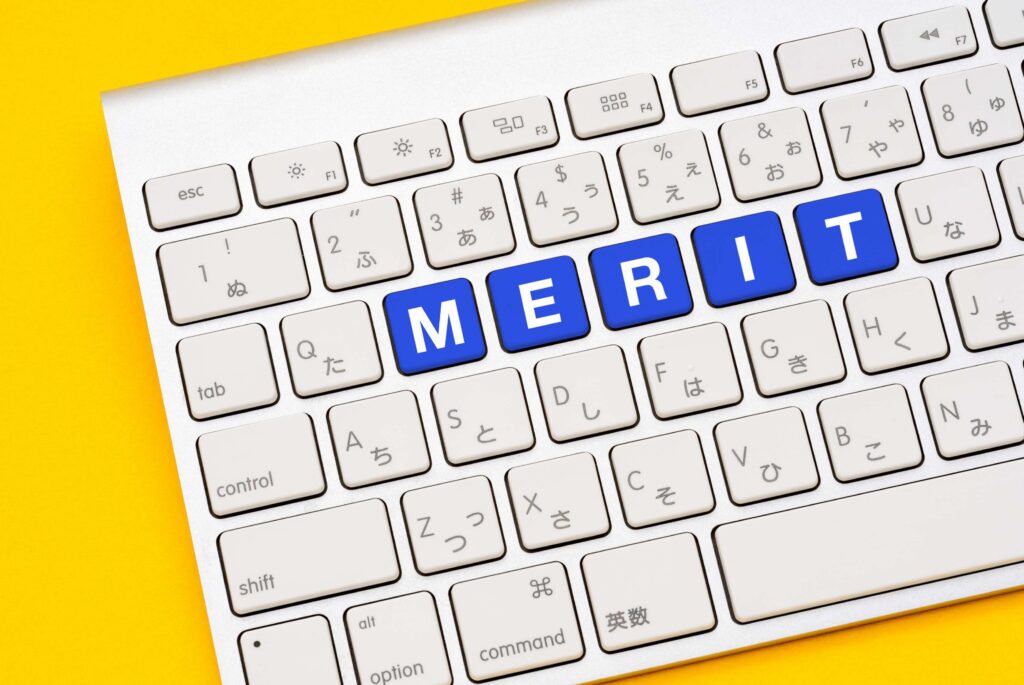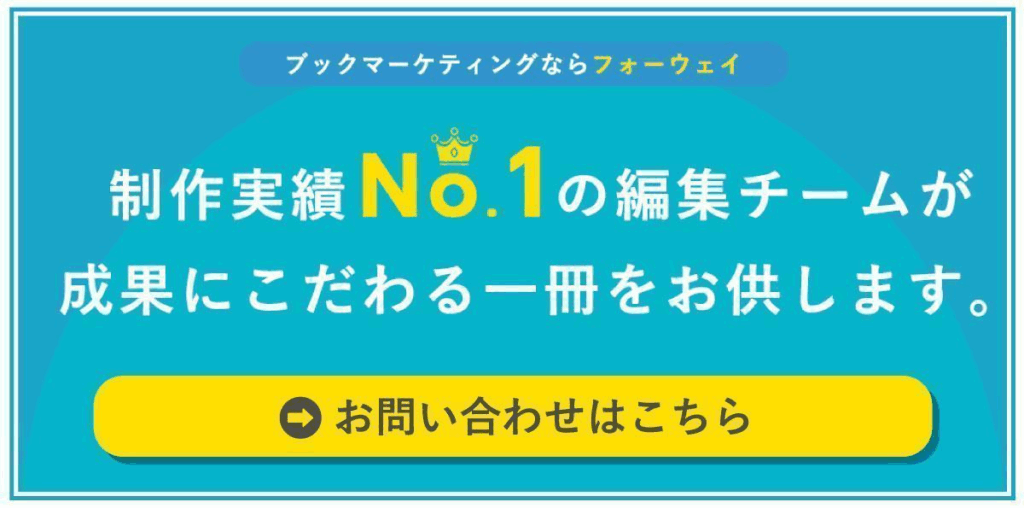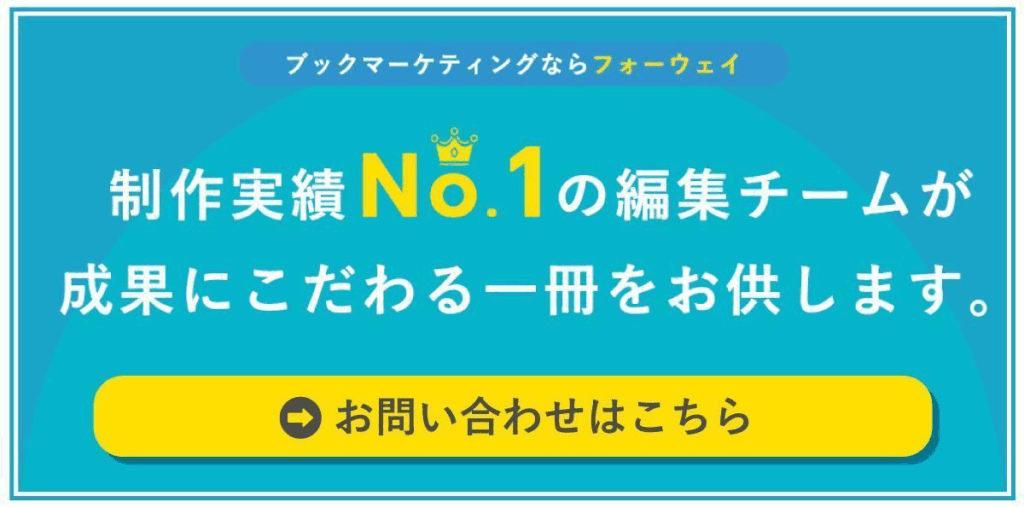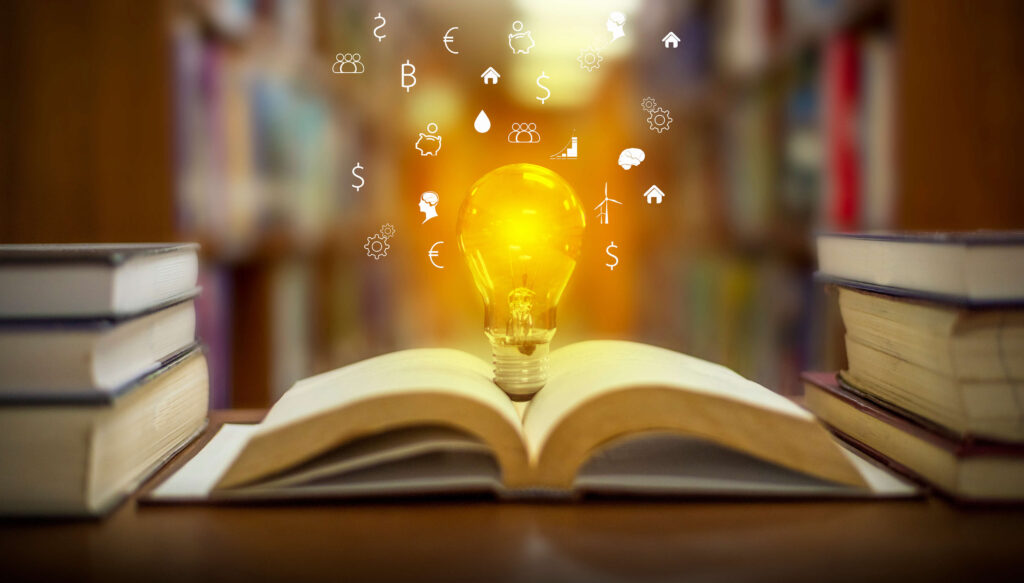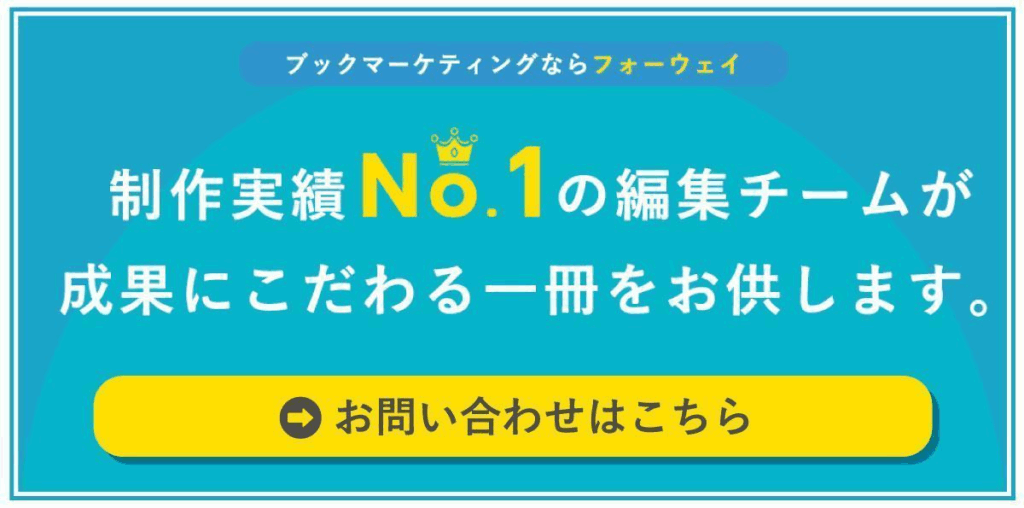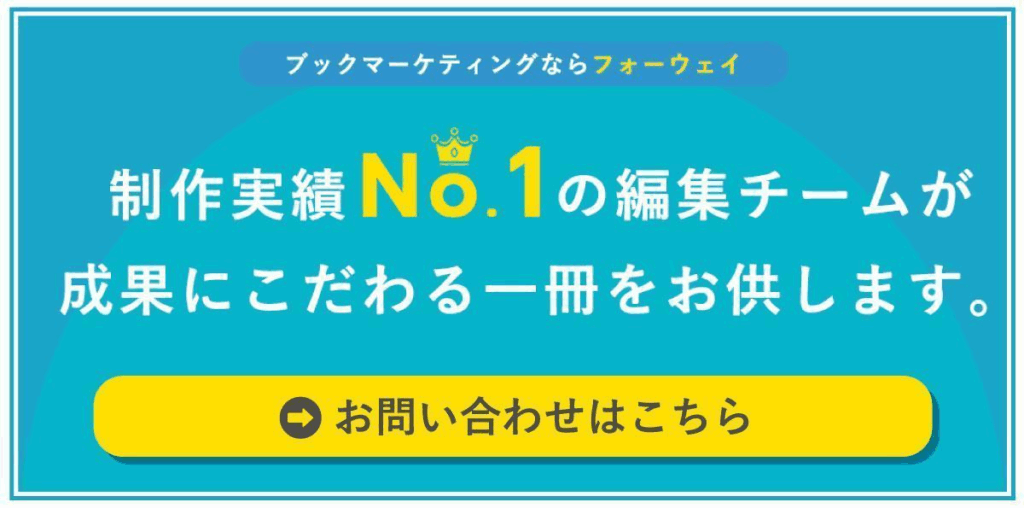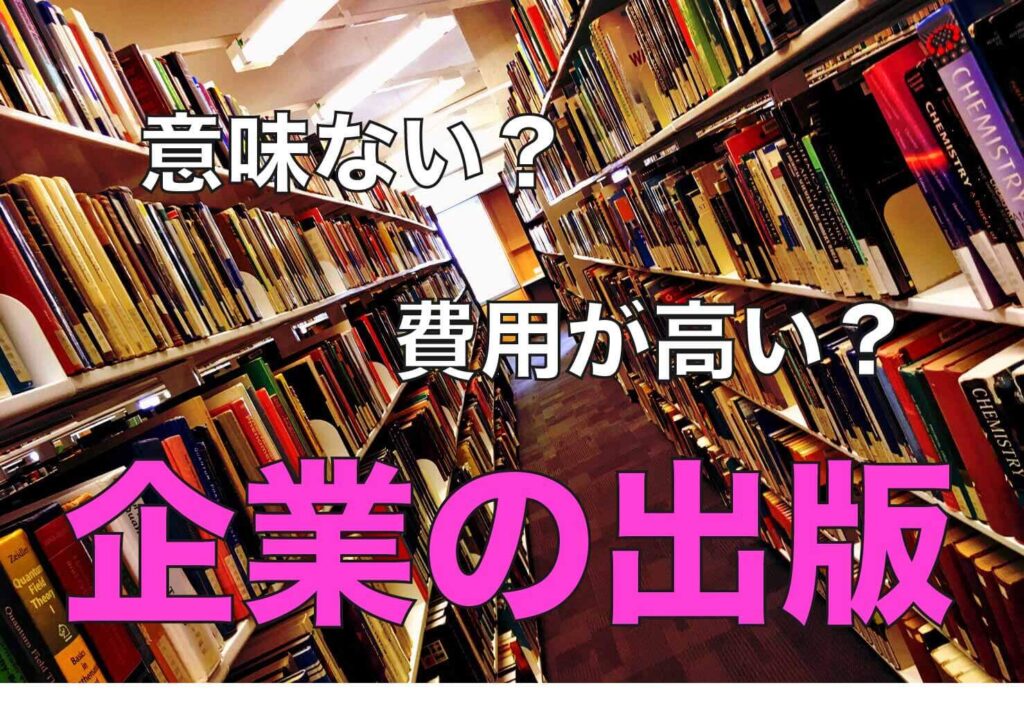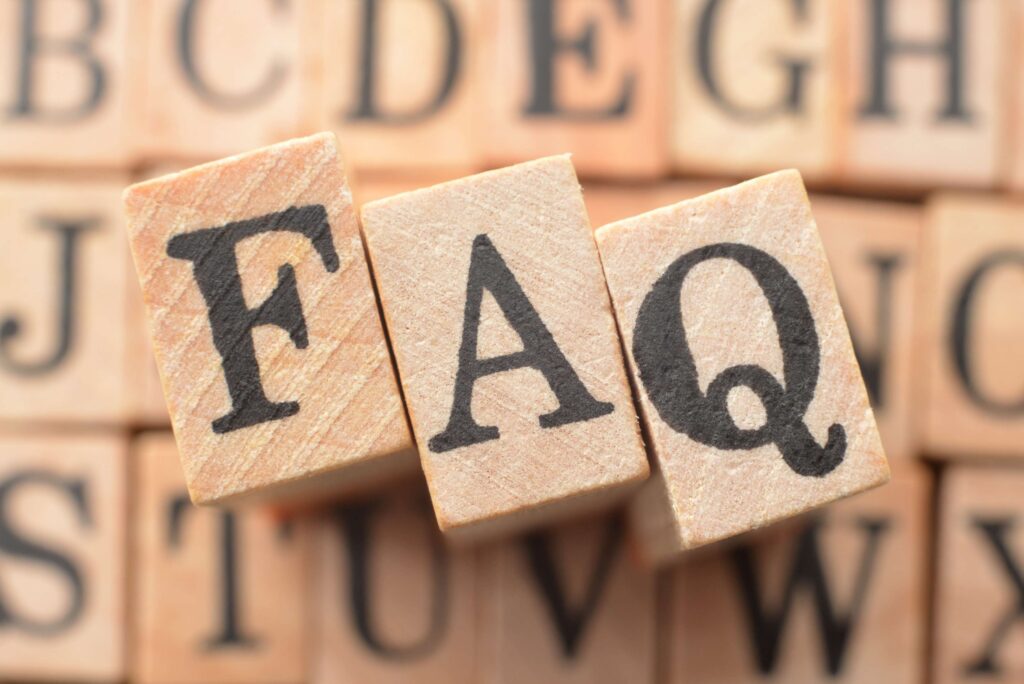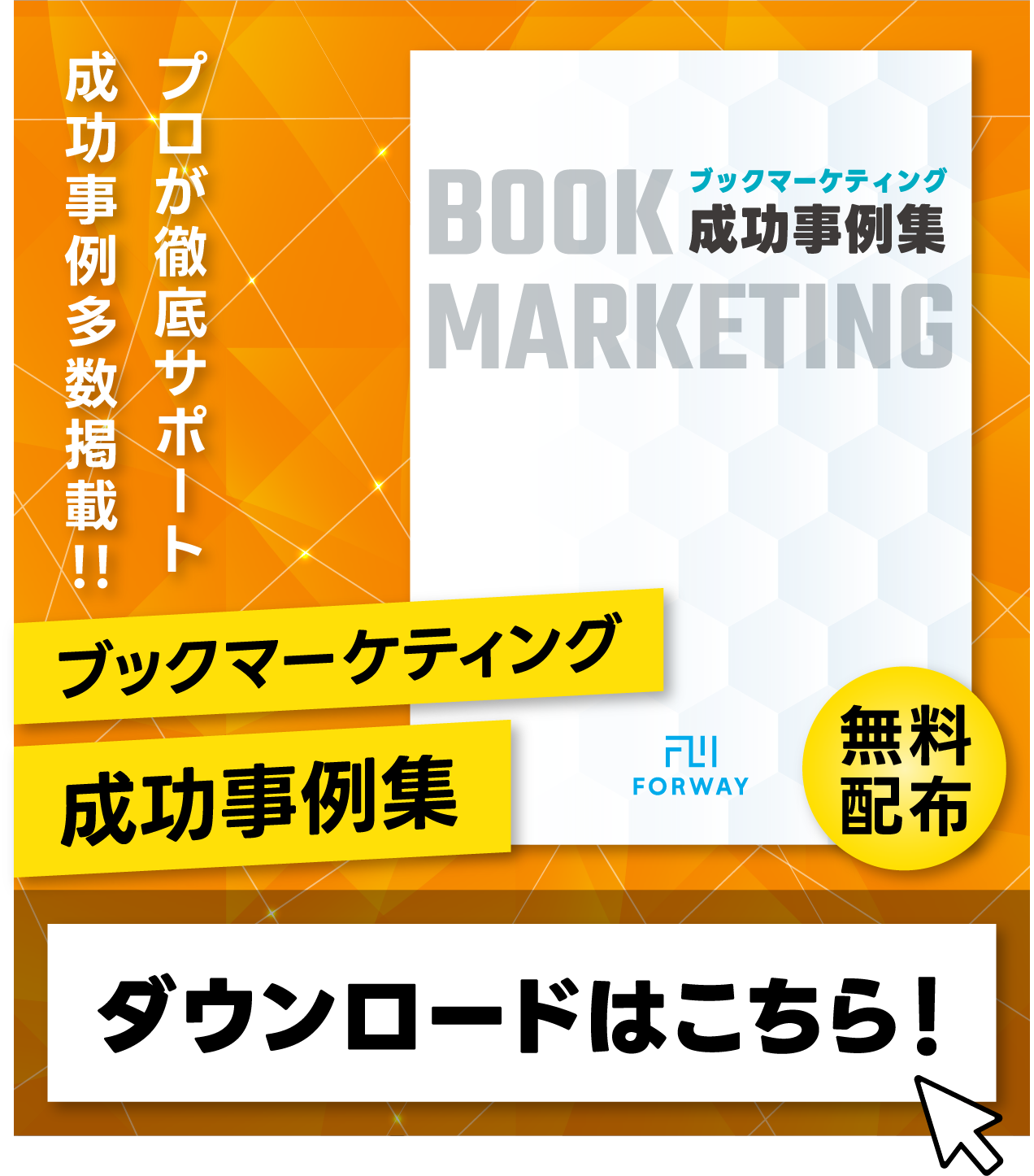高額商品や専門サービスを提供する企業にとって、富裕層の心をつかむことはビジネスの成長を左右する重要なテーマです。
しかし、富裕層の集客は一般消費者とは異なり、広告や低価格の訴求では成果を上げることはできません。
富裕層が重視するのは「信頼できる相手かどうか」です。
そのため、短期的な販促ではなく、専門性や世界観の一貫性を通じて信頼を積み上げていくアプローチが必要です。
この記事では、富裕層の集客を成功させるための手法やポイント、成功事例について詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
そもそも富裕層とは?

富裕層とは、単に高収入を得ている人を指すわけではありません。
金融資産を一定以上保有し、安定した資産運用や投資を行っている人々を含む広い概念です。
金融機関や調査機関によって定義は多少異なりますが、一般的には以下のように分類できます。
| 分類 | 純金融資産額 |
| 準富裕層 | 5,000万円~1億円未満 |
| 富裕層 | 1億円以上~5億円未満 |
| 超富裕層 | 5億円以上 |
野村総合研究所(NRI)の調査によれば、2023年時点で1億円以上の純金融資産を保有する富裕層と超富裕層の合計は約165.3万世帯に達しており、その内訳は富裕層が約153.5万世帯、超富裕層が約11.8万世帯という結果が示されています。
日本国内における富裕層は年々増加しており、投資・不動産・医療・教育など、さまざまな分野で影響力を拡大しています。
こうした層は、国内経済において重要な購買力と影響力を持ち、企業にとっても戦略的に無視できない顧客層といえるでしょう。
◉富裕層の集客に有効な手法

富裕層を対象とした集客では、一般的な広告やキャンペーンのように幅広い層への認知拡大を目指すよりも、信頼関係の構築と深いコミュニケーションが重要です。
ここでは、富裕層の心理や意思決定プロセスを踏まえて、5つの手法を紹介します。
- 知人やパートナー経由での紹介
- 限定感のある体験やイベントの活用
- 富裕層向けに特化した広告配信
- 富裕層ブランドとのコラボレーション施策
- 企業出版による専門性アピール
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、知人やパートナー経由での紹介
富裕層にとって、購買や投資の意思決定において影響力を持つのは「信頼できる人からの推薦」です。
知人やビジネスパートナーを通じた紹介は、広告にはない高い信頼性を持ち、成約につながりやすいという特徴があります。
そのため、企業は偶然の紹介に頼るのではなく、既存顧客やビジネスパートナーとの関係性を戦略的に構築し、自然な紹介が生まれる仕組みを整えることが重要です。
◉-2、限定感のある体験やイベントの活用
富裕層は、単なる商品ではなく、「体験」を重視する傾向があります。
そのため、少人数制や完全招待制などの特別な体験を提供するイベントが効果的です。
たとえば、高級住宅の内覧会や高級車の限定試乗会、専門家を招いたプライベートセミナーなどがあります。
このようなイベントで、他では得られないような価値を提供することが信頼関係を構築するきっかけになります。
◉-3、富裕層向けに特化した広告配信
富裕層を対象とした広告では、マス媒体での大量露出よりも、ターゲットの価値観やライフスタイルに寄り添った媒体選びがポイントとなります。
たとえば、高級志向の雑誌や経済・金融専門誌、ハイクラス層が閲覧するビジネスニュースサイトなど、信頼性と情報感度の高いメディアを活用することで、ブランドイメージを損なわずに訴求できます。
また、オンラインで広告を配信する場合は、属性でターゲティングするよりも、広告のコンテンツや文脈で興味を惹く方法が有効です。
◉-4、富裕層ブランドとのコラボレーション施策
富裕層は、信頼しているブランドやパートナーとの関係性を重視します。
そこで、コラボレーション施策として、すでに富裕層顧客を抱えている他ブランドや専門家との連携を行うことが効果的です。
たとえば、高級ホテルや不動産会社、金融機関、教育機関など、既存の信用ネットワークに属する企業と協働して共同イベントや限定キャンペーンを実施すると、自社の信頼性向上につながります。
こうしたコラボレーション施策は、販促効果だけでなく、「この企業は信頼できる」という印象を強化する役割も果たします。
◉-5、企業出版による専門性アピール
富裕層を惹きつけるには「信頼」と「専門性」が欠かせません。
企業出版(ブックマーケティング)は、この2つの要素を同時に高められる効果的なブランディング手法といえます。
書籍という形で企業の理念やノウハウ、実績を体系的に伝えることで、広告では得られない「知的な共感」を生み出すことができます。
また、書籍は出版社や編集者などの第三者を介するため、情報の信頼性が高まり、企業のブランド価値を一段上のレベルに引き上げる効果があるのです。
さらに、富裕層にとって「本を出している企業」は、社会的信用のある存在として認識されやすく、接点の質を高める効果も期待できます。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
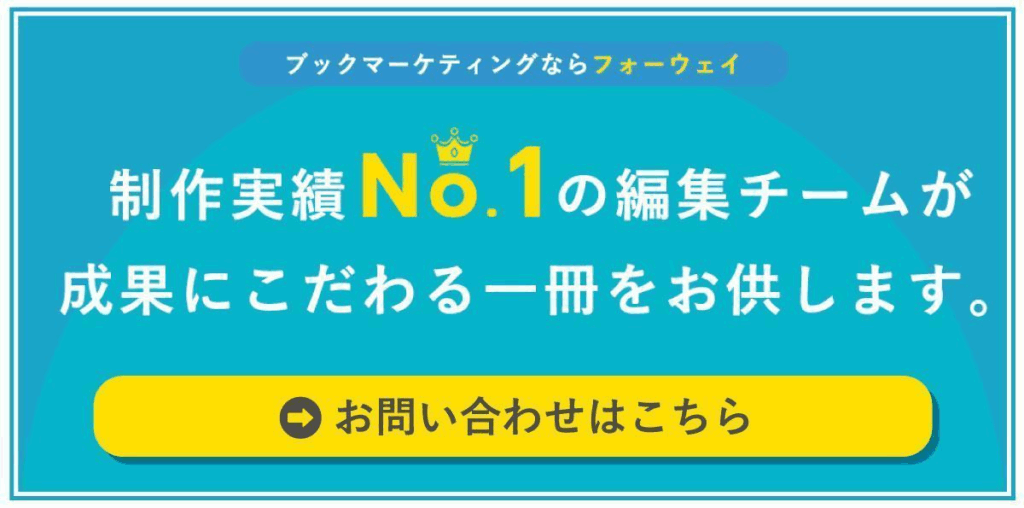
富裕層の集客を成功させるポイント

どんなに優れた商品やサービスであっても、「信頼」が得られなければ富裕層の集客にはつながりません。
ここでは、富裕層の集客を成功させるための4つのポイントを紹介します。
- 「信頼」を第一に導線を設計する
- 体験やブランドストーリーを提供する
- ブランドの世界観を一貫して伝える
- 時間をかけて関係を育てる意識を持つ
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、「信頼」を第一に導線を設計する
富裕層が重視するのは「信頼できる相手かどうか」です。
そのため、最初の接点から納品後のフォローに至るまで、あらゆるタッチポイントで信頼を積み上げる導線設計が重要です。
たとえば、専門性を示す実績や第三者による評価などを明確に提示し、透明性の高い説明を徹底する必要があります。
また、営業担当者の言葉遣いや姿勢、レスポンスの速さといった細部にまで配慮し、丁寧で誠実なコミュニケーションを徹底することが求められます。
過度なセールスよりも真摯な対応が、富裕層との長期的な信頼関係を築き、契約や紹介の拡大へとつながるでしょう。
◉-2、体験やブランドストーリーを提供する
富裕層はすでに生活に必要なモノをほとんど手にしているため、購買の動機は「機能」ではなく、「体験」や「共感」へと移っています。
そのため、「モノの性能や価格」よりも、「どのような体験が得られるのか」「そのブランドにどんな思想や物語が込められているのか」を訴求することが重要です。
たとえば、特別に設けられたプライベート空間でのテイスティング体験や、熟練の職人による製作工程を間近で見られるイベントなど、ブランドの美学や世界観を五感で体感できる機会は、富裕層の知的好奇心と感性を刺激します。
単なる販売促進ではなく、「このブランドの世界に共感したい」と思わせる体験が、富裕層の心を動かします。
◉-3、ブランドの世界観を一貫して伝える
富裕層は、ブランドの言葉や表現にブレがないかを見極めます。
Webサイトやパンフレット、SNS、イベント空間、営業担当者の言葉遣いに至るまで、すべての接点でトーンや価値観を統一することが信頼につながります。
つまり、一貫性が安心感を生み出し、その積み重ねがブランドへの信頼につながるのです。
また、装飾的な高級感よりも、余白の使い方や語彙の選び方、事実の提示方法など、細部の整合性が重要です。
短期的なキャンペーンで印象を操作するのではなく、長期的に一貫した世界観を築くことで、富裕層の記憶に残るブランドになります。
◉-4、時間をかけて関係を育てる意識を持つ
富裕層の集客では、短期的な「一度の購入」を狙うよりも「長く選ばれ続ける関係」を育てる姿勢が重要です。
高額な商品やサービスを扱う場合、購買までの検討期間が長く、紹介や口コミによる影響力も大きいため、短期的な成果を求めすぎると逆効果になることがあります。
定期的な情報提供やアフターフォローを通じて、継続的に接点を持ち続けることで、富裕層から「長く安心して付き合える企業」と認識されるようになります。
◉富裕層の集客には企業出版が効果的!

企業出版は、企業の理念や専門性を体系的に伝えることができることから、富裕層の集客に効果的です。
主な理由として、次の4つが挙げられます。
- 富裕層が求める信頼を出版で確立できる
- 企業の理念を明確に伝えられる
- 知的満足を与えて共感を生む
- 出版をきっかけに信頼関係が広がる
以下で、それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、富裕層が求める信頼を出版で確立できる
富裕層が重視するのは、「この企業は信頼できるか」という点です。
広告やSNSのように一過性の情報発信ではなく、企業出版は豊富な情報量を活かして、企業の専門性や理念、誠実な姿勢を体系的に伝えられます。
また、出版物は編集者や校正者といった第三者のチェックを経て完成するため、情報の正確性と客観性が担保されることもメリットです。
さらに、書籍というツール自体が信頼の象徴であるため、「本を出している企業」という事実が社会的な信用の裏づけとなります。
◉-2、企業の理念を明確に伝えられる
富裕層は商品やサービスの機能よりも、「企業の理念や価値観」に共感して購入の選択をします。
企業出版は、こうした企業の理念や背景、社会的使命を深く伝えることができる最適な手段です。
経営者の歩んできたストーリーや、企業が目指す未来像を一冊の本にまとめることで、企業の「軸」を読者に明確に伝えることができます。
◉-3、知的満足を与えて共感を生む
富裕層は知的好奇心が強く、新しい知識や視点に価値を感じる傾向があります。
企業出版では、業界の専門知識、独自のノウハウ、市場の分析などを体系的に伝えることができるため、「読む価値のある本」として知的満足を提供することが可能です。
また、内容が実践的かつ誠実であるほど、読者は「この企業はしっかり考えている」「社会的に意義のあることをしている」と感じ、企業に対する尊敬や共感を抱くようになります。
こうした知的共感は、富裕層との間に長期的な信頼関係を築くための重要な要素です。
◉-4、出版をきっかけに信頼関係が広がる
企業出版は、出版して終わりではなく始まりです。
書籍を通じて企業の理念や価値観に触れた読者が、セミナーやイベント、個別相談、共同プロジェクトなどへと関係を深めていくケースも少なくありません。
特に富裕層の場合は、「書籍を読んで感銘を受けた」「理念に共感した」といった動機で直接コンタクトを取ってくるケースがあり、そこから深い関係構築につながることもあります。
また、企業出版をきっかけとしてマスメディアやWebメディアからの取材機会が増え、結果として企業のブランド価値や社会的信用が大きく向上する事例も多く見られます。
▶︎企業出版(ブックマーケティング)については、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】も合わせて参考にしてください。

企業出版による富裕層集客の成功事例

ここでは、実際に企業出版を活用して富裕層の信頼を獲得し、事業成長につなげた3つの成功事例を紹介します。
- 医師を対象にした不動産投資ビジネスの出版事例
- アンティークコイン投資ビジネスの出版事例
- 生前の不動産対策に関する出版事例
3つの事例について詳しく見ていきましょう。
◉-1、医師を対象にした不動産投資ビジネスの出版事例
不動産会社の経営者は、高所得かつ納税額の高い医師に向けて、節税対策としての不動産投資を紹介する書籍を出版しました。
もともと紹介経由での新規顧客が中心で、関係構築に時間がかかる課題を抱えていましたが、書籍出版によって「医師専門の投資コンサルタント」という立ち位置を確立しました。
出版後は、Yahoo!ディスプレイ広告など従来の施策では得られなかった反響を次々と獲得。
発売1ヶ月で書籍読者からの問い合わせが複数寄せられ、医師との面談後に即決で10戸購入が成立し、出版費用をすぐに回収する成果を上げました。
また、大手病院勤務医からの問い合わせも増加し、発売から6ヶ月で読者反響から総額10億円の売上向上を達成。
会社の売上は前年比で2倍以上に成長しました。
書籍が「集客ツール」としてだけでなく、商談をスムーズに進めるクロージングツールとしての役割も果たしています。
◉-2、アンティークコイン投資ビジネスの出版事例
とある会社では、「アンティークコイン投資」をテーマに書籍を出版しました。
カバー装丁には、富裕層を意識してラグジュアリー感をもたせ、書籍の中では希少性や歴史的価値といった文化的観点からコイン投資の魅力を紹介しました。
その結果、出版直後から100名以上が無料資料をダウンロードし、数千万円規模の売上を記録。
また、出版記念セミナーでは3名の成約を獲得し、1件あたり数百万円の売上を達成しています。
さらに、書籍を読んだ医師からの問い合わせをきっかけに、面会からわずか3日で数億円規模の成約に至るなどの成果を上げました。
◉-3、生前の不動産対策に関する出版事例
ある不動産会社は、相続や事業承継を考えている富裕層に向けて、「生前の資産対策」の重要性を啓発する書籍を出版しました。
書籍の内容として、専門家の立場から法的・税務的アドバイスを分かりやすくまとめ、実際の事例を通じて読者の理解を深める構成にしました。
その結果、「単に物件を売る会社」ではなく「資産管理・承継を支援するパートナー」というブランドイメージを確立。
出版後は、書籍を読んで来社した顧客の理解度が高く、商談スピードが向上。
また、書籍連動セミナーでは400名を集客、60組以上が個別相談に参加し、その場で顧客化につながるケースが続出しました。
企業出版によって、自社の理念と専門性が伝わり、長期的な契約へ発展するケースも増えています。
◉【まとめ】富裕層の集客なら信頼を築ける企業出版がおすすめ!
この記事では、富裕層の集客に有効な手法や成功させるポイント、企業出版によって集客に成功した事例などについて紹介しました。
富裕層の集客では、一般的な広告やキャンペーンでは届かない「信頼」と「共感」をいかに築くかがポイントです。
この点で、企業出版は効果的な手法といえます。
書籍という媒体は、企業の思想や専門性を体系的に伝えるだけでなく、第三者の手を介することにより情報の信頼性が高まっているからです。
フォーウェイでは、書籍をマーケティングに活用する「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
富裕層の集客手段として活用されている事例も多く、書籍の出版からマーケティング全般までトータルでサポートさせていただきます。
富裕層の集客をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。


法人向け広告(BtoB広告)は、信頼性や実効性を重視され、顧客の課題解決に直結する提案が求められるのが特徴です。
そのため、BtoB広告では製品やサービスそのものよりも「どのように業務効率を高め、成果を生み出せるのか」を明確に伝えることが必要です。
また、最終的な意思決定は経営者や事業責任者が担うため、短期的な認知拡大ではなく、企業間の信頼構築と長期的な関係づくりが重要となります。
近年では、オンラインとオフラインを組み合わせた広告が主流となっているため、どのような手法を選び、どう成果につなげるかもポイントです。
この記事では、企業の経営者・事業責任者に向けて、BtoB広告の種類や成果を出すための戦略を紹介します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
法人向け広告(BtoB広告)とは?

法人向け広告(BtoB広告)とは、企業や組織を顧客とするBtoBビジネスにおいて、自社の製品やサービスを訴求する広告です。
目的は認知拡大ではなく、「企業課題の解決」や「業務の効率化」など、ビジネス成果につながる価値を伝えることです。
BtoBビジネスでは、複数の関係者が関与し、長期的な検討を経て意思決定が行われるため、感覚的なイメージ訴求よりも導入事例や効果などの客観的な根拠に基づいたメッセージ設計が重要とされます。
◉-1、BtoC広告との違い
BtoC広告が「個人の感情やライフスタイルに訴える広告」であるのに対し、BtoB広告は「企業の課題解決を支援する広告」です。
BtoCビジネスでは、消費者が自身の好みや感情で即時に購入を判断することが多いため、直感的なメッセージやビジュアルが有効です。
一方で、BtoBビジネスは複数の関係者による合意を経て進むため、信頼性や専門性、そして再現性の高い情報が重視されます。
また、BtoBでは一度の取引で終わらず、導入後のサポートやリピート購入を見据えた長期的な関係構築が前提です。
そのため、広告の目的は「販売促進」よりも「リード獲得・信頼形成・商談機会の創出」に置かれます。
BtoB広告とBtoC広告の違いは、次表のようにまとめることができます。
| 法人向け広告(BtoB広告) | 個人向け広告(BtoC広告) |
| ターゲット | 企業・組織の意思決定者 | 個人 |
| 購買動機 | 合理性・論理性を重視 | 感情・感覚を重視 |
| 購買プロセス | ・長期(数週間〜数年)・複数人による稟議・検討が必要 | ・短期(即日〜数日)・意思決定者が少ない |
| 広告メッセージ | 具体的・論理的(「〇〇の課題を解決」「導入実績〇〇件」など) | 情緒的・直感的(「新しい自分に」「この瞬間を楽しもう」など) |
| 広告の役割 | リード獲得・育成(資料請求、問い合わせ、ウェビナー参加) | 直接的な購入・来店(ECサイトへの誘導、店舗への集客) |
法人向け広告(BtoB広告)の種類

法人向け広告(BtoB広告)といっても、その手法は多岐にわたります。
目的やターゲットに応じて活用できるメディアが異なり、大きく次の2種類に分類できます。
それぞれの広告をさらに細分化して紹介します。
◉-1、デジタル広告
デジタル広告は、オンライン活動によって見込み顧客との接点を作る手法です。
代表的なものとして、次の6種類があります。
- リスティング広告
- ディスプレイ広告
- SNS広告
- 記事広告
- 動画広告
- 純広告
以下で、それぞれの特徴について解説します。
◉-1-1、リスティング広告
リスティング広告は、検索エンジンで特定のキーワードを検索した際に表示される広告です。
すでに課題を認識している「顕在層」への訴求に適しており、資料請求や問い合わせなどの行動につながりやすいという特徴があります。
また、広告の表示やクリック状況を細かく分析できるため、効果測定や改善を繰り返しやすい点も魅力です。
◉-1-2、ディスプレイ広告
ディスプレイ広告は、ニュースサイトや業界メディアなどの広告枠に表示されるバナー広告です。
主に認知拡大を目的としており、まだ課題を自覚していない「潜在層」にもリーチできる点が特徴です。
画像や動画などのビジュアル表現を活用することで、ブランドイメージを印象的に訴求できます。
◉-1-3、SNS広告
SNS広告は、LinkedInやX(旧Twitter)、Facebook、InstagramなどのSNSを活用した広告です。
業種・職種・役職などで細かくターゲティングできる点が特徴で、特にLinkedInはBtoB向け広告との親和性が高いプラットフォームです。
ユーザーとの双方向コミュニケーションが可能なため、信頼関係を築きながら潜在顧客を育成する効果も期待できます。
◉-1-4、記事広告
記事広告は、メディア記事形式で自社の製品やサービスを紹介する広告です。
読者は広告としてではなく「情報コンテンツ」として内容に触れるため、専門性や信頼性を自然に伝えることができます。
また、掲載先メディアのブランド力を活用できるため、読者からの信頼を得やすいというメリットもあります。
◉-1-5、動画広告
動画広告は、YouTubeやWebメディアなどで配信される映像形式の広告です。
BtoB商材のように内容が複雑なサービスを短時間で分かりやすく伝えるのに向いています。
音声や映像による臨場感があるため、視聴者の記憶に残りやすく、感情に訴える訴求も可能です。
◉-1-6、純広告
純広告は、特定のWebメディアや業界サイトに一定期間、固定枠として掲載する広告です。
安定した露出を確保できるため、企業認知を高めたい場合やブランドの信頼性を強化したい場合に有効です。
特に業界専門メディアへの掲載は、ターゲット層へのリーチ精度が高く、BtoBブランディングにも効果的です。
◉-2、オフライン広告
オフライン広告は、デジタル広告だけでは伝わりにくい「対面での信頼」や「ブランドの実体感」を補完する役割を担います。
代表的なものは次の3種類です。
- 専門誌・業界紙広告
- 展示会・イベント広告
- 交通広告
以下では、それぞれの特徴を解説します。
◉-2-1、専門誌・業界紙広告
専門誌広告や業界紙広告は、特定の業界を対象とした専門誌や業界紙に掲載する広告です。
読者はその業界の意思決定層が中心となるため、直接的なアプローチが可能になります。
また、専門知識を持つ読者を前提に、踏み込んだ内容や技術的な訴求をしても深く理解されやすく、高い成約効果が期待できます。
◉-2-2、展示会・イベント広告
展示会や業界イベントへの出展、またはセミナーやカンファレンスへの登壇を通じて、自社の製品やサービスを直接訴求する広告手法です。
展示会では、実際に製品を見せながら対面で説明や商談ができるため、顧客に具体的なイメージを持たせ、理解を深めやすいのが特徴です。
一方で、カンファレンスでは専門的な知見や成功事例を共有することで、業界内での信頼性や専門性を高める効果が期待できます。
さらに、リアルな交流を通じたネットワーキングから、新たな取引先の開拓やパートナーシップ構築につながる可能性もあります。
◉-2-3、交通広告
交通広告は、空港や駅、オフィス街などに掲示する広告で、主に経営層やビジネスパーソンを対象としたブランディング施策として活用されます。
特にBtoB分野では、企業の存在感や信頼性、事業規模の大きさを印象づける目的で活用されるケースが多く、大企業や法人顧客への訴求に効果的です。
さらに、通勤や移動などの日常の中で自然に目に触れるため、継続的なブランド想起や企業イメージの定着にもつながります。
▶︎ブランド想起については、関連記事【第一想起を獲得する方法とは?おすすめマーケティング施策と成功事例】もあわせて参考にしてください。
法人向け広告(BtoB広告)で成果を出すためのポイント

法人の購買プロセスは長期的で、複数の関係者が意思決定に関わるため、単に広告を出稿するだけでは成果につながりません。
法人向け広告(BtoB広告)で成果を出すためには、次の4つのポイントを押さえることが重要です。
- ターゲット・ペルソナを明確にしてメッセージを最適化する
- 顧客の関心レベルに合わせて広告を使い分ける
- 一貫性のある継続的な情報発信を行う
- 複数の広告チャネルと発信媒体を連携させる
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
◉-1、ターゲット・ペルソナを明確にしてメッセージを最適化する
BtoB広告の第一歩は、「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを明確にすることです。
BtoB広告では、単に「企業全体」をターゲットとするのではなく、企業内の担当者や経営層を具体的に想定したペルソナ設定が欠かせません。
たとえば、担当者には業務効率化や操作性の向上といった実務的なメリットを、経営層にはROI(投資対効果)や導入による経営改善といった戦略的メリットを訴求することが効果的です。
また、それぞれの立場で抱える課題や関心に合わせてメッセージを最適化することで、共感と信頼を得やすくなります。
◉-2、顧客の関心レベルに合わせて広告を使い分ける
BtoB取引の購買プロセスでは、担当者がまず情報を収集し、比較・検討を重ねたうえで、中間管理職や経営層に提案し、最終的な決裁を仰ぐという流れが一般的です。
担当者は業務効率化や操作性などの具体的な機能面に注目し、中間管理職はチーム全体の生産性や費用対効果を重視します。
さらに、経営層は企業戦略との整合性やROIといった経営的視点から導入可否を判断します。
このように、顧客企業内の職位ごとに関心の軸が異なるため、広告のメッセージや訴求ポイントを職位別に最適化することが重要です。
それぞれの立場に合った情報を届けることで、意思決定の確実性を高め、購買プロセスをスムーズに進められます。
また、こうした職位による関心レベルの差に加えて、購買ステージによる差も存在します。
たとえば、課題をまだ明確に認識していない潜在層には、SNS広告や記事広告を通じて問題提起や業界動向の共有を行うのが効果的です。
一方で、導入を具体的に検討している顕在層には、リスティング広告や導入事例を提示し、意思決定を後押しする情報を提供するのが適しています。
◉-3、一貫性のある継続的な情報発信を行う
BtoB広告は、長期的に一貫性のある発信を続けることが信頼形成につながります。
なぜなら、企業の購買行動は一度の接触で即座に契約に至ることは稀であり、繰り返し情報に触れる中で徐々に信頼関係が深まっていくからです。
ブランドのトーンやビジュアルを統一し、複数の広告チャネルで同じメッセージを発信し続けることで、「信頼できる企業」「業界のリーダー」という印象を形成できます。
結果として、商談機会の創出にもつながるでしょう。
◉-4、複数の広告チャネルと発信媒体を連携させる
BtoB広告の効果は、単一の広告チャネルだけでは限定的です。
検索広告やSNS広告、展示会、オウンドメディアなどを組み合わせ、一貫した導線を設計することで、接触から商談までの流れをスムーズにできます。
たとえば、リスティング広告で資料請求を促し、その後メールマーケティングやウェビナー案内につなげるという流れを作ることで、段階的に関心を高める施策が可能です。
広告以外にも実施しておくべき!法人向けのアプローチができる有効なマーケティング手法

法人向け広告(BtoB広告)は、見込み顧客との接点をつくるうえで強力な手段ですが、広告だけでは継続的な関係構築まで発展しにくい場合があります。
そのため、より高い成果を得るためには、広告以外のマーケティング手法も検討することが重要です。
ここでは、BtoB広告の効果を高めるために有効な施策として、次の4つを紹介します。
- 企業出版
- ホワイトペーパー
- SEO
- ウェビナー・セミナー
以下では、それぞれの特徴を解説します。
◉-1、企業出版
企業出版(ブックマーケティング)とは、自社の専門知識やノウハウ、企業理念などを一冊の書籍にまとめて発信するマーケティング手法です。
ほか、カスタム出版と呼ばれることもあります。
広告のような短期的な拡散力はないものの、読者との深い信頼形成とブランド価値の向上を実現できる点が特徴です。
◉-1-1、企業やブランドの信頼性と権威性を示せる
書籍出版は、出版社や編集者による第三者の審査・編集工程を経るため、広告よりも信頼性と客観性が高い情報発信手段とみなされます。
経営者や専門家が自らの知見や経験を体系的にまとめることで、業界内での専門性やリーダーシップを明確に打ち出し、ブランドの権威性を強化することが可能です。
特にBtoB取引では、「本を出版している企業」というだけで信用度が上がるケースが多く、営業活動における信頼獲得にも効果的です。
◉-1-2、広告クリエイティブやリード獲得に転用できる
書籍を出版した後は、タイトルや内容をもとにした広告展開へと発展させることが可能です。
たとえば「著書『〇〇戦略の教科書』の著者が語る──」といったコピーを広告に使用すれば、クリック率やコンバージョン率の向上が期待できます。
さらに、書籍内容を再構成してホワイトペーパーやLP(ランディングページ)のコンテンツに活用すれば、リード獲得から商談促進までの一貫した導線づくりが可能です。
また、「書籍プレゼント」をフックとしたキャンペーンを実施することで、問い合わせや資料請求といったリード獲得につなげる方法もあります。
書籍自体が信頼性の高いコンテンツであるため、ユーザーの関心を引きやすく、質の高い見込み顧客を集める効果が見込めます。
◉-1-3、長期的な資産になる
企業出版の強みは、長期にわたって効果が持続することです。
広告は出稿期間が終わると効果が途切れてしまいますが、書籍は書店やAmazonなどで長期的に流通し、発行から数年経っても新たな読者に届く可能性があります。
つまり、企業出版は企業の信頼性や専門性を積み重ね、時間とともにブランド価値を高め続ける長期的なマーケティング資産となるのです。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

◉-2、ホワイトペーパー
ホワイトペーパーは、企業の課題や業界動向を整理し、自社の解決策を分かりやすくまとめたコンテンツです。
BtoB広告で集客した見込み顧客に対して、「資料ダウンロード」というアクションを促すことで、リード情報を効率的に獲得できます。
また、自社の専門性や信頼性を伝えることができるため、営業活動の前段階で顧客の関心を高める効果もあります。
◉-3、SEO
SEOは、企業が長期的に顧客との接点を増やすための基本施策です。
広告は即効性がある一方で、出稿を止めると流入が途切れてしまいます。
しかしSEO対策を施したコンテンツは、検索結果に長期間表示され、継続的なリード獲得につながります。
短期の広告成果と中長期の自然流入を両立できる点が、SEOを取り入れる最大のメリットです。
▶︎SEOのやり方については、関連記事【SEO対策とは? 効果的な戦略の組み立て方と対策方法】もあわせて参考にしてください。
◉-4、ウェビナー・セミナー
オンライン・オフラインを問わず、セミナーはBtoB広告との相性が良い施策です。
広告で集客した見込み顧客をウェビナー・セミナーに誘導し、講演や質疑応答を通じて自社の専門性や実績を伝えることで、商談化率を高めることができます。
また、企業出版と組み合わせることで相乗効果も期待できます。
たとえば「書籍購入者限定ウェビナー」や「セミナー参加者特典として書籍プレゼント」といった企画を実施すれば、セミナー集客の強化や参加者の満足度向上にもつながります。
企業出版で法人にアプローチし、広告以上の価値を創出した事例
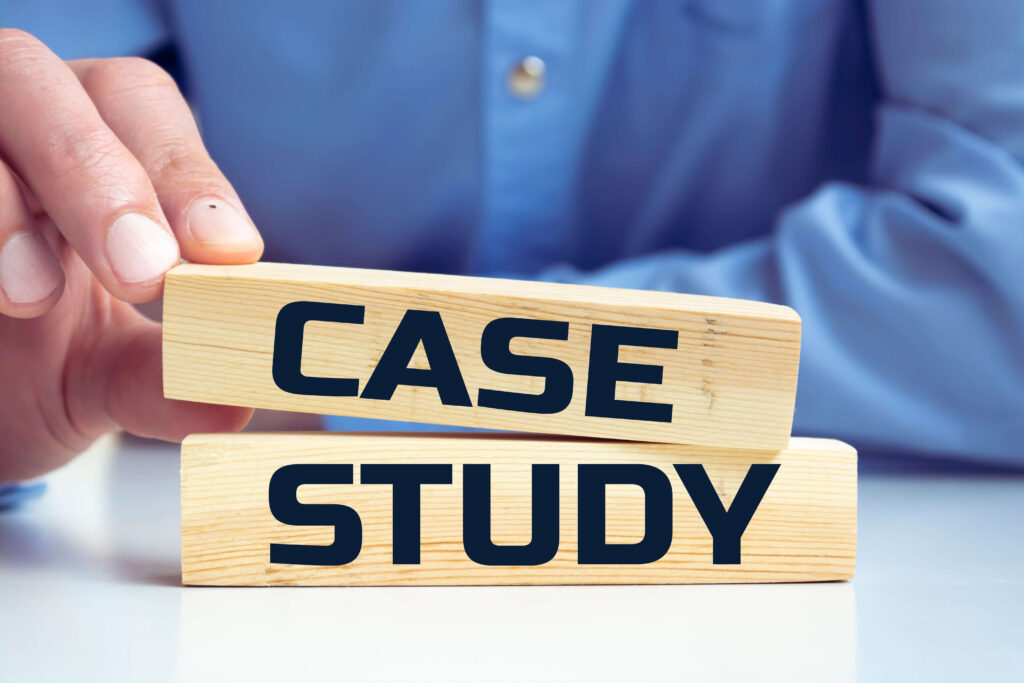
ここでは、実際に企業出版を活用して法人顧客との信頼関係を構築し、広告では得られない成果を上げた事例を3つ紹介します。
- 書籍出版によって集客と商圏拡大を実現した事例
- 新規事業の契約獲得に成功した法人向け保険代理店
- 海外案件の専門家という地位を確立した公認会計士事務所
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、書籍出版によって集客と商圏拡大を実現した事例
BtoBマーケティングのコンサルティング会社では、自社で取り扱ったデジタルマーケティングの事例を紹介する書籍を出版しました。
企業数が多い東京・大阪エリアを中心に、ビジネスマンの来店が多い主要書店への集中配本を実施。
また、経営者層・ビジネスパーソン向けフェアに積極的に参加し、日経新聞への掲載や書店での露出を強化する広告戦略を展開しました。
その結果、出版から半年で大手企業の課長級以上を中心に20〜30件の問い合わせを獲得し、約10件の受注に成功。
なかには、関西など遠方企業とのテレビ会議によるクロージングで成約したケースもあり、商圏の拡大にもつながりました。
さらに、コンペになった際に書籍を送ったことで、それが決め手になり受注に至るなど、書籍がクロージングツールとしての役割を果たしました。
以前はWeb広告に月間100万円ほどを投下していましたが、その後数万円程度の運用で安定的にリード獲得を継続しています。
◉-2、新規事業の契約獲得に成功した法人向け保険代理店
法人向け保険を扱う代理店は、新規事業の顧客獲得と業界内での差別化を目的に、自社の人材育成や経営理念をテーマにした書籍を出版しました。
保険代理店は全国に数多く存在し、扱う商品での差別化が難しい業界です。
そこで、「人材が育ち、組織が強くなる保険代理店経営」という独自の哲学を提唱し、業界に一石を投じる内容にしました。
結果として、出版直後から反響を呼び、同業他社からのコンサルティング依頼や保険会社からの講演依頼が相次ぎました。
特に、書籍を読んで共感した経営者が法人契約につながるケースが増加。
営業担当が面談前に書籍を送付すると、相手が事前に経営理念を理解してくれており、初対面の商談でも「価値観が共有された状態」でスタートできるようになったといいます。
書籍は単なる営業資料ではなく、信頼を育むコミュニケーションツールとしての役割も担っています。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-3、海外案件の専門家という地位を確立した公認会計士事務所
国際税務・監査を専門とする公認会計士は、独立開業のタイミングで、自身の専門性を社会に発信するマーケティング手段として書籍を出版しました。
書籍では、海外進出を検討する日本企業に向けて、グローバル展開時に起こりやすい税務・会計上のトラブルや、現場で培った解決策を実例とともに紹介。
難解になりがちな国際税務・監査のテーマを、小説仕立てのストーリー形式でわかりやすく伝える構成としました。
出版後は、SNSや同業ネットワークで話題となり、同業者からの紹介案件やセミナー登壇依頼が急増しました。
出版を通じて「海外案件に強い会計士」という明確なブランドポジションを確立。
出版からわずか半年で、大手企業の海外進出支援や国際取引をめぐる相談が相次ぎ、事業立ち上げの起爆剤となりました。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
【まとめ】BtoB広告に加えて、信頼を生むマーケティング施策を展開しよう
この記事では、BtoB広告の種類や成果を出すためのポイント、企業出版を活用した成功事例を紹介しました。
BtoB広告で成果を上げるためには、ターゲットの関心レベルに合わせたメッセージ設計と、デジタル広告とオフライン広告を連携させた複数チャネルの活用が重要です。
フォーウェイでは、書籍をマーケティングに活用する「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
広告施策と書籍出版を組み合わせることで、顧客との信頼関係を深化させるとともに、新たな顧客層へのアプローチも可能となります。
BtoBビジネスで継続的な成果を上げるための手段として、企業出版に興味を持たれた方は、ぜひ一度お問い合わせください。


昨今のビジネスでは、SNSやブログ、動画チャンネル、冊子といった各種のコンテンツを活用したマーケティングが必須となりました。
一方で、「発信するネタが思いつかない」「社内のリソースが不足している」「効果的な発信方法がわからない」といった課題から、なかなか施策を進められない企業も少なくありません。
しかし実際には、コンテンツマーケティングを戦略的に活用し、成果を上げている企業も多くあります。
そこでこの記事では、企業の経営者・経営企画担当者に向けて、コンテンツマーケティングの成功事例を12選紹介し、成果を出すための共通点について解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
【BtoB】コンテンツマーケティングの事例7選
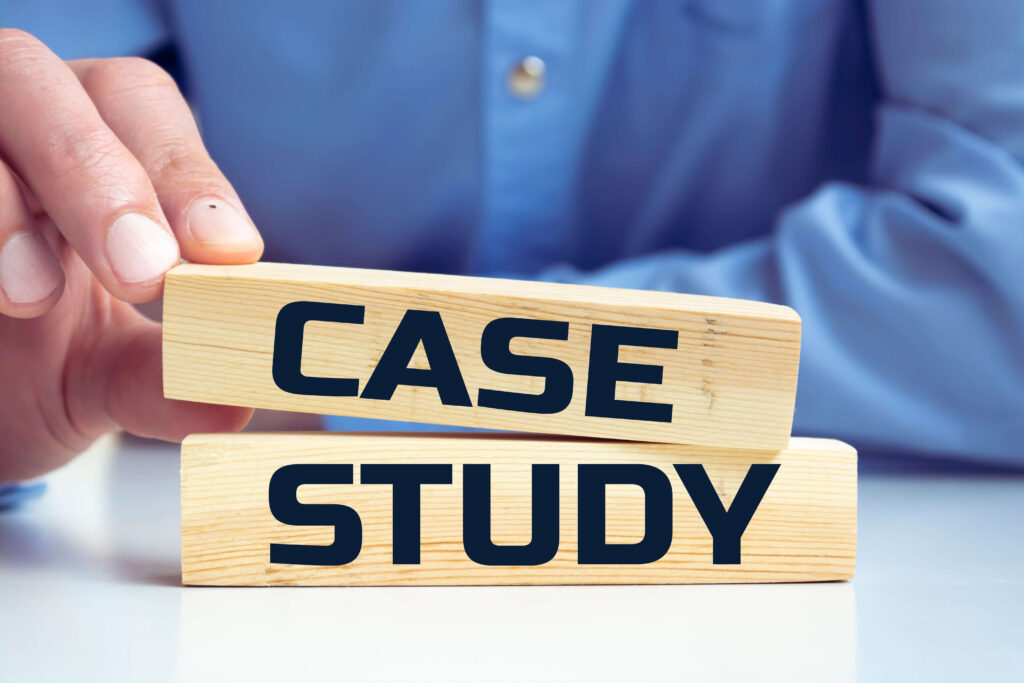
まず、BtoBビジネスでコンテンツマーケティングに成功した事例7選を紹介します。
・保険代理店|新規事業開拓とコンサル契約を獲得した事例
・経営コンサル会社|書籍出版で重版・ニュース掲載を獲得、新規顧客増につなげた事例
・不動産投資塾|SEOコラムで検索上位を独占し、売却相談を大幅増加させた事例
・企業出版会社|SNS運用で1,000万円の売上につながった事例
・建設会社|採用強化とブランド力向上を実現した事例
・医療コンサル会社|病院再建ノウハウを体系化し、売上12億円を達成した事例
・危機管理コンサル会社|出版で社会的注目を集め、重版達成と新規10件受注につながった事例 |
以下で、それぞれの事例について詳しく見ていきましょう。
◉-1、保険代理店|新規事業開拓とコンサル契約を獲得した事例
法人専門の保険代理店は、新たに立ち上げたコンサルティング業において、信頼を獲得し効果的に集客する方法を検討していました。。
そこで、自社の強みや経営ノウハウを体系的にまとめた書籍を出版しました。
出版後、業界内での認知度が一気に高まり、複数のコンサル契約を獲得することに成功。
また、大手の保険会社から講演や共同マーケティングの声がかかるなど、予想以上の反響がありました。
商談の場では顧客が事前に書籍を読んでくれていることが多くなり、経営課題についての相談を受けるなど、法人保険の大口契約や新規コンサル契約の成約につながりました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、経営コンサル会社|書籍出版で重版・ニュース掲載を獲得、新規顧客増につなげた事例
建設業専門の経営コンサル会社は、既存の顧客基盤に加えて新規案件の獲得とブランド強化を目的に書籍を出版しました。
タイトルに「建設業のための」と追記してターゲットを明確化することで、発売1か月で重版が決定し、累計発行部数は5,000部を突破。
また、書籍の新聞広告を実施したことで、Amazonや書店では売り切れが続出。
反響の大きさから、ターゲットとなる大手建設会社からも「この本はどこで買えますか?」と出版社宛に問い合わせが寄せられるほどでした。
さらに、大手メディアのニュースやWeb媒体でも紹介され、知名度が一気に向上しました。
その結果、顧客からの問い合わせが急増し、10件以上の新規コンサル契約を獲得。
出版により、首都圏を中心とした商圏拡大にも成功し、建設業界における専門コンサルタントとしてのブランドを確立しました。
◉-3、不動産投資塾|SEOコラムで検索上位を独占し、売却相談を大幅増加させた事例
不動産投資塾では、ブランディングの強化と認知度向上、そしてWeb経由での不動産売却相談の増加を目指してSEO施策を実施しました。
注力したのは、投資オーナーが特に気になる「失敗事例」や「投資の落とし穴」といったテーマを扱ったコラム配信です。
業界トレンドを分析し、読者が求めるテーマを的確に選定したうえで、毎月複数本のSEOコラムを継続的に公開しました。
その結果、検索順位は大幅に上昇し、コラムを毎月5~10本追加するたびにアクセス数は堅調に推移。
さらに、検索からの流入が競合を上回り、売却相談件数も大きく増加しました。
◉-4、企業出版会社|SNS運用で累計2,000万円の売上につながった事例
企業出版を手がける会社では、SNSを活用した情報発信に注力しました。
代表者自身のアカウントを軸に、出版に関心を持つ経営者層やビジネスパーソンに向けた発信を継続したところ、多くのフォロワーを獲得し業界内外からの認知度を高めました。
結果として、SNS経由のアプローチだけで累計2,000万円単位の売上につながっています。
さらに、コラボ商材販売につながる多数の協業依頼や、フォロワーからの紹介による受注案件も発生しました。
◉-5、建設会社|採用強化とブランド力向上を実現した事例
湘南エリアで成長を続ける建設会社では、慢性的な人材不足が深刻な課題でした。
せっかくの受注機会を十分に活かせない状況が続いていたため、成長にブレーキがかかっていました。
そこで、若手人材の採用強化と企業ブランド力の向上を目的に、自社の想いを込めた書籍を出版。
経営者の仕事観や経営哲学、そして創業ストーリーを丁寧に盛り込み、「この会社で働きたい」と地域の若手に感じてもらえる内容に仕上げたのです。
その結果、事前に書籍を読んでから面接を受ける応募者が増加し、採用決定率が向上。
年間500万円以上かかっていた採用エージェントの費用を削減することに成功しました。
さらに、出版をきっかけに地元紙など複数のメディアから取材を受けるようになり、地域での知名度が大きく向上し、一目置かれる存在になりました。
◉-6、医療コンサル会社|病院再建ノウハウを体系化し、反響売上12億円を達成した事例
医療機関の経営改善を支援するコンサル会社は、病院再建のノウハウを体系化して広く伝えることを目的に書籍を出版。
書籍では、病院経営の現場で培った具体的な再建手法や運営戦略をわかりやすく解説し、経営層が直面する課題を整理し、実践的な解決策を提示する内容としました。
出版に際して、医療法人や地域の病院理事長、事務長層をターゲットにして、医療系専門誌やビジネス誌を活用した広告・PRを展開し、業界内で大きな注目を集めました。
書籍の内容をテーマにしたセミナーや講演依頼も相次ぎ、出版後1年間で11件の登壇機会を獲得。
結果として、出版から1年で40件の契約を獲得し、反響売上は12億円を達成しました。
書籍出版によって、医療機関の再建に特化した専門コンサルとしての地位を確立しています。
◉-7、危機管理コンサル会社|出版で社会的注目を集め、重版達成と新規10件受注につながった事例
保育園の経営改善を支援する危機管理コンサル会社は、著者ブランディングと認知度向上を目的に書籍を出版しました。
社会問題化していた「待機児童」などの話題を織り込み、読者の関心を引きやすいタイトルを設定。
東名阪の大手書店を中心に配本を行い、業界関係者や保護者層の注目を集めました。
社会的テーマ性の強い内容であったため、メディア掲載も相次ぎ、出版直後から大きな話題になりました。
その結果、読者からの相談依頼が相次ぎ、新規で10件のコンサル契約を獲得。
書籍は短期間で重版が決まり、累計発行部数は6,000部を突破しました。
新聞や雑誌などの特集記事でも取り上げられ、認知度と信頼性が一段と高まりました。

【BtoC】コンテンツマーケティングの事例5選

次に、BtoCビジネスでコンテンツマーケティングに成功した事例5選を紹介します。
・サプリメントメーカー|顧客のファン化が加速!想定6倍の応募とリピート率アップを実現した事例
・省エネ一括査定サイト|予算比で想定を上回る成果を上げた事例
・会員ビジネス|信頼性を獲得し、ランキング1位と新規会員500人を獲得した事例
・食材メーカー|“わさび”の効能・文化を啓蒙し、理解促進と販売拡大を実現した事例
・不動産投資会社|医師に特化し、半年で10億円の売上につながった事例 |
以下で、それぞれの事例について詳しく見ていきましょう。
◉-1、サプリメントメーカー|顧客のファン化が加速!想定6倍の応募とリピート率アップを実現した事例
女性向けサプリメントを展開するサプリメントメーカーは、既存顧客との関係強化と新規顧客獲得の両立を目的に書籍を出版しました。
出版の狙いは、自社の信頼性を高めつつ「ファン化」を加速させ、LTV(ライフタイムバリュー)の向上につなげること。
書籍の刊行にあたっては、代表者自身の経験や健康に関する考え方をまとめ、読者にとって役立つ実用的な内容に仕上げました。
また、既存顧客向けに「書籍無料プレゼント」キャンペーンを展開したところ、想定を大きく上回る6倍もの応募が寄せられる結果になりました。
書籍をきっかけに企業や商品の背景を理解してもらえるようになり、購入者のリピート率が向上。
自社メディアやカスタマーサポートによる継続的なコミュニケーションとあわせて、ブランドへの信頼が高まりました。
▶︎サプリメントメーカーの詳しい事例については【【事例コラム】”書籍無料プレゼント”に想定の6倍の応募、リピート率アップにインパクト!サプリメントメーカーの出版プロジェクト】もあわせて参考にしてください。
◉-2、省エネ一括査定サイト|予算比で想定を上回る成果を上げた事例
省エネ関連の一括査定サービスを運営する企業では、SEOを中心とした集客施策に取り組みました。
特に検索需要の高い「太陽光発電 補助金」「太陽光発電 メーカー」などのキーワードを重点テーマに設定し、記事の品質向上に注力。
さらに、記事内にわかりやすい図解を挿入したり、CTAリンクの配置を最適化したりすることで、コンバージョン率の改善も図りました。
その結果、2024年上半期には、サイトAで予算比160%、サイトBで130%という成果を達成。
想定を大きく上回る結果となり、見込み顧客の流入増加を通じて事業全体の成長につながりました。
◉-3、会員ビジネス|信頼性を獲得し、ランキング1位と新規会員500人を獲得した事例
会員制ビジネスを展開する企業は、自社が提唱する「耳ツボダイエット」の信頼性と有用性を広く訴求するために書籍を出版しました。
書籍の中では、成功事例や会員の声を数多く紹介することで、読者が安心してプログラムに参加できるよう工夫し、「入会したい」と思わせるきっかけを作りました。
また、出版にあたっては、書籍へのリーチ機会を最大化するために広告施策や告知活動に注力。
全国の書店流通と並行して積極的な広報展開を行った結果、Amazonの「ビジネス実用書」カテゴリで1位を獲得するといった反響を呼びました。。
その結果、「ビジネス実用書」カテゴリで1位を獲得する快挙を達成しました。
出版後は、大規模なセミナーを全国で開催し、結果として半年間で新規会員が500人以上増加。
既存会員からの信頼度もさらに高まり、ブランディングと集客の両面で大きな成果を上げました。
◉-4、食材メーカー|わさびの効能・文化を啓蒙し、理解促進と販売拡大を実現した事例
わさびの製造・販売を行う食材メーカーでは、「商品の魅力が十分に伝わっていない」「他社との差別化が難しい」といった課題を抱えていました。
そこで、料理や健康に関心の高い30〜40代女性をメインターゲットに、わさびの効能や文化的背景、アレンジレシピをわかりやすく紹介する書籍を出版しました。
出版後には、レシピを監修した料理研究家を招いて名古屋の大型書店でトークイベントを実施。
会場は大盛況となり、その場で50冊以上を販売する成果を収めました。
このイベントをきっかけに、わさびの効能や楽しみ方に関する理解が広がり、ファン獲得につながりました。
また、出版を契機として平均聴取者数20万人を超える人気ラジオ番組から出演オファーを受け、2週連続で放送に登場。
さらに、自社営業マンが取引先への営業活動で書籍を配布・活用したことで、大口契約も獲得しています。
◉-5、不動産投資会社|医師に特化し、半年で10億円の売上につながった事例
ある不動産投資会社は、医師を明確なターゲットとして書籍を出版しました。
高収入ながらも税負担が大きい医師に対し、「不動産投資こそが最も効果的な節税対策である」ことを訴求し、関心を高めることを狙ったのです。
書籍では、まず「医師が抱えるお金の悩み」を提示して共感を引き出し、次に「医師に不動産投資が適している10の理由」を論理的に解説しました。
さらに「どのような物件を購入すべきか」を具体的に示すことで、読者が自然と投資に前向きになるように構成。
出版後は、書籍をきっかけに数多くの医師から問い合わせが寄せられ、その多くが不動産投資案件の成約につながりました。
その結果、書籍出版からわずか半年で10億円規模の売上を達成しました。

成功事例に共通するコンテンツマーケティングの特徴

これまでに説明してきた成功事例12選に共通する特徴は、次の4つです。
・明確なターゲット設定
・一貫性のあるブランドメッセージ
・価値ある情報提供
・SEO・SNS・メール・セミナーなどの連動 |
以下で、コンテンツマーケティングで成功するための秘訣について詳しく見ていきましょう。
◉-1、明確なターゲット設定
成功しているコンテンツは「誰に届けるのか」が明確になっています。
年齢・性別・職業・価値観・課題などを具体的にイメージし、ペルソナ設定を行ったうえで、その人が求める情報や解決策を提供しています。
「より多くの人に見てもらいたい」と思って、ターゲットがぼやけてしまうと、結果的に誰にも届かないコンテンツとなり、成果も出にくくなるのです。
ターゲットをあいまいにせず、ペルソナ設計や顧客の課題分析を行った上でコンテンツを企画することが大切です。
◉-2、一貫性のあるブランドメッセージ
成功しているコンテンツに共通しているのは、常に「ブランドらしさ」を意識して発信していることです。
ブログ記事やSNS投稿、メールマガジンなど、発信の場は違っても一貫したトーン&マナーでメッセージを伝え続けています。
そのため、ユーザーの頭の中に「この企業といえば〇〇」という認知が定着しやすくなります。
「自社が何を提供できるのか」「どのような価値を社会に示すのか」を明確に言語化し、すべてのチャネルで統一したメッセージを伝え続けることが重要です。
◉-3、価値ある情報提供
広告色や売り込み色の強いコンテンツではなく、ユーザーにとって有益な情報を提供することも成功のポイントです。
たとえば、悩みを解決するノウハウや業界トレンド、専門知識といった「読むだけで得をする」コンテンツは、自然とユーザーの信頼を獲得し、最終的に商品やサービスの利用につながります。
「価値提供の積み重ね」が潜在顧客との関係構築を生み出し、結果として購買につながるのです。
◉-4、SEO・SNS・メール・セミナーなどの連動
成功事例の多くでは、単発施策ではなくSEO・SNS・メール・セミナーなど複数チャネルを戦略的に連動させています。
たとえば、SEOで検索流入を確保し、SNSで拡散して認知を広げ、メールで深い関係性を築き、セミナーで直接の信頼を得るといった流れです。
チャネル同士を連携させることでユーザー接点が増え、成果が相乗的に高まる仕組みをつくれます。
【まとめ】成功事例を参考にしてコンテンツマーケティングで成果を出そう
この記事では、コンテンツマーケティングの成功事例12選を紹介し、成果を出すための共通点が何かを明らかにしました。
コンテンツマーケティングは、今や多くの企業にとって欠かせない施策となっています。
しかし、ただ発信を続けるだけでは思うような成果は得られません。
成功事例に共通しているのは、明確なターゲット設定、一貫したブランドメッセージ、価値のある情報提供、そして複数チャネルを連動させる仕組みです。
フォーウェイでは、書籍を活用した「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
「相手に伝わるコンテンツ」を「顧客へ伝わるコンテンツ」に変換して、顧客との関係構築やブランド価値向上に貢献します。
書籍出版に興味を持たれましたら、ぜひフォーウェイまでお問い合わせください。


経営者向けの広告は、一般的な営業手法や従来型の広告展開とは異なる特徴があります。
その理由として、経営者は多忙であり、限られた時間の中で効率的に情報収集を行い、会社の将来を左右する意思決定を下しているからです。
もし広告が経営者に響けば、短期間で導入や商談につながる可能性が高まるでしょう。
一方で、経営者向け広告は単なる露出だけでは効果を発揮しにくく、ターゲットに適した媒体や手法を選ぶことが欠かせません。
さらに、広告だけでは信頼関係を築いたり、潜在的なニーズを探り出したりするのは難しいため、広告以外の取り組みも合わせて行うことが重要です。
この記事では、広告戦略を検討している企業経営者や事業責任者の方に向けて、経営者向け広告の特徴や代表的な手法、広告以外の有効なアプローチ方法などについて詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
経営者向けに特化した広告出稿は効果的!

経営者は最終的な意思決定権を持ち、企業の方向性を左右する重要な立場にあります。
そのため、経営者に特化した広告には、次のような効果が期待できるのです。
・意思決定者に直接リーチできる
・非効率な営業活動をなくせる |
以下で、それぞれの効果について詳しく解説します。
◉-1、意思決定者に直接リーチできる
経営者は、商品やサービスの最終的な導入可否を決定します。
従来の広告手法では、まず担当者にアプローチし、そこから社内稟議を経て、ようやく経営者の決裁にたどり着くという長いプロセスを踏むのが一般的です。
その過程で、経営者に情報が届く前に却下されてしまうリスクも少なくありません。
もし経営者に直接リーチできれば、導入までのスピードを大きく短縮できることになります。
◉-2、非効率な営業活動をなくせる
多くの経営者は多忙なため、知らない電話や飛び込み営業に対応することはほとんどないでしょう。
そのため、従来の営業スタイルでは門前払いになりやすく、労力に見合う成果が得られにくいのです。
そこで有効なのが経営者向けに特化した広告の活用です。
経営者が自ら課題解決のための情報収集を行うタイミングで広告を提示できれば、関心を持ってもらえる確率が高まります。
結果として、無駄な営業活動を減らし、効率的に質の高いリードを獲得することが可能になります。
営業担当者は商談や提案に集中できるようになるので、より早く成果を出すことにつながるのです。
経営者向け広告は大きく分けて2種類

経営者に向けた広告は、次の2種類に分けることができます。
・オフライン広告|経営者が接触する媒体や場所に出稿する
・デジタル広告|特定の属性を持つ経営者に絞り込んでアプローチする |
以下では、それぞれの広告の具体的な方法について解説します。
◉-1、オフライン広告|経営者が接触する媒体や場所に出稿する
オフライン広告は、経営者が直接接触する機会の多い場所やシーンを狙って出稿することが重要です。
次のような場所や媒体に広告を出稿することで、効果的に認知を高めることができます。
・タクシー広告
・新幹線・飛行機内の広告
・空港ラウンジ・ゴルフ場での広告
・ビジネス誌・業界専門誌への広告掲載 |
4つの広告を見ていきましょう。
◉-1-1、タクシー広告
経営者は取引先への訪問や会合への移動などでタクシーを利用する頻度が高く、広告展開において有効な接点となります。
特に、車内モニターの動画広告や後部座席に貼られるステッカー広告は、移動中に自然と視界に入るため、訴求力が高いです。
◉-1-2、新幹線・飛行機内の広告
長距離移動の際に利用することが多い新幹線や飛行機も、経営者と接触できる場です。
座席前の情報誌や機内映像に広告を掲載すれば、移動中に自然と目に留まり、無理なくブランドを印象づけることが可能です。
◉-1-3、空港ラウンジ・ゴルフ場での広告
空港ラウンジやゴルフ場も、経営者が多く集まる場所です。
リラックスした状態で広告に触れることで、心理的な受け入れやすさも高まり、ポジティブなブランドイメージが形成されやすくなります。
◉-1-4、ビジネス誌・業界専門誌への広告掲載
情報収集に熱心な経営者は、ビジネス誌や業界専門誌を購読していることが多いため、これらの媒体への広告掲載は効果的です。
信頼性の高い媒体に掲載されることで、広告自体も価値ある情報として受け取られやすくなります。
◉-2、デジタル広告|特定の属性を持つ経営者に絞り込んでアプローチする
デジタル広告の場合も、経営者が持つ属性をターゲットとしてアプローチすることが有効です。
主なデジタル媒体としては、次のようなものがあります。
・SNS広告
・動画広告
・リスティング広告・ディスプレイ広告
・メール広告・DM |
それぞれ解説します。
◉-2-1、SNS広告
FacebookやInstagram、X(旧Twitter)やLinkedInなど、ビジネス層が積極的に利用するSNSは、経営者をターゲティングしやすい媒体です。
特にFacebookやInstagramは利用者数が多く、興味・関心や行動履歴に基づいたターゲティング精度が高いため、幅広い業界の経営者やビジネス層に効率的に広告を届けられます。
また、X(旧Twitter)は、情報の拡散性とリアルタイム性に優れており、経営者が業界動向や最新情報を収集する場として活用されるため、タイムリーな広告展開に適しています。
さらに、世界最大級のビジネスSNSのLinkedInは役職・業種・企業規模などで精緻なセグメント配信が可能で、意思決定者に直接リーチできることが特徴です。
経営者は情報収集や人脈形成の目的でSNSをチェックするため、自然な形で広告が目に留まりやすい環境が整っています。
◉-2-2、動画広告
短時間で強い印象を与えられる動画は、企業の経営理念やサービス価値を端的に伝える手段として効果的です。
テキスト広告や静止画広告に比べ、視覚と聴覚の両方に訴求できるため、記憶に残りやすいのが特徴です。
YouTubeのインストリーム広告や、ダイヤモンド・オンライン、日経ビジネス電子版などのビジネス系メディアでの動画枠を活用すれば、経営者がビジネス情報を収集しているタイミングで自然に接触できます。
◉-2-3、リスティング広告・ディスプレイ広告
経営者は課題解決のために、自ら検索エンジンで情報を調べるケースが少なくありません。
たとえば、「業務効率化」「資金調達」「M&A」「人材採用」など、経営者が検索しやすいキーワードに合わせて広告を出稿することで、ニーズが顕在化している層に的確にアプローチできます。
また、ディスプレイ広告を組み合わせれば、経営者が閲覧するビジネスメディアやニュースサイトで再度接触を図れるため、認知から検討、導入までをスムーズに促進することが可能です。
◉-2-4、メール広告・DM
ターゲットリストを活用したメールマーケティングやダイレクトメールは、経営者に直接広告を届けられる手段です。
特に経営層は日常的に多くのメールや郵送物に目を通すため、適切に設計されたメッセージであれば接触できる可能性が高いのです。
また、セグメントを絞り込み、関心度の高い層にピンポイントで届ければ、効率的に商談機会を創出できます。
経営者向け広告だけでは不十分!ほかのアプローチ方法も必要な理由

経営者に特化した広告は、認知や関心を高めるうえで大きな効果を持っています。
しかし、それだけに依存してしまうと成果が限定的になってしまいかねません。
主な理由として、次の3つが挙げられます。
・広告だけでは深い信頼関係を築けないから
・潜在的なニーズを掘り起こせないから
・他社との差別化が難しいから |
以下で、それぞれどのような理由なのかを見ていきましょう。
◉-1、広告だけでは深い信頼関係を築けないから
広告は「認知」や「関心」を広げるには効果的ですが、どうしても一方的な情報発信になりがちです。
経営者は商品やサービスの導入を判断する際に、企業の規模や実績だけでなく、経営理念やビジョン、担当者の人柄なども重視します。
広告だけではこれらを十分に伝えられず、「信頼」や「共感」といった深い関係性を築くのは難しいのが実情です。
また、広告で届けられる情報量が限定的であることも関係性の構築に不十分な要因です。
そのため、広告を通じて興味を持ってもらった後に、最終的な商談や契約につなげるためには、広告以外の方法で信頼を積み重ねることが欠かせません。
◉-2、潜在的なニーズを掘り起こせないから
広告は、すでに課題を明確に認識している経営者には効果的です。
たとえば、「業務効率化」というキーワードで検索している経営者には、解決策となるサービスを提示することができます。
しかし、多くの経営者は自社の課題を明確に言語化できていなかったり、潜在的な問題に気づいていなかったりします。
このような潜在ニーズを掘り起こすには、広告だけでは不十分です。
そこで、セミナーやウェビナー、専門的な質の高いコンテンツを通じて「気づき」を提供することが、初めて見込み客として認識してもらえるきっかけになります。
◉-3、他社との差別化が難しいから
特定の広告媒体は多くの企業が利用するため、競合他社の広告と並んで表示されることも少なくありません。
似たような広告が並ぶ中で、自社の強みや差別化ポイントを明確に伝えることはなかなか困難です。
そこで有効なのが、広告以外のアプローチ方法です。
たとえば、書籍出版やイベント登壇、専門性の高いオウンドメディアなどは、自社のユニークな価値や専門性を深く伝えることができ、競合との差別化につながります。
広告だけに頼らず、他のアプローチを組み合わせることで、経営者の記憶に残る存在になることができます。
経営者に届く!広告以外のアプローチ方法

広告は経営者に認知や関心を持ってもらう有効な手段ですが、信頼関係を築いたり、経営者自身がまだ自覚していない潜在的なニーズを掘り起こしたりするには限界があります。
そこで重要になるのが、広告以外の直接的かつ継続的なアプローチです。
ここでは、経営者に届く代表的な方法として、次の4つを紹介します。
・セミナー・ウェビナーの開催
・コンテンツマーケティングの活用
・業界のイベント・交流会への参加
・書籍出版(ブックマーケティング) |
それぞれどのような方法なのかを具体的に見ていきましょう。
◉-1、セミナー・ウェビナーの開催
経営者が関心を持ちやすいのは、自社の「経営課題の解決」や「業界の最新トレンド」に関する情報です。
セミナーやウェビナーを開催して、単なる商品説明ではなく専門的な知見や将来の展望を提示することで、信頼性と権威性を築くことにつながります。
また、リアルタイムで質疑応答できる点も経営者にとっては魅力的で、リード獲得や商談のきっかけになります。
◉-2、コンテンツマーケティングの活用
経営者は多忙な中でも「意思決定の参考になる情報」を求めています。
そのニーズに応える手段として、ホワイトペーパーや専門記事、動画などを活用したコンテンツマーケティングがあります。
特に、業界動向の解説や他社の成功事例、専門家によるインタビューなどは実務に直結する情報として価値が高く、経営者の興味を引きやすい内容です。
自社の商品やサービスを直接売り込むのではなく、価値ある情報を提供することで「信頼できる情報源」として認識されることがポイントとなります。
▶︎コンテンツマーケティングのやり方については、関連記事【コンテンツマーケティングとは?期待できる効果や具体的な手法、戦略の練り方まで解説!】もあわせて参考にしてください。
◉-3、業界のイベント・交流会への参加
経営者が集まる展示会や交流会、カンファレンスは、人脈形成や信頼関係を築く場です。
名刺交換や短時間の対話でも、リアルな接触は記憶に残りやすく、後日の商談につながるきっかけとなります。
広告にはない「対面の力」を活かすことで、より強固な関係が築けます。
◉-4、書籍出版(ブックマーケティング)
経営者に強い影響を与える手段として、書籍出版も効果的です。
書籍は深い専門性や実績を体系的に伝えられる媒体であり、広告よりも高い信頼性を持っています。
さらに、出版をきっかけにメディア露出や講演依頼が増えるケースも多く、経営者との接点を増やす効果があります。
特に専門性の高いテーマや経営課題に直結するテーマを扱えば、ターゲット層に深くアピールすることが可能です。
また、先に説明した「セミナー・ウェビナー」や「コンテンツマーケティング」「イベント・交流会」でも、書籍というアイテムを取り入れることによって、さらに効果を上げることができます。
たとえば、セミナーやウェビナーでは、書籍購入者に特典をつけたり、書籍のプレゼントによって集客を図ることができます。
コンテンツマーケティングでは、自社に著作権のある書籍の内容を引用するなどの横展開が可能です。
イベントや交流会では、書籍を持参して自己紹介のネタにしたり、書籍を出版していることで権威性を示したり、名刺代わりに書籍を配布して商談につなげたりと、幅広く活用できます。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

書籍出版で経営者にアプローチした事例

ここでは、実際に書籍出版を通じて経営者にアプローチした事例を3つ紹介します。
・出版で問い合わせの質が向上、受注単価2倍を実現した経営コンサルタント
・出版をきっかけに大型案件・人材・講演依頼が次々と舞い込んだ保険代理店
・出版1か月で即重版!ニュース掲載や新規顧客を獲得した建設業コンサルタント |
3つの事例を見ていきましょう。
◉-1、出版で問い合わせの質が向上、受注単価2倍を実現した経営コンサルタント
ある経営コンサルタントは、中小企業の経営者をターゲットに、自社の専門知識や実績を体系的にまとめた書籍を出版しました。
その結果、経営者層からの問い合わせが急増し、従来とは質の異なる顧客層を獲得できるようになりました。
特に、専門性と信頼性を評価して依頼してくれる経営者が増加し、結果として受注単価は出版前の2倍以上に向上。
相談件数も3〜4倍に拡大し、無料相談やコンサルティング指導も「1か月待ち」の状態となったと言います。
書籍出版によって「専門家としてのブランド」が定着し、同業他社との差別化、優秀な人材の獲得にもつながりました。
◉-2、出版をきっかけに大型案件・人材・講演依頼が次々と舞い込んだ保険代理店
ある法人保険代理店は、自社の経営ノウハウや人材育成の考え方をまとめた書籍を出版しました。
出版直後から経営者層や同業の保険代理店からの問い合わせが急増し、これまでアプローチできなかった層からの経営相談が数多く舞い込むようになりました。
特に、大型の法人契約が次々と決まるなど、直接的な売上アップに直結。
さらに、保険会社からの講演依頼や同業支援の依頼も増え、「保険会社にとって頼れる代理店」という強いブランドイメージが確立されました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-3、出版1か月で即重版!ニュース掲載や新規顧客を獲得した建設業コンサルタント
ある建設業専門のコンサルタントは、自身の最新ノウハウと豊富な実績をまとめた書籍を出版しました。
新聞広告の掲載をきっかけにAmazonや書店では売り切れが続出。
出版からわずか1か月で重版が決定し、累計発行部数は5,000部を突破しました。
さらに過去の著作との相乗効果も生まれ、シリーズ累計では6万部を超える大ヒットとなりました。
書籍は、livedoor NEWSやLINEニュースなど17媒体に取り上げられるなどメディア露出も拡大。
反響の大きさから、ターゲット層である大手建設会社からも「この本はどこで購入できますか?」と出版社に問い合わせが入るほどでした。
広告では得にくい信頼性と話題性を獲得し、ブランド価値を一気に高めることに成功しました。
【まとめ】広告よりも効果的!書籍出版で経営者にアプローチしよう
この記事では、経営者向け広告の特徴や代表的な手法、広告以外の有効なアプローチ方法、書籍出版の事例などについて解説しました。
経営者に向けた広告は、意思決定者に直接リーチできる点で大きなメリットがあります。
しかし、広告だけでは信頼関係を築いたり、潜在的ニーズを掘り起こすことには限界があります。
そこで有効なのが、広告以上に信頼性が高く、専門性や実績を体系的に伝えることができる書籍出版です。
フォーウェイでは、書籍をマーケティングに活用する「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
企業のブランディングにも直結する手法なので、経営者への新たなアプローチを検討している方は、ぜひフォーウェイまでお問い合わせください。


企業が競争優位を築くうえで、顧客に「真っ先に思い浮かべてもらえる存在」になることは欠かせません。
なぜなら、単に知られているだけでなく、比較検討する前に「思い浮かべてもらえるブランド」は、購買決定の場面で有利な立場になり得るからです。
この「第一想起」をいかにして獲得するかは、経営者や経営企画担当者にとって避けて通れないテーマです。
この記事では、第一想起マーケティングの基本的な考え方や効果的な施策、書籍出版を活用した成功事例などを詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
第一想起マーケティングとは?

「第一想起マーケティング」とは、顧客に特定の分野で「真っ先に思い浮かべてもらえる存在」になることを目指す戦略です。
単に知られているだけでなく、「この分野といえばこの会社」と強く記憶に残ることで、競合と比較される前に選ばれやすくなり、結果として売上の拡大とブランド価値の向上につながります。
ここでは、次の2点について説明します。
以下で、それぞれについて見ていきましょう。
◉-1、第一想起の定義
第一想起とは、顧客が特定のカテゴリーや課題を思い浮かべたときに、最初に連想するブランドのことです。
たとえば「検索エンジン=Google」「ファストフード=マクドナルド」のように、他の選択肢よりも先に頭に浮かぶ状態にあることを指します。
このポジションを獲得できれば、顧客は競合他社を検討する前にそのブランドを基準に考えるため、競合より有利な立場に立つことができます。
また、近年では、第一想起をさらに発展させた考え方として「カテゴリー戦略」も注目されています。
カテゴリー戦略とは、自社が属するカテゴリーそのものを定義づけし、その分野の代表格として認知されることを目指す戦略です。
第一想起と同様に、顧客が他社と比較する前に選ばれやすい効果があり、より大きな視点で市場でのポジションを確立できるのが特徴です。
詳しくは『急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略 頭に浮かべば、モノは売れる』でも紹介されています。
◉-2、認知度・ブランド想起との違い
認知度とは、「顧客がブランドの存在をどの程度知っているか」という度合いを示す指標です。
この段階では必ずしも購買行動につながるとは限りません。
「ブランド想起」とは、顧客が特定の状況や課題に直面したときに、そのブランドを思い出してもらえる状態のことです。
比較検討の候補には入りますが、最初に選ばれるとは限りません。
これに対して「第一想起」とは、顧客に真っ先に思い浮かべてもらえる状態にあることです。
課題解決の場面で真っ先に思い浮かべてもらえるため、顧客の選択の基準になりやすく、購買の対象として選ばれる可能性も高まります。
つまり、認知度を獲得し、ブランド想起を経て、最終的に第一想起へと進むことがマーケティングにおいて理想的なステップだといえます。
第一想起を獲得する!おすすめのマーケティング施策

第一想起を獲得するには、単発的な広告や露出だけでは不十分です。
顧客に「真っ先に思い浮かべてもらえる存在」になるためには、次の4つの施策が挙げられます。
・権威性・信頼性を高める施策
・デジタルでの第一想起を強化する施策
・体験や参加を通じた施策
・ブランド価値を高める施策 |
以下では、それぞれの施策の実践方法について詳しく解説します。
◉-1、権威性・信頼性を高める施策
市場における専門性やリーダーシップを確立することは、顧客からの信頼を得て第一想起につなげるために欠かせません。
特に専門家としての立場を明確に示す施策は、企業や経営者のブランド価値を一段と高めることにつながります。
以下では、権威性・信頼性を高めるための具体的な施策を3つ紹介します。
◉-1-1、書籍出版
専門知識を体系的にまとめて書籍として発信することは、業界内での権威性を確立するうえで有効です。
ネット記事やSNS投稿は情報が断片的になりがちですが、書籍は知識を体系的にまとめることで専門性を示すことが可能です。
また、書籍は書店やオンライン書店を通じて長期間流通し、読者の手元に残り続けるため、広告やWeb記事に比べて記憶に残りやすいという特徴もあります。
さらに、書籍出版はメディア取材や講演依頼のきっかけにもなり、権威性を一段と高める効果が期待できます。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

◉-1-2、調査PR
独自の調査データを発表することは、ニュース性を持たせながら企業の専門性をアピールできる施策です。
たとえば「市場動向」「顧客意識」「業界の最新課題」といったテーマで調査を行い、プレスリリースやホワイトペーパーとして発信することで、新聞・Webメディアに取り上げられる可能性が高まります。
継続的な調査PRによって、「この分野といえばこの会社」という第一想起が定着していきます。
◉-1-3、講演・セミナー登壇
業界イベントやセミナーでの講演や登壇は、専門性を直接アピールできる機会です。
特に、参加者はそのテーマに関心を持つ層であるため、「この分野といえばこの会社」という印象を強く残すことができます。
講演の様子はWeb記事やSNSで紹介されることも多いため、当日の参加者以外にも広く認知を拡大できるのもメリットです。
さらに、質疑応答や懇親会などのリアルな接点を通じて、顧客やパートナー候補との関係性を深められるため、「共感と信頼」を獲得できる点でも第一想起につながります。
◉-2、デジタルでの第一想起を強化する施策
オンラインの場は、顧客が最初に情報に触れる接点です。
検索やSNS、動画といったデジタルチャネルで「真っ先に思い浮かべてもらえる存在」になることが、第一想起につながります。
以下では、デジタルでの第一想起を強化する施策を3つ紹介します。
◉-2-1、SEO・オウンドメディア運営
検索エンジン経由で情報を探す顧客に対しては、SEO対策が欠かせません。
特定のキーワードで上位表示されることで、顧客は情報収集の初期段階からその企業を認識することになります。
さらに、オウンドメディアを継続的に運営し、課題解決型の記事や最新情報を発信することで、「このテーマといえばこの会社」という印象が強化されます。
▶︎SEO・オウンドメディア運営のやり方については、関連記事【SEO対策とは? 効果的な戦略の組み立て方と対策方法】もあわせて参考にしてください。
◉-2-2、SNSマーケティング
SNSで世界観やメッセージを継続して発信し続けることで、ブランドが顧客の頭に残りやすくなります。
コメントやDMなどを通じて双方向の関係を築けるため、「親近感+信頼感」という形で第一想起を強化できます。
また、拡散性が高いため、新規顧客への認知を広げるのにも有効です。
▶︎SNSマーケティングのやり方については、関連記事【【保存版】SNS運用とは?手順や失敗例、集客につなげる運用術を解説!】もあわせて参考にしてください。
◉-2-3、動画マーケティング
動画は顧客の視覚と聴覚に同時に訴求できるため、記憶に残りやすいメディアということができます。
情報の理解を助けるだけでなく、感情に訴えかける力が強いのが特徴です。
製品紹介、顧客事例、ストーリー性のある動画などを活用すれば、第一想起の獲得に効果的です。
▶︎動画マーケティングのやり方については、関連記事【YouTube動画の作り方をカンタン解説!初心者でも再生回数を稼ぐテクニック】もあわせて参考にしてください。
◉-3、体験や参加を通じた施策
ブランドと実際に触れ合う体験は、顧客の記憶に残りやすく、第一想起の形成に直結します。
以下では、体験や参加を通じて第一想起を獲得する施策を3つ紹介します。
◉-3-1、体験型イベント(展示会・ポップアップ)
展示会やポップアップイベントで、直接商品やサービスに触れるというリアルな体験は、顧客に強い印象を与えます。
また、来場者がSNSなどで体験をシェアすれば、オンラインでイベント自体が話題となることもあります。
こうした体験は「記憶に残るブランド」としての地位を確立し、第一想起を高める大きなきっかけになるのです。
◉-3-2、コミュニティ形成
ブランドがコミュニティを運営して、顧客と長期的な関係を築くことができます。
ユーザー会やファンイベントなどを通じた交流によって、仲間意識やブランドへの愛着が強まり、継続的な関係性が構築されるのです。
定期的に関わる場があることで、顧客の頭の中で自然と「真っ先に思い浮かべてもらえる存在」となります。
また、これらの施策はロイヤル顧客の育成にもつながります。
◉-4、ブランド価値を高める施策
第一想起は一過性の施策で築けるものではなく、ブランドそのものの価値を高めることで長期的に形成されます。
以下では、歴史・実績・独自性といった要素を活かしてブランド価値を高める施策を2つ紹介します。
◉-4-1、周年記念誌・社史
周年記念誌や社史は、企業の歩みや成果をまとめた資料であると同時に、信頼性を示す不可欠な媒体です。
長年にわたる歴史を形に残すことで、顧客や取引先には「信頼できる歴史あるブランド」という印象を与え、社員にとっては誇りや結束力を高める機会となります。
このように内外双方への効果が、業界内での第一想起につながる強固な基盤を築いていくのです。
▶︎周年記念誌・社史については、関連記事【周年事業の目的と意義ーー社史・周年史制作のもたらすもの】もあわせて参考にしてください。
◉-4-2、コラボレーション(異業種・有名人とのタイアップ)
異業種とのコラボや有名人とのタイアップは、意外性や新鮮さで話題になりやすく、顧客の記憶に残ります。
たとえば、ファッションブランドが食品メーカーと組んで限定商品を展開したり、人気タレントを起用してオリジナル企画を実施したりすることで、従来の顧客層には驚きを、新たな顧客層には「試してみたい」という興味を喚起できます。
こうした取り組みは、短期的な注目を集めるだけでなく、新たな顧客層の開拓にもつながり、第一想起として選ばれる可能性を高められるでしょう。
また、メディアやSNSでの拡散効果が期待できるため、認知度向上のスピードを高めることが可能です。
書籍の出版が第一想起を獲得するマーケティングに向いている理由

書籍出版は、第一想起を獲得するために有効な施策の一つです。
ここでは、その理由について次の4つのポイントから解説します。
・専門家のポジションを確立できる
・価格競争を回避できる
・メディア露出・二次的波及につながる
・記憶に定着しやすい |
以下で、それぞれについて見ていきましょう。
◉-1、専門家のポジションを確立できる
書籍は、ブログ記事やSNS投稿と異なり、分野ごとの知識を体系的に示すことができる媒体です。
出版を通じて専門家という認知がされやすくなり、「この分野といえばこの人・この会社」という立場が獲得できます。
その結果、第一想起のポジションをより強固に築くことができます。
◉-2、価格競争を回避できる
商品やサービスが一般化して差別化が難しくなると、価格競争に陥りがちです。
しかし、著者としての実績や専門性があると、「安さ」ではなく「信頼性」や「安心感」で選ばれる状況を生み出せます。
結果として、価格を下げなくても顧客が納得して選んでくれるようになり、長期的には付加価値を軸とした健全な競争にシフトしていくことが可能です。
◉-3、メディア露出・二次的波及につながる
出版された書籍は、新聞・雑誌・Webメディアなどで紹介されることが多く、メディア露出のきっかけになります。
実際にフォーウェイが携わったプロジェクトでも、出版をきっかけにメディアからの取材につながった事例は多くあります。
また、書籍を読んだ人が口コミやSNSで発信することで、著者や企業の名前が自然に広まっていきます。
こうした二次的な波及効果は他のマーケティング施策と比べて持続性が高いため、第一想起を長期的に支えることができるのです。
◉-4、記憶に定着しやすい
セミナーや広告が一過性の接触であるのに対して、書籍は紙媒体として手元に残り、長期間読者の目に触れ続けることができます。
そのため、一度読まれた後も本棚に並び続け、必要なときに再び開かれる可能性が高いのです。
さらに、文章を「じっくり読む」という行為そのものが、知識を深く理解させ、著者や企業の存在を記憶に強く刻み込みます。
結果として、読者の頭の中で「このテーマといえばこの人・この会社」というイメージが定着し、第一想起を持続的に高めることにつながります。

書籍出版で第一想起を獲得したマーケティング事例

書籍出版を通じて第一想起を獲得した事例は多く存在します。
出版は単なる自己表現の手段ではなく、顧客や社会から「その分野といえばこの人・この企業」と認識される大きなきっかけとなるのです。
ここでは、次の2つの事例を紹介します。
・書籍を出版し、「海外進出の第一人者」として知られるようになった公認会計士
・出版をきっかけに全国から200人集患、テレビ出演で第一想起を獲得した白内障手術の眼科医 |
以下で、それぞれどのような事例なのかを見ていきましょう。
◉-1、書籍を出版し、「海外進出の第一人者」として知られるようになった公認会計士
公認会計士事務所の経営者は、海外進出をテーマにした書籍を出版したことで「海外進出支援の第一人者」という第一想起を獲得しました。
出版後、地元紙や全国紙、ラジオ番組などへのメディア露出が増加し、専門性が広く認知され、企業からの相談依頼が増加。
さらに、「クーリエ・ジャポン」にも書籍の抜粋記事が8回にわたり連載され、グローバルな視点を持つ読者層に向けても専門性を強く印象づけています。
その結果、顧客の頭の中に「海外進出支援ならこの公認会計士」というイメージが定着し、競合との差別化や事務所のブランディング、ビジネス拡大に成功しました。
出版をきっかけに専門家のポジションを獲得し、顧客からの値下げ要求もなくなり売上の伸長にもつながりました。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉-2、出版をきっかけに全国から200人集患、テレビ出演で第一想起を獲得した白内障手術の眼科医
ある眼科医は、自身の専門分野である白内障手術に関する書籍を出版しました。
その書籍が患者やメディアの目に留まり、全国から200人以上の患者が来院する結果につながりました。
さらに、テレビ番組への出演も実現し、「白内障手術といえばこの医師」という第一想起の確立に成功。
出版を起点とした広がりが、地域を超えてブランド力を高める効果を発揮した好例です。
【まとめ】第一想起を獲得するマーケティングで業界のポジションを築こう
この記事では、第一想起マーケティングの定義や効果的なマーケティング施策、書籍出版による成功事例などについて解説しました。
第一想起を獲得すれば、顧客が購買行動を起こすときに「真っ先に思い浮かべてもらえる存在」となり、競合と比較する前に選んでもらえる可能性も高まります。
そのためには、権威性・信頼性の強化やデジタル施策、体験型イベント、ブランド価値の向上といった多面的な取り組みが欠かせません。
その中でも特に効果的なのが書籍の出版です。
フォーウェイが提供する「ブックマーケティングサービス」は、第一想起の獲得を目指す企業にとって最適な手段といえるでしょう。
ブックマーケティングを活用すれば、出版した書籍を自社のブランディングに活用し、専門家としてのポジション確立や価格競争からの脱却を図ることができます。
さらに、メディア露出の機会増加や顧客の記憶への定着、認知度の向上といった波及効果も見込めるため、第一想起の確立を後押しします。
ブックマーケティングによって、自社の専門性を広く伝え、業界で確固たるポジションを築いてみませんか。


「見込み客からの問い合わせを増やしたい」「自社の専門性をアピールしたい」「営業活動をもっと効率化したい」といった悩みを抱えているBtoB企業のマーケティング担当者や経営者の方は多いのではないでしょうか。
BtoBビジネスにおいては、新規顧客との接点づくりや長期的な関係構築が欠かせません。
そこで活用したいのがコンテンツマーケティングです。
コンテンツマーケティングには、Web記事やホワイトペーパー、動画などがありますが、やみくもに取り組んでも期待した成果は得られません。
この記事では、BtoBビジネスで成果を出すためのコンテンツマーケティング戦略をわかりやすく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
コンテンツマーケティングはBtoBと相性がよい!

一般的に、BtoB商材は高額かつ専門的で、導入決定までに時間がかかることが特徴です。
購入の意思決定には、社内稟議や複数部署との調整に加え、客観的なデータや導入事例の提示が求められます。
こうした状況において、コンテンツマーケティングを活用すれば、顧客企業の担当者が情報収集を始める初期段階から有益な情報を届けることが可能です。
その結果、「この会社は信頼できる情報を提供してくれる」といった評価を得やすく、信頼関係の構築につながります。
さらに、比較検討や意思決定の場面でも必要な情報を段階的に提示できるため、導入を後押しする有効な手法といえます。
BtoBコンテンツマーケティングの実践ステップ

実際にコンテンツマーケティングに取り組む際は、以下の流れに沿って行います。
・ステップ1:課題や目的を明確にする
・ステップ2:カスタマージャーニーを設計する
・ステップ3:作成するコンテンツを決定する
・ステップ4:コンテンツを作成し、公開する
・ステップ5:分析と改善を行う |
5つのステップと、それぞれのステップで押さえておくべきポイントを解説します。
◉-1、ステップ1:課題や目的を明確にする
まずは、コンテンツマーケティングで達成したい目的を具体的に定めることから始めましょう。
たとえば、「リード数を増やす」「商談化率を改善する」といった数値で測定できる目標を設定すれば、取り組むべき方向性がはっきり見えてきます。
また、自社の強みや競合との差別化ポイントを整理しておくことで、コンテンツの内容に一貫性を持たせることができます。
◉-2、ステップ2:カスタマージャーニーを設計する
次に、顧客が購買に至るまでの過程を整理します。
BtoBの購買プロセスは、一般的に「認知→比較検討→意思決定」のステップで進みます。
それぞれの段階で顧客が求める情報を把握し、適切に提供できるよう設計することが大切です。
特にBtoBでは、実務担当者と最終的な意思決定者では求める情報が異なることが多いため、それぞれのニーズに合わせたコンテンツ設計を行う必要があります。
◉-3、ステップ3:作成するコンテンツを決定する
目的や顧客のフェーズに合わせて、作成するコンテンツの形式を決めます。
記事やホワイトペーパー、動画、事例紹介など、さまざまな形式が考えられますが、基本的には売上に直結しやすいコンテンツから優先的に取り組むことが重要です。
ただし、売上への影響が小さいコンテンツばかりを発信していても、期待する成果は得られません。
リード獲得や商談化率の向上といった明確な目標につながるコンテンツを選び、戦略的に展開していくことが大切です。
◉-4、ステップ4:コンテンツを作成し、公開する
コンテンツを作成する際は、文章だけでなく、図表や動画を活用して視覚的に理解しやすくする工夫が必要です。
特にBtoBでは、専門性の高いテーマを扱うことが多いため、図解や実際の事例紹介を盛り込むと、より説得力のあるコンテンツになります。
コンテンツの公開先としては、自社サイトやSNSだけでなく、メールマガジン、展示会など複数のチャネルを組み合わせることで、接点を増やし、顧客との関係性を強化できます。
たとえば、展示会で配布した資料にQRコードを設置し、Web上のホワイトペーパーや解説動画に誘導すれば、オフラインとオンラインの両面でリード獲得につなげられます。
◉-5、ステップ5:分析と改善を行う
コンテンツマーケティングは、作って終わりではありません。
公開後に効果を定期的に測定し、改善を重ねていくことがポイントです。
そのためには、PV数や滞在時間、資料ダウンロード数、商談化率などのKPIをあらかじめ設定しておき、定期的に効果測定を行います。
得られたデータをもとに、「どのテーマが成果につながりやすいか」「どのチャネルが効果的か」を見極め、リソースを重点的に配分すれば、再現性のある運用が可能になります。
◉BtoBコンテンツマーケティングの主な手法

BtoBのコンテンツマーケティングには、さまざまな手法があります。
その中でも代表的なものとして、以下の5つを解説します。
・コンテンツSEO
・ホワイトペーパー
・動画コンテンツ
・メールマガジン(メルマガ)
・企業出版(ブックマーケティング) |
それぞれの特徴と活用ポイントについて見ていきましょう。
◉-1、コンテンツSEO
BtoBの購買プロセスでは、導入検討の初期段階で検索エンジンを利用した情報収集が行われることが多いため、コンテンツSEOは必須の施策です。
業界特有の課題や専門用語、比較検討に関連するキーワードを盛り込んだコンテンツを制作することで、見込み客が検索する段階から接点を持つことができます。
特にBtoBでは、検索ボリュームは少なくても意図の明確なキーワードを狙うことで、高いコンバージョン率を期待できる点が特徴です。
また、高品質なコンテンツは検索結果の上位に表示されるだけでなく、「AI Overview」にも掲載されやすくなります。
AI Overviewとは、Googleが検索結果ページ上部に表示するAIによる要約機能のことです。
ユーザーの疑問に的確に答え、簡潔にまとめられたコンテンツは、AIに評価されやすいため、より多くの見込み客にリーチできる可能性が高まります。
▶︎コンテンツSEOの詳細については、関連記事【SEO対策とは? 効果的な戦略の組み立て方と対策方法】もあわせて参考にしてください。
◉-2、ホワイトペーパー
ホワイトペーパーは、課題解決のためのノウハウや事例、調査データをまとめたPDF資料であり、ダウンロード時にリード情報を取得できるのが強みです。
専門情報を提供できるため、BtoB商材の比較検討段階において特に効果を発揮します。
顧客にとって有益な情報を提供することで信頼性を高め、商談につなげやすくなります。
◉-3、動画コンテンツ
製品のデモンストレーションや導入事例のインタビュー、ウェビナーの録画など、動画は「見て理解できる」ため、複雑な情報でも直感的に伝えられるのが特徴です。
BtoBの取引では、社内の複数部署や担当者が意思決定に関わることが多く、動画は社内で共有されたり、説明資料として活用されたりします。
また、制作した動画は YouTube・自社サイト・SNS・展示会での上映 など、さまざまなチャネルで再利用が可能です。
SEO効果の向上やSNSでの拡散も期待でき、効率的に認知度と信頼性を高めることができます。
▶︎動画コンテンツの詳細については、関連記事【動画制作のスケジュールは計画的に! 準備から実制作、編集、スケジュール管理まで解説】もあわせて参考にしてください。
◉-4、メールマガジン(メルマガ)
定期的なメール配信は、見込み客との関係を長期的に維持するために有効です。
特に強みとなるのは、読者の購買意欲が高まったタイミングで情報を届けられるため、スムーズに商談へつなげられる点です。
また、ホワイトペーパーやブログ記事、セミナー情報など他のコンテンツと組み合わせて配信すれば、顧客との接触回数を自然に増やすことができます。
◉-5、企業出版(ブックマーケティング)
企業出版とは、企業や経営者が持つ専門知識や成功事例を体系的に整理し、書籍という形で発信する手法です。
書籍は一度出版すると長期的に残るため、Web記事やパンフレット以上に信頼性や権威性を高める効果があります。
読者からは「この会社は専門分野における確かな知見を持っている」と認識されやすいため、企業ブランドの格を引き上げられるでしょう。
また、展示会やセミナーでの配布、営業訪問時の手渡しといったBtoBならではの対面営業の場でも活用しやすく、商談の突破口や顧客との信頼構築につながります。
▶︎企業出版の詳細については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
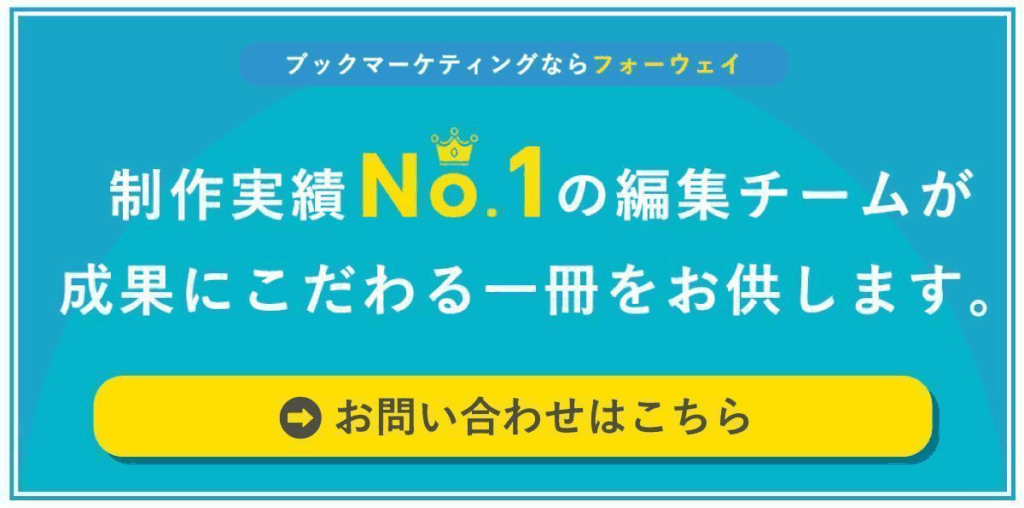
BtoBのコンテンツマーケティングで企業出版に取り組むメリット
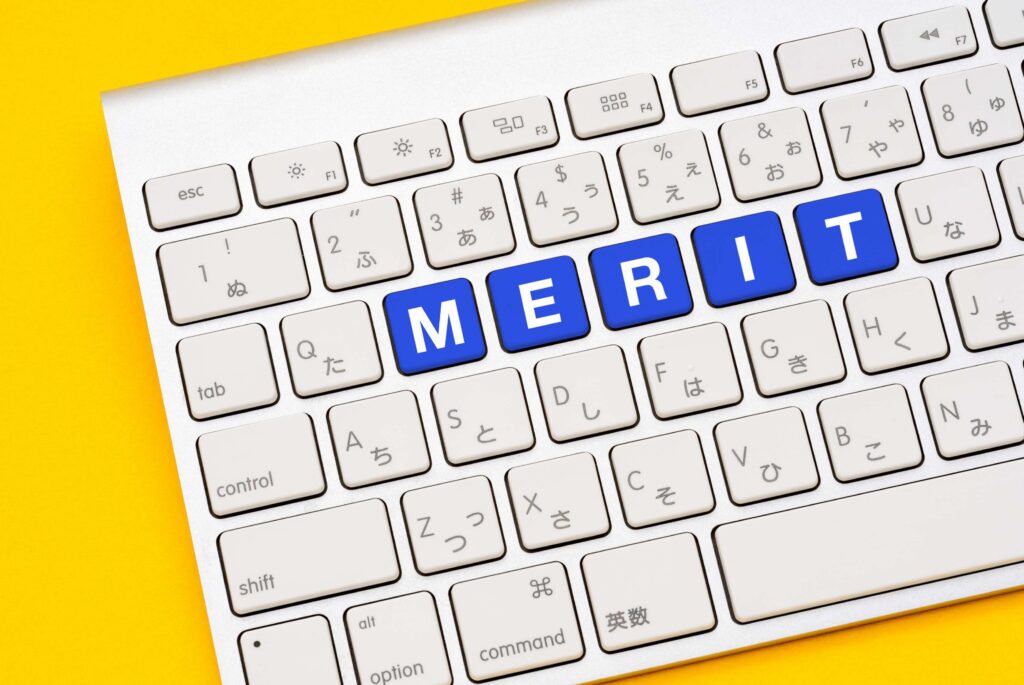
BtoBコンテンツマーケティングにおいて、企業出版に取り組むことは大きな効果をもたらします。
特に次の4つのメリットが挙げられます。
・信頼性と権威性を高められる
・長期的なコンテンツ資産になる
・リード獲得の起点になる
・営業ツールとしての差別化につながる |
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
◉-1、信頼性と権威性を高められる
BtoBの取引では、専門性や実績、信頼感が顧客企業内での購入意思決定に影響します。
そのため、これらをどのように示すかが重要なポイントとなります。
書籍はWeb記事やSNSに比べ、企画・執筆・編集・校正といった工程を経て世に出るため、情報の正確性や品質が担保されやすい媒体です。
結果として、顧客企業から「書籍を出版している=信頼できる」と認識されやすくなります。
さらに、経営者や専門部門の責任者が著者として名を示すことで、企業の知見や実績が社会的な信頼の裏付けとなり、ブランド価値を一層高める効果を発揮します。
出版は、企業ブランドの権威性を強化し、取引先からの信頼獲得につながる手段といえるでしょう。
◉-2、長期的なコンテンツ資産になる
Webコンテンツは更新頻度や検索エンジンのアルゴリズム変化の影響を受けやすく、長期的に安定した価値を保ちにくい傾向があります。
一方で、書籍は一度出版すれば長期にわたり活用できるコンテンツ資産です。
展示会やセミナーでの配布物として利用すれば、営業活動において長期的に役立つツールになります。
また、書籍は物理的に手元に残りやすいため、顧客が必要になったときに再び手に取り、「そういえばこの会社があった」と思い出してもらえるきっかけにもなります。
さらに、書籍を電子化してホワイトペーパーや電子書籍として二次利用すれば、オンラインでの配布やダウンロードを通じて新たな接点を作ることが可能です。
◉-3、リード獲得の起点になる
書籍を購入したり、無料配布に申し込んだりする人は、すでに自社の領域に強い関心や課題意識を持っている場合が多く、効率よく獲得できる購入確度の高いリードの対象となりえます。
出版記念セミナーや書籍と連動したキャンペーンを組み合わせれば、参加者や申込者からより確度の高い情報を収集することができ、営業成約につながる可能性が一層高まります。
また、書籍の企画と連動したLP(ランディングページ)を用意することで、より多くの顧客リードを獲得することが可能です。
たとえば、書籍の巻末にQRコードを設置し、そこからLPにアクセスした読者に「追加資料」や「限定特典」を提供すれば、自然な形でリード情報を収集できます。
このように、書籍は単なる認知拡大の手段ではなく、営業活動に直結するリード獲得の起点として機能します。
◉-4、営業ツールとしての差別化につながる
競合他社との差別化を図るうえで欠かせないのが、「自社ならではの知見や経験を形にすること」です。
企業出版は、その強みをわかりやすく体系化し、説得力を持って伝える手段となります。
たとえば、営業担当者が訪問時に書籍を手渡せば、会社案内やパンフレットよりも強く印象に残るでしょう。
なぜなら書籍は「この企業は専門知識をまとめ、出版するだけの実績がある」という信頼感を与えるからです。
また、商談の場で事例やノウハウが掲載された部分を資料として活用すれば、説得材料としても効果的です。
意思決定に複数の関係者が関わるBtoBでは、書籍が社内で共有されることで、直接会っていない意思決定者にもリーチできます。
結果として、競合他社との差別化を図りながら、営業活動を有利に進められます。
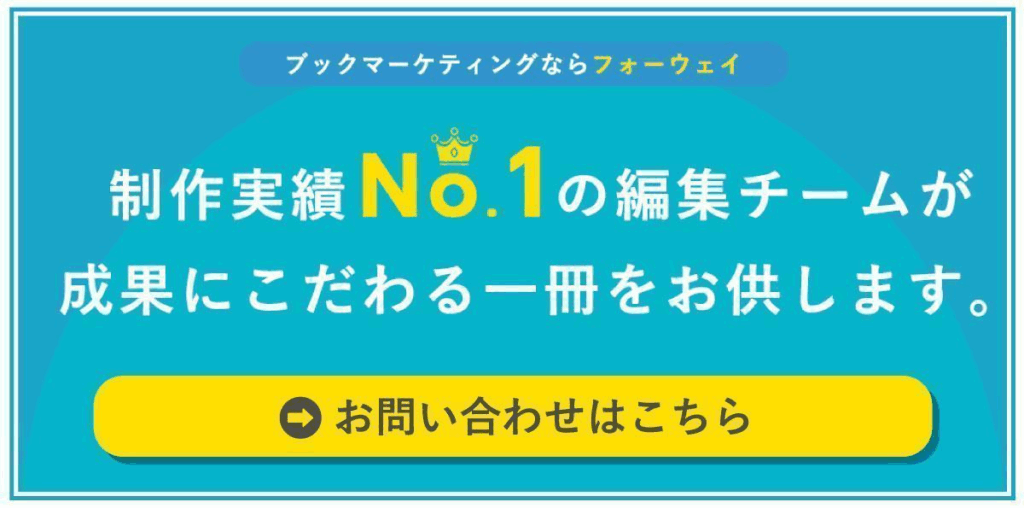
企業出版によるBtoBコンテンツマーケティングの成功事例

ここでは、企業出版によるBtoBコンテンツマーケティングの成功事例を3つ紹介します。
・新規事業の顧客開拓のために書籍を出版して契約を獲得した保険代理店
・企業出版によって商圏拡大と顧客獲得に成功した経営コンサルタント
・出版をきっかけに海外専門家の地位を確立した公認会計士事務所 |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、新規事業の顧客開拓のために書籍を出版して契約を獲得した保険代理店
保険代理店を営む経営者は、新規事業として保険代理店のコンサルタント業を立ち上げましたが、顧客獲得に苦労していました。
そこで、顧客開拓のために書籍を出版。
書籍の中で、保険業界の問題点とともに、「成果報酬型」を「一律報酬型」に変更することによって自社の業績が向上したことをアピールしました。
出版後、保険業界内での知名度が向上し、セミナーの講師に招かれるようになり、出版の目的だった新規コンサル契約を複数成約。
本業の保険契約でも、保険契約数が伸び、書籍出版が大口契約の成約につながるなど大きな効果がありました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、企業出版によって商圏拡大と顧客獲得に成功した経営コンサルタント
建設業専門の経営コンサルタントは、知名度向上による商圏拡大を狙って書籍を出版しました。
書籍のタイトルに「建設業のための」という文言を入れたことによって、ターゲットを明確化することができ、出版の翌日から多くの問い合わせが殺到して10件近くの顧問契約を獲得。
書籍の配本を首都圏中心に行うことによって、狙い通りの商圏拡大にも成功し、建設業界におけるコンサルティング会社としてのブランドを確立することができました。
◉-3、出版をきっかけに海外専門家の地位を確立した公認会計士事務所
公認会計士事務所の経営者は、自らの海外勤務経験の知識と専門性を訴求し「海外案件の専門家」という地位を確立するために書籍を出版しました。
出版後、地元紙や全国紙、ラジオ番組などへのメディア露出が増加し、専門性が広く認知されました。
その結果、外資系企業やグローバル案件にも対応できる公認会計士であることが、顧客企業に認知され、事務所のブランディングとビジネス拡大に成功。
出版をきっかけに専門性や権威性が高まり、顧客からの値下げ要求も減少し、売上が大幅に増加しました。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
【まとめ】BtoBのコンテンツマーケティングには企業出版が効果的!
この記事では、BtoBコンテンツマーケティングの実践ステップや主な手法、成功事例について詳しく解説しました。
BtoBビジネスでは、一般的に顧客企業の担当者と商談を進めますが、最終的な購入の意思決定には社内稟議や複数部署での調整が必要になります。
そのため、担当者を通じて「自社の魅力や専門性をいかに正しく伝えるか」が、成約を左右するポイントです。
このような社内決裁のプロセスにおいて、説得力ある情報提供の手段として有効なのが企業出版です。
フォーウェイでは、企業出版をマーケティングに活用する「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
「ブックマーケティングサービス」を活用すれば、技術面での専門性だけでなく、自社の成り立ちや経営方針などを含めた総合的な情報提供が可能となり、信頼性や権威性を高められます。
BtoBビジネスにおける「リード獲得」「成約率の向上」の具体的な施策として、ぜひフォーウェイのブックマーケティングをご検討ください。
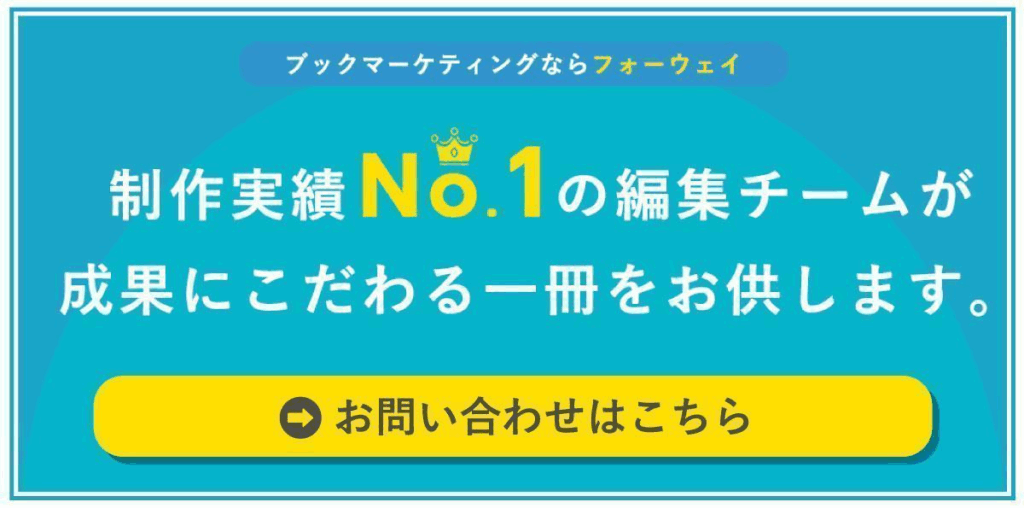

富裕層や高所得者向けに自社の商品やサービスをアピールしたい場合、適切な広告手法を選ぶことが重要です。
保有資産や年収、居住エリアなどの条件を絞れる広告手法なら、狙いたいターゲットにリーチできます。
しかし、「どんな広告手法が効果的なのだろう」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
富裕層は価格よりも価値や信頼性を重視し、日常的に多くの広告に触れているため、一般消費者向けの広告戦略がそのまま通用するとは限りません。
そこで本記事では、富裕層・高所得者向けの広告の種類や戦略のポイントなどについて解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
富裕層・高所得者向け広告とは

富裕層・高所得者向け広告とは、年収や資産規模が高い顧客層に特化して設計された広告手法です。
年収数千万円以上や、資産数億円といった高い経済力を持つ顧客層をターゲットとする業界で、富裕層・高所得者向けの広告が活用されます。
たとえば、高額商品やプレミアムサービス、高級不動産などを販売する際は、富裕層・高所得者向け広告が有効です。
また、投資商材やラグジュアリー体験などを訴求するケースでも活用できます。
◉-1、一般消費者向け広告との違い
一般消費者は、価格や機能、コストパフォーマンスといった実利的な価値を重視する傾向があります。
一方で、富裕層が重視する要素は、ブランドの信頼性や希少性、社会的評価などです。
そのため、一般消費者向け広告と富裕層向け広告では、効果的な表現や訴求軸、使用する媒体などが異なります。
富裕層・高所得層向け広告の種類

富裕層・高所得者層向け広告には、以下のような種類があります。
・運用型広告
・Webメディア広告
・情報誌広告
・タクシー広告
・サイネージ広告 |
それぞれ特徴が異なるため、商材の種類やターゲットに応じて最適な手法を選ぶことが重要です。
ここでは、各広告の特徴について解説します。
◉-1、運用型広告
運用型広告とは、広告主が配信先やターゲット、広告文などを自社で細かく設定して運用できる広告です。
検索エンジンの結果画面やSNS、Webサイト、ブログなどの広告枠に自社の広告を配信できます。
運用型広告は一般消費者向けにも活用されますが、富裕層向けでも利用することが可能です。
主な運用型広告のサービスとして、以下のようなものが挙げられます。
・Google広告
・Yahoo!広告
・Meta広告
・Microsoft広告
・LINE広告 |
これらを富裕層・高所得者向け広告として活用する際は、幅広く配信するのではなく、ターゲットの年収や職業、居住エリア、興味関心などを絞り込むことが重要です。
◉-2、Webメディア広告
Webメディア広告とは、オンラインで閲覧できるWebサイトやアプリに掲載される広告です。
富裕層が情報収集に利用する専門メディアや業界メディアに広告を出稿することで、信頼感を得られます。
経済・投資系、ラグジュアリーライフスタイル系のWebメディアは、読者層が明確なため、ブランドの格を損なわずに情報を届けることが可能です。
具体的なWebメディアとして、「Forbes Japan」や「ZUU ONLINE」などが挙げられます。
◉-3、情報誌広告
高級ホテルの客室や会員制クラブ、航空機内などに設置されるラグジュアリー系情報誌は、富裕層の手に直接届く媒体です。
誌面自体が高級感を演出しているため、情報誌広告を出すことで、ブランド価値を高める効果が期待できます。
情報誌広告を掲載できる主な媒体は、富裕層向けの情報誌「Nile’s NILE(ナイルスナイル)」や「PAVONE(パヴォーネ)」、ダイナースクラブの会員誌「シグネチャー」などです。
◉-4、タクシー広告
タクシー広告は、都市部のハイヤーやタクシーの後部座席モニターに配信できる広告です。
ハイヤーやタクシーの乗客には、経営者や役員クラスの人が含まれるため、タクシー広告を配信することでピンポイントにアプローチできます。
タクシー広告を出す際は、ターゲットの興味を引くために、商材の価値をわかりやすく訴求することが重要です。
また、移動中の限られた時間に情報を届けるため、簡潔かつ印象に残るクリエイティブを作る必要があります。
◉-5、サイネージ広告
サイネージ広告は、街中や施設内、建物の壁面などに設置されているディスプレイに配信できる広告です。
富裕層や高所得者がよく利用する場所にあるデジタルサイネージに広告を配信すると、自社の商品やサービスの認知を効果的に広げられます。
たとえば、空港ラウンジや高級マンション、ゴルフ場にサイネージ広告を出すと、富裕層・高所得者へのアプローチが可能です。
サイネージ広告の特徴として、視認性が高く、商品の世界観を短時間で伝えやすいことが挙げられます。
富裕層・高所得者向け広告で成果を出すポイント

富裕層・高所得者向け広告を出す際は、媒体選びだけでなく、以下のようなポイントも重要です。
・ターゲットを具体的に定義する
・価格ではなく、価値を訴求する
・洗練されたデザインと表現を追求する |
富裕層・高所得者向け広告で成果を出すポイントについて見ていきましょう。
◉-1、ターゲットを具体的に定義する
富裕層・高所得者層と一口に言っても、そのライフスタイルや価値観、興味関心は多岐にわたります。
そのため、自社のターゲットを具体的に定義することが、広告を出す際に重要です。
年齢層や性別、居住地域、家族構成、職業、役職、年収といったターゲット属性を明確にしましょう。
さらに、「どのような生活を送っているのか」「休日は何をしているのか」「どのような趣味を持っているのか」などを具体的に想定することも、広告の成果につながります。
◉-2、価格ではなく、価値を訴求する
富裕層は安さではなく、希少性やブランドストーリー、人生を豊かにする体験価値に惹かれる傾向があります。
そのため、富裕層向け広告を出す際は、価格ではなく価値を訴求することが重要です。
「なぜこの商品・サービスが特別なのか」「所有することでどんな価値が得られるのか」を明確に示すことで、興味を持ってもらいやすくなります。
◉-3、洗練されたデザインと表現を追求する
富裕層は日常的に質の高いデザインや演出に触れているため、広告クリエイティブも洗練されたデザインと表現を追求することがポイントです。
ターゲットとする富裕層にマッチする高品質なクリエイティブを作ることで、「本物を提供する企業である」という信頼感を持ってもらいやすくなります。
広告文の内容やフォント、配色、動画広告の場合は映像や音による演出など、細部まで妥協しない広告表現を追求する必要があります。
広告だけではない!富裕層・高所得層に効果的な集客施策

富裕層や高所得者に自社の商品・サービスを広める方法には、広告以外に以下のような手法があります。
・イベント出展
・富裕層向け商品・サービスとのコラボレーション
・セミナー・勉強会
・企業出版(ブックマーケティング) |
ここでは、各集客施策について解説します。
◉-1、イベント出展
富裕層が集まる展示会や限定イベントへの出展は、ターゲット層と直接関われる施策です。
たとえば、高級車やアート、ワイン、ジュエリー、海外不動産などをテーマにした展示会や、会員制・招待制の限定イベントに出展することが、認知拡大や商談の獲得につながります。
イベント出展時は、自社のブランドイメージを体験できるブース設計や、ストーリー性のあるプレゼンテーションを行い、ブランド価値を印象付けることが重要です。
◉-2、富裕層向け商品・サービスとのコラボレーション
自社と同じターゲット層を持つ高級ブランドと連携し、相互に送客をすることも、効果的な集客施策です。
たとえば、高級時計ブランドと高級ホテルの宿泊プラン、高級車メーカーとリゾート施設のタイアップといったコラボレーション企画が考えられます。
お互いの顧客に対して信頼ある企業として紹介されるため、初めての接触でも心理的なハードルが下がりやすいことが、コラボレーションのメリットです。
さらに、限定性や希少性を持たせた特別なプランを用意すると、より良い反応を得られる可能性があります。
◉-3、セミナー・勉強会
富裕層は自身の資産管理やライフスタイルの質向上に高い関心を持っています。
そのため、資産運用や税務、相続、健康などをテーマとしたセミナーや勉強会を開催することが、富裕層へのアプローチに有効です。
講師として各分野の専門家や著名人を起用すると、限定感や特別感を与えられるため、参加者の関心を高めて商談へつながりやすくなります。
また、参加者限定の相談会や交流会を設けて、より深い関係を構築することも効果的です。
◉-4、企業出版(ブックマーケティング)
企業出版は、自社の専門知識やブランドストーリー、理念などを一冊の書籍としてまとめることで、信頼性を高めるマーケティング施策です。
広告やWebサイトで発信する情報と異なり、書籍は多くの手間と時間をかけて出版されるため、権威性が高いという特徴があります。
中長期的にはブランド力を高め、競合との差別化が可能です。
ブックマーケティングの詳細については、以下の記事でも解説しています。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
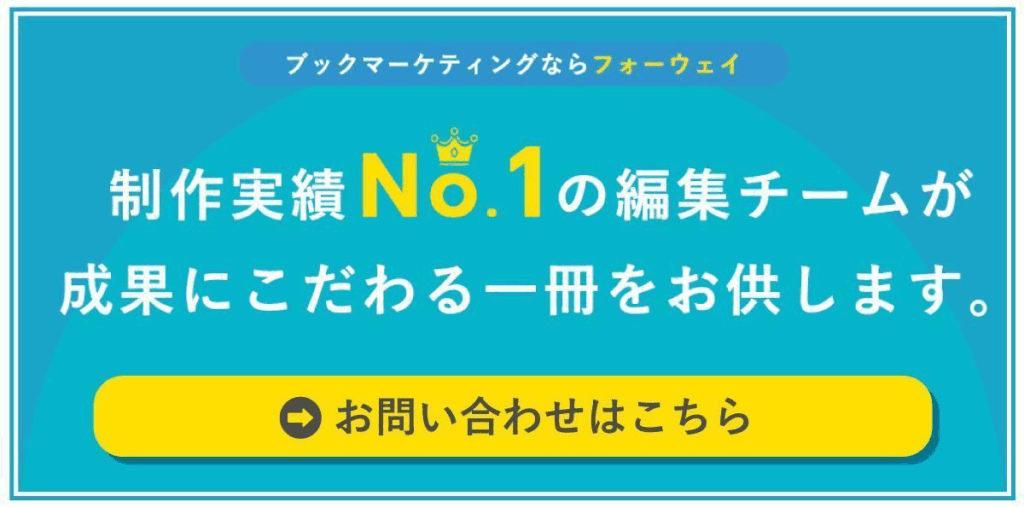
富裕層・高所得層にリーチするなら企業出版がおすすめ!
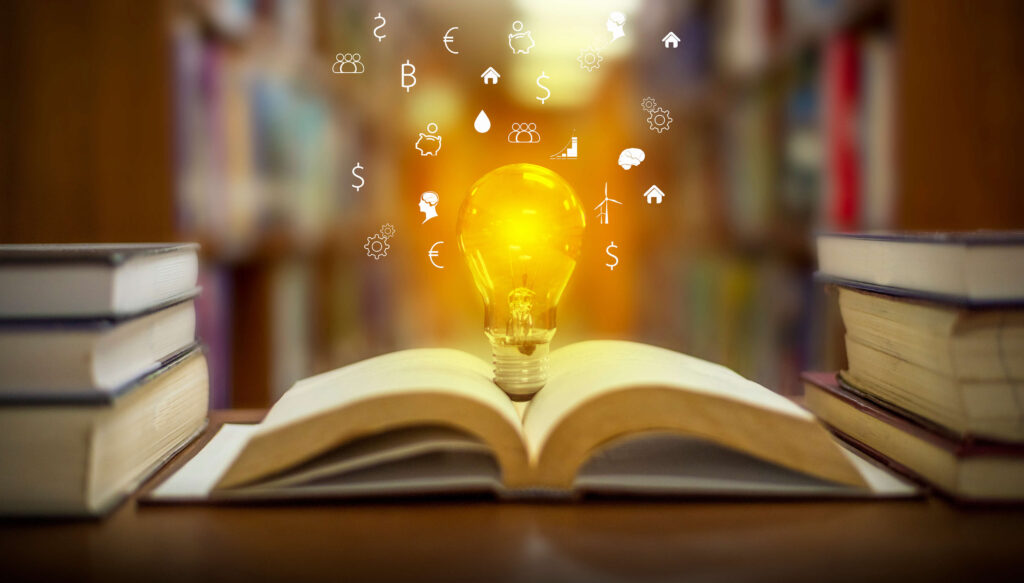
企業出版は、以下のような特徴があるため、富裕層・高所得者へのアプローチに有効です。
・信頼を獲得しやすい
・富裕層特有の購買行動に合っている
・継続的な見込み客(リード)の獲得につながる |
ここでは、企業出版ならではの特徴について解説します。
◉-1、信頼を獲得しやすい
富裕層は、信頼できる情報源から情報を得たいと考えていることが一般的です。
書籍を出版して、著者や企業の専門知識を体系的に伝えると、情報の信頼性を高められます。
一方的な宣伝ではなく、読者にとって有益な情報を届ける書籍は、信頼関係を築くための効果的な手段となります。
◉-2、富裕層特有の購買行動に合っている
富裕層は商品購入を検討する際、口コミや専門家の意見を参考にし、時間をかけて判断する傾向があります。
企業出版では、自社や商品・サービスに関する情報を詳しく伝え、富裕層に十分な検討材料を提供することが可能です。
書籍を通じて、企業の理念や商品・サービスの開発背景、創業者の想い、業界の課題といった深い情報を提供することで、富裕層から納得されやすくなります。
◉-3、継続的な見込み客(リード)の獲得につながる
一般的に、広告は出稿期間が終わると効果が途切れます。
一方で、書籍は出版後に長期的に残り続け、配布・販売を通じて新しい顧客へのリーチが可能です。
書店での流通をはじめ、セミナーやイベントでの配布、オンライン施策との組み合わせにより、長期的に安定したリード獲得ができます。
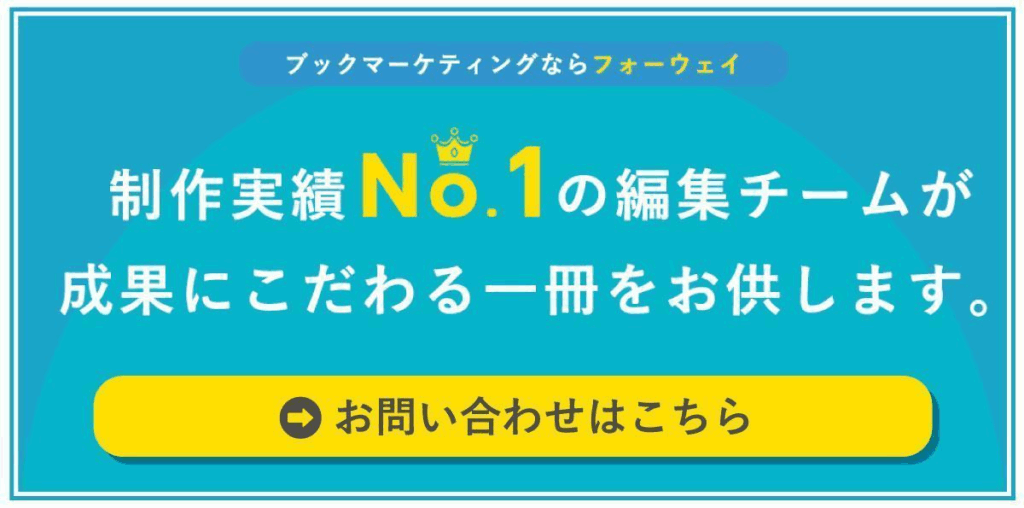
企業出版で富裕層・高所得者にリーチした成功事例
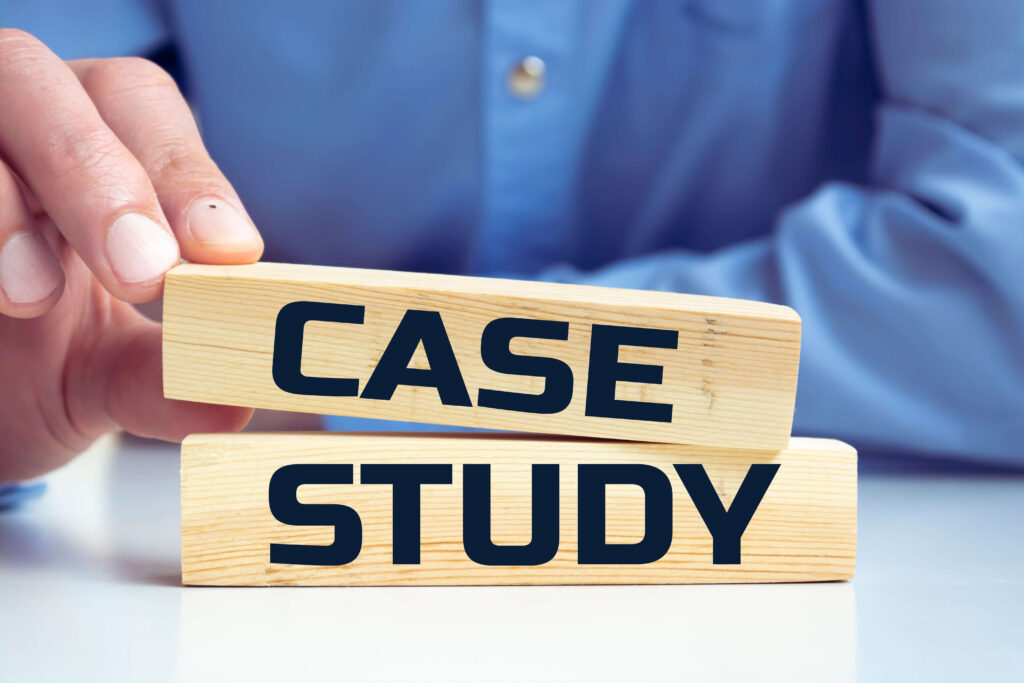
企業出版は、さまざまな業界における富裕層・高所得者向けとして有効です。
ここでは、企業出版で富裕層・高所得者にリーチした成功事例を3つ紹介します。
◉-1、アンティークコイン投資の分野で富裕層を獲得した事例
アンティークコインを扱う企業では、富裕層をターゲットにしたアンティークコイン投資に関する書籍を出版しました。
書籍の流通戦略として、投資関連書籍の販売好調店と、富裕層が住むエリアの書店に重点的に配本。
また、日経新聞の複数の広告枠に連続出稿し、認知度向上も図りました。
出版後間もなく100名以上の無料資料ダウンロードがあり、数千万円の売上につながっています。
また、出版記念セミナーでは、数百万円の売上を複数獲得。
書籍を購入した富裕層の顧客からも反響があり、面会の3日後に数億円の売上につながりました。
◉-2、セミナー講師に権威性がつき、富裕層から商談を獲得した事例
不動産投資業界のセミナー講師のブランディングを目的とした企業出版では、セミナー講師を著者、代表取締役を監修として書籍を制作しました。
同社が得意とする投資ノウハウをタイトルに据え、投資家の興味を引く書籍に仕上げたことも、企画編集のポイントです。
一都三県の中で高収入層の割合が多いエリアへの配本や、日本経済新聞への広告掲載、書籍のランキング獲得施策などを実施。
著者であるセミナー講師を指名する問い合わせが殺到し、出版後1か月で10件強の商談を獲得できました。
また、出版後に富裕層向けセミナーも開催し、不動産投資家やオーナー社長の集客にも成功しています。
◉-3、医師をターゲットに書籍を出版し、6か月で10億円以上の売上につながった事例
新規顧客の獲得経路がほとんど紹介のみに限られていた不動産投資企業では、医師をターゲットとした不動産投資の書籍を出版しました。
自社独自の不動産投資ノウハウや資産運用スキームをまとめ、権威性と信頼性を獲得することが、企業出版の狙いです。
書籍発売1か月で複数の反響があり、読者の医師との面談後に投資用区分10戸購入が決まりました。
また、大手病院の勤務医からの反響が成約につながるなど、出版から6か月で10億円以上の売上を獲得。
ほかにも書籍読者からの問い合わせがあり、不動産投資を検討している高所得者との商談が実現しています。
【まとめ】富裕層・高所得者向け企業出版で商品やサービスをアピールしよう!
富裕層・高所得者向けの広告は、高額商品やプレミアムサービスを販売するために有効な施策です。
価格の安さではなく、希少性やブランドストーリーなどの価値を訴求することで、富裕層からの信頼を得やすくなります。
また、富裕層・高所得者向けの集客施策の一つとして、企業出版も効果的です。
フォーウェイでは、富裕層・高所得者にリーチしたい企業に向けて、ブックマーケティングのサービスを提供しています。
企業出版で自社の商品やサービスを効果的にアピールしたい方は、ぜひフォーウェイにご相談ください。
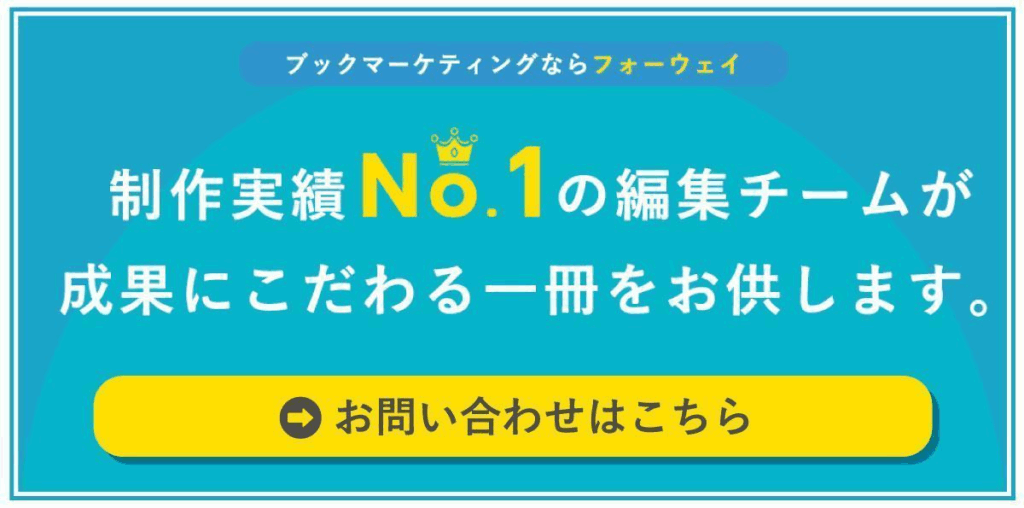

「自社のWebサイトに集客したい」「サービスや商品の認知度を上げたい」と考えている企業担当者の方は多いのではないでしょうか。
インターネットが普及した現代では、誰もが簡単に情報へアクセスできるようになり、従来のような一方的な広告だけでは顧客の心を動かすのが難しくなっています。
そこで、多くの企業が注目しているのが「コンテンツマーケティング」です。
言葉にすると簡単なようですが、コンテンツマーケティングを実践したものの成果が出ないという企業も少なくありません。
そこで今回は、コンテンツマーケティングの手法や効果を発揮するための戦略について解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
コンテンツマーケティングとは

コンテンツマーケティングとは、コンテンツを活用したマーケティングの手法を指します。
ここでいうコンテンツは、顧客や見込み顧客にとって有益で価値のある情報であることが重要です。
顧客が興味を持つコンテンツの発信・提供によって信頼関係を築き、最終的に自社の商品やサービスの購入・利用につなげます。
コンテンツマーケティングでは、広告のように積極的な売り込みは行いません。
読者や視聴者のニーズを満たしたり、課題を解決するための情報を提供し続けたりすることで、認知度向上や見込み顧客(リード)獲得といった効果を狙います。
◉-1、コンテンツマーケティングとコンテンツSEOは違う?
Webを活用したマーケティング手法として、メジャーになりつつあるコンテンツマーケティング。
しかし、コンテンツSEOと混同されているケースも散見されます。
コンテンツSEOとは、ターゲット読者が求める情報をコンテンツとして提供し続け、Googleなどの検索結果で上位を目指す手法のことです。
コンテンツマーケティングの一種ですが、イコールではありません。
コンテンツSEOは検索エンジン(SEO)対策の方法であり、あくまで検索結果の上位表示を目指してコンテンツを提供することが目的です。
一方、コンテンツマーケティングはさらに広い意味で用います。
広告以外の手段で有益な情報を発信し続け、見込み顧客に興味を持ってもらい、行動に移してもらうまでを戦略的に設計するのがコンテンツマーケティングです。
簡単にいうと、顧客側から興味を持ってこちら側に寄ってくるインバウンドマーケティングの仕組みづくりをコンテンツマーケティングといいます。
コンテンツマーケティングが重要視されるようになった背景

コンテンツマーケティングが重要視されるようになった背景として、以下の3つが挙げられます。
・売り込み型マーケティングの効果が下がった
・消費者の購買行動が変化した
・アルゴリズムが変化した |
それぞれ詳しく解説します。
◉-1、売り込み型マーケティングの効果が下がった
従来のマーケティングでは、テレビやラジオのCM、インターネットなどの広告で商品やサービスを知ってもらう売り込み型(プッシュ型)のマーケティングが一般的でした。
売り込み型のマーケティングは潜在層にも知ってもらえる可能性が高く、即効性も期待できます。
しかしその一方で、企業から一方的に押しつけられる情報になりやすく、受け手である消費者にとっては広告が不快に感じられるケースも少なくありません。
また、「そもそも広告を見ない」という消費者も増えており、売り込み型マーケティングの効果は薄れてきています。
さらに、プッシュ型手法の代表格であるアウトバウンドのテレアポも、難易度が上がり効果が出にくくなっています。
誰もが手軽に始められる一方で、成果を出すには高いスキルが求められるためです。
特に、コロナ禍を経てオンラインでの打ち合わせや在宅ワークが普及したことで担当者と直接つながりにくくなり、これまで以上に効果を出すのが難しくなっています。
◉-2、消費者の購買行動が変化した
インターネットが普及したことで、誰もがほしい情報を自分で調べられるようになりました。
今では、気になることは自分で検索し、比較・検討したうえで選択することが当たり前になっています。
そのため、自社の製品やサービスが選ばれるためには、ただ売り込むだけでなく、消費者にとって役立つ情報を提供することが重要になりました。
逆にいえば、良質なコンテンツを提供することで、これまで自社の製品やサービスを知らなかった消費者にも認知されるきっかけになります。
たとえば「就職祝いに贈る品物」で悩んでいる消費者が検索し、喜ばれる贈り物やマナーを紹介した記事に辿り着いたとします。
その情報を参考にして最適な品物を選び、「相手にも喜んでもらえた」「お祝いにまつわるマナーや知識も得られた」という体験ができたら、自然とその企業に好感を抱き、ファンになってくれる可能性が高まるでしょう。
◉-3、アルゴリズムが変化した
検索エンジンやSNSのアルゴリズムは従来に比べ、価値のあるコンテンツを評価するようになりました。
そのため、情報が薄いコンテンツや専門性が低いコンテンツは評価されにくく、Webページの上位に表示されません。
検索エンジンで露出を増やすためには、良質なコンテンツの作成が必要不可欠です。
信頼できる情報であるのはもちろん、専門性や独自性といった観点も踏まえ、質の高いコンテンツを提供することが重要です。
コンテンツマーケティング手法は主に2タイプ

コンテンツマーケティングの手法は、以下の2つのタイプに分けられます。
それぞれのタイプにはさらに細かい手法があるため、以下で各コンテンツの特徴を紹介します。
◉-1、ストック型
ストック型のコンテンツは一度制作すれば長期間にわたって価値が落ちず、時間が経っても需要が続くコンテンツのことを指します。
季節やトレンドなどに左右されることなく、安定したアクセスを見込めるのがメリットです。
こうしたコンテンツを継続的に蓄積していくことで、自社のWebサイトやアカウントに辿り着く消費者を増やせるでしょう。
具体的には、次のようなコンテンツがストック型にあたります。
| ストック型コンテンツ | 特徴 |
| ブログ記事 | ・オウンドメディアなどで自社の商品・サービスを紹介できる・ハウツー記事など役立つ情報を発信できる・主に長めのテキストで構成され、読み応えのある記事を蓄積すれば継続的なアクセスが期待できる |
| SNS(文字・画像・動画投稿コンテンツ) | ・InstagramやX(旧Twitter)などで、商品の使い方や企業紹介といった情報を発信する・時間が経っても役立つ内容は検索で見つけられやすく、ストック型として機能する |
| 動画コンテンツ | ・YouTubeやTikTokなどで配信される動画・テキストだけでは伝わりにくい情報を視覚的にわかりやすく届けられ、訴求力が高い |
| 音声コンテンツ | ・ラジオやポッドキャストなど音声のみの配信・ノウハウや課題解決のヒントをじっくり発信できる・通勤や作業中など「ながら利用」ができる点が魅力 |
| ホワイトペーパー | ・商品・サービスの概要や調査結果をまとめた資料・サイトからダウンロードでき、顧客も比較的気軽に入手しやすい |
| インフォグラフィック | ・データや調査結果をグラフやイラストでわかりやすくまとめたもの・一目で要点を伝えやすく、SNSなどでも拡散されやすい |
| 書籍 | ・出版には時間がかかるが、信頼性が高いコンテンツ・必要なときにあとから見返してもらいやすい・資料や情報源として長期的に活用できる |
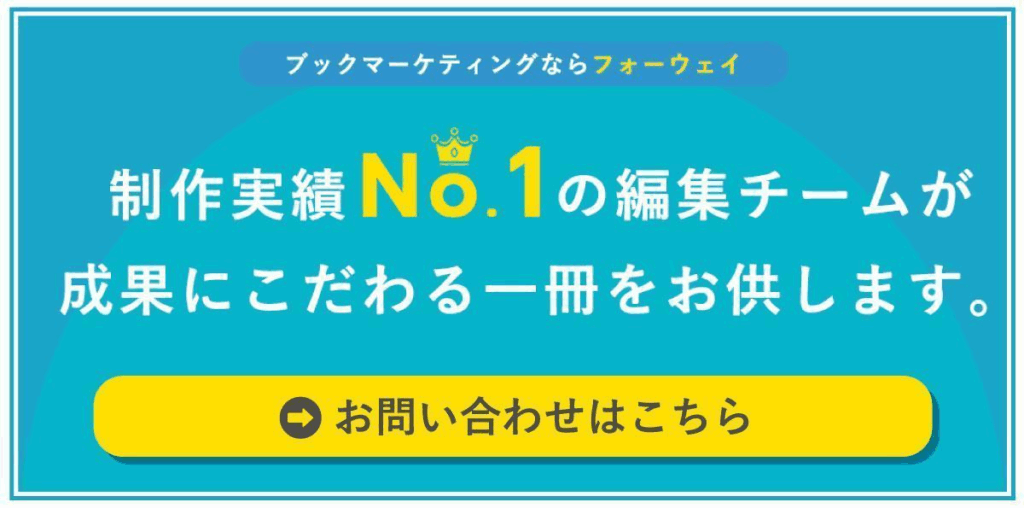
◉-2、フロー型
フロー型コンテンツは鮮度やタイミングが重視され、拡散されやすいのが特徴です。
そのため、新商品や新サービスの告知、キャンペーンなど「今すぐユーザーに知ってもらいたい情報」を伝えるのに適しています。
ただし、フロー型コンテンツは短期間で効果が出やすい反面、時間が経過すると発信した情報が埋もれてしまい、価値が薄れやすいのがデメリットです。
代表的なフロー型コンテンツとして、以下が挙げられます。
| フロー型コンテンツ | 詳細 |
| SNS(タイムライン消費型のコンテンツ) | ・SNSの中でもニュースやトレンド、キャンペーン告知、日常の出来事などをリアルタイムで発信・タイムライン投稿や、24時間で消えるストーリーズ機能が該当する |
| プレスリリース | ・新商品の発売やイベントの開催などをメディアを通じて発信する・記事に引用される可能性が高く、普段接点のない層にも届きやすい |
| メールマガジン | ・登録している既存顧客に直接アプローチできる・登録者の属性をもとに、特定のユーザーに合わせて配信可能 |
| イベント・セミナー | ・自社に関心を持つユーザーを集めやすく、新規層にもアプローチできる・ウェビナーのようにオンライン開催なら、録画を残して動画コンテンツとして再利用できる |
コンテンツマーケティングに取り組むメリット

コンテンツマーケティングを実践することで、以下のようなメリットが得られます。
・潜在顧客のリード獲得
・自社の認知度向上とブランディングの実現
・コンテンツの資産化
・将来的な広告費の削減 |
4つのメリットについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、潜在顧客のリード獲得
ユーザーが欲する情報を提供し続けることで、自社に興味を持ってもらうきっかけができます。
興味を持ったユーザーがホワイトペーパーをダウンロードする等のアクションを起こす際、連絡先など必要事項の記入を行います。
これが「リードの獲得」です。
リードを獲得できると、その連絡先に対して自社のメルマガを配信したり、電話やメールでキャンペーン情報を伝えるなど、具体的な営業活動につなげることができます。
ほかにも、コンテンツ発信をきっかけとしたメルマガの登録などもリード獲得の手法として考えられます。
◉-2、自社の認知度向上とブランディングの実現
ユーザーにとって有益な情報を提供し続ければ、SEO順位で上位獲得ができ、自社の認知度が上がることが期待できます。
有益な情報であれば、ユーザーによって拡散されていく可能性があるので、自ずと認知度が上がっていくのです。
さらに発信するコンテンツが企業のブランドイメージそのものになるため、自社の事業領域における専門家としてのブランディング効果が期待できます。
◉-3、コンテンツの資産化
コンテンツには情報の新鮮さが求められるフロー型コンテンツと、時間が経過しても価値が失われにくいストック型コンテンツがあります。
ストック型コンテンツは、フロー型のように短期間で大きく拡散されることは少ないものの、公開し続ける限り安定した集客効果を期待できるのが特徴です。
有益なコンテンツは既存顧客との関係強化に役立つだけでなく、検索から流入したユーザーが新規顧客になる可能性もあります。
蓄積されたコンテンツは自社にとって資産となり、さらにアクセス数を伸ばすことにもつながります。
◉-4、将来的な広告費の削減
自社のサービスや商品を購入してもらう手っ取り早い方法は、広告です。ただし、広告は成果が期待できますが、打ち続ける必要があり、結果的に広告費がかさみます。
しかし、コンテンツマーケティングで発信した情報は継続的に費用を投じなくてもネット上に残り続け、長期的な広告費の削減になります。
顧客がファン化して継続的に自社サービスを利用してくれれば、費用対効果が非常に高い施策となるのです。
【9ステップ】コンテンツマーケティングの戦略設計の仕方

コンテンツマーケティングの失敗でよくあるのが、目的設定や準備も行わずにいきなりコンテンツを作りはじめてしまうケースです。
しかし、まずは成果を得るために戦略を練る必要があります。
具体的には、以下のステップに沿って進めていきます。
・ステップ1:ターゲットを設定する
・ステップ2:カスタマージャーニーを作成する
・ステップ3:目的を明確化する
・ステップ4:コンテンツマーケティング手法を決める
・ステップ5:KGI・KPIを設定する
・ステップ6:責任者とメンバーを決定する
・ステップ7:スケジュールとコンテンツテーマを確定する
・ステップ8:コンテンツを制作する
・ステップ9:結果を測定してPDCAを回す |
順を追って詳しく解説します。
◉-1、ステップ1:ターゲットを設定する
ターゲットがぶれてしまうと、制作するコンテンツもテーマが不明瞭なものが増えてしまい、結果的にはコンテンツマーケティング自体が徒労に終わる可能性が高まってしまいます。
その中で、ターゲット設定のコツとしては「これまでに集客できていない理想の顧客像」を分析のうえ、設定することです。
マーケティング用語でいう「ペルソナ」を設計します。
自社の顧客になりうる人物像を想像し、言語化することが重要です。
ペルソナ設計では、「デモグラフィック」と呼ばれる人口統計の属性データを使います。
「住所」「性別」「年齢」「職業」「所得(年収)」「世帯規模」「学歴」など、自社サービスにマッチするよう細かく想定するのです。
そのうえで、求めるユーザーの「ライフスタイルの送り方」「思考の傾向」「特有の悩みやストレス」「願望」を設定し、明確に文章で言語化することでペルソナが完成します。
◉-2、ステップ2:カスタマージャーニーを作成する
ターゲットが設定できたら、カスタマージャーニーを作成します。
カスタマージャーニーとは、ターゲットが自社の商品やサービスを認知して購入に至り、その後も継続して利用してくれるまでのプロセスを可視化したものです。
カスタマージャーニーの作成では、認知・興味・比較検討・購入・継続利用といったフェーズごとに顧客の思考や感情、行動を洗い出します。
たとえば、「認知」のフェーズでは、自社の商品やサービスを知るきっかけがSNSなのか、動画コンテンツなのかなどが洗い出す要素の一つです。
顧客の志向や行動などを理解しておくことで、施策を立てやすくなります。
◉-3、ステップ3:目的を明確化する
カスタマージャーニーを作成したら、次に行うべきはコンテンツマーケティングの目的を明確にすることです。
まずは解決したい課題を整理し、そのうえで以下のような目的を具体的に設定します。
・CV(コンバージョン)の獲得
・見込み度の高いリードの獲得
・自社の認知度向上やイメージアップ
・採用活動につなげるためのブランディング |
さらに、CVやリードの獲得など、自社サービスや商品の購買につなげたい場合、「どのサービスおよび商品を誰に届けたいのか」を設定する必要があります。
目的とマーケティングの着地点となるサービスを明確化し、社内で共通認識を持って取り組むことが大切です。
◉-4、ステップ4:コンテンツマーケティング手法を決める
ターゲットやカスタマージャーニー、目的が明確になったら、次はどの媒体で、どのようなコンテンツマーケティングを実施するのかを決めていきます。
たとえば、Z世代や20代前半の層であれば、動画やSNSを活用したコンテンツが効果的です。
一方で、BtoB企業を対象とする場合は、サービス導入事例をまとめたホワイトペーパーや、専門的なノウハウを整理した書籍などが適しています。
ターゲットに合わせて媒体と手法を選択することで、より効果的なコンテンツマーケティングが可能になります。
◉-5、ステップ5:KGI・KPIを設定する
マーケティングでは、最終的な目標を示すKGIと、その進捗を測る中間指標であるKPIを決めます。
具体的な指標は、月間リード数や記事PV、コンバージョン率などです。
たとえば「最終的な成約数30件」をKGIとするなら、その達成に向けたKPIとして「月間リード数100件」を目標に設定するといった形です。
◉-6、ステップ6:責任者とメンバーを決定する
コンテンツマーケティングは成果を安定して出すまで時間がかかります。
したがって、コンテンツマーケティングのプロジェクトに根気よく情熱を持って取り組んでくれる、理解ある責任者を決定する必要があります。
コンテンツマーケティングでは、成果につながらない時期というのが訪れます。
常にトライアンドエラーを繰り返しながら、「成果につながらないコンテンツはどのように改善していくのか」といった意識が重要です。
責任感と覚悟を持って意思決定を行える責任者を任命しましょう。
そして、責任者を決めたら、次はともにプロジェクトに取り組むメンバーの招集をします。
会社としてコンテンツマーケティングを実施する目的と意義を理解して、そこに共感して取り組んでくれるメンバーを選びましょう。
ありがちな失敗としては、次のようなメンバーを集めてしまうパターンがあります。
・文章を書くのが好きなメンバー
・過去にライティング経験があるメンバー
・通常業務の合間に手伝ってくれそうなメンバー |
コンテンツマーケティングにおけるSEOライティングには、必ずしも紙媒体などでライティングに従事した経験は必要ありません。
また、片手間ではそのうち手が回らなくなって放置されてしまうのがオチです。
コンテンツの品質を保つには、あくまでビジョンと目的に共感してくれるメンバーを集めなければなりません。
▶︎コンテンツマーケティングの失敗要因については、関連記事【コンテンツマーケティングの失敗を招くNG行動6】もあわせて参考にしてください。
◉-7、ステップ7:スケジュールとコンテンツテーマを確定する
責任者とメンバーが決まったら「スケジュール」と「コンテンツテーマ」を確定させます。
コンテンツマーケティングは、一朝一夕で成果や効果が出にくい施策のため、最低でも1年間のスケジュール計画を立てる必要があります。
その際、決めなければならない要素としては以下の通りです。
・アクセスやCVといった1年後の数値目標
・具体的なコンテンツの内容と制作担当者、制作の締め切り |
コンテンツマーケティングによって、広告に頼らない価値ある基盤を1年後に作り上げるために、詳細なタスクを整理して、「誰が」「いつまでに」「どんなコンテンツ」を制作するのかを計画立てましょう。
目標達成に向けて、たとえば3か月目までは認知獲得や商品理解を促すコンテンツを制作し、6か月目以降は少しずつCVにつなげていくために、「購入欲求」をかき立てるコンテンツを制作する、といった計画です。
さらに、上記スケジュールの組み立てができたら、具体的なコンテンツの確定をしていきましょう。
目的や顧客がどのような情報を欲しているかを考え、テーマを選びます。
◉-8、ステップ8:コンテンツを制作する
コンテンツ制作では、マーケティングの目的を踏まえ、設定したターゲットやカスタマージャーニーに沿った内容を設計することが重要です。
ユーザーの関心を引きつけるためには、有益な情報を提供するだけでなく、デザイン面にも配慮する必要があります。
レイアウトや配色、フォントのサイズ、種類など、見た目の印象も影響を与えます。
また、制作したコンテンツには、自社サイトやサービスページへスムーズに移動できる導線を用意しておくことで、売上や商談といった成果につながりやすくなります。
◉-9、ステップ9:結果を測定してPDCAを回す
コンテンツは作成して終わりではなく、その後の効果測定と改善が欠かせません。
実際には、せっかく制作したコンテンツが期待した成果につながらない場合もあります。
また、新しい情報が次々に発信されるなかで、自社コンテンツの検索順位が下がってしまうことも考えられます。
そのため、あらかじめ設定したKGI・KPIを基準に、どの程度効果が出ているのかを定期的に確認しましょう。
そこで明らかになった課題や改善点を次の施策に反映させることで、PDCAを回しながら成果を高めていくことができます。
コンテンツマーケティングを成功させるにはターゲットに合わせた手法選びが重要!

コンテンツマーケティングは、広告のように企業側から積極的にアプローチする「攻めのマーケティング」ではなく、ターゲットが集まりやすい媒体に魅力的なコンテンツを配置し、自然に関心を持ってもらう「待ちのマーケティング」です。
そのため、ターゲットが集まりにくい媒体にコンテンツを置いても効果はありません。
成功のポイントは、ターゲットが集まる場所を見極め、そのうえで効果的な手法を選ぶことです。
たとえば、企業を対象とする場合、企業の課題解決につながる情報や専門性を示す書籍・ホワイトペーパー・プレスリリースといったコンテンツが有効です。
一方で、決裁者層へのアプローチや潜在顧客との関係構築においては、SNSやブログも重要な役割を果たします。
特に、自社の専門性を発信したり、企業のブランドイメージを伝えたりするうえで効果を発揮します。
このように、コンテンツマーケティングでは「ターゲットに最適化した手法の選択」が成功を左右するのです。
◉-1、富裕層や企業などがターゲットの場合は書籍でのコンテンツマーケティングがおすすめ!
現代はインターネットを通じて膨大な情報を得られる一方で、その中には根拠があいまいで信頼性に欠けるものも少なくありません。
一方、出版社から刊行された書籍は「現物」として手元に残るだけでなく、Web記事やSNS投稿と比べてテーマを深く掘り下げ、体系的にまとめられています。
そのため、専門性や権威性をアピールでき、読者からの信頼やブランド価値の向上につなげやすい点が魅力です。
また、出版後には出版記念イベントやセミナーの開催、SNSやオウンドメディアでの紹介といった形で二次活用でき、マーケティング効果をさらに広げられます。
▶︎企業出版の詳細については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

◉コンテンツマーケティングの成功事例
コンテンツマーケティングとして書籍を出版し、成功した事例として3つ挙げます。
・書籍でブランディングと見込み客獲得を実現した事例
・出版でファン化が加速し、LTV向上につながった事例
・発信に悩む食品メーカーが書籍によって差別化に成功した事例 |
それぞれの事例を以下で紹介します。
◉-1、書籍でブランディングと見込み客獲得を実現した事例
保険代理店向けのコンサルティング事業を立ち上げた経営者は、新規開拓の有効な手段がなく、信頼性を高めるブランディング施策を模索していました。
そこで選んだのが企業出版。
フルコミッション(成果報酬)が当たり前の保険業界において、「月額給与制の一律報酬型」で業績を伸ばした独自のノウハウを体系化し、書籍として発信しました。
出版後は大きな反響を呼び、わずか発売2週間で即重版が決定。
Amazonでも一時的に欠品するほどの人気となりました。
また、出版記念セミナーには60名が参加し、その場で20名と商談、複数件のコンサル契約へとつながっています。
さらに、大手生命保険会社の支社長や部課長クラスにも読まれ、講演依頼が継続的に舞い込むように。
加えて、書籍が経営者同士で紹介される動線が生まれ、紹介を通じて新たな見込み客との接点が広がりました。
結果として、本業である保険契約の件数も増加し、書籍出版がきっかけとなって大口契約の成約につながるなど、大きな成果を上げることができました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、出版でファン化が加速し、LTV向上につながった事例
あるサプリメントメーカーでは、商品の販促と長期的なブランド構築を目的に書籍を出版しました。
ターゲットは中年期以降の女性とし、「一生のうちで変化の多い「女性の人生の悩み」を解決する」というコンセプトを掲げたことで、顧客の共感を獲得しました。
出版時には著者と連携し、SNSでの情報発信を強化。
その結果、Amazon予約が殺到し発売前に重版が決定しました。
また、既存顧客向けに実施した書籍プレゼント企画では、予想の8倍にあたる240名以上が応募。
贈呈した顧客の半数以上がリピート購入を続けるなど、LTV(顧客生涯価値)の向上にもつながっています。
▶︎サプリメントメーカーの詳しい事例については【【事例コラム】”書籍無料プレゼント”に想定の6倍の応募、リピート率アップにインパクト!サプリメントメーカーの出版プロジェクト】もあわせて参考にしてください。
◉-3、発信に悩む食品メーカーが書籍によって差別化に成功した事例
わさびの開発・製造・販売を手がける食品メーカーは、日本文化の象徴である「わさび」の魅力を広めると同時に、自社のPRにつながる新たな発信手段を模索していました。
しかし、従来のプロモーションでは成果に限界があり、同業他社との差別化が大きな課題となっていたのです。
そこで、料理に関心を持つ30代〜40代女性をメインターゲットに設定し、わさびの効能や歴史、レシピを紹介する書籍を出版。
出版をきっかけに著者と料理研究家によるトークイベントを開催し、その場で50冊以上を販売する成果を上げました。
また、営業活動に活用できるよう書籍のダイジェスト版を小冊子として制作し、営業ツールとしても展開しました。
結果的に、書籍を通じて「わさびファン」を増やし、販売拡大につながっています。
◉コンテンツマーケティングに関するよくある質問

最後に、コンテンツマーケティングに取り組む際によくある質問に回答します。
◉-1、どのくらいで効果が出ますか?
コンテンツマーケティングは「攻める」手法ではなく、「待つ」手法であるため、新たに始めた場合は効果が出るまでに早くても3〜6か月、一般的には半年〜1年以上かかります。
SEOやSNSでは、継続的に取り組み、信頼や評価を積み重ねる必要があります。
そのため、即効性を期待するのではなく、長期的な視点で取り組むことが重要です。
◉-2、どんな企業に向いていますか?
コンテンツマーケティングは、BtoB・BtoCを問わず、顧客が購入前に情報収集を行う傾向が強い業界に適しています。
特に高額商品や専門性が高い商品、比較検討が必要な商品・サービスなどに、コンテンツマーケティングは効果的です。
◉-3、自社でやるべきですか?外注したほうがいいですか?
コンテンツマーケティングは自社でも取り組むことが可能ですが、すべてを内製化しようとするとリソースの負担につながるおそれがあります。
効果的なのは、役割を分担することです。
たとえば、戦略設計や自社にしかわからない専門知識の提供は社内で担い、記事執筆・デザイン・動画制作・編集といった制作部分は外注するといった形です。
こうすることで、自社の強みを活かしながら効率的に運用でき、クオリティも安定しやすくなります。
さらに、外注パートナーを活用することで最新のマーケティング手法や専門スキルを取り入れられるのもメリットです。
【まとめ】権威性を高めるなら書籍を活用したコンテンツマーケティングがおすすめ
この記事では、コンテンツマーケティングの手法や効果を発揮するための戦略について解説してきました。
コンテンツマーケティングは根気よく続ける必要がありますが、自社コンテンツを魅力に感じた顧客はファンとなり、長期的にサービスを利用し続けてくれる可能性があります。
そのためには、「ブレないためのターゲット設定」と「目的を見失わないための戦略設計」が重要です。
広告費を削減し、安定した売上を積み上げるためのコンテンツマーケティングを実施するうえで本記事の内容を参考にしてください。
「フォーウェイ」はブックマーケティングを主軸とし、徹底的な経営コンサルティング目線で書籍の出版をサポートしています。
企業のブランディングにも役立つ書籍を活用したコンテンツマーケティングを検討しているのなら、フォーウェイにご相談ください。
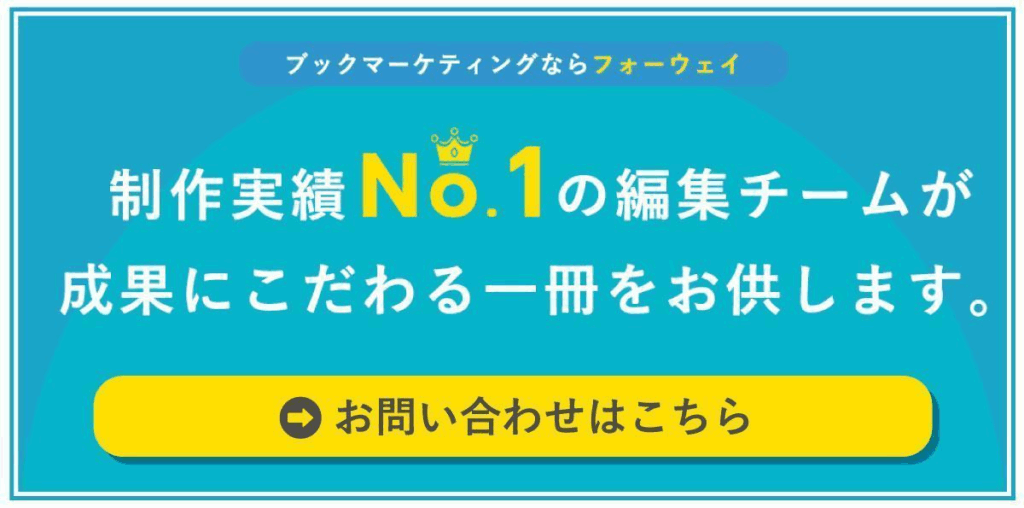

「今までいろいろな集客方法を試したけれど、どれが効果的か分からなかった……」このような悩みをお持ちの経営者は多くいらっしゃいます。
広告やチラシ、インターネットの対策など「これをやると良いよ!」と話には聞いていても、新しい施策を考えるのは難しいですよね。
本記事では不動産会社におすすめの集客方法や、役立つノウハウをまとめて紹介します。
新規顧客の獲得に力を入れたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
◉中小不動産会社が大手に勝てる集客の方法とは?
中小不動産会社が、大手不動産会社と戦うためには「自社の強みを活かした集客方法を考える」ことが重要です。
資金力や知名度などパワーのある大手不動産会社と勝負するためには、同じような広告やチラシだけでは勝てる可能性が低いです。
さまざまな施策を打つ際には、以下のようなポイントに力を入れてみてください。
・役立つコンテンツを作って顧客に貢献する
・大手に負けない情報を集めて量で勝負する
・自社のメインエリアの情報を充実させる
すぐに成果につながらないことでも「顧客のためになること」に注力して行動すると、会社のイメージアップにつながり、顧客からの信頼を得やすくなります。
また、一度に広範囲をカバーすると時間とコストがかかるので、まずは自社の周辺エリアに絞って情報を集めていくとよいでしょう。
最適な方法で集客活動を行えば、小さな不動産会社でも大手企業に勝てる可能性は十分にあります。
▶︎不動産会社の集客戦略については、関連記事【不動産会社の集客戦略を徹底解説|成果につながるオンライン・オフライン施策】もあわせて参考にしてください。
◉不動産会社におすすめの集客方法

不動産会社におすすめの集客方法は主に以下の6つです。
・営業代行
・リスティング広告
・ホームページ
・SNS
・ポータルサイト
・チラシ(ポスティング)
どれか1つに絞るのでなく2~3種類を併用していくことがおすすめです。
画像や文章、動画などは作成したものを複数の媒体に使いまわすことも可能なので、効率よく展開していくとよいでしょう。
◉-1、営業代行
集客に力を入れたいけれど、何からやればよいか分からない方は「営業代行」を依頼するのがおすすめです。
営業代行というと「テレアポ」や「訪問営業」などが思い浮かぶ人もいるかもしれませんが、依頼できる内容は多岐にわたります。
具体的には以下のような内容を依頼できます。
・テレアポ
・訪問営業
・リスト営業
・顧客管理
・社員教育
・SNS市場調査
・マーケティング戦略の選定
扱う作業範囲は代行会社によって異なりますが、自社の悩みを解決できるさまざまなサポートを行ってくれるケースが多いです。
自己流で施策を進めるよりも、専門家に頼んだほうが時間を無駄にせず売上を伸ばせる可能性があります。
◉-2、リスティング広告
「リスティング広告」とは、ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を自動的に表示させる仕組みを持つGoogle社の広告のことです。
例えば「大学受験」と検索すると、自動的に「予備校・塾」などの広告が表示され、ユーザーがわざわざ検索しなくても商品を見つけやすくなっています。
広告を出稿する際は、自社で以下のような情報を細かく設定できます。
・出稿期間
・出稿する時間や曜日
・表示させる地域
・ターゲットの年齢
このような設定をすることによって「土曜日の夜に東京都でインターネットを見る男性」といった人物像を指定できるので、届けたい人に広告を見てもらいやすくなります。
◉-3、ホームページ
不動産会社が集客するうえで欠かせないのは、自社ホームページの強化です。
チラシや広告などで集客を行う際も、会社情報の紹介としてホームページは欠かせません。
ホームページから直接、集客を行う場合は「SEO」の施策が必須です。
具体的に行う内容としては、以下のようなものがあります。
・サイトマップの設置
・ページスピードの改善
・内部リンクの設定
・タグの最適化
・有益なコンテンツ作成
自分で行うこともできますが、難しい作業も多いため「SEO専門会社」に依頼するのが得策です。
有益なコンテンツ作成としては、顧客にとって役立つ専門的な記事やTIPSなどを紹介すると効果的でしょう。
▶️SEO対策のためのコンテンツ作成については、関連記事「SEO対策とは? 効果的な戦略の組み立て方と対策方法」もご覧ください。
◉-4、SNS
企業が集客を行う際に欠かせないのが、SNSの活用です。
代表的なSNSは以下の5つです。
・X(旧Twitter)
・YouTube
・Instagram
・Facebook
・TikTok
これらのSNSを使って行う施策には、以下のようなものがあります。
・SNSインフルエンサーマーケティング
・自社アカウントでの情報発信
・SNS広告の運用
SNSは若年層に人気があるイメージをお持ちの方も多いですが、実際には幅広い年齢層が利用しています。
特に、中小企業のSNS運用は顧客と距離を縮めやすいのでおすすめです。
顧客との距離を近づけるためにはSNSの自社アカウントを運用するのが効果的です。
SNSごとに特性はありますが、企業ブランディングの一環としてX(旧Twitter)ならば代表者が情報発信し続けることで、一定のファンがつきます。
Instagramの場合は、企業の公式アカウントとして運用し、不動産情報を求めるユーザーが関心を持つような有益な情報発信を心がけましょう。
▶SNSマーケティングについては、関連記事【【保存版】SNS運用とは?手順や失敗例、集客につなげる運用術を解説!】もあわせて参考にしてください。
◉-5、ポータルサイト
不動産会社の集客で効果を上げやすい施策として「ポータルサイト」の活用があります。
ポータルサイトとは「インターネットの玄関口」のことで、不動産業界の代表格としては「SUUMO」や「LIFULL HOME’S」などがあります。
これらのサイトは非常に大規模なため、多くのアクセスが集まる点が魅力です。
ポータルサイトに掲載するとそこからの流入が期待できますが、掲載するには費用が発生することがあるので、事前にチェックしておきましょう。
◉-6、チラシ(ポスティング)
集客の方法として、チラシをポスティングすることも有効な手段です。
アナログな方法ですが、特にインターネットをあまり見ない年齢層には効果があります。
ターゲットとなるエリアの周辺に重点的にポスティングすることで、より高い効果を得られます。
チラシを作成する際には、見やすく、分かりやすいデザインにすることが重要です。
何種類か作ってみて反応の良いデザインを割り出し、繰り返しポスティングを行いましょう。
▶アナログマーケティングについては、関連記事【デジタル全盛期だからこそ重要なアナログマーケティング戦略】もあわせて参考にしてください。
◉営業代行や広告にはどのくらいの集客効果があるのか?

営業代行や広告運用では、どの程度の効果が得られるのでしょうか。
・リスティング広告のCV率
・折り込みチラシの反響率
・営業代行の集客効果
具体的に解説していきます。
なお、どの施策を行った場合でも、効果が出るまでには一定の期間が必要です。
はじめの一か月程度で思ったような結果がでなくても、継続して経過観察することが大切です。
◉-1、リスティング広告のCV率
不動産のリスティング広告のCV率は「約2.4%」が目安と言われています。
あくまで目安の数値となるので、広告の内容や出稿のタイミングで一件ごとに結果は異なります。
CV率がアップし問い合わせが増えたとしても、成約につながるかどうかはまた別の話です。
広告で良い効果を得られても、受け入れ体制が整っていないと機会損失してしまう可能性があるので注意しましょう。
顧客がスムーズに、ストレスなく問い合わせできる導線を整えておくことが肝心です。
◉-2、折り込みチラシの反響率
新聞に折り込みチラシを入れた際の反響率は「0.01~0.3%前後」が目安と言われています。
つまり5万枚のチラシを配布した場合、5~150名程度の反響を得られる可能性があります。
数としては少なく感じてしまうかもしれませんが、紙媒体での集客は時代に流されずに成果を出せるひとつの方法です。
チラシの素材や形、デザインなどにこだわれば、より良い成果を出せる可能性もあるでしょう。
◉-3、営業代行の集客効果
営業代行を利用した場合の集客効果を、平均値として表すのは難しい場合が多いです。
どのくらいの集客効果があるのかは、依頼した会社(営業担当者)や内容によって異なるので一概には言えません。
一般的な営業代行を依頼した場合「成果報酬」と「固定報酬」に分かれています。
成果報酬の場合であれば成約しなければ料金が発生しないので、初期コストがかからず利用しやすいです。
固定報酬の場合は、費用対効果が得られるのかをシミュレーションしてから利用しましょう。
◉-4、パンフレットや書籍出版での顧客獲得
顧客との関係性を構築するためには、パンフレット等の営業ツールを活用することも効果的です。
「紙媒体」の信頼性は今もなお根強く、ほかの情報発信施策と比べると、情報量も豊富です。
営業マンが口頭ですべてを説明するのは大変です。
自社が顧客にアピールしたい内容をパンフレットで明確にアピールすることで、伝えたい情報を過不足なく伝えることができます。
書籍についても同様に信頼性ある媒体としてはほかの追随を許しません。
企業向けの出版社や出版プロデュース会社もあり、以前に比べると出版すること自体のハードルは下がっています。
ただし、書店で販売したり、新規顧客を集客したりと広告効果を期待するならば、きちんと書籍を流通・販売してくれる出版社を選ばなければなりません。
書籍を出版することで、契約につながる見込みの高い顧客が集客できたという事例も少なくありません。
▶️出版による効果的なプロモーション方法については、関連記事「出版マーケティングの効果的なプロモーションとは? 広告手段も解説」を参考にしてください。
◉顧客を獲得できている不動産会社の特徴

顧客を獲得できている不動産会社の特徴を紹介します。
・口コミが良い
・オンライン・オフライン両方に対応している
・店舗の場所が分かりやすい
・営業時間が長い・いつでも開いている
成功している企業を参考に、自社でできる施策を取り入れてみてください。
◉-1、口コミが良い
売れている不動産会社の特徴のひとつは「口コミが良い」ことです。
不動産売買は顧客同士の「紹介」で繋がっていくケースも多くあるので、良い口コミを増やせば顧客の増加が期待できます。
友人知人からのリアルな口コミの他に、ポータルサイトの「口コミ欄」は顧客がよくチェックしている場所です。
良い口コミを書いてもらうためには、顧客に喜んでもらえる丁寧な接客をすることが重要です。
日頃から満足してもらえる接客を心がければ、自然と紹介も増えていきます。
◉-2、オンライン・オフライン両方に対応している
近年は「オンライン商談」を希望する方が増加しているので、こうしたニーズに対応できる企業が有利です。
いつでも顧客に対応できるよう、接続環境などを整えておくとよいでしょう。
オンライン商談が人気を集めている一方で、オフライン(対面)での説明を希望する顧客も一定数います。
どちらにも柔軟に対応できると、商機を逃しにくくなります。
◉-3、店舗の場所が分かりやすい
人気の不動産会社は、路面店や駅から近い場所など分かりやすい立地にあることが多いです。
立地の良い場所に店舗を出すのはコストがかかり大きなリスクにもなるので、一歩を踏み出せない人が多くいます。
しかし、知名度と信頼を一気に獲得したい場合は、実店舗の拡大も視野に入れてみましょう。
◉-4、営業時間が長い・いつでも開いている
顧客にとって、自分の好きなタイミング(時間)に対応してくれる不動産会社は非常に便利です。
夜遅くまで営業していたり、休日が少なかったりすると「いつでも相談できる」と感じ、顧客にとって頼れるお店になります。
ただし、この方法は自社スタッフにとっては負担になりすぎてしまうことがあります。
社員が気持ち良く働ける環境も大切なので、程よいバランスの営業時間を設定しましょう。
◉うまく集客できないときは誰に相談すればいい?

「集客をがんばってもなかなか成果が出ない……」と、悩んだ際は以下の業者に相談してみてください。
・コンサル会社
・広告代理店
・SEO対策会社
専門的な知識がないまま努力したとしても、時間を無駄にしてしまうことがあります。
多少費用がかかっても、適切なルートを示してくれる専門家に依頼することが業績アップへの近道と言えるでしょう。
◉-1、コンサル会社
「コンサル会社」では、専任のコンサルタントが経営者の相談に乗ってくれます。
「どういった方向性で経営を進めるのか?」「自社にマッチする施策は何か」など、経営者と話しながら、ベストな施策を決めていきます。
予算やかけられる時間などを把握した上で自社の状況にあう施策を提案してくれるので、失敗する可能性が少ないです。
◉-2、広告代理店
広告代理店では、リスティング広告やチラシの制作や配布方法、効果的なアプローチの仕方などを提案してくれます。
広告代理店はさまざまな企業の営業をサポートしていますが、不動産会社の広告を担当したことがある会社であればより安心して依頼できます。
過去の運用実績などをチェックして、信頼できそうな企業に依頼しましょう。
◉-3、SEO対策会社
SEOの施策を考えてくれる企業に依頼すると、自社ホームページから問い合わせが入るような施策を提案してくれます。
広告やポータルサイト、チラシなどは常にアプローチを繰り返さなくてはいけませんが、自社サイトは永続的に会社の財産となります。
そういった意味でも、自社ホームページのSEO強化は必ず行っておきたい施策と言えるでしょう。
ホームページ以外にもSNSや動画作成など、Web関連のことをまとめてお願いできる業者もあります。
新しい施策をはじめる前に、まずは自社ホームページを整えるところからはじめてみてはいかがでしょうか。
◉【まとめ】不動産会社の集客の悩みは専門家に相談しよう
不動産会社の集客にはいくつかの方法がありますが、時期や内容によってその時々に最適な方法が変化していきます。
考える施策がマンネリ化してしまう人や、新しい知識を取り入れたい経営者の方は、迷わず専門家に相談しましょう。
フォーウェイでは、Webサイトの集客に困っている企業に向けて「無料SEO診断」を行っています。
自社サイトの課題を洗い出すことで適切な施策が考えやすくなり、やるべきことが明確になります。
不動産会社の集客率を上げたい方は、ぜひフォーウェイにご相談ください。
参考:株式会社フォーウェイの出版サービスによって10億円以上の売上獲得をした不動産会社の事例など盛りだくさんの成功事例集の無料プレゼントはこちらから
参考記事:不動産会社の集客方法16選【成約件数9倍アップ!StockSun式戦略!】

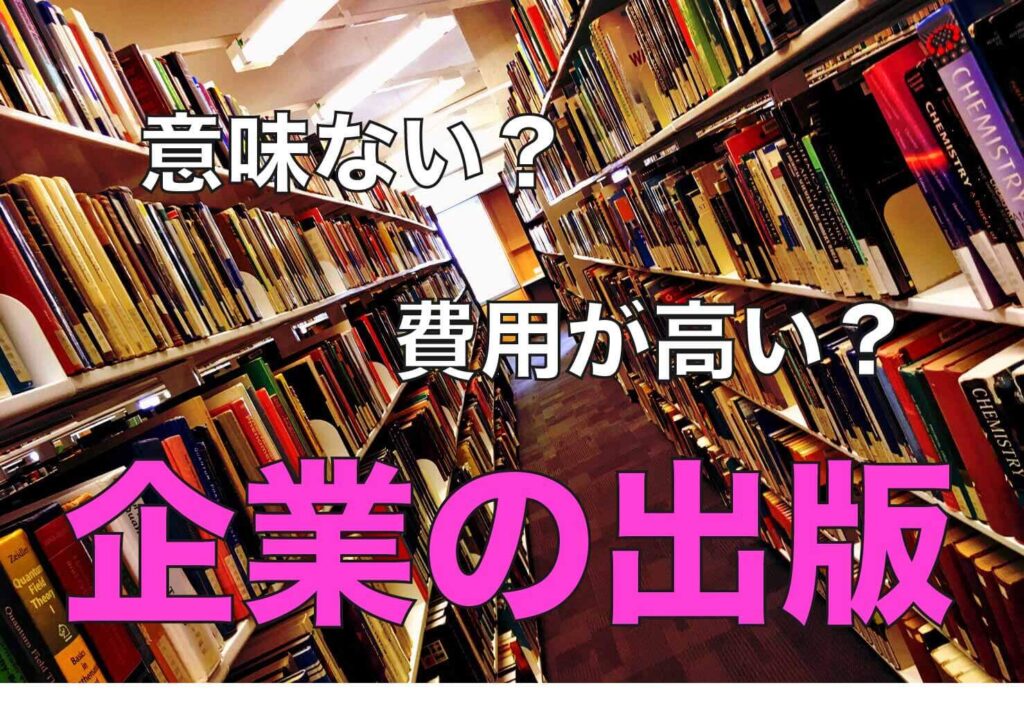
企業がマーケティングやブランディングのために行う企業出版(ブックマーケティング)。
出版不況と呼ばれる時代において、企業出版をメインでサポートしている出版社は売上や刊行点数を伸ばし続けています。
つまり、企業が企業出版を決断する機運は高まっているといえるでしょう。
企業が自らのストーリーや価値観を世に伝える手段として、書籍というメディアの可能性が再評価されています。
今回の記事では、企業出版(ブックマーケティング)のメリットを紹介しつつ、数字では表せない、企業出版だからこそ実現できる書籍の使い道を解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
企業出版とはベストセラーを狙う出版ではない

出版を実施するにあたり、どうしても気になるのは書籍が売れるかどうか。
ただし、企業出版については、売れる本を作ることを目的としていません。
誤解を避けるために詳しく解説すると、企業出版はベストセラーになる本を目指してはいませんが、「狙ったターゲット」に売れる本を作ります。
出版に際しては企業のマーケティング戦略同様、自社の商品やサービスを知ってほしい顧客層をターゲットとして設定します。
そのうえで、設定したターゲットが手に取りたくなるような企画づくりや、書籍のカバーデザインを仕上げるのです。
不特定多数へ知らしめる広告手法としてではなく、明確なターゲットがある企業であればあるほど、企業出版は適しているといっても良いでしょう。
改めて正確にお伝えすると、企業出版とは、企業が自社の情報や専門知識を書籍の形式で出版することです。
出版社によって「カスタム出版」とも呼ばれます。
企業出版はブランディングや販促活動の一環として活用され、読者に対して企業の知見や価値を提供し、著者のビジネスにつなげることを目的としています。
近年、経営課題を解決する方法として出版を選ぶ企業は増え続けており、多くの企画が実際に出版に至っています。
そうした需要を背景に、既存の出版社が企業出版サービスを提供するケースも増えており、企業出版を専門とする出版社も出始めているようです。
企業出版の発行部数は、プランによって幅がありますが1,000〜5,000部くらいです。
部数や流通範囲が拡大するほど出版費用は上がります。
流通については通常の商業出版と同様の規模で書店にまくケースや、特約書店のみに配本するケース、オンライン書店のみで流通するケースなどさまざまです。
ただ共通するのは、実際に本を店頭に並べるかどうかは書店側の判断になるため、出版前の想定どおりに書店に並ぶかどうかは出してみるまでわからないという点です。
本の企画をはじめ内容については、出版社からの提案を著者が承認して決める形になります。
自費出版のように自分ですべて作るのではなく、自分の表現したい内容をプロの編集者のスキルを借りて形にできるのは大きなメリットです。
出版社がプロのライターをつけてくれる方式が一般的なため、インタビューに答えて上がってきた原稿に赤入れすることが著者の負担になります。
なお、以下にフォーウェイが行った、企業出版経験者への効果実感アンケートの結果リンクも掲載します。
上記のメリットが想像以上に発揮されている事実がよくわかるので、興味があればぜひご覧ください(以下の画像をクリック)。

▶企業出版については、関連記事【「出版の広告効果とは? 企業出版と自費出版の違い」】もあわせてご参考にしてください。
企業出版と他の出版の違い

出版の方式には大きく分けて「商業出版」「自費出版」「企業出版」の3種類があります。
また、企業出版の中にも「集客・ブランディングなどのビジネスゴールの達成」を目的にする通常の企業出版と、弊社フォーウェイが提供する「費用対効果の高いマーケティング」を目的とする企業出版(ブックマーケティング)があります。
それぞれの違いは、次の通りです。
| 自費出版 | 商業出版 | 企業出版(通常) | 企業出版(ブックマーケティング) |
| 出版目的 | ⼩説・エッセイなど私的原稿の書籍 | ヒット作(ベストセラー)制作による出版社の利益確保 | 集客・ブランディングなどビジネスゴールの達成 | 最適な費⽤的効果によるマーケティング出版の実現 |
| 版元 | ⽂芸社、現代書林など | 通常の大手・中小出版社 | 幻冬舎、ダイヤモンド社など | フォーウェイのプロデュースによりグループ出版社パノラボから出版 |
| 編集体制 | なし(ほぼ校正・組版・製本のみ) | 出版社の編集者、実績豊富なライターやデザイナーによる制作(企画内容によってさまざまな形態がある) | フリー編集者や編プロへの委託制作経験の浅い編集担当による制作(の可能性) | 出版実績230冊を超えるプロデューサーの責任編集企業出版実績豊富な編集担当者を選抜ベストセラー実績の豊富なライターやデザイナーアサイン |
| 部数 | 最低500部程度から | 最低3000部程度から | 最低5,000部程度から | 最低1,000部程度から(企画内容により出版社負担での部数増あり) |
| 書店流通 | ほぼなし(⼤書店の「⾃費出版」棚への展開) | 出版社が積極的な書店流通を行う | ⼤⼿出版社通常(部数により500〜1,000書店程度) | 該当書籍のジャンルに合わせた書店営業の実施通常プランに100冊分の1か月書店プロモーション付き |
| プロモーション | ほぼなし | 出版社が積極的にプロモーションを行う | リリース送付+オプションにより買取施策や数百万円単位の広告出稿(追加料⾦なしでの雑誌への露出などは原則なし) | ・リリース送付+セットプランにより割安に広告施策を提供+Amazon販売促進施策のWEB広告をサービス内で実施+オプションとして各種コンテンツサービス、SNSブースト、クラウドファンディングなどの先進的施策・提携ビジネス媒体への掲載確約 |
| 適した著者 | ・とにかく費⽤を抑えて「出版した」という事実が欲しい個⼈・製本された現物を⼿元に持ちたい⼈ | ・基本的に出版社から依頼を受けた人 | ・多額の予算を⻑期的ブランディングに投資する余⼒のある企業・⼤部数の⾃社買取を前提に出版する企業 | ・経営施策として出版の成功を求める中⼩〜中堅企業・費⽤対効果にこだわる経営者やプロフェッショナル・⾃費出版や企業出版・カスタム出版に満⾜できなかった経験のある⼈ |
3つの出版方法について詳しく解説します。
商業出版
商業出版は、出版社が費用を負担して企画し、著者に執筆を依頼する出版方式です。
著者には出版社から、発行部数に応じた印税が支払われます。
出版した本が重版すればするほど印税が増える、著者にとっては夢のある出版です。
予算のかけ方は企画によってさまざまで、原稿の書けない著者にはゴーストライター(ブックライター)を用意したり、イラストレーターやデザイナーを用意して全ページカラーにしたりと、出版社が「売れる」と判断した企画内容に沿って体制が作られます。
注意点として、商業出版では企画から原稿の内容に至るまで、基本的には出版社に決定権があります。
書籍を売ることを目的に出版社が投資し、売れなかった場合のリスクも引き受けるためです。
したがって、自分の本であっても著者の希望は通らない場合が多くなります。
実際に、以下のようなケースが見られます。
・「著者にとってはマイナスイメージになりそうな企画でないと出さない」と言われた
・著者の事業の宣伝を入れようとしたら「流通に支障が出る」「作品性が損なわれる」と断られた
・全然気に入っていないカバーデザインに決められた |
そのため、商業出版の経験者のなかには、「自社のビジネスメリットにもなるかと思って依頼を受けたけど、全然思いどおりにならなかった」といった不満が残っている方もいるようです。
また、商業出版として進行していた企画でも、編集者からのレスポンスがなく停滞して出版されなかったり、実際に出版したものの思うように売れず、結果として数百万円分の在庫を買い取ることになったりと、自費出版と変わらない費用負担が発生するという事例も少なくありません。
このようなリスクもあるため、契約前には内容を十分に確認し、納得したうえで進めることが大切です。
▶︎商業出版については、関連記事【商業出版とは?企業がブランディングを考えたときの出版の選択肢】も合わせて参考にしてください。
自費出版
自費出版は、個人が自身の著作物を自己負担で出版する形式です。
「小説や詩集など趣味で書き溜めていた原稿を出版したい」「人生の軌跡を記録として残したい」といったニーズが多いです。
特徴としては、流通規模の小ささです。
自費出版はおおむね100〜500部程度の発行部数で、書店流通はまったくなしか、ごく一部の書店への配本に限られます。
書店へ配本されるケースでも、「自費出版棚」などの棚にまとめられたり、配本されても書棚に並ばないケースが多いようです。
内容については、自費出版は100%、著者の思いどおりです。
カバーに自作のイラストを入れたりといったアレンジも好きなようにできます。
自費出版での出版社の仕事は、持ち込まれた原稿を校正し、デザインレイアウトして印刷することです。
一方で、「内容に自信がないからもっと売れるように改善提案してほしい」といった希望は叶わないと思ったほうが良いでしょう。
▶︎自費出版については、関連記事【自費出版のやり方を現役書籍編集者が1から分かりやすく解説!】も合わせて参考にしてください。
企業出版(ブックマーケティング)
企業出版(ブックマーケティング)とは、書籍をマーケティングに活用する出版方法です。
企業が自社の事業や商品・サービスなどについてまとめた書籍を出版し、企業や商品・サービスの認知度向上や購買意欲向上などに役立てることを目的としています。
近年はインターネットで簡単に情報を得られるようになりましたが、根拠があいまいだったり、情報源が不明確だったり、発信者の信頼性が低いケースも少なくありません。
その点、書籍は出版社や著者が明示されており、手元に残る形ある媒体であることから、インターネット上の情報よりも信頼性が高いと考えられています。
企業の強みである独自の技術や実績、企業としての取り組みなどをストーリーとしてまとめて一冊の書籍という形で出版すれば、書籍そのものの信頼性や出版社の全国的な販路を活かした効果的なマーケティングが可能になります。
▶︎企業出版(ブックマーケティング)については、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】も合わせて参考にしてください。
企業出版を実施するメリット
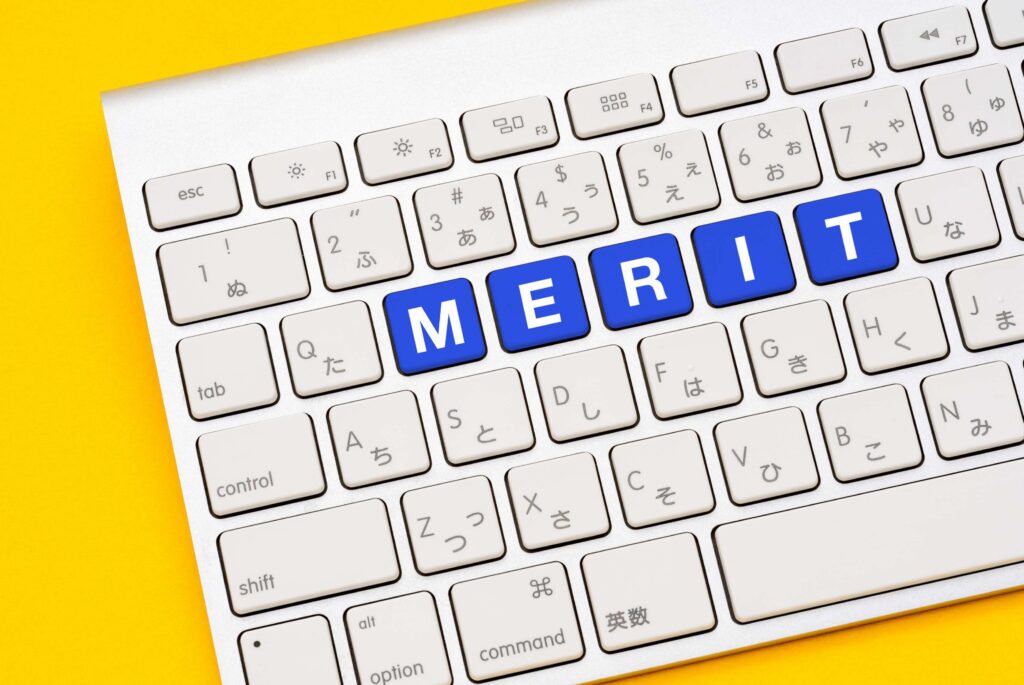
企業の商品やサービスをPRするうえで、世の中にはさまざまな広告手法があふれています。
そんななかで企業出版という形式だからこそ得られるメリットを紹介します。
自社商品やサービスを知ってほしいターゲットに認知拡大できる
世間一般的に認知度を上げるのに手っ取り早いのは、テレビCMや全国紙の新聞広告掲載です。
それぞれかなりの視聴者や購読者がいる媒体なので、認知度を上げるには最適でしょう。
ただし、こうしたマス媒体への広告は1回あたりの負担額が数百万〜数千万円と高額で、しかも広告を打ち続けないと効果は持続しません。
一方、企業出版の広告宣伝の場は書店にある各書棚になります。
先述した通り、狙ったターゲットに知ってもらえる理由の一つです。
たとえば、不動産投資会社が潜在顧客に自社を知ってほしければ、書店の「不動産投資」や「資産形成」の棚に並べることで、自ずと手にとってもらえます。
耳鼻科のお医者さんが耳の病気に関する書籍を出版すれば、耳の病気に悩む人が立ち寄る「家庭の医学」の棚に展開されます。
このように、知ってほしいターゲット層に認知してもらうには企業出版が適しているのです。
企業出版で医者というターゲットへの認知拡大に成功した事例
不動産投資会社が、収入も納税額も高額な医師をターゲットに「不動産投資が医師の節税対策に最適」という内容の書籍を出版しました。
書籍を購入した医師に、不動産投資に大きな節税効果があることを認知してもらうことができ、多くの成約につながりました。
競合に対する優位性を高め信頼度も向上する
書籍は出版社から取次会社を介して書店に流通し、値段をつけて販売されます。
「書籍を出版している企業」という事実により、競合企業に比べた優位性を高められ、信頼度が向上するのです。
書籍を活用した情報発信でその道のプロフェッショナルとして認知してもらえ、社会的な信用が上がり企業ブランディングに貢献します。
競合他社が多い中、確固たる地位を築いた保険代理店
ある保険代理店は、保険業界の問題点とそれを変えるための持論をまとめた書籍を出版。
競合が多く差別化が難しい業種にもかかわらず、業界内での地位確立と顧客企業からの信頼を獲得し、大きく業績を伸ばしました。
他媒体に比べて圧倒的な情報量を誇る
さまざまな広告手段のなかでも、書籍の持つ情報量は圧倒的といえます。
テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、看板……広告のどれと比較しても、書籍ほどの情報量を盛り込める媒体はないでしょう。
書籍一冊でおよそ200ページの量があり、文字の組み方によって変わりますが、文字数にすると7万〜10万字もの情報を発信できるのです。
企業の商品やサービスの魅力だけでなく、企業理念や代表者の考え方などを余すことなく伝えることができる稀有な媒体といえるでしょう。
質の高い顧客からの問い合わせが獲得できる
書籍制作をするにあたって最初に考えるのが、「出版の目的」です。
集客を目的にする場合、自社商品やサービスが見込み客にとってどうメリットになるのかを整理していきます。
マーケティング戦略の基本であるペルソナの設計を、書籍企画づくりの中で同時に行うことができるのです。
先に解説した通り、書籍は信頼度の高い媒体ということもあり、自らが欲する情報が掲載された書籍を読むことで、読者ならびに見込み客から著者の会社に問い合わせするという導線を作ることができます。
著者のファンになった読者は自社ビジネスの内容を理解しているため質の高い顧客となり、商談も簡略化することができます。
このように企業出版は、一冊出版するだけで、他の広告媒体にはなし得ない認知度拡大や啓蒙、集客力向上、そしてブランディングを同時に達成できます。
ニッチな業種でありながら、質の高い問い合わせ獲得につながった事例
建設業専門のコンサルティング会社は、知名度の向上と商圏の拡大を狙って書籍を出版。
タイトルに「建設業のための」というフレーズを盛り込んだことで、ターゲット層への訴求力が高まり、問い合わせが相次ぎました。
最終的に10件以上の顧問契約を獲得し、毎年数百万円の売上を得る結果につながりました。
企業出版による副次的効果とは

ここまでは、企業出版をすることで実現できるわかりやすいメリットを紹介してきました。
次に、出版という手段だからこそ発揮される副次的な効果を解説します。
・著作権が企業側に帰属するため二次活用ができる
・営業ツールとしての活用で囲い込みやクロージングに役立つ
・社員教育や採用強化に活用できる
・メディアに取り上げられる可能性が高まる |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
著作権が企業側に帰属するため二次活用ができる
企業のマーケティング戦略の一環として出版を実施する以上、無視できないのが著作権です。
著作権とは、書籍出版においては書籍の原稿や写真、イラストなど、著作物を保護するための権利です。
知的財産権の一つで、著作物を著作権者以外に無断で使用させない権利でもあります。
企業出版においては、ライターが取材して原稿執筆するケースが一般的ですが、ライターは著作権を放棄し、出版契約した企業側に著作権が帰属するのが基本です。
なかにはイラストや写真など、各コンテンツに応じて著作権が制作者側に帰属しているケースがあるため、使用の際は確認が必要ですが、基本的に原稿については自社の判断で二次利用ができます。
昨今はCookieの規制が強化されるという話題もあり、オンライン上のGoogle広告やSNS広告が利用できなくなる可能性も考えられます。
WEB広告でアクセスを集められなかった場合、SEO対策として自社サイトのコンテンツを強化する重要性はますます増すでしょう。
そこで書籍があれば、コンテンツをホームページや自社オウンドメディアに転載することで、SEO対策としても活用できるのです。
ただ、出版権や所有権については契約での取り決めがあるので、各出版社に問い合わせてみましょう。
営業ツールとしての活用で囲い込みやクロージングに役立つ
書籍が完成すれば、手元に営業ツールとして活用できる書籍が届きます。
活用の仕方は幅広くさまざまですが、来店した見込み客にプレゼントとしてお渡しすることで、信頼性を向上させ、サービスや会社に対する理解度を促進させることができます。
セミナーを開催して販売や配布するという手段も考えられるでしょう。
競合他社との相見積もりになった際に、書籍を送ることでクロージングツールとして効果を発揮したという例も珍しくありません。
ほか、見込み客のリストや過去名刺交換をしたような掘り起こし顧客にDM(ダイレクトメール)として送付するという活用方法も有効です。
社員教育や採用強化に活用できる
企業出版で制作する書籍には代表者の考え方やサービスのメリットが網羅されていることもあり、採用や人材育成に効果を発揮します。
企画内容によりますが、企業が成長するまでにぶつかった壁やそれを乗り越えた方法など、事業拡大するまでの紆余曲折を、これから入社する新人にも知ってもらうことができるのです。
会社がどのような考えをもって経営しているのかを新人が理解できれば、ミスマッチの防止に役立ち、採用後の定着率アップにも大きく寄与します。
メディアに取り上げられる可能性が高まる
企業出版による書籍は、単なる紙媒体としてではなく、企業の広報戦略としても効果を発揮します。
企業名や商品・サービスが新聞や雑誌、WEBメディアなどの第三者視点で紹介されると、広告とは異なる信頼性の高い認知拡大が期待できます。
また、メディア掲載は一時的な広告効果にとどまらず、企業の実績として蓄積されるため、今後のブランディングや営業活動、採用活動などのさまざまなシーンで活用可能です。
企業出版と他の発信施策の比較

続いて、企業出版と他の発信施策の特徴を比べてみましょう。
「紙媒体広告」「WEB広告」「WEB媒体施策」との比較は以下の通りです。
紙媒体広告との比較
まず、新聞や雑誌といった紙媒体への広告出稿を見てみましょう。
紙媒体の広告はその発行部数の多さを活かし、数万〜数百万の人々にリーチできる点が大きな強みです。
一方で、紙媒体は基本的に広告出稿される号が世に出た瞬間にのみ、効果を発揮する施策となります。
効果の長期的継続はありません。
さらに、出稿によってもらえる枠は限られており、盛り込むメッセージはかなり取捨選択しなければいけません。
書籍の場合は、書店流通によって広告効果が持続的に発揮されるのが紙媒体広告と比較した際の強みです。
さらに、詳細な情報や専門知識を一冊分盛り込めるため、読者に対してより深い理解や感動を与えることができます。
説明が難しい製品や、販売に時間がかかるサービスにとっては適した発信手段です。
WEB広告との比較
WEB広告はご存じの通り、費用を投じている間のみ広告が回ります。
メリットとして、少額でも始められること、詳細にデータが出ることで細かな改善アクションを繰り返しやすいことが挙げられます。
一方、実物がある紙媒体以上に「残らない」広告施策であるところが難点。
「先につながらないのはわかっているけど、広告止めると売上落ちるから止められない…」と悩む経営者は多いです。
企業出版では紙媒体との比較同様、長期間にわたって読者に提供されて持続的な効果が期待できる点がポイントになります。
また、本によって読者の関心を引きつけるコンテンツを提供することができるため、たとえば「WEB広告で集客した見込み客に書籍をプレゼント」といった組み合わせ施策で受注確度を高める戦略は効果的です。
WEB媒体施策との比較
WEB媒体施策はWEBメディアに対する記事広告出稿や、自社サイトでコンテンツを発信するオウンドメディア施策を指します。
WEBメディアの記事広告はずっと掲載してもらえる場合があり、自社サイトコンテンツも長期的に掲載される点は大きなメリットです。
一方でWEBコンテンツはどうしてもユーザーが軽い気持ちで閲覧する傾向にあり、問い合わせなどの反響につなげるには相当クオリティの高いコンテンツを自社で作る必要がある点がハードルになります。
また、WEBコンテンツの閲覧者と書籍の読者はかなり層が違うため、こちらもターゲットや目的によってうまく併用することが成果を出すコツです。
この点に関して著者がよく言っているのは、「WEBは良くも悪くも関心がライトで発注権限も予算もないようなリードが多いが、本の場合は“本気の人”が来る」ということです。
このような特性から、特に高単価な商品・サービスは、書籍との相性が良く、強力な集客・販促手段となる可能性があります。
【業種別】企業出版の成功事例

世の中の多くの出版支援サービスは、商業出版を主とする出版社が「副業」として提供しているものが大半です。
つまり、「本業はあくまで売れる本を作ること。出版したいなら費用を払ってくれれば対応します」という姿勢が根底にあるケースが少なくありません。
そうした構造上、顧客のために尽くす体制が築きにくいのが現実です。
それに対して、私たちフォーウェイでは企業出版に「本業」として取り組んでいます。
「顧客のために作り、顧客のために売る」ことを使命に掲げた体制を最初から構築しており、企業出版そのものに真剣に向き合っています。
実際に、業界最多クラスとなる230冊以上の企業出版実績を誇る編集チームがそろっていることが強みです。
在籍するメンバーは全員が、大手出版社の書籍制作を手がけてきた実力派クリエイター。
デザイナーやライター、校正者といった各専門分野においても、複数のベストセラーを生み出してきたトップレベルの人材で構成されています。
そのため、自費出版では実現が難しい、完成度の高い書籍づくりが可能です。
以下では、実際に企業出版を通じて成果を上げた10件の事例を紹介します。

保険代理店|出版を通じて業界内の信頼を獲得し、採用・新規契約数を大幅に向上させた事例
本業とは別に新規事業としてコンサル事業を立ち上げた保険代理店では、有効な集客手段が打てず信頼性獲得のためのブランディング施策を探していました。
そこで、成果報酬型が当たり前の保険業界で、一律報酬型を採用して成⻑を遂げた自社のノウハウをまとめ、保険代理店の経営者が読みたくなる企画・構成の書籍を出版しました。
出版後わずか2週間で重版が決定し、Amazonでは一時的に在庫切れとなるほどの反響を獲得。
出版記念セミナーには60名が参加し、複数のコンサル契約へとつながりました。
また、大手保険会社から講演依頼の増加にもつながっています。
さらに、自社での人材採用にも大きな効果があり、応募者が事前に読んでくれて自社への理解が進み、採用のミスマッチがなくなりました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
不動産会社|医師という専門層に向けた戦略的出版で高確度のリードを獲得し、売上10億円に貢献した事例
ある不動産投資会社では、Web広告による新規顧客の集客を行っていたものの効果がなく、ほぼ紹介に頼っている状況でした。
紹介の場合でも信頼関係構築に多くの時間を要し、成約リードタイムが長くなってしまうという問題がありました。
そこで、医師をターゲットとして「節税対策に不動産投資が効果的」という内容の書籍を出版したところ、多くの読者から問い合わせがあり、出版6か月で10億円以上の売上を達成。
問い合わせのほとんどは書籍を読んだ医師からだったため、成約までのリードタイムが短縮でき営業効率も向上しました。
さらに、同じ顧客が複数の物件を購入してくれるなど、通常の営業に比べて客単価が大きく向上したことも大きな効果でした。
建設会社|経営者の人間力を本で可視化し、採用コストゼロを可能にした事例
湘南エリアで業績拡⼤中の建設会社では、慢性的な⼈材不⾜により受注チャンスを逃してしまうことが課題でした。
そこで、若⼿人材の採用強化とブランド力向上を狙って書籍を出版。
経営者の仕事や経営に関する考え⽅や人柄、創業ストーリーなどを余すところなく盛り込んだ書籍にしました。
出版後、応募者の多くが事前に書籍を読んでから応募するようになり、企業への理解度が高まった結果、採用決定率が大幅に向上。
年間500万円以上かかっていた採用エージェントの費用をゼロに抑えることができました。
地元新聞など複数のメディアからの取材依頼があり、狙いどおりの認知アップ効果を実感したといいます。
若手経営者である社長は、これまで地域の同業他社との関係性に課題を感じていましたが、出版を機に一目置かれる存在へとブランディングに成功しています。
経営コンサル|書籍出版で新しい層にアプローチし、指名相談が急増した事例
建設業専門の経営コンサルタントは、これまで届いていなかった新たな層へのアプローチを目的に書籍を出版しました。
これまでの支援実績やノウハウをわかりやすく整理し、自身の思いや考え方も盛り込んだ一冊に仕上げました。
出版後はわずか1か月で重版が決まり、17媒体のWebニュースに掲載されるなど反響を獲得。
新たに10数件の顧客が増え、若手経営者からの育成相談も急増しました。
ブランド力を高めながら、顧客の接点を作り出すことができています。
食品メーカー|わさびの効果・効能を発信し、販促と啓蒙を両立させた事例
わさびの製造販売を行う企業では、「わさびの魅力が十分に伝わっていない」「他社との差別化が図れていない」といった課題を抱えていました。
そこで、料理に関心の高い30〜40代女性をメインターゲットに、わさびの効能や歴史、アレンジレシピを紹介する書籍を企画・出版。
発売後には、レシピを監修した料理研究家を招き、本社所在地・名古屋の書店で出版記念トークイベントを開催しました。
会場は満席となり、当日だけで50冊以上の売上を記録するなど、認知拡大とファン獲得につながっています。
その後、出版をきっかけに平均聴取者数20万人を超えるラジオ番組から2週連続の出演オファーがありました。
さらに、自社営業マンが取引先への配布やプレゼンで活⽤し、⼤⼝取引の獲得のきっかけにもなりました。
健康ビジネス|Amazon1位を獲得し、会員数が500人増加した出版プロモーション事例
健康ビジネスを展開する企業は、耳ツボダイエットの魅力を広く伝えるために書籍を出版しました。
全国書店への配本とWeb広告を組み合わせたプロモーションを行い、Amazon「ビジネス実用書」カテゴリで1位(総合3位)を獲得しました。
また、書籍特設LPでは、既存会員の声を紹介し、見込み会員への信頼構築と紹介促進を実現。
出版後には大規模なセミナーも開催し、結果として半年間で新規会員が500人以上増加するといった、ブランディングと集客の両面で成果を上げました。
美容食品企業|書籍が既存顧客の理解と共感を呼び、リピート率が向上した事例
ある美容食品企業は、商品販促と自社のブランディングを目的に書籍を出版しました。
中年期以降の⼥性をメインターゲットに、「⼀⽣のうちで変化の多い「⼥性の⼈⽣の悩み」を解決する」をコンセプトとしたことから、既存顧客がファン化してリピート購入が増加しました。
発売前からSNSを活用した告知を強化した結果、予約が殺到し、発売前に重版が決定。
また、メディア出演や講演依頼も相次ぎ、認知拡大に成功しました。
既存顧客への書籍プレゼント企画では、予想の8倍以上の応募があり、書籍を受け取った顧客の半数以上が継続購入へとつながるなど、高い販促効果を発揮した事例です。
写真館|書籍で経営ノウハウを発信し、セミナー依頼と過去最高売上を実現した出版事例
写真館の経営者は、経営のノウハウの啓蒙及び写真館と自身のブランディングのために書籍を出版。
利⽤者の減少によって年々姿を消している個⼈経営の写真館の現状を伝え、厳しい業界で⽣き残ってきた秘訣を提⽰して読者からの信頼を得る書籍構成にしました。
兵庫県と⼤阪府、東京都をメインに配本を実施したところ、地元の⼤型書店でランキング1位を獲得、写真館経営者だけでなく他業界の経営者からも経営相談の問い合わせが相次ぎました。
さらに、セミナー依頼が⼤幅に増加し、新型コロナによる休業要請後の営業再開時には3か月連続で過去最⾼売上を更新するという快挙を成し遂げました。
ITサービス|難解な技術を体験で伝え、RPA分野での信頼と受注を得た出版事例
ITサービス企業の代表者が、中⼩企業経営者にとって読みやすいRPAシステムの⼊⾨書を出版。
自身の体験談や解説、コラムを各章に盛り込み、読みやすさを追求しました。
商圏に合わせた⼀都三県、⼤阪、名古屋、中⼩企業の多い地⽅(広島、福岡、熊本)を中⼼に展開し、ビジネス層からの問い合わせ獲得を狙いました。
出版直後から複数の問い合わせが発生し、1か月で2件の受注を獲得。
さらに、全国からセミナー依頼が殺到し、企業のブランド⼒の強化にもつながりました。
採用コンサル|理念に共感した人材を自然に引き寄せ、商談件数が10倍になったブランディング事例
人材採用コンサルタントは、⼈材獲得に悩む中⼩企業経営者を意識したタイトルの書籍を出版し、類書と異なるデザインで差別化に成功しました。
サラリーマンが多く⽴ち寄る駅構内の書店に重点配本して3書店でランキング1位を獲得。
出版後は商談件数が前年⽐10倍、成約率も約9割となり、本とは「⼤きなエネルギーをもった名刺のようなもの」と、効果を実感しました。
内容を理解した上で商談が始まるケースが多く、商談の効率化にもつながりました。
好調な売れ行きを受けて重版が決定し、反響が続いています。
企業出版の費用相場

企業出版は、1,000万円以上が費用相場です。
他の出版方法と比べると、以下の通りです。
| 自費出版 | 商業出版 | 企業出版(通常) | 企業出版(ブックマーケティング) |
| 費用 | 250〜500万円程度 | 0円(出版費用は出版社が負担する) | 1,000万円以上 | 500〜800万円程度 |
なお、1,000万円以上というのは一般的な費用相場であり、依頼する企業によって費用は異なります。
フォーウェイでは、一般的な企業出版とは異なり、企業のマーケティングの一環として書籍を活用していく新しい企業出版サービス(ブックマーケティグ)を500〜800万円の価格帯で提供しています。
フォーウェイのブックマーケティンング(企業出版)では、企業のマーケティング規模に合わせた最適な価格での企業出版をご提案可能です。
企業出版の価格に影響する要素として、以下が挙げられます。
| 企業出版の価格に影響する要素 | 詳細 |
| 書籍の仕様 | ・通常仕様は四六判(130mm×188mmサイズ)、中面白黒で200ページ程度・仕様変更(大きな判型、中面カラー、ページ数の増加、写真やイラストを入れるなど)の場合は追加費用が発生する |
| 部数 | ・部数が多くなればなるほど印刷費用が高くなる・部数が増えると流通拡大による書店営業経費が加算される・返品による損失のヘッジ分も加算される |
| 制作費用 | ・基本的な費用は人件費のため、ライターが必要か、持ち込み原稿かにより大きく異なる・編集者の出張や取材先が多岐にわたる場合も追加費用が発生する |
| プロモーション費用 | ・基本的に書店やメディアへのリリース、書店営業は基本費用の範囲内となる・WEB広告、新聞広告、イベント実施などは追加費用が発生する |
基本的に値段が上がるほど出版社の規模が大きくなり、流通部数も多くなると考えてください。
どの価格帯での出版が最適かは、出版の目的や自社の事業規模に応じて判断する必要があります。
なお、費用を抑えるための工夫として、原稿を自社で用意することで料金の調整に応じてもらえるケースもあるので、出版社に確認をしてみましょう。
企業出版の流れ

実際に企業出版を行う場合(※ライターに原稿を書いてもらう場合)、流れは以下のようになります。
| ステップ①:企画立案 | 出版の目的やターゲット読者を明確にし、内容やテーマを決定します。企画段階では、書籍の仮タイトルや章立てを作成します。 |
| ステップ②:取材・執筆 | 著者本人や著者の会社の社員へのインタビュー取材を行い、必要な情報を収集します。取材データをもとにライターが執筆作業を進め、章ごとに文章をまとめていきます。インタビューは一冊分で合計10時間程度になることが多いです。 |
| ステップ③:編集・校正 | 執筆された原稿を、著者と編集者で協力して校正(チェック)します。文章のクオリティや表現を整え、誤字脱字や文法の修正なども行います。 |
| ステップ④:デザイン・レイアウト | 書籍のデザインやレイアウトを決定します。カバーデザインについては、いくつかの候補から最終的に著者が選ぶパターンが多いです。使用してほしい色や求めるテイストがあれば、事前に担当編集者に伝えておきましょう。 |
| ステップ⑤:印刷・製本 | カバーと本文が完成したら、印刷所に原稿を送り、書籍の印刷と製本を行います。ここまで来たら、著者は刷り上がりを待つだけです。印刷が完了したら、いよいよ書店に書籍が並びます。 |
一方で、弊社フォーウェイが展開する企業出版(ブックマーケティング)は、単なる書籍の発行にとどまりません。
中小企業から大企業まで、法人としてさらなる認知度や知名度の向上を目指す企業に対し、次のステージへと進むための後押しをするプロモーション施策として展開しています。
その流れは、以下の通りです。
| ステップ①:目的・ターゲットの確認 | 出版によって企業が達成したい目的やターゲット読者層を確認します。たとえば、集客強化、信頼構築、ブランディング、新規顧客開拓などの具体的なゴールを定めます。 |
| ステップ②:書籍企画設計図の作成 | 書籍出版の目的を達成するために、クライアント企業の業務内容や強み、提供価値を丁寧にヒアリングし、企画骨子を設計図としてまとめます。 |
| ステップ③:書籍企画案の作成 | 設計図を基に、より詳細な企画案へと深化させます。全体の構成や仮タイトル、目次案などを企画書として作成します。 |
| ステップ④:取材・執筆 | 著者や関係者へのインタビューを通じて取材し、その内容をプロのライターが書籍原稿として執筆します。次のステップ⑤のカバー作成と並行して、執筆原稿の赤字入れなどをクライアント企業側に行ってもらいます。 |
| ステップ⑤:カバー作成 | 複数のデザイン案を作成し、著者と相談しながら最適な表紙デザインを決定します。色使いやイメージのテイストもここで反映されます。 |
| ステップ⑥:プロモーション戦略策定 | 書籍発売に向けた広報・販促施策を計画。書店営業戦略、Web広告、SNSや動画を活用したPRなど、多チャネルでの戦略を構築します。 |
| ステップ⑦:書店営業・広告戦略実施 | 取次・書店へ営業をかけ、配本戦略を組み立てます。。オンライン・オフライン両面で広告出稿やSNS連動キャンペーンなどを企画します。 |
| ステップ⑧:出版 | 印刷・製本が完了し、書店に並び始めます。出版日はメディア露出や販促活動の起点となります。 |
| ステップ⑨:出版後の施策実施 | 重版対応、SNS運用支援、クラウドファンディングやウェビナー連動キャンペーン、Web広告による販促継続、成果測定を含むトータル支援を行います。 |

企業出版の失敗事例と成功のポイント

生涯に一度かもしれない企業出版、絶対に成功させたいのは著者として当然でしょう。
成功のポイントをつかむために、企業出版にありがちな失敗事例を6つ紹介します。
・失敗事例①出版目的が絞られていない
・失敗事例②ターゲット読者の選定ミス
・失敗事例③広告的な内容にしすぎる
・失敗事例④ターゲットに合わないデザイン
・失敗事例⑤出版後の活用戦略がない
・失敗事例⑥出版社・パートナーの選定ミス |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
失敗事例①出版目的が絞られていない
企業出版では、「何のために誰に向けて出版するのか」がしっかり定義されていてこそ、クオリティの高い企画ができます。
「集客にも採用にも個人ブランディングにも効かせたい」「若者にもシニア層にも届けたい」など欲張りすぎると、読者から見て役立つ本であると伝わりづらくなってしまいます。
特に企業出版は、一定のコストをかけて取り組む施策であるため、高単価な商材・サービスの集客手段として活用することがおすすめです。
WEB広告などでは良さが伝えづらく、比較検討されにくいサービスこそ、企業出版の本領が発揮される領域です。
出版の目的や届けたい相手像が明確であればあるほど、タイトル、構成、原稿のトーンすべてに一貫性が生まれ、クオリティの高い企画に仕上がります。
失敗事例②ターゲット読者の選定ミス
企業出版では、ターゲット読者のニーズや興味に合わせた出版物を提供することが重要です。
たとえば、マーケティングの初心者向けに書籍を出版したいのに、コトラーのマーケティング理論などを完璧に理解していないとわからないような高度な内容で本を書いても、ミスマッチになってしまいます。
加えて、そもそも本を読まない層をターゲットにしてしまうミスもあります。
一例として10代女性などは、ファッション系やタレントものなどでない限り、出版してもほとんど本を買ってもらえないので注意しましょう。
失敗事例③広告的な内容にしすぎる
読者のニーズを意識せず、自社の情報や宣伝ばかりを強調した内容にしてしまうのも、よくある失敗ケースです。
せっかく費用を投じての出版なので、著者として自社を存分に宣伝したいのは当然です。
ただし、書籍は読者が対価を払って購入する媒体であることを忘れてはなりません。
「広告だ」という認識で読者は本を手に取っていないので、著者の宣伝色が強すぎるとかなり違和感をもたれます。
「伝えたいこと」を「価値あるコンテンツ」に変更するためには、編集者を使い倒すのがコツです。
失敗事例④ターゲットに合わないデザイン
カバーをはじめとするデザインを選ぶうえでは、「ターゲットの好み」に合わせるのがとても重要です。
よくやってしまうのが、著者が「自分の好み」でデザインを指定してしまうパターン。
著者の好みがターゲットの求めるデザインに合致するとは限らず、自分の好みを優先しすぎると、違和感のあるデザインになってしまいます。
それを避けるため、どうしても譲れない部分は伝えつつも優秀な編集者の提案に任せたほうが出版効果は見込みやすいでしょう。
失敗事例⑤出版後の活用戦略がない
出版したことで満足してしまい、その後の活用について検討されていないという失敗ケースもあります。
せっかく完成度の高い書籍ができても、次のように販売促進やリード獲得、信頼獲得の導線が作られていないと効果が限定的になってしまいます。
・営業資料として配布していない
・ホームページで紹介していない
・セミナーや展示会で使っていない |
企業出版は「出したら終わり」ではなく、むしろ出版後の活用次第で成果に差が生まれるため、きちんと戦略を練っておくことが大切です。
失敗事例⑥出版社・パートナーの選定ミス
出版社の実績や得意ジャンル、自社との相性を見極めずに契約してしまうことも失敗ケースとしてあります。
その結果、「出版後の反響がほとんどなかった」「原稿のブラッシュアップが不十分だった」といった問題が起こります。
出版社ごとに得意なジャンルや販売ルートや編集スタイルがあるため、契約前の実績確認や出版目的の共有が必須です。

企業出版に関するよくある質問
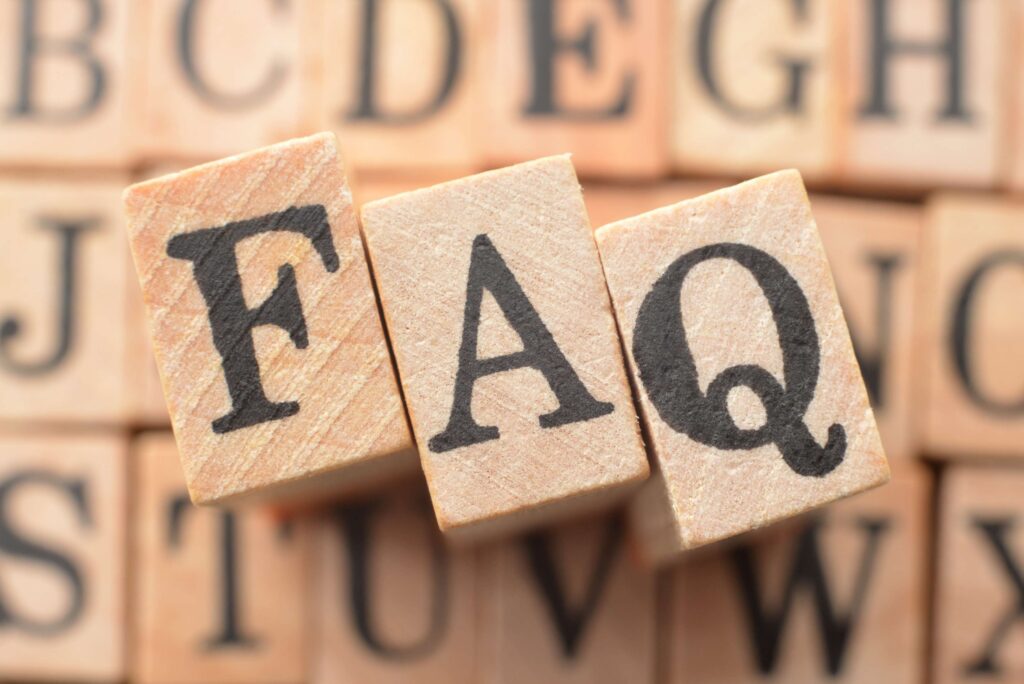
ここでは、企業出版の際に、弊社フォーウェイによく寄せられる質問の中から代表的なものを4つ紹介します。
企業出版までにどれくらいの期間がかかりますか?
企業出版には、全体で8か月程度の期間を見込んで進行します。
主な流れは、以下の通りです。
1. ヒアリング企画立案
2. 取材・原稿執筆
3. 原稿チェック
4. カバーデザイン
5. プロモーション戦略
6. 印刷・製本
7. 出版 |
制作期間については、企業の目的や事業フェーズに応じて、ご相談いただけます。
文章が書ける人間が社内にいないのですが、企業出版をすることは可能ですか?
フォーウェイでは、大手出版社での書籍制作経験が豊富なプロのライターが原稿を担当します。
忙しい著者に代わって、取材インタビューを基に構成・執筆を進めるので、文章作成に不安がある場合でも安心して出版できます。
本を書いてくださるライターの方との相性や文章のクオリティが不安です。
フォーウェイには、大手出版社の書籍案件を手がけた経験を持つ編集チームが在籍しており、専門ジャンルに強く、品質の高い原稿を担保します。
アサインするライターは、副業のWEBライターではなく、書籍制作の実績が豊富なプロフェッショナルを厳選。
提携ライターは200〜300名にのぼり、幅広い業種・業界の書籍に対応できる体制を整えています。
そのため、専門性の高いテーマや独自性のある企画であっても、安定したクオリティの原稿制作が可能です。
企業出版後もサポートは受けられますか?
フォーウェイでは、出版後の販促活動(Web広告出稿、書店プロモーション、SNS運用代行など)までトータルサポートします。
一般的な自費出版では、出版後の販促活動は基本的に著者自身の努力に委ねられがちです。
それに対して、フォーウェイの企業出版は「出版して終わり」ではなく、「出版した後まで徹底サポート」という考えのもと、出版後の展開にも責任を持って取り組んでいます。
【まとめ】企業出版でさらなる企業成長を実現しよう
この記事では、企業出版(ブックマーケティング)とは何かをはじめ、メリット・デメリット、ブックマーケティングの最新トレンドなどについて紹介しました。
企業出版は、しっかりしたパートナー出版社と戦略的に取り組めば、投資対効果としてほかの施策ではあり得ないほどの効果が見込めます。
上記のコラムを参考に、企業出版という選択肢をぜひ検討してみてください。
ブックマーケティングを活用すれば、ただ書籍を出版するだけでなく、その書籍を自社のブランディング、認知度や購買意欲向上などに積極的に役立ていくことができます。
主に次のような方にブックマーケティングは最適です。
・Web広告やSEOなどあらかたの集客施策をすでに行っているが、なかなかそれ以上の集客効果が得られないと悩んでいる中小企業
・難しすぎてWebではなかなか集客できないようなビジネスモデルをお持ちの経営者様
・ある程度事業も安定しているが、更なる成長をするための打ち手に困っている経営者様 |
そんな方は、新たな成長の一手として、ブックマーケティングの活用をご検討ください。