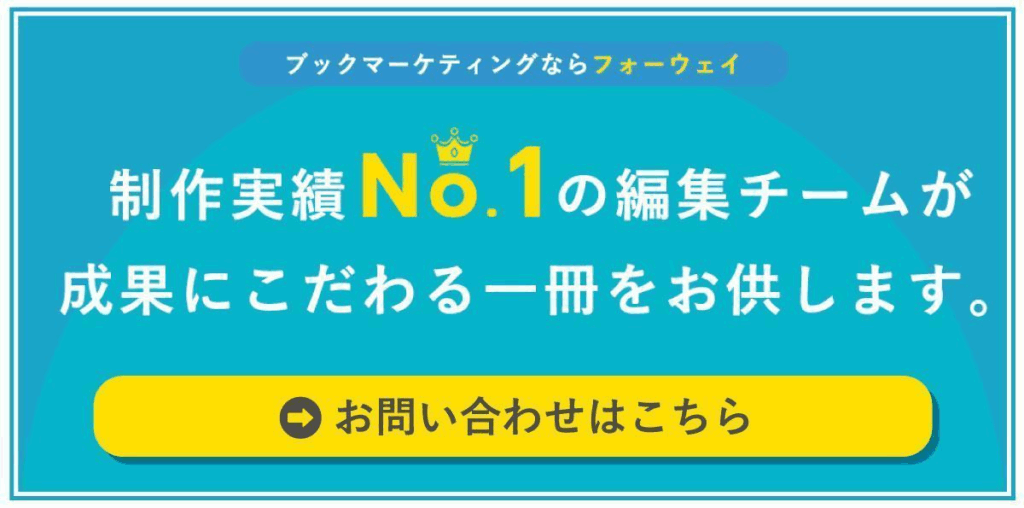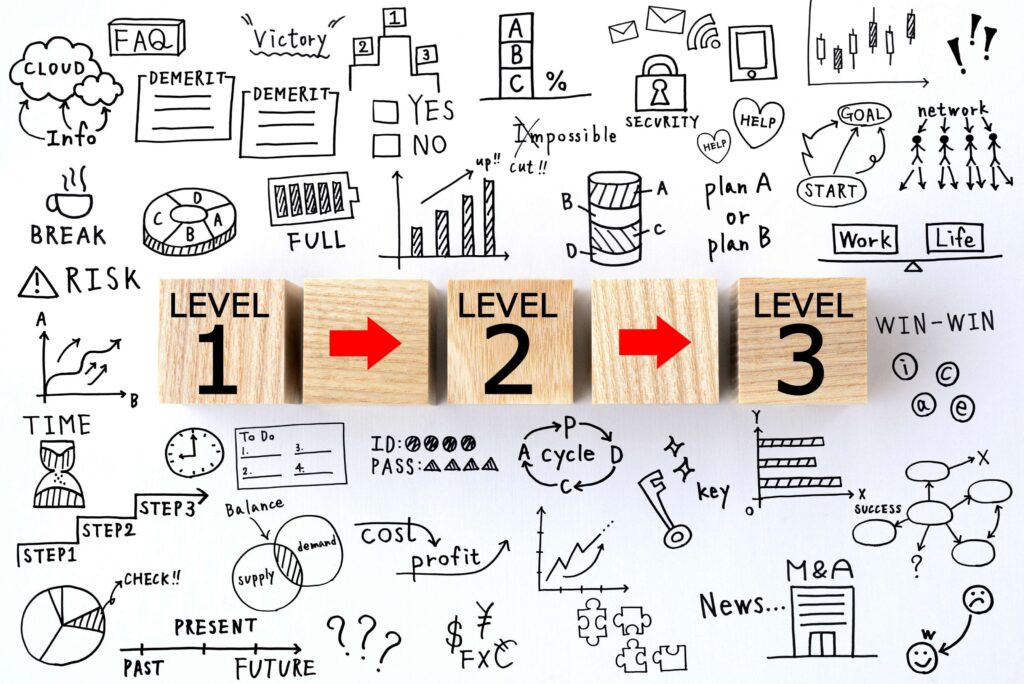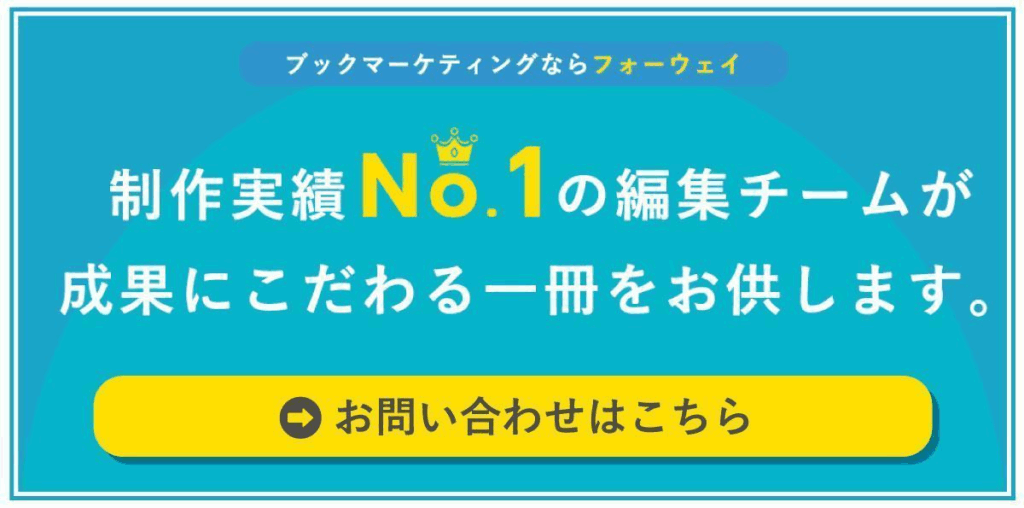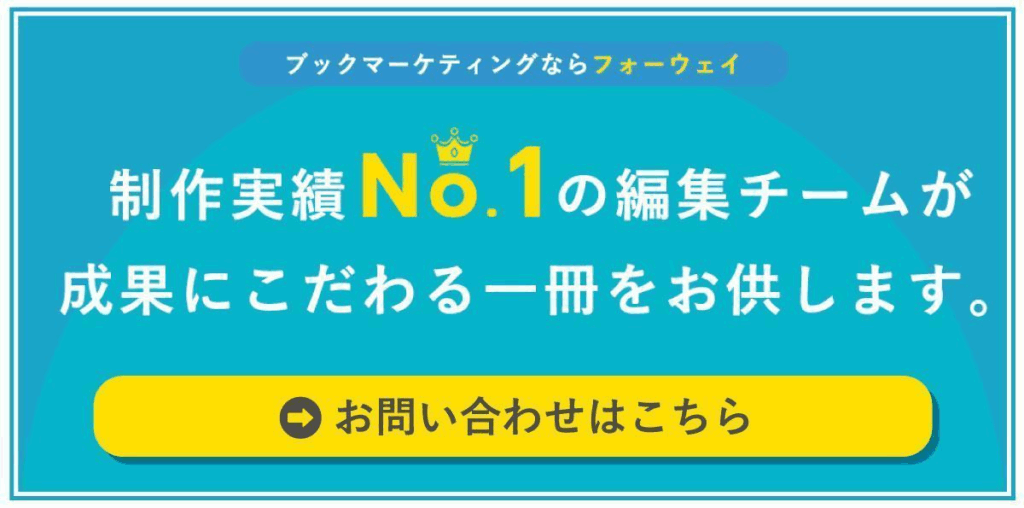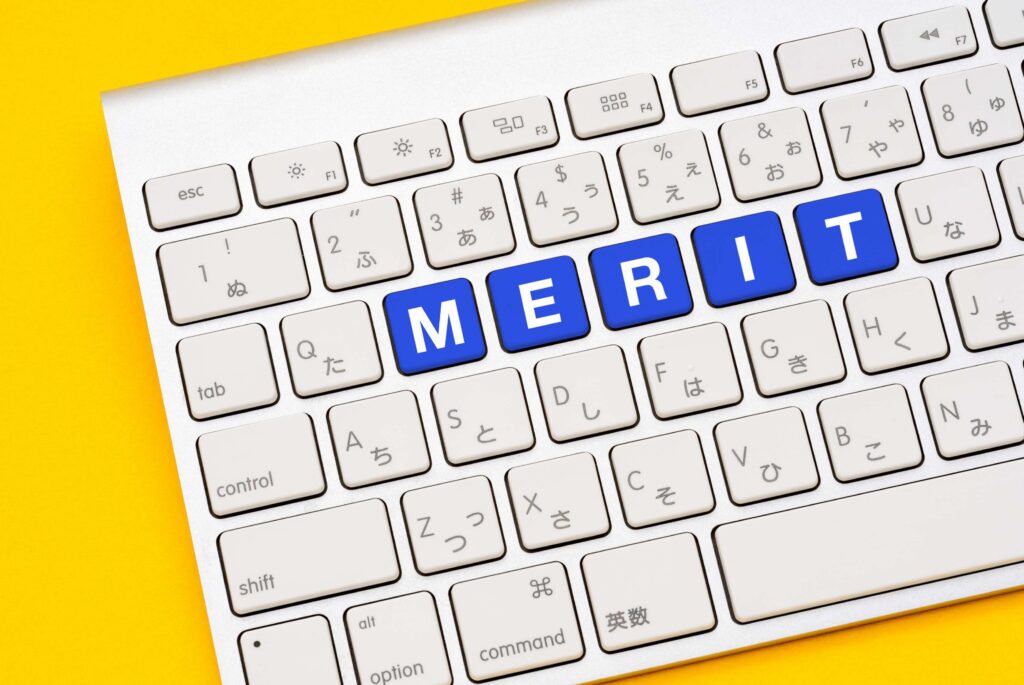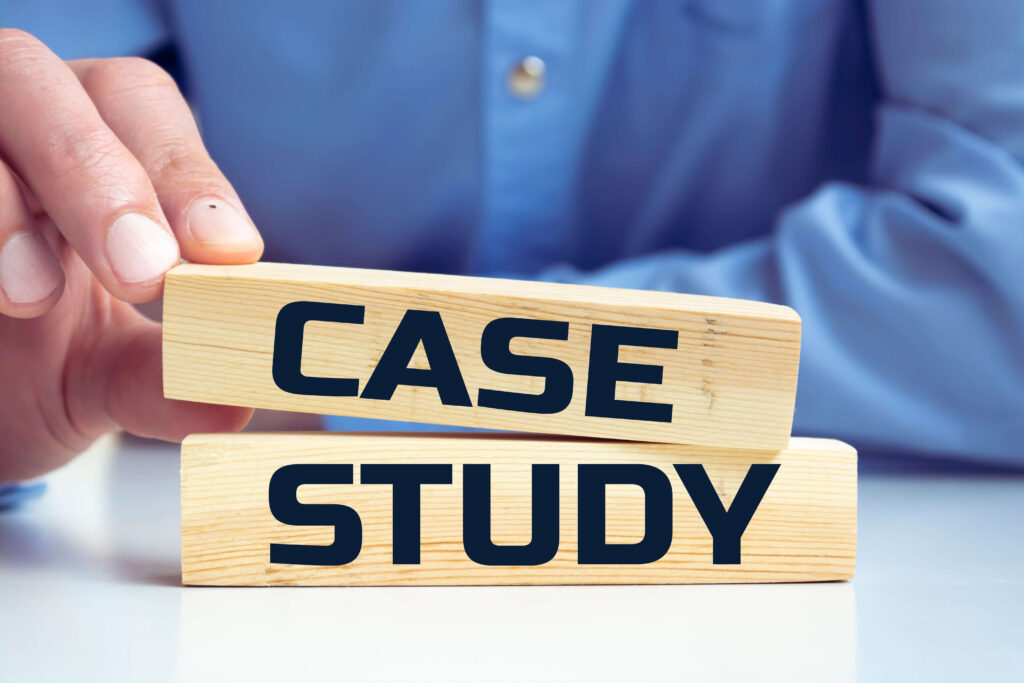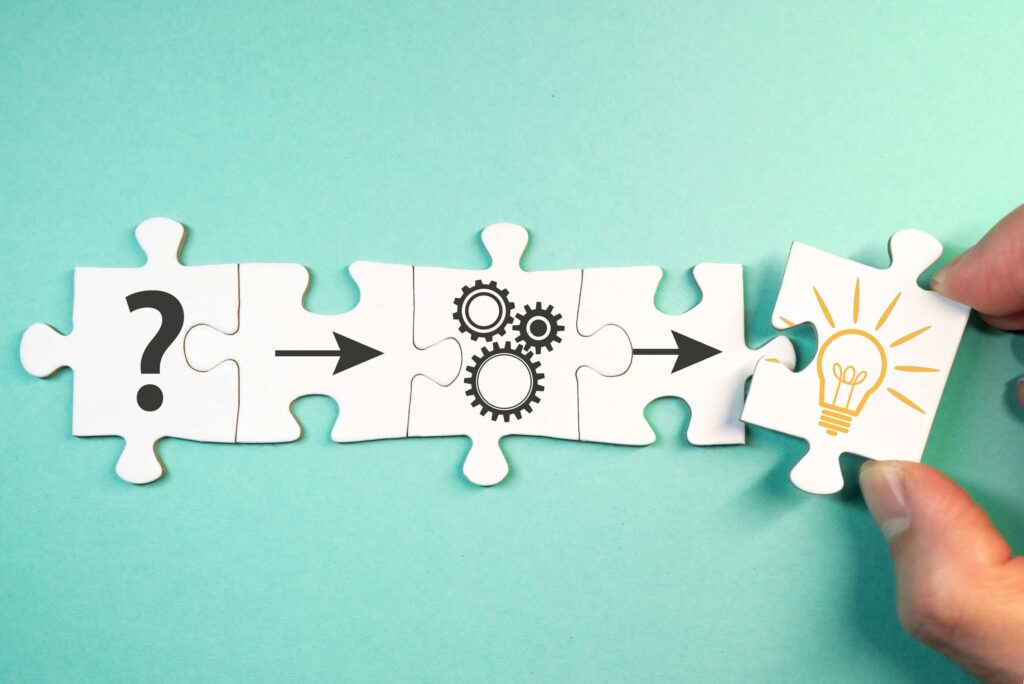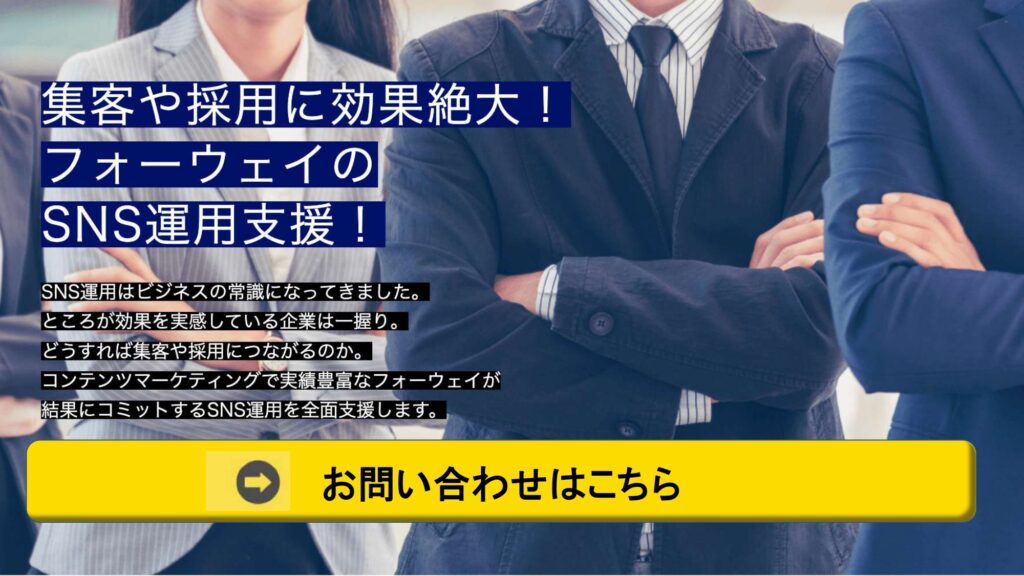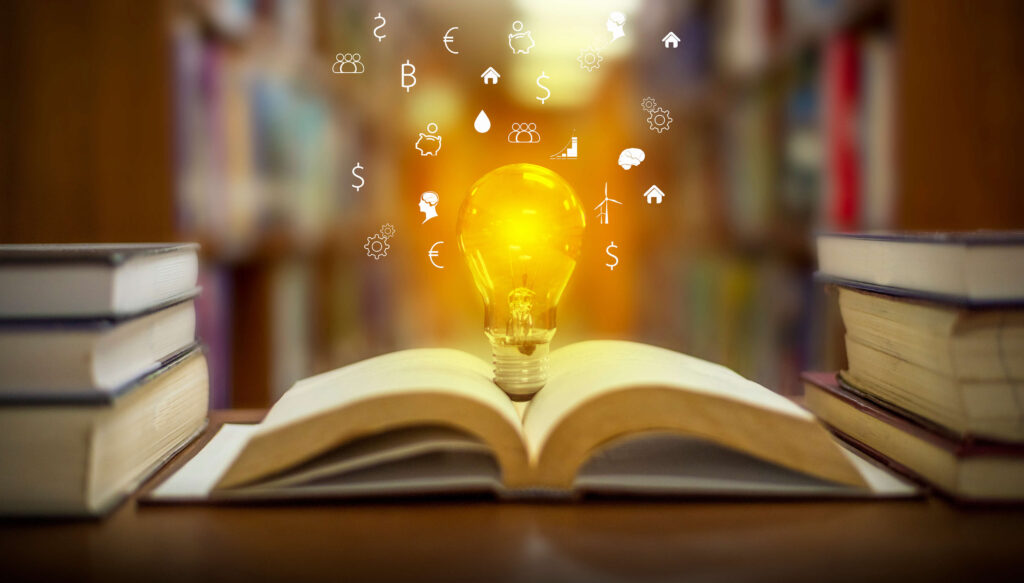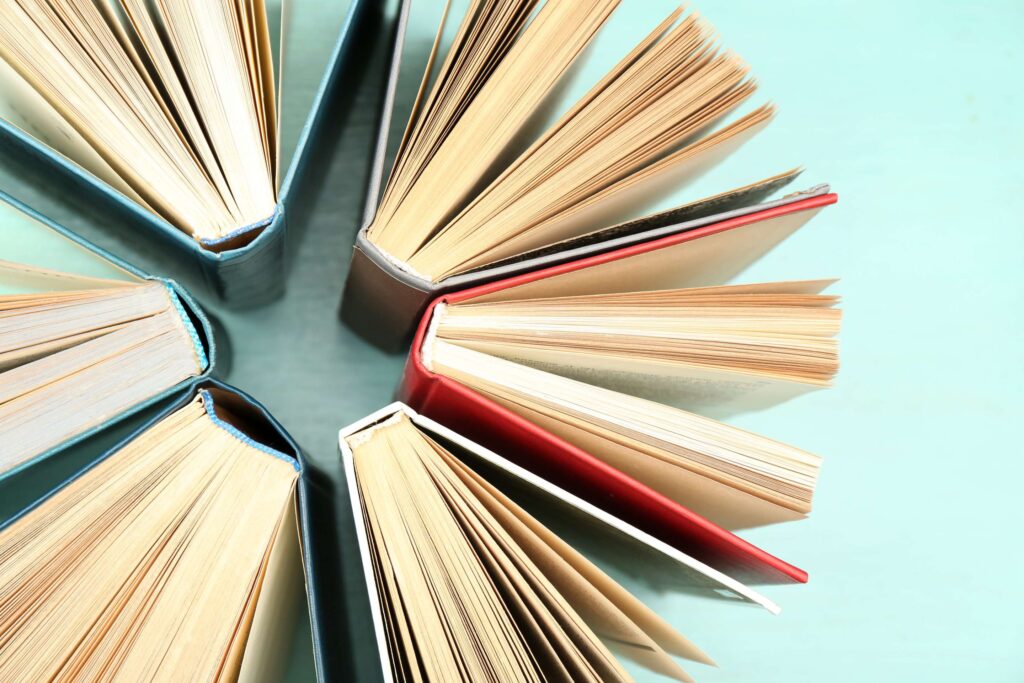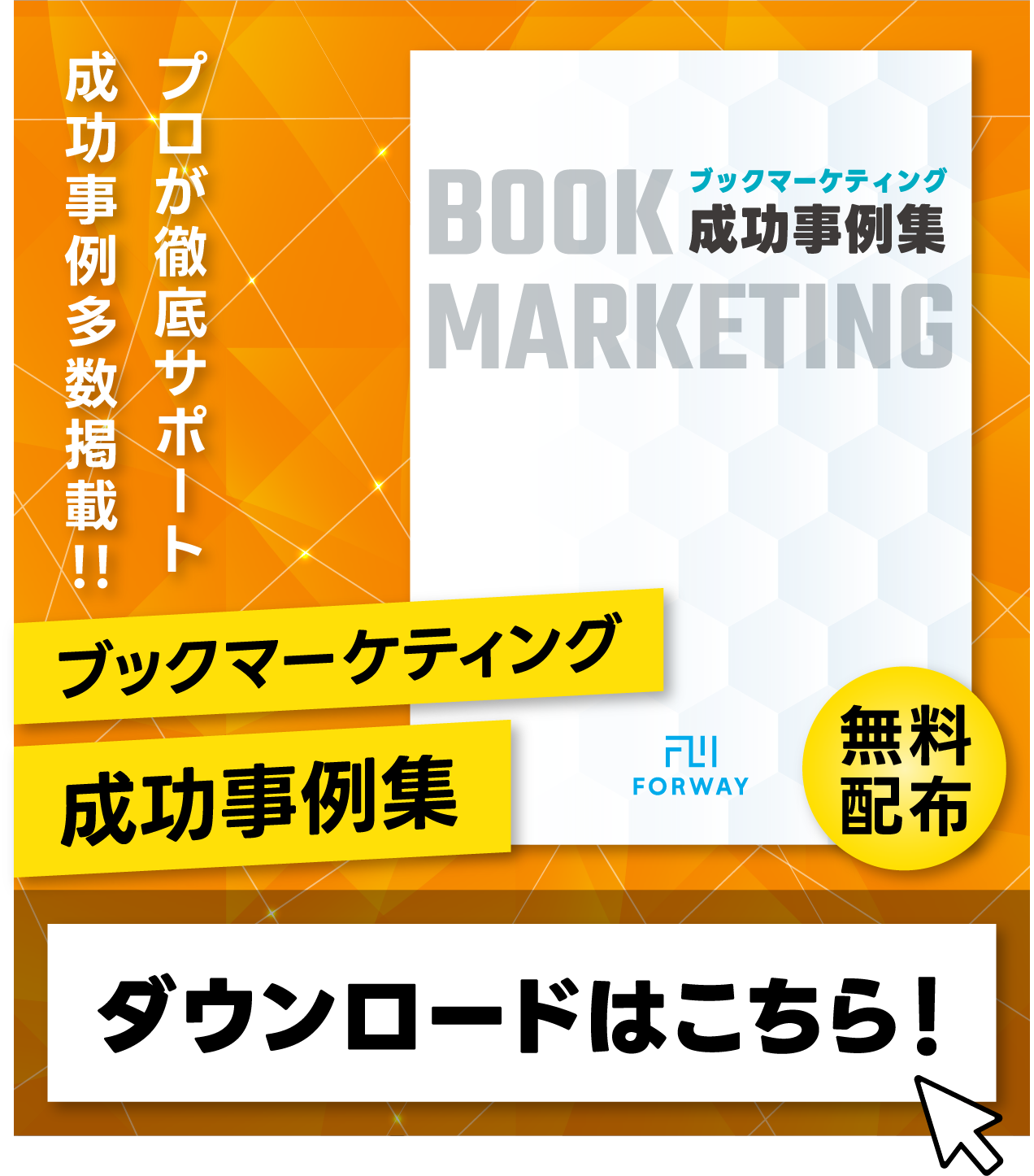メディア広告は、企業が市場で存在感を高め、売上や信頼性を伸ばすために欠かせない手段です。
しかし、近年ではメディアが多様化しているため、経営者が自社に適した広告手法を見極めることは簡単ではありません。
実際に「広告費をかけても効果が見えない」、「知名度や信頼度をどう高めればよいか分からない」という悩みを抱えている担当者や経営者も多いのではないでしょうか。
広告手法には短期で効果が表れやすいものから、中長期的に企業価値の向上に寄与するものまで多くの選択肢があります。
それぞれの広告手法の特徴を理解したうえで、自社の成長フェーズや目的に合わせて活用することが重要です。
この記事では、メディア広告の種類や効果、企業の成長フェーズや目的に応じた選び方について解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
メディア広告とは?

メディア広告とは、企業が商品やサービス、企業の価値などを伝えるために、新聞・テレビ・インターネット・出版物などの外部メディアを活用して情報発信を行う手法の総称です。
企業が伝えたいメッセージを、第三者が運営する媒体を通じて社会に届けることができます。
企業の情報発信というと、自社サイトや自社SNSアカウントを使った発信を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、自社メディアだけでは、すでに企業を知っている人や、ある程度関心を持っている層にしか情報が届きにくいという問題があります。
メディア広告は、そうした自社発信だけでは接点を持ちにくい層に対しても、第三者である外部メディアを通じて情報を届けられる点が特徴です。
広告は単なる宣伝ではなく、企業がどのように見られたいかを社会に伝える重要なコミュニケーション手段といえます。
メディア広告が企業にもたらす効果
メディア広告は、企業活動のさまざまな場面における効果が期待できます。
主な効果として次の3つが挙げられます。
- 短期の売上獲得
- 中長期の企業価値向上
- 第三者メディアによる客観性・信頼性の獲得
以下で、それぞれどのような効果なのかを見ていきましょう。
◉-1、短期の売上獲得
広告を出すことで問い合わせが増えたり、キャンペーンへの誘導が強化されたりするなど、短期間で売上を向上させることが可能です。
特定の商品やサービスを集中的に訴求することで、購買や申し込みといった行動につなげやすくなります。
特にインターネット広告は、消費者の行動を計測しやすい方法です。
たとえば、インターネット広告を出したら問い合わせ数が3倍に増えたなど、目に見える数字として把握できます。
SP(セールスプロモーション)広告も、クーポンの利用率のように比較的施策ごとの効果を把握しやすい傾向があります。
そのため、短期的な成果を求める場面や、限られた期間で反応を得たい場合には、メディアの活用が有効です。
◉-2、中長期の企業価値向上
メディア広告の効果は集客だけではありません。
露出が積み重なるほど、企業としての信頼性や専門性が評価され、ブランドへの好意形成などの中長期の企業価値向上につながります。
継続的に情報に触れてもらい、企業への理解が深まると、指名検索が増えるなど、選ばれやすい存在になる点も特徴です。
特に将来の資金調達や上場準備を見据える企業にとって、社会的信用の形成は欠かせない要素です。
◉-3、第三者メディアによる客観性・信頼性の獲得
新聞や雑誌、専門メディアといった第三者が運営する媒体に掲載されることで、自社発信とは異なる視点が加わり、企業情報の信頼性を高める効果が期待できます。
自社発信だけでは訴求しにくい専門性や取り組みの価値も、第三者メディアを通じて伝わるため、より客観的で信頼性の高い情報として受け取られやすくなります。
その結果、営業活動において一から説明する必要が減り、初回商談をスムーズに進めやすくなる点もメリットです。
こうした信頼の蓄積は、採用活動や協業先の獲得、金融機関との関係構築など、さまざまな企業活動に好影響をもたらします。
◉メディア広告の種類

一口でメディア広告と言っても、広告の目的や届け方によってさまざまな手法があります。
媒体ごとに役割や得意分野が異なるため、特徴を整理して理解することが重要です。
代表的な広告手法は、次の3種類です。
- マス広告
- インターネット広告
- SP(セールスプロモーション)広告
以下で、それぞれの特徴を順に見ていきましょう。
◉-1、マス広告
マス広告は、テレビ広告や新聞広告、雑誌広告などのように、比較的広い範囲に情報を届けるための広告手法です。
特定のターゲットに限定せず、多くの人の目に触れる点が特徴です。
幅広い層へ一度に情報を届けることができるため、企業の知名度向上やブランドイメージの形成に適しています。
新商品や新サービスの認知拡大、企業としての存在感を示したい場面で活用されることが多い広告です。
一方で広告費用が大きくなりやすく、効果測定が難しいというデメリットもあります。
そのため、目的や予算を明確にしたうえで活用することが重要です。
主なマス広告の種類と内容・具体例は次の通りです。
| 広告種別 | 内容・具体例 |
| テレビ広告 | 地上波CM、BS/CS放送CM、番組提供 |
| 新聞広告 | 全国紙・地方紙の全面広告、突き出し広告 |
| 雑誌広告 | 一般誌・専門誌への広告掲載、タイアップ |
| ラジオ広告 | スポットCM、番組内広告 |
| 屋外広告 | 看板広告、交通広告(電車・バス・駅) |
◉-2、インターネット広告
インターネット広告は、検索広告やSNS広告、動画広告など、利用者の属性や行動に応じて情報を届ける広告手法です。
関心の高い層に対して配信しやすく、比較的無駄の少ない形で訴求できるという特徴があります。
費用対効果が可視化しやすく、広告の反応を見ながらクリエイティブや配信条件をすばやく調整できるため、短期施策やテストマーケティングに強い媒体です。
限られた予算の中でも改善を重ねながら活用しやすい点もメリットといえます。
主なインターネット広告の種類と内容・具体例は次の通りです。
| 広告種別 | 内容・具体例 |
| 検索広告 | Google広告、Yahoo!検索連動型広告 |
| ディスプレイ広告 | Webサイト・アプリ上のバナー広告 |
| SNS広告 | Instagram、X(旧Twitter)、Facebook、TikTok広告 |
| 動画広告 | YouTube広告、SNS動画広告 |
| ネイティブ広告 | 記事広告、レコメンドウィジェット広告 |
| リターゲティング広告 | 過去訪問者への追跡配信広告 |
◉-3、SP(セールスプロモーション)広告
SP(セールスプロモーション)広告は、店頭販促やイベント、カタログ配布などを通じて、購入や来店、問い合わせなどの行動を促すことを目的とした広告手法です。
実際の購買シーンに近い場面で訴求できるという特徴があります。
生活者に近い接点でアプローチするため、短期的な売上につながりやすい一方で、広い認知を獲得するには不向きです。
そのため、特定の商品やキャンペーンを集中的に訴求したい場面で活用されることが多くなります。
主なSP(セールスプロモーション)広告の種類と内容・具体例は次の通りです。
| 広告種別 | 内容・具体例 |
| 店頭販促 | POP、什器、サイネージ |
| イベント・展示会 | 商品体験イベント、業界展示会出展 |
| サンプリング | 試供品配布、体験版提供 |
| DM・カタログ | 郵送DM、パンフレット配布 |
| キャンペーン施策 | クーポン、ノベルティ、ポイント施策 |
【企業の成長フェーズ別】最適なメディア広告の選び方
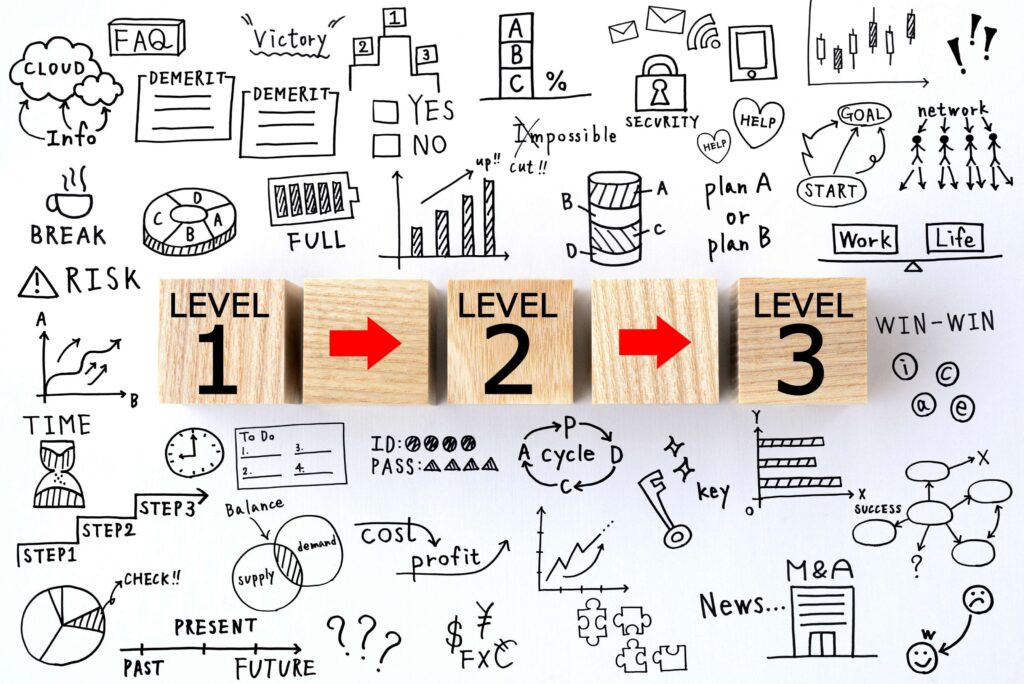
企業がどの広告を採用すべきかは、成長段階や目指す目的によって大きく変わります。
ここでは、企業の成長フェーズと目的を次の4つに分け、それぞれの段階でどのメディア広告が成果につながりやすいのかについて解説します。
- 起業・創業期|まずは認知を広げたい場合
- 事業拡張期|短期の反応やリードを獲得したい場合
- 上場準備期|信頼構築や企業としての評価を高めたい場合
- 全フェーズ共通|認知・信頼・リード獲得を同時に進めたい場合
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、起業・創業期|まずは認知を広げたい場合
創業期は、まず市場に「自社の存在」を知ってもらうことが重要です。
限られた予算の中で成果を高めるためには、少額からでも始められ、改善を繰り返しながら反応を確かめられる広告が向いています。
SNS広告や検索広告のようにターゲットを絞り込める媒体を活用することで、必要な層に効率よく情報を届けられます。
まずは小さくテストしながら、どのメッセージが効果的なのかを検証し、事業の方向性に役立つデータを蓄積していくことが、創業期の広告活用では大切です。
▶︎起業・創業期の広告採用については、関連記事【【経営者必見】知名度・認知度を高めるには?選ばれる企業になるための施策と成功事例まとめ】も合わせて参考にしてください。
◉-2、事業拡張期|短期の反応やリードを獲得したい場合
事業拡張期には、顧客接点を拡大して問い合わせを獲得し売上の増大につなげることが重要です。
この段階では、短期間で問い合わせや資料請求といったアクションにつながる広告が効果を発揮します。
検索広告やSNS広告、LPへの誘導を中心とした施策など、成果を数値で可視化できる媒体を活用することで、改善を繰り返しながら効率的にリードを獲得できます。
また、既存顧客の行動データを活用した広告運用も有効で、拡大期ならではの強みを生かした集客が可能です。
▶︎事業拡張期の広告運用については、関連記事【【目的別】売上を上げるために検討したい13の施策】も合わせて参考にしてください。
◉-3、上場準備期|信頼構築や企業としての評価を高めたい場合
上場準備期は、市場やステークホルダーからの信頼性や透明性を獲得することが重要です。
事業の強みや社会的意義を外部にわかりやすく伝えられる広告を選ぶことで、企業としての評価を高めやすくなります。
新聞広告や専門誌での露出は、第三者の視点が加わるため信頼性が高く、金融機関や投資家からの理解促進にもつながります。
また、企業の理念や事業の背景を丁寧に伝えられる媒体を活用することで、長期的なイメージ形成にも効果的です。
▶︎上場準備期のメディア活用については、関連記事【企業や経営者の権威性を高めるには?SEOやマーケティングへの活用法】も合わせて参考にしてください。
◉-4、全フェーズ共通|認知・リード獲得・信頼性獲得を同時に進めたい場合
認知拡大、信頼性向上、リード獲得を並行して進めたい場面では、単一の媒体に依存せず、多面的に企業の価値を示せる手法が適しています。
こうした役割を果たせる手法として挙げられるのが「企業出版」であり、フェーズに関係なく長期的な資産として機能する点が特徴です。
企業の理念や専門性、実績を深く伝えられる媒体を活用することで、短期と中長期の双方で効果を得ることができます。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
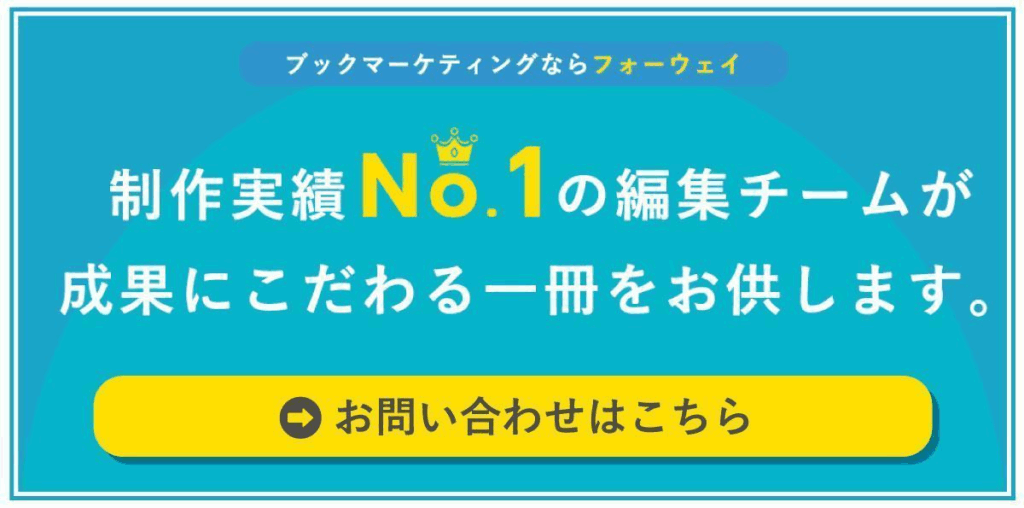
企業出版を活用したメディア広告の成功事例

実際の企業がどのようにメディア広告を活用し、成果につなげているのかを知ることで、より具体的なイメージが持てるようになります。
企業出版は一度作れば営業や企業のPRから採用まで長期間活用できる、資産としての面を持つメディアです。
ここでは、企業出版の活用によるメディア広告の成功事例を3つ紹介します。
- 経営者の認知度アップにつながった事例
- 新規事業の顧客獲得と採用強化につながった事例
- 信頼性と権威性を向上した事例
以下で、それぞれどのような事例なのかを見ていきましょう。
◉-1、経営者の認知度アップにつながった事例
ある建設会社では、建設業界全体で深刻化する人材不足の影響により、受注のチャンスがあっても十分に対応しきれない状況が続いていました。
そこで経営者は、自身および企業の認知度を高めることで若手人材の採用を強化しようと考え、書籍を出版しました。
書籍には、自社の創業に至るまでのストーリーや経営者自身の仕事に対する考え方、経営哲学などをまとめ、地域の若手人材に「この会社で働きたい」と感じてもらえる内容を盛り込みました。
出版後は、採用面接の際に事前に書籍を読んで応募してくる求職者が増えて、採用率が向上し、採用コストの削減に成功。
また、出版をきっかけとして地元紙などの多くのメディアからの取材機会が増え、地域内での認知度の向上にもつながっています。
◉-2、新規事業の顧客獲得と採用強化につながった事例
法人向けの保険代理店の経営者は、同業の保険代理店向けのコンサルティング事業を新たに立ち上げたばかりで、これからどのように新規顧客を獲得していくかを模索していました。。
そこで、自社の経営ノウハウや給与体系に対する考え方をまとめた書籍を出版し、集客を図りました。
書籍の中では、保険業界の問題点に触れたあとで、自社で「一律報酬型」を採用することで業績が向上し、社員が成長していることを紹介しました。
「成果報酬型」が当たり前の保険業界では画期的な取り組みとして注目を集めることに成功。
出版後は、業界内での認知度が一気に高まり、同業の保険代理店からのコンサルティング契約を複数獲得しました。
また、書籍を通じて経営姿勢や考え方が可視化されたことで、保険会社から「頼れる保険代理店」というイメージを持ってもらえるようになり、講演依頼や同業支援の依頼が舞い込むようになりました。
本業の法人保険の商談においては、顧客が事前に書籍を読んでくれていることが増えて、経営課題についての相談を受けるなど、法人保険の大口契約にも成功。
さらに、自社の人材採用においても、書籍を読んだ求職者からの応募が増え、人材採用面でも効果が出ました。
現在、社名変更を経て2冊目を書籍出版し、さらなる事業拡大に向けたフェーズへと進んでいます。
【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店
◉-3、信頼性と権威性を向上した事例
ある不動産投資会社の経営者は、医師をターゲットとした書籍を出版しました。
高収入でありながら支払う税金の負担額が大きい医師に対して、「不動産投資が特に効果的な節税対策である」ことを訴求し、関心を高めて集客を狙ったのです。
書籍では、まず最初に「医師が抱えるお金の悩み」を提示して共感を引き出し、続いて「医師に不動産投資が適している理由」を論理的に解説しました。
さらに「どのような物件を購入すべきか」を具体的に示すことで、読者が自然と投資に前向きになるように構成。
出版後は、書籍を読んだ数多くの医師から問い合わせが寄せられ、その多くが不動産投資物件の成約につながりました。
その結果、わずか半年で10億円以上の売上を達成しました。
このように、1冊目の出版で大きな効果を上げることができたことを受けて、さらなる自社のマーケティング戦略として第2弾の出版を予定しています。
第2弾は顧客の医師と共著で出版することになっており、より高い信頼性と権威性の獲得につながることが期待されます。
◉【まとめ】自社に最適なメディア広告を選び、企業成長を加速させよう
この記事では、メディア広告の種類や効果、企業の成長フェーズや目的に応じた広告手法の選び方について解説しました。
メディア広告は、目的や企業の成長段階によって得られる効果や影響が大きく異なります。
短期的な反応を重視するのか、長期的な企業価値の向上を目指すのか、その判断次第で選ぶべき広告が違ってくるのです。
この記事で紹介した視点を参考に、自社が置かれている状況や目的に合った広告手法を採用すれば、企業の成長を後押しする有効な手段となります。
広告を単なるコストではなく、資産として考えたい企業には、企業出版という選択肢を検討してみるのがおすすめです。
フォーウェイでは、企業出版を広告やブランディングに活用するブックマーケティングサービスを提供しています。
大手出版社で編集経験を積んだ専任スタッフが、本の企画立案から出版後のマーケティング活動までを一貫してサポートします。
企業出版を活用したメディア広告については、フォーウェイまでお気軽にご相談ください。
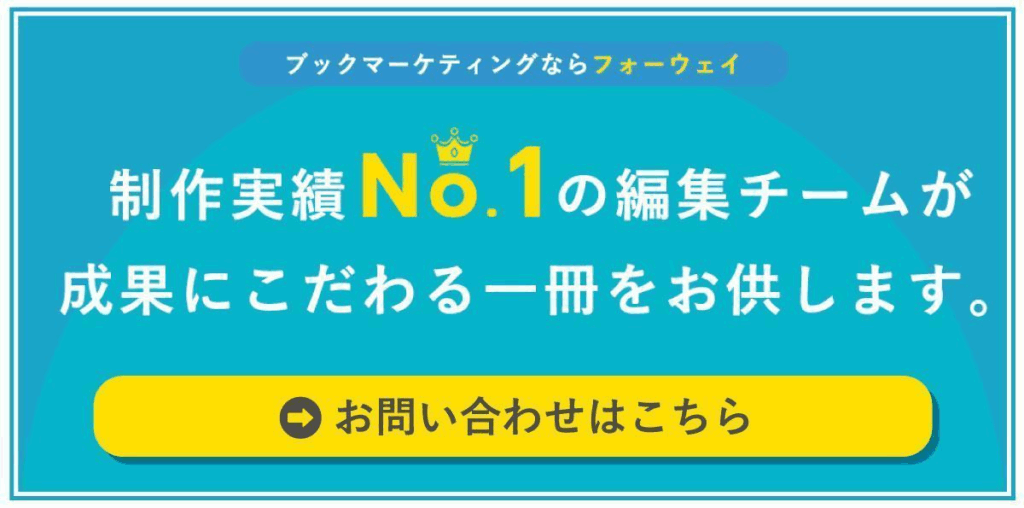

トップセールスは、企業が事業を拡大していく過程で重要な役割を果たす取り組みとして注目されています。
社長が自ら動くことで、通常の営業活動では得られない信頼やスピードが生まれ、新たな取引や大型案件につながりやすくなるからです。
トップが前に出ることの意味や効果を正しく理解することで、自社の営業戦略のなかでどのように活用すべきかが見えてきます。
この記事では、社長が自ら営業する重要性について詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
トップセールスとは?

トップセールスとは、企業や組織において高い営業成果を継続的に上げている営業担当者や営業責任者を指します。
商品・サービスへの深い理解力や高い提案力、ヒアリング力を備え、顧客の成功を第一に考える姿勢を持っている点が特徴です。
その結果、個人の成果にとどまらず、組織全体の営業力向上にも好影響を与える存在となります。
一方で、トップセールスという言葉は、文脈によって「社長や創業者など企業のトップ自らが営業・広報・交渉の場に立つこと」を指す場合もあります。
この場合は、トップという立場だからこそ語れるビジョンや意思決定の背景、責任の所在を示しながら、相手の信頼や共感を得ていく営業活動を意味します。
権限や説得力、ブランドへの影響力が一般的な営業担当者とは異なるため、社長によるトップセールスには特有の効果があります。
◉社長によるトップセールスが重要な理由

社長が営業の第一線に立つトップセールスが重要とされる理由は、主に次の3点です。
- 社長が営業に出るだけで信頼されやすい
- 決裁者同士が直接話すことで商談が早く進む
- トップが動くと大型案件が生まれやすい
それぞれどのような理由なのかを詳しく見ていきましょう。
◉-1、社長が営業に出るだけで信頼されやすい
社長自らが商談の場に立つことで、相手企業は「この会社は本気で取り組んでいる」と受け止めやすくなり、信頼感が高まります。
トップが時間を割いて直接対応する姿勢そのものが、企業としての誠実さや覚悟を示すからです。
また、意思決定権を持つトップが説明を行うことで、話の内容に一層の説得力が生まれます。
その結果、相手が抱く不安や懸念もその場で解消しやすくなり、商談の前提となる信頼関係を短期間で築くことが可能になります。
◉-2、決裁者同士が直接話すことで商談が早く進む
社長と相手企業の決裁者が直接対話することで、意思決定のスピードが向上します。
通常の営業プロセスで発生する社内確認や持ち帰り検討が不要になり、その場で方向性が決まるケースが多いためです。
さらに、立場の近い決裁者同士だからこそ、条件面だけでなく経営判断の背景や本音を含めた議論が可能になります。
その結果、短期的な取引ではなく、継続的な関係構築を前提とした合意に至る可能性が高まります。
◉-3、トップが動くと大型案件が生まれやすい
企業のトップが前に出ることで、その商談は経営レベルの案件として扱われます。
相手側も重要案件として向き合うため、取引規模や契約期間を含めた検討が行われるようになります。
結果として、案件の検討範囲や契約期間についても踏み込んだ判断が行われ、より規模の大きい案件に発展しやすくなるのです。
◉トップセールスを成功させるための情報発信施策

トップセールスを成果につなげるためには、商談の場だけでなく、普段から社長自身の考えや姿勢を情報発信しておくことが欠かせません。
情報発信を通じて理解と信頼を積み重ねておくことで、商談を始める時点ですでに相手の信頼を得やすくなり、対話がスムーズに進むようになります。
社長が取り組みやすく、かつ効果の高い具体的な施策として、次の8つが挙げられます。
- 社長ブログやコラムで思想を発信する
- SNSで経営者としての視点や日常の気づきを共有する
- ニュースレターやメルマガで継続的な接点をつくる
- 動画コンテンツで社長の人柄と思想を伝える
- ウェビナーやセミナーで専門性とビジョンを示す
- 第三者メディアへの露出で信頼性を高める
- 社長名義のホワイトペーパーで価値観を体系化する
- 書籍出版で社長の思想を深く伝え、権威性を高める
以下では、それぞれの施策がどのようにトップセールスの成果に結び付くのかを詳しく見ていきましょう。
◉-1、社長ブログやコラムで思想を発信する
社長が自社の価値観や事業に対する考え方を文章として発信すると、商談前から企業としての姿勢や方向性を伝えられます。
トップの考えが事前に共有されている状態で商談に入るため、対話の質も高まります。
また、経営者自身の言葉には、他のコンテンツにはない重みがあるものです。
そのため、ブログやコラムを通じて考え方に触れた読者が企業そのものに関心を持ち、商談や問い合わせにつながるケースも少なくありません。
◉-2、SNSで経営者としての視点や日常の気づきを共有する
SNSでは、社長の日々の気づきや業界に対する見方を短い言葉で伝えられます。
継続的に発信することで、社長の考え方が少しずつ伝わり、読み手との距離が縮まります。
こうした発信に触れた相手は、初めて話す場面でも社長の人物像をある程度理解しているため、商談に入る際の心理的なハードルが下がり、対話がスムーズに進むのです。
▶︎SNSの詳細については、関連記事【【保存版】SNS運用とは?手順や失敗例、集客につなげる運用術を解説!】もあわせて参考にしてください。
◉-3、ニュースレターやメルマガで継続的な接点をつくる
社長名義のニュースレターやメルマガは、見込み顧客との接点を継続的に保つ手段として効果的です。
一度きりの接触ではなく、定期的に考え方や情報を届けると、関係性を段階的に深めていくことが可能です。
売り込みを前面に出さず、価値ある内容を積み重ねることで、いざ商談の機会が訪れた際に「信頼できる相手」として想起されやすくなります。
◉-4、動画コンテンツで社長の人柄と思想を伝える
動画は、文章だけでは伝わりにくい声のトーンや表情、話し方といった要素まで含めて伝えられる点が特徴です。
社長の人柄や誠実さが自然に伝わることで、企業に対する安心感や信頼感を持ってもらいやすくなります。
事前に動画を通じて考え方を理解したうえで商談に臨んでもらえると、相手も構えずに話を聞きやすくなり、冒頭から具体的な議論を進められるでしょう。
◉-5、ウェビナーやセミナーで専門性とビジョンを示す
社長がウェビナーやセミナーで直接テーマを解説することで、その分野に対する理解の深さや視座の高さが明確に伝わります。
単なる商品説明ではなく、業界全体や課題の背景をどうとらえているかを示せる点も特徴です。
参加者にとっては、情報を得る場であると同時に「この社長と話してみたい」と感じるきっかけにもなり、その後の商談につながる重要な接点となります。
◉-6、第三者メディアへの露出で信頼性を高める
外部メディアに取り上げられることは、社長の発信内容が第三者の視点で評価された結果です。
自社による情報発信だけでは得られない客観性が加わることで、社長の発言がより信頼できるものとして受け取られるようになります。
結果として、社長個人への信頼だけでなく、企業全体のイメージ向上にもつながり、商談に入る前段階での信頼をより確かなものにします。
◉-7、社長名義のホワイトペーパーで価値観を体系化する
市場や顧客の課題、自社が提供できる価値を社長の視点で整理し、資料としてまとめることで、トップの考え方を体系的に伝えることができます。
ホワイトペーパーでは、断片的な情報ではなく全体像を示せる点が強みです。
商談前にこうした資料に目を通してもらうことで、相手の理解度が高まり、具体的な議論に時間を使えるようになります。
▶︎ホワイトペーパーの詳細については、関連記事【マーケティングにおけるホワイトペーパーの役割とは?信頼を生む情報発信の仕組み】もあわせて参考にしてください。
◉-8、書籍出版で社長の思想を深く伝え、権威性を高める
社長の思想や経験を一冊の書籍としてまとめると、背景や判断の理由まで含めて体系的に伝えられます。
書籍は時間をかけて読まれる媒体であり、信頼形成において重要な役割を果たすのです。
また、書籍を出版できること自体が企業の信頼性を補完する要素となり、高単価サービスやBtoB領域では、商談の成功率を高める強力な施策になります。
▶︎書籍出版の詳細については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

書籍をトップセールス強化に活用するメリット
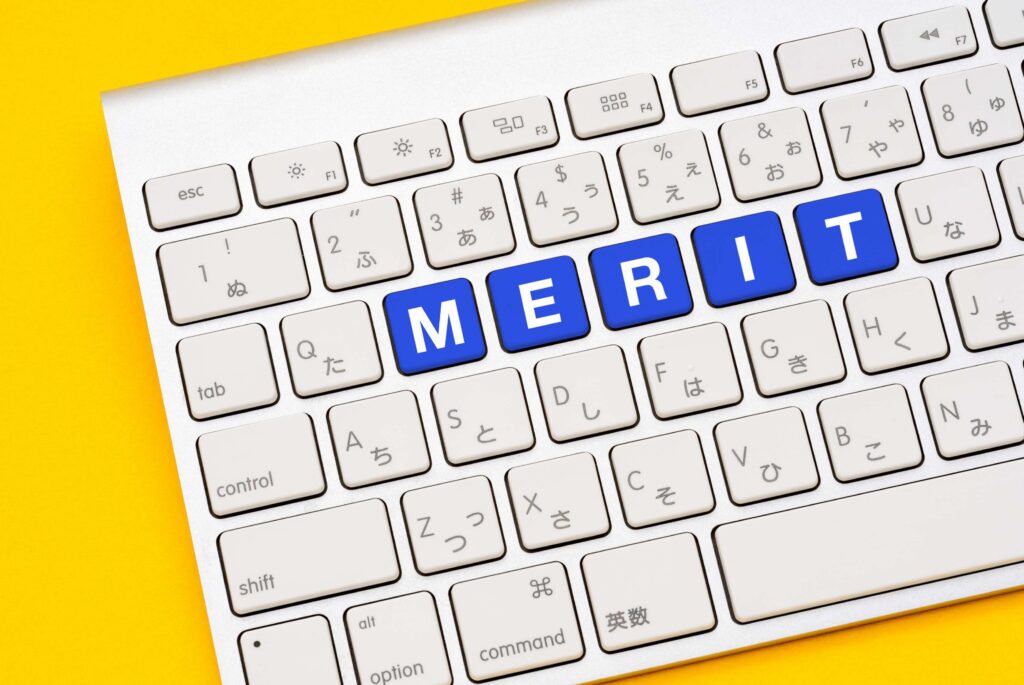
書籍を活用したトップセールスには、商談前の関係構築から営業活動の効率化まで、実務上の明確なメリットがあります。
代表的なポイントは、次の4つです。
- 商談前から顧客と信頼関係を築ける
- 長期間にわたって理念や価値観を伝えられる
- 営業活動の効率アップが図れる
- 読者からの紹介による新規顧客が獲得できる
以下で、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、商談前から顧客と信頼関係を築ける
書籍を読んだ状態で商談に進む顧客は、すでに社長の考え方や事業への姿勢を把握しています。
そのため、初回の商談の場でも前提が共有され、信頼関係を築くための土台が整った状態で話を進められます。
商談の際に一から背景を説明する必要が減り、より具体的で実務的な話に時間を使える点もメリットです。
◉-2、長期間にわたって理念や価値観を伝えられる
書籍は一度発行すれば、長期間にわたって読者の手元に残る媒体です。
社長の理念や価値観を、時間をかけて繰り返し伝えられる点は、他の情報発信手段にはない特徴といえます。
短期的な発信では伝えきれない背景や考え方まで含めて届けられるため、企業全体に対する理解が深まり、企業の方向性も明確に伝えることができます。
◉-3、営業活動の効率アップが図れる
書籍は営業資料としても活用できるため、顧客が事前に内容を理解したうえで商談に臨むことが可能です。
その結果、説明にかかる時間が削減され、より本質的な相談や判断に時間を使えるようになります。
また、書籍を通じて一定の信頼が形成されているため、商談の進行がスムーズになり、成約率の向上も期待できます。
◉-4、読者からの紹介による新規顧客が獲得できる
書籍は、顧客や関係者を通じて周囲に紹介されやすい媒体です。
読者が内容に共感した場合、知人や取引先に紹介してくれるケースも少なくありません。
その結果、書籍を通じて自社の理念や専門性を知った新たな層にリーチでき、営業活動の広がりを自然に生み出すことができるようになります。

書籍活用によるトップセールスの成功事例

ここでは、書籍活用によるトップセールスの成功事例を3つ紹介します。
- 書籍で持論を展開して大口案件や新規顧客を獲得した事例
- 社長の仕事観や経営哲学を書籍で訴えて採用強化を実現した事例
- 社長の経験や考え方を書籍で伝えてリピート率をアップした事例
以下で、それぞれの事例について詳しく見ていきましょう。
◉-1、書籍で持論を展開して大口案件や新規顧客を獲得した事例
法人向けの保険代理店の社長は、保険代理店向けのコンサルティング顧客の新規獲得と信頼性向上を目的に書籍を出版しました。
成果報酬が一般的な保険業界で、月額報酬制を採用して事業を伸長させた持論とノウハウを体系化して1冊の書籍にまとめています。
結果として、2週間で重版出来、出版記念セミナーには60名が参加し、うち5件が成約につながるなどの効果が得られました。
その後、さらなる事業拡大のために社名を変更し、そのタイミングでリブランディングのために2冊目の書籍を出版。
大手外資系生保の全国No.1セールスの実績を持つ社長が、「顧客に本当に必要とされる営業」の本質を体系化して公開し、さらなる事業拡大に成功しました。
【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店
◉-2、社長の仕事観や経営哲学を書籍で訴えて採用強化を実現した事例
湘南エリアを地盤に事業活動を行っている建設会社では、慢性的な人材不足が課題となっていました。
せっかくの受注機会を十分に活かせない状態が続いていたことから、人材の採用強化と自社のブランディングを目的として書籍を出版。
社長自身の仕事観や経営哲学、創業ストーリーなどを体系的にまとめて、地元の若手人材に「働きたい」会社だと思ってもらえるような内容にしました。
その結果、事前に書籍を読んで、その内容に共感した求職者の応募が増え採用率が向上しました。
また、年間500万円以上かかっていた採用エージェント費を削減することにも成功。
さらに、出版をきっかけに地元紙をはじめとした複数のメディアから取材依頼が寄せられ、地域内での認知度が一気に向上し、業界内で一目置かれるようになりました。
◉-3、社長の経験や考え方を書籍で伝えてリピート率をアップした事例
女性向けサプリメントを展開するサプリメントメーカーの経営者は、既存顧客との関係強化と新規顧客獲得の両立を目的として書籍を出版しました。
書籍には、社長自身の経験や健康に関する考え方をまとめ、読者にとって役立つ実用的な内容に仕上げました。
出版後の早い段階で、「書籍無料プレゼント」キャンペーンを実施したところ、想定を大きく上回る6倍もの応募を得ることができ、多くの新規顧客との接点を創出することにも成功。
加えて、書籍をきっかけに企業や商品の背景を理解してもらえるようになり、購入者のリピート率が向上しました。
自社メディアでの継続的なコミュニケーションとカスタマーサポートによって、ブランドへの信頼を高めることにも成功しました。
【事例コラム】”書籍無料プレゼント”に想定の6倍の応募、リピート率アップにインパクト!サプリメントメーカーの出版プロジェクト
◉【まとめ】トップセールスを成功させるために企業出版を有効活用しよう!
本記事では、トップセールスが企業にとって重要とされる理由や、成功につなげるための情報発信施策、書籍を活用するメリットや事例について解説しました。
トップセールスとは、企業のトップである社長が前面に立つことで、信頼性・スピード感・ブランド力を同時に高められる、非常に有効な営業手法です。
なかでも、書籍を活用した情報発信を組み合わせることで、商談前から見込み顧客に企業や経営者への理解を深めてもらいやすくなり、営業効率や成約率の向上が期待できます。
このように、企業出版は社長の思想を体系化し、長期的な信頼と事業機会を生み出す有効な手段なのです。
フォーウェイでは、企業出版による書籍を営業活動に活用する「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
これまで多くの企業の出版支援を行い、営業・採用・ブランディングといった分野での成果創出をサポートしてきました。
企業出版をマーケティングに活用したいとお考えの方は、ぜひフォーウェイまでお気軽にご相談ください。


近年、SNSやデジタル広告の普及によって、企業と顧客の接点は多様化しています。
一方で、「企業の想いをどう伝えるか」「ブランドをどう記憶に残すか」といった課題は、以前よりも難しくなっています。
こうした中で注目されているのが「キャラクターマーケティング」です。
キャラクターは、企業理念や価値を親しみやすい形で伝え、顧客とのコミュニケーションをスムーズにする役割を果たします。
この記事では、キャラクターマーケティングの効果や設計ポイント、成功事例などについて紹介します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
キャラクターマーケティングとは

キャラクターマーケティングとは、企業や商品・サービスの世界観を象徴するキャラクターを活用して、顧客との接点づくりとコミュニケーションを強化する手法です。
キャラクターには、ブランドの特徴をわかりやすく表現し、顧客の注意を引きやすいという特徴があります。
また、キャラクターを通じて企業が伝えたい情報を自然に届けることができるため、認知の獲得やロイヤルティの向上にもつながります。
このように、キャラクターは単なるデザイン要素ではなく、コミュニケーション全体を支えるために重要です。
企業がキャラクターマーケティングを行う目的

企業がキャラクターマーケティングを導入する目的は、キャラクターに「人格」をもたせて、ブランドメッセージを親しみやすい形で届けることです。
堅苦しくなりがちな企業理念や専門的な内容も、キャラクターが説明役として登場することで受け入れられやすくなります。
また、キャラクターの表情や言動は人の感情に訴えかけ、企業と顧客との心理的距離を縮める効果があります。
その結果、ブランドの理解促進や好感度の向上、継続的なファンづくりなど、複数の目的を同時に達成できることも特徴です。
キャラクターマーケティングが事業成長にもたらす効果

情報があふれている現代では「覚えてもらう工夫」が重要になっています。
キャラクターを使うと視覚的な印象を残しやすくなり、ブランドの世界観をわかりやすく伝えることができるようになります。
キャラクターを活用することによる主な効果は次の通りです。
- ブランドの認知度向上と差別化効果
- 顧客との心理的距離を縮める効果
- 継続的なファン育成につながる効果
- ブランドを資産化する効果
それぞれの効果を詳しく見ていきましょう。
◉-1、ブランドの認知度向上と差別化効果
市場に競合が多い場合でも、キャラクターを利用することでブランドの独自性を強く印象づけることができます。
特に視覚的に特徴のあるキャラクターは、一度見ただけで顧客に覚えてもらうことができ、広告やSNSに登場するたびに認知を積み重ねることができます。
さらに、同じ業界内に類似の商品やサービスが存在する場合でも、キャラクターの個性や世界観によって明確な差別化が可能です。
◉-2、顧客との心理的距離を縮める効果
人はキャラクターに対して感情移入しやすく、親しみを感じるとその背景にある企業や商品にも好意を抱くようになります。
キャラクターの言動やビジュアルは、企業メッセージに親しみをもたせ情報を受け取りやすい雰囲気をつくります。
結果として、企業への信頼醸成につながり、商品やサービスへの理解が進みやすくなるのです。
◉-3、継続的なファン育成につながる効果
キャラクターがSNSや動画の中で「語り手」として登場するだけで、情報を自然に読み進めてもらえるというメリットがあります。
キャラクターを通じてブランドの世界観が一貫して表現され、ストーリーが継続的に展開されるほど、顧客は先の展開に興味を持ちやすく、継続的なエンゲージメントにつながります。
企業と顧客のコミュニケーションを自然に維持できる点は、キャラクターマーケティングの強みです。
◉-4、ブランドを資産化する効果
魅力あるキャラクターは、ブランドの象徴として長期にわたり利用できる資産となります。
キャラクターを継続的に活用することで、企業が発信する情報のトーンが揃い、結果としてブランドの世界観が伝わりやすくなります。
また、キャラクターグッズの展開やライセンス販売などによって、新たな収益機会を生み出すことも可能です。
キャラクターマーケティングは主に2パターン

キャラクターマーケティングは主に次の2つの方法に分類できます。
以下で、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、既存キャラクター
既存キャラクターは、アニメや人気コンテンツなど、すでに認知されているキャラクターを企業のマーケティングに活用する手法です。
既存キャラクターの知名度を活用できるため、短期間で認知を拡大したい場合に効果的です。
また、キャラクター自体のファン層にリーチでき、話題化しやすいというメリットもあります。
一方で、ブランドとキャラクターの世界観の一致度に限界があり、他社と同じキャラクターを使う場合は独自性が出しにくいという側面もあります。
◉-2、オリジナルキャラクター
オリジナルキャラクターは、企業やブランド独自の世界観を体現するキャラクターをゼロから設計する手法です。
ブランドの世界観を一貫して伝えられるため、長期的なブランド資産として育てられます。
特にSNSや広告、出版物、イベントなど多様なチャネルで活用しやすく、顧客との関係性を深める効果が高いという特徴があります。
ただし、認知が広がるまで時間がかかるため、戦略的な育成と継続的な運用が不可欠です。
ブランド独自の世界観を構築したい企業や、長期視点で顧客と関係を築きたい場合に適しています。
キャラクターマーケティングを成功させるには?

キャラクターマーケティングを成功させるための施策として、主に次の4つの手法があります。
- 複数の顧客接点でキャラクターを活用する
- デジタル施策・イベント施策と連携する
- ファンのエンゲージメントを強化し、ファン層を育成する
- 出版物へのキャラクター活用によるブランド発信を行う
それぞれ、どのような手法なのかを詳しく見ていきましょう。
◉-1、複数の顧客接点でキャラクターを活用する
まずやるべきなのは、キャラクターの露出を増やして顧客に認知してもらうことです。
WebサイトやSNS、広告、イベントなど、顧客が利用する複数のチャネルでキャラクターを活用した露出を増やして認知の拡大を図ることが重要です。
たとえば、ある食品メーカーでは、自社オリジナルキャラクターをWebサイトの案内役として起用すると同時に、店頭POPやSNSにも継続的に登場させました。
その結果、購入前の認知度が向上し、SNSでの投稿数も増加するなど、ブランド全体の認知拡大につながっています。
◉-2、デジタル施策・イベント施策と連携する
デジタル施策としては、キャラクター自身のSNSアカウントを作成して企業メッセージを発信し、顧客に親近感を抱いてもらいエンゲージメントを高める手法があります。
また、イベントを開催して顧客との交流の場を設けてファン化を促進させることも可能です。
たとえば、あるアパレル企業は、キャラクター自身のSNSアカウントを運用し、イベント前にキャラクターが告知を行うことで参加申込数の増加につながった事例もあります。
複数のチャネルにキャラクターを登場させて、相乗効果を狙うことも考えられます。
◉-3、ファンのエンゲージメントを強化し、ファン層を育成する
キャラクターの認知が広がってきてファン層が獲得できたら、次のようなコミュニケーションを通じて関係性を深めていくことが重要です。
| 施策 | 具体的な内容 |
| 参加型キャンペーン | プレゼントキャンペーン、イベントの実施 |
| ユーザー生成コンテンツ(UGC)の促進 | SNSなどでファンによるコンテンツ発信 |
| ファンコミュニティの活用 | SNSなどでコミュニティを開設・運営 |
たとえば、ある雑貨メーカーで、キャラクターを使った写真投稿キャンペーンを実施したところ、ファンによるUGCが想定以上に拡散し、オンラインストアのアクセスが増えた事例があります。
また、地域密着型の飲食チェーンでは、キャラクターを用いたスタンプラリー企画を行い、限定ノベルティが話題となってファン化が進みました。
◉-4、出版物へのキャラクター活用によるブランド発信を行う
キャラクターは、情報を整理して分かりやすく伝えられる点で、出版物との親和性が高い存在です。
出版物内でキャラクターをナビゲーター役として配置することで、内容の理解度が高まり、企業理念や専門的な情報も無理なく読者に届けられます。
パンフレットやホワイトペーパーなどに継続的に登場させれば、表現のトーンや世界観に統一感が生まれ、長期的に活用できるブランド資産として育てていくことも可能です。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

出版物にキャラクターを取り入れる際の設計ポイント

企業パンフレットや採用案内、サービス紹介冊子などの出版物にキャラクターを取り入れる例は業種を問わず広がっています。
出版物でキャラクターを活用する際の主な設計ポイントとして、次の4つが挙げられます。
- ブランドトーンに合ったキャラクター設計を意識する
- 出版物全体にキャラクターを組み込む
- キャラクターの配置で読みやすさを高める
- キャラクターの表現ルールを設定する
以下で、それぞれについて詳しく解説します。
◉-1、ブランドトーンに合ったキャラクター設計を意識する
キャラクターを出版物で活用する際は、ブランドが伝えたい価値や方向性とキャラクターの性格・役割を一致させることが基本となります。
キャラクターの口調、行動、表情がブランドのトーンと合っていることで、出版物の内容が自然に受け取られやすくなります。
一貫性が保たれることで、読者の中にブランドの印象が定着し、長期的な信頼構築にもつながるのです。
◉-2、出版物全体にキャラクターを組み込む
キャラクターは単発で登場させるよりも、出版物全体に配置することで効果が高まります。
章やページごとにキャラクターがナビゲーターとして登場すると、読者は自然と読み進めやすくなり、出版物としての統一感が出ます。
キャラクターの役割を「案内役」「質問役」「まとめ役」などに設定することで、情報の流れが整理され、読者にストレスを与えない構成になるのです。
◉-3、キャラクターの配置で読みやすさを高める
難しい内容の噛み砕き役としてキャラクターを配置することで、読者の理解を助けることができます。
重要ポイントの説明や注意点の強調など、読んでほしい部分にキャラクターを添えるだけで、視線誘導が生まれ読みやすさが向上します。
特に専門性が高い内容を扱う場合は、キャラクターを要所に置くことで読者の負担が軽くなり、情報がスムーズに伝わる効果が期待できるのです。
◉-4、キャラクターの表現ルールを設定する
キャラクターを出版物で活用する際は、ビジュアルや口調に統一したルールを設けることが重要です。
表情・色・文字の扱い・セリフのトーンなどが場面ごとにばらつくと全体の印象が散漫になり、読者の理解を妨げてしまいます。
あらかじめ「どの場面でどの表情を使うか」「セリフはどの程度の口調にするか」などのガイドラインを定めておくことで、出版物全体に一貫性が生まれ、ブランドメッセージもより伝わりやすくなります。
キャラクターを活用した出版物の成功事例
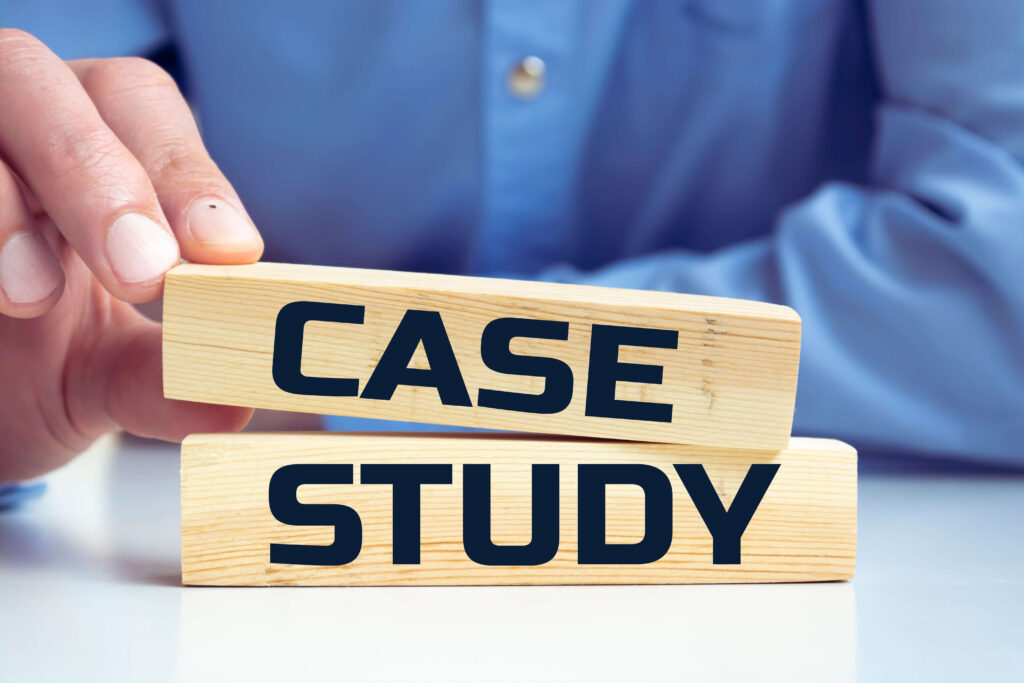
ここでは、紙媒体ならではの強みを生かした出版物の成功事例を5件紹介します。
- 観光パンフレットにおけるキャラクター活用
- 採用パンフレットでのキャラクター活用
- 会社案内冊子でのキャラクター活用
- 周年記念出版でのキャラクター活用
- ブランディング出版でのキャラクター活用
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、観光パンフレットにおけるキャラクター活用
群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」は、観光パンフレットやガイドブックで案内役として活躍しています。
観光地や名産品を紹介する際の導入役として登場し、冊子全体を親しみやすいトーンにまとめている点が特徴です。
ページごとに表情やポーズを変える工夫もあり、家族連れや若年層にとって読みやすいデザインを実現しています。
また、パンフレットから公式サイトやSNSへ誘導する導線にもぐんまちゃんが使われており、紙媒体とデジタル双方でブランド発信を支える存在となっています。
◉-2、採用パンフレットでのキャラクター活用
ある企業の新卒採用パンフレットでは、業界に対して抱かれがちな「まじめで堅い印象」をやわらげることを目的に、企業文化や職場の雰囲気を伝える案内役としてオリジナルキャラクターを導入しました。
冊子の各ページにキャラクターを配置し、制度や仕事内容のポイントを補足する構成としたことで、学生が内容を理解しやすくなり、最後まで読み進めてもらいやすくなったといいます。
◉-3、会社案内冊子でのキャラクター活用
あるBtoB企業では、セラミックなど専門性の高い事業内容をそのまま説明するのではなく、コーポレートキャラクターが噛み砕いて紹介する構成を採用しました。
キャラクターを通じて、「社会を支える存在として、目立たない部分で価値を提供している企業」という企業像を語ることで、抽象的になりがちな理念や事業の役割が直感的に伝わりやすくなった点が評価されています。
また、キャラクターが解説役として登場することで、難解になりがちな事業説明への心理的ハードルが下がり、読者がスムーズに内容へ入り込めるようになりました。
担当者からも、キャラクターの存在によって企業理解が早まり、「限られた時間の中でもブランドメッセージを効果的に伝えられた」との声が上がっています。
◉-4、周年記念出版でのキャラクター活用
リクルートが運営する不動産・住宅情報サイト「SUUMO」のブランドキャラクターとして知られているのが「スーモ」です。
スーモ誕生1周年を記念し、ブランドの世界観や価値観をより深く伝える施策として、絵本『スーモのさがしもの』が出版されました。
本施策では、キャラクターを物語の主人公に据えることで、Webサイトや広告だけでは伝えきれないスーモの個性や魅力を、体験的に感じてもらうことを狙っています。
出版物という形をとることで、ブランドの世界観を丁寧に表現できただけでなく、キャラクターへの親近感を高め、読者との心理的な距離を縮める効果も生まれました。
その結果、短期的な話題づくりにとどまらず、長期的なブランド浸透につながった好例といえるでしょう。
▶︎周年記念の詳細については、関連記事【企業が周年記念事業を成功させるポイント!おすすめの施策ややり方を解説】もあわせて参考にしてください。
◉-5、ブランディング出版でのキャラクター活用
自社をより身近に感じてもらう目的で、ブランディング出版として絵本を制作した企業もあります。
自社商品やサービスの価値をキャラクター化し、物語として表現することで、家族層を中心に自然な形でブランドに触れてもらう狙いがありました。
広告とは異なる接点として出版物を活用し、長期的な認知形成につなげた事例です。
【まとめ】出版物にキャラクターを取り入れてマーケティング効果を高めよう
この記事では、キャラクターマーケティングの目的や効果、設計ポイント、キャラクターを出版物に活用した成功事例などについて紹介しました。
出版物は情報を体系的に伝えられる媒体のため、キャラクターを活用して読者の理解が深まり、ブランドメッセージの浸透効果を高めることが期待できます。
出版物でキャラクターの存在感が確立できれば、WebやSNSへの展開もしやすくなり、企業全体のコミュニケーションを強化することが可能です。
フォーウェイは、企業の経営者や責任者が成果を生み出せるよう、企業出版(ブックマーケティング)を中心に、各種コンテンツを通じたブランド戦略支援を行っています。
キャラクターを取り入れた冊子制作や書籍出版を通じて、企業の想いや価値を分かりやすく伝えるブランディング支援にも対応しています。
キャラクターを活用した出版物についてのご相談やお問い合わせは、フォーウェイまでお気軽にお寄せください。


プル型営業とは、顧客が主体的に情報収集や比較検討を行うことを前提として、企業が信頼できる情報や価値を継続的に発信し、顧客からの自然な問い合わせにつなげることを目的とした営業モデルです。
近年は、広告費の上昇や営業活動の効率低下が進んだため、従来のように企業側から働きかける営業スタイルでは、十分な成果が得られなくなってきています。
こうした環境変化の中で、顧客が自ら企業を選ぶ傾向が強まり、信頼される情報を発信している企業ほど、問い合わせを受けやすく、商談や購買へ進む可能性が高くなっているのです。
この記事では、プル型営業とは何かを整理したうえで、具体的な手法や導入ステップについて詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
プル型営業とは?

プル型営業とは、企業が能動的に商品やサービスを売り込むのではなく、適切な情報設計や導線設計を行うことで、顧客側からの相談や問い合わせを促す営業モデルです。
インターネットやSNSの普及により、顧客は必要な情報を自ら調べ、比較し、納得したうえで購買行動を起こすようになりました。
このような環境では、企業が顧客の判断材料となる情報を整理して蓄積するとともに、それらを分かりやすく信頼される形で発信していくことが重要になります。
顧客は、商品やサービスだけでなく、企業の専門性や信頼性も重視するようになっているのです。
◉-1、プッシュ型営業との違い
プッシュ型営業は、テレアポや訪問など、企業側が積極的に働きかけて顧客と接触し、商談につなげる手法です。
一方、プル型営業では、顧客が自ら情報収集を行い、企業を見つけたうえで自発的に接触してくることを前提としています。
つまり、プル型営業は接触時点ですでに顧客の関心度が高く、接触のタイミングや意思決定などの主導権は顧客側にあります。
企業側としてその状況を作るために情報提供や導線設計を担う必要はありますが、無差別なアプローチは不要です。
結果として商談の質が高まりやすく、成約率の向上にもつながります。
プル型営業が必要な理由

現在の市場では、従来の営業手法だけで安定した成果を上げることが難しくなっています。
顧客の行動や競争環境が変化する中で、企業には日頃から信頼を築き、顧客から選ばれやすい状態をつくることが求められており、その手段としてプル型営業が注目されています。
プル型営業が必要とされる主な理由は、次の3つです。
- 顧客の購買行動が自発型へ移行しているから
- 差別化しにくい市場で選ばれる理由が必要になったから
- 広告や訪問営業の費用対効果が落ちているから
以下では、それぞれの理由について詳しく解説していきます。
◉-1、顧客の購買行動が自発型へ移行しているから
近年、顧客の購買行動は大きく変化しており、営業マンから説明を受けるよりも、自分自身で情報を調べ、納得したうえで判断したいと考える人が増えています。
インターネットの普及により、検索エンジンや口コミサイト、比較サイト、SNSなどを通じて、購入前の検討に必要な情報を容易に入手できるようになりました。
価格や機能だけでなく、実際の利用者の評価や他社との違いまで把握したうえで、ある程度候補を絞り込んでから企業に接触するのが一般的になっています。
このような環境では、顧客と最初に接点を持つのは営業マンではなく、Web上の情報であることがほとんどです。
そのため、企業に求められるのは売り込み色の強い情報ではなく、顧客が自ら調べた際に「信頼できる」と感じてもらえる情報を継続的に発信することなのです。
◉-2、差別化しにくい市場で選ばれる理由が必要になったから
多くの業界では、機能や価格、品質といった従来の要素だけで、他社との違いを明確に打ち出すことが難しくなっています。
競合が似通った価値を提供する状況では、表面的なスペックや条件だけでは、顧客の意思決定を左右する決め手になりにくくなっているのが実情です。
こうした背景から、顧客は商品・サービスそのものだけでなく、「どの企業を選ぶか」という点にも強い関心を向けるようになっています。
企業の理念や姿勢、これまでの実績、業界への理解度といった要素が、信頼して任せられる相手かどうかを判断する重要な基準となりつつあります。
◉-3、広告や訪問営業の費用対効果が落ちているから
近年、広告費の高騰やクリック単価の上昇が続いており、以前と同じ予算を投下しても十分な成果を得ることが難しくなっています。
また、訪問営業においても、アポイント獲得の難易度が上がり、移動時間や人件費に対する成果が見合わないケースが増えています。
こうした背景の中で、プル型営業は、広告への過度な依存を減らし、顧客の自発的な接触を増やすための長期的な手法として有効です。
役立つ情報や専門的な知見を継続的に発信することで、必要とする顧客から自然に見つけてもらえる状態をつくることができます。
プル型営業のメリットとは
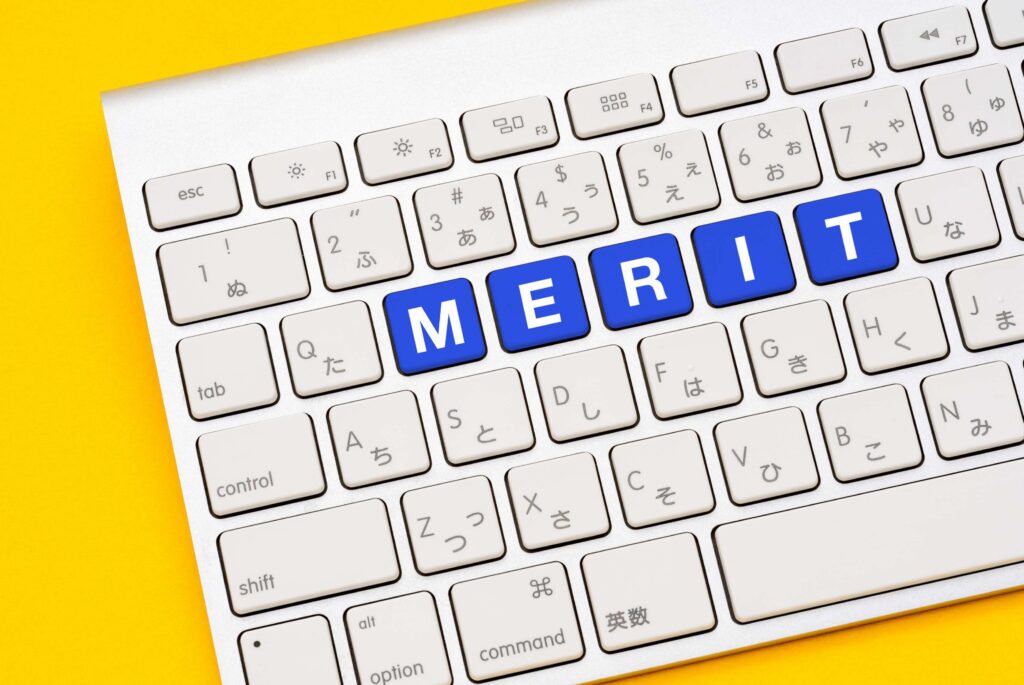
プル型営業のメリットをひと言で表すと「成約率の高い営業が効率よく少人数でできること」です。
一度に少人数の顧客にしかアプローチできないプッシュ型営業とは違い、プル型営業は一度に多くの人にアプローチすることができます。
仕組みを作るまでにある程度の時間と労力、お金がかかりますが、一度仕組みができてしまうと顧客側から自動的にアプローチしてもらえるような状態が構築されます。
このように、プッシュ型営業よりも効率よく、少人数で営業活動ができるのが、プル型営業のメリットと言えるでしょう。
そんな効率性の高さを含め、プル型営業に取り組むことで企業は次のような5つのメリットを享受することができます。
- アポ獲得率や営業成約率が向上する
- 営業効率が格段に上がる(営業工数の削減につながる)
- 信頼関係が構築しやすい
- 見込み顧客のニーズが把握しやすい
- 長期的な費用対効果が高い/コンテンツが資産になる
以下で、それぞれについて見ていきましょう。
◉-1、アポ獲得率や営業成約率が向上する
プル型営業のメリットとして、アポ獲得率や成約率の高さが挙げられます。
なぜなら、顧客がある程度興味を持ったうえで専用フォームや電話などで問い合わせをしてくれるからです。
サイトや記事、メルマガなどで、ある程度自社の商品やサービスの内容を理解し、興味を持った人だけが問い合わせをしてくれるので、アポイント獲得や成約につながりやすくなります。
また、企業としては、問い合わせを受けた時点で、事前に顧客が抱えている悩みなどを把握することができます。
それを元に商談の際に適切な解決策を提示したり、顧客に合わせた提案をする準備をしたりできるのもプル型営業ならではのメリットといえるでしょう。
たとえば、あなたが「是が非でも今日は焼肉を食べたい」と思っていたときに、友人から「この寿司屋めちゃくちゃ美味いからおすすめだよ」と言われても行こうとは思わないでしょう。
一方で、美味しそうな焼肉屋さんを食べログで見つけたり、友人に「そういえば今日焼肉行きたいって言ってたよね?めっちゃ美味い焼肉屋みつけたから行こうよ!」と言われたりすると、「行こうかな」と思ってしまうと思います。
このように、プル型営業は、ある程度自社商品やサービスに興味を持った状態で問い合わせをしてくれたことによる見込み度合いの高さや、問い合わせ内容に応じて相手に合った提案をすることができるという点から、アポ獲得率や営業成約率は自ずと高くなります。
◉-2、営業効率が格段に上がる(営業工数の削減につながる)
営業効率が格段に上がり、営業工数の削減につながることもメリットの一つでしょう。
プル型営業は、仕組みを作るまでが大変ですが、一度できあがってしまえば、1人の営業マンが、多くの顧客に無理なく情報を発信し続けることができます。
また、興味を持った見込み度合いの高い顧客が自動的に集まってくる状態になるので、少ない人員で回すことが可能です。
たとえば、化粧品を購入したい顧客が、Googleなどの検索エンジンで「化粧品 おすすめ」で検索したとしましょう。
検索上位に自社の商品が掲載されると、購買意欲の高い顧客に自社サイトや記事、商品・サービスページを見てもらうことができます。
同じような検索をする購買意欲の高い顧客が多数存在する可能性があるので、プッシュ型営業で個別にアプローチを行い、購買意欲を高めて成約を得るのに比べると営業効率が格段に上がります。
結果として、営業活動全体の効率を高めて営業工数を削減することができるのです。
◉-3、信頼関係が構築しやすい
プル型営業のメリットとして、顧客との信頼関係が構築しやすいことも挙げられます。
その理由は、プル型営業では、顧客が自分の都合でアプローチをしてくるからです。
プッシュ型営業の場合、企業の都合によって営業活動(売り込み)を行うため、顧客によっては迷惑と感じたり印象を悪くしたりします。
一方でプル型営業の場合は、顧客自身は営業を受けているという感覚を持つことはなく、むしろ必要な情報がタイムリーに得られたことに好印象を抱きやすくなります。
たとえば、自分が興味のある美顔器について問い合わせをした結果、営業マンが詳しく丁寧に教えてくれることに対して、好印象を抱く人は多いでしょう。
しかし、突然訪問してきた営業担当者から、興味のない商品を一方的に勧められた場合、好印象を抱くどころか、負担に感じてしまう人も少なくありません。
このように、プル型営業は、結果を急がず、顧客が主体的にアプローチしてくるように上手く誘導していく手法のため、顧客と良好な関係を構築しやすいのです。
◉-4、見込み顧客のニーズが把握しやすい
見込み顧客のニーズが把握しやすいというメリットもあります。
なぜなら、問い合わせの際に、見込み顧客の悩みやニーズなどを把握することができるためです。
たとえば、ダイエットに関心のある顧客に対して、問い合わせフォームに「食事改善を重視したいのか」「軽い運動を取り入れたいのか」「ハードなトレーニングにも取り組めるのか」といった質問項目を設けておけば、回答内容から顧客の具体的なニーズを読み取ることができます。
ニーズを明確に把握できれば、それに合わせた提案を事前に準備することが可能になります。
その結果、提案時に「自分に合った商品・サービスだ」と感じてもらいやすくなり、成約につながりやすくなるのです。
◉-5、長期的な費用対効果が高い/コンテンツが資産になる
資産性の高さや、長期的な費用対効果が高いこともプル型営業のメリットの一つでしょう。
プル型営業の場合は、SNS、メルマガ、オウンドメディアなどでの継続的な情報発信や、そこから成約させるための導線設計、成約しやすいLP(ランディングページづくり)、など営業の仕組みを作るのに手間がかかり、ある程度の初期投資が必要となります。
しかし、一度作った仕組みは長期間にわたって自社で活用できる営業資産となるうえ、顧客の反応やデータ分析を元にして最適化していくことができるので、長期的な運用により、費用対効果が徐々に高くなっていきます。
このように、プル型営業で作った営業の仕組みは、一過性のものではありません。
継続的に効果が続きます。
結果として、継続的な顧客獲得や売上向上につながるため、費用対効果が高くなるのです。
プル型営業のデメリットとは

プル型営業のデメリットを簡単に言えば、成果がでるまで時間がかかることや、短期で安定した成果が出にくいことなどです。
具体的には次の3つがプル型営業のデメリットです。
- 仕組みを作るまで時間がかかる
- 安定した成果を得るのが難しい
- 柔軟な提案につなげづらい
以下で、それぞれについて見ていきましょう。
◉-1、仕組みを作るまで時間がかかる
プル型営業では、顧客が自然と関心を持ち、問い合わせにつながる仕掛けづくりが欠かせません。
そのため、顧客教育につながるコンテンツの制作や、商品・サービスページへの流入を増やすためのSNSやオウンドメディアでの情報発信など、体系的な仕組みを整える必要があります。
たとえば、プル型営業の代表的な施策であるSEO対策では、以下のような事前準備が求められます。
- 見込み顧客が検索するキーワードの調査・選定
- コンテンツ制作
- コンテンツ改善
- お問い合わせフォームなど、導線作成
- LP(ランディングページ)の作成
また、これらの準備が整ったとしても、Googleで検索上位になり、成果を出すには最低でも6ヶ月程度かかります。
このように、プル型営業は成果が出るまでには仕組み作りや、サイト育成など、少なくとも数ヶ月以上はかかるといわれています。
そのため「成果を一刻も早く出したい」という企業や、「このような仕組みが出来上がるまで資金が続かない」という企業には向かない営業手法です。
◉-2、安定した成果を得るのが難しい
安定した成果を得るのが難しいこともプル型営業のデメリットの一つです。
なぜなら、問い合わせのタイミングを決めるのはあくまで顧客自身だからです。
つまり、SNSやオウンドメディア、メルマガなどで情報やコンテンツを発信して、LPやフォームなどの導線を整えたあとは、顧客からの問い合わせを待つしかありません。
見込み顧客が問い合わせをしやすいような誘導はできても、最後に問い合わせするかどうかを決めるのは顧客自身です。
これを企業側がコントロールすることは難しいといえます。
プル型営業の場合、問い合わせ数をコントロールすることが難しいため、予想以上の問い合わせの対応に追われたり、問い合わせが少なすぎて成果が表れないことなども十分に考えられます。
◉-3、柔軟な提案につなげづらい
柔軟な提案につなげづらいこともデメリットの一つでしょう。
その理由として、顧客が購入意欲を持って問い合わせをしてくるケースが多いためです。
顧客によっては、どの商品をどのように利用したいかまで決めている場合もあります。
そのため、プッシュ型営業のように、ヒアリングや関係性構築から始める場合と比べて、自社からの柔軟な提案をしづらくなります。
たとえば、顧客が「部屋の空気をきれいにしたい」と考えて、空気清浄機の購入を決めて問い合わせをしてきた場合、「空気をきれいにするだけではなく、水もきれいにしましょう。こちらも今安くなっていてお得ですよ」とウォーターサーバーの契約を提案しても、断られる可能性が高いと言えます。
このように、問い合わせをした時点で、顧客のニーズは決まっているので、その意思決定を変えることは難しいと言えるでしょう。
プル型営業の主な手法
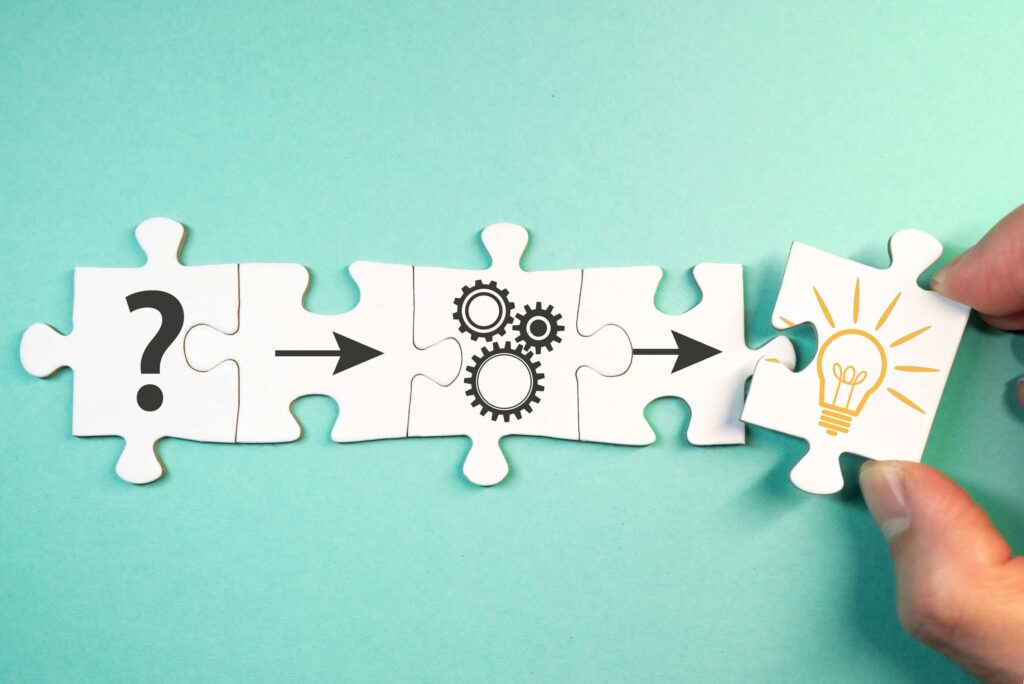
プル型営業の主な手法には、次の5つがあります。
- SNS
- SEO
- メールマガジン
- セミナー
- 企業出版(ブックマーケティング)
以下で、それぞれの手法について詳しく見ていきましょう。
◉-1、SNS
SEO対策などと同様に、自社のSNSでの情報発信も、より多くの見込み顧客を獲得する上で有効な手段です。
よく利用される主要SNSは、X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、YouTube、TikTokなどです。
近年は検索エンジンではなく、SNSで検索する顧客も増えています。
SNSは、拡散性の高い媒体なので、運用に成功すれば、多くの見込み顧客の流入が期待できます。
▶︎SNS運用については、関連記事【【保存版】SNS運用とは?手順や失敗例、集客につなげる運用術を解説!】もあわせて参考にしてください。
◉-2、SEO
顧客の多くは、商品やサービスを検討する際、GoogleやYahoo!などの検索エンジンを利用して情報を収集します。
そのため、顧客が検索した際に、検索結果の上位に自社サイトや自社の情報が表示されていれば、認知されやすくなり、プル型営業の仕組みに自然と流入する可能性が高まります。
このように、検索結果で自社サイトが上位表示されやすい状態を目指して取り組むのがSEO対策です。
顧客が検索するキーワードは数多く存在しますが、その中でも、購入や問い合わせにつながりやすいキーワードで上位表示できれば、安定的な見込み顧客の獲得につながります。
近年は、検索結果を一覧表示するだけでなく、AI Overviewのように、AIが検索意図を読み取り要点を提示する仕組みが広がってきました。
AIを活用した顧客の検索行動が一般的になりつつある状況を考えると、LLMOやAIOといった新たな施策も検討する必要があります。
LLMOはLarge Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)、AIOはAI Optimization(AI最適化)の略語で、どちらも生成AIの回答結果に自社の情報を表示させるための取り組みです。
今後は従来のSEO対策に加え、AIに正しく理解・参照されやすい情報を整備することも重要になってきます。
AIを介した新たな接点にも対応できれば、プル型営業の基盤を強化することが可能です。
▶︎SEO対策については関連記事【SEO対策とは? 効果的な戦略の組み立て方と対策方法】もあわせて参考にしてください。
◉-3、メールマガジン(メルマガ)
自社のWebサイトを訪問して無料会員登録や、資料請求をしてくれた顧客などに対して、メルマガを発行し、継続的な情報発信を行うことも有効です。
無料会員登録や資料請求の申込フォームで、記入を必須にしておけば、見込み顧客のメールアドレスを入手することができます。
このメールアドレスに対して、顧客の購買意欲を高めるような内容のメルマガを定期的に配信すれば、継続的にプル型営業の仕組みに見込み顧客を引き込むことが可能です。
「お問い合わせしてもらったが成約しなかった人」なども、こういった情報発信を継続して行い続けることで、後に成約につながるケースも多々あります。
◉-4、セミナー
セミナー(ウェビナー)を実施することも有効です。
しかし、「商品・サービスの説明」という名目でセミナーを開いても人は集まりません。
そのため、自社の商品・サービスに興味を持つ可能性の高い顧客が持つ悩みの解決方法を教えるセミナーを企画します。
たとえば、美顔器を販売する場合には、「40代女性向け、顔のたるみ解消セミナー」を企画するなどです。
こうすることで、「顔のたるみに悩む人」「顔のハリに悩む人」など美顔器への関心や購入意欲が高いであろう多くの見込み顧客を引き込むことができます。
何かしらの悩みがあり、「その解決策がわかるかもしれない」とセミナーに参加した見込み顧客に、解決策の一つとして自社の商品・サービスを提案していくのです。
◉-5、企業出版(ブックマーケティング)
企業出版(ブックマーケティング)もプル型営業において、見込み度の高い顧客を多く集めるのに有効な手法です。
プル型営業は、待ちの営業なので、「問い合わせをしてみたい」「興味がある」と顧客が思う状態をいかに作り出すのかがポイントです。
そのためには、商品・サービスの説明だけではなく「その商品やサービスがいまの自分に必要な理由」など、顧客がその商品・サービスに興味を持つように、顧客を教育していかなければなりません。
しかし、今は見込み顧客に文章を読んでもらうことが難しい時代です。
特に、見込み顧客との関係値構築が長期で必要なビジネスの場合、「Web上で発信してもなかなか商品・サービスの良さが伝わらない」などの悩みを抱えている方も多いと思います。
そんな方におすすめなのが、ブックマーケティングです。
書籍をただ出版するのではなく、いかに見込み度合いの高い顧客の手元に届けるのかまでを見据えてあらゆる施策を行っていくのがブックマーケティングです。
書籍は、読者がタイトルや内容に興味を持ち、お金を出して買っているため、基本的に長い文章が読まれます。
書籍が信頼性の高い媒体であることもあり、一冊読んでもらうだけで顧客教育がある程度できてしまうというのが、強みと言えるでしょう。
ある程度顧客教育ができた状態で問い合わせがくるため、必然的に成約率は高くなります。
このように、ブックマーケティングを活用することでも、見込み度合いの高い顧客を集めることが可能です。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

企業出版はプル型営業に効果的な施策!

企業出版がプル型営業に効果的な理由は、次の3つです。
- 書籍は専門性と信頼性を一度に伝えられる
- 長期的に価値を持つ情報資産となる
- 書籍がWebや営業施策と連動して顧客接点を広げる
以下で、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、書籍は専門性と信頼性を一度に伝えられる
書籍は、企業の専門分野や商品・サービスの価値を体系的に整理し、分かりやすく伝えられる媒体です。
自社の考え方やノウハウを一冊にまとめて発信することで、その分野における高い専門性を強く印象づけることができます。
また、書籍という形で情報を発信していること自体が、企業にとって「専門性の裏付け」や「信頼の証明」として機能します。
実際に、BtoBの士業やコンサルタント、あるいは高単価な商品・サービスを扱う企業など、信頼性が重視される業種ほど書籍との相性は良いといえるでしょう。
プル型営業において欠かせない「事前の信頼構築」を進める手段としても、書籍は非常に有効な施策です。
◉-2、長期的に価値を持つ情報資産となる
書籍は、Webコンテンツのように短期間で消費されてしまうものとは異なり、長く手元に残りやすいことが特徴です。
一度出版された書籍は、時間が経過しても価値が失われにくく、必要なタイミングで繰り返し読み返される可能性があります。
さらに、顧客企業の社内で回覧されたり再読されたりすることで、企業名やサービスを思い出してもらう接点が継続的に生まれます。
このように書籍は、一時的な販促ツールではなく、長期にわたってプル型営業を支える情報資産として機能するのです。
◉-3、書籍がWebや営業施策と連動して顧客接点を広げる
書籍は単独で完結するものではなく、Web施策や営業活動と組み合わせることで、より効果を発揮します。
書籍に関心を持った読者を、自社Webサイトやメールマガジン、セミナーなどへ自然な流れで導くことが可能です。
複数のチャネルを連携させることで、顧客との接点が一過性で終わることなく、継続的なコミュニケーションへと発展します。
その結果、企業やサービスへの理解・信頼が深まり、問い合わせや相談といった具体的な行動につながりやすくなるのです。
企業出版を活用してプル型営業を行う5ステップ

企業出版を活用したプル型営業の仕組みづくりは、次の5つのステップで進めることができます。
- ステップ1:読者層と書籍のテーマを明確にする
- ステップ2:企業の強み・専門性を整理して構成案に落とし込む
- ステップ3:読者に伝わる原稿として体系的にまとめる
- ステップ4:書籍の体裁を整え書籍として完成させる
- ステップ5:出版後の導線を設計し営業・Web施策と連動させる
以下で、それぞれのステップについて見ていきましょう。
◉-1、ステップ1:読者層と書籍のテーマを明確にする
はじめに、どのような顧客層に向けた書籍なのかを定め、 その読者が抱えている課題や関心事を整理します。
そして、読者が知りたいテーマを具体的に設定します。
あわせて、書籍全体を通して何を伝えるのかという方向性も、この段階で明確にしておくことが重要です。
これらの工程を丁寧に行うことで、書籍の内容に一貫性が生まれ、企業の専門性や強みが読者に伝わりやすくなります。
プル型営業として機能する書籍をつくるための土台となる重要なステップといえるでしょう。
◉-2、ステップ2:企業の強み・専門性を整理して構成案に落とし込む
次に、企業が持つ強みや実績、専門的なノウハウを洗い出し、書籍で伝えるべき要素を整理します。
それらの情報を、読者が理解しやすい順序や流れを意識しながら、全体の構成案に落とし込みます。
単に情報を並べるのではなく、「なぜこの企業は信頼できるのか」が自然と伝わる構成を意識することが重要です。
◉-3、ステップ3:読者に伝わる原稿として体系的にまとめる
構成案をもとに、専門的な内容でも読み進めやすい原稿へと落とし込んでいきます。
事例や具体的なエピソード、図解などを用いることで、読者の理解度が高まります。
自社目線の説明に偏らず、読者の立場に立った表現を意識することが重要です。
◉-4、ステップ4:書籍の体裁を整え書籍として完成させる
原稿が完成したら、書籍のサイズや章構成を確定し、編集や校正を行います。
あわせて、表紙デザインやレイアウト、装丁などを整え、読みやすさと見た目の品質を高めます。
書籍の印象は、内容だけでなく、表紙デザインや外観の質によっても左右されるからです。
自社のイメージやブランドに合った一冊として完成させることが重要です。
◉-5、ステップ5:出版後の導線を設計し営業・Web施策と連動させる
書籍は出版して終わりではなく、そこからどのように次の接点につなげるかを設計します。
書籍を読んだ読者を、自社Webサイトやメルマガ、セミナー、営業活動へと自然に誘導する導線を用意します。
複数の施策と連動させることで、書籍をきっかけとした接点を一度きりで終わらせず、購入や問い合わせを決める前の情報収集段階に応じた情報提供が可能になるのです。
こうした導線設計によって、企業出版はプル型営業の仕組みとして機能します。

企業出版を活用したプル型営業の成功事例

ここでは、企業出版によってプル型営業の成果につながった事例を2つ紹介します。
- 読者からの問い合わせが急増し、成約につながったケース
- 海外進出の専門家という信頼性を確立して売上を伸ばしたケース
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、読者からの問い合わせが急増し、成約につながったケース
ある不動産会社の経営者は、高収入で支払う税金が多い医師に向けた不動産投資サービスの情報を記事やSNS、Web広告などを通じて発信し続けていましたが、なかなか魅力が伝わらず、悩んでいました。
そこで、高収入で購買意欲が高い一方で税金が多いことに悩む医師に対して、「最も効果的な節税対策が不動産投資である」ということを伝える書籍を出版。
ただ出版するだけではなく、あらかじめ、その後のマーケティング施策や展開なども見据えて企画していたことから、ターゲットである多くの医師に書籍を届けることができました。
その結果、書籍を購入した多くの医師に不動産投資に大きな節税効果があることを認知してもらうことができ、出版から半年で10件の読者反響が発生。。
そのうち10件すべてが成約に至るという、高い成約率を記録しました。
そればかりか、既存の顧客が知り合いの医師に書籍を配ってくれて、そのことから新規の問い合わせにもつながったそうです。
ブックマーケティングによって書籍を出版して顧客からの問い合わせを待つという、まさにプル型営業を実践して、営業効率や成約率を高めることに成功した事例と言えるでしょう。
◉-2、海外進出の専門家という信頼性を確立して売上を伸ばしたケース
国際税務を専門とする公認会計士事務所の経営者は、海外進出を検討する法人向けに海外進出をテーマにした書籍を出版。
書籍では、グローバル展開時に起こりやすい税務上の課題や解決策を紹介しています。
出版後、地元紙や全国紙、ラジオ番組などへのメディア露出が増加し、あわせて企業からの相談依頼も増加しました。
出版をきっかけに海外進出の専門家としての信頼性が確立し、価格ではなく価値で選ばれるようになったことで、売上の伸長につながったのです。
結果として、広告や営業活動以上に、書籍が信頼構築と案件獲得の両面で高い効果を発揮しました。
【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士
【まとめ】プル型営業を成功させるために企業出版を検討しよう
この記事では、プル型営業とは何か、必要とされている理由、メリット・デメリットについて整理し、主な具体的手法や導入ステップ、成功事例について解説しました。
プル型営業は信頼される情報を発信している企業に問い合わせが集まる営業手法であり、企業出版はその信頼の土台を築き、見込み客との接点を長期的に生み出す情報発信手段です。
フォーウェイの「ブックマーケティングサービス」は、プル型営業で成功を目指す企業にとって最適な手段となります。
ブックマーケティングを活用すれば、出版した書籍を自社のブランディングに活用し、専門家としてのポジション確立や価格競争からの脱却を図ることが可能です。
さらに、メディア露出の機会増加、顧客の記憶への定着、認知度向上などに役立てることができます。
プル型営業を成功させるために、フォーウェイのブックマーケティングを活用してみませんか。


企業SNSを運用したいが、やり方がわからないーーこのように考えるマーケティングや広報の担当者は多いことでしょう。
以前は「個人の遊び」という印象が強かったSNSですが、時代はすっかり変わりました。SNSはビジネスにおけるコミュニケーションの重要な一部分である、という認識が多くの企業に浸透してきたのです。
しかし、企業SNSのアカウントが乱立するなかで、ビジネスにおけるメリットをきちんと獲得できているケースはごく一部と言わざるを得ません。
そこで本記事では、企業SNSの運用を考える方向けに、SNSによってビジネスメリットを実現する「運用のやり方」を解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
企業のSNS運用とは?

企業にとってSNS運用は、ビジネスの成長に欠かせないものとなっています。
企業のSNS運用は、一言でいえば「ビジネス目的」である点が最大のポイント。
個人のアカウントに比べてよりプロフェッショナルで戦略的な運用のやり方が求められます。
個人のSNS運用との違い
個人のSNS運用は、主に自己表現や交流が目的です。
もちろんSNSを通じたマネタイズに成功しているインフルエンサーなどの個人はいますが、そうした人たちはビジネス目的の運用という意味で、個人の趣味的なアカウントとは違う種類の運用だと言えるでしょう。
企業のSNS運用は、商品やサービスのプロモーションやブランドイメージの向上など、ビジネス上の目的があります。
そのため、やり方としても投稿内容や投稿頻度、ターゲット層など戦略的な視点が求められます。
また、ユーザーに悪印象を与えないようにする気配りも、個人アカウントに比べてより重要になるのです。
SNSマーケティングとの違い
SNSマーケティングは、SNSを活用してマーケティング活動を行うことです。
具体的には、下記のようなやり方があります。
・インフルエンサーマーケティング
・SNS広告運用
・ソーシャルリスニング
・SNSキャンペーンの実施 |
総じていえることとして、費用を投じたタイミングにだけ効果を発揮し、商品購入や問い合わせなど直接的なリターンを目指すのがSNS運用以外のSNSマーケティングです。
広告施策としての色が強い取り組みとも言い換えられます。
一方で、SNS運用はSNSマーケティングのくくりにはありますが、下記のような特徴があります。
・オーガニック投稿として自由度の高い発信が可能
・ユーザーとのコミュニケーションによりファン化を促進できる
・運用をやめたり頻度を鈍らせたりしてもアカウントや過去の投稿は残る
・一度フォローしてもらったユーザーをアカウントの資産として持ち続けられる
・長期にわたる施策の継続がやりやすい |
長期的なブランディングを目指したり、マーケティングの基盤を作ったりといった目的を達成するために適しているのがSNS運用です。
参考:SNSマーケティングとは?代表的な手法から戦略立案、成功事例まで徹底解説|株式会社ビーステップ
SNS運用が重要になっている理由

SNS運用がビジネスにおいて重要になっているトレンドは、データからもわかります。
「ソーシャルメディアマーケティング市場、2023年ついに1兆円を突破の予測【サイバー・バズ/デジタルインファクト調べ】」(https://webtan.impress.co.jp/n/2022/11/11/43642)によると、ソーシャルメディアマーケティングの市場規模は2020年の5,971億円から2022年には9,317億円へと大幅増加。
2027年には1兆8,868億円にまで市場が拡大すると推計されています。
SNS運用はやり方を工夫すれば大きなリターンを得られる一方で、フォロワーを増やすためにはどうしても一定の時間が必要です。
SNSの市場が伸びていくなかで、早く始めた企業ほど成功に近づくのは間違いありません。
SNS運用によって得られるメリット
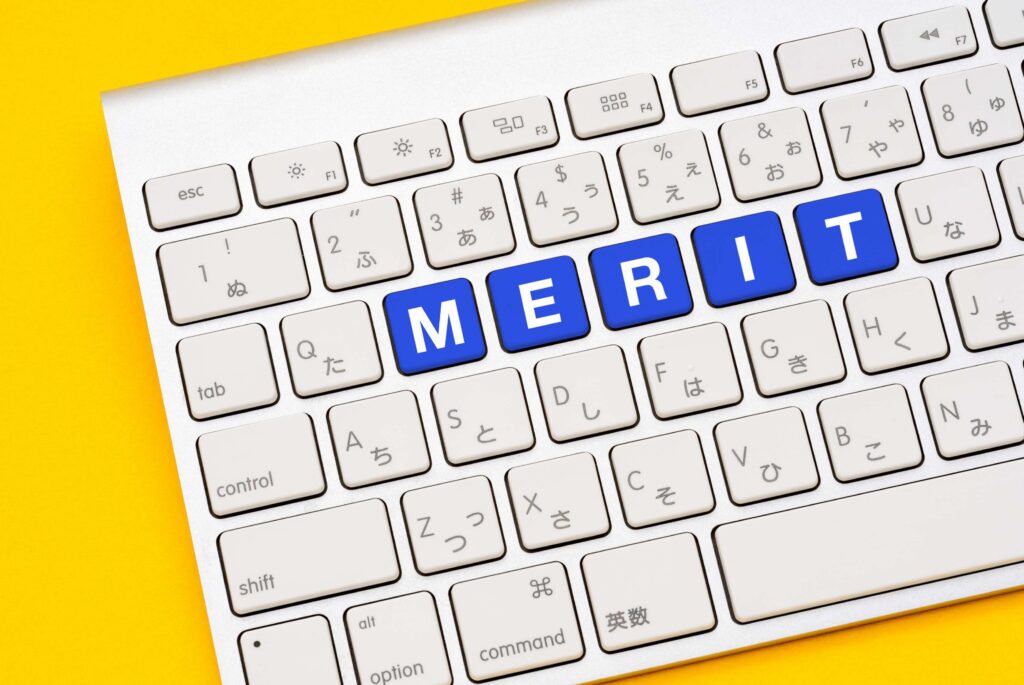
ここで、企業のSNS運用によって得られるメリットを改めて整理しましょう。
大きくいうと、以下の通りです。
・商品やサービスのプロモーションができる
・自社ターゲット層に直接訴求できる
・顧客とのコミュニケーションを深めることができる
・企業のブランドイメージを向上させることができる
・リアルタイムな情報の発信が可能になる |
いずれにも共通するのが、SNS運用によるメリットの発揮とは運用のやり方にかかっているということです。
SNSアカウントがあるだけで売上につながるような理想的状況を作るには、狙ったターゲット層のフォロワーをたくさん抱えた「強い」アカウントを作る労力を惜しまないことが、成功事例に共通した特徴です。
各SNSの特徴と運用のコツ

ビジネスでよく活用されるSNSは、主に以下の7つです。
・Instagram
・X(旧Twitter)
・Facebook
・LinkedIn
・LINE
・Tik Tok
・YouTube |
各SNSの特徴と運用のコツを詳しく解説します。
Instagram
Instagramは、写真や動画を投稿するSNSです。
ビジネスにおいては、商品の宣伝やイメージアップに活用されることが多く、特に若い世代に人気があります。
ただ、40代以上の層も利用率は低いものの、実数でいうと若年層に匹敵しており、実は全年齢に向けたアプローチにも使えます。
Instagramの運用のポイントは、以下の通りです。
・ハッシュタグや発見タブによって投稿を検索されやすくする
・投稿のビジュアルについて方向性を定め、ユーザーに価値を感じてもらえる投稿を一定頻度で続ける
・ストーリーズ機能を使い、日常的な情報を発信することでフォロワーとのコミュニケーションを深める
・インスタライブを使い、フォロワーとの関係性をより強化する |
勘違いされがちですが、「発信者のビジュアルが優れていて顔出しできる」「商品のきれいな宣伝写真がたくさんある」などの要素はInstagram運用で必須ではありません。
「商品のターゲット層が興味を持つノウハウを発信する」「日常風景の投稿でユーザーと距離感を縮める」など企画の方向性によって、あらゆるビジネスでInstagramの強みを発揮できます。
X(旧Twitter)
X(旧Twitter)は、140文字以内(X Premium加入者はそれ以上も可能)の短い文章を投稿することができるSNSです。
主にリアルタイム情報の収集や発信に使われ、特にニュースやトレンドに関する情報が多く取り扱われています。
Xの運用のポイントは、以下の通りです。
・アカウントのテーマに沿った自分なりの「情報提供」と「持論」を発信してフォロワーを増やす
・ほかのアカウントとコミュニケーションを増やし、タイムライン上の表示優先度を高める
・ほかのアカウントをフォローし、フォロー返しを獲得することでフォロワーを増やす |
Xは実名顔出しで運用するアカウントが多く、アカウント同士のコミュニケーションが重視されるカルチャーのSNSです。
企業アカウントとして活用する場合でも、事務的な発信だけでなく「中の人」の人柄が感じられるアカウントが好まれる場合があります。
リツイート機能でツイートが大きく拡散される仕様により、投稿が大きくバズる可能性のあるSNSでもあります。
Facebook
Facebookは、世界で最も利用者数の多いSNSの一つです。
友達や家族とのコミュニケーションが中心ですが、ビジネスにも活用されることが多く、商品の販売やブランドの発信などに使われます。
Facebookの運用のポイントは、以下の通りです。
・定期的にコンテンツを投稿することで、フォロワーの獲得やエンゲージメントの向上を目指す
・Facebookページを作成し、“いいね”を獲得することで拡散力を高める
・Facebookグループを作成し、ファンコミュニティを形成することで、ファンとの交流を深める |
Facebookは一定年齢以上の人のビジネス活用においては根強い人気のあるSNSです。
ただ、友達に追加する人数に5000人という制限があるため、つながりをたくさん増やして大きく拡散しようとする運用方針には向きません。
関係性のある相手から自社への認知を維持したり、仕事の相談をもらいやすくしたりする運用がFacebook活用のコツです。
LinkedIn
LinkedInは、ビジネス関係者が集まるSNSです。
求人情報やビジネスマッチングなどに使われることが多く、ビジネスユースに特化したSNSであるといえます。
LinkedInの運用のコツは、以下の通りです。
・原則実名登録なので、反感を招くような投稿は避ける
・ほかのアカウントと交流し、コミュニティなどにも積極的に参加する
・ターゲットに対して積極的にDMを送る |
いわゆる営業のためのDMや採用DMはほかのSNSだと嫌がられる場合がありますが、LinkedInはビジネスSNSである側面から、ほかアカウントへの直接アプローチは比較的、受け入れられているのが特徴です。
ただし、大量のスパム送信はLinkedIn側から制限をかけられる危険があります。
丁寧に絞り込んだターゲットアカウントに対し、一通一通、心を込めてDMを送ることが成果の秘訣です。
LINE
LINEは日本国内において、幅広い世代で利用されているSNSです。
2025年3月末時点のLINEアプリ月間アクティブユーザーはLINEの自社調べで約9,800万人、2023年1月1日時点の日本の人口約1億2,475万から推計すると、約70%以上が使っていることになります。
LINEにはビジネス用にLINE公式アカウントを開設できるサービスがあり、企業や店舗が友だち追加してくれた顧客に情報発信できます。
LINEの公式アカウントには以下のような特徴があります。
・リピーターが増える・売上につながる
・機能が充実・操作は簡単
・目的・用途に合わせて選べる料金プラン |
LINEが2021年7月に行った携帯電話のアンケートでは、LINE公式アカウントからメッセージを受け取って約80%がその日のうちに開封されていることが分かりました。
また、「よく行くお店のアカウントがあったら、友だち追加・フォローしたいサービス」として、57.8%がLINEと回答しています。
それだけ情報源としてLINEを活用したいと考えているユーザーは多く、リピーターの獲得や売上の向上につながりやすいSNSです。
LINEの公式アカウントはポイントカードの発行管理やクーポンの配信のほか、オリジナルのサブスクリプション型サービスを作成できます。
各種販促ツールも使えるなど、集客から販促まで活用できる機能が充実しているのもメリットでしょう。
3つの料金プランがあるため、想定するメッセージ数など、自社の状況に応じて選べます。
参考:LINEヤフーfor Business「LINE公式アカウント」
参考:総務省統計局「人口推計-2023年(令和5年)1月報-」
TikTok
Tik Tokは15~60秒程度の短い動画を投稿できるSNSで、X(旧Twitter)やFacebook、LINEなどに比べると比較的新しいサービスです。
Tik Tokの特徴は、以下の通りです。
・短尺動画がメイン
・若年層に人気
・トレンドに敏感
・拡散力が強い |
特に10~20代のユーザーが中心ですが、全世代でも利用率が伸びています。
総務省情報通信政策研究所が発表している「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」では、情報通信メディアの利用時間が報告されています。
主なソーシャルメディア系サービスやアプリの全世代利用率をみると、Tik Tokの利用率は2018年では10.3%でしたが、2020年には17.3%、2023年には32.5%にまで伸びました。
また、2023年の全世代利用率は32.5%であったのに比べ、10代は70.0%、20代では52.1%となっており、10~20代のユーザーが多いことが分かります。
短尺動画がメインということもあり、スキマ時間でも気軽に視聴しやすいのがTik Tokのメリットです。
限られた時間に伝えたい内容を盛り込む必要がありますが、「視覚的なインパクトを与えられる」「テンポの良いリズムで記憶に残りやすい」などのメリットがあります。
流行の音楽・ダンスや「○○チャレンジ」のようなトレンドに敏感な投稿が多く、ユーザーを巻き込み、拡散力が強いのも注目すべきポイントです。
Tik Tokには、ビジネス用の広告プラットフォーム「Tik Tok for Business」があります。
細かい設定の必要もなく、無料の動画広告制作ツールなどを利用して広告配信まですべてオンラインで完結します。
参考:総務省情報通信政策研究所「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」
YouTube
YouTubeの特徴は以下の通りです。
・短尺動画から長時間の動画まで投稿が可能
・ライブ配信もできる
・利用者の年齢層が幅広い |
YouTubeはTik Tokとは異なり、短尺動画だけではなく情報量の多い長時間の動画も投稿できます。
単に自社の商品やサービスを紹介するだけにとどまらず、商品の使い方を実演して見せるなど、How-To動画の提供も可能です。
リアルタイムで情報が更新されていくフロー型のSNSはバズって一気に拡散される可能性がある一方、短期間で忘れ去られることも考えられます。
しかし、YouTubeはストック型の動画として、コンテンツを蓄積しておけます。
たとえば、ギフト商品を扱う企業のコンテンツとして、「新社会人への贈り物におすすめのアイテム」や「お祝いのマナー」などの動画をアーカイブとして残しておいたとしましょう。
フロー型のSNSのように爆発的な拡散力はないかもしれませんが、ギフトを贈るシチュエーションでは、一定の再生回数を得られます。
YouTubeのコンテンツから自社のWebサイトへ誘導できるようにしておけば、売上にも結びつきやすくなります。
有益なコンテンツが蓄積されていくと中長期的に顧客の信頼を得られるメリットがあるため、ターゲット層が求める情報を把握し、コンテンツを充実させていくことが重要です。
新商品の発表会やセミナーなどには、ライブ配信も活用できます。
総務省情報通信政策研究所の「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によると、YouTubeの全世代の利用率は、2014年時点ですでに65.1%でした。
その後も徐々に利用率は上がり、2023年では全世代で87.8%です。
利用者の年齢層も幅広く、2023年時点では60代では66.3%にとどまっているものの、50代以下では80~90%台の高い利用率になっています。
幅広い層に自社の商品・サービスをアピールできるため、活用の幅は広いでしょう。
参考:総務省情報通信政策研究所「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」
SNS運用を始める前に決めること5つ

続いてはSNS運用の実践編です。
SNS運用は、やり方を決めずにとりあえず始めてみても成功率は低いです。
ビジネスにつなげるためには、事前準備がカギを握ります。
事前準備として考えるべき項目は、以下の通りです。
・決めること①運用の目的
・決めること②運用体制
・決めること③アカウントの方向性
・決めること④ターゲット層
・決めること⑤具体的なタスクとスケジュール |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
決めること①運用の目的
SNSを始める前に、まずは運用の目的を明確にすることが必要です。
たとえば、ブランド認知度の向上や製品やサービスの販売促進、情報発信や顧客対応など、目的はさまざまです。
目的に応じて運用するSNSの種類やコンテンツや投稿頻度、投稿内容、ターゲット層などが異なるため、運用の目的をはっきりと決めてから取り組むことが重要です。
気をつけたいのが、「運用目的は売上に決まっているでしょ」と単純に決めてしまうこと。
SNS運用は短期的な売上効果だけでなく、ブランディング効果やファンユーザーの獲得などさまざまな尺度での効果を視野に入れる必要があります。
長期的にアカウントを育てる施策だけに、短期の集客では広告施策より数値が劣る場合が多く、運用目的を売上だけと定めてしまうとスムーズな運用が進まない危険性が高いのです。
「短期で何を目的にするのか」「中期〜長期で何を目指すのか」など、細かく設計するのが成功するコツです。
▶︎SNS運用の目的設定については、過去コラム『SNS運用で大切な「目的設定」とは?運用効果を最大化する秘訣を徹底解説』で解説しているので、こちらもご参照ください。
決めること②運用体制
SNS運用では、運用担当者やチームの体制を整えることも大切です。
運用にあたっては、「誰が投稿するのか」「どのようなスケジュールで投稿するのか」「コメントやメッセージの返信は誰が担当するのか」といったことを明確にしておく必要があります。
また、社内で運用する場合は、社員の研修やマニュアル作成なども必要かもしれません。
会社としてSNS運用に取り組むときの体制で重要なのは、組織として担当者をフォローアップして運用を管理する仕組みをつくることです。
社内の担当者はほとんどの場合、SNSのプロではありません。
「いい感じにやっておいてくれ」と丸投げして放置していると、運用の目的が達成できないどころか投稿やアクション自体が止まってしまうケースも珍しくありません。
自社の貴重なリソースを使って、徒労に終わらないように気をつけましょう。
決めること③アカウントの方向性
SNSアカウントの方向性についても、事前に決めておくことが重要です。
たとえば、ファッションブランドのアカウントであれば、コーディネートの紹介や新作アイテムの情報を発信することが求められます。
一方で、医療機関のアカウントであれば、健康情報や病気の予防・治療についての情報提供がいいかもしれません。
アカウントの方向性を明確にしておくことで、フォロワーの期待に応えることができ、効果的な運用が可能になります。
たとえば、SNS運用の代行を請け負うプロであれば、クライアントへのヒアリングをもとにペルソナシートやアカウント構成シートといった資料を作成します。
ターゲット層や運用目的に合わせてデザインのトンマナから投稿文体まで細かく設定し、ブレない運用を実現するのです。
決めること④ターゲット層
SNSを利用するユーザーは、それぞれ年齢層や性別、興味関心、ライフスタイルなどが異なります。
運用するアカウントのターゲット層を明確にし、その層に合った投稿やコンテンツを提供することが必要です。
また、ターゲット層に応じて、運用するSNSや投稿する時間帯、投稿内容、コンテンツの種類なども変わってきます。
このターゲット設定は、「30代以上の女性」など大まかすぎるくくりではあまり意味がありません。
よくマーケティングで使われる「ペルソナ(代表的なターゲット像の架空のプロフィール)」を設定するのも効果的でしょう。
誰か一人に深く刺さるコンテンツはほかの人にも刺さるというのがSNS運用の原則です。
決めること⑤具体的なタスクとスケジュール
SNSの運用においては、具体的なタスクとスケジュールを決めておくことが大切です。
どのようなコンテンツを、どのようなタイミングで発信するのかを明確にすることで、運用がスムーズに行われます。
また、週次や月次での運用の報告や評価を行い、必要に応じて改善を行うことも大切です。
コツとしては、とにかくあいまいさを残さないこと。
「ネタがあるときに投稿する」「なるべくほかのアカウントに“いいね”する」といったルール設定ではなく明確に行動目標を決めましょう。
実際に運用をしてみると担当者に負担がかかりますが、強いアカウントを育てるにはそれなりの努力が必要です。
SNS運用の効果測定と運用改善

「SNSの運用成果は、どうやって評価・改善すればよいの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
SNS運用の効果を可視化するためには、以下のような指標を活用します。
・フォロワー数
・リーチ数
・エンゲージメント数(「いいね!」やコメント数など)
・コンバージョン数(集客数、商品の売上数など) |
計測すべき指標は、運用目的やどのSNSを用いるかによって変わってきます。
たとえば、対面アポイントの獲得を目標にする運用なら、DMのうちのアポイント率が指標になるでしょう。
改善項目としては普段の投稿の質よりも、アカウントの信頼性を高めるためのフォロワー増やDM文面の改善などの優先順位が高くなります。
おすすめとして、ある程度フォロワーが増えるまではフォロワー数だけをKPIにするのが良いでしょう。
SNS運用による効果の多くは、ある程度フォロワーがいないと発揮されにくいためです。
管理をシンプルにすることで運用もスムーズになります。
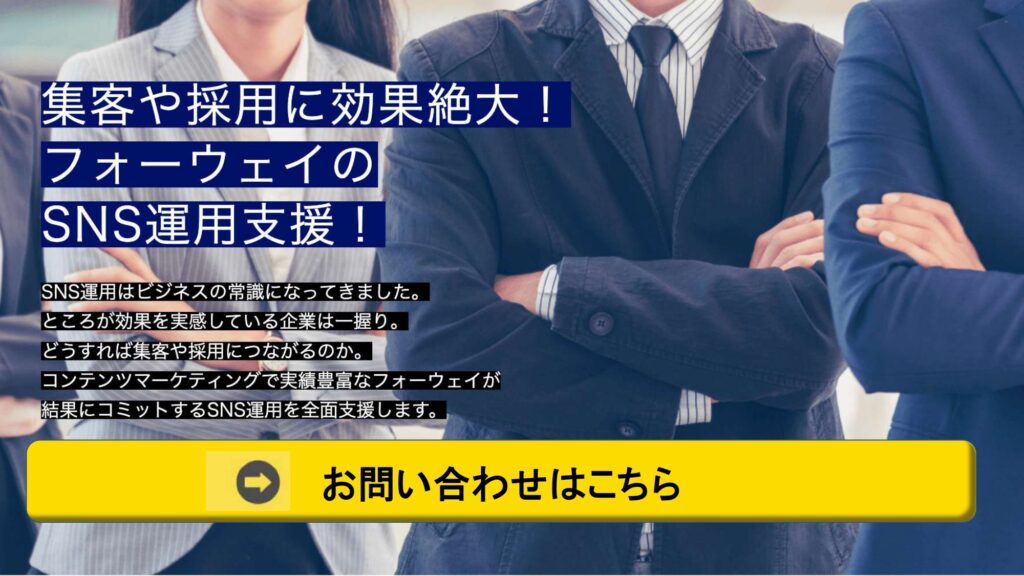
SNS運用のよくある失敗例4パターン
SNS運用をする際には、失敗の典型例に当てはまらないよう注意して運用しましょう。
よくある失敗例として、以下の4パターンがあります。
・失敗例①フォロワー数が増えない
・失敗例②運用が止まってしまう
・失敗例③運用の方向性が迷走する
・失敗例④炎上してしまう |
それぞれ詳しく解説します。
失敗例①フォロワー数が増えない
思うようにフォロワーが伸びないのは、SNS運用で最もよくある失敗ケースです。
理由として、たとえば下記が考えられます。
投稿頻度が低い
多くのSNSは、自アカウントの投稿がほかのユーザーのタイムラインに表示されることでフォローが発生します。
したがって、投稿が少なければどんなにアカウントを作り込んでいてもフォロワーが増えるチャンスはほとんどありません。
最低でもInstagramなら週3回、Xなら1日1回は投稿が必要です。
ほかアカウントとのコミュニケーション不足
「いいね」や「コメント」などほかのアカウントに対して自分からアクションするのも、フォロワーを増やすためには重要です。
ここを怠るとフォロワーはほとんど増えません。
ただし、アクションする先のアカウントの選定にもコツがあります。
リアクションを返してくれそうなアカウントや信頼度の高いアカウントの共通点を見出し、適切な相手に対してコミュニケーションを取る必要があります。
失敗例②運用が止まってしまう
SNS運用がストップしてしまう失敗事例はとても多いです。
その理由のほとんどは、はっきり方針を決めずに担当者に丸投げしたきり管理しない運用体制にあります。
投稿スケジュールの明確な設定と投稿物の確認、定例の確認ミーティングなどは組織内で必ず行いましょう。
また、「売上につながっていないからものすごくクオリティの高い投稿をしなきゃ」など、成果を焦って答えのない課題を設定してしまうのも投稿ストップの原因になります。
SNSは定期的にコンテンツを発信して自アカウントにあった運用のやり方を探っていくプロセスがとても重要です。
クオリティにこだわりすぎるよりも継続的な運用を重視しましょう。
失敗例③運用の方向性が迷走する
SNSの運用は、アカウントの方向性を守ることが重要です。
失敗例②に近いですが、成果を焦って方向性の切り替えを連発し、コンセプトのよくわからないアカウントになってしまうのもよくある失敗パターンです。
どんな方向性を試してみても、運用初期に一つの投稿でわかりやすい効果が発揮されることはなかなかありません。
まずは運用開始前のコンセプト設計を細かく行い、決めた方向性に則って腰を据えて取り組みましょう。
そうすれば長期的な成果に高い確率でつながります。
失敗例④炎上してしまう
SNSの運用で最も避けたい失敗が「炎上」です。
一度炎上してしまうと、ブランドイメージに大きなダメージを与えかねません。
具体的な炎上理由として、以下の3つが挙げられます。
・不適切な表現や誤解を招く
・投稿社内の機密情報や個人情報の漏えい
・社会的背景を無視した不用意な発言 |
悪気はなくても、意図せず自社の投稿がネガティブに解釈されることもあります。
炎上すると信頼回復にも長い時間とコストがかかるため、炎上リスクを理解したうえで活用することが重要です。
SNSの炎上を防ぐ対応策4選

SNS運用において、炎上を気にする方は多いかもしれません。
企業のSNS活用が普及するにあたって、炎上してしまった事例も多く聞かれるようになりました。
そこで以下に、SNSの炎上を防ぐための対応策を紹介します。
・炎上防止策①投稿ガイドラインの策定
・炎上防止策②対応ガイドラインの共有
・炎上防止策③投稿監視体制の整備
・炎上防止策④炎上事例の社内共有 |
4つの炎上防止策を見ていきましょう。
炎上防止策①投稿ガイドラインの策定
SNS運用を始める前に、社内でSNSマニュアルを策定しましょう。
このマニュアルには、発信内容のチェックや、危険な発言を行わないようにするためのガイドラインなどが含まれています。
ガイドラインを設定する際には、ぜひSNS慣れした若いスタッフの力を借りてください。
普段からSNSに慣れ親しんだ人間であれば、それぞれのSNSにおけるマナーを感覚で理解しています。
若いスタッフにたたき台をつくってもらったうえで、広報やリスク管理担当などプロの目で見てブラッシュアップする進め方がおすすめです。
炎上防止策②対応ガイドラインの共有
もしも炎上騒ぎが起こってしまった場合には、迅速かつ的確な対応が必要です。
SNS上でのトラブルの拡散を防ぐために、炎上した場合には速やかに謝罪し、原因究明を行いましょう。
ただし、SNS運用に慣れていない企業が担当者任せにする体制は危険です。
機転をきかせたつもりが火に油を注いでしまう可能性もあります。
投稿物だけでなく、炎上懸念がある場合の対応についても社内でガイドラインを設定し、フローを明確にするのがおすすめです。
弁護士やPR会社などの外部専門家にリアルタイムで相談できる体制を構築しておくのも効果的でしょう。
炎上防止策③投稿監視体制の整備
SNS上でのトラブルを未然に防ぐためには、定期的にSNSのコンテンツを監視し、問題のあるコメントや投稿に対して迅速に対応することが必要です。
また、不適切なコメントや投稿があった場合には、速やかに削除し、投稿者に対して注意喚起を行う必要があります。
投稿の監視には、「上司が毎日11時にチェック」「広報が朝礼でチェック」など、担当者ではなく第三者的な目線でチェックを入れる決まりごとを作っておきましょう。
社内リソース的に難しければアルバイト数人でチェックする体制でも、一般的な目線による第三者チェックは入れられます。
さらに、SNSコンテンツの監視を効率化するために、ソーシャルリスニングツールの活用もおすすめします。
Meltwaterのソーシャルリスニングツールは、SNSの投稿をリアルタイムで一元的に分析できるため、炎上の火種となりうる投稿の把握に役立ちます。
炎上防止策④炎上事例の社内共有
SNSの炎上を防ぐのに大事なのは、抽象的ながら社内のリテラシーです。
関係者の知識を増やし教育をしていくのが、時間はかかりますが炎上を防ぐために有効な施策です。
そこで、日々SNS上の炎上情報をウォッチし、社内で定期的に共有、ポイントを話し合う機会を設けましょう。
特に自社と業種や運用目的の近いアカウントが炎上してしまった事例は、貴重な学習材料になります。
SNS運用を成功させるためのコツ

SNS運用を成功させるためには、以下のようなコツがあります。
・目標を明確にする
・一貫性のある情報発信を意識する
・質の高いコンテンツを作成する
・データ分析に基づいた改善を行う
・ほかの集客施策と組み合わせる |
5つのコツについて詳しく解説します。
目標を明確にする
SNSを運用する際に重要なのは、「何のためにSNSを活用するのか」という目的とゴールを明確にすることです。
「自社の認知度を高めたいのか」「商品の購入につなげたいのか」「採用を強化やブランディングに力を入れたいのか」など、目的によって取るべき施策も違ってきます。
認知度を高めるのが目的なら、「SNS経由のWebサイト訪問者数を20%向上させる」のように、具体的な目標も設定できます。
目標を明確にすれば成果も見えやすく、投稿内容やKPI設定、分析の方針もブレません。
一貫性のある情報発信を意識する
SNSは「ブランドの人格」を映し出す場所です。
そのため、情報発信の仕方や内容に一貫性を持たせ、自社のイメージを損なわないようにする必要があります。
ビジュアルや投稿のトーンがバラバラでは、ユーザーに混乱を与えかねません。
たとえば、「シンプルながら温かみを感じる」イメージがそのブランドの「らしさ」ならば、色味やフォントもそのイメージに合わせて統一し、言葉選びも世界観や価値観に合わせるように心がけてください。
一貫性のある情報発信として、定期的なシリーズ投稿を設けるのも効果的です。
「このブランドらしさ」が定着すれば、ファンを育てることができます。
質の高いコンテンツを作成する
次々に投稿が更新されていくSNSは、情報量が膨大です。
ユーザーのスクロール速度も早いため、そのなかで目を留めてもらうためには、「質」の高いコンテンツが欠かせません。
そこで、以下の3点を意識することが重要です。
・見た瞬間に内容が伝わるビジュアル
・読者の悩みや興味に刺さるコピー
・保存したくなるようなノウハウ情報 |
読者の悩みや課題を解決する情報や興味を掻き立てるコピーで注意を引き、ビジュアルで内容がイメージできるようにしましょう。
一方的に商品やサービスをアピールするのではなく、保存したくなるような情報や再生したくなる動画などを盛り込むことが大切です。
データ分析に基づいた改善を行う
SNS運用は、「投稿して終わり」ではありません。
「どの投稿が反応を得られたのか」「どの時間帯の投稿が効果的なのか」など、以下の3点を踏まえた分析と改善が必要です。
・インサイト(解析ツール)を定期的にチェックする
・投稿のA/Bテストを行う
・KPI(リーチ数、保存数、クリック率など)を可視化する |
まずは、インサイト機能で定期的にリーチ数やフォロワー数、クリック率などをチェックし、記録してください。
特定の要素だけを変更した場合の成果を比較できるA/Bテストを実施すると、より高い成果を得られるパターンを見つけられます。
また、目標達成に向けた進捗を示すKPIは、可視化しておくと成果が見えやすいでしょう。
改善を繰り返すことで、SNS運用の精度は上がっていきます。
ほかの集客施策と組み合わせる
企業のSNS運用は、単体で完結させるものではありません。
SNS運用でより高い成果を生むポイントは、ほかの集客施策との組み合わせです。
SNSは、あくまでも入口であり、その先にある情報や体験にうまく接続できるかどうかがポイントになります。
ほかの集客施策との相乗効果でより高い成果を生み出し、ブランド理解や信頼構築はもちろん、行動喚起まで導くことが可能です。
SNSとの組み合わせで効果的なのは、以下の4つです。
・ブログ
・オフラインイベント
・広告運用
・ブックマーケティング |
各施策との組み合わせによる効果について、以下で詳しく解説します。
Webサイト・ブログとの連携
SNSとWebサイト・ブログとの連携でSNSから公式Webサイトやブログに誘導できると、商品の購入や問い合わせなどのコンバージョン(成果)に結びつきやすくなるのがメリットです。
ユーザーにとって、SNSは気軽にチェックできる点がメリットですが、一度の投稿で提供できる情報量はそう多くありません。
一方、情報が流れていくSNSとは違い、Webサイトやブログは必要な情報が整理されていて見つけやすい特徴があります。
SNSで興味を持ったユーザーを公式Webサイトやブログに誘導できれば、より自社の商品やサービスの詳細情報を紹介できます。
たとえば、新商品発売の告知はSNSで行い、機能の詳細や開発秘話などはブログ記事で公開するのも効果的な方法です。
「続きはプロフィールURLから!」のようにSNSの投稿からの導線を敷いておくと、興味を持ってくれたユーザーを確実にWebサイトに呼び込めます。
オフラインイベント・店舗との連携
以下のような施策により、SNSと実店舗やイベントを連動させることで来店促進やブランド体験の共有が可能です。
・SNSでイベント情報を事前告知する
・ストーリーズやライブ配信で現場の臨場感を伝える
・イベント参加者にハッシュタグ投稿を促す
・SNS経由での限定クーポンや特典を用意する |
SNSを使ってあらかじめイベントの情報提供やクーポンの配信などを行うと、興味を持ってくれたユーザーの来店を促しやすくなります。
イベントを開催する際、当日参加できない方に向け、InstagramのストーリーズやYouTubeのライブ配信などで発信すれば、現場の臨場感も伝えられるでしょう。
参加者にハッシュタグ付きの投稿を促すことで、イベントの情報拡散も期待できます。
BtoB企業なら会社説明会や展示会、セミナーや講演イベントなどをSNSと結び付けても、同様の相乗効果が期待できます。
ただし、BtoBの場合は成果を即時に得ることよりも、「信頼形成」や「専門性の訴求」が重要です。
オフラインイベントとSNSを掛け合わせてブランドの熱量を可視化することで、営業活動の後押しとなるケースもあります。
広告運用との組み合わせ
SNSはコストを抑えて広告宣伝できるのが大きなメリットですが、広告を使用せずにコンテンツを配信できる無料のオーガニック投稿だけでは、情報が届く範囲に限界があります。
もちろん、ユーザーにとって有益で魅力的なコンテンツは、拡散されてファンが増える可能性もあるでしょう。
ただ、せっかく情報を投稿しても、ターゲット層に届かなければ効果がありません。
広告運用と組み合わせ、より広範囲なターゲット層にアプローチすれば、集客力を高められます。
ブックマーケティングとの連携
ブックマーケティングは、書籍の出版をマーケティングに活用する手法です。
たとえば、ブックマーケティングで出版した書籍をSNSと連携させ、以下のように活用することも可能です。
・出版前からSNSで制作過程や想いを共有
・書籍の一部を図解や動画で発信して拡散
・SNSを活用した書籍プレゼントキャンペーンを実施 |
さらに注目すべきポイントは、書籍のコンテンツそのものはSNSのネタとして流用できる点です。
SNSでは「発信ネタが尽きてしまい、継続できなくなる」という課題を多くの企業が抱えています。
しかし、書籍の中には、すでにプロの編集者とともに構築された高品質な情報が豊富に詰まっています。
書籍の内容をSNS向けにアレンジして発信することで、コンテンツを少しずつ再利用でき、ネタ切れを防ぎながら、継続的な情報発信が可能になります。
▶︎ブックマーケティングについては、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】も合わせて参考にしてください。

SNS×ブックマーケティングの相乗効果とは?

SNSとブックマーケティングを掛け合わせることで、「信頼」と「共感」を育てられるメリットがあります。
編集者も交えてクオリティの高い書籍を出版すれば、読者に信頼性の高い情報を提供することが可能です。
書籍で打ち出した自社の専門性や理念、世界観を「日常の言葉」に落とし込んでSNSで伝えれば、ユーザーの理解や納得も深まりやすくなります。
また、SNSは拡散力があるのもメリットです。
書籍の発売をきっかけにアカウントの認知が広がったり、書籍を読んでくればフォロワーとの対話が生まれたりなど、良質なファン形成にもつながります。
出版を通じて得た「信頼」が、SNSを通じて強化される「接点」や「共感」が重なり、単なる集客以上のブランド価値を作り出せます。
▶︎ブックマーケティング(書籍の作り方)については、関連記事【本を出版するには?現役書籍編集者が本の出し方を分かりやすく解説】も合わせて参考にしてください。

SNS×ブックマーケティングで集客に成功した事例

実際にSNSとブックマーケティングを駆使し、集客に成功した事例を2つ紹介します。
・書籍出版とSNSの連動で問い合わせ・受注が劇的に増加した事例
・発売前からSNSを活用し、話題化に成功した事例 |
それぞれの事例を以下で詳しく解説します。
書籍出版とSNSの連動で問い合わせ・受注が劇的に増加した事例
資金調達支援のスペシャリストとしてのブランディングを目的に、書籍を出版した事例です。
出版する書籍には具体的な数字を入れて読者の興味を引き、ビジネス書の売れ行きが良好な大都市圏の書店を中心に配本する戦略をとりました。
また、この著者は、書籍発売から一定期間が経過した後も、Twitter(現X)で書籍プレゼントキャンペーンの告知を定期的に実施。
その継続的な投稿が注目を集め、キャンペーンの告知と連動する形でAmazonでの販売数が急増しました。
結果として書籍はロングセラーとなり、改訂版が出版されるまでに至りました。
書籍とSNS活用を組み合わせ、出版後は問い合わせが3~4倍アップしています。
発売前からSNSを活用し、話題化に成功した事例
商品の販促はもちろん、長期的なブランディングや顧客のファン化を目的として、「女性の悩み」に焦点を当てた書籍を出版した事例です。
「何一つ諦めることなく、女性に生涯にわたり輝いてほしい」という社長の思いを書籍として形にまとめました。
発売前から著者がSNSで積極的に情報発信を行ったことで注目を集め、予約が殺到し、発売前に重版が決定。
また、既存顧客を対象にした書籍プレゼント企画では、想定の8倍もの応募が集まる反響がありました。
出版が実績となり、新規顧客の獲得はもちろん、講演やメディア出演の機会も獲得しています。
SNS運用に関するよくある質問
最後にSNS運用について、よくある3つの質問に回答します。
SNSは毎日投稿しなければならない?
投稿は毎日する必要はありませんが、継続的に発信することが重要です。
定期的に投稿することで露出が増加し、自社がフォロワーにとってタイムライン上でよく見かける存在になりやすいでしょう。
しかし、内容が薄かったり質が悪かったりする投稿を重ねていても、ユーザーにとって価値のない情報になってしまうかもしれません。
コンテンツがパターン化して、飽きられる可能性もあります。
SNSでの発信は週2~3回など、無理なく続けられる頻度を設定してください。
「休まず続ける」ことが信頼やアルゴリズムの評価につながります。
どのようなコンテンツを投稿すればよい?
SNSで発信するコンテンツは、ユーザーが「見たい」「知りたい」と思う内容であることが重要です。
具体的には、以下のようなコンテンツがあります。
・商品の紹介
・サービスの活用事例
・Q&A
・舞台裏
・ユーザー参加型コンテンツ
・トレンド情報 |
実際に投稿する際は、競合他社にはない自社ならではの視点や世界観を反映させ、「らしさ」が伝わるようにしましょう。
また、単発で終わらせず、ストーリー性やシリーズ性を持たせて継続的に発信するのがおすすめです。
続きを待ち望むファンが増える可能性があり、つながりも深められます。
外注の運用パートナーは入れるべき?
SNS運用を外注化するかどうかは、企業の状況や目的によって異なります。
外注するメリットとしては、運用に必要な人材をスピーディに確保できることや、専門的なノウハウを持った運用パートナーを活用できることが挙げられます。
一つの考え方として、「人手が足りない」「アカウントを育てるのにそこまで長い期間をかけられない」という課題がある場合、外注を検討することがおすすめです。
ここまで述べたように、SNS運用をきちんとやると担当者にも組織にも意外に手間がかかります。
社員一人が常駐のような状態で対応している会社も多いです。
そうなると、人件費的にSNS運用会社に頼んだほうが安くつく場合も考えられます。
また、外注先は当然ノウハウを持っているため、プロの運用によって最短経路でアカウントを育ててくれるのは大きなポイントでしょう。
特に投稿コンテンツの企画は、一般企業のリソースではなかなか難しい場合も多いです。
ゼロの状態から探り探りでSNS運用をスタートすると、継続できても成果が出るのは数年後といったケースが少なくありません。
その時間を短縮して成果を確実にする選択肢として、外注を活用するのはおすすめです。
【まとめ】SNSとブックマーケティングを掛け合わせて、集客効果を高めよう!
ビジネスコミュニケーションや企業のブランディングでは、今やSNSの運用は欠かせません。
しかし、SNSにはさまざまな種類があり、特徴も異なります。
そのため、自社に合うSNSを選び、そのうえで運用体制を整えることが重要です。
また、SNSはほかの集客施策と組み合わせることで、より効果を発揮します。
特に信頼性や専門性を打ち出せるブックマーケティングと、拡散力のあるSNSは相乗効果が期待できます。
フォーウェイは、230社以上の実績を誇るブックマーケティングに加え、SNS運用をはじめとするマーケティング支援を行っています。
戦略立案から実行まで一貫してサポートが可能です。
SNS運用やブックマーケティングをご検討の際は、ぜひフォーウェイまでご相談ください。


経営者が本を出版しようと考える背景には、「自社の社会的信頼を高めたい」「企業理念を社会に伝えたい」といった目的があります。
そこで重要になるのは、「売れる本をつくる」ことではなく、本という媒体を通じて、いかにビジネス成果を得るかという視点です。
企業出版は、企業理念や自社の強みをわかりやすく社会に伝えて、売上や採用、ブランディングなどの企業活動につなげる手法として注目されています。
この記事では、企業の経営者や事業責任者に向けて、売れる本の共通点や企業出版で成果を出すための具体的なステップについて詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
経営者が狙うべき「売れる本」とは?
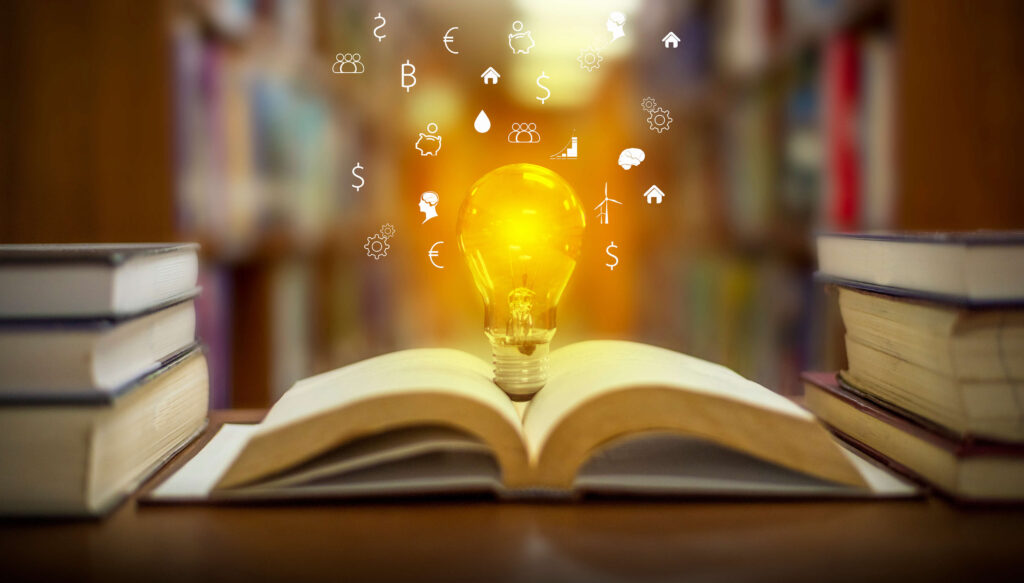
経営者が本を出版する際には、本の売上だけを基準にするのではなく、企業にどのような価値をもたらす本なのかを考えることが重要です。
ここでは、経営者が狙うべき「売れる本」の考え方について、次の2つの観点から整理します。
- 商業出版における「売れる本」と企業出版における「売れる本」の違い
- 重要なのは「ビジネスにおける成果」
それぞれの視点で押さえるべきポイントについて解説します。
◉-1、商業出版における「売れる本」と企業出版における「売れる本」の違い
商業出版は、本の市場性や話題性を重視し、どれだけ売れるかが目的になります。
出版社が読者ターゲットや内容を主導して設定するため、広く一般の読者に向けた企画となるのが特徴です。
一方、企業出版の目的は、自社の理念や強みを社会へ的確に伝えることにあります。
著者は経営者である場合が多く、読者として想定されるのは、顧客・取引先・業界関係者・就職希望者など、企業に関わる幅広いステークホルダーです。
そのため、経営者が目指すべき「売れる本」とは、販売部数よりも、企業の価値観を届け、信頼を築き、最終的にビジネス成果へつなげる一冊であるといえます。
◉-2、重要なのは「ビジネスにおける成果」
企業出版は、事業戦略を推進するための有効な手段です。
出版によって、以下のようにさまざまなメリットを得られます。
- 顧客からの信頼向上
- 新規リードの創出
- 既存顧客との関係強化
- 採用活動の質向上
また、書籍化することで理念やビジョンが明確に言語化され、社内外で共有しやすくなる点もメリットです。
企業としての方向性がよりはっきりし、顧客・社員・取引先との間に共通理解が生まれます。
こうした観点から、経営者にとって企業出版は単なる施策にとどまらず、ブランド価値を高めるための重要な投資だといえるでしょう。
書籍という媒体を通じて企業の姿勢や思想が伝わり、結果としてビジネス成果へとつながりやすくなります。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

企業出版で売れる本に共通する3つの要素

企業出版で売れる本には、読者に必要な情報がまとめられていて、企業の魅力や価値が明確に伝わるという共通点があります。
これは、読者ターゲットを適切に設定し、企業として伝えるべき内容が整理されていることによって生まれるものです。
ここでは、経営者が本を出版する際に押さえておきたい3つの重要なポイントを紹介します。
- 読者ターゲットを明確に設定している
- 独自の価値やストーリーが一貫している
- 出版後の活用設計(販促・PR・営業連携)がある
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、読者ターゲットを明確に設定している
成功する企業出版では、「誰に何を伝えるか」が明確に設定されています。
読者ターゲットを、たとえば顧客や業界の同業者、未来の社員などに設定して具体的に描き、その人が抱える課題や疑問に応える内容を設計することがポイントです。
漠然と「多くの人に読んでほしい」という発想では、結果として誰にも響かない本になってしまう可能性があります。
明確な読者像を描くことが、「売れる本」をつくる前提条件となります。
◉-2、独自の価値やストーリーが一貫している
企業や経営者がこれまでに経験してきた出来事、理念、成功や失敗のエピソードなど、他社にはないストーリーは読者の信頼と共感を生む重要な要素です。
読者は企業の背景や考え方に触れることで、「この会社に依頼したい」「この経営者と働きたい」と感じるようになります。
ストーリーが一貫しているほど、企業の姿勢や価値観が伝わりやすくなるのです。
理念から事業へのつながり、課題への向き合い方、解決に至るまでの道筋を丁寧に描くことで、読後に強い印象として残ります。
◉-3、出版後の活用設計(販促・PR・営業連携)がある
企業出版では、本をつくるだけで終わらせず、発行後にどのように活用するかを事前に設計しておくことが成果につながります。
たとえば、以下のように具体的な活用シーンを想定しておくことで、企業出版の効果が継続しやすくなります。
- 営業資料としての活用
- 展示会やセミナーでの配布
- 採用イベントでの紹介
本を出した後にどのように行動するかを決めておく企業ほど、売上や認知度の向上に結びつくのです。
本が売れることがビジネスにもたらすメリット

企業出版によって得られる成果は、単なる知名度向上にとどまらず、信頼性の向上、営業活動の効率化、採用力の強化など、多岐にわたります。
書籍という形で理念や強みを伝えることで、企業活動全体にプラスの効果を生み出せる点が特徴です。
ここでは、企業出版が企業にもたらす主なメリットを紹介します。
- 企業出版で信頼性と話題性を獲得できる
- 営業ツール・採用ツールとしても活用できる
- 競合との差別化ポイントになる
- 長期的なブランド資産になる
それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。
◉-1、企業出版で信頼性と話題性を獲得できる
書籍は、数ある情報発信手段の中でも特に社会的信頼性が高い媒体です。
企業の専門性や独自性を体系的に伝えられるため、ブランド価値を高める効果が期待できます。
また、第三者である出版社を通じて発行されることで、情報に客観性が付与される点も魅力です。
企業自らが発信する広告とは異なり、中立的な立場から認められた内容として受け止められやすくなります。
さらに、出版自体がニュース性を持つため、SNSや業界紙、地域メディアなどで取り上げられる可能性も広がります。
「書籍を出版した企業」という事実そのものが話題になり、自然と情報拡散が進むのも企業出版ならではのメリットです。
結果として、書籍を出している企業には「専門性が高く、信頼できる」という印象が生まれ、ブランドイメージ向上につながります。
◉-2、営業ツール・採用ツールとしても活用できる
営業活動の際に、事前に書籍を渡しておくことで企業の考え方や強みを理解してもらいやすくなり、信頼関係を築くきっかけになります。
また、採用活動では書籍が企業理念や文化を伝える役割を果たし、価値観に共感する人材の応募が増えることもメリットです。
書籍を読んだうえで応募する人は企業への理解が深く、採用のミスマッチを減らす効果も期待できます。
さらに、既存顧客からの紹介シーンで「この会社は書籍も出している専門家です」と自然に推薦してもらえることで、紹介の説得力が高まり、新たなビジネスチャンスにもつながります。
◉-3、競合との差別化ポイントになる
同業他社が書籍を出していない場合、書籍そのものが大きな差別化要素になります。
本を出版している企業は「その分野の第一人者」として認識されやすく、専門性や実績を示す有力な根拠として評価されます。
その結果、顧客からの信頼が高まり、価格だけで比較される状況から脱却しやすくなるのです。
さらに、書籍でノウハウなどを公開することで、競合には真似できない専門性のアピールが可能になります。
◉-4、長期的なブランド資産になる
書籍は一度発行すると長期にわたり残り続ける媒体で、広告やSNS投稿のように短期間で流れてしまうものとは異なります。
企業が大切にしてきた理念や経験を体系立てて発信することで、時間をかけて信頼や認知が蓄積されていきます。
こうした蓄積は企業ブランドを強固にする土台となり、中長期的な成長を支える力になるでしょう。
また、書籍が継続的に読まれることで、企業の価値観や姿勢が時代を超えて受け継がれていく点もメリットです。

企業出版で売れる本を作るための具体的なステップ

企業出版で成果を出すためには、書籍制作の流れを段階ごとに整理し、計画的に進めることが大切です。
ここでは、経営者が押さえておくべき具体的なステップを解説します。
- ステップ1:出版の目的とゴールを明確にする
- ステップ2:読者ターゲットと伝えるメッセージを設定する
- ステップ3:読者の共感を生む構成を設計する
- ステップ4:制作・編集の方向性を整理する
- ステップ5:出版後の活用戦略を設計する
- ステップ6:成果を検証し、次の施策につなげる
順を追って詳しく見ていきましょう。
◉-1、ステップ1:出版の目的とゴールを明確にする
最初に取り組むべきことは、「なぜ出版するのか」「何を達成したいのか」という目的を明確にすることです。
ブランディング、リード獲得、採用強化、信頼形成など、目的やゴールによって本の内容やトーン、構成は大きく変わります。
目的があいまいなままでは出版の効果が発揮されにくくなるため注意が必要です。
目的とゴールを数値や行動レベルで定義しておくと、制作途中の判断もぶれにくくなります。
◉-2、ステップ2:読者ターゲットと伝えるメッセージを設定する
次に取り組むのは、「誰に」「何を伝えるのか」を明確にすることです。
読者ターゲットには、企業経営者や顧客、取引先、就職希望者、業界関係者などを具体的に設定し、読者が抱える課題や期待に寄り添ったメッセージを設計します。
また、事業戦略上でどの層を集客したいのかを踏まえてターゲットを定めると、メッセージに一貫性と実効性が生まれるようになるので、この段階で事業全体との方向性が合っているかも確認しておくとよいでしょう。
読者を明確にすることで伝える内容に一貫性が生まれ、強調すべきポイントも判断しやすくなるため、メッセージがより的確に届くようになります。
◉-3、ステップ3:読者の共感を生む構成を設計する
章構成を考える際は、読者が理解しやすく、自然に読み進められる流れを意識します。
一般的には「事実」「考察」「価値」「未来」といった順序で構成すると、読者が納得しやすく、内容への共感も得られやすくなります。
読者の感情や思考の動きを踏まえて構成を組み立てることがポイントです。
構成を丁寧に設計することで、読者にきちんと企業の価値や意図が伝わるようになります。
◉-4、ステップ4:制作・編集の方向性を整理する
制作を進める前に、「誰が書くのか」「どのようなトーンで書くのか」を決めておくことが必要です。
ビジネス書の多くは専門のブックライターが執筆しており、著者自身がすべての文章を書くケースの方が実は少数派です。
ブックライターは経営者への丁寧なインタビューを通して、頭の中にあるノウハウや経験を言語化する専門職。
著者の想いや言葉を文章として再構成する役割であり、いわゆるゴーストライターとは異なります。
経営者本人が書く場合も、ライターに依頼する場合も、専門用語を多用しすぎず、企業の信念や想いが自然に伝わる文章になるよう意識しましょう。
伝えたい内容や表現の方向性をあらかじめ定めておくことで、書籍全体に一貫性が生まれます。
▶︎ゴーストライターについては、関連記事【ゴーストライターとはどういう意味?ビジネス書の執筆で活用すべき理由や高品質な原稿を書いてもらうためのポイントなども解説!】もあわせて参考にしてください。
◉-5、ステップ5:出版後の活用戦略を設計する
書籍をどの場面で活用するかを事前に具体的に決めておくことが重要です。
営業や採用、PR、講演、セミナーなど、社内外の接点に合わせて配布や紹介の方法を設計します。
また、出版前後には、プロモーションや広報、SNSでの発信などの動線を整えると、出版効果を高められます。
◉-6、ステップ6:成果を検証し、次の施策につなげる
出版後は、問い合わせ数、応募者の質、売上の変化など、具体的な指標を用いて成果を検証します。
結果を数値として把握することで、次の発信やブランディング施策、次回の出版企画に活かすことができます。
出版を単発のイベントとして終わらせず、経営のPDCAに組み込むことが効果を高めるポイントです。
検証と改善を繰り返すことで、ブランド戦略の一貫性と成果が高まります。
売れる本を生み出し、ビジネスで成果を上げた事例
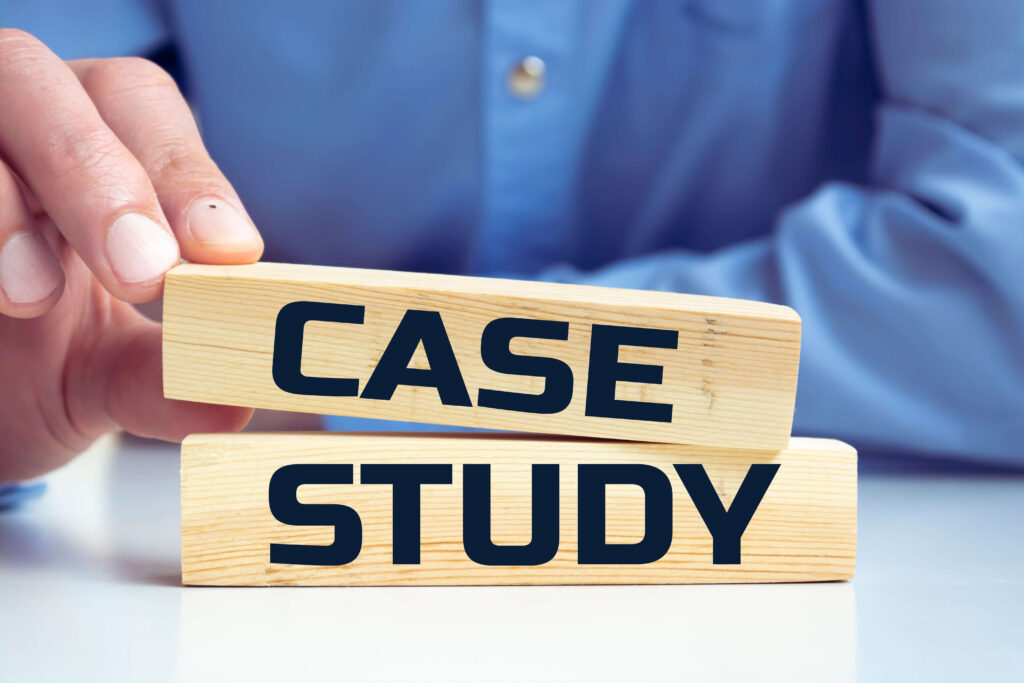
ここでは、売れる本によって実際にビジネスで成果を上げた事例を紹介します。
- 出版後2週間で重版出来!書籍をきっかけに問い合わせが増えた事例
- 権威性と信頼性を獲得し、10億円の売上に貢献した事例
- 出版後に新規顧客開拓とメディア露出が拡大した事例
3つの事例を詳しく見ていきましょう。
◉-1、出版後2週間で重版出来!書籍をきっかけに問い合わせが増えた事例
法人向け保険を専門とする保険代理店の経営者は、新規事業のコンサルティングの顧客獲得を目的に書籍を出版しました。
書籍では、保険業界で一般的な「成果報酬制」に対して、「月額報酬制」が業績向上に有効だという持論を展開して注目を集めました。
出版後2週間で重版出来、出版記念のセミナーの参加者60名のうち5件が成約につながるなどの成果につながりました。
【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店
◉-2、権威性と信頼性を獲得し、10億円の売上に貢献した事例
ある不動産会社の経営者は、高所得で納税額の高い医師に向けて、不動産投資が節税対策に有効であることを訴求する書籍を出版しました。
「医師」という明確なターゲットに向けて設計したことで、読者の多くが高い確度の見込み客となりました。
実際に、発売直後に寄せられた最初の10件の問い合わせは、全て成約につながりました。
自らお金を払って本を手に取る読者は、すでに課題を認識している「ホットリード」であることがわかります。
出版費用はすぐに回収でき、、6ヶ月で10億円もの売上向上に貢献しました。
◉-3、出版後に新規顧客開拓とメディア露出が拡大した事例
ある建設業専門の経営コンサルタントは、サービス内容の進化に合わせて自社のリブランディングのために書籍を出版しました。
新規顧客層へのアプローチを意識して「赤字続きの会社がみるみる蘇る」というタイトルを付けました。
発売から1ヶ月で重版出来、17媒体のWebニュースに掲載されてメディア露出が拡大。
その結果、コンサルティングや育成支援などで13件の新規顧客を獲得しました。
【まとめ】企業出版で売れる本をつくり、ビジネスで成果につなげよう
この記事では、売れる本の共通点や売れる本のビジネスメリット、企業出版の具体的なステップ、成功事例などについて詳しく解説しました。
企業出版は、単なるブランディング施策ではなく、企業の信頼性や売上の向上、採用への好影響などの成果を出すための経営課題の取り組みです。
フォーウェイでは、企業のブランディング力向上とマーケティング支援を目的としたブックマーケティング(企業出版)サービスを提供しています。
これまで数多くの企業様の書籍制作を手がけ、理念の可視化・専門性の発信・ブランド価値の向上につながる成果を生み出してきました。
もし「自社の想いを形にして世の中へ届けたい」「ブランド価値をさらに高めたい」とお考えでしたら、ぜひ一度フォーウェイへご相談ください。
企画構成から出版まで、経験豊富な担当者が丁寧にサポートいたします。


企業イメージは、顧客・取引先・株主・従業員・地域社会といったステークホルダーが企業に対して抱く総合的な印象を指します。
良い企業イメージを築くことは、信頼の獲得や採用・人材定着、売上向上につながります。
しかし、企業イメージは短期間で形成されるものではありません。
そのため、日々の情報発信や行動、理念の一貫性が重要となります。
この記事では、企業の経営者・事業責任者に向けて、企業イメージを向上させるための考え方や具体的な実践手法について解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
企業イメージとは

企業イメージは企業活動全体から形づくられるため、その仕組みを理解しておくことが、戦略的な取り組みを進めるうえで重要です。
ここでは、企業イメージの基本的な事項として、次の2つのポイントに分けて解説します。
以下で、それぞれ詳しく見ていきます。
◉-1、企業イメージの定義
企業イメージとは、顧客や従業員、取引先、社会などが企業に対して抱く印象や信頼、期待を総合したものを指します。
見た目や広告だけでなく、理念や日々の行動、社会的姿勢など、あらゆる接点によって形成されることが特徴です。
◉-2、企業イメージの構成要素
企業イメージは、次の5つの要素から成り立っています。
- ビジュアル
- コミュニケーション
- 商品やサービスの品質
- 従業員の対応
- 社会的責任
具体的には、ビジュアルとしてロゴやコーポレートカラー、Webサイトのデザインなどが挙げられます。
営業担当者の営業トーク、問い合わせ対応といった社外とのコミュニケーションも企業のイメージを左右する要素です。
企業の本質ともいえる商品やサービスの品質が、企業の評判に関わるのはいうまでもありません。
接客態度や電話応対などの従業員の対応も、企業イメージに影響します。
現代では、コンプライアンスの遵守や地域貢献、環境問題への取り組みのような、企業が社会的に責任を果たしているかどうかもイメージに影響をおよぼす要素です。
これらの5つの要素の一貫性が保たれることで、信頼性の高い企業イメージが確立されます。
企業イメージを向上させるメリット

企業イメージを向上させることは、信頼の獲得や収益性の向上、人材の採用や定着など、多方面に良い影響をもたらします。
主なメリットとして、次の4つが挙げられます。
- 顧客や取引先からの信頼が高まり、売上・利益が向上する
- 競合との価格競争に巻き込まれにくくなる
- 従業員満足度が向上し、優秀な人材の採用・定着につながる
- 社会的評価が高まり、持続的な企業成長を支える
以下で、具体的にどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
◉-1、顧客や取引先からの信頼が高まり、売上・利益が向上する
顧客や取引先は「信頼できる企業」から商品やサービスを選ぶ傾向が強く、企業イメージの良し悪しが売上や契約率に直結します。
たとえば、フォローに力を入れたことで、問い合わせだけで終わっていた見込み顧客が「御社に任せたい」と言ってくれるようになるなど、信頼を得ることが売上にもつながります。
信頼が高まるほど「選ばれる理由」が明確になり、競合他社との差別化が進むのです。
企業の信頼が高まることで、購入や継続的な取引につながり、結果として売上と利益の向上が期待できます。
◉-2、競合との価格競争に巻き込まれにくくなる
ブランド価値が確立された企業は、価格だけでなく、信頼や品質、社会的評価といった付加価値で選ばれるようになります。
こうした付加価値が確立されると、「価格以外の評価軸」で選ばれる機会が増え、価格競争への依存度が下がるのです。
そのため、競合他社との値下げ競争に陥りにくくなり、適正価格での取引や長期的な利益の確保が期待できます。
◉-3、従業員満足度が向上し、優秀な人材の採用・定着につながる
企業イメージが向上すると、社外だけでなく社内にも良い影響が生まれます。
社会から信頼される企業で働く誇りが従業員のモチベーションを高め、離職率の低下が期待できます。
また、理念に共感できる優秀な人材の応募が増えて、採用コストの削減や採用活動の効率化にもつながります。
◉-4、社会的評価が高まり、持続的な企業成長を支える
CSR活動や環境への取り組み、地域貢献などを通じて企業が社会に示す姿勢も、企業イメージの向上につながる要素です。
社会との信頼関係が深まることで、ステークホルダーからの期待や支持も安定し、企業の長期的な経営基盤が強化されます。
こうした取り組みの積み重ねによって、企業の社会的信頼の土台が形成され、持続可能な企業成長を支える基盤となります。
企業イメージを向上させる具体的な手法

企業イメージを高めるためには、外部への発信だけでなく、内部の意識改革や物語を通じた価値の伝達など、多角的な取り組みが必要です。
ここでは、代表的な4つの手法について解説します。
- アウターブランディング
- インナーブランディング
- ストーリーブランディング
- 採用ブランディング
以下で、それぞれについて詳しく解説します。
◉-1、アウターブランディング
アウターブランディングとは、社外に向けてブランド価値を発信し、理解や信頼を獲得するための取り組みです。
顧客や取引先、株主、従業員、地域社会などのステークホルダーに「どのような価値を提供できる企業なのか」を分かりやすく伝えることが重要になります。
アウターブランディングの主な手法は、以下の表の通りです。
| 主な手法 | 詳細 |
| コーポレートサイトの改善 | ・企業理念や強みが明確に伝わる構成
・デザインにすることで、企業理解が深まる
・第一印象を左右するため、信頼性を判断する重要な要素となる |
| SNS・オウンドメディアの活用 | ・企業の価値観や取り組みを継続的に発信でき、情報の透明性が高まる
・顧客との接点を増やし、関係構築を促進する |
| PR・広報活動の強化 | ・企業の取り組みや価値を社会に広く伝えることができる
・メディア掲載を通じて専門性の訴求や認知度の向上につながる |
| 顧客コミュニケーションの最適化 | ・丁寧な対応によって顧客満足度や信頼感の向上が期待できる
・充実したサポートは顧客の信頼を高め、長期的な関係構築に寄与する |
◉-2、インナーブランディング
インナーブランディングとは、従業員が企業理念やブランドの価値を理解し、自ら体現できる状態をつくる取り組みです。
従業員一人ひとりがブランドの担い手となることで、企業イメージは自然と外部にも良い形で広がっていきます。
インナーブランディングの主な手法は、以下の表の通りです。
| 主な手法 | 詳細 |
| 企業理念・ビジョンの浸透施策 | ・研修やワークショップを通じて、従業員が自社の価値や理念を理解できる
・理念が共有されることで、組織全体としての方向性が明確になり、行動の統一につながる |
| 社内コミュニケーションの活性化 | ・部署間の連携を円滑にし、組織全体の一体感を強化する
・意見交換が行われる環境を整えることで、ブランド価値の体現が進む |
| 表彰制度・評価制度の整備 | ・成果や行動を正しく評価する仕組みが、従業員の意欲向上に貢献する
・制度の透明性が組織文化の形成を支える |
| 研修・育成制度の拡充 | ・企業の価値観を理解した上で能力を伸ばす環境を整えられる
・理念に基づく行動が促進され、企業イメージの向上につながる |
▶︎インナーブランディングのやり方については、関連記事【インナーブランディングとは?施策や進め方、成功事例を紹介】もあわせて参考にしてください。
◉-3、ストーリーブランディング
ストーリーブランディングとは、企業や商品の背景にある物語を通じて価値を伝える手法です。
人はストーリーに共感しやすく、物語を通じて企業の価値や想いがより深く伝わる点が特徴です。
ストーリーブランディングの主な手法を、以下の表にまとめました。
| 主な手法 | 詳細 |
| 創業ストーリーの発信 | ・創業時の想いや背景を伝えることで、企業の存在意義や価値観が明確になる
・企業の原点を共有することで、顧客を含むステークホルダーとの共感が生まれ、信頼の構築につながる |
| 商品開発の裏側を紹介 | ・品質へのこだわりや開発部門の姿勢を具体的に示せる
・製品やサービスへの安心感や納得感を高め、ブランドに対する信頼と好感を高める |
| 従業員のストーリーを紹介 | ・従業員の働き方や成長の過程を紹介することで、企業文化や価値観が具体的に伝わる
・従業員のリアルな声が企業への信頼を高め、採用活動や社員の定着にも良い影響を与える |
| 顧客事例(ビフォーアフター)を活用 | ・商品やサービスが生み出す変化を具体的に示せる
・提供価値が明確になることで信頼性が高まり、新規顧客の獲得につながる |
| 書籍の出版 | ・企業の理念・専門性・実績を1冊の本に体系的にまとめて発信できる
・社会的信頼性の高いメディアとして受け取られ、潜在顧客の関心獲得にも効果がある
・書籍は長期的に残るため、企業イメージ向上に継続的に貢献する |
▶︎ストーリーブランディングのやり方については、関連記事【ストーリーブランディングとは?企業の物語を伝えてファンを作る方法】もあわせて参考にしてください。
◉-4、採用ブランディング
採用ブランディングとは、求職者から「働きたい」と思われる企業になるためのブランド構築を指します。
給与や福利厚生だけでなく、働く意義や企業文化を明確に伝えることで、優秀な人材の獲得につながります。
採用ブランディングの主な手法は、以下の表の通りです。
| 主な手法 | 詳細 |
| 採用サイト・採用SNSの強化 | ・専用サイトやSNSを通じて、企業文化や働く環境、従業員の姿を具体的に伝えられる
・求職者の企業理解が深まり、応募意欲の向上につながる |
| 企業カルチャーの可視化 | ・働く環境や価値観を明確に示すことで、ミスマッチ防止や採用精度の向上につながる
・求職者が企業との相性を判断しやすくなり、納得感の高い採用につながる |
| 求人票・募集要項のブラッシュアップ | ・仕事内容や求める人物像を明確化することで、適切な人材からの応募が増える
・業務内容や役割を正しく伝えられるため、入社後の定着率向上にもつながる |
| 採用広報・イベントの活用 | ・企業の魅力や働く価値を直接伝える機会をつくれる
・求職者との接点が広がり、応募意欲の向上に結びつく |
▶︎採用ブランディングのやり方については、関連記事【採用ブランディングの重要性とは? 目的やメリット、具体的な方法まで解説】もあわせて参考にしてください。
企業イメージを向上させるには信頼を継続的に築くことが重要!

企業イメージを向上させるために重要なのは、派手な広告や一時的な施策ではなく、顧客や社会からの信頼を継続的に積み上げていくことです。
優れた商品やサービスを提供していても、信頼が伴わなければ企業として正当に評価されず、長期的なファンを獲得することも難しくなります。
一方で、信頼を基盤としている企業は継続的な支持を得やすく、競合との差別化にもつながります。
企業出版(ブックマーケティング)なら持続的に企業イメージを高められる!

企業出版(ブックマーケティング)は、社外への発信、社内への浸透、社会との関係構築のすべてに効果的な手法です。
他の施策では得られない「信頼性」「統合性」「持続性」を兼ね備えており、企業イメージを長期的に高めることができます。
企業出版(ブックマーケティング)には、主に次の4つの特徴があります。
- 信頼性の高い情報をまとめて発信できる
- 企業理念を社内に浸透させることができる
- 社会的信頼や共感を醸成することができる
- 長期的なブランド資産化につながる
以下では、これらの特徴について詳しく解説します。
◉-1、信頼性の高い情報をまとめて発信できる
書籍という信頼性の高いメディアを通じて、企業の理念や実績、専門性を体系的に伝えることができます。
その内容は取引先や顧客、メディアからの評価向上につながり、企業の社会的信用を強化します。
書籍はWeb上の情報や断片的な内容だけを掲載している広告などに比べ、情報が豊富に盛り込まれているのが特徴です。
そのため、「この企業は何者か」を一冊で深く理解してもらえるツールとして機能します。
◉-2、企業理念を社内に浸透させることができる
書籍は、経営者の思想や企業の価値観を明確に示し、従業員が自社の方向性を理解しやすくします。
理念への共感や誇りが育まれ、組織としての行動の一貫性が高まります。
特に新入社員や中途入社した社員に対し、入社初期に企業文化をつかむための「共通テキスト」として活用できるのもメリットです。
◉-3、社会的信頼や共感を醸成することができる
書籍を通じて社会課題への向き合い方や企業としての責任を示すことで、社会からの信頼や共感を高めることが可能です。
また、CSRやSDGsの取り組みと組み合わせることで、倫理性や持続可能性を備えた企業イメージの構築にもつながります。
このような企業姿勢を書籍という形で言語化しておくことは、投資家や取引先などのステークホルダーが、自社のスタンスや長期的なビジョンを理解・評価するうえで重要な判断材料となります。
◉-4、長期的なブランド資産化につながる
書籍は時間が経っても残り続ける媒体であり、長期にわたり価値を発揮します。
営業・採用・広報など幅広い場面で活用でき、企業にとって継続的に使えるブランド資産となります。
また、書籍は増刷や改訂版の発行によって、内容をアップデートすることが可能です。
そのため、社会状況が変化したとしても、時代に合わせて価値を育て続けられます。
特に専門性の高いサービスを提供している企業や、創業のきっかけ・商品開発に独自のストーリーがある企業にとって、書籍は強力なブランド資産となります。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

出版によって企業イメージが向上した事例

ここでは、企業出版によって企業イメージを高めた事例を3つ紹介します。
- 出版を機に業界から一目置かれる存在へとイメージが向上した事例
- 出版をきっかけにブランド価値が向上し、顧客とのつながりを深めた事例
- 出版を通じて「海外進出支援の専門家」としてポジションを築いた事例
以下で、それぞれの事例について詳しく紹介します。
◉-1、出版を機に業界から一目置かれる存在へとイメージが向上した事例
法人保険を専門とする保険代理店は、自社の強みや経営ノウハウを体系的にまとめた書籍を出版しました。
書籍では、保険業界の「成果報酬型」を「一律報酬型」の給与体系に切り替えることで業績が向上した実例を紹介し、自社の独自性と専門性を明確に示しました。
出版後、業界内での認知度が一気に高まり、新規事業のコンサルティング契約を複数獲得することに成功。
さらに、大手保険会社からの講演依頼や共同マーケティングの打診が増えるなど、業界内で一目置かれる存在へと評価が高まりました。
【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店
◉-2、出版をきっかけにブランド価値が向上し、顧客とのつながりを深めた事例
女性向けサプリメントを販売するメーカーは、既存顧客との関係強化と新規顧客の獲得を目的に書籍を出版しました。
出版の狙いは、自社の信頼性を高めてファン化を促し、LTV(ライフタイムバリュー)の向上につなげること。
書籍では、代表者自身の経験や健康に対する考え方をまとめ、読者にとって役立つ実用的な内容に仕上げました。
その結果、読者が企業や商品の背景をより深く理解するようになり、購入者のリピート率が向上。
さらに、「書籍無料プレゼント」企画を実施したところ、想定の6倍の応募が寄せられ、多くの新規顧客との接点を創出することにも成功しました。
【事例コラム】”書籍無料プレゼント”に想定の6倍の応募、リピート率アップにインパクト!サプリメントメーカーの出版プロジェクト
◉-3、出版を通じて「海外進出支援の専門家」としてポジションを築いた事例
国際税務を専門とする公認会計士は、事務所開所後、海外勤務で得た実体験をもとに、海外進出企業が陥りやすい失敗をケーススタディ形式で解説した書籍を出版しました。
書籍では、失敗の背景や原因を具体的なストーリーとして描きながら、各ケースごとに企業が直面するリスクや課題、そして効果的な解決策を提示。
これから海外進出を目指す企業が避けるべき落とし穴を、実務目線で分かりやすくまとめています。
その結果、地元紙や全国紙、ラジオ番組からの注目が集まり、メディア露出が大きく増加しました。
書籍を通じて専門性が広く認知され、「海外進出支援の専門家」としてのポジションを確立。
ブランディングとビジネス拡大の両面で大きな成果を上げました。
【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士
【まとめ】企業イメージ戦略の中心に企業出版を位置づけよう!
この記事では、企業イメージを向上させるための基本的な考え方と具体的手法について解説しました。
企業イメージを向上させるためには、信頼を継続的に積み重ねる取り組みが欠かせません。
その中でも企業出版は、社外発信・社内浸透・社会的信頼を同時に高められる強力な手法です。
自社のブランド戦略の中心に企業出版を取り入れることで、持続的な企業イメージの向上が期待できます。
フォーウェイでは、企業出版(ブックマーケティング)サービスを提供しており、多くの企業がブランディング施策として活用しています。
ブックマーケティングサービスでは、企業理念や技術面での専門性、自社の成り立ちなどを含めた総合的な情報発信ができ、信頼性や権威性も高めることが可能です。
企業イメージの向上をお考えの方は、フォーウェイまでご相談ください。


BtoBマーケティングは、単なる集客活動ではなく、企業の成長戦略そのものです。
現代の市場では、顧客の購買行動が変化し、これまでのような営業活動に頼るだけでは新規顧客の獲得が難しくなってきています。
こうした市場変化に対応するためにも、経営層がマーケティングを理解し、意思決定に活かすことが必要です。
この記事では、BtoBマーケティングの基本から有効な手法、成功事例までを詳しく紹介します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
BtoBマーケティングとは?

BtoBマーケティングのBtoBとは「Business to Business」の略で、企業間の取引におけるマーケティング活動を指します。
BtoBマーケティングを効果的に経営に取り入れるためには、まずは基本となる考え方を理解しておくことが重要です。
BtoBマーケティングの最終目的は単なる売上拡大にとどまらず、見込み顧客との間で継続的な信頼関係を築き、長期的な取引が続く状態を作ることです。
そのため、単発の案件を追いかけるのではなく、顧客のLTV(顧客生涯価値)を高めることが重要で、結果として安定した収益につながります。
◉-1、BtoCマーケティングとの違い
BtoCマーケティングの対象が個人消費者であるのに対して、BtoBマーケティングの対象は企業です。
意思決定者が複数存在し、取引金額も大きくなります。
また、BtoCのように感情的な訴求が購買につながるケースは比較的少なく、合理的判断やリスク回避意識が重視されます。
そのため、顧客理解と長期的な関係構築が欠かせず、お互いに信頼関係を深めながら進めていく必要があります。
BtoBマーケティングを実施する5つのステップ

ここでは、BtoBマーケティングで成果を上げるための5つのステップを解説します。
- ステップ1:見込み顧客を獲得する(リードジェネレーション)
- ステップ2:見込み顧客を育てる(リードナーチャリング)
- ステップ3:見込み顧客を選別する(リードクオリフィケーション)
- ステップ4:商談・受注につなげる
- ステップ5:顧客との関係を維持・発展させる
以下で、順に見ていきましょう。
◉-1、ステップ1:見込み顧客を獲得する(リードジェネレーション)
最初のステップは、潜在顧客との接点を増やすことです。
以下のようなさまざまなチャネルを活用して、自社に関心を持つ企業を見つけ出します。
- 展示会
- セミナー
- SNSでの発信
- インターネット広告
- SEO対策
自社の商品やサービスに興味を持つ可能性が高い企業をターゲットとして、適切な施策を選択して実施することが重要です。
◉-2、ステップ2:見込み顧客を育てる(リードナーチャリング)
次のステップでは、獲得した見込み顧客との間に信頼関係を構築します。
メール配信やウェビナー、ニュースレター、ホワイトペーパーなどを通じて、相手の課題を理解しながら適切な情報提供を行い、関係性を深めていきます。
単なる情報提供ではなく、顧客の関心や課題に合わせた価値を届けることがポイントです。
◉-3、ステップ3:見込み顧客を選別する(リードクオリフィケーション)
次は、育成した見込み顧客の中から、営業がアプローチすべき企業を絞り込むステップです。
スコアリング(行動履歴や関心度の数値化)やデータ分析を通じて、関心度の高い顧客を抽出し「今アプローチすべき顧客」を見極めます。
優先度の高い見込み顧客を明確にすることで、営業チームのリソースの有効活用や効率的な商談創出が可能となります。
◉-4、ステップ4:商談・受注につなげる
見込み顧客を選別した後は、営業チームと連携し、選定した見込み顧客に対して商談を提案します。
マーケティングで得られた顧客情報(興味・課題・行動履歴)を営業チームに共有することで、スムーズな提案につながります。
商談率や受注率を定期的に分析し、マーケティングと営業を一体化した仕組みを構築することが、成果を最大化するポイントです。
◉-5、ステップ5:顧客との関係を維持・発展させる
BtoBマーケティングでは、受注後のフォローアップも重要です。
契約後も継続的にサポートを行い、定期的に有益な情報を提供することで、顧客の満足度を高め、リピート受注やアップセルにつなげられます。
また、満足度の高い顧客からは新たな紹介が生まれることも多く、追加の商談機会を創出するきっかけになります。
顧客を一度きりの取引相手として捉えるのではなく、長期的なパートナー(顧客資産)として育てていく姿勢が大切です。
BtoBマーケティングの手法一覧

BtoCマーケティングでは、「いかに多くの人へアプローチし、今すぐ購入したいと思わせるか」が重視されます。
一方で、BtoBマーケティングにおいては、企業が顧客から「信頼できる」と感じてもらうことが重要です。
基本的な手法自体はどちらも共通していますが、目指す目的が異なる点を理解して活用することが大切です。
以下では、代表的な2つの手法を紹介します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、オンライン施策
BtoBマーケティングのオンライン施策では、デジタル環境を活用して見込み顧客との接点を作り、興味関心を高めていきます。
次の表で代表的な手法とそれぞれの特徴を紹介します。
| 手法 | 詳細 |
| SEO対策 | ・「検索エンジン最適化」ともいい、自社Webサイトを検索エンジンで上位表示させ、自然流入を増やす手法・中長期的なリード獲得に有効 |
| オウンドメディア運用 | ・自社Webサイトでブログや事例、ノウハウを発信して専門性を訴求し、リード獲得につなげる手法・BtoBでは信頼構築の効果が大きい |
| ウェビナー(オンラインセミナー) | ・ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を組み合わせた造語で、インターネット上で開催されるセミナー・関心度の高い見込み顧客と接点をつくり、関係性を深められる手法・会場設営や移動が不要なためコストを抑えられる |
| SNSマーケティング | ・X(旧Twitter)、LinkedIn、InstagramなどのSNSを活用した手法・双方向のコミュニケーションが可能なため、信頼関係を構築することができる |
| メールマーケティング/MAツール活用 | ・メールを使って継続的に情報発信をして、見込み顧客の育成を行い、最終的に商品購入やサービス利用などの目標達成に導く手法・MAツールを活用すれば、顧客一人ひとりの興味や行動に合わせたメール配信やスコアリングが可能 |
| デジタル広告 | ・WebサイトやSNS・動画配信サービスなどのオンライン上のチャネルで、テキスト・画像・動画形式で配信される広告手法・ユーザーの年齢、性別、興味関心などの属性や行動履歴に基づくターゲティングが可能・短期間で成果が出やすい |
| ホワイトペーパー・資料ダウンロード | ・企業が見込み顧客や潜在顧客に向けて、課題解決や情報提供を目的として作成する資料・BtoBマーケティングでは、信頼関係の構築に有効 |
| オンライン展示会・バーチャルイベント | ・インターネット上のバーチャル空間で開催される展示会やイベント・参加者の属性や行動履歴などを取得して、後の営業やマーケティングに活用できる・時間や場所の制約がないため、幅広い層にアプローチできる |
◉-2、オフライン施策
BtoBマーケティングのオフライン施策では、対面のコミュニケーションを通じて深い信頼関係を築いていきます。
オンラインでは伝わりにくい価値を直接伝えられる点が強みです。
代表的な手法と特徴は次表の通りです。
| 手法 | 詳細 |
| 展示会・業界イベントへの出展 | ・展示会に出展することで、直接商品やサービスのアピールができる・見込み顧客との直接対話を通じて課題やニーズを把握しやすい・商談や他社との協業のきっかけとなりやすい |
| セミナー・講演会の開催 | ・セミナーを主催することで、専門性を訴求しながら参加者との関係性を深めることができる・関心度の高い見込み顧客が参加するため、次のステップにつながりやすい |
| 営業訪問・商談活動 | ・営業担当者が直接顧客を訪問し、対面で課題ヒアリングや提案を行う手法・顧客の反応を見ながら対応できるため、信頼関係を築きやすい |
| カタログ・パンフレット配布 | ・商品やサービスの特徴・導入事例をまとめた印刷物を顧客に直接届ける手法・ポストインや展示会・説明会での配布、DMでの送付などの方法がある |
| 異業種交流会への参加 | ・異なる業種・業界の人々が集まるため、情報交換や人脈づくりなどにつながる・潜在顧客との接点創出の可能性もある |
| 顧客向けイベント | ・既存顧客向けのイベントを開催して、信頼関係を強化する手法・顧客満足度の向上やアップセルにつながる |
| 企業出版(書籍出版) | ・企業が書籍を通じて、企業の理念や価値観、実績などを体系的に伝えることができる手法・広告と異なり、長期にわたってブランディング、専門性の訴求、リード獲得に効果を発揮する |
BtoBマーケティングで成功するには「信用してもらう」仕掛け作りが何より重要!

BtoCマーケティングとBtoBマーケティングでは、用いる手法そのものに大きな差はありません。
しかし、その手法をどの目的で活用するのかという点が異なることを理解しておく必要があります。
BtoCマーケティングが「購入してもらうための仕掛け」を組み込むのに対し、BtoBマーケティングでは「信用してもらうための仕掛け」を組み込むことが基本です。
たとえば、第一接触からいきなり売り込むのではなく、次のような手法を間に挟むことによって、信頼度を高めることが可能です。
| 手法 | 活用ポイント |
| ホワイトペーパーを活用する | Webサイトからすぐにお問い合わせページに誘導するのではなく、「サービスの導入事例」や「サービスの詳細説明」のホワイトペーパーをダウンロードしてもらう |
| 無料相談会を実施する | セミナーや講演会の場で、「興味のある方は問い合わせを!」といきなり売り込みをするのではなく、無料の個別相談会を設けて、対話によって信用を獲得していく |
| 書籍を活用する | 異業種交流会やイベントなどで、名刺交換後すぐに自社の商品やサービスの紹介をするのではなく、出版した書籍を渡して「この企業は書籍を出版するほど信頼性の高い企業である」ことを暗に伝える |
BtoBマーケティングなら企業出版が信頼獲得に効果的!
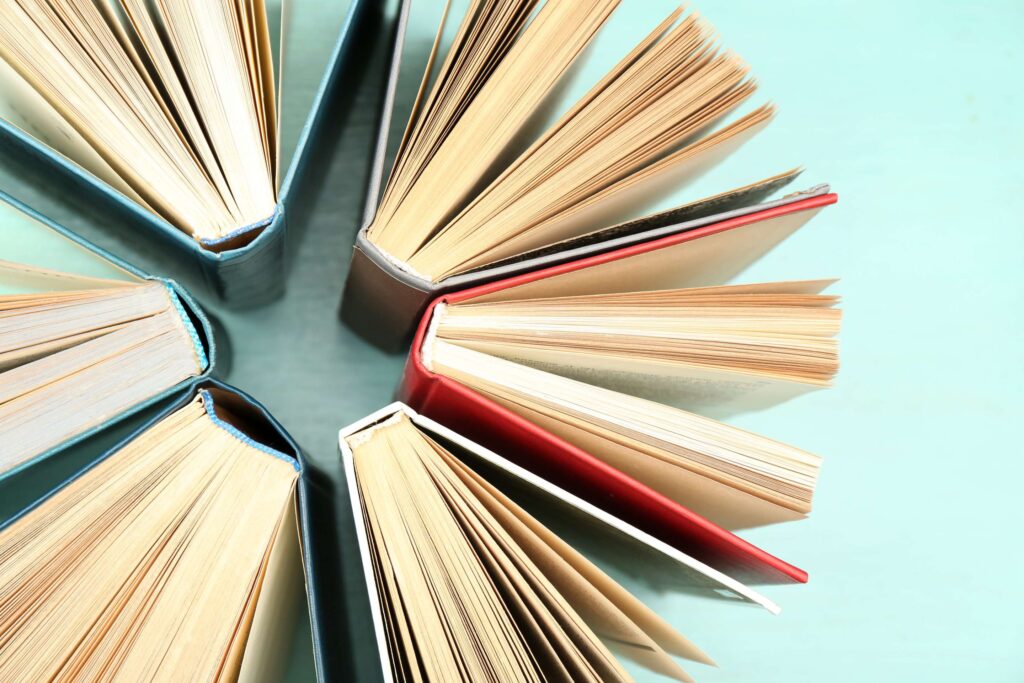
企業出版は、BtoBマーケティングにおいて信頼獲得とブランド構築を同時に実現できる有効な手段の一つです。
さらに、書籍をきっかけにリード獲得やメディア露出、採用強化など、さまざまな効果が期待できます。
ここでは、企業出版のメリットを4つ紹介します。
- 専門性・信頼性を訴求できる
- 経営層・意思決定者へのリーチが可能
- 他社との差別化・ブランディング効果が高い
- 他のマーケティング施策との相乗効果が高い
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、専門性・信頼性を訴求できる
企業出版(ブックマーケティング)は、書籍という社会的信頼性の高いメディアを通じて、自社の知見やノウハウを体系的に発信できます。
広告やWeb記事では伝えきれない企業の哲学や実績、事例をストーリーとして提示することで、読者の深い理解を促し、長期的に専門性と信頼性を築くことが可能です。
さらに、書籍化された情報は「長く保存される資産」として機能するため、時間が経っても専門家としての評価が積み重なり、結果としてブランド価値の向上にもつながります。
◉-2、経営層・意思決定者へのリーチが可能
BtoB取引では、最終的な購入判断を下すのは経営層や管理職といった限られた層です。
企業出版による情報発信は、書店やAmazon、ビジネス誌などを介して、こうした意思決定層に自然に届きやすく、質の高いリード獲得につながりやすい点が特徴です。
また、書籍出版後の講演やセミナー、メディア取材などを通じた経営者ネットワークの拡大にもつながります。
◉-3、他社との差別化・ブランディング効果が高い
BtoB取引では、商品やサービスの機能だけでは差別化が難しいケースも少なくありません。
企業出版を通じて「なぜこの事業を行っているのか」「社会へどのような価値を提供しているのか」を発信することで、理念や姿勢によって選ばれる企業へと進化することができます。
また、競合他社がWeb広告や展示会を中心に情報発信を行う中で、書籍を活用することで「知見の深い企業」「思想を持つ企業」という印象を強く与えられ、ブランディングの差別化にもつながります。
◉-4、他のマーケティング施策との相乗効果が高い
企業出版は単体の施策としても効果的ですが、他のマーケティング施策と組み合わせることで効果を最大化できます。
たとえば、次のようにオンライン施策・オフライン施策双方のハブとして機能させる展開が可能です。
- WebサイトやSNSで書籍内容を再編集して発信
- 展示会やセミナーで配布し、名刺交換から商談化
- プレスリリースやメディア露出を促進
書籍というまとまった情報資産があることで、コンテンツの再活用がしやすくなり、施策全体の効率化にもつながります。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

企業出版によるBtoBマーケティングの成功事例

ここでは、企業出版を活用してBtoBマーケティングに成功した4つの事例を紹介します。
- 企業出版でコンサル依頼!同業から一目置かれるようになった事例
- 事業の立ち上げとともに企業出版!メディアからも注目が集まった事例
- BtoB企業に特化した書籍を出版!商圏拡大に成功した事例
- 企業出版で自社製品の有用性を訴求して販路拡大を実現した事例
それぞれの事例について詳しく見ていきましょう。
◉-1、企業出版でコンサル依頼!同業から一目置かれるようになった事例
法人専門の保険代理店は、新規事業のコンサルティングで顧客獲得に苦戦し、自社の強みや経営ノウハウを体系的にまとめた書籍を出版しました。
出版後、業界内での認知度が一気に高まり、複数のコンサル契約を獲得することに成功。
大手保険会社からの講演依頼や共同マーケティングの声がかかるなど、同業から一目置かれるような存在になりました。
【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店
◉-2、事業の立ち上げとともに企業出版!メディアからも注目が集まった事例
公認会計士事務所を開所した1年目に「海外進出の第一人者」というポジションを確立するために書籍を出版。
出版後は、地元紙や全国紙、ラジオ番組などからの注目が集まり、メディア露出が増加したといいます。
書籍を通じて専門性が広く認知され、事務所のブランディングとビジネス拡大に成功しました。
【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士
◉-3、BtoB企業に特化した書籍を出版!商圏拡大に成功した事例
BtoB企業向けにデジタルマーケティングサービスを展開している企業が、ノウハウをまとめた書籍を出版したところ、大手企業の課長級以上からの問い合わせがあり、10件弱の受注につながりました。
遠方の企業からの問い合わせにはテレビ会議で柔軟に対応することで、新たな地域への商圏拡大も実現。
書籍出版を通じて信頼度が高まり、月間100万円のWeb広告費が数万円にまで減少したという成果も上がっています。
◉-4、企業出版で自社製品の有用性を訴求して販路拡大を実現した事例
ある食品製造会社は、自社製品の有用性を訴求する書籍を出版しました。
書籍の中でサラダ油の過剰摂取に警鐘を鳴らし、解決策として自社製品のこめ油の有用性を訴求。
結果として、書籍が反響を呼び、米油ブームの火付け役となり、全国から新規取引の問い合わせ獲得につながりました。
【まとめ】BtoBマーケティングは企業成長の鍵!企業出版も検討してみよう
BtoBマーケティングは営業支援ではなく、経営戦略の中核となる取り組みです。
市場の変化や顧客行動の変化に対応し、データとマーケティングを基盤とした経営判断を行うことが、安定した企業成長の鍵となります。
企業が成長するためにも、まずは自社の現状を可視化して、マーケティング体制の整備から始めてみましょう。
フォーウェイでは、企業出版(ブックマーケティング)サービスを行っています。
企業出版を通じて、伝わりにくかった自社の専門性や理念を信頼として発信し、長期的な顧客関係やブランド価値の向上につなげています。
これまで多くの経営者・専門家の方々の出版を支援し、リード獲得や採用強化、メディア露出など幅広い成果を生み出してきました。
企業出版を活用したBtoBマーケティングのことなら、フォーウェイまでご相談下さい。


マーケティング活動において、顧客との最初の接点をどのように築くかは重要な課題です。
しかし、Web広告やSNSでの情報発信だけでは、企業の専門性や信頼性を十分に伝えることが難しいという実情があります。
そこで近年注目を集めているのが「ホワイトペーパー」です。
自社の専門的な知見やデータをもとに作成されたホワイトペーパーは、単なる営業資料ではなく、顧客との信頼関係を構築し、購買意欲を高めるマーケティングツールとなります。
この記事では、企業経営者や事業責任者に向けて、マーケティングにおけるホワイトペーパーの役割と、信頼を生む情報発信の仕組みについて詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
ホワイトペーパーとは

ホワイトペーパーとは、企業が自社の専門知識やノウハウ、実績などを体系的にまとめて、顧客に提供する資料のことです。
本来は政府や公的機関が政策や調査内容をまとめた「白書」を意味していましたが、現在ではBtoBマーケティングにおいて見込み顧客の課題解決を支援し、自社への信頼を高めるためのコンテンツとして広く活用されています。
マーケティングにおけるホワイトペーパーの役割

BtoBマーケティングにおいて、ホワイトペーパーは顧客との関係構築を支える多面的な役割を担います。
主な役割として、次の6つが挙げられます。
- リード獲得のための「入り口」としての役割
- リードナーチャリングのための「教育コンテンツ」としての役割
- 商談・提案時の「専門性を証明する資料」としての役割
- 自社やブランドの「ポジションを高めるツール」としての役割
- 客観的データ・実績による「権威性構築」の役割
- ブランディング活動の「起点」としての役割
以下で、それぞれの役割について詳しく見ていきましょう。
◉-1、リード獲得のための「入り口」としての役割
ホワイトペーパーは、顧客(リード)が自社を知る最初の接点となる重要なコンテンツです。
Web広告やSEO記事、SNSなどの集客施策から「無料ダウンロード資料」へ誘導することで、まだ商談には至っていない潜在顧客のデータを獲得できます。
特に「業界課題の整理」や「導入事例集」といったテーマは、顧客が自社の現状や課題を整理したい段階で関心を持つことが多く、営業リストの質と量の両面を向上させる入り口の施策として効果的です。
◉-2、リードナーチャリングのための「教育コンテンツ」としての役割
一般的に、一度資料をダウンロードしただけですぐに商談や契約につながることはありません。
そこで重要になるのが、顧客の購買意欲を段階的に育てる「リードナーチャリング」です。
ホワイトペーパーをメール配信やMAツール(HubSpot、Marketoなど)と連携させることで、「初回資料 → 関連テーマ → 事例紹介 → 導入検討」といった流れを作ることができます。
顧客の理解を深めながら、自社への信頼と興味を高めていく「教育コンテンツ」として機能します。
◉-3、商談・提案時の「専門性を証明する資料」としての役割
商談や提案の場では、担当者からの説明だけでなく、信頼の裏付けとなる根拠資料の提示が効果的です。
ホワイトペーパーには、自社の専門知識や技術、導入実績などが体系的にまとめられているため、商談・提案時に提示することで、「この分野に強い企業である」ことを伝えられます。
また、数値データや事例、比較分析などを含めると、単なる説明資料ではなく「専門性を証明する客観的なエビデンス」となります。
◉-4、自社やブランドの「ポジションを高めるツール」としての役割
現代では、企業からの情報発信の質と量がブランド価値に影響を与える傾向が強くなっています。
ホワイトペーパーは、「この分野ならこの会社」と顧客から想起してもらうための重要なツールです。
特定のテーマについて継続的に発信することで、市場における自社の立ち位置を高め、専門性や信頼性をより明確にすることができます。
こうした取り組みは、長期的なブランディング基盤の形成にもつながります。
▶︎企業ブランディングのやり方については、関連記事【企業ブランディングとは?効果や具体的な8つの手法を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
◉-5、客観的データ・実績による「権威性構築」の役割
ホワイトペーパーは、主観的な宣伝ではなく、客観的なデータや第三者の調査結果をもとに作成されます。
そのため、読者は内容を「信頼できる情報」として受け止めやすく、自社への信頼も自然と高まります。
たとえば、業界調査やアンケート結果をまとめたホワイトペーパーは、専門誌やメディアにも引用されることも多く、企業の発信力と権威性の両方を強化することが可能です。
◉-6、ブランディング活動の「起点」としての役割
ホワイトペーパーは、短期的なリード獲得にとどまらず、自社の理念やビジョン、専門知識を社会に定着させるための「起点」となります。
テーマ設定やトーン、デザインを通じて「自社らしさ」を表現することで、一貫したブランドメッセージを発信でき、長期的なファン層の形成やリピート購入にもつながります。
成果を上げるホワイトペーパーの作成ステップ

一般的に、ホワイトペーパーの作成は次のステップで進めるのが効果的です。
- ステップ1:目的とターゲットを明確にする
- ステップ2:顧客課題からテーマを設計する
- ステップ3:構成と内容を設計する
- ステップ4:信頼性を高める表現とデザインを整える
- ステップ5:配信と運用を開始する
- ステップ6:定期的な更新と分析をする
以下で、それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、ステップ1:目的とターゲットを明確にする
まず最初に、ホワイトペーパーを「なぜ作るのか」という目的を明確にします。
「新規リードを獲得したい」「既存リードを育成したい」「商談を後押ししたい」などの目的によって、資料の構成やトーンは変わります。
さらに、「経営層向けなのか」「実務担当者向けなのか」といったターゲットの設定も重要なポイントです。
目的とターゲットをしっかり定めることで、読者のニーズに沿った内容を提供でき、メッセージの方向性がぶれることなく一貫性のある資料を作成できます。
◉-2、ステップ2:顧客課題からテーマを設計する
ホワイトペーパーは、企業が伝えたいことではなく、顧客が抱える課題を解決する視点から設計することが重要です。
読者が本当に求めているのは、商品の説明ではなく、「自分の課題をどう解消できるのか」という具体的なヒントや答えです。
また、自社の特長を伝える前に、まず業界全体の課題や市場動向を提示し、そのうえで解決策として自社のノウハウを示す構成にすると、説得力のある資料になります。
◉-3、ステップ3:構成と内容を設計する
テーマが決まったら、読者が理解しやすく、自然に次の行動へと進めるような構成を設計します。
まず導入部分では、現状の課題や問題点を提示し、その後にそれらを解決するための方向性や考え方を示します。
次に、自社の実績・事例・データなどを活用して内容の信頼性を高め、最後に問い合わせや資料請求などのアクションにつながる導線を設けましょう。
全体の情報の流れに一貫性を持たせることで、読者に「この企業なら信頼できそうだ」と感じてもらいやすくなります。
◉-4、ステップ4:信頼性を高める表現とデザインを整える
ホワイトペーパーで重視されるのは、情報の信頼性です。
主観的な表現を避け、第三者のデータや公的な統計、実際の顧客事例など、客観的な根拠を示すことが信頼につながります。
文章は簡潔で分かりやすくまとめ、図表やグラフを使って視覚的にも理解しやすくするのが理想です。
デザイン面では、過剰な装飾よりも読みやすさを優先し、余白や色使いで情報の整理を意識することで、より「ビジネス資料らしい信頼感」が伝わります。
◉-5、ステップ5:配信と運用を開始する
完成したホワイトペーパーは、ターゲットに応じた適切な手段で配信することが重要です。
自社サイトでのダウンロード配布に加えて、SNS広告や検索連動広告からの誘導、メルマガによる配信など、複数のチャネルを連携させると効果を高められます。
◉-6、ステップ6:定期的な更新と分析をする
ホワイトペーパーは、一度作成して終わりではありません。
ダウンロード数や閲覧時間、商談化率などのデータを継続的に分析し、改善を重ねることで成果を維持・向上させることが重要です。
さらに、市場環境や顧客ニーズの変化に合わせて内容をアップデートすることで、常に「いま求められている情報」を発信し続けられます。
ホワイトペーパーと組み合わせたいマーケティング施策

ホワイトペーパーの効果をさらに高めるためには、他のマーケティング施策と連携させて活用することが重要です。
特に、次の5つの施策と組み合わせることで高い効果が期待できます。
- 広告運用
- メールマーケティング
- ウェビナー・イベント
- オウンドメディア(SEO)
- 企業出版
以下で、それぞれの施策について詳しく見ていきましょう。
◉-1、広告運用
広告運用は、ホワイトペーパーのダウンロードを促進する直接的な手段です。
検索連動広告やディスプレイ広告、SNS広告などを活用することで、関心度の高い見込み顧客層へ効率的にアプローチできます。
たとえば、「無料資料ダウンロード」や「業界別導入事例集」といった訴求は、検討初期段階の顧客に響きやすく、リード獲得の入り口として効果的です。
また、広告運用ではターゲティングの精度が成果を左右します。
業種・職種・興味関心などの条件を細かく設定し、ホワイトペーパーのテーマと関連性の高い層に広告を配信することで、無駄なクリックを抑えつつ、より質の高いリードを確実に獲得できるようになります。
◉-2、メールマーケティング
ホワイトペーパーをダウンロードした顧客との関係を深めるには、メールマーケティングが有効です。
ダウンロード直後のサンクスメールや、関連コンテンツ・セミナー案内などを段階的に配信することで、顧客の理解を促し、商談化率を高められます。
たとえば、「課題解決の具体策を紹介するフォローアップ資料」や「導入企業の成功事例」を順に届けることで、自然な流れで関係性を育てることができます。
◉-3、ウェビナー・イベント
ホワイトペーパーで自社に関心を持った顧客を次のステップへ導く施策として、ウェビナーやイベントの開催は有効です。
リアルタイムで情報を共有し、直接質問し回答を得る機会を提供することで、企業への信頼感を高められます。
たとえば、ホワイトペーパーの内容をもとにした「成功事例セミナー」や「業界トレンド解説ウェビナー」を開催すると、参加者の関心が高まり商談に結びつく可能性があります。
さらに、ウェビナー終了後にアンケートを実施し、回答内容に合わせてフォローアップ資料を送付することで、顧客との関係をより強固にできるでしょう。
◉-4、オウンドメディア(SEO)
ホワイトペーパーとオウンドメディア(公式サイトや自社ブログなど)を組み合わせることで、検索経由のリード獲得を強化できます。
記事の中で読者の課題を整理し、具体的な解決策や関連データを提示したうえで、「詳しくはホワイトペーパーをダウンロード」という導線を設ければ、自然な流れで資料請求へとつなげられます。
▶︎SEOのやり方については、関連記事【SEO対策とは? 効果的な戦略の組み立て方と対策方法】もあわせて参考にしてください。
◉-5、企業出版
ホワイトペーパーの発展形として、企業出版(ブックマーケティング)を取り入れる企業が増えています。
書籍はWeb上の資料よりも深い専門性や独自の見解を伝えられるため、長期的なブランド構築や信頼性の向上に効果的です。
「ホワイトペーパーの拡張版」として、商談支援やブランディングを強力に後押しするマーケティング資産となります。
さらに、書籍をホワイトペーパーの代替としてリード獲得に活用することも可能です。
たとえば、書籍プレゼントの応募時にリード情報を入力してもらう方法が挙げられます。
書籍という「形のある情報発信」は、オンライン施策だけでは得にくい信頼感や権威性を高める点でもメリットがあります。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
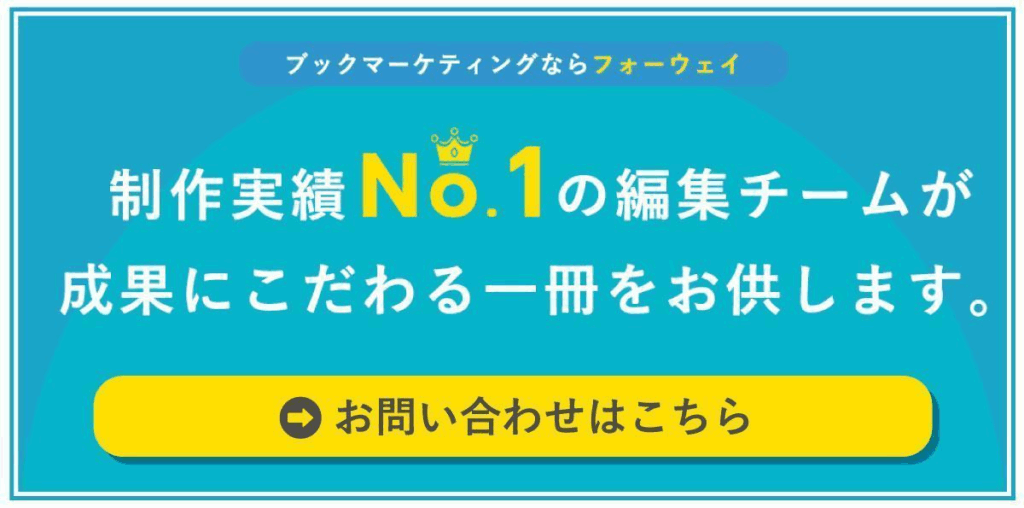
書籍をホワイトペーパーやバックアップツールとしてマーケティングに活用した事例

ここでは、実際に書籍をマーケティングに活用して成果を上げた事例を2つ紹介します。
- 書籍で専門性を伝え、信頼を獲得した事例
- 出版を通じてブランディングを確立した事例
以下で、それぞれどのような活用をしたのかを見ていきましょう。
◉-1、書籍で専門性を伝え、信頼を獲得した事例
ある公認会計士は、独立1年目という立ち上げ期に「海外進出支援」というポジション確立を狙い、書籍をマーケティングツールとして活用しました。
出版後は、新聞やビジネス誌、ラジオなど各メディアからの取材が相次ぎ、想定以上の反響を獲得。
「海外展開支援の第一人者」としての認知が一気に広がり、書籍をきっかけにセミナー講師依頼やメディア出演が増加しました。
また、商談時に書籍を「名刺代わり」に手渡すことで、短時間で専門性を印象づけることに成功。
特に、大手企業や海外進出を検討する経営層との商談で、「この人なら任せられる」という信頼を獲得しやすくなり、商談成立率が大幅に向上しました。
さらに、出版によるブランディング効果で価格交渉も減少し、安定的な高単価案件の受注へとつながりました。
結果として、書籍が単なるPR素材ではなく、商談支援や信頼獲得、リード拡大を同時に実現する強力なマーケティング資産となっています。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉-2、出版を通じてブランディングを確立した事例
クリニックの開業を専門とするコンサルタントは、案件獲得とブランディングを目的に書籍を出版しました。
書籍では、「地方や衛星都市で成功するための開業ノウハウ」をわかりやすく解説しながら、自然に著者への問い合わせへとつながる構成を採用。
出版からわずか3週間で問い合わせが殺到し、1ヶ月後には対応しきれないほどの案件が増加しました。
また、全国各地からの相談が寄せられ、地方・都市圏を問わず商圏が一気に拡大し、出版をきっかけに開業コンサルタントというポジションを確立しました。
特筆すべきは、出版後も書籍コンテンツを自社Webサイトに再利用したことです。
読者が書籍タイトルや著者名で検索した際に、スムーズに問い合わせページへ誘導できる導線を構築しました。
書籍の販促効果を一過性で終わらせず、継続的なリード獲得とブランド浸透につなげています。
【まとめ】ホワイトペーパー×企業出版は長期的に使えるマーケティング資産
この記事では、マーケティングにおけるホワイトペーパーの役割や効果的な施策、書籍と組み合わせた成功事例について詳しく解説しました。
ホワイトペーパーは、専門性と信頼性を伝えることで短期的なリード獲得だけでなく、中長期的な顧客関係の構築にも貢献するマーケティング資産です。
その効果をさらに高める手段として注目されているのが「企業出版」との組み合わせです。
企業出版を通じて自社の理念や専門性を社会に広く発信することで、ホワイトペーパーと相互に補完し合う長期的なマーケティング基盤を築くことができます。
株式会社フォーウェイでは、この企業出版(ブックマーケティング)の仕組みを活用し、企業のマーケティング活動を中長期的に支援しています。
ホワイトペーパーと書籍を戦略的に組み合わせることで、単発の施策にとどまらない「長く使えるマーケティング資産」を構築していきましょう。


デジタルマーケティングの重要性が高まる中、「どのツールを導入すべきか」「自社に本当に必要なのはどれか」で悩む経営者は少なくありません。
広告やSNS、SEO、CRMなど、マーケティング領域には多種多様なツールが存在し、それぞれ異なる役割があります。
デジタル活用が企業成長を左右する今こそ、ツールを現場任せにせず、経営戦略の一部として見直すことが重要です。
この記事では、経営者が知っておくべき主要なマーケティングツールについて解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
主要なマーケティングツール

マーケティングの成果を高めるためには、目的に応じたツールを適切に組み合わせることが重要です。
ここでは、主要なマーケティングツールを、次の13の目的別に分類して紹介します。
- 広告運用ツール
- SNS運用・分析ツール
- SEOツール
- LP・フォーム作成ツール
- Web最適化・接客ツール
- CMS(コンテンツ管理システム)
- メールマーケティングツール
- 顧客データ活用系ツール
- 資料・提案支援ツール
- ウェビナー・イベント運営ツール
- アンケート・NPS計測ツール
- データ分析・改善ツール
- 販売促進ツール
以下で、それぞれのツールの特徴や機能を紹介します。
◉-1、広告運用ツール
オンライン広告の運用において、ターゲット設定や効果測定の精度を高めるためには、代表的な広告プラットフォームを理解しておく必要があります。
主なツールは、次の通りです。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| Google広告 | ・世界最大の広告配信プラットフォーム・検索・ディスプレイ・YouTubeなど多様な形式に対応し、高精度なターゲティングができる |
| Meta広告マネージャー | ・FacebookやInstagramの広告を一元管理できるプラットフォーム・ユーザー属性や興味関心データを活用して配信できる |
| Yahoo!広告 | ・国内ユーザーへの訴求に強い・検索広告とディスプレイ広告を統合管理でき、日本市場向けの最適化に優れている |
◉-2、SNS運用・分析ツール
SNSの投稿管理や分析を自動化するツールを使えば、運用の効率化とデータ活用の両立が可能になります。
主なツールとして、以下が挙げられます。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| Hootsuite | ・X(旧Twitter)、Facebook、Instagramなど複数のSNSを一元管理する・投稿予約や自動配信、コメント管理やブランド名のモニタリングも可能・英語UI中心で、グローバル展開する企業に適している |
| SocialDog | ・X(旧Twitter)運用に特化したツール・フォロワー管理や自動投稿、エンゲージメント分析で運用改善を支援する |
| Buffer | ・X(旧Twitter)やFacebook、Instagramなどに対応している・投稿スケジュール管理とレポート機能が充実 |
◉-3、SEOツール
SEOツールを使うと、自社サイトの検索順位を高めて自然流入を増やすために必要なキーワード分析や被リンク調査、データに基づく改善を行えます。
主なツールは、次の通りです。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| Ahrefs | 被リンク分析や競合調査に強く、SEOに必要なデータを多角的に取得できるツール |
| Google Search Console | 検索パフォーマンスやインデックス状況を確認できる無料ツール |
| Semrush | キーワード分析、競合比較、コンテンツ最適化を包括的に支援する総合型SEOツール |
◉-4、LP・フォーム作成ツール
リード獲得やキャンペーン運用には、魅力的なLP(ランディングページ)やフォームの作成が不可欠です。
専門知識がなくてもデザインから運用まで対応できるツールが増えています。
具体的なツールとして、以下が挙げられます。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| ペライチ | ・ドラッグ&ドロップで簡単にLPを作成できる・豊富なテンプレートでデザイン統一も容易 |
| formrun | ・問い合わせや応募フォームを直感的に作成できる・チームでの回答管理に加え、Slack通知やスプレッドシート連携にも対応 |
| Unbounce | ・コンバージョン率の向上に特化したツール・A/Bテストや動的テキスト挿入など最適化機能を備えている |
◉-5、Web最適化・接客ツール
Web最適化・接客ツールを活用すると、Webサイトを訪れたユーザーに合わせた体験を提供し、離脱率を下げてコンバージョン率を高めることができます。
ユーザー行動を分析し、自動で個別対応を行えるツールが近年注目されています。
主なツールは、次の通りです。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| KARTE | ユーザー行動データに基づき、リアルタイムで最適なメッセージやポップアップを表示できる |
| ChatPlus | Webにチャット機能を簡単に導入し、自動応答から有人対応まで柔軟に設定できる |
| Zendesk Messaging | チャットやSNSを一元管理し、顧客対応を効率化できる |
| Optimizely | ・A/BテストやパーソナライゼーションでWeb体験を継続的に改善できる・デジタル体験全体の最適化を支援するプラットフォームとしても活用可能 |
| Hotjar | ・ヒートマップや録画機能で、ユーザーのサイト上での行動を可視化できる・顧客サポートの効率化にも役立つ |
◉-6、CMS(コンテンツ管理システム)
CMS(コンテンツ管理システム)を導入することで、自社サイトやオウンドメディアの運用を効率化できます。
非エンジニアでもコンテンツ更新やページ制作を容易に行える点が特徴です。
主なツールとして、次の2つを紹介します。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| WordPress | ・世界で最も普及しているCMS・豊富なプラグインで柔軟なカスタマイズが可能で、SEOやデザイン調整にも強い |
| HubSpot CMS Hub | ・HubSpotが提供するCMS・MAやCRMと連携でき、見込み顧客の行動分析からメール配信までを一元管理できる |
◉-7、メールマーケティングツール
メールマーケティングツールを導入すると、メール配信によるリード育成や既存顧客との関係維持を効果的に行えます。
配信リストの管理やパーソナライズされたセグメント別配信、効果測定を自動化することで、人的負担を軽減しながら成果を高めることが可能です。
主なツールは、次の通りです。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| Mailchimp | ・世界的に利用されるメール配信ツール・豊富なテンプレートと自動化シナリオで使いやすい・MA(マーケティングオートメーション)機能も搭載 |
| Twilio SendGrid | ・高い到達率と大量配信に対応している・API連携でトランザクションメールの運用にも適している・開発者向けに設計されており、システム連携に強い |
| Benchmark Email | ・操作がシンプルで導入しやすい・A/Bテストや自動ステップメール機能を備えている |
◉-8、顧客データ活用系ツール
顧客データ活用系ツールを導入することで、顧客情報を整理・分析し、営業やマーケティング活動に活用可能です。
顧客との関係構築やLTV(顧客生涯価値)の向上に直結するツール群として注目されています。
目的や機能によって、次の4種類に分類されます。
- CRM/SFAツール
- MAツール
- カスタマーサクセスツール
- 顧客分析・LTV分析ツール
以下で、それぞれの特徴を解説します。
◉-8-1、CRM/SFAツール
営業活動や顧客管理を効率化するためのツールで、顧客データを一元管理できるのが特徴です。
具体的なツールは、次の通りです。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| Salesforce | ・世界的に利用されているCRMの代表格・営業・マーケティング・サポートを統合管理できる・AI機能「Einstein」により予測分析や案件スコアリングも可能 |
| HubSpot CRM | ・HubSpot提供のCRM・顧客情報とマーケティングデータを連携し、リード育成を自動化する・無料プランもあり、導入ハードルが低い |
| Zoho CRM | ・中小企業でも導入しやすく、コストパフォーマンスに優れたCRM・カスタマイズ性と自動化機能が充実 |
| eセールスマネージャー | ・日本企業向けに設計されたCRM・顧客データや営業活動を一元管理できる |
◉-8-2、MAツール
マーケティング活動を自動化し、見込み顧客の獲得から育成までを効率化するためのツールです。
メール配信やスコアリング、行動分析などを通じて、購買意欲の高い顧客を抽出できます。
主なツールは、次の通りです。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| HubSpot | CRM機能を内蔵し、見込み顧客育成やキャンペーン管理を統合的に行えるツール |
| Adobe Marketo Engage | 高度なリード育成機能と柔軟なカスタマイズ性を備え、大規模BtoBマーケティングに適したツール |
| SATORI | 匿名ユーザーの行動データを活用し、潜在顧客を可視化できる国産ツール |
◉-8-3、カスタマーサクセスツール
既存顧客の満足度向上や継続利用・アップセル促進を支援するツールです。
顧客の利用状況やサポート履歴を分析し、関係維持と離脱防止を支援します。
主なツールは、次の通りです。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| HiCustomer | ・顧客の利用状況や契約リスクをスコア化し、継続率向上に向けた行動を可視化できるツール・アラート通知機能により、離脱兆候の早期発見にも対応 |
| Zendesk | ・問い合わせ対応を統合管理し、サポート体制を強化できる顧客対応ツール・CS部門の顧客サポート基盤として利用されることが多い |
| SuccessHub | ・SaaS向けのカスタマーサクセス支援ツール・ヘルススコアを基に離脱防止策を自動提案する |
◉-8-4、顧客分析・LTV分析ツール
顧客の行動や購買データを分析し、LTV(顧客生涯価値)を高めるための意思決定を支援するツールです。
具体的には、以下のツールが挙げられます。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| Amplitude | ・顧客行動データをリアルタイムで可視化する・利用傾向やセグメント分析に強い |
| Retool | ・ノーコードで分析アプリを構築できる・社内データを統合して柔軟なダッシュボードを作成可能 |
| Klaviyo | ・EC・D2C向けの顧客分析ツール・購買履歴をもとにLTV向上のシナリオを設計できる・ShopifyなどのECプラットフォームと連携可能 |
◉-9、資料・提案支援ツール
営業活動やプレゼンテーションで、情報を的確かつ魅力的に伝えるためのツールです。
チーム間で資料を共有・編集できる仕組みや、提案資料の閲覧データを分析する機能を備えたものも多く、営業プロセス全体の改善と提案精度の向上に役立ちます。
主なツールは、次の通りです。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| DocSend | ・提案資料の閲覧状況をリアルタイムで追跡し、ページごとの閲覧データを分析できる・共有リンクのアクセス権設定やパスワード保護も可能 |
| Miro | ・オンラインホワイトボードツール・会議や資料構成の整理、アイデア出しなど共同作業に最適 |
| Notion | ・情報共有・ドキュメント・プロジェクト管理を一元化する・営業資料やナレッジ蓄積、チーム間のコラボレーションにも有効 |
◉-10、ウェビナー・イベント運営ツール
ウェビナーやオンラインイベントの配信管理から参加者データの収集、アフターフォローまでを包括的にサポートするツールです。
主なツールは、次の通りです。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| Zoom Webinars (Zoom Events) | ・安定した配信と高い参加者対応が特徴・チャットやアンケート機能を備え、双方向イベントに適している |
| EventHub | ・登録・配信・アンケート・名刺交換を一括管理・商談管理や来場者分析機能も備え、オンライン展示会運営にも対応 |
| Cvent | ・グローバル対応のイベント管理プラットフォーム・オンライン・オフライン・ハイブリッドイベントの運営と分析を支援する |
◉-11、アンケート・NPS計測ツール
顧客満足度やロイヤルティを可視化し、改善施策の方向性を明確にできるツールです。
サービス品質の定量評価や、カスタマーサクセスの指標設定に活用できます。
主なツールは次の通りです。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| SurveyMonkey | ・質問形式が豊富な高機能アンケートツール・分析レポートを自動生成できる |
| Googleフォーム | ・無料で使える基本ツール・シンプルな設計で回答をスプレッドシートに連携可能 |
| Mopinion | ・Webやアプリ上で顧客の声を収集し、NPS・CSAT分析に活用できる・リアルタイムでフィードバックを可視化し、改善サイクルを高速化できる |
◉-12、データ分析・改善ツール
マーケティング活動の成果を可視化し、データに基づく意思決定を支えるツールです。
5つのツールを紹介します。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| Google Analytics 4 | ・Webやアプリのアクセス解析ツール・ユーザー行動をイベント単位で把握できる |
| Matomo | ・オープンソース型の解析ツール・自社でデータを管理でき、GDPRなどのプライバシー対応に優れている |
| Tableau | 大規模データをグラフやダッシュボードで可視化し、直感的に分析できる |
| Looker Studio | ・Googleの無料BIツール・複数データを統合し、レポートを自動生成できる |
| Power BI | ・MicrosoftのBIツール・社内システムと連携し、データ活用を支援する |
◉-13、販売促進ツール
販売促進ツールは、商品を紹介するためではなく、顧客に「この企業なら信頼できる」と感じてもらうための証拠づくりの手段です。
広告やWeb施策だけでなく、ストーリーベースのコンテンツ(書籍、ホワイトペーパー、導入事例など)を活用することで、中長期的なブランド形成と顧客育成を両立できます。
特に書籍は、企業や専門家の知見を体系的に伝え、業界内での信頼獲得や商談支援に効果を発揮します。
主なツールは次の通りです。
| 主なツール | 特徴・機能 |
| 書籍 | ・企業や専門家の知見を体系的に伝え、信頼と権威を確立する・営業資料としても有効で、商談時に強い印象を与える・ブランディング強化にも効果的 |
| ホワイトペーパー | ・特定テーマの課題解決やノウハウをまとめた資料で、リード獲得や育成に役立つ |
| 導入事例 | ・顧客の成功事例を紹介し、信頼性と具体的な効果を訴求できる・営業現場での説得力向上に有効 |
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
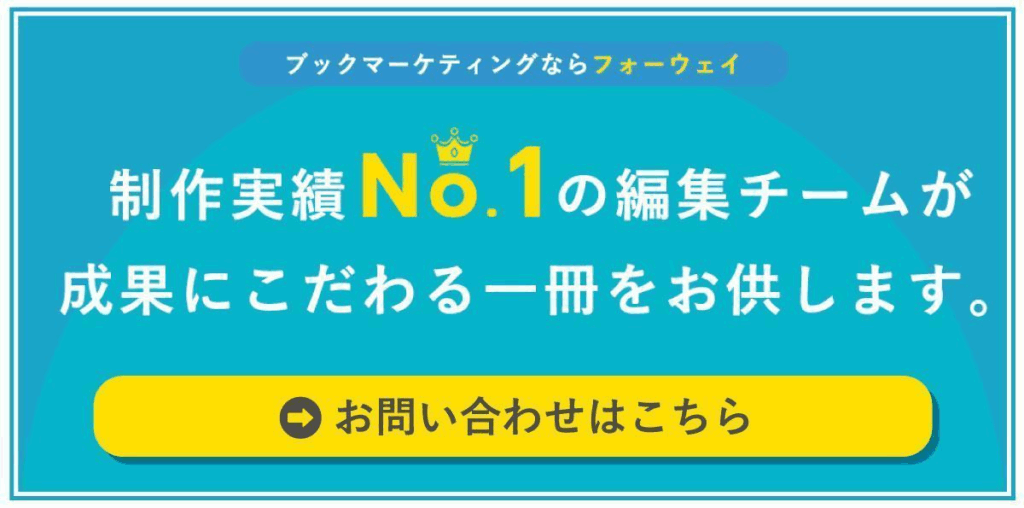
マーケティングツールの導入効果を高めるためのポイント

マーケティングツールは、導入するだけで成果が上がるものではありません。
自社の目的や体制に合った選定と運用設計を行うことで、導入効果を最大化できます。
ここでは、ツール活用の成果を高めるために押さえておきたい3つのポイントを紹介します。
- 目的を明確に設定する
- 既存の業務・ツールとの連携を意識する
- デジタルとアナログを組み合わせて導入効果を高める
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
◉-1、目的を明確に設定する
ツールを導入する際は、何を実現したいのかを明確にすることが重要です。
たとえば、リード獲得や顧客管理の効率化、分析精度の向上など、目的によって選ぶツールや運用方針は異なります。
目的があいまいだと機能を活かしきれず、効果を実感できません。
導入前にKPIやゴールを設定し、成果を定量的に評価できる体制を整えましょう。
◉-2、既存の業務・ツールとの連携を意識する
新しいツールを導入する際は、既存システムや業務フローとの連携を前提に設計することが重要です。
CRMやMAツールなどは、営業管理ツールやメール配信システムとデータを連動させることで、より効果を発揮します。
たとえば、商談履歴をMAツールに連携して自動でメールシナリオを生成したり、顧客のWeb行動データをCRMに統合して営業優先度を可視化するなどの活用が有効です。
ツールを点で導入するのではなく、全体の仕組みとしてどう活かすかを考える視点が求められます。
◉-3、デジタルとアナログを組み合わせて導入効果を高める
マーケティング活動は、デジタルとアナログを効果的に組み合わせることで、より高い成果を生み出せます。
ツール導入時は、両者の役割を明確にし、連携させることがポイントです。
たとえば、MAツールで蓄積した顧客データをもとに特定層にDMや書籍を送付したり、展示会で得た名刺情報をCRMに登録して自動フォローアップメールを送付するなどの活用が考えられます。
また、書籍の中にQRコードや専用LPのURLを掲載すれば、読者がWeb経由で問い合わせや資料請求を行う導線も作れます。
このように、リアルとデジタルを循環させる仕組みを作ることで、マーケティングツールの導入効果を最大化できるのです。
◉【まとめ】ツールを活用してマーケティングを強化しよう
マーケティングツールは、導入目的を明確にし、既存の仕組みや他のツールと連携させることで、効果を発揮します。
また、デジタル施策とアナログ施策を組み合わせることで、オンラインとオフラインの双方から顧客接点を強化できます。
なかでも書籍を活用したマーケティングは、短期的な成果だけでなく、長期的な信頼構築にも有効です。
フォーウェイでは、書籍をマーケティングに活用する「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
マーケティングツールの導入効果をさらに高めるために、書籍出版をご検討ください。