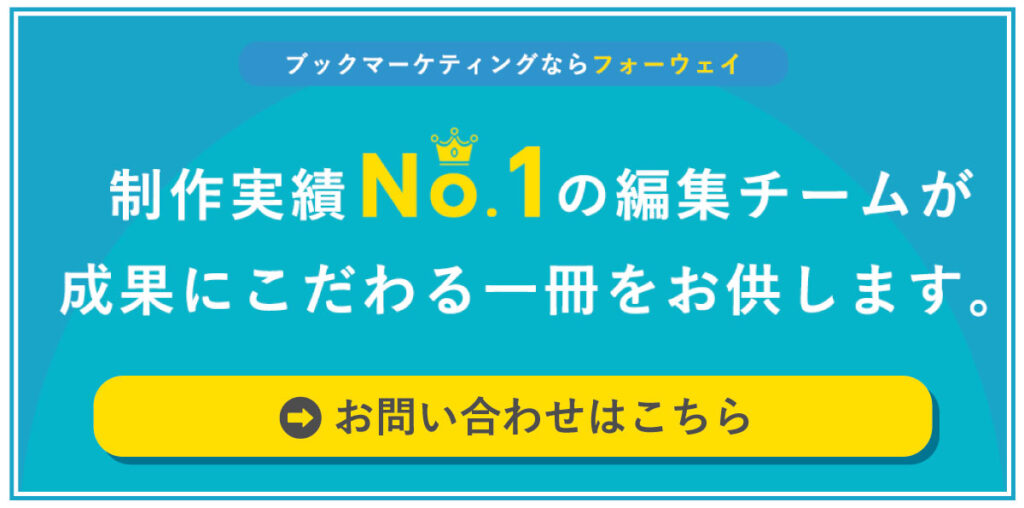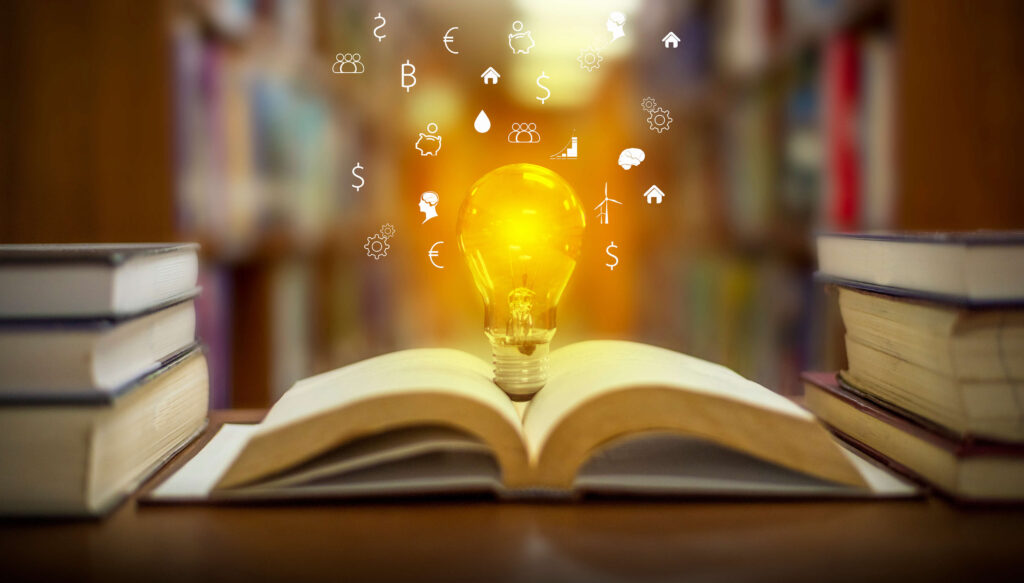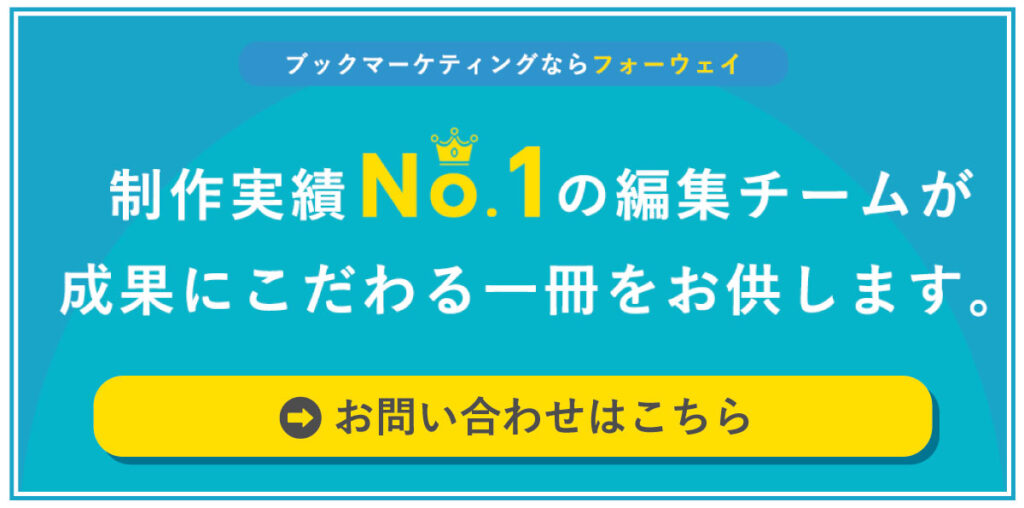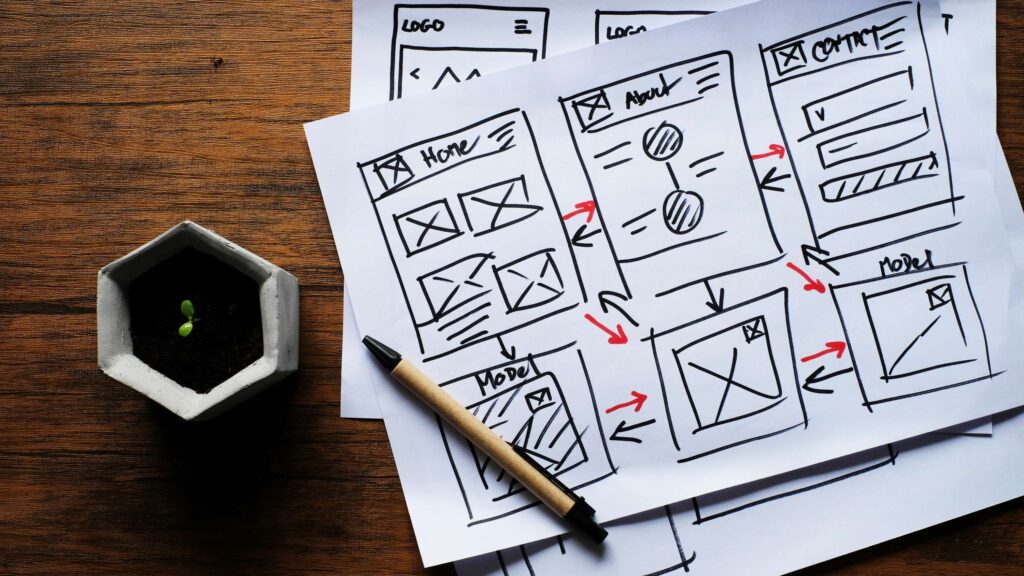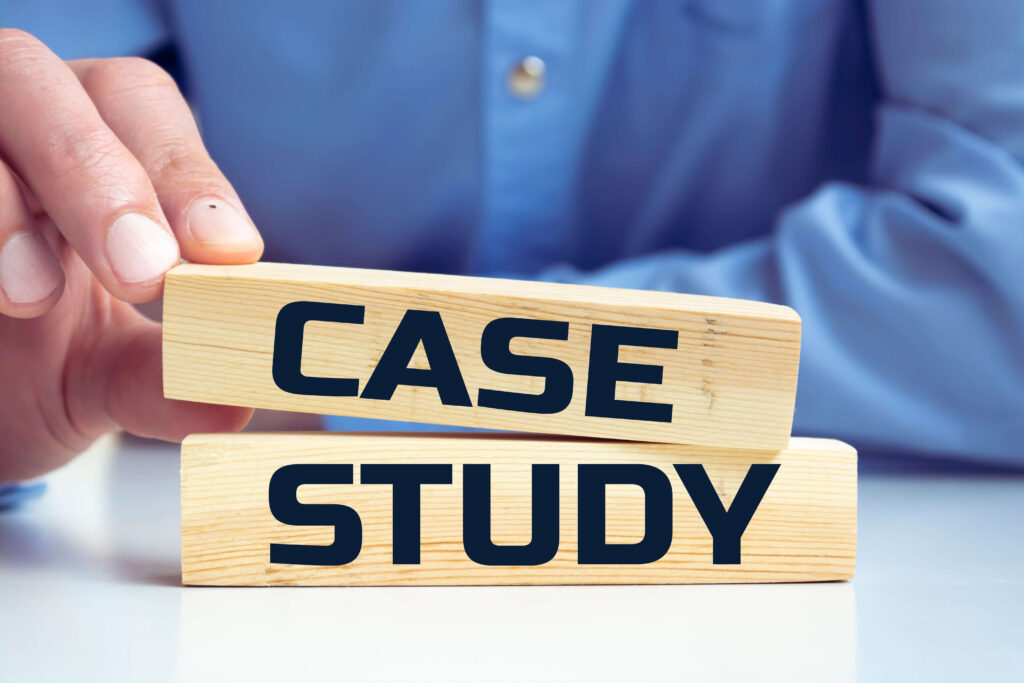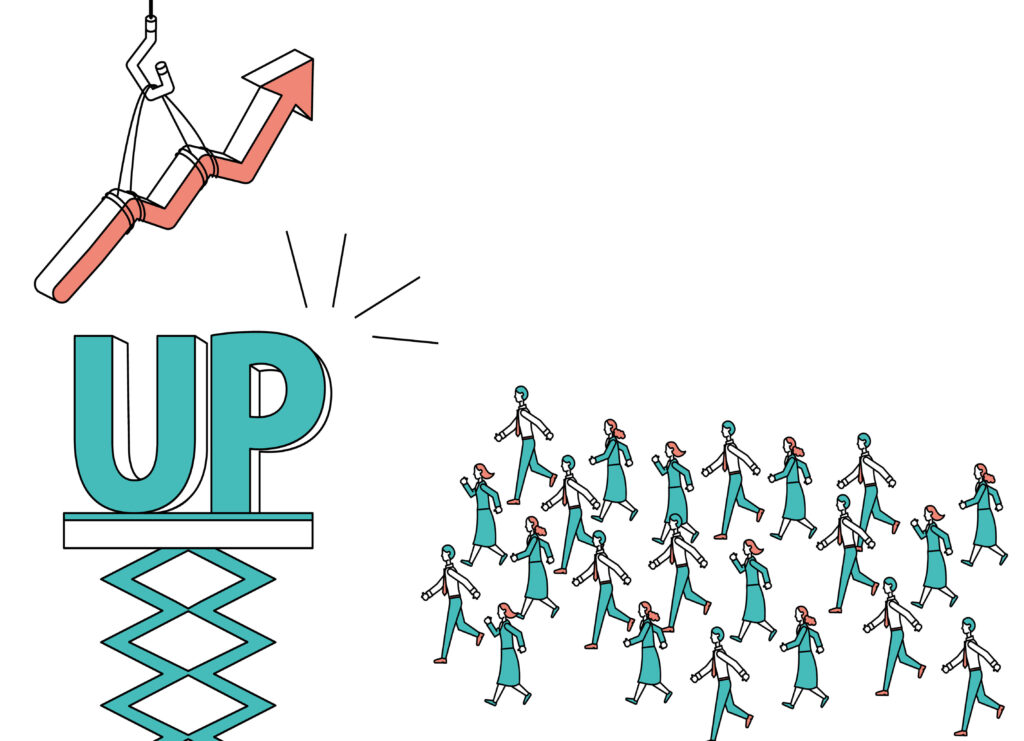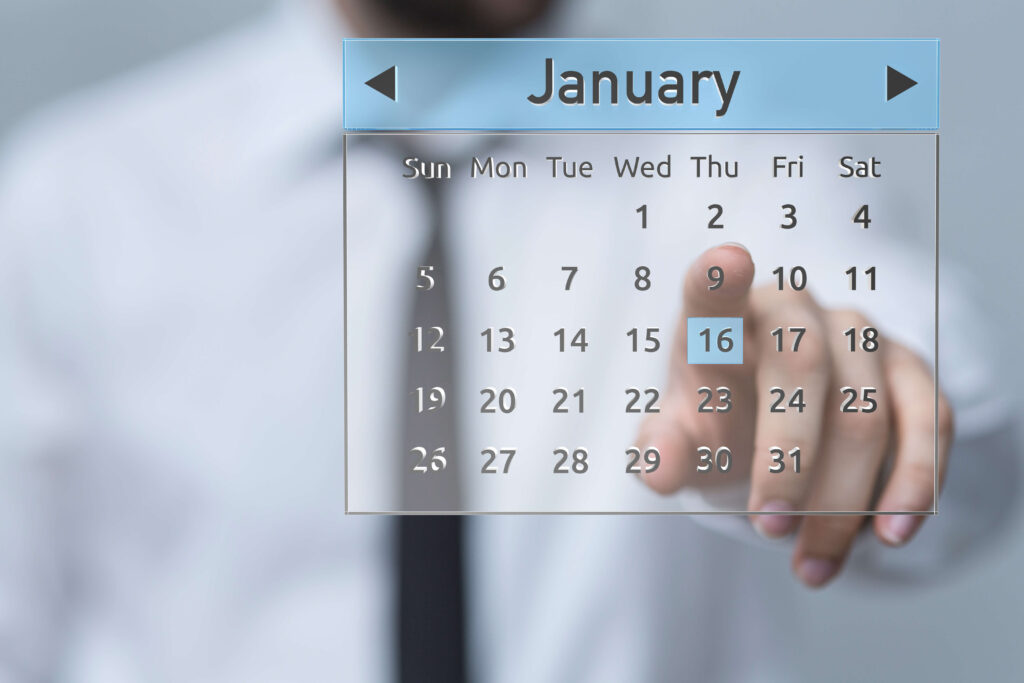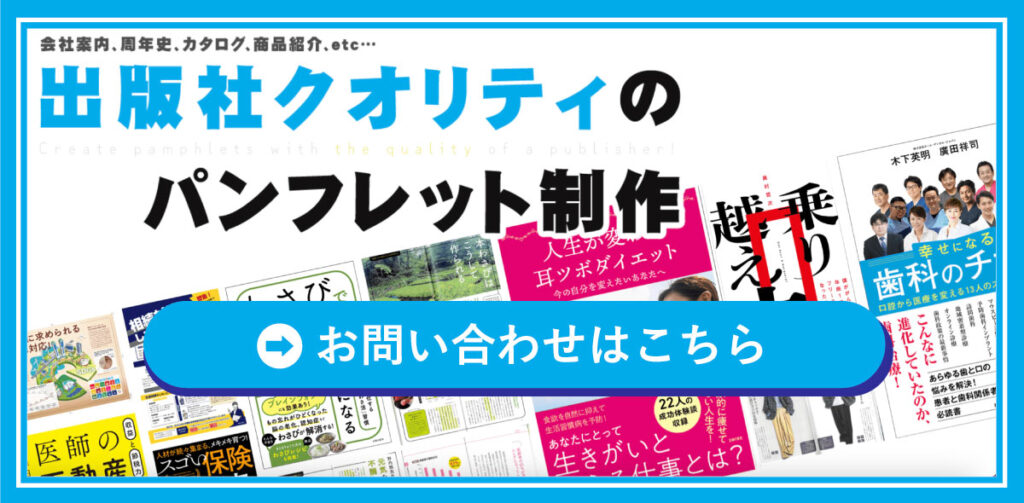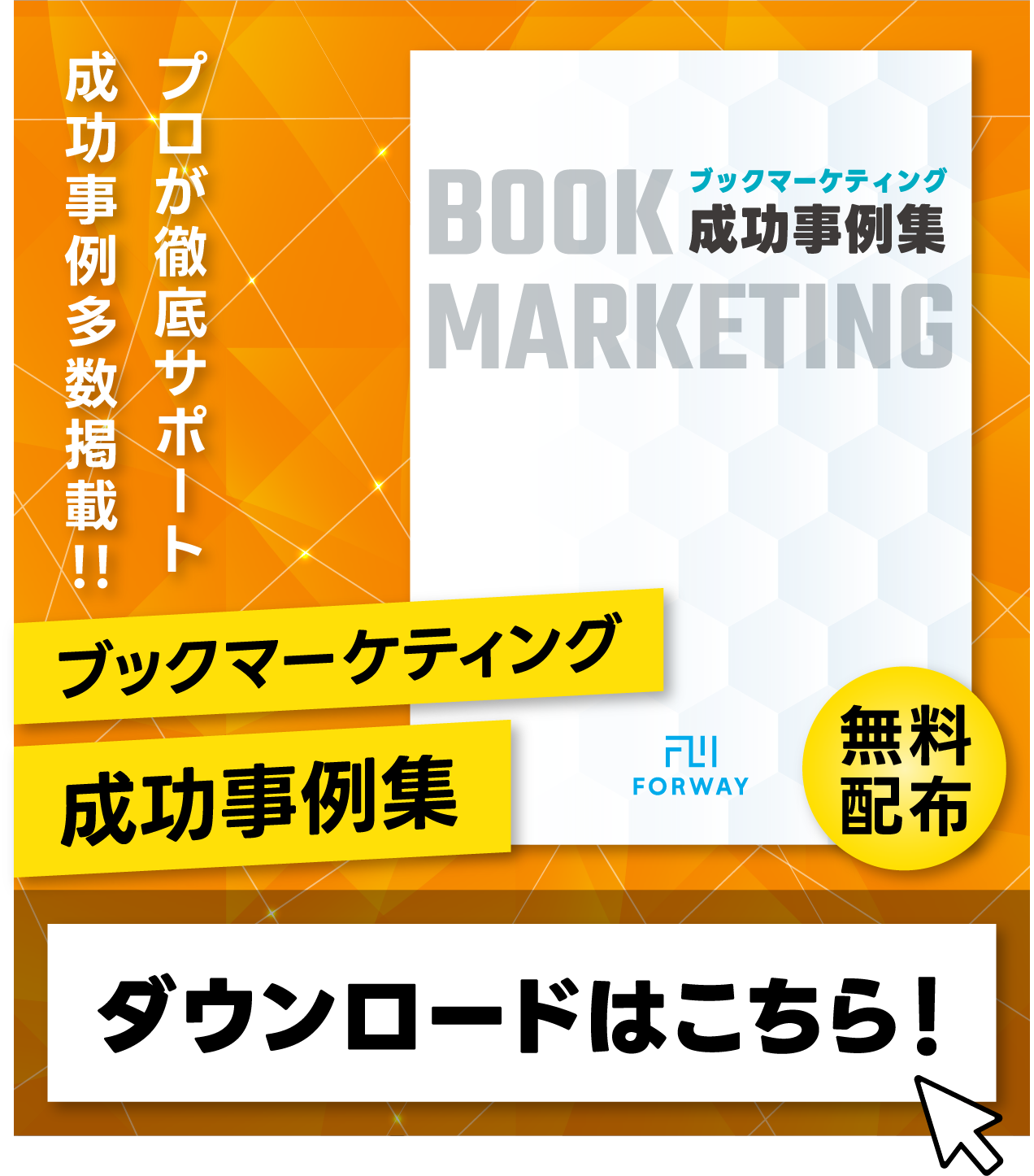企業にとって、「知られていること」は大きな強みです。
どれほど優れた製品やサービスを提供していても、それが世の中に認知されていなければ、顧客の選択肢に入ることすらできません。
特に情報があふれる現代では、消費者や取引先に「最初に思い浮かべてもらう存在」になることが重要です。
そのためには、自社の存在や価値を的確に伝える工夫が欠かせません。
「知名度」や「認知度」が高まることで、競合他社との差別化が図れるだけでなく、売上の向上、優秀な人材の採用、さらには社会的な信頼の獲得にもつながります。
この記事では、マーケティング戦略の基盤となる「知名度」と「認知度」に焦点を当て、それぞれの違いを明確にしながら、具体的な施策を紹介します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉「知名度」と「認知度」の違いとは?

「知名度」と「認知度」は、いずれも世間にどれだけ知られているかを表す言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。
以下で詳しく見ていきましょう。
◉-1、「知名度」とは何か?
知名度とは、企業やブランドの「名前」がどれだけ世間に知られているかを示す指標です。
具体的には、以下のような状態を指します。
- 社名やブランド名を聞いたことがある
- ロゴやキャッチコピーを目にしたことがある
- CMや広告、SNSなどで目にしたことがある
ただし、「誰もが名前は知っているが、実際に何をやっているのかわからない」という場合は、「知名度は高いが認知度は低い」という状態に該当します。
◉-2、「認知度」とは何か?
認知度とは、企業の事業内容や製品・サービスについて「どれだけ深く理解されているか」を表す指標です。
単に名前を知っているだけではなく、以下のような理解や行動が含まれます。
- 企業の強みや姿勢に共感している
- 製品やサービスを利用したことがある
- 他人にその企業や製品を紹介できる
こうした深い理解があると、BtoBでは信頼関係の構築に、BtoCではリピート購入やファン化につながります。
◉企業が知名度・認知度を高めるメリット

企業が知名度・認知度を高めるメリットとして、次の5つを挙げることができます。
- ブランド価値及び信頼性の向上
- 競合他社との差別化による新規顧客の獲得
- 業界内での影響力向上
- 広告宣伝費の長期的な削減
- 人材採用の決定率の向上
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、ブランド価値及び信頼性の向上
認知度が高い企業の製品・サービスは、信頼性の高さにもつながります。
なぜなら、認知度が上がれば製品・サービスとの接点(タッチポイント)が増え、顧客が製品・サービスに好意的なイメージを持ちやすくなるからです。
タッチポイントを増やせば、色々な角度から繰り返しアプローチできます。
結果として、ブランド価値の向上につながりやすくなるのです。
ブランド価値を向上させることができれば、「高級スーパーといえば⚫️⚫️」「深夜にゆっくり嗜むなら⚫️⚫️のウイスキー」といったように、優先的に選ばれやすくなります。
BtoBのビジネスでも「この案件を発注するなら⚫️⚫️」「この類のコンサルを依頼するなら⚫️⚫️」というように、その業界での第一想起を狙えるようになります。
このように、認知度を高められれば、顧客からの信頼の獲得にもつながり、リピート購入や固定客の獲得にもつながりやすくなるのです。
◉-2、競合他社との差別化による新規顧客の獲得
企業の認知度が向上すると、競合他社との差別化を図ることができ、価格競争から脱却できます。
なぜなら、「⚫️⚫️の製品ならば間違いない」という信頼性を獲得できるからです。
たとえば、家電製品を選ぶ時に、「知らないメーカーの安い製品ではなく、少し高くてもよく知っているメーカーのものを選ぶ」という人は多いと思います。
BtoBビジネスの場合でも同様のことが言えます。
このように、認知度によって差別化を図ることで、比較的高めの価格であっても顧客の方から選んでもらいやすくなるのです。
◉-3、業界内での影響力向上
企業の認知度が向上すると、必然的に業界に与える影響も大きくなります。
たとえば、ビール類で市場シェア2位を誇るキリンビールは、コロナ禍でビール市場が縮小したことにより、販売業績が前年を下回る結果となりました。そこで、起死回生を狙うべく投入したのは、「スプリングバレー」というブランドのクラフトビールです(2021年3月発売)。
テレビCMや広告、店舗向け小型ビールサーバーの展開により認知度を向上させた結果、クラフトビール業界をけん引する存在となりました。同社調べでは、2021年の国内の販売規模は6万リットル強と、20年と比較すると約1.6倍に増加しているそうです。(※1)
また、認知度が向上すれば、「影響力がある会社」として紹介が増えたりアライアンスの打診が増えたり、ビジネスチャンスの拡大につながりやすくなります。
このように、認知度を向上させることで、企業はさまざまな恩恵を受けることができるのです。
※1:日経クロストレンド「キリンはクラフトビールに活路 17年連続縮小のビール市場活性化へ」
◉-4、広告宣伝費の長期的な削減
企業の認知度が上がることは、広告宣伝費の削減にもつながります。
なぜなら、認知度が向上すると、口コミやSNSなどで製品・サービスの情報が自然と拡散されやすく、宣伝される機会が増えるためです。
たとえば、認知度が高い企業が生み出した製品・サービスが、SNSで拡散されているのを見たことがあるという人は多いのではないでしょうか。
このように、認知度が向上することで「この企業の製品だから自分も紹介したい」という状態を作ることができます。
ユーザーが自ら紹介したいと感じる状態が生まれれば、短期的な広告宣伝を行って購入を喚起する必要がなくなるため、結果的に広告宣伝費の長期的な削減にもつながります。
このように、「広告依存から脱却する」という観点からも、企業にとって、認知度を上げる活動は重要なのです。
◉-5、人材採用の決定率の向上
認知度が向上すると、「この企業で働きたい」という意欲を持った人が集まりやすくなります。
なぜなら、誰もが見知っていたり、どんな取り組みを行っているのか、どんな製品・サービスを提供しているのかイメージがつく企業に対して、人は好意的な印象を持つからです。
一方で、そもそも何をしている会社なのかが分からない場合、好意的な印象を持てないどころか、選択肢の1つにもなれません。
また、何をしている企業なのか分からないと、入社後のミスマッチにもつながりやすくなります。
このように、認知度を向上させることは、求職者数の増加にもつながるだけではなく、人材のミスマッチの予防も可能です。
結果的に、人材採用における決定率の向上につながります。
◉知名度や認知度を高めるための具体的な施策

知名度や認知度を効果的に高めていくには、ターゲットに合わせて適切な施策を組み合わせることが重要です。
これらの施策は、大きく次の2つに分けることができます。
企業や事業内容によって有効な方法は異なりますが、それぞれの特徴を理解し、バランスよく活用することで、より高い成果が狙えます。
具体的にどのような施策があるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
◉-1、オンライン施策
デジタル化が加速する現代において、オンライン施策は企業の知名度や認知度を高めるうえで大きな影響力を持っています。
スマートフォンの普及やSNSの利用が一般化したため、顧客が企業やサービスと出会う最初のきっかけは、オンライン上であることが多くなりました。
自社サイトやSNS、広告など、さまざまな施策がありますが、いずれもターゲットとの接点を意図的に作り出すことがポイントです。
オンライン施策は、比較的低コストで情報発信ができる点もメリットです。
ここでは、5つのオンライン施策を紹介します。
◉-1-1、広告媒体の活用
企業が認知度を向上させる一般的な方法が「広告媒体の活用」です。代表的なのが、テレビやラジオ・新聞・雑誌などのマスメディアを用いたマス広告や、検索連動型広告やディスプレイ広告・リターゲティング広告などのWeb広告です。
インターネットの普及によりマスメディアの影響力が落ちてきているといわれていますが、マス広告は、依然として高い効果が期待できる方法の1つです。
マス広告の場合、顧客は偶然に広告を見ることになるため、潜在顧客に対して広告を見せて認知を獲得する効果が期待できます。
たとえば、ふと目に入るテレビCMが印象的で、紹介されている製品やサービスについて調べた経験のある方はいるのではないでしょうか。
一方で、インターネット環境における広告媒体として検索連動型広告やディスプレイ広告・リターゲティング広告があります。
検索連動型広告やディスプレイ広告、リターゲティング広告の概要は以下の通りです。
| 検索連動型広告 | GoogleやYahoo! JAPANなどの検索エンジンで検索したときに、検索したキーワードに連動して表示される広告のこと。製品やサービスの購入を検討している顧客にアプローチできるため、費用対効果が高い点が特徴。 |
| ディスプレイ広告 | Webサイトやアプリの広告枠に表示される画像や動画の広告のこと。イメージとして顧客が視認することができるため、認知度の向上効果が高い点が特徴。書籍の広告も相性が良い。 |
| リターゲティング広告 | 自社のWebサイトに訪問したことのある顧客に再度広告を表示させるWeb広告。自社の製品やサービスに興味を持ってサイトを訪れた顧客に、再度広告を表示することができるため、認知率を向上させ購買につなげることが可能。 |
検索連動型広告やディスプレイ広告、リターゲティング広告は、ターゲットを細かく設定できるのが強みです。
たとえば、「キャンプ用品に関するサイトを訪れたら、YouTubeの広告にキャンプメーカーの広告が表示されるようになった」のような経験がある人は多いのではないでしょうか。
このように、マス広告とWeb広告は異なる強みや特徴があるため、2つを組み合わせることで認知度を効率的に向上させることが可能になります。
◉-1-2、SNS媒体の活用
SNSはコミュニケーションツールとしてだけではなく、情報収集ツールとして活用されています。
そのため、うまく活用することによって効率的に認知度を向上させることができます。
たとえば、アイスクリームメーカーのハーゲンダッツジャパンは、ハーゲンダッツのミニカップに現れるハート型をシェアしてもらうキャンペーンを実施しました。
このキャンペーンは、X(旧:Twitter)を媒体として行われ、約4,200件もの投稿が集まっています。
投稿がタイムライン上に表示されることで、普段から商品を購入している層だけでなく、これまで関心の薄かった層にも情報が届き、認知度を高めることにつながりました。
また、自社のアカウントを使ってSNSキャンペーンや広告を打つのではなく、「既にSNS上で一定の影響力を持つインフルエンサーに情報を発信してもらう」といった方法もあります。
インフルエンサーが製品やサービスに好意的な意見を投稿すると、自然に消費者目線の情報として拡散され、そのフォロワーにも情報が届きます。
インフルエンサーが、あたかも自然にその製品やサービスを使っているかのように見せかけるステルスマーケティングの規制には十分注意が必要ですが、「これはPRである」と明示したうえで、影響力のあるインフルエンサーに製品・サービス情報を発信してもらうのは、認知度の向上に効果的です。
また、SNSと言っても色々な種類があります。InstagramやX(旧:Twitter)、TikTok、YouTubeなどのSNSごとにユーザー層が異なるため、ターゲット層に合わせて最適なSNSを選ぶことが必要です。活用する際は、どの潜在層に届けたいのかを明確にして適切なSNS媒体を選ぶようにしましょう。
▶︎SNSマーケティングについては、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】をあわせて参考にしてください。
◉-1-3、コンテンツマーケティングの実施
コンテンツマーケティングでは、特定の企業の取り組みや製品・サービスについて知らない潜在層に対して認知を拡大させることが可能です。
なぜなら、企業の取り組みや製品・サービスを認知していないユーザーに、自然な形で知ってもらうことができるからです。
たとえば、新たな集客施策としてリスティング広告を検討している場合、いきなりリスティング広告の企業に依頼する人はいません。
まずは情報収集から始める人がほとんどでしょう。
この場合、検索エンジンで「リスティング広告とは」「リスティング広告 メリット」「リスティング広告 業者」などのキーワードで検索し検索上位にあるコラムなどを見て情報収集していくと思います。
その際に、検索上位に出てきたコラムを運営する企業に対して人は、「A社はリスティング広告において有名な企業」というイメージを持ちやすくなります。
また、そのコラムの内容が優れていた場合には、「この企業は信頼できる」というイメージもプラスされるでしょう。
このように、コンテンツマーケティングで質の高いコンテンツを作成して検索上位を狙うことは認知度の向上においても重要です。
◉-1-4、有名人やインフルエンサーとのコラボレーション
有名人やインフルエンサーとコラボレーションすることも、認知度の向上に効果的です。
特に、好感度の高い有名人やインフルエンサーを起用すれば、企業や製品・サービスに対するイメージアップを図ることができます。
さらに、「あの有名人がPRしている商品」として認知されるだけではなく、利用シーンも伝えることができるため、ユーザーにイメージを湧かせやすくなります。
たとえば、ヘアケア製品を扱う企業であれば、髪が綺麗な有名人を起用することで「私もこんな髪になれるかも」「この有名人が使っているなら効果があるだろう」と売上に直結させることができるのです。
このように、有名人やインフルエンサーとのコラボレーションによって認知度を向上させるためには、知名度や好感度、製品・サービスとの相性まで考えて起用することが大切です。
◉-1-5、プレスリリース(ニュースリリース)の配信
プレスリリースは、自社の活動やニュースを広く社会に伝えるうえで効果的な手法です。
単なる自社からの発信だけでなく、信頼性の高いメディアによって発信・掲載されることで、情報に説得力と影響力が加わります。
新商品や新サービス、業務提携、書籍出版、イベント開催などのニュース性のある情報をプレスリリースで発信すれば、メディア掲載や取材依頼につながる可能性が高まります。
◉-2、オフライン施策
オンライン施策は即効性や拡散力に優れている一方で、オフライン施策には信頼性やリアルな関係を築くことに強みがあります。
特にBtoB領域や地域密着型ビジネス、信頼性が重視される医療・士業・建設業などの分野では、対面やオフラインの活動が企業への信頼や知名度・認知度を高めることにつながります。
相手と実際に顔を合わせて会話することで、オンライン施策では得にくい信頼を得ることができるでしょう。
以下では、4つのオフライン施策を紹介します。
◉-2-1、展示会や地域イベントへの出展
展示会や地域イベントは、ターゲット層と直接対面し、商品やサービスの魅力をリアルに伝えられる機会です。
名刺交換や資料配布、デモ体験などを通じて、企業の雰囲気や担当者の人柄が伝わりやすく、参加者の印象に残りやすいのが特徴です。
展示会や地域イベントへの出展から関係性が深まれば、「この会社に相談してみたい」と感じてもらえるきっかけになります。
◉-2-2、新聞・雑誌・業界誌などへの掲載
新聞や雑誌、業界誌といった紙媒体への掲載は、第三者による評価として受け取られるため、信頼性を高められる手法です。
特に地方紙や専門誌は、読者との間にすでに信頼関係が築かれているケースが多く、「記事として紹介された」という事実自体が企業の信頼と認知度の向上に直結します。
また、紙媒体はオンライン記事と異なり、保存されやすいといった特徴があり、情報が定着しやすいといえます。
◉-2-3、パートナー企業との共同プロモーションの実施
信頼関係のあるパートナー企業と一緒にプロモーションを展開することで、自社だけでは届きにくい新たな層にも、自然に知ってもらうきっかけをつくることができます。
たとえば、既存の取引先や地域団体と協力してイベントやキャンペーンを行えば、「信頼できる相手からの紹介」として受け止められやすくなり、安心感や親しみを持ってもらえます。
お互いの得意分野を活かしながら、新しいお客さまと出会えるチャンスを広げる効果的な施策です。
◉-2-4、書籍出版
書籍の出版は、オフライン施策の中でも特に「信頼」と「深い認知」を獲得しやすい手法です。
書籍は「誰にでも簡単に出せるものではない」という印象があるため、社会的な信用度の高いコンテンツです。
また、企業や経営者の理念・価値観・専門性を体系的に伝えることができるため、認知の獲得だけでなく、読者との信頼関係にもつながります。
さらに、読み手との心理的な距離を縮めやすく、他のマーケティング施策と組み合わせることで、より大きな相乗効果が期待できるのも特徴です。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。
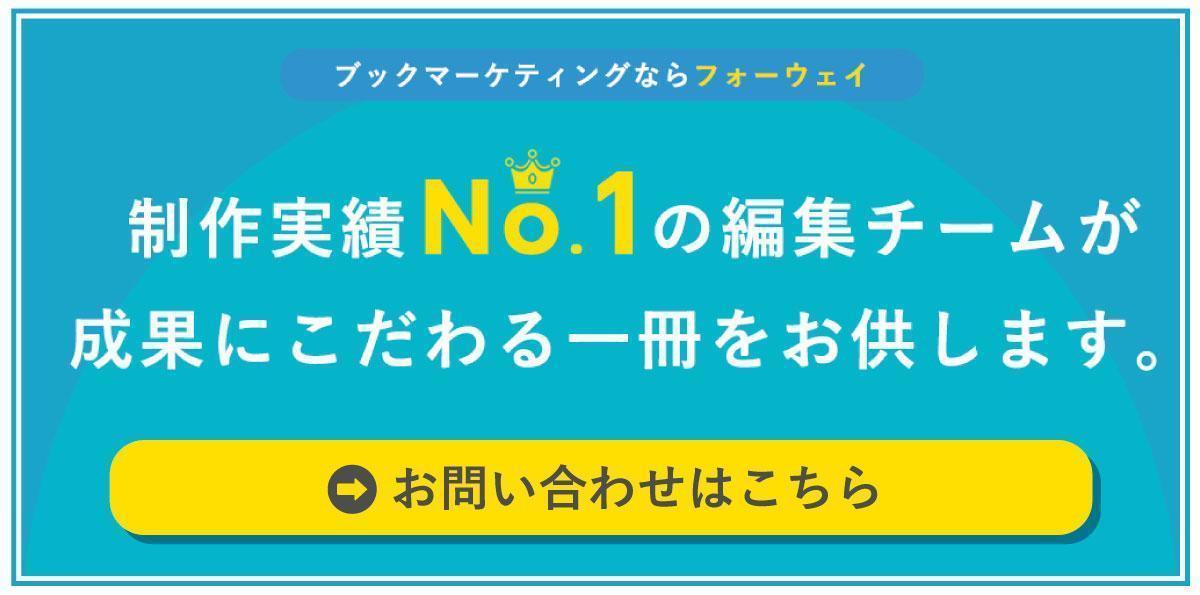
◉企業が知名度や認知度の向上施策で失敗する典型的な例

知名度や認知度の向上を目指す企業が失敗しがちな典型例として、次の3つが挙げられます。
- 情報発信に一貫性がなく、ブランドイメージが定まっていない
- 質より量に偏った情報発信になっている
- 一過性の話題作りで終わっている
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、情報発信に一貫性がなく、ブランドイメージが定まっていない
媒体ごとに異なるメッセージを発信してしまうのは、認知度向上を目指す企業が陥りがちな失敗の一つです。
たとえば、Webサイトでは「技術力重視の堅実な会社」と伝えているのに、SNSでは「親しみやすい雰囲気の会社」と発信しているようなケースです。
発信する情報に一貫性がないと、受け手は混乱してしまい、最終的には「なんとなく信用できない」という印象を抱いてしまいます。
◉-2、質より量に偏った情報発信になっている
知名度や認知度の向上を急ぐあまり、「とにかく露出を増やさなければ」と、質より量を優先した情報発信を行う企業も少なくありません。
しかし、発信する情報の質が伴っていなければ、むしろ「内容が薄い企業」「信頼できない企業」というマイナスの印象を与えてしまうおそれがあります。
◉-3、一過性の話題作りで終わっている
話題性を狙ったキャンペーンやSNS投稿は、成功すれば一時的に注目を集めることができます。
しかし実際には、「バズったものの、企業の認知や信頼には結びつかなかった」といったケースも少なくありません。
一過性の話題は顧客の記憶に定着しづらく、企業の価値観や理念が十分に伝わらないまま終わってしまうことが多いため、結果として継続的な認知度の向上にはつながりにくいのが現実です。
◉知名度・認知度の向上は「信頼構築」と「メッセージの一貫性」が鍵

たとえ社名が広く知られていたとしても、「何をしている会社なのか分からない」と思われてしまっては、逆にブランドイメージを損ねるリスクがあります。
重要なのは、ただ露出を増やすことではなく、「正確な情報」を「信頼できるかたち」で届けることが重要です。
認知度を向上させるためには、次の2つの視点を持って取り組む必要があります。
- 「認知→理解→信頼→ファン化へのステップ」を意識して施策を設計する
- 書籍やWeb、SNSで一貫したメッセージを発信する
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、「認知→理解→信頼→ファン化へのステップ」を意識して施策を設計する
認知はゴールではなく、あくまでスタート地点です。
その先に「理解される」「信頼される」「選ばれる」という段階があることを前提に、施策の流れを戦略的に設計することが重要です。
ただ知ってもらうだけで終わらせず、段階的に関係性を深めていく視点が求められます。
◉-2、書籍やWeb、SNSで一貫したメッセージを発信する
信頼は、あらゆる情報発信における統一感から生まれます。
たとえば、ある媒体で「人材育成に強い」と打ち出し、別の媒体では「コスト削減が得意」と伝えてしまうと、受け手に混乱や不信感を与えてしまいます。
「この会社は結局、何を提供しているのか」と疑念を抱かれる原因になりかねません。
そのため、WebサイトやSNS、採用パンフレット、セミナー資料など、あらゆる媒体でメッセージを統一することが重要です。
そして、その軸を作るのに適した施策が書籍出版です。
◉知名度・認知度アップなら企業出版(ブックマーケティング)がおすすめ
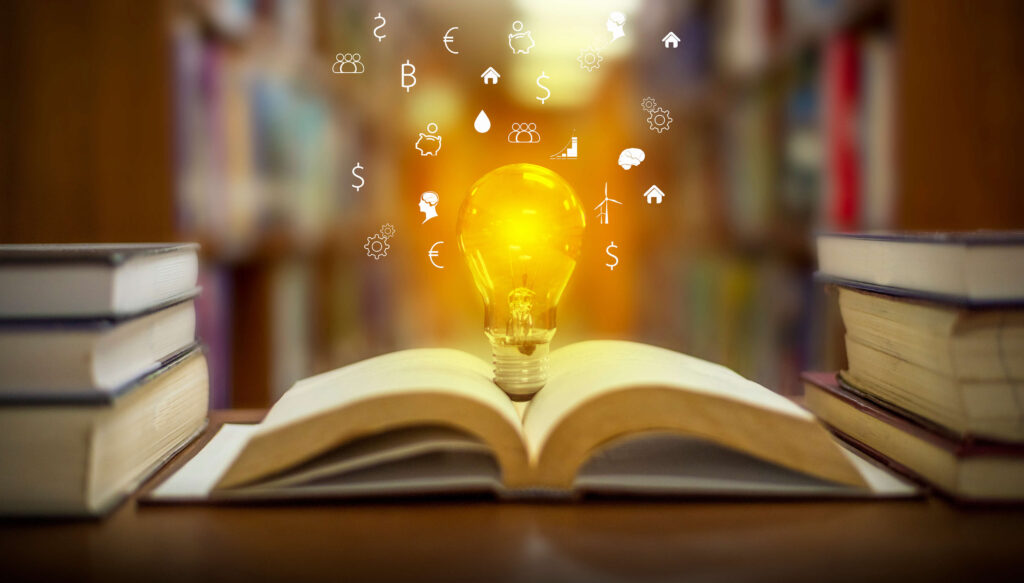
企業出版は、単なる情報発信では得られない「信頼」と「一貫性のあるメッセージ構築」が可能な施策です。
書籍を出版するには、自社や経営者の理念・実績・強みを洗い出し、伝えたい情報を体系的に整理する必要があります。
この作業を通じて、企業としての核となるメッセージが明確になり、それを軸とした一貫性あるブランディングが展開できます。
また、書籍で整理・構築したコンテンツは、ホームページのコラム化や小冊子としての再編集、SNS投稿、さらにはプレスリリースなど、他の媒体にも展開しやすく、広報活動全体の質と効率を高めることが可能です。
さらに、書籍という「社会的信用力の高い媒体」を用いることで、SEO対策やSNS発信、プレスリリース単体では築きにくい信頼関係を、読者や顧客との間に築くことにもつながります。
企業出版は、他の施策との連携による相乗効果を生みやすい点でも優れたマーケティング手法であり、知名度や認知度を高めたい企業にとって有効な選択肢といえます。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【本を出版するには?現役書籍編集者が本の出し方を分かりやすく解説】もあわせて参考にしてください。
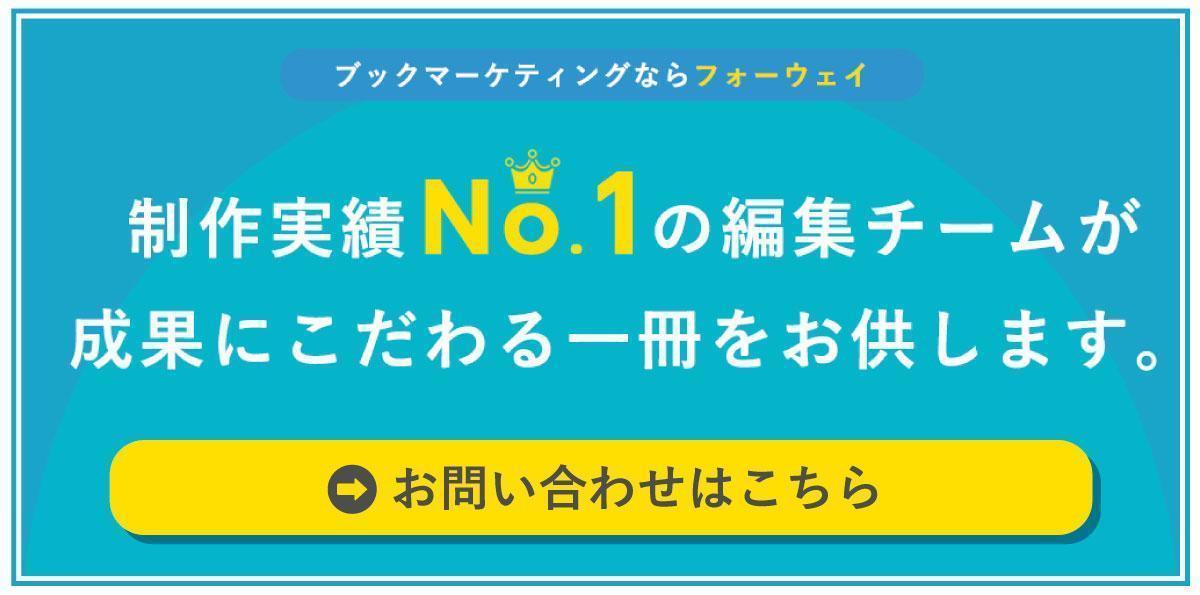
◉書籍を出版して知名度・認知度を着実に高めた成功事例

ここでは、書籍の出版によって知名度・認知度を高めることに成功した事例を7つ紹介します。
以下で、どのような事例なのかを見ていきましょう。
◉-1、保険代理店|業界内で「◯◯といえばあの会社」と呼ばれるまでに認知が定着した事例
法人向けの生命保険や損害保険を取り扱っている保険代理店では、業界内での認知向上を狙って書籍を出版。
書籍を読んだ同業他社からのコンサル依頼や保険会社の関係者から講演依頼を受けるようになり、「保険会社にとって頼れる代理店」というイメージが定着しました。
出版を通じて、業界内での認知度と信頼性を大きく高めることに成功しました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、不動産会社|医師という専門層に向けた戦略的出版でターゲット認知を拡大した事例
ある不動産会社は、医師をターゲットとした書籍を出版して認知拡大を図りました。
医師という特定のターゲットに向けた内容にすることで、「成約率100%」という大きな成果を上げました。
専門層に特化した戦略的な出版は、ターゲット層への効果的な手段となります。
◉-3、公認会計士|書籍出版をきっかけにメディア取材が増え、事務所の専門性が広く認知された事例
公認会計士事務所開設の1年目に「海外案件の専門家」というポジションを確立するために書籍を出版。
出版後をきっかけに、地元紙や全国紙、ラジオ番組などからの取材が相次ぎ、メディア露出が増加しました。
書籍を通じて専門性が広く認知され、事務所のブランディングとビジネス拡大に成功しました。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉-4、医師|成分解説に特化した書籍で「コラーゲンの専門家」としての認知を確立した事例
ある医師は、長年研究してきたコラーゲンの成分解説をテーマとした書籍を出版しました。
薬機法に配慮しながらも、消費者や同業者に対してもわかりやすく専門性を伝え、「コラーゲンの専門家」としての地位を確立。
書籍はサプリメントの販促にもつながり、ビジネス面でも成果を上げました。
◉-5、研究者|健康テーマの出版を通じて「米油ブーム」に影響を与えた社会的認知拡大の事例
研究者として食と健康をテーマに活動していた著者は、米油の健康効果に関する書籍を出版。
当時の健康志向の高まりと相まって、米油の需要拡大に貢献しました。
同時に、研究者としての社会的認知度も向上し、健康テーマに関する専門家としての地位を確立しました。
◉-6、がん治療専門クリニック|出版を機に遠方からの来院が増加した医療ブランディング事例
あるがん治療専門クリニックは、書籍を出版することで、治療方針や理念を広く伝えることに成功しました。
出版後、書籍を読んだ患者からの問い合わせや、遠方からの来院が増加し、クリニックのブランディングと集患に大きく貢献しました。
出版を通じて患者の信頼を獲得し、医療ブランディングの成功につながった事例です。
◉-7、建設業専門コンサルタント|書籍を通じて業界内での地位を確立した事例
ある建設業専門のコンサルタントは、業界の課題や解決策をまとめた書籍を出版しました。
出版をきっかけに業界内での専門家としての認知と信頼性が高まり、講演依頼やコンサルティングの相談も増加しました。
また、書籍を通じて新たな顧客層へのアプローチも可能となり、ビジネスの拡大へとつながっています。
◉【まとめ】書籍を活用した「知名度」「認知度」の向上によって「選ばれる会社」を目指そう!
この記事では、「知名度」と「認知度」の違いや具体的な施策、さらに書籍出版によって成果を上げた成功事例について解説しました。
知名度・認知度を効果的に高める手段として、現在注目されているのが「書籍の出版」です。
書籍は、信頼性・専門性・共感を伝えられるブランディング手段であり、営業や採用、広報などさまざまな場面で活用可能です。
フォーウェイでは、書籍を活用した「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
企業の強みや理念、サービスの特徴などをプロの編集者が丁寧にヒアリングし、1冊の書籍として形にします。
知名度・認知度の向上施策として書籍出版を検討している方は、フォーウェイまでお問い合わせください。
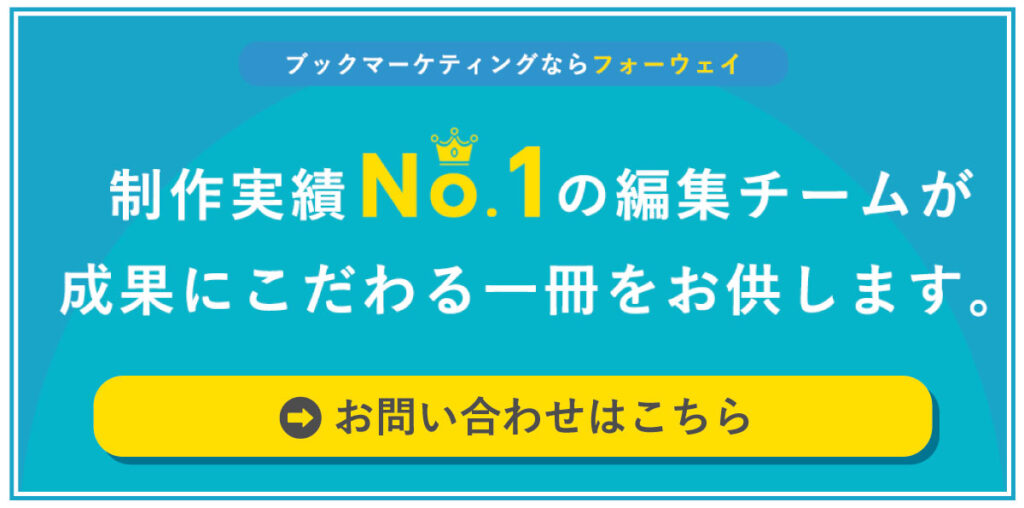

「集客がうまくいかない」「広告費をかけているのに反響が少ない」といった悩みを抱える不動産会社は少なくありません。
特に近年は、顧客の行動様式や価値観が大きく変化しており、これまでの集客手法だけでは十分な効果を得にくくなっています。
たとえば、かつては店舗への来店から始まっていた物件探しも、現在ではスマートフォンを使ったインターネット検索が主流です。
これまでの集客方法だけでは取りこぼしてしまう層が増えているのが現状です。
この記事では、なぜ不動産業界において集客が難しくなっているのかを解説したうえで、オンライン・オフラインの集客手法を紹介します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉不動産業界の集客が難しい理由

不動産業界での集客が難しい理由は、主に次の3つです。
・競合他社との差別化が難しくなっているため
・人口減少により市場そのものが縮小しているため
・顧客が契約するまでの過程が複雑・長期化しているため |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、競合他社との差別化が難しくなっているため
不動産業界の特徴として、同じエリア内に複数の不動産会社があり、似たような物件を扱っていることが挙げられます。
そのため、顧客サイドから見ると、どの不動産会社も同じように見えてしまいます。
それに加えて、SUUMOやHOME’Sなどのポータルサイトでは、複数の会社が同一物件を掲載することも珍しくないため、顧客には特定の不動産会社を選ぶ理由が見つからないのです。
このような中で、競合他社と差別化して「この会社に相談してみよう」と思ってもらうためには、担当者の対応力や会社の専門性や実績などを見せていく必要があります。
◉-2、人口減少により市場そのものが縮小しているため
日本では少子高齢化が進み、特に地方部を中心に人口が減少しています。
その結果、「住宅を買いたい」「家を借りたい」と考える人の母数自体が減っており、不動産市場全体の規模が縮小傾向にあります。
実際、国土交通省の「国土の長期展望」中間とりまとめ 参考資料によれば、日本の人口は2008年にピーク12,808万人を迎え、その後は減少に転じました。
今後は、2030年に11,913万人、2050年に10,192万人、2100年には5,972万人にまで減少すると予測されています。
なお、国立社会保障・人口問題研究所の人口統計資料集(2025年版)によれば、2023年の日本の人口は12,435万人でした。
日本の人口は中長期的に見ても減少が続くとされており、不動産業界の需要の減少は避けられない状況です。
特に地域密着型の企業にとっては、顧客層の確保がますます困難になることが想定され、集客方法の見直しが急務となっています。
◉-3、顧客が契約するまでの過程が複雑・長期化しているため
インターネットの普及により、顧客は物件情報を自宅にいながら簡単に入手・比較できるようになりました。
その結果、複数の不動産会社や物件をじっくりと比較検討する姿勢が一般化し、契約に至るまでの過程はより複雑で時間のかかるものとなっています。
いわゆる「成約までのリードタイム」が延びる傾向にあり、特に物件価格が高額になるほど、その傾向は顕著です。
◉【オンライン】不動産集客の主な施策8選

今では、不動産会社にとってオンラインでの集客は欠かせない手段となっています。
なぜなら、多くの人が家や土地を探すとき、最初にスマートフォンやパソコンで情報を調べるからです。
たとえば、物件情報を見たり、複数の不動産会社を比較したりするのは、もはや当たり前の行動になっています。
このときに、ホームページやSNS、Googleマップなど、ネット上で見つけてもらえる場所がなければ、そもそも候補にも入れてもらえません。
このような顧客に対応するための主なオンライン集客施策は、次の8つです。
・ホームページを作成して運用する
・オウンドメディアを活用してSEO対策を行う
・Googleビジネスプロフィールを活用してMEO対策を行う
・リスティング広告を活用して顕在層の集客を狙う
・SNSを活用して認知拡大とファンづくりを行う
・動画で信頼感と接触頻度を高める
・不動産ポータルサイトを活用して幅広いユーザーにリーチする
・不動産一括査定サイトに登録して売却ニーズを獲得する |
それぞれの施策を解説します。
◉-1、ホームページを作成して運用する
まず最初に取り組むべき施策は、会社の「顔」となるホームページの整備です。
ホームページが整っていれば、広告やSNS、Google検索などと連携した集客と成約率の向上を見込むことができます。
◉-2、オウンドメディアを活用してSEO対策を行う
不動産を探している人の多くは、「〇〇市 一戸建て」や「不動産 売却 流れ」など、具体的な言葉でインターネット検索をしています。
こうしたキーワードに合わせて、役立つ情報をブログや自社サイトに記事として掲載していく方法を「SEO対策(検索エンジン最適化)」といいます。
SEO対策は、成果が出るまでに時間がかかることが多いですが、記事がインターネット上に蓄積されていくことで、徐々に検索順位が上がり、安定したアクセスを得やすくなるのが特徴です。
▶︎SEO対策の詳細については、関連記事【SEO対策とは? 効果的な戦略の組み立て方と対策方法】もあわせて参考にしてください。
◉-3、Googleビジネスプロフィールを活用してMEO対策を行う
「近くの不動産会社」などと検索したとき、Googleマップに自社が上位表示されるようにするのがMEO対策(マップ検索エンジン最適化)です。
Googleビジネスプロフィールを整備しておくと、地域の顧客からの来店や問い合わせが増えることが期待できます。
特に、営業時間や写真、口コミといった情報をこまめに登録・更新しておくことが、効果を高めるポイントです。
◉-4、リスティング広告を活用して顕在層の集客を狙う
リスティング広告とは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで検索した際、その検索結果ページに表示される広告のことです。
たとえば、「〇〇市 中古マンション」「不動産売却 相場」といった具体的なキーワードで検索している人は、すでに不動産に興味・関心を持っている「顕在層」です。
このようなユーザーに向けて広告を表示することで、購入や売却の意欲が高い見込み客へ効率よくアプローチできます。
◉-5、SNSを活用して認知拡大とファンづくりを行う
InstagramやX(旧Twitter)、TikTokなどのSNSは、自社や物件の存在を多くの人に知ってもらうための有力な手段です。
たとえば、以下のような情報を発信することで、ユーザーに親しみを感じてもらいやすくなります。
・物件の内装写真や動画
・周辺環境の紹介
・イベントやキャンペーン情報 |
SNSはユーザーとの距離が近いため、信頼関係を築きながら見込み客をファンに育てることができます。
▶︎SNSの活用の詳細については、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】もあわせて参考にしてください。
◉-6、動画で信頼感と接触頻度を高める
動画は、写真や文章では伝えきれない臨場感や信頼感を届けられます。
特に、以下のようなコンテンツが効果的です。
・物件紹介や内覧の様子
・地域の住みやすさや利便性を伝える紹介動画
・不動産に関するQ&Aや住宅ローンの解説
・スタッフの紹介や仕事風景 |
動画はYouTubeやTikTok、Instagramなどに投稿するのが主流です。
視覚と音で印象に残りやすく、一度投稿すれば長期間にわたって再生され続けるのも大きなメリットです。
また、スタッフの人柄や会社の雰囲気が伝わりやすく、「この会社なら安心できそう」と思ってもらえるきっかけになります。
◉-7、不動産ポータルサイトを活用して幅広いユーザーにリーチする
物件を探している顧客は、SUUMOやHOME’S、アットホームなどの大手不動産ポータルサイトを利用しています。
これらのサイトに物件情報を掲載することで、自社のホームページだけではリーチできない幅広い層の見込み客にリーチできるようになります。
ただし、大手不動産ポータルサイトに物件情報を掲載するためには費用が発生します。
◉-8、不動産一括査定サイトに登録して売却ニーズを獲得する
不動産一括査定サイトは、不動産を売却したいと考えている顧客が複数の不動産会社に一括で査定を依頼できるサービスです。
登録は無料の場合もあれば有料の場合もあり、料金体系もサイトによって異なります。
売却ニーズが明確な見込み客の情報を獲得できるため、売却物件の獲得に力を入れたい場合には有効です。
◉【オフライン】不動産集客の主な施策8選

近年はオンライン施策が主流となっていますが、地域密着型のアプローチや顧客との直接的なコミュニケーションを重視するオフライン施策も依然として重要です。
代表的なオフライン集客施策としては、次の8つがあります。
・ポスティングを活用して地域住民に訴求する
・新聞・雑誌への広告掲載で認知度と信頼感を高める
・看板を設置して通行人への視認性を向上させる
・営業リストを活用して電話で見込み客にアプローチする
・ティッシュ配りなどの街頭配布で接点をつくる
・イベントやセミナーを開催して直接信頼関係を築く
・FAXやDMを送付してターゲットに情報を届ける
・書籍を出版して専門性と信頼性をアピールする |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、ポスティングを活用して地域住民に訴求する
ポスティングは、ターゲットとなる地域住民に対して、チラシなどを通じて直接情報を届ける施策です。
たとえば、新築物件のオープンハウス情報や売却物件の募集、賃貸キャンペーンの案内など、地域ごとのニーズに合わせた情報を発信することで、そのエリアの見込み客に効果的にアプローチできます。
▶︎ポスティングの詳細については、関連記事【デジタル全盛期だからこそ重要なアナログマーケティング戦略】もあわせて参考にしてください。
◉-2、新聞・雑誌への広告掲載で認知度と信頼感を高める
新聞や特定の雑誌への広告掲載は、その媒体の読者層にリーチし、会社の認知度向上につながります。
特に地域紙や専門誌などは、特定のターゲット層に深く訴求できる可能性があります。
「新聞・雑誌に掲載されている=信用できる企業」という印象を持ってもらいやすく、ブランディングにも効果があります。
◉-3、看板を設置して通行人への視認性を向上させる
店舗前や交通量の多い幹線道路沿いに看板を設置することで、日常的に多くの人の目に触れる機会が増えます。
会社名や主要なサービス内容、電話番号、QRコードなどを表示することで、通行人に「不動産のことならここ」と認知してもらえる可能性が高まります。
地域での認知度アップとブランド構築にもつながる施策です。
◉-4、営業リストを活用して電話で見込み客にアプローチする
営業リストとは、過去に問い合わせをした人やセミナーに参加した人など、一定の関心を持っている見込み客のデータです。
営業リストを活用して電話をかけるメリットは、一人ひとりのニーズに合わせた情報提供や相談対応ができることです。
相手の状況を丁寧にヒアリングしながら関係性を築けば、成約につながりやすくなります。
◉-5、ティッシュ配りなどの街頭配布で接点をつくる
駅前や商業施設周辺でのティッシュ配りやチラシの街頭配布は、不特定多数の人々に自社を認知してもらうためのきっかけ作りになります。
配布物にWebサイトやLINE登録のQRコードを印刷すれば、オンライン集客への導線としても活用できます。
◉-6、イベントやセミナーを開催して直接信頼関係を築く
不動産相談会や住宅ローンセミナー、空き家対策セミナーなどの開催は、不動産の専門家としての信頼性を高める場として有効です。
参加者からの質問に答えたり、個別にアドバイスしたりすることで、安心感と信頼感が生まれ、成約のきっかけになることも少なくありません。
数ある施策の中でも、顧客と直接対面で関係性を築ける施策といえます。
◉-7、FAXやDMを送付してターゲットに情報を届ける
FAXやDM(ダイレクトメール)は、見込み客に直接情報を届けることができる施策です。
物件情報だけでなく、地域開発の情報や不動産に関するニュースレターなどを定期的に送付することで、顧客との関係性を維持することができます。
メールよりも目に留まりやすく、シニア層にも有効です。
◉-8、書籍を出版して専門性と信頼性をアピールする
オフラインでの集客施策の中でも、特に競合他社と大きく差別化できるのが書籍の出版です。
不動産に関する内容で書籍を執筆・出版すれば、専門知識や実績を明確に示すことができ、自社の専門性を強力に訴求できます。
また、書籍という媒体自体が「信頼性」や「権威性」を持っているため、「不動産のプロフェッショナル」としてのポジションを確立しやすく、見込み客からの信頼を大きく高めることが可能です。
実際に書籍を活用して成果を上げている不動産会社の事例もあるので、詳しくは後述の「書籍を活用して集客に成功した不動産の成功事例」をご覧ください。
書籍の具体的な活用方法として、以下の3つが挙げられます。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。
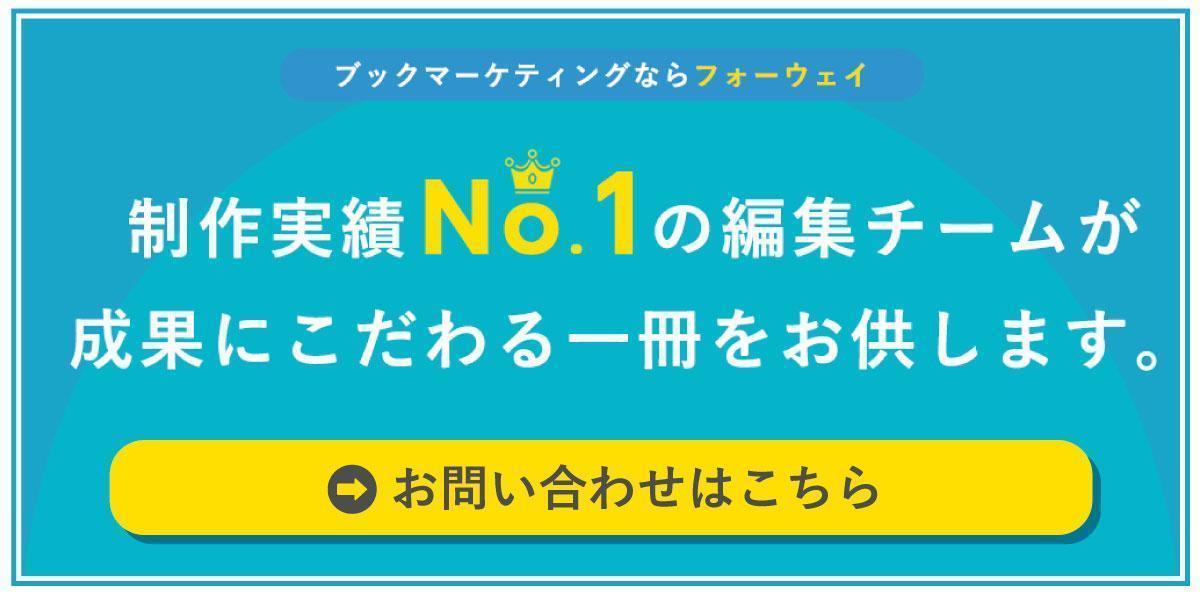
◉-8-1、活用方法①来店者に配布してクロージングを強化する
「本を出版している不動産会社なら信用できる」という顧客心理を活用することで、商談の信頼性を高め、成約率アップが期待できます。
また、商談中に話しきれなかった内容を補足する資料としても役立ち、顧客の不安解消につながります。
実際に、書籍を出版した後、見込み顧客に事前配布を行ったことで、商談時の質疑応答がよりスムーズになり、出版からわずか1ヶ月半で4件の成約につながったという事例もあります。
購入を検討している見込み客の背中を押すツールとして有効です。
◉-8-2、活用方法②イベントやセミナーで配布して信頼関係を築く
相談会や講演会などの場で、本を名刺代わりに配布することで、自社の専門性や想いを相手に印象づけることができます。
印刷物として手元に残るため、後日見返してもらいやすく、継続的な認知の定着にも効果的です。
「話だけではなく、しっかりとしたバックグラウンドがある会社」と感じてもらえるきっかけにもなるでしょう。
◉-8-3、活用方法③資料請求フォームからのリード獲得につなげる
自社ホームページなどで「書籍を無料プレゼント」と案内することで、資料請求フォームを通じて見込み客のリストを効率的に収集できます。
入力された住所や氏名に書籍を郵送する仕組みは、自然な導線としてユーザーの抵抗感も少ないのが特徴です。
また、送付後にフォローメールや電話をすることで、成約の可能性が高まります。
実際に、書籍の無料プレゼントを導線としたランディングページで、広告から100件以上の見込み客のリードを獲得した事例もあります。
書籍は企業の信頼性を高めるだけでなく、戦略的にリードを獲得できる施策です。
◉書籍を活用して集客に成功した不動産の成功事例

ここでは、出版した書籍を活用して集客に成功した事例を紹介します。
・事例1:医師に特化した不動産投資の集客の成功事例
・事例2:不動産業界の暴露本を出版して信頼を獲得した成功事例 |
2つの事例について詳しく見ていきましょう。
◉-1、事例1:医師に特化した不動産投資の集客の成功事例
不動産投資サービスを行っている不動産会社の経営者は、従来から医師をターゲットとして、SNSやWeb広告などで情報発信を行っていましたが、期待する効果が出ていませんでした。
そこで、「高収入なため支払う税金が多い医師に、最も効果的な節税対策は不動産投資である」ということを伝える書籍を出版しました。
書籍を通じて関心を持った読者に対して、フォローアップや提案を行った結果、出版からわずか6ヶ月で10件の反響を獲得。
そのすべてが成約に至るという、驚異の「成約率100%」を達成しました。
さらに、既存顧客からの紹介や口コミなどにより新規顧客の獲得にもつながっています。
◉-2、事例2:不動産業界の暴露本を出版して信頼を獲得した成功事例
ある不動産会社の経営者は、マイナスイメージの大きい不動産業界の暴露本を出版しました。
具体的には、「アパート・マンション経営」を勧める営業担当者が、表向きにはオーナーの利益を強調しながら、実際には自社の売上を優先しているという業界の裏側を取り上げています。
この出版の目的は、「このような不透明な営業が横行する業界でも、自社は誠実である」という姿勢を示し、信頼を得ることでした。
その狙いは的中し、大きな集客効果につながりました。
また、出版を機に無料だった相談サービスを有料に切り替えたところ、成約の可能性が高い顧客層の集客へとつながり、営業の効率化も実現しています。
さらに、この不動産会社では「書籍のタイトルと同じ公式サイト」を開設して書籍プレゼントを行っており、公式サイトを起点とした新規顧客の集客にも成功しています。
◉【まとめ】不動産業の集客にはブランディングにも効果がある書籍活用が有効!
この記事では、不動産業界で集客が難しい理由や不動産集客のためのオンライン施策・オフライン施策を紹介しました。
数ある施策の中でも、特に「書籍出版」は専門性と信頼性をアピールする集客施策として有効です。
今回紹介した2つの成功事例では、いずれも書籍を通じて「不動産の専門家」というイメージを確立し、集客数と成約率の向上につながりました。
株式会社フォーウェイでは、書籍をマーケティングに活用する「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
不動産業における効果的な集客施策として、これまでに多くの不動産会社が書籍を出版し、ブランディングと売上拡大の両面で成果を上げています。
中長期的に安定した集客と売上アップを目指すなら、ぜひ書籍出版をご検討ください。
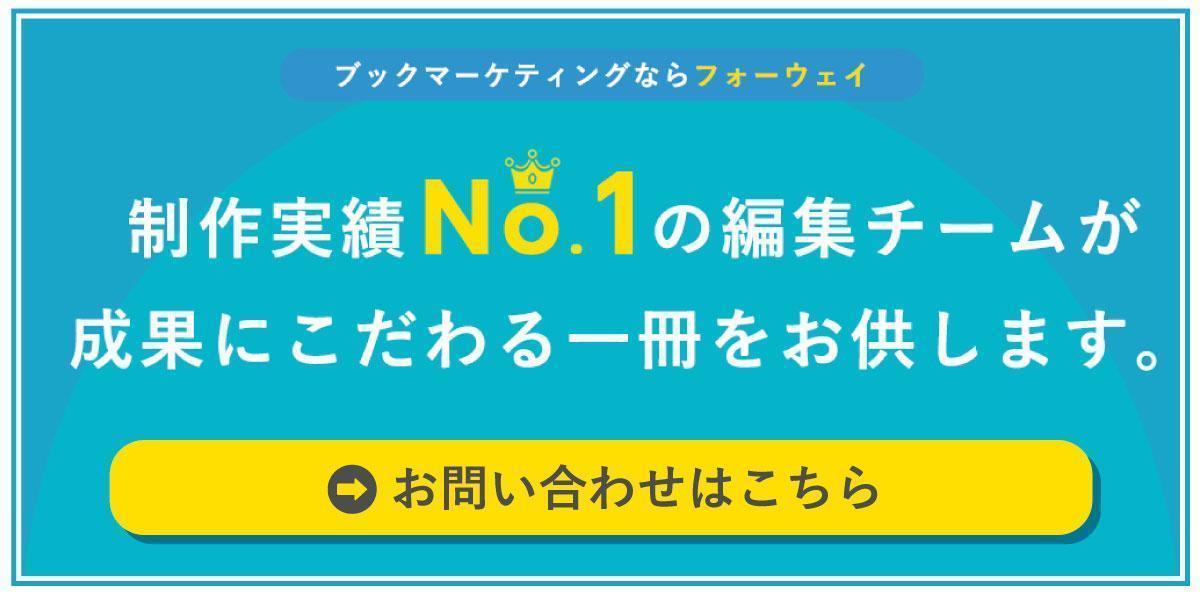

ビジネスを成長させるうえで、「売上を伸ばすこと」は業種や企業規模を問わず、すべての企業に共通する目標です。
しかし実際は、「広告を出しているのに反応が薄い」「キャンペーンを打ってもすぐ効果が切れる」「新規客は取れてもリピーターが定着しない」など、さまざまな課題に直面している企業も多いのではないでしょうか。
売上が伸び悩むと、「もっと目立つ広告を出そう」「話題になる企画で一発逆転を狙おう」とつい派手な手法を考えてしまいますが、本当に大切なのは、売上を構成する要素をきちんと理解し、自社に合った施策を行うことです。
本記事では、売上の基本構造を解説したうえで、実際に成果につながる具体的な施策や成功事例を紹介します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉売上を構成する3つの要素

売上を伸ばすためには、闇雲に施策を打つのではなく、まず「売上の構成要素とは何か」という基本構造を理解することが重要です。
売上は次のように、3つの要素の掛け算で決まります。
それぞれの意味は、以下の通りです。
| 売上を構成する要素 | 意味 |
| 客数 | どれだけ多くの顧客が商品やサービスを購入してくれるか |
| 客単価 | 1回の購入でどれだけの金額を使ってくれるか |
| 購買頻度 | 1人の顧客がどれくらいの頻度で繰り返し購入してくれるか |
この3つの要素のどれか1つだけを高めれば良いのではなく、バランスよく改善していくことが安定的な成長につながります。
「今、どの要素が弱いのか」「どこに注力すれば効果があるのか」を見極めて、適切な施策を打つことが売上向上の第一歩です。
◉【目的別】売上を上げるための具体的な施策
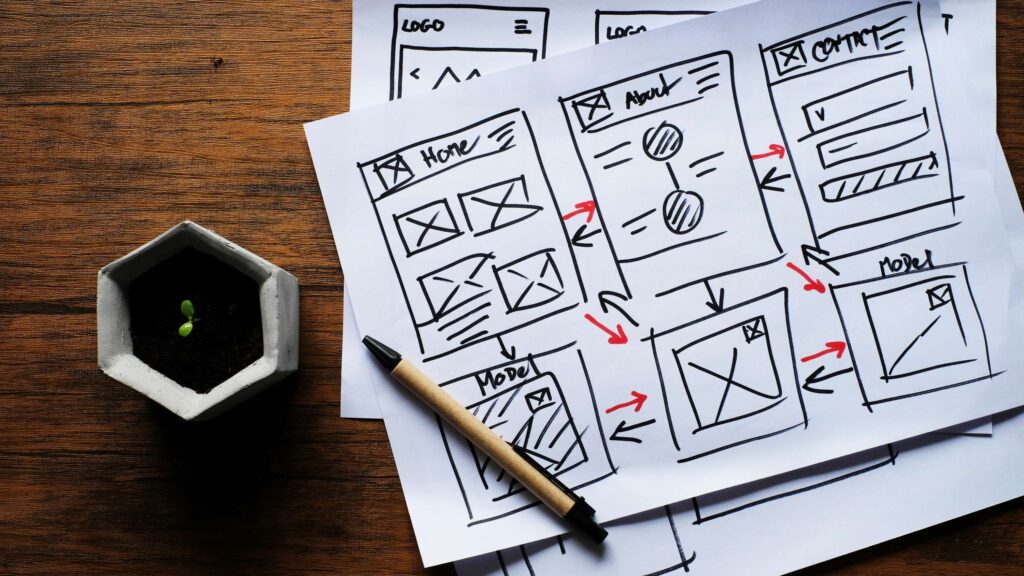
一口に売上を上げるといっても、業種や事業内容、競合の状況、顧客層など、各企業が置かれている状況によって有効な施策は変わってきます。
そのため、目的別に適切な施策を選ぶことが重要です。
ここでは、次の4つの視点から効果的な施策例を紹介します。
・新規顧客を獲得する施策
・既存顧客の離脱を防止し、リピート率を高める施策
・客単価を向上させる施策
・商品・サービスの価格見直しや価値の訴求の施策 |
以下で順番に見ていきましょう。
◉-1、新規顧客を獲得する施策
売上を伸ばすには、まず「買ってくれる人の数」を増やす必要があります。
ただし、単に広告の数を増やしたり、目立つキャンペーンを打ち出したりするだけでは、思うような成果は得られません。
本当に重要なのは、「誰に届けるのか」「どのように自社の商品やサービスを知ってもらい、購入してもらうのか」を戦略的に考えることです。
以下では、多くの業種で活用できる基本的な新規顧客の獲得施策を紹介します。
◉-1-1、多角的なチャネルを活用する
今の時代、顧客との接点は多様化しています。
Web広告やSNS、YouTube、LINE公式アカウント、オウンドメディアなど、情報を届けるためのチャネル(経路)はさまざまです。
そのため、ただ一つのチャネルに依存するのではなく、自社の商品やサービスに合ったチャネルを選び、それぞれの特性を活かした発信をすることが重要です。
たとえば、以下のようにチャネルを使い分けることができます。
・BtoC商材:SNSやLINE公式アカウントなど、顧客と密接にコミュニケーションをとれる媒体でこまめに情報を発信
・BtoB商材:信頼性を高めるオウンドメディアでの記事発信 |
もし新規顧客の獲得がうまくいかない場合は「今の集客経路に頼り切っていないか」を見直してみると良いでしょう。
◉-1-2、初回限定特典やキャンペーンを実施する
初めて商品を購入したりサービスを利用したりする際、多くの新規顧客は「本当に信頼できるのか」「失敗したくない」という不安を抱えています。
その不安を和らげるために有効なのが、初回限定特典やキャンペーンです。
たとえば、次のような施策を行うと、新規顧客の心理的ハードルを下げることができます。
・初回購入30%オフキャンペーン
・無料体験期間の提供
・お友達紹介で両者にクーポン進呈 |
このような特典があることで、「まずは一度使ってみようかな」という気持ちになりやすく、新規顧客の獲得につながります。
◉-1-3、イベント・セミナーを開催する
対面・オンラインを問わず、イベントやセミナーは新規顧客との最初の接点として有効です。
参加者に直接、商品やサービスの魅力を伝えられる場となります。
たとえば、以下のような施策が考えられます。
・店舗型ビジネス:試食会や体験会、トークイベントなど、実際に足を運んでもらう形式
・オンライン型ビジネス:無料セミナーや使い方講座、インスタライブ配信など、気軽に参加できる形式 |
実際に商品やサービスに触れてもらう機会を設けることで、その魅力が伝わりやすくなり、購入意欲が自然に高まります。
◉-2、既存顧客の離脱を防止し、リピート率を高める施策
新規顧客の獲得はもちろん大切ですが、すでに商品やサービスを購入・利用してくれた既存顧客との関係を維持し継続していくことも重要です。
マーケティングの世界では、「新規顧客を獲得するコストは既存顧客を維持するコストの5倍かかる」ともいわれているので、既存顧客にリピート購入してもらうことはコストパフォーマンスにも優れています。
以下では、既存顧客の離脱防止とリピート率向上のために有効な施策を紹介します。
◉-2-1、定期的なコミュニケーションをとる
一度は商品やサービスを購入・契約してくれた顧客でも、その後フォローしないままにしておくといずれ離れていってしまいます。
だからこそ、顧客との定期的な接点をつくることが、関係を維持し、長くつながるための重要なポイントです。
たとえば、次のようなフォローアップ施策があります。
・購入後1か月、3か月、6か月後のフォロー
・メール誕生日や記念日に合わせたメッセージ送付 |
顧客に「しっかりサポートしてくれる会社」という印象を与えることができれば、信頼感や親近感が増して離脱率を下げることができます。
◉-2-2、ポイント付与や会員ランク制度を設ける
「継続することでお得になる仕組み」をつくると、顧客は自然と離れにくくなります。
たとえば、次のような仕組みがあります。
・購入金額に応じたポイント還元
・上位ランク会員限定の特典(先行販売、限定イベント、割引率アップなど) |
こうした仕組みにより、顧客の中に「またここで買おう」と思わせる心理が生まれ、リピート購入へとつながりやすくなります。
◉-2-3、コンテンツやコミュニティを提供する
商品やサービスを「一度購入して終わり」にしないことが、リピートやファン化のポイントです。
そのために有効なのが、役立つ情報や楽しめるコンテンツの提供、そして顧客同士がつながれるコミュニティをつくることです。
たとえば、次のような施策が考えられます。
・商品活用ノウハウ記事や動画の発信
・開発秘話やQ&A・お悩み解決コンテンツの発信
・ファンが交流できるコミュニティの提供(SNSグループやリアルイベントなど) |
このようなコミュニティ型の施策によってファン化が促進され、長期的な売上向上につながります。
◉-2-4、定期的なキャンペーンやイベントを行う
リピート購入をしてもらうためには、顧客に「今買う理由」を感じてもらう必要があります。
その手段として効果的なのが、期間限定のキャンペーンやイベントの開催です。
たとえば、次のような施策が挙げられます。
・毎月内容が変わる「月替わりキャンペーン」
・創業祭や季節ごとのイベント(バレンタイン、夏祭り、年末感謝祭など) |
定期的なキャンペーンやイベントを通じて「今買う理由」を作り出すことで、リピート率の向上や顧客の購買意欲アップにつながります。
◉-2-5、メールやSNSでリマインド訴求を行う
一度購入した商品であっても「また買おう」と思い出す機会がなければ、リピート購入にはつながりません。
そこで、次のようなリマインド施策を行うことが有効です。
・購入から一定期間が経過した顧客に向けた再購入案内メールの送付
・SNSでのおすすめ投稿 |
特に、サブスクリプション以外の商品では、「購買のタイミングを促す」ことが重要です。
適切なタイミングでのリマインドは、自然なリピート購入へとつながります。
◉-2-6、サブスクリプションや定期購入プランを導入する
リピート購入が見込まれる商品やサービスは、サブスクリプション(定期販売)モデルへの転換や追加導入が効果的です。
たとえば、次のような方法が考えられます。
・消耗品の定期便サービス
・美容・健康商品などのサブスクリプションプラン |
「毎回購入を判断する手間」を不要にすることで、継続的な売上につながります。
◉-3、客単価を向上させる施策
売上を上げるためには、新規顧客の獲得やリピートの促進だけでなく、客単価(一人ひとりの顧客の購入金額)を高めることも重要です。
以下では、客単価を上げるための代表的な施策について紹介します。
◉-3-1、上位の商品を提案する(アップセル)
アップセルとは、顧客が購入を検討している商品よりも、より高価格・高付加価値な商品に誘導する販売手法です。
顧客が検討中の段階で提案できるためタイミングで提案するため、受け入れてもらいやすいのがポイントです。
たとえば化粧品の場合、普通サイズを見ている顧客に、「たっぷり使える大きなサイズ」や「特別な成分が入っているタイプ」をすすめることがあります。
また、コンサルティングサービスでは、1回だけの相談ではなく、6か月続けて受けられるプランを案内することもアップセルの一つです。
「このプランにすると、こんな良いことがありますよ」と具体的に伝えて、顧客に納得して選んでもらうことで、アップセルが成功しやすくなります。
◉-3-2、関連商品を提案する(クロスセル)
クロスセルは、メインの商品に加えて、関連性のある別の商品を提案する手法です。
たとえば、次のようなシーンが考えられます。
・スマートフォンを購入した顧客にケース・ガラスフィルムをすすめる
・カフェでドリンクを注文した顧客にスイーツをすすめる |
クロスセルが上手に設計されていると、顧客満足度も高まり、リピートにもつながりやすくなります。
◉-3-3、3段階の価格設定を行う
「松・竹・梅」のように、3つの価格帯を用意すると、真ん中かそれより少し高い商品やサービスが選ばれやすくなります。
これは、人は選ぶときに「一番安いものや高すぎるものは避けて、ちょうどよさそうな中間を選ぶ」という心理が働きやすいためです。
たとえば、以下のような例があります。
・フィットネスジムで「ライトプラン」「スタンダードプラン」「プレミアムプラン」と分ける
・オンライン学習で「動画視聴のみ」「動画+質問サポート」「動画+質問+個別指導」のように段階をつける
・美容室で「カットのみ」「カット+トリートメント」「カット+トリートメント+ヘッドスパ」の3つのコースを用意する |
このように価格の段階をしっかり設計することで、「もっとも安いものではなく、中間か上のものを選びたくなる」という顧客心理を活用することができます。
◉-3-4、セット商品で「ついで買い」を促す
「まとめて買うとお得」「セットにすると使いやすい」といった魅力を伝えることで、1回の買い物での購入金額を高くすることができます。
特に、日用品や食品、化粧品、文房具など、何度も使うような消耗品との相性がよく、たとえば次のような工夫があります。
・洗顔・化粧水・美容液のスキンケア3点セット
・3個買うと1個無料になるキャンペーン |
このようなセット販売は、「お得だから買っておこう」という気持ちを引き出しやすく、リピート購入にもつながりやすい方法です。
◉-4、商品・サービスの価格見直しや価値の訴求の施策
売上を上げるためには、その3つの要素である「客数」「客単価」「購入頻度」を高める工夫が必要です。
それに加えて「価格そのものの見直し」と「その価格に見合った価値をどう伝えるか」という視点を見逃してはいけません。
適正価格を設定し、納得してもらえる価値があることを訴求できれば、価格競争に巻き込まれることなく、安定した売上につながります。
以下では、これに関連するいくつかの施策を紹介します。
◉-4-1、価値に見合った価格設定を行う
売上アップの施策として「価格を上げる」ことは選択肢の一つですが、安易な値上げは顧客離れを招き、逆に売上が低下するリスクもあります。
そこで大切なのは、「商品の価値を高めたうえで、その価値に見合った価格に見直す」という考え方です。
たとえば、次のような付加価値の向上が考えられます。
「この価格なら仕方ない」ではなく「この値段でも納得できる」と感じてもらえるようにすることが、価格競争を避けて、質の高い顧客を集めるポイントです。
◉-4-2、専門性・信頼性を高める
売上を伸ばすには、ただ価格を上げるのではなく、「この人からなら、この会社からなら、その価格でも納得できる」と感じてもらうことが大切です。
たとえば、同じ商品やサービスであっても、専門的な知識や豊富な経験がある人や、実績があり顧客から高い評価を受けている会社であれば、信頼されやすくなります。
こうした専門性や信頼性は、ただ持っているだけでは意味がなく、相手にしっかり伝わるように見せる工夫が必要です。
◉-4-2-1、書籍を出版する
専門性や信頼性を高める手段の一つが「書籍の出版」です。
「書籍の出版」は、単に広報手段になるだけではなく、「この分野といえばこの人・この会社」と思ってもらえる立ち位置をつくる強力なブランディング手段です。
書籍を出版することで、「この人・この会社の意見は信頼できる」「安心して任せられそう」といった信頼感が自然と生まれます。
結果的に自社の商品の購入やサービスの申し込みにつながりやすくなり、成約率の向上や客単価アップにもつながります。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。
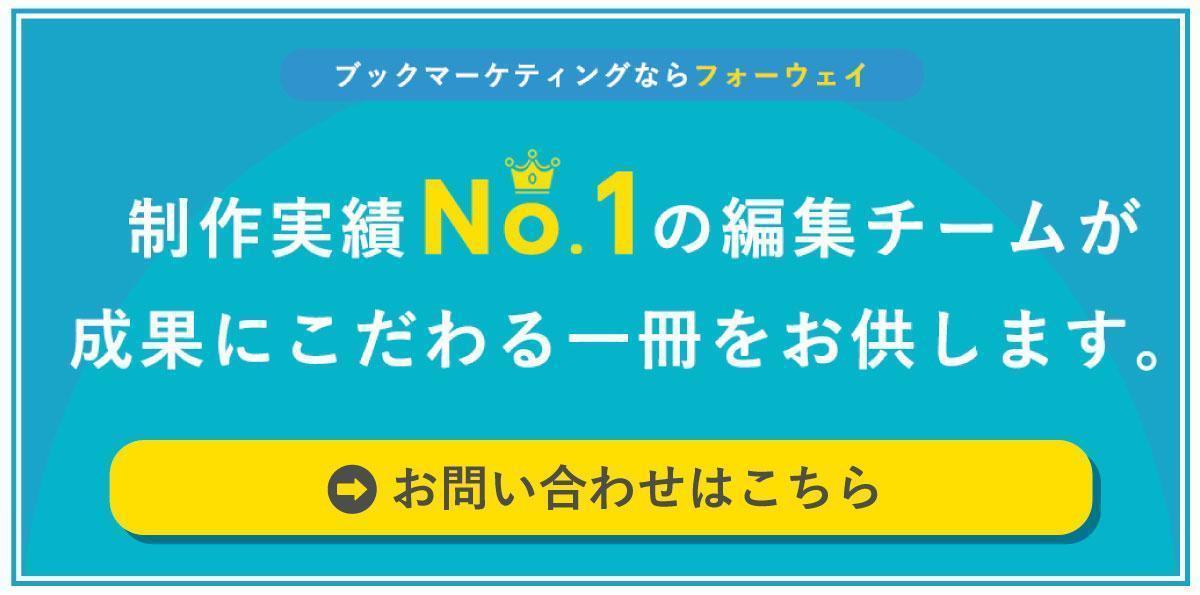
◉書籍活用で売上アップを実現した成功事例紹介
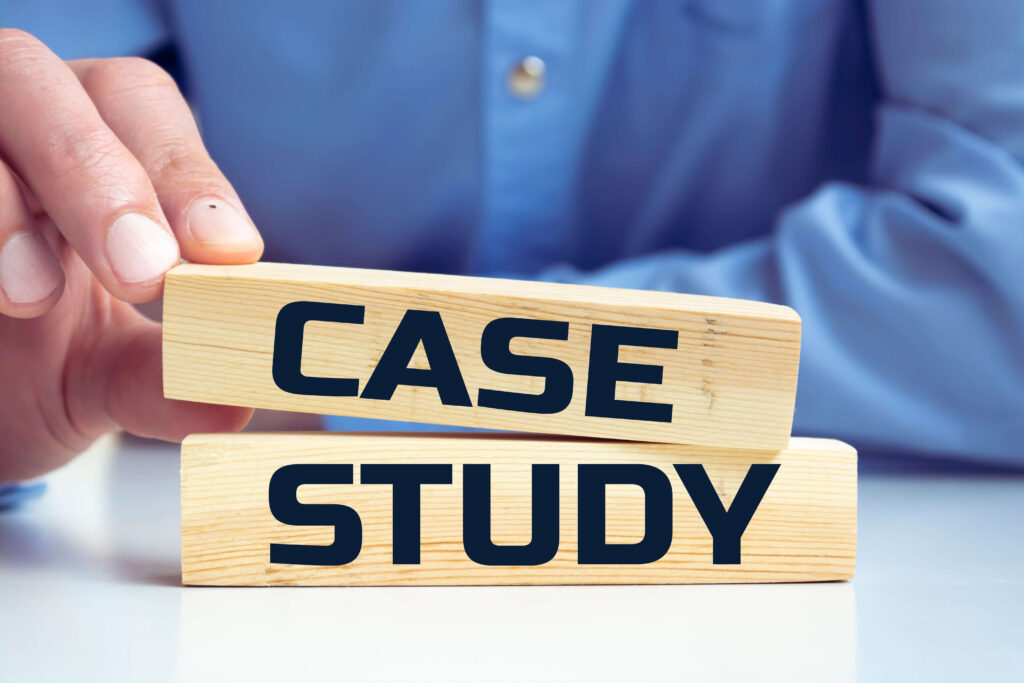
ここでは、実際に書籍活用によって売上アップを実現した成功事例を紹介します。
・事例1:書籍で専門性を伝え、売上が上がった保険代理店の事例
・事例2:出版によって同業他社と差別化し、売上を大きく伸ばした成功事例 |
それぞれの事例を詳しく見ていきましょう。
◉-1、事例1:書籍で専門性を伝え、売上が上がった保険代理店の事例
保険代理店の経営者は、新規事業の保険代理店のコンサル契約獲得のためには自社の専門性を訴求する必要があると考えて書籍出版を行いました。
従来からSNSで情報発信は行っていましたが、1つ上のステージに上るための手法として書籍を選びました。
書籍の中で、保険業界では当たり前の「成果報酬型」を「一律報酬型」に変更すべきだという持論を展開して、注目度を上げることに成功。
出版後は業界内での評価が変わり、セミナーの講師として招かれる機会も増え、コンサルティング契約も3件の成約につながりました。
さらに本業の保険契約でも大口案件を受注し、全体として売上が大きく伸びる結果となりました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、事例2:出版によって同業他社と差別化し、売上を大きく伸ばした成功事例
ある会計事務所の経営者は、自身の海外勤務経験で培った知識と専門性を広く伝えるために書籍を出版しました。
この出版によって、「外資系企業や国際案件にも対応できる公認会計士」としての認知が顧客企業に広まり、他の会計事務所との差別化に成功しました。
さらに、専門家としての信頼性や権威性を強く印象付けることができたことで、価格交渉の場面でも値下げを要求されることがなくなったといいます。
結果として、売上の大幅な増加につながりました。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉-3、事例3:医師に特化した書籍を出版し、売上を飛躍的に伸ばした成功事例
ある不動産投資サービス企業は、高収入で税負担の大きい医師層をターゲットに、SNSやWeb広告で訴求を試みていましたが、成果が出ていませんでした。
打開策として、「医師にとって最適な節税策は不動産投資」というテーマで書籍を出版。
企画からプロモーションまでを綿密に設計し、多くの医師に書籍を手に取ってもらうことができました。
結果として、読者からの反響だけで10億円以上の売上を創出し、会社の業績は前年比2倍以上に成長するという圧倒的な成果を上げました。
また、書籍を出版して終わりではなく、継続的なプレゼントキャンペーンにも活用。
特に医師向けのマーケティング(ドクターマーケティング)では、一度のキャンペーンで100件以上のリードを獲得し、書籍が長期的に機能する「営業資産」として活躍しています。
出版前は無料で受けていた相談も、問い合わせ増加に伴い有料化にも成功しました。
その結果、本気で購入を検討する顧客だけが残り、営業の効率も大きく改善されました。
◉【まとめ】書籍出版によって長期的な顧客獲得と売上増を目指そう!
この記事では、売上を構成する3つの基本要素と、売上を上げるための13の施策を目的別に詳しく解説しました。
特に注目したいのが、専門性と信頼性を強く印象づける「書籍出版」という施策です。
実際の成功事例を通じて、書籍が他社との差別化や顧客からの信頼獲得にどれほど効果的かを紹介しました。
「書籍出版」は、短期的な販促施策とは異なり、中長期的に商品・サービスの価値を高めつつ、安定した売上を実現するために有効です。
株式会社フォーウェイでは、書籍をマーケティングに活用する「ブックマーケティングサービス」を行っています。
長期的に顧客を獲得し売上を上げるための施策として、ぜひ書籍出版をご検討ください。
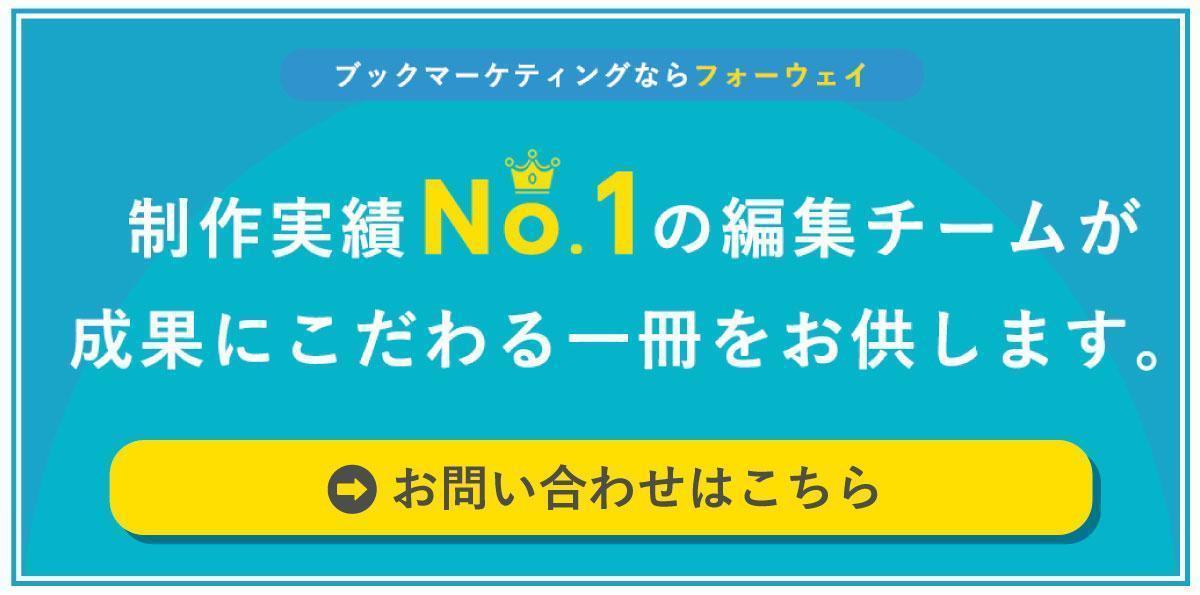

売上を高めるうえで欠かせないのが「客単価」の分析と改善です。
客単価とは、1人の顧客が1回の取引で支払う平均金額のことを指します。
一見単純な指標に思えるかもしれませんが、「顧客が何をどのように買っているか」「自社の商品・サービスの価値がどれだけ適切に伝わっているか」といった重要な情報が詰まっています。
たとえば、同じ売上金額でも、少数の顧客が高額商品を購入しているのか、それとも多くの人が少額ずつ買っているのかで、事業の方向性や戦略は大きく変わるでしょう。
客単価に注目することで、売上の内訳がはっきり見えてくるため、「どのターゲット層にどうアプローチするか」「どの商品を主力にするか」といった判断もつきやすくなります。
本記事では、客単価の定義や計算方法をわかりやすく解説し、分析によって得られるメリットや具体的な単価アップの施策について紹介します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉客単価とは?定義と計算式をわかりやすく解説

まず最初に、客単価とは何かについて説明しておきましょう。
客単価の定義と計算式は、次の通りです。
◉-1、客単価の定義
客単価とは、「1人の顧客が1回の購入で支払う平均金額」のことです。
ECサイトや飲食店、小売店などのさまざまな業種で活用されている代表的な経営指標の一つです。
顧客1人あたりの購買金額を把握することで、経営状況や販売施策の効果を客観的に評価できるようになります。
◉-2、客単価の計算式
客単価の計算式は、次の通りです。
たとえば、1日の売上が50万円で、来店客数が250人だった場合、「500,000円÷250人=2,000円」と計算できます。
なお、曜日や時間帯によって売上や販売量に大きな差がある場合は、分析対象の期間を「曜日別」や「時間帯別」に区切ることで、より精度の高い分析が可能になります。
ここで注意すべきなのは、「客単価」は実際に購入した顧客のみを対象として算出される点です。
つまり、いくら多くの人を集客しても、購入に至らなければ売上には結びつかず、客単価にも反映されません。
一見当たり前に思えることですが、プロモーションやマーケティング戦略を立てるうえで重要な視点です。
◉客単価を分析するメリット

では、客単価を分析するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
一般的に、次の3つのメリットがあります。
・売上向上の具体的な戦略立案に役立つ
・ターゲット顧客ごとにマーケティング最適化を図れる
・他社との差別化ポイントを把握しやすくなる |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、売上向上の具体的な戦略立案に役立つ
「売上が思うように伸びない」「最近落ち込み傾向にある」といった場合に、客単価を分析すると原因を探る手がかりになります。
単に売上金額だけを見ていても、その内訳がわからなければ、有効な対策を講じることはできません。
たとえば、売上が前月より20%減少したとき、この数字だけでは、何が問題だったのかはわかりません。
しかし、客単価のデータを確認すれば、「来店客数は変わらないのに、1人あたりの購入金額が減っている」といった具体的な傾向が浮き彫りになります。
逆に、「客単価は変わらないのに客数が減っている」という傾向が把握できたときは、集客施策の見直しが必要になります。
◉-2、ターゲット顧客ごとにマーケティングの最適化を図れる
顧客単価の分析は、単に顧客一人あたりの購入金額がわかるだけでなく、マーケティング活動を最適化するためにも役立ちます。
特に、ターゲット顧客ごとの客単価を比較することで、より効果的なマーケティング施策を立てるための方向性がつかめます。
たとえば、商品カテゴリー別に客単価を分析すれば、売上に貢献しているジャンルを特定することが可能です。
また、性別・年齢・地域・購入頻度・購買チャネルなど、さまざまな属性で顧客を分類し、それぞれの客単価を算出することで、「誰に何をどのように訴求すればよいか」がより明確になります。
このように、客単価は「誰に何を売るか」という視点を磨くための重要な指標といえます。
◉-3、他社との差別化ポイントを把握しやすくなる
客単価の分析は、自社の販売戦略や商品・サービスの市場評価を把握するうえで有効な手段です。
特に、同業他社と比較することで、自社の強みや弱み、そして競合との差別化ポイントを客観的に見極めることができます。
たとえば、同じ業種・同規模の企業と比べて自社の客単価が低い場合、価格設定や販売手法、提案内容に改善の余地があると考えられます。
一方で、高い客単価を維持できているのであれば、それは顧客が自社の商品やサービスに対して高い価値を認識している証拠です。
このような分析を通じて、「なぜ選ばれているのか」「どこで差別化できているのか」を明らかにすることができ、今後の戦略立案にも役立ちます。
▶︎差別化戦略の詳細については、関連記事【差別化戦略の成功の秘訣ーメリットやデメリット、成功事例とは!?】もあわせて参考にしてください。
◉客単価を上げるための具体的な施策
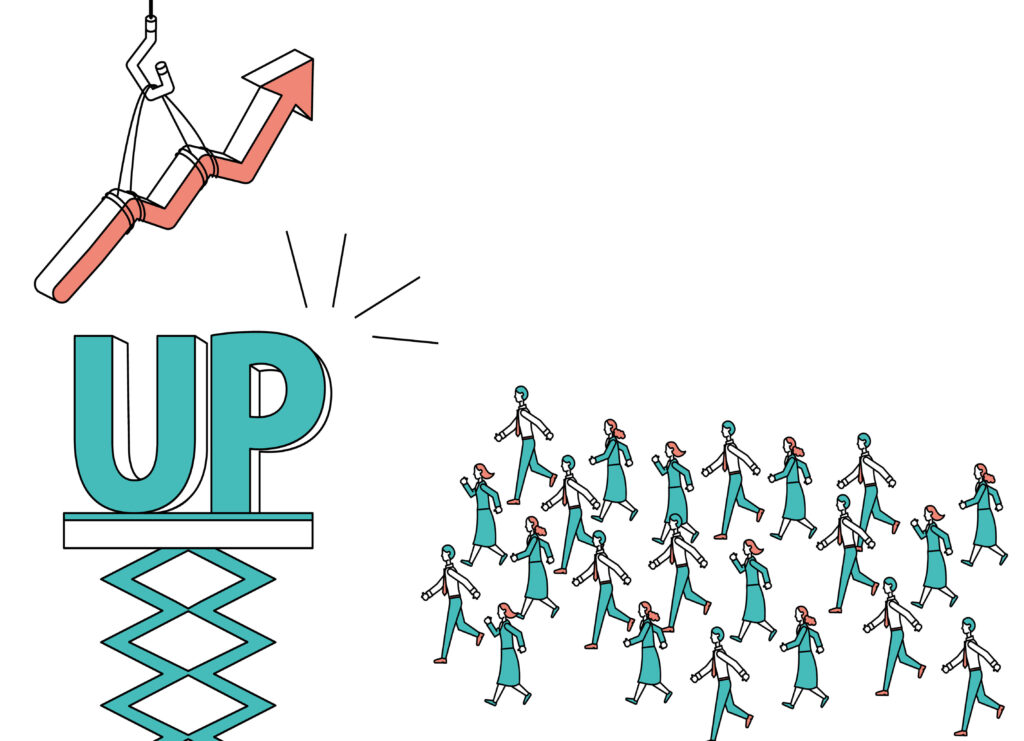
客単価を上げる具体的な施策として、次の4つが挙げられます。
・商品・サービスの設計で客単価を引き上げる施策
・販売方法で客単価を引き上げる施策
・購入しやすさを高めて客単価を引き上げる施策
・価値の訴求によって商品の魅力を高め、客単価を引き上げる施策 |
どのような施策なのか、詳しく見ていきましょう。
◉-1、商品・サービスの設計で客単価を引き上げる施策
商品やサービスそのものの価値を見直すことで、無理なく客単価を引き上げることができます。
顧客に「この金額を払っても良い」と納得して支払ってもらえるような仕組みを作ることで、値引きに頼らず安定的に売上を伸ばすことが可能になります。
◉-1-1、商品単価を上げる
客単価を引き上げる方法として、まず検討できるのが「商品単価の引き上げ」です。
一番シンプルな方法ですが、ただ価格を上げるだけでは「値上げ」と受け取られ、購入をためらわれる可能性があります。
そのため、「価格の引き上げ」と「提供価値の向上」をセットで行うことが重要です。
たとえば、素材の品質を高めたり、パッケージデザインを刷新したり、購入後のサポート体制を強化したりすることで、価格に見合う価値を感じてもらうことができます。
価格以上の満足感を提供することで、自然なかたちで商品単価を上げることが可能になります。
◉-1-2、高価格帯商品や限定品を追加する
顧客の選択肢の中に、あえて選びたくなるような高価格帯の商品や限定商品を加える方法も有効です。
すべての顧客が購入してくれなくても、一部の顧客が選んでくれるだけで全体の客単価を引き上げる効果があります。
たとえば、オーダーメイド対応品や季節限定品、数量限定品などがあります。
◉-1-3、購入特典を用意する
購入特典を用意することで、顧客の購買意欲を高め、自然と客単価の向上を促すことができます。
たとえば、「5,000円以上のご購入でオリジナルグッズをプレゼント」や「購入者限定で次回使えるクーポンを進呈」といった施策は、顧客にとって「もう少し買えば得をする」という動機づけになり、結果的に購入金額の底上げにつながります。
◉-2、販売方法で客単価を引き上げる施策
商品の販売手法を工夫することで、顧客がより自然に多くの商品や高価格帯の商品を選ぶように促すことができます。
ポイントは「お得感」や「選びやすさ」を意識した販売設計です。
◉-2-1、セット販売を導入してまとめ買いを促す
セット販売(バンドル販売)を導入することで、まとめ買いを促し、客単価の向上を図ることができます。
これは、複数の商品を組み合わせて一つのパッケージとして提供する販売手法です。
たとえば、飲食店では「メイン+ドリンク+デザート」のセット、小売店では「靴下3足組」といった組み合わせが考えられます。
また、「2点以上の購入で10%割引」「5,000円以上の購入で送料無料」というやり方もあります。
顧客にとっては単品購入よりもお得感があり、「せっかくならもう1点」といった追加購入につながりやすい点がメリットです。
◉-2-2、3段階の価格設定を行い、中価格帯の選択を促す
「松・竹・梅」のように、3つの価格帯を用意する方法です。
人は、最も安い選択肢には品質面で不安を感じやすく、最も高価な選択肢には手が届きにくいと感じる傾向があります。
その結果、無意識のうちに中間の価格帯を「妥当な選択」として選ぶ心理が働きます。
この心理を活用し、最も販売したい商品を中価格帯(竹)に設定し、その上下に高価格(松)と低価格(梅)の商品を配置することで、中価格帯の商品が選ばれやすくなります。
◉-2-3、上位商品を提案してアップセルを狙う
アップセルとは、顧客が検討している商品よりも上位のグレードや価格帯の商品を提案し、購入単価を引き上げる手法です。
「少しの追加予算で、より高品質な商品が手に入る」といった納得感を与えることで、顧客の選択を自然に上位商品へと誘導できます。
たとえば、美容院では「通常カット」に加えて「トリートメント付きプラン」を提案する、家電販売では「標準モデル」ではなく「高機能モデル」を紹介するといった施策が該当します。
ただし、過度な提案は押し売りと受け取られるリスクがあるため、顧客のニーズや状況を正確に把握し、それに基づいた適切な提案を行うことが重要です。
◉-2-4、関連商品を提案してクロスセルを狙う
クロスセルは、顧客が購入を検討している商品と一緒に使うと便利な商品を併せて提案する販売手法です。
たとえば、スマートフォンを買う顧客に、ケースや保護フィルム、充電器などを同時に提案するといったイメージです。
また、ECサイトなどでよく見られる「この商品を購入した人は、こちらの商品にも興味を持っています」といったレコメンド表示も、クロスセルの一種です。
◉-3、購入しやすさを高めて客単価を引き上げる施策
魅力的な商品やサービスを提供していても、顧客が「買いにくい」と感じるようであれば、客単価は伸び悩んでしまいます。
購買体験の中でストレスや不便さを感じさせないことは、結果として購入点数や売上の増加につながります。
◉-3-1、決済の選択肢を増やす
現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など、幅広い決済方法に対応することで、顧客が感じる購入時のハードルを大きく下げることができます。
特に近年はキャッシュレス決済を好む顧客が増加しており、対応していない場合は「買いたくても買えない」状況を招き、貴重な購買機会を失う可能性があります。
◉-4、価値の訴求によって商品の魅力を高め、客単価を引き上げる施策
顧客が高価格商品を購入するかどうかは、その商品に対する「納得感」や「共感」が得られるかどうかに左右されます。
価格が高い商品ほど、「なぜこの値段なのか」「価格に見合う価値があるのか」をきちんと伝える必要があります。
そのためには、商品そのもののスペックや特徴だけでなく、背景にあるストーリーやブランドの想いを、ターゲット顧客に合ったメディアでわかりやすく伝えることが重要です。
◉-4-1、SNSやホームページで商品の魅力をわかりやすく伝える
SNSや公式サイトでは、商品の魅力やこだわりをビジュアルでわかりやすく伝えることができます。
特にInstagramやX(旧Twitter)などのプラットフォームでは、写真や動画を活用して、使用シーンやビフォー・アフターの変化などを視覚的に訴求することが可能です。
「これならこの価格でも納得」と思ってもらうことができれば、購入につながる可能性が高くなります。
▶︎SNS運用のやり方については、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】もあわせて参考にしてください。
◉-4-2、書籍の制作・配布で商品の魅力や想いを届ける
SNSや公式サイトでは伝えきれない深い世界観やブランドの想いを伝える手段として効果的なのが、書籍による価値の訴求です。
書籍は、社会的信頼性の高いメディアであることに加えて、丁寧に作られた印象を与えるため、顧客との信頼関係の構築に役立ちます。
また、書籍は来店特典や購入特典としても活用できるため、商品やサービスのブランドイメージの構築と販売促進の両方に効果的です。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。
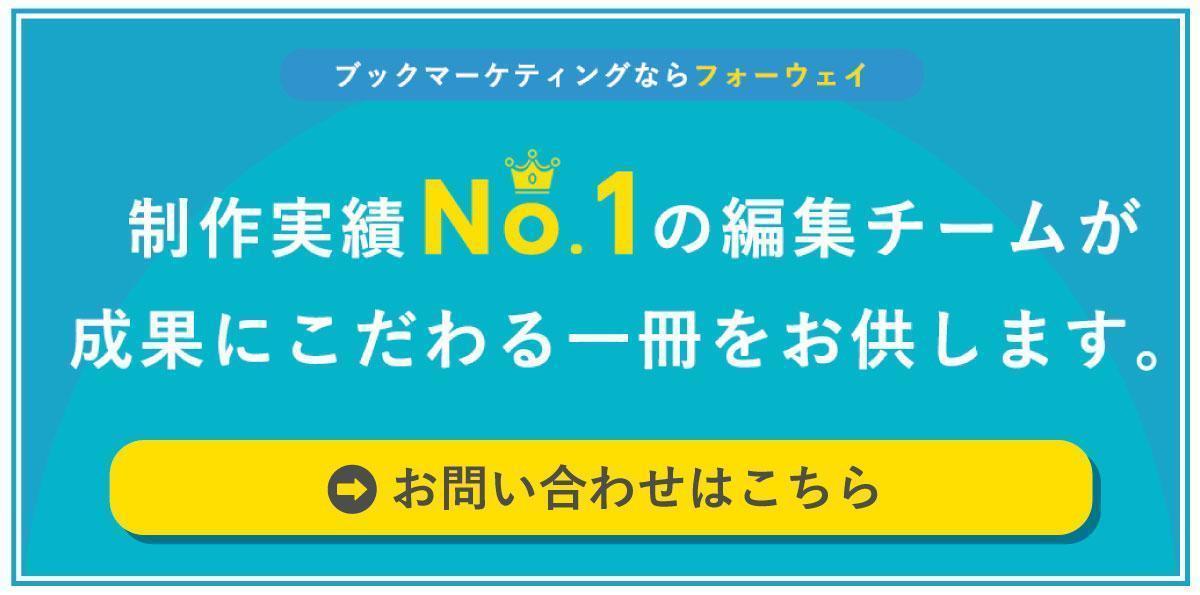
◉書籍出版によって客単価向上を実現した事例

実際に書籍を出版して客単価の向上を実現した事例を2つ紹介します。
・事例1:書籍出版で信頼を獲得し、法人保険の大型契約を実現した保険代理店の成功事例
・事例2:書籍出版を通じて専門性を可視化し、高単価案件の獲得に成功した公認会計士の事例 |
以下で、それぞれについて見ていきましょう。
◉-1、事例1:書籍出版で信頼を獲得し、法人保険の大型契約を実現した保険代理店の成功事例
法人保険を専門に取り扱う保険代理店の経営者は、業界の現状や課題を明らかにしながら、自社で実践している「一律報酬型」の給与制度が人材育成と業績向上に有効であるという持論をまとめた書籍を出版しました。
この書籍は業界内で大きな注目を集め、多くの反響を獲得。
出版をきっかけに顧客からの問い合わせが増加し、保険に関する相談だけでなく、経営理念や組織づくりに関する助言を求められるまでになりました。
企業との信頼関係が深まり、自社の価値観やスタンスが明確に伝わったことで、顧客視点に立った本質的な保険提案が可能となり、結果として法人保険の大型契約の受注を実現しました。
1社あたりの契約単価が上昇し、全体の売上拡大にもつながる成果を上げています。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、事例2:書籍出版を通じて専門性を可視化し、高単価案件の獲得に成功した公認会計士の事例
ある会計事務所の代表を務める公認会計士は、自身の豊富な海外勤務経験をもとに「海外ビジネス展開におけるリスク管理とマネジメント戦略」に関する専門書を出版しました。
この出版によって、「海外進出を支援できる高い専門性を持つ会計士」という専門家としての立場が確立され、顧客にもその実力が具体的に伝わるようになりました。
その結果、主力業務である海外進出企業向けの監査支援やアドバイザリー業務で、これまで見られたような過度な価格交渉に応じる必要がなくなったといいます。
提案段階からプランニングを一任されるケースが増え、業務そのものの価値が適切に評価されるように。
自然と客単価も向上し、事務所全体の売上アップにもつながっています。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉【まとめ】価値訴求による客単価向上を実現するために「書籍出版」を活用しよう!
この記事では、客単価の定義や計算方法をはじめ、分析によって得られるメリットや単価を引き上げるための具体的な施策、さらには成功事例までを幅広く紹介しました。
売上の向上を目指す経営者やマーケティング担当者にとって、「客単価」は単なる数値ではなく、顧客理解・商品戦略・価値訴求のすべてにおいて起点となる重要な指標です。
きちんと分析を行うことで、感覚に頼らない論理的で持続的な売上成長を実現することができるでしょう。
そして近年、客単価向上の手段として注目されているのが、「書籍出版」によるマーケティングです。
書籍は、商品の魅力や特長を伝えるだけでなく、企業の歴史や開発の裏側、ブランドに込めた想いなど、より深い価値を物語として伝えることができます。
さらに、流通を通じた新規顧客との接点づくりや、既存顧客との信頼関係の強化にもつながる有効な施策です。
株式会社フォーウェイでは、「ブックマーケティングサービス」を提供しており、書籍出版を通じて企業の価値や想いを発信するサポートをしています。
客単価を高める施策の一つとして、ぜひ「書籍出版」をご検討ください。
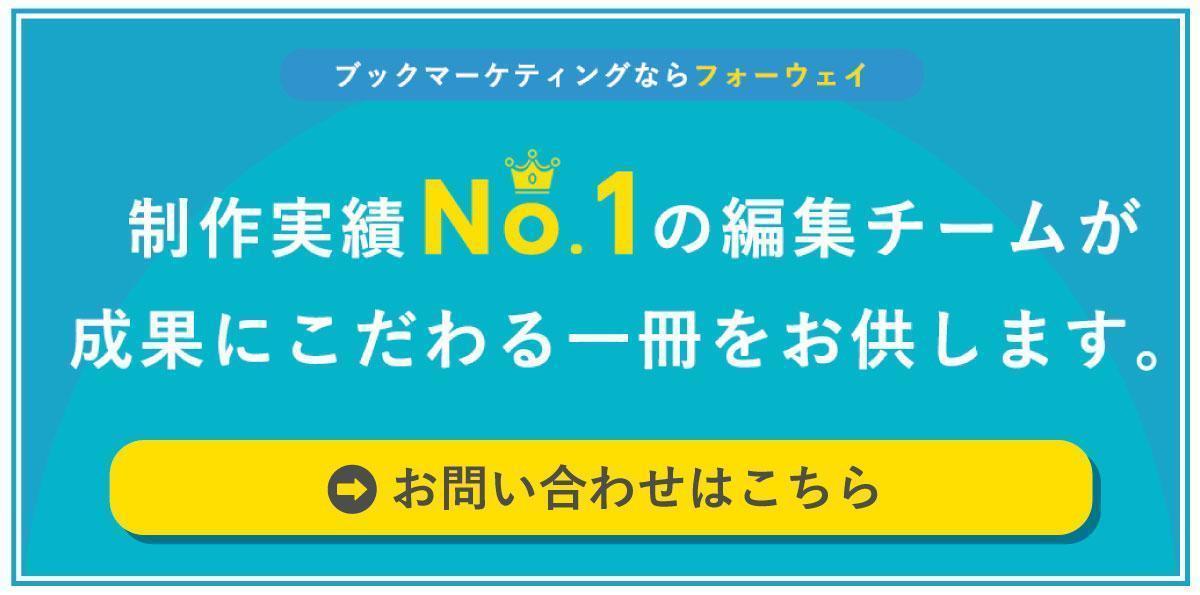

価格競争から抜け出せず、「価格を下げなければ売れない」と悩んでいる企業は少なくありません。
特に、商品やサービスの違いが明確に出しにくい業界では、価格競争に巻き込まれてしまうリスクが常につきまとっているといっても過言ではありません。
しかし、価格の安さだけで選ばれる状態が続くと、企業の利益もブランドも徐々にすり減り、衰退していってしまいます。
そうならないためにも、競合他社との価格競争から脱却していく必要があります。
この記事では、価格競争から脱却し、価格ではなく価値で選ばれる企業に変わるための実践的な方法について分かりやすく解説いたします。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉価格競争が企業にもたらすリスク

価格を下げることで一時的な売上を確保できる場合もありますが、それはあくまで短期的な対処方法にすぎません。
結果として、次の4つのリスクが生じて企業の競争力を大きく損なうことにつながります。
・利益率の低下
・商品・サービス品質の低下
・顧客ロイヤリティの低下
・ブランドイメージの低下 |
以下では、それぞれのリスクについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、利益率の低下
価格を下げると、売上は一時的に増えますが、利益率は確実に低下します。
十分な利益を確保できなければ、商品開発や人材育成といった将来への投資が難しくなり、企業の成長は次第に鈍化していくでしょう。
最終的には、利益減少に歯止めがかからず、打つ手が尽きて撤退や倒産に追い込まれるケースも少なくありません。
◉-2、商品・サービス品質の低下
価格を下げたうえで利益を確保しようとすると、仕入れコストや人件費の削減に踏み切らざるを得なくなります。
しかし、その影響で製品やサービスの品質は徐々に損なわれ、顧客満足度も次第に低下していきます。
品質の低下は、クレームや返品の増加、リピート率の減少といった悪循環を招き、最終的には企業への信頼そのものを揺るがすリスクとなりかねません。
◉-3、顧客ロイヤリティの低下
「価格が安いから選んだ」という顧客は、より低価格の競合商品が登場すれば、迷わずそちらに流れてしまう傾向があります。
価格以外の価値で選ばれていない場合、顧客との継続的な関係を築くのは困難です。
このような状態では、リピート購入や紹介をしてくれるロイヤリティの高い顧客が育ちにくくなり、長期的な利益につながる顧客との関係構築がしにくくなります。
◉-4、ブランドイメージの低下
頻繁な値下げを繰り返すと、「安さだけが魅力のブランド」「品質に不安があるのでは」といったイメージが定着しやすくなります。
その結果、どれだけ優れた商品やサービスを提供していても、本来の強みや価値が伝わらなくなり、企業のブランド価値が下がってしまうでしょう。
ブランドイメージが損なわれることで、価格以外の面で差別化することが難しくなり、さらなる値下げに頼らざるを得ないという悪循環に陥るリスクが高まります。
◉価格競争に巻き込まれてしまう原因

近年の価格競争の激化には、「比較サイト」や「レビュー文化」の浸透、市場のコモディティ化など、外部環境の変化が影響しています。
しかし、それ以上に重要なのが、企業側の姿勢や構造に起因する要因です。
企業が価格競争に巻き込まれてしまう主な原因として、次の5つが挙げられます。
・商品・サービスの価値が顧客に正しく伝わっていない
・コモディティ商品を取り扱っている
・安さをウリにしている
・競合他社と差別化ができていない
・営業部門に「値下げしてでも数字を取る」という文化がある |
以下では、それぞれの要因について詳しく解説していきます。
◉-1、商品・サービスの価値が顧客に正しく伝わっていない
たとえ他社より優れた商品やサービスを提供していても、その価値が顧客に伝わらなければ、最終的な購入判断は価格になってしまいます。
商品やサービスの価値が正しく伝わっていなければ、他社と価格で戦わざるを得なくなり、自然と価格競争に引き込まれていきます。
自社の強みや商品・サービスの価値を顧客に正しく伝える努力が不足していることが、価格競争に巻き込まれる原因の一つといえるでしょう。
◉-2、コモディティ商品を取り扱っている
どこで買っても大きな違いがない商品やサービスは、顧客にとって価格が判断基準になりやすいという傾向があります。
たとえば、以下のようなものがこれに該当します。
・事務用品
・日用品
・BtoB向けの部品や資材
・OEM製品 |
このような商品は、顧客から見ると違いが分かりづらいため、最も分かりやすい比較要素である「価格」が重視され、結果として価格競争に巻き込まれやすくなります。
そのため、価格以外の価値をどう打ち出すかが重要であり、明確な差別化要素がなければ価格競争から抜け出すのは困難でしょう。
◉-3、安さをウリにしている
「業界最安値」や「他社より〇%安い」といったアピールは、一時的な集客効果をもたらす反面、自ら価格競争に踏み込む行為でもあります。
こうしたアピールを続けていると、値下げが当たり前の状態となり、利益率が圧迫されていくという悪循環に陥ります。
安さをウリにするのではなく、「その価格で得られる価値は何か」を伝える視点が欠かせません。
◉-4、競合他社と差別化ができていない
商品やサービスの特徴、営業資料やWebサイトの内容などが競合他社と似通っていると、顧客は価格以外で比較することができなくなり、必然的に価格競争に陥ってしまいます。
差別化できていなければ、顧客にとって「選ぶ理由」は価格だけになってしまうからです。
価格以外の魅力を打ち出せなければ、顧客は最終的に「より安い方」を選ぶ傾向が強くなり、持続的な競争優位を築くことが難しくなります。
◉-5、営業部門に「値下げしてでも数字を取る」という文化がある
営業現場で「とにかく今月の数字を達成する」というノルマを重視しすぎると、「値引きしてでも購入してもらう」という安易な受注体質が生まれやすくなります。
このような姿勢が常態化すると、営業部門にとどまらず、組織全体に「価格で勝負するのが当たり前」といった意識が広がりやすくなります。
その結果、商品の価値を伝える工夫や、課題解決型の提案営業といった本来重視すべきアプローチが育ちにくくなるのです。
中長期的に見れば、価格競争からの脱却をますます困難にする大きな要因となります。
◉価格競争から脱却し、価値で選ばれる企業になるための方法

価格競争から抜け出し、価格ではなく価値で選ばれる企業になるためには、戦略的な見直しと社内体制の再構築が欠かせません。
そのための実践的な方法として、次の5つを紹介します。
・ターゲットの見直し
・自社や商品・サービスのUSPを再定義する
・商品・サービスに独自性(機能・体験・世界観)を持たせる
・ストーリーテリングによりファンを増やす
・営業・マーケティング部署を中心とした社内の意識・体質を変える |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、ターゲットの見直し
まず重要なのは、「誰に売るか」を見直すことです。
価格を重視する層ばかりにアプローチしていては価格競争から抜け出せないので、価格よりも価値を重視する顧客層にターゲットを絞ることが効果的です。
見込み顧客のニーズを再定義し、価格以外の魅力を求めている層に焦点を当てて、訴求内容や接点を見直していきましょう。
◉-2、自社や商品・サービスのUSPを再定義する
次に、自社や商品のUSP(Unique Selling Proposition)、すなわち顧客にとっての「選ぶ理由」を再設計します。
価格以外のどこに魅力があるのかを明確に言語化して発信していくことが、価値を重視する顧客層に響くアプローチになります。
たとえば、次のような視点について、自社の強みを洗い出してみましょう。
・高品質・高性能・専門性
・サポートの手厚さ
・納期の早さ・対応スピード
・社会的信頼
・長年の実績・顧客との関係性
・導入しやすさ
・パッケージング |
自社では当たり前と思っていたことでも、顧客から見ると大きな価値である可能性があります。
実際の顧客の声をヒアリングしながら、選ばれている理由を客観的に再発見することがUSPの見直しに有効です。
◉-2-1、高品質・高性能・専門性
競合には真似できない品質や技術、専門性は強力な差別化要素になります。
たとえば、「精度が1.5倍高い検査機器」「特定業界向けに開発された高耐久フィルター」「自社開発エンジンによる2倍以上の処理性能」「40年以上の実績を が裏付ける品質」などは、大手企業の資本力だけでは再現が難しい領域です。
こうした独自性の高い強みを明確に打ち出すことが、競争優位性を確立するポイントです。
◉-2-2、サポートの手厚さ
きめ細やかで手厚いサポート体制も顧客に選ばれる理由になります。
たとえば、「導入から初期設定まで専任スタッフがオンラインで対応」「電話・チャット・メールすべて即日返信」「マニュアルと操作研修がセットで初心者でも安心」といった対応は、かゆいところに手が届くサポートとして高く評価されます。
大手企業が規模の都合上提供しづらいサービスこそが、小回りの利く企業の差別化ポイントになり得ます。
◉-2-3、納期の早さ・対応スピード
納期の早さや対応スピードも強みになります。
たとえば、「午前11時までの注文は当日出荷」「初回見積もりは24時間以内に回答」「突発案件にも即日対応できる在庫体制あり」などの迅速な対応は顧客の信頼につながります。
ただし、過度なスピード対応は社内に負担をかけるため、持続できる体制を整えることが重要です。
◉-2-4、社会的信頼
地域活動への参加なども地域に特化した差別化に有効です。
「地域で50年以上の歴史」「行政や教育機関との協業実績」など、全国的な認知度が低くても、地域での強い支持を得ている企業は数多くあります。
地元に根ざした活動の積み重ねは、他社にはない信頼を築きます。
◉-2-5、長年の実績・顧客との関係性
積み重ねてきた実績は、何よりの信頼の証です。
たとえば、「創業50年」「累計導入企業2,000社以上」「15年以上継続取引の企業多数」「大手メーカー●●社に10年以上納品」といった具体的な数字があると、顧客に安心感を与えます。
特にBtoB取引においては、このような数字の裏付けがあると大きな説得力を持ちます。
◉-2-6、導入しやすさ
使いやすく、導入しやすい商品やサービスは、初めての顧客にとって大きな安心材料です。
たとえば、「初期費用ゼロで月額定額制から始められる」「マニュアルや初期設定キットが付属しており、現場ですぐに活用できる」「ITに不慣れでも安心の電話サポート付き」といった特徴は、現場の実用性を重視する顧客に高く評価されます。
また、導入のハードルが低いことで、購買意欲を後押しする効果も期待できます。
◉-2-7、パッケージング
商品やサービス自体での差別化が難しい場合は、パッケージや提供形式を工夫することで独自性を打ち出すことが可能です。
たとえば、キッコーマンは「しぼりたて生しょうゆ」を卓上ボトルで展開することで、他社と一線を画す価値を生み出しました。
このように、包装・提供方法・サブスクリプション化などで新たな価値を生むことができます。
特にコモディティ化しやすい商品やサービスを取り扱う企業は、パッケージングで競合他社との差別化を図るのがおすすめです。
◉-3、商品・サービスに独自性(機能・体験・世界観)を持たせる
価格だけで選ばれる状態から脱却するためには、商品やサービスに「体験価値」や「ブランドの世界観」などの情緒的な価値を加えることが有効です。
たとえば、「購入からアフターサポートまで一貫した顧客体験」や「ブランドの想いを物語として体現する演出」などを通じて、顧客の共感や愛着を引き出し「その企業で買いたい」と思わせることができます。
◉-4、ストーリーテリングによりファンを増やす
創業の理念や創業の背景、困難を乗り越えたエピソードなど、単なる商品説明では伝えきれない人間的な価値を伝える手法がストーリーテリングです。
企業の想いや価値観に共感した顧客は、価格ではなくそのブランドの姿勢に惹かれ、長期的な関係を築くロイヤルユーザーへと変わっていきます。
◉-4-1企業のストーリーを伝えるなら書籍出版がおすすめ
企業の想いや成り立ち、価値観を深く伝えたいなら、書籍が有効です。
書籍はマーケティングツールの中でも、社会的信頼性や専門性が高く、WebサイトやSNSと比べて「権威性のある情報発信」が可能になります。
また、読者は書籍という形式であれば長文をじっくり読んでくれるため、深い共感やファン化につながりやすいのも特徴です。
さらに、営業資料や広報活動におけるPRツールとしても活用でき、新規リード獲得のきっかけとしても効果が期待できます。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。

◉-5、営業・マーケティング部署を中心とした社内の意識・体質を変える
どれだけ価値を訴えても、現場が「売るためには値下げが必要」という意識のままでは、価格競争からの脱却は困難です。
そのため、営業やマーケティング部門を中心に、「価格ではなく価値で選ばれる」という文化を社内に浸透させることが重要です。
具体的には、教育や評価制度の見直し、KPI設計の再構築などを通じて、価格以外の魅力を語れる組織体制を整えていく必要があります。
◉書籍出版により価格競争から脱却した成功事例
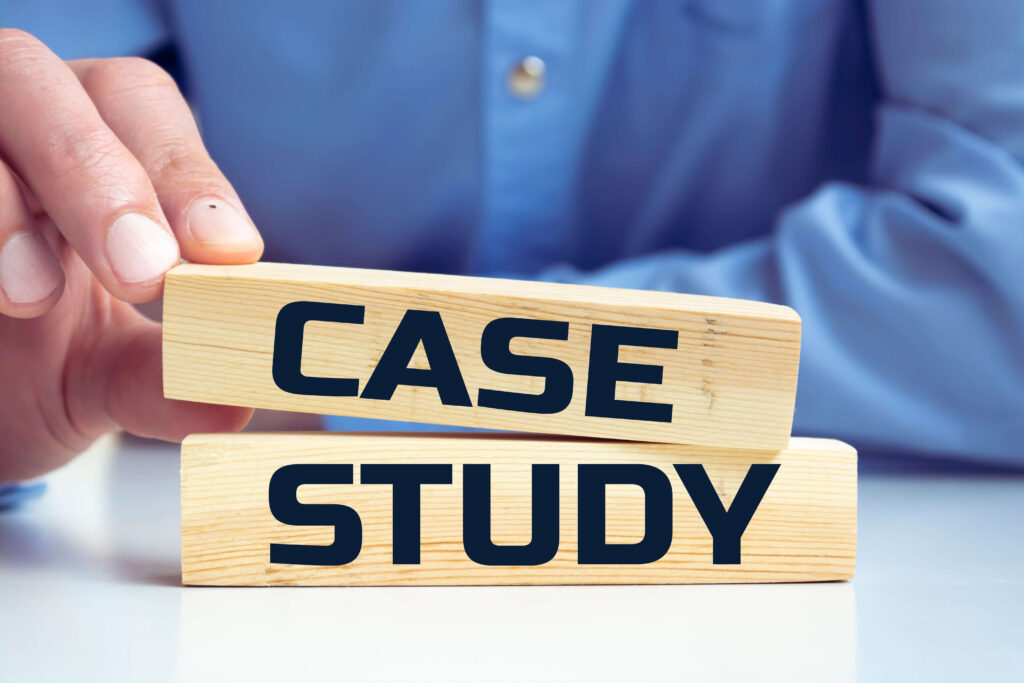
価格ではなく価値で選ばれるための手段として、近年注目を集めているのが書籍出版を活用したブランディングです。
ここでは、実際に書籍出版を通じて、価格競争から脱却し、自社ならではの強みを市場に浸透させた2つの事例を紹介します。
・事例1:常識を覆す持論を展開して注目を集めた保険代理店
・事例2:書籍出版により独自の強みをPRした会計事務所 |
以下で、それぞれ詳しく紹介します。
◉-1、事例1:常識を覆す持論を展開して注目を集めた保険代理店
保険商品は、どの保険代理店が販売しても商品内容も価格も基本的には同じという性質があります。
そのため、提案力や信頼性といった「見えにくい価値」が重視される業界だといえます。
そんな中で、この保険代理店の経営者は「成果報酬型ではなく、一律報酬型の給与制度こそが業績拡大につながる」という、業界の常識とは真逆の持論を打ち出し、その考えを一冊の書籍として出版しました。
この書籍は大きな話題を呼び、問い合わせが急増。
保険契約の件数が増えただけでなく、保険会社からの講演依頼も相次ぐなど、出版をきっかけに存在感が一気に高まりました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、事例2:書籍出版により独自の強みをPRした会計事務所
税理士・会計士業界も、価格競争に陥りやすい分野の一つです。
特に中小企業向けの税務顧問業務では、「記帳や申告だけしてくれればいいから安くしてほしい」といった要望が多く、価格以外で選ばれる理由をいかに示すかが課題となっています。
このような状況の中で、東京と名古屋で会計事務所を開設している代表者は、自らの海外における勤務経験を活かして「海外へのビジネス展開におけるリスクやマネジメントのポイント」をまとめた書籍を出版しました。
その結果、「外資系企業やグローバル案件にも対応できる会計事務所」であることを伝えることができ、結果として他事務所との差別化に成功しました。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉【まとめ】価格競争から脱却し、本質的な価値で選ばれる企業を目指そう!
この記事では、価格競争のリスクや価格競争に巻き込まれてしまう原因、価格競争から脱却して価値で選ばれる企業になるための方法などについて事例を交えて解説しました。
価格競争から抜け出すためには、「安さ」以外の魅力を明確に伝え、選ばれる理由を構築することが不可欠です。
その手段の一つとして、注目されているのが書籍出版です。
フォーウェイが提供する「ブックマーケティングサービス」は、企業が持つ強みや創業の背景、商品・サービスに込めた想いなどをプロの編集者が丁寧に掘り下げ、書籍という形で見える化します。
書籍出版は、単なる宣伝だけでなく、「信頼性」「専門性」「共感力」を備えた強力なブランディング手段です。
書籍という形で自社の独自性や強みを明確化することで、価格ではなく価値で選ばれる企業を目指すことが可能になります。
書籍出版に少しでもご興味のある方は、ぜひ一度フォーウェイまでお気軽にご相談ください。


企業が10周年・50周年といった節目を迎える際、多くの担当者が悩むのが「周年記念をどのように進めればいいのか」という点です。
周年記念は単なるお祝い事ではなく、企業の価値や歴史、理念を再確認し、社内外に発信する貴重な機会でもあります。
しかし、「何から手をつければよいのか」「どのような施策が効果的なのか」「どの部署を巻き込むべきか」など、企画段階で考えなければならないことは少なくありません。
また、周年記念は「数年に一度」や「数十年に一度」と頻度が低く、社内にナレッジが蓄積されにくいため、ゼロから着手するケースも多いでしょう。
本記事では、そもそも「周年とは何か」という基本から、周年記念事業を行う目的や進め方、そして成果につなげるための施策例まで、わかりやすく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
◉企業の周年とは?

周年とは、企業が創業や設立のタイミングを記念して、10周年や50周年といった節目でお祝いやイベントを実施することです。
企業の創業50周年記念といった事業立ち上げからの節目を祝うこともあれば、ブランドの立ち上げ10周年などを祝うケースもあります。
会社のほか、店舗や病院施設、福祉施設、学校など、業種・業態に関わらず、節目を祝うイベントとして催されます。
このような節目のタイミングで、周年を祝う社内外の関係者を招くイベントや記念品の制作などを行うのが通例です。
◉企業が周年記念を行う目的

企業が周年記念を行う主な目的として、次の6つを挙げることができます。
| 企業のブランド力の向上社内外のステークホルダーとの関係強化企業の理念や歴史、ビジョンの再整理・再発信企業のブランド再構築のきっかけ社員のモチベーション向上と組織力の強化採用・広報活動の強化 |
以下では、それぞれの目的について詳しく見ていきましょう。
▶︎周年記念を行う目的については、関連記事【周年事業の目的と意義ーー社史・周年史制作のもたらすもの】もあわせて参考にしてください。
◉-1、企業のブランド力の向上
周年記念は、企業が長年にわたり顧客や社会から信頼を積み重ねてきた「確かな実績」を象徴するものです。
特に10年、20年、50年といった節目は、企業の継続性や安定性を社会に示す絶好のタイミングであり、ブランド価値を再定義・強化する重要な機会となります。
このような節目に合わせて、企業理念を込めたメッセージの発信や記念キャンペーンの実施、メディアへの露出を積極的に行うことで、取引先や顧客、さらには求職者に対して「信頼できる企業である」というイメージをより強く訴求することが可能です。
◉-2、社内外のステークホルダーとの関係強化
周年記念は、日ごろから支えてくれている顧客や取引先、株主、地域社会、そして社員に対し、感謝の気持ちを改めて伝える機会です。
たとえば、周年イベントの開催や記念品の贈呈、特別キャンペーンの実施などは、感謝の意を伝えると同時に、相互のつながりを強化する有効な手段となります。
◉-3、企業の理念や歴史、ビジョンの再整理・再発信
周年記念は、これまでの歩みを振り返るだけでなく、企業の原点や存在意義を改めて見つめ直す機会でもあります。
この節目を活かして、「なぜ自社が存在するのか」「どこへ向かっていくのか」という企業理念やビジョンを再整理して、社内外に向けて力強く発信することが可能です。
◉-4、企業のブランド再構築のきっかけ
周年記念は、企業がブランドを再構築する絶好のタイミングといえます。
たとえば、ブランドロゴの刷新やコーポレートメッセージの見直し、Webサイトのリニューアルなど、通常であれば社内外の調整に時間を要する大きな施策も、「○○周年を機に」という明確な理由があれば、受け入れられやすくなります。
節目となる周年をきっかけにすれば、大胆な変革も違和感なく自然に進めることができ、新たなブランドイメージを浸透させたり、企業の次なるステージを切り開くきっかけになったりするでしょう。
◉-5、社員のモチベーション向上と組織力の強化
周年記念は、社員一人ひとりの貢献を称える場としても活用できます。
これまでの歩みや成果を共有することで、「自分たちがこの企業の成長に携わってきた」という誇りや実感が生まれます。
記念式典での表彰や記念動画の上映などを行えば、感謝の気持ちを具体的に伝えられるでしょう。
また、部門を超えて協力する記念プロジェクトの推進は、社員同士の一体感を高めるとともに、組織力の底上げにもなります。
◉-6、採用・広報活動の強化
周年記念は、企業の魅力を内外に伝える広報・採用活動の強化にもつながります。
周年を機に企業理念や社風、ビジョンなどを再定義し、社史や小冊子、特設サイト、映像コンテンツ、SNSなどで発信することで、求職者に対して企業の価値観や文化をより明確に伝えることが可能になります。
また、周年をテーマとした特集や取材など、メディア露出の機会も増えやすく、企業認知の向上やブランドイメージの強化にも効果的です。
特に中小企業や成長中の企業にとっては、外部への認知度を高めるチャンスとなるでしょう。
◉企業の周年記念の方法

企業の周年記念の具体的な方法として、次の7つがあります。
・周年記念のイベント開催
・社外向けキャンペーン・プロモーション
・ノベルティ配布・プレゼント企画
・周年限定商品の販売
・コラボレーション施策
・感謝を込めたメッセージの発信
・オリジナルコンテンツの企画と制作 |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、周年記念のイベント開催
周年記念の方法として代表的なものはイベントの開催です。
従業員やその家族、取引先など、感謝の意を表明した自社に関係する多くの人たちを招くパーティーが節目で開催されます。
このような周年記念の式典やパーティーは、普段過ごしている会社とは異なる空間で実施することが多いです。
たとえば、ホテルなどの豪華な空間を貸し切って開催するなどが考えられます。
自社の周年記念式典およびパーティーの模様を動画に撮影して、後日DVDとして配布したり、広報の一環でプレスリリースを配信したりする方法も良いでしょう。
◉-2、社外向けキャンペーン・プロモーション
周年記念を機に、顧客への感謝を込めた社外向けキャンペーンやプロモーションを実施するのも効果的です。
たとえば「創業○周年記念感謝キャンペーン」として、SNSを活用したフォロー&リポスト企画や、記念品が当たるプレゼント企画を展開するといった方法が挙げられます。
また、特別割引や限定クーポンなどの特典を用意すれば、顧客の購買意欲を喚起し、売上促進にもつなげられます。
周年という明確なテーマがあることで、キャンペーンにストーリー性を持たせやすく、企業のブランドイメージの向上にもつながるでしょう。
◉-2-1、販促イベントの開催
周年記念を盛り上げる施策として、リアルイベントを活用した販促プロモーションも効果的です。
具体的には、以下のような企画が考えられます。
・スタンプラリー・抽選会・スクラッチカードといった参加型の企画
・キッチンカーや地域密着型の出店イベント
・お笑い芸人やパフォーマーを招いたステージ演出 |
来場者が楽しめる体験を企画することで、企業への親近感や好印象を高めることができます。
◉-2-2、周年キャンペーン
周年をきっかけにした、ユーザーに向けたキャンペーンや特典の提供も一つの手段です。
周年記念限定の割引クーポンを発行して、ユーザーにはSNSなどで拡散してもらえる効果が期待できます。
「周年」というキーワードを皮切りに話題性を醸成することで、多くのユーザーと新規でつながるきっかけとなり得ます。
◉-3、ノベルティ配布・プレゼント企画
周年記念を盛り上げる施策として、来店者や参加者への特典としてノベルティを配布するのも有効な方法です。
配布するノベルティは、Tシャツやマグカップ、ボールペンなど、日常的に使える実用性の高いアイテムがおすすめです。
企業ロゴや周年ロゴを入れたオリジナルデザインにすることで、記念品としての価値も高まり、ブランド認知の拡大にもつながります。
◉-4、周年限定商品の販売
周年記念で限定商品を制作して販売するのもよくある方法の一つです。
商品販売を主たる事業とする会社であれば、限定商品をWEBサイトや広告などで打ち出し、消費者にインパクトを与えることができるでしょう。
また、購入者特典としてノベルティをセットにするなど、付加価値を加える施策もおすすめです。
さらに、レストランといった飲食事業であれば、周年記念の限定メニューを提供するのも一案です。
普段は提供されない特別メニューだからこそ、特にリピーターに来店を促すきっかけとなるでしょう
◉-5、コラボレーション施策
周年記念を機に、地元企業や人気ブランドと連携し、コラボレーション商品を企画・販売する方法もあります。
また、インフルエンサーやクリエイターとタイアップした周年記念企画もおすすめです。
限定性や話題性のあるコラボレーション施策は、ファン層の拡大や新たな顧客層へのリーチにつながり、ブランド価値も高められるでしょう。
◉-6、感謝を込めたメッセージの発信
周年記念は、さまざまな人たちに感謝の気持ちを表明する貴重な機会です。
そこで、日ごろの感謝をメッセージカードなどに込めて、社員や取引先の人たちに贈ってみましょう。
周年ならではの貴重なギフトや記念品を用意するのもおすすめです。
◉-7、オリジナルコンテンツの企画と制作
周年記念の施策として、企業独自のストーリーや価値観を伝える「オリジナルコンテンツ」の制作も効果的です。
企業の歴史や理念、社員の声などを活かした多様な表現手段を通じて、社内外へのメッセージ発信とブランディングを強化することができます。
◉-7-1、記念動画
周年の節目に、自社の歩みやビジョンをストーリーとして表現した記念動画を制作する企業もあります。
たとえば、ドキュメンタリーやブランドムービーといった形式で、経営者・社員へのインタビューや現場の風景を織り交ぜることで、リアリティと共感性の高いコンテンツになります。
◉-7-2、周年誌・記念誌・社史
周年の節目をまとめた冊子やデジタルブックも、企業の歩みや価値を可視化する有力な手段です。
たとえば、「年表+エピソード+社員の声」といった構成でストーリー性を持たせることで、読み物としての魅力が高まり、社員の参画意欲も引き出せます。
冊子形式とデジタルブックの併用が一般的で、書店流通は行わないのが基本です。
特にBtoB企業においては、取引先や学生を対象とした採用活動における訴求力が高いことが特徴です。
▶︎周年誌の詳細については、関連記事【周年史とは?出版目的や具体的な制作の流れや活用方法について解説】もあわせて参考にしてください。
▶︎記念誌の詳細については、関連記事【記念誌とは?読んでもらうためのコツや活用アイデアを解説】もあわせて参考にしてください。
▶︎社史の詳細については、関連記事【読まれ、活用される社史を作るコツ!作成後の有効活用方法も解説】もあわせて参考にしてください。
◉-7-3、周年ロゴ・スローガン
ロゴやスローガン、キャッチコピーで周年の世界観を表現する方法もあります。
作成したロゴやスローガンは、名刺・封筒・Webサイト・SNSアイコンなどに展開することで、企業メッセージに一貫性が生まれ、社内外への浸透力が高まります。
◉-7-4、周年記念特設Webサイト・Webページ
周年の世界観を表現する専用のWebサイトや特設ページを制作することで、情報発信を強化できます。
コンテンツとしては、以下のような情報を掲載するのが一般的です。
・企業の歴史タイムライン
・周年のコンセプト
・紹介社員インタビュー
・記念ムービー
・イベント情報 |
イベント終了後もブランドページとして残すことで、持続的なプロモーション資産として機能します。
◉-7-5、書籍出版(企業出版)
周年記念の機会に「書籍出版」を行うことは、企業にとって価値の高い施策といえます。
ブランド資産や企業理念を整理し、社会的信頼性を伴ったメッセージとして可視化できる点が魅力です。
周年記念誌とは異なり、一般書籍として流通させることで、社内外への発信力や信頼性の向上が期待できます。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。

◉企業の周年記念の効果を高めるうえで重要なポイント

周年記念でよくある失敗が、次の4つです。
・準備不足でグダグダのイベントになってしまう
・見た目だけのイベントで終わってしまう
・費用対効果が合わない
・社内の共感が得られなくて終わる |
しかし、このような失敗をすることなく、周年記念を一つのきっかけとして、その後の会社の業績に良い影響を与えることは十分可能です。
具体的には、次のポイントを意識して計画する必要があります。
・1年〜2年前から資料収集をすすめる
・目的を明確にする
・多くの社員を巻き込む
・一貫性のあるコンセプトとメッセージ
・社外への積極的な発信
・周年記念を資産として残す工夫
・振り返りと効果測定 |
企業の周年記念の効果を高めるうえで重要な7つのポイントを見ていきましょう。
◉-1、1年〜2年前から資料収集をすすめる
周年記念に向けて記念誌や社史を制作する場合、大量の資料や記録の収集が必要となります。
過去の社内報や写真、社外の掲載記事、沿革データなど、情報は多岐にわたるため、プロジェクトが本格始動する前段階から、計画的に資料収集や整理を進めておくことが重要です。
早い段階で準備を始めておけば、制作スケジュールに余裕が生まれ、直前になって情報が不足するというトラブルを未然に防ぐことができます。
◉-2、目的を明確にする
周年記念の効果を高めるには、まず「なぜやるのか」「何を達成したいのか」という目的を明確に定めることが不可欠です。
ただ記念日を祝うという目的だけでは、単発のイベントで終わってしまい、その後に続く効果は得られません。
たとえば、「社員のモチベーション向上」「社外へのブランド価値発信」など、具体的な目的を設定することが重要です。
◉-3、多くの社員を巻き込む
周年記念を経営層主導の「自己満足イベント」で終わらせないためには、社員一人ひとりを当事者として巻き込むことが大切です。
具体的な取り組み例としては、以下のような施策が挙げられます。
・周年ロゴの社内コンテスト
・記念ムービーや記念誌への社員の声・写真の掲載
・若手社員を中心とした実行委員会の結成 |
実際にある大手企業では、周年記念の一環として小説仕立ての書籍を制作し、その企画・執筆を若手社員中心のプロジェクトチームが担当しました。
営業やSE、総務などの部署から有志メンバーが参加し、完成した書籍が実際に書店に並んだことで、参加社員のモチベーションや帰属意識が大きく高まったといいます。
このように、自らが関わった成果が形として残る経験は、社内での評価向上やプロジェクトの継続的展開にもつながりやすく、企業全体に良い影響をもたらします。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【本を出版するには?現役書籍編集者が本の出し方を分かりやすく解説】もあわせて参考にしてください。
◉-4、一貫性のあるコンセプトとメッセージ
周年記念の取り組みでは、企業の「らしさ」を体現した統一感のあるコンセプト設計が不可欠です。
ロゴやスローガン、Webサイト、パンフレット、イベント演出など、すべての要素に一貫したメッセージを通すことで、社内外に強い印象を残すことができます。
また、デザインやコピー、表現のトンマナ(トーン&マナー)を統一することで、ブランドの世界観を効果的に伝えることが可能です。
◉-5、社外への積極的な発信
周年記念は、社外に自社の魅力や存在感をアピールするチャンスです。
次のような複合的なPR手段を使って、計画的な情報発信を行っていきましょう。
・プレスリリース配信+記者向けイベント
・SNS(X、Instagram、YouTube)での周年企画・動画展開
・採用サイトや企業紹介資料への周年要素組み込み
・周辺記念書籍の出版
・周年記念Webサイトの作成 |
こうした施策を複合的に展開し、メディア掲載の機会を増やすことが重要です。
▶︎PRのやり方については、関連記事【企業が広報に使える媒体とは?種類や費用対効果の高い選び方を解説!】もあわせて参考にしてください。
◉-6、周年記念を資産として残す工夫
周年記念で制作したムービーや社史、写真、社員の声などは、継続的なコンテンツとして再活用できます。
たとえば、以下のような活用方法があります。
・採用資料や営業資料への再利用
・SNS投稿やオウンドメディアへの二次展開
・Webサイト内のストーリーページとしての常設掲載 |
周年記念のコンテンツを「1日限り」で終わらせず、長期的に活用することで、ブランド強化にもつながります。
◉-7、振り返りと効果測定
周年記念を終えた後こそ、次への改善に向けた振り返りが欠かせません。
効果測定の方法として、以下があります。
・アンケート・ヒアリングによる社内評価
・SNSでの反応、WebサイトのPV数、取引先からの反響などの外部評価
・成果をまとめたレポート化・社内共有 |
実施して終わりにするのではなく、成果の可視化と評価を通じて、次の周年企画や他のマーケティング施策へと活かしていきましょう。
◉企業の周年記念の計画・実施の手順
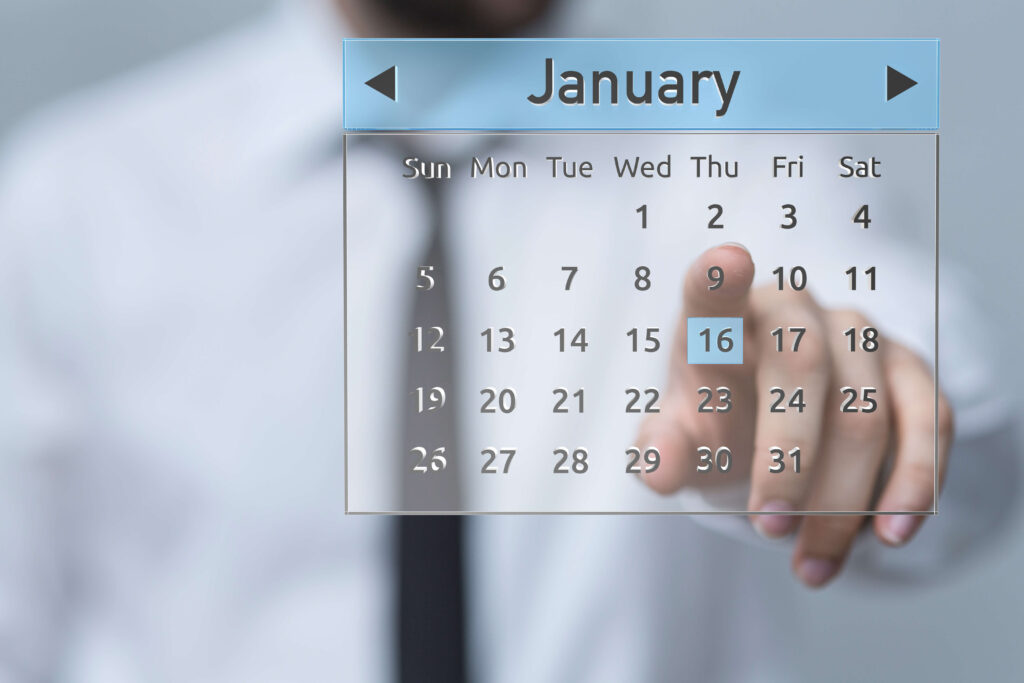
ここでは、企業の周年記念事業を計画・実施する手順について解説します。
一般的には、次の7つのステップで行います。
・ステップ1:【1年前】周年のゴール設定と目標の明確化
・ステップ2:【10ヶ月〜8ヶ月前】周年記念プロジェクト体制の構築
・ステップ3:【10ヶ月〜8ヶ月前】広報・宣伝戦略と大枠のスケジュールの決定
・ステップ4:【8ヶ月〜5ヶ月前】具体施策の企画・外注選定
・ステップ5:【5ヶ月〜2ヶ月前】制作と準備
・ステップ6:【1ヶ月〜当日】周年記念の実施
・ステップ7:【終了後】広報・宣伝戦略と大枠のスケジュールの決定 |
順を追って詳しく見ていきましょう。
◉-1、ステップ1:【1年前】周年のゴール設定と目標の明確化
周年記念のイベントをするにせよ、出版をするにせよ、ゴールの設定は最重要といえます。
周年事業を実施することで、「何を目指すのか」「どう見せたいのか」「どんなことを伝えたいのか」「何を作り出したいのか」といった目的をまず設定しましょう。
さらに、ターゲットの設定も重要です。
社員やその家族がメインのターゲットなのか、もしくは社外の取引先や潜在顧客、採用応募者がターゲットとなりうるのかなど、会社の予算を使って施策を実施する以上は、一つの経営戦略として施策実施後にどのようになっているのかの理想を思い描くと良いでしょう。
◉-2、ステップ2:【10ヶ月〜8ヶ月前】周年記念プロジェクト体制の構築
周年記念事業を成功させるために重要なポイントになるのが「どのようなプロジェクト体制を築くか」です。
準備段階を整えることが、プロジェクト全体の成功を左右するといっても過言ではありません。
まずは、各部門からメンバーを選出し、社内横断型の実行委員会を編成します。
役割ごとにチームを分けるのが一般的で、たとえば以下のような体制が想定されます。
・イベント企画チーム
・制作・クリエイティブチーム
・広報・PRチーム
・予算・進行管理チーム |
それぞれが明確な役割を持つことで、作業の抜け漏れを防ぎ、スムーズな進行を可能にします。
特に周年記念事業は、会社全体を巻き込んで進める「共創型」のプロジェクトとして設計することが重要です。
◉-3、ステップ3:【10ヶ月〜8ヶ月前】広報・宣伝戦略と大枠のスケジュールの決定
周年イベントを実施するには、広報や宣伝活動の戦略立案をしなければなりません。
周年事業をやる以上は知ってもらって、メディアにも取り上げられる、またとない機会だからです。
周年記念式典といったイベント実施の時期を確定させ、その期日に向けてプレスリリースや広告宣伝の準備を行いましょう。
イベントの規模にもよりますが、具体的な企画やアイデアを具現化するまでに半年程度は要すると考えられます。
そのため、広報や宣伝のスケジュールは全体で共有しながら丁寧に進めることをおすすめします。
◉-4、ステップ4:【8ヶ月〜5ヶ月前】具体施策の企画・外注選定
この段階では、周年記念の目的やゴールに基づき、「どのような施策を行うか」の具体的な中身を設計します。
たとえば、以下のような施策の組み合わせが考えられます。
・社内向け:記念式典、社員表彰、記念動画、記念誌
・社外向け:特設Webサイト、書籍出版、顧客向けキャンペーン、展示イベント
・ブランド強化:ロゴリニューアル、タグライン刷新、記念グッズ制作 |
必要に応じて外部パートナー(制作会社・PR会社・デザイナー・ライターなど)を選定してアサインします。
◉-5、ステップ5:【5ヶ月〜2ヶ月前】制作と準備
企画内容と外注先が決まったら、いよいよ実施に向けた制作フェーズに入ります。
記念映像やパンフレット、Webサイト、記念品など、制作物の進行管理に加えて、イベント運営に必要な備品や会場手配、登壇者との調整も行います。
制作はスケジュール通りに進まないこともあるため、修正対応や納期の遅れに備えて、余裕をもった工程管理が不可欠です。
トラブルが発生した際にも慌てず対応できるよう、事前の段取りを丁寧に進めておきましょう。
なお、周年記念に合わせて書籍出版を検討している場合は、他の制作物と比べて取材・執筆・編集などに時間がかかるのが一般的です。
そのため、1年前後の制作期間を見込んでおくとよいでしょう。
特に書籍は早い段階で企画を立ち上げ、全体スケジュールの初期段階から計画に組み込んでおくことが大切です。
◉-6、ステップ6:【1ヶ月〜当日】周年記念の実施
本番当日に向けて各施策の最終チェックを行い、運営チームで緊密に連携しながらリハーサルと確認作業を行います。
特にイベント当日は、「誰が・いつ・どこで・何をするのか」を明確にした詳細な運営マニュアルを準備しておくと安心です。
また、式典や展示の様子、参加者の表情などを写真や動画で記録しておくと、後日のレポート作成やSNS・メディアでの情報発信に活用できます。
◉-7、ステップ7:【終了後】振り返りと今後の情報発信計画の策定
周年記念の実施が無事終了した後も、それで終わりではありません。
施策の成果や社内外の反響を振り返り、今後の企業活動へとつなげる姿勢が大切です。
具体的には、以下のような対応を行います。
・社内向け:実施報告書の共有、アンケートによるフィードバック収集
・社外向け:公式レポートやSNSでの発信、メディア掲載記事の拡散 |
また、周年を機に自社の理念やビジョンを再整理した場合は、それをどのように情報発信していくのかという広報・宣伝戦略やスケジュールを決定します。
これらによって、周年記念事業が一過性ではなく、企業文化として根付くようになります。
◉近年は周年記念の書籍を出版する企業も多い!

近年では、その後のPRに長く活用できるという点や、通常の書籍と同様に書店流通することによる認知度向上の効果が期待できることから、企業出版を活用して書籍を出版する会社が増えてきています。
周年記念を機に書籍出版を行うことによる効果としては主に次の5つが考えられます。
・顧客ロイヤルティ向上に良い影響がある
・競合他社との差別化につながる
・出版を通じた認知度の向上につながる
・求職者にとって良いイメージがつく
・周年記念イベント後も営業・マーケティング・広報に活用しやすい |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、顧客ロイヤルティ向上に良い影響がある
周年記念の施策で重要な要素として考えられるのは、これまでの愛顧の気持ちをイベントやキャンペーンで表すことでしょう。
日ごろの感謝を示すイベントやキャンペーンを実施することで、顧客のロイヤリティ向上が期待できます。
たとえば、宝酒造の人気いも焼酎ブランド「一刻者」の20周年キャンペーンとして実施されたのが、「マストバイキャンペーン」です。
「頑固にこだわって20年」というキャッチフレーズを打ち出し、商品の購入者のうち抽選で500名に「一刻者」オリジナル陶器をプレゼントしました。
信頼の強固なロングセラー商品のファンに対して、オリジナル陶器をプレゼントすることでブランドのより一層のファン化が進んだ事例といえます。
◉-2、競合他社との差別化につながる
周年事業は、その貴重な機会をきっかけに競合他社との差別化を図る手段としても効果的です。
周年を記念した特別な企業ロゴを作れば、他社とは異なる印象をユーザーに印象付けることができます。
前述したキャンペーンやイベントなども差別化にはもってこいの方法ですが、ほか自社ならではの趣向を凝らしたノベルティを作成して配布するなどもおすすめの方法です。
このように競合他社では真似できない特別な手段を用いることで、現代ではSNSでユーザーが拡散してくれるPR効果も期待できるのです。
▶︎競合他社との差別化の詳細については、関連記事【差別化戦略の成功の秘訣ーメリットやデメリット、成功事例とは!?】もあわせて参考にしてください。
◉-3、出版を通じた認知度の向上につながる
周年史は、社内向けに配布するインナーツールと、社内外どちらにも訴求が可能になる流通書籍のタイプがあります。
この流通書籍として周年史を制作すると、一般の書店へ流通・配本されるため、一般読者への認知促進の効果が期待できます。
詳細は後ほどの事例紹介で解説しますが、会社の歴史を紐解く周年史を作ろうとして、結果的に自社製品にスポットを当てた出版をしたことで、全国各地の企業から「商品を仕入れたい」という声が殺到しました。
それだけでなく、出版をきっかけにテレビのディレクターの目にとまり、全国放送のバラエティ番組に著者の出演が決定。全国の視聴者に向けて自社製品のPRをすることができました。
▶︎認知度を上げる方法の詳細については、関連記事【経営者必読!認知度向上の方法と効果的なマーケティングの選択肢】もあわせて参考にしてください。
◉-4、求職者やその親にとって良いイメージがつく
一般市場に流通した書籍を出版している企業という箔がつくことで、求職者にとっては親御さんへの説得材料になります。
たとえば、競合他社に大手がひしめく業界で、書籍を手に取ったことをきっかけに親御さんから子どもに対して、「この企業を受けなさい」と中堅の企業を推薦した事例もあるほどです。
▶︎採用ブランディングのやり方については、関連記事【採用ブランディングとは?選ばれる企業になるための進め方とは】もあわせて参考にしてください。
◉-5、周年記念イベント後も営業・マーケティング・広報に活用しやすい
書籍は、周年記念イベントが終了した後も多方面で活用できます。
配布しやすく、自社の魅力や実績を効果的に伝えられるため、営業やマーケティング、広報活動をする際に役立つでしょう。
具体的には、営業提案時の資料として同封したり、リード獲得施策として配布したりすることで、信頼感を高めることができます。
また、書籍の内容をSNSと連動させて情報発信したり、一部を広報素材としてメディアに提供したりすることも可能です。
◉周年記念出版の成功事例

周年記念で書籍を出版して成功した事例は多々ありますが、ここでは次の3つの事例を紹介します。
・事例1:100周年記念出版をきっかけに商品が爆売れした老舗家具メーカー
・事例2:70周年記念出版が販路拡大に大きく貢献した食品製造会社
・事例3:30周年記念出版が中途採用に大きな効果を発揮した生命保険会社 |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、事例1:100周年記念出版をきっかけに商品が爆売れした老舗家具メーカー
ある老舗家具メーカーでは、創業100周年を機に記念書籍を出版しました。
著者は当時の経営トップで、廃業寸前の赤字企業をV字回復させた改革の手法を解説する内容となっています。
この書籍が人気テレビ番組の制作スタッフの目にとまり、後に番組出演のオファーへとつながりました。
番組放送後は企業サイトへのアクセスが集中し、サーバーが一時ダウンするほどの反響を呼びました。
結果として、出演からわずか1ヶ月間で前年の売上を超えるという大きな成果が得られたといいます。
なお、この書籍は100周年の前年に出版されたもので、周年事業全体も大きな盛り上がりを見せました。
◉-2、事例2:70周年記念出版が販路拡大に大きく貢献した食品製造会社
愛知県の食品製造会社は、創業70周年をきっかけに書籍を出版しました。
当初は社史の制作を検討していましたが、自社製品の有用性を訴求する書籍を出版することに方針転換しました。
一般的に使用されているサラダ油の過剰摂取に警鐘を鳴らし、その解決策としてこめ油の有用性を説いたのです。
この書籍が反響を呼び、全国から新規取引の問い合わせを獲得することができました。
また、TV番組への出演も決定し、メディアへのPRにも効果がありました。
◉-3、事例3:30周年記念出版が中途採用に大きな効果を発揮した生命保険会社
ある大手生命保険会社では、創業30周年の節目に、自社の理念や事業の意義を広く社会に伝える目的で記念書籍を出版しました。
同社は外資系保険会社との合弁によって日本市場に参入し、ライフプランニングという考え方をより多くの人々に理解してもらう必要性を感じていました。
その一環として、当時教育分野で高い実績を持ち、東京や大阪などの公教育改革にも関わっていた著名人に執筆を依頼。
教育と人生設計の視点を交えた内容により、幅広い層に共感を呼ぶ書籍が完成しました。
書店プロモーションは東京都、大阪府、愛知県などの大都市圏を中心に展開され、結果として7万部を超えるヒットを記録しました。
また、この書籍は社内にも好影響をもたらし、若手社員やマネージャー層への理念浸透に貢献。
さらに、中途採用の新入社員の多くが書籍を通じて企業への理解を深めており、ライフプランナーという職業に対する共感や憧れを育むきっかけにもなりました。
◉【まとめ】周年記念を「将来へ向けての再スタート」にしよう!
この記事では、企業が周年記念を迎えるにあたっての目的や意義、実施までの流れ、そして出版を活用した成功事例について紹介してきました。
周年記念は、企業のこれまでの歩みを振り返ると同時に、これからのビジョンを発信する機会です。
その想いや価値観を社内外に届ける手段として、注目されているのが「書籍出版(企業出版)」です。
フォーウェイが提供する「ブックマーケティングサービス」では、企業の歴史や価値観、創業者の想い、未来への展望などをプロの編集者が丁寧にヒアリングし、一冊の書籍として形にします。
書籍は、周年記念の場を一過性のイベントで終わらせず、その後の営業・採用・ブランディング活動にまで活かせる「資産」として活用できます。
周年記念にあたって書籍の出版にご興味をお持ちの方は、ぜひ一度フォーウェイまでご相談ください。
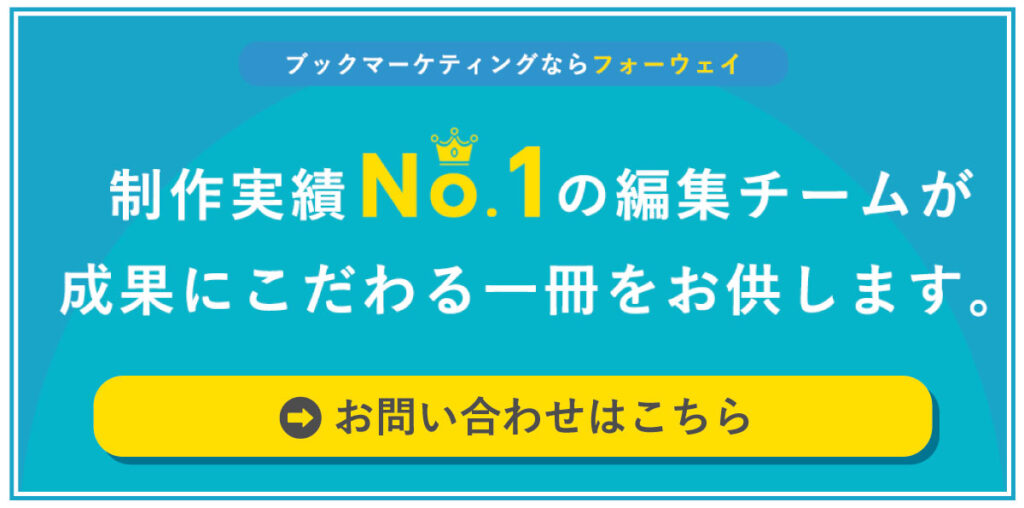

デジタル広告費の高騰が続くなか、「これだけ予算をかけているのに、売上につながらない」と頭を抱えるマーケティング担当者は少なくありません。
そんな課題を解決する手法として、いま再注目されているのがダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)です。
ダイレクトレスポンスマーケティングは、広告や販促の反応(レスポンス)を測定しながら、短期的な成果を狙って改善を繰り返すマーケティング手法です。
決して目新しい手法ではありませんが、少ないコストで成果を出すことを求められる現代のマーケティング現場において有効な手法の一つです。
また、チャットボットやMAツール、AIなどの進化により、誰でも手軽にダイレクトレスポンスマーケティングを実践しやすくなったことも普及の後押しとなっています。
この記事では、ダイレクトレスポンスマーケティングとはどのような手法なのか、そのメリットやデメリット、具体的な導入手順、継続的に成果を出し続けるポイントなどについて分かりやすく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
◉ダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)とは?

ダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)とは、広告や販促のメッセージを見た人に、その場で具体的な反応(レスポンス)を起こしてもらうことを目的としたマーケティング手法です。
資料請求や問い合わせ、商品購入など、明確なアクションを促すことを主な目的としています。
ダイレクトレスポンスマーケティングは1970〜1980年代にかけて、ダン・ケネディ(Dan Kennedy)やジェイ・エイブラハム(Jay Abraham)といったマーケティングの第一人者によって体系化されました。
彼らは「広告は即反応を得てなんぼ」という思想を打ち出し、成果の「測定」と「改善」を前提とした広告設計を重視してきました。
現在では、デジタルツールの進化により、誰でも効果検証可能な広告手法としてダイレクトレスポンスマーケティングを取り入れやすくなっており、コスト効率のよい集客手段として再注目されています。
◉-1、ダイレクトマーケティングとの違い
ダイレクトマーケティング(DM)とダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)は似た言葉ですが、目的やアプローチ・重視する指標が異なります。
ダイレクトマーケティングは、顧客と直接コミュニケーションをとる手法全般を指し、ダイレクトメールの送付やカタログ配送などが該当します。
一方、ダイレクトレスポンスマーケティングは顧客から即時の「反応」を得ることに特化した広告戦略であり、広告ごとの効果が数値で出てくるため、改善しやすいのが特徴です。
たとえば、「紙のカタログを送る」のがダイレクトマーケティング、「LP(ランディングページ)で購入や問い合わせを促す」のがダイレクトレスポンスマーケティング、という違いです。
目的や手法などの違いについて下表にまとめました。
| ダイレクトマーケティング(DM) | ダイレクトレスポンスマーケティング(DRM) |
| 目的 | 継続的関係の構築、ブランド理解、販売促進など | 資料請求・申込・登録など、今すぐ行動させること |
| 手法 | 郵送DM、メール、SMS、電話、訪問など | LP+Web広告、LINE誘導、セミナー申込、特典訴求など |
| 成果計測指標 | 開封率、到達率、返信率など | CVR(成約率)、CPA、LTVなど明確な数値成果 |
| 成果の出る速度 | 中長期的 | 短期的 |
◉ダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)を活用するメリット

「試しながら小さく始め、大きく育てる」のがダイレクトレスポンスマーケティングの特徴です。
ダイレクトレスポンスマーケティングの主なメリットとして、次の4つを挙げられます。
・即効性がある
・低予算で始めることができる
・費用対効果を明確に数値化できる
・データに基づくピンポイントな改善が可能 |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、即効性がある
ダイレクトレスポンスマーケティングとは、広告やオファーを通じて「その場で反応してもらうこと」を目的としたマーケティング手法です。
即効性が高いため、次のような短期間で成果を求める施策に特に効果を発揮します。
・限定キャンペーンの実施
・新商品のリリース告知
・セミナーやイベントの集客 |
ターゲットが明確でニーズと一致すれば、翌日から問い合わせが入ることも珍しくありません。
◉-2、低予算で始めることができる
ダイレクトレスポンスマーケティングは、少額の広告費から始められるのが特徴です。
そのため、大企業に限らず、中小企業やスタートアップでも無理なく導入できます。
広告への反応を見ながら段階的に予算を調整できるため、無駄なコストを抑えつつ、成果が出るポイントを見極めて運用を拡大することが可能です。
いわば「小さく試して、大きく育てる」戦略がとりやすく、特にリソースが限られた企業にとって実践しやすいマーケティング手法といえます。
◉-3、費用対効果を明確に数値化できる
ダイレクトレスポンスマーケティングの強みは、ユーザーの反応をすべて数値で可視化できる点です。
たとえば、広告やLPを通じて得られた「資料請求」「問い合わせ」「購入」といったアクションが具体的なデータとして記録されます。
そのため、「広告費に対してどれだけの成果があったか」という投資対効果(ROI)を明確に把握することができます。
感覚に頼るのではなく、数値に基づいて広告効果を判断できるため、改善にもつなげやすいのが特徴です。
◉-4、データに基づくピンポイントな改善が可能
ダイレクトレスポンスマーケティングでは、「どの広告やLPで何件反応があったか」「どの媒体で獲得単価が下がったか」など、詳細なデータがすぐに取得できます。
このため、社内の説得材料にもなりやすく、改善提案も具体的に出しやすくなります。
反応が悪ければ、見出し・オファー・CTA・媒体などの要素を仮説ベースで検証し、A/Bテスト(2つの広告パターンを比べるテスト)やPDCA(PLAN:計画、DO:実行、CHECK:確認、ACTION:改善のサイクル)で精度を高めることが可能です。
◉ダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)のデメリット

ダイレクトレスポンスマーケティングは、短期的に成果を出しやすい一方で、使い方を誤るとブランドイメージや営業効率に悪影響を及ぼす可能性もあります。
たとえば、短期成果を追求しすぎたり、「今すぐ購入を!」といった売り込み感の強い表現に偏ったりすると、ブランドの信頼性が損なわれるリスクが生じます。
即効性のある手法だからこそ、事前にリスクを理解したうえで運用することが重要です。
ダイレクトレスポンスマーケティングの主なデメリットとして、次の3つが挙げられます。
・強い訴求により誤解されるリスクがある
・中長期的なブランディング施策には向かない
・問い合わせの質が低下する可能性がある |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、強い訴求により誤解されるリスクがある
ダイレクトレスポンスマーケティングでは、限られた広告スペースや訴求機会の中で反応を得る必要があるため、キャッチコピーやオファーの表現が過剰になる傾向があります。
その結果、「押し売りのように感じる」「怪しい印象を受ける」といったネガティブな評価を受け、ブランドイメージを損なうリスクも生じます。
◉-1-1、社内理解が得られにくい場合もあるので注意
ダイレクトレスポンスマーケティングは、反応数や投資対効果(ROI)といった定量的な指標で効果を評価できるのが特徴です。
しかし、特にBtoB領域や経験重視の文化が強い業界では、「数値で反応を評価する」という文化が根付いていない場合も多く、社内の理解を得にくいことがあります。
そのため、導入にあたっては、KPI設計の妥当性を示す資料を用意したり、スモールスタートによる試験導入の成果を共有したりするなど、社内の合意を得ることが重要です。
◉-2、中長期的なブランディング施策には向かない
ダイレクトレスポンスマーケティングは、「今すぐ行動してもらうこと」を目的とした施策です。
そのため、ブランドの認知や顧客との信頼関係の構築といった、中長期的な視点でのマーケティングには向いていません。
そこで、ダイレクトレスポンスマーケティングを行う際は、ブランド価値を高めることを目的としたブランディング施策と組み合わせて運用することが重要です。
◉-3、問い合わせの質が低下する可能性がある
「無料プレゼント」や「割引キャンペーン」など、反応数の増加だけを目的にした施策を打ち出すと、購買意欲の低い層からの問い合わせが増える可能性があります。
その結果、実際の成約につながらなかったり、LTV(顧客生涯価値)が低くなったりと、見かけの数字は良くても、事業への実質的な成果は乏しくなることも考えられます。
ダイレクトレスポンスマーケティングを運用する際は、単なる反応数ではなく「質の高い反応」を得られる設計を意識しましょう。
◉ダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)の導入手順

ダイレクトレスポンスマーケティングは、以下の手順で導入するのが一般的です。
・手順1:目的設定
・手順2:ターゲット設計
・手順3:オファー設計
・手順4:導線設計
・手順5:広告媒体の選定・広告出稿
・手順6:反応計測
・手順7:改善 |
重要なのは、一度実施して終わりにするのではなく、この一連の流れをスピーディーに繰り返し、PDCAサイクルを回し続けることです。
つまり、「戦略的な設計」と「数値に基づく継続的な改善」の両輪で運用していくことが、成功のポイントとなります。
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、手順1:目的設定
はじめに行うべきは、「何をもって成功とするか」を明確に定義することです。
たとえば、以下のようなアクションをコンバージョン(CV)として設定します。
・資料請求
・問い合わせ
・無料相談
・予約メール・LINE登録
・商品購入 |
目的が明確でないと、適切な広告の種類・媒体・訴求方法・計測方法が定まりません。
ダイレクトレスポンスマーケティングを成功させるためには、最初に「コンバージョンの定義」を正確に行うことが不可欠です。
これがすべての施策設計の土台となります。
◉-2、手順2:ターゲット設計
次に、「今すぐ反応しそうな人」に絞ってペルソナを設計します。
ダイレクトレスポンスマーケティングでは、情報収集段階の「潜在層」よりも、すでに課題を自覚し行動に移ろうとしている「顕在層」を優先的に狙うことが成功のポイントです。
たとえば、次のような視点から「今まさに困っている人」「すでに比較検討を始めている人」などを具体的にイメージしましょう。
・年齢・性別・職業・家族構成
・現在の悩み・ニーズ
・どのような情報を求めているか |
「誰に届けるか」を絞り込むことで、反応率を高めることができます。
◉-3、手順3:オファー設計
ダイレクトレスポンスマーケティングでは、顧客の反応を引き出すための特典・提案を用意することが重要です。
そのためには、次のようなオファーを具体的に設計します。
・無料ダウンロード資料
・限定割引や特典付きキャンペーン
・診断サービスや無料相談
・来場特典・ノベルティの提供 |
オファーを設計する際は、顧客が「この価値なら手間や個人情報提供をしてもよい」と思える「価値>価格や手間」になるように設計するのがポイントです。
◉-4、手順4:導線設計
せっかく顧客が興味を持ってくれても、導線がわかりにくかったり、手間がかかったりすると、途中で離脱してしまう可能性があります。
そのため、「ストレスなく、迷わず行動できる導線設計」を徹底することが重要です。
具体的には、以下のポイントを意識して整えましょう。
・LPの構成・コピー・CTA配置
・CTAボタンのテキストと目立ちやすさ
・フォームの入力項目を最小限に
・モバイル最適化(レスポンシブ対応) |
また、電話・LINE・QRコードなど複数のアクション手段を用意することで、ユーザーの選択肢を広げることも効果的です。
◉-5、手順5:広告媒体の選定・広告出稿
どれだけ良い設計をしても、適切な場所に広告を出すことができなければ効果は得られません。
ターゲットに確実にリーチするためには、媒体の特性を理解し、適切な広告媒体を選定することが不可欠です。
主な広告媒体として、次のようなものがあります。
- Web広告
- 新聞
- 雑誌
- ポスティング
- 紙DM
- 交通広告
- メールマガジン
各媒体には、ユーザーの年齢層や行動パターンに違いがあります。
設計したペルソナをもとに、適切な媒体を選び、地域・属性・時間帯などのセグメント設定を最適化することが、広告効果を最大化するポイントです。
◉-6、手順6:反応計測
出稿したら終わりではなく、成果を数値で「見える化」することも重要です。
主な計測項目としては、次のようなものがあります。
・広告費用(Ad Cost)
・クリック率(CTR)
・LPの遷移率・離脱率
・CV数(資料請求数・問い合わせ数など)
・CPA(1件あたりの獲得コスト) |
また、計測には次のようなツールの活用が有効です。
・Google Analytics 4(GA4)
・広告マネージャー(Meta、Google Adsなど)
・ヒートマップ・フォーム解析ツール |
専用の電話番号やQRコードを活用することで、オフライン経由のコンバージョンを追跡することも可能です。
◉-7、手順7:改善
ダイレクトレスポンスマーケティングでは、反応の良し悪しを分析しながら、PDCAサイクルを継続的に回していくことが成果につながります。
反応が思わしくなかった場合は、その要因を特定し、1つずつ施策を調整・最適化していきましょう。
主な改善策として、以下があります。
・バナーのデザインやコピーをA/Bテスト
・LPの構成やCTA位置を変更
・オファーの種類や訴求内容を変更
・広告出稿先の媒体や時間帯を見直し |
一度で最適解を出そうとせず、「仮説→実行→検証→改善」のPDCAサイクルを繰り返すことが大切です。
◉ダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)で成果を出し続けるポイント

ダイレクトレスポンスマーケティングは、即効性のあるマーケティング施策として有効ですが、短期成果のみに依存すると、次第に成果が鈍化し、持続的な成長につながりにくくなるリスクがあります。
そのため、ダイレクトレスポンスマーケティングを単発の施策に終わらせず、継続的に成果を出し続けるための仕組み化が不可欠です。
具体的には、以下の3つのポイントを意識することで、ダイレクトレスポンスマーケティングを中長期にわたって有効活用できます。
・数値に基づきPDCAサイクルを回し続ける
・自動でリードを育成・反応させる仕組み化を行う
・中長期的なマーケティング施策と並行して実施する |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、数値に基づきPDCAサイクルを回し続ける
ダイレクトレスポンスマーケティングの強みは「効果を数値で測れること」です。
だからこそ、感覚や勘に頼らず、データを元に改善を積み重ねることが重要です。
具体的には、次のような方法があります。
・明確なKPI(CV数、CTR、CPAなど)の設計
・A/Bテストの実施
・数値分析→仮説立て→再検証のPDCA |
数値を見ながら「何がボトルネックか」「どこを改善すべきか」を冷静に分析し、施策を進化させていきましょう。
◉-2、自動でリードを育成・反応させる仕組み化を行う
ダイレクトレスポンスマーケティングは即効性に優れる手法ですが、毎回手作業で施策を実行するのは非効率です。
そこで重要になるのが、「リードナーチャリング(見込み顧客の育成)」と「アクション誘導」の仕組み化・自動化です。
主な手法としては、以下のようなものがあります。
・LINEステップ配信:見込み客に段階的に情報提供し、信頼関係を構築
・メールマーケティング(MA):セグメント別に最適なコンテンツを配信
・CRM連携:行動履歴に応じて適切な施策を自動実行 |
また、ただリードを集めるのではなく、質の高いリードへと育てるために、「教育→信頼構築→アクション」という一連の流れを設計することも必要です。
◉-3、中長期的なマーケティング施策と並行して実施する
ダイレクトレスポンスマーケティングは短期の刈り取り施策として強力ですが、「見込み客を増やす」「信頼を築く」といった中長期的視点のマーケティングとは役割が異なります。
そのため、次のような中長期施策と併用することが重要です。
・コンテンツマーケティング・SEO:潜在層や比較層との接点づくり
・SNS運用:接触頻度を高め、反応率を引き上げる土壌づくり
・書籍出版:信頼・専門性・ブランディングの向上 |
こうした中長期視点の施策とダイレクトレスポンスマーケティングを並行して行うことで、反応率やコンバージョン率(CVR)の向上が見込めるだけでなく、「広告依存型」の集客体質から脱却し、持続的なマーケティング戦略を築くことが可能になります。
◉-3-1、「ダイレクトレスポンスマーケティング」×「書籍出版」
書籍は、専門性や信頼性を読者に伝えるための中長期的なマーケティングツールとして有効です。
「ダイレクトレスポンスマーケティング」と「書籍出版」を組み合わせることで、短期と中長期の両面に効果を発揮するマーケティングを実施できます。
読者に価値ある情報を提供しながら、巻末にQRコードやURLを設置してLINE登録や特典配布へ誘導することで、「書籍→登録→特典→セミナー誘導」といったダイレクトレスポンスマーケティングの反応導線を設計することが可能です。
このように、書籍出版は認知の拡大や信頼構築と同時に、具体的なアクションを促す導線設計にも活用できるため、ダイレクトレスポンスマーケティングと高い親和性があります。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。

◉-3-2、「ダイレクトレスポンスマーケティング」×「SNS」
「ダイレクトレスポンスマーケティング」と「SNS」の組み合わせも効果的です。
InstagramやX(旧Twitter)、TikTokなどを活用して日常的に情報を発信し、ユーザーとの接点を増やすことで、信頼関係を築いていきます。
そこから、DMやプロフィールリンク、投稿内のCTAなどを活用してLINE登録やLPへの遷移を促すことで、SNSを「信頼形成→即レスポンス誘導」の導線として活用できます。
SNSは、接触頻度の増加を通じて「ダイレクトレスポンスマーケティングの反応率を底上げする土台」として有効です。
▶︎SNS運用のやり方については、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】もあわせて参考にしてください。
◉-3-2、「ダイレクトレスポンスマーケティング」×「SEO」
「ダイレクトレスポンスマーケティング」と「SEO」との連携も、広告に依存せずに質の高いリードを獲得できます。
検索から流入してくるユーザーは、課題意識が高く、すでに比較・検討フェーズに入っていることも多いため、「検索→情報収集→登録・相談」といった自然な導線を作りやすいのが特徴です。
・お役立ち資料のダウンロード
・無料相談の申し込み
・LINE登録やメルマガ登録の案内 |
このように、ダイレクトレスポンスマーケティングとSEOを連携させることで、中長期的にリードを獲得し続けるための安定した仕組みを作ることができます。
▶︎SEOのやり方については、関連記事【SEO対策とは? 効果的な戦略の組み立て方と対策方法】もあわせて参考にしてください。
◉【まとめ】ダイレクトレスポンスマーケティング×中長期施策で成果を出し続けることが重要!
この記事では、ダイレクトレスポンスマーケティングとは何か、メリット・デメリットや具体的な導入手順、継続的に成果を出し続けるポイントについて解説しました。
もともとダイレクトレスポンスマーケティングは短期的な成果を狙って改善を繰り返す手法ですが、これに書籍出版やSNS、SEOなどの中長期施策をうまく掛け合わせることで、ダイレクトレスポンスマーケティングの効果を一時的なものにとどめず、ブランド全体の成長戦略の中に組み込むことができます。
中長期的なマーケティング施策の中で特におすすめなのは書籍出版です。
信頼性を高めながら即時のアクションも促せるため、ダイレクトレスポンスマーケティングとの相性が良く、高い相乗効果が見込めます。
株式会社フォーウェイでは、書籍をマーケティングに活用する「ブックマーケティングサービス」を行っています。
書籍出版はダイレクトレスポンス効果に優れており、「書籍を読んだのがきっかけで問い合わせが入り、初回の商談で億単位の契約が即決された」という実績も多数あります。
ダイレクトレスポンスマーケティングと書籍出版の組み合わせについてのご相談は、株式会社フォーウェイまでお問い合わせください。


世の中は情報に溢れ、企業が情報発信しても全く見られなかったり、読まれなかったり、反応がほとんどなかったりが当たり前の時代。
・HPを作って情報発信を行ってみたけれど、閲覧者がほとんどいない…
・SNSで情報発信をしているが反応がいまいち…
・色々な媒体で情報発信を行っているのに、成果につながらない… |
そんな情報発信に関する悩みを抱え、どの情報発信ツールをどのように使えば良いのかが分からなくなっている経営者や広報・マーケティング担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、情報過多の時代にしっかりとターゲットに自社の情報を届けるために知っておくべき企業の情報発信に有効なツールや、それぞれの効果的な活用方法などを詳しく解説いたします。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉企業の情報発信に有効なツール一覧

企業が情報発信するために有効なツールとしては、以下のようなものがあります。
◉-1、HP(ホームページ)
HPは企業が情報発信を行うための軸となる情報発信ツールの1つです。
HPでは、主にミッションやビジョン、行動指針といった経営方針や、会社の沿革、行っている事業や商品・サービスの紹介、所在地や代表者名のような会社概要など、企業の基本情報を発信します。
HPに掲載する内容を定期的に更新したり、ブログ機能をつけてお知らせをしたり、「スタッフブログ」や「コラム」で記事という形で情報発信をしたり、比較的自由に情報発信を行うことができるというのが特徴です。
また、HPは銀行口座の開設や融資の審査などの際にHPの情報が求められたり、企業の信頼性を図る一つの指標ともなっており、企業の情報発信の基幹となる必須ツールとも言えるでしょう。
しかし、HP上で発信した情報をターゲットに見てもらえるまでにはタイムラグが発生するため、時間の経過とともに変わるトレンド性や即効性の高い情報の発信には不向きです。
恒久性のある情報をきちんと保存していく情報発信媒体として活用するのが効果的と言えます。
なお、HPをただ単に作っただけでは見てもらえません。
URLをSNSなどでシェアしたり、SEO対策をして検索結果で上位表示させたり、ブログ投稿で入り口を増やしたりするなど、HP上で情報発信を行っていることを周知していく施策を合わせて行う必要があります。
◉-2、SNS
SNSは気軽に情報を発信してフォロワーとの間でコミュニケーションを取ることができるツールです。
リアルタイムで膨大な情報が流れており、拡散性が高い反面、情報の寿命が短いという特徴があります。
また、SNSといっても多くの種類があります。
それぞれ、情報発信の方法やユーザー層、特性が異なるので、企業が発信したい情報や、ターゲットに合わせてSNSを使い分けていくことが大切です。
| SNS名 | 国内月間アクティブユーザー数 | 主なユーザー層 | 情報発信の方法 | 特性 |
| LINE | 9,600万人(2023年9月時点) | 全世代(中でも50代が多め) | ・LINEメッセージ | 自社サービスと連携してメルマガや1to1施策で活用できるSNS |
| YouTube | 7,120万人(2023年5月時点) | 全世代 | ・ショート動画・動画 | 世界最大の動画SNS。インフルエンサーマーケティングに活用される |
| X(旧Twitter) | 6,658万人(2024年1月時点) | 20代〜30代が過半数 | ・140文字以内の投稿・長文の投稿・画像 / 動画 | リアルタイム性のある情報が投稿され、情報拡散しやすい、一方で炎上しやすいSNS |
| Instagram | 6,600万人(2023年12月時点) | 20代〜30代で半数を占める | ・画像・リール動画・ストーリー | 雑誌感覚で食や美容、メイク、ファッションなどビジュアルの情報発信と相性が良いSNS |
| Facebook | 2,600万人(2019年3月時点。それ依頼発表なし) | 30代〜50代が多い | ・文章 / 画像 / 動画による投稿 | 実名登録がマストなため、安心感があり、ビジネスシーンでの活用が多いSNS |
| TikTok | 2,800万人(2024年2月時点) | 10代〜20代で半数を占める | ・ショート動画 | エンタメ系の投稿と相性が良く、企業の採用などによく使われるSNS |
▶︎SNS運用については、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】もあわせて参考にしてください。
◉-2-1、X(旧Twitter)
X(旧Twitter)は140文字の短文でコミュニケーションをするSNSです。
国内の月間アクティブユーザーは約6,658万人(2023年5月時点)で、若年層のユーザーが多い傾向にあります。
X上では、リアルタイム性の高い情報が日々飛び交っており、情報拡散がしやすいのが特徴。
興味を引く投稿はリポストなどによって拡散されて爆発的な集客を得ることもできます。
フォロワーからの反応も早いため、たとえば、次のようなトレンド性や即効性の高い情報の発信に向いています。
・新商品やサービスのティーザー(「あと数日で販売開始」など)
・期間限定のキャンペーン告知
・システム障害などの緊急情報
・時事性の高い情報 |
こういった特徴から東北大震災など災害の際の現地情報収集元として活用されたり、選挙活動など政治などにも活用されています。
一方で、投稿した情報がすぐに古くなってしまうため、あまり変化のない情報発信には向いていません。
むしろ、HPやWebメディアで発信した恒久的な情報を広く拡散するためにXを活用したりします。
◉-2-2、Instagram
Instagramは画像や動画の投稿がメインのSNSです。
国内の月間アクティブユーザーは約6,600万人(2023年12月時点)で、メインユーザーは20代~40代です。
総務省の「令和5年 情報通信に関する現状報告の概要」によれば、特に20代の利用者が最も多く、約78.6%の人が利用。
次いで10代(約72.3%)、30代(約57.1%)と利用者が多くなっています。
また、性別で言えば女性ユーザーの利用が約59%と多くなっています。
2017年に「インスタ映え」という言葉が流行語大賞を受賞したように、食や美容、メイク、衣類、アクセサリー・雑貨などの見た目のビジュアルが重要な情報発信と相性が良いのが特徴です。
近年、ビジネスアカウントの登場や、ストーリーズ、リール動画などさまざまな機能が追加された上、投稿から商品ページに直接遷移するショップ機能がついたため、自社で販売する商品やサービスの情報発信やブランディングなどに活用する企業も増えてきています。
一方で、ビジュアルで訴求が難しい情報との相性が悪いため、文章での情報発信や訴求には向いていません。
◉-2-3、Facebook
FacebookはMeta社が運営する全世界の利用者数が30億人を超える世界最大のSNSで、他のSNSとは違い、実名利用が必須なので炎上しにくく、ビジネスユーザーの利用が多いのが特徴。
国内の月間アクティブユーザーは約2,600万人(2019年3月時点、それ以降発表なし)で、30代~50代のユーザーが多い傾向があります。
実名登録が必須という制度上、企業の代表や営業マンなどが情報を投稿したり、DMで営業メールを送ったり、人主体での発信がメインになってしまうため、企業主体の発信には利用されない傾向があります。
企業による情報発信の場合、プラットフォーム内に年齢や性別、居住地、趣味・嗜好、行動傾向など膨大なデータが蓄積されており、精度の高いターゲティングができるということから、広告などが主に活用されます。
◉-2-4、TikTok
TikTokは中国発のショート動画SNSです。
15〜60 秒の短尺動画の投稿がメインです。
国内の月間アクティブユーザーは約2,800万人(2024年2月時点)で、総務省の「令和5年 情報通信に関する現状報告の概要」によれば、10代の利用率が約62.4%、20代の利用率が46.5%と多いことから、若年層向けの情報発信におすすめのSNSです。
X(旧Twitter)と同様にトレンド性の高い情報との相性がよく、拡散性も高いのが特徴。
1つの動画が一気に数千、数万、数十万回再生されるなど、話題になると一気に情報が拡散していきます。
若年層のユーザーが多いことや、エンタメ性のある投稿が多いことから、企業の採用活動などに活用されることが多くなっています。
◉-2-5、YouTube
YouTubeは世界最大の動画共有サイトで、国内のアクティブユーザーは約7,120万人(2023年5月時点)です。
ショート動画と長尺の動画が投稿でき、自社の商品やサービスに関連する有益な情報を分かりやすく紹介したり、YouTuberなどとコラボしたインフルエンサーマーケティングなどに活用されます。
Google社が運営しているため、Googleの動画検索などに表示ができ、SEO効果が期待できるのも特徴です。
YouTube内でも検索需要があり、動画の概要欄などを最適化してYouTubeの検索結果で上位表示を目指すことでより閲覧されるように工夫することも可能です。
▶︎Youtube動画については、関連記事【YouTube動画の作り方をカンタン解説!初心者でも再生回数を稼ぐテクニック】もあわせて参考にしてください。
◉-2-6、note
noteは文章や写真・イラスト・音楽・映像などの作品を配信できるブログ形式のサイトで、月間アクティブユーザー(ブラウザ数)は約5,145万人(2023年11月現在)です。
クリエイターやビジネスパーソンなどにブログとして、自社のノウハウや商品・サービスの開発背景などの情報発信に利用されています。
最大の特徴は、記事コンテンツの有料販売ができる点です。
情報発信自体を収益化することができます。
◉-2-7、LINE
LINEはLINEヤフー株式会社が運営するメッセージ型のSNSです。
国内の月間アクティブユーザー数は約9,700万人で、SNSというよりはメッセージアプリという印象が強いかもしれません。
企業アカウントを作成することで、友だち登録してくれたユーザーに向けてメッセージやクーポン・キャンペーン情報を送ることができたり、メルマガのような感覚で情報発信ができるのが特徴。
LINEから直接HPやECサイト、予約ページに遷移させたり、さまざまな機能が備わっていたり、個別にメッセージを送れたり、メルマガシステムなどに比べて気軽にユーザーと密にやりとりできる情報発信ツールとして多くの企業に活用されています。
◉-3、メルマガ
メルマガは登録した顧客やステークホルダーに、自社の製品やサービス、イベント、キャンペーンなどの情報を定期的に発信するツールです。
近年ではMA(マーケティング・オートメーション)ツールと連携して顧客の行動やステータスなどによってメールを出し分けたり、OnetoOne施策に欠かせないものとなっています。
また、見込み客獲得や顧客教育や、引き上げ(アップセル)になくてはならないツールと言えるでしょう。
送られたメールは新しく届くメールにどんどん流されていくため、新商品・サービスの販売、セミナー開催などの告知情報など、即効性やトレンド性の高い情報発信に適しています。
◉-4、オウンドメディア
オウンドメディアは企業が所有する情報発信メディアの総称です。
たとえば、自社のHPで更新しているコラムや、HPのサブドメインや別ドメインで運営するジャンルの情報発信に特化したWebメディアなどがオウンドメディアに該当します。
アメブロやはてなブログなどのブログサービス、noteなどのSNSなどと比べて、自社の意思によって自由に情報発信やコンテンツの保存ができ、第三者に削除されないという特徴があります。
一方で、記事を更新したからと言ってすぐに見られることはありません。
あるキーワードでの検索順位が上がったり、更新した記事をメルマガやSNSなどで告知することで見てもらえるようになってきます。
そのため、即効性やトレンド性の高い情報発信には向いていません。
知っておくと便利なお役立ち情報や知識、悩みの解決方法など長期間変わらないような情報発信に適しています。
▶︎SEO対策については、関連記事【SEO対策とは? 効果的な戦略の組み立て方と対策方法】もあわせて参考にしてください。
▶︎参照:オウンドメディアのメリット・デメリットとは?成果を出すポイントを解説! | COUNTER株式会社 | 埼玉県越谷市のデジタルマーケティングカンパニー
◉-5、ブログ
ブログはもともと個人の意見や情報を公開するプラットフォームでしたが、現在では企業の情報発信や集客ツールとしての利用が多くなっています。
「アメブロ」「はてなブログ」などのブログサービスを利用したり、自社HP内にブログ機能を設置して情報発信を行うのが一般的なやり方です。
自社HPに設置したブログを更新した場合は、オウンドメディアと同様にすぐに見られることはありませんが、ブログサービスを利用した場合には、「新規更新欄」などに掲載されるためSNSのnoteと同様に比較的早く見てもらうことができます。
そのため自社スタッフの日記など、リアルタイムの情報発信であればブログサービスの方が適しています。
検索経由でしっかりと発信したい情報などであれば自社HPに設置したブログを利用する方が良いと言えるでしょう。
◉-6、プレスリリース(PR)
プレスリリースは企業からメディアに向けた公式な情報発信手段です。
新商品や新サービスの発表や業績報告・業務提携・キャンペーンの案内などをメディアに対して行い、Webメディアや雑誌、新聞、TVなどで取り上げてもらうことが目的です。
ターゲット層が多く閲覧している各メディアに取り上げられることで認知獲得につながる可能性があります。
メディア側は常に新しい情報の種を探しているので、時代性やトレンド、今までになかったような切り口での情報発信を心がけることで、取り上げられやすくなります。
◉-7、Googleビジネスプロフィール
GoogleビジネスプロフィールはGoogleマップ上でビジネス情報を発信できる無料のサービスです。
たとえばGoogleマップ上で「駅名 居酒屋」と検索すると、多くの居酒屋の情報が出てきます。
表示できる情報は所在地・営業時間・電話番号・最新情報などがあり、最新情報を活用すると新商品・キャンペーン情報をタイムリーに発信することが可能です。
Googleマップ上に表示される情報であるため、店舗のあるビジネスとの相性が良いのが特徴。
店舗系ビジネスではぜひ活用しておくべき情報発信ツールと言えるでしょう。
◉-8、DM
DMは企業がターゲット層に郵送や電子メールを送付するという情報発信方法です。
具体的にはターゲット層の企業のリスト1つひとつにDMを郵送したり、企業のメールアドレスに直接広告メールを送付したりします。
郵送DMはコストはかかるものの、実体のあるものが届きますので比較的レスポンス率が高く、顧客の認知や関心を高めることが可能です。
利用できるクーポンなど次のアクションにつなげやすいオファーをつけておくのがポイントです。
メールについては基本的に無視されますが、郵送DMほど手間をかけずに多くのリスト向けに送付できるというメリットがあります。
郵送DMは確度の高いターゲット層向けや、高単価商品・サービスの場合、メールについてはBtoB向けの商品・サービスの場合、などうまく使い分けをしていくことが重要です。
◉-9、チラシ
チラシは1枚の紙の両面または片面に情報を印刷したものです。
商品やイベントなどの案内・告知を目的として大量に配布するために利用されます。
代表的な配布方法は、新聞折込チラシ・ポスティング・街頭ビラ配りなどです。
実態のあるものがターゲットに届くため、WebやSNSなどに比べて見てもらいやすいのがメリットと言えます。
地域密着型のビジネス(水道修理、士業、マッサージ店、美容院、不動産など)におすすめの情報発信方法です。
しかし制作に手間とコストがかかるので、ターゲット層の多いエリアをしっかりとセグメントをした上で配布していくのがポイントです。
◉-10、パンフレット
パンフレットは複数枚の紙を折り曲げて重ねて冊子にした印刷物です。
会社案内や製品・サービスの詳細な紹介など、情報量の多い用途に利用されます。
WebやSNS、また1枚もののチラシやDMとは違い、何度も作り直したりすることは難しいため、中長期で変わらないような情報の発信に向いています。
一方で、「パンフレットをきちんと作れるようなしっかりとしたところなんだ」という紙媒体ならではの信頼性のアピールにもつながるのが特徴です。
また、パンフレットはWebやSNSとは違い、机に並べて比較検討しやすいということもあり、大学や学習塾、老人ホーム・介護施設、建設会社など、商品やサービス、取引先選びの際に比較検討をするような業界の情報発信ツールとしてもおすすめです。
▶︎パンフレットのマーケティング活用については、関連記事【商品やサービスが売れるパンフレットを作るポイントと有効活用方法】もあわせて参考にしてください。
◉-10-1、パンフレットによる企業の情報発信成功事例
ある投資スクールでは、投資に興味があるものの何から取りかかれば良いのか分からないという人に向けて「入校を後押しする」パンフレットを制作。
パンフレットの中で、投資スクールのサービス内容や講師陣、受講料などの説明のほかに、実際に投資スクールを受講して利益を得た人のインタビューを掲載したり、メディア実績を掲載したりして、信頼性が得られるような工夫を行いました。
その結果、パンフレットを読んで「自分でもできるかもしれない」という気持ちになった多くの方から問い合わせが増え新規入校者の増加につながっています。
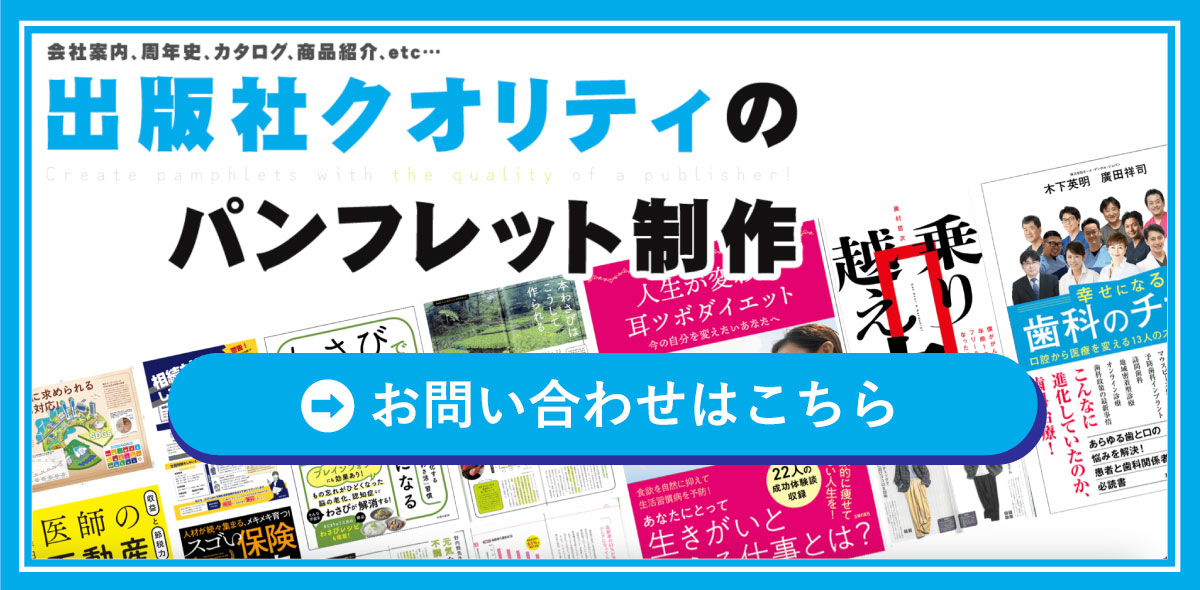
◉-11、名刺
名刺は名前や会社名・所属・住所などのプロフィールを記載した情報発信ツールです。
ビジネス上の初対面の相手に自分のプロフィール情報を伝えるのに適していますが、話のきっかけづくりや、後で見返した時に相手が興味を持つような工夫をするのがおすすめです。
掲載できる情報は少ないですが、うまく興味を惹くことができれば新規顧客の獲得にもつながる可能性があります。
◉-12、書籍
書籍は自社や自社の商品・サービスのことをより詳しく知ってもらいたい場合に有効な情報発信ツールです。
書籍の最大の特徴は社会的信頼性が高いことで、出版をきっかけに各種メディアに取り上げられたり、著者がセミナー講師に招かれたりすることもあります。
また、WebやSNSとは違い「読まれる媒体である」ということが大きな特徴です。
一般的な書籍の場合、7万字~10万字もの情報を盛り込むことができます。
そのため、商品やサービスの情報だけでなく企業の歴史・創業者の想い・理念・開発秘話などをストーリー性を持ってまとめて伝えることが可能です。
ただし、出版しただけで読まれる訳ではないですし、注目される訳でもないので、その点には注意しましょう。
出版後の書店配本はもちろんのこと、SNSやクラウドファンディング、SEOなどあらゆるデジタルマーケティングを駆使して、ターゲットの手元に届けることができてはじめて効果を発揮します。
信頼性の高さから、不動産投資や保険、コンサル、住宅など、契約までのリードタイムが長い業界、富裕層向けビジネス、広告規制が厳しい健康食品やサプリなどの情報発信に向きます。
また、競合が多すぎて差別化が難しいような業界や、あらゆるWebマーケティングなどをやり尽くした後のさらなる会社の発展、認知度拡大のための情報発信ツールとしても有効です。
▶︎ブックマーケティングについては、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】もあわせて参考にしてください。
◉-12-1、書籍による企業の情報発信成功事例
ある保険代理店の経営者は、保険業界の実態と保険業界に定着している「成果報酬型」の給与体系を「一律報酬型」に変えることによって業績向上が目指せるという持論を世に問うために書籍を出版。
その結果顧客や同業者からの見られ方が大きく変わって、大型契約などの成約に成功したり、講演会の講師に招かれたりするようになりました。
書籍の出版によって自社の信頼性が高まって、商談の際に顧客企業の経営にまで踏み込んだ相談を受けるケースも出てきています。
本来の出版目的であった、同業の保険代理店からのコンサル依頼がまず数件。そして驚いたのは、保険会社から講演の依頼が来たり同業支援の話が回ってきたりと、「保険会社にとって頼れる代理店」というありがたいイメージを持ってもらえるようになったことです。保険代理店はコンビニより数が多いうえ、扱う商品で差別化ができません。保険会社側から一目置いてもらえる代理店になることの価値はとても大きいんです。
引用元:【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店 |
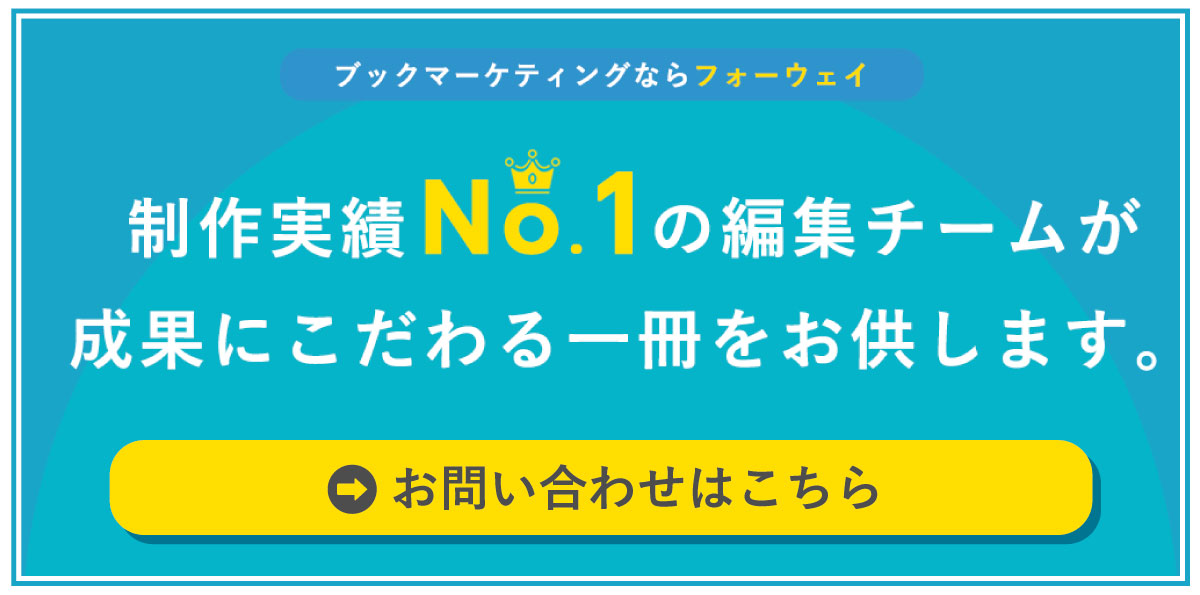
◉-13、ニュースレター
ニュースレターは、主に企業のファンづくりのためのコミュニケーションツールとして定期的にメールや郵送で配信されるものです。
ターゲットは顧客だけではなく、株主や従業員・メディア関係者などのさまざまなステークホルダーです。
DMが広告宣伝を主目的としているのに対して、ニュースレターは企業に対して親しみを持ってもらうことに重きを置いていることが特徴です。
そのため、商品やサービスの情報というよりはむしろ関連するお役立ち情報や、企業の社長、社員、スタッフなどのインタビュー、などの情報発信に向いています。
Web上のブログなどと比べて読まれやすく、印象に残りやすいのがメリットと言えるでしょう。
◉-14、Web広告
Web広告はインターネット上のメディアに掲載される広告の総称で、検索時に表示される広告やSNSで表示される広告などです。
Web広告と言っても広告の出し方や出す媒体によって、次のように多くの種類があります。
・リスティング広告
・ディスプレイ広告
・アフィリエイト広告
・記事広告
・動画広告
・メール広告
・SNS広告 |
そのため、年齢や性別などの属性によってターゲティングをして、特定のターゲットに向けて効率的に広告を配信することができるという特徴があります。
また、Web広告の閲覧数やクリック数などを集計してほぼリアルタイムに広告効果を分析でき、分析結果を見ながら訴求内容やターゲットの変更が行えるのも特徴の1つです。
コラムのような読み物系ではなく、商品やサービスの宣伝に向く情報発信ツールです。
◉-15、TVCM
テレビ番組の途中や番組の間に放送されるCMを活用する方法です。
企業が自社の商品やサービスの宣伝をするために、テレビ局のCM枠を購入して広告を配信します。
TVCMは年代や性別を問わず幅広い視聴者へ効率的に情報発信を行えるマス広告の一つで、即効性があり商品やサービスの認知や購買意欲を促進するというメリットがあります。
大きく認知を広げていきたい時におすすめの情報発信方法と言えるでしょう。
地方ローカル局や、TverなどのネットTVなど比較的安価で活用できるTVCMも増えてきていますが、キー局などは数千万円〜数億円など多額の費用がかかるので、なかなか情報発信方法としてはハードルが高い方法と言えます。
また、番組を見ている視聴者層や、曜日、時間帯などのターゲットは可能ですが、Web広告のように細かなターゲティングができず、広告効果の測定が難しいというデメリットもあります。
◉-16、デジタルサイネージ
デジタルサイネージは駅や店舗・施設・オフィスなどに、ディスプレイやプロジェクターを設置して情報を発信するシステムです。
従来ポスターや看板で情報発信していたものが、デジタルサイネージに置き換わってきています。
最初にデジタルサイネージが使われたのは駅構内でしたが、最近では各種店舗や病院・宿泊施設・銀行・学校などあらゆるところに設置されています。
◉情報過多の中、企業が情報発信ツールを効果的に活用するポイント

これまでに紹介してきたように多くの情報発信ツールがありますが、これらを何の意図もなく使っているだけでは効果的な情報発信はできません。
次の3つのポイントを押さえた上で、明確な意図と戦略をもって情報発信ツールを使い分けることが企業の情報発信のコツです。
◉-1、情報発信の目的を明確にする
情報発信をする際は「誰に何を伝えて」「どうしたいのか」という目的を明確にする必要があります。
なぜなら目的に応じた最適な情報発信ツールを選定しなければならないからです。
たとえば数日限定キャンペーンの応募者を増やす目的で、即効性やトレンド性の薄いHPを選択しても期待する効果は得られないでしょう。
情報発信の目的が「集客や問い合わせ数や売上数の向上」なのか、「認知度を拡大していきたい」のか、「世の中に周知したい」のかなどを明確にすることが大切です。
◉-2、情報発信ツールの得意・不得意を把握する
情報発信ツールには得意・不得意があるので、これをきちんと把握しておく必要があります。
たとえばX(旧Twitter)は拡散性が大きいため話題性やトレンド性のある情報発信は得意ですが、しっかりと文章を読みこんでもらいたい長文の情報発信は不得意です。
Instagramは画像や動画で視覚的に訴求するような情報発信は得意ですが、文章での情報発信は不得意です。
このように、「自社の発信したい情報をうまく訴求できる媒体は何か?」をしっかりと考えた上で情報発信ツールを選定していく必要があります。
◉-3、デジタルとアナログをうまく組み合わせる
企業の情報発信では、デジタルとアナログをうまく組み合わせることが効果的です。
たとえば、リコーが行なった「DM実証実験結果」によれば、顧客をWebサイトに誘導する手段としてeメール(メルマガ)を使っていましたが、開封率は13.8%、Webサイト遷移率は1.5%と低い成果しか出ていなかったそうです。
そこでeメール送付後に紙のDMを送る検証実験を行ったところ、Eeメールの開封率が5.5倍の75.8%に、Webサイト遷移率が3.4倍の4.4%に大幅に向上。
つまりデジタルだけでは弱かった訴求が、アナログの強みをうまく組み合わせることによって大きな相乗効果が得られることが確認できたのです。
このように、デジタルの時代だからデジタルだけを活用するのではなく、アナログの特性も活かしていくことでより効果的な情報発信が可能になります。
▶︎デジタルマーケティングとアナログマーケティングの効果的な活用については、関連記事【デジタル全盛期だからこそ重要なアナログマーケティング戦略】もあわせて参考にしてください。
◉-3-1、デジタルとアナログをうまく組み合わせた成功事例
ある不動産投資会社の経営者は、医師をターゲットとして「高収入な医師に最も効果的な節税対策は不動産投資である」という書籍を出版。
企画段階からSNSやクラウドファンディングなどのデジタルのプロモーションを検討し、出版タイミングに合わせて実施しました。
その結果、狙い通りに多くの医師に書籍を購入してもらうことができ、書籍を購入した医師から成約を獲得して売上を倍増させることに成功。
また、既存顧客からの口コミなどによって評判が広がり、新規顧客の獲得にもつながっています。
書籍というアナログな情報発信ツールとSNSやクラウドファンディングなど、デジタルな情報発信ツールを組み合わせ成果につながった好例と言えます。
◉【まとめ】情報発信ツールを効果的に活用しよう!
本記事では企業の情報発信に有効なツールの特徴や企業が効果的に活用するためのポイントについて解説しました。
情報発信ツールには多くの種類がありますので、目的を明確にしたうえで適切なツールを選ぶことが大切です。
また、デジタル全盛の現代だからこそ、デジタルとアナログをうまく組み合わせることが効果的です。
デジタルマーケティングと書籍やパンフレット、チラシなどアナログマーケティングとの組み合わせをお考えなら、まずはフォーウェイにご相談ください。
お悩みや課題に合わせて最適なご提案をさせていただきます。
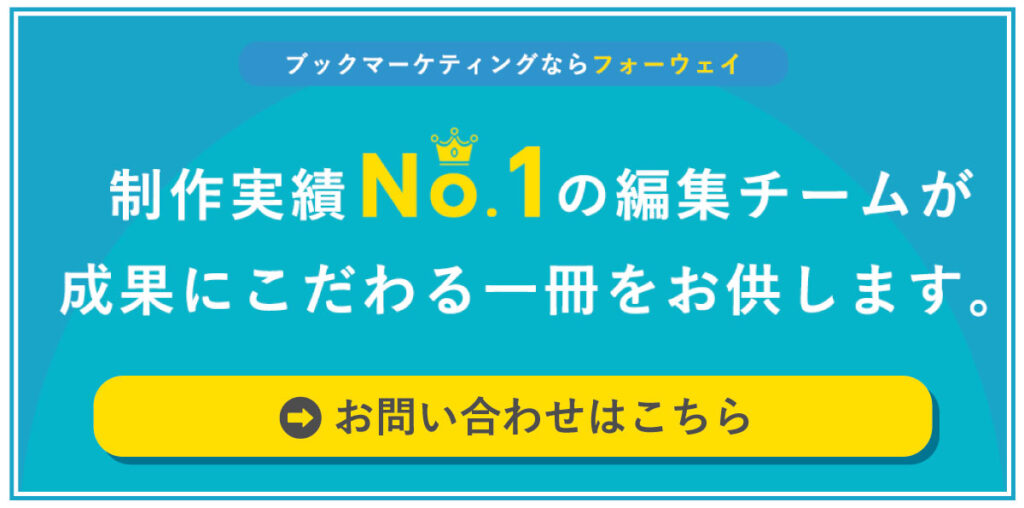
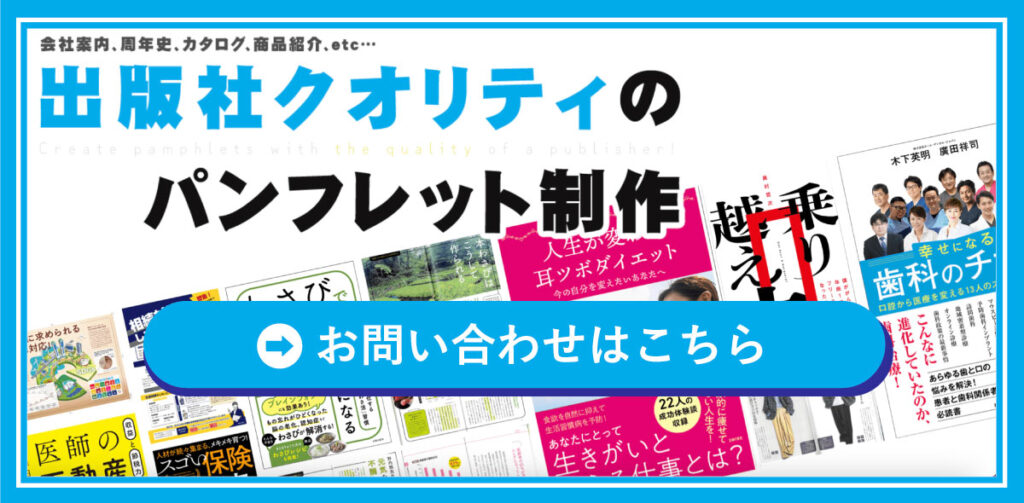

Webのマーケティング施策の一つとして、SEO対策という言葉が一般化しました。
とはいえ、上位獲得したいキーワードをサイトに散りばめたからといって簡単に検索上位に表示されるほど甘くないのが、SEO対策です。
SEO対策で検索上位に上げるために具体的にどのような対策を取るべきか、いま最も重要な要素といわれる「E-A-T」、そこからさらに発展した「E-E-A-T」を踏まえて解説していきます。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
◉SEO対策とは

SEOとは、Search Engine Optimizationの略称で、「検索エンジン最適化」と訳すことができます。検索エンジンがWEBサイトを回遊し、コンテンツが評価されると検索上位に表示されるようになります。
その検索上位に表示させるための対策を「SEO対策」と呼びます。
検索エンジンとは、GoogleやYahoo!のようにインターネット上の情報をキーワード検索できる機能やプログラムのことを指します。
なお、日本ではGoogleとYahoo!の検索エンジンが9割近いシェアを誇っています。割合としては、Googleが約75%、Yahoo!が約14%です。いかにGoogleのSEO対策が重要かわかると思います。
◉-1、検索エンジンはどのように順位を決めているのか
SEO対策をするうえで、検索エンジンの順位づけの仕組みは知っておいた方がよいでしょう。次の3つのステップで順位を決定しています。
①「クロール」:世界中を回遊し情報を探し回る
②「インデックス」:探し出した情報をデータベース上に登録する
③「ランキング」:登録した情報を順位づけする
ただコンテンツを無闇に増やしても、クロールして見つけてもらえなければSEOで上位表示されることは難しいです。さらに、インデックスされないことには上位表示は望めないでしょう。
後に解説する内部対策もきちんと遂行しなければ、ただコンテンツを増やしても徒労に終わるだけなのです。
◉なぜSEO対策が必要なのか

そもそも企業はなぜSEO対策をする必要があるのでしょうか。
ポイントとしては大きく2つあります。
1つ目は、WEB広告にかける予算です。
広告予算は中小企業にとって、無限にかけ続けることは難しいでしょう。しかし、広告は実施しなければ自社を見つけてもらえないため、広告費を投じ続けなければ集客効果を発揮しません。
つまり、WEB広告をやめた途端に、自社サイトを見てもらう機会がなくなり、商品の購買やサービスの認知に結びつかなくなるのです。
2つ目は、会社のブランディングです。キーワード検索にて上位表示される広告枠以外のサイトは大半がSEO対策を実施しています。
このような自然検索もしくはオーガニック検索で上位表示されると、特定キーワードで目的の情報を探しているユーザーに見つかりやすいため、その領域における第一人者として認知してもらいやすくなります。
参考コラム:SEOとPPCの大きな違い ユーザーの本気度が違いユーザーの質が変わってくる
◉具体的なSEO対策の方法

SEOで必要な対策は大きく3つあります。
それは「コンテンツSEO」「内部対策」「外部対策」です。
それらのどれが欠けてもWEBサイトの価値を上げて上位表示されるのは、至難の業と言えるでしょう。
それぞれの具体的な内容は次の通りです。
◉-1、コンテンツSEO:ターゲットユーザーの求める良質なコンテンツを提供する
コンテンツSEOは、SEO対策をするうえで最も重要な方法の一つです。高品質なコンテンツを作成しないことには、Googleのクローラーからの評価にも結びつかないからです。
良質なコンテンツを作成するために必要なリソースは、ライターと編集者です。
コンテンツSEOを成功させるためには、「最適なキーワード選定」「ユーザーの検索ニーズの分析」「競合サイトの比較調査」「タイトル・中見出し・小見出しの構成案作成」「E-A-Tを意識したライティング」の5つが必要です。
これらを実行できるライターと、チェックできる編集者が必須といえます。
検索上位に表示させるためには分析や改善も必要なため、記事が上位に入らない場合はリライトを繰り返すなどの対策もしなければなりません。
◉-2、内部対策:WEBサイトの土台をしっかりと作り込もう
SEOにおける内部対策とは、サイト全体に配置されるテキストや画像、リンクやHTMLタグ設定といったテクニカルなものまで改善する対策をいいます。
ホームページの土台をしっかりとさせ、インフラを整備して、ユーザーが読みたいサイトへとリフォームさせる必要があるのです。
前述したように、検索エンジンではクローラーが巡回し情報を探し回っています。
内部対策では、検索エンジンが巡回しやすいように、サイトマップを作成したり内部リンクを設置したりして正しく情報を伝えることが必要です。
そして、ユーザビリティが担保された、ユーザーが理解しやすいサイト作りをしなければなりません。
内部対策として土台づくりをしっかりとするためには、WordPressといったコンテンツSEO向きのCMSを使用することをおすすめします。
もちろんWordPressを使ったからといって無条件で検索上位になれるわけではありませんが、現在の世界中で使われているCMSのうち60%以上がWordPressといわれています。SEO対策に対応するプラグインやテーマが使われているため、きちんとしたSEO対策をしていれば結果が出やすいCMSです。
検索アルゴリズムは常に変動しており、内部対策をきちんと実行することでアップデートの影響を受けづらいメリットも考えられます。
◉-3、外部対策:数を増やす被リンク対策は禁物! 自然に評価されるサイト作りを
SEO対策と聞いて、被リンクを獲得する施策が思い浮かぶ人は多いでしょう。
気をつけてほしいのは、ただ被リンクを増やしさえすればSEO対策になるわけではないと言うこと。
外部対策が検索で評価される要因は、第三者による正当な評価だからです。自社と関連性の薄いサイトやブログなどにURLを貼ってもらったり、被リンクを購入したり、過剰な相互リンクを貼り付けたりしても、逆にペナルティを受けて検索順位が下がる危険性があります。
原則として、被リンクは自然獲得であるべきです。くわえて、被リンクはリンク数よりもドメイン数で評価されるため、色々なサイトに自然に認知を高めてリンクを貼り付けてもらうことが重要といえるでしょう。
良質なコンテンツを増やすことにも通じますが、コンテンツ自体を価値ある情報として認識してもらい、SNSで拡散してもらうことは外部対策として最も効果的です。
FacebookやTwitterなど、コンテンツを閲覧してもらった後に、「シェア」や「いいね」をしてもらいやすい仕掛けを施しておくことも重要でしょう。
◉SEO対策にはE-A-Tが重要(2022年12月からはE-E-A-T)

SEO対策の方法の一つで、「E-A-Tを意識したライティング」が重要だと紹介しました。
このE-A-Tとは、Googleが作った造語ですが、次のような意味で使われています。
・E=Expertise(専門性)
・A=Authoritativeness(権威性)
・T=Trustworthiness(信頼性)
Googleの『検索品質評価ガイドライン』で「ページ品質評価の最重要項目」とも記載されており、SEO対策には欠かせない項目となっています。
さらに、2022年12月15日のGoogleの公式発表を機に、「E-A-T」にもう一つ「E=Experience(経験)」が追加され、「E-E-A-T」が重要視されるようになりました。
出典:Google検索セントラルブログ/品質評価ガイドラインの最新情報:E-A-TにExperienceのEを追加
◉-1、専門性を高めるには
良質なコンテンツを求めている人は、情報発信者の専門性も確認しています。
そのため、専門性を高めるには「ジャンルに特化する」ことがとても重要です。
たとえば、自分が頭痛に悩まされているときに、「頭痛の専門医」が書いた情報サイトを発見し、それが納得のいく価値ある情報であれば「この先生に診てほしい」となるはずです。
そのようにジャンルに特化することで、情報を選んでもらいやすくする必要があります。
もちろん専門性を高めるためには、発信者側も専門知識の量や質は高めていかねばなりません。
ほか、専門家への取材を行なったり、体験談を入れたりすることで、情報としての信頼性も上がってきます。
◉-2、権威性を高めるには
権威性を高めるために、すぐできる対策としては著者名や運営会社名を明示することです。
ほか、良質な情報を発信し続けることで根気が必要ですが、ドメインパワーの強いサイトから紹介してもらい被リンクをもらうことも効果的。SNSなどで著者名や企業名などを発信してもらい、参考になる情報だと言及してもらうサイテーションを獲得すれば、権威性は高まるでしょう。
◉-3、信頼性を高めるには
前述の著者名や運営会社名を明示することと重なりますが、著者のプロフィールや経歴が掲載されていると一層信頼性は増します。
ただ投げっぱなしの情報ではなく、どのような人が書いているのかを明らかにすることで、誰が書いているのかわからない怪しい情報とは差別化ができます。
くわえて、専門性の高い他サイトから情報の一部を引用することも効果的。ただ、引用元を示さずにコピペするのは厳禁です。
他には、飲食店など店舗運営企業であれば多くが実施している、Googleマイビジネスへの登録も信頼性を高めるのによい方法といえるでしょう。
ユーザーをサイトに誘導することもできる対策です。
◉-4、経験を高めるには
経験を高めるには、「具体的な導入事例や実績」を表示するのがおすすめです。実際に、ユーザーがどのようなサービスを提供されて、どのような成果が出たかがすぐにわかるため、「経験豊富な会社だ」と認識してもらうには手っ取り早い方法となります。
くわえて、ユーザーレビュー(お客様のレビュー)や製品・サービスの使用体験なども効果的です。具体的にどのような顧客に選ばれ評価されているのかがアピールできる上、ユーザーに自分が体験した時のイメージを作り出すことができます。自社サイトやGoogleの口コミなどで、ユーザーレビューを集めていくのは有益な手段となり得ます。
ほか、①〜③すべてを高めるのに、書籍出版もおすすめの方法の一つです。
▶書籍出版については、関連記事【企業出版のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせてご参考にしてください。
◉【まとめ】付け焼き刃のSEO対策では意味がない! 長期的な視野で取り組もう
SEO対策の基本的な知識から具体的な対策方法、そして重要視されている「E-A-T」について解説しました。
いずれにしても一朝一夕で結果が出る簡単な施策ではありません。SEO対策で上位表示されるためには、良質なコンテンツを更新し続ける根気が必要です。
テクニックを身につけるのも大変ですので、できる部分は自社で行ない、困難な部分はSEOツールを利用できる外部のSEOコンサルティングなどに依頼するのも、選択肢となるでしょう。
また、SEO対策については次のコラムでもわかりやすく解説されているので参考にしてみてください。
参考コラム:SEO対策でやることとは?初心者向けに分かりやすく解説
参考:フォーウェイのブランディングサービスについてはこちらから

類似した商品やサービスが市場に溢れている昨今は、品質やデザインが優れているだけでは選ばれにくい時代です。
そのような状況では、企業の理念や価値観、社会的な姿勢といった企業そのものの魅力が、選ばれる決め手になりつつあります。
そこで注目されているのが「企業ブランディング」です。
本記事では、企業ブランディングの効果、実施手順、具体的な手法について解説いたします。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉企業ブランディングとは

企業ブランディングとは、企業の理念や価値観、ビジョンなどを明確にして社内外に発信し、企業のブランド価値を高める取り組みです。
商品やサービスの品質がどれほど優れていても、それを提供する企業に信頼がなければ、顧客から選んでもらうことはできません。
逆に、企業に一貫した姿勢や社会的な信頼があれば、商品やサービスそのものの評価も高まり、選ばれる理由になります。
たとえば、Apple社は世界中にアップル信者と呼ばれる熱烈なファンを獲得しています。
新型iPhoneの発売日には朝から長蛇の列ができるほどです。
同じ価格でiPhone以上の機能や性能が備わっているスマホは、世の中にたくさんありますが、企業ブランディングに成功したiPhoneは、機能や価格の競争対象とならずに顧客から選ばれ続けているのです。
◉-1、事業ブランディングとの違い
企業ブランディングと事業ブランディングは、ブランディングの対象が大きく異なります。
企業ブランディングが企業全体の信頼や価値を高める取り組みであるのに対し、事業ブランディングは事業の魅力や認知度を高める取り組みです。
企業ブランディングは企業全体の理念やビジョン、企業文化、社会的役割などを訴求する一方で、企業の中の各事業の強みや特徴を訴求します。
たとえば、楽器メーカーとして有名なヤマハを例にすると、ヤマハという企業全体を訴求するのが企業ブランディング、ヤマハが行っている「楽器事業」「音響機器事業」など個々の事業を訴求するのが事業ブランディングです。
企業ブランディングが成功すれば、企業の価値だけではなく、行っている事業の価値も向上させることができます。
◉企業ブランディングがもたらす8つの効果

企業ブランディングは、単なるイメージ戦略ではないため、企業の内外に多くのメリットをもたらします。
代表的な8つの効果は以下の通りです。
効果1:競合他社との差別化
効果2:顧客ロイヤリティの向上
効果3:信頼性の獲得
効果4:広告宣伝費の削減
効果5:価格競争からの脱却
効果6:優秀な人材の採用・定着
効果7:新規顧客の獲得
効果8:従業員のモチベーション向上 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、効果1:競合他社との差別化
企業ブランディングに成功してブランド価値が高まると、自社の製品やサービスにブランドという付加価値が付くことになります。
結果として競合他社との差別化を図ることができるのです。
たとえば、ダイソンには、「製品開発にただならぬこだわりを持ち、徹底的に作り込まれた高機能・高品質な製品を出す会社」というイメージを持つ人が多いと思います。
このイメージが自社の製品やサービスへの付加価値となり、たとえ他の製品より価格が高くても、他にコスパの良いものがあったとしても、「ダイソンの掃除機が欲しい」と選ばれる存在となります。
企業ブランディングに成功し、競合他社との差別化ができると、価格競争からの脱却や、新規参入企業の抑制、自社の特徴や強みの明確化などのメリットが得られますが、最大のメリットは「価格競争からの脱却」と言っても良いでしょう。
製品やサービスの基本機能は同じであっても、ブランドという付加価値が付くことによって差別化できるため、安定した企業経営を実現することができます。
◉-2、効果2:顧客ロイヤリティの向上
企業の理念やビジョンに共感が集まると、ブランドへの信頼が高まり顧客のロイヤリティも向上します。
顧客ロイヤリティとは、顧客が企業やブランドに対して抱く信頼や愛着を指すものです。
強い顧客ロイヤリティは、リピート購入の増加や口コミによる新規顧客の獲得など、企業にとって多くのメリットをもたらします。
たとえば、スターバックスは、「人々の心を豊かで活力のあるものにするために」というミッションのもと、顧客体験を重視した店舗運営を行っています。
店舗の雰囲気やスタッフの接客などが顧客の満足度を高め、強いロイヤリティを生み出している事例です。
このように、「この企業だから選ぶ」という心理が働けば、価格によらず選ばれ続けて安定した売上にもつながります。
◉-3、効果3:信頼性の獲得
効果的な企業ブランディングを行うことができれば、企業や自社の製品・サービスの信頼性を高めることができます。
たとえば、ダイソンは、創業者ジェームス・ダイソンが納得のいく掃除機を作るために、試作品を5,127台も作り開発を進めてきたプロセスを丁寧にユーザーに伝えています。
結果として、「高機能・高品質」だけではなく、「ジェームス・ダイソンが魂を込めて、試行錯誤をして作られた掃除機だから大丈夫だ」という信頼感の醸成に成功しました。
このように、企業ブランディングに成功すると、「この企業なら間違いない」「この企業なら期待に答えてくれる」という信頼感をユーザーに与えることができるようになります。
高い信頼性を有するブランドを作りあげることは容易なことではありませんが、信頼性の高いイメージを獲得しそれを維持することができれば、それは企業にとって大きな武器となるでしょう。
◉-4、効果4:広告宣伝費の削減
企業ブランディングに成功し、企業の知名度や認知度が向上すると、必要以上の広告宣伝をしなくても自社の製品やサービスが売れるようになります。
理由は2つあります。
1つはファンによるリピート購入が増えるため、2つ目は顧客のニーズが発生した時に選択肢に上がりやすくなるためです。
たとえば、「少し高級感のあるタオルをギフトとして送りたい」と思った時に、おそらくほとんどの人の頭の中に「今治タオル」が選択肢として思い浮かぶはずです。
このように「高級タオルと言えば今治タオル」というブランドが認知されれば、ニーズが発生した段階ですぐに選択肢にあがってくるようになります。
そのため、必要以上の広告宣伝をしなくても、自社の製品やサービスが安定的に売れるようになるのです。
テレビCMやWeb広告などは流している期間中は売上に貢献しますが、CMや広告をやめるとその効果がなくなるケースが多いものです。
しかし、企業ブランディングによって向上した企業の知名度や認知度は、継続的な経済効果を企業にもたらします。
このように、広告宣伝費が削減できることも企業ブランディングの大きなメリットの1つと言えるでしょう。
◉-5、効果5:価格競争からの脱却
企業ブランディングに成功すると自社の製品やサービスが高価格であったとしても購入してもらえるようになるため、価格競争から脱却できます。
たとえば、同じ素材・デザインの無地のパーカーでも、高級ブランドのタグやロゴがついているだけで、高額だったとしても「この高級ブランドの出しているパーカーならこれぐらいして当然だよな」と、市場が納得してくれるようになるのです。
また、自社の製品やサービスに固定客がつくようになり、リピート率の向上や、営業・販売コストの削減にもつながります。
◉-6、効果6:優秀な人材の採用・定着
企業が成長するためには優秀な人材を確保することが重要です。
企業ブランディングによって企業の魅力が広く周知されると、多くの人材が自社のことを知り好印象を抱いて応募してくることが期待できます。
たとえば、最強の町工場とも言われる浜野製作所は、どん底から這い上がった社長の創業ストーリーや、「脱下請け」の革新的なものづくりをいち早く打ち出し、「革新的な町工場」という企業ブランディングを確立しました。
企業ブランディングの一環として活用したのが「書籍の出版(ブックマーケティング)」です。
書籍の中で経営者のビジョンや考え方を共有したことで、深い共感を得ることができ、普通なら大企業やグローバル企業に行ってしまうような優秀な人材の確保ができるようになったそうです。
このように、求職メディアを利用しなくても、優秀な人材を獲得することができ、採用コストを大幅に削減できるのもメリットの1つと言えるでしょう。

◉-7、効果7:新規顧客の獲得
企業ブランドが認知されると、今まで接点のなかった層にも届き、新規顧客の獲得につながります。
特に、企業の価値観や社会的貢献に共感する消費者からの支持を得やすくなります。
たとえば、ヤンマーは、農業機械メーカーとしての伝統的なイメージを刷新するため、ブランドアイデンティティを「FLYING-Y」に統一し、デザイン面でも著名なデザイナーを起用しました。
これにより、若年層や新規顧客層からの注目を集め、ブランド価値の向上と新規顧客の獲得に成功しています。
◉-8、効果8:従業員のモチベーション向上
経営トップがビジョンや価値観を明確に発信すると、従業員のモチベーションやエンゲージメントが高まります。
たとえば、東京ディズニーリゾート(株式会社オリエンタルランド)では、従業員を「キャスト」と呼び、キャストをブランドの体現者としています。
最も重視すべきゴールや、5つの行動基準を共有し、キャスト自身が自分で考えて行動できるような教育方針を導入しているのが特徴です。
これにより、キャスト一人ひとりがブランドの価値や理念を理解している状態を作ることに成功しました。
理念が浸透すれば、自分の仕事が社会に貢献していることが実感でき、従業員の自発性や創造性が育まれ、モチベーションが向上します。

◉企業ブランディングの実施手順

企業ブランディングは、「どのような企業として世の中に認識されたいか」という根幹を定義する取り組みなので、最初の計画と準備が重要です。
企業ブランディングは、次のような5つのステップで進めます。
STEP1:現状分析を行う
STEP2:ターゲット顧客を明確にする
STEP3:ブランドの核(価値観・メッセージ)を策定する
STEP4:ブランド戦略を策定する
STEP5:実行・改善・測定を繰り返す |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、STEP1:現状分析を行う
まず最初に、自社や自社を取り巻く環境についての現状分析を行います。
ここでは、自社がどのように認知されているのか、競合環境はどうなっているのか、顧客が自社に抱いている印象やイメージは何かなどを調査することが大切です。
企業ブランディングの現状分析に用いられる代表的なフレームワークは、次の2つです。
| PEST分析 | 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4視点から、自社を取り巻くマクロ環境を分析する手法 |
| 3C分析 | 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3要素に着目して、自社の立ち位置を明確にする手法 |
PEST分析は、外部環境の大きな変化やトレンドを把握するのに適しており、3C分析は、具体的に市場でどのような競争が起こっているのかという点や、自社の立ち位置を明確にするのに適しています。
◉-2、STEP2:ターゲット顧客を明確にする
ブランディングでは、誰に伝えるかを明確にすることが重要です。
そのために、セグメント(顧客グループの分類)とペルソナ(具体的な理想顧客像)を設定します。
年齢や価値観などを細かく定めたペルソナを活用すると、より的確なメッセージ発信が可能です。
ターゲットを明確にすることで、ブランドのメッセージをピンポイントで届けることができます。
どの顧客層に対してどのような価値を提供するのかがはっきりするため、企業のブランドポジショニングも確立されていくのです。
また、マーケティング活動やプロモーション戦略をターゲットに合わせてカスタマイズすることも可能です。
◉-3、STEP3:ブランドの核(価値観・メッセージ)を策定する
ブランドの核となるのが、企業としてどんな価値を提供し、どんな存在でありたいのかという価値観やメッセージです。
ブランドの核には企業のミッション、ビジョン、バリューが含まれます。
ブランドの核は単なるスローガンではなく、企業としての哲学や世界観を明文化するもので、ここで決めたものがブランディングの軸となります。
ブランドの核がしっかりと定まることで、その後のマーケティング活動やコミュニケーションが一貫性を持ち、信頼感を高めることができるのです。
◉-4、STEP4:ブランド戦略を策定する
ブランドの核が明確になったら、次にそれを具体的にどのように伝えていくかを設計します。
具体的には、次のような要素があります。
・ロゴやカラー、フォントなどのビジュアル要素
・WebサイトやSNSでのメッセージの発信
・ブランディング広告やキャンペーン施策
ここで重要なことは、ブランドの方向性にブレがないように一貫したメッセージを発信していくことです。
ブランドがどのような立ち位置を取るのか、どのような市場に向けて発信するのかが定まるため、無駄の少ない効率的なマーケティング活動を行うことができます。
◉-5、STEP5:実行・改善・測定を繰り返す
ブランディングは一度やって終わりではありません。
実際に施策を実行したうえで、その効果を測定し必要に応じて改善し、PDCAサイクルを回します。
たとえば、次のような指標でブランド効果を評価していきます。
・SNSの投稿数やコメント数
・サイト滞在時間やコンバージョン率
経営環境や顧客ニーズの変化に合わせて継続的にアップデートすることが重要です。
◉企業ブランディングの手法

企業ブランディングを効果的に行うためには、一貫性が重要です。
それぞれの特徴を理解し、目的に応じて組み合わせることで、より強力なブランディングが可能になります。
企業ブランディングを効果的に行うための代表的な9つの手法は以下の通りです。
・ロゴとビジュアルアイデンティティの設計
・ブランディング広告の活用
・コンテンツマーケティングの実施
・SNSの活用
・インフルエンサーとのコラボレーション
・イメージキャラクターの作成
・イベント・セミナーの実施
・書籍の出版
・CSRの推進 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、ロゴとビジュアルアイデンティティの設計
ロゴや色、フォントといったビジュアル要素は、ブランドの世界観を視覚的に伝える重要なツールです。
たとえば、Appleのロゴやコカ・コーラの赤と曲線的なデザインなどは、強いブランドイメージを定着させています。
こうしたデザインには、まず企業の想いやストーリーを言葉として整理し、その内容をもとに一貫性あるビジュアルへ落とし込むプロセスが効果的です。
ロゴとビジュアルアイデンティティを作り上げるのと同時に使用方法についても厳しいガイドラインを設けることをおすすめします。
◉-2、ブランディング広告の活用
ブランディング広告は、企業の価値観や世界観を伝えるための広告手法です。
特に、企業ブランディングにおいては、マス広告、ディスプレイ広告、デジタル音声広告の3つが主に活用されます。
目的やターゲットに応じて使い分け、組み合わせることで、効果的にブランドイメージを浸透させることが可能です。
◉-2-1、マス広告
マス広告は、テレビCMや新聞・雑誌広告など、幅広い層にリーチできる伝統的な手法です。
信頼性やインパクトのある訴求に強く、企業の節目や社会的なメッセージ発信に適しています。
特に、ゴールデンタイムのテレビCMは、数百万人単位の視聴者にブランドをアピールできるため、一気に認知度を高め、ブランドを「知っている企業」に変えることが可能です。
マス広告の種類や特徴は次表の通りです。
| マス広告の種類 | 特徴 |
| テレビ | 全国規模での認知拡大に効果的 |
| ラジオ | 地域密着型の配信や「ながら聴き」に向く |
| 新聞 | 信頼性が高く、中高年層やビジネス層の読者が多い |
| 雑誌 | 専門性が高く読者ターゲットが明確で保存性も高い |
特に、新聞広告やNHKなどでの公共性の高いメディアでの広告出稿は、「この企業は信頼できる」と感じさせることができます。
特に保険・金融・医療など、信頼が重要な業種は信頼性を活用して広告を出稿すると良いでしょう。
◉-2-2、ディスプレイ広告
ディスプレイ広告は、画像や動画、フォント、色彩などを用いて、企業が伝えたいブランドイメージや世界観をそのまま表現できるのが強みです。
ターゲティング精度が高く、ペルソナに合わせた広告配信ができます。
また、リスティング広告とは異なり、検索行動をしていないユーザー(潜在顧客)にもリーチできるのが特徴です。
「知ってもらう」「印象づける」などの目的に適しており、ブランドの認知拡大に貢献します。
ディスプレイ広告の種類や特徴は次表の通りです。
| ディスプレイ広告の種類 | 特徴 |
| GDN(Google ディスプレイネットワーク) | Googleの提携先メディアに広告を配信できるネットワーク |
| YDA(Yahoo!ディスプレイ広告) | Yahoo! JAPANや提携メディアに配信される広告 |
| YouTube広告 | 動画による訴求力が高く、短時間で印象づけやすい |
広告のデザインがごちゃごちゃしていたり、メッセージが曖昧だったりすると、ユーザーには何の広告か分からずスルーされてしまいます。
ディスプレイ広告のビジュアルを作成する際は「誰に見せたいのか」「どんな印象を持ってもらいたいのか」を意識することが大切です。
◉-2-3、デジタル音声広告
音楽・音声メディアで配信される広告で、通勤中や作業中の「ながら聴き」で自然に情報が届き、声による共感や親近感を与えられます。
音声は、声のトーンやスピード、間などを通して、感情を伝えられるメディアです。
ナレーターやパーソナリティの声に親近感を持ちやすく、その親近感がそのまま企業の好感度に繋がります。
音声広告は、通勤中や家事の最中、運動中など、ながら時間に自然に耳に入ってくるため、視覚的広告よりもリスナーの注意を独占しやすいのが特徴です。
特に、Spotifyの音声広告は再生開始後はスキップできない仕様になっているため、広告が終了するまで視聴される割合は93%にのぼります。(※1)
デジタル音声広告の種類や特徴は次表の通りです。
| デジタル音声広告の種類 | 特徴 |
| Spotify | ・音楽ストリーミングサービス・無料ユーザー向けに楽曲の合間に音声広告が挿入される |
| YouTube | ・YouTube内で、音声中心の広告フォーマットを用いて配信・特にバックグラウンド再生時に効果的 |
| radiko | ・地上波ラジオをインターネット経由で聴けるサービス・地域密着型の広告展開が可能 |
| Voicy | ・パーソナリティによる音声コンテンツ配信プラットフォーム・情報感度の高いビジネス層へのアプローチに適している |
活用の具体例として、トヨタがSpotifyで出稿した音声広告が挙げられます。
若年層に向けたプロモーションの一環としてSpotifyを活用し、「ドライブに合うプレイリスト」とともに連動した音声広告を配信。
ブランドを「楽しいドライブ」と結び付けることで、ユーザーの印象に残りました。
視覚的なインパクトには欠けるため、短い言葉でどれだけ強く訴求するかが重要です。
参考※1:Spotify『デジタル音声広告って何?Spotifyの音声広告「きほんのき」』
◉-3、コンテンツマーケティングの実施
自社のWebサイトなどを利用して、顧客との信頼関係を構築する手法もあります。
これはコンテンツマーケティングと呼ばれ、顧客にとって役立つ知識やストーリーを発信し続けることによって、企業の信頼性を向上させるものです。
広告のように「売り込む」のではなく、価値ある情報を提供することで自然にブランドのファンを育てることができます。
多くの顧客は検索エンジンを利用して自分の興味や関心のある情報を検索するので、検索結果の上位に表示されるようなSEOライティングや、思わず読みたくなる、興味を湧かせるような企画力が重要となります。
主なコンテンツの種類と特徴は次表の通りです。
| コンテンツの種類 | 特徴 |
| オウンドメディア | ・企業が自社で運営する情報サイト・理念や専門性を継続的に発信できる |
| ブログ | ・社員の声や現場の情報を発信しやすい・柔軟な内容に対応可能 |
| 動画 | ・視覚と音でメッセージを伝えられる・SNSとも連携しやすい |
| ポッドキャスト | ・音声で継続的に情報を届けられる・通勤時間を狙った配信などに適している |
| ホワイトペーパー | ・専門性の高い資料でリード獲得や信頼構築に効果がある |
| メールマガジン | ・見込み顧客に直接情報を届け、関係性を維持できる |
| プレスリリース | ・企業のニュースや新商品を対外的に発信する |
| ランディングページ(LP) | ・特定の商品やサービスに特化したページ・成約率向上に効果がある |
たとえば、グループウェア開発のサイボウズは、自社の働き方改革やカルチャーを綴るコンテンツで、共感と話題性を両立し、ブランド好感度を向上させました。
このように、コンテンツマーケティングは、特に専門知識・ノウハウを持っている企業や、BtoB企業、化粧品などのリピート購入が重要な商品・サービスを展開する企業に向いています。
コンテンツは長期的に投稿していくことが前提となるため、短期的な数字ではなく企業の価値を伝え続ける姿勢が重要です。
▶︎コンテンツマーケティングについては、関連記事【コンテンツマーケティングとは? 広告費を削減して売上を増やす方法】をあわせて参考にしてください。
◉-4、SNSの活用
近年ではX(旧Twitter)やInstagram、TikTokなど、SNSを有効に活用して企業ブランディングを行う企業も増えています。
SNSは、ターゲット層や伝えたい内容の違いによってアカウントを使い分けられる上、Webサイトや文章、広告、CMなどでは伝わりきれない、社内の空気感や働いている社員の人間性、商品開発の細かいプロセスなどを、素早くユーザーに伝えることができます。
SNSの運用を成功させるポイントは、広告・宣伝ばかりを投稿するのではなく、ユーザーのニーズに寄り添った発信を心がけていくことです。
成果・結果を焦る余り、商品の広告や宣伝ばかり投稿していてはファンはつきません。
著名人とのコラボ企画を実施したり、フォロー&リポストキャンペーンを実施したり、代表者が想いを語ったり、開発者のこだわりをキャッチーに話したり、ユーザーといかに密なコミュニケーションを取れるかを考えていくことが何より重要です。
代表的なSNSの種類と特徴は次表の通りです。
| SNSの種類 | 特徴 |
| Facebook | 実名登録が基本で信頼性が高く、中高年層・ビジネス層に強い |
| Instagram | 写真・動画中心で、20~30代に人気 |
| X(旧Twitter) | 拡散力とリアルタイム性に優れ、幅広い世代が利用 |
| TikTok | 10~20代を中心に人気、トレンド性と拡散力が高い |
| YouTube | 中長尺動画の配信が可能で、専門性の高い発信に適している |
| LINE | 日本国内での利用率が高く、日常的な接点づくりに強み |
▶︎SNSマーケティングについては、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】をあわせて参考にしてください。
◉-5、インフルエンサーとのコラボレーション
インフルエンサーとの連携は、SNSを通じて多くの潜在顧客にリーチできる手法です。
特に若年層への訴求や、共感を得やすい第三者の推薦を得られる方法として有効です。
たとえば、海釣りに関する情報を発信しているインフルエンサーは、海釣りに興味があるフォロワーを多く抱えています。
そのため、海釣りに関する商品・サービスを展開している企業は、そのインフルエンサーとコラボレーションすれば、ターゲットにピンポイントで訴求することができるのです。
インフルエンサーに発信してもらうことができれば口コミのような効果が生まれ、ブランディングの効果を高めることができます。
インフルエンサーへの信頼も相まって企業自体の信頼も高めることが可能です。
ただし、インフルエンサーの価値観が自社ブランドと合っているかを慎重に見極めることが大切です。
◉-6、イメージキャラクターの作成
企業ブランディングにおいて、イメージキャラクターの作成も効果的な手法の1つです。
イメージキャラクターには、視覚的にストーリーやコンセプト・価値観などを伝える効果があるため、顧客の記憶に残りやすくブランドの認知度を高める効果が期待できます。
たとえば、不二家のペコちゃんや、ヤンマーのヤン坊・マー坊、NHKのチコちゃん、ソフトバンクのお父さん犬などが企業キャラクターとして有名です。
また、企業ではありませんが、ご当地キャラクターとして熊本のくまモンなども、キャラクターがきっかけで熊本に大きな経済効果をもたらしています。
このように接しやすいキャラクターがあることで、顧客との関係性が強くなり、購買意欲の向上による売上促進や競合他社との差別化にもつながります。
◉-7、イベント・セミナーの実施
企業が定期的に実施するイベントやセミナーも企業ブランディングに効果があります。
自社製品のプロモーションや自社の専門分野に関するセミナーや勉強会などを行うことによって知名度や顧客満足度の向上が期待できるのです。
また、企業の代表者や著名人を講師に招くことによって信頼感や安心感の向上が期待できます。
◉-8、書籍の出版
企業ブランディングの手法として企業出版という選択肢もあります。
企業出版と聞くと、企業が自費で名刺代わりに出版するようなイメージがあると思いますが、それとは目的が異なり、今注目されているブランディング手法の1つです。
企業出版は企業が自社の情報や専門知識を書籍の形式で出版し、著者のビジネスのブランディングや販促活動の一環として活用する手法です。
企業出版の代表的なメリットとして挙げられるのが、「業界内での知名度や信頼性の向上」「持続的な集客効果」「人材採用や人材教育への効果」です。
まず、出版物に自社の専門知識や実績をまとめることができるため、業界内での知名度や信頼性を高めることが可能です。
次に、出版物の流通期間は非常に長いため、広告やSNSなどと違って持続的な集客効果が期待できます。
また、出版物に企業理念やストーリー、自社商品の開発秘話などを盛り込むことができるため、人材採用や人材教育に効果を発揮することができます。
「文章を読まない」と言われる時代ですが、書籍を買う人は何らかの課題を持った上で文章を読みます。
そのため、一言では語れない創業ストーリーや、ビジネスモデル、こだわり、革新性、専門性を持っているような企業こそ、企業出版は「読まれる」という点で、おすすめの手法です。
企業出版を活用したマーケティング手法の一つに、ブックマーケティングがあります。
ブックマーケティングとは、企業出版などで出版した書籍やSNS、コンテンツマーケティングなど様々な手法を活用してブランディングやマーケティングを行い、信頼の獲得や認知の獲得といった企業の目的を達成するための手法です。
企業ブランディングを行うのであれば、企業出版という出版形態を活用しつつ、ブックマーケティングという視点からブランディングを行うのがおすすめです。
▶︎ブックマーケティング(企業出版)については、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】をあわせて参考にしてください。

◉-9、CSRの推進
CSR(企業の社会的責任)は企業の評価を高めるために重要なブランディング手法です。
CSRの推進が企業ブランディングに与える効果は、「社会と信頼関係の構築」「優秀な人材の獲得」など様々なものがありますが、最も効果が現れやすいのは「ブランドイメージの向上」でしょう。
たとえば、環境保全活動に取り組む企業は「エコに対する意識が高く、持続可能な社会に配慮する会社」として認知されやすくなります。
このように、CSRは企業のポジティブなイメージづくりに直結し、信頼性の高いブランドを形成する一助となるのです。
環境保護、地域社会への貢献、多様性の推進など、自社が社会に対してどのように責任を果たしているかを明確に発信することで、ポジティブなイメージを持ってもらうことができます。
◉企業ブランディングを成功に導く2つのポイント
企業ブランディングは一朝一夕で成果が出るものではありません。
特に重要な2つのポイントは以下の通りです。
・長期的な視点で取り組む
・適して指標を用いて効果検証する |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、長期的な視点で取り組む
企業ブランディングは短期間で効果が出るものではありません。
数年または10年ほどかかってやっとブランドイメージが定着することもありえます。
また、たとえ企業ブランディングが成功してブランド価値が向上したとしても、その後何もしなければ、時間と共にブランド価値は薄れていきます。
企業ブランディングは1度作り上げれば終わりではなく、それを維持して継続させることも重要なのです。
そのため、企業ブランディングには多くの時間とコストがかかりつづけることを認識しておきましょう。
◉-2、適した指標を用いて効果検証する
企業ブランディングを行っていく上では、定期的な指標のチェックが欠かせません。
しかし、企業ブランディングは、実際には目に見えない価値を伝えていくことになるため、効果検証がやりづらいという問題点があります。
たとえば、Web広告などであれば、クリック率や成約率など、数字で効果の検証をすることができますが、ブランディングの場合はどこでどのような数字に寄与しているのかを正確に測ることは難しいと言えます。
しかし、企業ブランディングは、企業として多大な時間とコストをかけて行うものだからこそ、方向性が間違っていないかどうか、などの判断は必要不可欠です。
そこで、企業ブランディングの評価によく用いられるのが「ブランドロイヤリティ」「ブランド認知度」「利益・売上貢献」と言った指標です。
効果検証がしづらい企業ブランディングですが、このように適した指標を使って、効果測定・評価をしていくことも重要です。
◉ブックマーケティング(企業出版)における企業ブランディングの成功事例

実際に、ブックマーケティング(企業出版)によって企業ブランディングに成功した事例を2件ご紹介します。
◉-1、出版による信頼性獲得で圧倒的な受注率を達成した不動産会社の事例
この不動産会社の経営者は、競合が多く、怪しい業者も多い中で、紹介から受注まで、顧客との関係性を構築していくまでに時間を必要としていました。
そのため、Web広告などでも正しくメリットを伝えきれず、悩んでいたそうです。
また、主要ターゲットが医師ということもあり、信頼性を獲得することに苦戦していました。
そこで、医師の悩みの1つである高額な税金について、最も効果的な節税対策として、不動産投資があることを紹介した書籍を出版。
書籍でしっかりと医師が不動産投資を行うメリットを詳しく説明したところ、多忙で節税対策などまで手が回らない多くの医師から信頼を得ることができ、発売2ヶ月で6億円の売上が生まれました。
結果として、医師向けの不動産投資の専門家としてのブランディングを確立。
その後も出版物を営業ツールとして配布したり、顧客間での紹介ツールに活用してもらったりすることによって、顧客との関係性構築までの時間の短縮につながり、成約率が飛躍的に上昇しています。
◉-2、セミナーや講演会依頼多数!新規事業の集客を実現した保険代理店の事例
この保険代理店の経営者は、保険業界に関する持論を提唱した書籍を出版。
保険業界の給与体系は成果に応じて給与が決まる「成果報酬型」が当たり前ですが、この保険代理店の経営者はこれに疑問を持ち「一律報酬型」に変えることを提唱していました。
つまり、少数のスーパー営業マンに頼る経営から、アベレージヒッターを育てていく再現性のある経営で業績拡大ができることを書籍で紹介したのです。
ひと言では伝え切ることができない持論について語った書籍を多くの業界関係者が読み、共感が生まれ、業界内でのブランディングを確立することができました。
結果として、多くのセミナーや講演会に招かれたり、新規のコンサル契約を獲得したり、紹介者が増えて本業の保険契約数が伸びるという効果が得られています。
◉【まとめ】企業によって最適なブランディング手法は異なる!まずは自社に合った手法を見つけよう
企業ブランディングは、企業が長期的に社会や顧客から信頼され、選ばれ続けるための戦略的な取り組みです。
重要なことは、自社の理念や価値観をしっかりと軸に据えたうえで、「誰に・どのように伝えるか」を明確にし、それに最適な手法を選ぶことです。
たとえば、前述した不動産会社や保険代理店の事例のように、ひと言で伝えることが難しいビジネスモデルや、こだわり、想いを持っているような方が、一瞬でユーザーメリットを伝えることが重要なWeb広告を活用してもあまり効果は期待できません。
一方で、ブックマーケティング(企業出版)という手法であれば、ターゲットに読んでもらえる、という点で有効なブランディング手段と言えます。
また、あらゆるブランディング手法などをすでにやっている企業がブランディングを強化していきたいという場合には、Web広告やSNSなど誰もができる手法よりも、ブックマーケティング(企業出版)やテレビCMなどのように、誰もがすぐにできない信頼性の高い手法を選んでいくことをおすすめします。
このように、会社によって最適なブランディング手法は異なります。
これから企業ブランディングを始める、または強化していきたいという方は、まずは自社に合ったブランディング方法は一体なんなのか、を考えるところから始めてみてはいかがでしょうか。