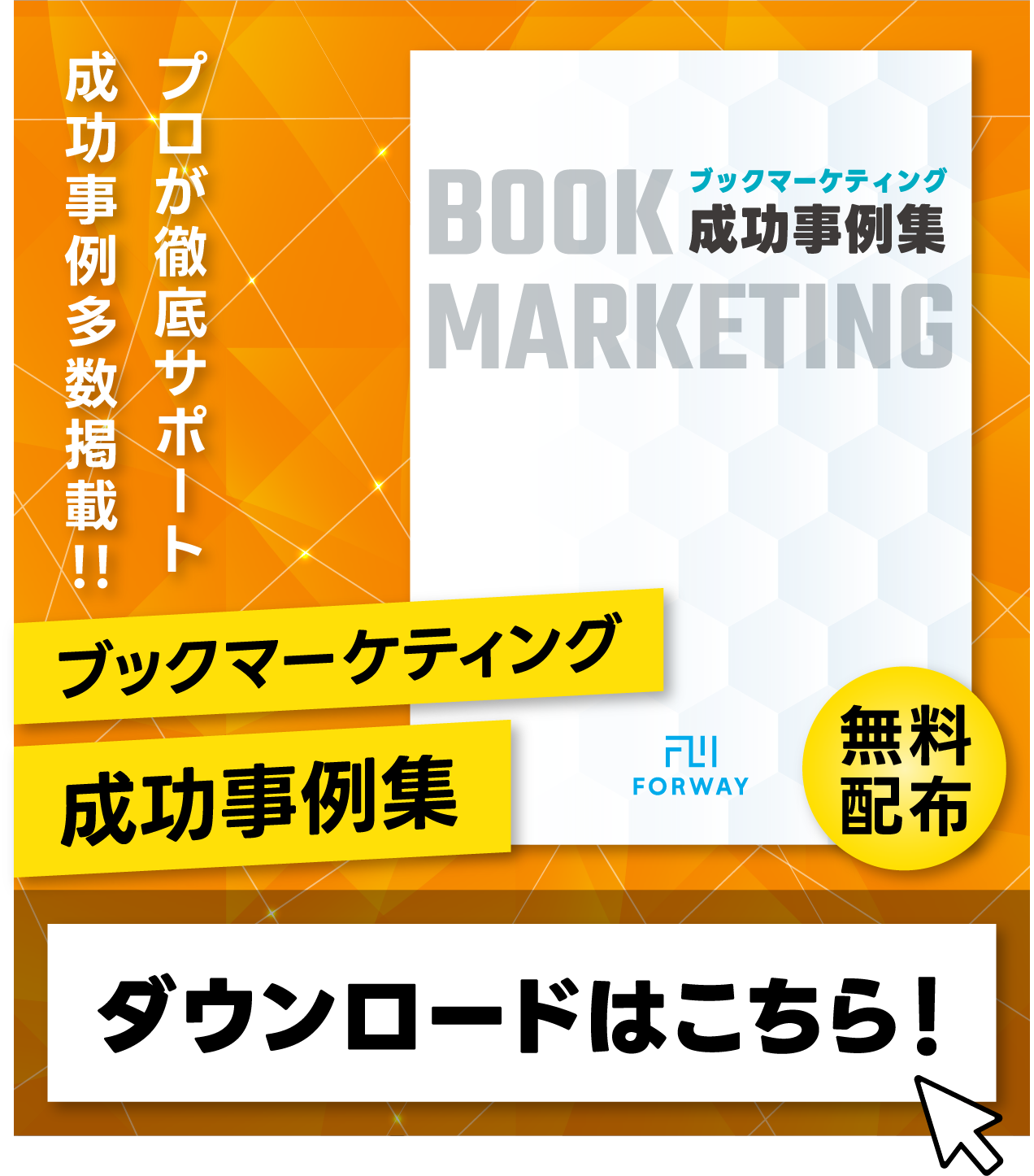Column
フォーウェイは、コンテンツマーケティングで成果を出したい経営者・マーケティング担当者向けの情報を発信しています。
今すぐ自社サイトのSEOを改善させる方法から長期的なブランディングの考え方まで、
実際に弊社のサービスに用いているノウハウを惜しみなく開示します。
2025.05.08
Branding
商品ブランディングとは?効果や手順、具体的な手法を解説

商品・サービスを提供している企業の多くは「自社の商品・サービスをもっと多くの人に知って欲しい」「競合他社との価格競争から脱却したい」という悩みを抱いています。
そんな悩みを解決するカギとなるのが「商品ブランディング」です。
競争が激しく、選択肢が多い現代では、ただ単に良い商品を作るだけでは他社が提供する商品・サービスに埋もれてしまいます。
他社との競争から脱却し「選ばれる商品」になるためには、商品・サービスの持つ価値や魅力を明確にし、顧客の心に訴えかけるブランドを構築する必要があるのです。
この記事では、「商品ブランディングとは」というところから、効果や手順、具体的な手法を解説します。
目次【本記事の内容】
- 1.商品ブランディングとは?
- 1-1.事業ブランディングとの違い
- 2.企業が商品ブランディングで得られる7つの効果
- 2-1.効果1:商品の知名度が向上する
- 2-2.効果2:価格競争に巻き込まれにくくなる
- 2-3.効果3:顧客ロイヤリティが向上する
- 2-4.効果4:マーケティング効果が向上する
- 2-5.効果5:ビジネスチャンスが増える
- 2-6.効果6:優秀な人材の確保につながる
- 2-7.効果7:社員のモチベーションが向上する
- 3.商品ブランディングの実施手順
- 3-1.ステップ1:現状分析
- 3-2.ステップ2:ブランディング戦略を練る
- 3-3.ステップ3:商品・サービスのビジュアルを開発する
- 3-4.ステップ4:戦略を実行に移す
- 3-5.ステップ5:実行・測定・改善を繰り返す(PDCAを回す)
- 4.商品ブランディングに効果的な手法
- 4-1.広告の運用
- 4-2.SNSの活用
- 4-3.インフルエンサーとの連携
- 4-4.コンテンツマーケティングの実施
- 4-5.メディアへの露出
- 4-6.イベント・ポップアップストア・展示会の開催
- 4-7.プレスリリースの配信
- 4-8.メールマーケティングの実施
- 4-9.書籍の出版(企業出版)
- 5.商品ブランディングにも応用できる!ブックマーケティングの成功事例
- 5-1.本物のわさびの良さを伝えるために出版した老舗わさびメーカーの事例
- 5-2.こめ油の有用性を伝えるために出版した食用油脂メーカーの事例
- 6.【まとめ】まずは自社商品の魅力をしっかりと把握することが重要!
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター) 慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉商品ブランディングとは?
商品ブランディングとは、ただ単に商品・サービスに名前やロゴを与えるだけでなく、商品・サービスに関する独自の価値観やイメージを顧客へ浸透させる活動のことを言います。
商品ブランディングでは、特にブランドのストーリーや価値観を伝え、ニーズや感情に訴えかけることが、競合商品との差別化に効果的です。
商品ブランディングが成功すると「この商品は◯◯な価値がある」「このブランドの商品だから安心して買える」などといった印象を持ってもらうことができます。
確立されたブランドができれば、安易な価格競争とは無縁の領域でビジネス展開ができるようになります。
長期的な信頼関係と顧客ロイヤリティを構築するためには、商品ブランディングが欠かせません。
◉-1、事業ブランディングとの違い
事業ブランディングと商品ブランディングは、ブランド戦略の対象範囲と目的が異なります。
事業ブランディングは、顧客をはじめ取引先や株主といった様々なステークホルダーに向けて行われますが、商品ブランディングは主に顧客がターゲットとなります。
目的という視点から見れば、事業ブランディングは企業が行っている事業の中の一つの価値を高めるための活動であるのに対し、商品ブランディングは事業が展開する商品を訴求するものです。
たとえば、世界的に人気のゲーム会社「任天堂」は、ゲーム専用機の製造事業のほかにも、グッズの制作・販売などいくつかの事業を展開しています。
いくつかある事業の中で、ゲーム専用機の製造事業にフォーカスして行うのが事業ブランディング、「Nintendo Switch」など個別の商品を訴求するのが商品ブランディングです。
事業ブランディングが成功すると、結果として事業全体や企業、商品・サービスのイメージ向上にも繋がります。
逆もまたしかりで、商品ブランディングが成功すれば、事業のイメージが向上するという相乗効果が生まれるのです。
◉企業が商品ブランディングで得られる7つの効果
商品ブランディングで得られる効果は、即時的に得られる効果よりも持続的に得られる効果の方が多いのが特徴です。
商品ブランディングの成功は、商品・サービスだけでなく企業にも大きな価値をもたらし、時間が経過するごとに効果がはっきりと現れます。
では、企業が商品ブランディングを積極的に行うことで得られる効果には、どのようなものがあるのでしょうか。
考えられる7つの効果は以下の通りです。
| 効果1:商品の知名度が向上する 効果2:価格競争に巻き込まれにくくなる 効果3:顧客ロイヤリティが向上する 効果4:マーケティング効果が向上する 効果5:ビジネスチャンスが増える 効果6:優秀な人材の確保につながる 効果7:社員のモチベーションが向上する |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、効果1:商品の知名度が向上する
商品ブランディングがうまくいくと、総合的な知名度向上に繋がります。
たとえば、スマートフォンの代表格であるiPhoneは「シンプルでスタイリッシュ」「直感的に操作できるユーザーインターフェース」などのデザイン・操作性により差別化を実現。
これらを一貫して訴求することにより消費者の関心を引き、ブランド価値や知名度を向上させることに成功しました。
「どんな商品か」「なぜ選ぶべきか」という理解を伴った知名度向上は、ファンの創出と継続的な購買に良い影響をもたらすでしょう。
◉-2、効果2:価格競争に巻き込まれにくくなる
商品ブランディングに成功すると、顧客はブランドのストーリーやイメージ、信頼性などに共感し、価格以上の価値を感じてくれるようになることから、安易な価格競争に陥りにくくなります。
確立されたブランドは顧客のロイヤリティを高めることから、多少価格が高くても選ばれる傾向が強いです。
たとえば、冷蔵庫を例にすると、「値段は安いがブランド名を聞いたことがない商品」よりも「値段は少し高いがブランド名を知っていて愛着を持っている商品」を選ぶ方が多いでしょう。
「ブランドで商品が売れる」というのは、安心感やステータス、自己表現などといった無形の価値が価格よりも重視されることを表しています。
商品ブランディングが成功すると、価格競争への依存から脱却できるため、より高い収益性と持続的な成長が期待できます。
◉-3、効果3:顧客ロイヤリティが向上する
商品ブランディングは商品の販売のみに止まらず、顧客との関係性を育むこともできます。
ブランド体験を通して、顧客が商品に愛着と信頼感を抱き、機能的な価値を超えた結びつきができるのは、商品ブランディングならではのものです。
魅力的なブランドストーリーや共感を呼ぶコミュニケーション、期待を超える顧客体験が積み重なれば顧客はブランドのファンとなり、継続的にブランドを選び続けてくれます。
強力な顧客ロイヤリティは長期的な売り上げの安定と成長に欠かせません。
◉-4、効果4:マーケティング効果が向上する
商品ブランディングによってマーケティング活動の一貫性が生まれ、方向性にもブレがなくなるため、高い効果が期待できるようになります。
また、顧客がすでにブランドの価値観や個性を理解していれば、マーケティング施策への反応がよくなり、共感に基づいた行動も期待できます。
たとえば、価値観や個性に共感し、愛着を持っている商品ブランドのキャンペーンや新商品の発売情報であれば、全く知らないブランドのものよりも受け入れやすいはずです。
さらに、一定の共感が得られれば、顧客はSNSや口コミサイトから自社商品やサービスの良さを発信してくれるようになります。
商品ブランディングができていれば、より少ない投資で大きな成果を得ることも夢ではありません。
◉-5、効果5:ビジネスチャンスが増える
確立されたブランドイメージは、顧客からの信頼と認知度を高める効果があり、新商品や関連サービスへの展開がスムーズになります。
具体的には、メディアへの露出や新規顧客の獲得、新市場の参入などです。
ブランドへの信頼感から参入障壁を下げる働きも期待できます。
たとえば、アウトドアウェアを販売する「パタゴニア」は、企業の社会的責任(CSR)に関する取り組みを評価され、企業や団体とのビジネスチャンスが増えました。
確立されたブランドは、他の企業とのコラボやライセンス供与によって、新たな収益源を生み出す可能性も秘めています。
さらには、投資家からの資金調達など、企業全体の成長に関して想定されるシナジー効果は想像以上のものです。
◉-6、効果6:優秀な人材の確保につながる
魅力的なブランドイメージは採用にも良い影響を与えます。
伝わりやすく共感を得やすいブランドストーリーやメッセージがあれば、より多くの人材を募ることも難しくはありません。
商品ブランディングによって良いイメージをつけることができれば、企業イメージも向上します。
その結果、「こんなに素敵な商品をつくる会社なら働いてみたい」「自分もこの会社で商品をつくってみたい」と感じてもらえるようになるのです。
若い世代は給与のみならず、企業の価値観や社会貢献度を重視する傾向があります。
強い商品ブランドは、若く優秀な人材を募る際に大いに役立つでしょう。
◉-7、効果7:社員のモチベーションが向上する
自分が関わる商品が確かなブランドイメージを持ち、多くの顧客に愛されている事実は、社員のモチベーションに良い効果をもたらします。
「良いものを作って多くの人々に喜んでもらっている」という実感は日々の業務への取り組みを支える大切な要素です。
商品ブランディングは企業の方向性と価値観を明確に示してくれるため、社員は自分の仕事の意義を理解しやすくなる効果もあります。
商品ブランディングは、共通の目標に向けてみんなで働く意義をもたらしてくれるでしょう。
◉商品ブランディングの実施手順
商品ブランディングを進めていく上で大切なポイントは、一貫性のある情報発信を継続的に行うことです。
とはいえ、ただ単に同じ情報を発信し続ければいいというというわけではありません。
自社の強みをもとに設定した価値感を「核」として設定し、発信していくことが重要になります。
戦略を実行に移す前後の手順も入念に行うことを意識した上で、順を追って進めていきましょう。
商品ブランディングの実施手順は以下の通りです。
| ステップ1:現状分析 ステップ2:ブランディング戦略を練る ステップ3:商品・サービスのビジュアルを開発する ステップ4:戦略を実行に移す ステップ5:実行・測定・改善を繰り返す(PDCAを回す) |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、ステップ1:現状分析
現状分析を行う際は、最初に自社商品の強みと弱み、ターゲットユーザー、市場における立場を客観的に分析します。
分析ができたら、競合商品のブランドイメージやシェア率、価格帯などを分析しつつ、差別化ポイントを洗い出していきましょう。
現状分析では、ブランドが置かれている立場を明確にしなければいけません。
正しい現状分析ができれば、その後に続く戦略立案もスムーズです。
◉-2、ステップ2:ブランディング戦略を練る
現状分析で得られた情報を元に、具体的なブランディング戦略の立案に進みます。
ブランディング戦略を練る段階では、理想的なブランドイメージや顧客へのメッセージ、競合との差別化ポイント、長期的なブランドの目標などを明確に定義します。
どのような価値を顧客に提供して関係性を作り上げたいのか、ブランドの個性をどのように表現するのか、などといったブランドの核となる重要な部分です。
たとえば、スキンケアブランドである「二ベア」は、「肌がふれあう。 ただそれだけで、人は人をあたためることができる。まもることができる。一生の素肌に。」という一貫したブランドメッセージを発信。
顧客の情緒面に訴えかけ、「保湿クリームと言えば二ベア」とイメージされるまでになりました。
ブランディング戦略が決まると、自然にマーケティング施策やコミュニケーション戦略の方向性が定まってきます。
一貫性のあるブランドイメージを築き上げるためには、ブランディング戦略は欠かせません。
◉-3、ステップ3:商品・サービスのビジュアルを開発する
商品のサービスとビジュアルの開発は、ブランドイメージを具現化し、顧客へ視覚的にアピールする大切な段階です。
ロゴ、パッケージデザイン、ウェブサイト、広告クリエイティブ、店舗デザインなどには、一貫したブランドのメッセージが込められている必要があります。
一貫性のあるビジュアルはブランドの認知度向上や競合との差別化において、大きな意味を持っています。
◉-4、ステップ4:戦略を実行に移す
次の段階では、ブランディング戦略を元に、具体的な手法を実行していきます。
戦略を実行に移す段階では、広告、SNS運用、コンテンツマーケティング、プレスリリースなど、様々な手法を通して一貫したブランドメッセージを発信することが欠かせません。
大切なポイントは、それぞれの手法がブランド戦略との整合性を維持しつつ、ターゲットへ効果的にリーチできているかという点です。
いきなりすべてがうまくいくことは少ないため、微調整を繰り返しながら理想に近づけていく必要があります。
◉-5、ステップ5:実行・測定・改善を繰り返す(PDCAを回す)
一通りマーケティングを終えた後は、効果をより最大化するためのPDCAが必要です。
PDCAを継続的に回すことで、市場の変化と顧客の反応に柔軟に対応することができます。
ブランド戦略の最適化を目指すためにアップデートを繰り返していきましょう。
◉商品ブランディングに効果的な手法
商品ブランディングでは、自社の強みや長所をもとに、価値感や個性を様々な手法を用いて訴求していくことが重要になります。
商品ブランディングに効果的な手法は以下の9つです。
| ・広告の運用 ・SNSの活用 ・インフルエンサーとの連携 ・コンテンツマーケティングの実施 ・メディアへの露出 ・イベント・ポップアップストア・展示会の開催 ・プレスリリースの配信 ・メールマーケティングの実施 ・書籍の出版(企業出版) |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、広告の運用
ブランドの認知度向上とイメージの浸透において、広告の運用は欠かせません。
それぞれの顧客に合わせたメッセージとビジュアルによって、ブランドの価値や個性を効果的に伝えることができます。
商品ブランディングに用いられる広告には、主に以下のようなものがあります。
・マス広告
・デジタル広告
・デジタルサイネージ広告
・デジタル音声広告
たとえば、マス広告の一つであるテレビCMは、幅広い層に対して情報を届けられることやテレビという媒体に対する信頼性が高いことがメリットです。
放映期間中は繰り返し目にしてもらえることも多いため、ブランドに対して愛着や信頼感を持ってもらうことができます。
特にお茶や水などの飲料、ティッシュ・トイレットペーパーなど消耗品など差別化しにくい商品は、「見たことがある商品」「信頼できる商品」を選ぶ傾向にあるため、テレビCMが適しています。
このように、自社の商品・サービスに適した媒体で継続的に広告運用することは、商品ブランディングに効果的です。
◉-2、SNSの活用
SNSの運用は、顧客との関係性を構築する上で欠かせません。
企業と顧客がお互いにコミュニケーションをとることで、ブランドへの共感と信頼感を育むことができます。
たとえば、「Instagramのライブ配信を実施し、視聴者からのコメントを読みながらやりとりする」という手法は近年様々な企業で取り入れられています。
ライブ配信の場で商品を詳しく紹介したり、商品の開発秘話などを伝えたりすることも商品ブランディングに有効です。
特に、視覚的なコンテンツは、ブランドイメージの効果的な訴求や口コミの拡散にも効果があります。
▶︎SNS運用のやり方については、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】もあわせて参考にしてください。
◉-3、インフルエンサーとの連携
インフルエンサーは、抱えているフォロワーから深い信頼や愛着を得ていることが多いため、連携すれば顧客との信頼関係をより強くすることができます。
旅行に関するサービスを提供する企業であれば、旅行に特化したインフルエンサーと連携することで、そのインフルエンサーが抱える旅行好きのフォロワーに訴求することができます。
何かのカテゴリに特化したインフルエンサーは、そのカテゴリに興味を持つフォロワーを抱えているため、ピンポイントに訴求することが可能になるのです。
ただし、ブランドイメージに合わないインフルエンサーを選んでしまうとイメージダウンにつながる恐れがあるため、選任する際は「ブランドイメージに合うかどうか」という点も考慮しましょう。
◉-4、コンテンツマーケティングの実施
コンテンツマーケティングは、オウンドメディアや、ブログなどで顧客にとって価値ある情報を提供することで、ブランドへの理解や愛着を深めてもらうための手法です。
SEO対策を施すことで検索流入も期待できるため、新規の顧客獲得にも効果的です。
たとえば、クラシコムが運営するECサイト「北欧、暮らしの道具店」では、商品の背景や使用シーンを紹介するコンテンツを公開することで、顧客が商品購入後のイメージや愛着を持ちやすくしています。
継続的なコンテンツマーケティングを行えば、顧客と強い関係性を築くことが可能です。
▶︎コンテンツマーケティングについては、関連記事【コンテンツマーケティングとは? 広告費を削減して売上を増やす方法】もあわせて参考にしてください。
◉-5、メディアへの露出
メディアへの露出ができるようになると、短期間で広い認知度と信用を獲得できます。
特に、テレビや雑誌などはその媒体自体が信頼性が高いものなので、顧客に良い印象を与え、ブランドに権威性をもたらします。
ただし、ポジティブなメディア露出は口コミ効果も伴って絶大な効果を発揮しますが、ネガティブな情報は逆に拭いきれない悪い印象を与えてしまうため、注意が必要です。
◉-6、イベント・ポップアップストア・展示会の開催
イベント・ポップアップストア・展示会の開催は、顧客との接点を作り出し、ブランドを体験してもらうための貴重な機会です。
リアルなコミュニケーションを通じて商品の魅力やブランドの世界観を伝えることができます。
たとえば、化粧品を訴求したい場合は、ポップアップストアを出店し実際に手に取って試してもらうのも一つの方法です。
顧客がイベントやポップアップストア、展示会で良い体験をすれば、ブランドに対する信頼性や愛着の向上につながります。
◉-7、プレスリリースの配信
プレスリリースの配信は、新商品や重要な情報を効率よくメディアへ届け、幅広い認知度と信頼性を獲得できる手段です。
プレスリリースによる客観的な情報は、ブランドの信頼感を高めつつ潜在的な顧客へのリーチも可能にします。
タイミングをよく吟味することによって大きな効果も期待できる施策です。
◉-8、メールマーケティングの実施
メールマーケティングは、ブランドロイヤリティを高めつつ既存顧客との関係性をより強くするために有効な手段です。
個別に送信される情報提供や限定オファーにて、顧客のエンゲージメントを促進し、リピート購入を促します。
ブランドの世界観を反映したメールデザインも大切です。
メールマーケティングの効果は折り紙付きですが、大きな効果を得るためにはテキストばかりの内容にならないよう、ひと工夫が求められます。
◉-9、書籍の出版(企業出版)
書籍の出版は、専門性と信頼性を高めつつ、ブランドの権威性を確立するための手段です。
自社が持つ知識や独自の視点を交えることによって、顧客からの信頼を集めつつ長期的な信頼関係を構築することができます。
商品の開発秘話、現場の声などを交えた内容にすることで商品・サービスへの信頼感や親しみやすさを伝えることも可能です。
このように、マーケティング戦略(ブランディング戦略)の一環として書籍を出版することをブックマーケティングと言います。
SNSの活用やコンテンツマーケティングなど他のブランディング手法と組み合わせることで効果を最大化させることが可能です。
▶︎ブックマーケティング(企業出版)については、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】もあわせて参考にしてください。
◉商品ブランディングにも応用できる!ブックマーケティングの成功事例
書籍を活用したブックマーケティングの成功事例を2件ご紹介します。
◉-1、本物のわさびの良さを伝えるために出版した老舗わさびメーカーの事例
わさび離れが進む昨今、本物のわさびの良さをPRするために、とある老舗わさびメーカーは出版プロジェクトに取り掛かりました。
書籍には老舗わさびメーカーの長い歴史の中で培われたわさびのおいしさの秘密や、健康効果に関する知識が詳しく伝えられています。
また、著名な料理研究家とのコラボによって、誌面を彩るわさびの色彩も十分に伝わる内容に仕上がりました。
出来上がった書籍は販売のみならず、営業用のプレゼン資料や小冊子にまとめた読み物として関係者に配布するなど、あらゆる場面で活躍しました。
わさびの本を使った広報活動が実を結び、本を読んだ関係者から無料でのラジオ出演や雑誌掲載に漕ぎ着けるまでに至ります。
結果として老舗わさびメーカーはブックマーケティングによって、広告出稿の費用対効果をはるかに上回る大成功を収めました。
◉-2、こめ油の有用性を伝えるために出版した食用油脂メーカーの事例
とある食用油脂メーカー企業は、企業設立75周年をきっかけに書籍出版を実施。
内容は、あえて「一般販売されているサラダ油の摂取が健康被害の原因になりうる」というテーマを選択し、よりこめ油の有用性を訴求する内容に仕上げました。
サラダ油の健康被害をテーマにした書籍出版は思わぬ反響を得ることとなり、全国放送の番組への出演依頼が相次ぎます。
出版をきっかけに問い合わせは大幅に増加し、著者のファンまでできる反響ぶりです。
結果としてBtoB取引の増加に繋がり、関東や名古屋の老舗有料企業や、遠く離れた鹿児島の企業との取引開始にも成功します。
小売店との取引獲得にも成功し、書籍出版が会社の業績を大きく変えることとなりました。
◉【まとめ】まずは自社商品の魅力をしっかりと把握することが重要!
商品ブランディングは、商品・サービスに根強いファンをつくるために欠かせないものです。
自社の商品・サービスの特性に合った手法を用いることで、ブランドの価値を高め、継続的な売り上げに繋げることができます。
商品ブランディングによって信頼度がアップすれば、新たな取引先の獲得や優秀な人材の獲得にも良い影響を及ぼします。
商品ブランディングを成功に導くために、まずは自社商品・サービスの魅力をしっかりと把握し、差別化できるポイントはどこにあるのか明確にしていきましょう。
商品ブランディングの一貫として書籍を活用したいのであれば、フォーウェイのブックマーケティングがおすすめです。
デジタル全盛の時代でありつつも、書籍の持つ意味は今だ衰えていません。
書籍を通じて届けられる質の高い情報は、確かな情報を得たい層から高い支持を獲得できるだけでなく、顧客から強い信頼を獲得できるはずです。
この記事をご覧になったあなたにおすすめのコラム
-
ブックマーケティングとは?メリットや...
2024.09.02Branding, Marketing
-
【会員制ビジネス・FCビジネス集客編】...
2025.07.22Branding, Marketing
-
「集客が難しい…」と感じる原因と突破口...
2024.11.21Marketing
-
SNS運用で大切な「目的設定」とは?運用...
2023.03.30Branding, Marketing
-
新規の問い合わせを増やすために検討す...
2025.01.08Marketing
-
非対面営業の意外な落とし穴! マーケ...
2021.11.24Marketing