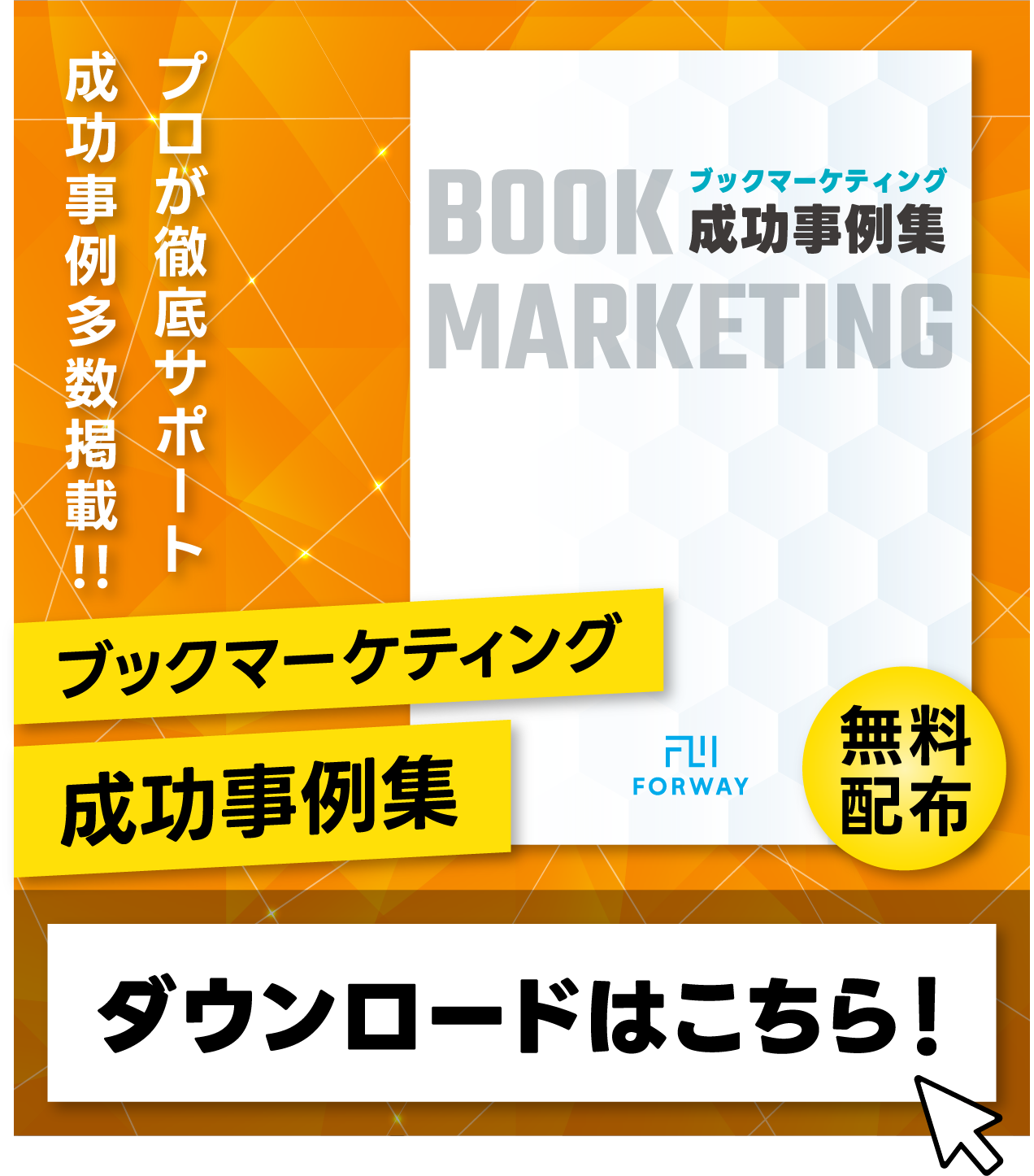Column
フォーウェイは、コンテンツマーケティングで成果を出したい経営者・マーケティング担当者向けの情報を発信しています。
今すぐ自社サイトのSEOを改善させる方法から長期的なブランディングの考え方まで、
実際に弊社のサービスに用いているノウハウを惜しみなく開示します。
2025.03.27
Branding
自費出版に費用はいくらかかる?相場や費用を安く抑えるポイントを解説

「本を出版したい」と思った時に、誰でも自由に出版できてしまうのが自費出版の魅力です。
しかし、自費出版はその名称の通り、自分で出版に関わる費用をすべて負担する必要があります。
実際にネットなどで検索してみると、出版社によって自費出版の費用は大きく異なります。
たとえば有名な大手出版社の自費出版を見てみると数百万円程度だったのが、聞いたことがない出版社では数十万円だったり。
「一体どの出版社に依頼するのが良いのだろう?」「そもそもなぜその金額なのだろう?」「本当にそんな費用がかかるのか?」など、不安に感じてしまう方も多いのではないでしょうか?
今回は、自費出版するためにかかる費用相場や、費用が変わる要因などを出版社の現役編集者が詳しく解説いたします。
目次【本記事の内容】
- 1.自費出版の費用相場
- 2.自費出版の費用が変わる主な要因
- 2-1.発行部数
- 2-2.本の制作分担(原稿・デザイン)
- 2-3.本のページ数・サイズ
- 2-4.製本の種類(ハード・ソフト)
- 2-5.書店流通・販促の有無
- 2-6.依頼する出版社の知名度
- 2-7.個人・法人
- 3.こんな時は自費出版の費用が高くなりやすい
- 3-1.本の制作をすべて出版社に依頼する
- 3-2.本の書店流通や販促をすべて依頼する
- 3-3.本のページ数が多い
- 3-4.フルカラー印刷
- 3-5.本のサイズ感が特殊
- 3-6.本の装丁が特殊
- 4.自費出版の費用を安くするためのポイント
- 4-1.本の原稿をできる限り自分で書く
- 4-2.こだわる部分を絞る
- 4-3.ソフトカバーにする
- 4-4.カラーを使わない(モノクロ印刷・2色刷り)
- 5.自費出版の費用を安くすればいいというものではない!
- 5-1.出版後の活用を見据えた提案をしてくれる出版社を選ぼう!
- 6.【まとめ】自費出版の費用が回収できるかどうかは出版後の活用法が重要!
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター) 慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉自費出版の費用相場

自費出版にかかる費用は出版社や作る本の仕様、制作の方法によって大きく異なりますが、大体100万円〜1,000万円程度が費用相場です。
実際に数十万円程度で出版できる出版社もあれば、数百万円〜一千万円で自費出版を行う会社も存在します。
しかし、安いから良い、高いからダメ、という訳ではありません。
それぞれ安い理由、高い理由ががあるのです。
著者が「どのような書籍にしたいのか?」「書籍の出版で何を得たいのか?」によって、安いから良い場合と、高くても良い場合が異なるので、自分が出版を通して達成したい目的と、目指すべき成果物が妥当な費用感でできる出版社、制作方法を検討することが何より大切です。
◉-1、自費出版にかかる費用の内訳
本を出版するためには、原稿作成や編集、デザイン、印刷、流通、マーケティング、営業など、思った以上に多くの工程を踏む必要があります。
商業出版の場合、その全ての工程を出版社が費用をかけて行います。
しかし、自費出版の場合、その工程をどれだけ出版社に任せるのか、によって以下のような費用がかかってくるのです。
| 内訳 | 概要 |
| 企画費 | 書籍のコンセプトや方向性、ターゲットや内容の企画や構成を作成するための費用。 |
| 取材・ライティング費 | 著者に代わり、ライターが著者にインタビュー取材を複数回行い、企画や構成に基づき原稿を書く費用。 |
| 撮影費 | 書籍に掲載する写真素材をプロのカメラマンに撮影してもらう費用。 |
| 編集費 | 1つの書籍として成り立たせるために、文章の流れや構成を整えたり、企画の意図に沿って読みやすく、伝わりやすいように文章を仕上げていく費用。 |
| 校正・校閲費 | 誤字脱字や表記ゆれ、表現の間違い、事実関係などをチェックし、修正する費用。 |
| デザイン費 | 表紙や誌面レイアウト、挿絵イラストなどのデザインにかかる費用。 |
| DTP費 | 印刷用データを作成する費用。 |
| 印刷・製本費 | 印刷し、書籍として製本するための費用。 |
| 書店流通費 | 書店やネット書店への流通を行うための費用。 |
| 保管費 | 出来上がった書籍を倉庫に保管しておくための費用。 |
| 販促・マーケティング費 | 本を販売するための広告宣伝やPRを行ったり、マーケティング施策を実施するための費用。 |
| 書籍買取費 | 著者が書籍を買い取る際に発生する費用。 |
こういった一連の費用がパッケージ化されていることも多いため、見積もりの際には「どの費用が内訳として含まれているのか?」「どの費用がオプションなのか?」などを確認することが大切です。
◉自費出版の費用が変わる主な要因

自費出版の費用は、著者がどこまで制作や工程を担うか、何部を印刷するのか、どのような仕様・装丁にするのか、オプションをどれだけつけるのか、などによって増減します。
自費出版の費用が変わる主な要因として抑えておきたいのが、以下の項目です。
| ・発行部数 ・本の制作分担(原稿・デザイン) ・本のページ数・サイズ ・製本の種類(ハード・ソフト) ・書店流通・販促の有無 ・依頼する出版社の知名度 ・個人・法人 |
それぞれどのような要因なのか、どのぐらい費用が変わるものなのかを詳しく解説します。
◉-1、発行部数
自費出版の場合、大手出版社の場合は初版部数が1,000部〜2,000部程度、中小出版社の場合には500部〜1,000部程度が一般的です。
発行部数が多くなればなるほど、1冊あたりの単価は下がりますが、全体的な費用は上がります。
◉-2、本の制作分担(原稿・デザイン)
自費出版の場合、本の制作のうちどこまで著者が関わるかによって費用が大きく変動します。
たとえば、原稿をすべて著者自身で執筆すればライターに依頼するためのライティング費用がかからず、その分費用は安くなります。
表紙や挿絵のデザインや校正・校閲、編集作業なども同様です。
たとえば書籍のライティングや編集経験があれば、ある程度自分でできてしまうとは思いますが、全くの素人が行うと完成度は明らかに下がります。
後から修正をする場合は、修正費が別途かかってしまうこともあるため、どこまでを自分自身が担当するかは出版社の担当者と話合い、慎重に決めていきましょう。
◉-3、本のページ数・サイズ
本のページ数が増えれば増えるほど、また、本のサイズが大きくなればなるほど、サイズが一般的ではなく特殊になればなるほど、次表のように印刷や製本費用が高くなります。
| 判型(サイズ) | 寸法 | 特徴 | 費用感 |
| 文庫判 | 約105×152mm | 文庫本のサイズ感。小型で軽量。再刊行に多いサイズ。 | 安め |
| 新書判 | 約109×173mm | 文庫本が少し縦長になったサイズ感。文庫本と同様に小型で軽量。 | やや安め |
| 四六判 | 約130×188mm | 一般的なビジネス書や自己啓発本、小説、エッセイ集などの単行本に多いサイズ感。普及率の高いサイズ。 | 普通 |
| 小B6判 | 約112×174mm | 少年・少女コミックスのサイズ感。 | 普通 |
| B6判 | 約128×182mm | 四六判よりも縦が短い。青年向けコミックスや歌集や句集、漫画、小説、エッセイなどに多いサイズ感。新書よりもやや大きく、イラストが多い書籍でも読みやすい仕様。 | 普通 |
| A5判 | 約148×210mm | 研究書や学術書、実用書、長編の文芸作品などに多いサイズ感。文藝春秋などの文芸誌もこのサイズ感。 | やや高め |
| B5判 | 約182×257mm | 一般的な週刊誌のサイズ感。週刊少年ジャンプなど漫画雑誌もこのサイズ感がほとんど。 | 高め |
| AB判 | 約210×257mm | 女性誌やファッション誌に多いサイズ感。 | 高め |
| A4判 | 約210×297mm | 写真集や画集、絵本などに多いサイズ感。記念誌や社史などにも使われることが多い。 | さらに高め |
◉-4、製本の種類(ハード・ソフト)
本のカバーをハードカバーにするか、ソフトカバーにするのか、製本の種類の選択によっても費用は変わります。
| 本のカバーの種類 | 特徴 |
| 上製(ハードカバー) | 硬いボール紙を貼ったカバーで、耐久性が高く、高級感のある仕上がりになります。一方で持ち運ぶには不向きです。 |
| 並製(ソフトカバー) | 表面に柔らかい厚紙を使ったカバーで、軽量で持ち運びやすいのが特徴。表紙が曲がるので読みやすいという特徴もあります。 |
| 中綴じ | 針金を使って綴じる方法。雑誌やパンフレット向きの製本仕様。 |
ハードカバーは見た目の高級感があり、耐久性などにも優れていますが、ソフトカバーに比べて製本費用が部数によりますが、数十万円程度上がります。
一方で、ソフトカバーは比較的安く仕上がるという点から、ビジネス書や実用書などさまざまなジャンルで採用されています。
どちらを選ぶのかは著者次第ではありますが、ハードカバーの書籍は紙代の高騰や書籍が売れにくいなど、様々な理由で減ってきているのが実情です。
特にこれといった理由やこだわりがない場合は費用も安く抑えられるソフトカバーを選ぶのが一般的です。
◉-5、書店流通・販促の有無
自費出版の場合、本の書店流通や販促などは著者自身が行うのが基本です。
出版社に書店流通や販促を依頼したい場合には別途費用がかかるか、出版社によっては「書店流通付きプラン」のようにパッケージが用意されている場合があるのでそれを選びましょう。
書店流通や営業などを行うには専門知識や、人脈などが必要なため、出版社に依頼すると費用はどうしても高くなってしまいます。
◉-6、依頼する出版社の知名度
名の知れた大手出版社で自費出版する場合と、あまり聞いたことがない中小の出版社で自費出版する場合では価格が大きく異なります。
大手出版社は中小の出版社に比べて知名度があります。
そのため、大手出版社で出版すると、「大手出版社から本を出すほどすごい人なんだ」というイメージを持ってもらえるため「大手の◉◉出版社から本を出しました」というだけで著者の信用度が上がりやすくなります。
また、大手出版社が持つ全国の書店と強いネットワークを活用した流通力の高さもメリットの1つでしょう。
費用はその分高額になってしまいますが、ブランド力や流通力を活かした書店配本・営業が可能です。
書店によっては大手出版社の本というだけで、他の出版社と取り扱われ方が違ったりする場合もありますし、優先的に書棚に置いてもらえる可能性も高くなります。
このように、大手出版社の場合、費用は中小と比べて高額ですが、それだけのメリットを得ることができるのです。
しかし、読者は本を購入する際に「この大手出版社だから」と購入するわけではありません。
中小であっても営業力が高く、書店流通をしっかりと行えるノウハウを持つ出版社であれば、コストを抑えられるという点でおすすめです。
◉-7、個人・法人
個人での自費出版の場合、出版の目的は著者によってさまざまです。
「自分の作品を形にしたい」など、出版することが目的の方もいれば、自身の手がける事業の認知度を上げたい方、商品・サービスのPRのために書籍を活用したい方、など目的の幅が広いのが特徴です。
たとえば自伝をただ形として残したい、というように「自分の書いた原稿をただ本として出版するだけ」の場合には費用は当然ながら安くなります。
一方でビジネスの発展のために書籍を活用したい、など明確な目的がある場合や、譲れないこだわりがある場合などには費用は高額になります。
法人の場合(※企業の場合は自費出版ではなく「企業出版」「カスタム出版」)は、基本的に「出版すれば良い」というよりも、ブランディングや集客、商品・サービスのPRなどビジネス的なゴールのために出版を活用することがほとんどです。
その際には本の販促活動や、マーケティング施策の実施、書店流通などの実施が含まれるため、費用が高額になる傾向があります。
◉こんな時は自費出版の費用が高くなりやすい!

自費出版は「こんな本にしたい」と、こだわればこだわるほど費用は高くなっていきます。
出版社が推奨する作り方やフォーマットから逸脱した場合や、一般的な本のサイズ・装丁・ページ数などを逸脱した際に費用が高くなりやすいと言えます。
特に費用が上がりやすいケースとして押さえておくべきは次の6つです。
| ・本の制作をすべて出版社に依頼する ・本の書店流通や販促をすべて依頼する ・本のページ数が多い ・フルカラー印刷 ・本のサイズ感が特殊 ・本の装丁が特殊 |
それぞれ詳しく解説します。
もし自費出版の費用を安くしたい場合は参考にしてみてください。
◉-1、本の制作をすべて出版社に依頼する
原稿執筆やデザイン、校正・校閲、編集など本を出版する一連の工程を出版社にすべて任せることも可能ですが、その分費用は高くなってしまいます。
もちろん、出版社にすべて依頼した方がそれぞれの工程をプロが対応するため、本の完成度や品質は高まりますが、自分である程度対応した方が費用は安くなります。
しかし、知識や経験がない素人なのに安さを求めすぎて「自分ができる部分」を見極めずにやってしまうと、完成度や品質の低下や、後々の修正発生により思わぬ追加費用がかかってしまう可能性があるので冷静に判断していくことが大切です。
◉-2、本の書店流通や販促をすべて依頼する
自費出版の場合、本の出版後の販促活動は著者が行うのが原則です。
また、書店流通や書店営業は、専門的な知識とネットワークが必要になるため著者個人が行うのは難しいと言えるでしょう。
書店流通や書店営業を出版社に追加費用を支払って依頼することもできます。
「出版後にしっかりと書店流通や営業などを実施していきたい」という明確な目的があれば良いですが、特にそういった目的がないのであれば、費用が膨らむだけなのでやめましょう。
◉-3、本のページ数が多い
本のページが増えればその分印刷の費用が高くなります。
専門書のように内容が厚くなってしまう場合には仕方ありませんが、無駄にページを増やすのはやめましょう。
そのページ数が本当に必要かどうか、編集段階でできるだけページの取捨選択を行っておくことが重要です。
◉-4、フルカラー印刷
コンビニのコピー機の場合、モノクロ印刷は1枚10円なのに対し、フルカラー印刷は1枚50円かかります。
フルカラー印刷の方が5倍お金がかかってしまいます。
これは書籍の場合も同様です。
使う色の数が増えるにしたがって印刷費用は増えていきます。
写真集やイラスト集など色味が重要なジャンルの本を出版する場合は必要経費ですが、文章中心の書籍に不必要にカラーを多用すると、費用が一気に高額になってしまう可能性が高いです。
できるだけモノクロで、使ったとしてもカラーを2色程度に留められないかを検討しましょう。
◉-5、本のサイズ感が特殊
一般的な書籍サイズではなく、大きな判型や、特殊な判型を採用すると、印刷会社の標準工程から外れてしまい、追加で費用がかかってしまいます。
美術系の画集や、コンセプトブックなどサイズが特殊なジャンルの出版物であれば良いですが、一般的なビジネス書や実用書を出版する場合に特殊な判型を採用してしまうと、予想外に費用が高額になってしまうので注意しましょう。
◉-6、本の装丁が特殊
装丁に凝ったり、特殊な素材を仕様したり、オリジナルの造本をする場合はその分制作費用も上がります。
たとえば、表紙に型押しや箔押し、布張りなどを採用すると、それだけ手間や技術力が必要になります。
せっかくの出版なので本を豪華で目立つような装丁にしたい気持ちは理解できますが、その分費用は高くなってしまうので、特に意味や目的がなければ、一般的な装丁で出版することをおすすめします。
◉自費出版の費用を安くするためのポイント

自費出版をできるだけ安くするポイントは、出版社などが推奨する一般的な書籍仕様にすることです。
流通量の多い一般的な書籍の仕様に合わせることで、出版社も印刷会社も手間がかかりにくくなり、費用を安く抑えることができるのです。
このように、「ここだけは外せない」というこだわりを除き、次のような観点で費用を安くできないか、検証してみてください。
| ・本の原稿をできる限り自分で書く ・こだわる部分を絞る ・ソフトカバーにする ・カラーを使わない(モノクロ印刷・2色刷り) |
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
◉-1、本の原稿をできる限り自分で書く
文章を書くのが得意であれば、取材やライティングを外部に依頼しないことで、大幅に費用を安くすることができます。
ただし、本1冊分で文字数は数万文字以上になります。
数千文字程度の記事を書くプロのライターであっても、書くのは難しいほどの桁違いの文章量です。
よく自分の力量や原稿作成にかけられる時間を見極めて判断しましょう。
ライターに依頼する費用相場は30万円〜150万円程度とピンキリです。
ライターに依頼した方が費用はかかりますが、読者目線で読み手にとって読みやすい文章にすることができます。
特に本を出版する理由が商品やサービスのマーケティングや自身のブランディングであれば、「読者に伝わりやすい内容になる」という点でライターに依頼した方が良いと言えるでしょう。
一方で、自己満足的に小説やエッセイをまとめたり、自伝を作りたいなど、費用を最優先で抑えたい方にとっては「本の原稿をできる限り自分で書く」というのは、費用を安くするために有効な方法と言えます。
◉-2、こだわる部分を絞る
自費出版では著者のこだわりが強ければ強いほど、費用は高くなる傾向があります。
「せっかく出版するのだから自分で納得のいく本が作りたい」という気持ちはあると思いますが、費用を安くするためには、こだわる部分とそうでない部分を明確に分けることが重要です。
たとえば、本のタイトルや表紙のデザイン、内容など読者に影響する部分は徹底的にこだわり、それ以外は一般的な仕様にする、などです。
目的達成に不要な要素までこだわり、豪華にしようとするとあっという間に費用が膨らみます。
こだわる部分を絞り込んでいくためにも、「自分が自費出版を通して何を為し得たいのか」を明確にし、そのために必要なこだわりをリストアップしたり、優先順位をつけておくと良いでしょう。
◉-3、ソフトカバーにする
特にこだわりがないのであれば、ソフトカバーで十分です。
ハードカバーには高級感があるため、特別感を演出するには適していますが、費用がその分高くなります。
実際にビジネス書や実用書の多くは特別感よりも「読みやすさ」や「扱いやすさ」が重要だったりするので、特別な理由がない限りはソフトカバーが好まれています。
◉-4、カラーを使わない(モノクロ印刷・2色刷り)
写真集やフォトエッセイなどフルカラーでなければ意味がない書籍を除き、文章が中心の書籍であればフルカラーにする必要性はありません。
フルカラーにするだけで印刷費は大幅に上がります。
解説用のイラストなど必要な箇所だけカラーを使いたい場合には、ポイント使いの2色刷りを検討しましょう。
余計なカラーを入れずにシンプルにまとめることで、見やすさを損なうことなく、印刷費用を削減できます。
◉自費出版の費用を安くすればいいというものではない!

自費出版の費用は安いに越したことはありませんが、ただ安くすれば良いというわけではありません。
本の売上を目的とする商業出版とは違い、「出版した本をどのように活用するか」「出版した本を通してどのような付加価値や利益を得るか」が自費出版においては重要です。
費用を安く抑えたいがあまり書いたことのない原稿を無理やり自分で原稿を書いたり、表紙を素人の著者がデザインしたり、必要な部分まで極端に費用を削減してしまうと、本のクオリティや読者の満足度の低下につながり、目的達成が遠のいてしまう可能性があります。
自費出版として費用をかけて本を作る以上、目的達成のために必要な要素なのであればむしろ費用をかけるべきです。
目的達成のために不要な要素を徹底して削減し、必要な箇所に集中させることで費用対効果の高い投資にすることができるのです。
◉-1、出版後の活用を見据えた提案をしてくれる出版社を選ぼう!
出版そのものがゴールではなく、あくまでブランディングやマーケティング、商品・サービスの販促手段の一つとして自費出版を活用したい場合は、本の企画段階から、出版後の活用まで一連の戦略をあらかじめ立てておく必要があります。
そのため、こういった一連の戦略を提案し、一緒に考えてくれるような出版社を選ぶことが重要です。
たとえば弊社のようなコンテンツマーケティングの専門会社であれば、デジタルとアナログの両方のマーケティング施策などに精通しているため、ターゲットの選定から、出版後の活用案、活用から逆算した書籍内容の企画まで、一連の流れをご提案させていただいております。
出版を戦略的に活用したい方は、マーケティング視点を持った出版社に相談するのがおすすめです。
◉【まとめ】自費出版の費用が回収できるかどうかは出版後の活用法が重要!
自費出版では数十万〜数百万円程度の費用がかかります。
かかった費用を本の売上だけで回収するのは難しいと言えます。
しかし、出版後にターゲットにしっかりと書籍を届け、自身のビジネスの新規依頼につながったり、本の売上以外のところで費用の回収やそれ以上の利益を上げることは十分に可能です。
自費出版に失敗した、という事例のほとんどが「とりあえず出版したが、その後うまく活用できずに大量の在庫が残り続けてしまう」というパターンです。
実際に弊社で出版した経営者の多くは、事前にしっかりと出版後の活用を見据えて企画・制作を行っているため、別のところで費用回収がスムーズにできています。
企業であれば、事業の認知度を高たり、ビジネスの商談ツールとして活用できますし、個人であっても出版した本をSNS上や、セミナーや講演会などのイベントで地道に配っていくことで新規顧客や人脈の開拓につながるかもしれません。
フォーウェイでは、あくまでも出版を一つの手段として捉え、事業の売上の拡大につなげたり、ブランディングにつなげていくにはどうすれば良いか、を考えて本づくりを行っております。
自費出版でかけた費用が高くても、そのおかげで良い本ができ、自身の事業で費用回収を上回る利益が出れば全く問題ありません。
自費出版の費用の検討は重要ですが、費用よりも「出版を通してしっかりと目的を達成できる本」を作ることの方が大事です。
もし自費出版を検討されている方は、フォーウェイまでご相談ください。