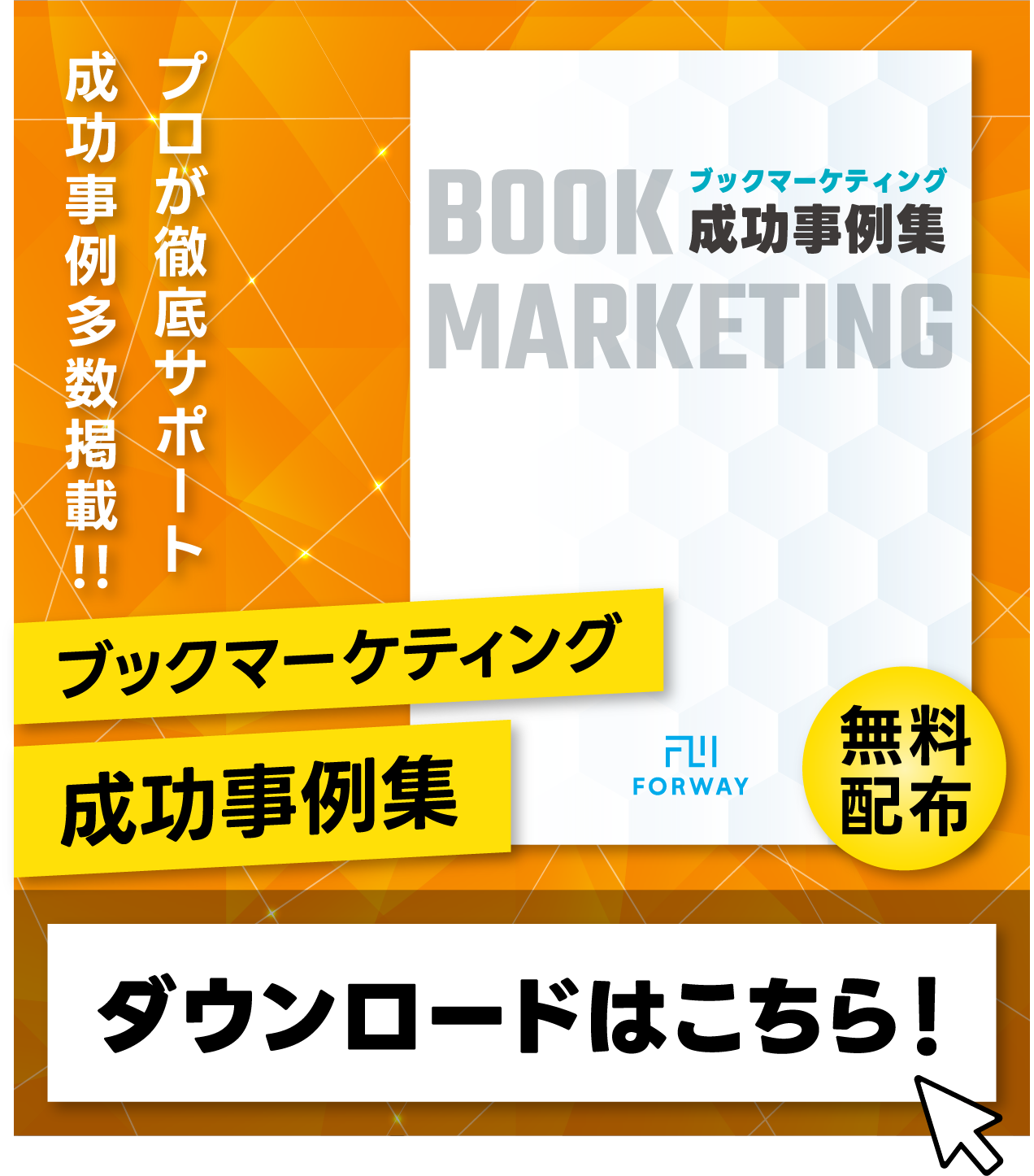Column
フォーウェイは、コンテンツマーケティングで成果を出したい経営者・マーケティング担当者向けの情報を発信しています。
今すぐ自社サイトのSEOを改善させる方法から長期的なブランディングの考え方まで、
実際に弊社のサービスに用いているノウハウを惜しみなく開示します。
2025.07.04
Branding, Marketing
客単価を上げるには?計算方法や改善するための施策を徹底解説

売上を高めるうえで欠かせないのが「客単価」の分析と改善です。
客単価とは、1人の顧客が1回の取引で支払う平均金額のことを指します。
一見単純な指標に思えるかもしれませんが、「顧客が何をどのように買っているか」「自社の商品・サービスの価値がどれだけ適切に伝わっているか」といった重要な情報が詰まっています。
たとえば、同じ売上金額でも、少数の顧客が高額商品を購入しているのか、それとも多くの人が少額ずつ買っているのかで、事業の方向性や戦略は大きく変わるでしょう。
客単価に注目することで、売上の内訳がはっきり見えてくるため、「どのターゲット層にどうアプローチするか」「どの商品を主力にするか」といった判断もつきやすくなります。
本記事では、客単価の定義や計算方法をわかりやすく解説し、分析によって得られるメリットや具体的な単価アップの施策について紹介します。
目次【本記事の内容】
- 1.客単価とは?定義と計算式をわかりやすく解説
- 1-1.客単価の定義
- 1-2.客単価の計算式
- 2.客単価を分析するメリット
- 2-1.売上向上の具体的な戦略立案に役立つ
- 2-2.ターゲット顧客ごとにマーケティングの最適化を図れる
- 2-3.他社との差別化ポイントを把握しやすくなる
- 3.客単価を上げるための具体的な施策
- 3-1.商品・サービスの設計で客単価を引き上げる施策
- 3-2.販売方法で客単価を引き上げる施策
- 3-3.購入しやすさを高めて客単価を引き上げる施策
- 3-4.価値の訴求によって商品の魅力を高め、客単価を引き上げる施策
- 4.書籍出版によって客単価向上を実現した事例
- 4-1.事例1:書籍出版で信頼を獲得し、法人保険の大型契約を実現した保険代理店の成功事例
- 4-2.事例2:書籍出版を通じて専門性を可視化し、高単価案件の獲得に成功した公認会計士の事例
- 5.【まとめ】価値訴求による客単価向上を実現するために「書籍出版」を活用しよう!
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター) 慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉客単価とは?定義と計算式をわかりやすく解説

まず最初に、客単価とは何かについて説明しておきましょう。
客単価の定義と計算式は、次の通りです。
◉-1、客単価の定義
客単価とは、「1人の顧客が1回の購入で支払う平均金額」のことです。
ECサイトや飲食店、小売店などのさまざまな業種で活用されている代表的な経営指標の一つです。
顧客1人あたりの購買金額を把握することで、経営状況や販売施策の効果を客観的に評価できるようになります。
◉-2、客単価の計算式
客単価の計算式は、次の通りです。
| 客単価=特定期間の売上金額÷その期間の購入者数 |
たとえば、1日の売上が50万円で、来店客数が250人だった場合、「500,000円÷250人=2,000円」と計算できます。
なお、曜日や時間帯によって売上や販売量に大きな差がある場合は、分析対象の期間を「曜日別」や「時間帯別」に区切ることで、より精度の高い分析が可能になります。
ここで注意すべきなのは、「客単価」は実際に購入した顧客のみを対象として算出される点です。
つまり、いくら多くの人を集客しても、購入に至らなければ売上には結びつかず、客単価にも反映されません。
一見当たり前に思えることですが、プロモーションやマーケティング戦略を立てるうえで重要な視点です。
◉客単価を分析するメリット

では、客単価を分析するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
一般的に、次の3つのメリットがあります。
| ・売上向上の具体的な戦略立案に役立つ ・ターゲット顧客ごとにマーケティング最適化を図れる ・他社との差別化ポイントを把握しやすくなる |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、売上向上の具体的な戦略立案に役立つ
「売上が思うように伸びない」「最近落ち込み傾向にある」といった場合に、客単価を分析すると原因を探る手がかりになります。
単に売上金額だけを見ていても、その内訳がわからなければ、有効な対策を講じることはできません。
たとえば、売上が前月より20%減少したとき、この数字だけでは、何が問題だったのかはわかりません。
しかし、客単価のデータを確認すれば、「来店客数は変わらないのに、1人あたりの購入金額が減っている」といった具体的な傾向が浮き彫りになります。
逆に、「客単価は変わらないのに客数が減っている」という傾向が把握できたときは、集客施策の見直しが必要になります。
◉-2、ターゲット顧客ごとにマーケティングの最適化を図れる
顧客単価の分析は、単に顧客一人あたりの購入金額がわかるだけでなく、マーケティング活動を最適化するためにも役立ちます。
特に、ターゲット顧客ごとの客単価を比較することで、より効果的なマーケティング施策を立てるための方向性がつかめます。
たとえば、商品カテゴリー別に客単価を分析すれば、売上に貢献しているジャンルを特定することが可能です。
また、性別・年齢・地域・購入頻度・購買チャネルなど、さまざまな属性で顧客を分類し、それぞれの客単価を算出することで、「誰に何をどのように訴求すればよいか」がより明確になります。
このように、客単価は「誰に何を売るか」という視点を磨くための重要な指標といえます。
◉-3、他社との差別化ポイントを把握しやすくなる
客単価の分析は、自社の販売戦略や商品・サービスの市場評価を把握するうえで有効な手段です。
特に、同業他社と比較することで、自社の強みや弱み、そして競合との差別化ポイントを客観的に見極めることができます。
たとえば、同じ業種・同規模の企業と比べて自社の客単価が低い場合、価格設定や販売手法、提案内容に改善の余地があると考えられます。
一方で、高い客単価を維持できているのであれば、それは顧客が自社の商品やサービスに対して高い価値を認識している証拠です。
このような分析を通じて、「なぜ選ばれているのか」「どこで差別化できているのか」を明らかにすることができ、今後の戦略立案にも役立ちます。
▶︎差別化戦略の詳細については、関連記事【差別化戦略の成功の秘訣ーメリットやデメリット、成功事例とは!?】もあわせて参考にしてください。
◉客単価を上げるための具体的な施策
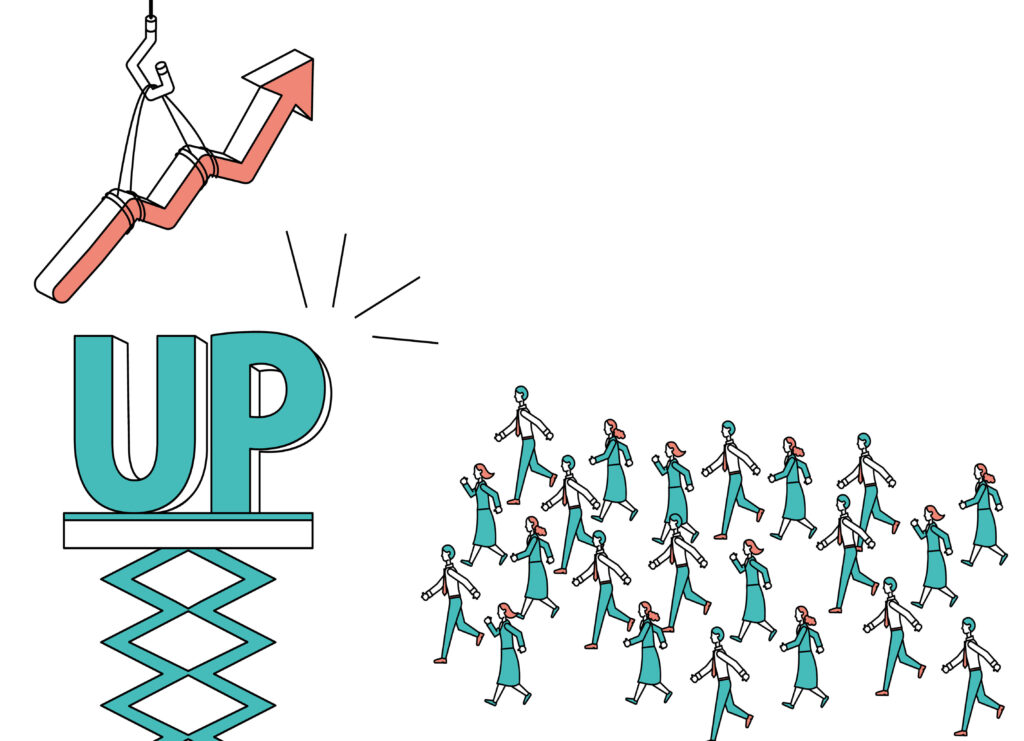
客単価を上げる具体的な施策として、次の4つが挙げられます。
| ・商品・サービスの設計で客単価を引き上げる施策 ・販売方法で客単価を引き上げる施策 ・購入しやすさを高めて客単価を引き上げる施策 ・価値の訴求によって商品の魅力を高め、客単価を引き上げる施策 |
どのような施策なのか、詳しく見ていきましょう。
◉-1、商品・サービスの設計で客単価を引き上げる施策
商品やサービスそのものの価値を見直すことで、無理なく客単価を引き上げることができます。
顧客に「この金額を払っても良い」と納得して支払ってもらえるような仕組みを作ることで、値引きに頼らず安定的に売上を伸ばすことが可能になります。
◉-1-1、商品単価を上げる
客単価を引き上げる方法として、まず検討できるのが「商品単価の引き上げ」です。
一番シンプルな方法ですが、ただ価格を上げるだけでは「値上げ」と受け取られ、購入をためらわれる可能性があります。
そのため、「価格の引き上げ」と「提供価値の向上」をセットで行うことが重要です。
たとえば、素材の品質を高めたり、パッケージデザインを刷新したり、購入後のサポート体制を強化したりすることで、価格に見合う価値を感じてもらうことができます。
価格以上の満足感を提供することで、自然なかたちで商品単価を上げることが可能になります。
◉-1-2、高価格帯商品や限定品を追加する
顧客の選択肢の中に、あえて選びたくなるような高価格帯の商品や限定商品を加える方法も有効です。
すべての顧客が購入してくれなくても、一部の顧客が選んでくれるだけで全体の客単価を引き上げる効果があります。
たとえば、オーダーメイド対応品や季節限定品、数量限定品などがあります。
◉-1-3、購入特典を用意する
購入特典を用意することで、顧客の購買意欲を高め、自然と客単価の向上を促すことができます。
たとえば、「5,000円以上のご購入でオリジナルグッズをプレゼント」や「購入者限定で次回使えるクーポンを進呈」といった施策は、顧客にとって「もう少し買えば得をする」という動機づけになり、結果的に購入金額の底上げにつながります。
◉-2、販売方法で客単価を引き上げる施策
商品の販売手法を工夫することで、顧客がより自然に多くの商品や高価格帯の商品を選ぶように促すことができます。
ポイントは「お得感」や「選びやすさ」を意識した販売設計です。
◉-2-1、セット販売を導入してまとめ買いを促す
セット販売(バンドル販売)を導入することで、まとめ買いを促し、客単価の向上を図ることができます。
これは、複数の商品を組み合わせて一つのパッケージとして提供する販売手法です。
たとえば、飲食店では「メイン+ドリンク+デザート」のセット、小売店では「靴下3足組」といった組み合わせが考えられます。
また、「2点以上の購入で10%割引」「5,000円以上の購入で送料無料」というやり方もあります。
顧客にとっては単品購入よりもお得感があり、「せっかくならもう1点」といった追加購入につながりやすい点がメリットです。
◉-2-2、3段階の価格設定を行い、中価格帯の選択を促す
「松・竹・梅」のように、3つの価格帯を用意する方法です。
人は、最も安い選択肢には品質面で不安を感じやすく、最も高価な選択肢には手が届きにくいと感じる傾向があります。
その結果、無意識のうちに中間の価格帯を「妥当な選択」として選ぶ心理が働きます。
この心理を活用し、最も販売したい商品を中価格帯(竹)に設定し、その上下に高価格(松)と低価格(梅)の商品を配置することで、中価格帯の商品が選ばれやすくなります。
◉-2-3、上位商品を提案してアップセルを狙う
アップセルとは、顧客が検討している商品よりも上位のグレードや価格帯の商品を提案し、購入単価を引き上げる手法です。
「少しの追加予算で、より高品質な商品が手に入る」といった納得感を与えることで、顧客の選択を自然に上位商品へと誘導できます。
たとえば、美容院では「通常カット」に加えて「トリートメント付きプラン」を提案する、家電販売では「標準モデル」ではなく「高機能モデル」を紹介するといった施策が該当します。
ただし、過度な提案は押し売りと受け取られるリスクがあるため、顧客のニーズや状況を正確に把握し、それに基づいた適切な提案を行うことが重要です。
◉-2-4、関連商品を提案してクロスセルを狙う
クロスセルは、顧客が購入を検討している商品と一緒に使うと便利な商品を併せて提案する販売手法です。
たとえば、スマートフォンを買う顧客に、ケースや保護フィルム、充電器などを同時に提案するといったイメージです。
また、ECサイトなどでよく見られる「この商品を購入した人は、こちらの商品にも興味を持っています」といったレコメンド表示も、クロスセルの一種です。
◉-3、購入しやすさを高めて客単価を引き上げる施策
魅力的な商品やサービスを提供していても、顧客が「買いにくい」と感じるようであれば、客単価は伸び悩んでしまいます。
購買体験の中でストレスや不便さを感じさせないことは、結果として購入点数や売上の増加につながります。
◉-3-1、決済の選択肢を増やす
現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など、幅広い決済方法に対応することで、顧客が感じる購入時のハードルを大きく下げることができます。
特に近年はキャッシュレス決済を好む顧客が増加しており、対応していない場合は「買いたくても買えない」状況を招き、貴重な購買機会を失う可能性があります。
◉-4、価値の訴求によって商品の魅力を高め、客単価を引き上げる施策
顧客が高価格商品を購入するかどうかは、その商品に対する「納得感」や「共感」が得られるかどうかに左右されます。
価格が高い商品ほど、「なぜこの値段なのか」「価格に見合う価値があるのか」をきちんと伝える必要があります。
そのためには、商品そのもののスペックや特徴だけでなく、背景にあるストーリーやブランドの想いを、ターゲット顧客に合ったメディアでわかりやすく伝えることが重要です。
◉-4-1、SNSやホームページで商品の魅力をわかりやすく伝える
SNSや公式サイトでは、商品の魅力やこだわりをビジュアルでわかりやすく伝えることができます。
特にInstagramやX(旧Twitter)などのプラットフォームでは、写真や動画を活用して、使用シーンやビフォー・アフターの変化などを視覚的に訴求することが可能です。
「これならこの価格でも納得」と思ってもらうことができれば、購入につながる可能性が高くなります。
▶︎SNS運用のやり方については、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】もあわせて参考にしてください。
◉-4-2、書籍の制作・配布で商品の魅力や想いを届ける
SNSや公式サイトでは伝えきれない深い世界観やブランドの想いを伝える手段として効果的なのが、書籍による価値の訴求です。
書籍は、社会的信頼性の高いメディアであることに加えて、丁寧に作られた印象を与えるため、顧客との信頼関係の構築に役立ちます。
また、書籍は来店特典や購入特典としても活用できるため、商品やサービスのブランドイメージの構築と販売促進の両方に効果的です。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。
◉書籍出版によって客単価向上を実現した事例

実際に書籍を出版して客単価の向上を実現した事例を2つ紹介します。
| ・事例1:書籍出版で信頼を獲得し、法人保険の大型契約を実現した保険代理店の成功事例 ・事例2:書籍出版を通じて専門性を可視化し、高単価案件の獲得に成功した公認会計士の事例 |
以下で、それぞれについて見ていきましょう。
◉-1、事例1:書籍出版で信頼を獲得し、法人保険の大型契約を実現した保険代理店の成功事例
法人保険を専門に取り扱う保険代理店の経営者は、業界の現状や課題を明らかにしながら、自社で実践している「一律報酬型」の給与制度が人材育成と業績向上に有効であるという持論をまとめた書籍を出版しました。
この書籍は業界内で大きな注目を集め、多くの反響を獲得。
出版をきっかけに顧客からの問い合わせが増加し、保険に関する相談だけでなく、経営理念や組織づくりに関する助言を求められるまでになりました。
企業との信頼関係が深まり、自社の価値観やスタンスが明確に伝わったことで、顧客視点に立った本質的な保険提案が可能となり、結果として法人保険の大型契約の受注を実現しました。
1社あたりの契約単価が上昇し、全体の売上拡大にもつながる成果を上げています。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、事例2:書籍出版を通じて専門性を可視化し、高単価案件の獲得に成功した公認会計士の事例
ある会計事務所の代表を務める公認会計士は、自身の豊富な海外勤務経験をもとに「海外ビジネス展開におけるリスク管理とマネジメント戦略」に関する専門書を出版しました。
この出版によって、「海外進出を支援できる高い専門性を持つ会計士」という専門家としての立場が確立され、顧客にもその実力が具体的に伝わるようになりました。
その結果、主力業務である海外進出企業向けの監査支援やアドバイザリー業務で、これまで見られたような過度な価格交渉に応じる必要がなくなったといいます。
提案段階からプランニングを一任されるケースが増え、業務そのものの価値が適切に評価されるように。
自然と客単価も向上し、事務所全体の売上アップにもつながっています。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉【まとめ】価値訴求による客単価向上を実現するために「書籍出版」を活用しよう!
この記事では、客単価の定義や計算方法をはじめ、分析によって得られるメリットや単価を引き上げるための具体的な施策、さらには成功事例までを幅広く紹介しました。
売上の向上を目指す経営者やマーケティング担当者にとって、「客単価」は単なる数値ではなく、顧客理解・商品戦略・価値訴求のすべてにおいて起点となる重要な指標です。
きちんと分析を行うことで、感覚に頼らない論理的で持続的な売上成長を実現することができるでしょう。
そして近年、客単価向上の手段として注目されているのが、「書籍出版」によるマーケティングです。
書籍は、商品の魅力や特長を伝えるだけでなく、企業の歴史や開発の裏側、ブランドに込めた想いなど、より深い価値を物語として伝えることができます。
さらに、流通を通じた新規顧客との接点づくりや、既存顧客との信頼関係の強化にもつながる有効な施策です。
株式会社フォーウェイでは、「ブックマーケティングサービス」を提供しており、書籍出版を通じて企業の価値や想いを発信するサポートをしています。
客単価を高める施策の一つとして、ぜひ「書籍出版」をご検討ください。
この記事をご覧になったあなたにおすすめのコラム
-
ファンマーケティングとは?企業の成功...
2024.10.21Branding, Marketing
-
コンテンツマーケティングの失敗を招くN...
2021.03.09SEO
-
SEO対策とは? 効果的な戦略の組み立て...
2025.05.19Marketing, SEO
-
人材獲得につながる採用パンフレットを...
2024.10.09Branding, Marketing
-
売れる効果的な商品・サービスパンフレ...
2024.10.11Marketing
-
企業として信頼性を高めるための方法と...
2024.11.25Branding, Marketing