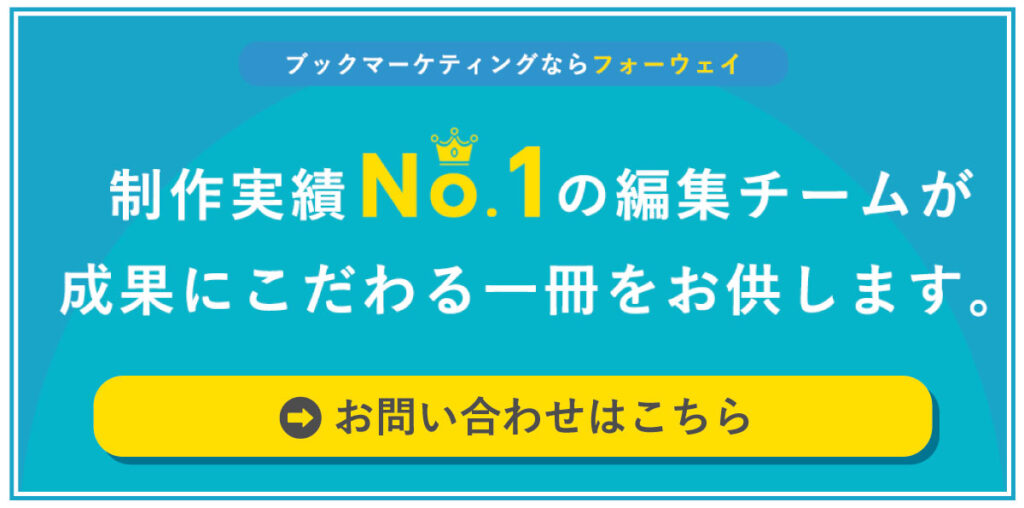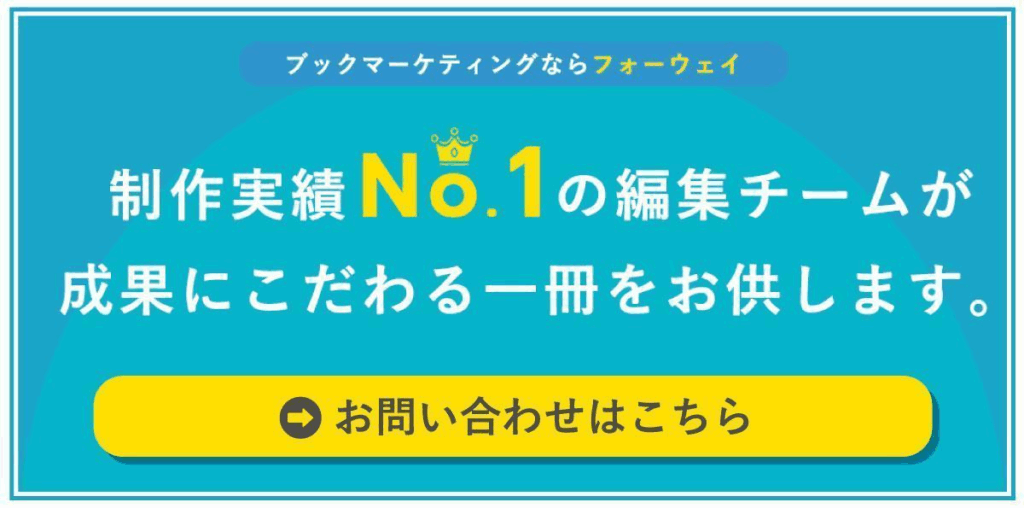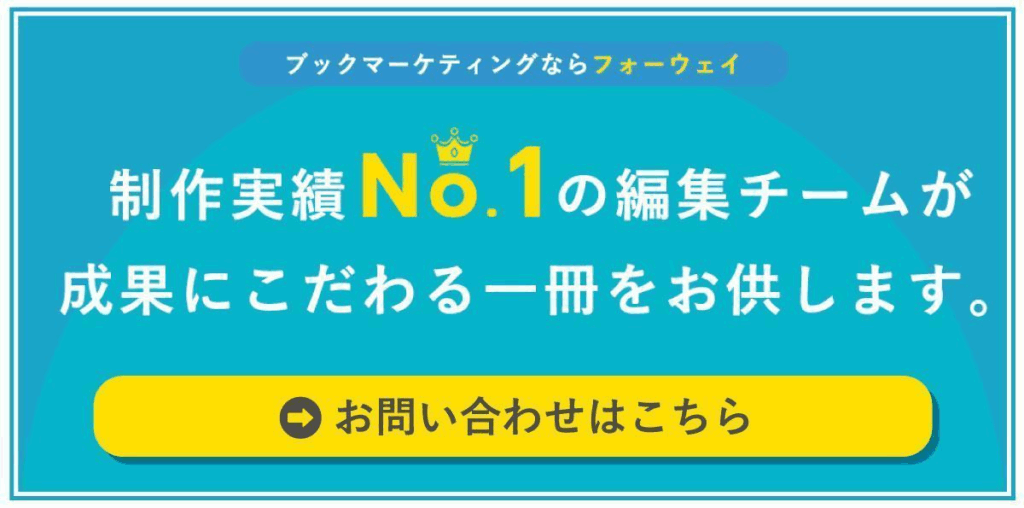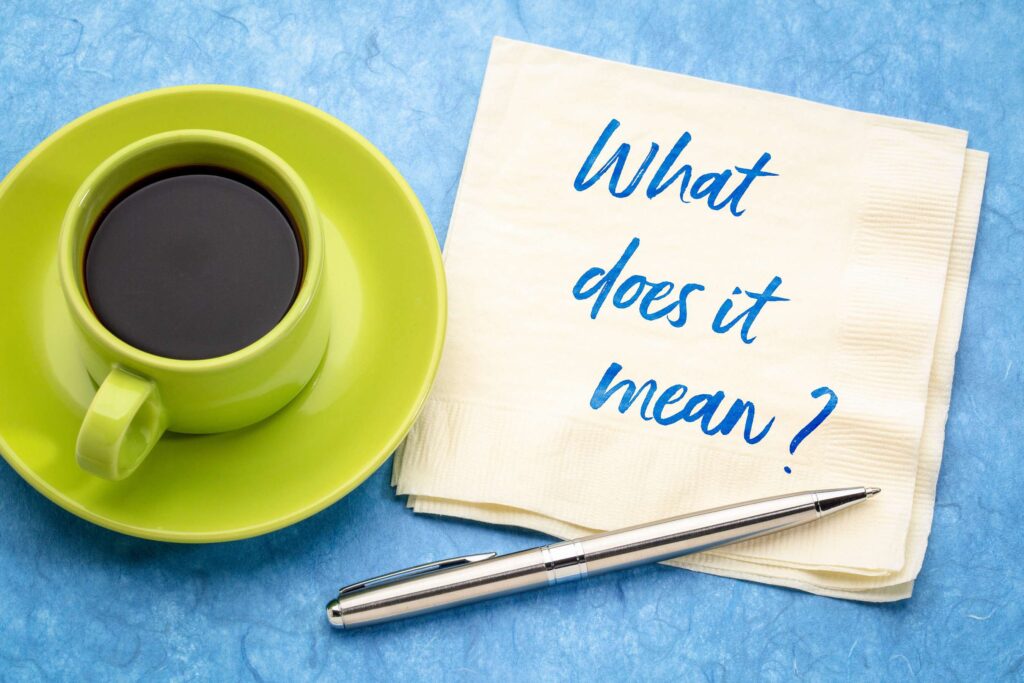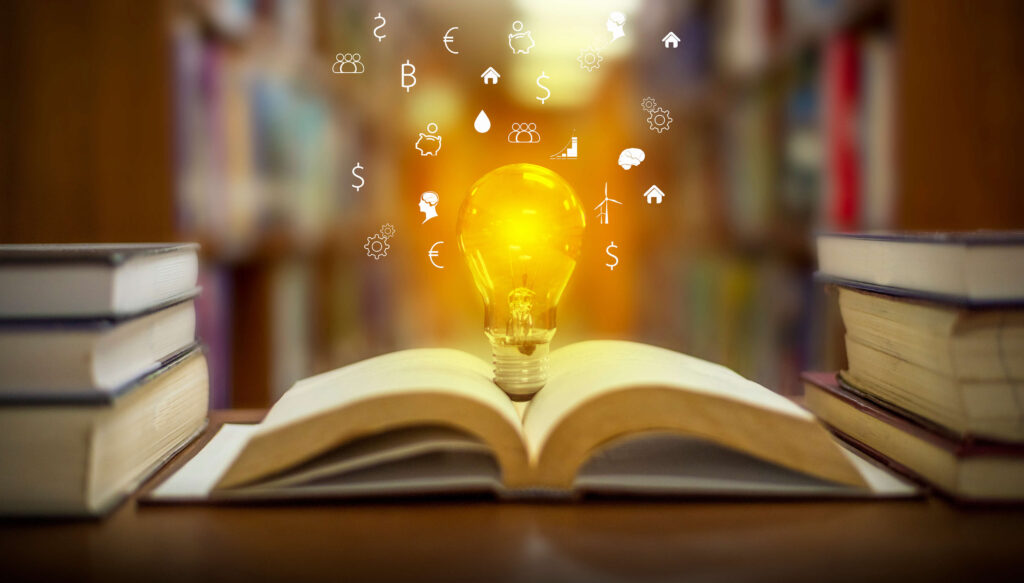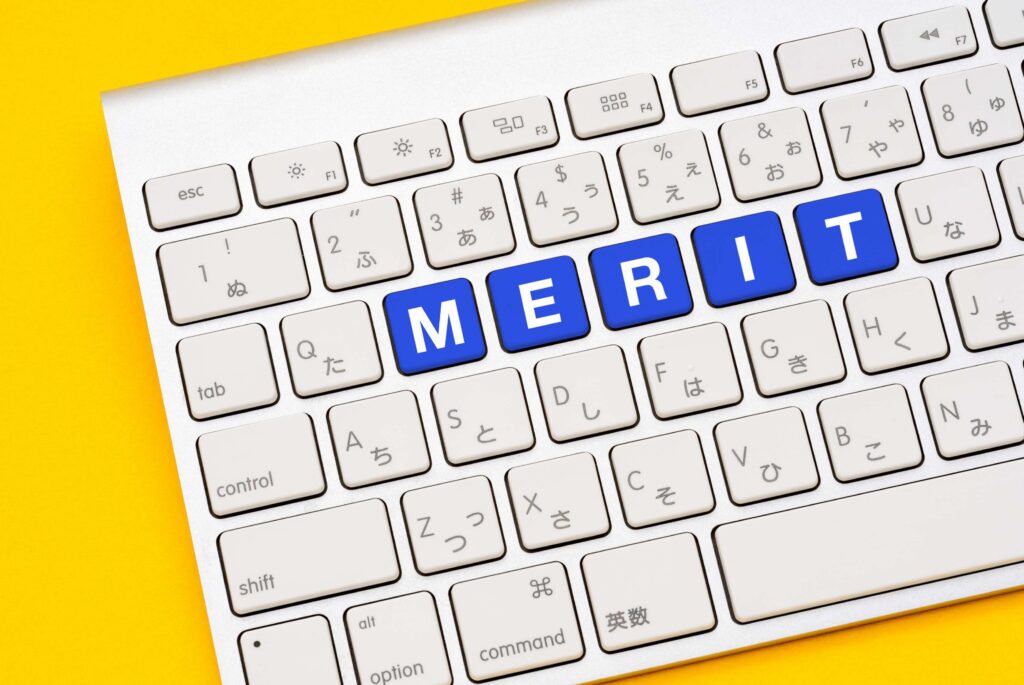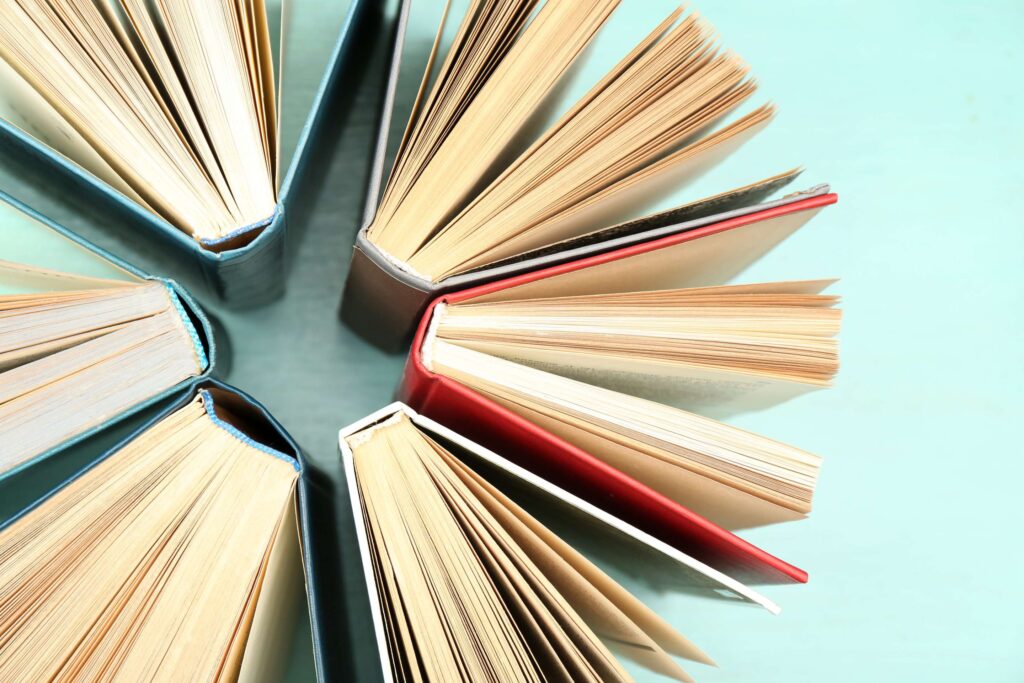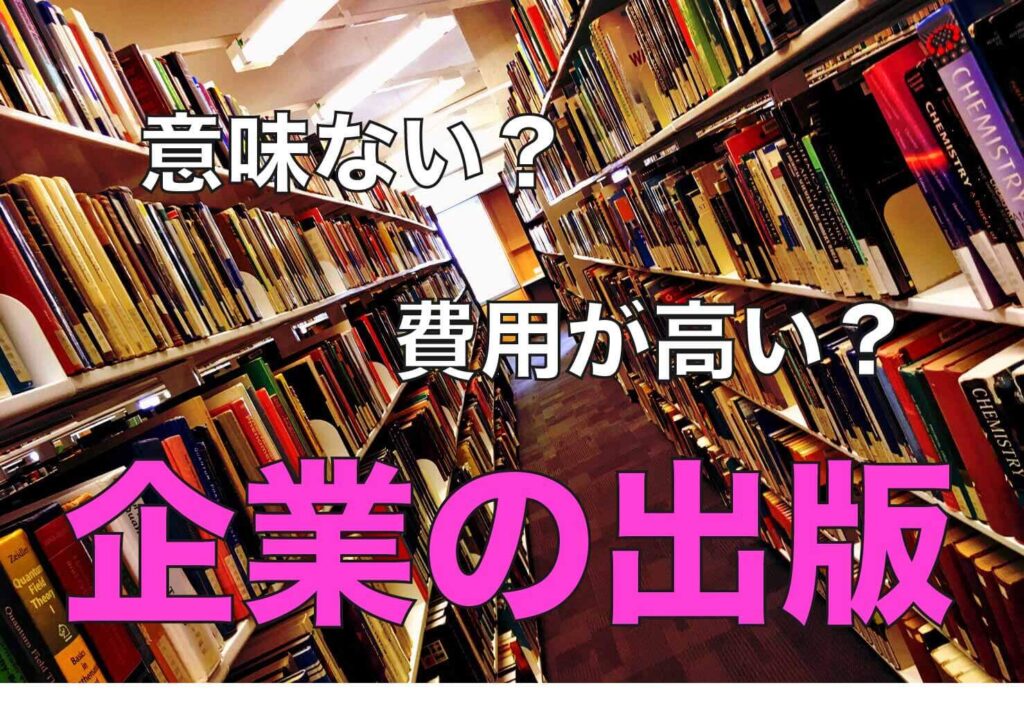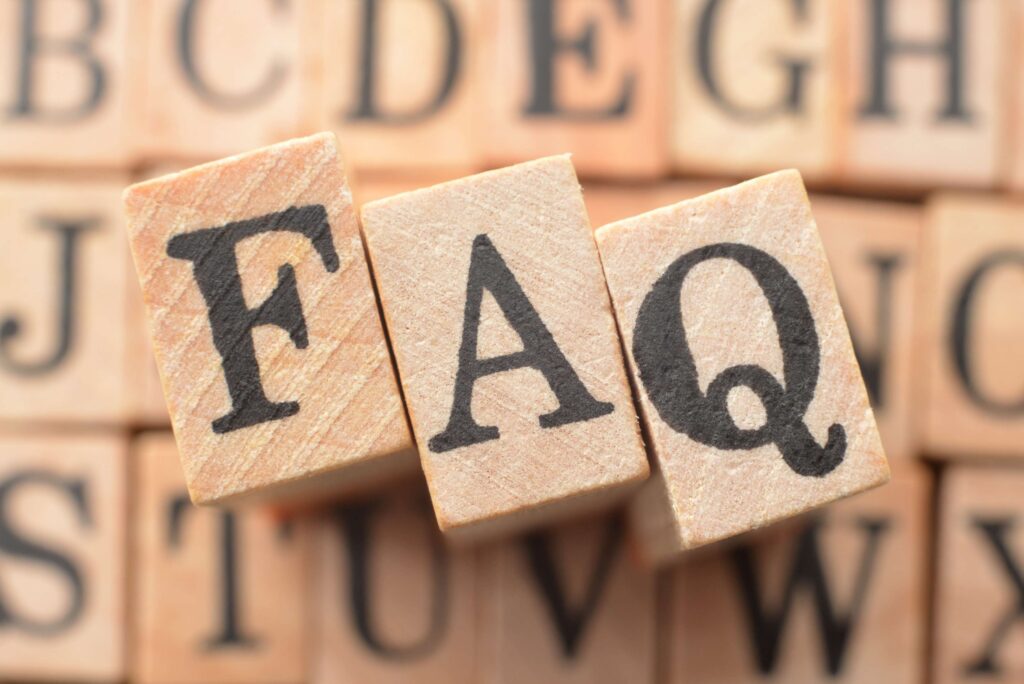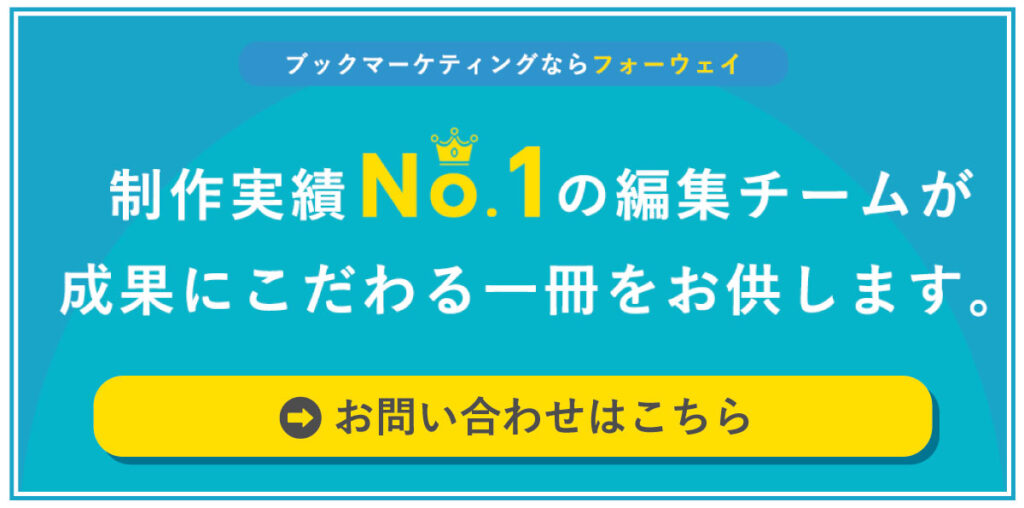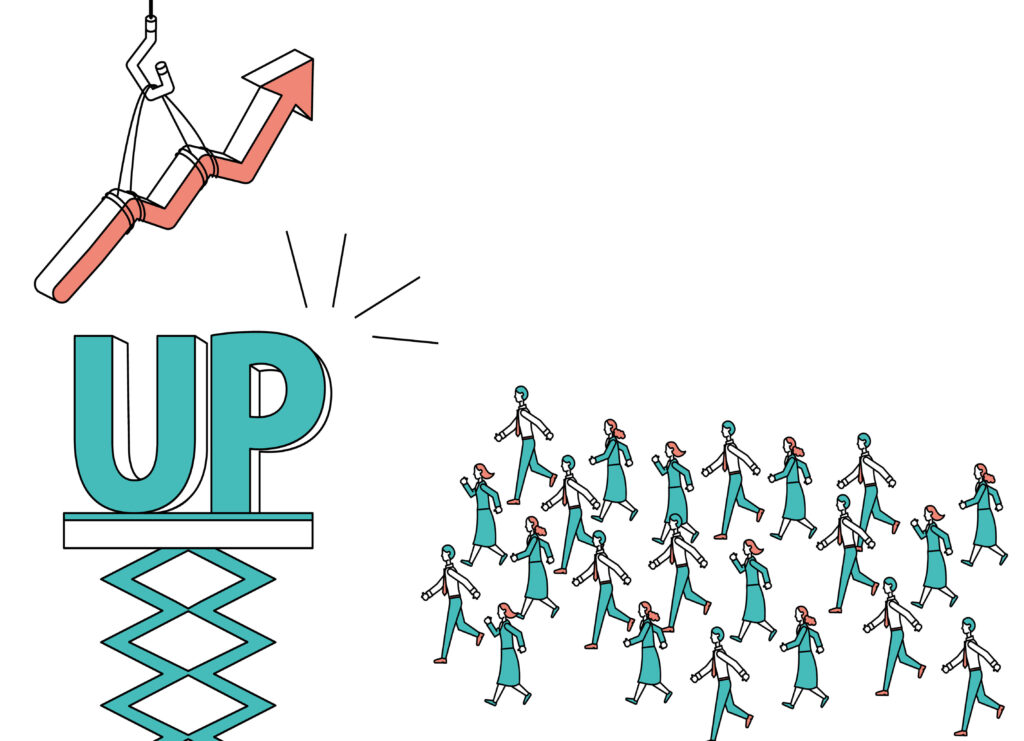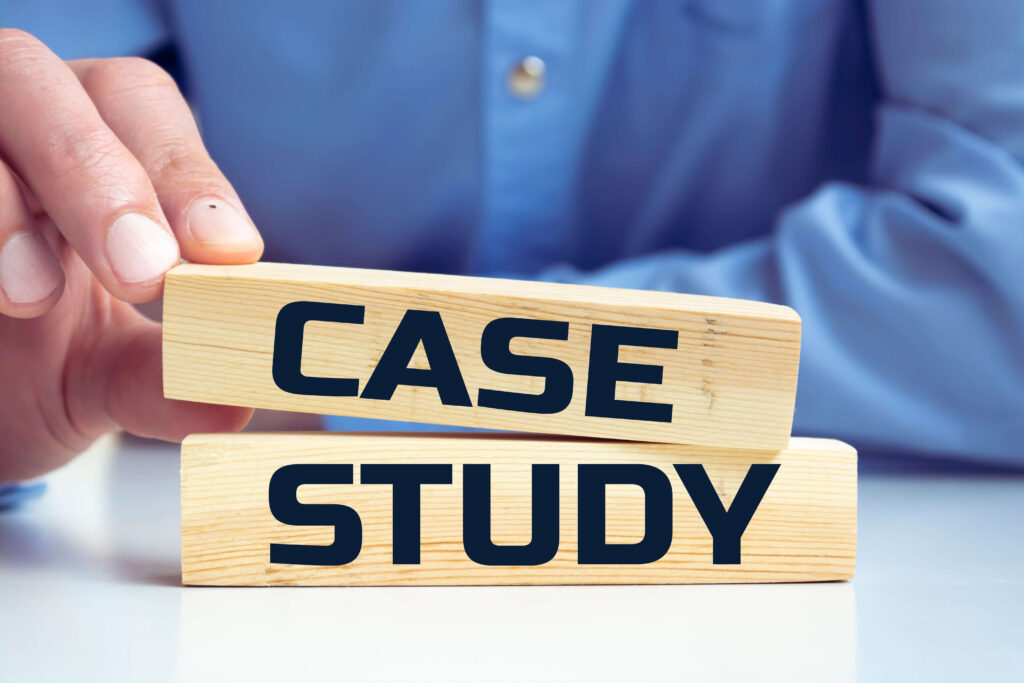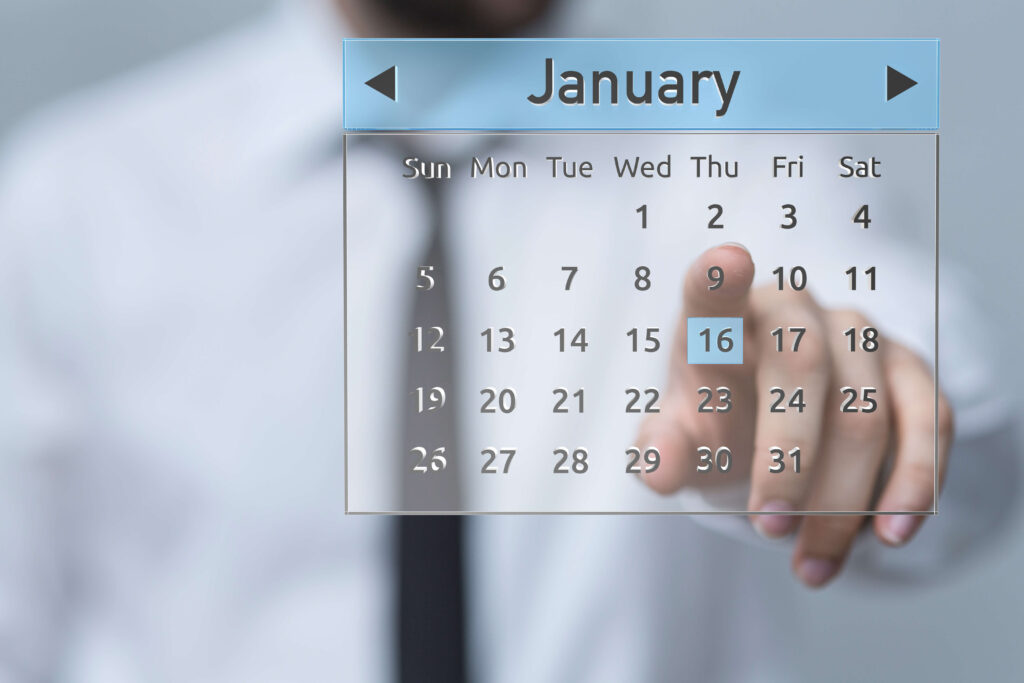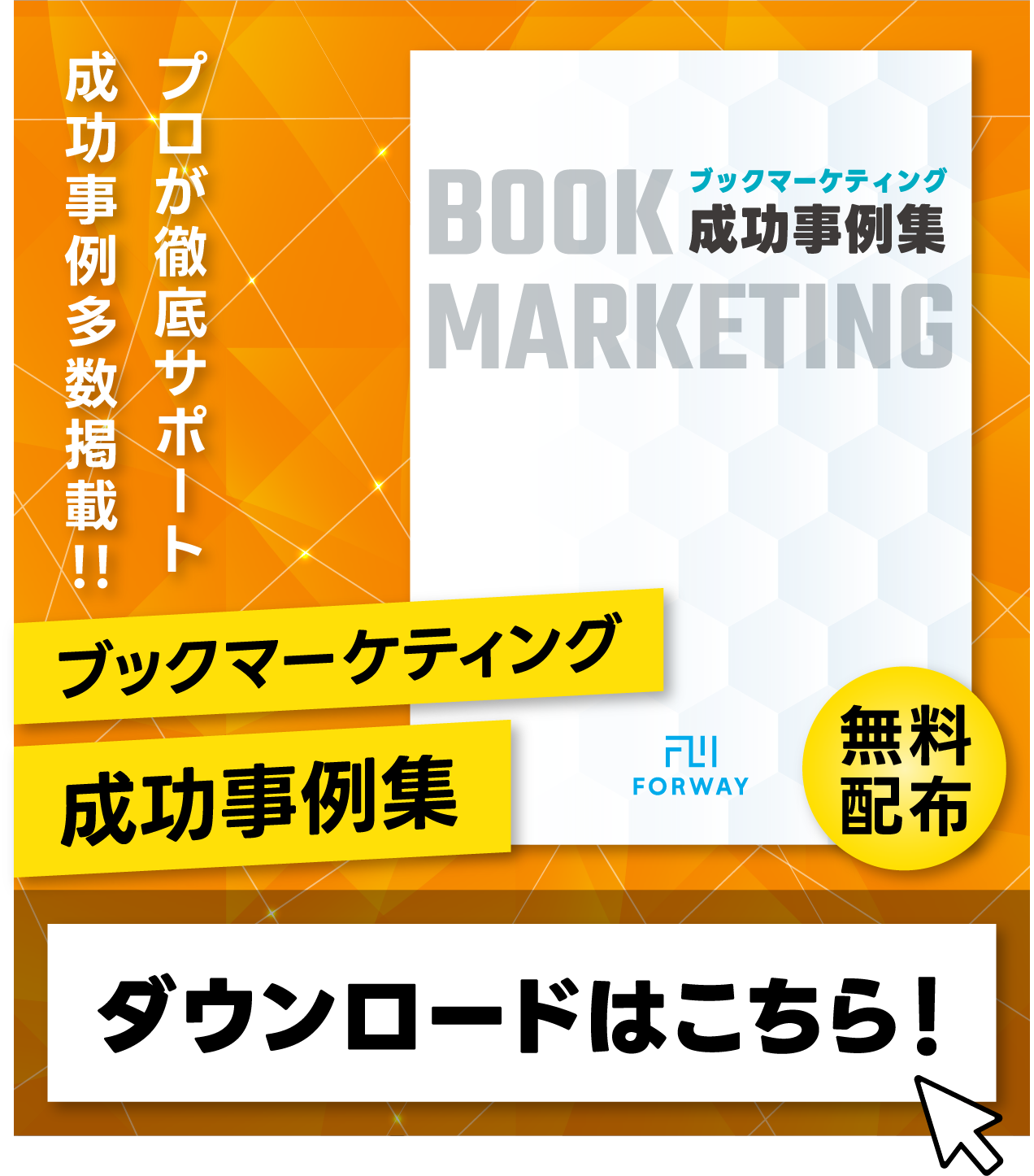「自社のWebサイトに集客したい」「サービスや商品の認知度を上げたい」と考えている企業担当者の方は多いのではないでしょうか。
インターネットが普及した現代では、誰もが簡単に情報へアクセスできるようになり、従来のような一方的な広告だけでは顧客の心を動かすのが難しくなっています。
そこで、多くの企業が注目しているのが「コンテンツマーケティング」です。
言葉にすると簡単なようですが、コンテンツマーケティングを実践したものの成果が出ないという企業も少なくありません。
そこで今回は、コンテンツマーケティングの手法や効果を発揮するための戦略について解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
コンテンツマーケティングとは

コンテンツマーケティングとは、コンテンツを活用したマーケティングの手法を指します。
ここでいうコンテンツは、顧客や見込み顧客にとって有益で価値のある情報であることが重要です。
顧客が興味を持つコンテンツの発信・提供によって信頼関係を築き、最終的に自社の商品やサービスの購入・利用につなげます。
コンテンツマーケティングでは、広告のように積極的な売り込みは行いません。
読者や視聴者のニーズを満たしたり、課題を解決するための情報を提供し続けたりすることで、認知度向上や見込み顧客(リード)獲得といった効果を狙います。
◉-1、コンテンツマーケティングとコンテンツSEOは違う?
Webを活用したマーケティング手法として、メジャーになりつつあるコンテンツマーケティング。
しかし、コンテンツSEOと混同されているケースも散見されます。
コンテンツSEOとは、ターゲット読者が求める情報をコンテンツとして提供し続け、Googleなどの検索結果で上位を目指す手法のことです。
コンテンツマーケティングの一種ですが、イコールではありません。
コンテンツSEOは検索エンジン(SEO)対策の方法であり、あくまで検索結果の上位表示を目指してコンテンツを提供することが目的です。
一方、コンテンツマーケティングはさらに広い意味で用います。
広告以外の手段で有益な情報を発信し続け、見込み顧客に興味を持ってもらい、行動に移してもらうまでを戦略的に設計するのがコンテンツマーケティングです。
簡単にいうと、顧客側から興味を持ってこちら側に寄ってくるインバウンドマーケティングの仕組みづくりをコンテンツマーケティングといいます。
コンテンツマーケティングが重要視されるようになった背景

コンテンツマーケティングが重要視されるようになった背景として、以下の3つが挙げられます。
・売り込み型マーケティングの効果が下がった
・消費者の購買行動が変化した
・アルゴリズムが変化した |
それぞれ詳しく解説します。
◉-1、売り込み型マーケティングの効果が下がった
従来のマーケティングでは、テレビやラジオのCM、インターネットなどの広告で商品やサービスを知ってもらう売り込み型(プッシュ型)のマーケティングが一般的でした。
売り込み型のマーケティングは潜在層にも知ってもらえる可能性が高く、即効性も期待できます。
しかしその一方で、企業から一方的に押しつけられる情報になりやすく、受け手である消費者にとっては広告が不快に感じられるケースも少なくありません。
また、「そもそも広告を見ない」という消費者も増えており、売り込み型マーケティングの効果は薄れてきています。
さらに、プッシュ型手法の代表格であるアウトバウンドのテレアポも、難易度が上がり効果が出にくくなっています。
誰もが手軽に始められる一方で、成果を出すには高いスキルが求められるためです。
特に、コロナ禍を経てオンラインでの打ち合わせや在宅ワークが普及したことで担当者と直接つながりにくくなり、これまで以上に効果を出すのが難しくなっています。
◉-2、消費者の購買行動が変化した
インターネットが普及したことで、誰もがほしい情報を自分で調べられるようになりました。
今では、気になることは自分で検索し、比較・検討したうえで選択することが当たり前になっています。
そのため、自社の製品やサービスが選ばれるためには、ただ売り込むだけでなく、消費者にとって役立つ情報を提供することが重要になりました。
逆にいえば、良質なコンテンツを提供することで、これまで自社の製品やサービスを知らなかった消費者にも認知されるきっかけになります。
たとえば「就職祝いに贈る品物」で悩んでいる消費者が検索し、喜ばれる贈り物やマナーを紹介した記事に辿り着いたとします。
その情報を参考にして最適な品物を選び、「相手にも喜んでもらえた」「お祝いにまつわるマナーや知識も得られた」という体験ができたら、自然とその企業に好感を抱き、ファンになってくれる可能性が高まるでしょう。
◉-3、アルゴリズムが変化した
検索エンジンやSNSのアルゴリズムは従来に比べ、価値のあるコンテンツを評価するようになりました。
そのため、情報が薄いコンテンツや専門性が低いコンテンツは評価されにくく、Webページの上位に表示されません。
検索エンジンで露出を増やすためには、良質なコンテンツの作成が必要不可欠です。
信頼できる情報であるのはもちろん、専門性や独自性といった観点も踏まえ、質の高いコンテンツを提供することが重要です。
コンテンツマーケティング手法は主に2タイプ

コンテンツマーケティングの手法は、以下の2つのタイプに分けられます。
それぞれのタイプにはさらに細かい手法があるため、以下で各コンテンツの特徴を紹介します。
◉-1、ストック型
ストック型のコンテンツは一度制作すれば長期間にわたって価値が落ちず、時間が経っても需要が続くコンテンツのことを指します。
季節やトレンドなどに左右されることなく、安定したアクセスを見込めるのがメリットです。
こうしたコンテンツを継続的に蓄積していくことで、自社のWebサイトやアカウントに辿り着く消費者を増やせるでしょう。
具体的には、次のようなコンテンツがストック型にあたります。
| ストック型コンテンツ | 特徴 |
| ブログ記事 | ・オウンドメディアなどで自社の商品・サービスを紹介できる・ハウツー記事など役立つ情報を発信できる・主に長めのテキストで構成され、読み応えのある記事を蓄積すれば継続的なアクセスが期待できる |
| SNS(文字・画像・動画投稿コンテンツ) | ・InstagramやX(旧Twitter)などで、商品の使い方や企業紹介といった情報を発信する・時間が経っても役立つ内容は検索で見つけられやすく、ストック型として機能する |
| 動画コンテンツ | ・YouTubeやTikTokなどで配信される動画・テキストだけでは伝わりにくい情報を視覚的にわかりやすく届けられ、訴求力が高い |
| 音声コンテンツ | ・ラジオやポッドキャストなど音声のみの配信・ノウハウや課題解決のヒントをじっくり発信できる・通勤や作業中など「ながら利用」ができる点が魅力 |
| ホワイトペーパー | ・商品・サービスの概要や調査結果をまとめた資料・サイトからダウンロードでき、顧客も比較的気軽に入手しやすい |
| インフォグラフィック | ・データや調査結果をグラフやイラストでわかりやすくまとめたもの・一目で要点を伝えやすく、SNSなどでも拡散されやすい |
| 書籍 | ・出版には時間がかかるが、信頼性が高いコンテンツ・必要なときにあとから見返してもらいやすい・資料や情報源として長期的に活用できる |
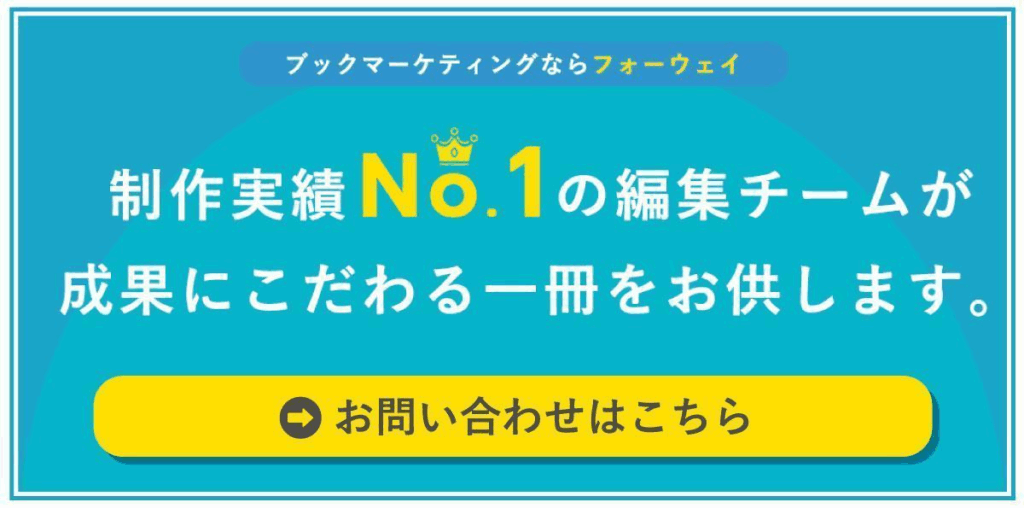
◉-2、フロー型
フロー型コンテンツは鮮度やタイミングが重視され、拡散されやすいのが特徴です。
そのため、新商品や新サービスの告知、キャンペーンなど「今すぐユーザーに知ってもらいたい情報」を伝えるのに適しています。
ただし、フロー型コンテンツは短期間で効果が出やすい反面、時間が経過すると発信した情報が埋もれてしまい、価値が薄れやすいのがデメリットです。
代表的なフロー型コンテンツとして、以下が挙げられます。
| フロー型コンテンツ | 詳細 |
| SNS(タイムライン消費型のコンテンツ) | ・SNSの中でもニュースやトレンド、キャンペーン告知、日常の出来事などをリアルタイムで発信・タイムライン投稿や、24時間で消えるストーリーズ機能が該当する |
| プレスリリース | ・新商品の発売やイベントの開催などをメディアを通じて発信する・記事に引用される可能性が高く、普段接点のない層にも届きやすい |
| メールマガジン | ・登録している既存顧客に直接アプローチできる・登録者の属性をもとに、特定のユーザーに合わせて配信可能 |
| イベント・セミナー | ・自社に関心を持つユーザーを集めやすく、新規層にもアプローチできる・ウェビナーのようにオンライン開催なら、録画を残して動画コンテンツとして再利用できる |
コンテンツマーケティングに取り組むメリット

コンテンツマーケティングを実践することで、以下のようなメリットが得られます。
・潜在顧客のリード獲得
・自社の認知度向上とブランディングの実現
・コンテンツの資産化
・将来的な広告費の削減 |
4つのメリットについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、潜在顧客のリード獲得
ユーザーが欲する情報を提供し続けることで、自社に興味を持ってもらうきっかけができます。
興味を持ったユーザーがホワイトペーパーをダウンロードする等のアクションを起こす際、連絡先など必要事項の記入を行います。
これが「リードの獲得」です。
リードを獲得できると、その連絡先に対して自社のメルマガを配信したり、電話やメールでキャンペーン情報を伝えるなど、具体的な営業活動につなげることができます。
ほかにも、コンテンツ発信をきっかけとしたメルマガの登録などもリード獲得の手法として考えられます。
◉-2、自社の認知度向上とブランディングの実現
ユーザーにとって有益な情報を提供し続ければ、SEO順位で上位獲得ができ、自社の認知度が上がることが期待できます。
有益な情報であれば、ユーザーによって拡散されていく可能性があるので、自ずと認知度が上がっていくのです。
さらに発信するコンテンツが企業のブランドイメージそのものになるため、自社の事業領域における専門家としてのブランディング効果が期待できます。
◉-3、コンテンツの資産化
コンテンツには情報の新鮮さが求められるフロー型コンテンツと、時間が経過しても価値が失われにくいストック型コンテンツがあります。
ストック型コンテンツは、フロー型のように短期間で大きく拡散されることは少ないものの、公開し続ける限り安定した集客効果を期待できるのが特徴です。
有益なコンテンツは既存顧客との関係強化に役立つだけでなく、検索から流入したユーザーが新規顧客になる可能性もあります。
蓄積されたコンテンツは自社にとって資産となり、さらにアクセス数を伸ばすことにもつながります。
◉-4、将来的な広告費の削減
自社のサービスや商品を購入してもらう手っ取り早い方法は、広告です。ただし、広告は成果が期待できますが、打ち続ける必要があり、結果的に広告費がかさみます。
しかし、コンテンツマーケティングで発信した情報は継続的に費用を投じなくてもネット上に残り続け、長期的な広告費の削減になります。
顧客がファン化して継続的に自社サービスを利用してくれれば、費用対効果が非常に高い施策となるのです。
【9ステップ】コンテンツマーケティングの戦略設計の仕方

コンテンツマーケティングの失敗でよくあるのが、目的設定や準備も行わずにいきなりコンテンツを作りはじめてしまうケースです。
しかし、まずは成果を得るために戦略を練る必要があります。
具体的には、以下のステップに沿って進めていきます。
・ステップ1:ターゲットを設定する
・ステップ2:カスタマージャーニーを作成する
・ステップ3:目的を明確化する
・ステップ4:コンテンツマーケティング手法を決める
・ステップ5:KGI・KPIを設定する
・ステップ6:責任者とメンバーを決定する
・ステップ7:スケジュールとコンテンツテーマを確定する
・ステップ8:コンテンツを制作する
・ステップ9:結果を測定してPDCAを回す |
順を追って詳しく解説します。
◉-1、ステップ1:ターゲットを設定する
ターゲットがぶれてしまうと、制作するコンテンツもテーマが不明瞭なものが増えてしまい、結果的にはコンテンツマーケティング自体が徒労に終わる可能性が高まってしまいます。
その中で、ターゲット設定のコツとしては「これまでに集客できていない理想の顧客像」を分析のうえ、設定することです。
マーケティング用語でいう「ペルソナ」を設計します。
自社の顧客になりうる人物像を想像し、言語化することが重要です。
ペルソナ設計では、「デモグラフィック」と呼ばれる人口統計の属性データを使います。
「住所」「性別」「年齢」「職業」「所得(年収)」「世帯規模」「学歴」など、自社サービスにマッチするよう細かく想定するのです。
そのうえで、求めるユーザーの「ライフスタイルの送り方」「思考の傾向」「特有の悩みやストレス」「願望」を設定し、明確に文章で言語化することでペルソナが完成します。
◉-2、ステップ2:カスタマージャーニーを作成する
ターゲットが設定できたら、カスタマージャーニーを作成します。
カスタマージャーニーとは、ターゲットが自社の商品やサービスを認知して購入に至り、その後も継続して利用してくれるまでのプロセスを可視化したものです。
カスタマージャーニーの作成では、認知・興味・比較検討・購入・継続利用といったフェーズごとに顧客の思考や感情、行動を洗い出します。
たとえば、「認知」のフェーズでは、自社の商品やサービスを知るきっかけがSNSなのか、動画コンテンツなのかなどが洗い出す要素の一つです。
顧客の志向や行動などを理解しておくことで、施策を立てやすくなります。
◉-3、ステップ3:目的を明確化する
カスタマージャーニーを作成したら、次に行うべきはコンテンツマーケティングの目的を明確にすることです。
まずは解決したい課題を整理し、そのうえで以下のような目的を具体的に設定します。
・CV(コンバージョン)の獲得
・見込み度の高いリードの獲得
・自社の認知度向上やイメージアップ
・採用活動につなげるためのブランディング |
さらに、CVやリードの獲得など、自社サービスや商品の購買につなげたい場合、「どのサービスおよび商品を誰に届けたいのか」を設定する必要があります。
目的とマーケティングの着地点となるサービスを明確化し、社内で共通認識を持って取り組むことが大切です。
◉-4、ステップ4:コンテンツマーケティング手法を決める
ターゲットやカスタマージャーニー、目的が明確になったら、次はどの媒体で、どのようなコンテンツマーケティングを実施するのかを決めていきます。
たとえば、Z世代や20代前半の層であれば、動画やSNSを活用したコンテンツが効果的です。
一方で、BtoB企業を対象とする場合は、サービス導入事例をまとめたホワイトペーパーや、専門的なノウハウを整理した書籍などが適しています。
ターゲットに合わせて媒体と手法を選択することで、より効果的なコンテンツマーケティングが可能になります。
◉-5、ステップ5:KGI・KPIを設定する
マーケティングでは、最終的な目標を示すKGIと、その進捗を測る中間指標であるKPIを決めます。
具体的な指標は、月間リード数や記事PV、コンバージョン率などです。
たとえば「最終的な成約数30件」をKGIとするなら、その達成に向けたKPIとして「月間リード数100件」を目標に設定するといった形です。
◉-6、ステップ6:責任者とメンバーを決定する
コンテンツマーケティングは成果を安定して出すまで時間がかかります。
したがって、コンテンツマーケティングのプロジェクトに根気よく情熱を持って取り組んでくれる、理解ある責任者を決定する必要があります。
コンテンツマーケティングでは、成果につながらない時期というのが訪れます。
常にトライアンドエラーを繰り返しながら、「成果につながらないコンテンツはどのように改善していくのか」といった意識が重要です。
責任感と覚悟を持って意思決定を行える責任者を任命しましょう。
そして、責任者を決めたら、次はともにプロジェクトに取り組むメンバーの招集をします。
会社としてコンテンツマーケティングを実施する目的と意義を理解して、そこに共感して取り組んでくれるメンバーを選びましょう。
ありがちな失敗としては、次のようなメンバーを集めてしまうパターンがあります。
・文章を書くのが好きなメンバー
・過去にライティング経験があるメンバー
・通常業務の合間に手伝ってくれそうなメンバー |
コンテンツマーケティングにおけるSEOライティングには、必ずしも紙媒体などでライティングに従事した経験は必要ありません。
また、片手間ではそのうち手が回らなくなって放置されてしまうのがオチです。
コンテンツの品質を保つには、あくまでビジョンと目的に共感してくれるメンバーを集めなければなりません。
▶︎コンテンツマーケティングの失敗要因については、関連記事【コンテンツマーケティングの失敗を招くNG行動6】もあわせて参考にしてください。
◉-7、ステップ7:スケジュールとコンテンツテーマを確定する
責任者とメンバーが決まったら「スケジュール」と「コンテンツテーマ」を確定させます。
コンテンツマーケティングは、一朝一夕で成果や効果が出にくい施策のため、最低でも1年間のスケジュール計画を立てる必要があります。
その際、決めなければならない要素としては以下の通りです。
・アクセスやCVといった1年後の数値目標
・具体的なコンテンツの内容と制作担当者、制作の締め切り |
コンテンツマーケティングによって、広告に頼らない価値ある基盤を1年後に作り上げるために、詳細なタスクを整理して、「誰が」「いつまでに」「どんなコンテンツ」を制作するのかを計画立てましょう。
目標達成に向けて、たとえば3か月目までは認知獲得や商品理解を促すコンテンツを制作し、6か月目以降は少しずつCVにつなげていくために、「購入欲求」をかき立てるコンテンツを制作する、といった計画です。
さらに、上記スケジュールの組み立てができたら、具体的なコンテンツの確定をしていきましょう。
目的や顧客がどのような情報を欲しているかを考え、テーマを選びます。
◉-8、ステップ8:コンテンツを制作する
コンテンツ制作では、マーケティングの目的を踏まえ、設定したターゲットやカスタマージャーニーに沿った内容を設計することが重要です。
ユーザーの関心を引きつけるためには、有益な情報を提供するだけでなく、デザイン面にも配慮する必要があります。
レイアウトや配色、フォントのサイズ、種類など、見た目の印象も影響を与えます。
また、制作したコンテンツには、自社サイトやサービスページへスムーズに移動できる導線を用意しておくことで、売上や商談といった成果につながりやすくなります。
◉-9、ステップ9:結果を測定してPDCAを回す
コンテンツは作成して終わりではなく、その後の効果測定と改善が欠かせません。
実際には、せっかく制作したコンテンツが期待した成果につながらない場合もあります。
また、新しい情報が次々に発信されるなかで、自社コンテンツの検索順位が下がってしまうことも考えられます。
そのため、あらかじめ設定したKGI・KPIを基準に、どの程度効果が出ているのかを定期的に確認しましょう。
そこで明らかになった課題や改善点を次の施策に反映させることで、PDCAを回しながら成果を高めていくことができます。
コンテンツマーケティングを成功させるにはターゲットに合わせた手法選びが重要!

コンテンツマーケティングは、広告のように企業側から積極的にアプローチする「攻めのマーケティング」ではなく、ターゲットが集まりやすい媒体に魅力的なコンテンツを配置し、自然に関心を持ってもらう「待ちのマーケティング」です。
そのため、ターゲットが集まりにくい媒体にコンテンツを置いても効果はありません。
成功のポイントは、ターゲットが集まる場所を見極め、そのうえで効果的な手法を選ぶことです。
たとえば、企業を対象とする場合、企業の課題解決につながる情報や専門性を示す書籍・ホワイトペーパー・プレスリリースといったコンテンツが有効です。
一方で、決裁者層へのアプローチや潜在顧客との関係構築においては、SNSやブログも重要な役割を果たします。
特に、自社の専門性を発信したり、企業のブランドイメージを伝えたりするうえで効果を発揮します。
このように、コンテンツマーケティングでは「ターゲットに最適化した手法の選択」が成功を左右するのです。
◉-1、富裕層や企業などがターゲットの場合は書籍でのコンテンツマーケティングがおすすめ!
現代はインターネットを通じて膨大な情報を得られる一方で、その中には根拠があいまいで信頼性に欠けるものも少なくありません。
一方、出版社から刊行された書籍は「現物」として手元に残るだけでなく、Web記事やSNS投稿と比べてテーマを深く掘り下げ、体系的にまとめられています。
そのため、専門性や権威性をアピールでき、読者からの信頼やブランド価値の向上につなげやすい点が魅力です。
また、出版後には出版記念イベントやセミナーの開催、SNSやオウンドメディアでの紹介といった形で二次活用でき、マーケティング効果をさらに広げられます。
▶︎企業出版の詳細については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

◉コンテンツマーケティングの成功事例
コンテンツマーケティングとして書籍を出版し、成功した事例として3つ挙げます。
・書籍でブランディングと見込み客獲得を実現した事例
・出版でファン化が加速し、LTV向上につながった事例
・発信に悩む食品メーカーが書籍によって差別化に成功した事例 |
それぞれの事例を以下で紹介します。
◉-1、書籍でブランディングと見込み客獲得を実現した事例
保険代理店向けのコンサルティング事業を立ち上げた経営者は、新規開拓の有効な手段がなく、信頼性を高めるブランディング施策を模索していました。
そこで選んだのが企業出版。
フルコミッション(成果報酬)が当たり前の保険業界において、「月額給与制の一律報酬型」で業績を伸ばした独自のノウハウを体系化し、書籍として発信しました。
出版後は大きな反響を呼び、わずか発売2週間で即重版が決定。
Amazonでも一時的に欠品するほどの人気となりました。
また、出版記念セミナーには60名が参加し、その場で20名と商談、複数件のコンサル契約へとつながっています。
さらに、大手生命保険会社の支社長や部課長クラスにも読まれ、講演依頼が継続的に舞い込むように。
加えて、書籍が経営者同士で紹介される動線が生まれ、紹介を通じて新たな見込み客との接点が広がりました。
結果として、本業である保険契約の件数も増加し、書籍出版がきっかけとなって大口契約の成約につながるなど、大きな成果を上げることができました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、出版でファン化が加速し、LTV向上につながった事例
あるサプリメントメーカーでは、商品の販促と長期的なブランド構築を目的に書籍を出版しました。
ターゲットは中年期以降の女性とし、「一生のうちで変化の多い「女性の人生の悩み」を解決する」というコンセプトを掲げたことで、顧客の共感を獲得しました。
出版時には著者と連携し、SNSでの情報発信を強化。
その結果、Amazon予約が殺到し発売前に重版が決定しました。
また、既存顧客向けに実施した書籍プレゼント企画では、予想の8倍にあたる240名以上が応募。
贈呈した顧客の半数以上がリピート購入を続けるなど、LTV(顧客生涯価値)の向上にもつながっています。
▶︎サプリメントメーカーの詳しい事例については【【事例コラム】”書籍無料プレゼント”に想定の6倍の応募、リピート率アップにインパクト!サプリメントメーカーの出版プロジェクト】もあわせて参考にしてください。
◉-3、発信に悩む食品メーカーが書籍によって差別化に成功した事例
わさびの開発・製造・販売を手がける食品メーカーは、日本文化の象徴である「わさび」の魅力を広めると同時に、自社のPRにつながる新たな発信手段を模索していました。
しかし、従来のプロモーションでは成果に限界があり、同業他社との差別化が大きな課題となっていたのです。
そこで、料理に関心を持つ30代〜40代女性をメインターゲットに設定し、わさびの効能や歴史、レシピを紹介する書籍を出版。
出版をきっかけに著者と料理研究家によるトークイベントを開催し、その場で50冊以上を販売する成果を上げました。
また、営業活動に活用できるよう書籍のダイジェスト版を小冊子として制作し、営業ツールとしても展開しました。
結果的に、書籍を通じて「わさびファン」を増やし、販売拡大につながっています。
◉コンテンツマーケティングに関するよくある質問

最後に、コンテンツマーケティングに取り組む際によくある質問に回答します。
◉-1、どのくらいで効果が出ますか?
コンテンツマーケティングは「攻める」手法ではなく、「待つ」手法であるため、新たに始めた場合は効果が出るまでに早くても3〜6か月、一般的には半年〜1年以上かかります。
SEOやSNSでは、継続的に取り組み、信頼や評価を積み重ねる必要があります。
そのため、即効性を期待するのではなく、長期的な視点で取り組むことが重要です。
◉-2、どんな企業に向いていますか?
コンテンツマーケティングは、BtoB・BtoCを問わず、顧客が購入前に情報収集を行う傾向が強い業界に適しています。
特に高額商品や専門性が高い商品、比較検討が必要な商品・サービスなどに、コンテンツマーケティングは効果的です。
◉-3、自社でやるべきですか?外注したほうがいいですか?
コンテンツマーケティングは自社でも取り組むことが可能ですが、すべてを内製化しようとするとリソースの負担につながるおそれがあります。
効果的なのは、役割を分担することです。
たとえば、戦略設計や自社にしかわからない専門知識の提供は社内で担い、記事執筆・デザイン・動画制作・編集といった制作部分は外注するといった形です。
こうすることで、自社の強みを活かしながら効率的に運用でき、クオリティも安定しやすくなります。
さらに、外注パートナーを活用することで最新のマーケティング手法や専門スキルを取り入れられるのもメリットです。
【まとめ】権威性を高めるなら書籍を活用したコンテンツマーケティングがおすすめ
この記事では、コンテンツマーケティングの手法や効果を発揮するための戦略について解説してきました。
コンテンツマーケティングは根気よく続ける必要がありますが、自社コンテンツを魅力に感じた顧客はファンとなり、長期的にサービスを利用し続けてくれる可能性があります。
そのためには、「ブレないためのターゲット設定」と「目的を見失わないための戦略設計」が重要です。
広告費を削減し、安定した売上を積み上げるためのコンテンツマーケティングを実施するうえで本記事の内容を参考にしてください。
「フォーウェイ」はブックマーケティングを主軸とし、徹底的な経営コンサルティング目線で書籍の出版をサポートしています。
企業のブランディングにも役立つ書籍を活用したコンテンツマーケティングを検討しているのなら、フォーウェイにご相談ください。
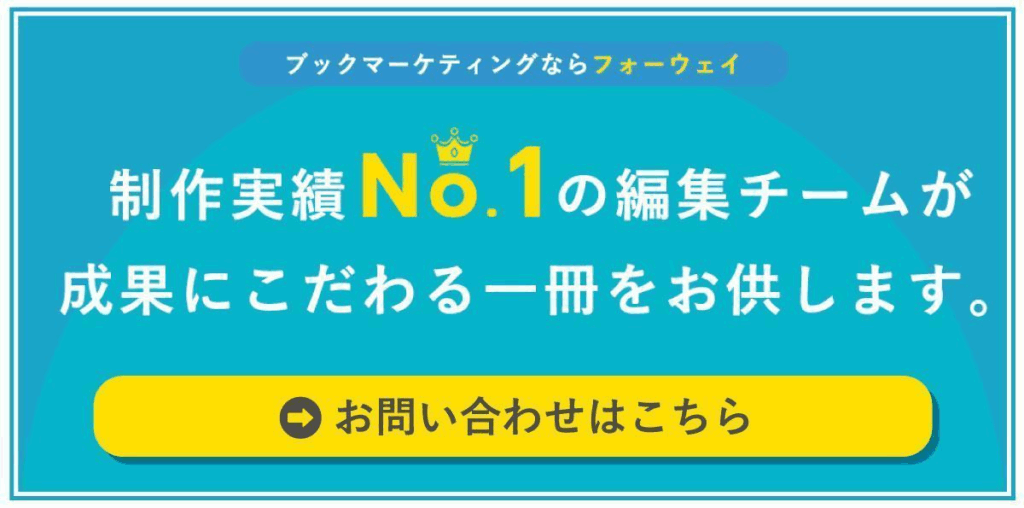

現代の市場では、ただ高品質な商品やサービスを提供するだけでは、顧客に選ばれるのが難しくなっています。
競合がひしめく中で「信頼できる企業」「格のあるブランド」として際立つためには、見た目や実績だけでなく、社会からの評価や存在感、つまり「箔」をいかにまとうかが重要です。
「箔をつける」という言葉は、もともと金箔を施して価値を引き立てるという意味に由来していますが、ビジネスの世界ではそれが「信頼性やブランド価値を高めるための働きかけ」として解釈されます。
本記事では、「箔をつける」という考え方を企業活動にどう応用できるのか、目的や得られるメリット、方法などを具体的に解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
「箔をつける」の意味とは?
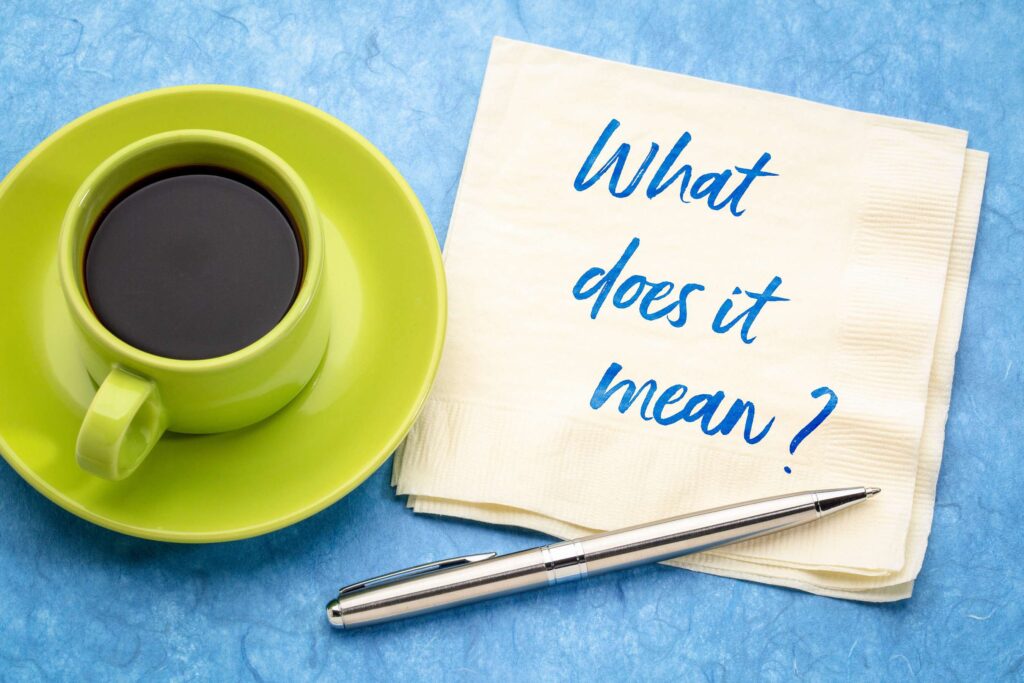
「箔をつける」とは、元々金箔や銀箔などで表面を装飾し、見た目を豪華にすることから生まれた言葉です。
そこから転じて、「見た目や評価をより魅力的に見せる」「価値があるように演出する」といった意味で使われるようになりました。
現代のビジネスシーンでは、企業や商品・サービスに「格式」「信頼性」「話題性」などを加えることで、その価値を高め、他者からの評価を上げるための表現として使われることが多くなっています。
自社や商品・サービスに箔をつける目的

まず、自社や商品・サービスに箔をつける目的は何なのかについて考えてみましょう。
主な目的として、次の4つが挙げられます。
・ブランドや企業価値の信頼性を高めるため
・市場での差別化を図るため
・認知度・知名度を高めるため
・高価格帯でも納得してもらえる価値を示すため |
以下で、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
ブランドや企業価値の信頼性を高めるため
箔をつけることで、顧客や取引先、ステークホルダーから信頼を得やすくなります。
たとえば、書籍の出版やメディアへの出演、講演活動などを通じて企業の専門性や実績を可視化することは、ブランドや企業の信頼の裏付けとなります。
また、認定資格の取得や各種受賞歴なども信頼を高める要素の一つです。
こうした「箔」があることで、初めて出会う相手にも安心感や期待感を与えやすくなります。
市場での差別化を図るため
同じような商品やサービスがあふれている現代においては、顧客に「選ばれる理由」を明確に示すことが重要です。
箔がついていると市場において差別化を図ることができ、価格競争に巻き込まれにくくなり、自社のポジションを高めることができます。
箔をつけることによって、顧客に「選ばれる理由」を提示することができるのです。
認知度・知名度を高めるため
企業が信頼性を得られたとしても、そもそも商品やサービスが知られていなければ選ばれることはありません。
しかし、箔をつけることが広報・PR施策になり、商品やサービスの認知度や知名度を高めることにつながります。
特にメディア露出は、第三者評価として顧客からの信頼を得やすく、SNSやWeb検索を通じて認知を拡大する起点にもなります。
▶︎知名度・認知度を高めるやり方については、関連記事【【経営者必見】知名度・認知度を高めるには?選ばれる企業になるための施策と成功事例まとめ】もあわせて参考にしてください。
高価格帯でも納得してもらえる価値を示すため
高価格帯の商品やサービスを提供する際には、「なぜこの価格なのか?」という問いに明確に答える必要があります。
このとき、その価値を裏付けて、顧客に納得感を与える要素が「箔」です。
たとえば、有名人の推薦やブランドヒストリーの明示などがあると、顧客は価格だけでなく「価値」に対してお金を払っているという納得感を得やすくなります。
結果として価格競争から脱却し、持続可能なビジネスモデルを築くことができるのです。
自社や商品・サービスに箔をつけるメリット

では、自社や自社の商品・サービスに箔をつけるとどのようなメリットが得られるのでしょうか。
主なメリットは、次の3つです。
・顧客の購買意欲を刺激し、売上が上がる
・ブランドに対するロイヤリティが高まり、リピート率が向上する
・専門家・権威として見られ、信用されやすくなる |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
顧客の購買意欲を刺激し、売上が上がる
商品やサービスを選ぶときに、「これは良さそう」「信頼できそう」と思わせる要素があると、顧客の購買意欲は自然と高まります。
たとえば、「〇〇賞受賞」「専門家監修」「有名人推薦」といった箔のついた情報は、顧客の背中を押す決め手となり、成約率や客単価の向上につながります。
ブランドに対するロイヤリティが高まり、リピート率が向上する
顧客に一度商品やサービスを利用してもらい、「やはりこの会社(商品)は信頼できる」と感じてもらえると、継続的な支持につながります。
ブランドに箔がつくことで、企業としての格が高まり、他社への乗り換えを防ぎやすくなります。
その結果、ブランドへのロイヤリティが深まり、リピート購入の可能性も高まるのです。
専門家・権威として見られ、信用されやすくなる
情報があふれている現代においては、「誰が発した情報なのか」がこれまで以上に重要です。
講演活動や書籍出版、メディア出演といった実績があると、それだけで専門家や権威として見られ、取引先や顧客からの信頼が得やすくなります。
特にBtoBビジネスにおいては、初対面であっても大きな信頼を得ることができ、その後の取引においても有利に働きます。
自社や商品・サービスに箔をつけるための方法

自社や商品・サービスに箔をつけるためには、信頼性や独自性を社会に示す必要があります。
箔をつけるための方法として、以下の3つが挙げられます。
・商品・サービスそのものを磨く
・実績や受賞歴をアピールする
・情報発信によってブランド価値を伝える |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
商品・サービスそのものを磨く
箔をつけるうえで、本質的で持続性の高い方法は、商品やサービスの質を高めることです。
クオリティが高ければ、顧客満足度が向上し、自然と好意的な評価が集まり、SNSやレビューでの高評価が箔となってブランドの信頼性を高めてくれます。
単なる装飾的な魅力アップではなく、本質的な価値に裏打ちされた信頼は、競合との差別化にもつながります。
実績や受賞歴をアピールする
他社や第三者からの評価は、「客観的な信頼」を得る手段となります。
たとえば、業界アワードの受賞や大手企業との取引実績、導入実績数の提示などは、信頼の証として積極的にアピールすべきポイントです。
受賞歴や実績は「第三者から評価されている」という説得力を持ち、見込み顧客やパートナー企業に好印象を与えます。
名刺やWebサイト、提案資料などに分かりやすく記載することで、箔を可視化できます。
情報発信によってブランド価値を伝える
自社や商品・サービスの価値や想いを正しく社会に伝えることで、箔をつけ、ブランド力を高めることができます。
情報発信の方法としては、主に次の3つがあります。
・講演・セミナーを開催する
・プレスリリースや取材対応を通じてメディア露出を図る
・書籍を出版する |
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
講演・セミナーを開催する
経営者や担当者が登壇する講演・セミナーは、企業のビジョンや専門性を直接顧客に届けられる場です。
講演やセミナーを開催することで、顧客やパートナーとの信頼関係を深め、業界内での自社のポジションを高めて存在感を示すことができます。
また、登壇の様子を動画やSNSで発信すれば、当日参加できなかった顧客にも企業の姿勢を届けることが可能です。
さらに、第三者主催のイベントに招かれることは、専門家であることの証明にもなり、さらなるブランド強化へとつながります。
プレスリリースや取材対応を通じてメディア露出を図る
マスコミや業界メディアへの情報提供を積極的に行うと、第三者評価としてのメディア掲載を得ることができます。
企業自らが語る自社の魅力よりも、第三者であるメディアが紹介することで、情報の信頼性や客観性が格段に高まります。
メディアへの露出が増えれば、「この会社は信頼できる」「注目されている」というポジティブな印象を広めることができるでしょう。
また、Webメディアでの掲載はSEO対策としても効果的です。
企業名やサービス名で検索した際に記事が上位表示されることで、検索エンジンからの信頼性(E-E-A-T:経験・専門性・権威性・信頼性)向上にもつながります。
書籍を出版する
書籍の出版は、企業の理念や専門的知見を体系的に伝える情報発信手段の一つです。
「著者」という肩書きは強力なブランディング要素となり、営業・採用・広報といったあらゆる企業活動において活用できます。
なかでも営業においては、書籍を名刺代わりに手渡すことで、初対面でも「信頼できる専門家」という印象を与えやすくなります。
出版はまさに「信用と実績の証」といえるため、独自性をアピールするうえで効果的です。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。

箔がつくだけではない!企業出版によって得られる効果

自社や商品・サービスに箔をつけるための方法の一つに書籍の出版があることを紹介しましたが、出版の効果は箔をつけるだけにとどまりません。
企業出版は、以下のような効果も期待できます。
・ブランディングの強化につながる
・メディア露出が増加する可能性が高まる
・営業ツールとして活用できる
・採用活動で人材が集まりやすくなる |
企業出版は一時的な効果ではなく、中長期的に企業の価値を高める資産として機能する点が特徴です。
4つの効果を詳しく見ていきましょう。
ブランディングの強化につながる
書籍は企業の「思想」「専門性」「社会的な立ち位置」を、信頼性のある形で社会に伝える媒体です。
WebサイトやSNSと異なり、本という媒体自体が「信頼の証」となるため、企業ブランドに箔をつけて格を上げる効果があります。
特に、オンライン上で情報があふれかえり、信頼性の見極めが難しくなっている現代においては、「時間と労力をかけて編集・出版された書籍」は、質の高い情報源として一目置かれる存在です。
出版社による審査や編集を経て出版されることで、企業の考えや専門性に対する本物感が生まれます。
メディア露出が増加する可能性が高まる
書籍を出版すると、書籍そのものが話題となって、メディアへの露出機会が広がるケースが多く見られます。
新聞や業界誌、Webメディアなどに「出版をきっかけとした取材」が入ることも少なくありません。
また、書籍出版のプレスリリースの発行や出版記念イベントなどを通じて、広報のフックとして活用することも可能です。
実際に、出版直後に「どのような経緯で書籍を出したのか」「どんな内容が書かれているのか」などを切り口に、多くのメディアからインタビューや記事掲載の依頼が寄せられることがあります。
こうした第三者による紹介は、企業自身の発信とは異なり、客観性と信頼性のある情報として受け取られるため、広報効果がより高まるでしょう。
営業ツールとして活用できる
書籍を営業活動に活用することもできます。
特に初回商談や提案の際に、自社の実績や理念をまとめた書籍を渡すことで、信頼性・専門性・安心感を短時間で伝えることが可能です。
たとえば、事前に商談が決まっている見込み客に書籍を送っておくことで、商談当日までに内容を読んでもらえる可能性が高くなります。
見込み客が書籍を読んだ状態で商談を迎えられれば、商品・サービスの基本理解が進んでいるため、質疑応答がスムーズに進むというメリットもあります。
実際にある企業では、初回商談時に見込み客が書籍に付箋を貼ってきたページの質疑に答えただけで、懸念点が解消され、スピーディーな受注につながったという事例もありました。
書籍は単なるパンフレットや会社案内とは異なり、幅広い情報や企業の哲学まで網羅しているため、「この企業は本気でこの分野に取り組んでいる」という印象を与えることができます。
採用活動で人材が集まりやすくなる
書籍は、採用活動においても役に立ちます。
会社の理念や代表者の考え方などを伝えることで、応募者が企業に共感しやすくなり、結果として企業理念に共感した人材を確保することにつながります。
特に若年層は、「どんな思いで仕事をしているのか」「どのような社会的使命があるのか」などに興味を持って応募するケースが増えており、書籍を通じて企業の価値観を伝えることは効果的です。
採用後のミスマッチを防ぐという意味でも、出版は有効な手段の一つといえるでしょう。

書籍出版で箔をつけることに成功した事例
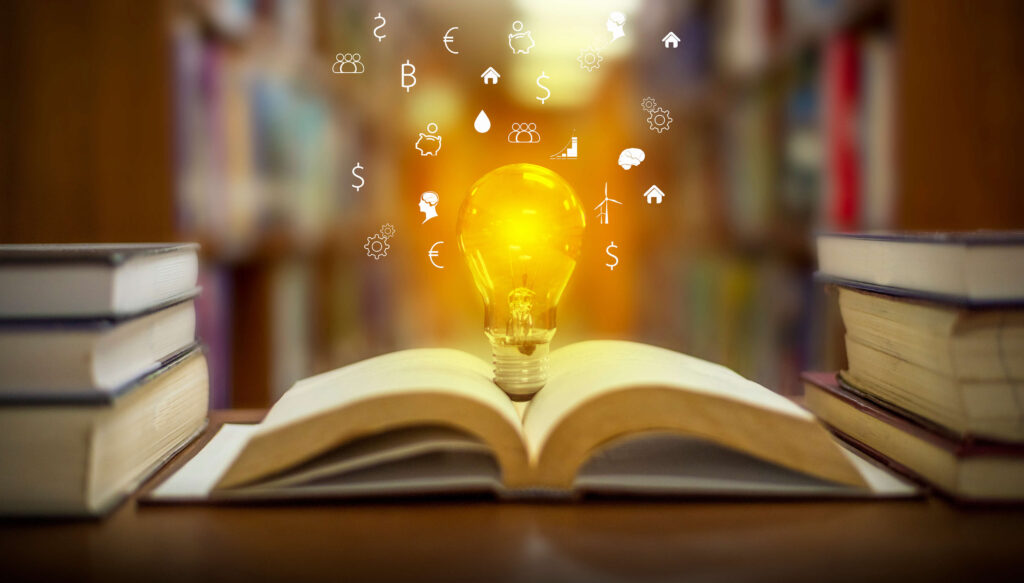
ここでは、書籍出版によって箔をつけることに成功した事例を紹介します。
・持論を形にして箔がついた保険代理店の事例
・他社との差別化と売上アップを実現した公認会計士事務所の事例 |
具体的にどのような取り組みが行われ、どのような効果が得られたのか、以下で見ていきましょう。
持論を形にして箔がついた保険代理店の事例
法人保険を取り扱っている保険代理店の社長は、2023年に『人材が続々集まる、メキメキ育つ!スゴい保険代理店経営』という書籍を出版し、人材育成に関する持論を展開しました。
その結果、業界内でのポジションが確立され、次のような成果を得ました。
| 同業からのコンサル依頼が複数寄せられた保険会社からの講演依頼が舞い込んだ商談前に本を読んでもらうことで、深い議論につながり大型契約が成約できた本を読んだ人材が応募してきて採用活動にも効果があった |
書籍出版によって箔がつき、直接的な売上だけでなく、ブランド力・人材力・企業文化に良い影響を及ぼした事例です。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
他社との差別化と売上アップを実現した公認会計士事務所の事例
公認会計士事務所の所長は、独立直後に海外進出の第一人者という「箔をつける」ために『次世代リーダーが知っておきたい 海外進出”失敗”の法則』という書籍を出版しました。
結果として、以下のような効果を得ました。
| 出版直後から同業の会計士コミュニティ内で注目されるようになった発売後わずか一週間でAmazonだけで数百冊を販売した地元新聞やラジオ、クーリエ・ジャポンなどの複数のメディアから取材の申し込みがあった出版をきっかけにセミナー講師依頼や商談の機会が急増した |
書籍の出版は「専門性」や「信頼性」を可視化する手段となり、出版をきっかけとしたブランド強化と事業拡大につながっています。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
【まとめ】「箔をつけたい」経営者こそ、企業出版で次のステージを目指そう!
本記事では、「箔をつける」ことの本質や必要性、自社ブランドの格を上げる具体的な方法としての企業出版の効果、さらには成功事例を通して、書籍を活用したブランド戦略の実践的なヒントをご紹介しました。
特に差別化が難しい現代において、信頼性や専門性といった「目に見えにくい価値」を可視化する手段として、箔をつけることの重要性が高まっています。
その中でも、自社の思想や強みを体系的に発信できる書籍出版は、他にはない独自性を打ち出す手段として注目されています。
フォーウェイでは、書籍をマーケティングに活用する「ブックマーケティングサービス」を行っており、箔をつける方法として有効です。
次のステージへと飛躍を目指す経営者にとって、企業出版は単なる広報手段ではなく、信頼とブランド価値を築く手段です。
あなたのビジョンを形にし、世の中に示す一冊を検討してみてはいかがでしょうか。


競合がひしめく現代の市場において、「選ばれる企業・商品」になるには「ブランド力」が不可欠です。
価格や機能だけでは差別化が難しいため、顧客からの信頼や共感を得るための「ブランディング」がますます注目されています。
しかし一口にブランディングといっても、「そもそも何を指すのか?」「マーケティングと何が違うのか?」といった疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
ブランディングの重要性は理解していても、具体的に何から始めればよいのか分からないという声も少なくありません。
本記事では、ブランディングの基本的な意味や手法、そして出版を活用した成功事例などを詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
ブランディングとは

ブランディングとは、自社独自のブランドを構築し、その価値を社会に認知・浸透させることで信頼や共感を得て、他社との差別化や企業価値の向上を図るマーケティング戦略の一つです。
ここでいう「ブランド」とは、単にロゴや名称を指すのではなく、他社とは明確に区別できる「企業や商品・サービスの個性」そのものを指します。
ブランドというとファッションや高級品などの世界を思い浮かべてしまうかもしれませんが、ブランディングは中小企業や地域密着の小規模事業者であっても、決して無関係なものではありません。
たとえば、「一人ひとりのお客様にきめ細やかな対応ができる」という点が自社の強みであれば、それもブランディングのポイントになるからです。
自社の商品やサービスをお客様に選んでもらうためには、選ばれる仕組みを作る必要があります。
つまり、ブランディングは意図的にブランドを設計し、市場に根付かせていくための一連の取り組み全般を意味します。
ブランディングの目的
市場に同様の商品やサービスがあふれるなかで、「この会社」や「この商品・サービス」を選ぶ理由を明確にするのがブランディングの目的です。
単に機能や価格だけの価値で判断するものではなく、感情や価値観によるつながりを重視します。
たとえば、「環境負荷への取り組みに熱心な企業」には、環境問題に対する意識の高い方が興味を寄せる可能性が高いといえるのではないでしょうか。
ブランディングによって企業や商品・サービスへのイメージが確立され、他社との差別化ができていれば、物や情報があふれるなかで記憶に残りやすくなります。
良いと思った顧客がSNSや口コミを通じて拡散する可能性が高く、「○○といえばこの商品」のように認知度の向上に役立つでしょう。
ブランディングで企業や商品・サービスに対する信頼性が高まれば、ブランドに愛着を持つロイヤルカスタマーやリピーターを獲得でき、長期的な売上や利益の向上にもつながります。
ブランディングとマーケティングの違い
ブランディングもマーケティングも企業が行う取り組みという点では共通していますが、その目的や手法が異なります。
マーケティングは自社の商品やサービスを販売することが目的です。
そのために顧客のニーズを知るために市場調査を行ったり、商品・サービスを理解してもらえるような宣伝広告や販売促進の活動を行ったりします。
一方で、ブランディングは、自社や自社の商品・サービスに対するイメージを構築することが目的です。
顧客からの好感や信頼を得ることを目的とし、他社とは異なる独自のイメージを思い浮かべてもらい、選ばれるような活動を行います。
▶︎マーケティングとブランディングの違いの詳細については、関連記事【マーケティングとブランディングの違いとは?経営戦略における重要性を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
現代のブランドを構成する要素
ビジネスでいわれるブランドとは、たとえば高級革製品のエルメスやグッチといったブランドが皆さんにも馴染み深いでしょう。
こうしたハイブランドのみならず、自動車のトヨタや家電のパナソニックなどもブランドです。
現代のブランドを構成する要素には、たとえば次のようなものがあります。
・企業や製品のロゴ
・名称や商標
・広告などに用いられるキャッチフレーズ
・WEBサイトやその他制作物のデザインとコンテンツ
・CSRなど企業の理念を体現した取り組み
・経営者や社員による社会への発信 |
企業と社会とが接点を持つすべての施策による総合的なイメージから、ブランドが形作られるのです。
そして、ブランドを意図して確立するために行なう取り組みを総称して、「ブランディング」と呼びます。
ブランディングには4つの分類がある

「○○ブランディング」と呼ばれる手法や考え方は多数存在しますが、実はその多くは4つの視点で分類できます。
・何をブランディングするのか?
・誰に向けたブランディングか?
・どの市場を意識したブランディングか?
・どんな手法でブランディングするか? |
以下で4つの視点からのブランディングを紹介します。
何をブランディングするのか?
何をブランディングしたいのかで、発信すべき内容や他社と差別化するポイントも変わってきます。
具体的には、以下の3つです。
・企業ブランディング
・商品・サービスブランディング
・採用ブランディング |
企業そのもののブランディングをしたい場合と、商品・サービスに焦点を当てたブランディング、自社に応募してくれる求職者に対するブランディングの3つに分けて解説します。
企業ブランディング
企業ブランディングは「コーポレートブランディング」とも呼ばれ、企業そのものの価値やイメージを社会に認知してもらうことを目的としたブランディングです。
経営理念やビジョン、企業文化や社会的なスタンスなどを社会に対し、一貫した形で発信することでその企業らしさを打ち出します。
▶︎企業ブランディングについては、関連記事【企業ブランディングとは?効果や具体的な8つの手法を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
商品・サービスブランディング
商品・サービスブランディングは、名前の通り、自社の商品やサービスの価値・魅力を高めるためのブランディングです。
品質・価格・独自性・ストーリー性など、競合他社と差別化できる要素を打ち出し、自社が「選ばれる理由」を確立します。
たとえば、「高品質ながらリーズナブルな価格」「専門知識の豊富なスタッフによる丁寧な対応」などです。
▶︎商品・サービスブランディングについては、関連記事【商品ブランディングとは?効果や手順、具体的な手法を解説】もあわせて参考にしてください。
採用ブランディング
採用ブランディングはお客様ではなく、求職者に対して自社の魅力や理念を訴求します。
自社に対して共感を持って応募してもらうためのブランディングであり、人手不足の時代において、良い人材に「この会社で働きたい」と選ばれる企業になることが目的です。
企業ブランディングで訴求する理念やビジョンとブレがないよう、連動している必要があります。
▶︎採用ブランディングについては、関連記事【採用ブランディングとは?選ばれる企業になるための進め方とは」もあわせて参考にしてください。
誰に向けたブランディングか?
誰に向けたブランディングかでも違いがあり、大きく分けて2種類があります。
内向きのインナーブランディングと外向きのアウターブランディングという、異なる視点のブランディングについて、さらに詳しく掘り下げます。
インナーブランディング
インナーブランディングとは、企業の理念やビジョン、価値観を社内に浸透させるためのブランディング施策です。
従業員が企業の方針に共感し、「自分もその価値を体現する存在である」という意識を持って働けるようになることで、結束力やエンゲージメントの向上につながります。
また、採用後のミスマッチを防ぎ、定着率を高めたい企業にとっても欠かせない取り組みです。
▶︎インナーブランディングについては、関連記事【インナーブランディングとは?組織としての連携を強化し企業価値を高めるための手法を解説】もあわせて参考にしてください。
アウターブランディング
アウターブランディングは、顧客や取引先はもちろん、求職者なども含めた社外に対して企業や商品・サービスの魅力を発信する活動です。
紙の広告やテレビCMからWebサイトやSNSまで、さまざまな媒体を通じてブランドイメージを定着させ、「この会社やこの商品・サービスなら信頼できる」と思ってもらうことを目的とします。
どの市場を意識したブランディングか?
どの市場に向けてブランディングを行うのかによっても、訴求の方法や踏まえておくべきポイントが異なります。
主な市場として、3つあります。
・BtoCブランディング
・BtoBブランディング
・地域ブランディング |
それぞれのブランディングの特徴と重要なポイントは、以下の通りです。
BtoCブランディング
BtoCブランディングは、個人の消費者を対象としたブランディングです。
BtoCブランディングでは、感情に訴えるメッセージやビジュアル訴求が重視されます。
商品に愛着を持ってもらったり、サービスを信頼してもらったりなど、ブランドへの共感を得る必要があります。
また、消費者が普段から直接手にする食品や化粧品、アパレル、サービスなどを対象としていることが多いため、ライフスタイルへの親和性があることもポイントです。
BtoBブランディング
BtoBブランディングは、法人向けのブランディングです。
BtoCブランディングのように感情を煽るようなメッセージやビジュアルに頼るのではなく、実績や専門性、信頼を訴求します。
一般の消費者は商品やサービスを気に入れば、すぐにでもアクションを起こす可能性がありますが、企業の場合、その場で決定することは稀です。
意思決定までの過程が多く、複数人によって選定されるため、論理に基づいた説明や安心感のある情報提供が重要です。
BtoBブランディングの具体例としては、コンサルティングやITサービス、製造業などがあります。
地域ブランディング
地域ブランディングは特定の地域に根ざした文化や資源の価値を明確にして発信することで、地域全体のブランド価値を高める活動です。
たとえば、地域産の製品をブランド化する、自然景観や食文化、温泉などの観光資源をもとに観光客を呼び込むなどの活動があります。
また、移住促進といった取り組みも、地方創生の一環として注目されています。
どんな手法でブランディングするか?
ブランディングの手法による分類も4つあります。
・デザインブランディング
・SNSブランディング
・ストーリーブランディング
・出版ブランディング |
それぞれの特徴や有効なケースを紹介します。
デザインブランディング
デザインブランディングは、視覚的要素を一貫させてブランドイメージを確立する手法です。
ただし、見た目が美しければいいというわけではありません。
たとえば、企業を象徴するカラーで統一すると、イメージと合致しやすいでしょう。
カラー以外でもロゴやフォント、パッケージやWebサイトに至るまで、ブランドに関わるものをイメージに合わせて統一する必要があります。
視覚に訴えかけるデザインブランディングは直感的な印象づけに強く、短時間でブランドを認識してもらうのに有効です。
SNSブランディング
SNSブランディングはSNSを活用してブランドの世界観を発信し、親近感を育てる手法です。
InstagramやX(旧Twitter)、Facebook、Tik Tokなど、複数のツールから顧客層に合うものを選び、発信します。
ユーザーが日常的に利用しているツールを活用し、双方向でやり取りできるのがメリットです。
ユーザーの反応を確認できるほか、意見や感想を受け取ったうえでコミュニケーションが取れるため、エンゲージメントの高いブランド構築に効果的です。
ストーリーブランディング
ストーリーブランディングは、ブランドの成り立ちや商品開発の背景、創業者の想いなどを物語として発信し、ユーザーの共感を得るブランディングの手法です。
「なぜこのブランドなのか」を言語化してストーリー仕立てにすることで、記憶にも残りやすくなり、ブランドそのもののファンになってくれる可能性も高まります。
▶︎ストーリーブランディングについては、関連記事【ストーリーブランディングとは?企業の物語を伝えてファンを作る方法】もあわせて参考にしてください。
出版ブランディング
出版ブランディングは、書籍や電子書籍、ホワイトペーパーなどを活用し、自社の思想や専門性、信頼性を発信することでブランドの権威づけを行う手法です。
インターネットを検索すれば多くの情報を得られるものの、根拠が不明な情報もあふれています。
その点、「書籍を出版した」という実績は、信用獲得につながりやすいのがメリットです。
▶︎出版ブランディングについては、関連記事【出版ブランディングとは?次なるステージに進みたい企業におすすめの施策】もあわせて参考にしてください。

ブランディングによって得られるメリット
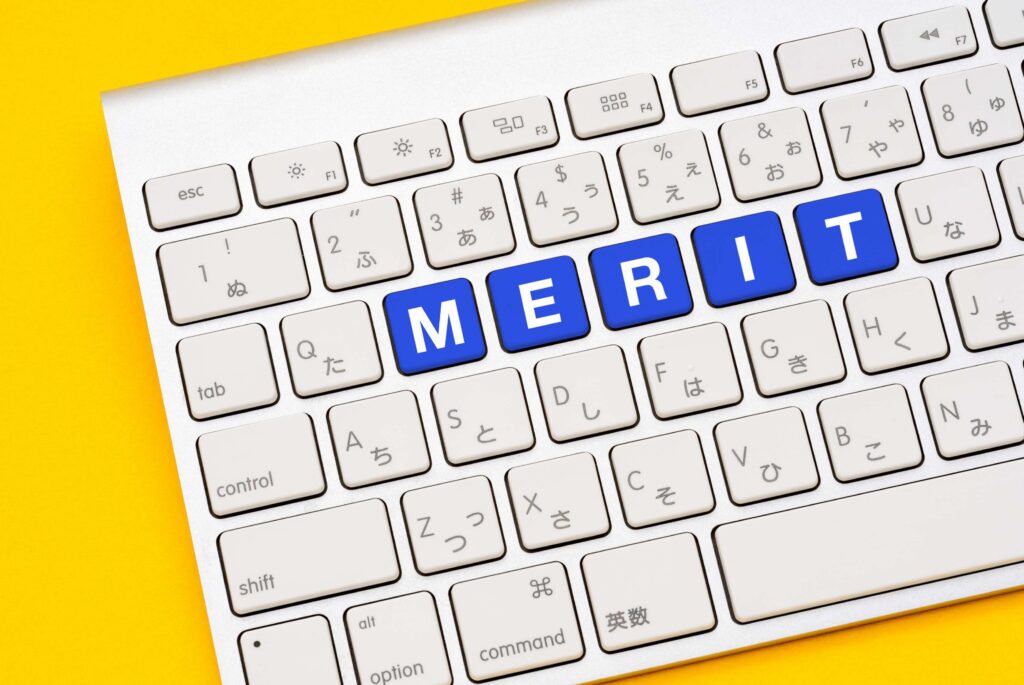
ブランディングによって得られるメリットは、主に5つです。
・価格競争から脱却できる
・顧客ロイヤルティが向上し、売上とリピート率のアップにつながる
・広告宣伝にかかるコストを抑えられる
・社員のモチベーションアップにつながる
・優秀な人材を集めやすくなる |
5つのメリットについて、それぞれ詳しく解説します。
価格競争から脱却できる
「ブランド力がある」というと、「高級なイメージがあって価格が高くても買ってもらえる」という意味と同義で考えている人が多いかもしれません。
こうした認識はブランドの一部を捉えていますが、本来のブランドはもう少し広い概念を含みます。
たとえば、アウトドアファッションブランドのパタゴニアは、「リサイクル素材100%使用のアイテム開発」「持続的な農業研究への参画」など、環境意識の高いサステナブルな企業としての取り組みを積極的に発信しています。
このブランディングが功を奏し、環境意識の高い先進的な人々から、他のブランドではなく絶対にパタゴニアを選ぶ、というファン層を多く獲得しているのです。
シューズメーカーのドクターマーチンは、その独特な丸みを帯びた靴のフォルムがイギリスのロックカルチャー文化の体現としてブランド化され、ブリティッシュロックのファン層から積極的に選ばれています。
ほかに有名どころだと、コーヒーチェーンのスターバックスは、元CEOのハワード・シュルツ氏による「サードプレイス(家でも職場でもない素敵な第三の場所)」というコンセプトに基づいたブランディングの成果で、外で落ち着いてコーヒーを飲みたいユーザーが真っ先に思い浮かべる場所として自社を位置づけることに成功しました。
これらのブランディング成功企業は、必ずしも競合に比べて価格がとても高いわけではありません。
重要なポイントは、ブランディングによって自社の位置付けや考え方をユーザーと明確に共有し、競合と比較されずに指名で選ばれる商品・サービスにできた点です。
ブランディングに成功すれば、競合との値下げ競争から解き放たれ、適正な利益を確保しながらブランドをより強化する取り組みに経営資源を割くことができています。
顧客ロイヤルティが向上し、売上とリピート率のアップにつながる
ブランディングが成功すると、自社そのものや提供する商品・サービスに対して、安心感や信頼感を持ってもらえます。
愛着が湧き、ファンとして育ってくれると、「また次も商品を購入しよう」「サービスを利用しよう」という感情を起こさせるため、結果的に売上やリピート率のアップにつながります。
広告宣伝にかかるコストを抑えられる
ブランディングによって既存の顧客がファン化してくれると、顧客自身がSNSや口コミで情報を拡散してくれる可能性が高まります。
SNSなどで拡散されれば、それまで自社や自社の商品・サービスに興味がなかった新しいターゲット層にも情報が届き、アプローチしやすくなるのもメリットです。
結果的に広告宣伝にかかるコストを抑えつつ、事業の拡大も狙うことができます。
社員のモチベーションアップにつながる
ブランドイメージが確立して自社が提供する商品やサービスに自信が持てるようになると、社員にも自社に対する誇りが生まれます。
企業が掲げる理念や価値観に共感し、やりがいを持って働けるようになることで業務に対するモチベーションも上がり、生産性の向上にもつながります。
優秀な人材を集めやすくなる
ブランディングによって企業の価値や信頼度が向上すると、既存の社員の共感を得られるだけではなく、求職者にとっても魅力のある企業として認識されます。
「この企業で働きたい」という応募者が集まりやすくなると、従来ほど採用に注力する必要がなくなり、コストの削減にもつながります。
ブランディングを成功させる4ステップ
では、実際にビジネスの現場でブランディング、あるいはリブランディングを成功させる方法を解説します。
今回は、個人事業主や小さな企業でもブランディングを実行できるように、ごくごくシンプルなステップにまとめました。
・ブランディングのステップ①自社ブランドの現状測定
・ブランディングのステップ②ブランドコンセプトとターゲットの決定
・ブランディングのステップ③個別施策の精査と実行
・ブランディングのステップ④効果の検証と改善(PDCAを回す) |
4つのステップに分けて、詳しく解説します。
ブランディングのステップ①自社ブランドの現状測定
ブランディングに取り組むうえでまず行なうべきは、現状の自社ブランドについて、客観的に把握することです。
それには、ユーザーの声を聞くことが最も有効です。
自社の既存ユーザーにアンケートを取ったりヒアリングをかけたりして、なぜ自社を選んだのか聞いてみてください。
自社の担当者から直接聞くとおべっかを使われてしまう可能性があるので、外部調査機関を使っても良いでしょう。
一方で、「選ばれなかった理由」を知るのはさらに重要です。
営業マンなどから、商談のなかで競合に決まってしまったケースの情報を可能な限り多く集め、社内で徹底的に分析しましょう。
この際、「価格では負けていなかったのに競合に取られてしまった」「競合であると考えていなかった低価格低品質の他社に取られた」といった事例が必ず出てくるはずです。
このような事例こそ、自社のブランド力不足を明らかにするヒント。
ブランドが確立していれば起こり得ないケースだからです。
とことん突っ込んで議論し、自社の現状を謙虚に把握しましょう。
ブランディングのステップ②ブランドコンセプトとターゲットの決定
自社のブランドについて現状を把握したら、次は進むべき方向を定めます。
ステップ①で把握した現状の不足に対して、それを克服できるようなブランドコンセプトを定め、自社のターゲットも同時に明確にします。
実在の例を用いると、次のような内部コンセプトを決定するイメージです。
おしゃれで先進的な人々に対し、クールな製品を通じたスタイリッシュなライフスタイルを提供する(Apple)最も安心できる自動車をお手頃価格で求める人々に対し、運転しやすく安全性能の高い、丈夫なクルマを適正価格で提供する(トヨタ自動車)モノへのこだわりを表現して自分自身をブランディングしたいハイソサエティ層に対し、職人一人ひとりのストーリーが詰まった最高品質の腕時計を提供する(リシャール・ミル)
※それぞれのブランドの内部コンセプトは、当社の独自分析によるものです。 |
このように、ターゲットを含めた内部コンセプトがはっきりすると、ブランディングの方向性は自然と明確になってきます。
ブランディングのステップ③個別施策の精査と実行
ブランドコンセプトとターゲットが定まったら、自社が現在、ユーザーと持っている接点をすべて再検証します。
たとえば、ハイソサエティ向けに高品質な商品・サービスを提供しているのに、自社サイトがポップなデザインで「安さ・手軽さ」を売りにしているようであれば、ブランドコンセプトとのミスマッチになります。
製品に対する哲学やサービスに対する思いを強みにしたいのに、自社の理念やストーリーを何も公開していないとしたら、ブランディングは成功しません。
このように、あるべき自社のブランドに沿った施策をきちんと取っているか精査し、足りない施策は新たに実行する必要があるのです。
ブランディングプロセスの好事例として、ゼネコンの前田建設工業の取り組みを紹介しましょう。
ゼネコンとはブランディングの難しい業種です。
ある程度の規模であればどこも技術力や得意な工事にはさほど差がなく、結局横並びで「安心」「誠実」といった抽象的なメッセージを発信するブランディング施策になってしまいがちなのです。
前田建設工業についても、特徴や強みの打ち出しに苦労していたことは容易に想像できます。
そこで前田建設工業が行なったのは、特設ページによる「前田建設ファンタジー事業部」というコンセプトの打ち出しです(https://www.maeda.co.jp/fantasy/)。
前田建設ファンタジー営業部は特設サイトにおいて、「マジンガーZ地下格納庫一式工事は予算72億円、工期6年5ヵ月(ただし機械獣の襲撃期間を除く)で引き受けます」など、ファンタジー世界の構造物を実際に大手ゼネコンが請け負ったらどうなるか、という空想を面白コンテンツとして展開。
そのマニアックさと異様なまでの緻密な分析によってサイトが大ヒットし、同テーマで出版した書籍もベストセラーになりました。
2020年には映画も公開されています。
こうした、ブランドの現状を見据えた一連のブランディング施策により、前田建設工業は「遊び心があって挑戦的なゼネコン」としてのブランドを確立することに成功。
会社の知名度を大きくアップさせるとともに、競合と比べられない独自の立ち位置を確立したのです。
このほかにも、テレビCMをはじめとした大規模な広告ブランディングや、自社店舗の全店改装でブランディングを成功させた事例が見られます。
ただ、今回は「予算がそれほど潤沢でなくても実行できる」という観点に重きをおいて解説しました。
ブランディングのステップ④効果の検証と改善(PDCAを回す)
ブランディングは一度行ったら終わりではありません。
トレンドが変化して、ブランディングの内容とは合わなくなってしまうこともあるでしょう。
また、競合他社が増え、市場の状況が変わる場合もあります。
そのため、ブランディングは中長期視点で考え、効果を上げているかどうかを定期的に検証することが重要です。
ブランドがどのくらい認知されているのかを検証する方法には、以下があります。
・Webサイトへのアクセス数や訪問者の行動
・SNSへのリアクション
・メディア掲載数
・口コミやレビューサイトでの評価 |
自社のブランディングに合う検証方法で効果を見直し、修正点が見つかれば戦略を練り直して改善に努めましょう。
ブランド力を高めるなら出版ブランディングがおすすめ!
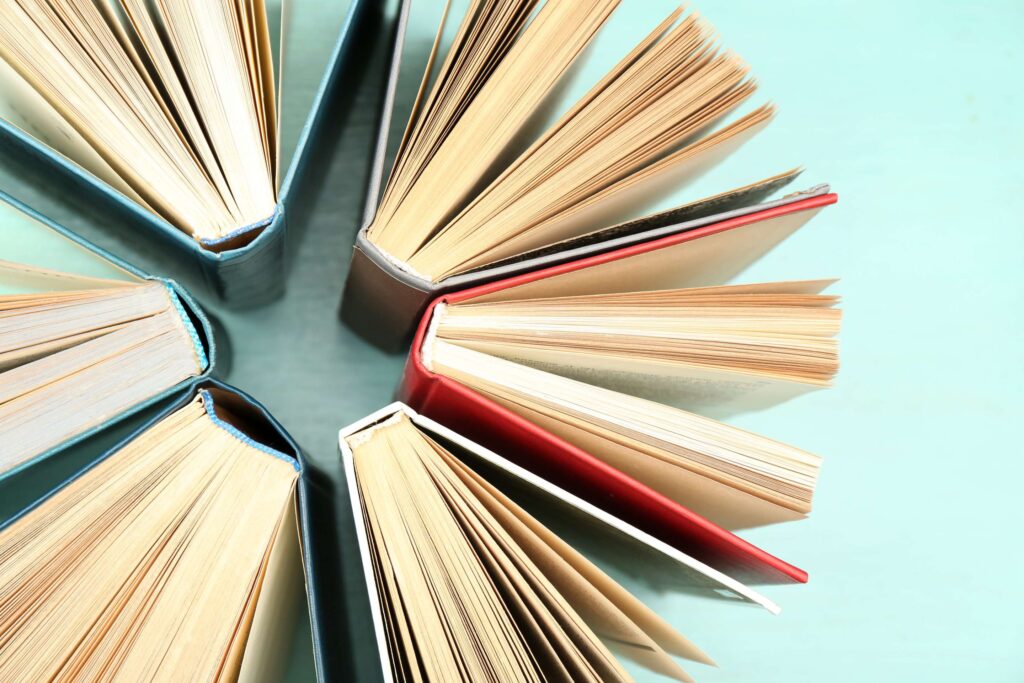
企業の専門性や信頼性を伝える手段として、出版ブランディングが効果的です。
現代ではインターネットを駆使すれば、さまざまな情報を入手できます。
しかし、根拠があいまいだったり、出典が明記されていなかったりする情報も多く、必ずしも正確な情報が得られるとは限りません。
一方、信頼できる出版社から書籍を出版し、自社の思想やノウハウを体系的に伝えられれば、ブランドに対する「信頼」や「共感」を獲得しやすいのがメリットです。
出版実績が注目されれば、他社との差別化やメディア露出のきっかけにもつながります。
書籍出版はBtoC・BtoB領域だけではなく、求職者に向けた採用ブランディングやPR強化にも活用できます。
ブランド価値を根本から高めたい企業には、出版ブランディングは効果的な施策です。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。

出版ブランディングの成功事例

実際に出版ブランディングを実施し、成功した事例は以下の3つです。
・出版を通じて著者をリブランディング!建設業コンサルタントの出版成功事例
・医師向けブランディングに成功!不動産投資会社の出版プロモーション事例
・発売前に重版決定!美容・健康食品ブランドの信頼性とリピート率を高めた出版事例 |
3つの事例をそれぞれ紹介します。
出版を通じて著者をリブランディング!建設業コンサルタントの出版成功事例
建設業専門のコンサルティング会社が、自社の事業を認知してもらうために書籍を出版しました。
同社は2016年にも書籍を出版しており、今回はその後に蓄積されたノウハウや成功事例をより分かりやすく体系化した最新版として再発信することが目的でした。
出版にあたって、ターゲット層に届けられるように「建設業のための」という文言をタイトルに入れ、専門分野を明確にしています。
その結果、発売からわずか1か月で重版が決定し、累計発行部数は5,000部を突破。
livedoor NEWSやLINEニュースをはじめ、計17媒体に取り上げられ、反響を呼びました。
出版をきっかけに、コンサルティング契約の問い合わせが10数件増え、顧客層の広がりにもつながっています。
医師向けブランディングに成功!不動産投資会社の出版プロモーション事例
不動産投資サービスを手がけるある不動産会社の経営者は、もともとSNSやWeb広告で情報を発信していたものの、効果は得られていませんでした。
そこで、「医師にとって最も効果的な節税対策は不動産投資である」というメッセージを軸にした書籍を出版。
企画段階からターゲット戦略を明確にし、出版後のプロモーションまで一貫して設計した結果、多くの医師に書籍を手に取ってもらうことができました。
その結果、書籍を読んだ医師に不動産投資による具体的な節税効果が伝わり、発売から6か月間で獲得した10件の問い合わせすべてが成約という、驚異の成約率100%を達成しました。
さらに既存顧客から情報が拡散され、新規顧客の獲得にもつながっています。
発売前に重版決定!美容・健康食品ブランドの信頼性とリピート率を高めた出版事例
美容・健康食品ブランドは、既存顧客のファン化と企業ブランディング強化を目的に、代表自らの人生観を反映した書籍を出版しました。
出版記念として行った書籍プレゼント企画には、想定の6倍以上の応募が集まり、読者から共感の声が多数届いたことでブランド好感度が上昇。
LTV(顧客生涯価値)も出版前より明確に向上しました。
著名人とも連携したことで発売前から重版が決定し、メディアにも取り上げられています。
さらに、自社メディアやSNSでの出版実績が差別化要素となり、テレビ通販番組への出演や講演依頼も実現し、出版が「信頼の証」として、ビジネスチャンスにつながりました。
【まとめ】出版ブランディングでブランド力を高めよう!
ブランディングは競合他社との差別化を図り、企業の価値を向上させるためにも重要な戦略です。
ブランディングは4つの視点で分類でき、目的に応じてさらに細かい手法があります。
なかでも、出版ブランディングは自社の理念や思想、ノウハウなどを書籍として体系的にまとめて伝えられるため、信頼や共感を獲得しやすいのがメリットです。
フォーウェイでは、出版マーケティングを中心として、企業の成長を支えるサービスを展開しています。
「集客のため」「採用活動のため」など、企業によって異なる具体的な目的を達成できるよう、コンサルティング目線でサポートしています。
出版ブランディングを含め、自社のブランディングにお悩みの方は、フォーウェイまでご相談ください。

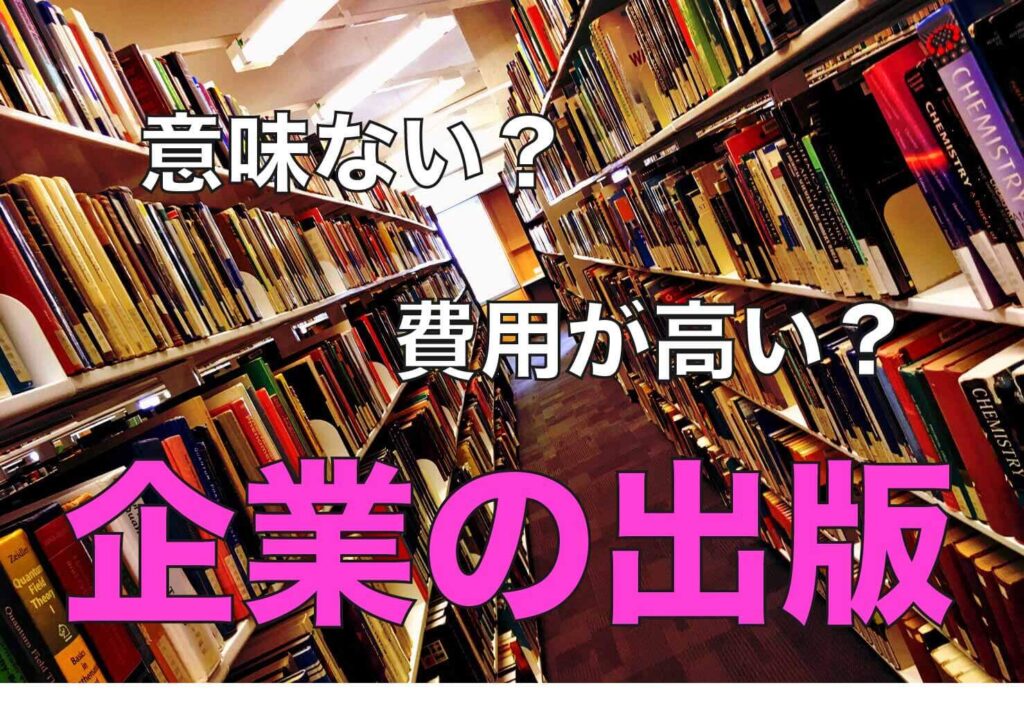
企業がマーケティングやブランディングのために行う企業出版(ブックマーケティング)。
出版不況と呼ばれる時代において、企業出版をメインでサポートしている出版社は売上や刊行点数を伸ばし続けています。
つまり、企業が企業出版を決断する機運は高まっているといえるでしょう。
企業が自らのストーリーや価値観を世に伝える手段として、書籍というメディアの可能性が再評価されています。
今回の記事では、企業出版(ブックマーケティング)のメリットを紹介しつつ、数字では表せない、企業出版だからこそ実現できる書籍の使い道を解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
企業出版とはベストセラーを狙う出版ではない

出版を実施するにあたり、どうしても気になるのは書籍が売れるかどうか。
ただし、企業出版については、売れる本を作ることを目的としていません。
誤解を避けるために詳しく解説すると、企業出版はベストセラーになる本を目指してはいませんが、「狙ったターゲット」に売れる本を作ります。
出版に際しては企業のマーケティング戦略同様、自社の商品やサービスを知ってほしい顧客層をターゲットとして設定します。
そのうえで、設定したターゲットが手に取りたくなるような企画づくりや、書籍のカバーデザインを仕上げるのです。
不特定多数へ知らしめる広告手法としてではなく、明確なターゲットがある企業であればあるほど、企業出版は適しているといっても良いでしょう。
改めて正確にお伝えすると、企業出版とは、企業が自社の情報や専門知識を書籍の形式で出版することです。
出版社によって「カスタム出版」とも呼ばれます。
企業出版はブランディングや販促活動の一環として活用され、読者に対して企業の知見や価値を提供し、著者のビジネスにつなげることを目的としています。
近年、経営課題を解決する方法として出版を選ぶ企業は増え続けており、多くの企画が実際に出版に至っています。
そうした需要を背景に、既存の出版社が企業出版サービスを提供するケースも増えており、企業出版を専門とする出版社も出始めているようです。
企業出版の発行部数は、プランによって幅がありますが1,000〜5,000部くらいです。
部数や流通範囲が拡大するほど出版費用は上がります。
流通については通常の商業出版と同様の規模で書店にまくケースや、特約書店のみに配本するケース、オンライン書店のみで流通するケースなどさまざまです。
ただ共通するのは、実際に本を店頭に並べるかどうかは書店側の判断になるため、出版前の想定どおりに書店に並ぶかどうかは出してみるまでわからないという点です。
本の企画をはじめ内容については、出版社からの提案を著者が承認して決める形になります。
自費出版のように自分ですべて作るのではなく、自分の表現したい内容をプロの編集者のスキルを借りて形にできるのは大きなメリットです。
出版社がプロのライターをつけてくれる方式が一般的なため、インタビューに答えて上がってきた原稿に赤入れすることが著者の負担になります。
なお、以下にフォーウェイが行った、企業出版経験者への効果実感アンケートの結果リンクも掲載します。
上記のメリットが想像以上に発揮されている事実がよくわかるので、興味があればぜひご覧ください(以下の画像をクリック)。

▶企業出版については、関連記事【「出版の広告効果とは? 企業出版と自費出版の違い」】もあわせてご参考にしてください。
企業出版と他の出版の違い

出版の方式には大きく分けて「商業出版」「自費出版」「企業出版」の3種類があります。
また、企業出版の中にも「集客・ブランディングなどのビジネスゴールの達成」を目的にする通常の企業出版と、弊社フォーウェイが提供する「費用対効果の高いマーケティング」を目的とする企業出版(ブックマーケティング)があります。
それぞれの違いは、次の通りです。
| 自費出版 | 商業出版 | 企業出版(通常) | 企業出版(ブックマーケティング) |
| 出版目的 | ⼩説・エッセイなど私的原稿の書籍 | ヒット作(ベストセラー)制作による出版社の利益確保 | 集客・ブランディングなどビジネスゴールの達成 | 最適な費⽤的効果によるマーケティング出版の実現 |
| 版元 | ⽂芸社、現代書林など | 通常の大手・中小出版社 | 幻冬舎、ダイヤモンド社など | フォーウェイのプロデュースによりグループ出版社パノラボから出版 |
| 編集体制 | なし(ほぼ校正・組版・製本のみ) | 出版社の編集者、実績豊富なライターやデザイナーによる制作(企画内容によってさまざまな形態がある) | フリー編集者や編プロへの委託制作経験の浅い編集担当による制作(の可能性) | 出版実績230冊を超えるプロデューサーの責任編集企業出版実績豊富な編集担当者を選抜ベストセラー実績の豊富なライターやデザイナーアサイン |
| 部数 | 最低500部程度から | 最低3000部程度から | 最低5,000部程度から | 最低1,000部程度から(企画内容により出版社負担での部数増あり) |
| 書店流通 | ほぼなし(⼤書店の「⾃費出版」棚への展開) | 出版社が積極的な書店流通を行う | ⼤⼿出版社通常(部数により500〜1,000書店程度) | 該当書籍のジャンルに合わせた書店営業の実施通常プランに100冊分の1か月書店プロモーション付き |
| プロモーション | ほぼなし | 出版社が積極的にプロモーションを行う | リリース送付+オプションにより買取施策や数百万円単位の広告出稿(追加料⾦なしでの雑誌への露出などは原則なし) | ・リリース送付+セットプランにより割安に広告施策を提供+Amazon販売促進施策のWEB広告をサービス内で実施+オプションとして各種コンテンツサービス、SNSブースト、クラウドファンディングなどの先進的施策・提携ビジネス媒体への掲載確約 |
| 適した著者 | ・とにかく費⽤を抑えて「出版した」という事実が欲しい個⼈・製本された現物を⼿元に持ちたい⼈ | ・基本的に出版社から依頼を受けた人 | ・多額の予算を⻑期的ブランディングに投資する余⼒のある企業・⼤部数の⾃社買取を前提に出版する企業 | ・経営施策として出版の成功を求める中⼩〜中堅企業・費⽤対効果にこだわる経営者やプロフェッショナル・⾃費出版や企業出版・カスタム出版に満⾜できなかった経験のある⼈ |
3つの出版方法について詳しく解説します。
商業出版
商業出版は、出版社が費用を負担して企画し、著者に執筆を依頼する出版方式です。
著者には出版社から、発行部数に応じた印税が支払われます。
出版した本が重版すればするほど印税が増える、著者にとっては夢のある出版です。
予算のかけ方は企画によってさまざまで、原稿の書けない著者にはゴーストライター(ブックライター)を用意したり、イラストレーターやデザイナーを用意して全ページカラーにしたりと、出版社が「売れる」と判断した企画内容に沿って体制が作られます。
注意点として、商業出版では企画から原稿の内容に至るまで、基本的には出版社に決定権があります。
書籍を売ることを目的に出版社が投資し、売れなかった場合のリスクも引き受けるためです。
したがって、自分の本であっても著者の希望は通らない場合が多くなります。
実際に、以下のようなケースが見られます。
・「著者にとってはマイナスイメージになりそうな企画でないと出さない」と言われた
・著者の事業の宣伝を入れようとしたら「流通に支障が出る」「作品性が損なわれる」と断られた
・全然気に入っていないカバーデザインに決められた |
そのため、商業出版の経験者のなかには、「自社のビジネスメリットにもなるかと思って依頼を受けたけど、全然思いどおりにならなかった」といった不満が残っている方もいるようです。
また、商業出版として進行していた企画でも、編集者からのレスポンスがなく停滞して出版されなかったり、実際に出版したものの思うように売れず、結果として数百万円分の在庫を買い取ることになったりと、自費出版と変わらない費用負担が発生するという事例も少なくありません。
このようなリスクもあるため、契約前には内容を十分に確認し、納得したうえで進めることが大切です。
▶︎商業出版については、関連記事【商業出版とは?企業がブランディングを考えたときの出版の選択肢】も合わせて参考にしてください。
自費出版
自費出版は、個人が自身の著作物を自己負担で出版する形式です。
「小説や詩集など趣味で書き溜めていた原稿を出版したい」「人生の軌跡を記録として残したい」といったニーズが多いです。
特徴としては、流通規模の小ささです。
自費出版はおおむね100〜500部程度の発行部数で、書店流通はまったくなしか、ごく一部の書店への配本に限られます。
書店へ配本されるケースでも、「自費出版棚」などの棚にまとめられたり、配本されても書棚に並ばないケースが多いようです。
内容については、自費出版は100%、著者の思いどおりです。
カバーに自作のイラストを入れたりといったアレンジも好きなようにできます。
自費出版での出版社の仕事は、持ち込まれた原稿を校正し、デザインレイアウトして印刷することです。
一方で、「内容に自信がないからもっと売れるように改善提案してほしい」といった希望は叶わないと思ったほうが良いでしょう。
▶︎自費出版については、関連記事【自費出版のやり方を現役書籍編集者が1から分かりやすく解説!】も合わせて参考にしてください。
企業出版(ブックマーケティング)
企業出版(ブックマーケティング)とは、書籍をマーケティングに活用する出版方法です。
企業が自社の事業や商品・サービスなどについてまとめた書籍を出版し、企業や商品・サービスの認知度向上や購買意欲向上などに役立てることを目的としています。
近年はインターネットで簡単に情報を得られるようになりましたが、根拠があいまいだったり、情報源が不明確だったり、発信者の信頼性が低いケースも少なくありません。
その点、書籍は出版社や著者が明示されており、手元に残る形ある媒体であることから、インターネット上の情報よりも信頼性が高いと考えられています。
企業の強みである独自の技術や実績、企業としての取り組みなどをストーリーとしてまとめて一冊の書籍という形で出版すれば、書籍そのものの信頼性や出版社の全国的な販路を活かした効果的なマーケティングが可能になります。
▶︎企業出版(ブックマーケティング)については、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】も合わせて参考にしてください。
企業出版を実施するメリット
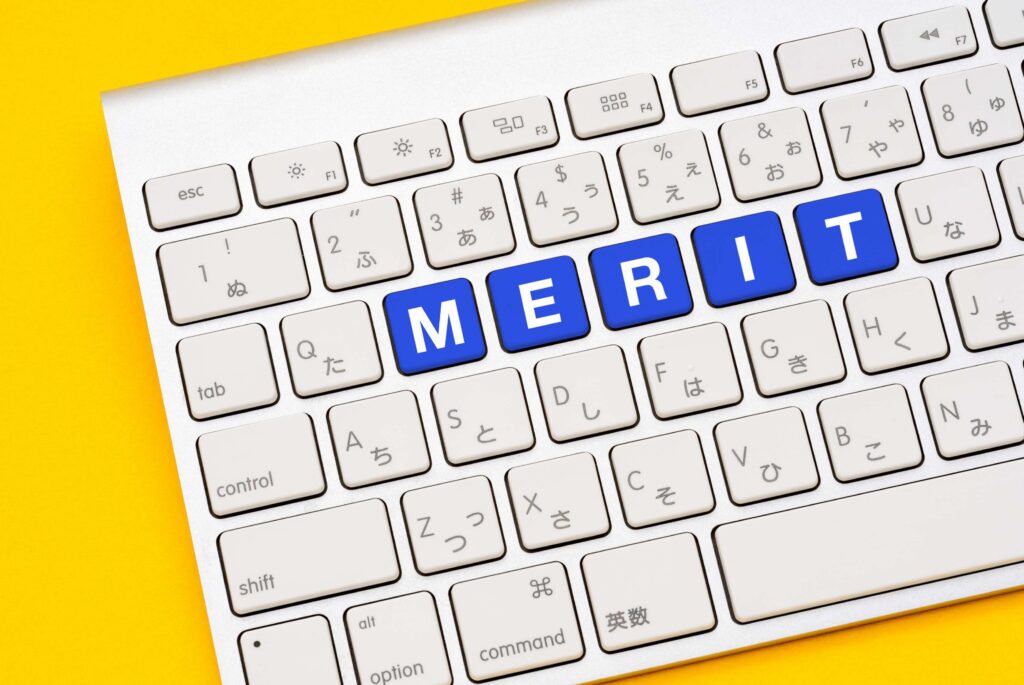
企業の商品やサービスをPRするうえで、世の中にはさまざまな広告手法があふれています。
そんななかで企業出版という形式だからこそ得られるメリットを紹介します。
自社商品やサービスを知ってほしいターゲットに認知拡大できる
世間一般的に認知度を上げるのに手っ取り早いのは、テレビCMや全国紙の新聞広告掲載です。
それぞれかなりの視聴者や購読者がいる媒体なので、認知度を上げるには最適でしょう。
ただし、こうしたマス媒体への広告は1回あたりの負担額が数百万〜数千万円と高額で、しかも広告を打ち続けないと効果は持続しません。
一方、企業出版の広告宣伝の場は書店にある各書棚になります。
先述した通り、狙ったターゲットに知ってもらえる理由の一つです。
たとえば、不動産投資会社が潜在顧客に自社を知ってほしければ、書店の「不動産投資」や「資産形成」の棚に並べることで、自ずと手にとってもらえます。
耳鼻科のお医者さんが耳の病気に関する書籍を出版すれば、耳の病気に悩む人が立ち寄る「家庭の医学」の棚に展開されます。
このように、知ってほしいターゲット層に認知してもらうには企業出版が適しているのです。
企業出版で医者というターゲットへの認知拡大に成功した事例
不動産投資会社が、収入も納税額も高額な医師をターゲットに「不動産投資が医師の節税対策に最適」という内容の書籍を出版しました。
書籍を購入した医師に、不動産投資に大きな節税効果があることを認知してもらうことができ、多くの成約につながりました。
競合に対する優位性を高め信頼度も向上する
書籍は出版社から取次会社を介して書店に流通し、値段をつけて販売されます。
「書籍を出版している企業」という事実により、競合企業に比べた優位性を高められ、信頼度が向上するのです。
書籍を活用した情報発信でその道のプロフェッショナルとして認知してもらえ、社会的な信用が上がり企業ブランディングに貢献します。
競合他社が多い中、確固たる地位を築いた保険代理店
ある保険代理店は、保険業界の問題点とそれを変えるための持論をまとめた書籍を出版。
競合が多く差別化が難しい業種にもかかわらず、業界内での地位確立と顧客企業からの信頼を獲得し、大きく業績を伸ばしました。
他媒体に比べて圧倒的な情報量を誇る
さまざまな広告手段のなかでも、書籍の持つ情報量は圧倒的といえます。
テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、看板……広告のどれと比較しても、書籍ほどの情報量を盛り込める媒体はないでしょう。
書籍一冊でおよそ200ページの量があり、文字の組み方によって変わりますが、文字数にすると7万〜10万字もの情報を発信できるのです。
企業の商品やサービスの魅力だけでなく、企業理念や代表者の考え方などを余すことなく伝えることができる稀有な媒体といえるでしょう。
質の高い顧客からの問い合わせが獲得できる
書籍制作をするにあたって最初に考えるのが、「出版の目的」です。
集客を目的にする場合、自社商品やサービスが見込み客にとってどうメリットになるのかを整理していきます。
マーケティング戦略の基本であるペルソナの設計を、書籍企画づくりの中で同時に行うことができるのです。
先に解説した通り、書籍は信頼度の高い媒体ということもあり、自らが欲する情報が掲載された書籍を読むことで、読者ならびに見込み客から著者の会社に問い合わせするという導線を作ることができます。
著者のファンになった読者は自社ビジネスの内容を理解しているため質の高い顧客となり、商談も簡略化することができます。
このように企業出版は、一冊出版するだけで、他の広告媒体にはなし得ない認知度拡大や啓蒙、集客力向上、そしてブランディングを同時に達成できます。
ニッチな業種でありながら、質の高い問い合わせ獲得につながった事例
建設業専門のコンサルティング会社は、知名度の向上と商圏の拡大を狙って書籍を出版。
タイトルに「建設業のための」というフレーズを盛り込んだことで、ターゲット層への訴求力が高まり、問い合わせが相次ぎました。
最終的に10件以上の顧問契約を獲得し、毎年数百万円の売上を得る結果につながりました。
企業出版による副次的効果とは

ここまでは、企業出版をすることで実現できるわかりやすいメリットを紹介してきました。
次に、出版という手段だからこそ発揮される副次的な効果を解説します。
・著作権が企業側に帰属するため二次活用ができる
・営業ツールとしての活用で囲い込みやクロージングに役立つ
・社員教育や採用強化に活用できる
・メディアに取り上げられる可能性が高まる |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
著作権が企業側に帰属するため二次活用ができる
企業のマーケティング戦略の一環として出版を実施する以上、無視できないのが著作権です。
著作権とは、書籍出版においては書籍の原稿や写真、イラストなど、著作物を保護するための権利です。
知的財産権の一つで、著作物を著作権者以外に無断で使用させない権利でもあります。
企業出版においては、ライターが取材して原稿執筆するケースが一般的ですが、ライターは著作権を放棄し、出版契約した企業側に著作権が帰属するのが基本です。
なかにはイラストや写真など、各コンテンツに応じて著作権が制作者側に帰属しているケースがあるため、使用の際は確認が必要ですが、基本的に原稿については自社の判断で二次利用ができます。
昨今はCookieの規制が強化されるという話題もあり、オンライン上のGoogle広告やSNS広告が利用できなくなる可能性も考えられます。
WEB広告でアクセスを集められなかった場合、SEO対策として自社サイトのコンテンツを強化する重要性はますます増すでしょう。
そこで書籍があれば、コンテンツをホームページや自社オウンドメディアに転載することで、SEO対策としても活用できるのです。
ただ、出版権や所有権については契約での取り決めがあるので、各出版社に問い合わせてみましょう。
営業ツールとしての活用で囲い込みやクロージングに役立つ
書籍が完成すれば、手元に営業ツールとして活用できる書籍が届きます。
活用の仕方は幅広くさまざまですが、来店した見込み客にプレゼントとしてお渡しすることで、信頼性を向上させ、サービスや会社に対する理解度を促進させることができます。
セミナーを開催して販売や配布するという手段も考えられるでしょう。
競合他社との相見積もりになった際に、書籍を送ることでクロージングツールとして効果を発揮したという例も珍しくありません。
ほか、見込み客のリストや過去名刺交換をしたような掘り起こし顧客にDM(ダイレクトメール)として送付するという活用方法も有効です。
社員教育や採用強化に活用できる
企業出版で制作する書籍には代表者の考え方やサービスのメリットが網羅されていることもあり、採用や人材育成に効果を発揮します。
企画内容によりますが、企業が成長するまでにぶつかった壁やそれを乗り越えた方法など、事業拡大するまでの紆余曲折を、これから入社する新人にも知ってもらうことができるのです。
会社がどのような考えをもって経営しているのかを新人が理解できれば、ミスマッチの防止に役立ち、採用後の定着率アップにも大きく寄与します。
メディアに取り上げられる可能性が高まる
企業出版による書籍は、単なる紙媒体としてではなく、企業の広報戦略としても効果を発揮します。
企業名や商品・サービスが新聞や雑誌、WEBメディアなどの第三者視点で紹介されると、広告とは異なる信頼性の高い認知拡大が期待できます。
また、メディア掲載は一時的な広告効果にとどまらず、企業の実績として蓄積されるため、今後のブランディングや営業活動、採用活動などのさまざまなシーンで活用可能です。
企業出版と他の発信施策の比較

続いて、企業出版と他の発信施策の特徴を比べてみましょう。
「紙媒体広告」「WEB広告」「WEB媒体施策」との比較は以下の通りです。
紙媒体広告との比較
まず、新聞や雑誌といった紙媒体への広告出稿を見てみましょう。
紙媒体の広告はその発行部数の多さを活かし、数万〜数百万の人々にリーチできる点が大きな強みです。
一方で、紙媒体は基本的に広告出稿される号が世に出た瞬間にのみ、効果を発揮する施策となります。
効果の長期的継続はありません。
さらに、出稿によってもらえる枠は限られており、盛り込むメッセージはかなり取捨選択しなければいけません。
書籍の場合は、書店流通によって広告効果が持続的に発揮されるのが紙媒体広告と比較した際の強みです。
さらに、詳細な情報や専門知識を一冊分盛り込めるため、読者に対してより深い理解や感動を与えることができます。
説明が難しい製品や、販売に時間がかかるサービスにとっては適した発信手段です。
WEB広告との比較
WEB広告はご存じの通り、費用を投じている間のみ広告が回ります。
メリットとして、少額でも始められること、詳細にデータが出ることで細かな改善アクションを繰り返しやすいことが挙げられます。
一方、実物がある紙媒体以上に「残らない」広告施策であるところが難点。
「先につながらないのはわかっているけど、広告止めると売上落ちるから止められない…」と悩む経営者は多いです。
企業出版では紙媒体との比較同様、長期間にわたって読者に提供されて持続的な効果が期待できる点がポイントになります。
また、本によって読者の関心を引きつけるコンテンツを提供することができるため、たとえば「WEB広告で集客した見込み客に書籍をプレゼント」といった組み合わせ施策で受注確度を高める戦略は効果的です。
WEB媒体施策との比較
WEB媒体施策はWEBメディアに対する記事広告出稿や、自社サイトでコンテンツを発信するオウンドメディア施策を指します。
WEBメディアの記事広告はずっと掲載してもらえる場合があり、自社サイトコンテンツも長期的に掲載される点は大きなメリットです。
一方でWEBコンテンツはどうしてもユーザーが軽い気持ちで閲覧する傾向にあり、問い合わせなどの反響につなげるには相当クオリティの高いコンテンツを自社で作る必要がある点がハードルになります。
また、WEBコンテンツの閲覧者と書籍の読者はかなり層が違うため、こちらもターゲットや目的によってうまく併用することが成果を出すコツです。
この点に関して著者がよく言っているのは、「WEBは良くも悪くも関心がライトで発注権限も予算もないようなリードが多いが、本の場合は“本気の人”が来る」ということです。
このような特性から、特に高単価な商品・サービスは、書籍との相性が良く、強力な集客・販促手段となる可能性があります。
【業種別】企業出版の成功事例

世の中の多くの出版支援サービスは、商業出版を主とする出版社が「副業」として提供しているものが大半です。
つまり、「本業はあくまで売れる本を作ること。出版したいなら費用を払ってくれれば対応します」という姿勢が根底にあるケースが少なくありません。
そうした構造上、顧客のために尽くす体制が築きにくいのが現実です。
それに対して、私たちフォーウェイでは企業出版に「本業」として取り組んでいます。
「顧客のために作り、顧客のために売る」ことを使命に掲げた体制を最初から構築しており、企業出版そのものに真剣に向き合っています。
実際に、業界最多クラスとなる230冊以上の企業出版実績を誇る編集チームがそろっていることが強みです。
在籍するメンバーは全員が、大手出版社の書籍制作を手がけてきた実力派クリエイター。
デザイナーやライター、校正者といった各専門分野においても、複数のベストセラーを生み出してきたトップレベルの人材で構成されています。
そのため、自費出版では実現が難しい、完成度の高い書籍づくりが可能です。
以下では、実際に企業出版を通じて成果を上げた10件の事例を紹介します。

保険代理店|出版を通じて業界内の信頼を獲得し、採用・新規契約数を大幅に向上させた事例
本業とは別に新規事業としてコンサル事業を立ち上げた保険代理店では、有効な集客手段が打てず信頼性獲得のためのブランディング施策を探していました。
そこで、成果報酬型が当たり前の保険業界で、一律報酬型を採用して成⻑を遂げた自社のノウハウをまとめ、保険代理店の経営者が読みたくなる企画・構成の書籍を出版しました。
出版後わずか2週間で重版が決定し、Amazonでは一時的に在庫切れとなるほどの反響を獲得。
出版記念セミナーには60名が参加し、複数のコンサル契約へとつながりました。
また、大手保険会社から講演依頼の増加にもつながっています。
さらに、自社での人材採用にも大きな効果があり、応募者が事前に読んでくれて自社への理解が進み、採用のミスマッチがなくなりました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
不動産会社|医師という専門層に向けた戦略的出版で高確度のリードを獲得し、売上10億円に貢献した事例
ある不動産投資会社では、Web広告による新規顧客の集客を行っていたものの効果がなく、ほぼ紹介に頼っている状況でした。
紹介の場合でも信頼関係構築に多くの時間を要し、成約リードタイムが長くなってしまうという問題がありました。
そこで、医師をターゲットとして「節税対策に不動産投資が効果的」という内容の書籍を出版したところ、多くの読者から問い合わせがあり、出版6か月で10億円以上の売上を達成。
問い合わせのほとんどは書籍を読んだ医師からだったため、成約までのリードタイムが短縮でき営業効率も向上しました。
さらに、同じ顧客が複数の物件を購入してくれるなど、通常の営業に比べて客単価が大きく向上したことも大きな効果でした。
建設会社|経営者の人間力を本で可視化し、採用コストゼロを可能にした事例
湘南エリアで業績拡⼤中の建設会社では、慢性的な⼈材不⾜により受注チャンスを逃してしまうことが課題でした。
そこで、若⼿人材の採用強化とブランド力向上を狙って書籍を出版。
経営者の仕事や経営に関する考え⽅や人柄、創業ストーリーなどを余すところなく盛り込んだ書籍にしました。
出版後、応募者の多くが事前に書籍を読んでから応募するようになり、企業への理解度が高まった結果、採用決定率が大幅に向上。
年間500万円以上かかっていた採用エージェントの費用をゼロに抑えることができました。
地元新聞など複数のメディアからの取材依頼があり、狙いどおりの認知アップ効果を実感したといいます。
若手経営者である社長は、これまで地域の同業他社との関係性に課題を感じていましたが、出版を機に一目置かれる存在へとブランディングに成功しています。
経営コンサル|書籍出版で新しい層にアプローチし、指名相談が急増した事例
建設業専門の経営コンサルタントは、これまで届いていなかった新たな層へのアプローチを目的に書籍を出版しました。
これまでの支援実績やノウハウをわかりやすく整理し、自身の思いや考え方も盛り込んだ一冊に仕上げました。
出版後はわずか1か月で重版が決まり、17媒体のWebニュースに掲載されるなど反響を獲得。
新たに10数件の顧客が増え、若手経営者からの育成相談も急増しました。
ブランド力を高めながら、顧客の接点を作り出すことができています。
食品メーカー|わさびの効果・効能を発信し、販促と啓蒙を両立させた事例
わさびの製造販売を行う企業では、「わさびの魅力が十分に伝わっていない」「他社との差別化が図れていない」といった課題を抱えていました。
そこで、料理に関心の高い30〜40代女性をメインターゲットに、わさびの効能や歴史、アレンジレシピを紹介する書籍を企画・出版。
発売後には、レシピを監修した料理研究家を招き、本社所在地・名古屋の書店で出版記念トークイベントを開催しました。
会場は満席となり、当日だけで50冊以上の売上を記録するなど、認知拡大とファン獲得につながっています。
その後、出版をきっかけに平均聴取者数20万人を超えるラジオ番組から2週連続の出演オファーがありました。
さらに、自社営業マンが取引先への配布やプレゼンで活⽤し、⼤⼝取引の獲得のきっかけにもなりました。
健康ビジネス|Amazon1位を獲得し、会員数が500人増加した出版プロモーション事例
健康ビジネスを展開する企業は、耳ツボダイエットの魅力を広く伝えるために書籍を出版しました。
全国書店への配本とWeb広告を組み合わせたプロモーションを行い、Amazon「ビジネス実用書」カテゴリで1位(総合3位)を獲得しました。
また、書籍特設LPでは、既存会員の声を紹介し、見込み会員への信頼構築と紹介促進を実現。
出版後には大規模なセミナーも開催し、結果として半年間で新規会員が500人以上増加するといった、ブランディングと集客の両面で成果を上げました。
美容食品企業|書籍が既存顧客の理解と共感を呼び、リピート率が向上した事例
ある美容食品企業は、商品販促と自社のブランディングを目的に書籍を出版しました。
中年期以降の⼥性をメインターゲットに、「⼀⽣のうちで変化の多い「⼥性の⼈⽣の悩み」を解決する」をコンセプトとしたことから、既存顧客がファン化してリピート購入が増加しました。
発売前からSNSを活用した告知を強化した結果、予約が殺到し、発売前に重版が決定。
また、メディア出演や講演依頼も相次ぎ、認知拡大に成功しました。
既存顧客への書籍プレゼント企画では、予想の8倍以上の応募があり、書籍を受け取った顧客の半数以上が継続購入へとつながるなど、高い販促効果を発揮した事例です。
写真館|書籍で経営ノウハウを発信し、セミナー依頼と過去最高売上を実現した出版事例
写真館の経営者は、経営のノウハウの啓蒙及び写真館と自身のブランディングのために書籍を出版。
利⽤者の減少によって年々姿を消している個⼈経営の写真館の現状を伝え、厳しい業界で⽣き残ってきた秘訣を提⽰して読者からの信頼を得る書籍構成にしました。
兵庫県と⼤阪府、東京都をメインに配本を実施したところ、地元の⼤型書店でランキング1位を獲得、写真館経営者だけでなく他業界の経営者からも経営相談の問い合わせが相次ぎました。
さらに、セミナー依頼が⼤幅に増加し、新型コロナによる休業要請後の営業再開時には3か月連続で過去最⾼売上を更新するという快挙を成し遂げました。
ITサービス|難解な技術を体験で伝え、RPA分野での信頼と受注を得た出版事例
ITサービス企業の代表者が、中⼩企業経営者にとって読みやすいRPAシステムの⼊⾨書を出版。
自身の体験談や解説、コラムを各章に盛り込み、読みやすさを追求しました。
商圏に合わせた⼀都三県、⼤阪、名古屋、中⼩企業の多い地⽅(広島、福岡、熊本)を中⼼に展開し、ビジネス層からの問い合わせ獲得を狙いました。
出版直後から複数の問い合わせが発生し、1か月で2件の受注を獲得。
さらに、全国からセミナー依頼が殺到し、企業のブランド⼒の強化にもつながりました。
採用コンサル|理念に共感した人材を自然に引き寄せ、商談件数が10倍になったブランディング事例
人材採用コンサルタントは、⼈材獲得に悩む中⼩企業経営者を意識したタイトルの書籍を出版し、類書と異なるデザインで差別化に成功しました。
サラリーマンが多く⽴ち寄る駅構内の書店に重点配本して3書店でランキング1位を獲得。
出版後は商談件数が前年⽐10倍、成約率も約9割となり、本とは「⼤きなエネルギーをもった名刺のようなもの」と、効果を実感しました。
内容を理解した上で商談が始まるケースが多く、商談の効率化にもつながりました。
好調な売れ行きを受けて重版が決定し、反響が続いています。
企業出版の費用相場

企業出版は、1,000万円以上が費用相場です。
他の出版方法と比べると、以下の通りです。
| 自費出版 | 商業出版 | 企業出版(通常) | 企業出版(ブックマーケティング) |
| 費用 | 250〜500万円程度 | 0円(出版費用は出版社が負担する) | 1,000万円以上 | 500〜800万円程度 |
なお、1,000万円以上というのは一般的な費用相場であり、依頼する企業によって費用は異なります。
フォーウェイでは、一般的な企業出版とは異なり、企業のマーケティングの一環として書籍を活用していく新しい企業出版サービス(ブックマーケティグ)を500〜800万円の価格帯で提供しています。
フォーウェイのブックマーケティンング(企業出版)では、企業のマーケティング規模に合わせた最適な価格での企業出版をご提案可能です。
企業出版の価格に影響する要素として、以下が挙げられます。
| 企業出版の価格に影響する要素 | 詳細 |
| 書籍の仕様 | ・通常仕様は四六判(130mm×188mmサイズ)、中面白黒で200ページ程度・仕様変更(大きな判型、中面カラー、ページ数の増加、写真やイラストを入れるなど)の場合は追加費用が発生する |
| 部数 | ・部数が多くなればなるほど印刷費用が高くなる・部数が増えると流通拡大による書店営業経費が加算される・返品による損失のヘッジ分も加算される |
| 制作費用 | ・基本的な費用は人件費のため、ライターが必要か、持ち込み原稿かにより大きく異なる・編集者の出張や取材先が多岐にわたる場合も追加費用が発生する |
| プロモーション費用 | ・基本的に書店やメディアへのリリース、書店営業は基本費用の範囲内となる・WEB広告、新聞広告、イベント実施などは追加費用が発生する |
基本的に値段が上がるほど出版社の規模が大きくなり、流通部数も多くなると考えてください。
どの価格帯での出版が最適かは、出版の目的や自社の事業規模に応じて判断する必要があります。
なお、費用を抑えるための工夫として、原稿を自社で用意することで料金の調整に応じてもらえるケースもあるので、出版社に確認をしてみましょう。
企業出版の流れ

実際に企業出版を行う場合(※ライターに原稿を書いてもらう場合)、流れは以下のようになります。
| ステップ①:企画立案 | 出版の目的やターゲット読者を明確にし、内容やテーマを決定します。企画段階では、書籍の仮タイトルや章立てを作成します。 |
| ステップ②:取材・執筆 | 著者本人や著者の会社の社員へのインタビュー取材を行い、必要な情報を収集します。取材データをもとにライターが執筆作業を進め、章ごとに文章をまとめていきます。インタビューは一冊分で合計10時間程度になることが多いです。 |
| ステップ③:編集・校正 | 執筆された原稿を、著者と編集者で協力して校正(チェック)します。文章のクオリティや表現を整え、誤字脱字や文法の修正なども行います。 |
| ステップ④:デザイン・レイアウト | 書籍のデザインやレイアウトを決定します。カバーデザインについては、いくつかの候補から最終的に著者が選ぶパターンが多いです。使用してほしい色や求めるテイストがあれば、事前に担当編集者に伝えておきましょう。 |
| ステップ⑤:印刷・製本 | カバーと本文が完成したら、印刷所に原稿を送り、書籍の印刷と製本を行います。ここまで来たら、著者は刷り上がりを待つだけです。印刷が完了したら、いよいよ書店に書籍が並びます。 |
一方で、弊社フォーウェイが展開する企業出版(ブックマーケティング)は、単なる書籍の発行にとどまりません。
中小企業から大企業まで、法人としてさらなる認知度や知名度の向上を目指す企業に対し、次のステージへと進むための後押しをするプロモーション施策として展開しています。
その流れは、以下の通りです。
| ステップ①:目的・ターゲットの確認 | 出版によって企業が達成したい目的やターゲット読者層を確認します。たとえば、集客強化、信頼構築、ブランディング、新規顧客開拓などの具体的なゴールを定めます。 |
| ステップ②:書籍企画設計図の作成 | 書籍出版の目的を達成するために、クライアント企業の業務内容や強み、提供価値を丁寧にヒアリングし、企画骨子を設計図としてまとめます。 |
| ステップ③:書籍企画案の作成 | 設計図を基に、より詳細な企画案へと深化させます。全体の構成や仮タイトル、目次案などを企画書として作成します。 |
| ステップ④:取材・執筆 | 著者や関係者へのインタビューを通じて取材し、その内容をプロのライターが書籍原稿として執筆します。次のステップ⑤のカバー作成と並行して、執筆原稿の赤字入れなどをクライアント企業側に行ってもらいます。 |
| ステップ⑤:カバー作成 | 複数のデザイン案を作成し、著者と相談しながら最適な表紙デザインを決定します。色使いやイメージのテイストもここで反映されます。 |
| ステップ⑥:プロモーション戦略策定 | 書籍発売に向けた広報・販促施策を計画。書店営業戦略、Web広告、SNSや動画を活用したPRなど、多チャネルでの戦略を構築します。 |
| ステップ⑦:書店営業・広告戦略実施 | 取次・書店へ営業をかけ、配本戦略を組み立てます。。オンライン・オフライン両面で広告出稿やSNS連動キャンペーンなどを企画します。 |
| ステップ⑧:出版 | 印刷・製本が完了し、書店に並び始めます。出版日はメディア露出や販促活動の起点となります。 |
| ステップ⑨:出版後の施策実施 | 重版対応、SNS運用支援、クラウドファンディングやウェビナー連動キャンペーン、Web広告による販促継続、成果測定を含むトータル支援を行います。 |

企業出版の失敗事例と成功のポイント

生涯に一度かもしれない企業出版、絶対に成功させたいのは著者として当然でしょう。
成功のポイントをつかむために、企業出版にありがちな失敗事例を6つ紹介します。
・失敗事例①出版目的が絞られていない
・失敗事例②ターゲット読者の選定ミス
・失敗事例③広告的な内容にしすぎる
・失敗事例④ターゲットに合わないデザイン
・失敗事例⑤出版後の活用戦略がない
・失敗事例⑥出版社・パートナーの選定ミス |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
失敗事例①出版目的が絞られていない
企業出版では、「何のために誰に向けて出版するのか」がしっかり定義されていてこそ、クオリティの高い企画ができます。
「集客にも採用にも個人ブランディングにも効かせたい」「若者にもシニア層にも届けたい」など欲張りすぎると、読者から見て役立つ本であると伝わりづらくなってしまいます。
特に企業出版は、一定のコストをかけて取り組む施策であるため、高単価な商材・サービスの集客手段として活用することがおすすめです。
WEB広告などでは良さが伝えづらく、比較検討されにくいサービスこそ、企業出版の本領が発揮される領域です。
出版の目的や届けたい相手像が明確であればあるほど、タイトル、構成、原稿のトーンすべてに一貫性が生まれ、クオリティの高い企画に仕上がります。
失敗事例②ターゲット読者の選定ミス
企業出版では、ターゲット読者のニーズや興味に合わせた出版物を提供することが重要です。
たとえば、マーケティングの初心者向けに書籍を出版したいのに、コトラーのマーケティング理論などを完璧に理解していないとわからないような高度な内容で本を書いても、ミスマッチになってしまいます。
加えて、そもそも本を読まない層をターゲットにしてしまうミスもあります。
一例として10代女性などは、ファッション系やタレントものなどでない限り、出版してもほとんど本を買ってもらえないので注意しましょう。
失敗事例③広告的な内容にしすぎる
読者のニーズを意識せず、自社の情報や宣伝ばかりを強調した内容にしてしまうのも、よくある失敗ケースです。
せっかく費用を投じての出版なので、著者として自社を存分に宣伝したいのは当然です。
ただし、書籍は読者が対価を払って購入する媒体であることを忘れてはなりません。
「広告だ」という認識で読者は本を手に取っていないので、著者の宣伝色が強すぎるとかなり違和感をもたれます。
「伝えたいこと」を「価値あるコンテンツ」に変更するためには、編集者を使い倒すのがコツです。
失敗事例④ターゲットに合わないデザイン
カバーをはじめとするデザインを選ぶうえでは、「ターゲットの好み」に合わせるのがとても重要です。
よくやってしまうのが、著者が「自分の好み」でデザインを指定してしまうパターン。
著者の好みがターゲットの求めるデザインに合致するとは限らず、自分の好みを優先しすぎると、違和感のあるデザインになってしまいます。
それを避けるため、どうしても譲れない部分は伝えつつも優秀な編集者の提案に任せたほうが出版効果は見込みやすいでしょう。
失敗事例⑤出版後の活用戦略がない
出版したことで満足してしまい、その後の活用について検討されていないという失敗ケースもあります。
せっかく完成度の高い書籍ができても、次のように販売促進やリード獲得、信頼獲得の導線が作られていないと効果が限定的になってしまいます。
・営業資料として配布していない
・ホームページで紹介していない
・セミナーや展示会で使っていない |
企業出版は「出したら終わり」ではなく、むしろ出版後の活用次第で成果に差が生まれるため、きちんと戦略を練っておくことが大切です。
失敗事例⑥出版社・パートナーの選定ミス
出版社の実績や得意ジャンル、自社との相性を見極めずに契約してしまうことも失敗ケースとしてあります。
その結果、「出版後の反響がほとんどなかった」「原稿のブラッシュアップが不十分だった」といった問題が起こります。
出版社ごとに得意なジャンルや販売ルートや編集スタイルがあるため、契約前の実績確認や出版目的の共有が必須です。

企業出版に関するよくある質問
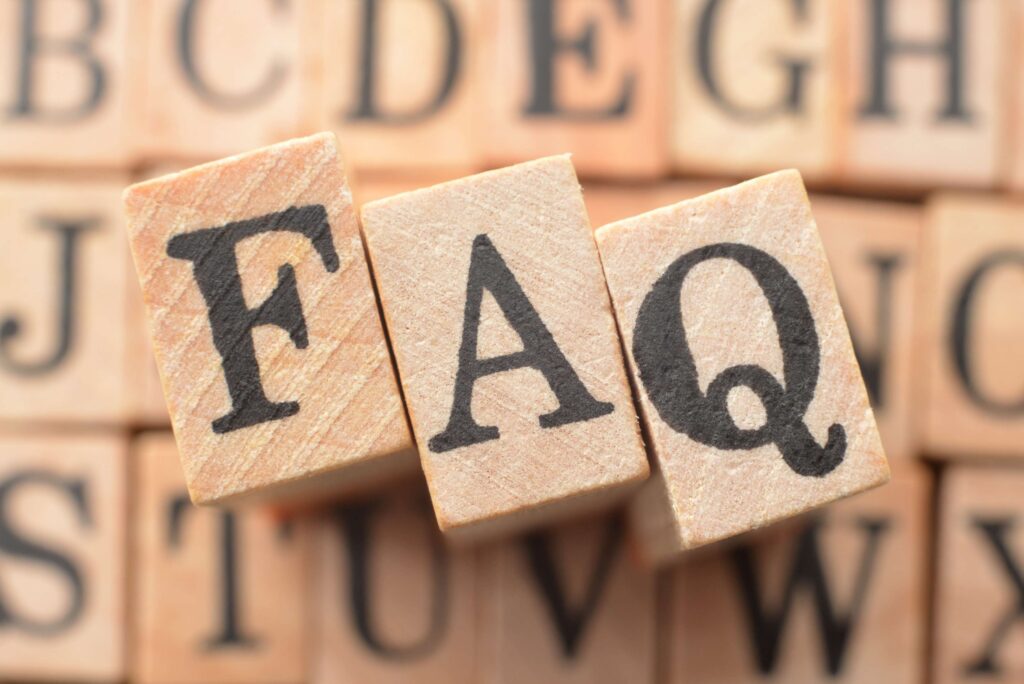
ここでは、企業出版の際に、弊社フォーウェイによく寄せられる質問の中から代表的なものを4つ紹介します。
企業出版までにどれくらいの期間がかかりますか?
企業出版には、全体で8か月程度の期間を見込んで進行します。
主な流れは、以下の通りです。
1. ヒアリング企画立案
2. 取材・原稿執筆
3. 原稿チェック
4. カバーデザイン
5. プロモーション戦略
6. 印刷・製本
7. 出版 |
制作期間については、企業の目的や事業フェーズに応じて、ご相談いただけます。
文章が書ける人間が社内にいないのですが、企業出版をすることは可能ですか?
フォーウェイでは、大手出版社での書籍制作経験が豊富なプロのライターが原稿を担当します。
忙しい著者に代わって、取材インタビューを基に構成・執筆を進めるので、文章作成に不安がある場合でも安心して出版できます。
本を書いてくださるライターの方との相性や文章のクオリティが不安です。
フォーウェイには、大手出版社の書籍案件を手がけた経験を持つ編集チームが在籍しており、専門ジャンルに強く、品質の高い原稿を担保します。
アサインするライターは、副業のWEBライターではなく、書籍制作の実績が豊富なプロフェッショナルを厳選。
提携ライターは200〜300名にのぼり、幅広い業種・業界の書籍に対応できる体制を整えています。
そのため、専門性の高いテーマや独自性のある企画であっても、安定したクオリティの原稿制作が可能です。
企業出版後もサポートは受けられますか?
フォーウェイでは、出版後の販促活動(Web広告出稿、書店プロモーション、SNS運用代行など)までトータルサポートします。
一般的な自費出版では、出版後の販促活動は基本的に著者自身の努力に委ねられがちです。
それに対して、フォーウェイの企業出版は「出版して終わり」ではなく、「出版した後まで徹底サポート」という考えのもと、出版後の展開にも責任を持って取り組んでいます。
【まとめ】企業出版でさらなる企業成長を実現しよう
この記事では、企業出版(ブックマーケティング)とは何かをはじめ、メリット・デメリット、ブックマーケティングの最新トレンドなどについて紹介しました。
企業出版は、しっかりしたパートナー出版社と戦略的に取り組めば、投資対効果としてほかの施策ではあり得ないほどの効果が見込めます。
上記のコラムを参考に、企業出版という選択肢をぜひ検討してみてください。
ブックマーケティングを活用すれば、ただ書籍を出版するだけでなく、その書籍を自社のブランディング、認知度や購買意欲向上などに積極的に役立ていくことができます。
主に次のような方にブックマーケティングは最適です。
・Web広告やSEOなどあらかたの集客施策をすでに行っているが、なかなかそれ以上の集客効果が得られないと悩んでいる中小企業
・難しすぎてWebではなかなか集客できないようなビジネスモデルをお持ちの経営者様
・ある程度事業も安定しているが、更なる成長をするための打ち手に困っている経営者様 |
そんな方は、新たな成長の一手として、ブックマーケティングの活用をご検討ください。


企業戦略においてマーケティングとブランディングが重要なのは周知の事実でしょう。
一方、その違いを明確に答えられる人は少ないかもしれません。
本記事では、マーケティングとブランディングの違いを紹介し、それらが経営戦略上どのように影響を及ぼすかを解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
◉マーケティングとブランディングとは

「マーケティング」と「ブランディング」は企業が商品やサービスを販売し、存続し続けていく上で必要不可欠な活動です。
まずは、マーケティングやブランディングについて、それぞれがどのような活動を指すのかを正しく把握しておきましょう。
◉-1、マーケティングとは何か
マーケティングとは、自社の商品やサービスを効率的に売るために行う活動全般のことを指し、「市場をつくる」という意味があります。
たとえば、市場調査や商品企画、価格設定、流通・販売チャネルの構築、広告宣伝、顧客の声のフィードバックなどの活動が含まれます。
商品やサービスを売るためのあらゆる活動がマーケティング活動に該当すると考えてください。
◉-2、ブランディングとは何か
ブランディングとは、自社や自社の商品・サービスそのものの価値やイメージを高めようとする活動のことで、顧客の頭の中に自社やサービスへの良いイメージを作ってもらうことを目的としています。
たとえば、ブランディングに成功している代表的な企業がiPhoneなどで有名なアップル社でしょう。
アップル社と聞けば、「こだわり抜かれたデザインや革新的な商品を出す会社」「創業者のスティーブジョブズの妥協なきものづくりの精神が根付いた会社」といったイメージを持つ人が多いと思います。
このようにアップル社に対する良いイメージが消費者に浸透しているため、たとえアップル社の出した商品が、他社よりも性能が劣っていたとしても、多少価格が高かったとしても、「アップル社の商品が欲しい」と選ばれるようになります。
このように、自社や自社の商品・サービスに良いイメージを持ってもらうための活動全般がブランディングです。
▶️企業ブランディングについては、関連記事【企業ブランディングとは?企業の成長における重要性や手法を徹底解説】もあわせて参考にしてください。
◉-3、リブランディングとは何か
リブランディングとは、今までに作り上げてきたブランドを再構築すること、およびその戦略のことです。
時代の変化や、消費者の価値観の変化、競合他社の成長などにより、古くなってしまったブランド価値を刷新するために行います。
具体的なリブランディングの方法としては、ターゲットの見直しや、ロゴ変更、パッケージデザインの刷新、コーポレートサイトの刷新などがあります。
たとえば、リブランディングに成功した代表的な企業がユニクロを運営するファーストリテイリング社です。
ユニクロはかつて2000年代後半に、「ユニクロとばれると恥ずかしい(ユニバレ)」という言葉が浸透するほど、安かろう悪かろうなイメージが定着していました。
しかし、メイドインジャパンを強調するロゴマークの刷新や、それと連動した世界各地の店舗デザインや商品企画、プロモーション戦略の刷新を実施。
見事に今現在のような「高品質の商品を低価格で提供するジャパンブランド」としてのリブランディングに成功しています。
時代の移り変わりが激しい時代だからこそ、時代に沿ったニーズに柔軟に適応していくために、ブランディングと共に重要視されているのがリブランディングです。
◉-4、PRとは何か
PRとは、「Public Relations(パブリック・リレーションズ)」の略語で、直訳すると「公衆との望ましい関係づくり」という意味です。
PRは宣伝や広報よりも広い概念で、自社の情報を広く社会に周知する活動全般を指します。
たとえば、「プレスリリース」「オウンドメディア」「社内報」「メディア対応」などが主なPR活動です。
よくマーケティングと混同されることもありますが、そもそもPRとマーケティングは目的が違います。
PRは企業価値の向上や認知度の拡大、マーケティングは商品・サービスの販売促進を目的としています。迷ったら「どんな目的で行うのか?」で見分けましょう。
また、PRはブランディングで形成されたイメージを元に実施されるのが一般的です。
そのため、ブランディングの延長線上にPRがあると考えてください。ブランディングで良いイメージを構築し、PRでさらにそれを広く社会に周知していくというのが一般的な流れです。
◉マーケティングとブランディングの違い

マーケティングとブランディングの違いは主に次の5つです。
- ・その1:目標
- ・その2:意義・方針
- ・その3:ニーズ・焦点
- ・その4:手段・方法
- ・その5:施策の期間
それぞれについて具体的にどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
◉-1、違いその1:目標
ブランディングとマーケティングはよく混同されますが、そもそも目標とするものが全く違います。
まず、ブランディングは、消費者に自社や自社の商品・サービスに対する良好なイメージを持ってもらうことが目標です。
一方で、マーケティングは、自社の商品やサービスの価値を効果的に訴求することが目標です。
そのため、商品・サービスをとにかく売りたいのであればマーケティング施策を、価格競争などから脱していきたいのであればブランディング施策を選択する必要があります。
「自社の商品を販売したいからブランディング施策を実施する」のは大きな間違いです。
目標とするものが何かによって取るべき最適な施策が異なるので注意しましょう。
◉-2、違いその2:意義・方針
ブランディングとマーケティングには、意義や方針の違いもあります。
ブランディングは、自社の商品やサービスが「どうあるべきか」という社会的存在意義や向かうべき方向性を大きな枠組みで考え続けることです。
時代により消費者の価値観が変わると、自社の商品やサービスに対するイメージも変化することが考えられます。ブランディングは一度考えたら終わりではなく、時代に沿って、継続的に「どうあるべきか」を考え続けることが大切です。
一方で、マーケティングは、自社の商品やサービスを売るために「どうすべきか」を考える具体的な活動方針です。
たとえば、テレビCMなどのマス広告、Web広告、SNSの利用などのプロモーション活動などがこれにあたりますが、商品やサービスが変われば活動方針も施策もガラリと変わります。
このように、大きな枠組みの中で存在意義や方向性を考え続けるのがブランディング、その土台の上で「自社の商品やサービスをどう売っていくのか」という具体的な活動方針を考えるのがマーケティングです。
◉-3、違いその3:ニーズ・焦点
ブランディングとマーケティングには、ニーズや焦点の当て方に違いがあります。
ブランディングは、自社の強みをターゲットの消費者に訴求して、「このブランドを選べば間違いない」というイメージを持ってもらうことに焦点を当てます。
つまり、焦点は自社です。
一方で、マーケティングは「消費者のニーズは何か」に焦点を当てます。
このように、「自社の強み」と「消費者のニーズ」どちらに焦点を当てるのかが、マーケティングとブランディングの大きな違いです。
また、消費者のニーズが顕在化している場合は、それに応える具体的な商品やサービスを訴求するようなマーケティングを実施します。
一方で、消費者のニーズが潜在的にある場合は、ニーズを深掘りし、自社の商品やサービスで解決できるようなイメージを持ってもらうようにブランディング施策を実施していきます。
つまり、顕在化した消費者のニーズにはマーケティングを、潜在的なニーズにはブランディングを、というように使い分けていく必要があるのです。
◉-4、違いその4:手段・方法
ブランディングとマーケティングには、手段や方法にも違いがあります。
ブランディングを行う際には、消費者の心理形成につながるような手段や方法を採用します。
なぜなら、消費者の心の中に良好なイメージを作ってもらう必要があるからです。
たとえば、消費者に対してのブランディングの場合、印象に残りやすいブランド名やロゴの設定、キャラクターの作成やコーポレートメッセージの作成、サイトの刷新などが主なブランディング施策の方法です。
また、社内に対するブランディングの場合、従業員向けのブランドブックの作成、独自の人事認定制度の創設などの方法があります。
一方、マーケティングでは、商品やサービスに対する消費者の理解や購買意欲向上につながるような手段や方法を採用します。
たとえば、各種広告やオウンドメディアのコンテンツ、SNSでの情報発信、メールマガジンなどを利用して消費者への広告宣伝を行う、などです。
このように、手段や方法も異なるので、混同してしまわないように注意しましょう。
◉-5、違いその5:施策の期間
ブランディングとマーケティングでは、施策に取り組む期間の長さが違います。
マーケティングと違い、ブランディングは長期的な取り組みが必要です。
なぜなら、ブランディングの目標であるブランドイメージを形成するには長い期間を必要とするからです。
一方で、マーケティングが目標とする顧客の購買行動は比較的短い期間で成果が表れます。
たとえば、ロゴを刷新したところで、すぐにその効果は感じられませんが、Web広告に出すページを修正した場合には、その効果はすぐに現れます。
このように、ブランディングとマーケティングはそもそも取り組む期間の長さが違うということを認識しておきましょう。
◉アウターブランディングとインナーブランディング

ブランディングには、大きく分けてアウターブランディングとインナーブランディングの2種類があります。
アウターブランディングとは、社外に対するブランディングのことです。
アウターブランディングの対象には、消費者や取引先をはじめとするステークホルダーのほか、新卒や中途採用の就職希望者なども含まれます。
消費者に自社やサービスに対して良いイメージを持ってもらうのが目的であり、一般的に多くの人が「ブランディング」と認識しているのが、このアウターブランディングです。
また、法人を対象としたビジネスをしている企業が行うBtoBブランディング、一般消費者を対象とする企業が行うBtoCブランディング、自分自身をブランド化して価値を高めるセルフブランディングなどのように、アウターブランディングの中でも細かく種類が分かれています。
一方で、インナーブランディングとは社内向けのブランディングで、その対象には従業員のほか経営層・マネジメント層も含まれます。
たとえば、インナーブランディングとは自社の企業理念やブランド価値、行動指針を従業員に浸透させて共有できるようにする取り組みのことです。
インナーブランディングによって企業理念や行動指針などの理解が深まると、従業員のモチベーションやパフォーマンスが向上し、定着率アップや優秀な人材の確保につながります。
このように企業体質の改善を図り、市場における競争力を企業の内側から高めていくことがインナーブランディングの目的です。
◉ブランディングを行う企業メリット
企業がブランディングを行うメリットは、顧客を自社やサービスのファンにできることです。
ファンが増えることにより、具体的に次の3つのようなメリットを得ることができます。
◉-1、ファン化の促進とリピーター獲得につながる
企業がブランディングに成功すると、ファンになってくれた人が商品やサービスを何度もリピートして購入してくれるようになります。
たとえば、アップル社の新商品販売日に、アップルストアに行列ができている光景をテレビなどで見たことがあるという方が多いのではないでしょうか。このように、企業がファン化に成功すると、消費者が頼んでもいないのに、一生懸命に購入してくれるようになります。
リピート購入とは、広告費用をかけずに購入してもらえるようになる、ということです。つまり、リピート購入が増えれば増えるほど、企業がかける1人あたりの広告費用は減っていきます。
このように、ブランディングにより顧客のファン化が促進し、リピーターが増えると、企業の利益向上が見込めるということです。
◉-2、同業他社との差別化の実現による競争力の強化
ブランディングにより自社や自社の商品・サービスへ信頼感が高まると、ブランド力だけで商品を購入してもらえるようになります。そのため、同業他社との差別化が実現でき、競争力が強化できます。
なぜなら、機能がほぼ同等の商品であれば、価格が多少高めであっても自社の商品やサービスを選んでくれるようになるからです。
たとえば、素材も製法もほぼ同じ商品やサービスがあったとしても、ブランディングを実現することで価格の高い自社商品・サービスを購入してもらえるようになります。
このように、ブランディングに成功することにより、市場における価格や性能の競争に巻き込まれずに、価値を提供することができるということです。
▶️差別化戦略については、関連記事【差別化戦略の成功の秘訣ーメリットやデメリット、成功事例とは!?】もあわせて参考にしてください。
◉-3、ブランド認知度および注目度の向上
ブランディングにより、ブランドの認知度や注目度が高まります。
なぜなら、ブランディングという活動自体が、自社や自社の商品・サービスに良いイメージを持ってもらうための施策だからです。
ブランディングを行ったから必ずブランド認知度や注目度が上がるという訳ではありません。
しかし、自社や自社の商品・サービスの強みや価値を見出し、それを上手く訴求できれば、ブランドの認知度および注目度の向上につながります。
たとえば、ユニクロは商品や店舗で使うロゴの刷新だけではなく、ユニクロの強みである「安くて良い品質のメイドインジャパン」を有名スポーツ選手をアンバサダーにするなど、戦略的に訴求したことによって世界的な認知度向上に成功しました。
また、今ではよく知られる鍋のメーカー、バーミキュラは日本の老舗中小企業「愛知ドビー株式会社」のブランドです。海外のメーカーだと思っていた人も多いのではないでしょうか。
バーミキュラの鍋は、「ホーロー加工された鋳物の鍋なのに、無水調理できるほどの機密性の高さ」という革新的な技術と、技術者の努力に裏付けされた説得力のあるブランドメッセージにより、世界的な認知度向上に成功しました。
このように、ブランディングに成功すると、企業活動自体が注目され、宣伝・販促活動が効果的に行えるようになります。
また、投資家からも注目されるようになり、資金調達も有利に行えるようになるなど、付加的なメリットにもつながります。
◉ブランディングを行うユーザーメリット

ブランディングは企業側のメリットばかりが語られますが、実は企業がブランディングを行うメリットはユーザーにもあります。
具体的には、次の2つのメリットをユーザー側は受けることができるのです。
◉-1、商品・サービスを選択しやすくなる
企業がブランディングを行うことによって、ユーザーは、商品やサービスを選択しやすくなります。
なぜなら、知っているブランドの商品であれば、購入時に迷わなくても済むからです。
たとえば、企業が全くブランディングを行わなかったらどうなるでしょうか。毎回性能や材質、品質などを見て自分自身で見極めていかなければなりません。
自分が欲しいと思っていたものとは違う商品を購入してしまうことも多くなるでしょうし、商品そのものを探す時間が多くかかってしまいます。
このように、企業がブランディングを行うことによって、私たちは自分の欲しいものを短時間で選ぶことができているのです。
◉-2、安心感が得られリスク回避になる
ブランディングは、購入するユーザー側の安心感にも繋がります。
なぜなら、信頼感のあるブランドを選べば、「商品やサービスを購入した後に後悔するのではないか」という不安を感じなくても済むからです。
たとえば、いつも購入しているブランドの食品があると安心して購入することができますが、はじめて購入するブランドの食品はどうでしょうか。きっと「美味しいのだろうか?」「ちゃんとした品質をしているのだろうか?」など色々な不安が出てくるはずです。
また、ブランドが確立している商品を選ぶことによってリスクの回避にもつながります。
なぜなら、新しい商品を購入する場合は、購入したものが期待した機能を果たすのか、支払った価格に見合うのか、などのリスクを消費者側が負わなければならないからです。
このように、企業がきちんと自社の強みを訴求してブランディングしてくれているおかげで、私たちは安心してリスクの少ない買い物ができているのです。
◉マーケティングとブランディングの相関関係と経営における重要性
マーケティングとブランディングはこれまで説明してきた通り全く違う施策ですが、相関関係にあります。
なぜなら、ブランディングは土台であり、その土台の上でマーケティングを行うことでより大きな影響力のあるプロモーションが行えるからです。
ブランディングによって認知度や信頼性が高くなると市場での競争力が強化されます。このような状態でマーケティング活動を行うと、より自社の優位性を高めた上で商品やサービスを販売することが可能です。
企業活動においてブランディングとマーケティングは車の両輪のようなものであり、経営の安定化を図るための重要な活動だということができます。
◉マーケティングとブランディングを同時に実現させる方法

ブランディングは自社や自社の商品・サービスのイメージを高めようとする活動で、マーケティングは商品やサービスを売るための活動です。いずれも企業活動を行うためには重要な活動です。
この2つの活動を同時に実現できる効率の良い方法が「ブックマーケティング」です。
なぜなら、書籍であれば1冊で、商品やサービスの特徴だけではなく、自社の強みや取り組みなどを含めたあらゆる情報を伝えることができるからです。
また、書籍は信頼性の高い媒体なので、オウンドメディアなどのWeb媒体に比べて、ターゲットである消費者に良いイメージを作ってもらうのに最適な媒体ということができます。
このように、信頼性の高い媒体で商品やサービスについてのマーケティング要素、自社の強みや取り組みなどを含めたブランディング要素の両方を一気に伝えられるという点で、書籍は効率的な媒体と言えるでしょう。
しかし、商業出版や企業出版をはじめとしてただ書籍を出版すれば良いという訳ではなく、それをしっかりとターゲットの手元に届け、読んでもらわなければ意味がありません。
そこで、出版するだけではなく、ターゲットに読んでもらうまでを戦略的に行っていくのが、ブックマーケティングです。
さらに、ブックマーケティングでは、どのようなターゲットに、どのような書籍を届けたいかの戦略設計を行います。
たとえば、ブランディングやマーケティングをこれまで全く意識的に行ってこなかった会社であってもブックマーケティングという施策を通して、自社の強みを見出し(ブランディング)、それを書籍としてまとめて見込み顧客に届ける(マーケティング)の両方を実施することになります。
今後マーケティングやブランディングを強化していきたい、という会社だけではなく、今までどちらも意識的にやってこなかった、という会社が行うファーストステップとしてもブックマーケティングはおすすめです。
▶️ブックマーケティングの施策内容や効果については、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】もあわせて参考にしてください。
◉【まとめ】マーケティングとブランディングはどちらも必要不可欠
この記事では、マーケティングとブランディングの違いや、ブランディングを行うことによる企業とユーザー双方のメリット、経営戦略におけるマーケティングとブランディングの重要性などについて詳しく解説しました。
前述しましたが、マーケティングとブランディングは企業という車の前進を支える両輪です。どちらも企業の存続には必要不可欠なものです。
ぜひ、この記事でマーケティングとブランディングについて正しく理解し、両方を上手く取り入れてみてください。
どのようにマーケティングやブランディングの施策を始めたら良いかわからないという方や、どちらもやっているけれどもなかなか成果がでない、という方は、それら2つの施策を同時に実行できる「ブックマーケティング」という施策を検討してみてはいかがでしょうか。
フォーウェイではブックマーケティングによる、企業のブランディングやマーケティングをサポートしております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


企業のブランド価値向上のために、出版という手段を選択する経営者は増加傾向にあります。
今回は数ある出版マーケティングの事例から、会員制ビジネスやFCビジネスを展開している企業の成功パターンを紹介します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
◉企業が取り組む書籍出版(企業出版)とは
近年、企業経営者が書籍を出版するケースが増えています。
一部のメディアに多く出演している著名人でない限り、ほとんどが印税目的で出版はしていません。
経営者の出版は、自社のブランディングや広告宣伝を目的としているのです。</p
企業側のメリットは書店に書籍が並ぶことによる広告効果や、出版をきっかけにメディアに取り上げられるなどの副次的効果にあります。
出版効果は数字では測りきれない様々な効果が同時に生まれます。そのため、拡大フェーズにあるタイミングで検討する企業が多いのも自然な流れでしょう。
考えられる出版効果としては以下のようなものがあります。
・すぐに顧客化につながる質の高い顧客の集客
・メディアに取り上げられることで自社の認知向上に寄与
・書籍制作を通して事業の棚卸しができる
・書籍が自社で活用できる営業ツールになる
・出版によりブランド価値が向上し採用面でも効果を発揮
・提携先など協力者が他社に紹介しやすくなる
・一過性の広告とは異なり一度出版することで長期的な広告効果が期待できる
上記のようなメリットが同時にやってくるのは一般的な広告とは大きく異なる部分です。
ある意味、1冊の書籍を出版することで、経営に革命が起きる可能性があるということです。
▶企業の書籍出版については、関連記事【企業出版のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。
◉企業出版と相性抜群な会員制ビジネスやフランチャイズビジネス
企業出版は一種の広告施策のため、コストがかかります。
企業としては費用対効果が気になるところでしょう。
まずは会員制ビジネスとフランチャイズビジネス(以下、FCビジネス)の特徴を整理していきます。
◉-1、会員制ビジネスは会員数がカギ
会員制ビジネスには、スポーツジムやレンタルショップが代表的です。ほか、会員限定のオンラインショップ、ネットワークビジネスなど様々な業種業態があります。
近年では、AmazonプライムやNetflixといった会員制サブスクリプションサービスも隆盛を極めており、会員数を大きく伸ばしています。
これらは個人情報を登録して会員になったユーザーに対して、有益なサービスを提供してマネタイズを図るビジネスモデルです。
会員制ビジネスの大きな特徴は、会員数が増えるほど月額課金をはじめとした収益が増加するため、経営の安定化と増益を同時に実現できる点です。
会員数を増やすことが一つの目的となるため、読者のファン化を促進できる出版は相性の良い宣伝手法となります。
◉-2、FCビジネスは共感性を得ることが重要
FCビジネスは、フランチャイズの本部が展開しているビジネスの看板を借りて、加盟した団体や個人が同様のサービスを提供していく内容です。
加盟店は本部が提供する看板やアイデア、商品などをそのまま使用することでビジネスが展開でき、売上の一部をフランチャイズ本部に支払うことで成り立っています。
いわゆる「ロイヤリティ」と呼ばれる加盟金を支払うビジネス構造です。
フランチャイズ本部目線でいえば、その事業を展開している理由や展望、メリットなどを発信して、ビジネスに共感してくれる加盟オーナーを増やしていく必要があります。
理念の発信を行ない、共感を得ることで、そのFCビジネスのファン化を狙っていくという意味では会員制ビジネス同様に書籍出版が効果的になり得るといえます。
◉会員制ビジネスやFCビジネスの具体的な企業出版事例
ここまでで会員制ビジネスやFCビジネスの一般的な特徴を解説してきましたが、次にそれぞれの具体的な企業出版事例を紹介していきます。
◉-1、会員制ビジネス事例:新たな顧客層を囲い込みでき会員数が急増!
会員制の投資助言サービスを展開している企業の事例を紹介します。
代表者が株式銘柄をテクニカルに分析し、短期売買で儲かる株式投資の成功者。大型銘柄から中型銘柄まで株価の上昇が期待される銘柄を会員向けに情報発信するサービスを展開しています。
もともとオンライン中心で発信を行なっていたため、シニア層や地方層へのアプローチに苦慮していました。また投資助言業という業種の印象から、顧客との信頼感を醸成しないとなかなか会員登録にまで誘導しづらいという課題もあったようです。
しかし、企業出版で株式投資のノウハウ書籍を全国展開したところ、販売好調によりたちまち重版。結果的に2万部を超える部数を世に輩出し、書籍読者からの問い合わせが大幅に増加したといいます。
問い合わせ数は出版前と比較して4倍。課題でもあったシニア層や地方の潜在顧客も書店やAmazonで書籍を購入したことで、著者への問い合わせのきっかけとなりました。
書籍出版をきっかけに読者がファン化し、新規会員が大きく増加した成功事例といえるでしょう。
◉-2、FCビジネス:自社のノウハウを発信することでビジネスの認知度が向上!
続いて、全世界で1万店舗以上を展開している高齢者向けの体操教室フランチャイズ企業の事例を紹介します。
2005年に日本に上陸し、FCビジネスで店舗数は780店鋪まで拡大。2010年にFC店舗のさらなる増加を目的に書籍出版を実施しました。
50歳以上の女性をターゲットにして「体が変われば気持ちも人生も変わる」のキャッチコピーで販売したところ、発売1ヶ月で発行部数3万部を達成。
書籍出版をきっかけに、自分でも体操教室をオープンできると希望を持ってFCオーナーとなった女性が急増し、発売から4年後の2014年には店舗数が1500店鋪を突破しました。
現在は2000店舗を超え、会員数は86万人を誇るFCビジネスが展開できており、2020年3月には東証一部に上場。
書籍出版をきっかけに、潜在的なFCオーナーだけでなく、一般層にも企業の取り組みを広めることができ、さらなる事業拡大に大きく貢献しました。
◉【まとめ】潜在顧客との信頼関係を構築しファン化を実現させよう
以上のように、会員制ビジネスやFCビジネスの企業出版は広告手段としてとても有益です。
ビジネスとしての優位性や独自のノウハウを発信することは、「自分も同じように成功したい!」という意欲をかき立てるきっかけとなります。
私たちフォーウェイが書籍出版をプロデュースした会員制ビジネスを展開している企業様は、出版直後にAmazonで購入が殺到しカテゴリ1位を獲得。さらなる会員獲得に大きく寄与しました。
今後の新規会員やFCオーナーを開拓するにあたり、書籍出版という手段を検討するのも一つの手かもしれません。


企業にとって、「知られていること」は大きな強みです。
どれほど優れた製品やサービスを提供していても、それが世の中に認知されていなければ、顧客の選択肢に入ることすらできません。
特に情報があふれる現代では、消費者や取引先に「最初に思い浮かべてもらう存在」になることが重要です。
そのためには、自社の存在や価値を的確に伝える工夫が欠かせません。
「知名度」や「認知度」が高まることで、競合他社との差別化が図れるだけでなく、売上の向上、優秀な人材の採用、さらには社会的な信頼の獲得にもつながります。
この記事では、マーケティング戦略の基盤となる「知名度」と「認知度」に焦点を当て、それぞれの違いを明確にしながら、具体的な施策を紹介します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉「知名度」と「認知度」の違いとは?

「知名度」と「認知度」は、いずれも世間にどれだけ知られているかを表す言葉ですが、その意味合いには明確な違いがあります。
以下で詳しく見ていきましょう。
◉-1、「知名度」とは何か?
知名度とは、企業やブランドの「名前」がどれだけ世間に知られているかを示す指標です。
具体的には、以下のような状態を指します。
- 社名やブランド名を聞いたことがある
- ロゴやキャッチコピーを目にしたことがある
- CMや広告、SNSなどで目にしたことがある
ただし、「誰もが名前は知っているが、実際に何をやっているのかわからない」という場合は、「知名度は高いが認知度は低い」という状態に該当します。
◉-2、「認知度」とは何か?
認知度とは、企業の事業内容や製品・サービスについて「どれだけ深く理解されているか」を表す指標です。
単に名前を知っているだけではなく、以下のような理解や行動が含まれます。
- 企業の強みや姿勢に共感している
- 製品やサービスを利用したことがある
- 他人にその企業や製品を紹介できる
こうした深い理解があると、BtoBでは信頼関係の構築に、BtoCではリピート購入やファン化につながります。
◉企業が知名度・認知度を高めるメリット

企業が知名度・認知度を高めるメリットとして、次の5つを挙げることができます。
- ブランド価値及び信頼性の向上
- 競合他社との差別化による新規顧客の獲得
- 業界内での影響力向上
- 広告宣伝費の長期的な削減
- 人材採用の決定率の向上
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、ブランド価値及び信頼性の向上
認知度が高い企業の製品・サービスは、信頼性の高さにもつながります。
なぜなら、認知度が上がれば製品・サービスとの接点(タッチポイント)が増え、顧客が製品・サービスに好意的なイメージを持ちやすくなるからです。
タッチポイントを増やせば、色々な角度から繰り返しアプローチできます。
結果として、ブランド価値の向上につながりやすくなるのです。
ブランド価値を向上させることができれば、「高級スーパーといえば⚫️⚫️」「深夜にゆっくり嗜むなら⚫️⚫️のウイスキー」といったように、優先的に選ばれやすくなります。
BtoBのビジネスでも「この案件を発注するなら⚫️⚫️」「この類のコンサルを依頼するなら⚫️⚫️」というように、その業界での第一想起を狙えるようになります。
このように、認知度を高められれば、顧客からの信頼の獲得にもつながり、リピート購入や固定客の獲得にもつながりやすくなるのです。
◉-2、競合他社との差別化による新規顧客の獲得
企業の認知度が向上すると、競合他社との差別化を図ることができ、価格競争から脱却できます。
なぜなら、「⚫️⚫️の製品ならば間違いない」という信頼性を獲得できるからです。
たとえば、家電製品を選ぶ時に、「知らないメーカーの安い製品ではなく、少し高くてもよく知っているメーカーのものを選ぶ」という人は多いと思います。
BtoBビジネスの場合でも同様のことが言えます。
このように、認知度によって差別化を図ることで、比較的高めの価格であっても顧客の方から選んでもらいやすくなるのです。
◉-3、業界内での影響力向上
企業の認知度が向上すると、必然的に業界に与える影響も大きくなります。
たとえば、ビール類で市場シェア2位を誇るキリンビールは、コロナ禍でビール市場が縮小したことにより、販売業績が前年を下回る結果となりました。そこで、起死回生を狙うべく投入したのは、「スプリングバレー」というブランドのクラフトビールです(2021年3月発売)。
テレビCMや広告、店舗向け小型ビールサーバーの展開により認知度を向上させた結果、クラフトビール業界をけん引する存在となりました。同社調べでは、2021年の国内の販売規模は6万リットル強と、20年と比較すると約1.6倍に増加しているそうです。(※1)
また、認知度が向上すれば、「影響力がある会社」として紹介が増えたりアライアンスの打診が増えたり、ビジネスチャンスの拡大につながりやすくなります。
このように、認知度を向上させることで、企業はさまざまな恩恵を受けることができるのです。
※1:日経クロストレンド「キリンはクラフトビールに活路 17年連続縮小のビール市場活性化へ」
◉-4、広告宣伝費の長期的な削減
企業の認知度が上がることは、広告宣伝費の削減にもつながります。
なぜなら、認知度が向上すると、口コミやSNSなどで製品・サービスの情報が自然と拡散されやすく、宣伝される機会が増えるためです。
たとえば、認知度が高い企業が生み出した製品・サービスが、SNSで拡散されているのを見たことがあるという人は多いのではないでしょうか。
このように、認知度が向上することで「この企業の製品だから自分も紹介したい」という状態を作ることができます。
ユーザーが自ら紹介したいと感じる状態が生まれれば、短期的な広告宣伝を行って購入を喚起する必要がなくなるため、結果的に広告宣伝費の長期的な削減にもつながります。
このように、「広告依存から脱却する」という観点からも、企業にとって、認知度を上げる活動は重要なのです。
◉-5、人材採用の決定率の向上
認知度が向上すると、「この企業で働きたい」という意欲を持った人が集まりやすくなります。
なぜなら、誰もが見知っていたり、どんな取り組みを行っているのか、どんな製品・サービスを提供しているのかイメージがつく企業に対して、人は好意的な印象を持つからです。
一方で、そもそも何をしている会社なのかが分からない場合、好意的な印象を持てないどころか、選択肢の1つにもなれません。
また、何をしている企業なのか分からないと、入社後のミスマッチにもつながりやすくなります。
このように、認知度を向上させることは、求職者数の増加にもつながるだけではなく、人材のミスマッチの予防も可能です。
結果的に、人材採用における決定率の向上につながります。
◉知名度や認知度を高めるための具体的な施策

知名度や認知度を効果的に高めていくには、ターゲットに合わせて適切な施策を組み合わせることが重要です。
これらの施策は、大きく次の2つに分けることができます。
企業や事業内容によって有効な方法は異なりますが、それぞれの特徴を理解し、バランスよく活用することで、より高い成果が狙えます。
具体的にどのような施策があるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
◉-1、オンライン施策
デジタル化が加速する現代において、オンライン施策は企業の知名度や認知度を高めるうえで大きな影響力を持っています。
スマートフォンの普及やSNSの利用が一般化したため、顧客が企業やサービスと出会う最初のきっかけは、オンライン上であることが多くなりました。
自社サイトやSNS、広告など、さまざまな施策がありますが、いずれもターゲットとの接点を意図的に作り出すことがポイントです。
オンライン施策は、比較的低コストで情報発信ができる点もメリットです。
ここでは、5つのオンライン施策を紹介します。
◉-1-1、広告媒体の活用
企業が認知度を向上させる一般的な方法が「広告媒体の活用」です。代表的なのが、テレビやラジオ・新聞・雑誌などのマスメディアを用いたマス広告や、検索連動型広告やディスプレイ広告・リターゲティング広告などのWeb広告です。
インターネットの普及によりマスメディアの影響力が落ちてきているといわれていますが、マス広告は、依然として高い効果が期待できる方法の1つです。
マス広告の場合、顧客は偶然に広告を見ることになるため、潜在顧客に対して広告を見せて認知を獲得する効果が期待できます。
たとえば、ふと目に入るテレビCMが印象的で、紹介されている製品やサービスについて調べた経験のある方はいるのではないでしょうか。
一方で、インターネット環境における広告媒体として検索連動型広告やディスプレイ広告・リターゲティング広告があります。
検索連動型広告やディスプレイ広告、リターゲティング広告の概要は以下の通りです。
| 検索連動型広告 | GoogleやYahoo! JAPANなどの検索エンジンで検索したときに、検索したキーワードに連動して表示される広告のこと。製品やサービスの購入を検討している顧客にアプローチできるため、費用対効果が高い点が特徴。 |
| ディスプレイ広告 | Webサイトやアプリの広告枠に表示される画像や動画の広告のこと。イメージとして顧客が視認することができるため、認知度の向上効果が高い点が特徴。書籍の広告も相性が良い。 |
| リターゲティング広告 | 自社のWebサイトに訪問したことのある顧客に再度広告を表示させるWeb広告。自社の製品やサービスに興味を持ってサイトを訪れた顧客に、再度広告を表示することができるため、認知率を向上させ購買につなげることが可能。 |
検索連動型広告やディスプレイ広告、リターゲティング広告は、ターゲットを細かく設定できるのが強みです。
たとえば、「キャンプ用品に関するサイトを訪れたら、YouTubeの広告にキャンプメーカーの広告が表示されるようになった」のような経験がある人は多いのではないでしょうか。
このように、マス広告とWeb広告は異なる強みや特徴があるため、2つを組み合わせることで認知度を効率的に向上させることが可能になります。
◉-1-2、SNS媒体の活用
SNSはコミュニケーションツールとしてだけではなく、情報収集ツールとして活用されています。
そのため、うまく活用することによって効率的に認知度を向上させることができます。
たとえば、アイスクリームメーカーのハーゲンダッツジャパンは、ハーゲンダッツのミニカップに現れるハート型をシェアしてもらうキャンペーンを実施しました。
このキャンペーンは、X(旧:Twitter)を媒体として行われ、約4,200件もの投稿が集まっています。
投稿がタイムライン上に表示されることで、普段から商品を購入している層だけでなく、これまで関心の薄かった層にも情報が届き、認知度を高めることにつながりました。
また、自社のアカウントを使ってSNSキャンペーンや広告を打つのではなく、「既にSNS上で一定の影響力を持つインフルエンサーに情報を発信してもらう」といった方法もあります。
インフルエンサーが製品やサービスに好意的な意見を投稿すると、自然に消費者目線の情報として拡散され、そのフォロワーにも情報が届きます。
インフルエンサーが、あたかも自然にその製品やサービスを使っているかのように見せかけるステルスマーケティングの規制には十分注意が必要ですが、「これはPRである」と明示したうえで、影響力のあるインフルエンサーに製品・サービス情報を発信してもらうのは、認知度の向上に効果的です。
また、SNSと言っても色々な種類があります。InstagramやX(旧:Twitter)、TikTok、YouTubeなどのSNSごとにユーザー層が異なるため、ターゲット層に合わせて最適なSNSを選ぶことが必要です。活用する際は、どの潜在層に届けたいのかを明確にして適切なSNS媒体を選ぶようにしましょう。
▶︎SNSマーケティングについては、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】をあわせて参考にしてください。
◉-1-3、コンテンツマーケティングの実施
コンテンツマーケティングでは、特定の企業の取り組みや製品・サービスについて知らない潜在層に対して認知を拡大させることが可能です。
なぜなら、企業の取り組みや製品・サービスを認知していないユーザーに、自然な形で知ってもらうことができるからです。
たとえば、新たな集客施策としてリスティング広告を検討している場合、いきなりリスティング広告の企業に依頼する人はいません。
まずは情報収集から始める人がほとんどでしょう。
この場合、検索エンジンで「リスティング広告とは」「リスティング広告 メリット」「リスティング広告 業者」などのキーワードで検索し検索上位にあるコラムなどを見て情報収集していくと思います。
その際に、検索上位に出てきたコラムを運営する企業に対して人は、「A社はリスティング広告において有名な企業」というイメージを持ちやすくなります。
また、そのコラムの内容が優れていた場合には、「この企業は信頼できる」というイメージもプラスされるでしょう。
このように、コンテンツマーケティングで質の高いコンテンツを作成して検索上位を狙うことは認知度の向上においても重要です。
◉-1-4、有名人やインフルエンサーとのコラボレーション
有名人やインフルエンサーとコラボレーションすることも、認知度の向上に効果的です。
特に、好感度の高い有名人やインフルエンサーを起用すれば、企業や製品・サービスに対するイメージアップを図ることができます。
さらに、「あの有名人がPRしている商品」として認知されるだけではなく、利用シーンも伝えることができるため、ユーザーにイメージを湧かせやすくなります。
たとえば、ヘアケア製品を扱う企業であれば、髪が綺麗な有名人を起用することで「私もこんな髪になれるかも」「この有名人が使っているなら効果があるだろう」と売上に直結させることができるのです。
このように、有名人やインフルエンサーとのコラボレーションによって認知度を向上させるためには、知名度や好感度、製品・サービスとの相性まで考えて起用することが大切です。
◉-1-5、プレスリリース(ニュースリリース)の配信
プレスリリースは、自社の活動やニュースを広く社会に伝えるうえで効果的な手法です。
単なる自社からの発信だけでなく、信頼性の高いメディアによって発信・掲載されることで、情報に説得力と影響力が加わります。
新商品や新サービス、業務提携、書籍出版、イベント開催などのニュース性のある情報をプレスリリースで発信すれば、メディア掲載や取材依頼につながる可能性が高まります。
◉-2、オフライン施策
オンライン施策は即効性や拡散力に優れている一方で、オフライン施策には信頼性やリアルな関係を築くことに強みがあります。
特にBtoB領域や地域密着型ビジネス、信頼性が重視される医療・士業・建設業などの分野では、対面やオフラインの活動が企業への信頼や知名度・認知度を高めることにつながります。
相手と実際に顔を合わせて会話することで、オンライン施策では得にくい信頼を得ることができるでしょう。
以下では、4つのオフライン施策を紹介します。
◉-2-1、展示会や地域イベントへの出展
展示会や地域イベントは、ターゲット層と直接対面し、商品やサービスの魅力をリアルに伝えられる機会です。
名刺交換や資料配布、デモ体験などを通じて、企業の雰囲気や担当者の人柄が伝わりやすく、参加者の印象に残りやすいのが特徴です。
展示会や地域イベントへの出展から関係性が深まれば、「この会社に相談してみたい」と感じてもらえるきっかけになります。
◉-2-2、新聞・雑誌・業界誌などへの掲載
新聞や雑誌、業界誌といった紙媒体への掲載は、第三者による評価として受け取られるため、信頼性を高められる手法です。
特に地方紙や専門誌は、読者との間にすでに信頼関係が築かれているケースが多く、「記事として紹介された」という事実自体が企業の信頼と認知度の向上に直結します。
また、紙媒体はオンライン記事と異なり、保存されやすいといった特徴があり、情報が定着しやすいといえます。
◉-2-3、パートナー企業との共同プロモーションの実施
信頼関係のあるパートナー企業と一緒にプロモーションを展開することで、自社だけでは届きにくい新たな層にも、自然に知ってもらうきっかけをつくることができます。
たとえば、既存の取引先や地域団体と協力してイベントやキャンペーンを行えば、「信頼できる相手からの紹介」として受け止められやすくなり、安心感や親しみを持ってもらえます。
お互いの得意分野を活かしながら、新しいお客さまと出会えるチャンスを広げる効果的な施策です。
◉-2-4、書籍出版
書籍の出版は、オフライン施策の中でも特に「信頼」と「深い認知」を獲得しやすい手法です。
書籍は「誰にでも簡単に出せるものではない」という印象があるため、社会的な信用度の高いコンテンツです。
また、企業や経営者の理念・価値観・専門性を体系的に伝えることができるため、認知の獲得だけでなく、読者との信頼関係にもつながります。
さらに、読み手との心理的な距離を縮めやすく、他のマーケティング施策と組み合わせることで、より大きな相乗効果が期待できるのも特徴です。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。
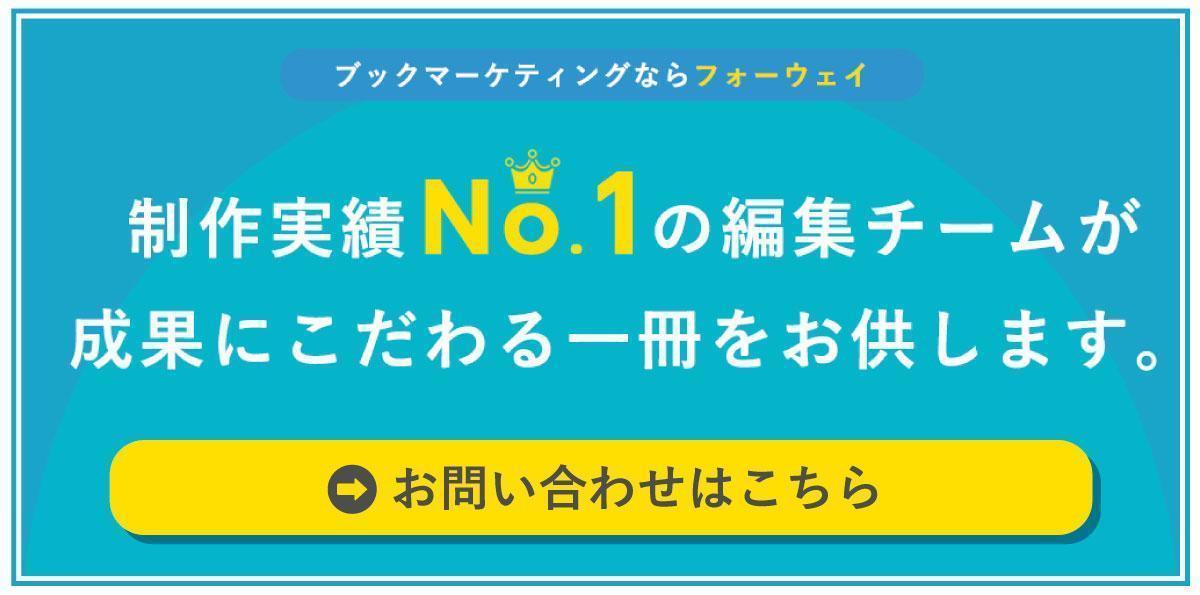
◉企業が知名度や認知度の向上施策で失敗する典型的な例

知名度や認知度の向上を目指す企業が失敗しがちな典型例として、次の3つが挙げられます。
- 情報発信に一貫性がなく、ブランドイメージが定まっていない
- 質より量に偏った情報発信になっている
- 一過性の話題作りで終わっている
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、情報発信に一貫性がなく、ブランドイメージが定まっていない
媒体ごとに異なるメッセージを発信してしまうのは、認知度向上を目指す企業が陥りがちな失敗の一つです。
たとえば、Webサイトでは「技術力重視の堅実な会社」と伝えているのに、SNSでは「親しみやすい雰囲気の会社」と発信しているようなケースです。
発信する情報に一貫性がないと、受け手は混乱してしまい、最終的には「なんとなく信用できない」という印象を抱いてしまいます。
◉-2、質より量に偏った情報発信になっている
知名度や認知度の向上を急ぐあまり、「とにかく露出を増やさなければ」と、質より量を優先した情報発信を行う企業も少なくありません。
しかし、発信する情報の質が伴っていなければ、むしろ「内容が薄い企業」「信頼できない企業」というマイナスの印象を与えてしまうおそれがあります。
◉-3、一過性の話題作りで終わっている
話題性を狙ったキャンペーンやSNS投稿は、成功すれば一時的に注目を集めることができます。
しかし実際には、「バズったものの、企業の認知や信頼には結びつかなかった」といったケースも少なくありません。
一過性の話題は顧客の記憶に定着しづらく、企業の価値観や理念が十分に伝わらないまま終わってしまうことが多いため、結果として継続的な認知度の向上にはつながりにくいのが現実です。
◉知名度・認知度の向上は「信頼構築」と「メッセージの一貫性」が鍵

たとえ社名が広く知られていたとしても、「何をしている会社なのか分からない」と思われてしまっては、逆にブランドイメージを損ねるリスクがあります。
重要なのは、ただ露出を増やすことではなく、「正確な情報」を「信頼できるかたち」で届けることが重要です。
認知度を向上させるためには、次の2つの視点を持って取り組む必要があります。
- 「認知→理解→信頼→ファン化へのステップ」を意識して施策を設計する
- 書籍やWeb、SNSで一貫したメッセージを発信する
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、「認知→理解→信頼→ファン化へのステップ」を意識して施策を設計する
認知はゴールではなく、あくまでスタート地点です。
その先に「理解される」「信頼される」「選ばれる」という段階があることを前提に、施策の流れを戦略的に設計することが重要です。
ただ知ってもらうだけで終わらせず、段階的に関係性を深めていく視点が求められます。
◉-2、書籍やWeb、SNSで一貫したメッセージを発信する
信頼は、あらゆる情報発信における統一感から生まれます。
たとえば、ある媒体で「人材育成に強い」と打ち出し、別の媒体では「コスト削減が得意」と伝えてしまうと、受け手に混乱や不信感を与えてしまいます。
「この会社は結局、何を提供しているのか」と疑念を抱かれる原因になりかねません。
そのため、WebサイトやSNS、採用パンフレット、セミナー資料など、あらゆる媒体でメッセージを統一することが重要です。
そして、その軸を作るのに適した施策が書籍出版です。
◉知名度・認知度アップなら企業出版(ブックマーケティング)がおすすめ
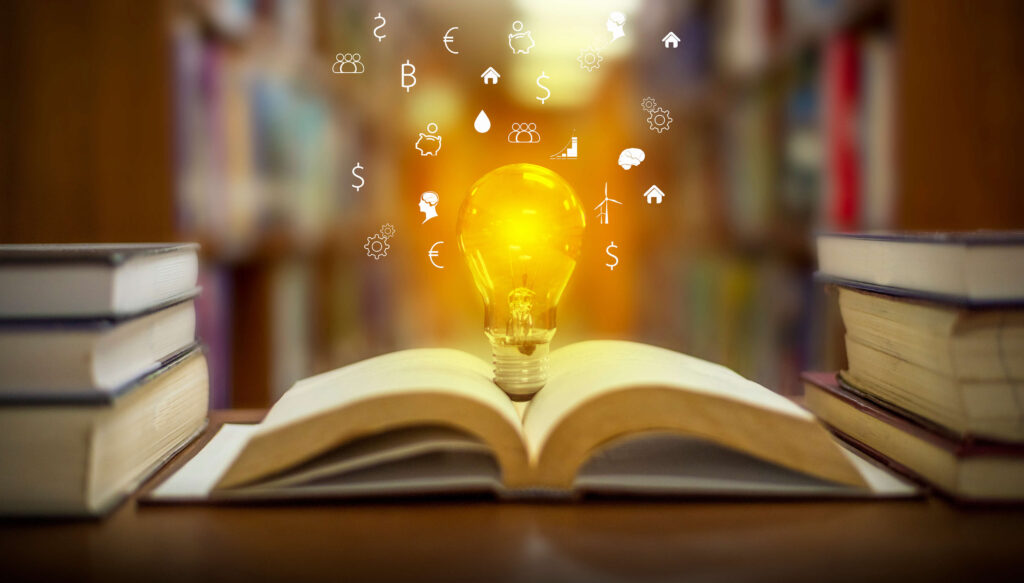
企業出版は、単なる情報発信では得られない「信頼」と「一貫性のあるメッセージ構築」が可能な施策です。
書籍を出版するには、自社や経営者の理念・実績・強みを洗い出し、伝えたい情報を体系的に整理する必要があります。
この作業を通じて、企業としての核となるメッセージが明確になり、それを軸とした一貫性あるブランディングが展開できます。
また、書籍で整理・構築したコンテンツは、ホームページのコラム化や小冊子としての再編集、SNS投稿、さらにはプレスリリースなど、他の媒体にも展開しやすく、広報活動全体の質と効率を高めることが可能です。
さらに、書籍という「社会的信用力の高い媒体」を用いることで、SEO対策やSNS発信、プレスリリース単体では築きにくい信頼関係を、読者や顧客との間に築くことにもつながります。
企業出版は、他の施策との連携による相乗効果を生みやすい点でも優れたマーケティング手法であり、知名度や認知度を高めたい企業にとって有効な選択肢といえます。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【本を出版するには?現役書籍編集者が本の出し方を分かりやすく解説】もあわせて参考にしてください。
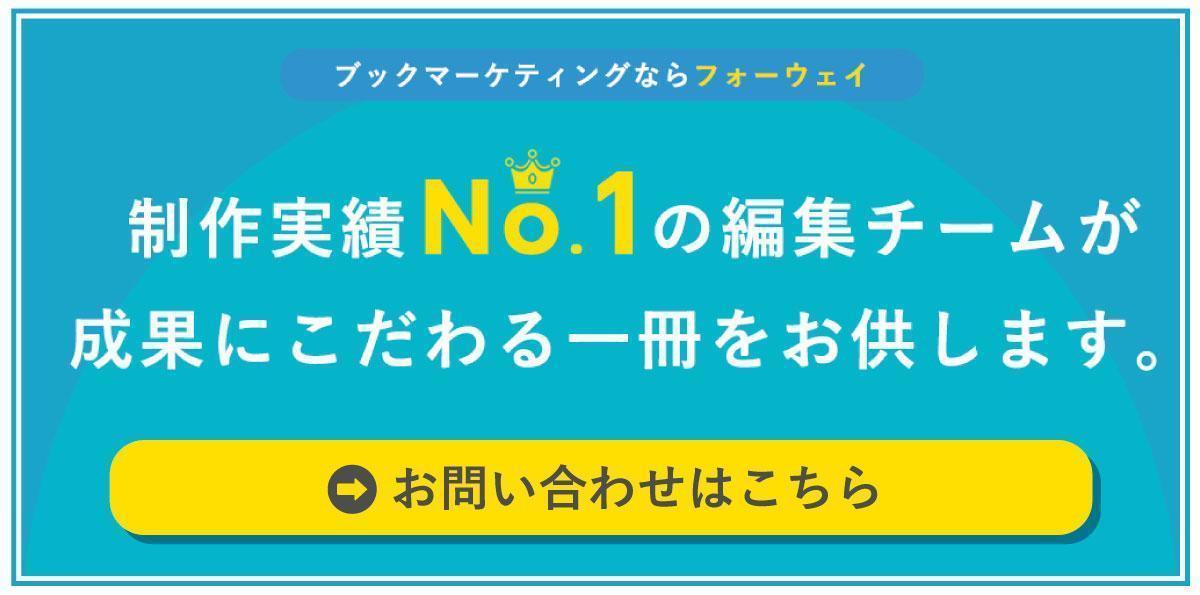
◉書籍を出版して知名度・認知度を着実に高めた成功事例

ここでは、書籍の出版によって知名度・認知度を高めることに成功した事例を7つ紹介します。
以下で、どのような事例なのかを見ていきましょう。
◉-1、保険代理店|業界内で「◯◯といえばあの会社」と呼ばれるまでに認知が定着した事例
法人向けの生命保険や損害保険を取り扱っている保険代理店では、業界内での認知向上を狙って書籍を出版。
書籍を読んだ同業他社からのコンサル依頼や保険会社の関係者から講演依頼を受けるようになり、「保険会社にとって頼れる代理店」というイメージが定着しました。
出版を通じて、業界内での認知度と信頼性を大きく高めることに成功しました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、不動産会社|医師という専門層に向けた戦略的出版でターゲット認知を拡大した事例
ある不動産会社は、医師をターゲットとした書籍を出版して認知拡大を図りました。
医師という特定のターゲットに向けた内容にすることで、「成約率100%」という大きな成果を上げました。
専門層に特化した戦略的な出版は、ターゲット層への効果的な手段となります。
◉-3、公認会計士|書籍出版をきっかけにメディア取材が増え、事務所の専門性が広く認知された事例
公認会計士事務所開設の1年目に「海外案件の専門家」というポジションを確立するために書籍を出版。
出版後をきっかけに、地元紙や全国紙、ラジオ番組などからの取材が相次ぎ、メディア露出が増加しました。
書籍を通じて専門性が広く認知され、事務所のブランディングとビジネス拡大に成功しました。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉-4、医師|成分解説に特化した書籍で「コラーゲンの専門家」としての認知を確立した事例
ある医師は、長年研究してきたコラーゲンの成分解説をテーマとした書籍を出版しました。
薬機法に配慮しながらも、消費者や同業者に対してもわかりやすく専門性を伝え、「コラーゲンの専門家」としての地位を確立。
書籍はサプリメントの販促にもつながり、ビジネス面でも成果を上げました。
◉-5、研究者|健康テーマの出版を通じて「米油ブーム」に影響を与えた社会的認知拡大の事例
研究者として食と健康をテーマに活動していた著者は、米油の健康効果に関する書籍を出版。
当時の健康志向の高まりと相まって、米油の需要拡大に貢献しました。
同時に、研究者としての社会的認知度も向上し、健康テーマに関する専門家としての地位を確立しました。
◉-6、がん治療専門クリニック|出版を機に遠方からの来院が増加した医療ブランディング事例
あるがん治療専門クリニックは、書籍を出版することで、治療方針や理念を広く伝えることに成功しました。
出版後、書籍を読んだ患者からの問い合わせや、遠方からの来院が増加し、クリニックのブランディングと集患に大きく貢献しました。
出版を通じて患者の信頼を獲得し、医療ブランディングの成功につながった事例です。
◉-7、建設業専門コンサルタント|書籍を通じて業界内での地位を確立した事例
ある建設業専門のコンサルタントは、業界の課題や解決策をまとめた書籍を出版しました。
出版をきっかけに業界内での専門家としての認知と信頼性が高まり、講演依頼やコンサルティングの相談も増加しました。
また、書籍を通じて新たな顧客層へのアプローチも可能となり、ビジネスの拡大へとつながっています。
◉【まとめ】書籍を活用した「知名度」「認知度」の向上によって「選ばれる会社」を目指そう!
この記事では、「知名度」と「認知度」の違いや具体的な施策、さらに書籍出版によって成果を上げた成功事例について解説しました。
知名度・認知度を効果的に高める手段として、現在注目されているのが「書籍の出版」です。
書籍は、信頼性・専門性・共感を伝えられるブランディング手段であり、営業や採用、広報などさまざまな場面で活用可能です。
フォーウェイでは、書籍を活用した「ブックマーケティングサービス」を提供しています。
企業の強みや理念、サービスの特徴などをプロの編集者が丁寧にヒアリングし、1冊の書籍として形にします。
知名度・認知度の向上施策として書籍出版を検討している方は、フォーウェイまでお問い合わせください。
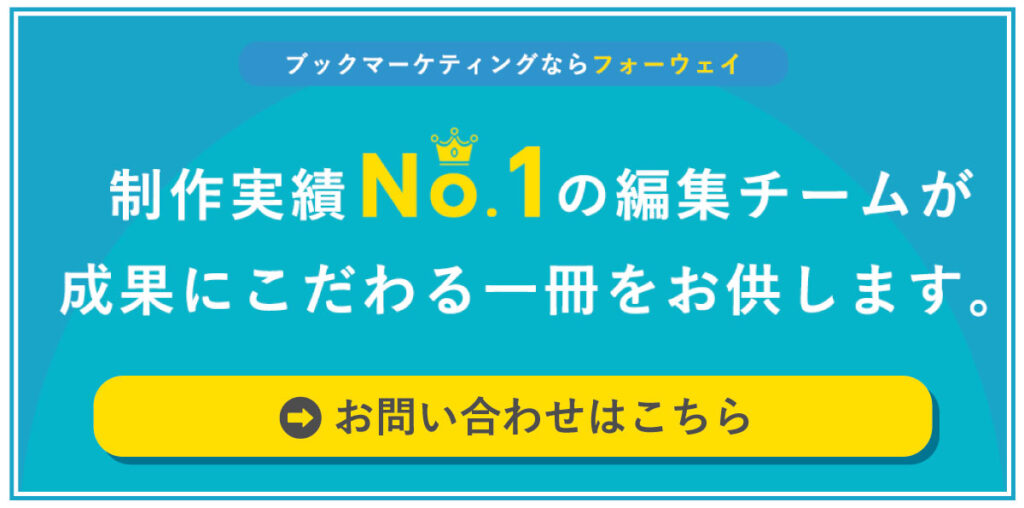

売上を高めるうえで欠かせないのが「客単価」の分析と改善です。
客単価とは、1人の顧客が1回の取引で支払う平均金額のことを指します。
一見単純な指標に思えるかもしれませんが、「顧客が何をどのように買っているか」「自社の商品・サービスの価値がどれだけ適切に伝わっているか」といった重要な情報が詰まっています。
たとえば、同じ売上金額でも、少数の顧客が高額商品を購入しているのか、それとも多くの人が少額ずつ買っているのかで、事業の方向性や戦略は大きく変わるでしょう。
客単価に注目することで、売上の内訳がはっきり見えてくるため、「どのターゲット層にどうアプローチするか」「どの商品を主力にするか」といった判断もつきやすくなります。
本記事では、客単価の定義や計算方法をわかりやすく解説し、分析によって得られるメリットや具体的な単価アップの施策について紹介します。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉客単価とは?定義と計算式をわかりやすく解説

まず最初に、客単価とは何かについて説明しておきましょう。
客単価の定義と計算式は、次の通りです。
◉-1、客単価の定義
客単価とは、「1人の顧客が1回の購入で支払う平均金額」のことです。
ECサイトや飲食店、小売店などのさまざまな業種で活用されている代表的な経営指標の一つです。
顧客1人あたりの購買金額を把握することで、経営状況や販売施策の効果を客観的に評価できるようになります。
◉-2、客単価の計算式
客単価の計算式は、次の通りです。
たとえば、1日の売上が50万円で、来店客数が250人だった場合、「500,000円÷250人=2,000円」と計算できます。
なお、曜日や時間帯によって売上や販売量に大きな差がある場合は、分析対象の期間を「曜日別」や「時間帯別」に区切ることで、より精度の高い分析が可能になります。
ここで注意すべきなのは、「客単価」は実際に購入した顧客のみを対象として算出される点です。
つまり、いくら多くの人を集客しても、購入に至らなければ売上には結びつかず、客単価にも反映されません。
一見当たり前に思えることですが、プロモーションやマーケティング戦略を立てるうえで重要な視点です。
◉客単価を分析するメリット

では、客単価を分析するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
一般的に、次の3つのメリットがあります。
・売上向上の具体的な戦略立案に役立つ
・ターゲット顧客ごとにマーケティング最適化を図れる
・他社との差別化ポイントを把握しやすくなる |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、売上向上の具体的な戦略立案に役立つ
「売上が思うように伸びない」「最近落ち込み傾向にある」といった場合に、客単価を分析すると原因を探る手がかりになります。
単に売上金額だけを見ていても、その内訳がわからなければ、有効な対策を講じることはできません。
たとえば、売上が前月より20%減少したとき、この数字だけでは、何が問題だったのかはわかりません。
しかし、客単価のデータを確認すれば、「来店客数は変わらないのに、1人あたりの購入金額が減っている」といった具体的な傾向が浮き彫りになります。
逆に、「客単価は変わらないのに客数が減っている」という傾向が把握できたときは、集客施策の見直しが必要になります。
◉-2、ターゲット顧客ごとにマーケティングの最適化を図れる
顧客単価の分析は、単に顧客一人あたりの購入金額がわかるだけでなく、マーケティング活動を最適化するためにも役立ちます。
特に、ターゲット顧客ごとの客単価を比較することで、より効果的なマーケティング施策を立てるための方向性がつかめます。
たとえば、商品カテゴリー別に客単価を分析すれば、売上に貢献しているジャンルを特定することが可能です。
また、性別・年齢・地域・購入頻度・購買チャネルなど、さまざまな属性で顧客を分類し、それぞれの客単価を算出することで、「誰に何をどのように訴求すればよいか」がより明確になります。
このように、客単価は「誰に何を売るか」という視点を磨くための重要な指標といえます。
◉-3、他社との差別化ポイントを把握しやすくなる
客単価の分析は、自社の販売戦略や商品・サービスの市場評価を把握するうえで有効な手段です。
特に、同業他社と比較することで、自社の強みや弱み、そして競合との差別化ポイントを客観的に見極めることができます。
たとえば、同じ業種・同規模の企業と比べて自社の客単価が低い場合、価格設定や販売手法、提案内容に改善の余地があると考えられます。
一方で、高い客単価を維持できているのであれば、それは顧客が自社の商品やサービスに対して高い価値を認識している証拠です。
このような分析を通じて、「なぜ選ばれているのか」「どこで差別化できているのか」を明らかにすることができ、今後の戦略立案にも役立ちます。
▶︎差別化戦略の詳細については、関連記事【差別化戦略の成功の秘訣ーメリットやデメリット、成功事例とは!?】もあわせて参考にしてください。
◉客単価を上げるための具体的な施策
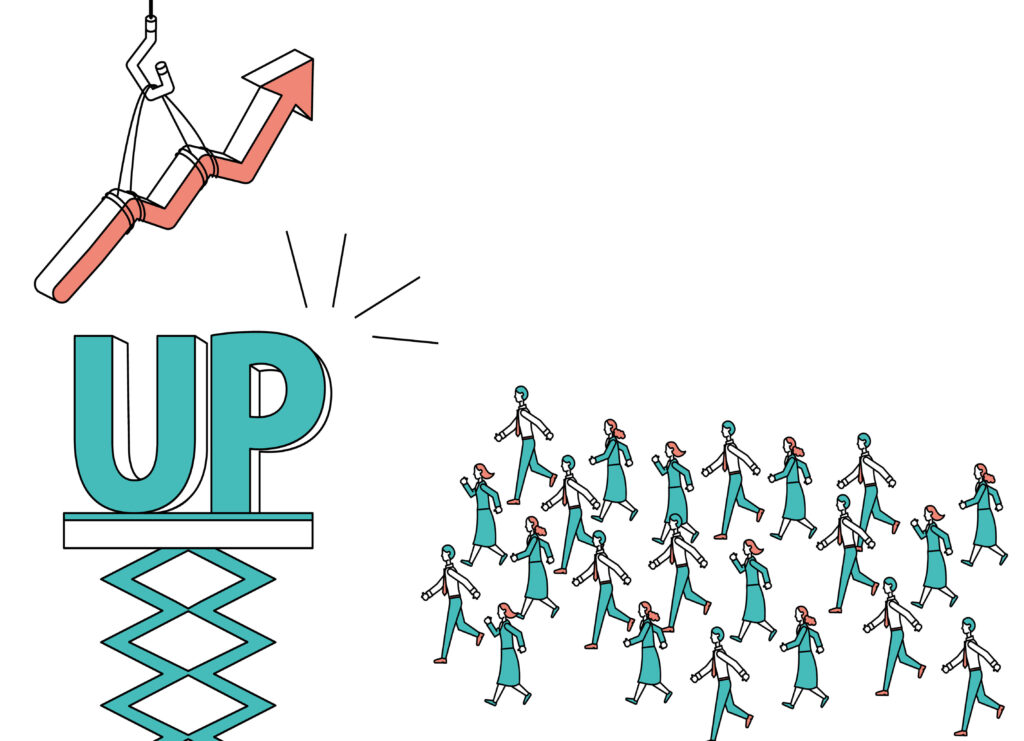
客単価を上げる具体的な施策として、次の4つが挙げられます。
・商品・サービスの設計で客単価を引き上げる施策
・販売方法で客単価を引き上げる施策
・購入しやすさを高めて客単価を引き上げる施策
・価値の訴求によって商品の魅力を高め、客単価を引き上げる施策 |
どのような施策なのか、詳しく見ていきましょう。
◉-1、商品・サービスの設計で客単価を引き上げる施策
商品やサービスそのものの価値を見直すことで、無理なく客単価を引き上げることができます。
顧客に「この金額を払っても良い」と納得して支払ってもらえるような仕組みを作ることで、値引きに頼らず安定的に売上を伸ばすことが可能になります。
◉-1-1、商品単価を上げる
客単価を引き上げる方法として、まず検討できるのが「商品単価の引き上げ」です。
一番シンプルな方法ですが、ただ価格を上げるだけでは「値上げ」と受け取られ、購入をためらわれる可能性があります。
そのため、「価格の引き上げ」と「提供価値の向上」をセットで行うことが重要です。
たとえば、素材の品質を高めたり、パッケージデザインを刷新したり、購入後のサポート体制を強化したりすることで、価格に見合う価値を感じてもらうことができます。
価格以上の満足感を提供することで、自然なかたちで商品単価を上げることが可能になります。
◉-1-2、高価格帯商品や限定品を追加する
顧客の選択肢の中に、あえて選びたくなるような高価格帯の商品や限定商品を加える方法も有効です。
すべての顧客が購入してくれなくても、一部の顧客が選んでくれるだけで全体の客単価を引き上げる効果があります。
たとえば、オーダーメイド対応品や季節限定品、数量限定品などがあります。
◉-1-3、購入特典を用意する
購入特典を用意することで、顧客の購買意欲を高め、自然と客単価の向上を促すことができます。
たとえば、「5,000円以上のご購入でオリジナルグッズをプレゼント」や「購入者限定で次回使えるクーポンを進呈」といった施策は、顧客にとって「もう少し買えば得をする」という動機づけになり、結果的に購入金額の底上げにつながります。
◉-2、販売方法で客単価を引き上げる施策
商品の販売手法を工夫することで、顧客がより自然に多くの商品や高価格帯の商品を選ぶように促すことができます。
ポイントは「お得感」や「選びやすさ」を意識した販売設計です。
◉-2-1、セット販売を導入してまとめ買いを促す
セット販売(バンドル販売)を導入することで、まとめ買いを促し、客単価の向上を図ることができます。
これは、複数の商品を組み合わせて一つのパッケージとして提供する販売手法です。
たとえば、飲食店では「メイン+ドリンク+デザート」のセット、小売店では「靴下3足組」といった組み合わせが考えられます。
また、「2点以上の購入で10%割引」「5,000円以上の購入で送料無料」というやり方もあります。
顧客にとっては単品購入よりもお得感があり、「せっかくならもう1点」といった追加購入につながりやすい点がメリットです。
◉-2-2、3段階の価格設定を行い、中価格帯の選択を促す
「松・竹・梅」のように、3つの価格帯を用意する方法です。
人は、最も安い選択肢には品質面で不安を感じやすく、最も高価な選択肢には手が届きにくいと感じる傾向があります。
その結果、無意識のうちに中間の価格帯を「妥当な選択」として選ぶ心理が働きます。
この心理を活用し、最も販売したい商品を中価格帯(竹)に設定し、その上下に高価格(松)と低価格(梅)の商品を配置することで、中価格帯の商品が選ばれやすくなります。
◉-2-3、上位商品を提案してアップセルを狙う
アップセルとは、顧客が検討している商品よりも上位のグレードや価格帯の商品を提案し、購入単価を引き上げる手法です。
「少しの追加予算で、より高品質な商品が手に入る」といった納得感を与えることで、顧客の選択を自然に上位商品へと誘導できます。
たとえば、美容院では「通常カット」に加えて「トリートメント付きプラン」を提案する、家電販売では「標準モデル」ではなく「高機能モデル」を紹介するといった施策が該当します。
ただし、過度な提案は押し売りと受け取られるリスクがあるため、顧客のニーズや状況を正確に把握し、それに基づいた適切な提案を行うことが重要です。
◉-2-4、関連商品を提案してクロスセルを狙う
クロスセルは、顧客が購入を検討している商品と一緒に使うと便利な商品を併せて提案する販売手法です。
たとえば、スマートフォンを買う顧客に、ケースや保護フィルム、充電器などを同時に提案するといったイメージです。
また、ECサイトなどでよく見られる「この商品を購入した人は、こちらの商品にも興味を持っています」といったレコメンド表示も、クロスセルの一種です。
◉-3、購入しやすさを高めて客単価を引き上げる施策
魅力的な商品やサービスを提供していても、顧客が「買いにくい」と感じるようであれば、客単価は伸び悩んでしまいます。
購買体験の中でストレスや不便さを感じさせないことは、結果として購入点数や売上の増加につながります。
◉-3-1、決済の選択肢を増やす
現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など、幅広い決済方法に対応することで、顧客が感じる購入時のハードルを大きく下げることができます。
特に近年はキャッシュレス決済を好む顧客が増加しており、対応していない場合は「買いたくても買えない」状況を招き、貴重な購買機会を失う可能性があります。
◉-4、価値の訴求によって商品の魅力を高め、客単価を引き上げる施策
顧客が高価格商品を購入するかどうかは、その商品に対する「納得感」や「共感」が得られるかどうかに左右されます。
価格が高い商品ほど、「なぜこの値段なのか」「価格に見合う価値があるのか」をきちんと伝える必要があります。
そのためには、商品そのもののスペックや特徴だけでなく、背景にあるストーリーやブランドの想いを、ターゲット顧客に合ったメディアでわかりやすく伝えることが重要です。
◉-4-1、SNSやホームページで商品の魅力をわかりやすく伝える
SNSや公式サイトでは、商品の魅力やこだわりをビジュアルでわかりやすく伝えることができます。
特にInstagramやX(旧Twitter)などのプラットフォームでは、写真や動画を活用して、使用シーンやビフォー・アフターの変化などを視覚的に訴求することが可能です。
「これならこの価格でも納得」と思ってもらうことができれば、購入につながる可能性が高くなります。
▶︎SNS運用のやり方については、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】もあわせて参考にしてください。
◉-4-2、書籍の制作・配布で商品の魅力や想いを届ける
SNSや公式サイトでは伝えきれない深い世界観やブランドの想いを伝える手段として効果的なのが、書籍による価値の訴求です。
書籍は、社会的信頼性の高いメディアであることに加えて、丁寧に作られた印象を与えるため、顧客との信頼関係の構築に役立ちます。
また、書籍は来店特典や購入特典としても活用できるため、商品やサービスのブランドイメージの構築と販売促進の両方に効果的です。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。
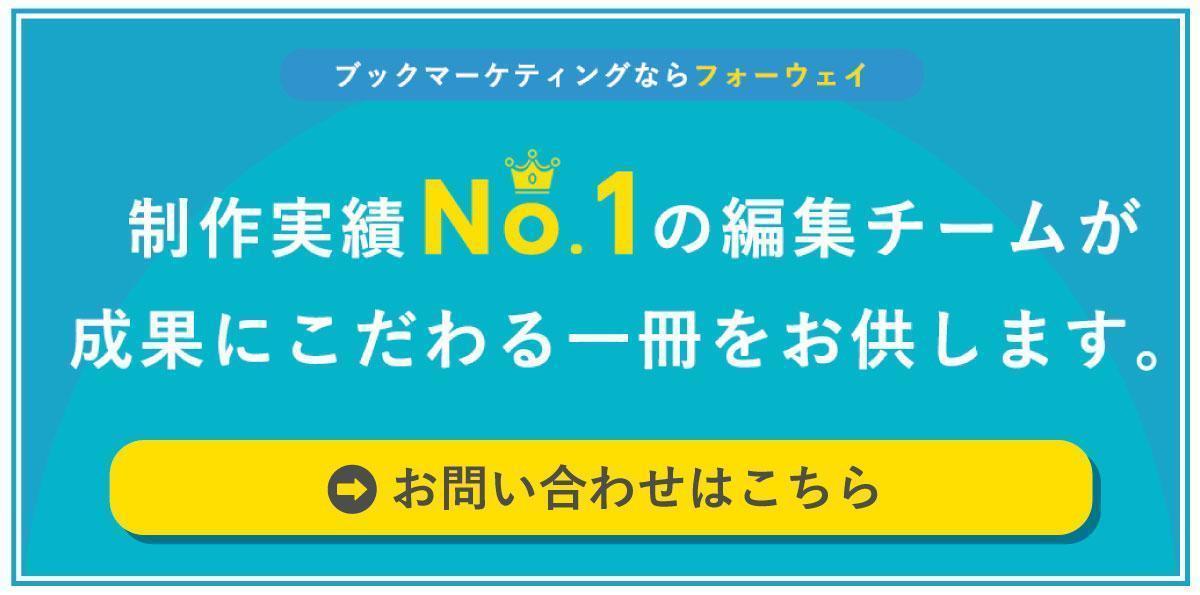
◉書籍出版によって客単価向上を実現した事例

実際に書籍を出版して客単価の向上を実現した事例を2つ紹介します。
・事例1:書籍出版で信頼を獲得し、法人保険の大型契約を実現した保険代理店の成功事例
・事例2:書籍出版を通じて専門性を可視化し、高単価案件の獲得に成功した公認会計士の事例 |
以下で、それぞれについて見ていきましょう。
◉-1、事例1:書籍出版で信頼を獲得し、法人保険の大型契約を実現した保険代理店の成功事例
法人保険を専門に取り扱う保険代理店の経営者は、業界の現状や課題を明らかにしながら、自社で実践している「一律報酬型」の給与制度が人材育成と業績向上に有効であるという持論をまとめた書籍を出版しました。
この書籍は業界内で大きな注目を集め、多くの反響を獲得。
出版をきっかけに顧客からの問い合わせが増加し、保険に関する相談だけでなく、経営理念や組織づくりに関する助言を求められるまでになりました。
企業との信頼関係が深まり、自社の価値観やスタンスが明確に伝わったことで、顧客視点に立った本質的な保険提案が可能となり、結果として法人保険の大型契約の受注を実現しました。
1社あたりの契約単価が上昇し、全体の売上拡大にもつながる成果を上げています。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、事例2:書籍出版を通じて専門性を可視化し、高単価案件の獲得に成功した公認会計士の事例
ある会計事務所の代表を務める公認会計士は、自身の豊富な海外勤務経験をもとに「海外ビジネス展開におけるリスク管理とマネジメント戦略」に関する専門書を出版しました。
この出版によって、「海外進出を支援できる高い専門性を持つ会計士」という専門家としての立場が確立され、顧客にもその実力が具体的に伝わるようになりました。
その結果、主力業務である海外進出企業向けの監査支援やアドバイザリー業務で、これまで見られたような過度な価格交渉に応じる必要がなくなったといいます。
提案段階からプランニングを一任されるケースが増え、業務そのものの価値が適切に評価されるように。
自然と客単価も向上し、事務所全体の売上アップにもつながっています。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉【まとめ】価値訴求による客単価向上を実現するために「書籍出版」を活用しよう!
この記事では、客単価の定義や計算方法をはじめ、分析によって得られるメリットや単価を引き上げるための具体的な施策、さらには成功事例までを幅広く紹介しました。
売上の向上を目指す経営者やマーケティング担当者にとって、「客単価」は単なる数値ではなく、顧客理解・商品戦略・価値訴求のすべてにおいて起点となる重要な指標です。
きちんと分析を行うことで、感覚に頼らない論理的で持続的な売上成長を実現することができるでしょう。
そして近年、客単価向上の手段として注目されているのが、「書籍出版」によるマーケティングです。
書籍は、商品の魅力や特長を伝えるだけでなく、企業の歴史や開発の裏側、ブランドに込めた想いなど、より深い価値を物語として伝えることができます。
さらに、流通を通じた新規顧客との接点づくりや、既存顧客との信頼関係の強化にもつながる有効な施策です。
株式会社フォーウェイでは、「ブックマーケティングサービス」を提供しており、書籍出版を通じて企業の価値や想いを発信するサポートをしています。
客単価を高める施策の一つとして、ぜひ「書籍出版」をご検討ください。
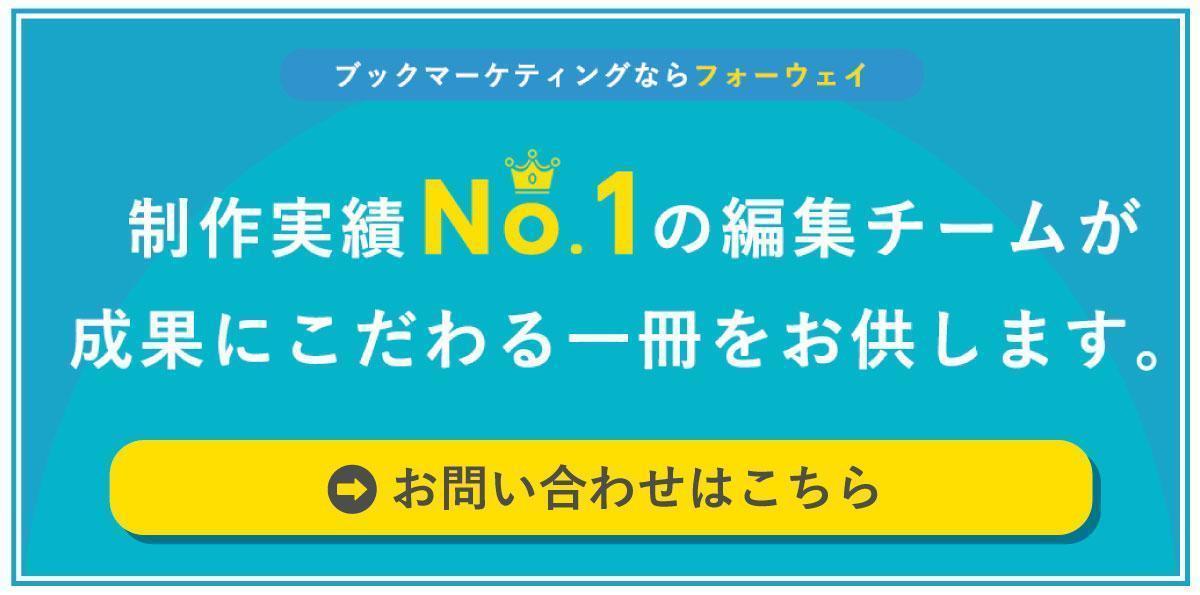

価格競争から抜け出せず、「価格を下げなければ売れない」と悩んでいる企業は少なくありません。
特に、商品やサービスの違いが明確に出しにくい業界では、価格競争に巻き込まれてしまうリスクが常につきまとっているといっても過言ではありません。
しかし、価格の安さだけで選ばれる状態が続くと、企業の利益もブランドも徐々にすり減り、衰退していってしまいます。
そうならないためにも、競合他社との価格競争から脱却していく必要があります。
この記事では、価格競争から脱却し、価格ではなく価値で選ばれる企業に変わるための実践的な方法について分かりやすく解説いたします。
目次【本記事の内容】
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉価格競争が企業にもたらすリスク

価格を下げることで一時的な売上を確保できる場合もありますが、それはあくまで短期的な対処方法にすぎません。
結果として、次の4つのリスクが生じて企業の競争力を大きく損なうことにつながります。
・利益率の低下
・商品・サービス品質の低下
・顧客ロイヤリティの低下
・ブランドイメージの低下 |
以下では、それぞれのリスクについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、利益率の低下
価格を下げると、売上は一時的に増えますが、利益率は確実に低下します。
十分な利益を確保できなければ、商品開発や人材育成といった将来への投資が難しくなり、企業の成長は次第に鈍化していくでしょう。
最終的には、利益減少に歯止めがかからず、打つ手が尽きて撤退や倒産に追い込まれるケースも少なくありません。
◉-2、商品・サービス品質の低下
価格を下げたうえで利益を確保しようとすると、仕入れコストや人件費の削減に踏み切らざるを得なくなります。
しかし、その影響で製品やサービスの品質は徐々に損なわれ、顧客満足度も次第に低下していきます。
品質の低下は、クレームや返品の増加、リピート率の減少といった悪循環を招き、最終的には企業への信頼そのものを揺るがすリスクとなりかねません。
◉-3、顧客ロイヤリティの低下
「価格が安いから選んだ」という顧客は、より低価格の競合商品が登場すれば、迷わずそちらに流れてしまう傾向があります。
価格以外の価値で選ばれていない場合、顧客との継続的な関係を築くのは困難です。
このような状態では、リピート購入や紹介をしてくれるロイヤリティの高い顧客が育ちにくくなり、長期的な利益につながる顧客との関係構築がしにくくなります。
◉-4、ブランドイメージの低下
頻繁な値下げを繰り返すと、「安さだけが魅力のブランド」「品質に不安があるのでは」といったイメージが定着しやすくなります。
その結果、どれだけ優れた商品やサービスを提供していても、本来の強みや価値が伝わらなくなり、企業のブランド価値が下がってしまうでしょう。
ブランドイメージが損なわれることで、価格以外の面で差別化することが難しくなり、さらなる値下げに頼らざるを得ないという悪循環に陥るリスクが高まります。
◉価格競争に巻き込まれてしまう原因

近年の価格競争の激化には、「比較サイト」や「レビュー文化」の浸透、市場のコモディティ化など、外部環境の変化が影響しています。
しかし、それ以上に重要なのが、企業側の姿勢や構造に起因する要因です。
企業が価格競争に巻き込まれてしまう主な原因として、次の5つが挙げられます。
・商品・サービスの価値が顧客に正しく伝わっていない
・コモディティ商品を取り扱っている
・安さをウリにしている
・競合他社と差別化ができていない
・営業部門に「値下げしてでも数字を取る」という文化がある |
以下では、それぞれの要因について詳しく解説していきます。
◉-1、商品・サービスの価値が顧客に正しく伝わっていない
たとえ他社より優れた商品やサービスを提供していても、その価値が顧客に伝わらなければ、最終的な購入判断は価格になってしまいます。
商品やサービスの価値が正しく伝わっていなければ、他社と価格で戦わざるを得なくなり、自然と価格競争に引き込まれていきます。
自社の強みや商品・サービスの価値を顧客に正しく伝える努力が不足していることが、価格競争に巻き込まれる原因の一つといえるでしょう。
◉-2、コモディティ商品を取り扱っている
どこで買っても大きな違いがない商品やサービスは、顧客にとって価格が判断基準になりやすいという傾向があります。
たとえば、以下のようなものがこれに該当します。
・事務用品
・日用品
・BtoB向けの部品や資材
・OEM製品 |
このような商品は、顧客から見ると違いが分かりづらいため、最も分かりやすい比較要素である「価格」が重視され、結果として価格競争に巻き込まれやすくなります。
そのため、価格以外の価値をどう打ち出すかが重要であり、明確な差別化要素がなければ価格競争から抜け出すのは困難でしょう。
◉-3、安さをウリにしている
「業界最安値」や「他社より〇%安い」といったアピールは、一時的な集客効果をもたらす反面、自ら価格競争に踏み込む行為でもあります。
こうしたアピールを続けていると、値下げが当たり前の状態となり、利益率が圧迫されていくという悪循環に陥ります。
安さをウリにするのではなく、「その価格で得られる価値は何か」を伝える視点が欠かせません。
◉-4、競合他社と差別化ができていない
商品やサービスの特徴、営業資料やWebサイトの内容などが競合他社と似通っていると、顧客は価格以外で比較することができなくなり、必然的に価格競争に陥ってしまいます。
差別化できていなければ、顧客にとって「選ぶ理由」は価格だけになってしまうからです。
価格以外の魅力を打ち出せなければ、顧客は最終的に「より安い方」を選ぶ傾向が強くなり、持続的な競争優位を築くことが難しくなります。
◉-5、営業部門に「値下げしてでも数字を取る」という文化がある
営業現場で「とにかく今月の数字を達成する」というノルマを重視しすぎると、「値引きしてでも購入してもらう」という安易な受注体質が生まれやすくなります。
このような姿勢が常態化すると、営業部門にとどまらず、組織全体に「価格で勝負するのが当たり前」といった意識が広がりやすくなります。
その結果、商品の価値を伝える工夫や、課題解決型の提案営業といった本来重視すべきアプローチが育ちにくくなるのです。
中長期的に見れば、価格競争からの脱却をますます困難にする大きな要因となります。
◉価格競争から脱却し、価値で選ばれる企業になるための方法

価格競争から抜け出し、価格ではなく価値で選ばれる企業になるためには、戦略的な見直しと社内体制の再構築が欠かせません。
そのための実践的な方法として、次の5つを紹介します。
・ターゲットの見直し
・自社や商品・サービスのUSPを再定義する
・商品・サービスに独自性(機能・体験・世界観)を持たせる
・ストーリーテリングによりファンを増やす
・営業・マーケティング部署を中心とした社内の意識・体質を変える |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、ターゲットの見直し
まず重要なのは、「誰に売るか」を見直すことです。
価格を重視する層ばかりにアプローチしていては価格競争から抜け出せないので、価格よりも価値を重視する顧客層にターゲットを絞ることが効果的です。
見込み顧客のニーズを再定義し、価格以外の魅力を求めている層に焦点を当てて、訴求内容や接点を見直していきましょう。
◉-2、自社や商品・サービスのUSPを再定義する
次に、自社や商品のUSP(Unique Selling Proposition)、すなわち顧客にとっての「選ぶ理由」を再設計します。
価格以外のどこに魅力があるのかを明確に言語化して発信していくことが、価値を重視する顧客層に響くアプローチになります。
たとえば、次のような視点について、自社の強みを洗い出してみましょう。
・高品質・高性能・専門性
・サポートの手厚さ
・納期の早さ・対応スピード
・社会的信頼
・長年の実績・顧客との関係性
・導入しやすさ
・パッケージング |
自社では当たり前と思っていたことでも、顧客から見ると大きな価値である可能性があります。
実際の顧客の声をヒアリングしながら、選ばれている理由を客観的に再発見することがUSPの見直しに有効です。
◉-2-1、高品質・高性能・専門性
競合には真似できない品質や技術、専門性は強力な差別化要素になります。
たとえば、「精度が1.5倍高い検査機器」「特定業界向けに開発された高耐久フィルター」「自社開発エンジンによる2倍以上の処理性能」「40年以上の実績を が裏付ける品質」などは、大手企業の資本力だけでは再現が難しい領域です。
こうした独自性の高い強みを明確に打ち出すことが、競争優位性を確立するポイントです。
◉-2-2、サポートの手厚さ
きめ細やかで手厚いサポート体制も顧客に選ばれる理由になります。
たとえば、「導入から初期設定まで専任スタッフがオンラインで対応」「電話・チャット・メールすべて即日返信」「マニュアルと操作研修がセットで初心者でも安心」といった対応は、かゆいところに手が届くサポートとして高く評価されます。
大手企業が規模の都合上提供しづらいサービスこそが、小回りの利く企業の差別化ポイントになり得ます。
◉-2-3、納期の早さ・対応スピード
納期の早さや対応スピードも強みになります。
たとえば、「午前11時までの注文は当日出荷」「初回見積もりは24時間以内に回答」「突発案件にも即日対応できる在庫体制あり」などの迅速な対応は顧客の信頼につながります。
ただし、過度なスピード対応は社内に負担をかけるため、持続できる体制を整えることが重要です。
◉-2-4、社会的信頼
地域活動への参加なども地域に特化した差別化に有効です。
「地域で50年以上の歴史」「行政や教育機関との協業実績」など、全国的な認知度が低くても、地域での強い支持を得ている企業は数多くあります。
地元に根ざした活動の積み重ねは、他社にはない信頼を築きます。
◉-2-5、長年の実績・顧客との関係性
積み重ねてきた実績は、何よりの信頼の証です。
たとえば、「創業50年」「累計導入企業2,000社以上」「15年以上継続取引の企業多数」「大手メーカー●●社に10年以上納品」といった具体的な数字があると、顧客に安心感を与えます。
特にBtoB取引においては、このような数字の裏付けがあると大きな説得力を持ちます。
◉-2-6、導入しやすさ
使いやすく、導入しやすい商品やサービスは、初めての顧客にとって大きな安心材料です。
たとえば、「初期費用ゼロで月額定額制から始められる」「マニュアルや初期設定キットが付属しており、現場ですぐに活用できる」「ITに不慣れでも安心の電話サポート付き」といった特徴は、現場の実用性を重視する顧客に高く評価されます。
また、導入のハードルが低いことで、購買意欲を後押しする効果も期待できます。
◉-2-7、パッケージング
商品やサービス自体での差別化が難しい場合は、パッケージや提供形式を工夫することで独自性を打ち出すことが可能です。
たとえば、キッコーマンは「しぼりたて生しょうゆ」を卓上ボトルで展開することで、他社と一線を画す価値を生み出しました。
このように、包装・提供方法・サブスクリプション化などで新たな価値を生むことができます。
特にコモディティ化しやすい商品やサービスを取り扱う企業は、パッケージングで競合他社との差別化を図るのがおすすめです。
◉-3、商品・サービスに独自性(機能・体験・世界観)を持たせる
価格だけで選ばれる状態から脱却するためには、商品やサービスに「体験価値」や「ブランドの世界観」などの情緒的な価値を加えることが有効です。
たとえば、「購入からアフターサポートまで一貫した顧客体験」や「ブランドの想いを物語として体現する演出」などを通じて、顧客の共感や愛着を引き出し「その企業で買いたい」と思わせることができます。
◉-4、ストーリーテリングによりファンを増やす
創業の理念や創業の背景、困難を乗り越えたエピソードなど、単なる商品説明では伝えきれない人間的な価値を伝える手法がストーリーテリングです。
企業の想いや価値観に共感した顧客は、価格ではなくそのブランドの姿勢に惹かれ、長期的な関係を築くロイヤルユーザーへと変わっていきます。
◉-4-1企業のストーリーを伝えるなら書籍出版がおすすめ
企業の想いや成り立ち、価値観を深く伝えたいなら、書籍が有効です。
書籍はマーケティングツールの中でも、社会的信頼性や専門性が高く、WebサイトやSNSと比べて「権威性のある情報発信」が可能になります。
また、読者は書籍という形式であれば長文をじっくり読んでくれるため、深い共感やファン化につながりやすいのも特徴です。
さらに、営業資料や広報活動におけるPRツールとしても活用でき、新規リード獲得のきっかけとしても効果が期待できます。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。

◉-5、営業・マーケティング部署を中心とした社内の意識・体質を変える
どれだけ価値を訴えても、現場が「売るためには値下げが必要」という意識のままでは、価格競争からの脱却は困難です。
そのため、営業やマーケティング部門を中心に、「価格ではなく価値で選ばれる」という文化を社内に浸透させることが重要です。
具体的には、教育や評価制度の見直し、KPI設計の再構築などを通じて、価格以外の魅力を語れる組織体制を整えていく必要があります。
◉書籍出版により価格競争から脱却した成功事例
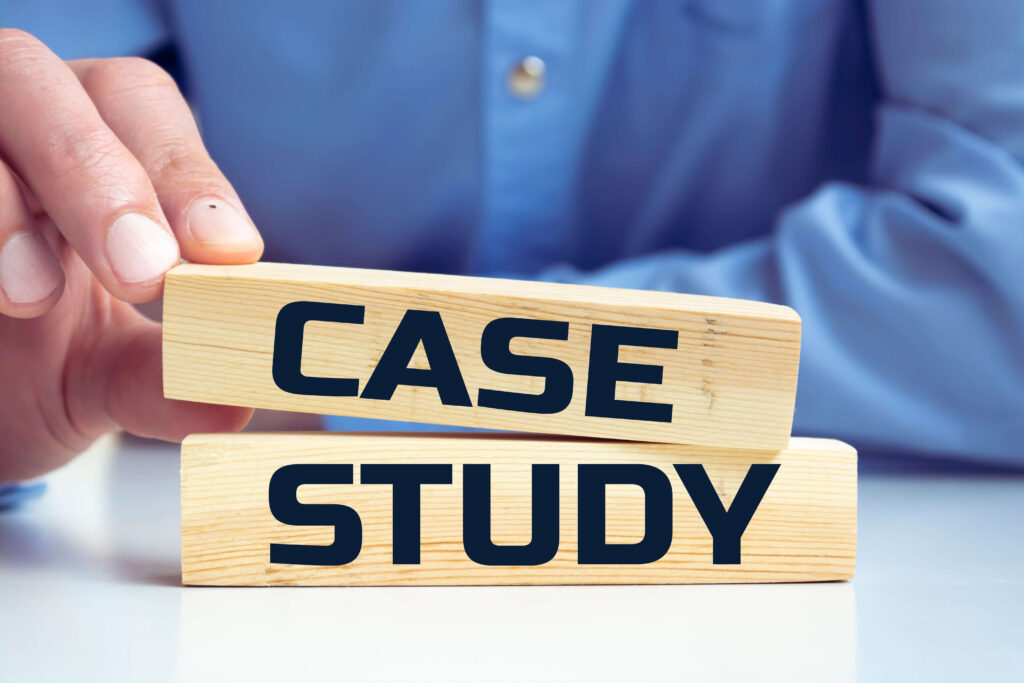
価格ではなく価値で選ばれるための手段として、近年注目を集めているのが書籍出版を活用したブランディングです。
ここでは、実際に書籍出版を通じて、価格競争から脱却し、自社ならではの強みを市場に浸透させた2つの事例を紹介します。
・事例1:常識を覆す持論を展開して注目を集めた保険代理店
・事例2:書籍出版により独自の強みをPRした会計事務所 |
以下で、それぞれ詳しく紹介します。
◉-1、事例1:常識を覆す持論を展開して注目を集めた保険代理店
保険商品は、どの保険代理店が販売しても商品内容も価格も基本的には同じという性質があります。
そのため、提案力や信頼性といった「見えにくい価値」が重視される業界だといえます。
そんな中で、この保険代理店の経営者は「成果報酬型ではなく、一律報酬型の給与制度こそが業績拡大につながる」という、業界の常識とは真逆の持論を打ち出し、その考えを一冊の書籍として出版しました。
この書籍は大きな話題を呼び、問い合わせが急増。
保険契約の件数が増えただけでなく、保険会社からの講演依頼も相次ぐなど、出版をきっかけに存在感が一気に高まりました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、事例2:書籍出版により独自の強みをPRした会計事務所
税理士・会計士業界も、価格競争に陥りやすい分野の一つです。
特に中小企業向けの税務顧問業務では、「記帳や申告だけしてくれればいいから安くしてほしい」といった要望が多く、価格以外で選ばれる理由をいかに示すかが課題となっています。
このような状況の中で、東京と名古屋で会計事務所を開設している代表者は、自らの海外における勤務経験を活かして「海外へのビジネス展開におけるリスクやマネジメントのポイント」をまとめた書籍を出版しました。
その結果、「外資系企業やグローバル案件にも対応できる会計事務所」であることを伝えることができ、結果として他事務所との差別化に成功しました。
▶︎公認会計士事務所の詳しい事例については【【事例コラム】出版をきっかけにメディア取材が続々、著名人との対談も実現!”海外進出の第一人者”のポジションを得た公認会計士】もあわせて参考にしてください。
◉【まとめ】価格競争から脱却し、本質的な価値で選ばれる企業を目指そう!
この記事では、価格競争のリスクや価格競争に巻き込まれてしまう原因、価格競争から脱却して価値で選ばれる企業になるための方法などについて事例を交えて解説しました。
価格競争から抜け出すためには、「安さ」以外の魅力を明確に伝え、選ばれる理由を構築することが不可欠です。
その手段の一つとして、注目されているのが書籍出版です。
フォーウェイが提供する「ブックマーケティングサービス」は、企業が持つ強みや創業の背景、商品・サービスに込めた想いなどをプロの編集者が丁寧に掘り下げ、書籍という形で見える化します。
書籍出版は、単なる宣伝だけでなく、「信頼性」「専門性」「共感力」を備えた強力なブランディング手段です。
書籍という形で自社の独自性や強みを明確化することで、価格ではなく価値で選ばれる企業を目指すことが可能になります。
書籍出版に少しでもご興味のある方は、ぜひ一度フォーウェイまでお気軽にご相談ください。


企業が10周年・50周年といった節目を迎える際、多くの担当者が悩むのが「周年記念をどのように進めればいいのか」という点です。
周年記念は単なるお祝い事ではなく、企業の価値や歴史、理念を再確認し、社内外に発信する貴重な機会でもあります。
しかし、「何から手をつければよいのか」「どのような施策が効果的なのか」「どの部署を巻き込むべきか」など、企画段階で考えなければならないことは少なくありません。
また、周年記念は「数年に一度」や「数十年に一度」と頻度が低く、社内にナレッジが蓄積されにくいため、ゼロから着手するケースも多いでしょう。
本記事では、そもそも「周年とは何か」という基本から、周年記念事業を行う目的や進め方、そして成果につなげるための施策例まで、わかりやすく解説します。
目次【本記事の内容】
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括)

福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
◉企業の周年とは?

周年とは、企業が創業や設立のタイミングを記念して、10周年や50周年といった節目でお祝いやイベントを実施することです。
企業の創業50周年記念といった事業立ち上げからの節目を祝うこともあれば、ブランドの立ち上げ10周年などを祝うケースもあります。
会社のほか、店舗や病院施設、福祉施設、学校など、業種・業態に関わらず、節目を祝うイベントとして催されます。
このような節目のタイミングで、周年を祝う社内外の関係者を招くイベントや記念品の制作などを行うのが通例です。
◉企業が周年記念を行う目的

企業が周年記念を行う主な目的として、次の6つを挙げることができます。
| 企業のブランド力の向上社内外のステークホルダーとの関係強化企業の理念や歴史、ビジョンの再整理・再発信企業のブランド再構築のきっかけ社員のモチベーション向上と組織力の強化採用・広報活動の強化 |
以下では、それぞれの目的について詳しく見ていきましょう。
▶︎周年記念を行う目的については、関連記事【周年事業の目的と意義ーー社史・周年史制作のもたらすもの】もあわせて参考にしてください。
◉-1、企業のブランド力の向上
周年記念は、企業が長年にわたり顧客や社会から信頼を積み重ねてきた「確かな実績」を象徴するものです。
特に10年、20年、50年といった節目は、企業の継続性や安定性を社会に示す絶好のタイミングであり、ブランド価値を再定義・強化する重要な機会となります。
このような節目に合わせて、企業理念を込めたメッセージの発信や記念キャンペーンの実施、メディアへの露出を積極的に行うことで、取引先や顧客、さらには求職者に対して「信頼できる企業である」というイメージをより強く訴求することが可能です。
◉-2、社内外のステークホルダーとの関係強化
周年記念は、日ごろから支えてくれている顧客や取引先、株主、地域社会、そして社員に対し、感謝の気持ちを改めて伝える機会です。
たとえば、周年イベントの開催や記念品の贈呈、特別キャンペーンの実施などは、感謝の意を伝えると同時に、相互のつながりを強化する有効な手段となります。
◉-3、企業の理念や歴史、ビジョンの再整理・再発信
周年記念は、これまでの歩みを振り返るだけでなく、企業の原点や存在意義を改めて見つめ直す機会でもあります。
この節目を活かして、「なぜ自社が存在するのか」「どこへ向かっていくのか」という企業理念やビジョンを再整理して、社内外に向けて力強く発信することが可能です。
◉-4、企業のブランド再構築のきっかけ
周年記念は、企業がブランドを再構築する絶好のタイミングといえます。
たとえば、ブランドロゴの刷新やコーポレートメッセージの見直し、Webサイトのリニューアルなど、通常であれば社内外の調整に時間を要する大きな施策も、「○○周年を機に」という明確な理由があれば、受け入れられやすくなります。
節目となる周年をきっかけにすれば、大胆な変革も違和感なく自然に進めることができ、新たなブランドイメージを浸透させたり、企業の次なるステージを切り開くきっかけになったりするでしょう。
◉-5、社員のモチベーション向上と組織力の強化
周年記念は、社員一人ひとりの貢献を称える場としても活用できます。
これまでの歩みや成果を共有することで、「自分たちがこの企業の成長に携わってきた」という誇りや実感が生まれます。
記念式典での表彰や記念動画の上映などを行えば、感謝の気持ちを具体的に伝えられるでしょう。
また、部門を超えて協力する記念プロジェクトの推進は、社員同士の一体感を高めるとともに、組織力の底上げにもなります。
◉-6、採用・広報活動の強化
周年記念は、企業の魅力を内外に伝える広報・採用活動の強化にもつながります。
周年を機に企業理念や社風、ビジョンなどを再定義し、社史や小冊子、特設サイト、映像コンテンツ、SNSなどで発信することで、求職者に対して企業の価値観や文化をより明確に伝えることが可能になります。
また、周年をテーマとした特集や取材など、メディア露出の機会も増えやすく、企業認知の向上やブランドイメージの強化にも効果的です。
特に中小企業や成長中の企業にとっては、外部への認知度を高めるチャンスとなるでしょう。
◉企業の周年記念の方法

企業の周年記念の具体的な方法として、次の7つがあります。
・周年記念のイベント開催
・社外向けキャンペーン・プロモーション
・ノベルティ配布・プレゼント企画
・周年限定商品の販売
・コラボレーション施策
・感謝を込めたメッセージの発信
・オリジナルコンテンツの企画と制作 |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、周年記念のイベント開催
周年記念の方法として代表的なものはイベントの開催です。
従業員やその家族、取引先など、感謝の意を表明した自社に関係する多くの人たちを招くパーティーが節目で開催されます。
このような周年記念の式典やパーティーは、普段過ごしている会社とは異なる空間で実施することが多いです。
たとえば、ホテルなどの豪華な空間を貸し切って開催するなどが考えられます。
自社の周年記念式典およびパーティーの模様を動画に撮影して、後日DVDとして配布したり、広報の一環でプレスリリースを配信したりする方法も良いでしょう。
◉-2、社外向けキャンペーン・プロモーション
周年記念を機に、顧客への感謝を込めた社外向けキャンペーンやプロモーションを実施するのも効果的です。
たとえば「創業○周年記念感謝キャンペーン」として、SNSを活用したフォロー&リポスト企画や、記念品が当たるプレゼント企画を展開するといった方法が挙げられます。
また、特別割引や限定クーポンなどの特典を用意すれば、顧客の購買意欲を喚起し、売上促進にもつなげられます。
周年という明確なテーマがあることで、キャンペーンにストーリー性を持たせやすく、企業のブランドイメージの向上にもつながるでしょう。
◉-2-1、販促イベントの開催
周年記念を盛り上げる施策として、リアルイベントを活用した販促プロモーションも効果的です。
具体的には、以下のような企画が考えられます。
・スタンプラリー・抽選会・スクラッチカードといった参加型の企画
・キッチンカーや地域密着型の出店イベント
・お笑い芸人やパフォーマーを招いたステージ演出 |
来場者が楽しめる体験を企画することで、企業への親近感や好印象を高めることができます。
◉-2-2、周年キャンペーン
周年をきっかけにした、ユーザーに向けたキャンペーンや特典の提供も一つの手段です。
周年記念限定の割引クーポンを発行して、ユーザーにはSNSなどで拡散してもらえる効果が期待できます。
「周年」というキーワードを皮切りに話題性を醸成することで、多くのユーザーと新規でつながるきっかけとなり得ます。
◉-3、ノベルティ配布・プレゼント企画
周年記念を盛り上げる施策として、来店者や参加者への特典としてノベルティを配布するのも有効な方法です。
配布するノベルティは、Tシャツやマグカップ、ボールペンなど、日常的に使える実用性の高いアイテムがおすすめです。
企業ロゴや周年ロゴを入れたオリジナルデザインにすることで、記念品としての価値も高まり、ブランド認知の拡大にもつながります。
◉-4、周年限定商品の販売
周年記念で限定商品を制作して販売するのもよくある方法の一つです。
商品販売を主たる事業とする会社であれば、限定商品をWEBサイトや広告などで打ち出し、消費者にインパクトを与えることができるでしょう。
また、購入者特典としてノベルティをセットにするなど、付加価値を加える施策もおすすめです。
さらに、レストランといった飲食事業であれば、周年記念の限定メニューを提供するのも一案です。
普段は提供されない特別メニューだからこそ、特にリピーターに来店を促すきっかけとなるでしょう
◉-5、コラボレーション施策
周年記念を機に、地元企業や人気ブランドと連携し、コラボレーション商品を企画・販売する方法もあります。
また、インフルエンサーやクリエイターとタイアップした周年記念企画もおすすめです。
限定性や話題性のあるコラボレーション施策は、ファン層の拡大や新たな顧客層へのリーチにつながり、ブランド価値も高められるでしょう。
◉-6、感謝を込めたメッセージの発信
周年記念は、さまざまな人たちに感謝の気持ちを表明する貴重な機会です。
そこで、日ごろの感謝をメッセージカードなどに込めて、社員や取引先の人たちに贈ってみましょう。
周年ならではの貴重なギフトや記念品を用意するのもおすすめです。
◉-7、オリジナルコンテンツの企画と制作
周年記念の施策として、企業独自のストーリーや価値観を伝える「オリジナルコンテンツ」の制作も効果的です。
企業の歴史や理念、社員の声などを活かした多様な表現手段を通じて、社内外へのメッセージ発信とブランディングを強化することができます。
◉-7-1、記念動画
周年の節目に、自社の歩みやビジョンをストーリーとして表現した記念動画を制作する企業もあります。
たとえば、ドキュメンタリーやブランドムービーといった形式で、経営者・社員へのインタビューや現場の風景を織り交ぜることで、リアリティと共感性の高いコンテンツになります。
◉-7-2、周年誌・記念誌・社史
周年の節目をまとめた冊子やデジタルブックも、企業の歩みや価値を可視化する有力な手段です。
たとえば、「年表+エピソード+社員の声」といった構成でストーリー性を持たせることで、読み物としての魅力が高まり、社員の参画意欲も引き出せます。
冊子形式とデジタルブックの併用が一般的で、書店流通は行わないのが基本です。
特にBtoB企業においては、取引先や学生を対象とした採用活動における訴求力が高いことが特徴です。
▶︎周年誌の詳細については、関連記事【周年史とは?出版目的や具体的な制作の流れや活用方法について解説】もあわせて参考にしてください。
▶︎記念誌の詳細については、関連記事【記念誌とは?読んでもらうためのコツや活用アイデアを解説】もあわせて参考にしてください。
▶︎社史の詳細については、関連記事【読まれ、活用される社史を作るコツ!作成後の有効活用方法も解説】もあわせて参考にしてください。
◉-7-3、周年ロゴ・スローガン
ロゴやスローガン、キャッチコピーで周年の世界観を表現する方法もあります。
作成したロゴやスローガンは、名刺・封筒・Webサイト・SNSアイコンなどに展開することで、企業メッセージに一貫性が生まれ、社内外への浸透力が高まります。
◉-7-4、周年記念特設Webサイト・Webページ
周年の世界観を表現する専用のWebサイトや特設ページを制作することで、情報発信を強化できます。
コンテンツとしては、以下のような情報を掲載するのが一般的です。
・企業の歴史タイムライン
・周年のコンセプト
・紹介社員インタビュー
・記念ムービー
・イベント情報 |
イベント終了後もブランドページとして残すことで、持続的なプロモーション資産として機能します。
◉-7-5、書籍出版(企業出版)
周年記念の機会に「書籍出版」を行うことは、企業にとって価値の高い施策といえます。
ブランド資産や企業理念を整理し、社会的信頼性を伴ったメッセージとして可視化できる点が魅力です。
周年記念誌とは異なり、一般書籍として流通させることで、社内外への発信力や信頼性の向上が期待できます。
▶︎企業出版のやり方については、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】もあわせて参考にしてください。

◉企業の周年記念の効果を高めるうえで重要なポイント

周年記念でよくある失敗が、次の4つです。
・準備不足でグダグダのイベントになってしまう
・見た目だけのイベントで終わってしまう
・費用対効果が合わない
・社内の共感が得られなくて終わる |
しかし、このような失敗をすることなく、周年記念を一つのきっかけとして、その後の会社の業績に良い影響を与えることは十分可能です。
具体的には、次のポイントを意識して計画する必要があります。
・1年〜2年前から資料収集をすすめる
・目的を明確にする
・多くの社員を巻き込む
・一貫性のあるコンセプトとメッセージ
・社外への積極的な発信
・周年記念を資産として残す工夫
・振り返りと効果測定 |
企業の周年記念の効果を高めるうえで重要な7つのポイントを見ていきましょう。
◉-1、1年〜2年前から資料収集をすすめる
周年記念に向けて記念誌や社史を制作する場合、大量の資料や記録の収集が必要となります。
過去の社内報や写真、社外の掲載記事、沿革データなど、情報は多岐にわたるため、プロジェクトが本格始動する前段階から、計画的に資料収集や整理を進めておくことが重要です。
早い段階で準備を始めておけば、制作スケジュールに余裕が生まれ、直前になって情報が不足するというトラブルを未然に防ぐことができます。
◉-2、目的を明確にする
周年記念の効果を高めるには、まず「なぜやるのか」「何を達成したいのか」という目的を明確に定めることが不可欠です。
ただ記念日を祝うという目的だけでは、単発のイベントで終わってしまい、その後に続く効果は得られません。
たとえば、「社員のモチベーション向上」「社外へのブランド価値発信」など、具体的な目的を設定することが重要です。
◉-3、多くの社員を巻き込む
周年記念を経営層主導の「自己満足イベント」で終わらせないためには、社員一人ひとりを当事者として巻き込むことが大切です。
具体的な取り組み例としては、以下のような施策が挙げられます。
・周年ロゴの社内コンテスト
・記念ムービーや記念誌への社員の声・写真の掲載
・若手社員を中心とした実行委員会の結成 |
実際にある大手企業では、周年記念の一環として小説仕立ての書籍を制作し、その企画・執筆を若手社員中心のプロジェクトチームが担当しました。
営業やSE、総務などの部署から有志メンバーが参加し、完成した書籍が実際に書店に並んだことで、参加社員のモチベーションや帰属意識が大きく高まったといいます。
このように、自らが関わった成果が形として残る経験は、社内での評価向上やプロジェクトの継続的展開にもつながりやすく、企業全体に良い影響をもたらします。
▶︎書籍出版のやり方については、関連記事【本を出版するには?現役書籍編集者が本の出し方を分かりやすく解説】もあわせて参考にしてください。
◉-4、一貫性のあるコンセプトとメッセージ
周年記念の取り組みでは、企業の「らしさ」を体現した統一感のあるコンセプト設計が不可欠です。
ロゴやスローガン、Webサイト、パンフレット、イベント演出など、すべての要素に一貫したメッセージを通すことで、社内外に強い印象を残すことができます。
また、デザインやコピー、表現のトンマナ(トーン&マナー)を統一することで、ブランドの世界観を効果的に伝えることが可能です。
◉-5、社外への積極的な発信
周年記念は、社外に自社の魅力や存在感をアピールするチャンスです。
次のような複合的なPR手段を使って、計画的な情報発信を行っていきましょう。
・プレスリリース配信+記者向けイベント
・SNS(X、Instagram、YouTube)での周年企画・動画展開
・採用サイトや企業紹介資料への周年要素組み込み
・周辺記念書籍の出版
・周年記念Webサイトの作成 |
こうした施策を複合的に展開し、メディア掲載の機会を増やすことが重要です。
▶︎PRのやり方については、関連記事【企業が広報に使える媒体とは?種類や費用対効果の高い選び方を解説!】もあわせて参考にしてください。
◉-6、周年記念を資産として残す工夫
周年記念で制作したムービーや社史、写真、社員の声などは、継続的なコンテンツとして再活用できます。
たとえば、以下のような活用方法があります。
・採用資料や営業資料への再利用
・SNS投稿やオウンドメディアへの二次展開
・Webサイト内のストーリーページとしての常設掲載 |
周年記念のコンテンツを「1日限り」で終わらせず、長期的に活用することで、ブランド強化にもつながります。
◉-7、振り返りと効果測定
周年記念を終えた後こそ、次への改善に向けた振り返りが欠かせません。
効果測定の方法として、以下があります。
・アンケート・ヒアリングによる社内評価
・SNSでの反応、WebサイトのPV数、取引先からの反響などの外部評価
・成果をまとめたレポート化・社内共有 |
実施して終わりにするのではなく、成果の可視化と評価を通じて、次の周年企画や他のマーケティング施策へと活かしていきましょう。
◉企業の周年記念の計画・実施の手順
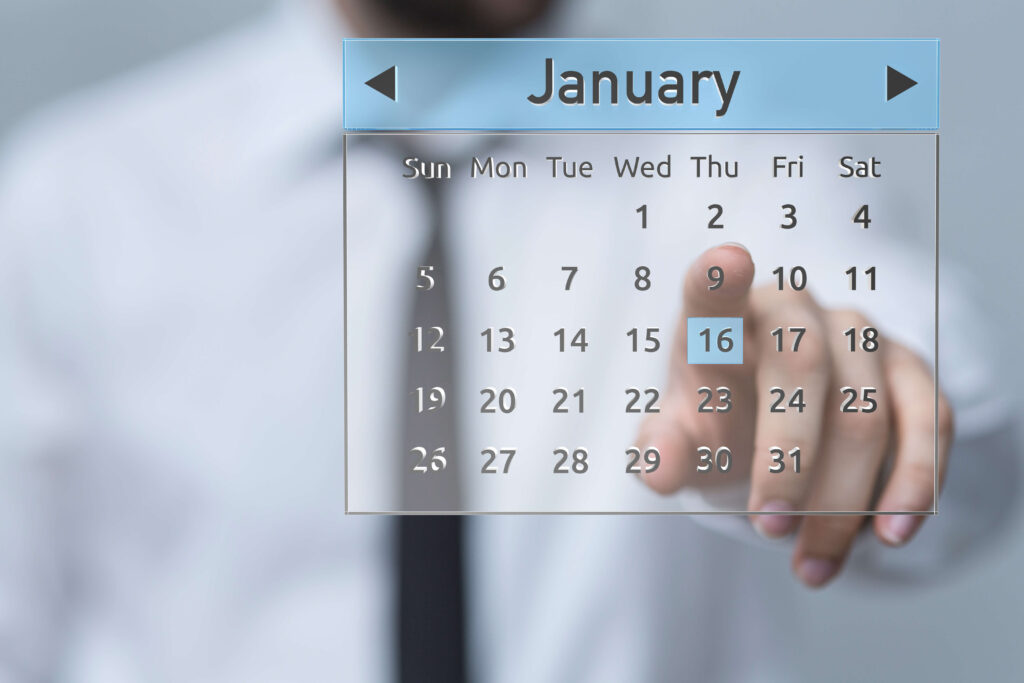
ここでは、企業の周年記念事業を計画・実施する手順について解説します。
一般的には、次の7つのステップで行います。
・ステップ1:【1年前】周年のゴール設定と目標の明確化
・ステップ2:【10ヶ月〜8ヶ月前】周年記念プロジェクト体制の構築
・ステップ3:【10ヶ月〜8ヶ月前】広報・宣伝戦略と大枠のスケジュールの決定
・ステップ4:【8ヶ月〜5ヶ月前】具体施策の企画・外注選定
・ステップ5:【5ヶ月〜2ヶ月前】制作と準備
・ステップ6:【1ヶ月〜当日】周年記念の実施
・ステップ7:【終了後】広報・宣伝戦略と大枠のスケジュールの決定 |
順を追って詳しく見ていきましょう。
◉-1、ステップ1:【1年前】周年のゴール設定と目標の明確化
周年記念のイベントをするにせよ、出版をするにせよ、ゴールの設定は最重要といえます。
周年事業を実施することで、「何を目指すのか」「どう見せたいのか」「どんなことを伝えたいのか」「何を作り出したいのか」といった目的をまず設定しましょう。
さらに、ターゲットの設定も重要です。
社員やその家族がメインのターゲットなのか、もしくは社外の取引先や潜在顧客、採用応募者がターゲットとなりうるのかなど、会社の予算を使って施策を実施する以上は、一つの経営戦略として施策実施後にどのようになっているのかの理想を思い描くと良いでしょう。
◉-2、ステップ2:【10ヶ月〜8ヶ月前】周年記念プロジェクト体制の構築
周年記念事業を成功させるために重要なポイントになるのが「どのようなプロジェクト体制を築くか」です。
準備段階を整えることが、プロジェクト全体の成功を左右するといっても過言ではありません。
まずは、各部門からメンバーを選出し、社内横断型の実行委員会を編成します。
役割ごとにチームを分けるのが一般的で、たとえば以下のような体制が想定されます。
・イベント企画チーム
・制作・クリエイティブチーム
・広報・PRチーム
・予算・進行管理チーム |
それぞれが明確な役割を持つことで、作業の抜け漏れを防ぎ、スムーズな進行を可能にします。
特に周年記念事業は、会社全体を巻き込んで進める「共創型」のプロジェクトとして設計することが重要です。
◉-3、ステップ3:【10ヶ月〜8ヶ月前】広報・宣伝戦略と大枠のスケジュールの決定
周年イベントを実施するには、広報や宣伝活動の戦略立案をしなければなりません。
周年事業をやる以上は知ってもらって、メディアにも取り上げられる、またとない機会だからです。
周年記念式典といったイベント実施の時期を確定させ、その期日に向けてプレスリリースや広告宣伝の準備を行いましょう。
イベントの規模にもよりますが、具体的な企画やアイデアを具現化するまでに半年程度は要すると考えられます。
そのため、広報や宣伝のスケジュールは全体で共有しながら丁寧に進めることをおすすめします。
◉-4、ステップ4:【8ヶ月〜5ヶ月前】具体施策の企画・外注選定
この段階では、周年記念の目的やゴールに基づき、「どのような施策を行うか」の具体的な中身を設計します。
たとえば、以下のような施策の組み合わせが考えられます。
・社内向け:記念式典、社員表彰、記念動画、記念誌
・社外向け:特設Webサイト、書籍出版、顧客向けキャンペーン、展示イベント
・ブランド強化:ロゴリニューアル、タグライン刷新、記念グッズ制作 |
必要に応じて外部パートナー(制作会社・PR会社・デザイナー・ライターなど)を選定してアサインします。
◉-5、ステップ5:【5ヶ月〜2ヶ月前】制作と準備
企画内容と外注先が決まったら、いよいよ実施に向けた制作フェーズに入ります。
記念映像やパンフレット、Webサイト、記念品など、制作物の進行管理に加えて、イベント運営に必要な備品や会場手配、登壇者との調整も行います。
制作はスケジュール通りに進まないこともあるため、修正対応や納期の遅れに備えて、余裕をもった工程管理が不可欠です。
トラブルが発生した際にも慌てず対応できるよう、事前の段取りを丁寧に進めておきましょう。
なお、周年記念に合わせて書籍出版を検討している場合は、他の制作物と比べて取材・執筆・編集などに時間がかかるのが一般的です。
そのため、1年前後の制作期間を見込んでおくとよいでしょう。
特に書籍は早い段階で企画を立ち上げ、全体スケジュールの初期段階から計画に組み込んでおくことが大切です。
◉-6、ステップ6:【1ヶ月〜当日】周年記念の実施
本番当日に向けて各施策の最終チェックを行い、運営チームで緊密に連携しながらリハーサルと確認作業を行います。
特にイベント当日は、「誰が・いつ・どこで・何をするのか」を明確にした詳細な運営マニュアルを準備しておくと安心です。
また、式典や展示の様子、参加者の表情などを写真や動画で記録しておくと、後日のレポート作成やSNS・メディアでの情報発信に活用できます。
◉-7、ステップ7:【終了後】振り返りと今後の情報発信計画の策定
周年記念の実施が無事終了した後も、それで終わりではありません。
施策の成果や社内外の反響を振り返り、今後の企業活動へとつなげる姿勢が大切です。
具体的には、以下のような対応を行います。
・社内向け:実施報告書の共有、アンケートによるフィードバック収集
・社外向け:公式レポートやSNSでの発信、メディア掲載記事の拡散 |
また、周年を機に自社の理念やビジョンを再整理した場合は、それをどのように情報発信していくのかという広報・宣伝戦略やスケジュールを決定します。
これらによって、周年記念事業が一過性ではなく、企業文化として根付くようになります。
◉近年は周年記念の書籍を出版する企業も多い!

近年では、その後のPRに長く活用できるという点や、通常の書籍と同様に書店流通することによる認知度向上の効果が期待できることから、企業出版を活用して書籍を出版する会社が増えてきています。
周年記念を機に書籍出版を行うことによる効果としては主に次の5つが考えられます。
・顧客ロイヤルティ向上に良い影響がある
・競合他社との差別化につながる
・出版を通じた認知度の向上につながる
・求職者にとって良いイメージがつく
・周年記念イベント後も営業・マーケティング・広報に活用しやすい |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、顧客ロイヤルティ向上に良い影響がある
周年記念の施策で重要な要素として考えられるのは、これまでの愛顧の気持ちをイベントやキャンペーンで表すことでしょう。
日ごろの感謝を示すイベントやキャンペーンを実施することで、顧客のロイヤリティ向上が期待できます。
たとえば、宝酒造の人気いも焼酎ブランド「一刻者」の20周年キャンペーンとして実施されたのが、「マストバイキャンペーン」です。
「頑固にこだわって20年」というキャッチフレーズを打ち出し、商品の購入者のうち抽選で500名に「一刻者」オリジナル陶器をプレゼントしました。
信頼の強固なロングセラー商品のファンに対して、オリジナル陶器をプレゼントすることでブランドのより一層のファン化が進んだ事例といえます。
◉-2、競合他社との差別化につながる
周年事業は、その貴重な機会をきっかけに競合他社との差別化を図る手段としても効果的です。
周年を記念した特別な企業ロゴを作れば、他社とは異なる印象をユーザーに印象付けることができます。
前述したキャンペーンやイベントなども差別化にはもってこいの方法ですが、ほか自社ならではの趣向を凝らしたノベルティを作成して配布するなどもおすすめの方法です。
このように競合他社では真似できない特別な手段を用いることで、現代ではSNSでユーザーが拡散してくれるPR効果も期待できるのです。
▶︎競合他社との差別化の詳細については、関連記事【差別化戦略の成功の秘訣ーメリットやデメリット、成功事例とは!?】もあわせて参考にしてください。
◉-3、出版を通じた認知度の向上につながる
周年史は、社内向けに配布するインナーツールと、社内外どちらにも訴求が可能になる流通書籍のタイプがあります。
この流通書籍として周年史を制作すると、一般の書店へ流通・配本されるため、一般読者への認知促進の効果が期待できます。
詳細は後ほどの事例紹介で解説しますが、会社の歴史を紐解く周年史を作ろうとして、結果的に自社製品にスポットを当てた出版をしたことで、全国各地の企業から「商品を仕入れたい」という声が殺到しました。
それだけでなく、出版をきっかけにテレビのディレクターの目にとまり、全国放送のバラエティ番組に著者の出演が決定。全国の視聴者に向けて自社製品のPRをすることができました。
▶︎認知度を上げる方法の詳細については、関連記事【経営者必読!認知度向上の方法と効果的なマーケティングの選択肢】もあわせて参考にしてください。
◉-4、求職者やその親にとって良いイメージがつく
一般市場に流通した書籍を出版している企業という箔がつくことで、求職者にとっては親御さんへの説得材料になります。
たとえば、競合他社に大手がひしめく業界で、書籍を手に取ったことをきっかけに親御さんから子どもに対して、「この企業を受けなさい」と中堅の企業を推薦した事例もあるほどです。
▶︎採用ブランディングのやり方については、関連記事【採用ブランディングとは?選ばれる企業になるための進め方とは】もあわせて参考にしてください。
◉-5、周年記念イベント後も営業・マーケティング・広報に活用しやすい
書籍は、周年記念イベントが終了した後も多方面で活用できます。
配布しやすく、自社の魅力や実績を効果的に伝えられるため、営業やマーケティング、広報活動をする際に役立つでしょう。
具体的には、営業提案時の資料として同封したり、リード獲得施策として配布したりすることで、信頼感を高めることができます。
また、書籍の内容をSNSと連動させて情報発信したり、一部を広報素材としてメディアに提供したりすることも可能です。
◉周年記念出版の成功事例

周年記念で書籍を出版して成功した事例は多々ありますが、ここでは次の3つの事例を紹介します。
・事例1:100周年記念出版をきっかけに商品が爆売れした老舗家具メーカー
・事例2:70周年記念出版が販路拡大に大きく貢献した食品製造会社
・事例3:30周年記念出版が中途採用に大きな効果を発揮した生命保険会社 |
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、事例1:100周年記念出版をきっかけに商品が爆売れした老舗家具メーカー
ある老舗家具メーカーでは、創業100周年を機に記念書籍を出版しました。
著者は当時の経営トップで、廃業寸前の赤字企業をV字回復させた改革の手法を解説する内容となっています。
この書籍が人気テレビ番組の制作スタッフの目にとまり、後に番組出演のオファーへとつながりました。
番組放送後は企業サイトへのアクセスが集中し、サーバーが一時ダウンするほどの反響を呼びました。
結果として、出演からわずか1ヶ月間で前年の売上を超えるという大きな成果が得られたといいます。
なお、この書籍は100周年の前年に出版されたもので、周年事業全体も大きな盛り上がりを見せました。
◉-2、事例2:70周年記念出版が販路拡大に大きく貢献した食品製造会社
愛知県の食品製造会社は、創業70周年をきっかけに書籍を出版しました。
当初は社史の制作を検討していましたが、自社製品の有用性を訴求する書籍を出版することに方針転換しました。
一般的に使用されているサラダ油の過剰摂取に警鐘を鳴らし、その解決策としてこめ油の有用性を説いたのです。
この書籍が反響を呼び、全国から新規取引の問い合わせを獲得することができました。
また、TV番組への出演も決定し、メディアへのPRにも効果がありました。
◉-3、事例3:30周年記念出版が中途採用に大きな効果を発揮した生命保険会社
ある大手生命保険会社では、創業30周年の節目に、自社の理念や事業の意義を広く社会に伝える目的で記念書籍を出版しました。
同社は外資系保険会社との合弁によって日本市場に参入し、ライフプランニングという考え方をより多くの人々に理解してもらう必要性を感じていました。
その一環として、当時教育分野で高い実績を持ち、東京や大阪などの公教育改革にも関わっていた著名人に執筆を依頼。
教育と人生設計の視点を交えた内容により、幅広い層に共感を呼ぶ書籍が完成しました。
書店プロモーションは東京都、大阪府、愛知県などの大都市圏を中心に展開され、結果として7万部を超えるヒットを記録しました。
また、この書籍は社内にも好影響をもたらし、若手社員やマネージャー層への理念浸透に貢献。
さらに、中途採用の新入社員の多くが書籍を通じて企業への理解を深めており、ライフプランナーという職業に対する共感や憧れを育むきっかけにもなりました。
◉【まとめ】周年記念を「将来へ向けての再スタート」にしよう!
この記事では、企業が周年記念を迎えるにあたっての目的や意義、実施までの流れ、そして出版を活用した成功事例について紹介してきました。
周年記念は、企業のこれまでの歩みを振り返ると同時に、これからのビジョンを発信する機会です。
その想いや価値観を社内外に届ける手段として、注目されているのが「書籍出版(企業出版)」です。
フォーウェイが提供する「ブックマーケティングサービス」では、企業の歴史や価値観、創業者の想い、未来への展望などをプロの編集者が丁寧にヒアリングし、一冊の書籍として形にします。
書籍は、周年記念の場を一過性のイベントで終わらせず、その後の営業・採用・ブランディング活動にまで活かせる「資産」として活用できます。
周年記念にあたって書籍の出版にご興味をお持ちの方は、ぜひ一度フォーウェイまでご相談ください。