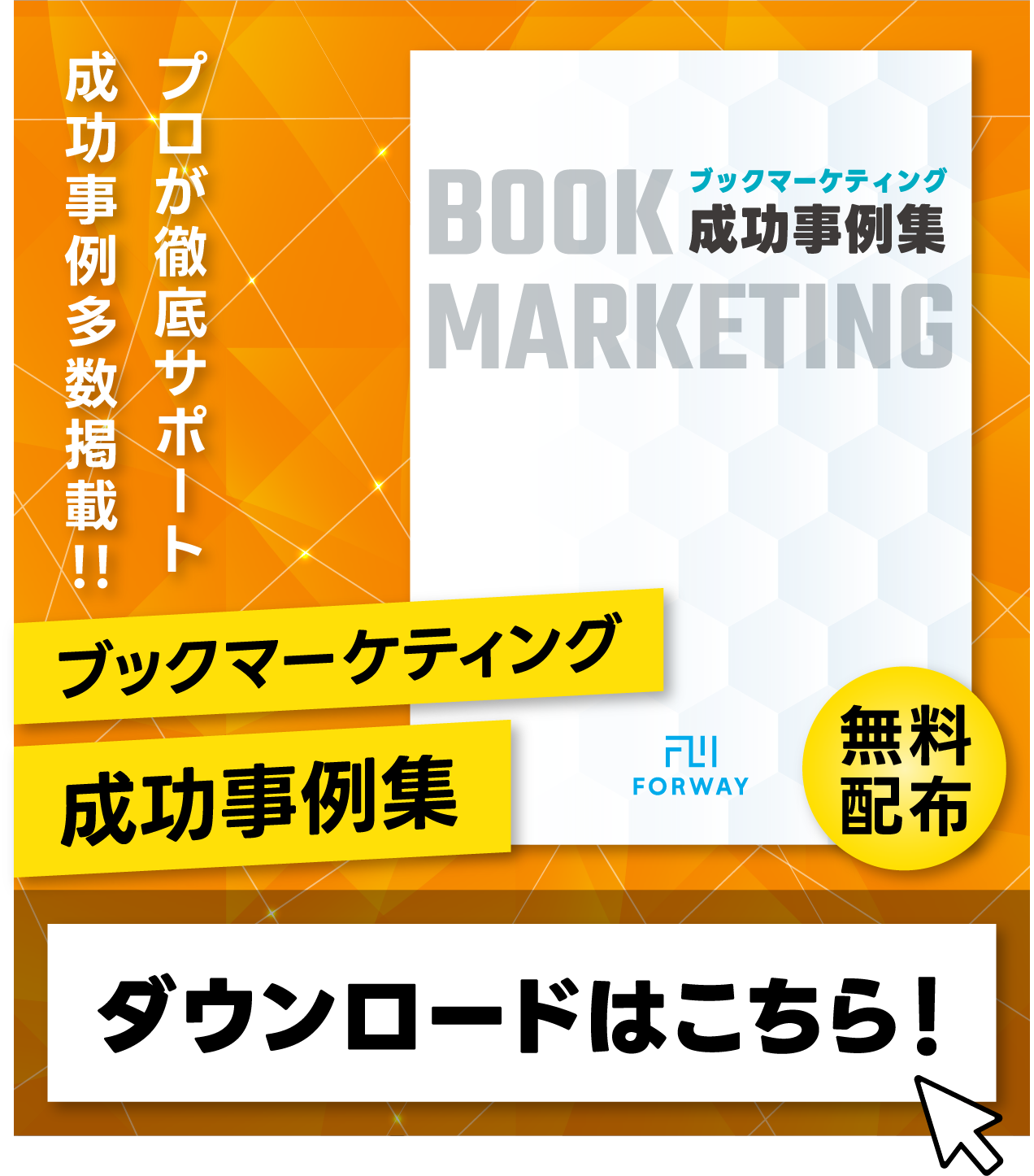Column
フォーウェイは、コンテンツマーケティングで成果を出したい経営者・マーケティング担当者向けの情報を発信しています。
今すぐ自社サイトのSEOを改善させる方法から長期的なブランディングの考え方まで、
実際に弊社のサービスに用いているノウハウを惜しみなく開示します。
2025.12.23
Branding, Marketing
【保存版】SNS運用とは?手順や失敗例、集客につなげる運用術を解説!

企業SNSを運用したいが、やり方がわからないーーこのように考えるマーケティングや広報の担当者は多いことでしょう。
以前は「個人の遊び」という印象が強かったSNSですが、時代はすっかり変わりました。SNSはビジネスにおけるコミュニケーションの重要な一部分である、という認識が多くの企業に浸透してきたのです。
しかし、企業SNSのアカウントが乱立するなかで、ビジネスにおけるメリットをきちんと獲得できているケースはごく一部と言わざるを得ません。
そこで本記事では、企業SNSの運用を考える方向けに、SNSによってビジネスメリットを実現する「運用のやり方」を解説します。
目次【本記事の内容】
- 1.企業のSNS運用とは?
- 1-1.個人のSNS運用との違い
- 1-2.SNSマーケティングとの違い
- 2.SNS運用が重要になっている理由
- 3.SNS運用によって得られるメリット
- 4.各SNSの特徴と運用のコツ
- 4-1.Instagram
- 4-2.X(旧Twitter)
- 4-3.Facebook
- 4-4.LinkedIn
- 4-5.LINE
- 4-6.TikTok
- 4-7.YouTube
- 5.SNS運用を始める前に決めること5つ
- 5-1.決めること①運用の目的
- 5-2.決めること②運用体制
- 5-3.決めること③アカウントの方向性
- 5-4.決めること④ターゲット層
- 5-5.決めること⑤具体的なタスクとスケジュール
- 6.SNS運用の効果測定と運用改善
- 7.SNS運用のよくある失敗例4パターン
- 7-1.失敗例①フォロワー数が増えない
- 7-2.失敗例②運用が止まってしまう
- 7-3.失敗例③運用の方向性が迷走する
- 7-4.失敗例③運用の方向性が迷走する
- 8.SNSの炎上を防ぐ対応策4選
- 8-1.炎上防止策①投稿ガイドラインの策定
- 8-2.炎上防止策②対応ガイドラインの共有
- 8-3.炎上防止策③投稿監視体制の整備
- 8-4.炎上防止策④炎上事例の社内共有
- 9.SNS運用を成功させるためのコツ
- 9-1.目標を明確にする
- 9-2.一貫性のある情報発信を意識する
- 9-3.質の高いコンテンツを作成する
- 9-4.データ分析に基づいた改善を行う
- 9-5.ほかの集客施策と組み合わせる
- 10.SNS×ブックマーケティングの相乗効果とは?
- 11.SNS×ブックマーケティングで集客に成功した事例
- 11-1.書籍出版とSNSの連動で問い合わせ・受注が劇的に増加した事例
- 11-2.発売前からSNSを活用し、話題化に成功した事例
- 12.SNS運用に関するよくある質問
- 12-1.SNSは毎日投稿しなければならない?
- 12-2.どのようなコンテンツを投稿すればよい?
- 12-3.外注の運用パートナーは入れるべき?
- 13.【まとめ】SNSとブックマーケティングを掛け合わせて、集客効果を高めよう!
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター) 慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
企業のSNS運用とは?

企業にとってSNS運用は、ビジネスの成長に欠かせないものとなっています。
企業のSNS運用は、一言でいえば「ビジネス目的」である点が最大のポイント。
個人のアカウントに比べてよりプロフェッショナルで戦略的な運用のやり方が求められます。
個人のSNS運用との違い
個人のSNS運用は、主に自己表現や交流が目的です。
もちろんSNSを通じたマネタイズに成功しているインフルエンサーなどの個人はいますが、そうした人たちはビジネス目的の運用という意味で、個人の趣味的なアカウントとは違う種類の運用だと言えるでしょう。
企業のSNS運用は、商品やサービスのプロモーションやブランドイメージの向上など、ビジネス上の目的があります。
そのため、やり方としても投稿内容や投稿頻度、ターゲット層など戦略的な視点が求められます。
また、ユーザーに悪印象を与えないようにする気配りも、個人アカウントに比べてより重要になるのです。
SNSマーケティングとの違い
SNSマーケティングは、SNSを活用してマーケティング活動を行うことです。
具体的には、下記のようなやり方があります。
| ・インフルエンサーマーケティング ・SNS広告運用 ・ソーシャルリスニング ・SNSキャンペーンの実施 |
総じていえることとして、費用を投じたタイミングにだけ効果を発揮し、商品購入や問い合わせなど直接的なリターンを目指すのがSNS運用以外のSNSマーケティングです。
広告施策としての色が強い取り組みとも言い換えられます。
一方で、SNS運用はSNSマーケティングのくくりにはありますが、下記のような特徴があります。
| ・オーガニック投稿として自由度の高い発信が可能 ・ユーザーとのコミュニケーションによりファン化を促進できる ・運用をやめたり頻度を鈍らせたりしてもアカウントや過去の投稿は残る ・一度フォローしてもらったユーザーをアカウントの資産として持ち続けられる ・長期にわたる施策の継続がやりやすい |
長期的なブランディングを目指したり、マーケティングの基盤を作ったりといった目的を達成するために適しているのがSNS運用です。
参考:SNSマーケティングとは?代表的な手法から戦略立案、成功事例まで徹底解説|株式会社ビーステップ
SNS運用が重要になっている理由

SNS運用がビジネスにおいて重要になっているトレンドは、データからもわかります。
「ソーシャルメディアマーケティング市場、2023年ついに1兆円を突破の予測【サイバー・バズ/デジタルインファクト調べ】」(https://webtan.impress.co.jp/n/2022/11/11/43642)によると、ソーシャルメディアマーケティングの市場規模は2020年の5,971億円から2022年には9,317億円へと大幅増加。
2027年には1兆8,868億円にまで市場が拡大すると推計されています。
SNS運用はやり方を工夫すれば大きなリターンを得られる一方で、フォロワーを増やすためにはどうしても一定の時間が必要です。
SNSの市場が伸びていくなかで、早く始めた企業ほど成功に近づくのは間違いありません。
SNS運用によって得られるメリット
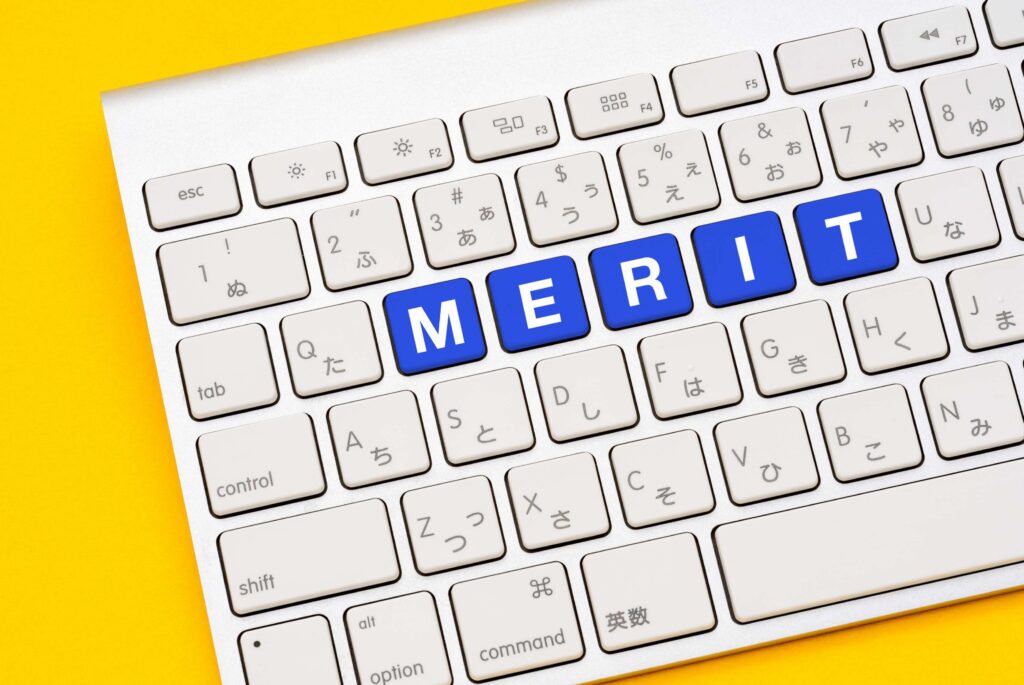
ここで、企業のSNS運用によって得られるメリットを改めて整理しましょう。
大きくいうと、以下の通りです。
| ・商品やサービスのプロモーションができる ・自社ターゲット層に直接訴求できる ・顧客とのコミュニケーションを深めることができる ・企業のブランドイメージを向上させることができる ・リアルタイムな情報の発信が可能になる |
いずれにも共通するのが、SNS運用によるメリットの発揮とは運用のやり方にかかっているということです。
SNSアカウントがあるだけで売上につながるような理想的状況を作るには、狙ったターゲット層のフォロワーをたくさん抱えた「強い」アカウントを作る労力を惜しまないことが、成功事例に共通した特徴です。
各SNSの特徴と運用のコツ

ビジネスでよく活用されるSNSは、主に以下の7つです。
| ・Instagram ・X(旧Twitter) ・LINE ・Tik Tok ・YouTube |
各SNSの特徴と運用のコツを詳しく解説します。
Instagramは、写真や動画を投稿するSNSです。
ビジネスにおいては、商品の宣伝やイメージアップに活用されることが多く、特に若い世代に人気があります。
ただ、40代以上の層も利用率は低いものの、実数でいうと若年層に匹敵しており、実は全年齢に向けたアプローチにも使えます。
Instagramの運用のポイントは、以下の通りです。
| ・ハッシュタグや発見タブによって投稿を検索されやすくする ・投稿のビジュアルについて方向性を定め、ユーザーに価値を感じてもらえる投稿を一定頻度で続ける ・ストーリーズ機能を使い、日常的な情報を発信することでフォロワーとのコミュニケーションを深める ・インスタライブを使い、フォロワーとの関係性をより強化する |
勘違いされがちですが、「発信者のビジュアルが優れていて顔出しできる」「商品のきれいな宣伝写真がたくさんある」などの要素はInstagram運用で必須ではありません。
「商品のターゲット層が興味を持つノウハウを発信する」「日常風景の投稿でユーザーと距離感を縮める」など企画の方向性によって、あらゆるビジネスでInstagramの強みを発揮できます。
X(旧Twitter)
X(旧Twitter)は、140文字以内(X Premium加入者はそれ以上も可能)の短い文章を投稿することができるSNSです。
主にリアルタイム情報の収集や発信に使われ、特にニュースやトレンドに関する情報が多く取り扱われています。
Xの運用のポイントは、以下の通りです。
| ・アカウントのテーマに沿った自分なりの「情報提供」と「持論」を発信してフォロワーを増やす ・ほかのアカウントとコミュニケーションを増やし、タイムライン上の表示優先度を高める ・ほかのアカウントをフォローし、フォロー返しを獲得することでフォロワーを増やす |
Xは実名顔出しで運用するアカウントが多く、アカウント同士のコミュニケーションが重視されるカルチャーのSNSです。
企業アカウントとして活用する場合でも、事務的な発信だけでなく「中の人」の人柄が感じられるアカウントが好まれる場合があります。
リツイート機能でツイートが大きく拡散される仕様により、投稿が大きくバズる可能性のあるSNSでもあります。
Facebookは、世界で最も利用者数の多いSNSの一つです。
友達や家族とのコミュニケーションが中心ですが、ビジネスにも活用されることが多く、商品の販売やブランドの発信などに使われます。
Facebookの運用のポイントは、以下の通りです。
| ・定期的にコンテンツを投稿することで、フォロワーの獲得やエンゲージメントの向上を目指す ・Facebookページを作成し、“いいね”を獲得することで拡散力を高める ・Facebookグループを作成し、ファンコミュニティを形成することで、ファンとの交流を深める |
Facebookは一定年齢以上の人のビジネス活用においては根強い人気のあるSNSです。
ただ、友達に追加する人数に5000人という制限があるため、つながりをたくさん増やして大きく拡散しようとする運用方針には向きません。
関係性のある相手から自社への認知を維持したり、仕事の相談をもらいやすくしたりする運用がFacebook活用のコツです。
LinkedInは、ビジネス関係者が集まるSNSです。
求人情報やビジネスマッチングなどに使われることが多く、ビジネスユースに特化したSNSであるといえます。
LinkedInの運用のコツは、以下の通りです。
| ・原則実名登録なので、反感を招くような投稿は避ける ・ほかのアカウントと交流し、コミュニティなどにも積極的に参加する ・ターゲットに対して積極的にDMを送る |
いわゆる営業のためのDMや採用DMはほかのSNSだと嫌がられる場合がありますが、LinkedInはビジネスSNSである側面から、ほかアカウントへの直接アプローチは比較的、受け入れられているのが特徴です。
ただし、大量のスパム送信はLinkedIn側から制限をかけられる危険があります。
丁寧に絞り込んだターゲットアカウントに対し、一通一通、心を込めてDMを送ることが成果の秘訣です。
LINE
LINEは日本国内において、幅広い世代で利用されているSNSです。
2025年3月末時点のLINEアプリ月間アクティブユーザーはLINEの自社調べで約9,800万人、2023年1月1日時点の日本の人口約1億2,475万から推計すると、約70%以上が使っていることになります。
LINEにはビジネス用にLINE公式アカウントを開設できるサービスがあり、企業や店舗が友だち追加してくれた顧客に情報発信できます。
LINEの公式アカウントには以下のような特徴があります。
| ・リピーターが増える・売上につながる ・機能が充実・操作は簡単 ・目的・用途に合わせて選べる料金プラン |
LINEが2021年7月に行った携帯電話のアンケートでは、LINE公式アカウントからメッセージを受け取って約80%がその日のうちに開封されていることが分かりました。
また、「よく行くお店のアカウントがあったら、友だち追加・フォローしたいサービス」として、57.8%がLINEと回答しています。
それだけ情報源としてLINEを活用したいと考えているユーザーは多く、リピーターの獲得や売上の向上につながりやすいSNSです。
LINEの公式アカウントはポイントカードの発行管理やクーポンの配信のほか、オリジナルのサブスクリプション型サービスを作成できます。
各種販促ツールも使えるなど、集客から販促まで活用できる機能が充実しているのもメリットでしょう。
3つの料金プランがあるため、想定するメッセージ数など、自社の状況に応じて選べます。
参考:LINEヤフーfor Business「LINE公式アカウント」
参考:総務省統計局「人口推計-2023年(令和5年)1月報-」
TikTok
Tik Tokは15~60秒程度の短い動画を投稿できるSNSで、X(旧Twitter)やFacebook、LINEなどに比べると比較的新しいサービスです。
Tik Tokの特徴は、以下の通りです。
| ・短尺動画がメイン ・若年層に人気 ・トレンドに敏感 ・拡散力が強い |
特に10~20代のユーザーが中心ですが、全世代でも利用率が伸びています。
総務省情報通信政策研究所が発表している「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」では、情報通信メディアの利用時間が報告されています。
主なソーシャルメディア系サービスやアプリの全世代利用率をみると、Tik Tokの利用率は2018年では10.3%でしたが、2020年には17.3%、2023年には32.5%にまで伸びました。
また、2023年の全世代利用率は32.5%であったのに比べ、10代は70.0%、20代では52.1%となっており、10~20代のユーザーが多いことが分かります。
短尺動画がメインということもあり、スキマ時間でも気軽に視聴しやすいのがTik Tokのメリットです。
限られた時間に伝えたい内容を盛り込む必要がありますが、「視覚的なインパクトを与えられる」「テンポの良いリズムで記憶に残りやすい」などのメリットがあります。
流行の音楽・ダンスや「○○チャレンジ」のようなトレンドに敏感な投稿が多く、ユーザーを巻き込み、拡散力が強いのも注目すべきポイントです。
Tik Tokには、ビジネス用の広告プラットフォーム「Tik Tok for Business」があります。
細かい設定の必要もなく、無料の動画広告制作ツールなどを利用して広告配信まですべてオンラインで完結します。
参考:総務省情報通信政策研究所「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」
YouTube
YouTubeの特徴は以下の通りです。
| ・短尺動画から長時間の動画まで投稿が可能 ・ライブ配信もできる ・利用者の年齢層が幅広い |
YouTubeはTik Tokとは異なり、短尺動画だけではなく情報量の多い長時間の動画も投稿できます。
単に自社の商品やサービスを紹介するだけにとどまらず、商品の使い方を実演して見せるなど、How-To動画の提供も可能です。
リアルタイムで情報が更新されていくフロー型のSNSはバズって一気に拡散される可能性がある一方、短期間で忘れ去られることも考えられます。
しかし、YouTubeはストック型の動画として、コンテンツを蓄積しておけます。
たとえば、ギフト商品を扱う企業のコンテンツとして、「新社会人への贈り物におすすめのアイテム」や「お祝いのマナー」などの動画をアーカイブとして残しておいたとしましょう。
フロー型のSNSのように爆発的な拡散力はないかもしれませんが、ギフトを贈るシチュエーションでは、一定の再生回数を得られます。
YouTubeのコンテンツから自社のWebサイトへ誘導できるようにしておけば、売上にも結びつきやすくなります。
有益なコンテンツが蓄積されていくと中長期的に顧客の信頼を得られるメリットがあるため、ターゲット層が求める情報を把握し、コンテンツを充実させていくことが重要です。
新商品の発表会やセミナーなどには、ライブ配信も活用できます。
総務省情報通信政策研究所の「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によると、YouTubeの全世代の利用率は、2014年時点ですでに65.1%でした。
その後も徐々に利用率は上がり、2023年では全世代で87.8%です。
利用者の年齢層も幅広く、2023年時点では60代では66.3%にとどまっているものの、50代以下では80~90%台の高い利用率になっています。
幅広い層に自社の商品・サービスをアピールできるため、活用の幅は広いでしょう。
参考:総務省情報通信政策研究所「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」
SNS運用を始める前に決めること5つ

続いてはSNS運用の実践編です。
SNS運用は、やり方を決めずにとりあえず始めてみても成功率は低いです。
ビジネスにつなげるためには、事前準備がカギを握ります。
事前準備として考えるべき項目は、以下の通りです。
| ・決めること①運用の目的 ・決めること②運用体制 ・決めること③アカウントの方向性 ・決めること④ターゲット層 ・決めること⑤具体的なタスクとスケジュール |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
決めること①運用の目的
SNSを始める前に、まずは運用の目的を明確にすることが必要です。
たとえば、ブランド認知度の向上や製品やサービスの販売促進、情報発信や顧客対応など、目的はさまざまです。
目的に応じて運用するSNSの種類やコンテンツや投稿頻度、投稿内容、ターゲット層などが異なるため、運用の目的をはっきりと決めてから取り組むことが重要です。
気をつけたいのが、「運用目的は売上に決まっているでしょ」と単純に決めてしまうこと。
SNS運用は短期的な売上効果だけでなく、ブランディング効果やファンユーザーの獲得などさまざまな尺度での効果を視野に入れる必要があります。
長期的にアカウントを育てる施策だけに、短期の集客では広告施策より数値が劣る場合が多く、運用目的を売上だけと定めてしまうとスムーズな運用が進まない危険性が高いのです。
「短期で何を目的にするのか」「中期〜長期で何を目指すのか」など、細かく設計するのが成功するコツです。
▶︎SNS運用の目的設定については、過去コラム『SNS運用で大切な「目的設定」とは?運用効果を最大化する秘訣を徹底解説』で解説しているので、こちらもご参照ください。
決めること②運用体制
SNS運用では、運用担当者やチームの体制を整えることも大切です。
運用にあたっては、「誰が投稿するのか」「どのようなスケジュールで投稿するのか」「コメントやメッセージの返信は誰が担当するのか」といったことを明確にしておく必要があります。
また、社内で運用する場合は、社員の研修やマニュアル作成なども必要かもしれません。
会社としてSNS運用に取り組むときの体制で重要なのは、組織として担当者をフォローアップして運用を管理する仕組みをつくることです。
社内の担当者はほとんどの場合、SNSのプロではありません。
「いい感じにやっておいてくれ」と丸投げして放置していると、運用の目的が達成できないどころか投稿やアクション自体が止まってしまうケースも珍しくありません。
自社の貴重なリソースを使って、徒労に終わらないように気をつけましょう。
決めること③アカウントの方向性
SNSアカウントの方向性についても、事前に決めておくことが重要です。
たとえば、ファッションブランドのアカウントであれば、コーディネートの紹介や新作アイテムの情報を発信することが求められます。
一方で、医療機関のアカウントであれば、健康情報や病気の予防・治療についての情報提供がいいかもしれません。
アカウントの方向性を明確にしておくことで、フォロワーの期待に応えることができ、効果的な運用が可能になります。
たとえば、SNS運用の代行を請け負うプロであれば、クライアントへのヒアリングをもとにペルソナシートやアカウント構成シートといった資料を作成します。
ターゲット層や運用目的に合わせてデザインのトンマナから投稿文体まで細かく設定し、ブレない運用を実現するのです。
決めること④ターゲット層
SNSを利用するユーザーは、それぞれ年齢層や性別、興味関心、ライフスタイルなどが異なります。
運用するアカウントのターゲット層を明確にし、その層に合った投稿やコンテンツを提供することが必要です。
また、ターゲット層に応じて、運用するSNSや投稿する時間帯、投稿内容、コンテンツの種類なども変わってきます。
このターゲット設定は、「30代以上の女性」など大まかすぎるくくりではあまり意味がありません。
よくマーケティングで使われる「ペルソナ(代表的なターゲット像の架空のプロフィール)」を設定するのも効果的でしょう。
誰か一人に深く刺さるコンテンツはほかの人にも刺さるというのがSNS運用の原則です。
決めること⑤具体的なタスクとスケジュール
SNSの運用においては、具体的なタスクとスケジュールを決めておくことが大切です。
どのようなコンテンツを、どのようなタイミングで発信するのかを明確にすることで、運用がスムーズに行われます。
また、週次や月次での運用の報告や評価を行い、必要に応じて改善を行うことも大切です。
コツとしては、とにかくあいまいさを残さないこと。
「ネタがあるときに投稿する」「なるべくほかのアカウントに“いいね”する」といったルール設定ではなく明確に行動目標を決めましょう。
実際に運用をしてみると担当者に負担がかかりますが、強いアカウントを育てるにはそれなりの努力が必要です。
SNS運用の効果測定と運用改善

「SNSの運用成果は、どうやって評価・改善すればよいの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
SNS運用の効果を可視化するためには、以下のような指標を活用します。
| ・フォロワー数 ・リーチ数 ・エンゲージメント数(「いいね!」やコメント数など) ・コンバージョン数(集客数、商品の売上数など) |
計測すべき指標は、運用目的やどのSNSを用いるかによって変わってきます。
たとえば、対面アポイントの獲得を目標にする運用なら、DMのうちのアポイント率が指標になるでしょう。
改善項目としては普段の投稿の質よりも、アカウントの信頼性を高めるためのフォロワー増やDM文面の改善などの優先順位が高くなります。
おすすめとして、ある程度フォロワーが増えるまではフォロワー数だけをKPIにするのが良いでしょう。
SNS運用による効果の多くは、ある程度フォロワーがいないと発揮されにくいためです。
管理をシンプルにすることで運用もスムーズになります。
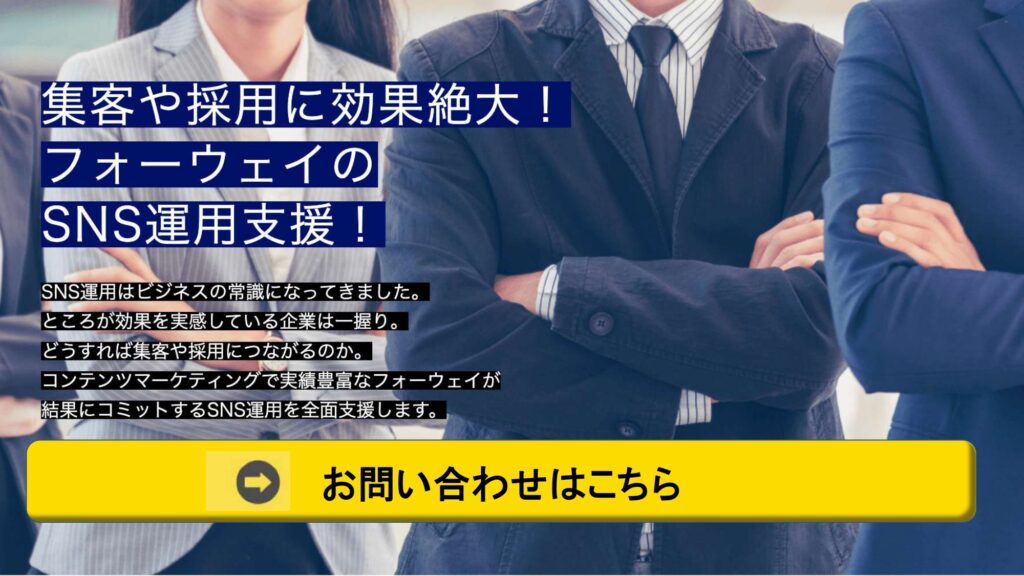
SNS運用のよくある失敗例4パターン
SNS運用をする際には、失敗の典型例に当てはまらないよう注意して運用しましょう。
よくある失敗例として、以下の4パターンがあります。
| ・失敗例①フォロワー数が増えない ・失敗例②運用が止まってしまう ・失敗例③運用の方向性が迷走する ・失敗例④炎上してしまう |
それぞれ詳しく解説します。
失敗例①フォロワー数が増えない
思うようにフォロワーが伸びないのは、SNS運用で最もよくある失敗ケースです。
理由として、たとえば下記が考えられます。
投稿頻度が低い
多くのSNSは、自アカウントの投稿がほかのユーザーのタイムラインに表示されることでフォローが発生します。
したがって、投稿が少なければどんなにアカウントを作り込んでいてもフォロワーが増えるチャンスはほとんどありません。
最低でもInstagramなら週3回、Xなら1日1回は投稿が必要です。
ほかアカウントとのコミュニケーション不足
「いいね」や「コメント」などほかのアカウントに対して自分からアクションするのも、フォロワーを増やすためには重要です。
ここを怠るとフォロワーはほとんど増えません。
ただし、アクションする先のアカウントの選定にもコツがあります。
リアクションを返してくれそうなアカウントや信頼度の高いアカウントの共通点を見出し、適切な相手に対してコミュニケーションを取る必要があります。
失敗例②運用が止まってしまう
SNS運用がストップしてしまう失敗事例はとても多いです。
その理由のほとんどは、はっきり方針を決めずに担当者に丸投げしたきり管理しない運用体制にあります。
投稿スケジュールの明確な設定と投稿物の確認、定例の確認ミーティングなどは組織内で必ず行いましょう。
また、「売上につながっていないからものすごくクオリティの高い投稿をしなきゃ」など、成果を焦って答えのない課題を設定してしまうのも投稿ストップの原因になります。
SNSは定期的にコンテンツを発信して自アカウントにあった運用のやり方を探っていくプロセスがとても重要です。
クオリティにこだわりすぎるよりも継続的な運用を重視しましょう。
失敗例③運用の方向性が迷走する
SNSの運用は、アカウントの方向性を守ることが重要です。
失敗例②に近いですが、成果を焦って方向性の切り替えを連発し、コンセプトのよくわからないアカウントになってしまうのもよくある失敗パターンです。
どんな方向性を試してみても、運用初期に一つの投稿でわかりやすい効果が発揮されることはなかなかありません。
まずは運用開始前のコンセプト設計を細かく行い、決めた方向性に則って腰を据えて取り組みましょう。
そうすれば長期的な成果に高い確率でつながります。
失敗例④炎上してしまう
SNSの運用で最も避けたい失敗が「炎上」です。
一度炎上してしまうと、ブランドイメージに大きなダメージを与えかねません。
具体的な炎上理由として、以下の3つが挙げられます。
| ・不適切な表現や誤解を招く ・投稿社内の機密情報や個人情報の漏えい ・社会的背景を無視した不用意な発言 |
悪気はなくても、意図せず自社の投稿がネガティブに解釈されることもあります。
炎上すると信頼回復にも長い時間とコストがかかるため、炎上リスクを理解したうえで活用することが重要です。
SNSの炎上を防ぐ対応策4選

SNS運用において、炎上を気にする方は多いかもしれません。
企業のSNS活用が普及するにあたって、炎上してしまった事例も多く聞かれるようになりました。
そこで以下に、SNSの炎上を防ぐための対応策を紹介します。
| ・炎上防止策①投稿ガイドラインの策定 ・炎上防止策②対応ガイドラインの共有 ・炎上防止策③投稿監視体制の整備 ・炎上防止策④炎上事例の社内共有 |
4つの炎上防止策を見ていきましょう。
炎上防止策①投稿ガイドラインの策定
SNS運用を始める前に、社内でSNSマニュアルを策定しましょう。
このマニュアルには、発信内容のチェックや、危険な発言を行わないようにするためのガイドラインなどが含まれています。
ガイドラインを設定する際には、ぜひSNS慣れした若いスタッフの力を借りてください。
普段からSNSに慣れ親しんだ人間であれば、それぞれのSNSにおけるマナーを感覚で理解しています。
若いスタッフにたたき台をつくってもらったうえで、広報やリスク管理担当などプロの目で見てブラッシュアップする進め方がおすすめです。
炎上防止策②対応ガイドラインの共有
もしも炎上騒ぎが起こってしまった場合には、迅速かつ的確な対応が必要です。
SNS上でのトラブルの拡散を防ぐために、炎上した場合には速やかに謝罪し、原因究明を行いましょう。
ただし、SNS運用に慣れていない企業が担当者任せにする体制は危険です。
機転をきかせたつもりが火に油を注いでしまう可能性もあります。
投稿物だけでなく、炎上懸念がある場合の対応についても社内でガイドラインを設定し、フローを明確にするのがおすすめです。
弁護士やPR会社などの外部専門家にリアルタイムで相談できる体制を構築しておくのも効果的でしょう。
炎上防止策③投稿監視体制の整備
SNS上でのトラブルを未然に防ぐためには、定期的にSNSのコンテンツを監視し、問題のあるコメントや投稿に対して迅速に対応することが必要です。
また、不適切なコメントや投稿があった場合には、速やかに削除し、投稿者に対して注意喚起を行う必要があります。
投稿の監視には、「上司が毎日11時にチェック」「広報が朝礼でチェック」など、担当者ではなく第三者的な目線でチェックを入れる決まりごとを作っておきましょう。
社内リソース的に難しければアルバイト数人でチェックする体制でも、一般的な目線による第三者チェックは入れられます。
さらに、SNSコンテンツの監視を効率化するために、ソーシャルリスニングツールの活用もおすすめします。
Meltwaterのソーシャルリスニングツールは、SNSの投稿をリアルタイムで一元的に分析できるため、炎上の火種となりうる投稿の把握に役立ちます。
炎上防止策④炎上事例の社内共有
SNSの炎上を防ぐのに大事なのは、抽象的ながら社内のリテラシーです。
関係者の知識を増やし教育をしていくのが、時間はかかりますが炎上を防ぐために有効な施策です。
そこで、日々SNS上の炎上情報をウォッチし、社内で定期的に共有、ポイントを話し合う機会を設けましょう。
特に自社と業種や運用目的の近いアカウントが炎上してしまった事例は、貴重な学習材料になります。
SNS運用を成功させるためのコツ

SNS運用を成功させるためには、以下のようなコツがあります。
| ・目標を明確にする ・一貫性のある情報発信を意識する ・質の高いコンテンツを作成する ・データ分析に基づいた改善を行う ・ほかの集客施策と組み合わせる |
5つのコツについて詳しく解説します。
目標を明確にする
SNSを運用する際に重要なのは、「何のためにSNSを活用するのか」という目的とゴールを明確にすることです。
「自社の認知度を高めたいのか」「商品の購入につなげたいのか」「採用を強化やブランディングに力を入れたいのか」など、目的によって取るべき施策も違ってきます。
認知度を高めるのが目的なら、「SNS経由のWebサイト訪問者数を20%向上させる」のように、具体的な目標も設定できます。
目標を明確にすれば成果も見えやすく、投稿内容やKPI設定、分析の方針もブレません。
一貫性のある情報発信を意識する
SNSは「ブランドの人格」を映し出す場所です。
そのため、情報発信の仕方や内容に一貫性を持たせ、自社のイメージを損なわないようにする必要があります。
ビジュアルや投稿のトーンがバラバラでは、ユーザーに混乱を与えかねません。
たとえば、「シンプルながら温かみを感じる」イメージがそのブランドの「らしさ」ならば、色味やフォントもそのイメージに合わせて統一し、言葉選びも世界観や価値観に合わせるように心がけてください。
一貫性のある情報発信として、定期的なシリーズ投稿を設けるのも効果的です。
「このブランドらしさ」が定着すれば、ファンを育てることができます。
質の高いコンテンツを作成する
次々に投稿が更新されていくSNSは、情報量が膨大です。
ユーザーのスクロール速度も早いため、そのなかで目を留めてもらうためには、「質」の高いコンテンツが欠かせません。
そこで、以下の3点を意識することが重要です。
| ・見た瞬間に内容が伝わるビジュアル ・読者の悩みや興味に刺さるコピー ・保存したくなるようなノウハウ情報 |
読者の悩みや課題を解決する情報や興味を掻き立てるコピーで注意を引き、ビジュアルで内容がイメージできるようにしましょう。
一方的に商品やサービスをアピールするのではなく、保存したくなるような情報や再生したくなる動画などを盛り込むことが大切です。
データ分析に基づいた改善を行う
SNS運用は、「投稿して終わり」ではありません。
「どの投稿が反応を得られたのか」「どの時間帯の投稿が効果的なのか」など、以下の3点を踏まえた分析と改善が必要です。
| ・インサイト(解析ツール)を定期的にチェックする ・投稿のA/Bテストを行う ・KPI(リーチ数、保存数、クリック率など)を可視化する |
まずは、インサイト機能で定期的にリーチ数やフォロワー数、クリック率などをチェックし、記録してください。
特定の要素だけを変更した場合の成果を比較できるA/Bテストを実施すると、より高い成果を得られるパターンを見つけられます。
また、目標達成に向けた進捗を示すKPIは、可視化しておくと成果が見えやすいでしょう。
改善を繰り返すことで、SNS運用の精度は上がっていきます。
ほかの集客施策と組み合わせる
企業のSNS運用は、単体で完結させるものではありません。
SNS運用でより高い成果を生むポイントは、ほかの集客施策との組み合わせです。
SNSは、あくまでも入口であり、その先にある情報や体験にうまく接続できるかどうかがポイントになります。
ほかの集客施策との相乗効果でより高い成果を生み出し、ブランド理解や信頼構築はもちろん、行動喚起まで導くことが可能です。
SNSとの組み合わせで効果的なのは、以下の4つです。
| ・ブログ ・オフラインイベント ・広告運用 ・ブックマーケティング |
各施策との組み合わせによる効果について、以下で詳しく解説します。
Webサイト・ブログとの連携
SNSとWebサイト・ブログとの連携でSNSから公式Webサイトやブログに誘導できると、商品の購入や問い合わせなどのコンバージョン(成果)に結びつきやすくなるのがメリットです。
ユーザーにとって、SNSは気軽にチェックできる点がメリットですが、一度の投稿で提供できる情報量はそう多くありません。
一方、情報が流れていくSNSとは違い、Webサイトやブログは必要な情報が整理されていて見つけやすい特徴があります。
SNSで興味を持ったユーザーを公式Webサイトやブログに誘導できれば、より自社の商品やサービスの詳細情報を紹介できます。
たとえば、新商品発売の告知はSNSで行い、機能の詳細や開発秘話などはブログ記事で公開するのも効果的な方法です。
「続きはプロフィールURLから!」のようにSNSの投稿からの導線を敷いておくと、興味を持ってくれたユーザーを確実にWebサイトに呼び込めます。
オフラインイベント・店舗との連携
以下のような施策により、SNSと実店舗やイベントを連動させることで来店促進やブランド体験の共有が可能です。
| ・SNSでイベント情報を事前告知する ・ストーリーズやライブ配信で現場の臨場感を伝える ・イベント参加者にハッシュタグ投稿を促す ・SNS経由での限定クーポンや特典を用意する |
SNSを使ってあらかじめイベントの情報提供やクーポンの配信などを行うと、興味を持ってくれたユーザーの来店を促しやすくなります。
イベントを開催する際、当日参加できない方に向け、InstagramのストーリーズやYouTubeのライブ配信などで発信すれば、現場の臨場感も伝えられるでしょう。
参加者にハッシュタグ付きの投稿を促すことで、イベントの情報拡散も期待できます。
BtoB企業なら会社説明会や展示会、セミナーや講演イベントなどをSNSと結び付けても、同様の相乗効果が期待できます。
ただし、BtoBの場合は成果を即時に得ることよりも、「信頼形成」や「専門性の訴求」が重要です。
オフラインイベントとSNSを掛け合わせてブランドの熱量を可視化することで、営業活動の後押しとなるケースもあります。
広告運用との組み合わせ
SNSはコストを抑えて広告宣伝できるのが大きなメリットですが、広告を使用せずにコンテンツを配信できる無料のオーガニック投稿だけでは、情報が届く範囲に限界があります。
もちろん、ユーザーにとって有益で魅力的なコンテンツは、拡散されてファンが増える可能性もあるでしょう。
ただ、せっかく情報を投稿しても、ターゲット層に届かなければ効果がありません。
広告運用と組み合わせ、より広範囲なターゲット層にアプローチすれば、集客力を高められます。
ブックマーケティングとの連携
ブックマーケティングは、書籍の出版をマーケティングに活用する手法です。
たとえば、ブックマーケティングで出版した書籍をSNSと連携させ、以下のように活用することも可能です。
| ・出版前からSNSで制作過程や想いを共有 ・書籍の一部を図解や動画で発信して拡散 ・SNSを活用した書籍プレゼントキャンペーンを実施 |
さらに注目すべきポイントは、書籍のコンテンツそのものはSNSのネタとして流用できる点です。
SNSでは「発信ネタが尽きてしまい、継続できなくなる」という課題を多くの企業が抱えています。
しかし、書籍の中には、すでにプロの編集者とともに構築された高品質な情報が豊富に詰まっています。
書籍の内容をSNS向けにアレンジして発信することで、コンテンツを少しずつ再利用でき、ネタ切れを防ぎながら、継続的な情報発信が可能になります。
▶︎ブックマーケティングについては、関連記事【企業出版(ブックマーケティング)のメリットとは? 企業が考えるべき出版による効果】も合わせて参考にしてください。
SNS×ブックマーケティングの相乗効果とは?

SNSとブックマーケティングを掛け合わせることで、「信頼」と「共感」を育てられるメリットがあります。
編集者も交えてクオリティの高い書籍を出版すれば、読者に信頼性の高い情報を提供することが可能です。
書籍で打ち出した自社の専門性や理念、世界観を「日常の言葉」に落とし込んでSNSで伝えれば、ユーザーの理解や納得も深まりやすくなります。
また、SNSは拡散力があるのもメリットです。
書籍の発売をきっかけにアカウントの認知が広がったり、書籍を読んでくればフォロワーとの対話が生まれたりなど、良質なファン形成にもつながります。
出版を通じて得た「信頼」が、SNSを通じて強化される「接点」や「共感」が重なり、単なる集客以上のブランド価値を作り出せます。
▶︎ブックマーケティング(書籍の作り方)については、関連記事【本を出版するには?現役書籍編集者が本の出し方を分かりやすく解説】も合わせて参考にしてください。
SNS×ブックマーケティングで集客に成功した事例

実際にSNSとブックマーケティングを駆使し、集客に成功した事例を2つ紹介します。
| ・書籍出版とSNSの連動で問い合わせ・受注が劇的に増加した事例 ・発売前からSNSを活用し、話題化に成功した事例 |
それぞれの事例を以下で詳しく解説します。
書籍出版とSNSの連動で問い合わせ・受注が劇的に増加した事例
資金調達支援のスペシャリストとしてのブランディングを目的に、書籍を出版した事例です。
出版する書籍には具体的な数字を入れて読者の興味を引き、ビジネス書の売れ行きが良好な大都市圏の書店を中心に配本する戦略をとりました。
また、この著者は、書籍発売から一定期間が経過した後も、Twitter(現X)で書籍プレゼントキャンペーンの告知を定期的に実施。
その継続的な投稿が注目を集め、キャンペーンの告知と連動する形でAmazonでの販売数が急増しました。
結果として書籍はロングセラーとなり、改訂版が出版されるまでに至りました。
書籍とSNS活用を組み合わせ、出版後は問い合わせが3~4倍アップしています。
発売前からSNSを活用し、話題化に成功した事例
商品の販促はもちろん、長期的なブランディングや顧客のファン化を目的として、「女性の悩み」に焦点を当てた書籍を出版した事例です。
「何一つ諦めることなく、女性に生涯にわたり輝いてほしい」という社長の思いを書籍として形にまとめました。
発売前から著者がSNSで積極的に情報発信を行ったことで注目を集め、予約が殺到し、発売前に重版が決定。
また、既存顧客を対象にした書籍プレゼント企画では、想定の8倍もの応募が集まる反響がありました。
出版が実績となり、新規顧客の獲得はもちろん、講演やメディア出演の機会も獲得しています。
SNS運用に関するよくある質問
最後にSNS運用について、よくある3つの質問に回答します。
SNSは毎日投稿しなければならない?
投稿は毎日する必要はありませんが、継続的に発信することが重要です。
定期的に投稿することで露出が増加し、自社がフォロワーにとってタイムライン上でよく見かける存在になりやすいでしょう。
しかし、内容が薄かったり質が悪かったりする投稿を重ねていても、ユーザーにとって価値のない情報になってしまうかもしれません。
コンテンツがパターン化して、飽きられる可能性もあります。
SNSでの発信は週2~3回など、無理なく続けられる頻度を設定してください。
「休まず続ける」ことが信頼やアルゴリズムの評価につながります。
どのようなコンテンツを投稿すればよい?
SNSで発信するコンテンツは、ユーザーが「見たい」「知りたい」と思う内容であることが重要です。
具体的には、以下のようなコンテンツがあります。
| ・商品の紹介 ・サービスの活用事例 ・Q&A ・舞台裏 ・ユーザー参加型コンテンツ ・トレンド情報 |
実際に投稿する際は、競合他社にはない自社ならではの視点や世界観を反映させ、「らしさ」が伝わるようにしましょう。
また、単発で終わらせず、ストーリー性やシリーズ性を持たせて継続的に発信するのがおすすめです。
続きを待ち望むファンが増える可能性があり、つながりも深められます。
外注の運用パートナーは入れるべき?
SNS運用を外注化するかどうかは、企業の状況や目的によって異なります。
外注するメリットとしては、運用に必要な人材をスピーディに確保できることや、専門的なノウハウを持った運用パートナーを活用できることが挙げられます。
一つの考え方として、「人手が足りない」「アカウントを育てるのにそこまで長い期間をかけられない」という課題がある場合、外注を検討することがおすすめです。
ここまで述べたように、SNS運用をきちんとやると担当者にも組織にも意外に手間がかかります。
社員一人が常駐のような状態で対応している会社も多いです。
そうなると、人件費的にSNS運用会社に頼んだほうが安くつく場合も考えられます。
また、外注先は当然ノウハウを持っているため、プロの運用によって最短経路でアカウントを育ててくれるのは大きなポイントでしょう。
特に投稿コンテンツの企画は、一般企業のリソースではなかなか難しい場合も多いです。
ゼロの状態から探り探りでSNS運用をスタートすると、継続できても成果が出るのは数年後といったケースが少なくありません。
その時間を短縮して成果を確実にする選択肢として、外注を活用するのはおすすめです。
【まとめ】SNSとブックマーケティングを掛け合わせて、集客効果を高めよう!
ビジネスコミュニケーションや企業のブランディングでは、今やSNSの運用は欠かせません。
しかし、SNSにはさまざまな種類があり、特徴も異なります。
そのため、自社に合うSNSを選び、そのうえで運用体制を整えることが重要です。
また、SNSはほかの集客施策と組み合わせることで、より効果を発揮します。
特に信頼性や専門性を打ち出せるブックマーケティングと、拡散力のあるSNSは相乗効果が期待できます。
フォーウェイは、230社以上の実績を誇るブックマーケティングに加え、SNS運用をはじめとするマーケティング支援を行っています。
戦略立案から実行まで一貫してサポートが可能です。
SNS運用やブックマーケティングをご検討の際は、ぜひフォーウェイまでご相談ください。

この記事をご覧になったあなたにおすすめのコラム
-
パンフレットの作り方ガイドーー会社案...
2023.06.20Branding, Marketing
-
顧客教育で成約までのリードタイムを短...
2024.08.14Branding, Marketing
-
SEO対策のキーワード選定で大事なポイン...
2022.01.27Marketing, SEO
-
マーケティングツール一覧|経営者が知...
2025.11.11Marketing
-
コンテンツマーケティングとは?期待で...
2025.09.17Branding, Marketing, SEO
-
【新刊発売】『不動産投資の最適解〜家...
2025.04.24NEWS