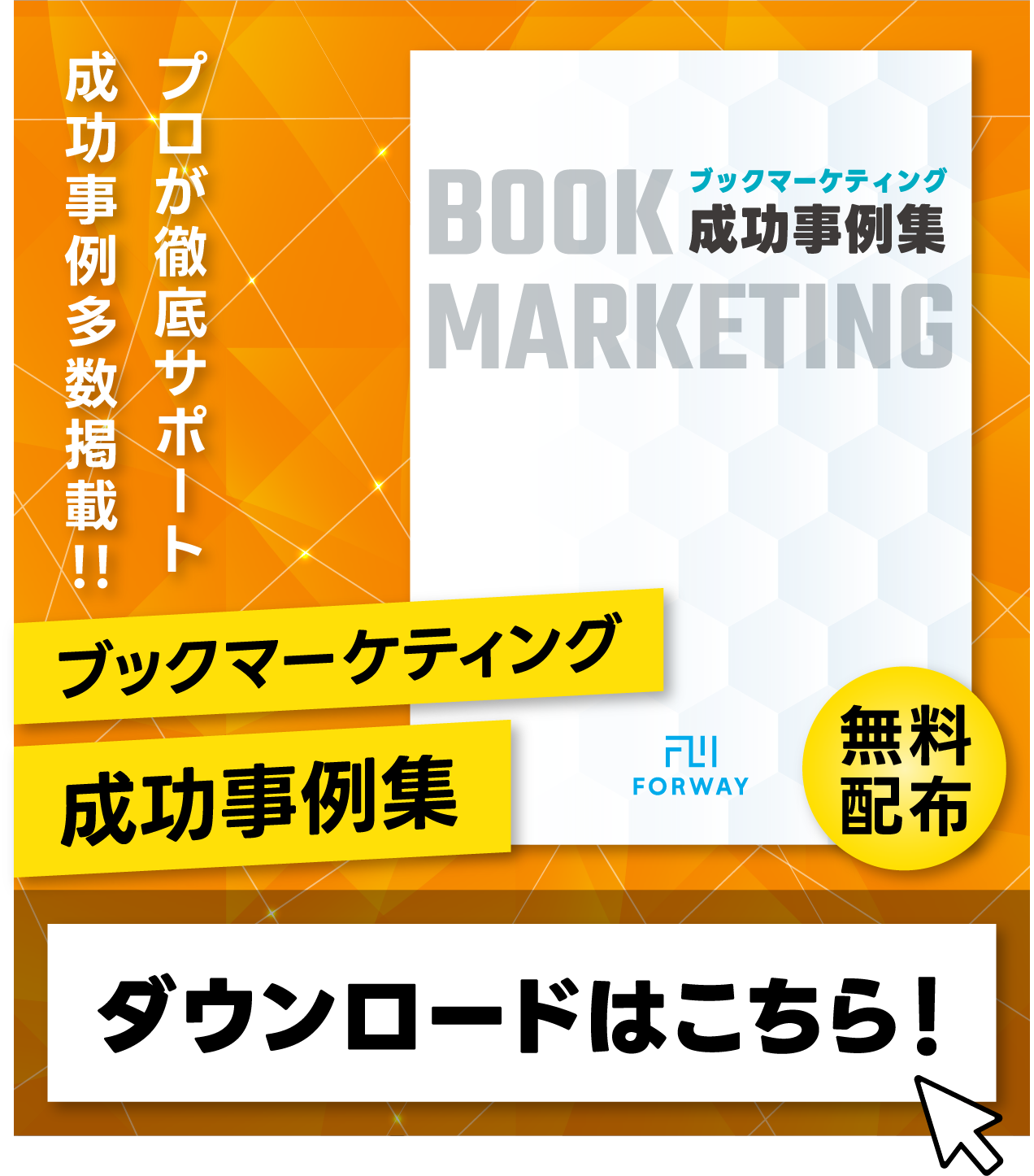Column
フォーウェイは、コンテンツマーケティングで成果を出したい経営者・マーケティング担当者向けの情報を発信しています。
今すぐ自社サイトのSEOを改善させる方法から長期的なブランディングの考え方まで、
実際に弊社のサービスに用いているノウハウを惜しみなく開示します。
2025.09.17
Branding, Marketing, SEO
コンテンツマーケティングとは?期待できる効果や具体的な手法、戦略の練り方まで解説!

「自社のWebサイトに集客したい」「サービスや商品の認知度を上げたい」と考えている企業担当者の方は多いのではないでしょうか。
インターネットが普及した現代では、誰もが簡単に情報へアクセスできるようになり、従来のような一方的な広告だけでは顧客の心を動かすのが難しくなっています。
そこで、多くの企業が注目しているのが「コンテンツマーケティング」です。
言葉にすると簡単なようですが、コンテンツマーケティングを実践したものの成果が出ないという企業も少なくありません。
そこで今回は、コンテンツマーケティングの手法や効果を発揮するための戦略について解説します。
目次【本記事の内容】
- 1.コンテンツマーケティングとは
- 1-1.コンテンツマーケティングとコンテンツSEOは違う?
- 2.コンテンツマーケティングが重要視されるようになった背景
- 2-1.売り込み型マーケティングの効果が下がった
- 2-2.消費者の購買行動が変化した
- 2-3.アルゴリズムが変化した
- 3.コンテンツマーケティング手法は主に2タイプ
- 3-1.ストック型
- 3-2.フロー型
- 4.コンテンツマーケティングに取り組むメリット
- 4-1.潜在顧客のリード獲得
- 4-2.自社の認知度向上とブランディングの実現
- 4-3.コンテンツの資産化
- 4-4.将来的な広告費の削減
- 5.【9ステップ】コンテンツマーケティングの戦略設計の仕方
- 5-1.ステップ1:ターゲットを設定する
- 5-2.ステップ2:カスタマージャーニーを作成する
- 5-3.ステップ3:目的を明確化する
- 5-4.ステップ4:コンテンツマーケティング手法を決める
- 5-5.ステップ5:KGI・KPIを設定する
- 5-6.ステップ6:責任者とメンバーを決定する
- 5-7.ステップ7:スケジュールとコンテンツテーマを確定する
- 5-8.ステップ8:コンテンツを制作する
- 5-9.ステップ9:結果を測定してPDCAを回す
- 6.コンテンツマーケティングを成功させるにはターゲットに合わせた手法選びが重要!
- 6-1.富裕層や企業などがターゲットの場合は書籍でのコンテンツマーケティングがおすすめ!
- 7.コンテンツマーケティングの成功事例
- 7-1.書籍でブランディングと見込み客獲得を実現した事例
- 7-2.出版でファン化が加速し、LTV向上につながった事例
- 7-3.発信に悩む食品メーカーが書籍によって差別化に成功した事例
- 8.コンテンツマーケティングに関するよくある質問
- 8-1.どのくらいで効果が出ますか?
- 8-2.どんな企業に向いていますか?
- 8-3.自社でやるべきですか?外注したほうがいいですか?
- 9.【まとめ】権威性を高めるなら書籍を活用したコンテンツマーケティングがおすすめ
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター) 慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
コンテンツマーケティングとは

コンテンツマーケティングとは、コンテンツを活用したマーケティングの手法を指します。
ここでいうコンテンツは、顧客や見込み顧客にとって有益で価値のある情報であることが重要です。
顧客が興味を持つコンテンツの発信・提供によって信頼関係を築き、最終的に自社の商品やサービスの購入・利用につなげます。
コンテンツマーケティングでは、広告のように積極的な売り込みは行いません。
読者や視聴者のニーズを満たしたり、課題を解決するための情報を提供し続けたりすることで、認知度向上や見込み顧客(リード)獲得といった効果を狙います。
◉-1、コンテンツマーケティングとコンテンツSEOは違う?
Webを活用したマーケティング手法として、メジャーになりつつあるコンテンツマーケティング。
しかし、コンテンツSEOと混同されているケースも散見されます。
コンテンツSEOとは、ターゲット読者が求める情報をコンテンツとして提供し続け、Googleなどの検索結果で上位を目指す手法のことです。
コンテンツマーケティングの一種ですが、イコールではありません。
コンテンツSEOは検索エンジン(SEO)対策の方法であり、あくまで検索結果の上位表示を目指してコンテンツを提供することが目的です。
一方、コンテンツマーケティングはさらに広い意味で用います。
広告以外の手段で有益な情報を発信し続け、見込み顧客に興味を持ってもらい、行動に移してもらうまでを戦略的に設計するのがコンテンツマーケティングです。
簡単にいうと、顧客側から興味を持ってこちら側に寄ってくるインバウンドマーケティングの仕組みづくりをコンテンツマーケティングといいます。
コンテンツマーケティングが重要視されるようになった背景

コンテンツマーケティングが重要視されるようになった背景として、以下の3つが挙げられます。
| ・売り込み型マーケティングの効果が下がった ・消費者の購買行動が変化した ・アルゴリズムが変化した |
それぞれ詳しく解説します。
◉-1、売り込み型マーケティングの効果が下がった
従来のマーケティングでは、テレビやラジオのCM、インターネットなどの広告で商品やサービスを知ってもらう売り込み型(プッシュ型)のマーケティングが一般的でした。
売り込み型のマーケティングは潜在層にも知ってもらえる可能性が高く、即効性も期待できます。
しかしその一方で、企業から一方的に押しつけられる情報になりやすく、受け手である消費者にとっては広告が不快に感じられるケースも少なくありません。
また、「そもそも広告を見ない」という消費者も増えており、売り込み型マーケティングの効果は薄れてきています。
さらに、プッシュ型手法の代表格であるアウトバウンドのテレアポも、難易度が上がり効果が出にくくなっています。
誰もが手軽に始められる一方で、成果を出すには高いスキルが求められるためです。
特に、コロナ禍を経てオンラインでの打ち合わせや在宅ワークが普及したことで担当者と直接つながりにくくなり、これまで以上に効果を出すのが難しくなっています。
◉-2、消費者の購買行動が変化した
インターネットが普及したことで、誰もがほしい情報を自分で調べられるようになりました。
今では、気になることは自分で検索し、比較・検討したうえで選択することが当たり前になっています。
そのため、自社の製品やサービスが選ばれるためには、ただ売り込むだけでなく、消費者にとって役立つ情報を提供することが重要になりました。
逆にいえば、良質なコンテンツを提供することで、これまで自社の製品やサービスを知らなかった消費者にも認知されるきっかけになります。
たとえば「就職祝いに贈る品物」で悩んでいる消費者が検索し、喜ばれる贈り物やマナーを紹介した記事に辿り着いたとします。
その情報を参考にして最適な品物を選び、「相手にも喜んでもらえた」「お祝いにまつわるマナーや知識も得られた」という体験ができたら、自然とその企業に好感を抱き、ファンになってくれる可能性が高まるでしょう。
◉-3、アルゴリズムが変化した
検索エンジンやSNSのアルゴリズムは従来に比べ、価値のあるコンテンツを評価するようになりました。
そのため、情報が薄いコンテンツや専門性が低いコンテンツは評価されにくく、Webページの上位に表示されません。
検索エンジンで露出を増やすためには、良質なコンテンツの作成が必要不可欠です。
信頼できる情報であるのはもちろん、専門性や独自性といった観点も踏まえ、質の高いコンテンツを提供することが重要です。
コンテンツマーケティング手法は主に2タイプ

コンテンツマーケティングの手法は、以下の2つのタイプに分けられます。
| ・ストック型 ・フロー型 |
それぞれのタイプにはさらに細かい手法があるため、以下で各コンテンツの特徴を紹介します。
◉-1、ストック型
ストック型のコンテンツは一度制作すれば長期間にわたって価値が落ちず、時間が経っても需要が続くコンテンツのことを指します。
季節やトレンドなどに左右されることなく、安定したアクセスを見込めるのがメリットです。
こうしたコンテンツを継続的に蓄積していくことで、自社のWebサイトやアカウントに辿り着く消費者を増やせるでしょう。
具体的には、次のようなコンテンツがストック型にあたります。
| ストック型コンテンツ | 特徴 |
| ブログ記事 | ・オウンドメディアなどで自社の商品・サービスを紹介できる・ハウツー記事など役立つ情報を発信できる・主に長めのテキストで構成され、読み応えのある記事を蓄積すれば継続的なアクセスが期待できる |
| SNS(文字・画像・動画投稿コンテンツ) | ・InstagramやX(旧Twitter)などで、商品の使い方や企業紹介といった情報を発信する・時間が経っても役立つ内容は検索で見つけられやすく、ストック型として機能する |
| 動画コンテンツ | ・YouTubeやTikTokなどで配信される動画・テキストだけでは伝わりにくい情報を視覚的にわかりやすく届けられ、訴求力が高い |
| 音声コンテンツ | ・ラジオやポッドキャストなど音声のみの配信・ノウハウや課題解決のヒントをじっくり発信できる・通勤や作業中など「ながら利用」ができる点が魅力 |
| ホワイトペーパー | ・商品・サービスの概要や調査結果をまとめた資料・サイトからダウンロードでき、顧客も比較的気軽に入手しやすい |
| インフォグラフィック | ・データや調査結果をグラフやイラストでわかりやすくまとめたもの・一目で要点を伝えやすく、SNSなどでも拡散されやすい |
| 書籍 | ・出版には時間がかかるが、信頼性が高いコンテンツ・必要なときにあとから見返してもらいやすい・資料や情報源として長期的に活用できる |
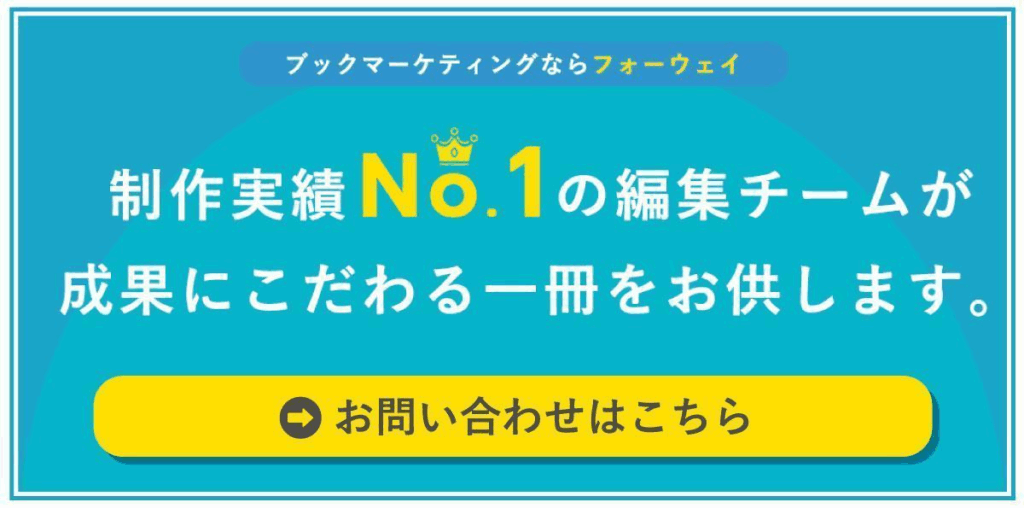
◉-2、フロー型
フロー型コンテンツは鮮度やタイミングが重視され、拡散されやすいのが特徴です。
そのため、新商品や新サービスの告知、キャンペーンなど「今すぐユーザーに知ってもらいたい情報」を伝えるのに適しています。
ただし、フロー型コンテンツは短期間で効果が出やすい反面、時間が経過すると発信した情報が埋もれてしまい、価値が薄れやすいのがデメリットです。
代表的なフロー型コンテンツとして、以下が挙げられます。
| フロー型コンテンツ | 詳細 |
| SNS(タイムライン消費型のコンテンツ) | ・SNSの中でもニュースやトレンド、キャンペーン告知、日常の出来事などをリアルタイムで発信・タイムライン投稿や、24時間で消えるストーリーズ機能が該当する |
| プレスリリース | ・新商品の発売やイベントの開催などをメディアを通じて発信する・記事に引用される可能性が高く、普段接点のない層にも届きやすい |
| メールマガジン | ・登録している既存顧客に直接アプローチできる・登録者の属性をもとに、特定のユーザーに合わせて配信可能 |
| イベント・セミナー | ・自社に関心を持つユーザーを集めやすく、新規層にもアプローチできる・ウェビナーのようにオンライン開催なら、録画を残して動画コンテンツとして再利用できる |
コンテンツマーケティングに取り組むメリット

コンテンツマーケティングを実践することで、以下のようなメリットが得られます。
| ・潜在顧客のリード獲得 ・自社の認知度向上とブランディングの実現 ・コンテンツの資産化 ・将来的な広告費の削減 |
4つのメリットについて詳しく見ていきましょう。
◉-1、潜在顧客のリード獲得
ユーザーが欲する情報を提供し続けることで、自社に興味を持ってもらうきっかけができます。
興味を持ったユーザーがホワイトペーパーをダウンロードする等のアクションを起こす際、連絡先など必要事項の記入を行います。
これが「リードの獲得」です。
リードを獲得できると、その連絡先に対して自社のメルマガを配信したり、電話やメールでキャンペーン情報を伝えるなど、具体的な営業活動につなげることができます。
ほかにも、コンテンツ発信をきっかけとしたメルマガの登録などもリード獲得の手法として考えられます。
◉-2、自社の認知度向上とブランディングの実現
ユーザーにとって有益な情報を提供し続ければ、SEO順位で上位獲得ができ、自社の認知度が上がることが期待できます。
有益な情報であれば、ユーザーによって拡散されていく可能性があるので、自ずと認知度が上がっていくのです。
さらに発信するコンテンツが企業のブランドイメージそのものになるため、自社の事業領域における専門家としてのブランディング効果が期待できます。
◉-3、コンテンツの資産化
コンテンツには情報の新鮮さが求められるフロー型コンテンツと、時間が経過しても価値が失われにくいストック型コンテンツがあります。
ストック型コンテンツは、フロー型のように短期間で大きく拡散されることは少ないものの、公開し続ける限り安定した集客効果を期待できるのが特徴です。
有益なコンテンツは既存顧客との関係強化に役立つだけでなく、検索から流入したユーザーが新規顧客になる可能性もあります。
蓄積されたコンテンツは自社にとって資産となり、さらにアクセス数を伸ばすことにもつながります。
◉-4、将来的な広告費の削減
自社のサービスや商品を購入してもらう手っ取り早い方法は、広告です。ただし、広告は成果が期待できますが、打ち続ける必要があり、結果的に広告費がかさみます。
しかし、コンテンツマーケティングで発信した情報は継続的に費用を投じなくてもネット上に残り続け、長期的な広告費の削減になります。
顧客がファン化して継続的に自社サービスを利用してくれれば、費用対効果が非常に高い施策となるのです。
【9ステップ】コンテンツマーケティングの戦略設計の仕方

コンテンツマーケティングの失敗でよくあるのが、目的設定や準備も行わずにいきなりコンテンツを作りはじめてしまうケースです。
しかし、まずは成果を得るために戦略を練る必要があります。
具体的には、以下のステップに沿って進めていきます。
| ・ステップ1:ターゲットを設定する ・ステップ2:カスタマージャーニーを作成する ・ステップ3:目的を明確化する ・ステップ4:コンテンツマーケティング手法を決める ・ステップ5:KGI・KPIを設定する ・ステップ6:責任者とメンバーを決定する ・ステップ7:スケジュールとコンテンツテーマを確定する ・ステップ8:コンテンツを制作する ・ステップ9:結果を測定してPDCAを回す |
順を追って詳しく解説します。
◉-1、ステップ1:ターゲットを設定する
ターゲットがぶれてしまうと、制作するコンテンツもテーマが不明瞭なものが増えてしまい、結果的にはコンテンツマーケティング自体が徒労に終わる可能性が高まってしまいます。
その中で、ターゲット設定のコツとしては「これまでに集客できていない理想の顧客像」を分析のうえ、設定することです。
マーケティング用語でいう「ペルソナ」を設計します。
自社の顧客になりうる人物像を想像し、言語化することが重要です。
ペルソナ設計では、「デモグラフィック」と呼ばれる人口統計の属性データを使います。
「住所」「性別」「年齢」「職業」「所得(年収)」「世帯規模」「学歴」など、自社サービスにマッチするよう細かく想定するのです。
そのうえで、求めるユーザーの「ライフスタイルの送り方」「思考の傾向」「特有の悩みやストレス」「願望」を設定し、明確に文章で言語化することでペルソナが完成します。
◉-2、ステップ2:カスタマージャーニーを作成する
ターゲットが設定できたら、カスタマージャーニーを作成します。
カスタマージャーニーとは、ターゲットが自社の商品やサービスを認知して購入に至り、その後も継続して利用してくれるまでのプロセスを可視化したものです。
カスタマージャーニーの作成では、認知・興味・比較検討・購入・継続利用といったフェーズごとに顧客の思考や感情、行動を洗い出します。
たとえば、「認知」のフェーズでは、自社の商品やサービスを知るきっかけがSNSなのか、動画コンテンツなのかなどが洗い出す要素の一つです。
顧客の志向や行動などを理解しておくことで、施策を立てやすくなります。
◉-3、ステップ3:目的を明確化する
カスタマージャーニーを作成したら、次に行うべきはコンテンツマーケティングの目的を明確にすることです。
まずは解決したい課題を整理し、そのうえで以下のような目的を具体的に設定します。
| ・CV(コンバージョン)の獲得 ・見込み度の高いリードの獲得 ・自社の認知度向上やイメージアップ ・採用活動につなげるためのブランディング |
さらに、CVやリードの獲得など、自社サービスや商品の購買につなげたい場合、「どのサービスおよび商品を誰に届けたいのか」を設定する必要があります。
目的とマーケティングの着地点となるサービスを明確化し、社内で共通認識を持って取り組むことが大切です。
◉-4、ステップ4:コンテンツマーケティング手法を決める
ターゲットやカスタマージャーニー、目的が明確になったら、次はどの媒体で、どのようなコンテンツマーケティングを実施するのかを決めていきます。
たとえば、Z世代や20代前半の層であれば、動画やSNSを活用したコンテンツが効果的です。
一方で、BtoB企業を対象とする場合は、サービス導入事例をまとめたホワイトペーパーや、専門的なノウハウを整理した書籍などが適しています。
ターゲットに合わせて媒体と手法を選択することで、より効果的なコンテンツマーケティングが可能になります。
◉-5、ステップ5:KGI・KPIを設定する
マーケティングでは、最終的な目標を示すKGIと、その進捗を測る中間指標であるKPIを決めます。
具体的な指標は、月間リード数や記事PV、コンバージョン率などです。
たとえば「最終的な成約数30件」をKGIとするなら、その達成に向けたKPIとして「月間リード数100件」を目標に設定するといった形です。
◉-6、ステップ6:責任者とメンバーを決定する
コンテンツマーケティングは成果を安定して出すまで時間がかかります。
したがって、コンテンツマーケティングのプロジェクトに根気よく情熱を持って取り組んでくれる、理解ある責任者を決定する必要があります。
コンテンツマーケティングでは、成果につながらない時期というのが訪れます。
常にトライアンドエラーを繰り返しながら、「成果につながらないコンテンツはどのように改善していくのか」といった意識が重要です。
責任感と覚悟を持って意思決定を行える責任者を任命しましょう。
そして、責任者を決めたら、次はともにプロジェクトに取り組むメンバーの招集をします。
会社としてコンテンツマーケティングを実施する目的と意義を理解して、そこに共感して取り組んでくれるメンバーを選びましょう。
ありがちな失敗としては、次のようなメンバーを集めてしまうパターンがあります。
| ・文章を書くのが好きなメンバー ・過去にライティング経験があるメンバー ・通常業務の合間に手伝ってくれそうなメンバー |
コンテンツマーケティングにおけるSEOライティングには、必ずしも紙媒体などでライティングに従事した経験は必要ありません。
また、片手間ではそのうち手が回らなくなって放置されてしまうのがオチです。
コンテンツの品質を保つには、あくまでビジョンと目的に共感してくれるメンバーを集めなければなりません。
▶︎コンテンツマーケティングの失敗要因については、関連記事【コンテンツマーケティングの失敗を招くNG行動6】もあわせて参考にしてください。
◉-7、ステップ7:スケジュールとコンテンツテーマを確定する
責任者とメンバーが決まったら「スケジュール」と「コンテンツテーマ」を確定させます。
コンテンツマーケティングは、一朝一夕で成果や効果が出にくい施策のため、最低でも1年間のスケジュール計画を立てる必要があります。
その際、決めなければならない要素としては以下の通りです。
| ・アクセスやCVといった1年後の数値目標 ・具体的なコンテンツの内容と制作担当者、制作の締め切り |
コンテンツマーケティングによって、広告に頼らない価値ある基盤を1年後に作り上げるために、詳細なタスクを整理して、「誰が」「いつまでに」「どんなコンテンツ」を制作するのかを計画立てましょう。
目標達成に向けて、たとえば3か月目までは認知獲得や商品理解を促すコンテンツを制作し、6か月目以降は少しずつCVにつなげていくために、「購入欲求」をかき立てるコンテンツを制作する、といった計画です。
さらに、上記スケジュールの組み立てができたら、具体的なコンテンツの確定をしていきましょう。
目的や顧客がどのような情報を欲しているかを考え、テーマを選びます。
◉-8、ステップ8:コンテンツを制作する
コンテンツ制作では、マーケティングの目的を踏まえ、設定したターゲットやカスタマージャーニーに沿った内容を設計することが重要です。
ユーザーの関心を引きつけるためには、有益な情報を提供するだけでなく、デザイン面にも配慮する必要があります。
レイアウトや配色、フォントのサイズ、種類など、見た目の印象も影響を与えます。
また、制作したコンテンツには、自社サイトやサービスページへスムーズに移動できる導線を用意しておくことで、売上や商談といった成果につながりやすくなります。
◉-9、ステップ9:結果を測定してPDCAを回す
コンテンツは作成して終わりではなく、その後の効果測定と改善が欠かせません。
実際には、せっかく制作したコンテンツが期待した成果につながらない場合もあります。
また、新しい情報が次々に発信されるなかで、自社コンテンツの検索順位が下がってしまうことも考えられます。
そのため、あらかじめ設定したKGI・KPIを基準に、どの程度効果が出ているのかを定期的に確認しましょう。
そこで明らかになった課題や改善点を次の施策に反映させることで、PDCAを回しながら成果を高めていくことができます。
コンテンツマーケティングを成功させるにはターゲットに合わせた手法選びが重要!

コンテンツマーケティングは、広告のように企業側から積極的にアプローチする「攻めのマーケティング」ではなく、ターゲットが集まりやすい媒体に魅力的なコンテンツを配置し、自然に関心を持ってもらう「待ちのマーケティング」です。
そのため、ターゲットが集まりにくい媒体にコンテンツを置いても効果はありません。
成功のポイントは、ターゲットが集まる場所を見極め、そのうえで効果的な手法を選ぶことです。
たとえば、企業を対象とする場合、企業の課題解決につながる情報や専門性を示す書籍・ホワイトペーパー・プレスリリースといったコンテンツが有効です。
一方で、決裁者層へのアプローチや潜在顧客との関係構築においては、SNSやブログも重要な役割を果たします。
特に、自社の専門性を発信したり、企業のブランドイメージを伝えたりするうえで効果を発揮します。
このように、コンテンツマーケティングでは「ターゲットに最適化した手法の選択」が成功を左右するのです。
◉-1、富裕層や企業などがターゲットの場合は書籍でのコンテンツマーケティングがおすすめ!
現代はインターネットを通じて膨大な情報を得られる一方で、その中には根拠があいまいで信頼性に欠けるものも少なくありません。
一方、出版社から刊行された書籍は「現物」として手元に残るだけでなく、Web記事やSNS投稿と比べてテーマを深く掘り下げ、体系的にまとめられています。
そのため、専門性や権威性をアピールでき、読者からの信頼やブランド価値の向上につなげやすい点が魅力です。
また、出版後には出版記念イベントやセミナーの開催、SNSやオウンドメディアでの紹介といった形で二次活用でき、マーケティング効果をさらに広げられます。
▶︎企業出版の詳細については、関連記事【企業出版の効果とは?費用相場や成功のポイント、事例を徹底解説】もあわせて参考にしてください。

◉コンテンツマーケティングの成功事例
コンテンツマーケティングとして書籍を出版し、成功した事例として3つ挙げます。
| ・書籍でブランディングと見込み客獲得を実現した事例 ・出版でファン化が加速し、LTV向上につながった事例 ・発信に悩む食品メーカーが書籍によって差別化に成功した事例 |
それぞれの事例を以下で紹介します。
◉-1、書籍でブランディングと見込み客獲得を実現した事例
保険代理店向けのコンサルティング事業を立ち上げた経営者は、新規開拓の有効な手段がなく、信頼性を高めるブランディング施策を模索していました。
そこで選んだのが企業出版。
フルコミッション(成果報酬)が当たり前の保険業界において、「月額給与制の一律報酬型」で業績を伸ばした独自のノウハウを体系化し、書籍として発信しました。
出版後は大きな反響を呼び、わずか発売2週間で即重版が決定。
Amazonでも一時的に欠品するほどの人気となりました。
また、出版記念セミナーには60名が参加し、その場で20名と商談、複数件のコンサル契約へとつながっています。
さらに、大手生命保険会社の支社長や部課長クラスにも読まれ、講演依頼が継続的に舞い込むように。
加えて、書籍が経営者同士で紹介される動線が生まれ、紹介を通じて新たな見込み客との接点が広がりました。
結果として、本業である保険契約の件数も増加し、書籍出版がきっかけとなって大口契約の成約につながるなど、大きな成果を上げることができました。
▶︎保険代理店の詳しい事例については【【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店】もあわせて参考にしてください。
◉-2、出版でファン化が加速し、LTV向上につながった事例
あるサプリメントメーカーでは、商品の販促と長期的なブランド構築を目的に書籍を出版しました。
ターゲットは中年期以降の女性とし、「一生のうちで変化の多い「女性の人生の悩み」を解決する」というコンセプトを掲げたことで、顧客の共感を獲得しました。
出版時には著者と連携し、SNSでの情報発信を強化。
その結果、Amazon予約が殺到し発売前に重版が決定しました。
また、既存顧客向けに実施した書籍プレゼント企画では、予想の8倍にあたる240名以上が応募。
贈呈した顧客の半数以上がリピート購入を続けるなど、LTV(顧客生涯価値)の向上にもつながっています。
▶︎サプリメントメーカーの詳しい事例については【【事例コラム】”書籍無料プレゼント”に想定の6倍の応募、リピート率アップにインパクト!サプリメントメーカーの出版プロジェクト】もあわせて参考にしてください。
◉-3、発信に悩む食品メーカーが書籍によって差別化に成功した事例
わさびの開発・製造・販売を手がける食品メーカーは、日本文化の象徴である「わさび」の魅力を広めると同時に、自社のPRにつながる新たな発信手段を模索していました。
しかし、従来のプロモーションでは成果に限界があり、同業他社との差別化が大きな課題となっていたのです。
そこで、料理に関心を持つ30代〜40代女性をメインターゲットに設定し、わさびの効能や歴史、レシピを紹介する書籍を出版。
出版をきっかけに著者と料理研究家によるトークイベントを開催し、その場で50冊以上を販売する成果を上げました。
また、営業活動に活用できるよう書籍のダイジェスト版を小冊子として制作し、営業ツールとしても展開しました。
結果的に、書籍を通じて「わさびファン」を増やし、販売拡大につながっています。
◉コンテンツマーケティングに関するよくある質問

最後に、コンテンツマーケティングに取り組む際によくある質問に回答します。
◉-1、どのくらいで効果が出ますか?
コンテンツマーケティングは「攻める」手法ではなく、「待つ」手法であるため、新たに始めた場合は効果が出るまでに早くても3〜6か月、一般的には半年〜1年以上かかります。
SEOやSNSでは、継続的に取り組み、信頼や評価を積み重ねる必要があります。
そのため、即効性を期待するのではなく、長期的な視点で取り組むことが重要です。
◉-2、どんな企業に向いていますか?
コンテンツマーケティングは、BtoB・BtoCを問わず、顧客が購入前に情報収集を行う傾向が強い業界に適しています。
特に高額商品や専門性が高い商品、比較検討が必要な商品・サービスなどに、コンテンツマーケティングは効果的です。
◉-3、自社でやるべきですか?外注したほうがいいですか?
コンテンツマーケティングは自社でも取り組むことが可能ですが、すべてを内製化しようとするとリソースの負担につながるおそれがあります。
効果的なのは、役割を分担することです。
たとえば、戦略設計や自社にしかわからない専門知識の提供は社内で担い、記事執筆・デザイン・動画制作・編集といった制作部分は外注するといった形です。
こうすることで、自社の強みを活かしながら効率的に運用でき、クオリティも安定しやすくなります。
さらに、外注パートナーを活用することで最新のマーケティング手法や専門スキルを取り入れられるのもメリットです。
【まとめ】権威性を高めるなら書籍を活用したコンテンツマーケティングがおすすめ
この記事では、コンテンツマーケティングの手法や効果を発揮するための戦略について解説してきました。
コンテンツマーケティングは根気よく続ける必要がありますが、自社コンテンツを魅力に感じた顧客はファンとなり、長期的にサービスを利用し続けてくれる可能性があります。
そのためには、「ブレないためのターゲット設定」と「目的を見失わないための戦略設計」が重要です。
広告費を削減し、安定した売上を積み上げるためのコンテンツマーケティングを実施するうえで本記事の内容を参考にしてください。
「フォーウェイ」はブックマーケティングを主軸とし、徹底的な経営コンサルティング目線で書籍の出版をサポートしています。
企業のブランディングにも役立つ書籍を活用したコンテンツマーケティングを検討しているのなら、フォーウェイにご相談ください。
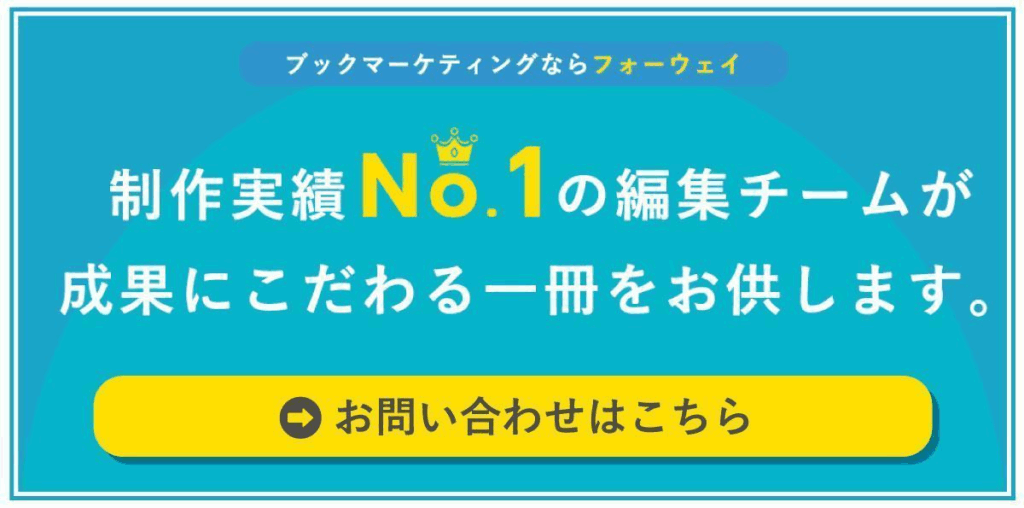
この記事をご覧になったあなたにおすすめのコラム
-
高単価、BtoB営業におけるリードタイム...
2024.10.16Branding, Marketing
-
自費出版とは?メリットやデメリット、...
2024.09.19Branding, Marketing
-
記念誌とは?読んでもらうためのコツや...
2024.11.20Branding, Marketing
-
集客できないコンサル必見!効果的なブ...
2025.01.06Branding, Marketing
-
薬機法(旧薬事法)の規制を遵守しながら...
2025.01.23Branding, Marketing
-
ストーリーブランディングとは?企業の...
2024.09.24Branding, Marketing