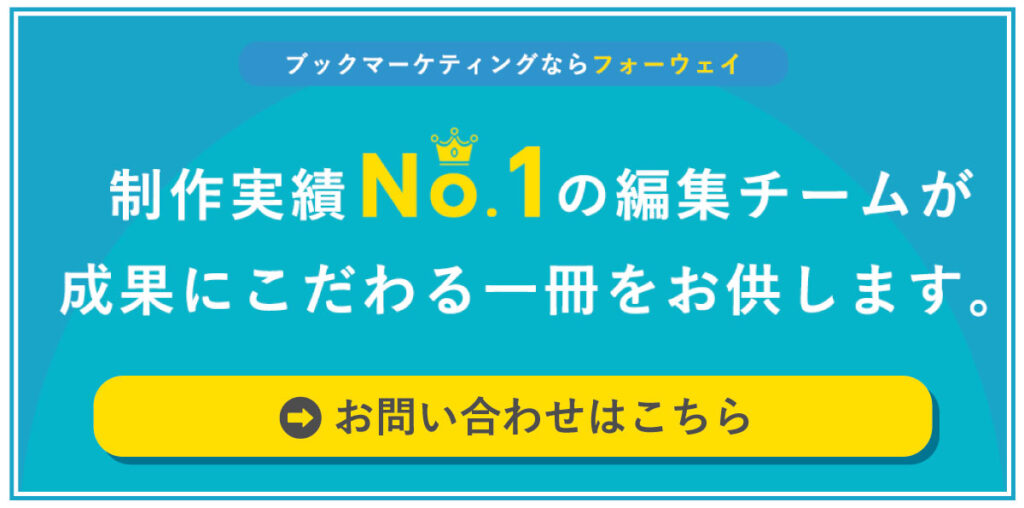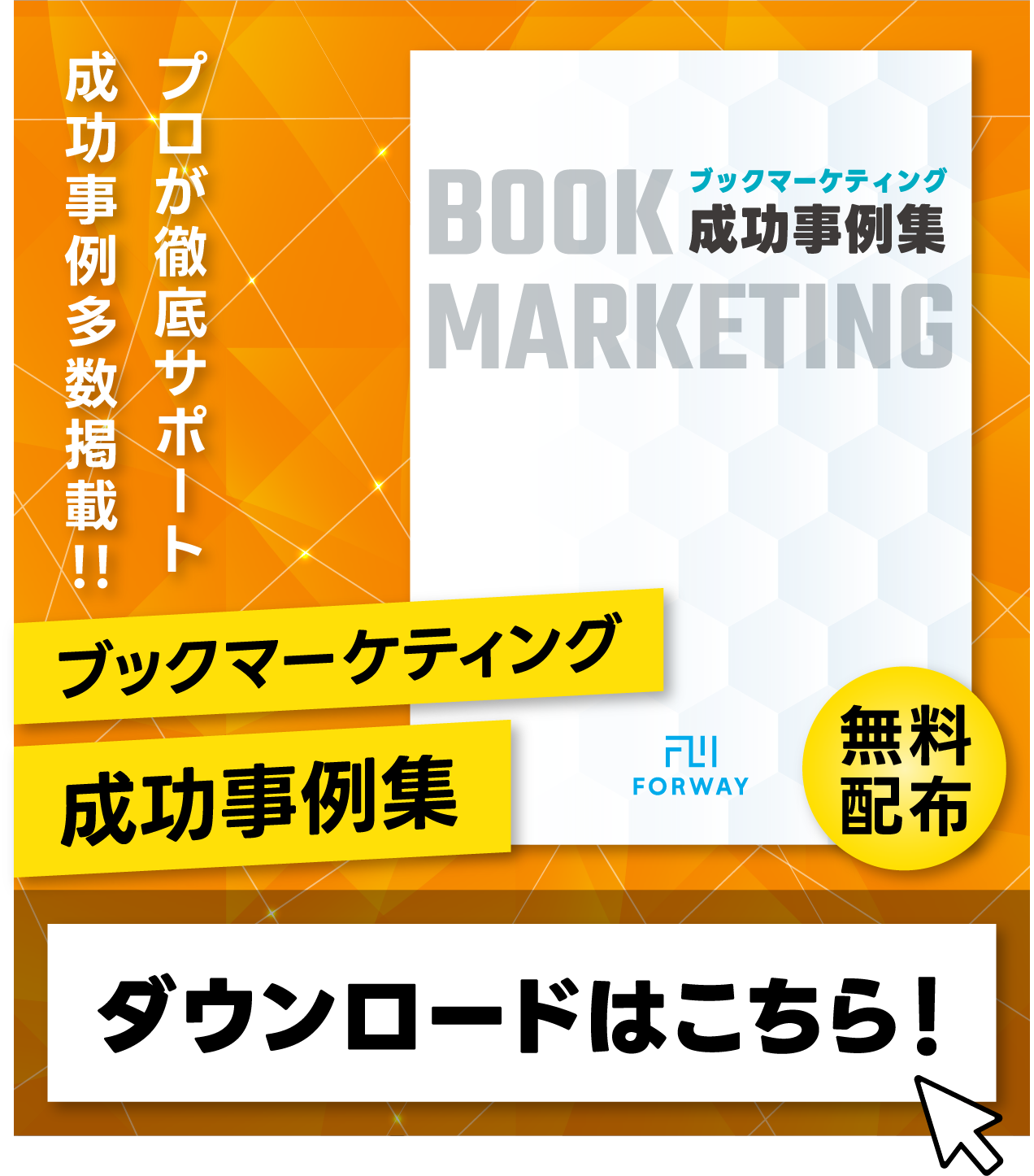Column
フォーウェイは、コンテンツマーケティングで成果を出したい経営者・マーケティング担当者向けの情報を発信しています。
今すぐ自社サイトのSEOを改善させる方法から長期的なブランディングの考え方まで、
実際に弊社のサービスに用いているノウハウを惜しみなく開示します。
2025.05.07
Branding, Marketing
企業ブランディングとは?効果や具体的な8つの手法を徹底解説

類似した商品やサービスが市場に溢れている昨今は、品質やデザインが優れているだけでは選ばれにくい時代です。
そのような状況では、企業の理念や価値観、社会的な姿勢といった企業そのものの魅力が、選ばれる決め手になりつつあります。
そこで注目されているのが「企業ブランディング」です。
本記事では、企業ブランディングの効果、実施手順、具体的な手法について解説いたします。
目次【本記事の内容】
- 1.企業ブランディングとは
- 1-1.事業ブランディングとの違い
- 2.企業ブランディングがもたらす8つの効果
- 2-1.効果1:競合他社との差別化
- 2-2.効果2:顧客ロイヤリティの向上
- 2-3.効果3:信頼性の獲得
- 2-4.効果4:広告宣伝費の削減
- 2-5.効果5:価格競争からの脱却
- 2-6.効果6:優秀な人材の採用・定着
- 2-7.効果7:新規顧客の獲得
- 2-8.効果8:従業員のモチベーション向上
- 3.企業ブランディングの実施手順
- 3-1.STEP1:現状分析を行う
- 3-2.STEP2:ターゲット顧客を明確にする
- 3-3.STEP3:ブランドの核(価値観・メッセージ)を策定する
- 3-4.STEP4:ブランド戦略を策定する
- 3-5.STEP5:実行・改善・測定を繰り返す
- 4.企業ブランディングの手法
- 4-1.ロゴとビジュアルアイデンティティの設計
- 4-2.ブランディング広告の活用
- 4-3.コンテンツマーケティングの実施
- 4-4.SNSの活用
- 4-5.インフルエンサーとのコラボレーション
- 4-6.イメージキャラクターの作成
- 4-7.イベント・セミナーの実施
- 4-8.書籍の出版
- 4-9.CSRの推進
- 5.企業ブランディングを成功に導く2つのポイント
- 5-1.長期的な視点で取り組む
- 5-2.適した指標を用いて効果検証する
- 6.ブックマーケティング(企業出版)における企業ブランディングの成功事例
- 6-1.出版による信頼性獲得で圧倒的な受注率を達成した不動産会社の事例
- 6-2.セミナーや講演会依頼多数!新規事業の集客を実現した保険代理店の事例
- 7.【まとめ】企業によって最適なブランディング手法は異なる!まずは自社に合った手法を見つけよう
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター) 慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉企業ブランディングとは

企業ブランディングとは、企業の理念や価値観、ビジョンなどを明確にして社内外に発信し、企業のブランド価値を高める取り組みです。
商品やサービスの品質がどれほど優れていても、それを提供する企業に信頼がなければ、顧客から選んでもらうことはできません。
逆に、企業に一貫した姿勢や社会的な信頼があれば、商品やサービスそのものの評価も高まり、選ばれる理由になります。
たとえば、Apple社は世界中にアップル信者と呼ばれる熱烈なファンを獲得しています。
新型iPhoneの発売日には朝から長蛇の列ができるほどです。
同じ価格でiPhone以上の機能や性能が備わっているスマホは、世の中にたくさんありますが、企業ブランディングに成功したiPhoneは、機能や価格の競争対象とならずに顧客から選ばれ続けているのです。
◉-1、事業ブランディングとの違い
企業ブランディングと事業ブランディングは、ブランディングの対象が大きく異なります。
企業ブランディングが企業全体の信頼や価値を高める取り組みであるのに対し、事業ブランディングは事業の魅力や認知度を高める取り組みです。
企業ブランディングは企業全体の理念やビジョン、企業文化、社会的役割などを訴求する一方で、企業の中の各事業の強みや特徴を訴求します。
たとえば、楽器メーカーとして有名なヤマハを例にすると、ヤマハという企業全体を訴求するのが企業ブランディング、ヤマハが行っている「楽器事業」「音響機器事業」など個々の事業を訴求するのが事業ブランディングです。
企業ブランディングが成功すれば、企業の価値だけではなく、行っている事業の価値も向上させることができます。
◉企業ブランディングがもたらす8つの効果

企業ブランディングは、単なるイメージ戦略ではないため、企業の内外に多くのメリットをもたらします。
代表的な8つの効果は以下の通りです。
| 効果1:競合他社との差別化 効果2:顧客ロイヤリティの向上 効果3:信頼性の獲得 効果4:広告宣伝費の削減 効果5:価格競争からの脱却 効果6:優秀な人材の採用・定着 効果7:新規顧客の獲得 効果8:従業員のモチベーション向上 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、効果1:競合他社との差別化
企業ブランディングに成功してブランド価値が高まると、自社の製品やサービスにブランドという付加価値が付くことになります。
結果として競合他社との差別化を図ることができるのです。
たとえば、ダイソンには、「製品開発にただならぬこだわりを持ち、徹底的に作り込まれた高機能・高品質な製品を出す会社」というイメージを持つ人が多いと思います。
このイメージが自社の製品やサービスへの付加価値となり、たとえ他の製品より価格が高くても、他にコスパの良いものがあったとしても、「ダイソンの掃除機が欲しい」と選ばれる存在となります。
企業ブランディングに成功し、競合他社との差別化ができると、価格競争からの脱却や、新規参入企業の抑制、自社の特徴や強みの明確化などのメリットが得られますが、最大のメリットは「価格競争からの脱却」と言っても良いでしょう。
製品やサービスの基本機能は同じであっても、ブランドという付加価値が付くことによって差別化できるため、安定した企業経営を実現することができます。
◉-2、効果2:顧客ロイヤリティの向上
企業の理念やビジョンに共感が集まると、ブランドへの信頼が高まり顧客のロイヤリティも向上します。
顧客ロイヤリティとは、顧客が企業やブランドに対して抱く信頼や愛着を指すものです。
強い顧客ロイヤリティは、リピート購入の増加や口コミによる新規顧客の獲得など、企業にとって多くのメリットをもたらします。
たとえば、スターバックスは、「人々の心を豊かで活力のあるものにするために」というミッションのもと、顧客体験を重視した店舗運営を行っています。
店舗の雰囲気やスタッフの接客などが顧客の満足度を高め、強いロイヤリティを生み出している事例です。
このように、「この企業だから選ぶ」という心理が働けば、価格によらず選ばれ続けて安定した売上にもつながります。
◉-3、効果3:信頼性の獲得
効果的な企業ブランディングを行うことができれば、企業や自社の製品・サービスの信頼性を高めることができます。
たとえば、ダイソンは、創業者ジェームス・ダイソンが納得のいく掃除機を作るために、試作品を5,127台も作り開発を進めてきたプロセスを丁寧にユーザーに伝えています。
結果として、「高機能・高品質」だけではなく、「ジェームス・ダイソンが魂を込めて、試行錯誤をして作られた掃除機だから大丈夫だ」という信頼感の醸成に成功しました。
このように、企業ブランディングに成功すると、「この企業なら間違いない」「この企業なら期待に答えてくれる」という信頼感をユーザーに与えることができるようになります。
高い信頼性を有するブランドを作りあげることは容易なことではありませんが、信頼性の高いイメージを獲得しそれを維持することができれば、それは企業にとって大きな武器となるでしょう。
◉-4、効果4:広告宣伝費の削減
企業ブランディングに成功し、企業の知名度や認知度が向上すると、必要以上の広告宣伝をしなくても自社の製品やサービスが売れるようになります。
理由は2つあります。
1つはファンによるリピート購入が増えるため、2つ目は顧客のニーズが発生した時に選択肢に上がりやすくなるためです。
たとえば、「少し高級感のあるタオルをギフトとして送りたい」と思った時に、おそらくほとんどの人の頭の中に「今治タオル」が選択肢として思い浮かぶはずです。
このように「高級タオルと言えば今治タオル」というブランドが認知されれば、ニーズが発生した段階ですぐに選択肢にあがってくるようになります。
そのため、必要以上の広告宣伝をしなくても、自社の製品やサービスが安定的に売れるようになるのです。
テレビCMやWeb広告などは流している期間中は売上に貢献しますが、CMや広告をやめるとその効果がなくなるケースが多いものです。
しかし、企業ブランディングによって向上した企業の知名度や認知度は、継続的な経済効果を企業にもたらします。
このように、広告宣伝費が削減できることも企業ブランディングの大きなメリットの1つと言えるでしょう。
◉-5、効果5:価格競争からの脱却
企業ブランディングに成功すると自社の製品やサービスが高価格であったとしても購入してもらえるようになるため、価格競争から脱却できます。
たとえば、同じ素材・デザインの無地のパーカーでも、高級ブランドのタグやロゴがついているだけで、高額だったとしても「この高級ブランドの出しているパーカーならこれぐらいして当然だよな」と、市場が納得してくれるようになるのです。
また、自社の製品やサービスに固定客がつくようになり、リピート率の向上や、営業・販売コストの削減にもつながります。
◉-6、効果6:優秀な人材の採用・定着
企業が成長するためには優秀な人材を確保することが重要です。
企業ブランディングによって企業の魅力が広く周知されると、多くの人材が自社のことを知り好印象を抱いて応募してくることが期待できます。
たとえば、最強の町工場とも言われる浜野製作所は、どん底から這い上がった社長の創業ストーリーや、「脱下請け」の革新的なものづくりをいち早く打ち出し、「革新的な町工場」という企業ブランディングを確立しました。
企業ブランディングの一環として活用したのが「書籍の出版(ブックマーケティング)」です。
書籍の中で経営者のビジョンや考え方を共有したことで、深い共感を得ることができ、普通なら大企業やグローバル企業に行ってしまうような優秀な人材の確保ができるようになったそうです。
このように、求職メディアを利用しなくても、優秀な人材を獲得することができ、採用コストを大幅に削減できるのもメリットの1つと言えるでしょう。
◉-7、効果7:新規顧客の獲得
企業ブランドが認知されると、今まで接点のなかった層にも届き、新規顧客の獲得につながります。
特に、企業の価値観や社会的貢献に共感する消費者からの支持を得やすくなります。
たとえば、ヤンマーは、農業機械メーカーとしての伝統的なイメージを刷新するため、ブランドアイデンティティを「FLYING-Y」に統一し、デザイン面でも著名なデザイナーを起用しました。
これにより、若年層や新規顧客層からの注目を集め、ブランド価値の向上と新規顧客の獲得に成功しています。
◉-8、効果8:従業員のモチベーション向上
経営トップがビジョンや価値観を明確に発信すると、従業員のモチベーションやエンゲージメントが高まります。
たとえば、東京ディズニーリゾート(株式会社オリエンタルランド)では、従業員を「キャスト」と呼び、キャストをブランドの体現者としています。
最も重視すべきゴールや、5つの行動基準を共有し、キャスト自身が自分で考えて行動できるような教育方針を導入しているのが特徴です。
これにより、キャスト一人ひとりがブランドの価値や理念を理解している状態を作ることに成功しました。
理念が浸透すれば、自分の仕事が社会に貢献していることが実感でき、従業員の自発性や創造性が育まれ、モチベーションが向上します。
◉企業ブランディングの実施手順

企業ブランディングは、「どのような企業として世の中に認識されたいか」という根幹を定義する取り組みなので、最初の計画と準備が重要です。
企業ブランディングは、次のような5つのステップで進めます。
| STEP1:現状分析を行う STEP2:ターゲット顧客を明確にする STEP3:ブランドの核(価値観・メッセージ)を策定する STEP4:ブランド戦略を策定する STEP5:実行・改善・測定を繰り返す |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、STEP1:現状分析を行う
まず最初に、自社や自社を取り巻く環境についての現状分析を行います。
ここでは、自社がどのように認知されているのか、競合環境はどうなっているのか、顧客が自社に抱いている印象やイメージは何かなどを調査することが大切です。
企業ブランディングの現状分析に用いられる代表的なフレームワークは、次の2つです。
| PEST分析 | 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4視点から、自社を取り巻くマクロ環境を分析する手法 |
| 3C分析 | 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3要素に着目して、自社の立ち位置を明確にする手法 |
PEST分析は、外部環境の大きな変化やトレンドを把握するのに適しており、3C分析は、具体的に市場でどのような競争が起こっているのかという点や、自社の立ち位置を明確にするのに適しています。
◉-2、STEP2:ターゲット顧客を明確にする
ブランディングでは、誰に伝えるかを明確にすることが重要です。
そのために、セグメント(顧客グループの分類)とペルソナ(具体的な理想顧客像)を設定します。
年齢や価値観などを細かく定めたペルソナを活用すると、より的確なメッセージ発信が可能です。
ターゲットを明確にすることで、ブランドのメッセージをピンポイントで届けることができます。
どの顧客層に対してどのような価値を提供するのかがはっきりするため、企業のブランドポジショニングも確立されていくのです。
また、マーケティング活動やプロモーション戦略をターゲットに合わせてカスタマイズすることも可能です。
◉-3、STEP3:ブランドの核(価値観・メッセージ)を策定する
ブランドの核となるのが、企業としてどんな価値を提供し、どんな存在でありたいのかという価値観やメッセージです。
ブランドの核には企業のミッション、ビジョン、バリューが含まれます。
ブランドの核は単なるスローガンではなく、企業としての哲学や世界観を明文化するもので、ここで決めたものがブランディングの軸となります。
ブランドの核がしっかりと定まることで、その後のマーケティング活動やコミュニケーションが一貫性を持ち、信頼感を高めることができるのです。
◉-4、STEP4:ブランド戦略を策定する
ブランドの核が明確になったら、次にそれを具体的にどのように伝えていくかを設計します。
具体的には、次のような要素があります。
・ロゴやカラー、フォントなどのビジュアル要素
・WebサイトやSNSでのメッセージの発信
・ブランディング広告やキャンペーン施策
ここで重要なことは、ブランドの方向性にブレがないように一貫したメッセージを発信していくことです。
ブランドがどのような立ち位置を取るのか、どのような市場に向けて発信するのかが定まるため、無駄の少ない効率的なマーケティング活動を行うことができます。
◉-5、STEP5:実行・改善・測定を繰り返す
ブランディングは一度やって終わりではありません。
実際に施策を実行したうえで、その効果を測定し必要に応じて改善し、PDCAサイクルを回します。
たとえば、次のような指標でブランド効果を評価していきます。
・SNSの投稿数やコメント数
・サイト滞在時間やコンバージョン率
経営環境や顧客ニーズの変化に合わせて継続的にアップデートすることが重要です。
◉企業ブランディングの手法

企業ブランディングを効果的に行うためには、一貫性が重要です。
それぞれの特徴を理解し、目的に応じて組み合わせることで、より強力なブランディングが可能になります。
企業ブランディングを効果的に行うための代表的な9つの手法は以下の通りです。
| ・ロゴとビジュアルアイデンティティの設計 ・ブランディング広告の活用 ・コンテンツマーケティングの実施 ・SNSの活用 ・インフルエンサーとのコラボレーション ・イメージキャラクターの作成 ・イベント・セミナーの実施 ・書籍の出版 ・CSRの推進 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、ロゴとビジュアルアイデンティティの設計
ロゴや色、フォントといったビジュアル要素は、ブランドの世界観を視覚的に伝える重要なツールです。
たとえば、Appleのロゴやコカ・コーラの赤と曲線的なデザインなどは、強いブランドイメージを定着させています。
こうしたデザインには、まず企業の想いやストーリーを言葉として整理し、その内容をもとに一貫性あるビジュアルへ落とし込むプロセスが効果的です。
ロゴとビジュアルアイデンティティを作り上げるのと同時に使用方法についても厳しいガイドラインを設けることをおすすめします。
◉-2、ブランディング広告の活用
ブランディング広告は、企業の価値観や世界観を伝えるための広告手法です。
特に、企業ブランディングにおいては、マス広告、ディスプレイ広告、デジタル音声広告の3つが主に活用されます。
目的やターゲットに応じて使い分け、組み合わせることで、効果的にブランドイメージを浸透させることが可能です。
◉-2-1、マス広告
マス広告は、テレビCMや新聞・雑誌広告など、幅広い層にリーチできる伝統的な手法です。
信頼性やインパクトのある訴求に強く、企業の節目や社会的なメッセージ発信に適しています。
特に、ゴールデンタイムのテレビCMは、数百万人単位の視聴者にブランドをアピールできるため、一気に認知度を高め、ブランドを「知っている企業」に変えることが可能です。
マス広告の種類や特徴は次表の通りです。
| マス広告の種類 | 特徴 |
| テレビ | 全国規模での認知拡大に効果的 |
| ラジオ | 地域密着型の配信や「ながら聴き」に向く |
| 新聞 | 信頼性が高く、中高年層やビジネス層の読者が多い |
| 雑誌 | 専門性が高く読者ターゲットが明確で保存性も高い |
特に、新聞広告やNHKなどでの公共性の高いメディアでの広告出稿は、「この企業は信頼できる」と感じさせることができます。
特に保険・金融・医療など、信頼が重要な業種は信頼性を活用して広告を出稿すると良いでしょう。
◉-2-2、ディスプレイ広告
ディスプレイ広告は、画像や動画、フォント、色彩などを用いて、企業が伝えたいブランドイメージや世界観をそのまま表現できるのが強みです。
ターゲティング精度が高く、ペルソナに合わせた広告配信ができます。
また、リスティング広告とは異なり、検索行動をしていないユーザー(潜在顧客)にもリーチできるのが特徴です。
「知ってもらう」「印象づける」などの目的に適しており、ブランドの認知拡大に貢献します。
ディスプレイ広告の種類や特徴は次表の通りです。
| ディスプレイ広告の種類 | 特徴 |
| GDN(Google ディスプレイネットワーク) | Googleの提携先メディアに広告を配信できるネットワーク |
| YDA(Yahoo!ディスプレイ広告) | Yahoo! JAPANや提携メディアに配信される広告 |
| YouTube広告 | 動画による訴求力が高く、短時間で印象づけやすい |
広告のデザインがごちゃごちゃしていたり、メッセージが曖昧だったりすると、ユーザーには何の広告か分からずスルーされてしまいます。
ディスプレイ広告のビジュアルを作成する際は「誰に見せたいのか」「どんな印象を持ってもらいたいのか」を意識することが大切です。
◉-2-3、デジタル音声広告
音楽・音声メディアで配信される広告で、通勤中や作業中の「ながら聴き」で自然に情報が届き、声による共感や親近感を与えられます。
音声は、声のトーンやスピード、間などを通して、感情を伝えられるメディアです。
ナレーターやパーソナリティの声に親近感を持ちやすく、その親近感がそのまま企業の好感度に繋がります。
音声広告は、通勤中や家事の最中、運動中など、ながら時間に自然に耳に入ってくるため、視覚的広告よりもリスナーの注意を独占しやすいのが特徴です。
特に、Spotifyの音声広告は再生開始後はスキップできない仕様になっているため、広告が終了するまで視聴される割合は93%にのぼります。(※1)
デジタル音声広告の種類や特徴は次表の通りです。
| デジタル音声広告の種類 | 特徴 |
| Spotify | ・音楽ストリーミングサービス・無料ユーザー向けに楽曲の合間に音声広告が挿入される |
| YouTube | ・YouTube内で、音声中心の広告フォーマットを用いて配信・特にバックグラウンド再生時に効果的 |
| radiko | ・地上波ラジオをインターネット経由で聴けるサービス・地域密着型の広告展開が可能 |
| Voicy | ・パーソナリティによる音声コンテンツ配信プラットフォーム・情報感度の高いビジネス層へのアプローチに適している |
活用の具体例として、トヨタがSpotifyで出稿した音声広告が挙げられます。
若年層に向けたプロモーションの一環としてSpotifyを活用し、「ドライブに合うプレイリスト」とともに連動した音声広告を配信。
ブランドを「楽しいドライブ」と結び付けることで、ユーザーの印象に残りました。
視覚的なインパクトには欠けるため、短い言葉でどれだけ強く訴求するかが重要です。
参考※1:Spotify『デジタル音声広告って何?Spotifyの音声広告「きほんのき」』
◉-3、コンテンツマーケティングの実施
自社のWebサイトなどを利用して、顧客との信頼関係を構築する手法もあります。
これはコンテンツマーケティングと呼ばれ、顧客にとって役立つ知識やストーリーを発信し続けることによって、企業の信頼性を向上させるものです。
広告のように「売り込む」のではなく、価値ある情報を提供することで自然にブランドのファンを育てることができます。
多くの顧客は検索エンジンを利用して自分の興味や関心のある情報を検索するので、検索結果の上位に表示されるようなSEOライティングや、思わず読みたくなる、興味を湧かせるような企画力が重要となります。
主なコンテンツの種類と特徴は次表の通りです。
| コンテンツの種類 | 特徴 |
| オウンドメディア | ・企業が自社で運営する情報サイト・理念や専門性を継続的に発信できる |
| ブログ | ・社員の声や現場の情報を発信しやすい・柔軟な内容に対応可能 |
| 動画 | ・視覚と音でメッセージを伝えられる・SNSとも連携しやすい |
| ポッドキャスト | ・音声で継続的に情報を届けられる・通勤時間を狙った配信などに適している |
| ホワイトペーパー | ・専門性の高い資料でリード獲得や信頼構築に効果がある |
| メールマガジン | ・見込み顧客に直接情報を届け、関係性を維持できる |
| プレスリリース | ・企業のニュースや新商品を対外的に発信する |
| ランディングページ(LP) | ・特定の商品やサービスに特化したページ・成約率向上に効果がある |
たとえば、グループウェア開発のサイボウズは、自社の働き方改革やカルチャーを綴るコンテンツで、共感と話題性を両立し、ブランド好感度を向上させました。
このように、コンテンツマーケティングは、特に専門知識・ノウハウを持っている企業や、BtoB企業、化粧品などのリピート購入が重要な商品・サービスを展開する企業に向いています。
コンテンツは長期的に投稿していくことが前提となるため、短期的な数字ではなく企業の価値を伝え続ける姿勢が重要です。
▶︎コンテンツマーケティングについては、関連記事【コンテンツマーケティングとは? 広告費を削減して売上を増やす方法】をあわせて参考にしてください。
◉-4、SNSの活用
近年ではX(旧Twitter)やInstagram、TikTokなど、SNSを有効に活用して企業ブランディングを行う企業も増えています。
SNSは、ターゲット層や伝えたい内容の違いによってアカウントを使い分けられる上、Webサイトや文章、広告、CMなどでは伝わりきれない、社内の空気感や働いている社員の人間性、商品開発の細かいプロセスなどを、素早くユーザーに伝えることができます。
SNSの運用を成功させるポイントは、広告・宣伝ばかりを投稿するのではなく、ユーザーのニーズに寄り添った発信を心がけていくことです。
成果・結果を焦る余り、商品の広告や宣伝ばかり投稿していてはファンはつきません。
著名人とのコラボ企画を実施したり、フォロー&リポストキャンペーンを実施したり、代表者が想いを語ったり、開発者のこだわりをキャッチーに話したり、ユーザーといかに密なコミュニケーションを取れるかを考えていくことが何より重要です。
代表的なSNSの種類と特徴は次表の通りです。
| SNSの種類 | 特徴 |
| 実名登録が基本で信頼性が高く、中高年層・ビジネス層に強い | |
| 写真・動画中心で、20~30代に人気 | |
| X(旧Twitter) | 拡散力とリアルタイム性に優れ、幅広い世代が利用 |
| TikTok | 10~20代を中心に人気、トレンド性と拡散力が高い |
| YouTube | 中長尺動画の配信が可能で、専門性の高い発信に適している |
| LINE | 日本国内での利用率が高く、日常的な接点づくりに強み |
▶︎SNSマーケティングについては、関連記事【SNS運用のやり方をとことん解説|フォロワーを集めてビジネスに繋げる成功法則とは?】をあわせて参考にしてください。
◉-5、インフルエンサーとのコラボレーション
インフルエンサーとの連携は、SNSを通じて多くの潜在顧客にリーチできる手法です。
特に若年層への訴求や、共感を得やすい第三者の推薦を得られる方法として有効です。
たとえば、海釣りに関する情報を発信しているインフルエンサーは、海釣りに興味があるフォロワーを多く抱えています。
そのため、海釣りに関する商品・サービスを展開している企業は、そのインフルエンサーとコラボレーションすれば、ターゲットにピンポイントで訴求することができるのです。
インフルエンサーに発信してもらうことができれば口コミのような効果が生まれ、ブランディングの効果を高めることができます。
インフルエンサーへの信頼も相まって企業自体の信頼も高めることが可能です。
ただし、インフルエンサーの価値観が自社ブランドと合っているかを慎重に見極めることが大切です。
◉-6、イメージキャラクターの作成
企業ブランディングにおいて、イメージキャラクターの作成も効果的な手法の1つです。
イメージキャラクターには、視覚的にストーリーやコンセプト・価値観などを伝える効果があるため、顧客の記憶に残りやすくブランドの認知度を高める効果が期待できます。
たとえば、不二家のペコちゃんや、ヤンマーのヤン坊・マー坊、NHKのチコちゃん、ソフトバンクのお父さん犬などが企業キャラクターとして有名です。
また、企業ではありませんが、ご当地キャラクターとして熊本のくまモンなども、キャラクターがきっかけで熊本に大きな経済効果をもたらしています。
このように接しやすいキャラクターがあることで、顧客との関係性が強くなり、購買意欲の向上による売上促進や競合他社との差別化にもつながります。
◉-7、イベント・セミナーの実施
企業が定期的に実施するイベントやセミナーも企業ブランディングに効果があります。
自社製品のプロモーションや自社の専門分野に関するセミナーや勉強会などを行うことによって知名度や顧客満足度の向上が期待できるのです。
また、企業の代表者や著名人を講師に招くことによって信頼感や安心感の向上が期待できます。
◉-8、書籍の出版
企業ブランディングの手法として企業出版という選択肢もあります。
企業出版と聞くと、企業が自費で名刺代わりに出版するようなイメージがあると思いますが、それとは目的が異なり、今注目されているブランディング手法の1つです。
企業出版は企業が自社の情報や専門知識を書籍の形式で出版し、著者のビジネスのブランディングや販促活動の一環として活用する手法です。
企業出版の代表的なメリットとして挙げられるのが、「業界内での知名度や信頼性の向上」「持続的な集客効果」「人材採用や人材教育への効果」です。
まず、出版物に自社の専門知識や実績をまとめることができるため、業界内での知名度や信頼性を高めることが可能です。
次に、出版物の流通期間は非常に長いため、広告やSNSなどと違って持続的な集客効果が期待できます。
また、出版物に企業理念やストーリー、自社商品の開発秘話などを盛り込むことができるため、人材採用や人材教育に効果を発揮することができます。
「文章を読まない」と言われる時代ですが、書籍を買う人は何らかの課題を持った上で文章を読みます。
そのため、一言では語れない創業ストーリーや、ビジネスモデル、こだわり、革新性、専門性を持っているような企業こそ、企業出版は「読まれる」という点で、おすすめの手法です。
企業出版を活用したマーケティング手法の一つに、ブックマーケティングがあります。
ブックマーケティングとは、企業出版などで出版した書籍やSNS、コンテンツマーケティングなど様々な手法を活用してブランディングやマーケティングを行い、信頼の獲得や認知の獲得といった企業の目的を達成するための手法です。
企業ブランディングを行うのであれば、企業出版という出版形態を活用しつつ、ブックマーケティングという視点からブランディングを行うのがおすすめです。
▶︎ブックマーケティング(企業出版)については、関連記事【ブックマーケティングとは?メリットや効果的な戦略の作り方】をあわせて参考にしてください。
◉-9、CSRの推進
CSR(企業の社会的責任)は企業の評価を高めるために重要なブランディング手法です。
CSRの推進が企業ブランディングに与える効果は、「社会と信頼関係の構築」「優秀な人材の獲得」など様々なものがありますが、最も効果が現れやすいのは「ブランドイメージの向上」でしょう。
たとえば、環境保全活動に取り組む企業は「エコに対する意識が高く、持続可能な社会に配慮する会社」として認知されやすくなります。
このように、CSRは企業のポジティブなイメージづくりに直結し、信頼性の高いブランドを形成する一助となるのです。
環境保護、地域社会への貢献、多様性の推進など、自社が社会に対してどのように責任を果たしているかを明確に発信することで、ポジティブなイメージを持ってもらうことができます。
◉企業ブランディングを成功に導く2つのポイント
企業ブランディングは一朝一夕で成果が出るものではありません。
特に重要な2つのポイントは以下の通りです。
| ・長期的な視点で取り組む ・適して指標を用いて効果検証する |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、長期的な視点で取り組む
企業ブランディングは短期間で効果が出るものではありません。
数年または10年ほどかかってやっとブランドイメージが定着することもありえます。
また、たとえ企業ブランディングが成功してブランド価値が向上したとしても、その後何もしなければ、時間と共にブランド価値は薄れていきます。
企業ブランディングは1度作り上げれば終わりではなく、それを維持して継続させることも重要なのです。
そのため、企業ブランディングには多くの時間とコストがかかりつづけることを認識しておきましょう。
◉-2、適した指標を用いて効果検証する
企業ブランディングを行っていく上では、定期的な指標のチェックが欠かせません。
しかし、企業ブランディングは、実際には目に見えない価値を伝えていくことになるため、効果検証がやりづらいという問題点があります。
たとえば、Web広告などであれば、クリック率や成約率など、数字で効果の検証をすることができますが、ブランディングの場合はどこでどのような数字に寄与しているのかを正確に測ることは難しいと言えます。
しかし、企業ブランディングは、企業として多大な時間とコストをかけて行うものだからこそ、方向性が間違っていないかどうか、などの判断は必要不可欠です。
そこで、企業ブランディングの評価によく用いられるのが「ブランドロイヤリティ」「ブランド認知度」「利益・売上貢献」と言った指標です。
効果検証がしづらい企業ブランディングですが、このように適した指標を使って、効果測定・評価をしていくことも重要です。
◉ブックマーケティング(企業出版)における企業ブランディングの成功事例

実際に、ブックマーケティング(企業出版)によって企業ブランディングに成功した事例を2件ご紹介します。
◉-1、出版による信頼性獲得で圧倒的な受注率を達成した不動産会社の事例
この不動産会社の経営者は、競合が多く、怪しい業者も多い中で、紹介から受注まで、顧客との関係性を構築していくまでに時間を必要としていました。
そのため、Web広告などでも正しくメリットを伝えきれず、悩んでいたそうです。
また、主要ターゲットが医師ということもあり、信頼性を獲得することに苦戦していました。
そこで、医師の悩みの1つである高額な税金について、最も効果的な節税対策として、不動産投資があることを紹介した書籍を出版。
書籍でしっかりと医師が不動産投資を行うメリットを詳しく説明したところ、多忙で節税対策などまで手が回らない多くの医師から信頼を得ることができ、発売2ヶ月で6億円の売上が生まれました。
結果として、医師向けの不動産投資の専門家としてのブランディングを確立。
その後も出版物を営業ツールとして配布したり、顧客間での紹介ツールに活用してもらったりすることによって、顧客との関係性構築までの時間の短縮につながり、成約率が飛躍的に上昇しています。
◉-2、セミナーや講演会依頼多数!新規事業の集客を実現した保険代理店の事例
この保険代理店の経営者は、保険業界に関する持論を提唱した書籍を出版。
保険業界の給与体系は成果に応じて給与が決まる「成果報酬型」が当たり前ですが、この保険代理店の経営者はこれに疑問を持ち「一律報酬型」に変えることを提唱していました。
つまり、少数のスーパー営業マンに頼る経営から、アベレージヒッターを育てていく再現性のある経営で業績拡大ができることを書籍で紹介したのです。
ひと言では伝え切ることができない持論について語った書籍を多くの業界関係者が読み、共感が生まれ、業界内でのブランディングを確立することができました。
結果として、多くのセミナーや講演会に招かれたり、新規のコンサル契約を獲得したり、紹介者が増えて本業の保険契約数が伸びるという効果が得られています。
| 本来の出版目的であった、同業の保険代理店からのコンサル依頼がまず数件。そして驚いたのは、保険会社から講演の依頼が来たり同業支援の話が回ってきたりと、「保険会社にとって頼れる代理店」というありがたいイメージを持ってもらえるようになったことです。 引用元:【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店 |
◉【まとめ】企業によって最適なブランディング手法は異なる!まずは自社に合った手法を見つけよう
企業ブランディングは、企業が長期的に社会や顧客から信頼され、選ばれ続けるための戦略的な取り組みです。
重要なことは、自社の理念や価値観をしっかりと軸に据えたうえで、「誰に・どのように伝えるか」を明確にし、それに最適な手法を選ぶことです。
たとえば、前述した不動産会社や保険代理店の事例のように、ひと言で伝えることが難しいビジネスモデルや、こだわり、想いを持っているような方が、一瞬でユーザーメリットを伝えることが重要なWeb広告を活用してもあまり効果は期待できません。
一方で、ブックマーケティング(企業出版)という手法であれば、ターゲットに読んでもらえる、という点で有効なブランディング手段と言えます。
また、あらゆるブランディング手法などをすでにやっている企業がブランディングを強化していきたいという場合には、Web広告やSNSなど誰もができる手法よりも、ブックマーケティング(企業出版)やテレビCMなどのように、誰もがすぐにできない信頼性の高い手法を選んでいくことをおすすめします。
このように、会社によって最適なブランディング手法は異なります。
これから企業ブランディングを始める、または強化していきたいという方は、まずは自社に合ったブランディング方法は一体なんなのか、を考えるところから始めてみてはいかがでしょうか。