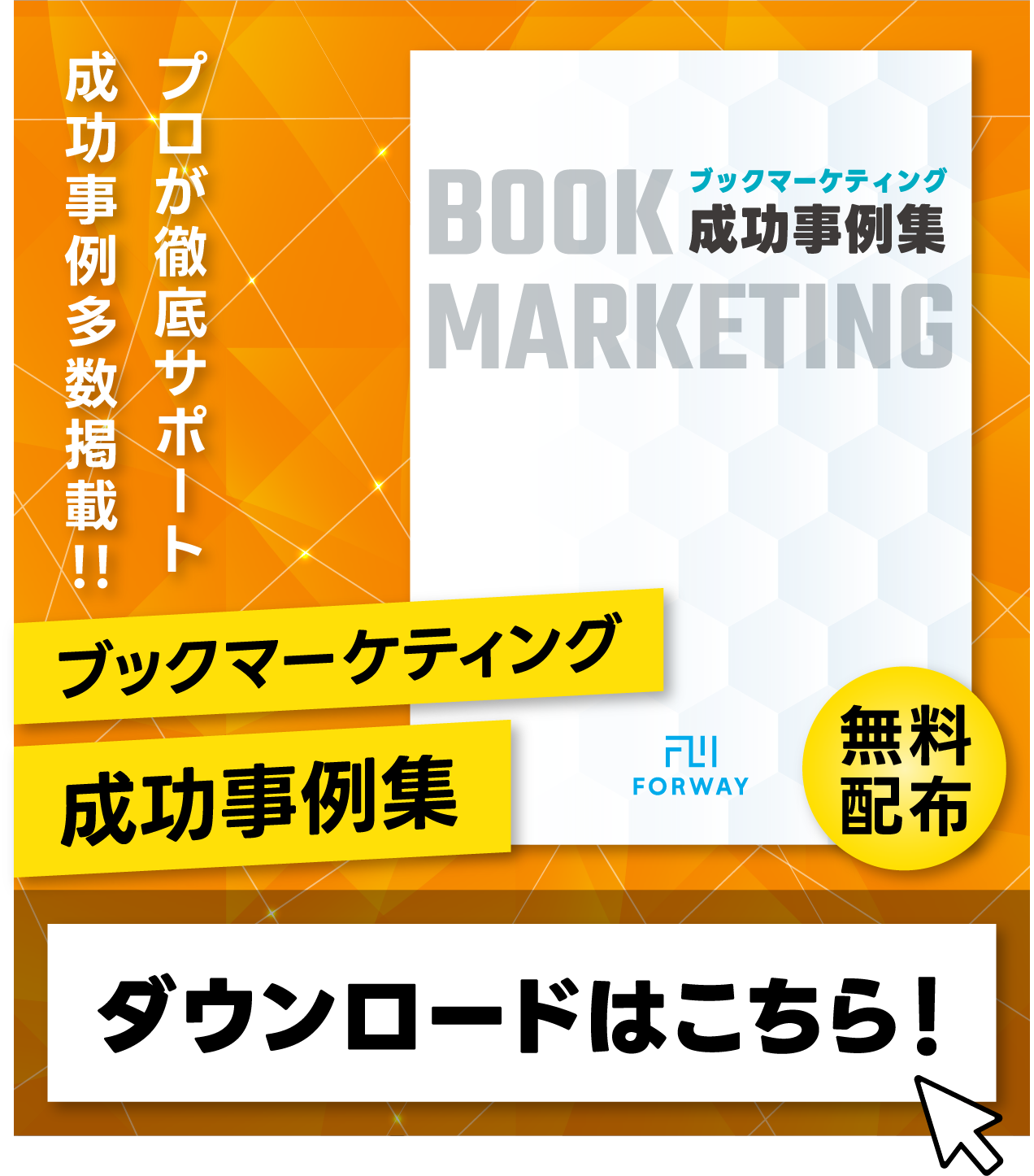Column
フォーウェイは、コンテンツマーケティングで成果を出したい経営者・マーケティング担当者向けの情報を発信しています。
今すぐ自社サイトのSEOを改善させる方法から長期的なブランディングの考え方まで、
実際に弊社のサービスに用いているノウハウを惜しみなく開示します。
2025.03.28
Branding, Marketing
自費出版で印税はいくら入る?売上による利益で儲かるの?

出版する際に「出版することでどれぐらいの利益が出るのか?」という費用回収面が気になる方は多いのではないでしょうか。
出版社が利益をあげる目的で行う商業出版の場合は印刷・発行部数や販売部数によって著者に報酬(印税)が発生する場合が多いですが、自費出版の場合、結論から言えば印税はほとんど発生しません。
「じゃあ、自費出版する人は何で出版費用を回収しているの?」と思ってしまうかもしれません。
今回は、そんな自費出版の印税事情や、また自費出版の場合どういった点で利益をあげているのか、著者の報酬という観点で現役の書籍編集者が詳しく解説いたします。
目次【本記事の内容】
- 1.自費出版は印税が発生しないのが基本
- 1-1.出版社によっては本の売上によって印税ではなく還付金が発生する場合もある
- 1-2.自費出版でも契約によって印税が発生する場合もある
- 2.自費出版は儲からない?
- 3.自費出版は本の販売以外で多くの利益を得られる
- 3-1.事例1:出版により大口契約が決まるなど他社との差別化に成功した保険代理店
- 3-2.事例2:ターゲットにしっかりと本が届くことにより売上が向上した不動産会社
- 4.自費出版で印税に代わる利益を得るための4つのポイント
- 4-1.ポイント1:本の売上自体で儲けようとしない、副次的な利益を目的にする
- 4-2.ポイント2:明確なターゲットを決め、内容も工夫する
- 4-3.ポイント3:出版後に本をターゲットに届けられるような施策を実施する
- 4-4.ポイント4:出版企画時点で出版後の活用を想定して戦略を練る
- 5.【まとめ】自費出版は印税ではなく、副次的な利益を目的に検討しよう!
執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター) 慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |
◉自費出版は印税が発生しないのが基本

著者の著作物(本の内容)を出版社が費用を負担して本という形に仕上げ、本の販売によって得た利益の一部を著者に支払うのが著作権使用料であり、印税です。
自費出版の場合、著者自身が発行した本の代金を含めすべての出版コストを支払っており、自身でそれを販売していくのが基本です。
販売や流通をオプションで出版社に依頼できる場合もありますが、これはあくまで「著者が自分の代わりに出版社に販売や流通をお金を払って依頼している」だけです。
このように、商業出版のような著作権使用料は、自費出版の仕組みでは発生しません。
しかし、出版社との契約内容や、本の売れ行き次第で例外的に出版社から印税が発生するケースもあります。
◉-1、出版社によっては本の売上によって印税ではなく還付金が発生する場合もある
自費出版という仕組み上、著作権使用料としての印税は発生しませんが、本が売れた分だけ「売上金」や「売上還付金」「売上分配金」という形で支払われる場合があります。
これは、出版費用を全額負担した著者に対して、出版社が本の売上の一部を著者に還元する仕組みです。
本が実際に売れた分だけ著者に収益が入るという点では、印税に近い印象がありますが、あくまで売上を著者と出版社で分け合う仕組みであり、売上連動型の報酬に近いイメージです。
◉-1-1、自費出版の場合の売上金比率
自費出版では出版費用を全額著者が負担しているということもあり、出版社が費用を全負担する商業出版に比べてリスクが少ない分、本の売上があった際の著者の取り分は、商業出版の印税率に比べて高くなる傾向があります。
たとえば、売上金比率が30%という契約になっている場合は、本の定価が1,500円だった場合、1冊売れるごとに著者が受け取れるのは450円です。
商業出版の印税率の相場は5%〜10%程度なので、それに比べると高い割合です。
しかし、出版社から還付される「売上還付金」「売上分配金」だけで出版費用全額を回収するには相当の部数が売れる必要があります。
◉-1-2、自費出版の場合の支払い比率
自費出版した本を出版社を通して書店流通させた場合、売れた本1冊分の費用は次のような項目で分配されます。
| ・売上還付金、売上分配金(著者の取り分) ・出版社の取り分 ・書店、取次店の取り分 ・入出庫手数料 ・配送経費など |
また、上記のような項目での分配が行われるのは、出版社に書店流通を依頼した場合の流通部数に限ります。
たとえば、1,000冊作った本のうち700冊を書店流通に回し、300冊を自分自身で販売した場合、700冊で売れた本に関しては出版社から決まった割合で売上還付金・売上分配金が支払われますが、300冊で売れた本に関しての著者の取り分は100%です。
◉-2、自費出版でも契約によって印税が発生する場合もある
本の売れ行きが予想を大きく上回った場合や、出版社が増刷を決定した場合には、出版社との再契約や特約により著者に印税が入ることがあります。
しかし、このように自費出版で予想以上に売れて増刷がかかることは、本の内容の良し悪しにかかわらず稀です。
契約書の特約に「3,001冊目からは印税を支払う」という項目があったとしても、自費出版では印税を期待しない方が無難と言えるでしょう。
◉-2-1、自費出版の場合の印税比率
自費出版で印税が設定される場合、商業出版に比べて印税率が高めになる場合が多いです。
商業出版の印税率が5%〜10%程度であるのに対し、自費出版では15%や20%となることも珍しくありません。
高い出版社では50%のところもあります。
たとえば、本の定価が1,500円だった場合、印税率15%であれば、1冊あたり225円が著者に入ります。
◉自費出版は儲からない?

自費出版では印税はほぼ発生しないと考えておきましょう。
そのため、本の売上だけで出版費用を回収し、儲けを出すのは難しく、商業出版と同じように印税で儲けることは期待できません。
前述の通り、出版社によっては本の売上に応じて「売上還付金」「売上分配金」を受け取れる可能性があるものの、出版費用の回収は難しいのが実情です。
つまり自費出版は本の売上自体では儲からないと考えておきましょう。
一方で、自費出版により本を通して自身の事業や商品・サービスをPRしたり、ブランディングを行ったり、営業・販促ツールとして活用したりすることで、別のところで費用回収をすることは十分に可能です。
たとえば、弊社で出版を行ったある保険代理店では、本を出版したことにより、大手企業の案件獲得につながったり、同業他社からのコンサル依頼につながったり、本業で売上・利益をのばし、出版費用を上回る成果をあげています。
| 本来の出版目的であった、同業の保険代理店からのコンサル依頼がまず数件。そして驚いたのは、保険会社から講演の依頼が来たり同業支援の話が回ってきたりと、「保険会社にとって頼れる代理店」というありがたいイメージを持ってもらえるようになったことです。 引用元:【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店 |
むしろ自費出版で儲けたいと思うのであれば、本を売ることではなく、本を通して自身の商品やサービスの売上を伸ばす方が現実的です。
◉自費出版は本の販売以外で多くの利益を得られる

商業出版に比べて、自費出版は著者が伝えたい内容を自由にコントロールできる(※薬機法や景品表示法など法に触れない部分でコントロールが可能)点が強みです。
そのため、本自体が自身のブランディングやマーケティングに活用しやすく、自身の事業や商品・サービスの特徴や魅力、強みを効果的にアピールすることができます。
こういった自費出版ならではの強みを生かし、本の販売以外で多くの利益を得られる可能性を秘めているのです。
実際に本の出版により、本の販売以外で利益を得た経営者の事例を2つ紹介します。
◉-1、事例1:出版により大口契約が決まるなど他社との差別化に成功した保険代理店
ある保険代理店の経営者は、企業としてもう一段上のステージに登るための手段の1つとして書籍を出版。
本の売上を目的とするのではなく、企業としてのブランディングを目的としていましたが、出版後に予想以上の反響があり、あっという間に出版費用を回収されました。
また、大手案件が決まったり、講演活動が決まったり、優秀な人材が獲得できるようになったり、費用以上の売上・利益につながったそうです。
何より、保険代理店で難しいと言われる競合他社との差別化にも成功。
| 保険代理店はコンビニより数が多いうえ、扱う商品で差別化ができません。保険会社側から一目置いてもらえる代理店になることの価値はとても大きいんです。 引用元:【事例コラム】大口案件の集客、人材採用、大手企業からの講演依頼!出版ですごいことになった保険代理店 |
本の販売以外のところで多くの利益につながっています。
◉-2、事例2:ターゲットにしっかりと本が届くことにより売上が向上した不動産会社
ある不動産会社の経営者は、医師向けの不動産投資サービスを提供していましたが、多額のお金が動くビジネスということから、見込み顧客との関係構築や顧客教育に時間がかかってしまうことが悩みでした。
また、金額が大きいだけにWeb広告やSNSなどではあまり良い問い合わせなどにはつながらなかったそうです。
そんな現状を変える目的で、出版。
本を多く売る、というより、しっかりとターゲットである医師に届ける施策を実施したことで、出版後2ヶ月で合計6億円もの売上につながったのだそうです。
もちろん出版にかかった費用もあっという間に回収。
医師間での口コミも広がり、今でも見込み度合いの高い顧客からの問い合わせにつながっているんだそうです。
このように、本の売上では難しい出版費用の回収も、「本業を伸ばして売上をのばす」という目的であれば、あっという間にできてしまいます。
◉自費出版で印税に代わる利益を得るための4つのポイント

自費出版で印税に代わる副次的な利益をより得やすくするためのポイントは次の4つです。
| ・ポイント1:本の売上自体で儲けようとしない、副次的な利益を目的にする ・ポイント2:明確なターゲットを決め、内容も工夫する ・ポイント3:出版後に本をターゲットに届けられるような施策を実施する ・ポイント4:出版企画時点で出版後の活用を想定して戦略を練る |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◉-1、ポイント1:本の売上自体で儲けようとしない、副次的な利益を目的にする
「自費出版では印税はもらえない」「売上還付金や売上分配金はあくまでおまけ」と考え、本を自身の販促ツールの一つとして活用することに注力しましょう。
どうしても「本の出版をする」と聞くと「本が売れれば印税が入る」というイメージが先行してしまい、本の売上による儲けを期待してしまう人が多いように思います。
本がたくさん売れるよりも、「本が自身の事業や商品・サービスのターゲットとなる見込み顧客にどれだけ届けられるか」の方が重要です。
本の出版による副次的な利益を目的にして本を企画し、制作・活用していく方が、費用回収も早く、損をするリスクも少なくなります。
◉-2、ポイント2:明確なターゲットを決め、内容も工夫する
自費出版は商業出版に比べて、自由に本の内容を企画できます。
そのため、「自分自身がただ書きたいこと」をつらつらと書いてしまいがちですが、印税に代わる副次的なメリットを追求するのであれば、「どんな人に読んでもらいたいか?」というターゲットを明確にし、そのターゲットに刺さる内容や、悩みの解決策やアドバイスを中心に内容を作りあげていくことが大切です。
自身の伝えたいことを盛り込むよりも、ターゲットが「この本なら自分の悩みを解決できそうだ」と感じてもらえるような内容であれば、読者からの見込み度合いの高い問い合わせや、ブランドイメージの向上などにつながりやすくなります。
◉-3、ポイント3:出版後に本をターゲットに届けられるような施策を実施する
自費出版でのよくある失敗は「出版して満足して終わってしまう」というケースです。
出版後にターゲットにどのように本を届けるのか、出版後のマーケティング施策を実施することが重要です。
いくら内容がターゲットに寄り添っていたとしても、それがターゲットの手元に届かなければ意味がありません。
たとえば、営業先などで名刺代わりに渡したり、自身の登壇するセミナーや講演会などで配布したり、SNSやWebサイトなどで情報発信をしたり、PR(プレスリリース)を打ったり、Web広告を打ったり、さまざまな施策を行い、ターゲットに届ける努力をしましょう。
出版社によっては書店流通や営業、マーケティング施策を依頼できる場合があるので、そういった外部サービスを活用するのも一つの手です。
◉-4、ポイント4:出版企画時点で出版後の活用を想定して戦略を練る
出版後の本の活用方法は、出版企画の段階から検討しておくのがおすすめです。
たとえば、「出版後にこういったマーケティングを行い、本をターゲットに届ける」「ブランディングに活用する」など、具体的な戦略を事前に決めておくことで、本の構成や内容なども目的に合わせて仕上げることができます。
出版してから「どう使おうか?」「どうターゲットに届けようか?」と考えるよりも、最初からそれを見据えて戦略設計しておく方が効果的な活用ができます。
◉【まとめ】自費出版は印税ではなく、副次的な利益を目的に検討しよう!

自費出版はそもそも印税が期待できるような出版形態ではありません。
短期的に本の印税や売上還付金、売上分配金だけで費用を回収しようとするのではなく、出版した本を自身の事業に活かすことで、副次的に利益を上げていくことが自費出版の成功のカギと言えます。
コンテンツマーケティング専門会社のフォーウェイでは、本をマーケティングツールの1つとして、活用を見据えた戦略設計、企画、本の制作、書籍流通や営業、マーケティング施策を一貫してサポートしております。
自費出版を検討されている方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。