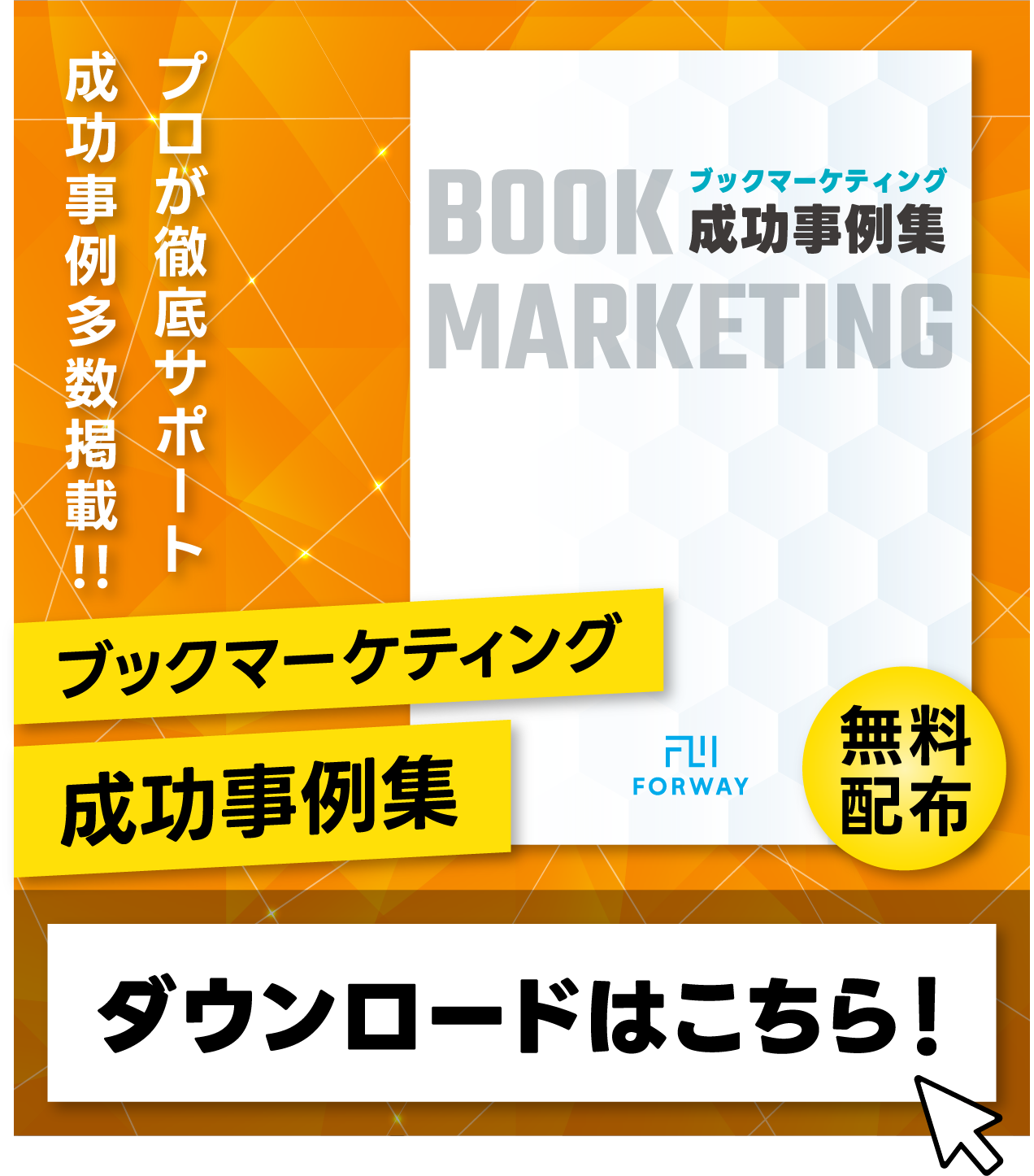Column
フォーウェイは、コンテンツマーケティングで成果を出したい経営者・マーケティング担当者向けの情報を発信しています。
今すぐ自社サイトのSEOを改善させる方法から長期的なブランディングの考え方まで、
実際に弊社のサービスに用いているノウハウを惜しみなく開示します。
2025.04.16
Branding
個人出版とは?自費出版との違いやメリット・デメリットを解説

個人で「本を出版したい」と思った時に、誰でも出版できる方法が自費出版です。
自費出版は、従来出版社を通して出版するのが一般的でしたが、電子書籍やオンデマンド印刷などの普及により、出版社を通さずに出版することも可能になりました。
個人出版もそんな時代の流れから生まれた出版社を通さずにできる出版方法の1つです。
しかし、本を出したい個人の方すべてに個人出版が適しているとは限りません。
個人出版にも向き、不向きがあるのです。
今回は、個人出版とはどのような出版方法なのか、従来の自費出版との違い、メリット・デメリットなどについて詳しく解説いたします。
自身が目指す目的を達成する最良の出版方法は、個人出版なのか、出版社を通した自費出版なのか、はたまたそれ以外の出版方法が適しているのか、を検討してみてください。
目次【本記事の内容】
- 1.個人出版とは?
- 1-1.自費出版との違い
- 1-2.電子出版も個人出版の一種
- 2.個人出版のメリット
- 2-1.本の内容やデザインの自由度が高い
- 2-2.出版費用が安い
- 2-3.出版までのスピードが早い
- 3.個人出版のデメリット
- 3-1.印刷データの制作に時間がかかる
- 3-2.本としてのクオリティが低くなりやすい
- 3-3.書店流通しない
- 3-4.法的責任がすべて自分にある
- 4.個人出版でよく作られる本の種類
- 5.個人出版はこんな人におすすめ
- 5-1.コミケなどのイベントでの販売用に本を作りたい(販売先が決まっている)
- 5-2.自分の作品を本という形にしたい
- 5-3.セミナーや講演会などで配る用に簡単な本を作りたい
- 6.個人出版はこんな人には不向き
- 6-1.商品・サービスのマーケティングに本を活用したい
- 6-2.自社のブランディングに本を活用したい
- 6-3.事業の認知度向上に本を活用したい
- 6-4.名刺代わりに配りたい
- 7.【まとめ】個人的な範囲での本の出版に個人出版はおすすめ!
執筆者:江崎雄二(株式会社フォーウェイ取締役マーケティング統括) 福岡県出身。東福岡高校、山口大学経済学部経済法学科卒業。大学卒業後、月刊誌の編集者兼ライターに携わる。その後時事通信社での勤務を経て、幻冬舎グループに入社。書店営業部門の立ち上げメンバーとして活躍後、書籍の販売促進提案のプロモーション部を経て、法人営業部へ。東京と大阪にて書籍出版の提案営業を担当し、2020年11月、株式会社フォーウェイに参画。2023年9月取締役就任。グループの出版社、株式会社パノラボの流通管理も担う。 |
◉個人出版とは?

個人出版とは、著者が自分で原稿を書き、できあがった印刷データを印刷会社に持ち込んで印刷・製本をしてもらう出版方法です。
出版にかかる費用はすべて著者が負担します。
出版社を通さないので、編集やデザイン、レイアウト、校正などの制作工程を自分でやる必要があります。
また、本の発行者欄などを入れるなども通常の出版物のように明確なルールはありません。
◉-1、自費出版との違い
自費出版とは、その名の通り著者が自分の費用で本を出版する方法のことを言います。
この意味から、個人出版は自費出版の一種ということになります。
一般的な自費出版の場合は、出版社に自分で執筆した原稿を持ち込んで編集やデザイン、校正などの制作工程を依頼します。
著者の意向によっては、原稿も出版社が手配したライターに執筆してもらい、すべての制作工程を出版社に依頼することもできます。
◉-2、電子出版も個人出版の一種>
電子出版も個人出版の一種で、紙の本ではなく電子(デジタル情報)という形で出版した本です。
著者が作成した印刷データを、次のような出版先で電子書籍化して簡単に出版することができます。
・Amazon Kindle
・楽天Kobo
・Google Play Books
・Apple Books
・forkN
・BCCKS
・Shopify+bookend
◉個人出版のメリット

個人出版のメリットとしては、主に次の3つを挙げることができます。
・本の内容やデザインの自由度が高い
・出版費用が安い
・出版までのスピードが早い
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、本の内容やデザインの自由度が高い
個人出版は、本の企画から原稿執筆、デザイン、レイアウト、編集、印刷データ作成などのすべての制作工程を著者自身が行わなければなりません。
しかしその反面、出版社からの制約を受けないため、本の内容やデザインの自由度が高いという大きな特徴があります。
◉-2、出版費用が安い
自費出版をするためには次のような費用がかかりますが、個人出版の場合は印刷・製本代しかかからないため、自費出版より安い費用で出版することができます。
・原稿執筆(ライティング費)
・編集費
・デザイン費
・DTP費
・校正費
・印刷、製本代
・書店流通費(オプション)
・保管費(オプション)
なお、電子出版であれば印刷・製本代もかかりませんので、個人出版よりも安い費用で出版することができます。
◉-3、出版までのスピードが早い
個人出版の場合、印刷データさえできてしまえば、あとは印刷会社に依頼して印刷・製本してもらうだけなので、出版社などに依頼する自費出版と比べて出版までのスピードが早いのもメリットです。
しかしながら、原稿執筆や編集・デザインなどに時間がかかり、なかなか印刷データが完成しない場合は出版までのスピードは遅くなってしまいます。
◉個人出版のデメリット

個人出版のデメリットは、主に次の4つです。
・印刷データの制作に時間がかかる
・本としてのクオリティが低くなりやすい
・書店流通しない
・法的責任がすべて自分にある
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、印刷データの制作に時間がかかる
個人出版では、本の企画から原稿執筆、デザイン、レイアウト、編集、校正などの制作工程をすべて自分で行わなければならないため、印刷データの制作に時間がかかります。
自費出版で出版社に依頼する場合は、ライターやデザイナー、カメラマン、編集者などプロの力を借りることができるため、費用はかかりますが印刷データの制作はスムーズに進みます。
◉-2、本としてのクオリティが低くなりやすい
個人出版する際に、著者に本の出版経験や制作経験がない場合は、どうしても本としての完成度やクオリティが低くなってしまう傾向があります。
個人出版の場合は本の企画から原稿執筆、デザイン、レイアウト、編集、校正、印刷データ作成までをすべて自分でやるわけですから、これらの経験があるかないかで本のクオリティに大きな差が出てくるのです。
見た目についても、一般的に書店で販売されている本と比べるとチープな見栄えになりやすいと言えるでしょう。
◉-3、書店流通しない
個人出版で出版される本の多くは、同人誌などのようにコミケなどで販売・配布されたり、セミナーなどで配布されたり、家族や友人などに配布されるものなので、ISBNコードや書籍用JANコードが付けられません。
これらのコードがないと出版はできても書店流通ができないのですが、個人出版の多くの用途の場合は問題はありません。
以下では、これらのコードについて詳しく説明します。
◉-3-1、ISBNコード
ISBN(International Standard Book Number:国際標準図書番号)コードとは、書籍に付けられる国際的な書籍識別番号です。
200以上の国と地域で発行される書籍に表示されていて、「どこの国の」「何という名前の出版社の」「何という書名の書籍か」という書誌情報を使って、書籍の取引や販売などに使われています。
ISBNが付与できる出版物の範囲は、その発行形態によって決められており、ISBNの付与対象となる出版物の形態は次の通りです。
・印刷・製本された書籍
・雑誌扱いのコミックスやムック
・点字出版物
・マイクロフィルム出版物
・電子書籍、書籍をデジタル化した出版物
・オーディオブック
・地図
・複合メディア出版物
日本国内で発行する出版物にISBNを付けたい場合は、日本図書コード管理センターに申請して手続きをする必要があります。
◉-3-2、書籍用JANコード
書籍用JAN(Japanese Article Number)コードとは、出版物用のJANコードで2段のバーコードで構成されています。
1段目は「978」から始まる国際標準コードのISBN用バーコード、2段目は日本独自の図書分類と税抜き本体価格です。
出版物を市場で流通して販売する場合は、書籍JANコードを表記することが必要とされており、ネット書店で販売する場合にも表記を求められます。
書籍JANコードを使用する場合は、出版者ごとに流通システム開発センター(通称GS1 Japan)に申請して手続きをする必要があります。
◉-4、法的責任がすべて自分にある
自費出版の場合で出版社に依頼する場合は、本の発行元の欄に出版社の名前が載ります。
そのため、出版社の編集者は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、景品表示法、ステルスマーケティング規制など法に違反するような内容がないかどうかを入念にチェックして、必要があれば修正を行います。
なぜなら、本の内容が法律違反に問われた場合は、その責任が出版社にも及ぶからです。
しかしながら、個人出版の場合、法的な責任はすべて著者にゆだねられることになります。
個人出版で出版する場合は、知らぬ間に法律違反をしている可能性もあり得るため十分な注意が必要です。
◉個人出版でよく作られる本の種類

出版方法として個人出版が選ばれるのは、同人誌や電子書籍、主に家族や友人向けに限定的な用途で作られる「私家版」や「私家本」などです。
これらの個人出版で出版される本に共通しているのは、特定のターゲットに特定の場所で配布・販売する本や、個人的な範囲で配布する本だということです。
しかしながら、企業や商品・サービスの認知度向上やマーケティング、ブランディングなどのビジネス目的で個人出版が使われることはほとんどありません。
ビジネス目的の本の多くは、自費出版か企業出版(カスタム出版)で出版されています。
◉個人出版はこんな人におすすめ

個人出版におすすめなのは、たとえば次のような人たちです。
・コミケなどのイベントでの販売用に本を作りたい(販売先が決まっている)
・自分の作品を本という形にしたい
・セミナーや講演会などで配る用に簡単な本を作りたい
以下で、詳しく見てみましょう。
◉-1、コミケなどのイベントでの販売用に本を作りたい(販売先が決まっている)
コミケなどのような個人ファン向けやイベントに来ている人向けに販売する本を作りたい場合は、本の見栄えなどの完成度よりは本の内容やデザインなどの自由度の高さが必要となります。
そのため、自由度が高く出版費用も抑えられる個人出版がおすすめです。
◉-2、自分の作品を本という形にしたい
自分自身が書いた小説や漫画、写真集、画集、エッセイなどを「とにかく本という形でまとめたい」という目的であれば、出版費用が抑えられて自由度の高い個人出版がおすすめです。
出版社の意向や制約などに左右されることなく、自分の好きな作品を自由に掲載して自分だけの本を作ることができます。
◉-3、セミナーや講演会などで配る用に簡単な本を作りたい
セミナーや講演会などで、参加者やファンなどの特定の人に向けて簡単な本を配布したいという場合には個人出版がおすすめです。
このように流通させる必要がなく、個人的なつながりで配布することが目的の場合は、特に高い完成度などは求められないことから個人出版で十分でしょう。
◉個人出版はこんな人には不向き

個人出版は以下のような人には不向きです。
・商品・サービスのマーケティングに本を活用したい
・自社のブランディングに本を活用したい
・事業の認知度向上に本を活用したい
・名刺代わりに配りたい
以下で、詳しく見ていきましょう。
◉-1、商品・サービスのマーケティングに本を活用したい
商品やサービスのマーケティングに本を活用したいという場合は、本のターゲット設定や内容についても、商品やサービスのマーケティングの一環として制作していく必要があります。
プロのライターや編集者、デザイナーの力を借りて、1人でも多くの人に本を購入してもらい、商品・サービスのファンになってもらい、最終的に自社の商品やサービスを購入してもらうことが目的になります。
このことから、個人出版は不向きで、企業出版(カスタム出版)のように書店流通を前提とした出版方法が適しています。
個人出版で、安く出版できたとしてもファン化につながらなかったり、期待したマーケティング効果が得られにくくなってしまいます。
もし商品やサービスのマーケティング本を活用したい場合には、弊社フォーウェイまでご相談ください。
◉-2、自社のブランディングに本を活用したい
自社のブランディングに本を活用したい場合は、本の内容や出来栄えにクオリティが求められますから、個人出版は不向きです。
本のクオリティが低いと、読者に「その程度の会社なんだ」と思われてしまい、ブランディングに悪影響が出てしまう可能性があります。
「書店に置いてある」「一般的なビジネス書と遜色ないクオリティである」「ブランディング方針に沿った内容である」などもブランディングする上では重要な要素なので、自費出版や書店流通を前提とした企業出版(カスタム出版)が適しています。
企業出版(カスタム出版)は、企業経営者などが経営課題を解決するために利用する出版方法です。
本の社会的信頼性の高さやストーリー性という特徴を使って、ブランディングや信頼性の向上、自社の商品やサービスの認知度向上、従業員への企業理念の浸透、採用活動におけるミスマッチの減少などの経営課題を解決することができます。
◉-3、事業の認知度向上に本を活用したい
自社の事業の認知度向上に本を活用したい場合は、今まで自社を知らなかった潜在層にアプローチすることが大切なので、書店に流通しない個人出版は不向きと言えるでしょう。
この場合も、書店流通を前提とした企業出版(カスタム出版)がおすすめです。
◉-4、名刺代わりに配りたい
名刺代わりに本を配りたいという場合は、あらかじめ配布先が決まっていると思われますので、あえて書店流通をする必要はありません。
しかし、「本を出版するようなすごい人なんだ」という権威性や専門性が伝わるような本のクオリティが必要となりますので、個人出版は不向きです。
価格も抑えやすいことから自費出版がおすすめです。
◉【まとめ】個人的な範囲での本の出版に個人出版はおすすめ!
この記事では、個人出版とはどのような出版方法なのか、従来の自費出版との違い、個人出版のメリット・デメリット、個人出版がおすすめな人・不向きな人などについて詳しく解説しました。
個人で本を出版する場合には、目的をよく考えて出版方法を決める必要があります。
「趣味の集大成として本という形にまとめたい」「コミケやイベントのみで配布・販売したい」「セミナーや講演会で配布する簡単な本を作りたい」という個人的な目的であれば、書店流通も本のクオリティも必要ありませんので個人出版で構わないでしょう。
しかし、個人的ではなく、商品やサービスのマーケティングや自社のブランディングなどのビジネスに活用したいとお考えなら、出版社に依頼する自費出版や企業出版(カスタム出版)をおすすめします。
弊社「株式会社フォーウェイ」では、本の出版をマーケティングやブランディングに活用する「ブックマーケティングサービス」を行っており、本を活用したビジネス展開に多くの実績を持っています。
この記事をご覧になったあなたにおすすめのコラム
-
契約・発注につながる建設・建築業の会...
2024.09.12Branding, Marketing
-
不動産の成約につながる会社案内を作る...
2025.01.20Branding, Marketing
-
【事例コラム】出版をきっかけにメディ...
2025.05.01Interview
-
出版マーケティングの効果的なプロモー...
2024.09.30Branding, Marketing
-
富裕層の集客を成功させるには?信頼性...
2025.11.10Branding, Marketing
-
【メディア掲載】弊社サービスを朝日放...
2024.02.27NEWS